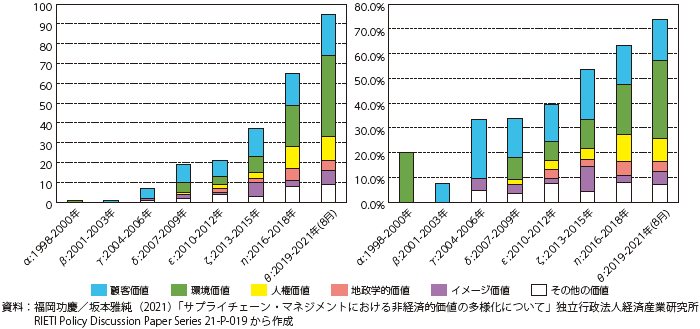第2節 アジア大のスタートアップによる新しい経済機会の創出
1.スタートアップをめぐる動向
(1)急拡大したベンチャーキャピタル投資
スタートアップは、その急激な成長によってマクロ経済の成長をけん引し、将来の雇用、所得、財政を支える新たな駆動力となり得る。ベンチャーキャピタルは、数あるスタートアップの中から大きな成長ポテンシャルを有する主体を発掘するとともに、初期段階から急激な成長を支えるためのリスクマネー供給の中核的役割を担っている。
2021年は、世界のベンチャーキャピタル投資が飛躍的に拡大した1年であった。2021年の投資額は、2020年の3,467億ドルから6,710億ドルへとほぼ倍増している(第Ⅱ-2-2-1図)。
第Ⅱ-2-2-1図 世界のベンチャーキャピタル投資
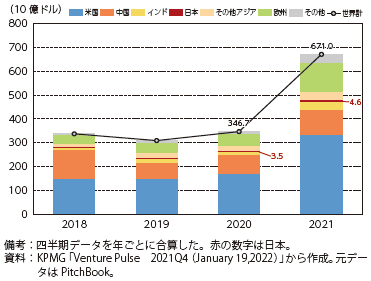
2021年の大型資金調達案件を見ると、件数では、米国および中国企業が多いものの、案件別に見ると、インドネシアのロジスティクス・E-コマース関連企業、インドのエドテック(教育テック)関連企業といった中国以外のアジア新興諸国企業や、ブラジルのフィンテック関連企業が数十億ドル規模の調達を行っている(第Ⅱ-2-2-2表)。デジタルを通じたサービス(教育やヘルスケア、金融サービス等の“テック”分野)やソフトウェア、コンシューマ向けサービス(E-コマースやデリバリー)に加え、グリーン・循環経済、航空宇宙等の新しい分野への関心の高まりがうかがえる。
第Ⅱ-2-2-2表 2021年の大規模資金調達案件(各四半期上位10企業)
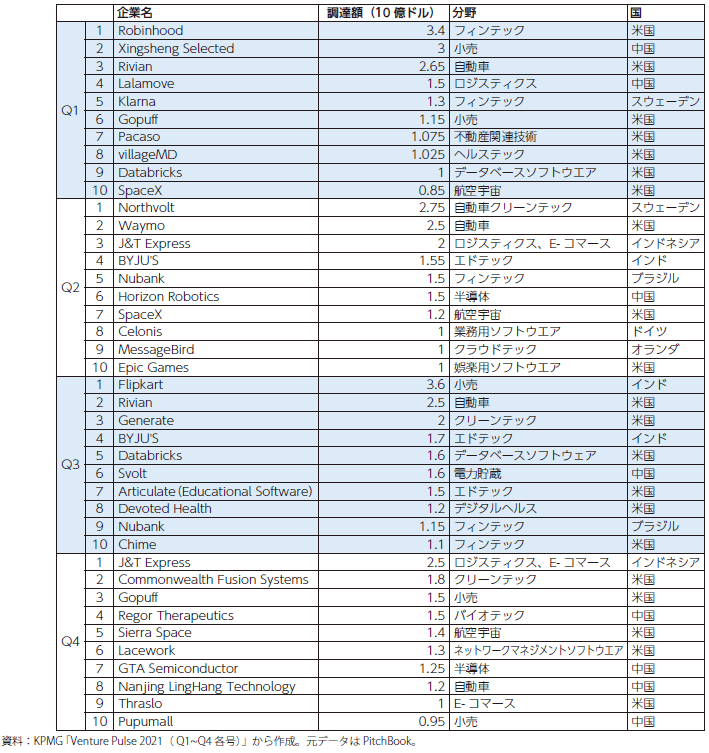
(2)資金供給主体、資金調達手段の多様化
ベンチャー投資の最近の動きとして注目されるのは、伝統的なベンチャーキャピタル以外の投資家(プライベートエクイティ(PE)、ミューチュアルファンド、ソブリンウエルスファンド(以下SWF)、ヘッジファンド等)の参入が拡大している点である132。上原(2021)によれば、米国のユニコーン企業への投資主体を投資件数(投資企業数)の多い順に整理すると、2021年の首位はヘッジファンドであった(2020年と2021年の33位までの投資会社数133を比べると、2020年は非伝統的投資主体が8社であったのに比し、2021年は14社と大幅に増加している)。また、各国のSWFや公的年金ファンド(PPF)が、コロナ禍の回復途上にあって2021年に投資を拡大させており(第Ⅱ-2-2-3図、第Ⅱ-2-2-4図)、運用の重心をテクノロジーやコンシューマ、ヘルスケアといった成長分野にシフトさせてきている(第Ⅱ-2-2-5図)。このほか、再生可能エネルギーへの投資等、サステナビリティ関連の投資にも関心が寄せられている134ほか、サウジアラビア公共投資基金(PIF)による米配車サービスUberへの出資やシンガポールTemasekによる米民泊シェアリングサービスAirbnbへの出資等135、これまでにもSWFによるスタートアップ投資の事例が知られている。
第Ⅱ-2-2-3図 ソブリンウエルスファンド(SWF)、公的年金ファンド(PPF)による投資件数
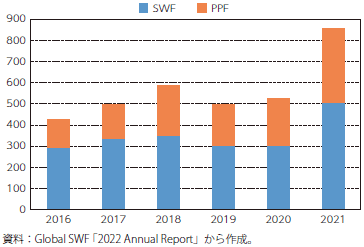
第Ⅱ-2-2-4図 ソブリンウエルスファンド(SWF)、公的年金ファンド(PPF)による投資金額
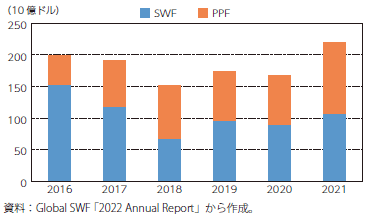
第Ⅱ-2-2-5図 ソブリンウエルスファンド(SWF)、公的年金ファンド(PPF)の投資分野別比率(金額ベース)
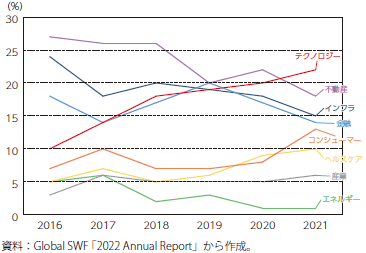
スタートアップ側の資金調達手段も多様化してきている。ベンチャー投資における投資回収段階であるエグジットにおいて、IPO(新規株式公開)のほかに、諸外国では特別買収目的会社(SPAC:Special Purpose Acquisition Company)を通じて上場するケースが見られるようになっている。SPACとは、それ自体は特定の事業を持たず、未公開企業の買収のみを目的として組成される会社で、上場後、未公開企業を買収し、当該企業の事業を営む上場企業として存続する136。スタートアップ側にとってはSPACに買収されることで複雑な手続きを伴うIPOを行うよりも速やかに上場を果たすことが可能となる。このほか、明確な定義はないものの一般に企業等が電子的にトークン(証票)を発行して資金調達を行う137ICO(Initial Coin Offering)や新規成長企業等が必要な資金をインターネット経由で多くの人から少額ずつ集める138クラウドファンディング等の新しい資金調達方法もとられるようになっている。
132 上原(2021)、PitchBook ウェブサイト記事(2021年7月8日)“Why nontraditional investors are expected to continue their push into venture”(https://pitchbook.com/newsletter/why-nontraditional-investors-are-expected-to-continue-their-push-into-venture![]() )
)
133 同順位に複数の企業が含まれる(2020年は33位までに34社、2021年は36社が入っている)。
134 例えばノルウェー年金基金の再生可能エネルギーインフラ投資等(https://www.nbim.no/contentassets/f8c5e301ff804c09881b1beb5299dc30/gpfg-annual-report-2021-web.pdf![]() )。
)。
135 経済産業省(2017a)「第四次産業革命に向けたリスクマネー供給について」(第四次産業革命に向けたリスクマネー供給に関する研究会(第1回)事務局説明資料(2017年10月18日))
136 金融庁(2021a)内閣官房スタートアップの育成の在り方に関するワーキンググループ(第2回)参考資料(2021年4月19日)
137 金融庁ウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html![]() )
法令・指針等/ 事務ガイドライン/ 第三分冊:金融会社関係16. 暗号資産交換業者関係(2021年7月現在))
)
法令・指針等/ 事務ガイドライン/ 第三分冊:金融会社関係16. 暗号資産交換業者関係(2021年7月現在))
138 金融庁(2021b)「成長資金の供給のあり方に関する検討」(金融審議会「市場制度ワーキング・グループ(第6 回)」事務局説明資料(2021 年2月18日。2021年6月16日更新))
(3)巨大化するスタートアップ ~ユニコーン企業の動向~
活発なベンチャー投資が行われる中、いわゆるユニコーン企業(企業価値又は時価総額が10億ドル以上となる未上場ベンチャー企業)の数も足下(2022年2月時点)1,000社を越え、2020年比で約2倍と、1年余りで急速に増加している(第Ⅱ-2-2-6図)。内訳は、多い国から米国512社、中国167社、インド62社、英国40社となっている(第Ⅱ-2-2-7図)。時価総額でみると、世界計(3.3兆ドル)のうち、米国が52.7%と過半を占め、中国の17.1%、インドの5.5%と続く(第Ⅱ-2-2-8図)。国別の業種構成(第Ⅱ-2-2-9~11図)をみると、米国ではフィンテック(23.6%)、インターネットソフトウェア・サービス(22.7%)、中国ではAI(30.1%)、E-コマース・D to C(18.3%)、インドではフィンテック(23.1%)、エドテック(16.9%)の比率が高くなっている。ユニコーン企業が立地する都市に着目すると(第Ⅱ-2-2-12図)、米国西海岸のサンフランシスコを筆頭にニューヨークやボストンなどの米国の主要都市、北京、上海、パリ、ロンドン等で多くなっている。スタートアップのエコシステムが急速に発展してきている139インドのベンガルールの存在も注目される。
第Ⅱ-2-2-6図 世界のユニコーン企業数の推移
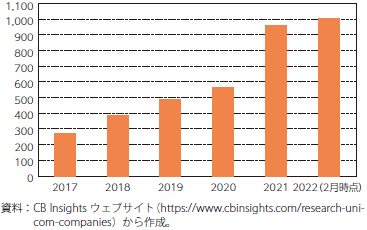
第Ⅱ-2-2-7図 主要国・地域別に見たユニコーン企業数(2022年2月時点)
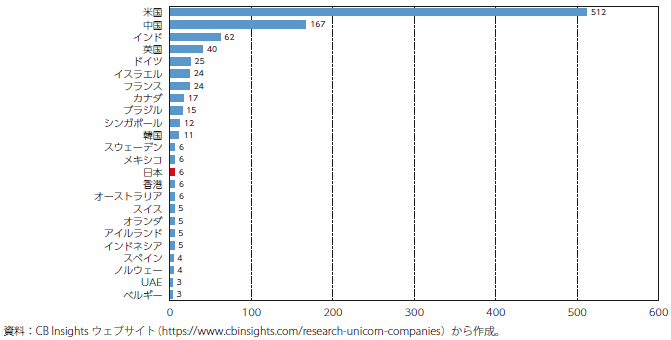
第Ⅱ-2-2-8図 世界のユニコーン企業時価総額
(世界計3.3 兆ドルに占める各国比率 2022年2月時点)
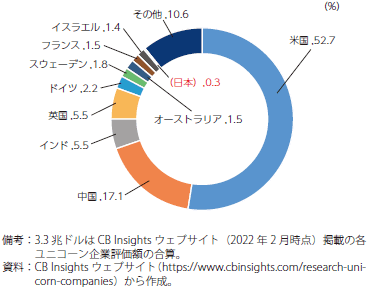
第Ⅱ-2-2-9図 米国のユニコーン企業時価総額分野別比率(%)
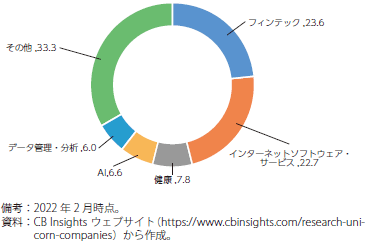
第Ⅱ-2-2-10図 中国のユニコーン企業時価総額分野別比率(%)
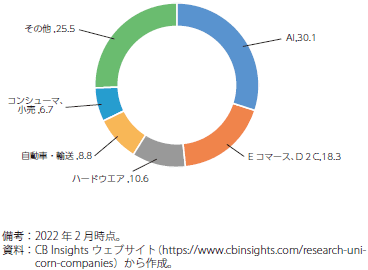
第Ⅱ-2-2-11図 インドのユニコーン企業時価総額分野別比率(%)
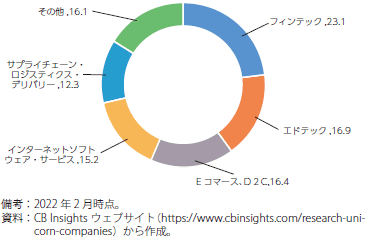
第Ⅱ-2-2-12図 都市別に見たユニコーン企業数(2022年2月時点)
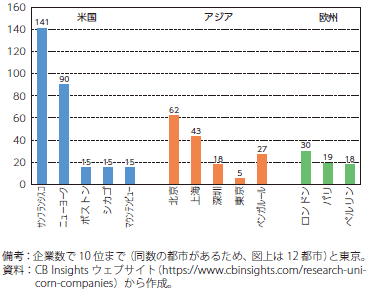
スタートアップからエグジットの段階に成長している企業も複数出てきており、中には創業地ではない国の証券取引所で上場する例も見られる。2021年12月にはシンガポールのGrab社の米国NASDAQ 市場への上場(SPACとの合併による)や、Sea(シンガポール、オンラインゲーム等コンシューマ向けインターネットサービス、2017年10月にニューヨーク証券取引所に上場)、Bukalapak(インドネシア、E-コマース、2021年8月にインドネシア証券取引所に上場)、インドのOne 97 Communications(決済サービスPaytmを運営、2021年11月にムンバイ証券取引所に上場)のほか、2022年4月には、GoTo(インドネシア配車サービスのGojekと同国E-コマースのTokopediaが2021年5月に合併)がインドネシア証券取引所に上場した。
139 滝 幸乃(2019)「ベンガルールを中心に急発展するイノベーション・エコシステム(インド)」(2019年6月10日)(JETRO ウェブサイト)。
(4)出遅れる日本のスタートアップ
大きく成長する世界のスタートアップに比べ、日本企業の出遅れが目立つ。日本のユニコーン企業の数や評価額は、米国のみならず中国やインドに及ばない(第Ⅱ-2-2-7図、第Ⅱ-2-2-8図。日本のユニコーン企業数は2022年2月時点で6社140、世界全体の時価総額に占める比率は0.3%)。また、単純比較は難しいが、諸外国と比べても日本における開業率は低位で推移している(第Ⅱ-2-2-13図)。
第Ⅱ-2-2-13図 開業率の国際比較
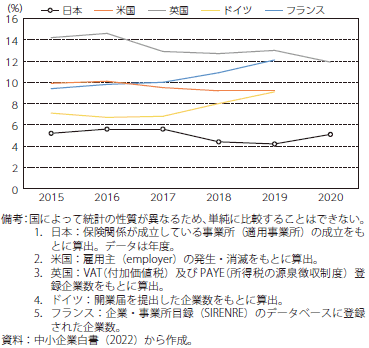
日本のスタートアップをめぐる課題を、人材、事業、資金の切り口で整理してみる(第Ⅱ-2-2-14表)。人材をめぐる課題としては、リスク回避的な志向(「起業マインド」の低さ)や、スタートアップへの人材移動の不足が指摘されている。事業面の課題としては、研究成果の事業化を支える資金や経営人材・伴走者の不足、基礎研究から事業化に至るプロセスで越えるべき関門141を突破するためのリスクマネーの不足や量産化のための設備・ノウハウの不足、また、市場とのミスマッチ(国内に閉じていてグローバル展開できない、国内市場が革新的な製品やサービスに対して未成熟等)がある。また、資金面の課題としては、ファンドの規模そのものが小さいことや、海外からのリスクマネー供給が限定的である等の理由から資金の絶対量が不足していること、エグジットの選択肢や機会が限られていることによる流動性不足の問題等が指摘されている142。
第Ⅱ-2-2-14表 日本のスタートアップエコシステムの課題
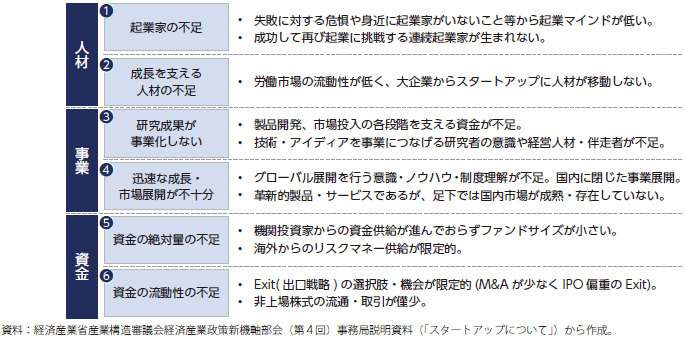
スタートアップは成長のドライバーであり、上記の諸課題を解決していくことにより日本のスタートアップエコシステムを好循環に導く必要がある。特に「市場の創出」や研究開発成果の「事業化・社会実装」に当たって、アジア新興諸国等の海外市場への展開、現地スタートアップ等との連携・協業が有望と考えられる。この点については3.で検討したい。
140 Preferred Networks(深層学習、ロボティクス関連技術開発)、SmartNews(モバイル・テレコミュニケーション)、SmartHR(フィンテック)、Spiber(バイオ素材)、Liquid(フィンテック)、Playco(インスタントゲーム開発)。
141 研究・技術シーズを製品化につながる開発段階につなげられるかの関門(「魔の川」)、開発した製品・サービスを事業化につなげられるかの関門(「死の谷」)の二つの関門がある。(経済産業省(2022a)「スタートアップについて」産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会(第4回)事務局資料(2022年2月16日))
142 経済産業省(2022a)
2.プラットフォームビジネスの動向
(1)各国・地域のプラットフォーム企業143
プラットフォームとは、多数の生産者と多数の消費者をつなぐ「場」(共通機能)のことであり、経済がデジタル化する以前にも存在していたが、インターネットの進展によりデジタルプラットフォームの構築が可能になると、ビジネスの規模は飛躍的に拡大した144。プラットフォーム企業は、プラットフォームの参加者が増えることで便益が増すネットワーク効果を生み、市場への影響力を拡大する。世界のプラットフォーム企業の時価総額上位100社(2021年5月時点)をみると、企業数では米州が41社、中国を含むアジア太平洋地域が45社と拮抗しているが、時価総額では米州が67%、中国を含むアジア太平洋が29%となっている145(第Ⅱ-2-2-15図)。主要企業の個別の評価額(2021年末時点)を見ると、GAFA(M)等、米国プラットフォーム企業群の企業価値が他地域の企業を圧倒している(第Ⅱ-2-2-16図)。
第Ⅱ-2-2-15図 プラットフォーム企業時価総額上位100社の国・地域別内訳
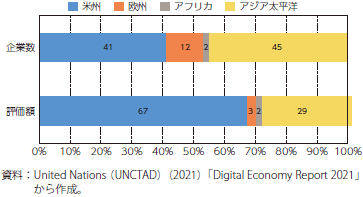
第Ⅱ-2-2-16図 プラットフォーム企業時価評価額(2021年末)
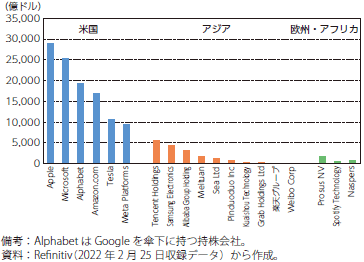
① 米国企業
クスマノほか(2020)は、OSをコンピュータ向けにいかに高く売るかではなく、コンピュータの周辺に発生する様々な補完製品(アプリやデジタルサービス)等の複数の市場をいかに巻き込んで関与させる仕組みをつくるかに着眼するという1980年代のMicrosoftの戦略を「プラットフォーム」思考を具現化した初期の画期的事例として紹介している(クスマノほか(2020)による年代別の代表的プラットフォーム企業群の分類は第Ⅱ-2-2-17図参照)。Appleは、一般の人たちが使いやすいスマートフォンの発明で市場を席捲したことに加え、デジタルコンテンツや決済サービス、アプリケーションストア等のプラットフォームビジネスで収益を拡大している。Amazon(E-コマース)、Google(親会社はAlphabet。検索エンジン)、Facebook(現Meta。ソーシャルメディア)も、それぞれ自社のプラットフォーム機能の向上により短期間で巨大化した。GAFAあるいはGAFAMと総称され、既によく知られているこれら米国のITプラットフォーム企業群は、人々の行動様式を変え社会に大きな影響を及ぼしたイノベーションの担い手であるともいえる。Airbnb(民泊シェアリングサービス)やUber(配車サービス)は、物件の保有者やサービスの提供者と共・利用希望者をマッチングさせるプラットフォームであり、近年注目されているシェアリングエコノミーをけん引するパイオニアである。
第Ⅱ-2-2-17図 プラットフォーム戦略やビジネスモデルを形成した大企業の例
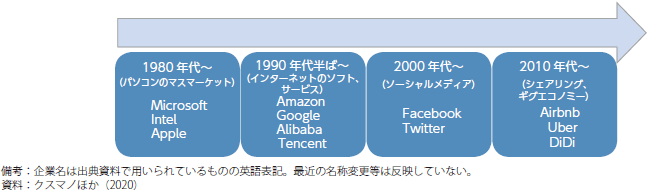
こうした状況下、新型コロナウイルス感染拡大に伴う制限措置は、「対人」、「接触」が通常であった領域のデジタルによる代替需要を更に増大させた。また、5GやVR(virtual reality。仮想空間)等の新しい技術がプラットフォームビジネスにおいて生み出す価値への期待が高まっている。Facebookは2021年10月に社名をMeta Platformsに変え146、従来の主力事業であるSNSサービス(Facebook)の運営のほかに仮想空間「メタバース147」の開発に注力すると発表した。また、Appleの株価は上昇が続き2022年初めに一時、時価総額が米国の上場企業として初めて3兆ドルを突破して話題となった。
② 中国企業
中国では、人口大国としてのポテンシャル(インターネットユーザーの規模)、海外プラットフォームのアクセス規制等により、Baidu(検索エンジン)、Alibaba(E-コマース)、Tencent(ソーシャルメディア、ゲーム)が先行組として地歩を固めた(BATと総称される)。AlibabaとTencentは、それぞれAlipay、WeChatという支払、メッセージ、配車やチケット予約が可能な統合アプリケーションを提供し、数億人単位のユーザーを有する。また、近年ではTMD(Toutiao(ニュースアプリ)、Meituan(フードデリバリー)、Didi(配車サービス))やPKQ(Pinduoduo(E-コマース)、Kuaishou(動画アプリ)、Qutoutiao(ニュースアプリ))、ByteDance(動画アプリ)といった新興のプラットフォーム企業群が台頭しており、中国国内の競争が激化している148。
中国市場の成熟化とあいまって、中国プラットフォーム企業が次の成長市場として期待される東南アジアのE-コマース 分野等に進出する動きが活発化している。具体的には現地E-コマース企業への出資や買収、業務提携等であり、TencentのSanook(タイ。オンラインメディア)やSea(シンガポール。ネットゲーム企業として出発した後、多角化)への出資、AlibabaのLazada(シンガポール。E-コマース)への出資・経営権取得等の案件が注目された。またAlibabaは、東南アジアの主要国政府との連携(タイのE-コマース発展への協力、マレーシアのデジタル自由貿易区構想への参加、フィリピンへの研修プログラムの提供等149)やAI技術研究拠点の設置(シンガポール・南洋工科大学キャンパス内)等、活発な展開を見せている150。同社は、世界規模の越境ECプラットフォーム構想(e WTP:Electronic World Trading Platform)を有しており、東南アジアへの展開も同構想に基づくものといえる。同構想には、単に企業戦略というだけでなく、貿易やフィンテックによるインクルーシブなグローバル社会の実現(途上国や中小企業等でもデジタル技術を通じて世界市場に参加しグローバル化の恩恵を得ることができる、銀行口座を持たない人々にも金融サービスをもたらす等151)を目指すという側面があり、デジタルを通じた成長戦略や社会課題の解決等を模索する東南アジア諸国もこの点を歓迎していると見られる。
③ アジア等新興国企業
アジア等新興国のプラットフォーム企業には、プラットフォームというビジネスの戦略性への志向のほかに、市場の潜在ニーズへの対応、課題解決を通じた成長というインセンティブが強く働いている。東南アジアの代表的プラットフォーム企業としてよく知られている配車サービスのGrab(マレーシアで設立。シンガポールに本社移転)やGojek(インドネシア)は、ドライバーと利用者双方にとっての安全性や信頼性、業務効率性等に関する課題を配車アプリでのマッチングを通じて解決してきた。また、サービスの多角化を積極的に推し進め、多様なデリバリーサービスやキャッシュレス決済、保険プラン等の提供を行っており、デジタルプラットフォームを通じた経済・社会インフラへのアクセス改善を図っている。Gojekは、インド国内のIT企業や人材リクルーティング会社を買収し、インドを研究開発及びエンジニア獲得拠点としている点も注目される。また、2021年にはGojekとTokopedia (インドネシア。E-コマース)が合併してGo-toとなるなど企業規模の更なる拡大を目指す動きも見られた。
インドでは、Flipkart等のE-コマース企業やByju's(エドテック)等が大規模資金調達を行う等、活発な事業展開を行っている(第Ⅱ-2-2-2表)。エドテックについては、農村部等における教育インフラ整備の遅れや新型コロナウイルス感染拡大の影響で学校が閉鎖される等の事態を受けてオンライン学習、VR学習へのニーズが高まっていることから注目が集まっている。特に若年人口の多いインド等新興国においては事業のポテンシャルも大きいと考えられる。また、財閥系企業リライアンス傘下のJio Platformには、同社が有するデジタルプラットフォームリソース(4億人近いJio Infocom携帯電話ユーザー、Jio MartのE-コマースサービス展開等)への期待から、Facebook(現Meta Platforms)やアブダビ投資庁等の国外企業やSWFからも投資が行われている152。One 97 Communicationsはインド系住民人口の多い国・地域に展開し、子会社であるPaytmを中核としてオンライン決済・金融サービス等を提供している。日本のスマートフォン決済サービスにもPaytmのQRコード決済の技術が使われている。
新興諸国におけるプラットフォーム展開においては、銀行口座やクレジットカードを持たない人々への決済手段の提供といった金融包摂の視点も重要である。Alibabaが提供するAlipayはスマートフォンでQRコードを読み込むことで決済と送金を可能とする。Safaricom(ケニア、通信プロバイダー)が提供するM-Pesaは、携帯電話(フィーチャーフォン)のショートメッセージ送信により決済・送金が可能となり、売店(キオスク)で現金の受け渡しができるというものである153。中南米のフィンテック企業として台頭してきたNubank(ブラジル)は、銀行口座を持たない人にスマートフォンを通じて銀行口座類似のアカウントを無料で提供しているほか、クレジットカードの発行や融資、保険等の金融サービスの提供も行っている154。新興諸国で活発化するフィンテックは、リープフロッグ現象の一つの形としても注目される。
新興国のスタートアップをめぐる新しい動きとして、B to Cサービスだけでなく、B to Bサービスにも事業領域が広がってきていると指摘されている。岩崎(2022)は、もともと世界の他の地域に比べてB to Cサービスの比率が高いアジアにおいても、近年、B to Cサービスから派生する形でB to Bサービスに乗り出す企業が出てきているとし、中小小売店や個人事業主を卸売業者やメーカーにつなげるB to Bマーケットプレイスを立ち上げたZilingo(シンガポール)を代表例として紹介している155。
●プラットフォーム企業の多様性
<国際事業展開の方向性>
プラットフォーム企業の事業展開の在り方にはいくつかの類型がある(第Ⅱ-2-2-18表)。人口の多い国内市場を有するがゆえに国内向けにリソースを集中しているTencent、Meituan、Tokopediaや、東南アジア地域内の横展開を推進しているGrab等がある。一方、グローバル市場を志向する企業群においても、AmazonやApple等の巨大プラットフォームのように人口若しくは所得の大きな市場のポテンシャルを追求する企業や、海外の自国出身移民・移住者(いわゆる「ディアスポラ」)のコミュニティと本国人口をつなぐニーズに着目しているBaidu、Alibaba、One 97 Communications等のほか、競合相手の少ない新興市場への進出を積極的に推進しているDiDiやSea等がある。プラットフォーム企業の事業展開の方向性は様々である。
第Ⅱ-2-2-18表 主要プラットフォーム企業の国際的事業展開の方向性
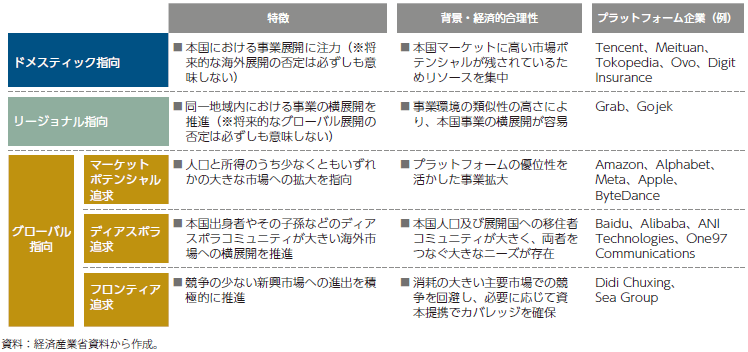
<収益改善モデル>
配車サービス等を単独で展開しているプラットフォーム企業は売上の拡大と利益の改善の間にジレンマを抱えている場合がある。この課題を打開すべく、一部のプラットフォーム企業では、薄利多売ではあるものの顧客の安定的獲得につながるライドシェアや決済サービスを入口として活用し、より利益率の高いEコマース等へ誘導する事業方法をとり、黒字化を図っている(第Ⅱ-2-2-19図)。
第Ⅱ-2-2-19図 スーパーアプリ化の例(概念図)
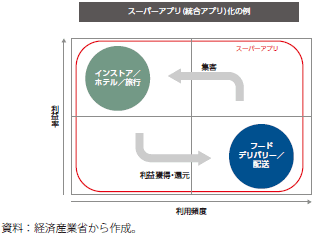
<研究開発拠点>
アジア新興諸国のプラットフォーム企業の中には、本国以外に研究開発拠点及びエンジニア採用に向けた拠点を構えるケースがある。Baiduは米国カリフォルニア州に拠点を設置し、自動運転、ディープラーニング、ロボティクス等の新規成長分野の研究開発を行っている。One 97 Communicationsはカナダ・オンタリオ州に拠点を設置し、顧客データの分析等を行っている。Gojekはインドで現地IT企業や人材リクルーティング企業の買収を通じて研究開発拠点を構築している。
143 本節で取り上げている各社の事業内容については例示である。
144 元橋(2020)
145 United Nations( UNCTAD)(2021)「Digital Economy Report 2021」
146 本節においては、便宜上、Facebook の名を用いて記述している箇所がある。
147 ブルームバーグの試算では、ソーシャルメディアやゲームなどの周辺業界も含めたメタバースの市場規模は4,787億ドル(約55兆円)、2024年には7,833億ドル(約90兆円)を超え、年平均13.1%成長する可能性があると推計されている。メタバースの課題として、AR・VRデバイスやコンテンツの開発、演算処理能力や通信能力の向上等に関する技術的課題や、プラットフォームの覇権競争と相互運用性の確保、従来のプラットフォームでも課題となっている独占・寡占、情報操作、偽情報、プライバシー侵害、ターゲット広告等の政策的課題等が考えられる。こうした論点については、今後議論が進んでいくであろう。
148 伊藤(2020)、野村證券(2020)(「中国新御三家「TMD」とは何か?それでも中国プラットフォーマーが伸び続ける理由」(2020年4月23日)(野村證券ウェブサイト)。
149 岩崎(2018)
150 本田 智津絵(2020) JETRO「テクノロジーの世界で高まる中国企業の存在感(シンガポール)」(JETRO ウェブサイト)(2020年1月10日)及びシンガポール南洋工科大学ウェブサイト(https://www.ntu.edu.sg/alibaba-ntu-jri![]() )。企業の業務内容は一部加筆。
)。企業の業務内容は一部加筆。
151 伊藤(2020)
152 遠藤壮一郎(2020)「フェイスブック、ジオ・プラットフォームズに約6,000億円の出資を発表」(2020年4月30日)(JETRO ウェブサイト)、遠藤壮一郎・谷口晃希(2020)「ジオ・プラットフォームズ、コロナ禍の中、資金調達を加速化」(2020年6月15日)(JETRO ウェブサイト)
153 楊・小池(2018)
154 山岡 浩巳(2021)「南米のデジタル企業」(2021年12月8日)(https://future-fintech.github.io/articles/20211208/![]() )
)
155 岩崎(2022)
(2)プラットフォームビジネスをめぐる新たな動き
プラットフォームビジネスに係る問題については、様々な論点があり、国際機関や各国・地域政府による新たな規制、制度構築の動きが出てきている。
① 国際課税
国際課税については、従来の課税ルールが企業の市場国における物理的拠点の有無を問題にしてきたため、国外のプラットフォーム企業の活動に対する市場国の課税権の配分や課税根拠の考え方、無形資産の軽課税国への移転への対応等、経済のデジタル化に伴う新たな問題が指摘されてきた。
OECDでは、BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトの一環として、経済のデジタル化に伴う国際課税ルールの見直しが検討されており、2021年10月、(1)多国籍企業の本拠地国等から、消費者やユーザーがいる市場国に対して、物理的拠点の有無にかかわらず課税権の一部を配分すること(第1の柱)、(2)グローバルに最低法人税率を15%と設定し、軽課税国の子会社等の税負担が最低税率に至るまで、親会社の所在地国で課税すること(第2の柱)の二つの柱からなる新制度の枠組みが公表され、136か国・地域が合意した(2021年10月時点)。(1)については全世界売上が200億ユーロを超え、かつ、利益率が10%を超える多国籍企業が対象となっており、2022年に多国間条約の策定、2023年に適用開始を目指している。(2)については年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業に適用され、2022年に各国国内法制化(導入は各国の任意)、2023年から順次適用開始を目指している。
伊藤(2021)は、この新しい課税ルールが、自国発のプラットフォーム企業を持たない一方で多数のプラットフォームユーザーが存在する新興国に新たな税収基盤を提供する可能性があると指摘する156。
OECDを中心とした国際議論が行われていた一方で、各国が(暫定的措置として)独自のデジタルサービス課税(DST:Digital Services Tax)等の導入に動いてきたことに留意する必要がある。フランス、イギリス、オーストリア、チェコ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、ノルウェー、ポーランド、スロバキア、スロベニア、スペイン、トルコ等がこれにあたるとされる157。各国の措置をめぐっては、国際通商ルールとの整合性(一方的措置等)や法人税・DST同士の二重課税の問題等、様々な論点が指摘される。また、当該措置をめぐって二国間が対立する事例も見られた(フランス等の課税措置に対する米国の通商301条調査等)。2021年10月の国際合意に関する声明においては、第1の柱を実施するために今後策定する多国間条約において、その締約国は、全ての企業に対する全てのデジタルサービス税及びその他の関連する類似の税制措置を廃止し、また、将来にわたり導入しないことが定められた。また、新たに施行されるデジタルサービス税及びその他の関連する類似の税制措置は、2021年10月8日から、2023年12月31日または多国間条約発効のいずれかの早い日まで課されないことも合わせて定められた。今回のOECD合意後の各国DST等の動向や取扱いを注視していく必要がある。
② 競争・透明性の確保、優越的な地位の濫用防止
競争や透明性の確保、優越的な地位の濫用防止の観点から、各国政府がプラットフォーム企業に対して訴追や制裁その他の措置の発動に動く事例も見られるようになった。最近の事例としては、米国では反トラスト法違反でFacebook(現Meta Platforms)やGoogleが規制当局から提訴(2020年)されたケース、欧州ではフランス当局によるGoogleとAmazonへの制裁金賦課(事前同意なしのCookie取得、利用者への説明不足についてEUの一般データ保護規則(GDPR:General Data Protection Regulation)違反とされた(2020年))等が知られる158。中国では政府の新たなスローガンである「共同富裕」の下、プラットフォーム企業の規制が強化されており、Alibabaグループの金融サービス会社Ant Financialの上場が延期されたり(2020年)、Didiがニューヨーク証券取引所に上場後、中国政府から調査を受け、中国国内のアプリストアでの新規ダウンロードが停止されるケース(2021年)が見られている159。
また、デジタルプラットフォームに関する包括的なルール形成の動きもある。
2020年12月、欧州委員会は巨大プラットフォーム企業がEU市場において守るべき二つの規則案(“DMA:Digital Markets Act”と“DSA:Digital Services Act”)を公表した。DMAは、競争政策の観点から自社独自サービス優先の禁止や他プラットフォームとの間のポータビリティ確保、個人データの取り扱い等、DSAはプラットフォーム上の違法コンテンツへの対応を求めるものである。それぞれ違反した場合の罰則もある。今後の導入に向けた動きに留意する必要がある。なお、DMAについては、2022年3月25日に欧州委員会、欧州理事会、欧州議会の間で政治的合意に至っており、2022年10月中の発効が見込まれる。
日本においても政府内でデジタルプラットフォームをめぐる取引環境整備に関する検討や実態調査等が行われ、デジタル市場のルール整備に向けた取組が行われてきた。2020年5月にはデジタルプラットフォームに対して取引条件変更時の利用事業者への事前通知や苦情・紛争処理のための自主的な体制整備、運営状況の報告等を義務づける「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(デジタルプラットフォーム取引透明化法)」が成立し、2021年2月に施行されている。
③ リアルデータへの視点
本節で見てきたようにGAFA等のデジタルプラットフォーム企業は、インターネット上の膨大なバーチャルデータの収集を強みとして市場への影響力を拡大してきたが、近年、実生活環境から生成されるリアルデータの収集のため、製造業等の異業種への進出を急速に進めてきている。例えばIoT機器をB to Cサービスに投入してデータを直接収集したり、B to B向けのプラットフォームサービスを通じて間接的にデータを収集したりとアプローチの仕方は様々であるが、医療や介護、自動運転、AI次世代家電、デジタル・ガバメント、中小企業の生産性革命等の分野においてGAFAが進出済みであると指摘されている160。
リアルデータの領域においてもGAFAが影響力を拡大しつつある中、欧州では域内一体の次世代クラウド/データインフラ構想(GAIA-Xプロジェクト)が進められている(2019年10月、ドイツとフランス両政府が表明。2020年以降、構想実現に向けた取組が本格化)161。構想の概要や仕組みについては第Ⅱ部第1章第3節で触れているが、GAIA-Xを通じて安全なデータ管理・流通インフラを構築して欧州のデータ主権を保護し、社会・産業インフラ分野の競争力強化を目指す取組といえる162。なお、GAIA-Xのアプローチは、GAFA等に競合するプロバイダーを育成するのではなく、域内の既存のクラウドサービスを相互に接続・運用する分散型のデータインフラの構築を目指すものである163。リアルデータを価値の源泉として重視するアプローチは、IoTを通じて収集されるデータの活用によってマスカスタマイゼーションを実現し産業競争力の強化を図る取組164であったドイツの"Industry 4.0(2011年提唱)"に遡ることができる。さらに「サステナビリティ」や「相互運用性」、「自律性」、「人間中心」、「回復力」といった価値機軸を加えた欧州の新たな戦略である165ドイツの“Vision2030”やEUの“Industry5.0”等にも通底しているといえる。
日本でも、従前より、ハード面の優位性(ロボット、センサー、自動車等の世界シェア、高速データ通信網、スーパーコンピュータ技術)や現場に蓄積されているビッグデータの存在といった強みを活かした新たなビジネス機会を創出するものとしてリアルデータの利活用の重要性が指摘されてきた166。日本企業の中にも、事業活動の中で蓄積されたリアルデータを分析し社会課題の解決につなげるビジネスモデル構築に動き出している例が見られる167。一方で、日本企業におけるデジタル投資の低迷やデジタルによるバリューチェーン可視化の取組の遅れ等も指摘されている。日本としても、リアルデータに関する各国・地域の動きを注視しながら、データ連携の取組等を加速させていく必要がある。経済産業省では、日本企業の競争力強化やサプライチェーン、バリューチェーンのアップグレード(環境や人権等の諸課題への対応等)等の観点から、GAIA-X等を参考にアジア有志国とのデータ連携の取組を進めるべく検討を行っている168。
156 伊藤(2021)
157 渡辺(2020)
158 一般財団法人インターネット協会ほか(2021)「インターネット白書2021」
159 伊藤(2021)。
160 亀井(2019)
161 第Ⅱ部第1章第3節参照。
162 松本・安田(2020)
163 松本・安田(同)
164 経済産業省・厚生労働省・文部科学省(2015)
165 小宮・山本・岩﨑(2021)を参考にした。
166 経済産業省(2017b)
167 日本経済新聞「リアルデータ、社会課題に生かす」(2022年2月19日)、SOMPO ホールディングス新中期計画(2021~2023年度)。
168 経済産業省(2022b)
3.アジアとの「共創」がもたらす新たな経済機会
(1)アジアにおけるデジタル化の進展
若年人口が多く将来にわたって人口ボーナスを享受すると期待される東南アジアの国々やインドといったアジア新興諸国の市場規模とデジタル技術が結びついた場合の成長のポテンシャルには、内外から大きな期待が寄せられている。
アジアのデジタル化は急速に進んでおり、例えば、インドにおけるインターネット利用者数は2016年末の3.9億人から2021年9月時点で8.3億人と5年でほぼ2倍以上になっている169。東南アジア170では2019年の3.6億人から2020年に4億人、2021年に4.4億人となり、このうちE-コマースなどのデジタル消費を行っている人は新型コロナウイルス感染拡大前171の2.9億人から2021年は3.5億人に増加している172。
① コロナ後も続く不可逆的なデジタル化の流れ
新型コロナウイルス感染拡大に伴う制限措置により、リモートワークやオンライン授業など、生活のデジタル化が加速している。こうした動きは不可逆的なものとして定着していくと見られる。
例えば、東南アジアのデジタル動向を人々の意識調査から分析した“e-Conomy SEA 2021173”によれば、2020年にデジタルサービスの利用を始めた人の約90%以上が2021年も継続してサービスを利用している。デジタルサービス利用者に当該サービスを利用する理由を尋ねると単に「便利だから」というだけでなく「自身の生活ルーティンの一部になっているから」と答える人が約40~60%に上っており、人々の生活にデジタル消費が深く浸透してきていることが分かる(第Ⅱ-2-2-20図)。また、デジタル消費を行うようになった人の60%弱は都市部ではない地域に住んでおり(2021年上半期時点)、デジタル技術が新しい消費マーケットを開拓していること、地方に新しい消費習慣が生まれてきていることがうかがえ(第Ⅱ-2-2-21図)、ビジネス部門においてもデジタルの利活用が進んできている。今後5年間でデジタルツールの利用を継続・増加する事業者はおおむね70%以上となっている(第Ⅱ-2-2-22図)。東南アジアのインターネット経済規模は2021年の1,740億ドルから7,000億~1兆ドルに到達する見通しである(第Ⅱ-2-2-23図)。
第Ⅱ-2-2-20図 東南アジアの人々がデジタルサービスを利用する理由
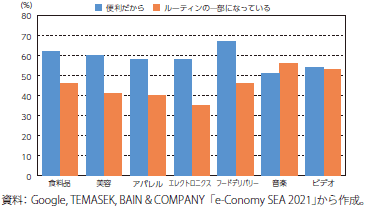
第Ⅱ-2-2-21図 都市部以外に広がるデジタル消費(東南アジア)
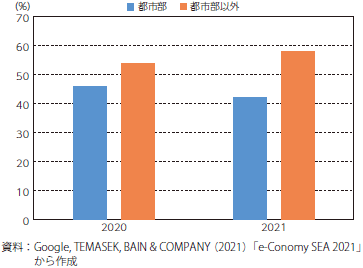
第Ⅱ-2-2-22図 今後5 年間の事業者のデジタルツール利用予定(東南アジア)
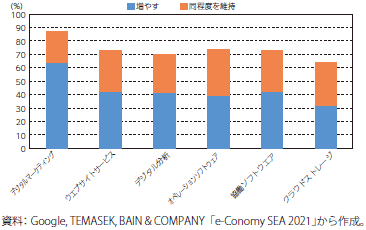
第Ⅱ-2-2-23図 東南アジアのインターネット経済規模(GMV)の見通し
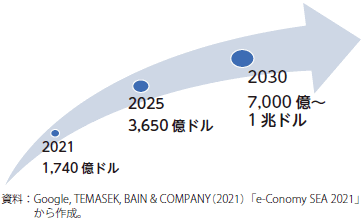
② デジタル技術を活用した社会課題への解決に対する関心
こうしたデジタル市場の広がりとともに、先述のようにアジア新興諸国ではスタートアップやデジタルプラットフォームが次々と生まれている。近年、世界においてテック・プラットフォーム企業の規制が強化される中、インド、ASEAN等のアジア新興諸国では、相対的にベンチャーフレンドリーな環境が確保されているともいえる。アジア各国政府も、デジタルを軸とした成長戦略を推し進めようとしている。足下のコロナ禍からの経済回復だけでなく、いわゆる「中所得国の罠」に陥らないための「知識」や「情報」による経済の高付加価値化が意識されている。また、根強い貧困の存在、医療・教育の不足・偏在といった伝統的開発課題、地方部や中小企業の成長機会獲得の要請、都市部の渋滞や住環境の悪化、質の高いインフラ需要の高まり等、様々な社会課題の解決につながるデジタル・イノベーションに深い関心が寄せられている174。
169 Telecom Regulatory Authority of India, CEIC Database。
170 ここではインドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、ベトナムの6か国。
171 2020年3月以前(Google, Temasek, Bain & Company(2021) “e-Conomy SEA 2021”)
172 Google, Temasek, Bain & Company (2021)
173 Google, Temasek, Bain & Company (2021)
174 経済産業省(2022c)
(2)アジアDXへの参画の意義
こうした状況にあるアジア新興諸国と日本はどのように向き合っていくべきか。日本とアジア新興諸国の関係は、かつてのように先進国である日本から技術やノウハウを移転するという一方向のものではすでにない。多様な発展を遂げているアジア新興諸国を安価な労働力の供給源としてのみ位置づけることも適切ではない。アジアのスタートアップの先進的な取組や成長力に見られるように、むしろ日本が学ぶべき点、取り入れるべき点が多くなっている。
伊藤(2021)は、足下(2010年代後半以降)のデジタル化の時代において、日本は新興諸国の「共創」パートナーとしての位置づけを模索すべきであるとする(第Ⅱ-2-2-24図)。高齢化・人口減少による国内市場の縮小や社会における担い手不足、資源の制約、インフラの老朽化、災害の多発といった日本の課題群についてはこれまでも繰り返し指摘されてきた。デジタル化やデータの利活用が遅れ、新規分野の起業・投資も低調である。そうした中、デジタル技術を活用した「課題解決」と「価値創造」を目指すDX(デジタルトランスフォーメーション)への関心が高まっている。
第Ⅱ-2-2-24図 日本とアジア新興諸国との関係性の変化
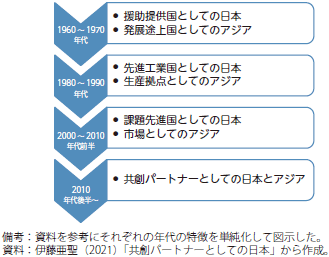
アジア新興諸国にとっては、まさにこのDXが成長の起爆剤となっており、DXモデルの社会実装の経験などは日本に先んじているといえる。日本企業も、投資等を通じたアジアDXへの参画や日本のスタートアップのアジアでの展開・協業等による新しい経済機会を積極的に探っていくべきである。日本が経済社会の新しい局面であるSociety 5.0へと踏み出すという観点からも、アジアDXとの連携がもたらすイノベーション(新興諸国における現地ニーズをきめ細やかに掘り下げることで生まれる現地発の製品や技術、ビジネスモデルを先進諸国に還流させるリバースイノベーション、外部との連携を通じて新しいアイディアを生み出していくオープンイノベーション等)の効果が期待される。また、インドやASEANの企業と日本企業が連携し、アフリカ等の第三国・地域でDXを展開していくことも、新しい経済機会を創出するものとして期待される。
① アジアDXと日本企業
アジアのDXへの日本企業の参画事例も増え始めている。例えば、ASEANにおいてサプライヤー等のデータを活用したサプライチェーンの生産・在庫計画の最適化等の支援、自動運転プラットフォームに関する寄附講座の実施、医療データの統合・活用による遠隔診療や医療資源の有効活用事業への出資等の事例175や、様々な実証事業176(ASEAN、インドにおいて衛星技術を用いた農地情報のデジタル基盤構築および農家の生産性向上に貢献、ASEANにおいてAIやモバイル技術を用いた医療従事者間コミュニケーションや遠隔手術支援に貢献、インドにおいて産業用ドローン販売提供による労働力の省力化を支援、ASEANにおいて衛星技術やAIを用いて海外サプライチェーンの可視化とトレーサビリティを確保等)の事例がある。
プラットフォームビジネスにおいても、アジアのプラットフォーム企業と連携したり、メガプラットフォームとは異なる領域で独自のビジネスモデルを展開したりといった事例177がある。例えば、デジタル化が進展する中、もの(自動車)の製造・販売だけでなく「シェア」、「デジタル化(接続性、自動化、電動化)」にも対応したビジネスモデル構築に舵を切りアジアの配車サービスとの協業を深めている事例や、現地のパートナーと連携して農家や金融機関、農業資材企業等をつなぐプラットフォームを東南アジアや南アジアで展開している事例等がある178。現地のスタートアップやプラットフォームへの出資を通じた参画も多数行われている。貿易実務の電子化プラットフォームによりアジア地域を含む国際的な貿易円滑化を図る取組みもある。また、新興国政府の生体認証システムに対し指紋認証・顔認証技術の提供を行うなど、新興国政府のデジタル政策をインフラ面で支える事例も見られる179。インドではスタートアップやイノベーションのエコシステムが発展してきており、現地の有望なスタートアップとの接触機会を積極的に求める日本企業も出てきている(優秀なIT人材の採用に向けてハッカソンを開催する事例等)180。
② DX支援の取組
日本政府は、日本企業の企業文化を変革するきっかけとして、日本企業と新興国企業との連携による新事業創出を「アジアDXプロジェクト」として推進している。経済産業省および関係機関が連携して先進事例となるいくつかのパイオニア的企業をピックアップし、「同僚・同士効果(Peer Effect)」を起こすリーディングモデルの創出を目指している181。経済産業省と日本貿易振興機構(JETRO)は、オンラインを活用したマッチングやウェブセミナーなどの開催、アジア新興国企業と日本企業間での実証事業支援等、事業フェーズに応じた様々な支援を行っている。例えば、オンラインプラットフォーム「ジャパンイノベーションブリッジ(J-Bridge)」を通じて基本的な情報収集、有望な協業・連携先の発見、面談支援やマッチングイベントの実施を通じて協業案件の創出等が行われている。先進事例に関する情報発信も積極的に行われており、先進事例を紹介するウェブセミナー(2021年3月のADX Pioneers、同年5月の日ASEANビジネスウィークにおけるデジタル、グリーン分野での協業に関する情報発信等)が開催されている。日ASEAN経済産業協力委員会(AMEICC)やJETROを通じたASEAN・インドの企業と日本企業との協業実証プロジェクトの支援(経費補助)も行われており、ASEANについては2020年に23件、2021年に17件(第Ⅱ-2-2-25図)、インドについては2020年に10件、2021年に8件が採択されている182。支援企業からは、政府関係機関と連携することで、現地における自社の信頼性が高まり、現地との共創を円滑に進めることができたとの声も寄せられている183。
第Ⅱ-2-2-25図 アジアDX支援事業採択案件の状況(ASEAN)分野別・国別件数
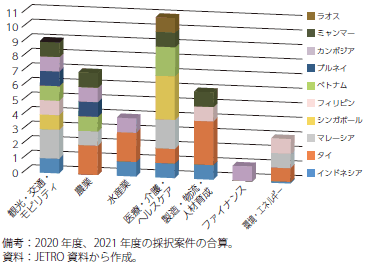
アジア新興諸国のDX連携については欧米諸国や韓国なども自国企業に対する支援策を展開している。事業のフィージビリティ調査、企業幹部どうしの対話の場の提供、現地企業とのマッチング支援等を行っているほか、ASEAN地域にスタートアップセンターを設置する例も見られる184。先進諸国のイノベーション戦略における新興国との連携の動きにも目を向けていきたい。
175 経済産業省(2022c)
176 JETRO アジアDX 促進事業採択事例。
177 小宮・楊・小池(2020)
178 小宮・楊・小池(2020)
179 伊藤(2021)
180 滝(2019)
181 「 成長戦略実行計画(2020年)」内閣官房ウェブサイト(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/kettei.html![]() )
)
182 「日ASEANにおけるアジアDX促進事業」、「アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(日印経済産業協力事業)」。採択案件についてはJETRO ウェブサイト((https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2020/89bff31203b57b8b.html![]() )、(https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2021/d38074f8efc798ae.html
)、(https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2021/d38074f8efc798ae.html![]() )、(https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2021/6854667ac8d219bd.html
)、(https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2021/6854667ac8d219bd.html![]() ))参照。2020年の案件については、令和元年度補正予算「日ASEANにおけるアジアDX促進事業」、2021年の案件については令和2年度第3次補正予算「アジアDX促進事業」より拠出。
))参照。2020年の案件については、令和元年度補正予算「日ASEANにおけるアジアDX促進事業」、2021年の案件については令和2年度第3次補正予算「アジアDX促進事業」より拠出。
183 経済産業省ウエブサイト(https://meti-journal.jp/p/16061/![]() )
)
184 経済産業省・EY 新日本有限責任監査法人(2021)
(3)取組が求められる課題
アジア新興諸国との「共創」を通じた新しい経済機会を模索する上で、内外双方における課題への取組が求められている。
対外的には、従前から問題となっている様々な貿易・投資ルール上の課題を始め、コロナ禍で顕在化した各国の保護主義的な行動、サプライチェーンのぜい弱性、人権や環境等の共通価値をめぐる規制やデータ流通・利用に関する規制の導入・強化がもたらす影響、サイバーセキュリティに関するリスク増大など、多くの新しい課題が現出している。多国間の国際ルール形成の場や各国との経済連携・通商交渉、様々な対話のチャネル等を通じてアジア地域を始めとする海外の事業環境整備を進める必要がある。本節で検討したデジタル・イノベーションに関するものとして、越境データの取扱いをめぐるデジタル保護主義やデジタル覇権主義のような動きへの対応が求められる。プライバシー保護やサイバーセキュリティの確保等、信頼性のある自由なデータ流通(DFFT:Data Free Flow with Trust)の実現に向けた具体的な仕組みや制度を策定していく必要がある185。
一方で、日本がアジアから「共創」のパートナーとして選ばれるよう、日本経済自体の「グローバル化」、「デジタル化」、また「スタートアップ」をめぐる諸課題にも取り組んでいく必要がある。「グローバル化」については、日本独自の雇用環境や外国人材の活用・雇用の難しさ、グローバル人材の不足、中堅・中小企業の海外展開の遅れ、低水準にとどまる対内直接投資、諸外国と比べた英語力の低さ、グローバルレベルの教育環境の不足等が指摘されている186。「デジタル化」については、世界とつながるオープンイノベーションのエコシステムや国際アライアンスを築けず自前主義に陥ったことの弊害、国内のデジタル投資の遅れ、デジタル人材の不足等が指摘されており、コロナ禍における行政の対応においても国と地方のシステムの不整合やオンライン手続きの不具合など、日本のデジタル化をめぐる多くの課題と教訓が明らかになった187。「スタートアップ」については、1.(4)で見たとおりである。
アジアとの連携を深めていくための内外の環境整備が急がれる。
●アジア未来投資イニシアティブ
2022年1月、経済産業省は、ASEANとともに未来志向の新たな投資を積極的に推進するための「アジア未来投資イニシアティブ(AJIF:ASIA-Japan Investing for the Future Initiative)」を発表した(第Ⅱ-2-2-26図)。アジアのエネルギー・トランジションの加速を目指す取組として2021年5月に発表した「アジア・エネルギートランジション・イニシアティブ(AETI:Asia Energy Transition Initiative)」とともに日ASEAN経済関係を次のステージへ押し上げていくことを目指す取組である。(1)グローバル・サプライチェーンのハブとしての地域の魅力向上、(2)持続可能性を高め社会課題の解決につながるイノベーションの創出、(3)エネルギー・トランジションの加速という3つの未来像に向け、サプライチェーン、連結性、デジタル・イノベーション、人材、グリーン・脱炭素の5分野で協力を進めるため、予算措置のほか様々な支援策を講じていく。前述のアジアDX支援の強化のほか、アジア高度人材の日本企業・日系企業への就職機会提供支援(今後5年間で5万人)、等、アジア人材に選ばれる日本を目指す取組も進めていく。また、アジア有志国とのデータ連携を通じたサプライチェーンのアップグレード等にも取り組んでいく。
第Ⅱ-2-2-26図 アジア未来投資イニシアティブ
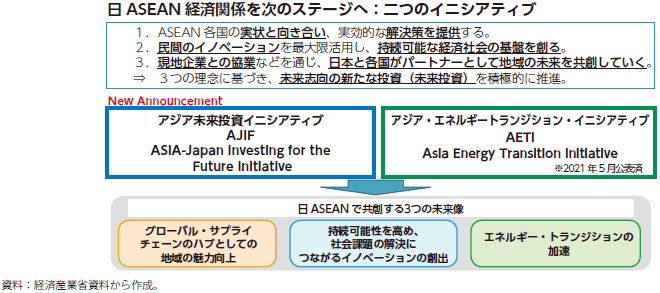
●「暗黙知」への視点
“デジタル”、“スタートアップ”、“プラットフォーム”の切り口でグローバル経済、アジア経済を見ると、足下の日本企業の存在感は大きいとはいえない。意思決定に時間が掛かる、様々なレガシーの存在やシステムの成熟ゆえにかえってデジタル時代のイノベーションになじみにくいなどの指摘もよく聞かれる。日本国内のスタートアップエコシステムも好循環を実現しているとはいい難い。乗り越えるべき課題は多いといえるが、一方で、日本企業が築いてきたもの、日本の強みといえるものに光を当てていくことも必要ではないか。
後藤(2019)は、日本(企業)が持つ強みとして「暗黙知」の存在を挙げている。
暗黙知は、言語を超えた「直観」、実践の中で習得される「勘」や「コツ」などといったもので、デジタルやAIが追求する「形式知」とは異なる知の概念である。暗黙知は「言語化」が難しく「その人に属する」ゆえに共有(模倣や移転)が難しい。そうした暗黙知の蓄積と巧みなすり合わせの力によって「現場」で高い対応力を発揮するというやり方は、日本企業の競争力の源泉でもあった。後藤(同)は、アジア新興国に対する日本の経済協力事案の中で、インフラ整備等のハード面だけでなく、推奨作業手順や安全管理手法といった日本的経営から生まれたソフト面に関わる暗黙知的ノウハウを相手国パートナーとの協働を通じて移転していたことに注目し、こうした総合的な管理能力は日本企業が強みを発揮する領域であると述べている188。伊藤(2021)も日系企業が製造業における優れた生産管理能力を活かし、先進工業国・課題先進国としての日本の経験を強みとしてアジアDXと協業することの意義を指摘する189。
暗黙知は「ほかに真似のできない」、「それゆえ選ばれる」日本品質を追求するものであると同時に、アジア新興国の多様なステークホルダーとの接続性を確保するものであるべきだ。暗黙知をつながらないまま、見えないままに放置すれば、実践の中で培ってきた日本の強みを発揮することも難しくなる。日本の製品やサービス、マネジメントがアジアで選ばれるためにも、各現場に散在し「閉じている」暗黙知を可視化し有機的につないでいくことが必要である。現場で蓄積されるデータの利活用等、デジタル技術の貢献も期待される。
185 経済産業省では、2023年に日本がG7議長国となる機会を捉え、2019年に日本が提唱したDFFTの具体化に向けた新たな提案を行うべく、2021年11月「データの越境移転に関する研究会」を立ち上げ、データの越境移転に係る相互運用可能な枠組みの検討を進めている。2022年2月、報告書に2021年度の検討内容をとりまとめ、DFFT具体化に向けて核となる5つの領域(透明性の確保、技術と標準化、相互運用性、関連する制度との補完性、DFFT具体化の履行枠組みの実装)を特定、2022年末に向けて更に検討を続ける。
186 経済産業省(2022b)
187 経済産業省(2022d)「デジタル社会の実現について」第2回 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会事務局説明資料(2022年1月6日)
188 後藤(2020)
189 伊藤(2021)