第3節 無形資産と経済成長
本節では、イノベーションがもたらす経済成長の道筋を示すものとして、企業が競争を優位に進めていく上で、無形資産(定義や詳細については後述する)への投資がいかに重要であるのかを見ていく。今後、市場規模の拡大が見込まれる先端産業は、技術的なイノベーションによって生み出された産業であり、特に情報技術分野において、市場で独占的な地位を築いているいわゆるプラットフォーム企業の競争優位が研究開発をはじめとした無形資産への投資によって形成されていることなどを鑑みても、その詳細を議論することは重要である。以下では、今後の拡大が見込まれている先端技術産業での無形資産投資の重要性、プラットフォーム企業の利益動向に見られる無形資産投資の役割、イノベーションを促進するための金融制度の重要性、主要国における無形資産投資の比較、無形資産投資を促進する要因としてのオープン・イノベーションの重要性について議論していく。
1.先端技術産業の市場規模拡大から示唆される無形資産投資の重要性
企業などが行う投資は、概念的には主に二つに分類される。一つ目は有形資産投資であり、その名称が示唆するとおり機械設備や工場などの構築物といった実物的な生産設備への投資がそれに当たる。二つ目は無形資産投資であり、主に研究開発(Research & Development:R&D)への投資などがあり、計測や可視化をすることは困難であるものの生産活動に重要な影響を与える投資である。
Elsten and Hill (2017)によれば、米国の代表的な株価指数であるS&P500に採用されている企業の市場価値を要因分解すると、2015年時点で84%が無形資産であり、欧州のS&P Europe350に採用されている企業の市場価値は71%が無形資産としている一方で、我が国の日経225に採用されている企業を含め、アジア諸国では企業価値に占める無形資産の割合が比較的低い(第Ⅱ-2-3-1図)。以下に見るとおり、新興技術に関連する市場の規模が急激に拡大することが見込まれる中で、企業がビジネス機会を見出していく上では、新たなアイデアに投資していく等といった無形資産投資を増加させていくことは重要である。我が国を含めたアジア諸国の企業価値に占める無形資産の割合が比較的低いことは、同割合を高めていくことで企業としての存在感を打ち出していくことが重要な課題であることが示唆されている。
第Ⅱ-2-3-1図 各国の企業価値に占める無形資産と有形資産の割合
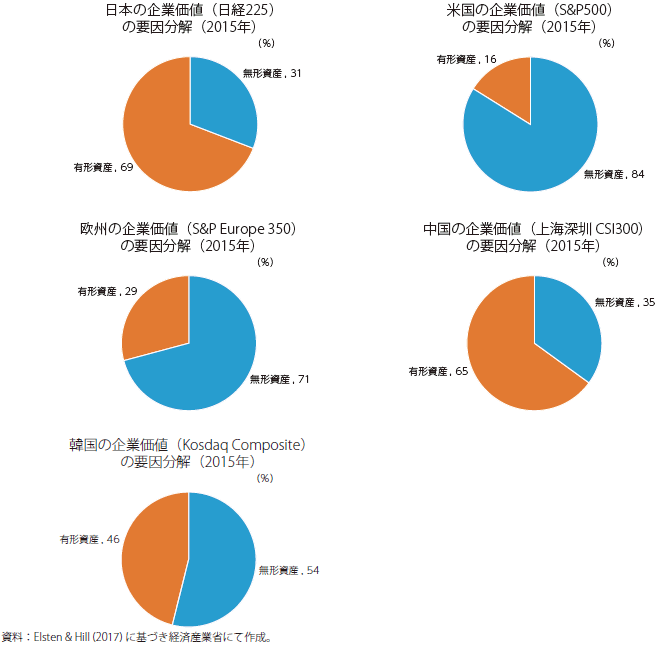
国連貿易開発会議(UNCTAD)の報告書によると、先端技術産業として位置づけられる産業の市場規模は、2018年から2025年にかけて3,500億ドルから3兆2,000億ドルと9.1倍に拡大することが見込まれている(第Ⅱ-2-3-2図)。その中でも、同期間で、IoTは1,300億ドルから1兆5,000億ドル(11.5倍)、ロボットは320億ドルから4,990億ドル(15.6倍)、そして人工知能は160億ドルから1,910億ドル(11.9倍)と大幅な市場規模の拡大が見込まれており、現状での市場規模は比較的に限定的ではあるものの、ブロックチェーンは7億ドルから610億ドル(87.1倍)、そして5Gについては6億ドルから2,770億ドル(461倍)と急速な市場規模の拡大が見込まれている。企業にとっては、それら先端技術産業の最終財生産者としての役割や、もしくはそれらの産業に部材などを提供することでバリューチェーンの中に自らを組み込んでいくといった多様な競争戦略があり得るが、大きく成長する市場に参加していくことは必須であると考えられ、高い技術が求められる市場で生存していくためには上述の研究開発といった無形資産への投資は今後更に重要になると考えられる。
第Ⅱ-2-3-2図 先端技術産業の市場規模
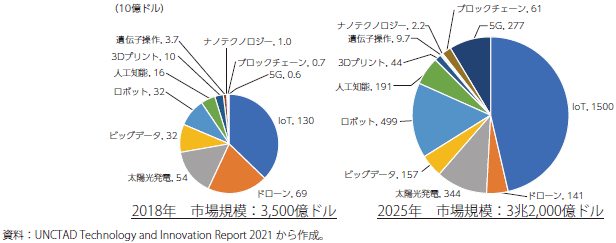
2.プラットフォーム企業の市場支配力の源泉としての無形資産投資
次に、上述のような先端技術産業を中心として多くの人々へサービスを提供しているいわゆるプラットフォーム企業の動向を見ていく。プラットフォーム企業について明確な定義はないものの、経済活動を行う際に、特定の企業が提供しているサービスを利用することが必要不可欠とされる場合は、そうした企業がプラットフォーム企業と呼ばれている場合が多い193。例えば、小売店がオンライン販売を開始する際に、より多くの購買者の目に止まるように、オンラインで大規模な販売サイトを運営している企業のサービスを利用する場合に、そうした大規模なオンライン販売サイトを運営している企業がプラットフォーム企業に当たる。そのようなプラットフォーム企業が、どのようにして他企業にとってそのサービスが必要不可欠であるとの立場を形成することができるのか、すなわちどのようにして市場において支配的な立場を形成することができるのかということは重要な論点である。
それを踏まえて、下記(第Ⅱ-2-3-3図)において、OECDの報告書でプラットフォーム企業と見なされた企業の従業員一人当たり純利益を見ると、米国において主要なプラットフォーム企業とされるAmazonの従業員一人当たり純利益が特に低いことが示されている。これについて、米国の連邦取引委員会のリナ・カーン委員長は、コロンビア大学ロースクール在学時(同委員長就任前)に、Amazonにおいては巨額の売上が市場支配力を確立するための技術開発に利用されることが株主を中心としたステークホルダーの間でコンセンサスになっているため、従業員一人当たりの純利益といった経営指標が低迷していても問題になっていないなどと指摘している194。同氏の指摘は、換言すれば、研究開発等の無形資産への投資は、市場支配力を獲得し、それを維持する上で重要な要因になるということを示唆している。
第Ⅱ-2-3-3図 主なプラットフォーム企業の従業員一人当たり純利益(2017年)
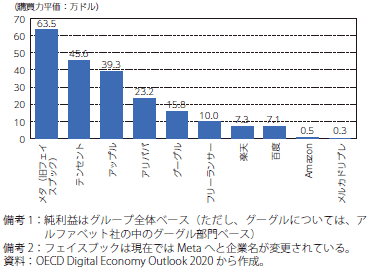
193 例えば、平成29年度経済産業省委託事業『プラットフォーマーを巡る法的論点検討調査報告書』では、欧州委員会や我が国の総務省が定義しているプラットフォーム企業の特徴が例示されている。
194 Khan (2017)。
3.イノベーションを後押しするための金融市場
先端技術産業では、取り扱う技術が新たなものであることから一般的に普及していない場合があり、それゆえに評価すること自体が困難であり、企業にとっては銀行からの借入といった間接金融での資金調達や、企業に対する資本金等や、企業に対する資本金の拠出などを用いた従来型の直接金融による資金調達が困難であると考えられる。
この面で、近年で特に米国で活発であり、技術やアイデアなどの評価が難しい新興企業にとって重要な資金調達の手法の一つと指摘されているのが、特別目的買収会社(SPAC:Special Purpose Acquisition Company)を通した資金調達である195。この手法では、事業を持たない企業が証券取引所に上場することで資金を調達し、その後の一定期間内で未上場企業を買収することを目指すものである。自力での資金調達が困難な新興企業にとって重要な仕組みとなっている(第Ⅱ-2-3-4図)。
第Ⅱ-2-3-4図 SPACによる資金調達の概念図
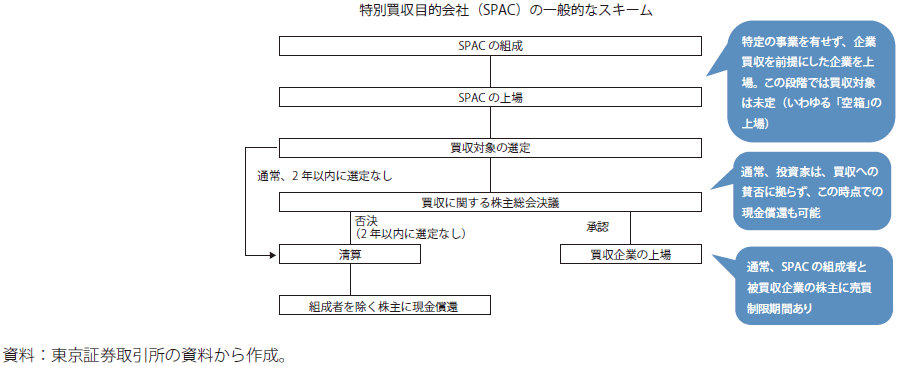
新型コロナウイルスの感染が深刻化した2020年以降では、米国ではSPACの仕組みを用いた新規株式上場(Initial Public Offering:IPO)が大幅に増加しており、接触型の経済活動が抑制されるという社会の仕組みが変容せざるを得なかった中で、新たな技術やアイデアを持った企業の資金調達需要が高かったことが示唆されている(第Ⅱ-2-3-5図)。このように、新興企業のイノベーションを促すような金融インフラが整備されていることは、新たな製品やサービスを生み出していく機運を高めていく素地にもなり得ることから重要である。
第Ⅱ-2-3-5図 SPACのIPO件数(左図)とIPO金額(右図)
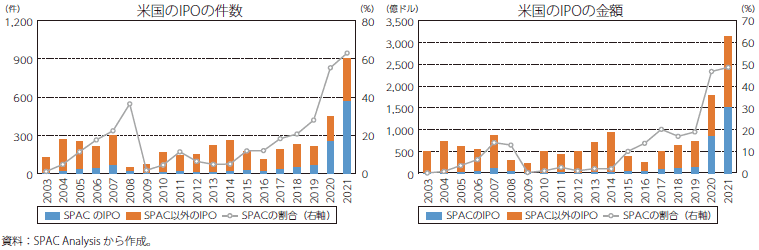
実際に、SPACの仕組みを用いて上場し、その際に発行する有価証券である「ユニット」の収益率が高い企業を見ると(第II-2-3-6表)、再生エネルギー関連(Primoris、Archaea Energy)、天然資源の採掘(MP Materials、HighPeak Energy、Magnolia Energy)、高性能電池である全固体電池の開発(QuantumScape)、神経疾患の治療法開発(Cerevel Therapeutics)等があり、多様なアイデアや技術が金融市場で評価され、企業の資金調達が可能になっている。
第Ⅱ-2-3-6表 ユニットの収益率が高いSPAC による米国の上場企業
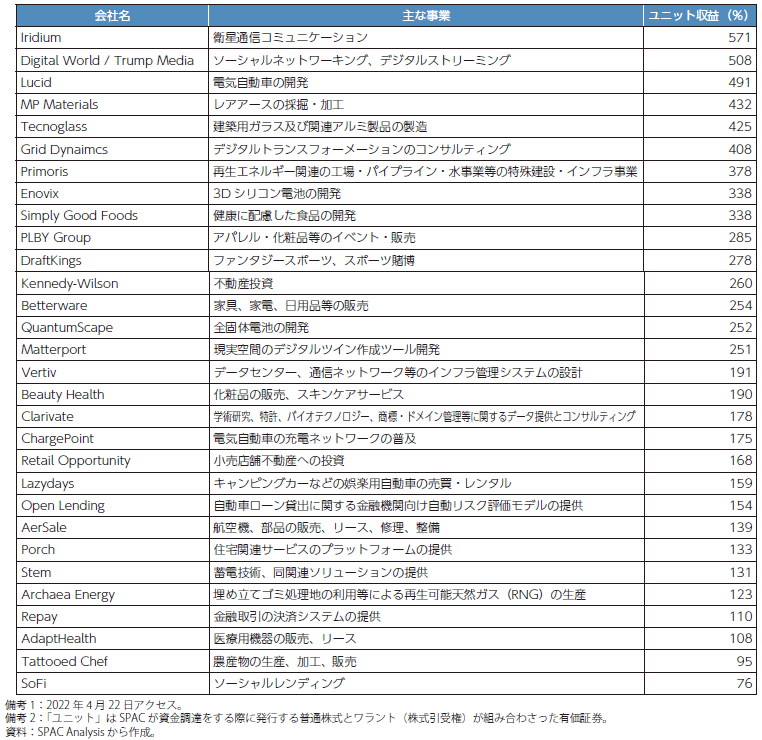
195 東京証券取引所が設置したSPAC制度の在り方等に関する研究会において、2021年10月1日に開催された第1回研究会の説明資料では、米国や諸外国におけるSPACについてのメリットとデメリットに関する議論を紹介している。事業会社へのメリットの一つとして、宇宙やモビリティなどの上場実績が少ない新規分野の会社に上場機会が出てくるとしている。
4.主要国の無形資産投資の比較
本節の冒頭で無形資産の重要性について述べたが、国内総生産を推計する国民経済計算は、国連で採択される国際基準(2008NSA)に基づき作成される統計であり、同統計では、無形資産投資は知的財産等生産物への支出として推計されている。国民経済計算おける無形資産投資にはR&Dやコンピュータ・ソフトウェア投資、娯楽作品の原本等への投資が含まれる一方、後述で説明する無形資産投資はより広義なものであり、対象とする項目が多くなっている。具体的には、企業が所属する従業員に対して、業務に関する技術や知識の水準を向上させるための研修を行えば、それが労働生産性を向上させるなどの効果が期待され、広い意味での無形資産への投資と見なすことができる。本項では、そうした広義の無形資産投資について、各国にどのような違いがあるのかを見ていく。
無形資産投資については、対象とする資産の範囲が明確に定義されていないものの、本項では複数名の経済学者が欧米諸国についての無形資産投資を集計したデータベースであるINTAN-Investを参照し、我が国については独立行政法人経済産業研究所による集計を参照する。具体的に、両集計においては、無形資産投資として、ソフトウェア・データベース、芸術文学作品原本・鉱山開発、意匠(デザイン)、金融業における商品開発、研究開発、ブランド、組織改革、人的資本が含まれている。
下図(第Ⅱ-2-3-7図)は、先進国の中でも経済規模が大きい主要国で実質無形資産投資の総額を実質付加価値比で見たものである。同図によると、米国では同比率が2015年から2年連続で低下しているものの、長期的に見れば、我が国以外では2000年に比較して同比率が上昇しており、緩やかに上昇している。
第Ⅱ-2-3-7図 実質無形資産投資の実質付加価値比
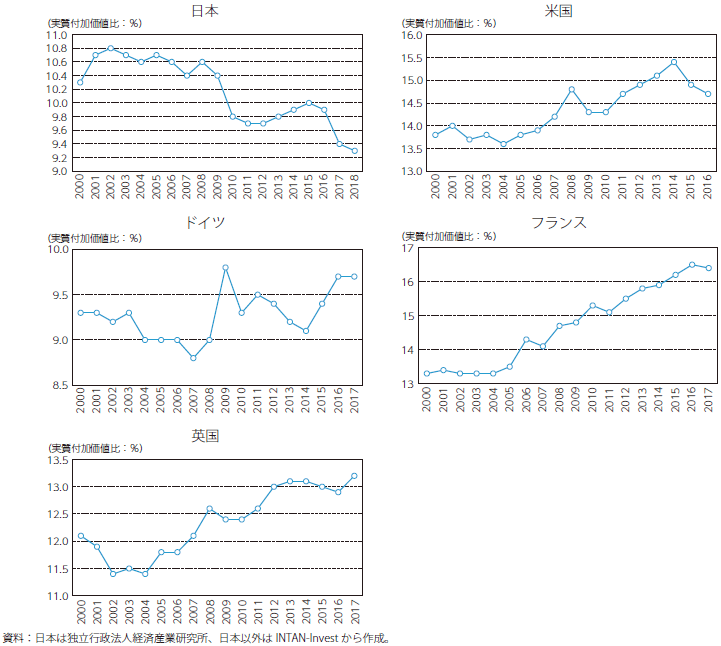
更に、下図(第Ⅱ-2-3-8図)は、実質無形資産投資の各構成項目が、実質無形資産投資に占める比率を各国で比較したものである。特に我が国についての特徴を見ると、R&Dの比重が先進国の中では高くなっているが、組織改革や人的資本の比重が特に低くなっている。こうした特徴を踏まえると、我が国では技術開発への重要性が理解されている一方で、従業員が労働する企業の仕組みや職業訓練への投資が遅れていることが示唆されている。
第Ⅱ-2-3-8図 各国の無形資産投資の構成項目の割合
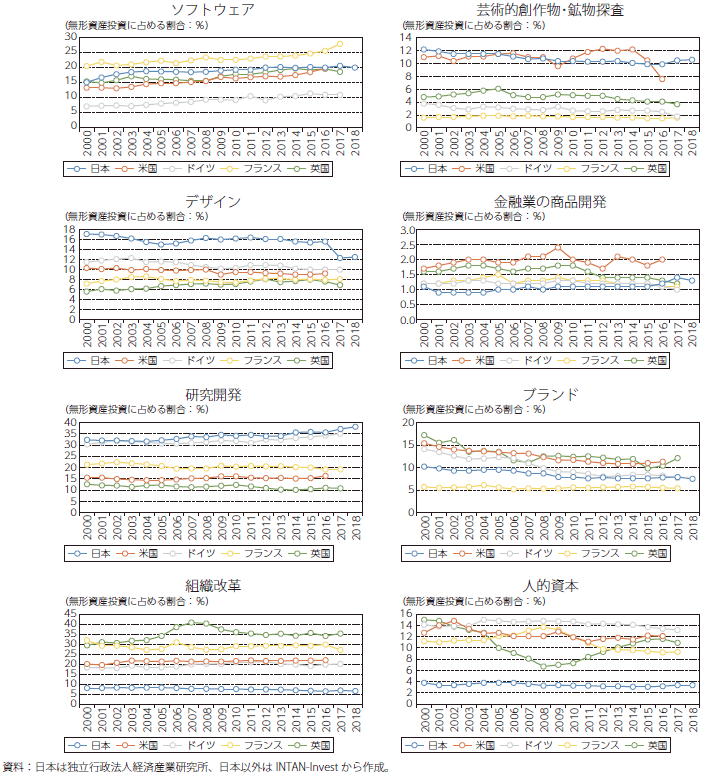
上述のように、我が国では無形資産投資の中でも特に研究開発の比重が他の先進国よりも高く、独立行政法人経済産業研究所のデータによると我が国の研究開発投資の7割程度と大部分が製造業で支出されており、それが我が国の製造業の多様性維持に貢献していると考えられる。具体的に、任意の国の製造業における活動がどれだけ多様であり、またどれだけ特殊性が高いのかを示す指標として経済複雑性指数が知られている。同指数を本節で取り上げている5か国で比較してみると、我が国とドイツの数値が高くなっており、研究開発の比重と整合的な推移が見られる(第Ⅱ-2-3-9図)。第II部第2章第1節で議論しているように、国際的な分業体制の確立といったグローバル化や、ロボット技術の発達による自動化が製造業の雇用を削減するのではないかといった議論があるものの、こうした研究開発を背景とした製造業の多様性と特殊性は雇用の維持にも貢献している可能性が考えられる。
第Ⅱ-2-3-9図 経済複雑性指数
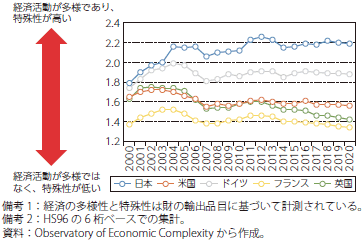
人的資本や組織改革への投資が明示的な例となるように、無形資産投資は概して従業員のソフトスキルや帰属意識を高めるための投資であると考えられ、引いては労働生産性を高めることに寄与することが期待されていると考えられる。それを踏まえて、下の表は各国の無形資産投資に含まれる項目と労働生産性の前年比を用いて、これらの相関係数を計測したものである(第Ⅱ-2-3-10表)。同表によると、我が国については特徴的な動向が見られ、無形資産投資の構成項目の全ての前年比が労働生産性の前年比と正の相関を示している。また、我が国では研究開発が無形資産投資全体の4割程度を占めているが、労働生産性との相関は0.15と低位である。また、労働生産性との相関係数が比較的高い組織開発が占めるシェアは高くはなく、他の先進国と比較してもシェアは低い。ただし、我が国以外を見ても、労働生産性との相関係数が高い項目について無形資産に占めるシェアが必ずしも高くはなく、無形資産投資への資金配分の難しさが示唆されている。
第Ⅱ-2-3-10表 各国の無形資産投資の構成項目と生産性の相関
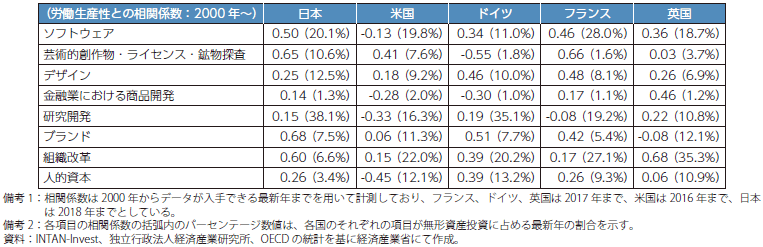
我が国において無形資産投資の実質GDP比が他国対比で小規模に留まっていることの背景の一つとして、我が国の企業では、危機管理対策などの目的で、余剰資金を厚めに準備をしておく傾向があることが考えられる。具体的には、下図(第Ⅱ-2-3-11図)は企業部門の資金余剰動向を、本項で取り上げている各国の投資について比較したものである。それを見ると、世界金融危機の影響が深刻であった2009年前後では、企業が投資に慎重になったこともあり、名目GDP比で見た余剰資金規模はカナダを除き増加した。一方で、それ以外の時期を比較してみると、我が国の余剰資金の名目GDP比の高さが目立っており、企業として利益を留保金として残しておく傾向が強いことが示唆されている。企業による過度な借入と投資は、その分だけ景気後退に陥った時の経済への打撃が深刻にはなるものの、平時の安定的な投資は経済成長の観点からも重要であり、企業が無形資産を含めた投資に対して積極的になることができる制度を整備していくことが望ましいと考えられる。
第Ⅱ-2-3-11図 各国企業の余剰資金動向
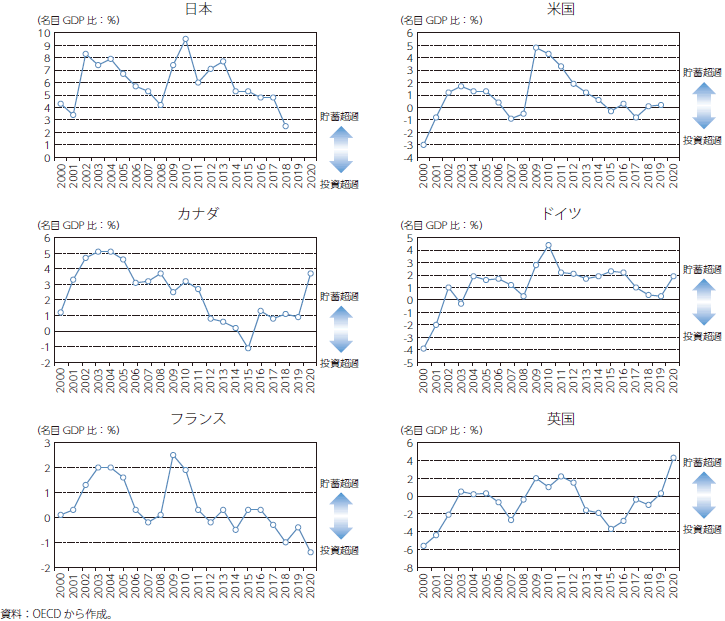
また、企業による投資への資金分配を見る上で、労働分配率の動向も重要である。下図(第Ⅱ-2-3-12図)は本項で取り上げている各国の労働分配率を比較したものである。それを見ると、米国ではすう勢的な低下が見られているものの、我が国を含めたその他の各国では、近年で労働分配率が上昇している。個人消費を安定させていく上で付加価値に占める雇用者報酬の割合を高めることは重要である一方で、資本への分配を通じて企業が成長していくための投資資金を確保するも重要であり、国の社会経済状況に合わせた両者の適切なバランスを維持していくことが必要である。
第Ⅱ-2-3-12図 各国の労働分配率
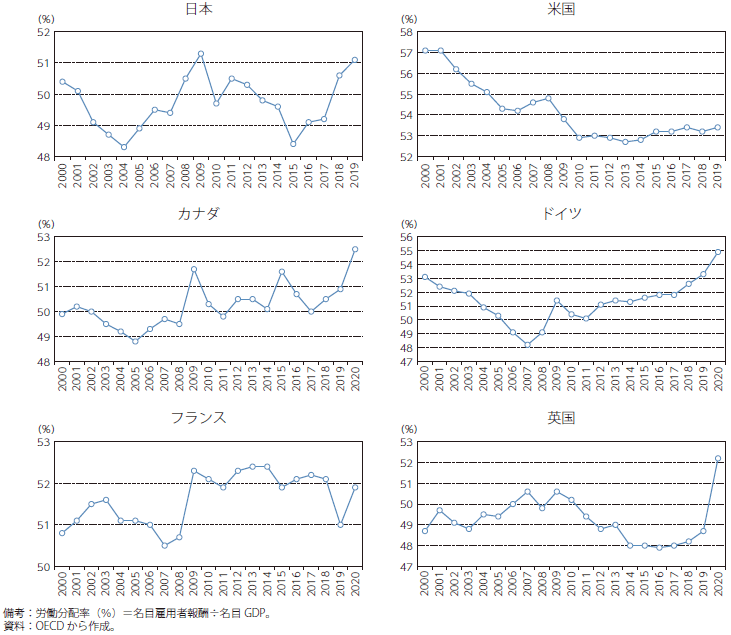
実際に、米国で見られている労働分配率のすう勢的な低下は、換言すれば、付加価値に占める資本の割合がすう勢的に高まっていることを意味している。即ち、企業側が得る付加価値の比率が高まることで、企業にとっては投資や内部留保といった利益の使用用途を判断するための自由度が高まるということを意味している。それを踏まえて、現行で正式統計となっている国民経済計算を基に米国の設備投資の動向を見ると(第Ⅱ-2-3-13図)、現行の統計では無形資産投資に含まれるのは研究開発やソフトウェア等と狭義に留まっていることもあり、構築物や機械といった有形資産投資よりも付加価値に占める割合は低くなっているものの196、無形資産投資の付加価値比は有形資産のそれに近づいている。無形資産投資を中心にして、米国企業が成長のために積極的な利益金の運用を行っていることが示唆されている。
第Ⅱ-2-3-13図 国民経済計算における米国の有形資産投資と無形資産投資
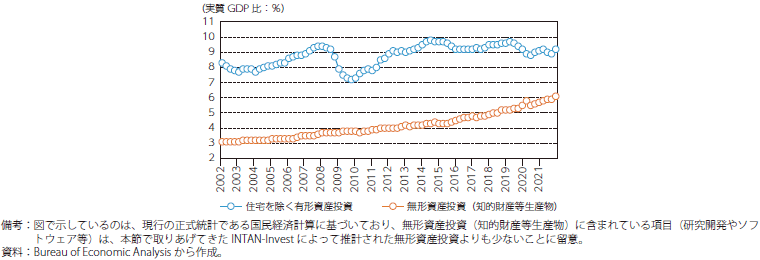
196 Corrado, Hulten, and Sichel (2006) は、米国では、無形資産投資の定義をより広義にすれば、無形資産投資の規模が有形資産投資の規模を上回ると指摘している。
5.知的財産の生産を促進するためのオープン・イノベーション
いわゆるプラットフォーム企業が、なぜ市場で有力な立場を確立できたのかという根本的な要因を考えると、革新的なビジネスモデルなどのアイデアを生み出すことができたということが主な理由の一つとして考えられる。具体的には、現代のプラットフォーム企業に主に見られるように、AI等を用いた詳細な顧客行動などのデータ分析が企業の収益源として重要であるといった考え方は、技術発展によって生み出された革新的な考え方の一つである。
このように、革新的なアイデアや技術発展などを生み出していく上で注目されるのが、オープン・イノベーションという概念である。チェスブロウ(2004)によると、「オープン・イノベーションは、企業内部と外部のアイデアを有機的に結合させ、価値を創造することをいう」とある197。すなわち、アイデアや技術を生み出していく上で、組織内部だけではなく、広く外部との協力体制を築くことが重要であることを意味している(第Ⅱ-2-3-14表)。一方で、組織内で全てを行うべきであるとの従来的な概念はクローズド・イノベーションと呼ばれる。
第Ⅱ-2-3-14表 クローズド・イノベーションとオープン・イノベーション
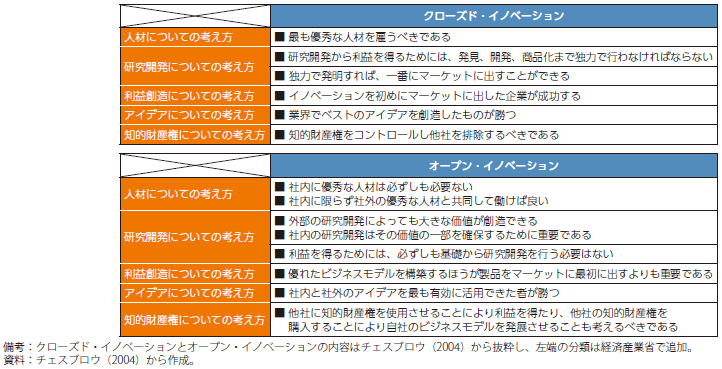
上述の無形資産投資の内訳において、オープン・イノベーションに関連すると考えられるのは、「組織改革」の項目であると考えられる(第Ⅱ-2-3-15図)。オープン・イノベーションは、その定義として人材やアイデアを組織外へも広く求めることとしており、実際に企業などの組織がそうした行動をとるためには、組織文化としての柔軟性が必要である。それを踏まえると、組織改革の項目の推計には、企業によるコンサルティングへの支出が含まれており、組織の柔軟性の向上を含めた改革に積極的であるほどそうした支出が多くなり、組織内だけではなく組織外との交流が活性化されていることが考えられる。
第Ⅱ-2-3-15図 先進国の無形資産投資に占める組織改革の割合
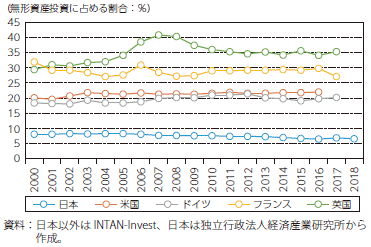
また、オープン・イノベーションは労働生産性にも好影響を与えることを示唆する実証分析もある。下図は、研究による知見の積み上げ(研究ストック)の増加が、労働生産性にどれだけの影響を与えるのかを示したものである(第Ⅱ-2-3-16図)。それによると、研究ストックの労働生産性への影響は、自国の研究ストックが増えることよりも、外国の研究ストックが増えた方が労働生産性を改善させる効果が高いことが示されている。こうした結果は、労働生産性を向上させるためには、外国での知見の積み上げを活用すべきであることを示唆しており、また組織というミクロ的な視点だけではなく、国外で生み出されたアイデアを取り入れるといったマクロ的な視点でオープン・イノベーションが重要であることが示唆されているといえる。
第Ⅱ-2-3-16図 研究ストックの労働生産性への影響
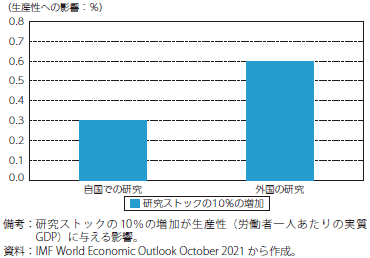
上述のチェスブロウ(2004)によるオープン・イノベーションの定義によると、知的財産については、自組織が保有する知的財産を他組織に使用させることで収益を上げるだけではなく、他組織の知的財産について購入等を通して活用することも重要であることが述べられている。それを踏まえると、各国がいかにオープン・イノベーションについて積極的であるのかを計測する指標として、知的財産権使用料の受取と支払を合計した金額の経済規模に対する推移を見ることが有用であると考えられる。下図(第Ⅱ-2-3-17図)は、それについて無形資産投資の詳細で取り上げた諸国について示したものである。これによると、米国以外の先進諸国では知的財産権使用料の資金フローの名目GDPはすう勢的に上昇しており、国家間というマクロ的な視点でオープン・イノベーションが浸透していると見ることもできる。
第Ⅱ-2-3-17図 知的財産権使用料の資金フロー
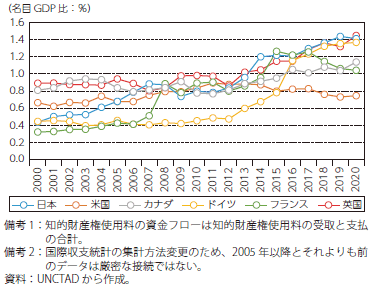
前述のとおり、オープン・イノベーションにおいては、自組織が保有する知的財産を他組織に使用させたり、他組織の知的財産を自組織において活用したりすることが重要であるところ、知的財産の権利帰属の不安定性の問題が生じると、オープン・イノベーションの障害になり得る。また、発明者に対する報奨も重要である。それを踏まえると、我が国でも2015年に法改正がなされたように、職務発明制度の整備が重要である。我が国の特許法の定義によると、「職務発明とは、従業者等がした発明であって、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」であり、同制度は職務発明についての権利や報酬の取扱い等を定める制度である。
我が国を含めた諸外国の職務発明制度を見ると(第Ⅱ-2-3-18表)、職務発明よって生み出された特許を受ける権利の所有者(原始的帰属)は、使用者等(すなわち企業等の雇用者)に属する場合と、発明者(すなわち従業者等の被雇用者)に属する場合とがあり、各国によって異なるものの、関連法の定めるところにより、概して特許を受ける権利が使用者等に譲渡・継承され、発明者に対してはその相当の利益を支払うことが制度化されている。
第Ⅱ-2-3-18表 我が国と諸外国の職務発明制度
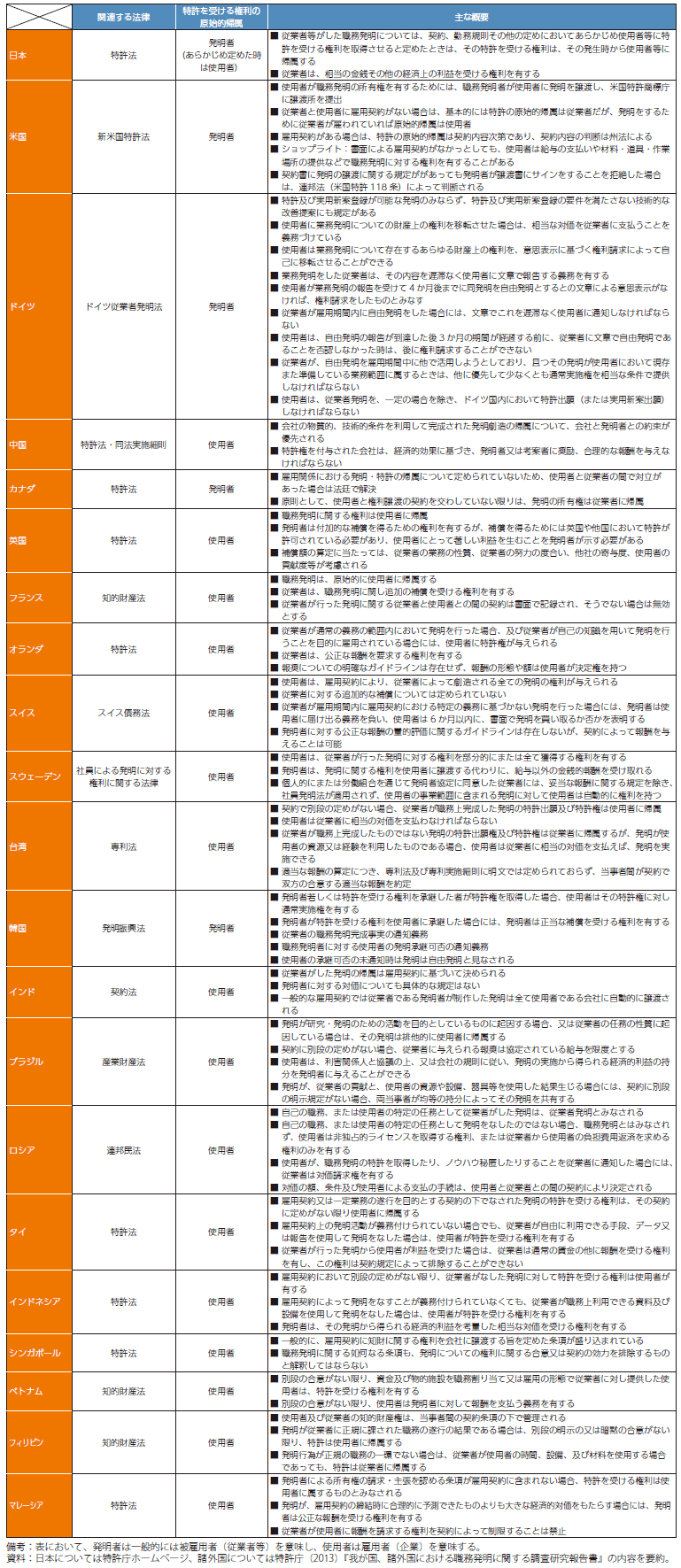
我が国でも、2015年の特許法の改正により、従来の規定では特許を受ける権利は従業者等にあるとされていたところ、契約や勤務規則であらかじめ定めた場合には、特許を受ける権利が使用者等にあるとすることが可能になった。この改正により、特許を受ける権利が、一旦は従業者等に帰属した後に、従業者等から使用者等に承継されるといった事務的な手続きの負担の軽減や、従業者等が特許を受ける権利を勤務先以外の第三者に譲渡してしまうといった問題も解決されている。また、特許法に基づいて、経済産業大臣が定めて公表した指針(ガイドライン)では、契約等で定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であるか否かの判断に当たっての考慮要素についてより具体的に明示するとともに、「相当の利益」について契約等で定めた場合における不合理性の判断においては、特許法に例示する手続の状況が適正か否かがまず検討され、それらの手続が適正であると認められる限りは、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約等が尊重され、その結果、不合理性が否定されるという原則を明示した。こうした法改正により、企業にとっては、オープン・イノベーションによって組織内外の知的財産を広く活用することのリスクが低減されている。
上述のとおり、我が国では特許法が改正され、職務開発に従事する従業員を雇用することに伴う企業の事務負担等が低減された一方で、オープン・イノベーションを更に推進していくための課題も残っている。具体的には、下図(第Ⅱ-2-3-19図)は、クロスアポイントメント制度を利用した教職員数の動向を示したものである。クロスアポイントメント制度とは、研究者等が複数の大学・公的機関や民間企業等で、それぞれと雇用契約を結び、業務を行うことを可能とする制度である。同制度を利用した教職員数の動向を見ると、特に企業の受入と出向が、企業以外(大学、研究開発法人、その他機関)の受入と出向よりも大幅に少ないことが示されている。
第Ⅱ-2-3-19図 クロスアポイントメント制度の実施状況
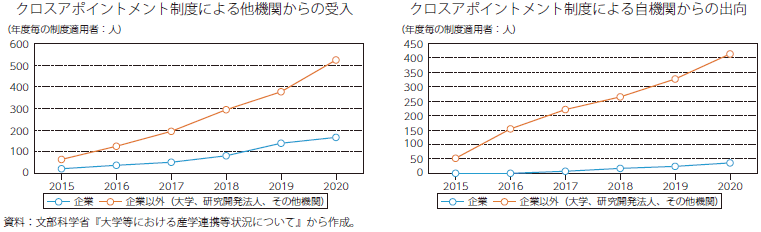
オープンイノベーション白書第二版によれば、10年前よりもオープンイノベーションを活発化させていると調査アンケートの回答した企業について、オープンイノベーションを推進する仕組みの問題点・課題として、51.3%の企業が「外部の連携相手委を探すのは非常に大変である」と回答している(第Ⅱ-2-3-20図)。同アンケートは2015年度に実施されているが、上述の企業によるクロスアポイントメント制度の利用が現状でも低水準に留まっていることを鑑みれば、当時と状況が大きくは変わっていない可能性がある。同制度の積極的な活用を後押ししていくことが重要であることが示唆されている。
第Ⅱ-2-3-20図 オープン・イノベーションを推進する仕組みの問題点・課題
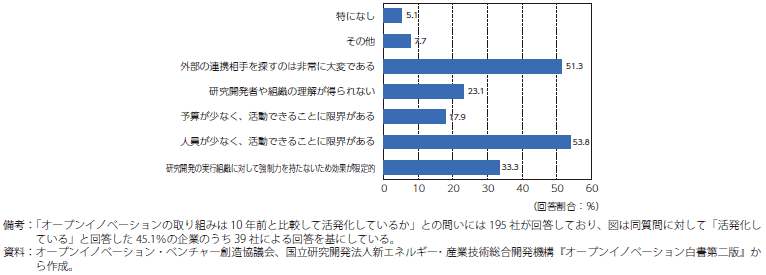
197 チェスブロウ(2004)。