第5節 分断の危機に直面する世界経済
1.20世紀以降の貿易大国の変遷と国際協調の動き
歴史を振り返れば、20世紀初頭から自由貿易と保護主義は約20年ごとに台頭してきた。世界経済は今、再び分断の危機に直面しており、本節では、令和元年版通商白書も踏まえながら、貿易大国の変遷を軸として20世紀以降の保護主義思想や懸念の高まりとそれを受けた保護主義抑止のための国際協調の動きについて概観する。
20世紀初頭に覇権国として力を付けていたのは英国である。1588年英国海軍がアルマダ海戦でスペインを破って以来、英国は数々の戦争を繰り返しながら植民地を広げ、その国威を発揚し続けてきた。1760年代には世界に先駆けて産業革命に成功し、国内産業が隆盛し「世界の工場」と呼ばれるまでの経済力を持った。特に、1814、1815年に行われたウィーン会議以降約100年間は「パクス・ブリタニカ」と呼ばれ、英国が世界的な覇権国となり帝国主義によるグローバリゼーションを進展させた。1900年当時では英国の貿易量が世界全体の約20%を占めていた。
1929年には世界恐慌が起こり、自国経済を守るために各国が保護主義的な措置を打ち出した。世界の貿易額は1929年約684億ドルから1932年には約270億ドルにまで落ち込んだ(第I-1-5-1図)。各主要国は共通通貨を用いた排他的な貿易体制を構築し、世界的なブロック経済化が進行した。
第Ⅰ-1-5-1図 貿易総額の推移及び主要国のシェア(第二次世界大戦前)
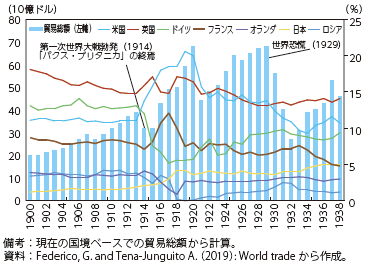
第二次世界大戦後に英国に代わって貿易大国となったのが米国である。1948年にはGATT体制が始まり、世界初の貿易多角化協定が結ばれ、関税の大幅な引き下げにより貿易自由化が進展した。1960年には世界の貿易量は1938年比で約5倍となったが、1970年代になると米国は貿易赤字拡大に伴い各国との間で貿易摩擦問題が生じるようになった(第I-1-5-2図)。
第Ⅰ-1-5-2図 貿易総額の推移及び主要国のシェア(1960年以降)
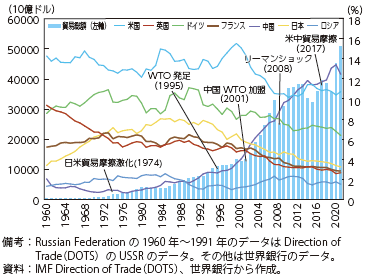
特に1974年に通商法(301条)が制定されてからは、日米間での貿易摩擦が激化し、米国は輸入制限措置の対象品目を次々と拡大していった。301条は日本の他、EC、カナダ、韓国等も対象に発動された。また、先進諸国における急速な経済発展の結果、これら先進諸国と発展テンポが相対的に遅い発展途上国との格差が拡大した結果、多くの発展途上国では輸入代替型の工業政策がとられ、高関税や数量制限等の保護主義的措置が導入された。このように、米国を中心に保護主義の動きが強まり、紛争処理手続等に強い規制力を持たなかったGATT体制の限界が露呈した。このような中、ドイツや日本は米国に次ぐ貿易大国となっていった。その背景として、貿易収支の不均衡によって日米貿易摩擦等重要な国際問題に発展する中で、従来は貿易黒字国の輸出自主規制が繰り返されてきたが、1970年代後半の「機関車論」や1985年の「プラザ合意」等で試みられたような国際マクロ政策協調や国際収支黒字国の黒字削減策(市場開放・輸入促進策等)の推進などの新たな対応が求められるに至った。日本は、輸入促進や市場開放のための規制緩和及び内需拡大政策を推進したが、経常収支不均衡の問題に対しては十分な成果を上げたとは言いがたい。実際に日米間の貿易収支を見てみると、日米間の輸出入総額は増加傾向にあり、日本から見た対米黒字は1987年の約600億ドルまで増加を続けた37(第I-1-5-3図)。
第Ⅰ-1-5-3図 日米間貿易の輸出入の動向
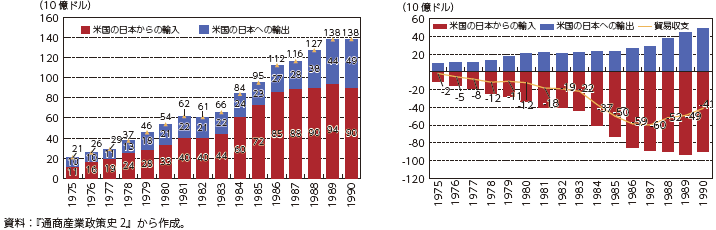
1995年にはGATT体制の紛争解決手続等を始めとする問題点を改善し、発展的な多角的貿易体制を構築するための枠組みであるWTO体制が発足したことで、世界は再び自由貿易の道を歩み始めた。2001年には中国がWTOに加盟し、中国は2010年には米国を抜き世界最大の貿易大国となった。その結果、2001年には中国のGDPが世界のGDPに占めるシェアは4%に過ぎなかったが、2017年には15%にまで拡大した。一方、世界のGDPに占めるアメリカのシェアは、2001年には31%であったが、2017年には24%とやや低下した。
2017年には米中財貿易赤字の大きさを問題視したトランプ政権が、貿易制限措置をかけるようになり、米中貿易摩擦が表面化した。また、米国のTPP離脱やWTO上級委員会の機能停止、英国のEU離脱などルールベースの国際枠組みからの離反が相次ぎ、2017年以降のG20、主要国首脳会談、IMF、WTO等で保護主義や貿易摩擦の緊張の高まりに懸念が示されるようになった。
さらに、2020年には新型コロナウイルス感染症が流行し、緊急時における自国中心主義という国際協調への遠心力が見られたが、一方で首脳・閣僚レベルで国際協調の求心力維持に向けた動きもなされた。こうした中、2022年2月にはロシアによるウクライナ侵略が開始され、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序が重大な挑戦にさらされている中で、G7、NATO、EUを始めとした同志国間での連携が際立っている。特にG7においては、2022年1年間だけでオンラインと対面を合わせ、首脳会合を6回も開催し、ロシアによる違法で、不当で、いわれのないウクライナに対する侵略戦争を非難し、国際的に認められた国境内におけるウクライナの独立、領土一体性及び主権に対する支持を確認するとともに、ロシア等に対する経済制裁の実施や、ウクライナへの財政的、人道的、外交的支援、世界の経済の安定、食料及びエネルギー安全保障への影響に対処にしていくこと等について、G7で協調して取り組んでいくことを確認した(詳細は第Ⅲ部第1章第1節参照)。
これに対し、G20はロシアや新興国を含む枠組みであり、ロシアの侵略をいかに扱うかが注目されたが、2022年11月にインドネシア主催で開催されたG20バリ・サミットでは、同国ジョコ大統領の指導力もあり、厳しい調整の末発出された首脳宣言に「ほとんどのメンバーがウクライナにおける戦争を強く非難した」と記載された38。
37 阿部武司(2013)『通商産業政策史2』、財団法人経済産業調査会。
38 外務省(2023)『令和5年度外交青書』より抜粋。
2.最近の国際動向
冷戦終焉から30年余り経った今、国際社会は歴史の転換点にある。自由・民主主義・人権・法の支配といった基本的価値に基づく自由で開かれた国際経済秩序が世界に拡大したことで、経済のグローバル化や相互依存が進み、国際社会に一定の安定や経済成長がもたらされた一方で、中国を始めとする新興国・途上国の台頭は、近年、国際社会にパワーバランスの変化をもたらし、地政学的な国家間競争が激しさを増している。また、一部の国家は急速かつ不透明な軍事力の強化を進め、独自の歴史観・価値観に基づき既存の国際秩序に対する挑戦的姿勢と自己主張を強めている39。経済成長の収入やテクノロジーの進展が覇権国家の軍事力増強と近代化に使用され、経済的な相互依存を逆手に取った経済的威圧が外交・安全保障上の武器として利用されるようになり、さらにはロシアのウクライナ侵略のような国際秩序への重大な挑戦が起きた。
このような状況の中、各国は輸出管理や投資規制等を強め、米国のインフレ削減法や「EUグリーン・ディール産業計画」等政府主導の積極的な産業政策の動きが見られている。
一方で、フォン・デア・ライエン欧州委員長も言うように、もはや権威主義国との完全なデカップングは不可能であり、デカップリングの進行は世界経済の成長の大きな下押しリスクとなる可能性がある。既述のとおり、2022年は同志国間での連携に向けた動きが目立ち、2023年1月に開催されたダボス会議では、「分断された世界における協力の姿」をテーマに議論がなされた。
本項では、米中間の経済的な結びつきの強さから改めて両国間のデカップリングの難しさを示した上で、デカップリングが世界経済に与える影響の試算について紹介する。また、自由貿易体制のルールメーカーであったWTOが機能不全に陥っている中で、EUを中心にWTO改革への取組と同時にWTOシステムの限界を見据え、それを補完する取組が行われている。このような自由で公正、包摂的な国際経済秩序の再構築に向けた国際協調の例として、経済的威圧に対する国際協調及び各国の取組について見ていく。
39 外務省(2023)『令和5年度外交青書』参照。
(1)米中の経済的な結びつきと貿易摩擦の動向
2022年の米中間の貿易総額は過去最大の6,906億ドルとなっており、両国の経済的な結びつきは引き続き強いと言える。特に、米国の中国からの輸入は5,368億ドルと2018年以来の高水準となり、2020年以降米国の貿易赤字は拡大傾向にある(第I-1-5-4図)。
第Ⅰ-1-5-4図 米中間の輸出入の動向
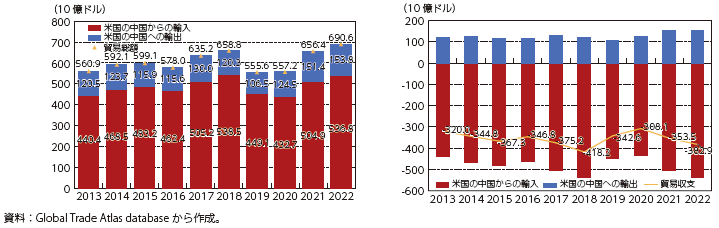
次に、最終用途分類別で見ると、2022年の対中輸出は大豆を始めとする「食品・飼料・飲料」、原油を始めとする「工業用原材料」が増加している。対中輸入は、携帯電話、おもちゃ、アパレル等の「消費財」や電気機器やコンピュータ付属品等の「自動車を除く資本財」が増加した(第I-1-5-5図、第I-1-5-6表)。
第Ⅰ-1-5-5図 米中間の輸出入の動向(最終用途分類別)
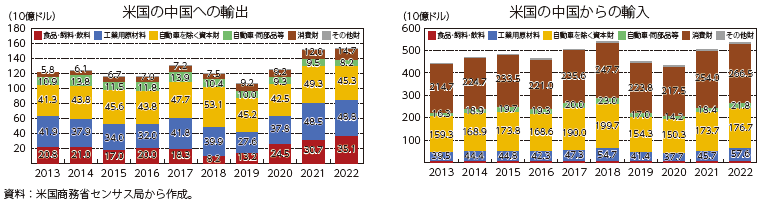
第Ⅰ-1-5-6表 米中貿易上位10品目
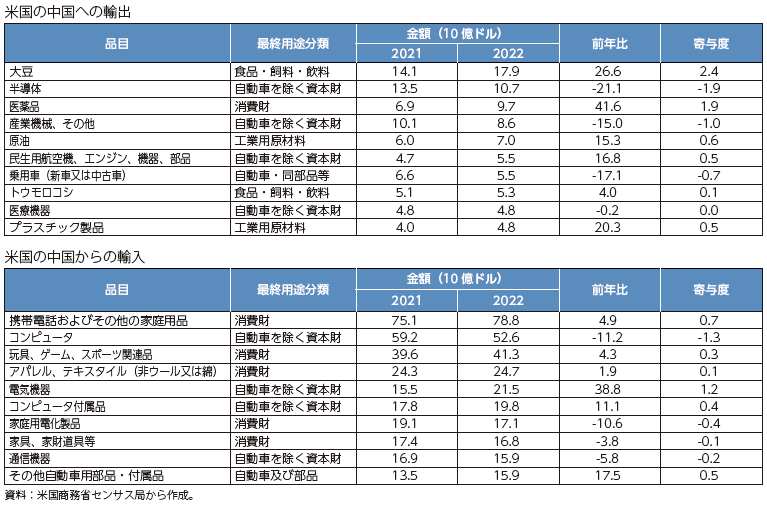
次に、米中間のハイテク分野における貿易について確認する。過去2年間のハイテク分野の輸出入額については、ともに微減となっている(第I-1-5-7図)。構成を見ると、中国からの輸入についてはその約9割を「情報通信」が占めるのに対し、輸出は「電子」「バイオテクノロジー」「航空宇宙」など多岐にわたっている。また、輸出において、2022年に前年比で最も減少しているのは「電子」(前年比-18%)であり、米国の中国に対する半導体の輸出管理規制(詳細は後述)の影響もあると考えられる。
第Ⅰ-1-5-7図 米中間のハイテク分野の輸出入動向
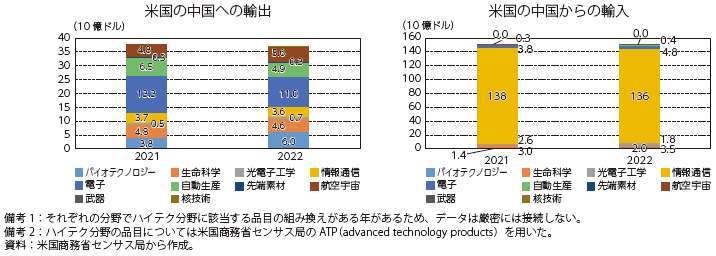
米中技術覇権争いに関係の深い、ハイテク分野の米国から中国への輸出について推移を確認すると、足下ではハイテク分野は輸出額全体の約25%を占めており、そのシェアは2020年以降低下していることが分かる(第I-1-5-8図)。
第Ⅰ-1-5-8図 米国の中国への輸出(ハイテク分野・非ハイテク分野別)推移
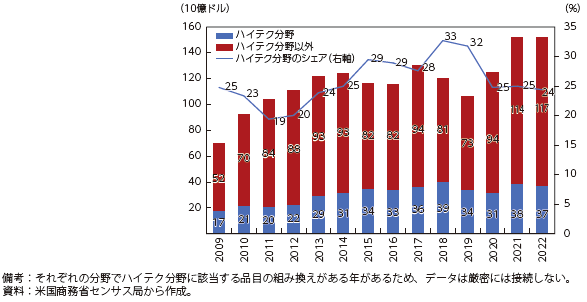
品目別で確認すると、2018年には約47%を占めていた「航空宇宙」が2020年以降は約13~15%までシェアを落としている一方、「バイオテクノロジー」は増加傾向にある。どの品目においても今後米国の輸出規制の対象となる可能性があり、引き続き注視が必要である(第I-1-5-9図)。
第Ⅰ-1-5-9図 ハイテク分野における米国の中国への輸出のシェアの推移(品目別)
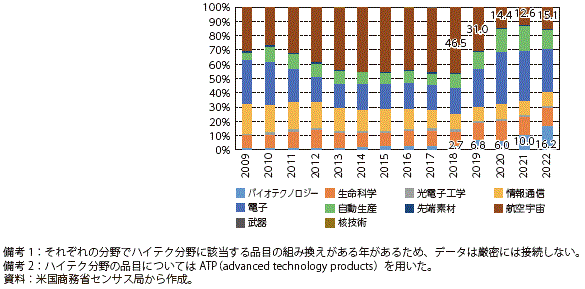
以上のように、ハイテク分野における米国から中国への輸出のシェアは低下傾向にあるものの、特に消費財等の米国の輸入の伸びは大きく、2022年の米国の対中貿易額は4年ぶりに過去最高となっている。
また、IMF(2023)40によれば、半導体等の戦略的部門における海外直接投資はデカップリングの傾向が強まりつつある。アジア諸国に対する戦略的FDIの流入は2019年に減少に転じ、2020年半ばにはやや持ち直したものの、中国への流入はまだ回復していない。また、この10年間、地政学的な立場を同じくする国間のFDIが占める割合は、地理的により近い国間のFDIが占める割合以上に増え続けてきた。仮に投資フローのデカップリングが進めば、長期的にはGDPを2%近く下押しすると試算している。
米国では、半導体製造能力に占める米国のシェアが著しく低下している41ことへの危機感もあり、半導体CHIPSおよび科学法(CHIPS and Science Act、以下CHIPSプラス法という)を2022年8月に成立させた。CHIPSプラス法は、2021年1月に成立した半導体産業向けインセンティブ制度のCHIPS(Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors)に5年で527億ドルの予算を充当した法律である。このうち390億ドルは半導体関連投資等補助基金として国内半導体関連投資を行う企業への資金援助に充てられる予定であり、2023年2月には商務省が、2030年に向けた目標及び補助金に関する詳細を公開した。また、第一弾として、最先端・現世代・成熟ノード半導体(後工程含む)についても受付を開始した42。米国半導体産業協会(Semiconductor Industry Association)によれば、このCHIPSプラス法によって約2,100億ドルの民間投資(2020年5月~2022年12月の集計)が発表されており、4.4万人の新規雇用を創出する見込みとなっている43。中国においては、2014年に国家IC産業投資基金を創設し、約1,390億元の資金枠を設定し、同基金の第二期基金として2019年に約2,040億元を設定し、半導体メーカーを支援している。
また、米国による中国への輸出規制はトランプ政権下では個別企業向けのものが多かったが、バイデン政権下では中国企業全体向けへと対象を拡大している。米国商務省産業安全保障局(以下、BISという)は輸出管理規則(EAR)に基づき、国家安全保障や外交政策上の懸念があるとして指定した企業を列挙したエンティティー・リスト(以下、ELという)を公表している。掲載された企業に物品やソフトウェア、生産・開発に必要な技術を輸出する際にはBISの許可が必要となる。2018年10月にはJHICC、2019年5月及び2020年8月にはHUAWEIとその関連会社、2020年12月にはSMIC、と中国の大手半導体メーカーが次々とELに追加された。また、外国直接製品規制(FDPR)は、再輸出規制の一種であり、米国外で生産された製品であっても、米国製の技術・ソフトウェアを用いている場合に、EARの対象として、輸出などについてBISの事前の許可申請を求めるルールのことであり、2020年5月、8月に制度化されて、HUAWEIとそのグループ企業向けに初めて適用された。バイデン政権下の2022年10月には、中国向けに輸出される、AI処理やスーパーコンピュータに利用される半導体、先進的な半導体製造に利用される半導体製造装置等に対する新たな輸出管理措置の導入を発表した。これらの規制においては、一定性能以上のスーパーコンピュータに利用される一定の半導体や一定性能以上の製造に用いられるすべての半導体製造装置の輸出を管理対象とするなど、規制の範囲は幅広いものとなっている。また、CHIPS法では、所謂ガードレール条項と呼ばれる規定が存在し、中国等の特定懸念国での先端半導体製造基盤の新増設の禁止、懸念企業との共同研究・技術供与の禁止が含まれており、2023年3月より60日間のパブリックコメントに付された。
近年の米中貿易摩擦の動向を見ていくと、2018年3月にトランプ前大統領が、1974年の通商法301条に基づく、中国に対する制裁措置を命ずる大統領覚書に署名して以降、2018年7月頃から米中間の関税引き上げ合戦が激化したが、2020年1月に第一段階米中通商合意に署名したことで両国の貿易摩擦は一段落の様相を呈していた44 45。このような状況下で2021年1月に発足したバイデン政権は、同盟国との協調を掲げている一方で、対中追加関税や経済安全保障を巡る輸出管理措置等は継続・強化している。2022年9月には、通商法301条に基づく中国原産品に対する追加関税の継続を発表し、11月~翌1月にかけて、見直しに向けたパブリックコメントを実施した46。
同10月には、「国家安全保障戦略」を発表し、中国を「国際秩序を再形成する意図と能力を備えた唯一の相手」と位置づけた。さらに、対中政策の調整や情報共有の強化を図るため、米国国務省は2022年12月にチャイナ・ハウス(Office of China Coordination)を新設した。また、現在米国議会は上下両院がねじれ、各種法案の成立が難しいと言われているなかでも、対中政策については、超党派で今後も活発な立法活動が見込まれており、2023年1月には下院が中国特別委員会を設立する決議案を可決した47。
このようにトランプ政権期以降顕在化した米中対立の背景には、技術を含む経済安全保障を巡る覇権争いがある。2022年9月には米国サリバン大統領補佐官が輸出管理や投資審査などの安全保障政策に関して講演を行い、米国が引き続き科学技術の優位性を保つことの重要性を示した。その戦略の四つの柱として①米国の科学技術エコシステムへの投資、②STEM(科学、技術、工学、数学)分野の高度人材育成、③米国の技術優位の保護、④同盟・パートナーシップの深化と統合を挙げている48。
仮に、米国と外交政策の類似度が高い諸国による西側陣営と米国によって経済制裁を科されている諸国による東側陣営との間でグローバルな「デカップリング」49が起きた場合、熊谷他(2022)50の試算によれば、米中貿易戦争並みの分断(非関税障壁の付加:シナリオ①)では2030年の世界のGDPへの影響は-2.3%、相互に100%の非関税障壁を設ける場合(シナリオ②)では同-7.9%となる。地域別では両陣営に分断される欧州、米国、東アジア各国については GDP に大幅なマイナスの影響が出る一方、グローバル・サウスなど中立的な国々は両陣営の対立によって「漁夫の利」を得ることが示された(第I-1-5-10図)。すなわち、デカップリングは両陣営に大きなダメージを与える一方、中立的立場を維持することで両陣営から利益を得ることのできるグローバル・サウスを自陣営へ引き入れることは難しいため、相手陣営を完全に世界から孤立させることは難しいことが示されている。
第Ⅰ-1-5-10図 「デカップリング」が世界経済に与える影響(上図:シナリオ①、下図:シナリオ②)
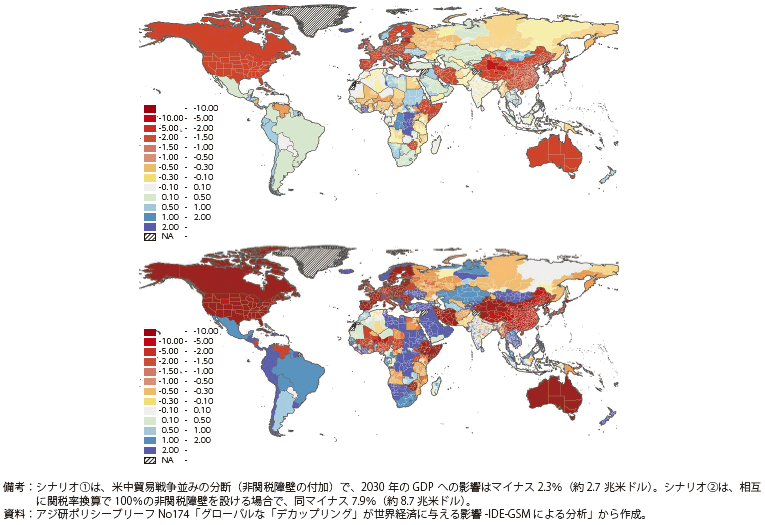
40 IMF「WEO」(2023年4月)。
41 Knometa Research「China's share of global wafer capacity continues to climb」(https://knometa.com/news/?post=china-039-s-share-of-global-wafer-capacity-continues-to-climb&tag=global-wafer-capacity![]() )参照。
)参照。
42 経済産業省「半導体・デジタル産業戦略(改定案)」から取得。
43 Semiconductor Industry Association「The CHIPS Act Has Already Sparked $200 Billion in Private Investments for U.S. Semiconductor Production」(https://www.semiconductors.org/the-chips-act-has-already-sparked-200-billion-in-private-investments-for-u-s-semiconductor-production/![]() )参照。
)参照。
44 経済産業省(2020)『令和二年版通商白書』第1 章第Ⅱ部第5 節第Ⅱ -1-5-7 表に日米貿易摩擦のタイムラインの記載あり。
45 第一段階米中通商合意に盛り込まれた「中国が米国から財・サービスの輸入を2017年水準から2000億ドル以上増加」は約束の2021年末時点で未達成となっている。
46 JETRO Webサイト(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/10/878f166b31c8c505.html![]() )参照。
)参照。
47 JETRO Webサイト(https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/01/5535e470d89c1944.html![]() )参照。
)参照。
48 JETRO Webサイト(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/09/7233677f51420994.html![]() )参照。
)参照。
49 デカップリングの想定として、世界が米国陣営(西側)、中国・ロシア陣営(東側)に分断されると想定し、各陣営に属する国は以下のように想定した。西側陣営は、米国と外交政策の類似度が高い国々34カ国・地域。すなわち、米国、英国、EU27カ国、カナダ、日本、韓国、台湾、豪州。東側陣営は、2023年1月時点で米国によって何らかの経済制裁を科されている国々のうち、IDE-GSMでカバーされている16カ国。すなわち、中国(香港、マカオを含む)、ロシア、ベラルーシ、キューバ、ベネズエラ、ニカラグア、イラン、イラク、イエメン、レバノン、ミャンマー、リビア、スーダン、コンゴ民主共和国、ジンバブエ、ソマリア。
50 アジ研ポリシーブリーフNo174「グローバルな「デカップリング」が世界経済に与える影響-IDE-GSMによる分析」熊谷聡、早川和伸他(2023.2)
(2)経済的威圧に対する国際協調及び各国の取組
近年、経済的威圧(economic coercion)と呼ばれる行為が多発している。経済的威圧には国際的に定まった定義はないが、一般的に経済的脆弱性及び経済的依存関係を悪用し、他国の外交政策及び国内政策並びにその立場を損なうことを企図するような行為を指すとされている。米国シンクタンクによれば、中国及びロシアによる経済的威圧に該当する主要な事例は131件にものぼっている51。経済的威圧について、G7首脳声明等で同盟国・同志国は懸念を表明し、その対応に向けて連携を模索しており、G7広島サミットにおいて「経済的強靱性及び経済安全保障に関するG7首脳声明」(2023年5月)が発出され、経済的威圧に対する共同の評価、準備、抑止及び対応を強化するため、「経済的威圧に対する調整プラットフォーム」を立ち上げ、連携を強化していくとともに、G7以外のパートナーとの協力を更に促進していくとした(第I-1-5-11表)。このように、基本的価値を共有する同志国とともに、経済的威圧に対する強靱性の促進及び抑止の両面から効果的な対応をとる動きが見られる。
第Ⅰ-1-5-11表 経済的威圧に言及した会談やスピーチ等の概要(2022年以降)
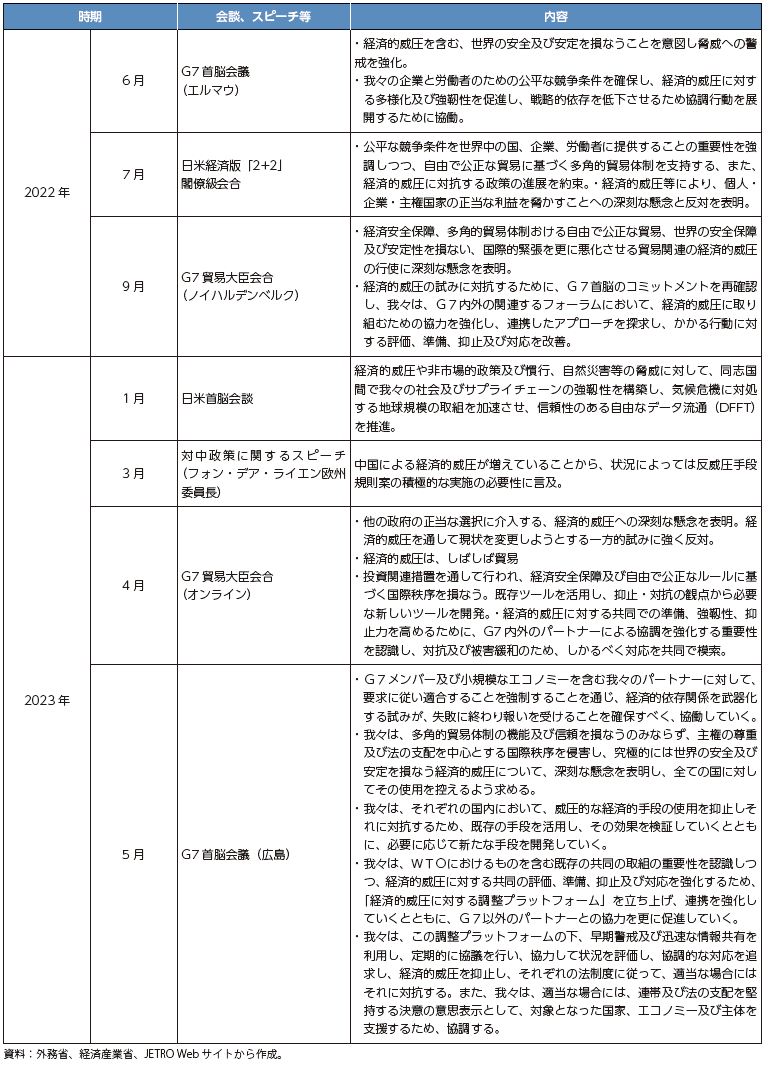
また、一部の国は抗議やWTO紛争解決手続に加え、経済的威圧に対応・対抗すべく関連法制度や戦略の整備・策定も進めている。
EUは、経済的威圧行為や市場歪曲的措置に対して、独自に対抗できる措置を相次いで公表しており、欧州委員会の提案に基づき、理事会・欧州議会の審議を経て順次、実行に移されている。欧州委員会は2021年12月、EU又は加盟国に対する非EU諸国による経済的威圧に対して、貿易・投資等に制限を課すことで迅速に対抗措置をとることを可能にする反威圧手段規則案を提案し、2022年10月に欧州議会、11月にEU理事会がそれぞれの機関として立場を決定し、2023年3月には暫定的な政治合意に達した。対抗措置としては、関税の引上げ、輸入・輸出許可の制限、サービスや公共調達の分野での制限などが含まれる52。
米国においては、2022年12月に成立した2023年度国防授権法(NDAA2023)の中で、2023年6月下旬までに関係省庁から成る「経済的威圧への対抗に関するタスクフォース(Countering Economic Coercion Task Force)」を設置し、中国による経済的威圧に対処するための統合戦略を策定・実施することとしている。具体的には、中国の慣行が米国企業及び米国経済のパフォーマンスに与えるコストの評価や、省庁間の政策調整、施策提言などを盛り込んでいる。
我が国では「国家安全保障戦略」(2022年12月閣議決定)において「本来、相互互恵的であるべき国際貿易、経済協力の分野において、一部の国家が、鉱物資源、食料、産業・医療用の物資等の輸出制限、他国の債務持続性を無視した形での借款の供与等を行うことで、他国に経済的な威圧を加え、自国の勢力拡大を図っている」とし、「世界貿易機関(WTO)を中核とした多角的貿易体制の維持・強化を図りつつ、不公正な貿易慣行や経済的な威圧に対抗するために、我が国の対応策を強化しつつ、同盟国・同志国等と連携し国際規範の強化のために取り組んでいく。」としている。 以上、本章では、ロシアによるウクライナ侵略による不確実性の高まりや世界的なインフレの高進等により減速感を強める世界経済の現状とともに、権威主義国の台頭により世界経済は今、分断の危機に直面していることを示すことで、世界経済はまさに岐路に立たされている状況にあることを示してきた。世界経済がある種の機能不全に陥る中で、次章では、世界経済の機能回復に向けた課題について示していく。
51 The German Marshall Fund「Tool: Economic Coercion」Webサイト参照。
(https://securingdemocracy.gmfus.org/asd_tools/strategic-economic-coercion/![]() )。事例数は2023年4月時点。
)。事例数は2023年4月時点。
52 JETRO Webサイト(https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/04/4eb32219bb2a435f.html![]() )参照。
)参照。