第1節 供給サイドの強化
本章では、足下の世界的なインフレは供給不足による側面が強いこと、インフレ緩和には設備投資等による供給力強化や生産性の向上、サプライチェーンの強靱化が重要であることを示す。
また、貿易の開放は生産性の上昇を通じて経済成長につながる一方、貿易相手国の不確実性は自国の貿易に負の影響を与えること、ただし、自由・民主主義・人権・法の支配といった基本的価値を尊重する貿易相手ほど、不確実性の高まりによる貿易減少効果が小さいことを示す。
そして、諸外国における経済安全保障政策を概観するとともに、自由で公正な貿易秩序と経済安全保障の両立に向け、我が国としてはルールベースの国際貿易秩序の再構築、有志国との信頼できるサプライチェーンの構築、グローバル・サウスとの連携強化の取組を同時に進めることが重要であることを示す。
また、持続可能で包摂的な経済成長及び発展の確保に向けた取組として、気候変動リスクへの対応や人権問題への対応に焦点を当て、その重要性を指摘した上で、諸外国及び我が国の取組について紹介する。
1.供給力の強化や生産性の向上によるインフレ圧力の緩和
まず本節では、足下で高まっているインフレ圧力がどのように生じたものであるかについて、需給均衡メカニズムの観点から概説し、足下で中央銀行が講じている金融引締め政策が需要抑制によるインフレ圧力の緩和であるのに対し、中長期的には、供給力を拡大することで生産の拡大とインフレ圧力の緩和を図っていくことが重要であることを示す。また、生産性の向上もインフレ圧力を緩和する上で重要であることを示すとともに、その手段としての貿易開放の重要性について示していく。
第I-2-1-1図は、⓪パンデミック前(2019年)、①パンデミック期(2020年)、②パンデミックからの需要回復期(2021年)、③ロシアによるウクライナ侵略以降(2022年)のそれぞれの時期における物価変動を需給均衡メカニズムの観点から概説したイメージ図である。まず、⓪から①に対しての変化は、経済社会活動の停滞に伴う需要曲線と供給曲線の左側シフトであった。供給能力以上に需要が減少したため、この時期の物価はパンデミック前と比して低水準であった。①から②の状態に移行するに連れ、経済社会活動の再開により主に欧米諸国で需要曲線は右側にシフトしていった一方で、労働市場に人が戻ってこず、また、財の供給元である新興国・途上国では依然としてパンデミックに伴う経済社会活動の制限のために供給は依然としてパンデミック前の状態には戻らなかったため、物価は上昇した。こうした状況の中、③ロシアによるウクライナ侵略により、エネルギーや食料供給リスクが高まり、供給曲線がさらに左側にシフトし、更なる物価上昇を招いた。このように整理すると、近年の物価上昇は供給サイドに起因するものであるということができる。
第Ⅰ-2-1-1図 需要曲線と供給曲線から見た価格変動メカニズム(イメージ)
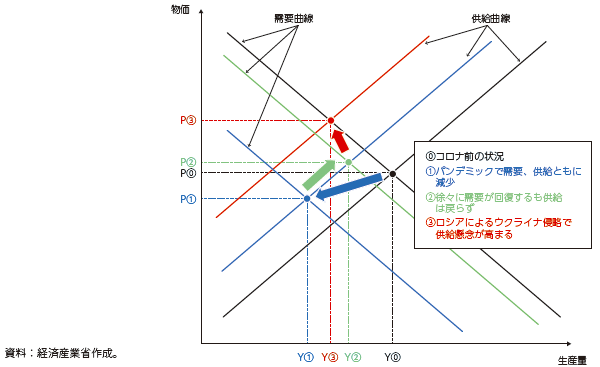
第I-2-1-2図は、インフレ圧力を低減させるための方策を需給均衡メカニズムの観点から概説したイメージ図であるが、足下で中央銀行が講じている金融引締め政策は、需要曲線を再び左側にシフトさせ、インフレ圧力を低減させようとするものである。ただし、この手法では、インフレ圧力を低減させるものの、需要の抑制を通じて生産量も減少することに留意が必要である。もう一つの方策は、供給能力の拡大を通じて、供給曲線を右側にシフトさせることにより、インフレ圧力を低減させるものである。ただし、設備能力の増強のための投資を行い、供給能力が拡大するまでには時間的なラグを伴う。この間、投資拡大は短期的には需要拡大を通じてインフレ圧力に作用することに留意が必要である。
第Ⅰ-2-1-2図 インフレ抑制に向けた方策
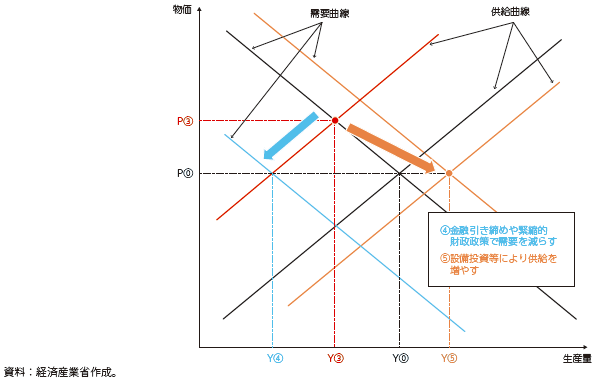
このように整理すると、近年の物価上昇が供給サイドに起因する側面が強いものであるにも関わらず、金融引締め政策を講じることは、需要の抑制を通じて経済を緊縮させうるものであり、労働力の減少やサプライチェーンの混乱等に伴う供給のボトルネックを早期に解消するとともに、これらの強靱性を高め、供給力を強化させることで、インフレ圧力を低減させると同時に経済成長を促していくことが重要であるということができる。
また、インフレ圧力を緩和するためには、供給力を強化するとともに、生産性を高めておくことも重要である。生産1単位当たりの労働コストを表す単位労働コストの上昇は、物価上昇圧力を高めると指摘されており、インフレ圧力を測る上での重要な指標となっている。第I-2-1-3図のとおり、この単位労働コストは、賃金と労働生産性の二つの要素に分解することができ、賃金の上昇は単位労働コストの上昇に、労働生産性の上昇は単位労働コストの低下に作用する。これを敷衍することで、労働生産性の上昇はインフレ圧力の緩和に作用するということができる。
第Ⅰ-2-1-3図 単位労働コストの分解
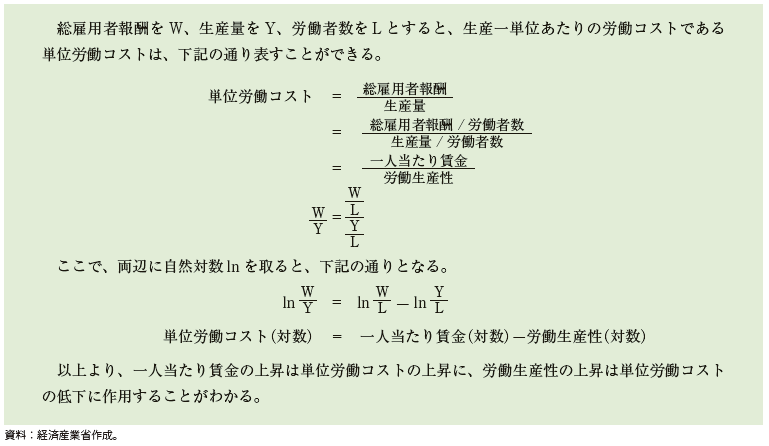
実際にこの関係を示したものが第I-2-1-4図である。本分析は、118か国の1950年~2019年までの長期データを用いて、インフレと生産性の関係を示しており、労働生産性をさらに全要素生産性と資本装備率に分解(第I-2-1-5図)して、それぞれがインフレに与える影響について推計したものである。なお、推計に当たっては、高齢化率の上昇がインフレ率の上昇に作用するとの指摘がなされている53ことも踏まえ、高齢化率も説明変数に加えている(分析の詳細については付注1を参照。)。これを見ると、全要素生産性、資本装備率ともに、他の要因をコントロールしたインフレ率と有意な負の関係があることが確認され、これらを高めることはインフレ圧力の緩和に資するといえる。
第Ⅰ-2-1-4図 労働者一人当たり資本ストック・全要素生産性のインフレ抑制効果
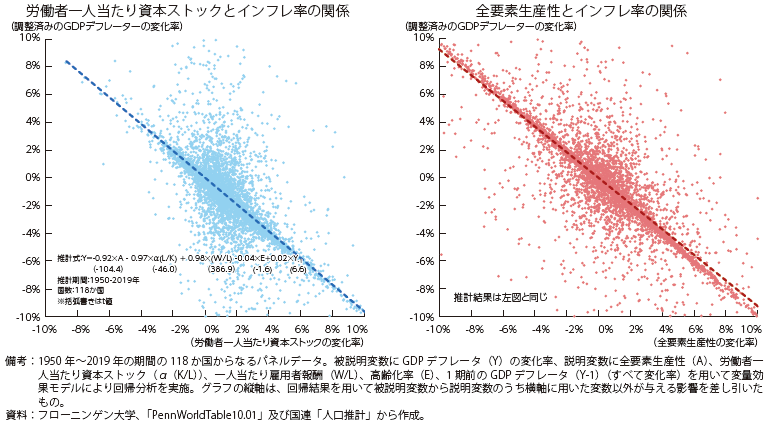
第Ⅰ-2-1-5図 労働生産性の分解
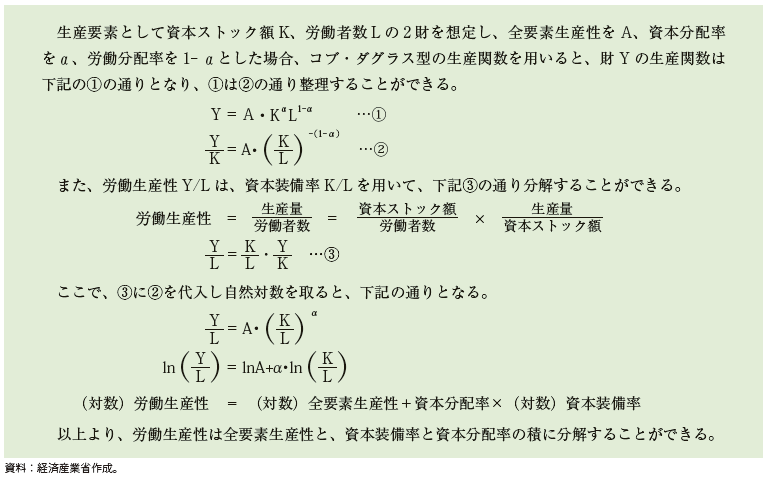
以上、足下で生じているインフレは、供給サイドに起因する側面が強いこと、これを緩和させるためには、供給力を強化させることが重要であること、生産性の向上もまたインフレ圧力を緩和させるという観点で有効であることを示した。次項では、貿易の開放度を高めておくことが生産性を向上させる上で重要であることを示すとともに、その効果は、多角的でルールに基づく貿易体制下での自由貿易を志向する国でより強く出ていることを示す。また、不確実性の高まりが貿易に与える負の影響について指摘するとともに、法の支配などを始めとするガバナンス評価が高い国との貿易ほど、その影響が小さいことを示す。
53 Goodhart, C., Pradhan, M., (2020), The Great Demographic Reversal : Ageing Societies, Waning Inequality, and an Inflation Revival, (澁谷浩訳(2022)『人口大逆転 高齢化、インフレの再来、不平等の縮小』日経BP 日本経済新聞出版。).
2.貿易の開放を通じた生産性の向上
前項では、インフレ圧力を緩和させるために生産性の向上が重要であることを示したが、世界経済がこの難局を乗り越えるという観点からは、各国が貿易の開放度を高めることを通じて、貿易に参加する国々の生産性を高めていくことは、一つの有効な手段であるといえる。本項では、貿易の開放度が生産性に与える効果について分析を行うとともに、貿易相手国の不確実性が自国に対して与える負の影響についても分析を行い、貿易のレジリエンシーを高めつつも、自由貿易の果実を享受可能とするパートナーシップの構築の在り方について示していく。
まず、世界の貿易の開放度がどのように変遷してきたかを見ていく。貿易の開放度については様々な尺度があるが、本分析ではSqualli and Wilson (2011)54が考案したComposite Trade Share(以下、CTSという)を用いて見ていくこととする。例えば、貿易開放度を貿易額の対GDP比で測ると小国が上位になりやすくなり、逆に貿易額の世界シェアを用いると経済規模の大きな国が上位になりやすくなるなどの傾向が見られるが、CTSは貿易額対GDP比や貿易額の世界シェアの双方の情報を取り込みつつ、経済規模を考慮した上で貿易の開放度を測定しているという点で指標として優れている。第I-2-1-6図は世界各国のCTSの第一四分位値(下位25%)、中央値、第三四分位値(上位25%)を示したものである。これを見ると、第三四分位値が中央値を大きく上回っており、貿易開放度の高い国は一部の上位国に限られており、これらの上位国ではグローバル化の進展とともに2000年代にCTSが大きく上昇したものの、2010年代以降は低下傾向にある。第I-2-1-7図は2019年時点における各国のCTSをマッピングしたものである。これを見ると、欧米諸国に加え、日本、韓国、豪州、それに中国、ロシア、一部の中南米諸国、東南アジア諸国が上位に来ていることが分かる。
第Ⅰ-2-1-6図 貿易開放度(CTS)の分布
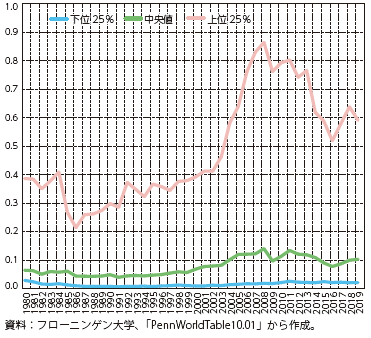
第Ⅰ-2-1-7図 世界各国の貿易開放度(CTS)の分布(2019年)
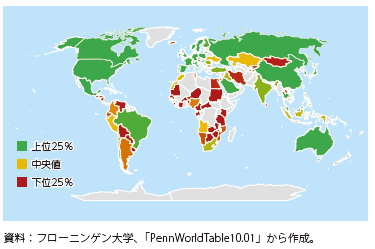
次に、貿易開放度が生産性に与える影響について検証を試みる。具体的には、日本経済研究センター(2019)55を参考にしつつ、生産性の指標として一国の全要素生産性の水準を用い、上記で確認したCTSが全要素生産性に与える影響について検証を行う。その際、全要素生産性に影響を与えうる他の指標として高齢化率を説明変数に用いたほか、経済規模をコントロールする観点から説明変数には実質GDPも含めている。また、全要素生産性がCTSに影響を与えうるという逆因果をコントロールするために、1年前の全要素生産性を操作変数に用いて推計を行った(分析の詳細については付注2を参照)。第I-2-1-8図は、CTS以外の要因(ここでは高齢化率、実質GDP)が全要素生産性に与える影響をコントロールした全要素生産性とCTSとの関係について見たものであるが、CTSが高くなるほど、全要素生産性が高くなるという関係が見て取れる。ここで着目すべき点としては、サンプルをOECD加盟国とそれ以外に分けて見てみると、OECD加盟国ではCTSが高まるほど全要素生産性が高くなる傾向が顕著であり、かつ、サンプルのばらつきも小さいことが確認できる。OECD加盟国とはすなわち、多角的でルールに基づく貿易体制下での自由貿易を志向する諸国の集まりであり、こうした目的を重んじる諸国では貿易の開放を通じて全要素生産性を高める効果が大きいことの一例を示しているといえる。
第Ⅰ-2-1-8図 貿易開放度と全要素生産性
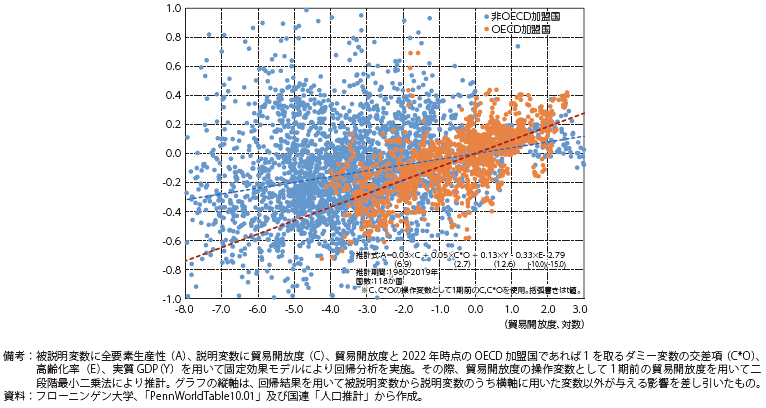
このように、貿易開放度を高めることで生産性が高まることを示してきたが、貿易開放度を高めることには一定のリスクを伴うことにも留意が必要である。ここでは、貿易相手国の不確実性の高まりが自国の貿易を減少させうることを示していく。以降、分析手法について解説していく。基本モデルとして、自国と相手国との貿易量は、自国と相手国との間の物理的な距離と経済規模に比例するという重力モデルの考え方にのっとり、被説明変数を自国と相手国との貿易額、説明変数を自国と相手国との距離、名目GDP、さらに世界不確実性指数のデータセットに含まれる貿易不確実性指数を加え、固定効果モデルで推計を行い、距離とGDPをコントロールした上で、相手国の貿易不確実性の高まりが自国の貿易額に与える影響を計測する。その際、貿易不確実性指数の操作変数として、世界銀行が公表する世界ガバナンス指標(Worldwide Governance Indicators(WGI))を用いることで、貿易相手国のガバナンス状況が貿易の不確実性を通じて自国の貿易に与える影響を計測する形とし、自国が貿易上の不確実性を如何にコントロールすればよいか示唆を与えるものとする。世界ガバナンス指標とは、世界銀行が世界各国のガバナンス状況を評価するために作成した指標であり、「国民の発言力と説明責任(Voice and Accountability)」、「政治的安定と暴力の不在(Political Stability and Absence of Violence)」、「政府の有効性(Government Effectiveness)」、「規制の質(Regulatory Quality)」、「法の支配(Rule of Law)」、「汚職の抑制(Control of Corruption)」の六つの指標が存在する(第I-2-1-9図)。推計に当たっては、これら六つの指標を主成分分析により一つに集約化した指標を作成し、これを操作変数として用いることとする(分析の詳細については付注3を参照。)。
第Ⅰ-2-1-9図 世界ガバナンス指標(2021年)
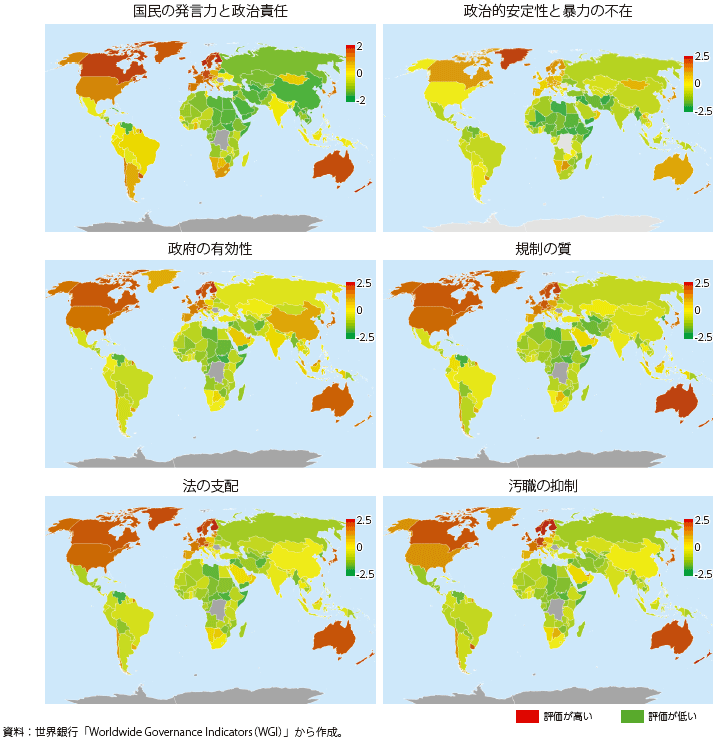
第I-2-1-10図は、上記の推計に基づいた、2000年以降のガバナンス評価と貿易相手国の不確実性の高まりによる自国の貿易減少効果の関係について、貿易開放度の高い国に焦点を当て図示したものであるが、貿易相手国のガバナンス評価が高くなるほど、貿易相手国の不確実性の高まりによる自国の貿易減少効果が小さくなる傾向があることが分かる。この結果は、自国が貿易パートナーシップを構築していく上で、貿易相手国のガバナンス評価が重要なシグナルとなっていることを示唆している。
第Ⅰ-2-1-10図 世界ガバナンス指標と不確実性の高まりによる貿易減少効果の関係
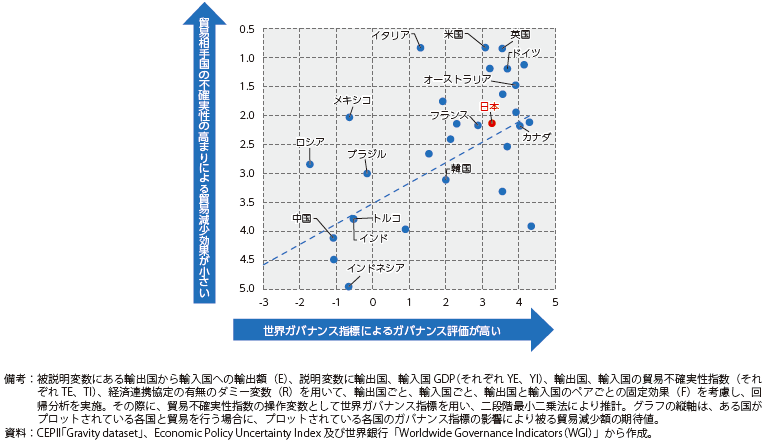
以上をまとめると、自国の貿易のレジリエンシーを高めつつ、自由貿易による生産性の向上を通じた経済成長の実現へとつなげるためには、貿易自由化、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった価値を重んじる国とのパートナーシップを深めることが重要であるといえる。
54 Squalli, J., and Wilson, K. (2011), “A new measure of trade openness”, The World Economy, 34(10), 1745-1770.
55 日本経済研究センター(2019)「貿易取引の停滞、世界的な生産性低下の恐れ -自由貿易の枠組み広げる取り組み重要に-」経済百葉箱第137号