第2節 自由で公正な貿易秩序と経済安全保障の両立
1.経済安全保障の類型
「経済安全保障」という概念は、冷戦直後に米国のクリントン政権が、米国の政策課題の中心として経済の重要性を強調するために用いたことから急速に一般化した56。E.H.Carr(1939)は、1930年代末に「政治と経済の分離」を「幻想」と批判し、「政治経済学」を唱導していた57が、冷戦時代には経済と安全保障の分離が当然視され、安全保障は専ら軍事的観点から考察されてきた。こうした中、冷戦が終結し、主要国間の国家中心、軍事中心の伝統的な安全保障問題が遠景に退く中で、国同士の相互依存の深まりから他国の経済政策や国際経済体制の運営・管理に一段と敏感になり、国外から国内経済への影響を「安全保障」問題と表現する度合いが高まってきたからと考えられる。さらに、2018年8月に成立した米国の国防権限法により、米国の輸出管理の強化および安全保障上の投資審査の強化が図られたことは、更に経済と安全保障の密接な結びつきを印象づけた。
「経済安全保障」という言葉は様々な意味で用いられているが58、「国家安全保障戦略」(2022年12月閣議決定)で「我が国の平和と安全や経済的な繁栄等の国益を経済上の措置を講じ確保すること」と定義された。本項では、まず、「経済安全保障」を考えるにあたっていくつかの論考を紹介する。
鈴木(2022)は、「経済安全保障」について、「供給の安全保障」「技術の不拡散の安全保障」「他国の規制からの安全保障」と三つに分類している59。「供給の安保障」はすなわちサプライチェーンの安全保障であり、2022年5月に成立した「経済安全保障推進法」の四つの柱の一つにもなっている。他国においてもサプライチェーン見直しの動きは顕著であり、例えば米国バイデン政権は2021年2月に重要製品の国内サプライチェーンを強化するための大統領令14017号に署名し、半導体製造、バッテリー、レアアース、医薬品等4分野の重要製品に関するサプライチェーンのリスク特定とリスクへの対処方法をまとめた報告書を同年6月にまとめさせた60。さらに、翌年2月にはエネルギー、運輸、農産物・食料生産、公衆衛生、情報通信技術、防衛の6分野についてもサプライチェーンを強化する戦略を含めた報告書がまとめられた61。
「技術の不拡散の安全保障」は貿易等を通じて技術が拡散・流出することで、他国の軍事能力が強化されたり、我が国の国際競争力が低下することが懸念される。米中対立は新興技術を巡る技術覇権競争の側面も大きく、我が国としてもこのような世界的な技術覇権競争の中で、「技術の不拡散の安全保障」の重要性が高まっている。
「他国の規制からの安全保障」については、例えば、米国の「グローバル・マグニツキー人権問責法」とそれに対抗する中国の「反外国制裁法」を巡る動向が挙げられる。このような他国の法律や規制はコントロールすることが難しく、日本企業はこれらの法律や規制にあわせて企業行動を変更させる必要を迫られる。
飯田(2023)は、経済安全保障を「経済が軍事力に影響する場合」及び「経済が交渉力に影響する場合」の二つの類型に整理している62。前者は、輸出管理、投資審査、武器移転、武器の国産化などが挙げられ、後者は経済制裁・経済的共生、エネルギー・食料安全保障、関与政策、サプライチェーンの多角化・強靱化などが挙げられる。
56 野林健、大芝亮、納家政嗣、山田敦、長尾悟(2007)『国際政治経済学・入門第3版』、有斐閣アルマ。
57 Edward Hallett Carr, The Twenty Year’s Crisis,1919-1939:An Introduction to the Study of International Relations(London:Macnillan,1939),pp.147,149
58 例えば、野林健他(2007)『国際政治経済学・入門第3版』においては、「ごく一般的にいえば、経済安全保障とは、「国家やそれを支える国民経済の一体性、その維持、発展が脅かされているという認識の下にとられる対外経済政策、あるいは経済(財、その交換にかかわるさまざまな行為)を『力の資源(手段)』として市場ルールを逸脱して用いる行為およびその相互作用」と定義できる」としている。長谷川将規(2013)『経済安全保障』(日本経済評論社)においては「最低限の共通項として、「安全保障の構成要素である、目標、脅威、手段のいずれかに経済的な要素が入り込んだ場合、これを経済安全保障と呼ぶのが一般的である」。」としている。
59 鈴木一人(2022)「自由貿易体制における経済安全保障」(http://ssdpaki.la.coocan.jp/proposals/102.html![]() )。
)。
60 米国ホワイトハウスWebサイトから取得(https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf![]() )。
)。
61 米国ホワイトハウスWebサイトから取得(https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/the-biden-harris-plan-to-revitalize-american-manufacturing-and-secure-critical-supply-chains-in-2022/![]() )。
)。
62 公益財団法人日本国際問題研究所「経済・安全保障リンケージ研究会最終報告書」(2023年3月)。
2. 自由貿易体制における経済安全保障
前項で見てきたように、安全保障の裾野は経済や機微・新興技術にまで拡大している。機微技術・新興技術は、将来の国家の競争力を左右する重要な技術であることから、国際平和を脅かすおそれのある国家やテロリスト等への流出を防ぎ、経済安全保障を確保するため、各国において輸出管理制度の強化を含めた様々な対策が進められている。また、近年では機微技術・新興技術獲得を目的とした企業の買収・合併等の対内直接投資が増加していることから、各国において対内直接投資管理制度の強化も進められている。また、新型コロナウイルス感染症拡大やロシアによるウクライナ侵略は、サプライチェーンのぜい弱性を明らかにし、各国は同志国との連携を模索する一方で、国内産業政策の強化を図っている(第1部第1章第5節「分断の危機に直面する世界経済」参照)。
本項では、経済安全保障への各国の対応として産業政策、輸出管理、対内直接投資管理等の動向についてまとめた上で、2023年G7議長国である日本が国際社会に対して果たすべき役割について触れる。
(1)経済安全保障への各国の対応
① 米国
産業政策
バイデン政権は2021年4月、「米国雇用計画」と「米国家族計画」を議会に提案した。前者はインフラ投資や供給網の強化、後者は人的投資や気候変動対策を柱としている。議会は「米国雇用計画」のうち、インフラ分野に特化した1兆2,000億ドル規模(今後5年での新規支出は5,500億ドル)の超党派法案を提出し、2021年11月に「インフラ投資雇用法」として成立させた。
他方で、「米国家族計画」を受け、民主党内で、気候変動対策や人的投資を盛り込んだビルド・バック・ベター法案が作成された。その予算規模は、1兆8,500億ドルに及んだが、支出規模が大きく政府債務の増加や高インフレの助長につながるなどの理由から民主党内からも反発があり、法案成立は頓挫した。その後、支出規模の縮小や歳入の確保等を入れ込んだ形で2022年8月に成立したのが「インフレ削減法(Inflation Reduction Act、以下IRAという)」である。IRAは、気候変動対策に約3,700億ドルの財源が確保されており、気候変動対策に関する米国史上最大の歳出法案となった。具体的には、太陽光パネル、風力タービンなどを製造するための設備投資等クリーンエネルギー導入に伴い認められる税額控除や電気自動車(Electric Vehicle、以下EVという)の購入に伴う税額控除等により、クリーンエネルギーのインフラ投資を促すものである。法案成立の背景には、バイデン政権が2021年4月の気候変動サミットで、パリ協定の下での2030年目標として「温室効果ガス排出量を2005年比で50-52%削減する」との目標を発表していることがあげられる。米国のシンクタンク戦略国際問題研究所(Center for Strategic and International Studies、以下CSIS)のレポート(2023年3月)によれば、IRA成立以来、欧州の大手企業を含む約20の企業がクリーンエネルギー生産施設の新設・拡張を発表し、10万人以上の新規雇用が米国で創出される見込みである63。
輸出管理政策
2018年8月に成立した輸出管理改革法(Export Control Reform Act、以下ECRA)によって、軍民両用のデュアルユース貨物等の輸出管理が実施されている。ECRAは、国防総省に予算権限を与える2019年度国防授権法(NDAA2019)の一部として成立しており、ECRAの中で「新興技術」(emerging technologies)や「基盤的技術」(foundational technologies)を追加することとしている。さらに、ECRAの下位規則である輸出管理規則(Export Administration Regulations、以下EAR)には、米国政府が軍事転用リスクのあるデュアルユース品目と指定した製品を掲載するリスト(Commerce Control List、以下CCL)やエンティティリスト(Entity List)等が含まれており、米国原産品等の輸出・再輸出等が規制されている。
2019年8月にはNDAA2019に基づき政府機関によるHUAWEIやZTEなど中国ハイテク企業5社などからの調達を禁じる規則が施行され、通信機器・ビデオ監視装置またはそのサービスの調達・使用が禁止された。2020年8月には、政府機関がHUAWEIなど懸念企業から製品などを調達している企業と契約することを禁じた。
2022年12月には2023年度国防授権法(NDAA2023)が成立し、主な対中条項として、既述の「経済的威圧への対抗に関するタスクフォース(Countering Economic Coercion Task Force)」の設置や、台湾に対して2027年までの5年間に計100億ドルの軍事支援、中国製半導体の政府調達の禁止(中芯国際集成電路製造(SMIC)、長鑫存儲技術(CXMT)、長江メモリ(YMTC)、及びこれらの子会社によって設計・製造された半導体が対象)、などが盛り込まれている。
対内直接投資管理政策
投資規制については、外国人による対内直接投資等を審査する権限を有した省庁横断的組織として、対米外国投資委員会(CFIUS)が、米国の経済安全保障に及ぼす影響を判断している。NDAA2019の一部として盛り込まれた外国投資リスク審査現代化法(Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018)により、CFIUSの審査権限が強化された。具体的には、新興技術や重要インフラに関する対内直接投資について、外国政府の影響下にある投資家による投資のうち、企業経営に影響を与えるものは、新たに事前審査が義務化された。2022年9月にはCFIUSが重点的にフォローすべき分野・要因を定めた大統領令が発出された64。
さらに、対内投資規制だけではなく対外投資に対する規制についても議論がなされており、2022年6月には上院及び下院の超党派議員団が国家重要能力防衛法案(National Critical Capabilities Defense Act of 2022)を発表した。内容としては、政府機関の長で構成される「国家重要能力委員会(NCCC)」を新設し、中国等懸念国へ向けた投資を審査する責任を持たせる。CFIUSの対外投資版と見られるが、産業界などから強い反発が出ている。
その他、アプリに関する規制として、2021年6月には、トランプ政権によるTikTokとWeChatの利用を禁止する大統領令及び電子決済サービス「アリペイ」など八つの中国製アプリを制限する大統領令を無効とし、米国機微データを保護するための大統領令を発出した。2023年2月には、連邦政府機器でのTik Tok使用禁止に向けたガイダンスが発表され、すべての連邦政府でTik Tokに加えTik Tokの親会社である中国のバイトダンスが開発・提供するそのほかの後継アプリサービスの使用が禁止されることとなった65。2023年3月には下院外交委員会がTik Tok等の動画アプリの米国内運用を事実上禁止する法案DATA Act(Deterring America’s Technological Adversaries Act)を可決し、上院情報委員会でも超党派で同趣旨の法RESTRICT Act(Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act)が提出された。
63 CSIS“Getting Real on the Inflation Reduction Act” (https://www.csis.org/analysis/getting-real-inflation-reduction-act![]() )
)
65 JETRO Webサイト参照(https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/03/b0f6ff29793ec8af.html![]() )。
)。
② 中国
産業政策
中国では、対外開放路線を継続しつつ(国際循環)、内需を拡大しながら(国内大循環)、自国の巨大市場の魅力により諸外国の投資・技術を引きつけるという「双循環政策」を第14次5カ年計画(2021~2025年)で打ち出している。「自主的・コントロール可能なサプライチェーンの能力強化」としてサプライチェーンの主要部分は国内にとどめておき、強制的な技術移転を迫るなど、先進的なコア技術の国産化を推進することで外国企業の中国依存度を強化している。また、これによりサプライチェーンの断絶に対する抑止力の構築にも成功しているといえる。最近の外資誘致の動きとして、2022年10月「外商投資奨励産業目録」が改定され、前年から200以上の項目を追加され、特に先端製造業分野の項目拡充(エネルギー、医療、金属、光学材料など)が目立った。外資系企業はこの目録に含まれている産業に投資する場合に政府から税制優遇などを享受することが可能となっている。また、同月「製造業を重点とする外資の投資促進措置」が発表され、外資誘致として重視する分野に、先端製造業・ハイテク分野、情報通信・ソフトウェア・情報技術、金融、不動産、ビジネスサービス、教育などの研究開発・設計、現代物流、新エネルギー、グリーン・低炭素に関する技術イノベーションなどが挙げられた。
また、2015年に発表した「中国製造2025(Made in China 2025)」を継続し、5Gを含む次世代情報技術、新材料、バイオ医薬品など、10の戦略ハイテク分野で国内産業の高度化を目指して、中国政府はこれら重点分野に国有企業だけでなく民営企業含め幅広い企業に対して柔軟な支援を行っている66。また、2023年3月の「党・国家機関改革案」が公表され、中国共産党中央委員会に新組織を設けることで、科学技術や金融分野について党中央の集中的・統一的指導を強化している67。
輸出管理政策
中国は足下で輸出管理を強化している。一般的な技術の輸出禁止および輸出制限に関しては、「輸出禁止・輸出制限技術目録」に基づき管理されており、2020年8月には12年ぶりに「輸出禁止・輸出制限技術目録」の大幅改正を行い、中国の昨今のテクノロジーの発展や安全保障的な観点等を背景に、人工知能(AI)、暗号・ITセキュリティ、バイオテクノロジー、工作機械・プラント、航空宇宙等の関連技術が追加された。2022年12月には「輸出禁止・輸出制限技術目録」改訂のパブリックコメント草案が公開され68、生物研究、希土類、太陽光発電、スマートカーなどの技術品目が追加された。
2020年9月には「信頼できないエンティティ・リスト」制度が公布・施行された。外国企業が正常な市場取引の原則に反して、特定の中国企業との取引の中断等、差別的な措置を講じ、取引先中国企業の正当な権益を損なっているなどとして本制度を導入したとされる69。2023年2月に本制度を初運用し、台湾への度重なるミサイルや戦闘機などの攻撃兵器売却によって、中国の安全と主権・領土の完全性を損なったためとして、米国のLockheed Martin社とRaytheon Missiles & Defense社の2社をリスト入りさせた。これにより、両社に対しては、中国と関係する輸出入活動や投資を禁じる等五つの措置がとられることとなった70。
2020年12月には輸出管理法が施行された。それまでは、両用品目、軍用品、核等国家安全保障貿易管理の観点からの輸出管理規制が存在したが、体系的ではなく不十分と考えられていた。そこで、安全保障貿易管理の観点からの輸出を包括的、全体的に管理規制する基本法と規制品リストの整備や、特定品目の輸出を禁止する主体を定めるリストの導入、みなし輸出、再輸出規制導入、域外適用の原則、報復措置について記載されている。
対内直接投資管理政策
2021年1月国家発展改革委員会と商務部は、国家安全法に基づき、国家安全に影響する投資等への事前審査を明記した「外商投資安全審査弁法」を施行した。2020年1月に施行された外商投資法では「外商投資安全審査制度を構築し、国家安全に影響をもたらす、または影響をもたらし得る外商投資に対して安全審査を行う」ことが規定されており、同弁法により、審査の対象範囲や申告・審査のプロセスを明確化する意図があったものと解し得るが、今後の運用を注視していく必要がある71。
また2022年10月の共産党大会での政治報告では、国家安全保障の章が設けられ、国家安全保障は民族復興の基盤であり、国家富強の前提であるとした上で総体的国家安全保障観72を揺るぎなく貫徹するとしている。
66 経済産業省(2022)『令和四年版通商白書』 第Ⅰ部第2章第4節「中国経済の動向」。
67 JETRO Webサイト参照(https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/03/1da9488b36d5a331.html![]() )。
)。
68 CISTEC Webサイト参照(https://www.cistec.or.jp/service/uschina/63-20230131.pdf![]() )。
)。
69 JETRO Webサイト参照(https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/580a6448fa87f0bb/20210056_02.pdf![]() )。
)。
70 JETRO Webサイト参照(https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/02/ac9dbb6d2bab4f0d.html![]() )。
)。
71 JETRO Webサイト参照(https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/01/72daea1b41a678f9.html![]() )。
)。
72 習近平国家主席が2014年から提唱しているもので、人民の安全を目的として政治の安全と経済の安全を基礎として行く考え方。政治、国土、軍事、経済、文化、社会、科学技術、情報、生態、資源、核の11分野を対象。2015年にこの考え方を含めて「国家安全法」が制定された。
③ EU
産業政策
EUは2023年2月に「EUグリーン・ディール産業計画」として、欧州域内への投資を促進する計画を発表した。欧州委員会は、米国のIRAに対し、ネット・ゼロ産業などを念頭にEUの競争力に対する脅威とし、同計画はIRAに対する対抗策だと明言している73。具体的には、欧州のネット・ゼロ産業の競争力強化のため、既存予算を含む総額2700億ユーロと今後発表予定の欧州主権基金を活用する。また、重要原材料や水素等の重要セクターの規制環境整備、資金への迅速なアクセス確保、人材育成、貿易協定等による貿易促進を通じて、クリーン技術の域内確保を目指す。施策としては、2023年3月に国家補助金の暫定危機・移行枠組(緩和策)74、重要原材料法、ネット・ゼロ産業法などを発表した。
輸出管理政策
2021年9月には輸出管理規制の見直しが行われ、サイバー監視技術など軍事・安全保障に使用される可能性のある民生品や技術(デュアルユース品目)に対する管理を強化し、人権侵害に利用されうるサイバー監視品目の輸出に対する許可制を導入した75。
2023年3月にはフォン・デア・ライエン欧州委員長が「future of EU-China relations」と題するスピーチを実施し、経済リスク回避の必要性の中で、年内後半にEUとしての「経済安全保障戦略」策定に初めて言及し、6月には同戦略の政策文書を発表することが公表されている。
対内直接投資管理政策
これまで安全保障の観点からの対内投資規制について、EUとしてまとまった形でのルールが存在しなかったが、2020年10月に「対内直接投資審査規則」が全面適用された。安全保障や公の秩序の保護を目的に、域外からの直接投資に対し、その是非を審査するものであり、投資規制の導入、内容、判断は加盟国の判断に委ねられているが、ドイツやフランス、イタリアなどの主要国では同規則に準拠するかたちで自国の投資スクリーニング制度の強化が行われた76。同規則では外国投資の審査時に検討すべき要素を例示しており、例えば審査対象とすべき重要技術には人工知能、ロボティクス、半導体、サイバーセキュリティ、航空・宇宙、防衛、エネルギー貯蔵、量子・核技術、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーなどが含まれる。
73 JETRO Webサイト参照(https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/02/61fa6e9285deed7f.html![]() )。
)。
74 域外への投資移転の抑止等を目的とし、補助上限額の引上げを含めた補助金ルールを緩和。
75 欧州委員会Webサイト参照(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4601![]() )。
)。
76 JETRO Webサイト参照(https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/10/9d4da3edbc8c7938.html![]() )。
)。
(2)自由貿易体制の維持に向けた日本の役割
歴史を振り返れば、自由主義と保護主義の台頭は繰り返されてきたが、自由貿易が世界経済の成長を促進してきたことに疑う余地はない。日本は、第二次石油危機後、それまで自由貿易体制を推進してきた米国の経済力が低下していた中で保護主義がまん延した際も、一貫して輸入自由化を推進し、多国間貿易交渉東京ラウンドの成功にも大きな役割を果たし、世界の自由貿易体制の維持のためにリーダー・シップを発揮した77。2023年は日本がG7の議長国を務めた年であり、自由貿易の旗を掲げ、自由で公正、包摂的な経済秩序の構築に向けリーダー・シップを発揮し、自由貿易に伴うリスク低減に同志国と連携して取り組んでいく。まず、我が国は、インド太平洋経済枠組み(IPEF)、サプライチェーン強靱化イニシアティブ(SCRI)、日米豪印、CPTPPや日EU・EPAを含む経済連携協定といった同志国での枠組みを活用し、経済安全保障の観点も踏まえつつ、強靱で信頼あるサプライチェーンの構築を進めていく。G7広島サミットで発出された「経済的強靱性及び経済安全保障に関するG7首脳声明」(2023年5月)においても、透明性、多様性、安全性、持続可能性、信頼性がG7内外の信頼できるパートナー国との間で強靱なサプライチェーンネットワークを構築及び強化するに当たり不可欠な原則(「強靱で信頼性のあるサプライチェーンに関する原則」)であることを認識し、支持することを奨励している。また、我が国にとっては鉱物資源供給の多元化も大きな課題であり、同志国との連携を更に進めていくとともに、民間の資源開発リスクを大きく軽減する新たな支援制度を設けている78。
また、ルールベースの国際貿易秩序の再構築を進めていく。自由貿易体制のルールメーカーであったWTOの上級委員会が機能不全に陥っている中で、既述のとおり、EUを中心に、WTO改革への取組と同時にWTOシステムの限界を見据え、それを補完する取組が行われており、2023年3月には日本もMPIAへの参加を閣議了解した。独自の制度構築はルールベースの国際貿易秩序にとっては、米国やEUのような大規模市場を持つ国・地域にとっては有効である一方、その他の国にとっては諸刃の剣となる懸念もある。
さらに、グローバル・サウスとの連携も強力に進めていく。2023~2037年まで、ASEANは年率平均7%、インドは9%弱の成長が続く見通しであり、極めて高い成長率が期待される(第Ⅰ-2-2-1図)。人口動態で見ても、中東、アフリカ、中南米地域の人口増加は継続し、グローバル・サウス全体では2100年まで人口増加が見込まれる(第I-2-2-2図)。特にインドは、非同盟主義を掲げ、長年にわたり新興国の結束をリードしてきた歴史があり、2023年のG20サミットの議長国でもある。今年1月には、「グローバル・サウスの声サミット(Voice of Global South Summit)」を主催し、南半球を中心とした途上国125か国の首脳や閣僚がオンライン形式で参加し、途上国が直面する課題に対して議論を深めた。このように、経済でみても人口で見ても存在感を高めているグローバル・サウスの中でリーダー・シップをとることで、インドは国際社会の中での存在感を更に高めている。我が国も、インドを価値観を共有する重要なパートナーと位置付け、日米豪印4か国の枠組み、インド太平洋経済枠組み(IPEF)、日豪印サプライチェーン強靱化イニシアティブ(SCRI)等、多方面での連携を深めてきており、2022年に首脳間で合意した5兆円規模の対印投融資の目標実現に取り組む79など、更に連携を強化していく。
第Ⅰ-2-2-1図 中国及びグローバル・サウスの年平均名目GDP成長率の変化
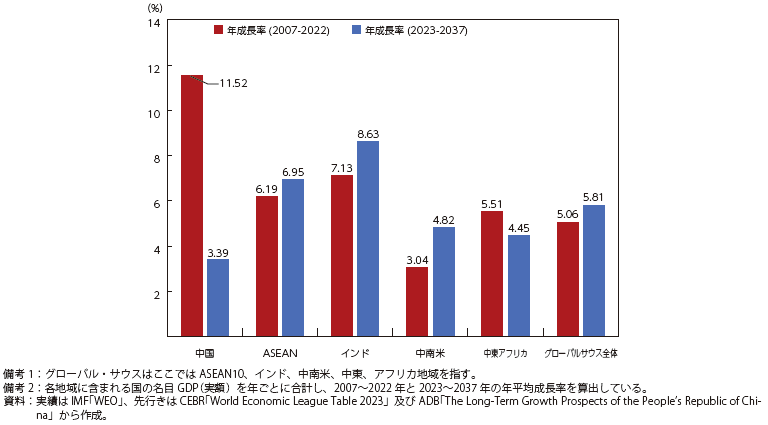
第Ⅰ-2-2-2図 中国及びグローバル・サウスの人口動態予測
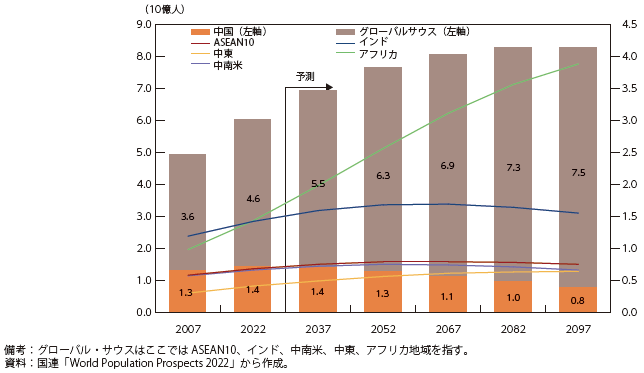
以上で見てきたように、EU等の主要国は、産業政策をテコとした、WTOを補完する独自措置を整備しており、各国は同志国との間で信頼できるサプライチェーン構築のため、合意作りに取り組み始めている。日本としては、これらの取組を踏まえ、ルールベースの国際貿易秩序の再構築、同志国との信頼できるサプライチェーンの構築、グローバル・サウスとの連携強化の取組を同時に進めていく。
第Ⅰ-2-2-3図 自由貿易体制と経済安全保障の両立に向けた取組
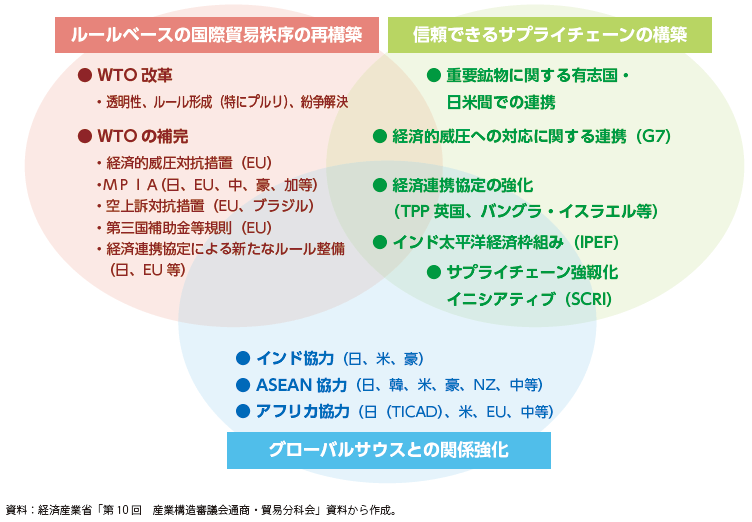
77 内閣府(1981)『昭和56年年次経済報告』参照。
78 「経済環境変化に応じた重要物資サプライチェーン強靱化支援事業」として、バッテリーメタルやレアアースを対象として、探鉱FS、鉱山開発、分離・製錬及び技術開発に係る民間企業の取組に対する支援を行う。
79 外務省資料(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100407780.pdf![]() )参照。
)参照。