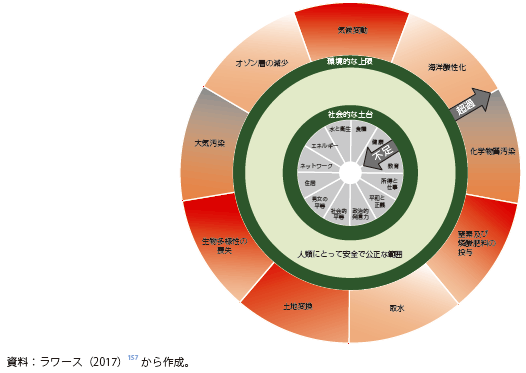第3節 持続可能で包摂的な経済成長及び発展の確保
国連が2022年7月に発表した「世界人口推計2022年版」によると、1950年に25億人と推計されていた世界の総人口は、2030年に約85億人、2050年に約97億人、2080年代中に約104億人でピークに達し、2100年までそのレベルにとどまると予測されている80。
このような世界人口の増加や工業化による都市化などに伴い、資源、エネルギー、食料の需要が増大し、廃棄物量も増加している。石油大手BPが発表した「世界エネルギー統計2022」によると、世界のエネルギー消費量(一次エネルギー)は、新興国の消費増加にけん引され、2021年はコロナ禍前の2019年と比較して1.3%増加した81。また、2018年9月に公表された世界銀行の報告書「What a Waste 2.0:2050年に向けた世界の廃棄物管理の現状」82は、緊急対策が講じられなければ、世界の廃棄物の発生量は、2050年までに2016年と比べて70%増加すると分析している。
このような状況の中、世界は、気候変動を始めとする環境問題の深刻化、格差や貧困の拡大、人権問題など、相互につながりあった複雑な課題に直面している。これらの課題は、国境を越えた人類全体の問題であり、誰一人取り残さない包摂的で持続可能な発展を実現するためには、協同で取り組まなければいけない喫緊の課題である。世界銀行のエコノミストであったデイリー(1990)は、持続可能な発展の三原則83として、①再生可能な資源の消費速度は、その再生速度を上回ってはならない、②汚染の排出量は環境の吸収能力を上回ってはならない、③再生不可能な資源の消費速度は、それに代わり得る持続可能な再生可能資源が開発される速度を上回ってはならない、と提唱した。これらの課題は、一か国だけで解決できる課題ではない。また、相互に連関しているため、一か国あるいは個別の問題として捉えた場合には合理的な解決策が、世界全体にとっては悪い結果をもたらしてしまう場合もある。
例えば、経済学に、「合成の誤謬」という言葉がある。これは、個々の単位、つまりミクロの視点では、合理的で正しい行動あるいは対応をした場合であっても、経済全体、つまりマクロの視点では、当初意図しなかった悪い結果をもたらしてしまう場合があることを意味している。また、ハーバート・サイモンは、限定合理性84という概念を提示し、人間は合理的な意思決定を意図したとしても、情報収集力の限界など様々な制約条件があることから、限定された合理性に基づく意思決定(不完全な意思決定)しか行えないと論じている。
国際的な研究・提言機関であるローマクラブが、マサチューセッツ工科大学に委託して1972年に発表したレポート「成長の限界」85のモデル策定に関わったメドウズ(2008)86は、「何かを達成するように一貫性を持って組織され、相互につながっている」システムの中では、「すべてが関連し」、「すべてが役割を持って」おり87、多くの場合、「最も目につかない部分である機能または目的」が、「そのシステムの挙動を決する上で最も重要で」あると述べている。なお、システムで起こっている問題のレバレッジ・ポイント(小さな変化が挙動の大きなシフトをもたらすシステムの場所)は、「直感では理解できない」ことが多く、また、仮に「直感で分かったとしても、ほとんどの場合、私たちは逆向きに使ってしまい、解決しようとしている問題が何であれ、システム構造的に悪化させてしまう」。人間は、「システムのつくりだす出来事」やフローの挙動に「心を奪われ過ぎ」ることが多いが、システムの複雑なつながりをよく見て、出来事や挙動を生み出している構造についての手がかりを探し、その全体像を捉えることが大切であるとし、「システムは相互につながって」いるので、「地球環境が破綻しているのに、世界経済がうまくいくということは不可能」だろうと述べている。
このような視点も踏まえると、上述した相互につながりあった複雑な課題への対応に当たっては、全体のシステムのつながりを見て、努めてグローバルな視点(地球の視点)で考え、ローカルに(足下で)行動することが求められてくる。
本節では、我々が直面している相互につながりあった複雑な課題の中から、深刻化する気候変動に伴うリスクへの対応等に焦点を当てて概観する。
80 United Nations, (2022), “World Population Prospects 2022”. https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf![]()
81 BP, (2022), “BP Statistical Review of World Energy 2022/71st Edition”. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf![]()
82 World Bank Group, (2018), “What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050”. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30317/211329ov.pdf?sequence=11&isAllowed=y![]()
83 Daly, H., (1990), “Toward Some Operational Principles of Sustainable Development”, Ecological Economics, 2(1990): 1-6. https://docs.ufpr.br/~jrgarcia/Economia%20Ecologica/Toward%20some%20operational%20principles%20of%20sustainable%20development.pdf![]()
84 Simon, H., (1945, 1947, 1957, 1976, 1997), Administrative Behavior, 4/E, (二村敏子他訳(2009)『経営行動 経営組織における意思決定過程の研究』、ダイヤモンド社。).
85 Meadows, D. et al., (1972), “The Limits to Growth”. https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/![]() .
.
86 Meadows, D., (2008), Thinking in Systems, (枝廣淳子訳(2015)『世界はシステムで動く』、英治出版。).
87 「世界(少なくとも人間が、自分たちが理解していると思っている部分)は、サブシステムが集まって、より大きなサブシステムになり、それが集まってさらに大きなサブシステムになる形で組織化されて」おり、「あなたの肝臓の細胞は、一つの器官のサブシステムで、それは有機体としてのあなたの一つのサブシステムであり、あなたは、家族、スポーツチーム、音楽グループなどの一つのサブシステムであり、こういったグループは、町や都市のサブシステムであり、それから国、グローバルな社会経済システム全体となり、生物圏システムの中に存在してい」ると述べている。
1.気候変動リスクへの対応
気候変動に関する国連気候変動枠組条約(UNFCCC)88によると、「気候変動」とは、「地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生ずるもの」と定義されている。国連は、1800年代以降の気候変動は、主に人間活動が引き起こしており、特に、化石燃料(石炭、石油、ガスなど)を燃やすことで、温室効果ガスが発生し、地球を覆う毛布のように太陽の熱を閉じ込め、気温が上昇することが主な原因であるとしている89。2023年1月、世界気象機関(WMO)は、六つの国際気象データセットに基づき、2015年から八年間の世界の年平均気温は観測史上最も高いこと、また2022年の世界の平均気温は産業革命前に比べて約1.15℃(1.02~1.28℃)上昇したことを発表した90。
近年、世界各地で熱波、干ばつ、大洪水などの異常気象91や気象災害が発生している。気象庁によると92、2022年、中国、欧州中部から北アフリカ北部、豪州北部からニュージーランドでは異常高温、東アジア南部から東南アジア、豪州南東部では異常多雨、欧州中部から北アフリカ北西部、南米中部では異常少雨などが発生した。後述する気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第六次評価報告書第一作業部会報告書(政策決定者向け要約)は、「人為起源の気候変動は、世界中の全ての地域で多くの極端な気象と気候に既に影響を及ぼしている」と記している93。また、2023年1月に世界経済フォーラムが発表した「グローバルリスク報告書2023」94によると、今後10年間で最も深刻な影響を及ぼす可能性のあるリスクの一位は、気候変動緩和策の失敗、二位は気候変動への適応(あるいは対応)の失敗、三位は自然災害と極端な異常気象となっている(第I-2-3-1表)。
第Ⅰ-2-3-1表 今後10年間で最も深刻な世界規模のリスクは何か
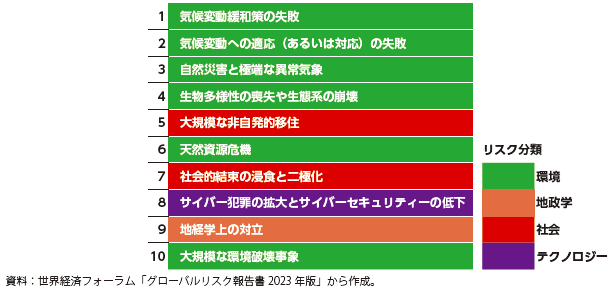
スウェーデンの環境学者ロックストローム(2015)95 96は、「地球は、すべてが相互につながる自己制御的なシステム」で、プロセスが二段階となっており、「第一段階では、まだ回復力が高く」「もとの状態にとどまろう」とするが、「第二段階に達し、地球の回復力が失われて諸条件が臨界点に達すると、均衡状態が移行し始め」、「もう後戻りできなくなる」と記している。同氏が率いた、地球の破局をもたらす臨界点を示す地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)に関する分析評価の更新版(2015年)によると、最重要なものに絞られた九つの環境項目のうち、地球は、「気候変動」、「生物多様性」、「土地利用の変化」、「窒素の生物地球化学的循環」の四つの項目において、既に限界値を超過していることが示されている。さらに、2022年には、「プラスチックなどの化合物による汚染に関連した新規化学物質の境界」についても、既にプラネタリー・バウンダリーを超えていると、別の研究チームが評価している97。
気候変動に関する世界的な議論は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が数年おきに発行している評価報告書を、科学的な拠り所としている。IPCCは、1988年11月に国連環境計画(UNEP)とWMOによって設立された政府間組織で、2023年3月時点で195か国・地域が参加している98。IPCCの目的は、気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えることで、評価報告書の策定に当たっては、各国政府等を通じて推薦された科学者が参画し、気候変動に関する科学的・技術的・社会経済的な見地から評価を行い、報告書にまとめている。評価報告書は、評価対象により分けられた三つの作業部会による「作業部会報告書」や「統合報告書」等から構成されており、基礎となるのは、気候システム及び気候変動の自然科学的根拠について評価を行う第一作業部会(WG1)の報告書である。人間活動が及ぼす温暖化への影響についての評価を、これまでのWG1の報告書(政策決定者向け要約)で見ると(第I-2-3-2表)、それぞれシナリオの設定が異なるものの、報告書が公表されるごとに、確信度が高くなり、次第に明確な表現で記されるようになってきている。2021年8月に公表された第六次評価99のWG1報告書は、「人間の影響が大気、海洋、及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」と断定し、温暖化の進行に伴って、「極端な高温、海洋熱波、大雨、及びいくつかの地域における農業及び生態学的干ばつの頻度と強度の増加」などが拡大すると指摘している100。
第Ⅰ-2-3-2表 人間活動が及ぼす温暖化への影響についての評価
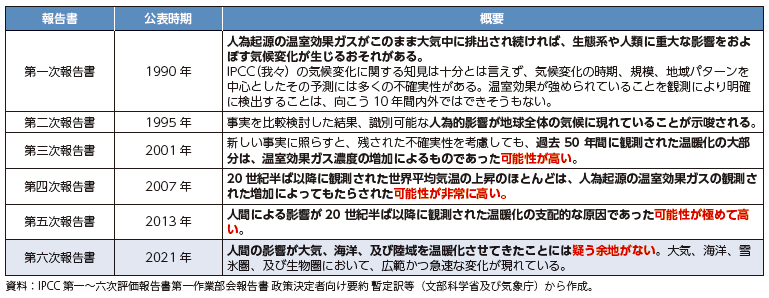
気候変動リスクに対して、民間での取組も進んでいる。2015年、金融安定理事会(FSB)は、G20からの要請を受け、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)を設置した。同タスクフォースは、2017年6月に公表した最終報告書101で、環境・社会・企業統治(ESG)に配慮した投資を行う投資家や金融機関などに適切な投資判断を促すため、企業が一貫性、比較可能性、信頼性、明確性をもつ、効率的な気候関連財務情報を開示することを提言・推奨した。気候変動リスクを、低炭素経済への移行に関連するリスクと気候変動の物理的影響に関連するリスクに大別し、企業が気候変動のリスク・機会を認識して経営戦略に織り込むことの重要性に言及している。2018年以降、大企業約1,400社の気候関連財務情報の開示状況をまとめたステータスレポートが毎年公表されており、「2022 ステータスレポート」102では、大きな前進の余地は引き続きあるが、気候関連情報を開示する企業数は順調に増加していることが報告されている。日本においては、TCFDコンソーシアムの設立や2021年のコーポレートガバナンスコード改訂によるTCFD開示の実質義務化を通じ、世界最大となる1,300超の企業が賛同を示している。東京証券取引所、大阪取引所、東京商品取引所等を運営する株式会社日本取引所グループが2023年1月に公表した「TCFD提言に沿った情報開示の実態調査(2022年度)」103によると、1年前の同調査と今回の調査のいずれにも含まれていた165社では、TCFDが推奨している全ての開示項目について、開示している会社の割合が増加している。また、CDP(カーボン・ディスクロージャ・プロジェクト)による気候変動関連等の開示の質への評価において、最高ランクとなるAリストに該当する日本企業は92社と世界1位となっており、開示の量のみならず質もリードしている。
気候変動を始めとする環境問題への対応には、産官学及び一般市民が相互信頼の下、一人一人が自分の問題と捉え、ともに助け合い取り組んでいくことが欠かせない。
本項では、気候変動対策の土台となる代表的な国際的枠組みや主要国の取組などを見ていく。
88 1992年5月に採択、1994年3月に発効(締約国数:198か国・機関)。https://unfccc.int/![]()
89 国連Webサイト参照(https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change![]() )。
)。
91 気象庁の定義によると、原則として「ある場所(地域)・ある時期(週、月、季節)において30年に1回以下で発生する現象」。
92 気象庁Webサイト参照(https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/annual/annual_2022.html![]() )。
)。
93 IPCC, (2019), “Summary for Policymakers, Working Group 1, Sixth Assessment Report”, (文部科学省及び気象庁(2022)「IPCC第六次評価報告書第一作業部会報告書 政策決定者向け要約 暫定訳」。).https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/summary-for-policymakers/https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/IPCC_AR6_WGI_SPM_JP.pdf![]()
94 World Economic Forum, (2023), “The Global Risks Report 2023”. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf![]()
95 Rockström, J. et al., (2015), Big World Small Planet, (武内和彦 石井菜穂子監修(2018)『小さな地球の大きな世界 プラネタリー・バウンダリーと持続可能な開発』、丸善出版。).
96 ロックストロームは、「地球システムの機能に関する科学的理解は大きく進歩したものの、まだ不完全」であり、「気候の閾値がどこにあるのか、科学はまだ正確に解明」しておらず、「地球の一角で私たちが何かを行うと、即座に地球の他の地域の人々の生活環境に影響する」と分析している。
97 Persson, L., (2022), “Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities”, Environmental Science and Technology. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c04158![]()
98 IPCC Webサイト参照(https://www.ipcc.ch/about/![]() )。
)。
99 IPCC Webサイト参照(https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/![]() )。
)。
100 IPCC, (2019), “Summary for Policymakers, Working Group 1, Sixth Assessment Report”, (文部科学省及び気象庁(2022)「IPCC第六次評価報告書第一作業部会報告書 政策決定者向け要約 暫定訳」。).https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/IPCC_AR6_WGI_SPM_JP.pdf![]()
101 TCFD, (2017), “Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures”. https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf![]()
102 TCFD, (2022), “2022 Status Report”. https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2022/10/2022-TCFD-Status-Report.pdf![]()
103 株式会社日本取引所グループ(2023)「TCFD提言に沿った情報開示の実態調査(2022年度)」。https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esgknowledgehub/disclosure-framework/nlsgeu0000053pgw-att/TCFDsurveyjp.pdf![]() (JPX日経インデックス400構成銘柄を対象)
(JPX日経インデックス400構成銘柄を対象)
(1)国際的な枠組み
気候変動への対策には、大きく分けて、「緩和」策と「適応」策の二つがある。緩和策とは、気候変動の原因となる温室効果ガスの排出抑制や、森林等の吸収作用を保全及び強化する施策を指し、適応策とは、既に生じている、あるいは、将来予測される気候変動の影響による被害を回避・軽減させる施策を指す。これらを車の両輪として効果的に組み合わせて実施することが重要と考えられている104。
緩和策として最優先の取組の一つが、温室効果ガスの排出削減だが、近年、適応策をもっと考えるべきだとの認識も広がりつつある。また、途上国を中心に、適応によっても回避できない気候変動に起因する影響への対策として気候変動の悪影響に伴う損失及び損害(ロス&ダメージ)に対する備えが必要だとの意見も強まっている。
104 環境省Webサイト参照。
① 持続可能な開発目標(SDGs)
2015年9月、国連持続可能な開発サミットが開催され、成果文書として、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ105」が採択された。同アジェンダに基づき、人間、地球及び繁栄のための行動計画として、誰一人取り残さない世界を実現するための持続可能な開発目標(SDGs)が定められた。同目標は、2030年を達成年限とし、相互に関係している17の目標及び169のターゲットを、互いに独立したものではなく、統合された方法で達成することを目指すものとなっている。気候変動に関しては、目標13「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」で掲げられ、同目標は五つのターゲットから構成されている(第I-2-3-3表)。
第Ⅰ-2-3-3表 SDGs及び開発目標13のターゲット
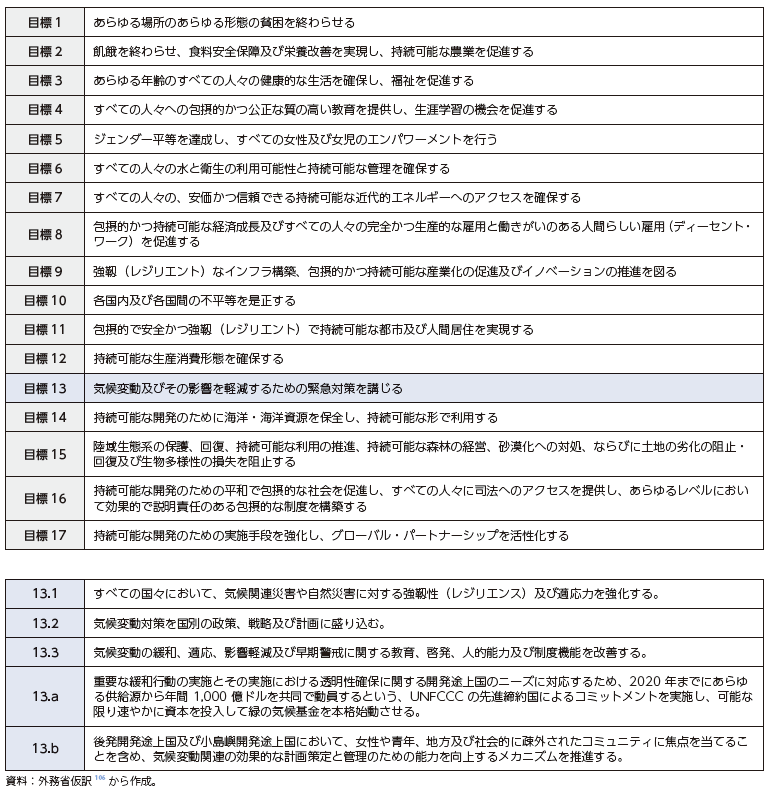
レジリエンスと持続可能性科学の国際的な研究拠点であるスウェーデンのレジリエンス研究所が考案したウェディングケーキモデルでは、上述した17の目標を三層のウェディングケーキに見立てて分類し、総合的に整理している(第I-2-3-4図)。同モデルでは、「経済圏(Economy)」(目標8.9.10.12)の発展は、「社会圏(Society)」(目標1.2.3.4.5.7.11.16)によって成り立ち、「社会圏」は、「生物圏(Biosphere)」(目標6.13.14.15)によって支えられて成り立っていることが概念化されている。そしてその頂点には、目標17の「持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する」が置かれている。
第Ⅰ-2-3-4図 ウェディングケーキモデル
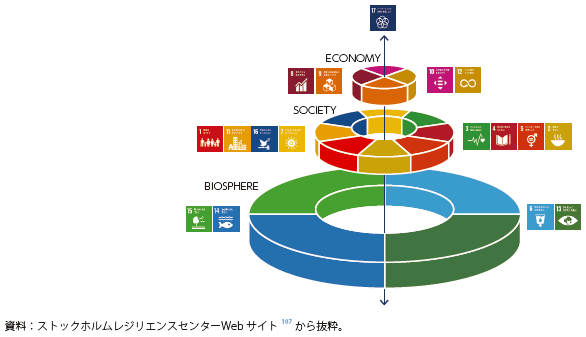
2019年9月に開催されたSDGサミットにおいて、首脳レベルでSDGsに係る過去の取組のレビューが行われ、目標達成を10年後に控えた2020年1月からの10年をSDGs達成のための取組を加速させていく「行動の10年」とすることが合意された108。国連は、毎年SDGsの達成度及び進捗状況に関する「持続可能な開発レポート」を発表しており、この中で国別のSDGs目標の達成度合いを四段階で評価し、順位やスコアを公表している。2022年のレポート109によると、2015年から2019年までに世界全体でSDGsの達成度は向上したが、新型コロナウイルス感染症拡大などの影響により、2019年から2021年にかけては進捗が見られず、停滞している。
英国の経済学者マッツカート(2021)110は、資本主義は、「何より環境危機に対して何の答えも持ち合わせて」こなかったことから、「国連の持続可能な開発目標に2030年までに取り組むという公約」を果たすには、「これまでとはまったく違う官民のパートナーシップが必要」で、「政府の役割と必要とされる能力を根本から見直さなければならない」と述べ、「人と地球にとって本当に大切なことに目を向けた、課題解決型の経済を創造すること」(ミッション経済)が大切であると述べている。
105 United Nations, (2015), “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”.
107 https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-the-sdgs-wedding-cake.html![]()
108 国連Webサイト参照(https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit![]() )。
)。
109 Sachs, J. et al., (2022), “Sustainable Development Report 2022”, Cambridge University Press. https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2022/2022-sustainable-development-report.pdf![]()
110 Mazzucato, M., (2021), Mission Economy A Moonshot Guide to Changing Capitalism, (関美和・鈴木絵里子訳(2021)『ミッション・エコノミー』、ニュースピックス。).
② 国連気候変動枠組条約締約国会議
1992年5月、大気中の温室効果ガス(二酸化炭素、メタンなど)の濃度を安定化させることを究極の目的とするUNFCCCが採択された。同条約に基づき1995年から毎年(新型コロナウイルス感染症拡大の影響による2020年を除く)、気候変動に対する具体的な政策を締約国間で議論するため、国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)と呼ばれる国際会議が開催されている。これまで27回開催されており、主だった交渉内容・結果は以下のとおりである。
1997年に京都で開催されたCOP3では、日本が議長国として取りまとめ、全会一致で京都議定書が採択された(2005年2月発効)111。同議定書は、「共通だが差異ある責任及び各国の能力に従い」、「先進国が率先して気候変動に対処すべき」との考え方に基づき、2008年から2012年までの約束期間に、先進国(市場経済移行国を含む)が排出する温室効果ガスの量を1990年時点と比べて全体で少なくとも5%削減することを念頭に、先進国(市場経済移行国を含む)が削減目標を設定し、その目標を達成することを義務付けた。
2015年にパリ(フランス)で開催されたCOP21では、パリ協定が採択された(2016年11月発効)112。同協定は、京都議定書に代わる、2020年以降の温室効果ガス排出削減のための枠組みとして、先進国だけに特化せず、先進国途上国の区別なく全ての締約国が、世界全体の平均気温の上昇を産業革命前に比べて2℃よりかなり低く抑えること並びに1.5℃以内に抑えるための努力を追求することに合意した。また、そのために、できる限り早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、今世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量との均衡を達成することも長期目標に掲げた。全ての締約国は、温室効果ガスの排出削減目標を「自国が決定する貢献」 (Nationally Determined Contribution: NDC)として五年ごとに提出・更新することが義務付けられた。
2022年にシャルム・エル・シェイク(エジプト)で開催されたCOP27では、緩和、適応、ロス&ダメージなどの各分野における取組の強化を求める「シャルム・エル・シェイク実施計画」及び「緩和作業計画」(2030年までの緩和の野心と実施を向上するための作業計画)が採択された113。同会議では、途上国側の強い要請を受けて、ロス&ダメージの資金面での措置が正式なアジェンダとして議論された。同議論では、先進国と途上国との間で意見の隔たりが大きく、閣僚級での議論に持ち込まれた結果、ロス&ダメージを支援するための措置の一環として、ロス&ダメージ基金(仮称)を設置すること等が決定された114。
近年、Climate Justice(気候の正義あるいは公正)を求める声も高まっている。Climate Justiceとは、パリ協定の前文にも明記されている言葉115だが、米国バイデン政権は、類似の概念であるEnvironmental Justiceを政策の中心に据えている116。このような状況を背景に、法律の力で気候変動の影響を食い止めようとする動きも広がっている。UNEPが2021年に発表した報告書117では、国や企業に対する気候変動訴訟の数が、2017年24か国884件から2020年には38か国1,550件以上起こされており、ほぼ倍増したことが明らかになっている。また、気候変動は、環境問題であるだけではなく、安全保障の問題でもあるとするClimate Security(気候安全保障)という考え方も欧米を中心に広がっている。
そのような状況の中、全ての締約国がともに努力することが合意されたパリ協定の目標達成と現実とのギャップは大きく、気候変動に係る国際的な目標が達成されていない等の警鐘の声が挙がっている。
例えば、国連防災機関(UNDRR)は、2022年4月に公表した「自然災害の世界評価報告書」118で、人間が現在の活動を続けていると、2015年に世界全体で年間400回だった自然災害の発生は、2030年までに一日当たり1.5回、年間560回に達するとの見通しを示し、人間の活動や行動が世界の災害をますます増加させ、何百万人もの生命とあらゆる社会的・経済的利益を危険にさらしていると警鐘を鳴らしている。また、過去20年で年間350回から500回の中規模・大規模な災害が起きたが、それらが人類に及ぼす長期的な影響は、過小評価されてきているとも指摘している。UNEPは、2022年10月に公表した「排出ギャップ報告書2022」119で、現状の排出削減対策は、産業革命以前の水準と比べて1.5℃に抑えるというパリ協定の温度目標を達成するための信頼できる道筋ではないと主張し、1.5℃目標を達成するには、2030年までに排出量を45%削減する必要があると述べている。WMOは、大気中の主要な温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素)の2021年の世界平均濃度がいずれも観測史上最高を更新したことを、2022年10月に発表した120。2022年11月に発表された「戦争の地球温暖化ガス算定に関するイニシアティブ121」は、ロシアによるウクライナ侵略に起因する温室効果ガスの排出量は増加の一途を辿っており、気候変動問題に負の影響を及ぼしていると記している。
また、気候変動問題への対応にはそもそも抜本的な変革が必要であるとする声も挙がっている。2000年、ノーベル化学賞受賞者パウル・クルッツェン他は、人類が地球の生態系や気候に大きな影響を及ぼすようになった時代という意味で、「完新世」122とは区別して、「人新世」123という新しい地質学的時代に突入したと提唱した124。斎藤(2021)125は、「人類の経済活動が全地球を覆ってしまった「人新世」」において、経済の在り方を変えていかなければ、気候変動は止められないことを指摘している。
ローマクラブ(2022)126は、「多くの人は「個人としての未来」を大切にしている。しかし、一つの文明として、80億人もの集団として、そして複雑に絡み合った社会のネットワークとして、私たちは人類の「集団としての未来」を大切にしているだろうか」と問い、「人類の長期的な可能性は、その文明が今後数十年の間に」「劇的な方向転換を遂げられるか否かにかかっている」と述べている。そして、私たちが正しい選択をすれば、「人類にとって最も困難な問題の解決にも貢献できるだろう」と述べている。
190人の研究者、専門家、化学者の国際的なグループが結集してまとめた『ドローダウン 地球温暖化を逆転させる100の方法』127は、「間違った道を進んでいるなら、ゆっくり進んだところで間違った道にいることには変わりありません」と記し、「大気の異変は私たちが何をつくり、どう行動するかすべてを変えなさい、再考しなさいというメッセージなのだと考えてみたら、生きる世界が違って」くると述べている。
大気の流れなどに人間の作った国境や境界線はなく、各レベルでそれぞれの主張の隔たりを超えて共通の価値を見いだし、一緒に取り組んでいくことができるかが鍵となってくるだろう。
111 UNFCCC Webサイト参照(https://unfccc.int/kyoto_protocol#:~:text=In%20short%2C%20the%20Kyoto%20Protocol,accordance%20with%20agreed%20individual%20targets![]() )。
)。
112 UNFCCC Webサイト参照(https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement![]() )。
)。
113 UNFCCC Webサイト参照(https://unfccc.int/cop27![]() )。
)。
114 外務省Webサイト参照(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1_001420.html![]() )。
)。
115 環境省Webサイト参照(https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cop/attach/paris_agr20160422.pdf![]() )。
)。
116 White House Webサイト参照(https://www.whitehouse.gov/environmentaljustice/![]() )。“We’ve put environmental justice at the center of what we do, addressing the disproportionate health, environmental, and economic impacts that have been borne primarily by communities of color — places too often left behind.”
)。“We’ve put environmental justice at the center of what we do, addressing the disproportionate health, environmental, and economic impacts that have been borne primarily by communities of color — places too often left behind.”
117 UNEP, (2021), “Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review”. https://www.unep.org/resources/report/global-![]() .climate-litigation-report-2020-status-review
.climate-litigation-report-2020-status-review
118 UNDRR, (2022), “Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction”. https://www.undrr.org/media/79595/download![]()
119 UNEP, (2022), “Emissions Gap Report”. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022![]()
120 WMO Webサイト参照(https://public.wmo.int/en/media/press-release/more-bad-news-planet-greenhouse-gas-levels-hit-new-highs![]() )。
)。
121 Initiative on GHG accounting of war, (2022), “Climate Damage Caused by Russia’s War in Ukraine”. https://climatefocus.com/wp-content/uploads/2022/11/ClimateDamageinUkraine.pdf![]()
122 最終氷河期が終わった約1万7,000年前から始まり、最近まで続いた最も新しい地質時代の区分。この時代の気候は、極めて安定したリズムで落ち着いており、これにより人類は農耕が可能となり余剰生産が増大。
123 2023年3月時点、地質学の国際組織である国際地質科学連合(IUGS)が公式に認めた時代区分ではない。
124 International Geosphere-Biosphere Programme Webサイトを参照(http://www.igbp.net/news/opinion/opinion/haveweenteredtheanthropocene.5.d8b4c3c12bf3be638a8000578.html![]() )。
)。
125 斎藤幸平(2021)『人新世の「資本論」』、集英社新書。
126 The Club of Rome, (2022), Earth for All, (ローマクラブ日本監修(2022)『Earth for All 万人のための地球「成長の限界から50年 ローマクラブ新レポート」』、丸善出版株式会社。).
127 Hawken, P., (2017), Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming, (江守正多監訳(2021)『ドローダウン 地球温暖化を逆転させる100の方法』、山と渓谷社。).
(2)主要国の取組
多くの国にとって、気候変動問題は、最上位の政策となっており、2050年までにカーボンニュートラルを実現することを掲げる国は、2021年4月時点で125か国・1地域に上っている。カーボンニュートラルとは、二酸化炭素を始めとする温室効果ガスのうち人為的なものの「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、実質的に合計をゼロにすることを意味している。G7広島サミットにおいては、「G7クリーン・エネルギー経済行動計画」(2023年5月)が発出され、2050年までにネット・ゼロ排出を達成するために、世界のクリーン・エネルギーへの移行を加速させるべく行動し、協力を深化させており、パリ協定への揺るぎないコミットメントを再確認した。
気候変動対策に意欲的に取り組んでいるEUは、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長のリーダーシップの下、2019年12月、気候政策を重点分野の一つに位置付け、EUを公平で豊かな社会に変えるための成長戦略、欧州グリーン・ディール128を発表した。同戦略は、EUが2050年までの温室効果ガスの実質排出をゼロにすることや経済成長と資源利用を切り離すこと等を目指している。さらに、EUの自然資本を保全・強化し、市民の健康とウェルビーイングを環境関連リスクや影響から守ることも目的とした。また、達成に向けて、2030年までの温室効果ガスの削減を1990年比で55%以上とする野心的な計画も掲げた。
2020年3月には、グリーンでデジタルな経済への移行などを目指す新産業戦略129を発表し、同年同月、同戦略の一貫として新たな循環型経済行動計画130を打ち出した。欧州委員会は、同計画は、欧州グリーン・ディールの核となる要素の一つであり、2050年の気候中立目標を達成するために不可欠と位置づけている131。また、2021年5月、2020年新産業戦略のアップデート132も公表した。
2021年7月には、欧州気候法133が成立し、温室効果ガス排出量を2030年までに1990年比で55%以上削減するという目標が、EU域内で法的拘束力を持つものとなった。また、同年同月、同目標の達成に向けて、EUの気候、エネルギー、土地利用、運輸(輸送)、税制の各政策を調整することを目的としたFit for 55パッケージと呼ばれる一括法案134を発表し、2035年までに内燃機関車販売禁止や炭素国境調整措置など既存法の改正や新法を含む13の法案を提案した。同年12月には、Fit for 55パッケージを補完する第二弾も公表されている。
また、2021年7月に欧州委員会が発表した炭素国境調整メカニズム(CBAM)の設置に関する規則案について、2022年12月、条件付きではあるが暫定的な政治合意に達した135。同制度では、対象となる炭素集約型の製品(暫定案では前駆体なども含む)をEU域外から輸入する域内事業者に、域内で製造した場合に課される炭素価格に相当する価格の支払いを義務付けるものとなっている。一部確定していない部分もあるが、2023年10月から報告義務のみを課す移行期間が設けられ、同制度は適用される予定となっている136。
2023年1月の世界経済フォーラムの年次総会(ダボス会議)で、欧州委員会は、グリーン・ディール産業計画の構想を発表し、同年2月に同計画の詳細を発表した137。温室効果ガスの実質排出ゼロに取り組む欧州産業の競争力を強化し、気候中立への早急な移行を支援することを目指すとしている(第I-2-3-5図)。
第Ⅰ-2-3-5図 EUの主要な気候変動政策
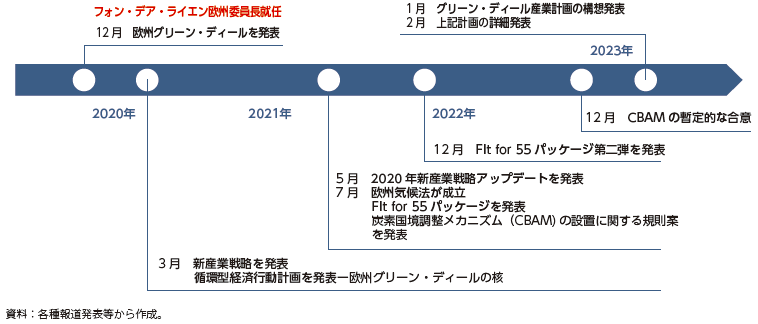
米国は、2021年2月、バイデン政権の発足を機に、トランプ政権下で脱退したパリ協定に正式に復帰した138。2022年8月には、主たる支援対象を気候変動対策とする前例のない規模のインフレ削減法が正式に成立した139。3,690億ドルが、気候変動対策に充てられることとなっている140。
我が国は、2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス排出量46%削減(2013年度比)と50%の高みに向けた挑戦という野心的な国際公約に向け、グリーン成長戦略、エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略等を策定し、今後の進むべき方向性を示してきている。
2022年1月、岸田首相は、世界の排出量の半分以上を占めるアジアのグリーン・トランスフォーメーション(GX)の実現に貢献するため、アジア各国が脱炭素化141を進めるとの理念を共有し、エネルギー・トランジション142を進めるために協力することを目的とした「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」構想を発表した143。GXとは、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造や社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換することを意味する。2023年3月には、エネルギー・トランジションを所掌するパートナー国閣僚による閣僚会合が東京で開催され、AZECの枠組みが立ち上った144。
2022年12月、岸田首相を議長とするGX実行会議は、「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」145を取りまとめ、同基本方針は2023年2月に閣議決定された146。同基本方針では、2030年度の温室効果ガス46%削減、2050年カーボンニュートラルの達成に向け、GXに関連する投資が今後10年間で官民合わせて150兆円を超えると試算しており、この巨額のGX投資を官民協調で実現するため、「成長志向型カーボンプライシング構想」を速やかに実現・実行していく必要があることなどが盛り込まれた。具体的には、「成長志向型カーボンプライシング構想」の下、「GX経済移行債」等を活用した20兆円規模の大胆な先行投資支援(規制・支援一体型投資促進策等)を行っていくとともに、カーボンプライシング(排出量取引制度・炭素排出に対する一律の賦課金)によるGX投資先行インセンティブ及び新たな金融手法の活用の3つの措置を講ずることとされている。同基本方針に基づき、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が2023年2月に閣議決定され、第211回通常国会に提出された147。
128 欧州委員会Webサイト参照(https://commission.europa.eu/publications/communication-european-green-deal_en![]() )。
)。
129 欧州委員会Webサイト参照(https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en![]() )。
)。
130 欧州委員会Webサイト参照(https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf![]() )。
)。
131 欧州委員会Webサイト参照(https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en#:~:text=It%20is%20one%20of%20the,create%20sustainable%20growth%20and%20jobs![]() )。
)。
132 欧州委員会Webサイト参照(https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf![]() )。
)。
133 欧州委員会 Webサイト参照(https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_en![]() )。
)。
134 欧州委員会Webサイト参照(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541![]() )。
)。
135 欧州理事会及びEU理事会Webサイト参照(https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/![]() )。
)。
136 欧州委員会Webサイト参照(https://taxation-customs.ec.europa.eu/green-taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_en![]() )。
)。
137 欧州委員会 Webサイト参照(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_510![]() )。
)。
138 UNFCCC Webサイト参照(https://unfccc.int/news/un-welcomes-us-announcement-to-rejoin-paris-agreement#:~:text=A%20new%20instrument%20of%20acceptance,States%20on%2019%20February%202021![]() )。
)。
139 White House Webサイト参照(https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/08/16/remarks-by-president-biden-at-signing-of-h-r-5376-the-inflation-reduction-act-of-2022/![]() )。
)。
140 米国財務省 Webサイト参照(https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1128![]() )。
)。
141 化石燃料からの脱却を目指すこと。
142 現在使用している化石エネルギーを、炭素排出量のより少ない別のエネルギーに転換すること。
143 経済産業省Webサイト参照(https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221215007/20221215007.html![]() )。
)。
144 経済産業省Webサイト参照(https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230306005/20230306005.html![]() )。
)。
145 経済産業省(2023)「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」。https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230210002/20230210002_1.pdf![]()
146 経済産業省Webサイト参照(https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230210002/20230210002.html![]() )。
)。
147 経済産業省Webサイト参照(https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230210004/20230210004.html![]() 、https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230228005/20230228005.html
、https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230228005/20230228005.html![]() )。
)。
2.人権問題への対応
グローバル化の進展によって、企業活動が人権に及ぼす負の影響が拡大し、近年、企業活動による人権侵害についての企業の責任に対する国際的な議論がより活発になっている。グローバル企業がNGO等から名指しで批判されるケースも生じており、企業活動において、サプライチェーン上の人権尊重の取組が不十分とみなされた場合には、人権侵害を理由とした製品・サービスの不買運動、投資先としての評価の降格、投資候補先からの除外、投資の引揚げ、既存顧客との取引停止など多くのリスクに直面する可能性が存在している。企業にとって、このような潜在的経営リスクを排除し、付加価値を向上し、強靱で包摂的なサプライチェーンを構築する観点からも、サプライチェーン上の企業等も含めて人権尊重の取組を実施・強化していくことが必要である。
(1)企業に人権尊重を求める海外の動き
2011年6月、「ビジネスと人権に関する指導原則」(国連指導原則)が、国連人権理事会において全会一致で支持(endorse)された。同原則では、人権を保護する国家の義務、人権を尊重する企業の責任、救済へのアクセス、という三つの柱を規定し、国家と企業とが、相互に補完し合いながらそれぞれの役割を果たしていくことが求められている。企業は、人権を尊重する責任を果たすため、①人権方針の策定、②人権デュー・ディリジェンス182、③救済(苦情処理メカニズムの設置を含む)、を実施すべきとされている。また、同原則の履行として、各国に対し国別行動計画(National Action Plan (NAP))の策定を推奨しており、2022年末時点で日本を含む世界の20か国以上がNAPを策定している。
また、OECD多国籍企業行動指針及びILO多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言の最新の改定が、それぞれ2011年、2017年に行われ、国家の人権保護義務や企業の人権尊重責任が盛り込まれた。
このように、国家が人権保護義務を負うことはもちろん、企業に人権尊重責任があることが国際的な原則となっており、企業はこれらの国際的文書に沿って行動することが求められている。
現在、欧州を中心として人権尊重に向けた取組を企業に義務付ける国内法の導入が進むほか、米国等で強制労働を理由とする輸入差止を含む人権侵害に関連する法規制が強化されている183。ドイツでは、2021年6月、「サプライチェーンにおける企業のデュー・ディリジェンスに関する法律(サプライチェーン法)」が成立し、2023年1月に発効した。同法では、一定規模以上の企業に人権デュー・ディリジェンスの実施や、その結果に関する報告書の作成・公表等を義務づけている。
欧州では、EUが2021年7月に、「EU企業による活動・サプライチェーンにおける強制労働のリスク対処に関するデュー・ディリジェンス・ガイダンス」を発表184した。また、2022年2月には、欧州委員会が一定規模の企業に対して人権及び環境に関するデュー・ディリジェンス(DD)を義務化する「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令案」を公表185した。このほか、欧州委員会は、2022年9月に、強制労働関連産品のEU域内における上市・EU域外への輸出を禁止する規則案を公表186した。
米国のバイデン政権は、外交政策における人権重視を掲げ、欧州とも連携して、新疆ウイグル自治区における人権侵害への関与を理由とした制裁を含む措置を実施している。また、2021年7月には、新疆ウイグル自治区での強制労働のほか、人権侵害に関与する事業体がサプライチェーンに含まれていないか、産業界に注意を促す「新疆サプライチェーンビジネス勧告書(2020年7月)」を公表187した。同年12月、中国の新疆ウイグル自治区で一部なりとも生産等された製品や、米国政府がリストで示す事業者により生産された製品は、全て強制労働によるものと推定し、原則として米国への輸入を禁止する「ウイグル強制労働防止法」が成立188し、2022年6月に施行された。同法に基づき、輸入貨物を差し止められた場合、輸入者は、輸入物品とその原材料が新疆ウイグル自治区で生産されていないこと等を示す必要がある。同法の対象である(輸入物品とその原材料が新疆ウイグル自治区で生産されたものを含む)場合、輸入物品が一部なりとも強制労働に依拠していないこと等を、輸入者が「明確かつ説得力のある証拠」を提出し証明する必要がある。
こうした国際社会の動きも踏まえ、企業としても事業活動における人権尊重の取組を行っていく必要があり、自社内だけでなく自社のサプライチェーンやバリューチェーン全体を見据えた対応と情報開示が求められている。
182 人権デュー・ディリジェンス:人権への負の影響を①特定し、②防止・軽減し、③取組の実効性を評価し、④どのように対処したかについて説明・情報開示していくために実施する一連の行為を指す。
183 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」巻末において、海外法制の概要を紹介している。https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf![]()
184 欧州委員会 Webサイト参照(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3664![]() )。
)。
185 欧州委員会 Webサイト参照(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1145![]() )。
)。
186 欧州委員会 Webサイト参照(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5415![]() )。
)。
187 米国国務省Webサイト(https://www.state.gov/xinjiang-supply-chain-business-advisory/![]() )。
)。
188 米国議会Webサイト参照(https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6256/text?r=1&s=1![]() )。
)。
(2)我が国の取組
我が国政府は、国連指導原則を踏まえ、2020年10月に「「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)」を策定し、日本企業に対して、規模、業種等にかかわらず、人権デュー・ディリジェンスのプロセスの導入を期待する旨を表明した。
また、経済産業省は外務省と連名で、2021年9月~10月にかけて、政府として初めて、行動計画のフォローアップの一環として、日本企業のビジネスと人権への取組状況に関する調査を実施(「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査」189)した。調査結果を見ると、回答企業のうち、人権方針を策定している企業は約7割となっているほか、人権デュー・ディリジェンスを実施している企業は、約5割程度にとどまっている。また、人権を尊重する経営を実践する上での課題としては、「サプライチェーン上における人権尊重の対応状況を評価する手法が確立されていない」、「サプライチェーン構造が複雑で、対象範囲の特定が難しい」、「十分な人員・予算を確保できない」との回答が多く見られた。一方で、人権を尊重する経営を実践した結果、得られた成果・効果としては、「自社内の人権リスクの低減」、「SDGsへの貢献」、「サプライチェーンにおける人権リスクの低減」、「ESG評価機関からの評価向上」との回答が多く見られた。政府に対する要望としては、ガイドライン整備を期待する声が最も多く寄せられた。人権尊重への取組が進んでいない企業の半数からは、具体的な取組方法が分からないとの回答も寄せられ、サプライチェーンの範囲が拡大かつ複雑化している中で、企業の理解の深化を助け、その取組をさらに促進する必要があることが明らかになった。
このような状況を踏まえ、企業が国際スタンダードに沿った人権尊重に積極的に取り組めるよう、2022年3月、経済産業省において、「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」を設置し、同検討会での議論を重ね、同年9月、「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」において、日本政府として「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定・公表した。
同ガイドラインは、法的拘束力を有するものではないが、国連指導原則、OECD多国籍企業行動指針及びILO多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言を始めとする国際スタンダードを踏まえ、企業に求められる人権尊重の取組について、日本で事業活動を行う企業の実態に即して、具体的かつわかりやすく解説し、企業の理解の深化を助け、その取組を促進することを目的としたものであり、企業の規模、業種等にかかわらず、日本で事業活動を行う全ての企業を対象としている。同ガイドラインにおいて、企業は、国際的に認められた人権190を尊重すべきとされ、その責任を果たすため、①企業トップを含む経営陣の承認を経た人権方針の策定・公表、②人権デュー・ディリジェンスの実施、③自社が人権への負の影響を引き起こし又は助長している場合における救済を行うことが求められている。
同ガイドラインにおける人権デュー・ディリジェンスとは、その性質上、人権侵害が存在しないという結果を企業が担保するものではなく、ステークホルダーとの対話を重ねながら、人権への負の影響を防止・軽減するための継続的なプロセスを指している(第I-2-3-6図)。
第Ⅰ-2-3-6図 責任あるサプライチェーン等における人権尊重の全体像
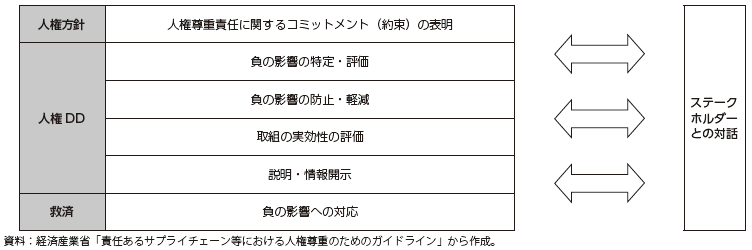
我が国政府としても、企業による人権尊重の取組を促進すべく、企業に対する情報提供、周知・啓発活動を推進していくとともに、国際協調により、企業が公平な競争条件の下で積極的に人権尊重に取り組める環境、各国の措置の予見可能性が高まる環境の実現に向け取り組んでいくこととしている。
189 経済産業省Webサイト参照(https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211130001/20211130001.html![]() )。
)。
190 少なくとも、国際人権章典で表明されたもの、及び、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に挙げられた基本的権利に関する原則が含まれる。