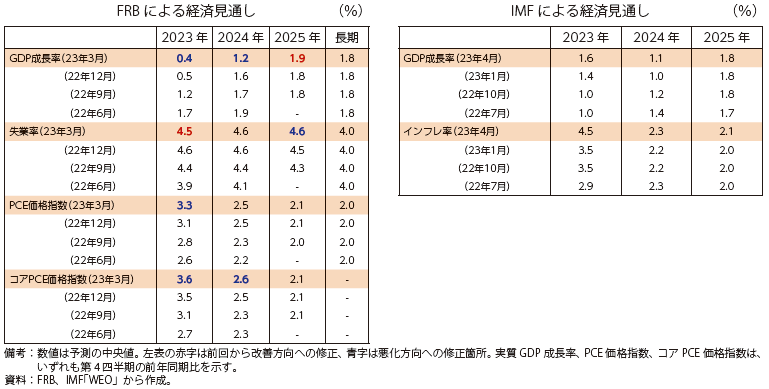第1節 米国
1.GDP
(1)実質GDP成長率
2022年における米国の実質GDP成長率は、前年比+2.1%と前年(同+5.9%)から減速したものの、主に個人消費が寄与し、2年連続のプラス成長となった。四半期別成長率について、高インフレに伴う購買力の低下や金融引締めを映じた投資抑制などから、第1四半期が前期比年率-1.6%、第2四半期が同-0.6%と、テクニカルリセッション(2四半期連続のマイナス成長)入りとなっていた。その後、純輸出(輸出-輸入)による押し上げによって、第3四半期には同+3.2%とプラス成長に転じている。2023年第1四半期(一次推計)は同+1.1%と、2022年第4四半期(同+2.6%)から伸びが鈍化するも、民間最終需要(個人消費+設備投資+住宅投資)が同+2.9%と内需が堅調であることを示しており、特に個人消費が同+3.7%と高い伸びとなっている。設備投資と住宅投資については金融引締めの影響が明確に表れている。(第I-3-1-1図)。
第Ⅰ-3-1-1図 米国の実質GDP成長率
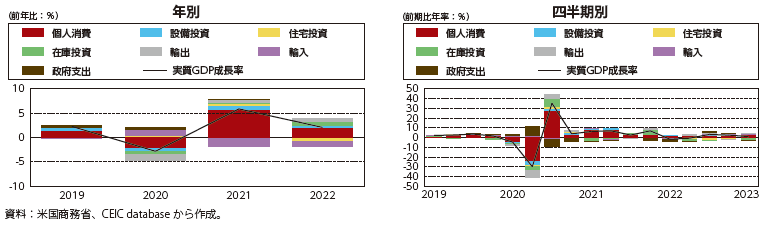
(2)個人消費
米国の個人消費は底堅さを維持している。2023年3月の個人消費支出(PCE、名目)は前月比+0.0%と2月の同+0.1%から横ばいとなった。また、実質個人消費支出についても、前月比0.0%(2月:同-0.2%)から横ばいとなった。1月が前月比+1.4%と高い伸びであったことを踏まえると弱くない結果となっている。3月の個人所得(名目)は前月比+0.3%と2月(同+0.3%)に続き、労働需給のひっ迫を背景に堅調な伸びが続いている(第I-3-1-2図)。
第Ⅰ-3-1-2図 米国の家計消費
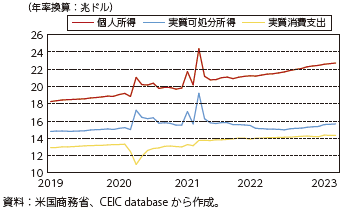
(3)投資
① 設備投資
民間設備投資の動向をみると、2020年第3四半期以降プラスの推移が続いている。その中で、金融引締めの影響を受けた金利上昇や高インフレが下押しに作用したとみられ、2022年第4四半期には機器投資がマイナスに寄与している。知的財産投資についてはプラス成長が継続しており設備投資全体のプラス成長に寄与している(第I-3-1-3図)。
第Ⅰ-3-1-3図 米国の民間設備投資
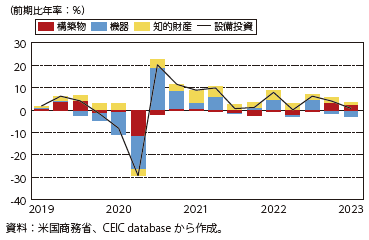
② 住宅投資
住宅市場の状況について、まず、住宅着工件数を確認すると、2023年3月の住宅着工件数(年率換算、季調値)は前月比-0.8%の142.0万件と、2月(同+7.3%、143.2万件)から減少している。6か月ぶりにプラスに転じた前月からの反動減とみられ、基調としては住宅着工件数、住宅建設許可件数も持ち直しの動きが見られることから、市場が回復傾向にある可能性を示している(第I-3-1-4図)。
第Ⅰ-3-1-4図 米国の住宅着工許可、着工、完成件数
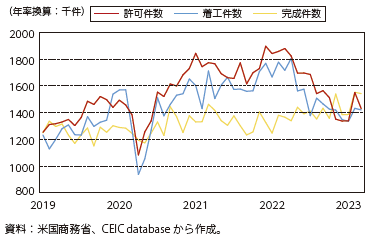
ケースシラー住宅価格指数の動向をみると、2022年4月には前年同月比+21.3%となっていたが、住宅ローン金利の上昇によって住宅価格の急騰を抑えることにつながり、2023年2月には前年同月比+0.4%となり、前月比についても2022年7月以降おおむねマイナスで推移している。住宅ローン金利の動向を併せてみると、住宅ローン金利の上昇が一服していることが住宅需要の増加や景況感の改善につながっていると考えられるが、依然として住宅ローン金利の水準は高く、住宅需要の下押し圧力は強い。今後も住宅ローン金利が高水準で推移することが予想されることから、住宅市場が本格的な回復に向かうのは、FRBによる利下げ開始後になると見込まれる(第I-3-1-5図)。
第Ⅰ-3-1-5図 米国の住宅価格指数と住宅ローン金利
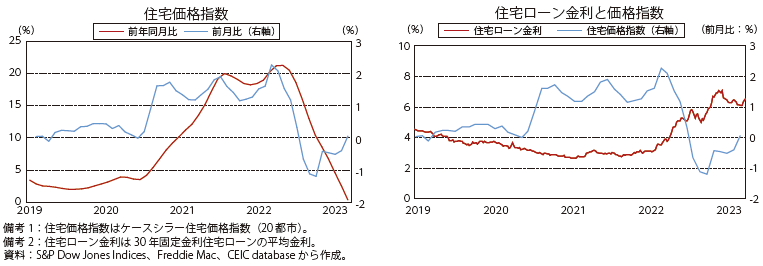
(4)政府支出
政府支出の動向をみると、コロナ禍当初における現金給付や失業給付といった大規模な財政出動を実施した2020年第2四半期や2021年第1四半期には金額が大きく増加している。特に、実質GDP成長率が大きくマイナス成長した2020年第2四半期においては政府支出の対GDP比が高くなっている。2022年は実質GDP成長率と連動しており、対GDP比はほぼ横ばいで推移している(第I-3-1-6図)。
第Ⅰ-3-1-6図 米国の実質政府支出
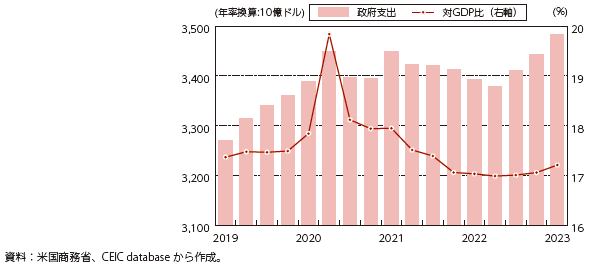
(5)貿易収支
貿易収支についてみると、コロナ禍で輸出の回復の動きが緩やかな中において、財政出動によって財需要が増加したため、輸入の拡大によって貿易収支の赤字幅が拡大していた。2022年には世界的な高インフレや、各国中央銀行の金融引締めによって外需が減速している可能性がうかがえる(第I-3-1-7図)。
第Ⅰ-3-1-7図 米国の貿易収支
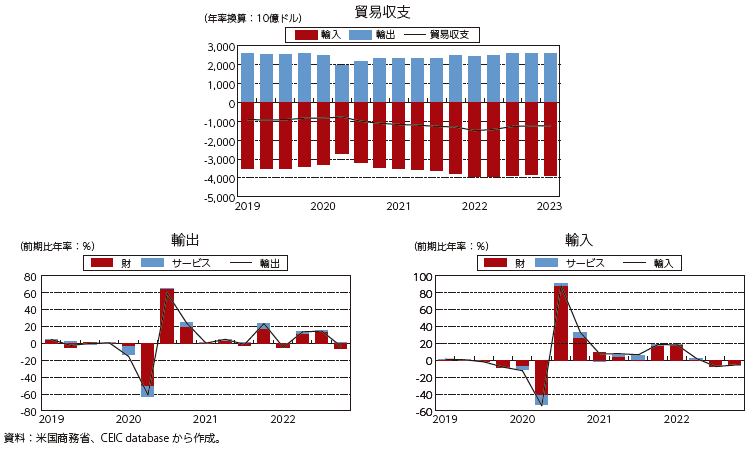
(6)鉱工業生産
米国の鉱工業生産は、コロナ禍で生じた物流混乱や行動制限の緩和によって、製造業を中心に増加基調で推移してきた。一方、足下では金融引締めの進展によって需要の鈍化による生産活動の減速が見受けられる(第I-3-1-8図)。
第Ⅰ-3-1-8図 米国の鉱工業生産
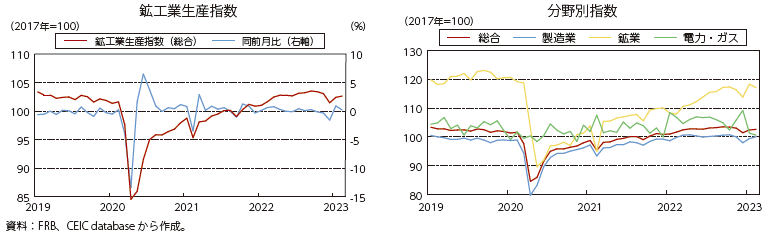
2.物価
(1)消費者物価
米国では2021年以降歴史的な水準でインフレが高進しており、ピークは脱するも、依然として高止まりの状況が続いている。米国の消費者物価指数(Consumer Price Index: CPI)は2022年6月に前年同月比+9.1%と40年ぶりの高さを記録し、その後、ピークアウトして、2023年3月には同+5.0%と8か月連続で伸び率が縮小している。一方で、前月比について、総合指数(2月:前月比+0.4%→3月:同+0.1%)、コア指数(2月:同+0.5%→3月:同+0.4%)とプラスで推移しており、物価上昇率は鈍化基調にあるものの、足下では依然としてインフレ圧力が根強いことを示している(第I-3-1-9図)。
第Ⅰ-3-1-9図 米国の消費者物価指数
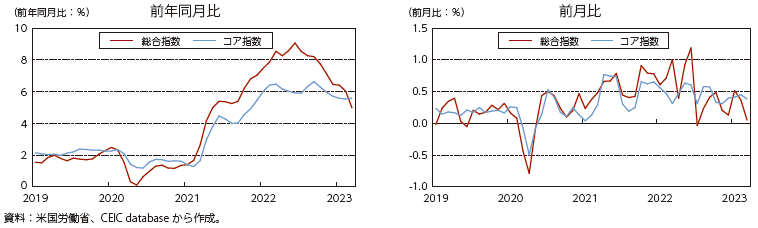
第1章第3節第1項において記しているように、米国におけるインフレの要因は、2021年から2022年初にかけて食品やエネルギーを除く財や、エネルギーが主因であったものの、その後、サービス価格や食料価格の影響が約9割を占める状況となっている。2023年3月にはコア指数の前年同月比が+5.6%であるのに対して、総合指数が+5.0%と、2021年1月以来、約2年ぶりにコア指数が総合指数を上回る状況となっている。
(2)生産者物価
次に、生産者物価指数の動向について見ていく。生産者物価指数は、コロナ禍前には前年同月比+2%程度で推移していたが、経済活動の回復に伴う上昇に加え、ロシアによるウクライナ侵略を背景とした物流制約やエネルギー価格の上昇を映じて、2022年3月時点で最終需要の総合指数が同+11.7%、コア指数については同+9.7%となっている。その後、物流制約やエネルギー価格高騰の緩和を受けてピークアウトし、2023年3月時点で総合指数の前年同月比は+2.7%、コア指数は+3.4%と伸び率が鈍化しており、消費者物価と同様に前年同月比ベースでコア指数が総合指数を上回っており、食品やエネルギーを除く財・サービス(コア指数)がインフレ率高止まりの主因となっている(第I-3-1-10図)。
第Ⅰ-3-1-10図 米国の生産者物価指数
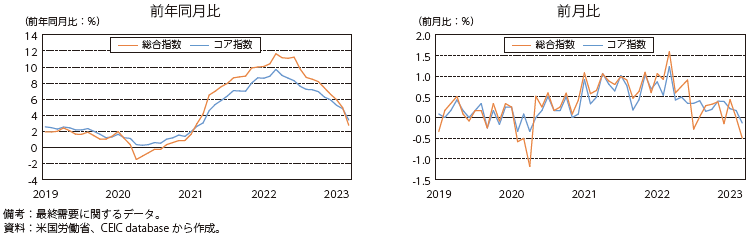
3.労働市場
(1)雇用統計
米国の労働市場ではペースは緩やかではあるものの労働参加率が上昇基調となっている。コロナ禍前の2020年2月に63.3%であった全体の労働参加率は2020年4月の60.1%をボトムとして緩やかに上昇し、2023年3月には62.6%となっている。また、プライムエイジ(25~54歳)の労働参加率についても、2020年2月には83%であったが、2020年4月の79.9%をボトムとして、2023年3月には83.1%となっている。失業率(一般的な失業率であるU-3)は2020年4月には14.7%に達していたが、2023年3月には3.5%と、コロナ禍前の水準へと改善している。また、より広義の失業率である失業率(U-6)は2020年4月には22.4%に達していたが、2023年3月には、6.7%へと改善している。労働参加率が上昇する中で足下では失業率が低下しており、労働需給のひっ迫が継続していることがうかがえる(第I-3-1-11図)。
第Ⅰ-3-1-11図 米国の雇用統計
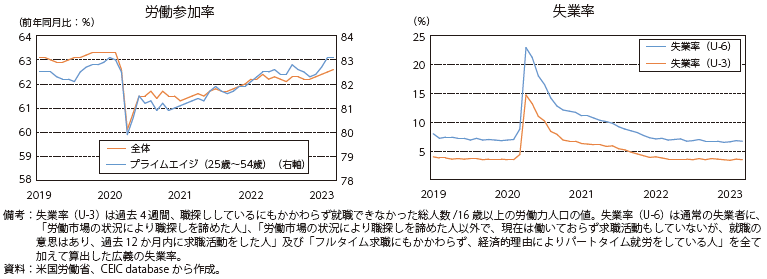
(2)労働需給の状況
2021年以降、経済活動の再開に伴い、求人数が増加しているものの、雇用数は追いついておらず、人手不足が深刻化している。また、労働条件の見直しの動きが活発化していることを映じて自主退職者が増加しており、求人数は過去最多の1,000万人を越える水準になっている。2023年2月には993万人と2021年5月以来の1,000万人を割る水準となったが、依然として高い水準が継続しており、労働需給ひっ迫の様子がうかがえる(第I-3-1-12図)。
第Ⅰ-3-1-12図 米国の求人数、就職者数、退職数
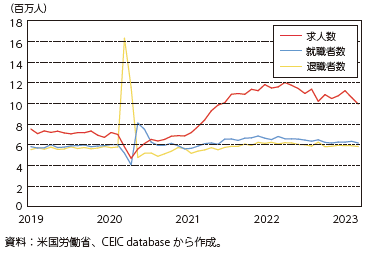
(3)実質賃金と貯蓄率
労働条件見直しといった労働市場の流動性の高まりや人手不足が賃金上昇圧力となり、名目賃金(平均時給)は高止まりとなっている。一方で、賃金上昇がインフレの高進に追いついておらず、2021年11月以降、実質賃金上昇率はマイナスで推移している。実質賃金上昇率は2022年6月の-3.9%をボトムとして、その後、消費者物価の伸び率鈍化を受けてマイナス幅が減少しているものの、2023年3月には-0.7%と依然としてマイナスの水準と継続している。また、貯蓄率はコロナ禍前の2019年には年平均8.8%となっていたが、2022年6月の2.7%をボトムとして、2023年3月現在では5.1%と上昇しており、賃金が目減りする中で消費を抑え始めている可能性がうかがえる(第I-3-1-13図)。
第Ⅰ-3-1-13図 米国の実質賃金上昇率と貯蓄率
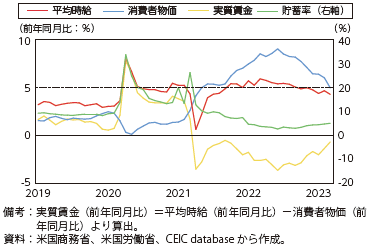
4.金融政策
(1)政策金利の推移
FRBは米国経済におけるインフレの高進を受けて、2022年3月から継続的に政策金利を引上げている。2023年5月2日、3日に開催されたFOMCにおいては、これまでの4.75%~5.00%から0.25%ポイント引上げ5.00%~5.25%としている。2022年には4会合連続で0.75%ポイントの利上げをしたのち、利上げ幅は縮小されているものの、10会合連続での政策金利の引上げとなった。2023年3月のFOMCにおける声明文では、「インフレ率がやや鈍化した」との文言は削除され、「引き続きインフレ率は高止まりしている」とされたが、5月のFOMCにおいても同文言が記されている。また、3月の声明文では「継続的な利上げが適切」との文言が「必要に応じて追加的な金融政策を行うことが適切」へと変更されたが、5月の声明文では同文言は削除となっており、次回の会合(6月13日、14日)における利上げ停止を示唆する内容となっている(第I-3-1-14図)。
第Ⅰ-3-1-14図 米国の政策金利の推移
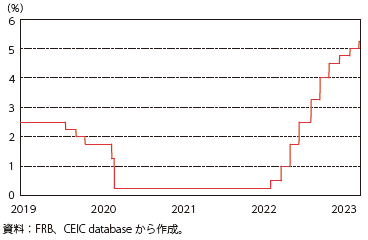
(2)政策金利の見通し
2023年3月のFOMCで公表された各年末時点の政策金利見通し(いわゆるドット・プロット)では2023年末の政策金利誘導目標の中央値は5.125%と、前回(2022年12月)から据え置きとなっている。また、2024年末には4.250%、2025年末には3.125%までそれぞれ引下げられる見通しとなっている。2024年末の見通しは前回から上昇シフトしており、依然としてFRBとしてのインフレリスクに対する警戒がうかがえる(第I-3-1-15図)。
第Ⅰ-3-1-15図 FOMCの政策金利見通し
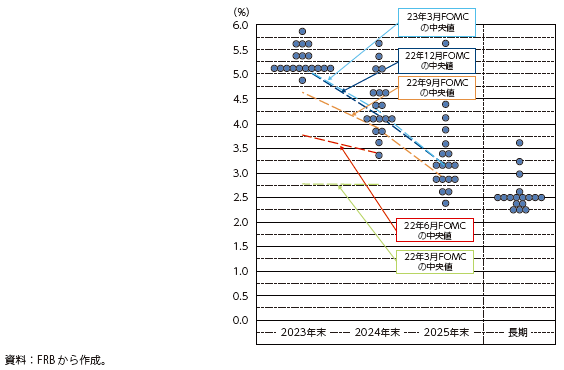
5.今後の見通し
IMFによる経済見通しをみると、2023年の実質GDP成長率とインフレ率のいずれも上方修正が続き、実質GDP成長率は+1.6%、インフレ率(前年比、年平均)は+4.5%との見通しとなっている(第I-3-1-16図)。また、FRBによる経済見通しをみると、実質GDP成長率については、2023年、2024年はともに下方修正が続き、2023年は+0.4%、2024年は+1.2%となっている。FRBが物価指標の中で最も重視しているコアPCE価格指数の見通しについては、2023年は+3.6%、2024年は+2.6%といずれも上方修正が続いており、インフレの長期化や経済の減速に引き続き注視が必要な状況が続いている。
第Ⅰ-3-1-16表 米国の経済見通し