第3節 中国
2022年の中国経済は、ゼロコロナ政策の下、上海の都市封鎖などたびたびの感染拡大による規制の導入等により、低い成長率にとどまった。ここでは主要な統計指標を追いながら経済の推移を見ていく。
1.GDP
2022年の中国の実質GDP成長率は、ゼロコロナ政策による厳格な規制が経済活動の足枷となり、通年で+3.0%と低い伸びにとどまった(第I-3-3-1図)。政府の目標「5.5%前後」を大幅に下回り、新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年(+2.2%)を除けば、マイナス成長であった1976年(-1.6%)以来の低成長となった。需要項目別には、上海の都市封鎖を始め、国内各地にわたる感染症拡大に伴う規制のため、GDPの過半を占める最終消費の寄与が大きく縮小し、世界経済の成長鈍化から純輸出も寄与を落とした。総資本形成も小幅ながら寄与を縮小させた。
第Ⅰ-3-3-1図 中国の実質GDP成長率の推移
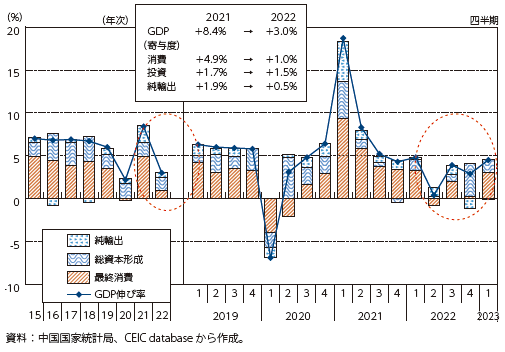
四半期別の推移を見ると、2022年第1四半期は伸びが加速に向かったが、第2四半期は上海の都市封鎖のため成長率が大きく低下し、特に最終消費の寄与がマイナスに落ち込んだ(第I-3-3-2表)。上海の都市封鎖が解除された第3四半期は、回復に向かうが、各地で散発的な感染症による規制が導入され、成長率は低い伸びにとどまった。第4四半期はゼロコロナ政策が大きく緩和されたが、急速な政策変更によって都市部を中心に感染症が急拡大して、最終消費はゼロ成長近くまで低下した。さらに欧米を中心に金利引上げによる景気減速から外需が縮小して純輸出の寄与がマイナスに転じた。このような中で、第4四半期は総資本形成の寄与が大きく拡大しており、政府はインフラ投資などの拡大によって景気の下支えを図ったことがうかがえる。
第Ⅰ-3-3-2表 中国の実質GDP成長率(需要項目別)の推移
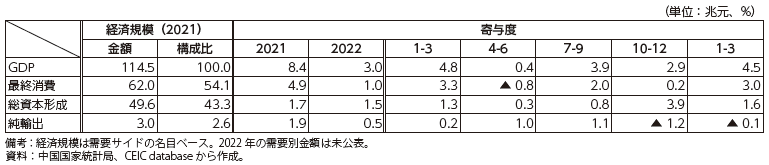
業種別には、第2次産業が通年で+3.8%と、前年(+8.7%)に比べて成長が鈍化した(第I-3-3-3表)。上海の都市封鎖のあった第2四半期に製造業がマイナスに転じるなど大きく成長率を落としたことが影響した。第3次産業も通年で+2.3%と低い伸びにとどまった。特に第2四半期に、感染症の影響から、飲食・宿泊、卸・小売、運輸など接触型サービスを中心とする業種がマイナスに転じ、情報通信・情報サービスの好調にかかわらず、第3次産業全体としてマイナスに陥った。第3四半期はプラス成長に戻ったものの、第4四半期は都市部を中心とする感染症の拡大から、再び、宿泊・飲食、運輸などがマイナスとなった。バブルを警戒した政府の規制により悪化の続く不動産業は年間を通じて前年割れが続いた。
第Ⅰ-3-3-3表 中国の実質GDP成長率(業種別)の推移
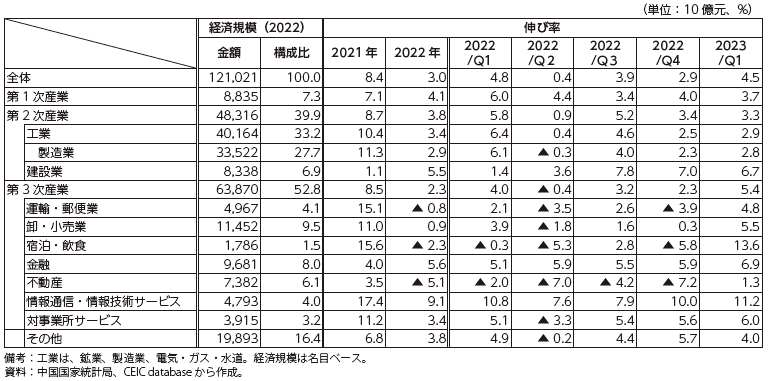
2023年に入ると、第1四半期は、ゼロコロナ政策が終了し、4年ぶりに規制のない春節休暇を受けて、宿泊・飲食、卸・小売、運輸が大きく改善し、第3次産業が全体を押し上げた。なお、不動産も低い伸びながらプラスに転じた。
2.工業生産
ここからは、主要な月次統計を参照しながら、経済動向、特徴的な業種別・品目別の動きを確認していく。まず、工業生産は、2022年通年としては+3.6%と2021年通年の+9.6%から鈍化した(第I-3-3-4図)。4月に上海の都市封鎖のため大きく落ち込んだほか、国内各地で散発的に感染症が拡大した影響で、年間を通じて低い伸びとなった192。生産面では、工場の稼働率の低下やサプライチェーンの混乱が生じるとともに、需要面では、低調な消費や不動産市場の不調などから需要に盛り上がりを欠いた。業種別には、不動産市場の不調から、建材に利用されるセメント、ガラスなどの窯業土石がマイナスとなり、鉄鋼も低い伸びにとどまった(第I-3-3-5表)。工作機械、ロボットなどの一般機械もマイナスに転じ、前年に大きく伸びた医薬品は反動もありマイナスとなった。なお、2023年に入ってからの月次の推移は、2022年末の低い伸びからは緩やかに回復している。
第Ⅰ-3-3-4図 中国の工業生産の推移
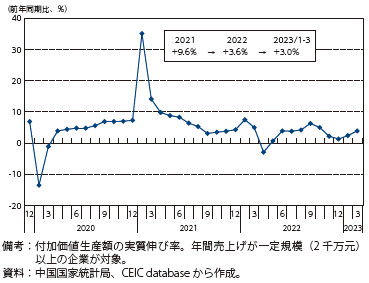
第Ⅰ-3-3-5表 中国の工業生産(業種内訳)
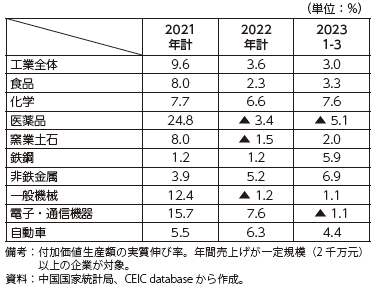
192 前年の2021年が、コロナ禍の反動から、高めの伸び率となっていたことも鈍化の一因といえる。
3.固定資産投資
2022年の固定資産投資の通年伸び率は+5.1%であった(第I-3-3-6図)。業種別には、不動産市場の不調等から、鉱業、製造業は鈍化する一方で、政府の景気支援策により、インフラ等の伸びが加速した(第I-3-3-7表)。なお、病院などの衛生・社会サービスは高い伸びが続いている。企業形態別には、2022年はインフラの入札に強いとの指摘がある国有企業が加速する反面で、民間企業の伸びは鈍化した。2023年に入っても、鉱業、製造業の伸びが鈍く、インフラが下支えする構図や民営企業の苦境が続いている。
第Ⅰ-3-3-6図 中国の固定資産投資の推移
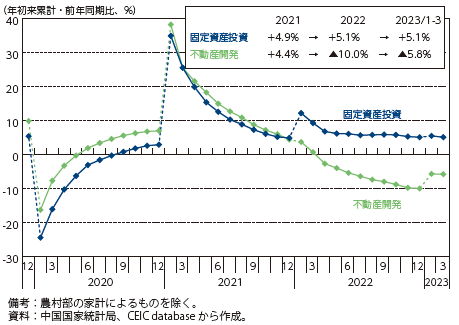
第Ⅰ-3-3-7表 中国の固定資産投資(業種内訳)
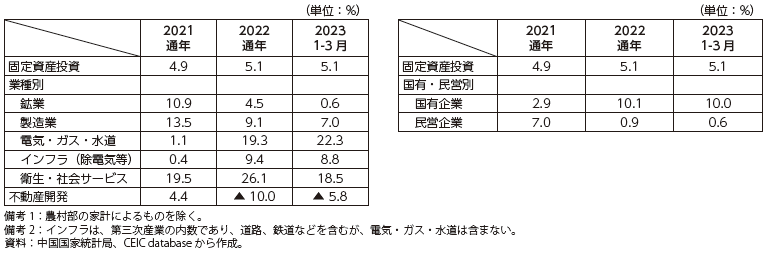
不動産開発は、前年からの悪化が続き、2022年通年で-10.0%と大幅なマイナスに転じた。2023年に入ってから、下落幅は縮小したものの、前年割れが続いている。なお、不動産開発については本節「10. 不動産問題」でより詳しく見ることとする。
4.小売売上高
2022年の小売売上高は、感染症拡大の影響から通年で-0.2%と前年比マイナスに転じた(第I-3-3-8図)。月次の推移を見ると、3月末からの上海の都市封鎖に加えて、年末にも感染症拡大でマイナスに陥った。特に小売売上高の約1割を占める飲食業は感染症の影響を受けやすく通年で-6.3%とマイナスに転じた(第I-3-3-9表)。物品販売も+0.5%の低い伸びにとどまり、家電・映像音響機器、通信機器などの耐久消費財はマイナスに転じ、大型商品である自動車も低い伸びとなった。インターネットを通じた販売はプラスを維持したが、2021年に比べれば大きく鈍化した。2023年に入ると、ゼロコロナ政策の終了により、飲食業中心に回復に向かったが、耐久消費財の不調は続いている。2022年の一人当たり所得の伸びは、名目、実質ともに2021年から鈍化し、コロナ禍前の2019年の伸びには届いていない(第I-3-3-10表)。また、後で見るように雇用環境も厳しく、家計が消費に慎重になっている可能性がある。
第Ⅰ-3-3-8図 中国の小売売上高の推移
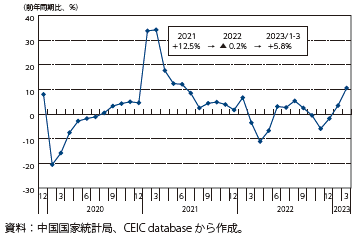
第Ⅰ-3-3-9表 中国の小売売上高(品目内訳)
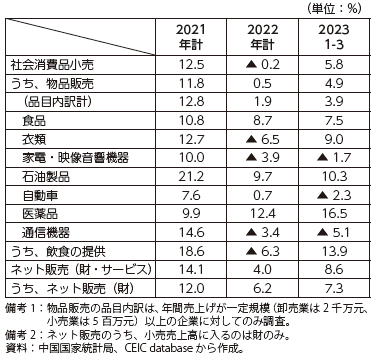
第Ⅰ-3-3-10表 中国の一人当たり可処分所得
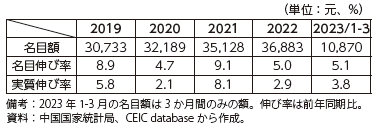
5.貿易
2022年の輸出は通年で+7.0%、輸入は+1.1%と、輸出入とも3割増を記録した2021年から大幅に減速した(第I-3-3-11図)。輸出については、上海都市封鎖のあった4月に伸びが大きく落ち込んだほか、インフレと利上げによる世界経済の成長鈍化のため次第に伸びが低下し、年末にはマイナスに転じた。輸入については、年初からほぼゼロ成長が続き、年末は輸出同様にマイナスに転じている。内外需の弱さの影響が指摘されている。
第Ⅰ-3-3-11図 中国の貿易の推移
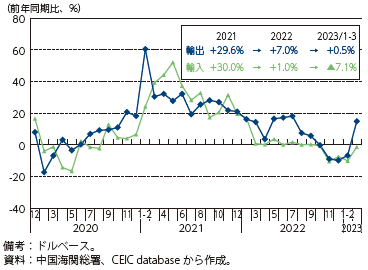
国・地域別には、2022年通年の輸出は、インフレと利上げによる経済減速が指摘される欧米向けが低い伸びにとどまった(第I-3-3-12表)。アジア内はASEAN向けが好調な一方で、台湾向けは低い伸びとなるなど相違が見られる。輸入は大半の主要国でマイナスを記録した。一方、ロシアに対しては、輸出入とも2桁台の高い伸びを記録し、特に輸入の伸びが大きい。
第Ⅰ-3-3-12表 中国の相手国・地域別の貿易の伸び率
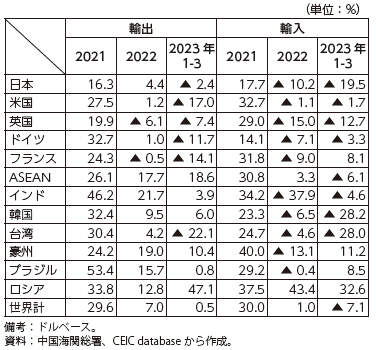
2022年の品目別輸出は、電子計算機、携帯電話、家電など電気・電子機器関係がマイナスに転じ、集積回路も低い伸びにとどまった(第I-3-3-13表)。コロナ禍後のテレワーク等のIT需要が一服したとの見方がある。輸入は原油、天然ガス等は通年でプラスとなったが、弱い内外需から、鉄鉱石、集積回路、電子計算機部品など資源や部材の多くの品目はマイナスを記録した。
第Ⅰ-3-3-13表 中国の主要品目別の貿易の伸び率
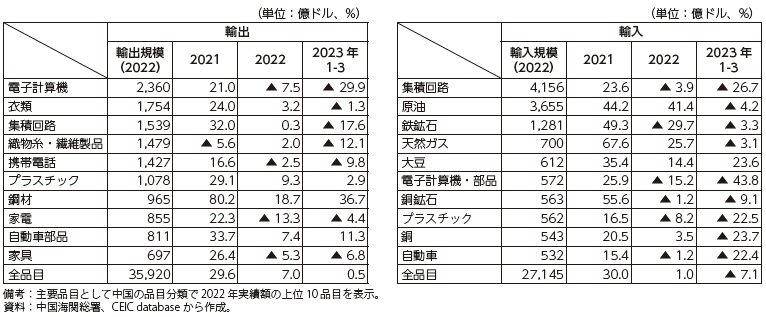
6. 物価
2022年の消費者物価の上昇率は通年で+2.0%と2021年から加速したが、+3%前後という政府の抑制目標は下回った(第I-3-3-14図)。月次の推移を見ると、消費者物価は、食品やエネルギー価格の上昇を背景に2022年初めから秋口まで上昇したが、その後は原油等の国際市況の低下を反映して低下に向かった。一方、食品・エネルギーを除くコア指数は、弱い国内需要のため、年初から次第に減速して、通年で+0.9%と低い伸びにとどまった。
第Ⅰ-3-3-14図 中国の消費者物価・生産者物価の推移
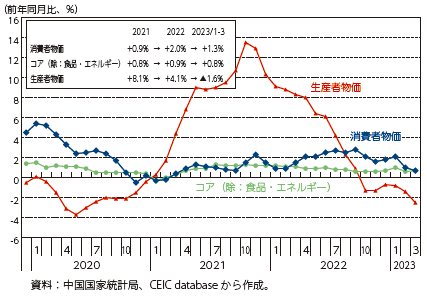
また、生産者物価は通年で+4.1%と前年から鈍化した。原油等の国際市況の低下や中国国内の弱い内需から、年初から鈍化が続いて年末はマイナスに転じた。2023年に入ってもマイナスが続いている。
7. 雇用
2022年の都市部調査失業率は、ほぼ年間を通じて2021年よりも高い失業率で推移した。2022年平均では5.6%と、政府目標「5.5%以下」を小幅ながら上回った(第I-3-3-15図)。特に若年層は、新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年以降、年平均で見た失業率は上昇の一途をたどり、その高さが指摘されている(第I-3-3-16表)。
第Ⅰ-3-3-15図 中国の都市部調査失業率の推移
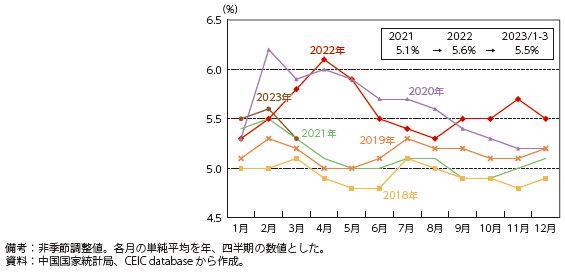
第Ⅰ-3-3-16表 中国の都市部調査失業率(年齢階層別)

また、2022年の都市部新規就業者数は、1206万人と政府目標1200万人を達成したものの、前年比では5.0%の減少となった(第I-3-3-17図)。
第Ⅰ-3-3-17図 中国の都市部新規就業者数(年初来累計・前年同期比)
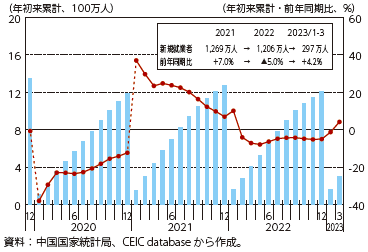
8.政策金利
このように景気に弱さが見られる中で、中国人民銀行(中央銀行)は、2021年から政策金利や預金準備率をたびたび引き下げ、景気下支えを図ってきた。特に不動産市場の不調を受けて、住宅ローン金利に参照される5年物最優遇貸出金利(LPR)を2022年1月に0.05%ポイント引き下げるとともに、5月及び8月にはそれぞれ0.15%ポイントもの大幅引下げを行った(第I-3-3-18図)。預金準備率については、2021年7月から段階的に引き下げ、銀行が融資を拡大できるよう余力を与えた(第I-3-3-19図)。
第Ⅰ-3-3-18図 中国の最優遇貸出金利(LPR)の推移
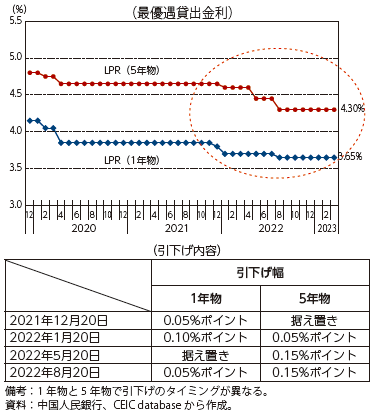
第Ⅰ-3-3-19図 中国の預金準備率の推移
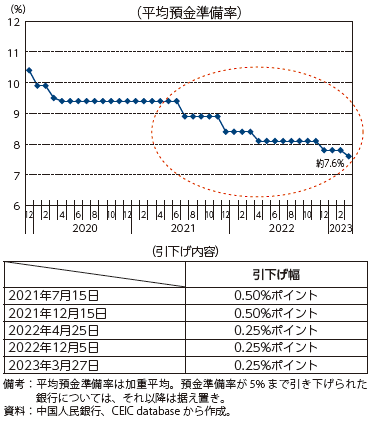
9. 人口動態
これまで最近の中国の景気動向を見てきたが、長期的な成長を考える上では構造的な問題にも目を向ける必要がある。これ以降、いくつかの構造的な課題について考察する。
まず、少子高齢化の進む人口動態を見てみる。国連の人口推計(中位推計)によれば、中国の生産年齢人口は既に2011年にピークを迎え、総人口も2021年にピークに達したと見られる(第I-3-3-20図)193。仮に国連推計どおりに推移するとすれば、2050年までに、生産年齢人口、年少人口は、それぞれ2.2億人、1億人減少し、反対に老齢人口は2.3億人増加する。その結果、総人口は1億人減少し、生産年齢人口比率はほぼ50%まで低下し、生産年齢人口1人が0.8人の高齢者と0.2人の年少者の負担をする計算となる(第I-3-3-21表)。
第Ⅰ-3-3-20図 中国の人口構成の将来予測(国連推計)
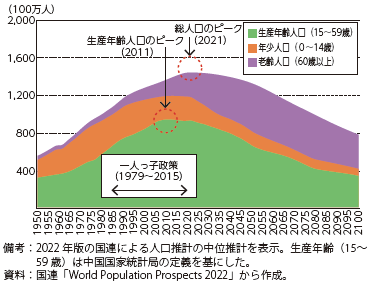
第Ⅰ-3-3-21表 中国の人口予測
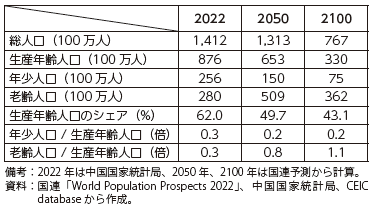
将来の人口動態は、1人の女性が一生の間に出産する子どもの推定値である合計特殊出生率に影響され、人口を維持するためには2.1程度が必要とされる。中国については最新の第七次人口センサス(2020年の全国民を対象とする調査)で1.3という低い数値が公表されている。その背景には長年にわたる一人っ子政策の影響が挙げられる。一人っ子政策は2015年末に廃止され、すべての夫婦に2人目が認められ、さらに2021年以降は3人目まで認められているが、生活費や養育費の問題、生活パターンの変化等から、期待されたほど出生率は上がっていないことが示唆される(第I-3-3-22図)。このような人口動態は将来の経済成長や次に見る住宅などの需要動向に影響する。
第Ⅰ-3-3-22図 中国の人口に対する出生率及び死亡率の推移
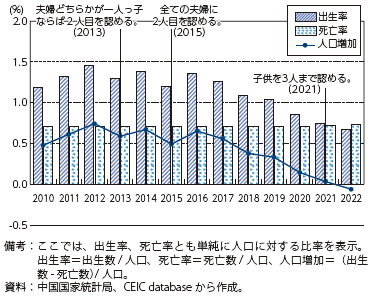
193 生産年齢人口の定義は中国国家統計局プレス発表にある「16~59 歳」を基本とした(下記アドレス参照)。第I-3-3-20 図は国連推計データを基にしているが、国連推計では5 歳きざみの推計値となるため、便宜的に最も近い「15~59 歳」を生産年齢人口としてプロットした。なお、統計局定義より1 歳分だけ幅が広がるが、動向に大きな相違はない。中国国家統計局が公表した「16~59 歳」データを基にしても、生産年齢人口は2011 年にピークに達しており、総人口についても、2022 年は14 億1175 万人と2021 年の14 億1260 万人から減少したことが公表されている。(http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202301/t20230117_1892094.html![]() )
)
10.不動産問題
中国では不動産開発は経済への影響が大きいことが指摘されている。不動産部門にとどまらず、鉄鋼、セメント、ガラスなど建設資材や、購入者が新しい家庭を築くための、家具、家電製品、自動車など耐久消費財の需要を誘発するなど関連部門への影響が大きい。一方で、住宅市場に資金が流入して価格が高騰し、バブルの危険性もたびたび指摘され、政府が規制を導入して加熱を抑制するなどの対策がとられることも多かった(第I-3-3-23図)。コロナ禍後の金融緩和に際して、不動産バブルを警戒した中国政府は「住宅は住むものであって投機をするものではない」との方針の下、2020年8月に「三つのレッドライン」と呼ばれる不動産会社への財務規制や2020年12月末には銀行への不動産融資への規制を課した。その結果、借り入れや前払い金に依存していた恒大など大手不動産会社の資金繰りが悪化し、不動産開発の減速を余儀なくされるにとどまらず、建設工事の中断や引渡しの停滞なども生じた194(第I-3-3-24図)。このような事態は住宅取引への信頼を損ね、一部には住宅ローンの不払い運動に発展するなど、不動産市場の悪化をもたらした。2022年の住宅販売面積は前年比3割近く減少しており、2022年の不動産開発投資の前年比は毎月悪化幅の拡大が続いた(第I-3-3-25図)。
第Ⅰ-3-3-23図 中国の主要都市の新築住宅販売価格の推移
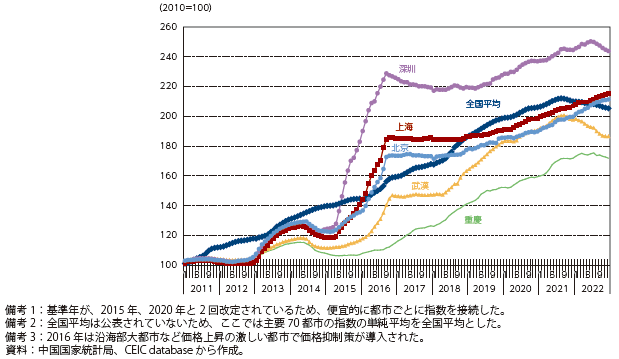
第Ⅰ-3-3-24図 中国の不動産会社の資金調達の推移
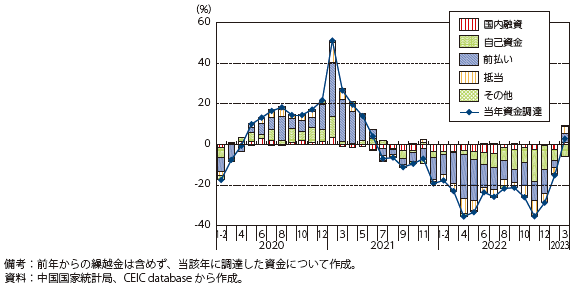
第Ⅰ-3-3-25図 中国の住宅販売・不動産開発投資の推移
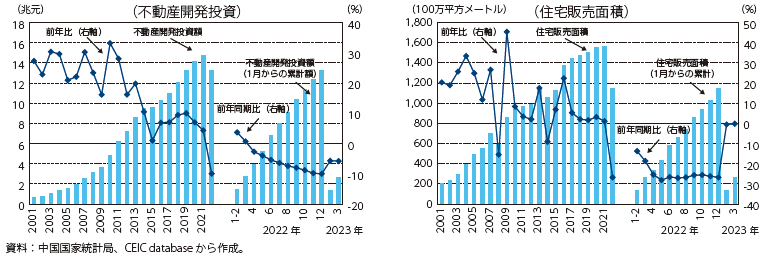
新築住宅の価格動向を見ると、新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年前半は、武漢や北京などで横ばいとなったが、景気支援の金融緩和を背景に、年半ば以降は上昇に転じた。これに対して不動産規制が導入され、2021年半ばから全国平均は低下に向かった。資金繰りに窮した不動産会社が価格引下げを行ったことも低下に拍車をかけた。なお、都市別に相違があり、北京、上海など大都市で上昇が続くが、武漢、重慶など地方都市で価格が低下している。既に記したような不動産の引き渡しへの不安に加えて、将来の値上がり期待の低下や購入後の資産価格の下落懸念なども、住宅市場の悪化につながったと見られる。2023年に入ると住宅価格については好転の動きも見られる195。
また、住宅販売や不動産開発は、第I-3-3-25図が示すように短期的な動きだけでなく、長期的な視点で見ても2000年代は次第に減速してきている。先に見た少子高齢化という人口動態も考えると、将来結婚して新たな家庭を築くと思われる年齢層は先細りであり、不動産開発に多くを依存する成長モデルは持続が難しい(第I-3-3-26図)。
第Ⅰ-3-3-26図 中国の25~34歳の人口予測196。
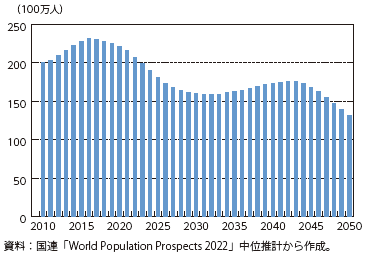
このような中で、政府は政策金利引下げなどの金融緩和を行うとともに、不動産規制の緩和、不動産業界への融資拡大などで不動産市場の安定化を図ろうとしている。不動産開発は下落幅が縮小したものの、2023年初頭時点でも前年割れが続いている。
194 中国ではマンション購入者は工事完了前に前払いをする慣行があるが、一部の不動産会社は前払金を別のプロジェクトに流用していたため、資金繰りがつかず、工事中断にいたるケースが続発した。
195 2023年から第I-3-3-23図の統計は公表されなくなったが、別の統計で見ると、主要70都市のうち、前月に比べて価格上昇した都市は、2022年12月の15都市から、2023年3月は全体の約9割に当たる64都市へと拡大し、価格回復の動きが広がっている。
196 この年齢層に結婚して住宅購入する者が多いとの指摘がある(福本智之「苦境続く中国経済㊤-人口動態、不動産不況に影響」(2022年9月5日付け日本経済新聞「経済教室」)など)。
11.地方政府財政
先に見た不動産市場の低迷は中国の地方政府の財政にも影響を与えている。中国では土地の所有権は国家にあり、地方政府は土地の使用権を不動産開発業者に譲渡することで収入を得てきた。特に2010年代後半、土地使用権譲渡収入の総歳入に占めるシェアは年々拡大し2021年には約3割を占めるに至っていた(第I-3-3-27図)。しかしながら、2022年は、感染症対策、景気対策などから必要な支出は拡大するのに対して、低調な不動産開発から土地使用権譲渡収入は前年比で4分の1近い減少となった197。。
第Ⅰ-3-3-27図 中国の地方政府の土地使用権譲渡収入の推移
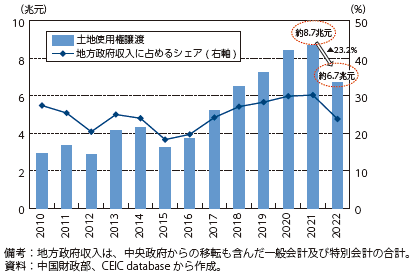
一方で、地方政府が発行できる地方債は中央政府から上限が定められているが、毎年、発行されているため、債務残高は拡大している。債務残高のGDP比を見ると、2018年末に約20%だったが、新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年に急速に上昇し、2022年末までの4年間で10ポイント近く上昇している(第I-3-3-28図)。さらに地方政府傘下の地方融資平台の債務を指摘する声もある。このような中で地方政府収入が減少したことで、財政基盤の弱い地方政府の債務不安が指摘されている。
第Ⅰ-3-3-28図 中国の地方債務残高の推移
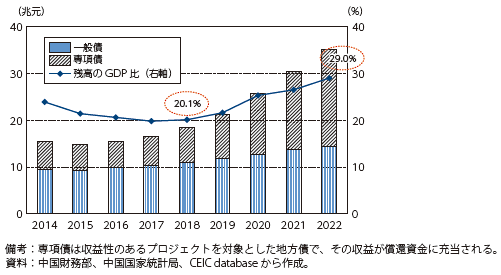
197 2023年1-3月期においても、土地使用権譲渡収入は、8,728億元、前年同期比-27%と大幅な減少が続いている。
12.今後の見通しと中国政府の政策
今後の中国の経済成長の見通しと中国政府の目標や政策について見ていく。まず、2023年、2024年の経済成長については、主要な国際機関から見通しが公表されている。それによれば、2023年はおおむね5%前後の成長率と見通されており、2024年はやや減速して4%台半ばから後半と見られている(第I-3-3-29表)。
第Ⅰ-3-3-29表 中国の実質GDP成長率の見通し
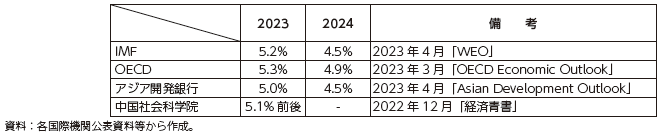
次に中国政府の経済運営方針を見てみる。中国政府は、2023年3月、全国人民代表大会(全人代、我が国の国会に相当)を開催して、今年の主要な数値目標や政策方針を公表した。今年の経済運営の基本方針としては、昨年同様、経済の安定を重視する方針が掲げられている。今年の経済成長率の目標は「5%前後」と昨年の「5.5%前後」から引き下げられた(第I-3-3-30表)。昨年はゼロコロナ政策の下で3.0%の低い成長率にとどまり、目標の達成はかなわなかった。今年の成長率目標が5%前後とされた背景には、ゼロコロナ政策が終了し、経済活動の正常化が進むと見られるが、消費を中心とする内需の動向や世界経済の先行きなど不透明な面があることも考慮されたものと見られる。この目標値は先に記載した国際機関の見通しに近い。雇用については、都市部新規就業者数の目標が1,200万人と昨年の1,100万人から引き上げられた。今年の大学卒業者は1,158万人いると見られ、若年層の失業率が高い中で、雇用を安定させる観点からの変更ではないかとの指摘がある。一方、都市部調査失業率は昨年の目標「5.5%以下」に対して、実績は年間平均で「5.6%」とわずかに外れており、今年は「5.5%前後」と幅のある目標となっている。消費者物価は昨年と同じ「3%前後」とされた。これら目標を達成するため、積極的な財政政策として、財政赤字は対GDP比で3%(昨年は2.8%前後)、地方政府の専項債は3.8兆元(昨年は3.65兆元)と昨年より高めの目標となっている198。。
第Ⅰ-3-3-30表 中国の2023年の主要数値目標
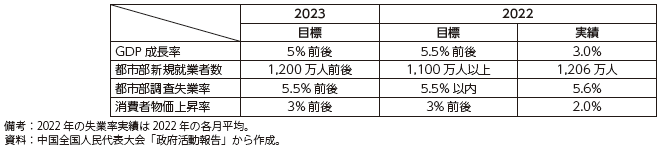
198 2022年の専項債3.65兆元は、3月の全人代で決定された当初額。8月に0.5兆元が増額され、最終的には4兆元を超える専項債が発行された。