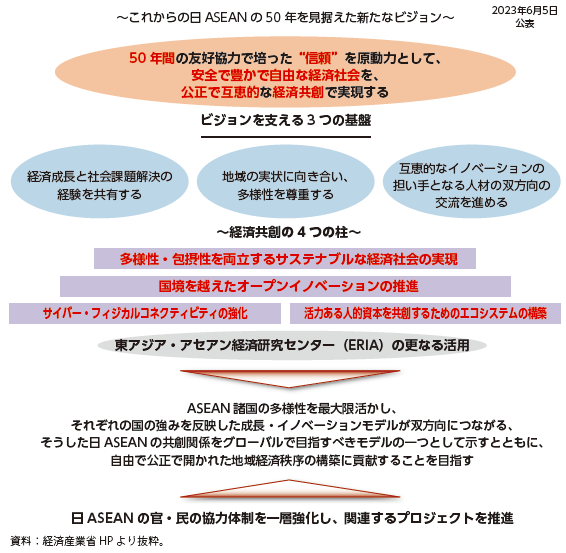第1節 我が国を取り巻くグローバル・バリューチェーンの強靱化
本章では、米中貿易摩擦の激化や権威主義国家の台頭等により、地政学的リスク、経済安全保障上のリスクを中心に、我が国企業を取り巻くサプライチェーンリスクに対する認識が高まっていることを指摘するとともに、こうした背景から調達・販売・投資先として重視する国・地域が変化してきていることを指摘した上で、こうした情勢の変化も踏まえた我が国を取り巻くグローバル・バリューチェーンの強靱化に向けた課題について整理する。また、不確実性の高まりにより厳しさを増すサプライチェーン環境の中で、我が国における経済安全保障政策の展開や、半導体等重要物資における国内製造拠点強化の取組について紹介する。
1.グローバル・バリューチェーンの実態
(1)日系製造業の海外展開
我が国企業のグローバル・バリューチェーンを把握するに当たって、まず、日系製造業の生産拠点の海外展開を概観する。それは日本国内の本社を含めた生産拠点間の資材の流れが、グローバル・バリューチェーンの重要部分を構成すると考えられるからである200。まず、対外直接投資統計で日系製造業の海外展開を見るとアジアへの立地が多いことが分かる。残高ベースで約4割がアジアに投資されており、そのシェアは拡大傾向にある(第II-1-1-1図)。
第Ⅱ-1-1-1図 日本の対外直接投資残高(製造業分野)の推移
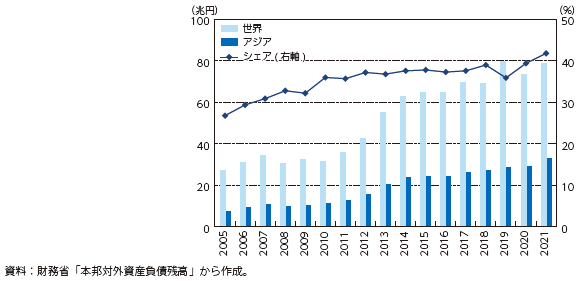
アジアの中での立地先としては、「世界の工場」ともいわれる中国が最大で、タイが続いている(第II-1-1-2図)201。中国への投資は金額ベースでの拡大が続くが、総投資残高に占めるシェアは2012年をピークに縮小に転じている。かわって、タイ、インド、ベトナムなどのシェアが上昇しており、分散化が緩やかに進行していることが分かる。また、ASEANを一つの地域と考えれば、中国を上回る投資規模を有しており、2010年代半ば以降、中国より速いテンポで残高、シェアの拡大が続いている。なお、2020年以降は再び中国のシェアが拡大する動きが見られ、新型コロナウイルス感染症拡大により世界経済の成長が減速した中で、プラス成長を実現した影響が考えられる。
第Ⅱ-1-1-2図 日本のアジア主要国・地域向け直接投資残高(製造業部門)
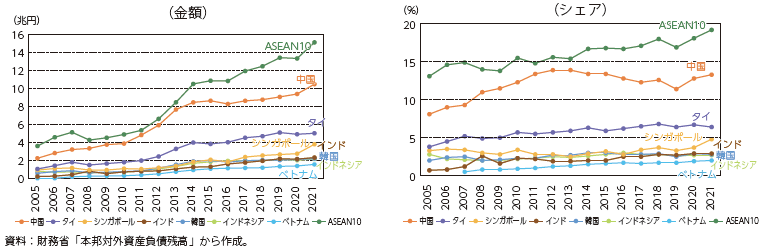
日系企業の立地や調達の流れについて企業統計を使って確認する。経済産業省「海外事業活動基本調査」によれば、世界で日系製造業現地法人は約11,000社が操業している(第II-1-1-3表)202。そのうち、約8割に当たる約8,500社がアジアに立地しており、企業数ベースで見ると製造業のアジア展開はより顕著に現れている。アジアの中では、中国とASEANが主要な立地地域であり、業種としては、化学、鉄鋼・金属などの素材関係、一般機械、電気・情報通信機械、輸送機械などの機械関係が多い。これらの業種では国際的な生産分業が発達しており、国境をまたいだ資材調達が行われている。
第Ⅱ-1-1-3表 日系海外現地法人の企業数(2020年度)
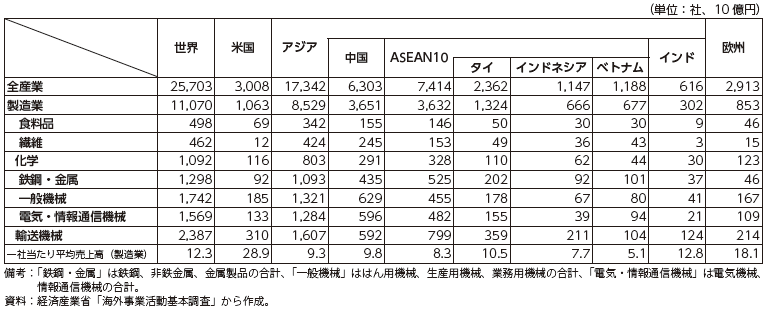
これら海外の生産拠点と日本国内の生産拠点間の部材調達の流れを考察する(第II-1-1-4図)。海外現地法人の部材調達は、日本(本社)、現地国内、地域内を中心にやりとりが観察され、立地国での現地調達がもっとも大きいが、日本からも現地生産が出来ない基幹部品を中心に一定額の部材を供給している。なお、アジア域内での調達は大きいが、アジアと北米、アジアと欧州など地域をまたいだ調達は金額的には限られている。
第Ⅱ-1-1-4図 日系製造業の立地・調達(2020年度)
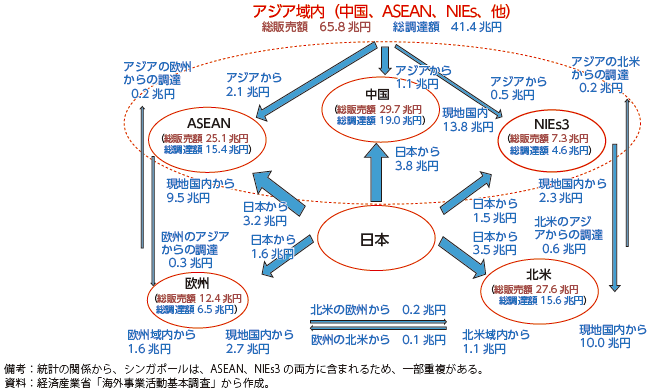
アジアに立地する製造業現地法人の調達先の推移を見ると、現地に進出した日系企業も含めた現地調達が拡大してきている(第II-1-1-5図、第II-1-1-6図)。日本からの調達は金額ベースではある程度維持されるものの、シェアとしては2割程度まで低下している。ただし、シェアは高くないとしても、生産に必須な基幹部品が多いと見られ、東日本大震災の際、国内からの部材供給の停滞が、海外拠点の生産にまで影響が及んだ。この傾向は中国、ASEANとも大きくは変わらないが、両地域を比べると、中国の場合は国内現地調達がやや多く、現地において日系企業、地場企業を含めた産業集積が発達していることを示唆している。一方、ASEANはアジア域内調達が相対的に多く、ASEAN相互での部材の融通をしていることが考えられる。このようなASEAN域内での相互調達から2011年のタイの洪水の際には他のASEAN諸国へも影響が及んだと考えられる。なお、業種別には、情報通信機械は日本やアジア域内からの調達が多く、輸送機械は現地調達が多いなどの業種別特性が見られる(第II-1-1-7図)。
第Ⅱ-1-1-5図 アジア(中国・ASEAN)に立地する日系製造業現地法人の調達先(金額)
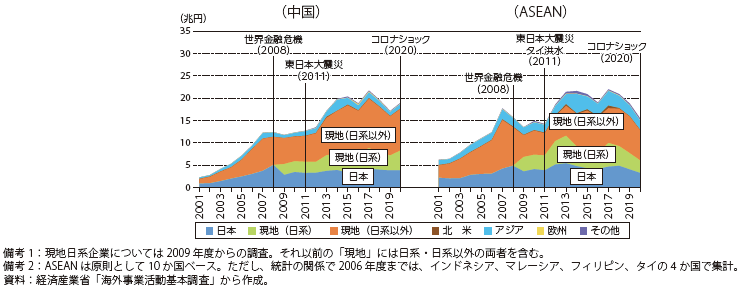
第Ⅱ-1-1-6図 アジア(中国・ASEAN)に立地する日系製造業現地法人の調達先(シェア)
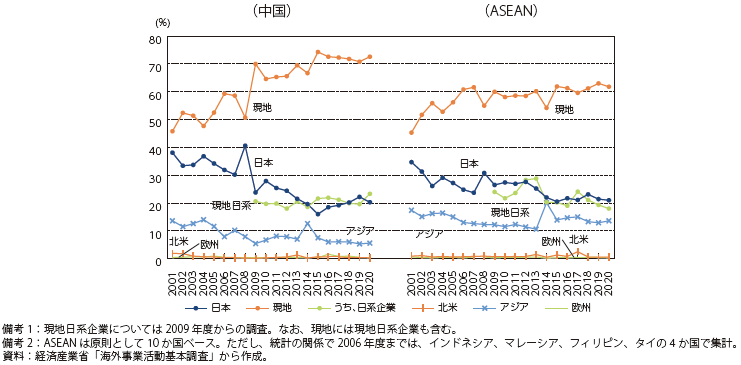
第Ⅱ-1-1-7図 アジアに立地する日系製造業現地法人の調達先(業種別)
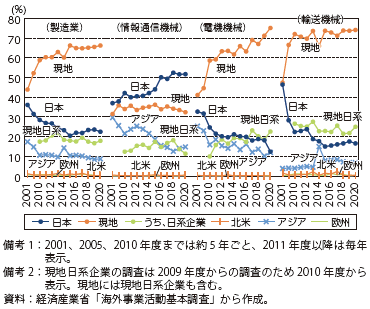
一方、日本国内の製造業の調達額を「経済産業省企業活動基本調査」で見ると、世界金融危機、東日本大震災に際して減少したが、その後は緩やかに回復し、2010年代半ば以降はほぼ横ばいで推移している(第II-1-1-8図)。調達先については、金融危機後から2010年代中頃にかけて、海外からの調達シェアが上昇に向かっており、特に中国を含むアジアのシェアが上昇している。海外から労働集約的な汎用部材を調達して、日本で製造するようなケースが考えられる。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大以降、海外、特に中国からの部材の供給が寸断され、日本国内での生産が滞ったことで、海外からの調達に関するリスクへの懸念が高まった。
第Ⅱ-1-1-8図 日本に立地する機械製造業の総調達額に占める調達先シェア
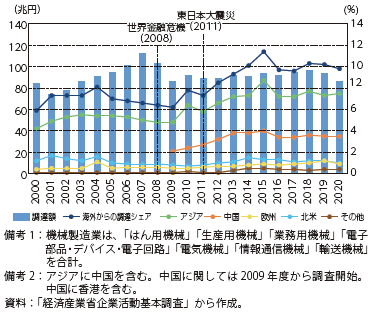
業種別に見ると、電子部品、情報通信機械等で、中国を中心に海外からの調達シェアが上昇している(第II-1-1-9図)。なお、輸送機械は海外からの調達比率は必ずしも高くないが、代表的な製品である自動車は部品点数の多い、すりあわせ型の製品といわれ、少数の部品でも不足すれば生産に大きな影響が生じる可能性がある。
第Ⅱ-1-1-9図 日本に立地する機械製造業の調達先シェア(業種別)
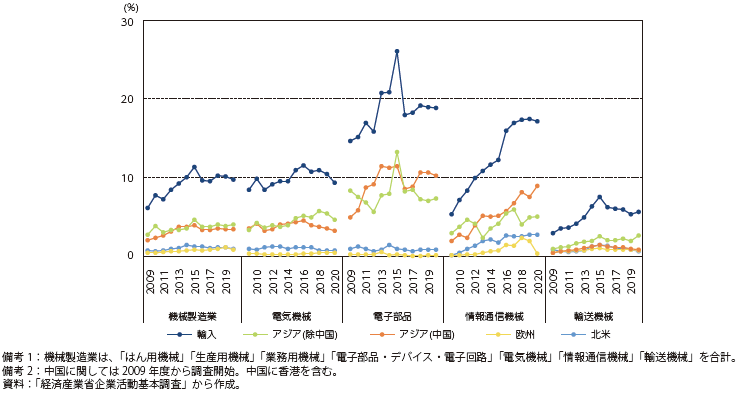
また、日系機械製造業の海外からの調達は、国内からの調達に比べて、企業内取引の面が強い(第II-1-1-10図)203。具体的には、海外からの調達先は、資本関係のある関係会社からの調達シェアが高く、品質の確証や日本にある本社のコントロールが効きやすい点が影響していると考えられる204。また、地域別には、中国からの調達は相対的に企業内調達のシェアが高く、欧米からの調達では相対的に低い。
第Ⅱ-1-1-10図 日本に立地する機械製造業の調達における関係会社からの調達シェア
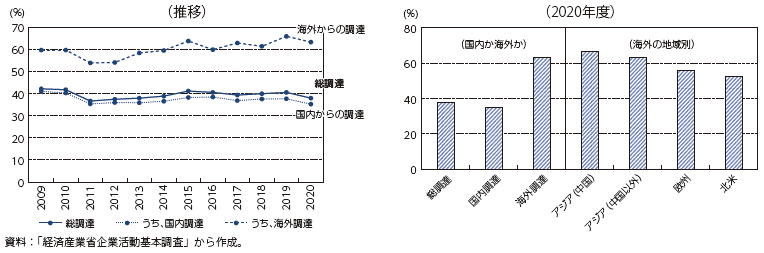
海外現地法人の立地の見直しという観点から、「海外事業活動基本調査」で「新規設立」、「解散・撤退・出資比率低下」(以下「撤退等」と略す)の動向を見ると、経済的ショックの後には、立地見直しの動きが観察される。例えば、世界金融危機の際は、2008年度と直後の2009年度に新規設立件数が低下して解散等が増加している(第II-1-1-11図)。新型コロナウイルス感染症の拡大した2020年度も同様である。反対に東日本大震災やタイの洪水の影響で2011年度は、ASEANや中国を中心に新規設立件数が増加しており、翌2012年度も増加が続いている。災害を踏まえて被災した施設の再配置が行われたことが示唆される。また、国・地域別の特色を見ると、各国・地域とも、毎年、一定数の新規設立、撤退等が見られるが、2000年代は中国への新規設立が多く、反対に2010年代に入ってからは、中国からの撤退等を選ぶ企業が増えている205。中国における撤退等を業種別に見ると、繊維など労働集約的業種のほか、電機・情報通信機械、輸送機械などの機械製造業の立地見直しが多い(第II-1-1-12図)。もちろん、立地企業総数と比べれば必ずしも高い比率ではなく、多くの企業は操業を続けている点には注意が必要であるが、企業は事業環境やリスクに応じて、常に立地の見直しを進めていることがうかがえる。
第Ⅱ-1-1-11図 日系製造業現地法人の新規設立、撤退等の企業数
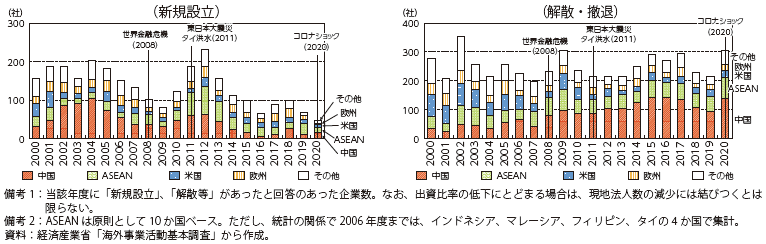
第Ⅱ-1-1-12図 撤退等企業の主要な業種(2020年度)
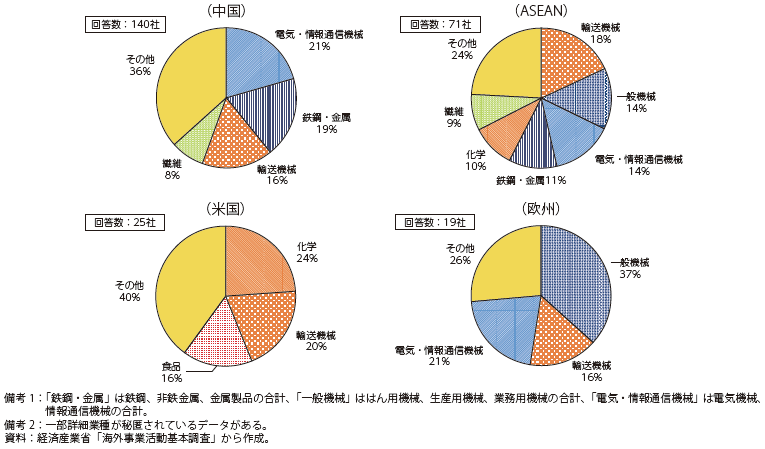
以上をまとめると、我が国を取り巻くグローバル・バリューチェーンの変遷は以下のとおりである。我が国の製造業はアジアを中心に海外展開し、生産拠点間のグローバル・バリューチェーンが形成された。中国のプレゼンスは高いが、ASEAN諸国への分散化の動きも見られる。海外の生産拠点は調達の現地化も進んだが、情報通信機器製造業を筆頭に、基幹部品など日本から一定の調達は続いている。日本国内の生産拠点では、世界金融危機、東日本大震災後、海外からの調達シェアが上昇して、中国への部材依存も高まった。しかし、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大を契機に供給寸断への懸念も認識されるようになった。企業は災害や経済的ショックなど事業環境に応じて、生産拠点の見直しを行っており、依然として操業を続ける企業は多いものの、一部には中国などの拠点を見直す動きも見られる。
200 一般に、グローバル・バリューチェーンは、企画、研究開発から、製造、販売、メンテナンスに至る広い範囲を指すが、サプライチェーン(供給網)は、その中でも特に製造過程における原料資材・製品の供給網を指すことが多い。両者は意味が重なることが多く、本節においても厳密な区別をしないこととする。
201 本節において、特に断らない限り、中国は本土のみで香港は含まない。ASEANは10か国ベース。
202 経済産業省「海外事業活動基本調査」は、海外に現地法人を有する日本企業(金融・保険業、不動産業を除く)に対する調査。ここで、「海外現地法人」とは、「海外子会社」と「海外孫会社」を総称し、「海外子会社」とは、日本側出資比率が10%以上の外国法人を指し、「海外孫会社」とは、日本側出資比率が50%超の海外子会社が50%超の出資を行っている外国法人を指す。回収率は75.2%(2020年度実績調査)。
203 製造業全体とすると原油の輸入精製なども含まれ焦点がぼやけてしまうため、グローバル・バリューチェーンの分析に当たって機械製造 業に絞った。
204 「経済産業省企業活動基本調査」において、「関係会社」とは、「親会社」、「子会社」及び「関連会社」をいう。「親会社」とは、企業の議決権の50%を超えて所有している会社。「子会社」とは、企業が50%超の議決権を所有する会社(50%以下であっても実質的に支配している会社も含む)。「関連会社」とは、企業が20%以上50%以下の議決権を所有する会社(15%以上20%未満であっても重要な影響を与えることができる会社を含む)。
205 2000年代の新規設立の増加は2001年末にWTOに加盟した中国への期待が高まっていたことがうかがえる。2010年代の撤退等の増加は、2012年の尖閣諸島国有化による抗日運動の高まりや2015年の6月からの上海株式市場の急落、8月の人民元切下げ等による中国経済への信頼低下が背景にあることが考えられる。
(2)主要国のグローバル・バリューチェーン
ここまで我が国製造業の海外展開や国際的な資材の流れ(グローバル・バリューチェーン)を見てきたが、日本以外の諸外国はどうなっているであろうか。国際的な資材の流れは貿易統計で補足できるが、国際的な生産分業に基づくグローバル・バリューチェーンにおいては、中間財の形で海外において生産された付加価値が集積していくため、通常の貿易統計では把握が困難になってきている。このような問題に対処するため、OECDは付加価値貿易統計(OECD TiVA)を開発した。ここではOECD TiVAを利用して、主要国・地域のグローバル・バリューチェーンへの参加の実態を考察する206。
グローバル・バリューチェーンへの参加には二通りのタイプがあり、単純な例を挙げれば、A国のように生産工程の上流に位置して中間財を供給するケース(前方参加)とB国のように自国の生産のために中間財の供給を受けるケース(後方参加)がある(第II-1-1-13図)。
第Ⅱ-1-1-13図 グローバル・バリューチェーンへの前方参加・後方参加
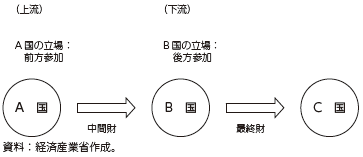
主要国の特徴を見ると、一般に日本や欧米先進国は中間財を供給する前方参加が大きく、中国、ベトナムなど新興国は中間財の供給を受けて国内で組み立てる後方参加の形で、グローバル・バリューチェーンに参加することが多い(第II-1-1-14図)。この関係は当該国の産業・貿易構造の変化によって変わってきている。例えば日本においては2000年代、前方参加が安定的に推移する一方で、次第に後方参加も拡大してきた。反対に中国は、他国からの中間財を受けて加工組立てを行う後方参加から、むしろ他国へ中間財を供給する前方参加へとシフトしている。言い換えれば、中国は単なる加工組立てを行う生産地から、他国に中間財を供給する立場に変わってきている。そのことを相手国の側から見れば、中間財の中国依存が強まっていることを意味し、新型コロナウイルス感染症拡大時に起きたようなグローバル・バリューチェーン途絶のリスクも高まっていることを示唆している。
第Ⅱ-1-1-14図 主要国のグローバル・バリューチェーンへの参加(世界との前方連関・後方連関)
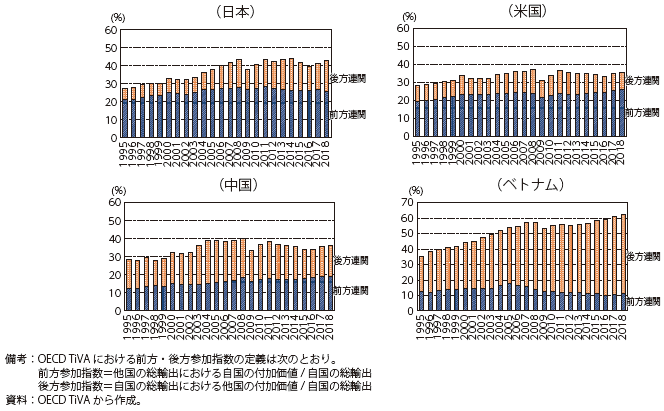
(主要国・地域と中国との関係)
そこでOECD TiVAを利用して、主要国・地域と中国とのグローバル・バリューチェーン上の関係を見てみる。第II-1-1-15図は横軸にOECDが定義するグローバル・バリューチェーンへの前方参加指数、縦軸に後方参加指数をプロットし、円は各国・地域の総輸出額の大きさを反映している。いくつかのグループに分けて考えれば特徴が分かり易い。例えば、韓国、台湾は中国に中間財を供給する前方参加を中心に中国と特に強い関係を有している。豪州、サウジアラビアなど資源国は資源の供給を通じて中国との間で強い前方連関を持っている。このグループの中には、中央アジアの一帯一路沿線国のカザフスタンやロシアも含まれる。中央部にASEAN諸国が展開している。ASEANの中でも、ベトナム、カンボジア、タイ、シンガポールなどは、中国から中間財の供給を受けて加工、組立て、輸出を行う後方連関の強い国が多い。一方で、ASEANの中でも、資源国でもあるインドネシア、半導体を中国に輸出しているフィリピン、マレーシアなどは、前方連関も強く双方向の関係を有している。欧米主要国は左下に固まっており、貿易額は大きいものの、他に関係の強い国(例えば欧州諸国にとって同じ欧州諸国、米国にとってカナダ・メキシコなど)があるため中国とのグローバル・バリューチェーン指数は必ずしも大きくはない。アジアの中では中国との関係の薄いインドもこの位置にいる。日本は中国と前方連関の方がやや強いが、後方も強い関係を有している。
第Ⅱ-1-1-15図 主要国・地域の中国との前方連関・後方連関
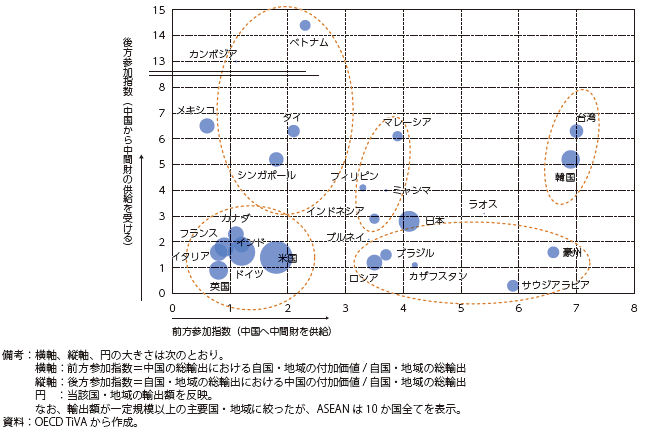
時系列での変化を見ると、各国・地域とも、中国がWTOに加盟した2000年から2005年の間に急速に中国との関係が強まっている(第Ⅱ-1-1-16図)。その後、日本は、垂直方向の移動が多く、中国から中間財の供給を受ける後方連関を強めていることが分かる207。一方、韓国、台湾は、その後も斜め上方に移動して前方・後方とも中国との関係を強めている。ASEANの場合、国による相違があり、資源国でもあるインドネシアが水平方向に移動し、中国との前方連関を強めているのに対して、ベトナム、タイは2010年頃から垂直方向への移動が目立ち、中国の中間財を利用する後方連関が強まっている。
第Ⅱ-1-1-16図 主要国・地域の中国との前方・後方連関の変化
(1995 → 2000 → 2005 → 2010 → 2015 → 2018)
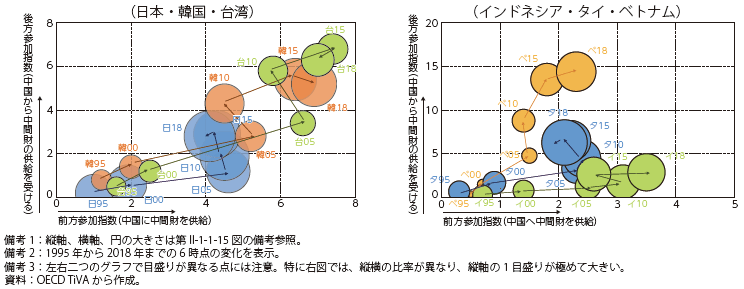
中国とのグローバル・バリューチェーン上の関係を業種別に見たのが第II-1-1-17図である。各国・地域が電気・電子機器、自動車の輸出を行うに当たって、相手国・地域にどの程度、部材を依存しているかを示している。左図の横軸は、中国の電気・電子機器輸出の中に含まれる各国・地域の付加価値成分のシェアで、中国の輸出額のうち、韓国が5%弱、日本、台湾、米国がそれぞれ2~3%を占めている208。これらの国・地域が供給している具体的品目はOECD TiVAからは分からないものの、化学、金属、電子部品などが考えられ、これら諸国・地域にとって中国は重要な顧客であるとともに、中国から見れば産業に重要な物資の貴重な供給国・地域といえる。
第Ⅱ-1-1-17図 主要国・地域の中国との連関(電気・電子機器、自動車)
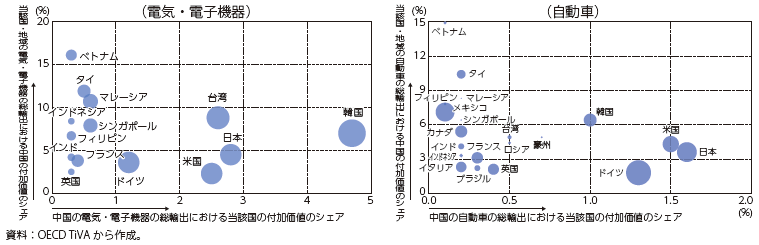
反対に縦軸は相手国・地域の電気・電子機器輸出に含まれる中国の付加価値成分のシェアである。例えば、ベトナムの電気・電子機器輸出の15%以上、タイ、マレーシアも10%以上が中国で生産された付加価値となっている。このように見てくるとASEAN諸国は電気・電子機器輸出において、中国に大きく中間財を頼っていることが分かる。また、縦横の目盛りを比較すれば、各国・地域は中国に中間財を供給するよりも、中国からの中間財に頼る傾向が強い。
同様に右図では、自動車輸出における中国と主要国・地域の関係を示している。横軸方向を見ると、中国の自動車輸出に対して、アジアの日本、韓国や米国、ドイツなどの欧米諸国が中間財を供給する前方連関を持つことを示しているが、その程度は限定的である。一方、縦軸方向を見ると、ベトナム、タイなどASEAN諸国が並ぶとともに、メキシコ、カナダも中国から中間財供給を受けて国内で組立てを行う後方連関の関係が強いことが分かる。
(主要国・地域の輸出における米中のバランス)
ここまで中間財の供給・調達という観点から考えてきたが、ここでは輸出先という観点から考えてみる。近年、米中貿易摩擦の激化が懸念される中で、輸出先としての米中の重要性はどうなっているのであろうか。主要国・地域の輸出における両国のシェアの推移をプロットしたのが第II-1-1-18図である。中国がWTOに加盟した2000年代初頭から、中国の成長とともに中国向け輸出のシェアが拡大している。特に日本、韓国、台湾、ASEAN等のアジア諸国・地域は大きく中国依存を高めてきた。その背景にあるのはアジア域内における国際的生産分業、それに基づくグローバル・バリューチェーンの拡大であった。機械分野における輸出を例に、中間財・最終財に分けて米国・中国向け輸出シェアを同じようにプロットしてみると、アジア諸国・地域の中間財輸出において、中国向けシェアは米国向けを上回って拡大した209。一方で、最終財輸出においては、依然として、アジア諸国・地域の輸出先として米国の存在の方が大きい。
第Ⅱ-1-1-18図 主要国・地域の輸出における米国・中国のシェア(2000 → 2015 → 2021)
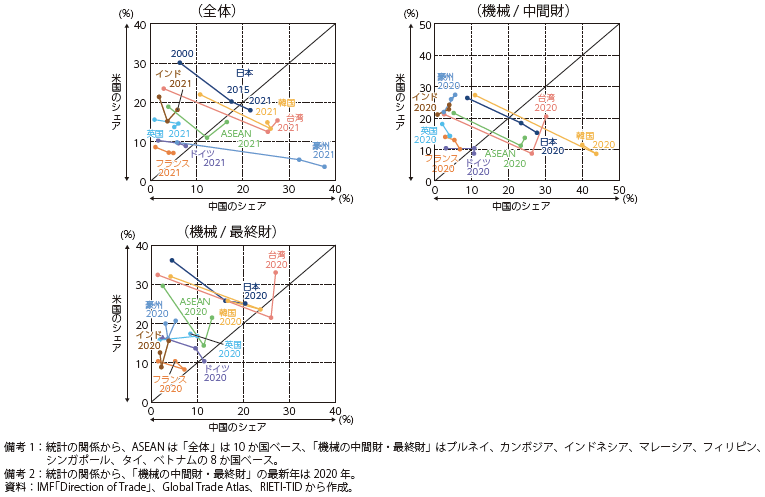
また、期間を分けて2010年代の半ば以降の動きを見ると、ASEANや台湾では45度線に沿って移動し米国シェアも拡大に転じるなど揺り戻しの動きも見られる。財別に分けると、中間財は中国向けシェアが米国向けシェアを上回ることは変わらないが、ASEANや台湾では米国向けシェアも拡大して、中国シフトの勢いは弱まっている。また、最終財は、依然として米国向けシェアが中国向けシェアを上回っており、ASEAN、台湾においては米国シェアがさらに拡大している。
ここまで見たことをまとめると、中国はグローバル・バリューチェーンにおいて、他国に中間財の供給を行う形での連関を強めている。アジア諸国・地域の中国との関係を見ると、韓国、台湾は前方連関を中心に中国との関係が強く、ASEAN諸国は、インドネシアは前方連関で、ベトナムなどは後方連関で中国と強い関係を有している。特に電気・電子機器や自動車などの分野を見ると、ASEAN諸国は中国から中間財の供給を受ける後方連関が強いことが分かる。しかし、それはサプライチェーン寸断によるリスクが高いことを示唆している。最近の米中貿易摩擦の中で、輸出先のバランスを見ると、特に中間財輸出で中国向けのシェアが高まっていたが、近年では米向け輸出のシェアが上昇するなど、揺り戻しの動きが見られる。
206 OECD TiVA(2021年版)を利用。2021年版は1995年から2018年を対象としたデータを提供している。なお、2023年6月1日現在、2022年暫定版も公表されているが、最近年について各国が公表した国民経済計算を必ずしも反映しておらず、近々改定される予定とのことで利用を見送った。
207 OECD TiVAでは、付加価値を生産国ベースで集計しており、外資系企業の生産した付加価値も立地国の付加価値と見なしている。日本の中国との後方連関の高まりも、中国に進出した日系サプライヤーから部材の逆輸入が行われるようになった影響も含まれる。
208 OECD TiVAでは業種別の前方参加・後方参加の指数は定義されていない。中国側、相手国・地域側、2種類の業種があるため特定する必要がある。ここでは、横軸に中国の電気・電子機器産業の総輸出に対する、その中に含まれる相手国・地域の付加価値成分のシェアをとった。この場合、相手国・地域側の業種は問わない(電子部品かもしれないし、金属製品かもしれないし、化学薬品かもしれない)。縦軸には相手国・地域の電子・電気機器産業の総輸出に対する、その中に含まれる中国の付加価値成分のシェアとした。この場合、中国側の業種は問わない。
209 中間財全体では、原油、天然ガスなど資源が含まれるため、国際的生産分業の対象として、機械分野のデータを観察した。
2.サプライチェーンの寸断が我が国経済に及ぼす影響
前項では、我が国を取り巻くグローバル・バリューチェーンの実態について確認してきたが、本項及び次項では、ノムラ・リサーチ・インスティテュート・シンガポールが実施した「我が国企業の海外展開の実態及び課題に係るアンケート調査(2022年度)」210の調査結果等を中心に、海外展開を行う我が国企業の視点に立ち、我が国企業を取り巻くサプライチェーンにおけるリスク認識の実態について見ていくとともに、サプライチェーンの強靱化に向けた課題について整理していく。
まず、本項では、新型コロナウイルス感染症の流行により露呈したサプライチェーンのぜい弱性が我が国企業に及ぼした影響について見ていくとともに、こうした経験に基づき我が国企業はどのような課題認識を持っているかについて確認していく。
第II-1-1-19図は、新型コロナウイルス感染症の流行以降の我が国企業におけるサプライチェーンの途絶経験について尋ねたものであるが、非製造業で途絶経験ありと答えた企業が約2割にとどまっているのに対し、製造業では約4割と半数近くに上っていることが分かる。
第Ⅱ-1-1-19図 2020年以降のサプライチェーン途絶経験の有無
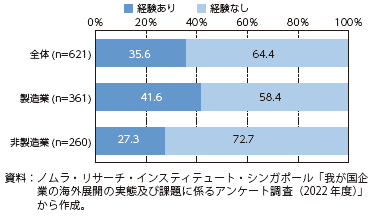
さらに、サプライチェーンの途絶がどの国・地域で生じたかを尋ねたものが第II-1-1-20図であるが、中国が最も多く、次に日本、ASEAN6と続いており、日本国内でのサプライチェーン途絶経験も多いことが分かる。ただし、日本国内におけるサプライチェーンの途絶は、元をたどれば国外に起因している場合も少なくないと考えられる。
第Ⅱ-1-1-20図 サプライチェーンの途絶が生じた国・地域(2020-2022年度)
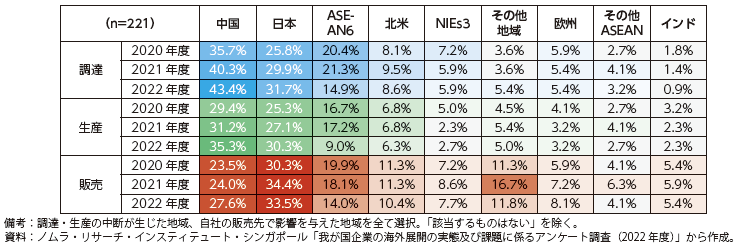
第II-1-1-21図は、サプライチェーンの途絶の影響がどの程度であったかを生産・販売別に尋ねたものであるが、生産・販売ともに「自社の対象事業における生産・販売の全部または一部が1か月以内の期間停止」と答える企業が最も多くなっていたが、「1か月以上生産・販売の全部または一部が停止」と答えた企業も少なくなく、「1か月以上生産・販売の全部が停止」とする企業もあったことが分かる。また、生産よりも販売において、1か月以上影響が出たと回答する企業が多く、自社の生産が仕入先から受ける直接的影響は一時的なものにとどまる一方で、サプライチェーン全体の機能停止により販売・納入が滞る影響は長期に及んでいる可能性が示唆される。
第Ⅱ-1-1-21図 サプライチェーン途絶による生産と販売への影響
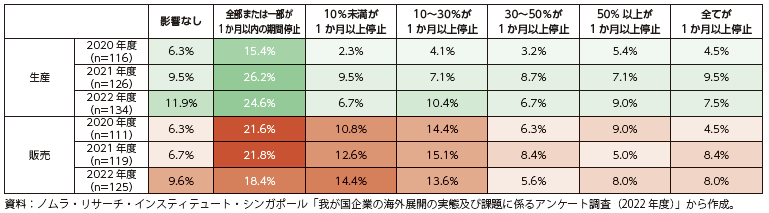
こうしたサプライチェーンの途絶の経験の有無別にサプライチェーンの強靱化に向けた課題認識について尋ねたものが第II-1-1-22図である。ここで示されている数値は、上位3位をウェイト付け(1位:3点、2位:2点、3位:1点)集計し、平均=0,標準偏差=1となるようにスコアリングした結果を表している。これを見ると、途絶経験ありと答えた企業では、「戦略的な在庫の積み増し」や「調達拠点・生産拠点・販売拠点の分散化」を課題として認識する傾向が強く、「国内における調達・生産・販売の強化」も平均を上回っている。一方、途絶経験のない企業について見てみると途絶経験のある企業では、「調達・生産・販売の現地化の強化」に対する課題認識が平均以下だったのに対し、途絶経験のない企業では平均以上となっている。ここから、サプライチェーンの途絶経験のある企業は経験のない企業と比べて、調達・生産・販売の現地化の強化を課題として強く認識していないといえる。
第Ⅱ-1-1-22図 サプライチェーンの途絶経験を踏まえた課題認識
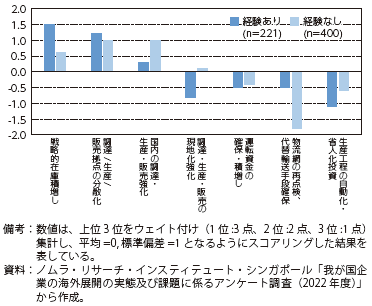
以上、サプライチェーンの途絶が我が国企業に及ぼした影響について見てきたが、新型コロナウイルス感染症の流行以降、主に製造業においてサプライチェーンの途絶を経験してきたこと、生産への影響が局所的・一時的なものにとどまっても、サプライチェーン全体の機能が停止することにより、販売・納入の滞りは長期化する可能性があること、サプライチェーン強靱化のための課題としては、戦略的な在庫積み増しや調達・生産・販売の分散化を基本としながらも、調達・生産・販売については、海外現地よりも日本国内を重視する傾向があることを示した。
次項では、我が国企業を取り巻くサプライチェーンのリスク認識について見ていくとともに、サプライチェーンの強靱化に向けた課題について示していく。
210 アンケート実施期間:2023年2~3月。調査対象:金融・保険業を主業から除く、関係会社に海外企業を含む企業に送付(関連企業は、出資比率50.1%以上)。調査方法:調査票を郵送し、WEBでの回答を依頼。有効回答数:621社、回収率:6.6%。
3.サプライチェーンリスクに対する認識の高まりとサプライチェーン強靱化に向けた取組
近年、我が国企業を取り巻くサプライチェーン環境では、新型コロナウイルス感染症流行の影響のみならず、政治経済的要因など様々なリスクに対する認識が強まっている。本項では、我が国企業を取り巻くサプライチェーンについて、具体的にどのような国や地域でどのようなリスクが高まっているのか、またこうした認識を踏まえ、調達・生産・投資先としてどのような国・地域を重視する動きが見られるのかについて見ていくとともに、我が国企業を中心としたサプライチェーンを強靱化してくための方策について示していく。
第II-1-1-23図は、海外展開を行う我が国企業に、直近10年間でサプライチェーンリスクが高まった国・地域と今後5年でサプライチェーンリスクが高まると考えられる国・地域を尋ねたものである。ここで示されている数値は、サプライチェーン上でリスクに対する認識が高まった上位3位の国・地域について、ウェイト付け(1位:3点、2位:2点、3位:1点)集計し、平均=0、標準偏差=1となるようにスコアリングした結果を示したものであり、グラフはスコアが平均値を上回っている国・地域を示したものだが、直近10年間、今後5年間ともに中国に対するリスク認識が突出している。
第Ⅱ-1-1-23図 サプライチェーンリスクが高まった国・地域
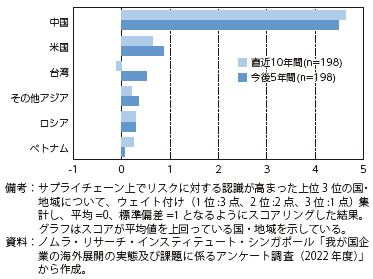
さらに、どのようなリスクが高まったかを複数回答で尋ねたものが第II-1-1-24図になるが、中国に着目すると、直近10年では、地政学的なリスクや経済安全保障上のリスクと答える企業の割合が最も高くなっており、続いて、感染症を含む環境リスクや、マクロ経済リスクやサプライチェーンリスクを挙げる企業も一定数おり、人権リスクを挙げる企業もあった。一方、今後については、感染症を含む環境リスクを挙げる企業は減少し、地政学的なリスクや経済安全保障上のリスクと答える企業の割合がさらに高まっている。このように、我が国企業は中国における地政学的リスク、経済安全保障上のリスクが高まっていると認識していることが分かる。
第Ⅱ-1-1-24図 サプライチェーン上のリスク
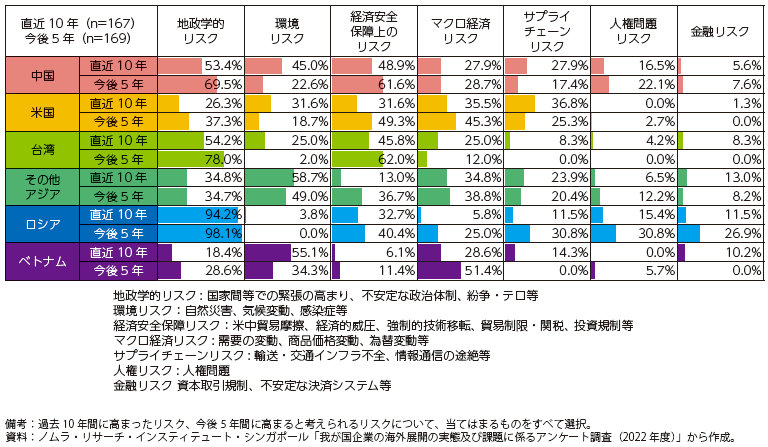
第II-1-1-25図は、海外展開を行う我が国企業に対して、直近10年間で調達先・販売先・直接投資先として重視してきた国・地域、今後5年間で調達先・販売先・直接投資先として重視していく国・地域について尋ねたものである。ここで示されている数値は、重視する国・地域について上位3位をウェイト付け(1位:3点、2位:2点、3位:1点)集計し、平均=0,標準偏差=1となるようにスコアリングした結果を表したものだが、直近10年間では調達先・販売先・直接投資先ともに、中国が最も重視され、その次にASEAN6が続いている。これに対し、今後5年間では調達先は依然として中国が最も重視されているが、販売先・直接投資先についてはASEAN6が上回っている。また、直近10年間と今後5年間を比較し、販売先・直接投資先としてインド重視する傾向も強まっている。
第Ⅱ-1-1-25図 調達先、販売先、直接投資先として重視する国・地域
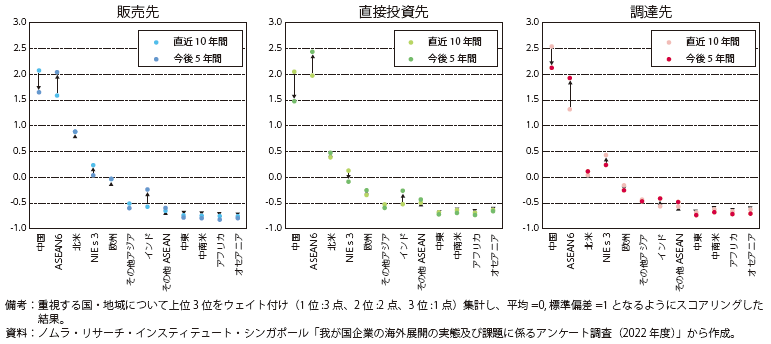
また、直近10年間と今後5年間で直接投資先として重視してきた国・地域について、その理由を尋ねたものが第II-1-1-26図である。中国やASEAN6では、直近10年、今後5年ともに「市場の成長性」や「納入先への地理的アクセス」とする傾向が強いが、直近10年では中国でその傾向が強く出ている一方で、今後5年間ではASEAN6の方がその傾向が強く出ているという特徴が見られる。また、ASEAN6では「政治的安定性、治安」を理由とする傾向もある程度強い一方で、中国では「政治的安定性、治安」を理由として挙げる傾向は見られないのも特徴的である。また、直近10年と比較して、今後5年間では、中国で「安価な労働コスト」を理由として挙げる傾向が極端に下がるといった特徴や、ASEAN6では「第三国輸出」を理由として挙げる傾向が強まっているといった特徴が見られる。
第Ⅱ-1-1-26図 直接投資先として重視する理由(中国、ASEAN6)
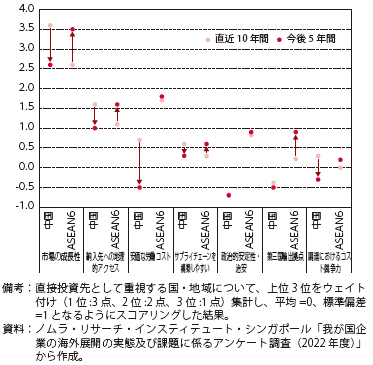
株式会社国際協力銀行(JBIC)の「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告(アンケート結果)」(2022年12月)211では、中期的、長期的に有望な事業展開先国について尋ねている。
下図(第II-1-1-27図:左図)のとおり、中期的(今後3年程度)な有望国では、中国、米国、ASEAN諸国を抑え、インド(40.3%)が首位となった。インドを有望国とした理由では、「現地マーケットの今後の有望性」(85.5%)、「現地マーケットの現状規模」(43.4%)が高く、現在、そして将来のインド市場への強い期待が見てとれる。
第Ⅱ-1-1-27図 中・長期的に有望な事業展開先国
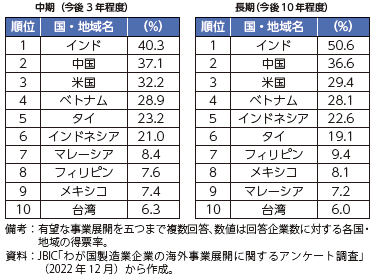
さらに長期的(今後10年程度)な有望国としても、インド(50.6%)が首位となり、中国、米国、ASEAN諸国が続く(同図:右図)。同社のアンケート調査は毎年実施されており、インドは13年連続で長期的な有望国の首位を維持したことから、インドに対する高い期待が長期間継続していることが分かる。
さらにJETROの「海外進出日系企業実態調査」(2022年12月)212では、短期的(今後1~2年)な事業展開の方向性について尋ねており、インド(72.5%)、ベトナム(60.0%)で半数を上回る企業が短期的に事業を拡大する意向を示している。2021年の同調査結果と比べると、両国とも2022年の「拡大」の割合は上昇しており、コロナ禍から回復し事業展開に積極的な姿勢がうかがえる。
第Ⅱ-1-1-28図 短期的に事業を「拡大する」比率の推移
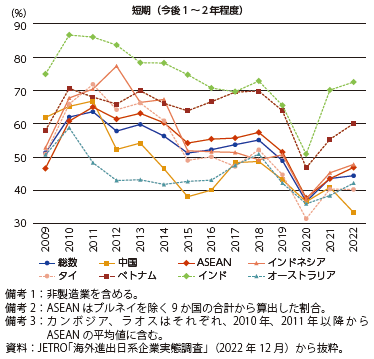
同調査では事業を展開する上でどのような問題点があるかについても尋ねており、前述したインドにおける問題点をみると、「従業員の賃金上昇」(77.2%)、「調達コストの上昇」(76.1%)が上位に挙げられ、「通関等手続きが煩雑」(63.0%)、「競合相手の台頭(コスト・価格面で競合)」(59.2%)、「税務(法人税、移転価格課税)の負担」(58.6%)と続いた。コストの上昇が課題となるほか、通関手続や税等の制度面での改善が望まれる。
第Ⅱ-1-1-29図 インドにおける経営上の問題点
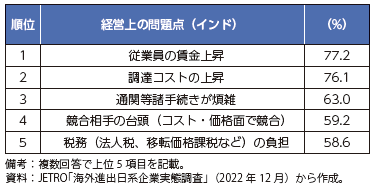
JBICとJETROによるアンケートではインドを最も有望視する結果となったが、実際2021年の名目GDPをみると、インドは米国、中国、日本、ドイツに続く世界第5位の規模に成長しているほか、2021年の実質GDP成長率ではインド(9.1%)は中国(8.5%)を上回った。
人口でも、国連人口基金(UNFPA)の「世界人口報告書2023(State of World Population report 2023)」213によると、インドは2023年半ばまでに中国を抜き、世界最多の14億2860万人となる見通しが示された(第II-1-1-30図)。インドは成長の原動力となる若年層の多さが特徴的で、今後も安定した人口増加が見込まれることから、内需の拡大を背景に将来の経済成長への期待も大きい。
第Ⅱ-1-1-30図 国連人口基金(UNFPA)による人口関連統計指標
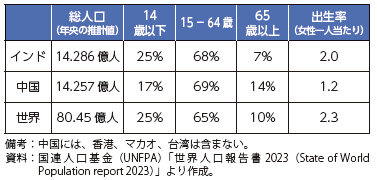
以上、サプライチェーンリスクに対する認識の高まりや調達・販売・投資先として重視する国・地域の変化について見てきたが、以降ではサプライチェーンの実態把握の状況や課題について、前述したノムラ・リサーチ・インスティテュート・シンガポールのアンケートを中心に確認していく。第II-1-1-31図は、社内におけるサプライチェーンリスクの管理体制の状況について尋ねたものだが、全社的に体制構築できているが約3割、全社的にはできておらず部署ごとに把握しているのが現状なのが約5割、把握できていないが約1割となっており、約半数が現場レベルでの把握にとどまっている。
第Ⅱ-1-1-31図 サプライチェーンリスクの管理体制の状況
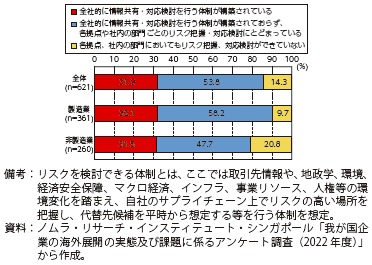
また、第II-1-1-32図はサプライチェーンの把握状況について尋ねたものであるが、直接の仕入先・販売先から遠くなるほど、状況を把握できておらず、3次取引先以上になると半数以上が把握できていない状況にある。
第Ⅱ-1-1-32図 サプライチェーンの実態把握の状況
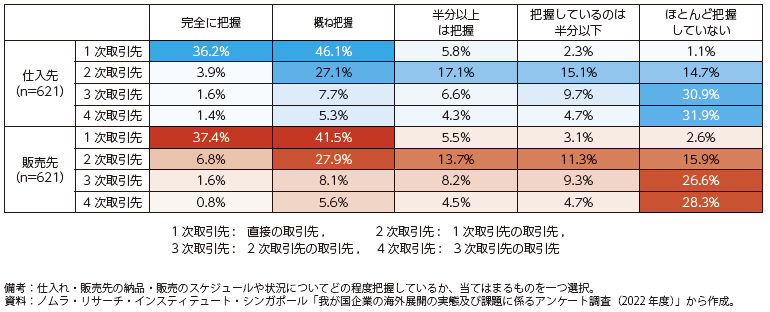
こうした中、サプライチェーンの実態把握に向けた課題について複数回答で尋ねたものが第II-1-1-33図となっているが、直接の仕入先・販売先と近いほど取引先の理解・協力と答える企業が多くなる一方で、直接の仕入先・販売先との近さや遠さに関わらず、取引先とのデータ連携を課題として認識しており、サプライチェーンの実態把握に向けたデータ共有が企業の課題となっていることが分かる。
第Ⅱ-1-1-33図 サプライチェーンの実態把握に向けた課題
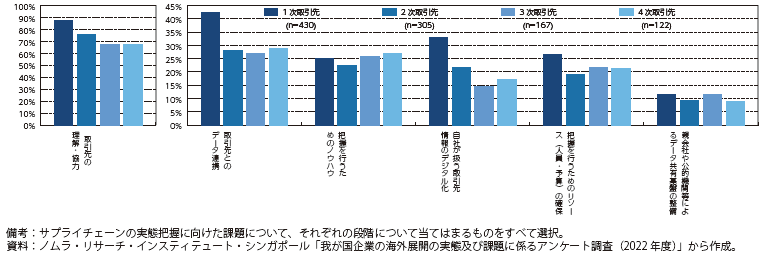
以上、我が国企業は、中国に対してサプライチェーン上のリスクが高まっているとの認識を強める一方で、ASEANやインドを重視する動きが強まっていること、サプライチェーンの実態把握に向けては取引先とのデータ連携を課題として認識しており、サプライチェーンの実態把握に向けたデータ共有が企業の課題となっていることを示してきたが、我が国としても、ASEANを始めとする友好国との連携を強化しつつ、アジア地域で企業間のデータ連携を促す基盤の整備を進め、データ連携を通じてサプライチェーンを強化していくことが重要な課題となっている。
こうした中、経済産業省で2022年度に開催した「デジタル時代におけるグローバル・サプライチェーン高度化研究会」及びその下に位置付けた「サプライチェーンデータ共有・連携WG」においては、足元の産業とサプライチェーンで求められるサプライチェーン構造の把握を切り口の一つとして検討を行い、企業間でのデータ連携によるサプライチェーン把握の実現に向けて必要な要素や課題の整理を行った。検討の結果、データ連携の必要性の理解不足、データ化/データ共有方法の未整備、情報取扱への理解不足、リソース配分の優先度が低い、といった課題に対し、官、公(横串で必要な役割を官と民がともに関わって取り組む組織体など)、民が役割分担をしながらユースケース組成、データ共有インフラ整備、ビジネスルールや体制/エコシステム形成に向けて取り組むことが、サプライチェーン把握、GHG排出可視化などの今日的な課題に対応しつつ製造業の高度化にもつながる政策的方向性になり得ることがわかった。
この研究会とWGでは加えて、より中長期的な時間軸と視座で、今後、産業とエコシステムにおいてデータが果たす役割が拡大する中で、従前より製造業でのつながりが強い日ASEANの地域大の産業エコシステムの方向性と目指す姿について検討すると共に、産業におけるデータの活用モデル(以下、ユースケース)と、それを支えるアーキテクチャやエコシステムの在り方についても検討を実施した。
まず、デジタルサプライチェーンのアーキテクチャを描く上では、ユニバーサルな相互接続性の担保に加えて、自律性の確保が求められ、そのためには、諸外国との連携は担保しつつも、自域内にとって不利益になる仕組み・ルールが存在した場合に、域内で受け入れるかの判断権を留保し、場合によって条件提示や代替オプションを持てるようにすることが必要との議論がなされた。
そこで、アジア大でのサプライチェーン上のデータ連携、デジタル化に向けて、東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)では、アジア大でのサプライチェーン上のデータ連携、デジタル化に向けて、日ASEANのサプライチェ-ンの現状調査や、今後のサプライチェーン強靱化へ向けた方向性の検討のための有識者グループの立ち上げに向けた準備を開始した。2023年にERIAに設置予定のデジタルイノベーション・サステナブルエコノミーセンターにおいて、この取組を加速していく方針が示されており、日ASEANでのサプライチェーンデータ連携を実現、ひいてはサプライチェーンの統合的な管理実現に向けた検討を加速していく。
211 JBIC「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告-2022 年度海外直接投資アンケート結果」(2022年12月)Web サイトを参照(https://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2022/pdf/1216-017128_3.pdf![]() )。
)。
212 JETRO「海外進出日系企業実態調査」(2022 年12 月)Web サイトを参照(https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/e98672da58f93cd3/20220039rev2.pdf![]() )。
)。
213 国連人口基金(UNFPA)「世界人口報告書2023(State of World Population report 2023)」Web サイトを参照(https://www.unfpa.org/sites/default/files/swop23/SWOP2023-ENGLISH-230329-web.pdf![]() )。
)。
4.国内製造拠点強化の動き
前項では日本企業の中国に対するリスク認識の高まりと、ASEANやインドを重視する動きが見られることを確認した。最近の国際政治経済環境の変化に対応したサプライチェーンの再編が急務となる中、海外からも半導体や蓄電池など戦略的な物資の供給等を我が国に期待し、求める動きが高まっている。本項では、我が国の有志国から期待される半導体等の戦略的物資のサプライチェーンの強靱化に向けた製造拠点強化の動きについて概観する。
(1)我が国製造拠点をめぐる環境変化
国内の人件費の上昇等、製造コスト面の課題、貿易摩擦、為替、新興諸国市場のポテンシャルを踏まえた現地・近接地での生産のメリットへの期待等、様々な要因により、我が国製造業はすう勢的に国内から海外へ生産をシフトさせてきた。海外生産比率の推移を見ると、1990年代から2000年代半ば世界金融危機前にかけて上昇した後、一服し、再び2010年代半ばにかけて上昇、足下は20%台を維持している。海外設備投資比率も、特に2010年代前半に顕著な上昇が見られ、近年はおおむね20%台で推移している(第II-1-1-34図)。
第Ⅱ-1-1-34図 我が国製造業の海外生産比率と海外設備投資比率
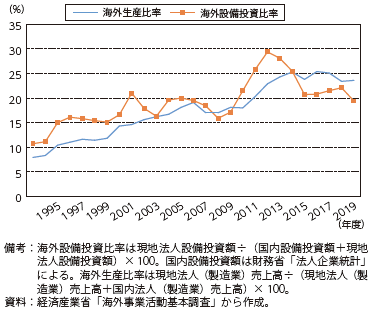
海外生産比率を業種別に見ると、相対的に比率が高いのは輸送機械工業(2020年度40%超)、情報通信機械工業(同約30%)である(第II-1-1-35図)。
第Ⅱ-1-1-35図 我が国製造業の海外生産比率(業種別)
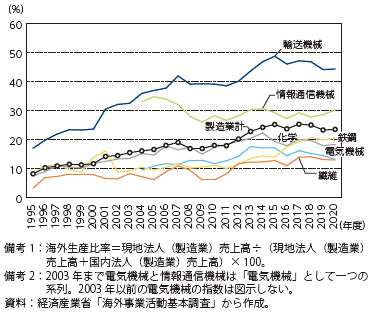
これに伴い、製造工業全体では国内生産能力は縮小傾向にある。一方で、輸送機械工業は国内生産能力指数が近年やや増加している。また電子部品・デバイス工業については2000年代に国内生産能力が大きく増大し、2010年代後半以降は増大のスピードに一服感が見られる(第II-1-1-36図)。
第Ⅱ-1-1-36図 生産能力指数の推移
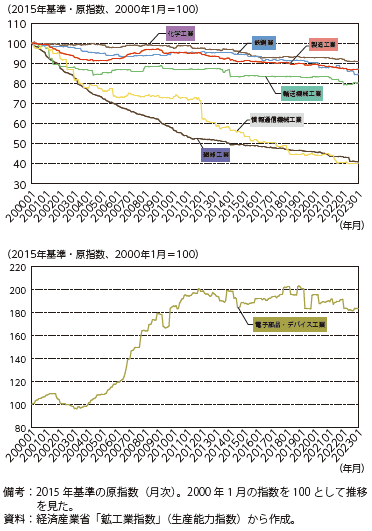
また、鉱工業出荷のうち国内向け出荷に輸入を合算した「鉱工業総供給表」における輸入も新型コロナ感染症拡大前の水準を超えて増加傾向にある(第II-1-1-37図)。
第Ⅱ-1-1-37図 鉱工業総供給・国産・輸入指数の推移
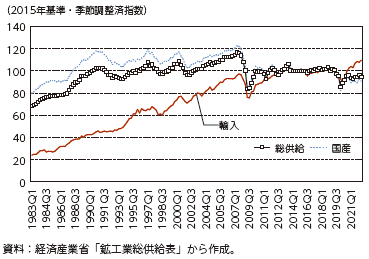
製造業の海外生産の増大とともに、国内供給における輸入浸透度(国内総供給における輸入の比率)も上昇基調にある。業種により浸透度の大きさや上昇のスピードにはばらつきがあるが、国内生産能力縮小が進んだ繊維工業や情報通信機械工業の輸入浸透度は大きい。電子部品・デバイス工業については、2000年代後半に国内生産能力が拡大したこともあり、同時期には輸入浸透度が低下したが、2010年代以降、足下まで再び輸入浸透度が上昇している(第II-1-1-38図)。
第Ⅱ-1-1-38図 業種別に見た輸入浸透度
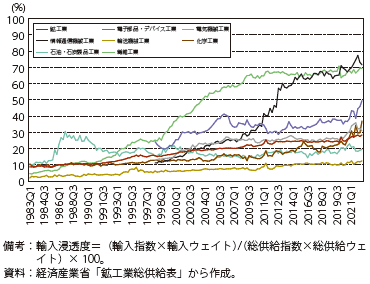
また、輸入先の集中度をハーフィンダール・ハーシュマン指数214によって見ると、日本は米国、中国、ドイツ等より輸入先の集中度が高い(第II-1-1-39図)。
第Ⅱ-1-1-39図 日本及び主要国の輸入先集中度
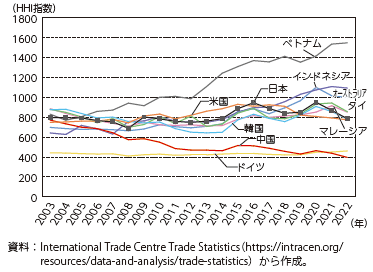
我が国の輸入比率を見ると、中国からの輸入比率が最も高く約24%を占める。次いで、米国約11%、豪州約7%となっており、中国の輸入比率の高さが際立つ。(第II-1-1-40図)。
第Ⅱ-1-1-40図 日本の輸入先集中度と輸入上位国のシェア
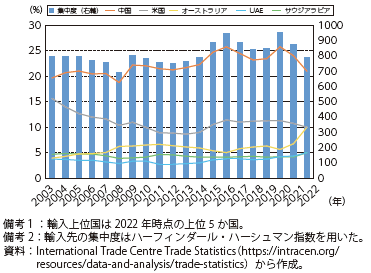
新型コロナウイルス感染症の流行やロシアによるウクライナ侵略で顕在化したサプライチェーン上の諸課題や一部の国による保護主義的な動き、地政学リスクの増大、米中対立、特定国からの供給への過度な依存に対する問題意識の高まり、インバウンド需要取り込みへの関心や為替の状況等は、企業が従来の生産・調達体制を見直す契機となっており、サプライチェーン最適化の文脈の中で、製造拠点の多元化や国内生産の強化等が論じられるようになっている。ASEANビジョン、ERIAの体制強化、日豪印の枠組みであるサプライチェーン強靱化イニシアティブ(SCRI)等、日本と有志国、友好国との間でもグローバル・バリューチェーン、サプライチェーンの強靱化に向けた検討や取組が始まっている。前述のように各国において輸入先の集中度が高まってきたこと、輸入先・調達先の適切な分散を通じたサプライチェーンの強靱化が求められていることを踏まえると、高い技術力を有し高品質の製品を安定的に生産する日本の製造拠点が果たしていく役割は友好国にとっても大きいといえよう。
214 ハーフィンダール・ハーシュマン指数とは各国においてその輸入に占める相手国のシェアの二乗和で表される指数。輸入先が一国のみである場合に同指数は1万となる一方、輸入先が分散している場合に同指数は0に近づく。例えば、A国がB国から50%、C国から30%、D国から20%の輸入をしている場合、A国のHHI指数は502+302+202=3,800となる。最大値(一国のみから輸入した場合)は1002=10,000となる(経済産業省(2020)『令和二年版通商白書』より)。
(2)国内製造体制強化の動き
国内製造体制強化に向けた動きが加速している例として、半導体を取り上げたい。
新型コロナウイルス感染症の拡大による行動制限下でのデジタル需要(パソコン、テレビ等)の高まり、コロナ禍からの回復途上での自動車等需要の回復に伴い、2020年秋頃から世界的な半導体不足が顕在化した。不足の要因については様々な指摘がされているが、半導体の供給途絶により日本や各国における生産活動に支障が生じた。加えて、半導体は5G、ビッグデータ、AI、IoT、自動運転、ロボティクス、スマートシティ、デジタルトランスフォーメーション(DX)等のデジタル社会を支える重要基盤であり、安全保障にも直結する死活的に重要な戦略技術である215。特に、ロシアによるウクライナ侵略は、サプライチェーンの混乱を招き、経済安全保障の重要性を一層顕在化させた。このような状況を背景に各国は、経済安全保障の観点等から重要な半導体の生産基盤を確保すべく、異次元の半導体支援策等を引き続き実施している。
「産業の米」とも称され重要度が増している半導体の製造については、日本の国際競争力は大きく低下している。世界の半導体売上高における日本企業のシェアは1988年時点の50.3%をピークに低下し、2019年時点で約10%にまで落ち込んでいる(第II-1-1-41図)。
第Ⅱ-1-1-41図 世界の半導体売上シェア
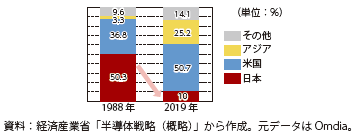
また、半導体デバイス、集積回路の輸入先集中度も上昇している(第II-1-1-42図)。
第Ⅱ-1-1-42図 日本の半導体デバイス、集積回路輸入先の集中度
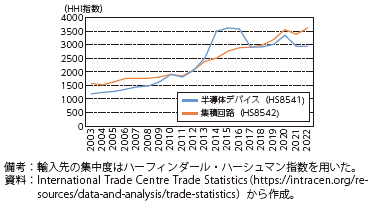
このような状況下において、我が国では、2021年6月に経済産業省が策定した半導体・デジタル産業戦略等に基づき、半導体産業復活に向けた基本戦略を着実に実行してきた。
先端半導体については、デジタル化の進展で自動車・医療機器等の様々な分野での活用が拡大する一方、地政学的な事情からグローバルなサプライチェーンが影響を受けるリスクが高まっており、日本における生産能力の確保が喫緊の課題となっている。このため、事業者による製造基盤整備への投資判断を後押しすべく、「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」に基づいて、認定を受けた先端半導体の生産施設整備及び生産に関する計画について、2023年5月までに3件(TSMC・JASM(熊本県)、キオクシア等(三重県)、マイクロン(広島県))が経済産業大臣により認定されており、例えば、TSMC・JASMが事業を実施している熊本・九州エリアでは、関連産業による投資拡大、人材育成のための産学官連携による体制構築、九州エリアにおける賃金の上昇傾向など、好循環の兆しが現れている。
また、マイコン、アナログ及びパワー半導体といった、従来型半導体については、様々な産業の生産活動に必要不可欠であることから、その製造拠点における設備刷新を支援するため、「サプライチェーン上不可欠性の高い半導体の生産設備の脱炭素化・刷新事業費補助金」を措置している。これにより従来型半導体の国内生産能力を新型コロナウイルス感染症流行前(2019年)比で15%以上向上させる見込みである。
また、戦略物資として半導体の重要性が高まる中、従来型半導体に加えて、我が国が強みを有する半導体製造装置や部素材等については、経済安全保障の観点からも、国内製造基盤の維持・強化が重要な課題である。このため、昨年5月に成立した経済安全保障推進法に基づき、半導体が特定重要物資に指定されたことを踏まえて、従来型半導体や半導体製造装置・部素材・原料の安定供給の確保に向けて、国内製造能⼒の維持・強化に取り組む事業者に対して、助成等を行っている。
研究開発に関しては、2020年後半における次世代半導体の設計・製造基盤の構築に向けた取組を開始している。現在、オープンな研究開発プラットフォームの立ち上げ、将来の量産を見据えた製造拠点の立ち上げの二本の柱を有する次世代半導体プロジェクト構想が進められている。前者については、国立研究開発法人、大学、産業界が参加して、海外の関係機関との連携を行う国内外にオープンな研究開発プラットフォームを構築し、次世代半導体の量産実現に向けた技術開発プロジェクトを組成・実施するもので、「技術研究組合最先端半導体技術センター(Leading-edge Semiconductor Technology Center (LSTC))」の設立が2022年12月に認可されている。後者の製造拠点については、国内トップの技術者が集結して2022年8月に設立し、国内主要企業の賛同を得た216Rapidus社が2020年代後半の次世代半導体の製造基盤確立に向けた研究開発プロジェクト(開発費700億円)の採択先となり(2022年11月)、建設予定地として北海道千歳市が選定された(2023年2月)。さらにRapidus社と海外研究機関・企業との共同研究プロジェクトの組成も進んでおり、2022年12月には米IBM社と2nmノード半導体の共同開発パートナーシップを締結、欧州トップレベルの半導体研究開発エコシステムを形成するimecと次世代半導体開発に係る協力覚書を締結している。今後、LSTCと両輪となって我が国における次世代半導体の量産基盤の構築を目指していく217。
半導体等の重要物資の安定した供給体制の構築は、円滑な経済活動のみならず国家安全保障の確保にも関わってくる重要な課題であり、同盟国や有志国・地域で連携して取り組むことが不可欠となっている。世界の半導体エコシステムを支えるチョークポイントとしての役割を果たすべき半導体製造装置・素材技術の磨き上げを行うほか、外為法に基づく輸出管理や投資管理、半導体技術の流出防止策の構築を行うことが想定される。また、同志国・地域間の半導体をめぐる産業政策の協調や次世代半導体プロジェクトを進めていく必要がある。米国とは、2022年5月にオープンな市場、透明性、自由貿易を基本とし、日米及び同志国・地域でサプライチェーンの強靭性を強化するという目的を共有し、双方に認め合い、補完し合う形で行うことを基本原則として二国間の半導体サプライチェーンの協力を行うことを定めた「半導体協力基本原則」が合意され、同原則に基づく次世代半導体開発の共同タスクフォースが設置されることとなった。また、同年7月には重要・新興技術の育成・保護に向けて日米共同研究開発の推進に合意し、日本側の取組として既述のLSTCの立ち上げが発表されている。米国に加えて、例えば、EU・ベルギー・オランダ・英国・韓国・台湾をはじめ、諸外国・地域と、次世代半導体のユースケース作り、研究開発、緊急時の連携等に関し、相手国・地域のニーズ・実情に応じて進めていく。また、台湾との間では民間交流の下、定期的に半導体等に関する緊密な情報共有や意見交換を実施する。台湾との間では民間交流の下、定期的に半導体等に関する緊密な情報共有や意見交換を実施する。また、政府当局間の会合であるGAMS(Government/Authorities Meeting on Semiconductors)でも、引き続き、各国の補助金制度等について情報共有し、貿易を歪曲することのない透明で非差別的な補助金等制度が実施されるよう議論していく。
このような状況の下、2023年4月には半導体・デジタル戦略の改定案が公表され、2030年に国内で半導体を生産する企業の合計売上高(半導体関連)として、15兆円超を実現し、我が国の半導体の安定的な供給を確保することが目標として定められた。この目標に向けて、有志国・地域との補完的な協力関係を強化しつつ、ステップ1で足下、産業界で産業界や社会に不可欠な製造基盤を確保・強化し、ステップ2で次世代計算基盤の実現に必要な技術を確立し、ステップ3では2030年の先を見据えてゲームチェンジとなる将来技術の開発に取り組むとして、対象5分野(先端ロジック半導体、先端メモリ半導体、産業用スペシャリティ半導体、先端パッケージ技術、製造装置・部素材)のロードマップを作成・公表している。これらの着実な実行により、我が国のDX/GX/経済安全保障を実現するとともに、国内投資・イノベーション・所得拡大の好循環に繋げていく。
215 経済産業省(2021)「半導体戦略(概略)」(2021年6月)
216 キオクシア、ソニーグループ、ソフトバンク、デンソー、トヨタ自動車、日本電気、日本電信電話、三菱UFJ銀行が出資。
217 経済産業省(2022)「次世代半導体の設計・製造基盤確立に向けて」(2022年11月)。