第2節 我が国の経済安全保障戦略の展開と企業側の課題
1.我が国の経済安全保障戦略の展開
第Ⅰ部第2章第2節で見たように、米中両国による技術覇権争い等を背景として、コロナ禍やロシアのウクライナ侵略によりサプライチェーンのぜい弱性が顕在化したことも相俟って、各国は経済安全保障の取組を強化している。
我が国では、投資審査・輸出管理の強化、研究インテグリティの確保、サプライチェーン強靱化等、経済安全保障上の取組を強化してきた。2021年11月には、第1回経済安全保障推進会議が開催され、①自律性の向上、②優位性ひいては不可欠性の確保、③基本的価値やルールに基づく国際秩序の維持・強化という三つの目標を、経済安全保障政策の大きな方向性として示し、経済安全保障を推進する法案の策定の準備が開始された。これを受け、有識者会議での検討を踏まえ、2022年5月、経済安全保障推進法(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)が可決、成立した。
(1)経済安全保障推進法
経済安全保障推進法は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設するものである。具体的には、法制上の手当てが必要な喫緊の課題に対応するため、「①重要物資の安定的な供給の確保」、「②基幹インフラ役務の安定的な提供の確保」、「③先端的な重要技術の開発支援」、「④特許出願の非公開」に関する四つの制度を創設した(第II-1-2-1図)。
第Ⅱ-1-2-1図 経済安全保障推進法の概要
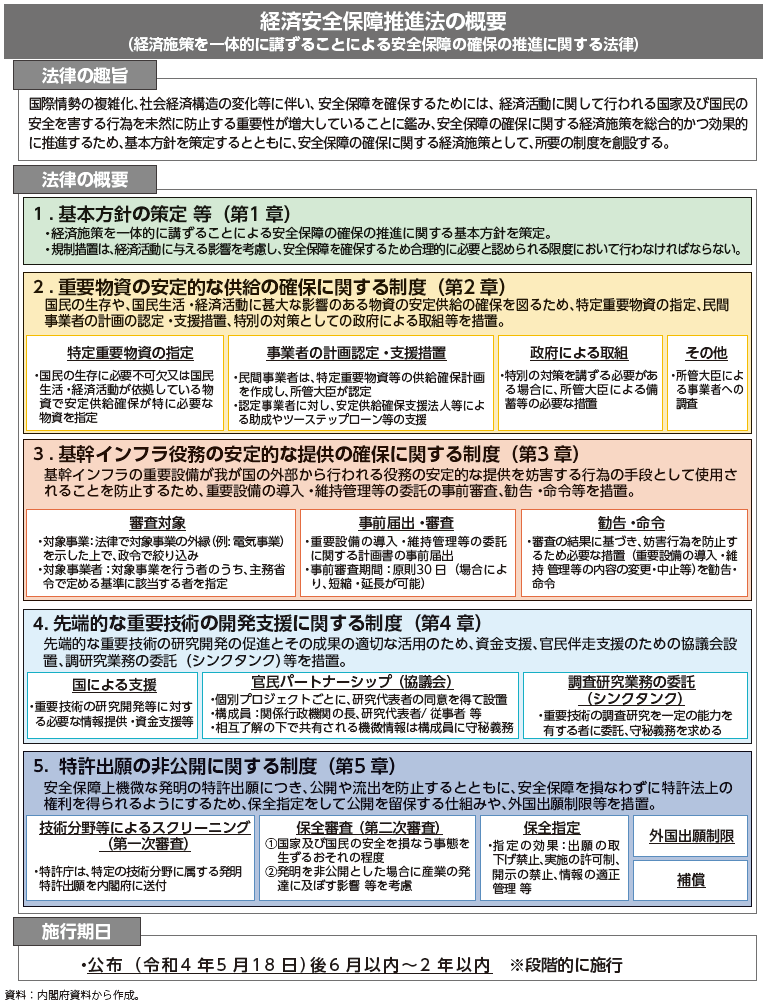
「①重要物資の安定的な供給の確保」については、国民の生存や、国民生活・経済活動に甚大な影響のある物資の安定供給の確保を図るため、特定重要物資の指定、民間事業者の計画の認定・支援措置、特別の対策としての政府による取組等を規定している。特定重要物資として指定した物資については、物資ごとに施策の方向性及び支援対象となる取組の内容を定めた取組方針を当該物資の所管大臣が定める。その上で、取組方針を踏まえて、民間事業者が供給確保計画を作成し、所管大臣による認定を受けた場合、認定事業者は助成等の支援を受けることが可能となる。
「②基幹インフラ役務の安定的な提供の確保」については、基幹インフラ(電気・ガス・水道等)の重要設備が我が国の外部から行われる役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止するため、重要設備の導入・維持管理等の委託の事前審査、勧告・命令等を規定している。
「③先端的な重要技術の開発支援」については、先端的な重要技術の研究開発の促進とその成果の適切な活用のため、情報提供や資金支援、官民伴走支援のための協議会設置、調査研究業務の委託(シンクタンク)等を規定している。
「④特許出願の非公開」については、安全保障上機微な発明の特許出願について、公開や流出を防止するとともに、安全保障を損なわずに特許法上の権利を得られるようにするために、保全指定をして出願公開等の手続を留保する仕組みや外国出願制限等を規定している。
経済安全保障推進法は、公布から2年以内に段階的に施行することとされており、2022年8月、総則部分のほか、上記の四つの制度のうち、「①重要物資の安定的な供給の確保」と、「③先端的な重要技術の開発支援」に係る部分が施行され、また、法律に基づく事務を担当する組織として、内閣府に経済安全保障推進室が設置された。
同年9月には、法律全体の実施に係る基本方針(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針)及び、「①重要物資の安定的な供給の確保」に関する基本指針(特定重要物資の安定的な供給の確保に関する基本指針)、「③先端的な重要技術の開発支援」に関する基本指針(特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針)が閣議決定された。基本方針では、自由で開かれた経済を原則とし、民間活力による経済発展を引き続き指向しつつも、市場や競争に過度に委ねず、政府が支援と規制の両面で一層の関与を行っていくことが必要との基本的考え方とともに、留意事項として、自由な経済活動との両立、国際協調主義、事業者等との連携を示した。
特定物資の安定的な供給の確保に関する基本指針では、特定重要物資に指定する際の要件として、重要性、外部依存性、外部から行われる行為による供給途絶等の蓋然性、本制度により安定供給確保のための措置を講ずる必要性、の四つが定められた。これを受け、同年12月には、特定重要物資として、抗菌性物質製剤、肥料、永久磁石、工作機械・産業用ロボット、航空機の部品、半導体、蓄電池、クラウドプログラム、天然ガス、重要鉱物並びに船舶の部品の11物資が政令で指定された(第II-1-2-2表)。これらの物資について、物資所管大臣により「安定供給確保を図るための取組方針」が策定、公表されている218。
第Ⅱ-1-2-2表 政令で指定された特定重要物質
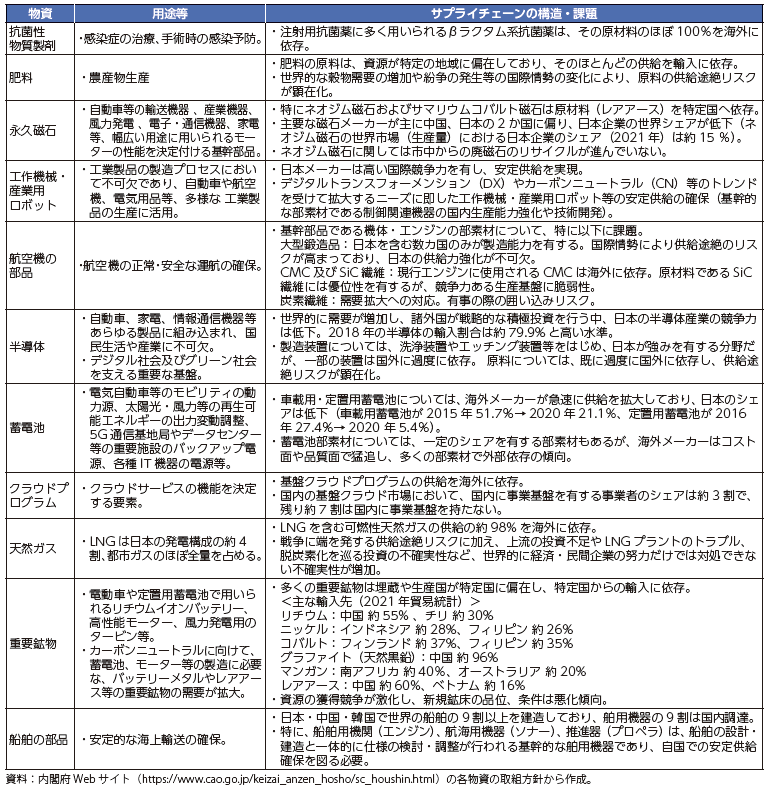
特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針では、特定重要技術を見極める上で調査研究を実施する際に参考とする領域として、バイオ、AI、量子等の20の技術領域が示された219。また、特定重要技術のうち特に優先して育成すべきものについては、指定基金を活用して研究開発等を推進することとされており、2022年9月に経済安全保障推進会議及び統合イノベーション戦略推進会議にて決定された経済安全保障重要技術育成プログラムに係る研究開発ビジョン(第一次)において、支援対象とする重要技術として、「海洋領域」、「宇宙・航空領域」、「領域横断・サイバー空間領域」、「バイオ領域」の四つの領域から27の技術が示された220。これらの技術について研究開発を進めるため順次公募が開始されている。
2023年4月には、「②基幹インフラ役務の安定的な提供の確保」に関する基本指針(特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針)、「④特許出願の非公開」に関する基本指針(特許法の出願公開の特例に関する措置、同法第三十六条第一項の規定による特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に係る情報の適正管理その他公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明に係る情報の流出を防止するための措置に関する基本指針)が閣議決定された。今後、関係政省令等の策定を行い、両制度とも2024年春頃の運用開始を予定している。
218 内閣府Web サイト(https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/sc_houshin.html![]() )。
)。
219 20の技術領域とは、バイオ技術、医療・公衆衛生技術(ゲノム学含む)、人工知能・機械学習技術、先端コンピューティング技術、マイクロプロセッサ・半導体技術、データ科学・分析・蓄積・運用技術、先端エンジニアリング・製造技術、ロボット工学、量子情報科学、先端監視・測位・センサー技術、脳コンピュータ・インターフェース技術、先端エネルギー・蓄エネルギー技術、⾼度情報通信・ネットワーク技術、サイバーセキュリティ技術、宇宙関連技術、海洋関連技術、輸送技術、極超音速、化学・生物・放射性物質及び核、先端材料科学、を指す。
220 経済安全保障重要技術育成プログラム研究開発ビジョン(第一次)(2022年9月)https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/2_vision.pdf![]()
(2)国家安全保障戦略
また、2022年12月には新たな国家安全保障戦略が閣議決定された221。国家安全保障戦略は、我が国の安全保障に関する最上位の政策文書として位置づけられ、外交、防衛、経済安全保障、技術、サイバー、海洋、宇宙、情報、政府開発援助(ODA)、エネルギー等の我が国の安全保障に関連する分野の諸政策に戦略的な指針を与えるものである。同戦略では、戦略的なアプローチの一つとして、経済安全保障政策の促進が盛り込まれ、我が国の自律性の向上、技術等に関する我が国の優位性、不可欠性の確保等に向けた必要な経済施策を講じていくとされた。具体的には、同盟国・同志国や民間と連携しつつ、経済安全保障推進法の着実な実施とともに、サプライチェーン強靱化、重要インフラ分野、データ・情報保護、セキュリティ・クリアランスを含む情報保全の強化の検討、技術育成・保全、外国からの経済的な威圧に対する効果的な取組といった措置に取り組むことが記載された。
221 国家安全保障戦略(2022 年12 月)https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshounss-j.pdf![]()
(3)経済産業省等の取組
経済産業省では、サプライチェーンのグローバル化、新型コロナウイルス感染症の拡大、国際法違反の武力による一方的な現状変更等の国際情勢の変化を踏まえ、我が国の存立、国民生活、経済、産業にとって不可欠な戦略物資・エネルギー供給におけるぜい弱性を解消するとともに、グローバル・サプライチェーンにおけるチョークポイント技術の優位性を獲得・維持するため、2022年3月、「戦略物資・エネルギーサプライチェーン対策本部」を設置した。同月開催された第1回会合では、「ウクライナ情勢を踏まえた緊急対策」として、石油・石炭・天然ガスのエネルギーや半導体といった、社会経済活動への影響が広範な物資に加え、対ウクライナ・対ロシア依存度が高い品目について分析を行い、安定供給確保のための対策を早急に講じる必要のある物資と、その対策を検討して取りまとめた。また、同年6月には第2回会合を開催し、経済安全保障推進法における特定重要物資の指定も見据え、経済安全保障の観点から重要な物資・技術の特定や対応策の検討を行った。引き続き、今後の状況変化も想定しながら、サプライチェーンを脅かす潜在的なリスクにも目配せしつつ、抜かりなく万全の対策を期していく。
また、経済安全保障推進法における重要物資の指定を受け、令和4年度第2次補正予算では、半導体、クラウド、蓄電池、永久磁石、工作機械・産業用ロボット、航空機の部品、重要鉱物、天然ガスといった経済安全保障上重要な物資に関し、それぞれの特性に応じた、生産基盤の整備、供給源の多様化、備蓄、生産技術の導入・開発・改良、代替物資の開発等の安定供給確保を図るための取組に対し必要な支援を行うため、9,582億円を計上した222。
重要技術開発に関しては、経済安全保障重要技術育成プログラム223を通じた、AI、量子等の経済安全保障上重要な技術の研究開発・社会実装の推進のため、令和3年度補正予算、令和4年度第2次補正予算で計2,500億円の資金が確保された。
また、半導体に関しては、日米を始めとする国際連携での次世代半導体の製造技術開発、我が国が強みを有する半導体製造装置等のさらなる高度化に向けた技術開発や、データセンターやAI等の最先端技術に必要不可欠な先端半導体の国内生産拠点の整備等を進めている(半導体に関する取組については第Ⅱ部第1章第1節4.参照)。
さらに、鉱物のサプライチェーン強靱化のため、カーボンニュートラル実現に向けて需要の増大が見込まれるバッテリーメタルやレアアース等の鉱山開発や製錬等を行う民間企業を出資により支援している。2023年3月、日本として初となるレアアース(重希土類)の権益を獲得することが発表された224。独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)と双日株式会社が豪レアアース大手に出資し、EVや風力発電モーター用磁石等に使用されるレアアースであるジスプロシウム及びテルビウムの最大65%を日本向けに供給する契約を締結した。これは国内需要の3割程度に相当するものと見込まれ、日本へのレアアースの安定供給に寄与する。
こうした取組も含めたレアメタル権益の確実な確保に向けた支援措置など安定供給体制の強化や、メタンハイドレート、海底熱水鉱床、レアアース泥等の国産海洋資源の確保に取り組んでいく。
222 抗菌性物質製剤、肥料、船舶の部品についても、それぞれ、厚生労働省、農林水産省、国土交通省において必要な措置がとられている。
223 経済安全保障推進会議及び統合イノベーション戦略推進会議の下、内閣官房、内閣府、文部科学省及び経済産業省が中心となって、府省横断的に、経済安全保障上重要な先端技術の研究開発を推進するもの。具体的には、有識者等で構成されるプログラム会議における検討を経たうえで国のニーズ(研究開発ビジョン)を上記二つの閣僚級会議で決定し、これを実現するための研究開発を公募により推進。政府全体の予算額は計5,000億円(国立研究開発法人科学技術振興機構及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構にそれぞれ2,500億円の基金を設置)。
224 経済産業省Web サイト(https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230307001/20230307001.html![]() )から取得。
)から取得。
2.企業側の取組状況と課題
経済的手段を通じた様々な脅威が顕在化し、経済安全保障に関する意識が国内外で強まる中、各国で経済安全保障に関する制度整備が進んでいる。経済安全保障の範囲は非常に多岐にわたり、企業活動にも様々な面で影響が及ぶ可能性がある。特に他国の法律や規制はコントロールすることが難しく、日本企業はこれらの法律や規制にあわせて企業行動を変更させる必要を迫られているが、企業としても、こうしたサプライチェーン上のリスクを始めとした経済安全保障上のリスクをしっかりと精査して判断を行うことが必要であり、そのための体制整備等も重要となっている。
ノムラ・リサーチ・インスティテュート・シンガポール「我が国企業の海外展開の実態及び課題に係るアンケート調査(2022年度)」225によると、経済安全保障に関する「取組を行っている」と回答した企業は11.4%で、「取組に向けた準備をしている段階」(6.6%)との回答と合わせても、約18%と2割に満たない。「取組を行うか行わないか未定で現状では判断できない」と回答した企業が最も多く(49.1%)、約半数を占めており、現状では取組方針が定まっていない企業が多いことが見受けられる。「取組を検討しているが準備に着手していない」は21.6%だった。また、11.4%の企業は「取組は行わない、行う必要はないと判断した」と回答した。
業種別では、「取組を行っている」、「取組に向けた準備をしている段階」と回答した企業は、製造業では19.4%に対し、非製造業では16.2%と、製造業の方が取組がやや進んでいる(第II-1-2-3図)。
第Ⅱ-1-2-3図 経済安全保障に関する取組の状況
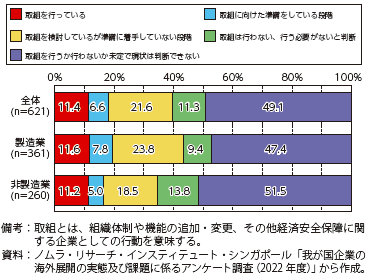
具体的な取組内容(予定を含む)に関しては、回答企業の半数以上(55.6%)が「情報収集の機能強化」と回答した。次いで、「有事に備えた事業継続計画(BCP)の策定」(47.7%)、「全社共通の対応方針の策定・実施」(40.2%)が多く挙げられた。「サプライチェーンの多元化」は31.0%、「専門部署や責任者の設置」は30.1%だった。また、「役員会や戦略会議で情報分析を行っている」との回答もあった(第II-1-2-4図)。
第Ⅱ-1-2-4図 経済安全保障に関する体制整備の状況
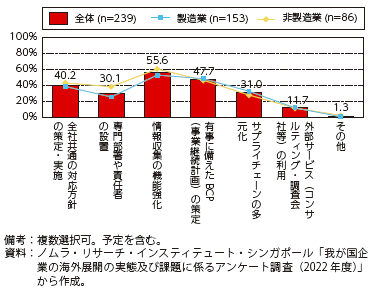
経済安全保障に関する体制整備を行うに当たっての課題については、「経済安全保障に精通した専門人材の確保が難しい」(54.2%)、「関連情報の収集が難しい」(51.9%)を挙げた企業が半数以上に上り、人材確保や情報収集に苦慮している様子が示唆される。「経営層をはじめ社内における理解や課題認識の浸透が不十分」は24.5%、「取引先の協力・理解を得るのが難しい」は19.0%と、経営層をはじめとした社内や、取引先の理解の浸透も課題となっている。「取組を行うだけの予算がない」との回答は17.6%だった。
また、約15%の企業が「何から手を付けてよいかわからない」と回答した。「他社の取組など参考になる情報がない」、「どこまで対応すれば十分かが不明」といった声もあり、手探り状態の企業も存在することが見受けられる。「人的リソースの余裕がない」、「対応に時間がかかる」といった声もあった(第II-1-2-5図)。
第Ⅱ-1-2-5図 経済安全保障に関する体制整備の課題
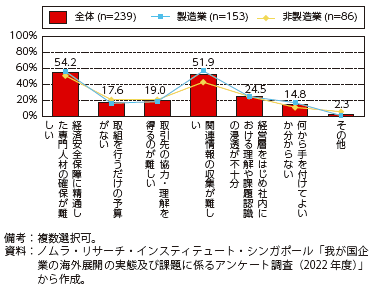
公益財団法人国際文化会館地経学研究所(IOG)は日本企業100社に対し経済安全保障に関するアンケート調査(2023年)を実施している226。同調査は、日本の経済安全保障において重要な位置を占め、またその影響を敏感に受けていると考えられる日本の企業100社(研究機関等を含む。)を対象としており、その9割近くが経済安全保障の取組を行っていると回答していることから回答企業は経済安全保障に対する高い意識を持ち取組を進めている企業と考えられる。昨年度調査から最も増加した経済安全保障の取組は、「生産拠点移管」「情報管理の強化」であった。また経済安全保障推進法施行後の新たな対応としては「専門部署設置」「先端技術への取組強化」と回答した企業が多かった。
また、岡崎、齊藤、土屋、佐橋(2023)による「サプライチェーン及び技術ノウハウ管理をめぐるアンケート調査」227によると、回答企業のうち技術ノウハウ管理を行っていると回答した企業は67%であった。従業員規模が50人を超える企業では、60%以上が管理を行っている一方、従業員規模が50人未満の企業については、50%を下回る結果となっており、企業規模によって対応に差異が見られる。
経済産業省では、中小企業等における安全保障管理制度、技術情報管理認証制度、不正競争防止法等各種制度に基づく包括的な技術管理体制の構築・運用改善のため、説明会の開催、専門人材の派遣による個別相談等を通じた指導・支援・普及啓発を実施しており、このような制度の活用も有効と考えられる。
前項で見たように、我が国の経済安全保障推進法や国家安全保障戦略においては、自由な経済活動との両立、民間との連携といった要素が取り入れられている。経済安全保障推進法の基本方針では、「安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進していくためには、政府がその役割を果たすことはもとより、実際に経済活動を行っている事業者等を含む国民全体の理解と協力が不可欠である。すなわち、経済活動における様々な場面において、技術力の維持・向上及び技術流出の防止を始め、安全保障上の視点も踏まえた自発的な行動に努める事業者等が増えていくことによって、政府の措置と合わせて、経済面から国家及び国民の安全が確保されることが重要である。」とされており、経済安全保障の確保のため官民が連携して取り組んでいくことが重要である。
225 アンケート実施期間:2023年2~3月。調査対象:金融・保険業を主業から除く、関係会社に海外企業を含む企業に送付(関連企業は、出資比率50.1%以上)。調査方法:調査票を郵送し、WEBでの回答を依頼。有効回答数:621社、回収率:6.6%。
226 公益財団法人国際文化会館地経学研究所(IOG)「経済安全保障に関する第2回日本企業100 社アンケートの結果を発表」(https://apinitiative.org/2023/02/06/43564/![]() )。
)。
227 岡崎友⾥江、⿑藤孝祐、⼟屋貴裕、佐橋亮(2023)「サプライチェーン及び技術ノウハウ管理をめぐるアンケート調査」RIETI Discussion Paper Series 23-J-013(https://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/23030015.html?id=nl![]() )。
)。