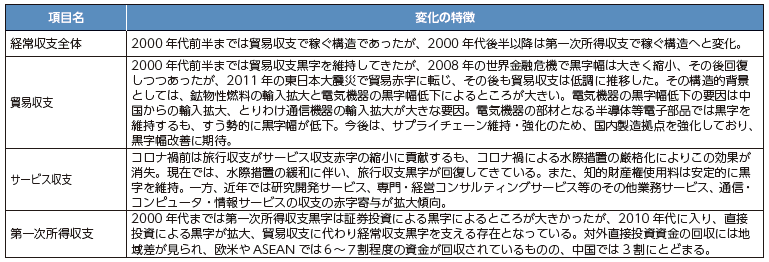第1節 我が国の経常収支の動向
本章では、2022年は資源高と円安の進行により、過去最大の貿易赤字に直面したが、その大宗は鉱物性燃料の輸入価格の上昇によるものであり、貿易構造の強靱化を図る上でも、鉱物性燃料の依存低減は重要な課題であることを示す。
また、円安は輸出の好機である一方、一部の品目では円安を円建て輸出収益の増加につなげられていないこと、ただし、これらの品目でも、単価の見直しにより収益改善の余地がある可能性があることを示す。
また、企業の海外展開は収益、雇用、賃金、生産性のみならず、地域の輸出促進の観点からも国内経済に貢献していること、スタートアップをはじめ、企業の海外展開を強力に推進していくことを示す。
また、我が国のグローバルな競争力の強化には、「内なる国際化」も重要であり、対日直接投資の促進や高度外国人材の獲得を強化していくことを示す。
1.経常収支の動向
まずは1990年代以降の経常収支について見ていく。第II-2-1-1図は1996年以降の経常収支を見たものだが、2000年代前半までは、経常収支黒字を支えていたのは貿易収支黒字であったが、リーマン・ショックを経て2000年代後半以降は、貿易黒字よりも第一次所得収支の黒字によって、経常収支黒字が支えられていることが分かる。すなわち、我が国経済は国内で生産しそれを輸出することで稼ぐという構造から、海外拠点の売上によって得られた利益の一部を我が国に還元することで稼ぐ構造へと変化しているといえる。
第Ⅱ-2-1-1図 日本の経常収支の推移
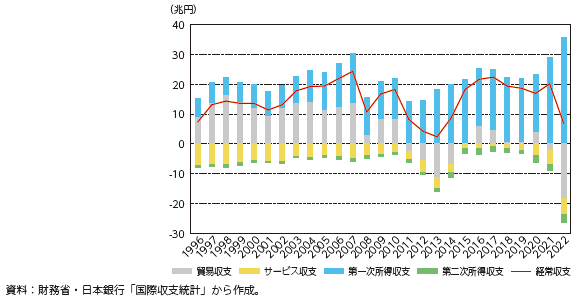
2.貿易収支の動向
次に、経常収支を構成する内訳別に子細に見ていく。 まずは2000年以降の貿易収支について見ていく。第II-2-1-2図は2000年以降の貿易収支を主要品目別・輸出入別に見たものだが、電気機器に着目すると、2000年代前半までは貿易黒字に寄与してきたが、2010年代以降はその寄与が小さくなっている。また、鉱物性燃料は一貫して貿易赤字に寄与しているが、2000年代後半以降、その寄与が大きくなっている。第II-2-1-3図はこの傾向をよりはっきりと見せるために、2000年時点を基準にした貿易収支変化を主要品目別に要因分解して見てみたものであるが、輸送用機器や一般機械では2000年時点から貿易黒字が拡大傾向にある一方で、鉱物性燃料と電気機器ではすう勢的に赤字方向への寄与が拡大している。
第Ⅱ-2-1-2図 日本の貿易収支の推移(主要品目別)
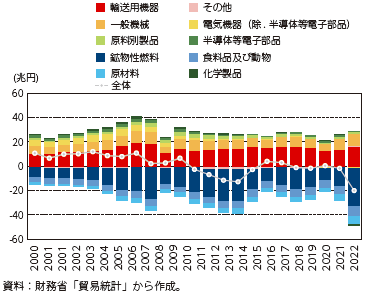
第Ⅱ-2-1-3図 2000年時点を基準とした日本の貿易収支の主要品目別増減
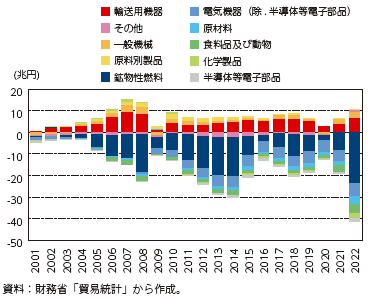
第II-2-1-4図は2000年以降の貿易収支を主要地域別に見たものだが、米国、NIEs3、香港、インドでは貿易黒字を維持している一方、中東や大洋州、中国では貿易赤字が拡大傾向にあるのが見て取れる。
第Ⅱ-2-1-4図 貿易収支の推移(主要地域別)
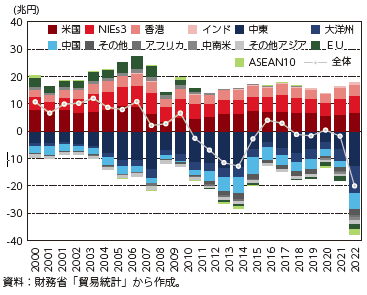
第II-2-1-5図は主要品目別かつ主要地域別の貿易収支について、2000年代前半(2000年~2004年の平均値)から2010年代後半(2015年~2019年の平均値)にかけての変化のうち、黒字方向に寄与した上位10位と赤字方向に寄与した上位10位を見たものである。輸送用機器が幅広い地域で黒字に寄与しているほか、アジアの化学製品、アジアの一般機械が黒字に寄与している。一方、赤字方向への寄与では、その他地域(主に大洋州)と中東の鉱物性燃料がとりわけ大きく寄与しているほか、中国の電気機器の赤字寄与が大きくなっている。
第Ⅱ-2-1-5図 主要品目別×主要地域別の貿易収支変化(2000年代前半→ 2010年代後半)
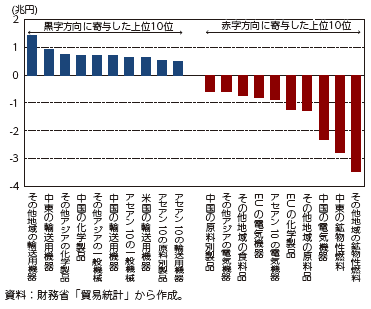
第II-2-1-6図は中国の電気機器に着目し、2000年時点と比較した中国からの電気機器の輸入をさらに品目別内訳で見たものだが、通信機の寄与が最も大きくなっており、かつては携帯電話を国内で生産し供給していたが、現在ではその大半が中国からの輸入に代替されていることが主な要因と考えられる。
第Ⅱ-2-1-6図 2000年時点と比較した中国からの電気機器の輸入の品目別増減
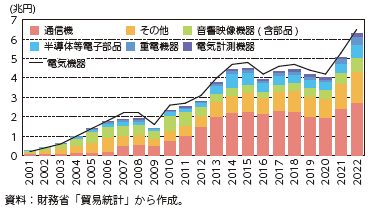
3.サービス収支の動向
次に1996年以降のサービス収支について見ていく。第II-2-1-7図は1996年以降のサービス収支・サービス輸出・サービス輸入の推移をサービス別に見たものだが、サービス収支は一貫して赤字となっているが、2014年以降は旅行によるサービス輸出が拡大し、旅行収支は黒字に寄与するようになった。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行による水際措置の厳格化により、2020年以降は旅行収支の黒字寄与は大幅に縮小した。また、2000年代半ば以降、知的財産権使用料の収支が黒字に寄与している。一方、近年では研究開発サービス、専門・経営コンサルティングサービス等のその他業務サービス、通信・コンピュータ・情報サービスの収支の赤字寄与が拡大傾向にある。
第Ⅱ-2-1-7図 サービス収支の推移
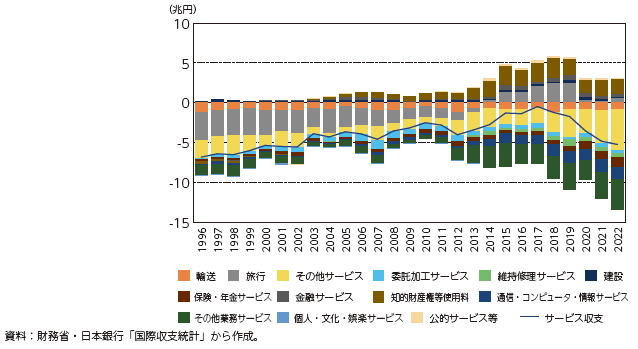
地域別に見ると、主に旅行収支黒字により、中国の収支が黒字に寄与している(第II-2-1-8図)。一方、通信・コンピュータ・情報サービス輸入の拡大を背景に、米国やEU、また2019年以降は、その他業務サービスの輸入拡大を背景にASEANの収支の赤字寄与が拡大傾向にある。
第Ⅱ-2-1-8図 サービス収支(地域別)
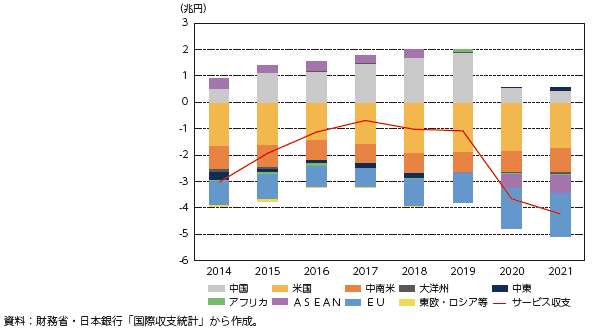
4.第一次所得収支の動向
最後に1995年以降の第一次所得収支について見ていく。第II-2-1-9図は1995年以降の第一次所得収支の前年比を内訳別に見たものである。第一次所得収支は一貫して黒字となっているが、その内訳を見ると2000年代までは大半が証券投資収益によるものであったが、2010年代以降は直接投資収益による寄与が拡大しており、我が国企業の製造・販売拠点のグローバル化が安定して我が国の経常収支に対して黒字をもたらしている様子がうかがえる。第II-2-1-10図は2014年以降の直接投資収益を地域別に見たものであるが、ASEANをはじめとするアジア(中国を除く)からの収益が最も大きく、次に米国、中国と続く。第II-2-1-11図は直接投資の実行に対する回収の割合を見たものだが、欧米諸国やASEAN諸国では投資実行に対して6~7割程度が回収されている一方で、中国では回収率が3割程度にとどまっている。
第Ⅱ-2-1-9図 日本の第一次所得収支の推移
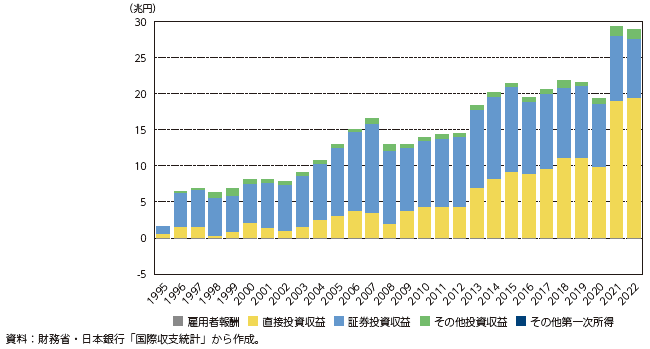
第Ⅱ-2-1-10図 日本の地域別対外直接投資収益の推移
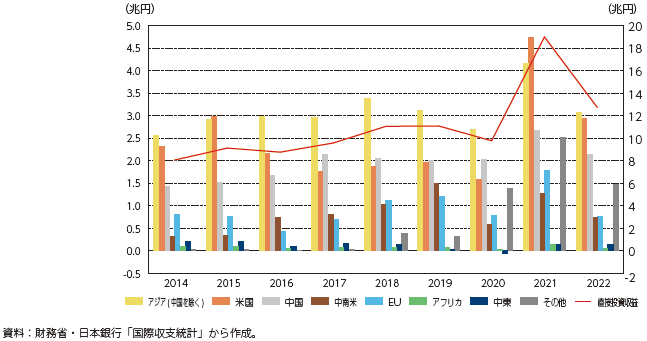
第Ⅱ-2-1-11図 直接投資実行に対する回収の割合の推移
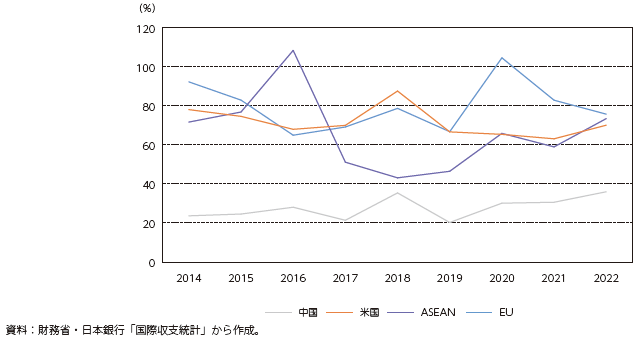
上記を踏まえると、我が国の中長期的な稼ぐ力の変化は下表のように整理できる(第II-2-1-12表)。次節では、足下の貿易収支に焦点を当て、そのぜい弱性を特定し、安定的に稼ぐ力を高めるための方策を探っていく。
第Ⅱ-2-1-12表 経常収支から見た稼ぐ力の変化