第2節 我が国の貿易収支構造の強靱化に向けた課題
1.過去最大となった2022年の貿易赤字の要因分析
資源価格の高騰や主要国と我が国の金融政策の方向性の違い等に起因する円安進行を背景に、2022年の貿易赤字は過去最大となった。本項では、その要因について分析を行う。具体的には、日本銀行が公表する輸出物価指数及び輸入物価指数、並びに実質輸出入指数を用いることで、貿易収支の変動要因を為替変動によるもの、契約通貨建ての価格変動によるもの、名目の輸出入額から物価変動を取り除いた実質の輸出入の変動によるものの3要素に要因分解し、何が貿易赤字の主因であるかを特定する。
第II-2-2-1図は貿易収支変動の、為替変動要因と契約通貨建ての価格変動要因と実質輸出入変動要因への要因分解について解説したものであるが、円建ての輸出額(輸入額)=為替×契約通貨建て輸出価格(輸入価格)×実質輸出(輸入)【(1)式】という形で表すことができる。すなわち、両辺の対数をとることで、円建ての輸出額(輸入額)の対数=為替の対数+契約通貨建て輸出価格(輸入価格)の対数+実質輸出(輸入)の対数【(2)式】と表すことができ、さらに変化率を対数差分として表せば、円建ての輸出額(輸入額)の変化率=為替の変化率+契約通貨建て輸出価格(輸入価格)の変化率+実質輸出(輸入)の変化率【(3)式】と表すことができる。ここで、貿易収支への要因分解を分かりやすくするために、貿易収支を輸出額/輸入額として定義すれば、貿易収支の変化率=円建ての輸出額の変化率-円建ての輸入額の変化率【(4)式】となり、(4)式に(3式)を代入して整理することで、貿易収支の変化率=契約通貨建て価格変動要因(契約通貨建て輸出価格の変化率-契約通貨建て輸入価格の変化率)+実質数量変動要因(実質輸出の変化率-実質輸入の変化率)に分解できる。
第Ⅱ-2-2-1図 貿易収支変動の要因分解の解説
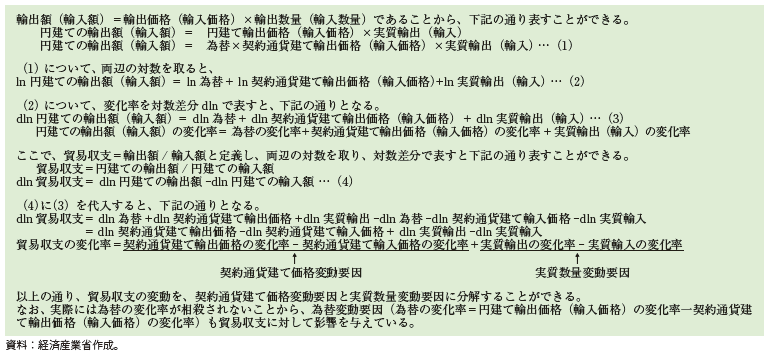
この考え方の下、2021年から2022年にかけての貿易収支の変化率を要因分解したものが第II-2-2-2図である。まず、実質数量の変動要因については、輸出、輸入ともに寄与は小さく、主たる要因でないことが分かる。次に契約通貨建て価格の変動要因を見てみると、輸出価格の変動の寄与が限定的であるのに対して、輸入価格の変動が大きく赤字方向に寄与しており、貿易赤字に対する主たる要因となっていることが分かる。また、為替変動要因を見てみると、輸入価格の為替変動要因の寄与が契約通貨建て輸入価格の寄与を上回るほどに大きくなっており、円安が円建て輸入価格の増加を通じて貿易赤字に寄与していることが分かる。しかし、輸出価格の為替変動要因については、大きく黒字方向に寄与しており、貿易収支全体への影響で見れば、為替変動要因よりも契約通貨建て価格変動要因の方が大きく、貿易収支赤字をもたらしている主因は契約通貨建て価格変動要因であると結論付けることができる。さらに契約通貨建て輸入物価の変動を、品目別に寄与度分解すると、鉱物性燃料価格の変動で全体の変動の約8割超を占めている。すなわち、契約通貨建ての価格変動要因が貿易収支の変動に占める寄与が約7割程度であるため、2022年の貿易収支変動の太宗は、契約通貨ベースの鉱物性燃料の輸入価格の上昇に起因していると言い換えることができる。
第Ⅱ-2-2-2図 2022年の貿易収支の変動要因分解
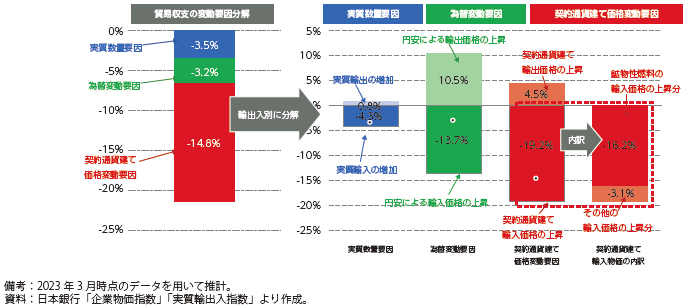
現在の貿易収支構造が鉱物性燃料の輸入価格の影響を受けやすいということは、我が国の鉱物性燃料の輸入依存度の高さが、現在の貿易収支構造のぜい弱性となっていることを意味する。第II-2-2-3図は我が国の1次エネルギーの供給構成を見たものであるが、東日本大震災のあった2011年を境にして鉱物性燃料への割合が断層的に上昇しており、依存度が高まっている様子がうかがえる。ただし、第II-2-2-4図は、経済活動(GDP)1単位の増加によって生じる鉱物性燃料の輸入量の増加分(弾性値)の推移を見たものであるが、エネルギー効率の上昇等を背景に中長期的にみて弾性値は減少トレンドにあり、2012年以降はこの減少トレンドがより顕著になっている。これは東日本大震災以降、原子力の利用が限られている中において、省エネ・再エネが加速していることの証左と言えよう。しかし、今般生じた過去最大の貿易収支赤字は、我が国の鉱物性燃料の輸入依存度の高さが貿易収支構造のぜい弱性となっていることを露呈させたと言え、引き続き、省エネ・再エネの拡大を進めつつ、また、安全性の確保を前提とした原子力の利用も含めた多様な電源利用を進め、鉱物性燃料の輸入依存の低減を図ることが、貿易収支構造の強靱化を図る上でも重要な課題であることを示唆している。
第Ⅱ-2-2-3図 日本の一次エネルギー供給構成
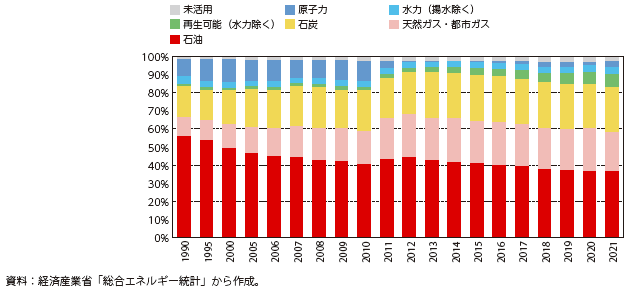
第Ⅱ-2-2-4図 実質GDP1単位の増加に対する鉱物性燃料輸入の弾力性
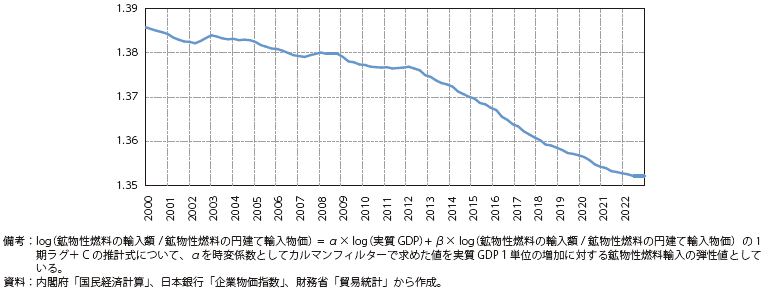
以上、過去最大となった2022年の貿易収支赤字を変動要因分解すると、大部分は契約通貨建ての輸入物価の上昇に起因しており、その大半は鉱物性燃料の輸入価格上昇によってもたらされていること、我が国の一次エネルギー供給構造を見ると、東日本大震災以降、化石燃料輸入依存の低減は進んできているものの依然高い水準にあり、貿易構造を強靱化する観点からも、鉱物性燃料依存の低減は引き続き重要な課題であるといえる。一方で、資源に乏しくエネルギーや食料の多くを輸入に頼らざるを得ない我が国にとって、自由貿易体制を維持し強化していくことは、自国の利益にかなうものであるとともに、世界の主要貿易国としての責務でもある。また、今般の円安方向への動きは輸出拡大の好機であったにも関わらず、輸出が貿易収支に与える影響が限定的であったことも、我が国の稼ぐ力を維持・強化していく上での課題である。また、経済安全保障やサプライチェーンの強靱化の観点から国内製造拠点を強化する動きもある中で、この流れも踏まえつつ、国内投資拡大、イノベーション加速、所得向上という三つの好循環の実現へとつなげていくことが重要である。
2.輸出収益の改善に向けた課題
前項でみたとおり、円安は輸出拡大の好機であったにも関わらず、輸出が貿易収支に与える影響は限定的であったが、本項では、今般の円安局面における輸出収益の状況を子細に見ていくことで、輸出収益の改善に向けた課題を明らかにしていく。
まず、第II-2-2-5図を用いながら、円安による輸出促進効果について解説する。円安による輸出促進効果とは、円安が結果的に輸出数量を増加させる効果のことをいう。今、ドル円の為替レートについて円安方向への動きが生じたとする。この時、輸出企業が円建ての輸出価格を据え置くという行動をとれば、円が減価しているのでドル建ての輸出価格は下落する。ドル建ての輸出価格の減少で価格競争力が生まれ、輸出数量が増加する。これが円安による輸出促進効果である。しかし、輸出価格の下落を上回る輸出数量の増加が得られなければ、輸出金額の増加には結びつかないことに留意が必要である。
第Ⅱ-2-2-5図 円安による輸出促進効果(ドル建ての場合)
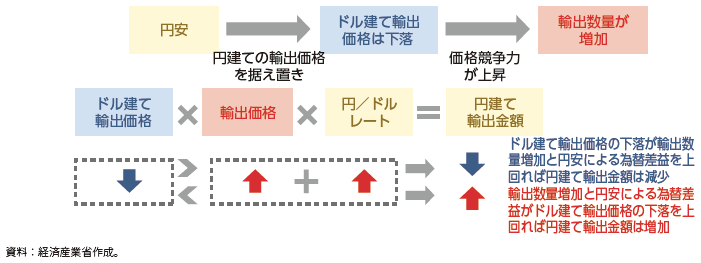
JETRO(2022)228では、Markit社のGlobal Trade Atlasに収録されている輸出数量とドル建ての輸出額を用いて、2022年上期の品目ごとの輸出を見ると、HS6桁コード4199品目中1942品目で前年同期の輸出数量が増加、このうち7割近い1320品目で前年同期に比べてドル単価が下落していること、このうち半数を上回る861品目で前年同期から輸出額が増えていたことを分析しており、一部の品目では円安による輸出促進効果が見られる可能性を示唆している。
この分析を参考にしつつ、通年ベースでの2021年から2022年の輸出の変化について、ドル単価の変化と円建て輸出収益の状況に着目して見てみたものが第Ⅱ-2-2-6図である。これを見ると、HS6桁コード全体の輸出品目のうち、約7割が円建ての輸出収益増となっている一方、約3割が円建ての輸出収益減となっていることが分かる。より子細に見ると、全体の約4割でドル単価が下落する一方で収益増となっており、円安による輸出促進効果により収益増となっている様子がうかがえる。特に、精密機器や食料品、繊維、一般機械、輸送用機器でその割合が高くなっている。一方、約2割の品目でドル単価の下落が輸出収益増につながっていないことも分かる。特に窯業・土石製品、紙・パルプ・木材・木製品、電気機械でその割合が高くなっている。また、ドル単価の上昇で収益増となっている品目も全体の約3割あり、特に石油・石炭製品、鉄鋼・非鉄金属・金属製品、化学製品でその割合が高くなっている。一方、ドル単価の上昇で収益減となっている品目は全体の1割程度存在している。
第Ⅱ-2-2-6図 ドル単価の変化と円建て輸出収益の状況(2021年→ 2022年)
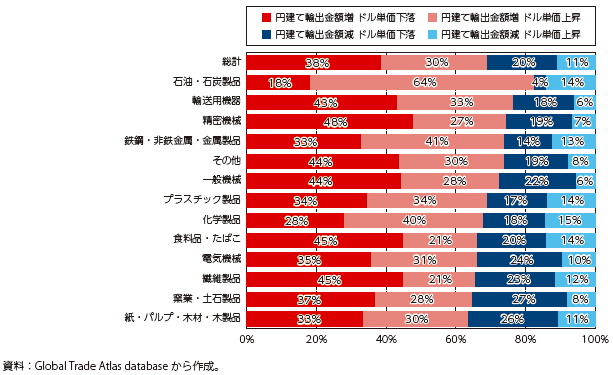
次に、2021年から2022年にかけてのドル単価の変化と円建て輸出金額の変化との関係について理解を深めるため、その特徴をより子細に見ていく。まず、HS6桁品目ごとの2021年から2022年にかけてのドル単価の変化率と輸出数量の変化率の関係に着目し、ドル単価下落かつ円建て輸出金額増加、ドル単価上昇かつ円建て輸出金額増加、ドル単価下落かつ円建て輸出金額減少、ドル単価上昇かつ円建て輸出金額減少の4つのタイプに分けて、ドル単価の変化による輸出数量の感応度を算出し、さらにそこから円建て輸出金額の感応度を算出したものが第Ⅱ-2-2-7図である。ドル単価下落かつ円建て輸出金額増加の品目とドル単価上昇かつ円建て輸出金額減少の品目では、ドル単価の下落で円建て輸出収益が増加する傾向にあることが分かる。一方で、ドル単価上昇かつ円建て輸出金額増加の品目とドル単価下落かつ円建て輸出金額減少の品目では、ドル単価の上昇で円建て輸出収益が増加する傾向にあることが分かる。
第Ⅱ-2-2-7図 ドル単価10%の下落による円建て輸出収益の変化
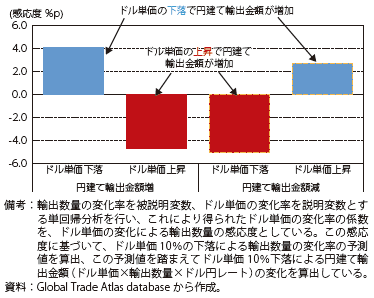
第Ⅱ-2-2-8図は、2021年から2022年にかけての実際のドル単価の変化率を見たものであるが、円建て輸出金額が減少したグループに着目すると、実際のドル単価の変化の方向と、第Ⅱ-2-2-7図で見た収益が出るドル単価の方向が逆になっていることが分かる。これは、ドル単価下落の品目では、ドル単価上昇で収益が改善する可能性があり、ドル単価上昇の品目では、ドル単価下落で収益が改善する可能性があることを示唆している。
第Ⅱ-2-2-8図 ドル単価の変化率(2021年→ 2022年)
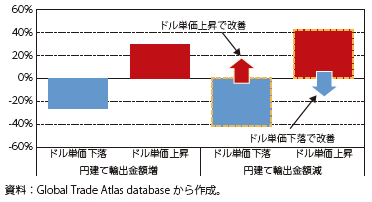
以上で見てきたことは、円安方向への動きの中でのドル単価の変化、円建て輸出金額の変化を見たものではあるが、貿易相手国の需要変動の影響なども含まれており、厳密には円安方向への動きに起因する輸出の変化を分析したものにはなっていない。そこで、1994年~2022年までの期間における、HS6桁コード4000品目超をさらに国ごとに分けた上で、輸出先の国の需要変動による影響をコントロールしつつ、円安がドル単価の下落を通じて輸出数量の増加をもたらしているのかについて検証することとする。
まずは検証方法について概説する。本分析で用いるデータは上述のHS6桁コードの品目をさらに国別に分けたもの(以下、これを「市場」という)を使用し、データが取得可能な1994年~2022年の年間の値を使用する。また、上述に倣い、市場別のドル建ての輸出額を輸出数量で除すことにより得た値をドル建て単価として用いる。為替にはドル円レートを用い、為替の変化がドル建て単価の変化を通じて輸出数量に与える影響を、操作変数法を用いて推計する。推計に当たっては、輸出数量が為替のみならず輸出相手国の需要の影響を受けることを考慮し、説明変数には輸出相手国のGDPの変化率を追加するとともに、品目別国別の輸出固有の動きやHSコード改定に伴う統計への影響もコントロールするなど、可能な限り他の影響を排除した上で、為替の変化がドル建て単価の変化を通じて輸出数量に与える影響を分析する。
分析結果の詳細は付注4のとおりであるが、貿易相手国の需要要因をコントロールした上でも、円安方向への動きはドル単価の下落を通じて輸出数量を増加させる効果があることが示されている。ただし、平均的には、円安方向への動きによるドル単価の下落分に対して、輸出数量の増加効果は価格下落分を下回るため、収益確保の観点からは、円安局面でもドル単価の下げ過ぎは収益を損なう可能性があることに留意が必要であるといえる。
228 JETRO「特集:世界経済の混乱で求められる海外ビジネスの再構築 円安下、半数近くの商品が輸出数量を伸ばす(日本)2022 年上半期の貿易を分析」https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2022/1002/a9c529af460e7ded.html![]()