第3節 我が国経済の成長のけん引役として期待されるインバウンド需要
観光は、日本の力強い経済を取り戻すための極めて重要な成長分野である。今後人口減少・少子高齢化が見込まれる中、国内の観光需要を喚起するとともに、急速に成長するアジアを始めとする世界の観光需要を取り込むことにより、地域経済の活性化、雇用機会の増大などにつなげていくことが重要である。
我が国は、政府が一丸となってインバウンド(訪日外国人旅行)を推進してきた。第二次安倍政権以降では、2013年に設置された「観光立国推進閣僚会議」により策定された「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」の実行により、同年には訪日外国人旅行者数が初めて1,000万人を上回り、翌年には訪日外国人による旅行消費額も2兆円を突破した。さらに2016年に策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」では、2020年までに訪日外国人旅行者数4,000万人、訪日旅行消費額8兆円、2030年までに同6,000万人、15兆円という目標が掲げられ、順調に訪日外国人旅行者数、消費額を拡大させ続けてきた。
しかし、2020年の新型コロナウイルス感染症の世界的大流行という不可抗力により2年超の間インバウンドは大きく落ち込んだ。2022年6月からは段階的に観光目的の受入れが再開され、インバウンドの回復に向けた機運が高まった。さらにこの時期、ドル円レートは米国の急速な利上げ等を要因として、2022年10月には一時1ドル151円台後半まで円安が進み、1990年以来32年ぶりの水準を更新した。円安傾向となると、訪日外国人旅行者の自国通貨ベースでの負担額が減ることから、インバウンド消費へのさらなる後押しとして期待された。
このような中、本節では、日本経済の持続的な底上げへの寄与が期待されるインバウンドの方向性について概観する。
1.これまでの水際対策の主な経緯
2020年初に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、日本へ入国する際の水際対策が強化されることとなった。
水際対策の経緯を振り返ると、まず2020年2月から中国の一部地域を入国拒否対象地域に指定し、同地域からの入国を原則拒否した。これを皮切りに、同年4月までに米国、中国、韓国、欧州各国を始めとする多数国を対象に指定し、インバウンドはほぼ消失することとなった。その後、ビジネス目的の往来等は感染状況を見極めながら入国規制の緩和と強化を繰り返していたが、観光目的の入国に対する制限は続けられていたことから、国内外から観光客受入れ再開を求める声が高まっていた。
このような中、2022年5月に岸田首相がロンドンでの講演にて、「(水際対策の)G7諸国並みの緩和」を表明し、翌6月から添乗員付きパッケージツアー等の条件付きで、観光客受入れが再開された。さらに、同年10月からは、水際対策が大幅に緩和され、査証(ビザ)なし渡航や個人旅行が再開されたほか、入国人数の上限が撤廃された(第II-2-3-1表)。ビザは、書類準備の手間や審査条件の厳しさにより訪日の障壁となっていたり、個人旅行は、コロナ禍前には訪日外国人旅行者の8割超を占めていたりしたことから、ビザなし渡航や個人旅行の受入れ再開により、インバウンドが回復基調になった。下図(第II-2-3-2図)は、訪日外国人旅行者数の推移を月次で示しているが、2020年1月を境に激減し、同年4月からはゼロ近傍が続いていたが、水際対策が大幅に緩和された2022年10月以降堅調に回復しており、2023年1月以降は2019年の半分の水準を上回っている。
第Ⅱ-2-3-1表 観光目的の水際対策についての主な経緯
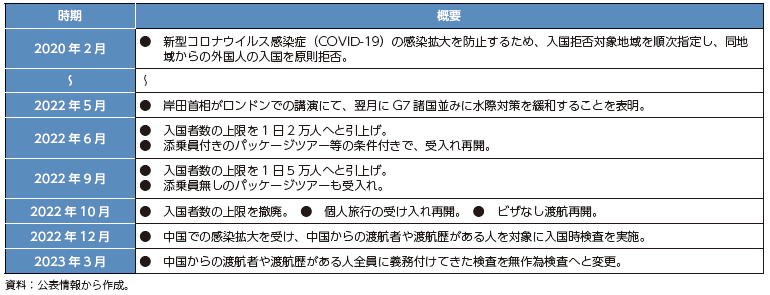
第Ⅱ-2-3-2図 訪日外国人旅行者数の推移(2019年1月~2023年3月)
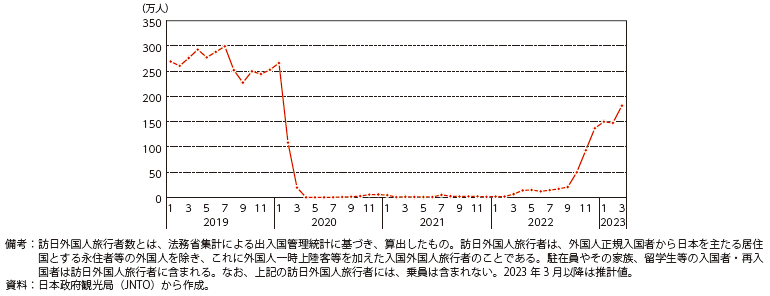
それではインバウンドは、日本経済の中でどの程度の規模を示しているのか。インバウンド消費は、GDP統計(国民経済計算)の中で「サービス輸出」に分類されることから、日本の主要品目の輸出額と比較してみる。下図(第II-2-3-3図)で示したとおり、インバウンド消費は「サービス輸出」の中の「非居住者家計の国内での直接購入」に計上され、2019年は4.6兆円となる。貿易統計の主要品目別対世界輸出額(2019年)をみると、自動車(12.0兆円)、半導体等電子部品(4.0兆円)、自動車部品(3.6兆円)、鉄鋼(3.1兆円)が上位に並ぶ。インバウンド消費は、半導体等電子部品を上回って自動車に次ぐ輸出産業となっており、日本経済をけん引する存在となっていることが分かる。
第Ⅱ-2-3-3図 訪日外国人旅行消費額と主要品目別輸出額の比較(2019年)
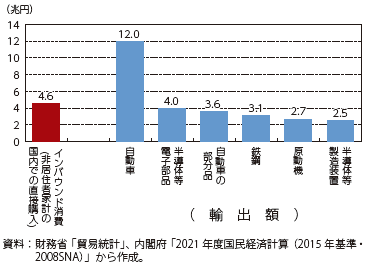
第II-2-3-4表は、経済産業省(2020)229が試算した2019年の訪日外国人旅行消費額約4.8兆円の生産波及効果を示しており、「生産誘発額(消費額含)(一次)」は、7兆7,756億円で、消費額の1.75倍となった。つまり訪日外国人による旅行消費が国内に波及したことにより、プラスで75%の新たな生産を生じさせる効果があることを示している。
第Ⅱ-2-3-4表 訪日外国人旅行消費の生産波及効果(2019年)
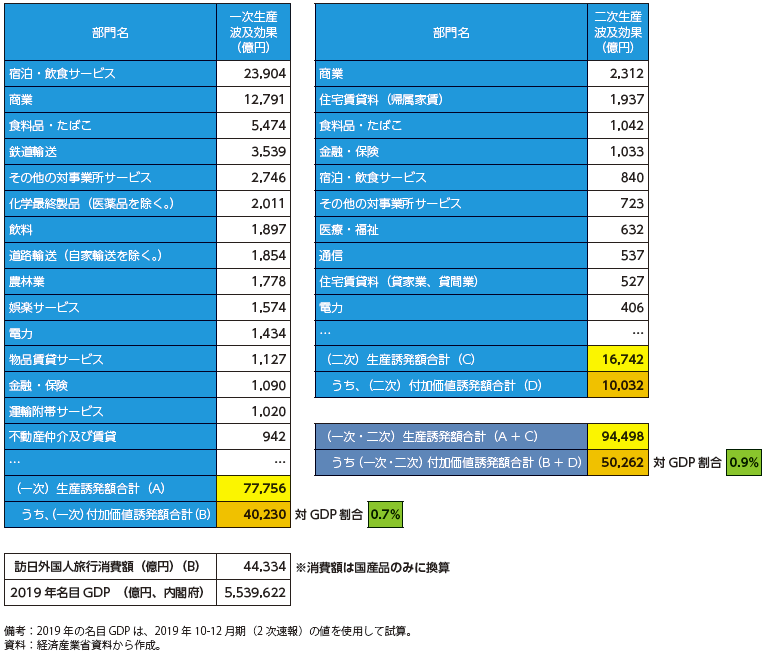
この「生産誘発額」は「売上高」に相当するものであることから、「生産誘発額」から中間投入を除いた「付加価値誘発額」も試算されている。結果、「付加価値誘発額(一次)」は、4兆230億円で、2019年の名目GDPの0.7%相当となった。「付加価値誘発額」の内訳である「雇用者所得誘発額」は、その一部が消費に回ることで「さらなる生産」が誘発される(二次波及効果という)。二次波及効果としての「生産誘発額(二次)」は1兆6,742億円、「付加価値誘発額(二次)」は1兆32億円と試算された。
以上をまとめると、生産誘発額総額(一次、二次)は約9.4兆円、ここから中間投入を除いた付加価値誘発額(一次、二次)は約5.0兆円となり、これはGDPの0.9%に相当する。このように、インバウンド消費を波及効果も含めてみるとすそ野広く伝播しており、日本経済に与えるインパクトはより大きくなることが分かる。
229 経済産業省「ひと言解説:訪日外国人旅行消費の蒸発の影響試算;年間で9割減少すると、GDPに0.8%の押し下げ効果」Webサイトを参照(https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20200804hitokoto.htmlhttps://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20200804hitokoto.html![]() )。
)。
3.インバウンド関連政策230 と訪日外国人旅行者の増加(コロナ禍前)
我が国はインバウンドを成長戦略の柱と位置づけ、関連する政策を講じインバウンド拡大を力強く推進してきた。ここでは第二次安倍政権発足以降の取組に焦点を当ててインバウンド関連政策と訪日外国人旅行者の増加の過程を見ていく。
2013年に、安倍総理大臣(当時)は施政方針演説の中で「世界の人たちを惹きつける観光立国を推進すること」を表明し、新たに創設した「観光立国推進閣僚会議」において「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」を取りまとめた。さらに同年9月には「2020年オリンピック・パラリンピック夏季大会」の開催地に東京が選出されたことから、この絶好の機会を追い風として、2020年に向けて訪日外国人旅行者数2000万人の高みを目指すことが2014年のアクション・プログラム231で明記された。政府一丸、官民一体となってアクション・プログラムの実施に取り組み、戦略的なビザの緩和や免税制度の拡充、出入国管理体制の充実、航空ネットワーク拡大等の改革が次々と進められた。
その結果、2015年の訪日外国人旅行者数は、2012年に比べ2倍増の約2000万人(2012年836万人)、2015年の訪日外国人旅行消費額は、3倍増の約3.5兆円(2012年約1.1兆円)を突破した。
2016年には、次なる目標とその実現のために必要な対策を検討する「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」が開催され、「明日の日本を支える観光ビジョン232」が取りまとめられた。同ビジョンの中で、新たな目標として「2020年までに訪日外国人旅行者数4,000万人、訪日旅行消費額8兆円、2030年までに同6,000万人、同15兆円」と掲げ、着実に訪日外国人旅行者数、消費額を拡大させ続けてきた。
2020年には、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行という不可抗力により目標値を大幅に下回ったものの、前年(2019年)は訪日外国人旅行者数3,188万人、訪日旅行消費額4.8兆円と過去最高を記録した。国別でみると、訪日外国人旅行者数、訪日外国人旅行消費額ともに、地理的優位性のある中国、韓国、台湾、香港等東アジアからが全体の約7割を占める(第II-2-3-5図、第II-2-3-6図)。
第Ⅱ-2-3-5図 国籍・地域別訪日外国人旅行者数と訪日外国人旅行消費額の推移(2003~2022年)
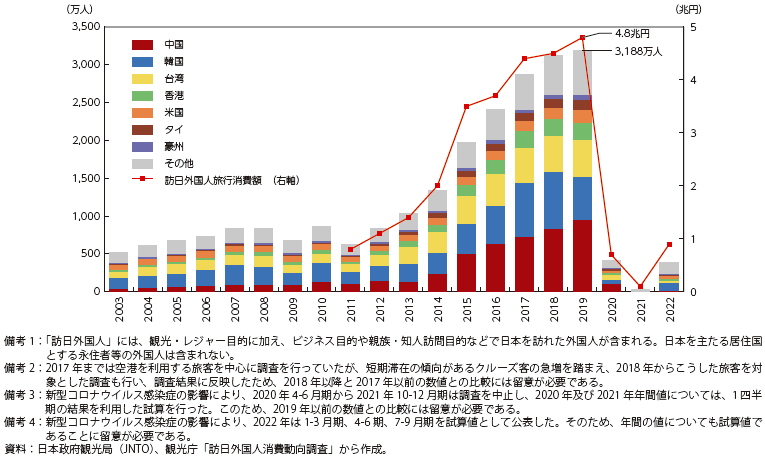
第Ⅱ-2-3-6図 国籍・地域別訪日外国人旅行消費額の構成比(2019年)
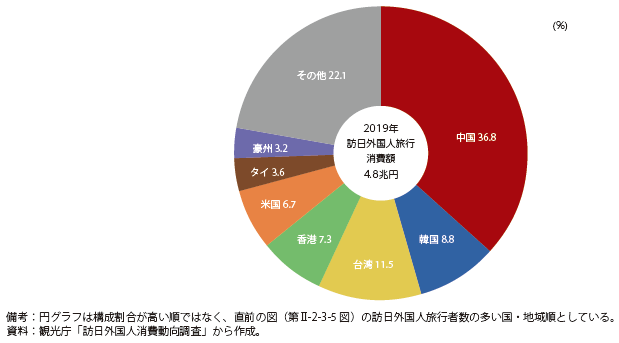
2023年3月には、2023~2025年度の新たな計画として「観光立国推進基本計画」が閣議決定された。「持続可能な観光」、「消費額拡大」、「地方誘客促進」という三つをキーワードとしており、同計画に基づき、コロナ禍後の持続可能な形での観光立国の復活に向けた取組が講じられていく。
230 観光庁「観光立国推進基本法」Web サイトを参照(https://www.mlit.go.jp/kankocho/kankorikkoku/index.html![]() )。
)。
231 観光庁「アクション・プログラム2014」Web サイトを参照(https://www.mlit.go.jp/common/001046636.pdf![]() )。
)。
232 232 観光庁「明日の日本を支える観光ビジョン」概要(https://www.mlit.go.jp/common/001126601.pdf![]() )。
)。
4.コロナ禍前の訪日外国人旅行者の増加の背景
コロナ禍前に顕著に増加したインバウンドの背景について、内閣府では36か国・地域の訪日外国人旅行者数のデータからその変化の要因を分析している(第II-2-3-7表)。その分析結果によると、出発国の経済成長と為替レートが訪日外国人者数の増加に大きな影響を与えたとし、さらにビザの緩和措置や、LCCの就航便増加の寄与も高いことが分かった。
第Ⅱ-2-3-7表 訪日外国人旅行者数の増加要因
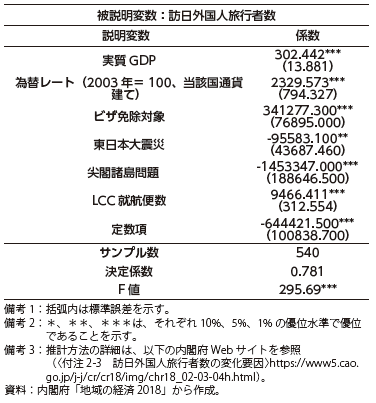
仔細に見ていくと、実質GDPについては、インバウンドの主体となっている東アジアが高い経済成長を遂げたことで、国民の経済的な豊かさが向上し、訪日人数の増加につながった(第II-2-3-8図(左))。為替レートについては、対円名目為替レートでみた円安傾向が訪日人数の増加に寄与していた(第II-2-3-8図(右))。ビザ免除対象については、日本国内の治安への十分な配慮を前提としつつ、訪日外国人旅行者増加に大きな効果が見込まれる国・地域を対象に要件の緩和が進められた(第II-2-3-9表)。ビザ緩和は、具体的な緩和内容だけではなく、我が国が相手国と活発な人的交流を歓迎しているメッセージとなり、旅行者、旅行業界にとっては訪日に対する安心材料になるという側面もある。
第Ⅱ-2-3-8図 東アジア主要国・地域の実質GDP と為替レートの推移
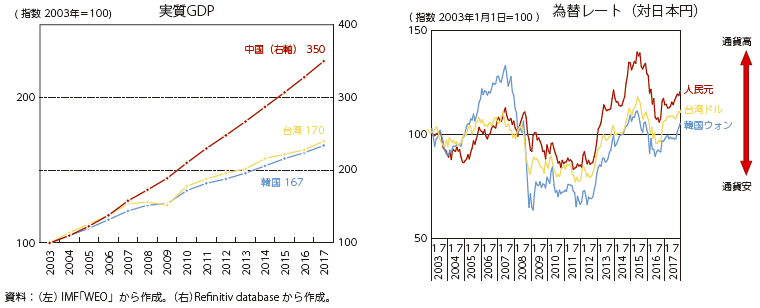
第Ⅱ-2-3-9表 訪日旅行客向けの主なビザの緩和状況
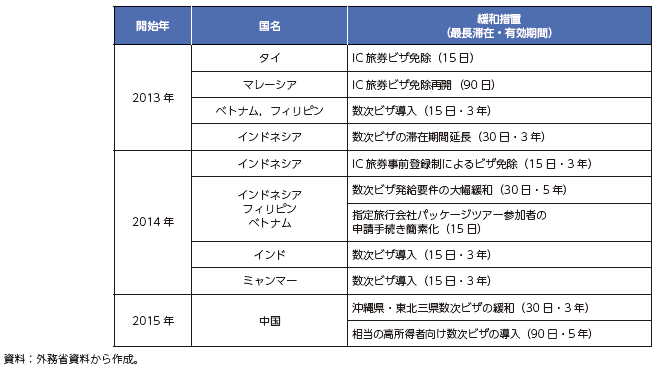
5.為替レートの変動がインバウンド消費に与える影響
為替レートの円安傾向は、前述した訪日外国人者数の増加とともに、インバウンド消費(訪日外国人旅行消費)にもプラスの影響を与えた。
2010年からの為替レート(日本円/米ドル)の変動を振り返ると、2012年にかけて1ドル当たり90円台から80円前後まで円高方向に推移した後、2013年末にかけて100円台へと円安方向に進んだ。その後さらに加速し2014年後半~2015年には120円前後で推移した(第II-2-3-10図)。
第Ⅱ-2-3-10図 為替レートと訪日外国人旅行者数の推移(2010年1月~2023年3月)
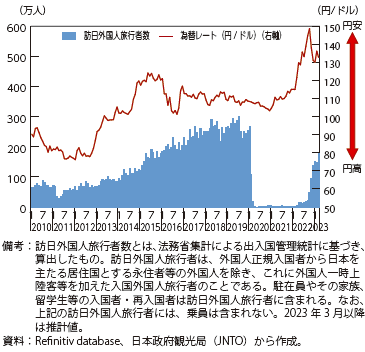
第II-2-3-11図は、訪日外国人旅行者一人当たりの旅行支出額と、前年増減率を示している。2013年に13.7万円となった支出額は、2014年には15.1万円(伸び率+10.6%)、2015年には17.6万円(同+16.5%)と、2015年にかけて2桁台の伸びを示した。このように、2012年から2015年にかけての円安方向への動きに伴い、自国通貨ベースでの負担額が減り、日本での滞在や買物が割安となったことで消費が増加したことが示唆される。その翌年(2016年)には、中国経済の減速や原油価格の大幅下落等を背景に円高基調に転じ、旅行支出額は15.6万円(同-11.5%)と減少した。
第Ⅱ-2-3-11図 訪日外国人旅行者一人当たりの旅行支出額と伸び率の推移
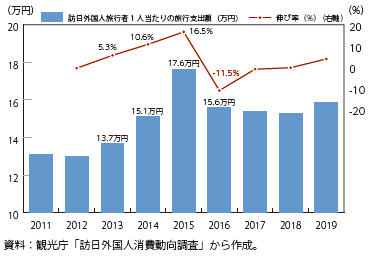
6.インバウンドにおける課題
インバウンドがもたらすのは、経済効果等の正の影響だけではないことにも留意が必要である。特定の地域に過度に観光者が集中すると、居住者の日常生活や自然環境等に悪影響を与える可能性がある。観光地で受忍レベル以上の負の影響が生じている状況は、「オーバーツーリズム」と言われている。日本では、スペインのバルセロナやイタリアのヴェネチアのような深刻な状況に陥っているわけではないが、インバウンドのネガティブな側面も念頭に入れ、人気が過度に集中している観光地を隣接地域へと分散させるなど、持続可能な方法でインバウンドを推進していくことが重要である。
実際、訪日外国人旅行者の日本国内での訪問先は、利便性が良く知名度の高い観光資源が多い大都市圏に集中しており、その他地域への訪問は少ない傾向にある。下図(第II-2-3-12図)は、訪日旅行者の訪問率が高い上位20都道府県を示している。際立って高いのは、東京都、大阪府、千葉県で30%を上回っている。さらに歴史・文化遺産が数多くある京都府・奈良県、第三の都市圏で国際空港もある愛知県が上位となっている。また福岡県は韓国からの訪日者、沖縄県は台湾からの訪日者が多く、地理的に近距離であることも影響する。一方で、その他多くの県(35県)では訪問率が5%を下回り、地域間で訪問率に違いが生じていることが分かる。この訪問地域への偏りを解消し、日本全体へとインバウンド効果を波及させることが課題の一つとなっている。
第Ⅱ-2-3-12図 上位20都道府県の訪日旅行者訪問率(2019年)
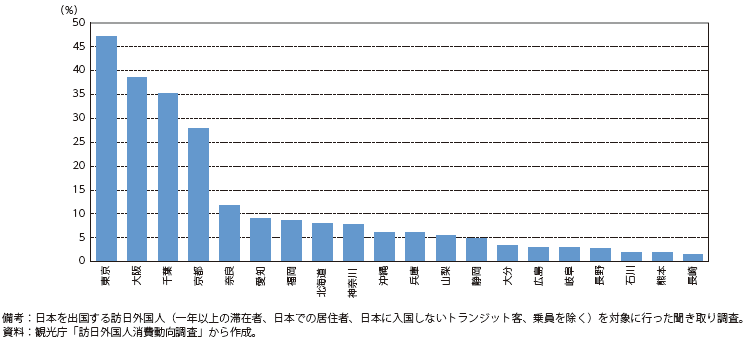
7.今後のインバウンドへの期待
前述したとおり、コロナ禍以前の訪日外国人旅行者数は増加基調となっており、観光立国の実現に向けて着実に前進してきた。下図(第II-2-3-13図)は外国人旅行者受入数ランキング(2019年)であるが、世界全体でみると日本の訪日外国人旅行者数は、世界第12位、アジアの中では中国、タイに次いで第3位に位置している。世界第1位はフランス(約8,900万人)、第2位はスペイン(約8,400万人)、第3位は米国(約7,900万人)、アジアで最も多い中国は第4位(約6,600万人)となり、上位の国々は日本の2倍以上の外国人旅行者が訪問している。世界の海外旅行市場は非常に大きく、日本が世界の海外旅行需要を獲得する余地は十分あると考えられる。
第Ⅱ-2-3-13図 外国人旅行者受入数ランキング(2019年)
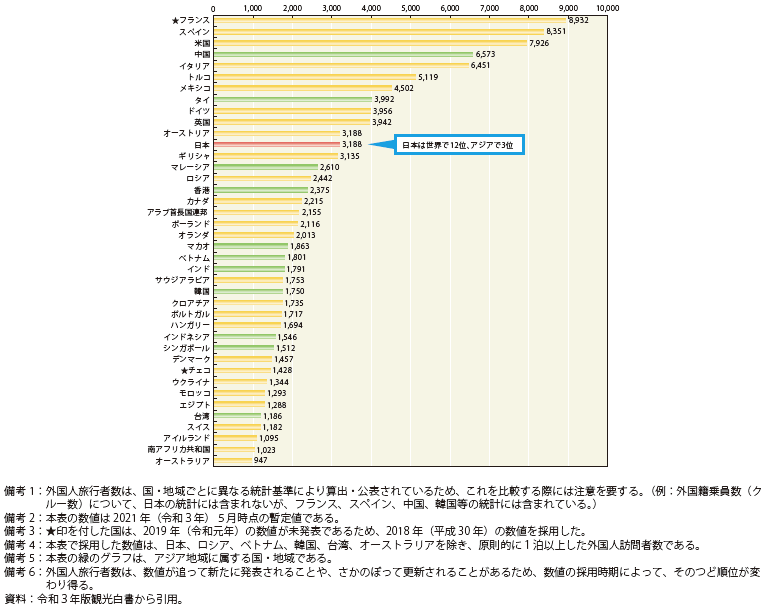
世界の海外旅行需要を獲得するために魅力ある観光資源は欠かせないが、昨年(2022年)5月に世界経済フォーラムで発表された「持続可能な旅行・観光開発力ランキング」において、世界117か国中、日本は総合順位で初の首位を獲得しており、日本は観光地として世界から高く評価されている(第II-2-3-14図)。ランキングを詳しくみると、特に健康・衛生、航空インフラ、文化資源、非レジャー資源の分野で高い評価を得た一方、観光に対する優先順位、価格競争力、環境の持続可能性は改善の余地があることが指摘された。
第Ⅱ-2-3-14図 持続可能な旅行・観光開発力ランキング
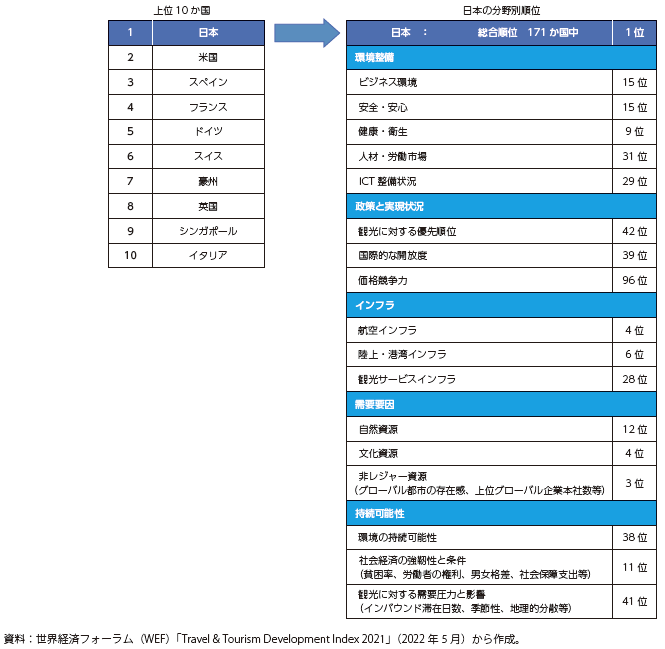
日本の観光が評価される中、インバウンド拡大に向けた動きが加速している。岸田総理大臣は、2022年10月の所信表明演説で「訪日外国人旅行消費額の年間5兆円超の達成を目指す」と、我が国全体でインバウンド需要を獲得していくことを表明している。
2023年3月には前述した「観光立国推進基本計画」が閣議決定されており、「持続可能な観光」、「消費額拡大」、「地方誘客促進」を三つのキーワードとして2023~2025年度の新たな計画が取りまとめられた。具体的な数値目標として、持続可能な観光地域づくりに取り組む地域を2025年までに100地域設置、訪日外国人旅行額単価を20万円/人に(2019年実績:15.9万円)、訪日外国人旅行者一人当たり地方部宿泊数を2泊にする(2019年実績:1.4泊)等が2025年までの目標として掲げられた。2025年には大阪で「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」の開催が予定されており、これを追い風としてインバウンドをさらに拡大させ、日本経済底上げの重要な役割を果たすことが期待されている。