第1節 困難に直面する世界経済秩序
グローバルな構造変化の中で、世界経済は様々な困難に直面しており、再び安定成長の軌道に乗せるための岐路に立たされている。本章では、厳しさを増す国際経済情勢を概観するとともに、こうした中で、各国で輸出・投資管理政策の強化が行われている状況や、積極的な産業政策の展開が貿易に及ぼす影響について見ていく。一方で、グローバル・サウス諸国はアジアを筆頭に経済規模・貿易の双方において存在感を増していくことが見込まれ、こうした国々とも連携しながら、ルールベースの国際経済秩序の維持・強化に取り組むとともに、世界経済の包摂的で持続可能な成長を確保していくことが重要であることを示す。
グローバルな不確実性が増大する中で、WTO上級委員会の機能不全が続いており、さらには経済依存関係を武器化する経済的威圧への懸念も高まるなど、国際経済情勢は依然厳しい状況が続いている。本節では、こうした厳しい国際経済情勢について概観するとともに、こうした状況に対する各国の対応について取り上げる。
1.グローバルな不確実性の増大
まず、不確実性を表す各種指標の動向を見ていく(第II-1-1-1図)。世界の不確実性を表す世界不確実性指数27を見ると、過去数年間、米中間の緊張の高まりや新型コロナウイルス感染症拡大、ロシアによるウクライナ侵略等の影響により急上昇が見られたが、足下ではやや落ち着いている。貿易の不確実性を表す貿易不確実性指数28を見ると、米中貿易摩擦が激化した2018年から2019年にかけて急上昇したが、その後は低下し、2023年に一時上昇を見せたが、足下では落ち着いている。経済政策の不確実性を表す経済政策不確実性指数29を見ると、新型コロナウイルス感染症拡大により急上昇した2020年前半よりは低下したものの、依然として高い水準を維持しており、長期的に上昇傾向が見られる。また、地政学的な不確実性を表す地政学的リスク指数30を見ると、ロシアによるウクライナ侵略の影響により2022年3月に急上昇し、その後徐々に低下していたが、イスラエル・パレスチナ武装勢力間の衝突の影響により2023年10月に再度上昇し、その後高い水準を維持している。
第Ⅱ-1-1-1図 不確実性指数の推移
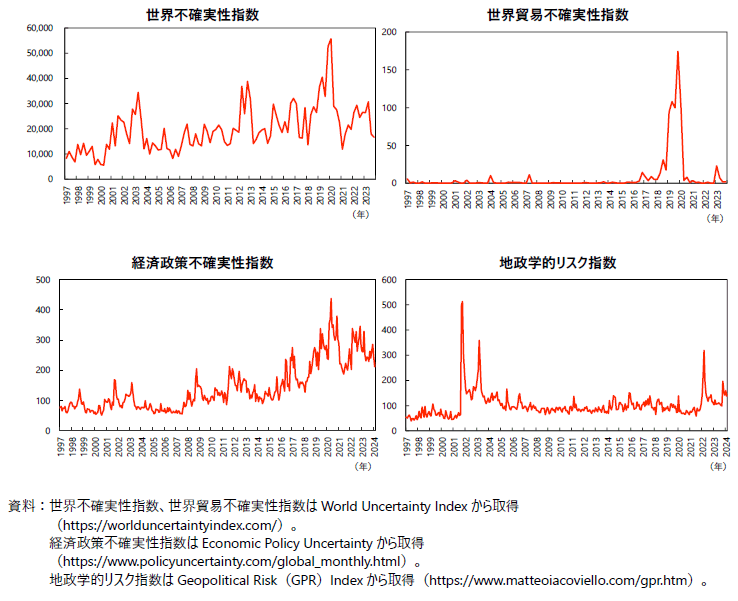
これらの不確実性を表す指数の推移から、世界経済の不確実性は新型コロナウイルス感染症拡大時やロシアによるウクライナ侵略の直後と比較すると低下してはいるものの、いつ不確実性が再び高まるか分からない状況が続いている。
このようにグローバルな不確実性が増大する中で、世界の分断化は、貿易にも影響を及ぼしつつある。例えば、2024年4月に公表されたIMF「WEO」の分析31によれば、豪州、カナダ、EU、ニュージーランド、米国のグループと中国、ロシアのほか、2022年3月2日の国連総会でロシアによるウクライナ侵略に対する非難決議に反対した国のグループの両グループ内(友好国間)、グループ間(友好国でない国同士)での貿易変化率を、ロシアによるウクライナ侵略前後で算出したところ、グループ間の貿易はグループ内の貿易と比べて大きく減少しており、戦略分野の貿易に限って見ると、グループ内の貿易の落ち込みはわずかであったのに対して、グループ間の貿易は大きく減少していることが示されている。
27 英国の定期刊行物「エコノミスト」の調査部門エコノミック・インテリジェンス・ユニットの各国の報告書内における「不確実(uncertain)」及びそれに関連する言葉の割合を計算したもの。数字が大きくなるほど不確実性が高いことを示す。
28 「不確実(uncertain)」及びそれに関連する言葉が貿易に関連する単語の近くで言及された割合を計算したもの。
29 各国の新聞において経済政策の不確実性(Economic Policy Uncertainty)について論じた記事の割合を計算したもの。数字が大きくなるほど政策不確実性が高いことを示す。
30 新聞の記事内において、地政学的事象に関連する記事の割合を計算したもの。戦争の脅威、平和への脅威、軍備増強、核の脅威、テロの脅威、戦争の開始、戦争の拡大、テロ行為、の八つのカテゴリーからなる。数字が大きくなるほど地政学的リスクが高いことを示す。
31 詳細は、IMF「WEO(2024年4月見通し)」のChapter1 Box1.1を参照
(https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024![]() )。
)。
2.WTOが抱える課題
続いて、現在世界が抱える通商課題について見ていく。多角的貿易体制の根幹として機能してきたWTOは、2019年12月以降、紛争処理を担う上級委員会が委員任期満了や退任により機能しない状態に陥っている。WTOの紛争解決制度の年間利用件数は、機能停止前の半分以下に減少(毎年平均で約 20件程度から、2021年は9件、2022年は8件、2023年は6件)している(第II-1-1-2図)。また、上級委員会の不在が長期化する中、上訴することで紛争案件を事実上の塩漬け状態とする「空上訴」が既に24件積み重なっている(2023年12月時点)。
第Ⅱ-1-1-2図 WTO紛争解決制度の利用件数
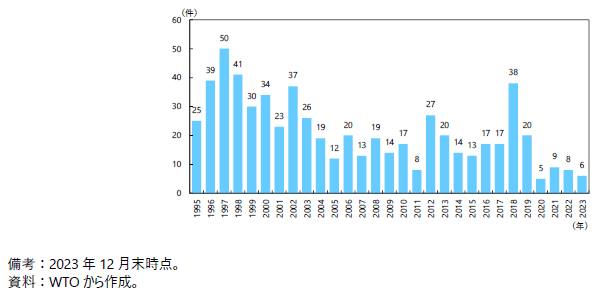
こうした中、WTO加盟国は、2022年6月に開催された第12回閣僚会議(MC12)において、「2024年までに全ての加盟国が利用できる完全なかつよく機能する紛争解決制度の実現を目的として議論を行うこと」に合意し、2024年2月に開催された第13回閣僚会議(MC13)では、MC12における合意を再確認し、これまでに既になされた進捗を今後の議論の土台とした上で、目標達成に向けた議論を加速させることに合意した。
また、2020年4月、一部のWTO加盟国が、上級委員会が機能停止する中での暫定的な対応として、多数国間暫定上訴仲裁アレンジメント(Multi-party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA))を立ち上げた。MPIAは、上級委員会が完全に機能するまでの間に限り、パネルの判断を不服とする場合には、機能停止中の上級委員会に上訴するのではなく、仲裁により解決することを定める紳士協定であり、日本も、2023年3月に参加した(日本を含め53か国・地域が参加)。
3.経済的威圧
近年、経済的威圧(economic coercion)と呼ばれる行為が多発しているとされている32。経済的威圧には国際的に定まった定義はないが、例えばEU の反威圧措置(ACI:Anti Coercion Instrument)規則では、第三国が、EU又はEU加盟国による特定の行動を妨げ、又はその中止、修正若しくは採択を得るため、貿易・投資に影響を与える措置を適用し、又は適用すると威嚇し、それによりEU又はEU加盟国の正当な主権的選択に干渉する行為がある場合、「経済的威圧」が存在すると規定している。また、米国の経済的威圧対抗法案(2023年2月米国連邦議会上院に提出)は、「経済的損害や政治的主権に影響を与える目的の下、貿易・対外支援・投資を、非対称・恣意的・不透明な方法で規制・妨害する敵国の行為・措置やその脅し」を経済的威圧と定義している。経済的威圧は新たに生まれた概念では必ずしもなく、貿易措置等の執行やそれらを執行するという脅しにより、他国の政策決定に影響を及ぼそうとする行為への懸念は、貿易措置の武器化等として従前から認識されてきた33。近年グローバル化が進展し、サプライチェーンの相互依存が深化する中で、大規模な政策支援や経済的威圧を可能ならしめる巨大なマーケットパワー、国家統制を組み合わせることで、サプライチェーンや市場が一部の国に過剰に依存する構造が生まれつつあり、そうした状況が経済的威圧につながっていると考えられる。
経済的威圧に対し、同盟国・同志国はG7首脳声明等で懸念を表明し、その対応に向けて連携を強化している。2023年5月のG7 広島サミットにおいて「経済的強靱性及び経済安全保障に関するG7首脳声明」が発出され、経済的威圧に対する共同の評価、準備、抑止及び対応を強化するため、「経済的威圧に対する調整プラットフォーム」を立ち上げ、連携を強化していくとともに、G7 以外のパートナーとの協力を更に促進していくとした。同年10月のG7貿易大臣会合でも、経済的威圧に対処するため共同の取組を継続していくことや、経済的威圧に対する企業の備えを強化するための取組を強化することが確認された(第II-1-1-3表)。
第Ⅱ-1-1-3表 経済的威圧に言及した主な会談等の概要(2022年以降)
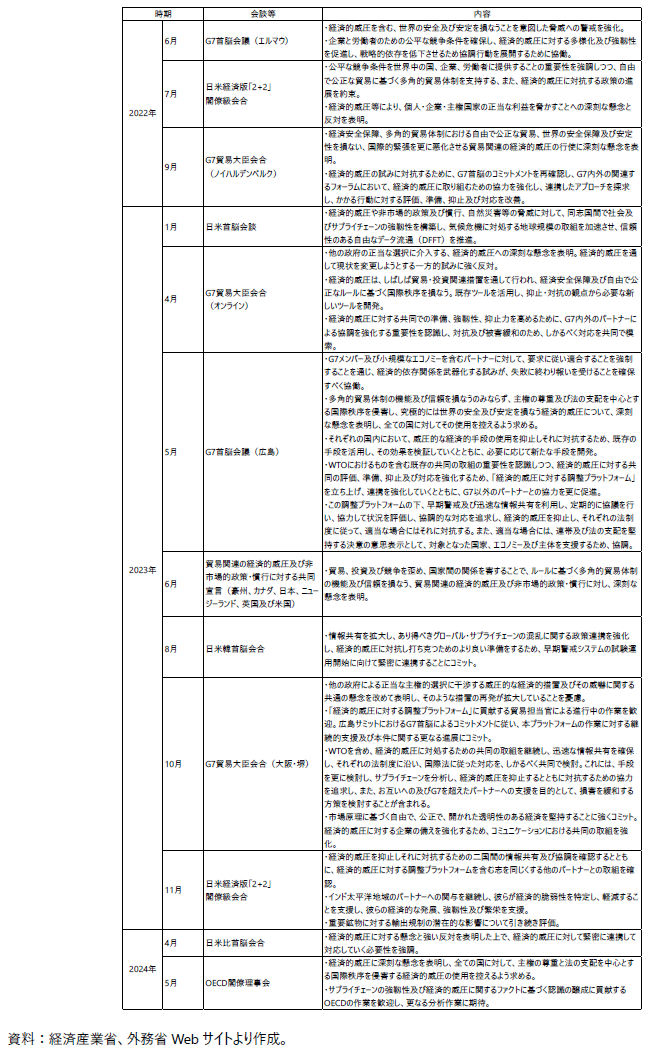
経済的威圧目的が疑われる措置に対して、二国間で当該措置の撤廃・改善を求めるほか、WTOでの紛争解決手続要請といった対応が行われている。加えて、一部の国は経済的威圧に対応・対抗すべく関連法制度や戦略の整備・策定を進めている。EUでは、2021年12月に欧州委員会がEU又は加盟国に対し経済的威圧を行う非EU諸国に対して、最終的な手段として貿易・投資等に制限を課す対抗措置をとることを可能にする反経済的威圧措置(ACI: Anti Coercion Instrument)法案を公表し、欧州議会及びEU 理事会での可決を経て、2023年12月に発効した34。同規則は、第三国の一方的な威圧的措置を抑止することを目的としており、第一段階としては対話を通じて措置の解消を目指し、対抗措置は最終手段とすることが想定されている。対抗措置としては、関税の引上げ、輸出入の制限、サービスや公共調達、直接投資の分野での制限などが含まれる。
米国では、2023年2月に経済的威圧対抗法案 (Countering Economic Coercion Act) が連邦議会上院に提出された。同法案は経済的威圧を受けた同盟国・パートナー国への経済支援、威圧を実施した国等への対応措置を規定する内容となっている。
我が国では、経済産業省が2023年10月に発表した「経済安全保障に係る産業・技術基盤強化アクションプラン」35において、平時においては、強靱なサプライチェーンの実現を通じ、一部の国への過剰依存の解消を、経済的威圧を受けた時は、威圧被害企業への救済を図るとともに、JETRO・NEXI 等の支援を強化するなど、いずれの場合にも必要な具体的措置を国際法に沿った形で適切に検討することを示した。
また、国際機関等においては、経済的威圧に関する分析も行われている。例えば、経済的威圧の貿易に対する影響を分析したOECD(2024年5月公表)のレポート36では、経済的威圧を特定ないし影響を評価することは困難であるが、過去事例における貿易データの分析を通して、被威圧国にとって重要な産品の輸出入量が威圧国との関係でのみ突然減少する等、共通のパターンが見いだされた。また、経済的威圧が、輸出入先や輸出量の変化、物価の変動などを通じて、被威圧国に経済的損失をもたらしていることも明らかになった。一方で、被威圧国が代替市場や代替供給者を見つけることで威圧の影響を緩和した例もあり、開かれた国際市場が有用であることが確認された。さらに、経済的威圧に対処する上で紛争解決制度を含むルールに基づく貿易システムとWTOが活用されていることや、経済的威圧を抑止し被威圧国を支援する上で国際協力が重要であることが指摘されている。
32 豪州戦略政策研究所(ASPI)のレポートによると、2020年から2022年の間に確認された中国による経済的威圧事案(サイバー攻撃含む)は73件にのぼる。Fergus Hunter, Daria Impiombato, Yvonne Lau and Adam Triggs with Albert Zhang and Urmika Deb (2023) , “Countering China’ s coercive diplomacy: prioritising economic security, sovereignty and the rules-based order”, Policy Brief Report No. 68/2023, ASPI参照(https://www.aspi.org.au/index.php/report/countering-chinas-coercive-diplomacy![]() )。Mercator Institute for China Studies(MERICS)のレポートによると、2010年2月から2022年3月の間に確認された中国による経済的威圧事案は、123件にのぼる。Aya Adachi, Alexander Brown, Max J. Zenglein (2022), “Fasten your seatbelts: How to manage China’s economic coercion”, Mercator Institute for China Studies参照(https://merics.org/en/report/fasten-your-seatbelts-how-manage-chinas-economic-coercion
)。Mercator Institute for China Studies(MERICS)のレポートによると、2010年2月から2022年3月の間に確認された中国による経済的威圧事案は、123件にのぼる。Aya Adachi, Alexander Brown, Max J. Zenglein (2022), “Fasten your seatbelts: How to manage China’s economic coercion”, Mercator Institute for China Studies参照(https://merics.org/en/report/fasten-your-seatbelts-how-manage-chinas-economic-coercion![]() )。
)。
33 経済産業省(2023)『不公正貿易報告書』参照(https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/3_dispute_settlement/32_wto_rules_and_compliance_report/322_past_columns/2023_03.pdf![]() )。
)。
34 欧州委員会Webサイト参照(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6804![]() )。
)。
35 経済産業省「経済安全保障に係る産業・技術基盤強化アクションプラン(10/31時点版)」(https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/231031actionplan.pdf![]() )
)
36 OECD「Trade impacts of economic coercion」(https://www.oecd.org/publications/trade-impacts-of-economic-coercion-d4ab39b9-en.htm![]() )
)