第4節 世界経済及び貿易構造の中長期的な展望と新興国・発展途上国との連携強化及び共創の実現
我が国が通商政策の方向性を検討する際、中長期的視点に立った世界経済及び貿易構造に対して、一定程度の予見性を確保しておくことは重要であるが、そこには多くの不確実性が伴うため、その動向を正確に予測することは困難である。しかし、これまで蓄積されてきた経済成長のメカニズムに対する理論・実証双方の研究成果を踏まえながら、一定の条件の下で中長期的な世界経済の成長やそれに伴う貿易構造変化の合理的予測を示すことは可能であり、こうした試みは世界経済及び貿易構造の変容をもたらす根源的な要因の一部を理解することにもつながる。
本節では、これまで蓄積されてきた経済成長のメカニズムに対する理論・実証双方の研究成果を踏まえながら、一定の条件の下で中長期的な世界経済の成長やそれに伴う貿易構造変化の合理的予測を示す。また、これを変化させ得る外生的要因として、ガバナンス、対外開放度、イノベーションの三つの要因に着目し、これらを高める支援を行うことを通じて、新興国・発展途上国の経済成長を後押しし、連携強化と共創の実現を図っていくことの重要性を指摘する。
1.中長期的な経済成長及び貿易構造変化の推計方法
まず、本項では、今後約50年間における中長期的な世界経済の成長及びそれに伴う貿易・投資構造の変化について、経済学における基本的な理論モデルの考え方に基づいた推計方法について解説する。
世界経済の動向の予測に当たっては、まず、各国の名目GDPを一人当たり名目GDP(一人当たりGDP)と人口に分けて考える。そして、人口については国連のWorld Population Prospectsの中位推計を、一人当たりGDPについては条件付き収束の考え方に基づいた経済成長モデルにより推計した収束経路を用いることで、各国の中長期的なGDPの成長経路の推計を行う。ここで、条件付き収束とは、経済の状態の類似した国の間では、各国の所得水準である一人当たりGDPの水準の小さい国ほど成長率が高く、水準の大きい国ほど成長率が低いという傾向が見られることから、一人当たりGDPはある一つの水準へと収束していくという仮説のことをいう。
なお、こうした仮説の背景にはマクロ経済学における代表的な経済成長理論であるソロー・モデルという考え方がある。ソロー・モデルでは、一人当たりGDPは一人当たり資本ストックの関数であり、資本の投資効率は徐々に低下することから、追加的な一人当たり資本ストック1単位の増加によりもたらされる一人当たりGDPの増加分である、資本の限界生産性は逓減すると仮定98する。この仮定により、一人当たり資本ストックが小さい経済では資本の限界生産性が大きいため資本投資が多く99、一人当たりGDP成長率は高くなるが、時間経過とともに一人当たり資本ストックが大きくなるにつれて、資本の限界生産性が逓減することから資本投資が減少し、一人当たりGDP成長率が低くなる。そして、やがて資本の限界生産性はゼロとなり、追加的な資本投資により一人当たりGDPが増加しないことから、経済は一人当たり資本ストックがそれ以上増加せず一定となる状態である、定常状態へと収束していくと考えられている100。これら一連の考え方の概念図が第II-1-4-1図である。こうしたソロー・モデルの考え方を踏まえて、全ての国の一人当たりGDPはある一つの定常状態に収束するという絶対的収束仮説と、各国の経済的条件によって定常状態や収束の様子は異なるという条件付き収束仮説が考察されてきたが、塚田(2017)101などによると、これまでの実証研究においては条件付き収束仮説の妥当性が広く認められているとされている。このため、本節においても条件付き収束仮説に基づいて一人当たりGDPの収束経路の推計を試みることとする。
第Ⅱ-1-4-1図 ソロー・モデルの基本的な考え方(概念図)
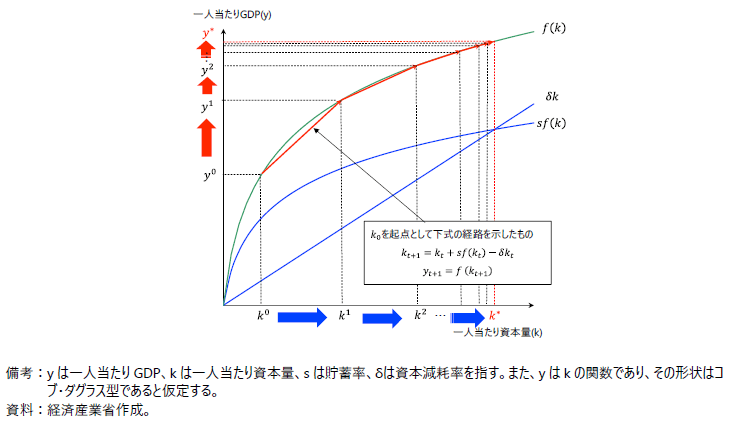
一人当たりGDPの収束経路の推計に当たり、まず、Phillips et al. (2007)102の提唱したクラスタリング手法を用いて、各国を条件付き収束のパターンごとの集合である「クラブ」へと分類する。同手法は、観察された一人当たりGDPの変動からその収束経路を特定し、経路が類似した国ごとの集合(クラブ)に各国を分類することで、サンプル内で観察される条件付き収束のパターンの数を特定103するものである。本項で分析に用いた1995年から2022年の172か国の購買力平価ベースの一人当たりGDPのデータ104に同手法を適用したところ、172か国は8つのクラブへと分類され、同データにおいては8つの条件付き収束のパターンが見られることが示唆された。次に、Acemoglu(2009)105などの手法に基づき、クラブごとの条件付き収束のパターンを考慮した上で一人当たりGDP成長率の推計を行う。具体的には、クラブごとの収束速度や定常状態の違い及び、各年固有の要因による影響を制御した上で、1期前の一人当たりGDPの水準や成長率を用いて、当期の一人当たりGDP成長率の推計を行う。同モデルにおいて、1期前の一人当たりGDPの水準が大きいほど当期の一人当たりGDPの成長率が低いという負の関係が確認された場合、クラブごとに条件付き収束が成立していると解釈することができる。そして、モデルに基づいて2023年から2075年の期間の成長率を推計し、成長率の推計結果を用いて同期間の一人当たりGDPの水準を推計(推計や試算の方法の詳細は付注1.1を参照)した。また、試算された一人当たりGDPの水準と国連のWorld Population Prospectsの人口の中位推計を用いて、同期間の購買力平価ベースのGDPを推計した。
上記の推計を行ったところ、前期の一人当たりGDPの水準が大きいほど当期の一人当たりGDP成長率が低いという傾向があることが観察され、クラブごとに条件付き収束が成立することが確認された。また、推計結果について、横軸にt年(tは1997年、2022年、2047年のいずれかとする。)の各国の一人当たりGDP水準、縦軸にt+25年の各国の一人当たりGDP水準(推計値を含む)をプロットし、8つのクラブごとの収束の傾向線を図示したものが第II-1-4-2図である。第II-1-4-2図を見ると、クラブごとでは、t期の一人当たりGDPの水準が大きいほど25期後の一人当たりGDPの増加分が小さいという傾向が確認され、条件付き収束の仮説とも整合的な推計結果が得られていることが分かる。一方で、第II-1-4-2図からは、条件付き収束における収束速度や収束先の水準はクラブごとに大きく異なっており、経済成長の収束に対して各国の経済的条件が与える影響が顕著に大きいことが示唆される。
第Ⅱ-1-4-2図 条件付き収束の推計結果
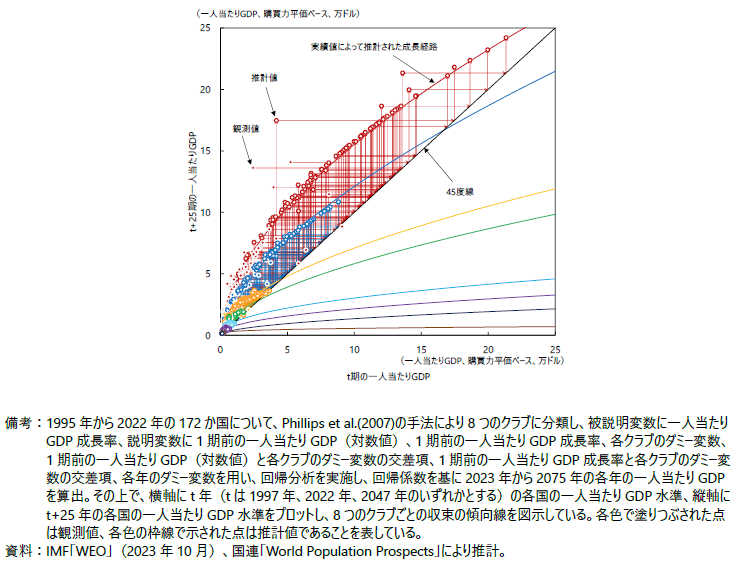
また、貿易及び投資構造の推計においては、二国間の貿易量(及び投資量)は輸出国(出資国)及び輸入国(投資先国)のGDPが大きいほど大きく、二国間の距離が大きいほど小さくなるという重力モデルの理論106の考え方に基づき、各二国間の輸出量及び、日本から各国への直接投資量107の推計を行う。そして、推計されたモデルに2075年時点のGDPの推計値を代入し、GDPの増加による各二国間の輸出量の変化について推計を行う(推計の詳細は付注1.2及び付注1.3を参照)。貿易については2010年~2019年、約170か国の二国間の輸出量のデータを、投資については、その代理変数として日本企業の各国・業種ごとの海外現地法人の数108を用い、2012年~2019年の16業種(製造業及び卸・小売業)の105か国への進出企業数を分析対象とし、それぞれ各輸出国(投資元国)、輸入国(投資先国)や二国間関係、各年、各業種(投資のみ)に固有の要因の制御を行った上で、ポワソン疑似最尤法を用いて推計を行う。推計の結果、輸出量については、輸出国のGDP、輸入国のGDPともに、その水準が大きいほど二国間の輸出量は大きくなるという傾向や、輸出国のGDPの水準の大きさが輸出量に与える影響の方が輸入国のGDPの水準の大きさが輸出量に与える影響と比較して相対的に大きいという傾向が確認された(付注1.2)。また投資量については、投資先国のGDPが大きいほど進出企業数は多くなるという傾向が確認された(付注1.3)。
98 一人当たりGDPがコブ・ダグラス型の生産関数に従うと仮定することで、限界生産性逓減の仮定が成立する。
99 より正確には、各期の一人当たり資本ストック投資量は、前期の一人当たりGDP(前期の一人当たり資本ストックの関数)のうち貯蓄に回る部分から、資本減耗分を引いた値と仮定される。なお、基本的なソロー・モデルにおいては、貯蓄率及び資本減耗率は一定とされる。
100 「ソロー・モデルの更なる詳細な議論は、Acemoglu , Daron(2009) “Introduction to Modern Economic Growth” , Princeton University Pressや、齋藤誠、岩本康志、太田聰一、柴田章久「マクロ経済学〔新版〕」、有斐閣などを参照のこと。
101 塚田和也(2017)「中所得国の経済成長とキャッチアップ」(https://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Analysis/2017/ISQ201710_001.html![]() )(2023年3月27日閲覧)
)(2023年3月27日閲覧)
102 Phillips, Peter, and Donggyu Sul (2007) "Modeling and Econometric Convergence Tests", Econometrica, Vol 75(6).
103 本手法はクラスタリングの際に1変数のみを使用し、クラスター数は統計学的な判断基準を用いて決定されるアルゴリズムであることから、分類に使用する変数やクラスター数の選定における恣意性が排除できるという点で優れている。
104 一人当たりGDPは、IMF「WEO」の購買力平価ベースのGDPを国連のWorld Population Prospectsの人口で除したものに、ホドリック・プレスコットフィルターをかけた数値を用いている。。
105 「Acemoglu, Daron(2009)”Introduction to Modern Economic Growth”,Princeton University Press
106 重力モデルについての詳細はRIETI「国際貿易と貿易政策研究メモ 第13回「重力方程式」」(https://www.rieti.go.jp/users/tanaka-ayumu/serial/013.html![]() (2024年3月27日閲覧)等を参照のこと
。
(2024年3月27日閲覧)等を参照のこと
。
107 二国間の投資量については網羅的なデータが存在しないことから、日本から各国への対外直接投資のみを分析対象とする。
108 経済産業省「海外事業活動基本調査」を用いて算出。
2.地域別にみた中長期の経済成長
本項では、上述のモデルに基づいて推計した各国のGDP、貿易量及び我が国企業の海外進出企業数についての推計結果を地域109単位ごとに集計し、それらの地域ごとの中長期的な変化について見ていく。まず、第II-1-4-3図は、本推計によって得られた地域ごとのGDPの中長期的な変化を示したものである。アジアでは、ほかの地域を大きく上回る経済成長の経路を辿ることが示されており、世界経済に占めるアジアのシェアが上昇していくことを示している。欧州と北米では、アジアと比較すると緩やかではあるものの、比較的高い経済成長の経路を辿ることが示されている。なお、欧州及び北米の経済成長の動き方は類似しているものの、中長期的にも欧州の経済規模が北米をやや上回るという状態が継続することが分かる。中南米と中東では、欧州や北米と比較して更に緩やかな経済成長の経路を辿ることが示されており、両地域の経済成長の辿る経路は水準・変化ともに類似している。アフリカでは、推計初期時点のGDP規模に鑑みれば、高い経済成長の経路を辿ることが示されており、中南米や中東の経済規模を上回り、アジア、欧州、北米に次ぐ規模となることが示されている。大洋州では、緩やかな経済成長の経路を辿ることが示されているが、その水準はほかの地域と比べて小さいものとなっている。これらの結果は、今後の世界経済におけるアジアの存在感の高まりや、アフリカの成長のポテンシャルの大きさ、欧州や北米の経済成長の持続性を示唆するものである。中でも、グローバル・サウスと呼ばれる国々では今後大きく成長することが見込まれており、例えば、アジア地域では、インド、インドネシア、バングラデシュ、ベトナム、パキスタンで、中南米地域では、ブラジル、アルゼンチン、コロンビアで、中東地域では、トルコ、サウジアラビアで、アフリカ地域では、エジプト、ナイジェリアで特に大きな成長が見込まれている。
第Ⅱ-1-4-3図 地域ごとのGDP(PPPベース・合計値)の推移
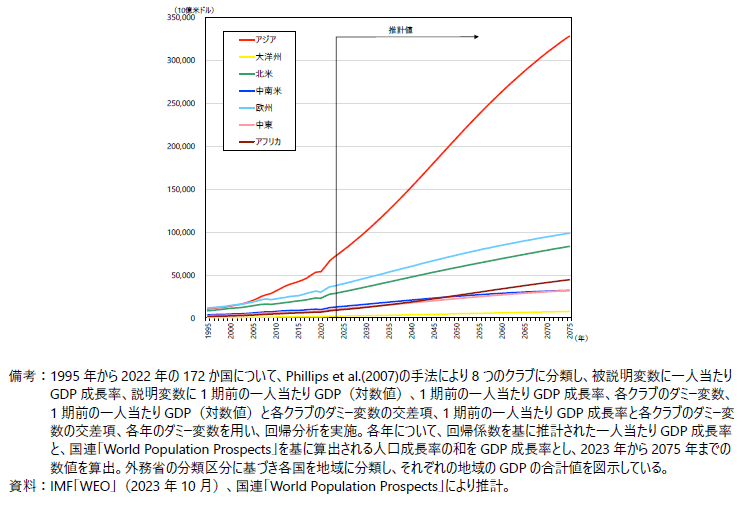
次に、各地域が辿る経済成長の経路の性質をより具体的に理解するため、GDPを一人当たりGDPと人口に要因分解し、各地域の経済成長に対して一人当たりGDPの成長と人口の成長がそれぞれ与える影響の大きさを見たものが第II-1-4-4図である。これを見ると、アジアやアフリカでは、一人当たりGDPの成長と人口の成長の双方が経済成長を牽引していることが分かる。北米、欧州、中南米、中東では、人口の成長は緩やかであり、一人当たりGDPの成長が牽引する経済成長であることが分かる。なお、一人当たりGDPの成長には地域間で差があり、これらの4地域間では、北米や欧州は相対的に高く、中東や中南米は相対的に低いことが分かる。大洋州は、経済規模は相対的に小さいものの、一人当たりGDPと人口の双方が牽引する安定した経済成長となっている。これらの結果から、アジアやアフリカの急速な経済成長は、一人当たりGDPの伸びもさることながら、大きな人口の増加によってもたらされること、また、北米や欧州などのように、人口の成長の緩やかな地域においても、一人当たりGDPの伸びにより、比較的高い経済成長を維持することができることが示唆される。
第Ⅱ-1-4-4図 地域ごとのGDPの要因分解
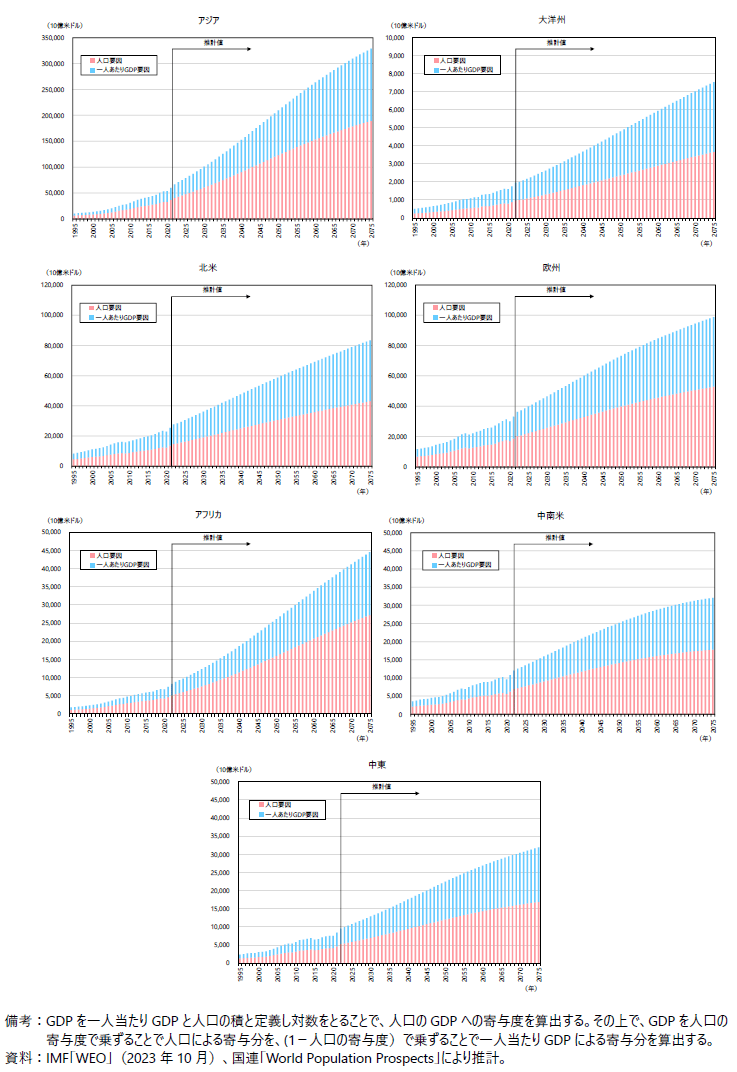
109 各国の地域への分類に当たっては、外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html![]() )を参照。
)を参照。
3. 中長期的な世界経済の成長が貿易構造に及ぼす影響
本項では、第1項において説明したモデルを用いた二国間の貿易量の推計結果について、輸出国側、輸入国側それぞれを地域ごとにまとめた上で、各地域から各地域への輸出額と、中長期的な輸出の変化額の推計値、すなわち、ほかの条件を一定として、各地域の経済成長に伴い生じた貿易構造の変化について図示したものが第II-1-4-5図である。同図の外側の円は、各地域の貿易及びその変化額が全体の貿易額及び変化額に占める割合を表している。また、円内の線はそれぞれ各地域から各地域への輸出額及びその変化額を示しており、各線は、その色で示された地域から矢印の方向への輸出額及びその変化額を表している。
第Ⅱ-1-4-5図 中長期的な世界経済の成長が貿易構造に及ぼす影響
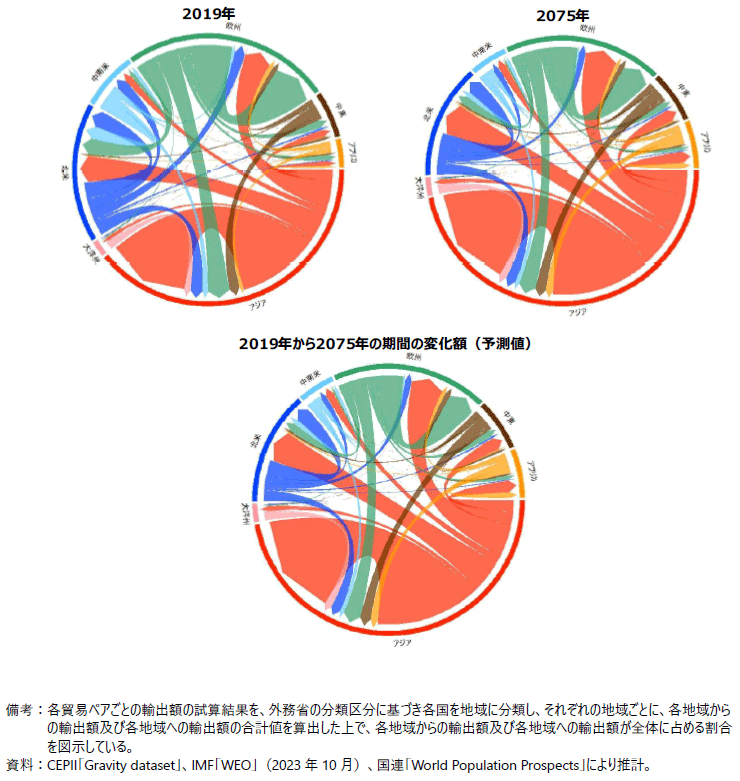
まず、最も大きな経済規模になるとの予測が示されているアジアを中心とした貿易に着目すると、2019年から2075年の期間の変化額では、世界全体の貿易の増加のうち、輸出先及び輸入先がアジアである貿易が占める割合が顕著に大きいことが分かる。特にアジアの貿易においては、輸出額の増加の大きさが顕著であり、全ての地域において、各地域からの輸入の増加額のうち、アジアからの輸入の増加額が最も大きいことが分かる。そして、2075年には、全ての地域で、輸入に占めるアジアからの輸入のシェアが最も大きくなることが示されている。なお、世界全体の貿易に占める各地域の割合の変化について見ると、アジアの割合が大きく増加し、アフリカは、規模は小さいものの、一定程度割合の増加が見られる一方で、北米、欧州、中南米の占める割合が低下し、大洋州や中東では、その割合には大きな変化が見られないことが分かる。
次に、域内貿易・域外貿易に着目すると、2019年から2075年の期間の変化額では、経済規模の大きな地域では同一地域内での貿易の割合が大きく、経済規模の比較的小さい地域では、経済規模の大きな近隣地域との貿易の割合が大きいことが分かる。具体的には、欧州、アジア、北米といった、経済規模の大きい地域では、輸入のうち同一地域内からの輸出が占める割合が大きいことや、経済規模の小さい中南米、中東、アフリカ、大洋州では、アジア、北米、欧州といった近隣の経済規模の大きい地域との貿易の割合が大きいという傾向が確認される。
ここまでの結果をまとめれば、中長期的にはアジアを中心とした経済圏・貿易圏の存在感が大きくなり、世界の各地域との結びつきを強めることが示唆される。
4. 中長期的な世界経済の成長を踏まえた我が国企業の海外進出の展望
本項では、中長期的な世界経済の成長が我が国企業の海外進出に及ぼす影響について見ていく。我が国の製造業及び卸・小売業の2019年の海外進出企業数について図示したものが第II-1-4-6図、推計結果に基づいて算出された製造業及び卸・小売業の2075年時点の海外進出企業数の予測値を2019年の海外進出企業数で除した値、すなわち今後の増加倍率の予測値を図示したものが第II-1-4-7図である。まず、第II-1-4-6図より、我が国企業の製造業及び卸・小売業の海外現地法人は、アジアや欧州、北米に多く存在することが分かる。このような観測値から、我が国企業の海外現地法人は、日本との距離が近い国や、経済規模の大きい国・地域に多く存在しており、重力モデルの理論が観測される事実と整合的であることが見てとれる。次に、第II-1-4-7図によると、中長期的に大きな経済成長が見込まれ、2019年から2075年の増加倍率が高いと推計された国はアジアやオセアニア、中東、欧州、北米、中南米など、様々な地域に存在していることが分かる。これらの観測値及び推計結果から、第一に、中長期的な我が国企業の海外進出先として、既に多くの企業が存在しており、かつ増加倍率の予測値が大きいアジアの中所得国の重要性がますます高まることが示唆される。第二に、現在では我が国企業の進出は少ないものの経済規模の拡大が見込まれ、新たな投資先として中長期的に重要となり得る国・地域が各地域に存在していることが示唆される。ただし、本推計結果は、統計上把握可能であり、かつ、既に一定数が海外進出している国・地域の企業数に対する今後の予測を示したものであり、統計上の制約で我が国企業の進出状況が把握できていない国・地域や、現在進出していない国・地域、現在進出しているがその数が少ない国・地域に、今後我が国企業が進出する可能性があることに留意が必要である。
第Ⅱ-1-4-6図 2019年における日本の製造業及び卸・小売業の海外現地法人数
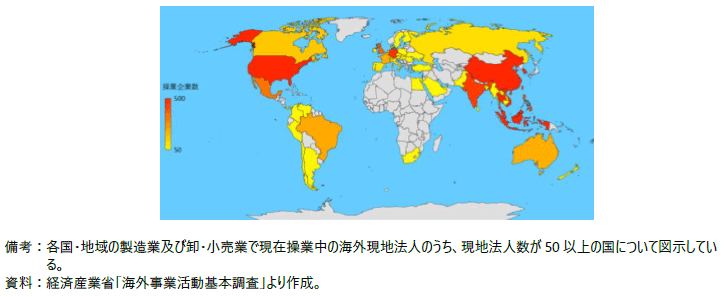
第Ⅱ-1-4-7図 2019年から2075年の期間における日本の海外現地法人数の増加倍率の予測値
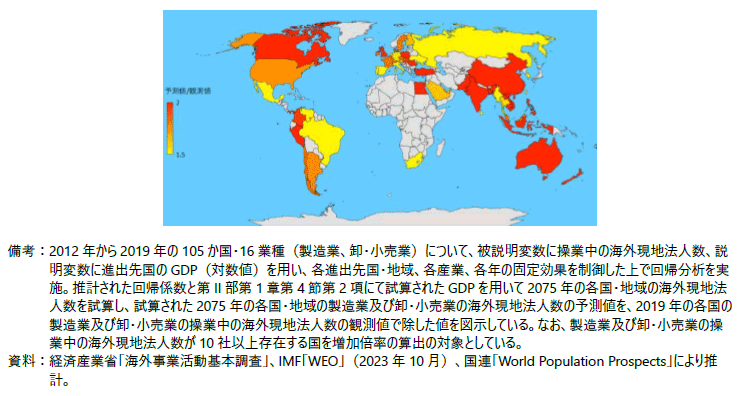
5. 中長期的な経済成長の経路に影響を与え得る外生的要因に関する考察
これまで、中長期的な経済成長の経路は地域ごとに多様であることを確認したが、本項では、所得グループごとのGDPの成長経路の特徴について確認する。
まず、所得グループごとの推移について、足下、2022年の購買力平価ベースの一人当たりGDPが上位25%の国・地域を高所得グループ、下位25%を低所得グループ、それ以外を中所得グループと定義し、所得グループごとの一人当たりGDPの平均値の推移を見る。2022年から2075年までの一人当たりGDPの推計値の平均を見ると、第II-1-4-8図の上段左図のとおり、その水準、増加幅ともに高所得グループ、中所得グループ、低所得グループの順に大きく、今後、全ての所得階層において所得水準の成長トレンドが継続すると同時に、所得階層間の格差も拡大する傾向となることが示された。前述のとおり、GDPは一人当たりGDPと人口の積であると考えると、各グループのGDPは、各グループに属する国の一人当たりGDP(所得水準)の平均値と当該グループの人口の合計の積により概算することができる。よって、この推計結果から、高所得国では所得水準の増加が経済成長に与える影響が大きく、中所得国でも所得水準の増加による経済成長が一定程度見込まれる一方で、低所得国では経済成長に対して、所得水準の増加が与える影響は限定的であることが示唆される。
次に、所得グループごとの人口の推移について見る。第II-1-4-8図の上段右図のとおり、各国・地域の人口を国連のWorld Population Prospectsにおける中位推計の値とし、所得グループごとの合計値を算出すると、2023年から2075年までの期間においては一貫して中所得グループが最も大きいと予測されている。中所得グループでは、当面の間人口増加が見込まれるものの、その増加幅は逓減し、2050年代の約60億人をピークに減少へと転じることが予測されている。高所得グループの人口は、今後大きな伸びは見込まれておらず、人口は2040年代の約12億人をピークに緩やかな減少傾向へと転じ、2075年には11.6億人程度となると予測されている。低所得グループの人口について見ると、継続的に上昇を続ける見通しである。低所得グループの人口は足下の2022年には10億人程度であるが、2020年代には高所得グループの人口を上回り、2075年には30億人にも迫るほどにまで増加する見通しとなっている。これらの結果から、中所得グループは人口が大きいことにより、経済規模も大きいという特徴が観察された。また、今後も人口の増加を通じた経済成長が見込まれるものの、こうした成長が継続するのは2050年代までである可能性が示唆された。高所得グループでは、人口に大きな変化は見られず、人口変化による経済成長は限定的であることが示唆された。また、低所得グループでは、人口増加による経済成長が継続的に見込まれることが示唆された。
第Ⅱ-1-4-8図 所得階層ごとの一人当たりGDP・人口・GDPの推移
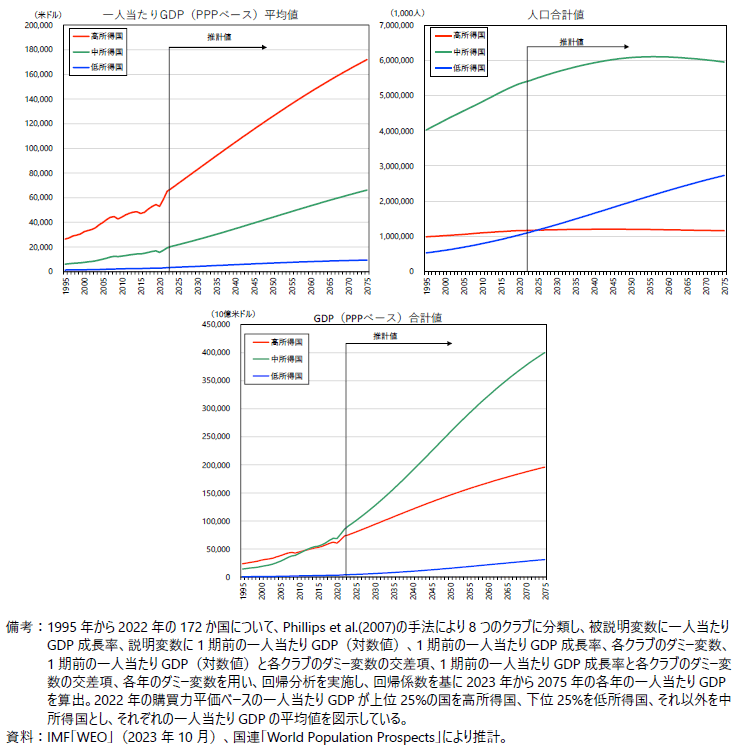
そして、所得グループごとの一人当たりGDPと人口の推移を踏まえ、所得グループごとのGDPの合計の推移を見る。第II-1-4-8図の下段中央図のとおり、中所得グループのGDPの合計は、1995年から2022年の観察値に基づくと、2010年代後半に高所得グループのGDPの合計を上回っていたことが分かる。さらに、中所得グループのGDPの合計は、2023年から2075年の期間においても継続的に高い成長を遂げることが予測された。高所得グループのGDPの合計についても、今後継続的に上昇することが予測されたが、その増加幅は中所得グループと比較すると小さいことから、高所得国と中所得国のGDPの差は今後ますます拡大することが示唆された。また、こうした変化率の違いから、世界経済に占める中所得国の割合が増加し、高所得国の割合は相対的に低下することが示唆された。低所得国のGDPについては、2030年代中盤から成長が加速し、高い成長が続くものの、高所得国と比較するとその増加幅が小さいことから、2023年から2075年の期間においては、高所得国と低所得国のGDPの差は拡大傾向にあることが示唆された。
以上より、所得グループ間の経済成長の経路には大きな差があり、所得グループ間の経済規模の差は今後拡大傾向にあることが示唆された。低所得グループにおいても人口の成長は見込まれていることから、こうした経済規模の格差拡大は、所得水準である一人当たりGDPの成長の差による要因が大きいと考えられる。以降では、一人当たりGDPの成長に影響を与え得る要因について考察し、新興国・発展途上国の更なる成長発展の実現に向けた方策について検討する。
本節でこれまで前提としていたモデルでは、経済成長率を決定する要因として、条件付き収束のみを考慮しており、推計には一人当たりGDPのみを用いていた。一方で、例えばAcemoglu(2009)で説明されているように、これまでの条件付き収束に関する研究においては、条件付き収束以外の経済成長率に影響を与える要因についても考察が行われている。Kremer et al.(2021)110によると、これまでの研究においては、労働力やその質、政治制度、ガバナンスの質、財政政策、金融制度、文化などが一人当たりGDPの成長に影響を与え得る要因と考えられてきている。一人当たりGDPに影響を与える要因を挙げれば枚挙にいとまがないが、本項では、データ制約の関係から対象サンプル数(国・地域数、期間の双方)の確保を優先しつつ、その上で、先行研究にものっとりながら、本質的に重要となり得る指標として、ガバナンス、経済の対外開放、全要素生産性(TFP)成長率が一人当たりGDP成長率に対して与える影響について着目する。具体的な変数として、ガバナンスには、世界銀行のWorldwide Governance Indicators(世界ガバナンス指標)111を用いる。Worldwide Governance Indicators とは、世界銀行が世界各国のガバナンス状況を評価するために作成した指標であり、「国民の発言力と説明責任(Voice and Accountability)」、「政治的安定と暴力の不在 (Political Stability and Absence of Violence)」、「政府の有効性(Government Effectiveness)」、「規制の質(Regulatory Quality)」、「法の支配(Rule of Law)」、「汚職の抑制(Control of Corruption)」の6つの指標が存在する。なお、推計の際、多重共線性の問題が起こり得ることを考慮し、これら6つの指標について主成分分析を実施し、その第一主成分のスコアを算出することで一つの変数に統合している。経済の対外開放度にはSqualli and Wilson (2011) 112により提唱された貿易開放度指標であるCTS(Composite Trade Share)を用いる。CTSとは各国の貿易開放度を「サンプル内の国数」、「当該国が世界の貿易額に占めるシェア」、「当該国の貿易額対 GDP比」の3項目の積と定義113するものである。TFP成長率についてはフローニンゲン大学のPenn World Table 10.01114により作成されたものを用いる。
推計モデルとしては、二つの手法を用いる。まず、一つ目の推計では、Acemoglu(2009)などに基づき、各国ごとの定常状態の違い及び、各年に固有の要因による影響を制御した上で、一人当たりGDPの水準に加えて、世界ガバナンス指標、貿易開放度(CTS)、TFP成長率の変化率が、一人当たりGDP成長率に対して与える影響を検証する(推計の詳細は付注1.4を参照)。なお、これまでのモデルにおいてはクラブごとの条件付き収束を仮定していたが、本推計においてはAcemoglu(2009)にならい、各国ごとに定常状態が異なると仮定して条件付き収束をモデル化している。2010年~2019年の期間における170か国について推計を行った結果、世界ガバナンス指標、貿易開放度(CTS)、TFP成長率のいずれについても、それぞれ第II-1-4-9図のとおり、それらの値が大きいほど、一人当たりGDP成長率が大きいという関係性が確認された。この結果は、一国のガバナンスの向上、対外開放度の上昇、TFP成長率の高まりは、一人当たりGDP成長率を条件付き収束により規定される成長率から更に押し上げる可能性を示唆するものである。
第Ⅱ-1-4-9図 成長因子と一人当たりGDP成長率の関係
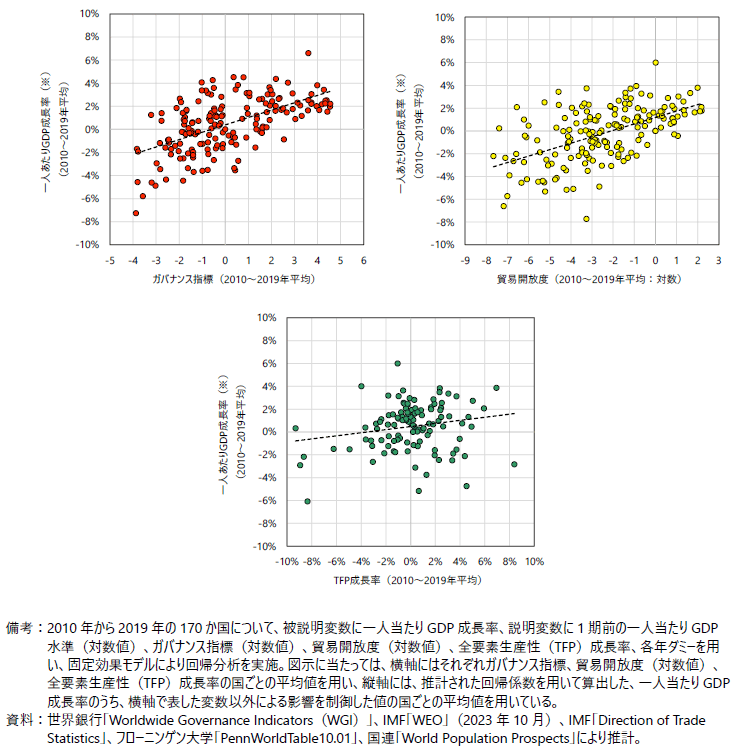
次に、二つ目の推計では、クラブごとの条件付き収束を仮定し、一人当たりGDP水準のみを用いて推計した一人当たりGDP成長率と実際に観測された一人当たりGDP成長率の差(一人当たりGDP水準のみによっては予測できなかった誤差)が、一国のガバナンス、対外開放度、TFP成長率とどの程度関係しているかについて検証を行う。具体的には、まず、1980年~1999年の20年間の142か国の一人当たりGDPのデータにPhillips et al. (2007)の提唱したクラスタリング手法を適用して7つの「クラブ」へ分類した上で、クラブごとの収束速度や定常状態の違い及び各年固有の要因による影響を制御しつつ、1期前の一人当たりGDPの水準や成長率を用いて、当期の一人当たりGDP成長率の推計を行う。次に、推計されたモデルに基づいて2000年から2019年の期間の一人当たりGDP成長率を推計し、同期間に実際に観察された成長率とクラブごとの条件付き収束を仮定したモデルに基づく推計値の差、つまり、同モデルでは予測出来なかった成長の差を算出する。そして、各国、各年に固有の影響を制御した上で、2000年から2019年における観測値と推計値の差と、世界ガバナンス指標、貿易開放度(CTS)、TFP成長率との間の関係性を確認する(推計の詳細は付注1.5を参照)。142か国について上記のとおりの手順で推計を行ったところ、それぞれ第II-1-4-10図のとおり、世界ガバナンス指標、貿易開放度(CTS)、TFP成長率の値が大きいほど、一人当たりGDPの観測値と推計値の差が大きいという傾向が確認された。この結果は、将来観測される一人当たりGDPの成長率は、一国のガバナンスの向上、対外開放度の上昇、TFP成長率の高まりが起こった場合、クラブごとの条件付き収束を仮定したモデルによる推計値から上振れる可能性があることを示唆するものである。
第Ⅱ-1-4-10図 各成長因子と一人当たりGDP成長率の推計誤差の関係
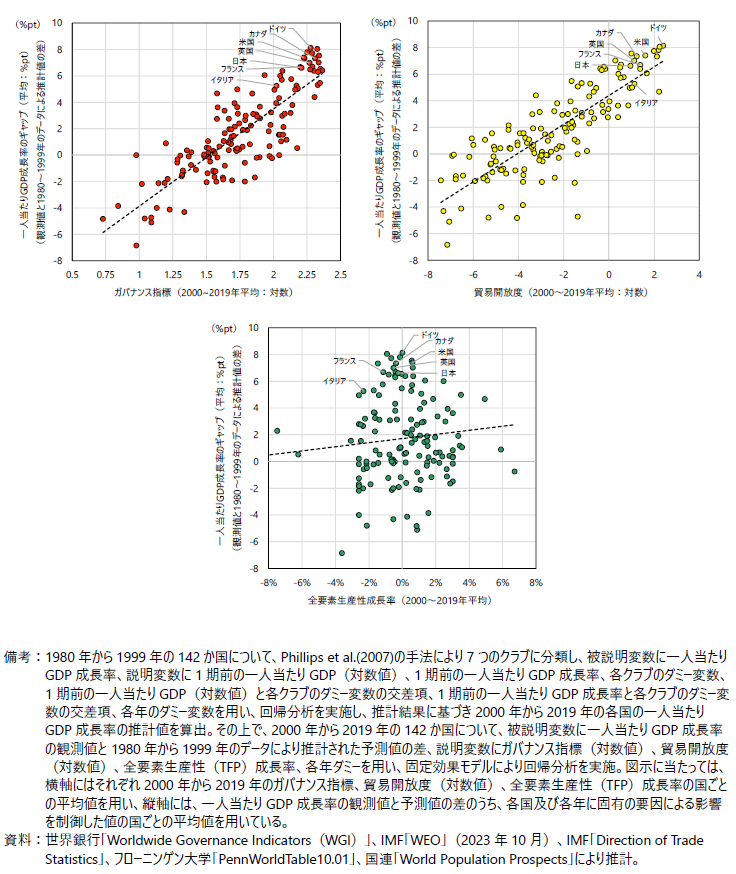
以上より、一国のガバナンスの向上、市場の対外開放度の上昇、TFP成長率の高まりは、一人当たりGDPの成長に資する重要な要因であり、これらの要因により一人当たりGDPは、基本モデルの推計結果を上回る成長を実現し得ること、逆にいえば、これらの要因が現状より後退するようなことがあれば、成長が下振れる可能性があることが示唆された。特に低所得グループのガバナンス、対外開放、イノベーションは、高所得グループや中所得グループと比較すると水準が低く、大幅な改善の余地がある。そのため、我が国を含む先進国には、低所得国それぞれの実情を考慮しつつ、ガバナンスの向上や貿易の開放、TFP成長率の押し上げを支援することを通じて、低所得国の経済発展を支援することが求められる。
本節では、世界経済の中長期的な成長の展望について見てきたが、こうした成長の実現には、地球環境や人権への配慮といった包摂的で持続可能な成長及び発展の確保が大前提となる。次節では、包摂的で持続可能な成長及び発展の確保の必要性について検討していく。
110 Kremer, Michael, Jack Willis, and Yang You (2022) "Converging to Convergence", NBER Macroeconomics Annual, Vol 36.
111 https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators![]() (2024年3月27日閲覧)
(2024年3月27日閲覧)
112 Squalli, Jay, and Wilson, Kenneth(2011) “A New Measure of Trade Openness”, The World Economy, vol.34
113 「例えば、貿易開放度を貿易額の対 GDP 比で測ると小国が上位になりやすくなり、逆に貿易額の世界シェアを用いると経済規模の大きな国が上位になりやすくなるなどの傾向が見られるが、CTS は貿易額対 GDP 比や貿易額の世界シェアの双方の情報を取り込みつつ、経済規模を考慮した上で貿易の開放度を測定しているという点で指標として優れている」(経済産業省「令和5年版通商白書」p.82より引用)と考えられている。
114 https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en![]() (2024年3月27日閲覧)
(2024年3月27日閲覧)