第5節 包摂的で持続可能な成長及び発展の確保
本節では、国境を越えて地球規模で解決すべき課題である気候変動や生物多様性に係る最近の国際的な議論や取組の動向について概観するとともに、人権問題を巡る最近の国際的な議論や取組の動向について概観する。
1.気候変動と生物多様性
2023年7月、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は米国ニューヨークの国連本部の記者会見で、「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来した」と述べた115。そして、同年9月、北半球の夏が記録的な暑さになったことを受け、「気候崩壊が始まった」と危機感を示し、各国の指導者に気候変動対策の加速を強く促した116。
気候変動は、主に気温上昇に起因するものと捉えられがちだが、地球はあらゆるものがつながったシステムで、ある分野での変化がほかのあらゆる分野での変化に影響を及ぼす可能性があり、気温上昇は問題の始まりに過ぎない117と、国連は指摘している。ロックストローム(2015)118は、地球は「すべてが相互につながる自己制御的なシステム」であると述べている。なお、メドウズ(2008)119によれば、システムとは、「部分の総和以上のもの」で、「何かを達成するように一貫性を持って組織され、相互につながっている一連の構成要素」で、イメージがしやすい最も身近なシステムの例としては、我々の人体を挙げることができる。我々の人体は、まさに、「統合され、相互につながった自己維持型」の複雑なシステムの一つであるといえる。
2こうしたシステムとして世界を捉えれば、世界は、小さなシステムが集まってより大きなシステムになり、それが集まって、更に大きなシステムになる形で組織化されている。例えば、国は、グローバルな社会経済システムの中に存在するサブシステムで、グローバルな社会経済システムは、生物圏システムの中に存在するサブシステムである120。メドウズ(2008)は、サブシステムは、それ自体が一つのシステムとして機能できるため、取り外して還元的に個々を分析することもできるが、それぞれのサブシステムをほかのサブシステムやヒエラルキーのより高いレベルにつなげている重要な関係性を見失ってはいけないと指摘する。
地球では、太陽の恵みの下、人間を含む動物、植物、微生物など様々な生物が、それらを取り囲む大気、水、土という自然環境の中で、複雑につながり合いながら共生しており、人間だけ独立して生存しているわけではない。生態系システムは、「生産者」である植物などが、太陽からのエネルギーを受けて無機物から有機物を合成し、それらを「消費者」である人間やそのほかの動物などが、直接又は間接的に食べ、それらの排泄物、死骸、落ち葉などに含まれる有機物を、土壌動物、菌類や細菌類などの微生物などが取り入れて、「分解者」として無機物に変換し、この無機物を「生産者」である植物などが吸収し、有機物を合成するという循環によって保たれている。宮脇(2013)121は、この循環システムの中で、森林は、「いのち」を守る母体ともいえる唯一の生産者である一方、人間は、当該システムの枠の中でしか生きていけないとても弱い存在で、消費者の立場で生かされているだけだと指摘する。人間は、生物の豊かな個性とつながりである生物多様性122を基盤とする生態系がもたらす恵みを享受することにより生存しており、人間と生態系は不可分の関係にある。
グテーレス国連事務総長は、2022年の国際マザーアース・デーに寄せるビデオメッセージにおいて、地球はいま、気候崩壊、自然と生物多様性の喪失、そして汚染と廃棄物という「惑星としての三重の危機」に直面しており、一つしかない私たちの地球を守るために、全力を尽くさなければならない123と改めて指摘した。本項では、気候変動と生物多様性の喪失の危機を取り上げ、現状を概観する。また、両者は、長い間、個別の問題として扱われてきたが、近年、二つを同じ見方で捉え、統合的に対応することの重要性が国際的にも強調されている。後半ではその動向を一部紹介する。
115 国連広報センターWebサイト参照(https://www.unic.or.jp/news_press/messages_speeches/sg/49287/![]() )。
)。
116 国連Webサイト参照(https://press.un.org/en/2023/sgsm21926.doc.htm![]() )。
)。
117 国連Webサイト参照(https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change![]() )。
)。
118 Rockström, J. et al., (2015), Big World Small Planet, (武内和彦 石井菜穂子監修(2018)『小さな地球の大きな世界 プラネタリー・バウンダリーと持続可能な開発』、丸善出版。).
119 Meadows, D., (2008), Thinking in Systems, (枝廣淳子訳(2015)『世界はシステムで動く』、英治出版。).
120 Meadows, D., (2008), Thinking in Systems, (枝廣淳子訳(2015)『世界はシステムで動く』、英治出版。).
121 宮脇昭(2013)『森の力 植物生態学者の理論と実践』、講談社現代新書。
122 生物多様性Webサイト参照(https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/about.html![]() )。
)。
123 国連広報センターWebサイト参照(https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/45006/![]() )。
)。
(1) 現状
2023年の世界平均気温は、工業化前(1850~1900年)と比較して1.45(±0.12)°C上昇し、世界気象機関(WMO)の174年間の観測史上で最も暑かった124。太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなるエルニーニョ現象の影響もあり、日本を含む各地で異常高温が発生し、中国、ベトナム、ブラジルでは国内の最高気温の記録を更新したほか、森林火災、大雨などに伴う気象災害が各地で発生した125。
現在見られる気候変動の影響としては、深刻な干ばつ、水不足、大規模火災、海面上昇、洪水、極地の氷の融解、壊滅的な暴風雨、生物多様性の減少などが挙げられる126。国連防災機関(UNDRR)の「自然災害の世界評価報告書」(2022年4月公表)は、2030年までに自然災害の発生は世界全体で一日当たり1.5回、年間で560回に達する見通しで、人類は温暖化を助長し、リスクを無視することを通じて、自己破壊の連鎖に陥っていると指摘した127。世界銀行の報告書(2021年9月公表)128は、気候変動対策が早急に講じられなければ、2050年までに世界の六地域129で2億1,600万人が、国内移住を余儀なくされると警告する。2024年1月に世界経済フォーラムが発表した「グローバルリスク報告書2024」では、今後10年間で最も深刻な影響を及ぼす可能性のあるリスクの上位三位は全て環境リスクで、一位は異常気象、二位は地球システムの危機的変化(気候の転換点)、三位は生物多様性の喪失と生態系の崩壊だった130(第II-1-5-1図)。
第Ⅱ-1-5-1図 今後10年間で最も深刻な世界規模のリスクは何か
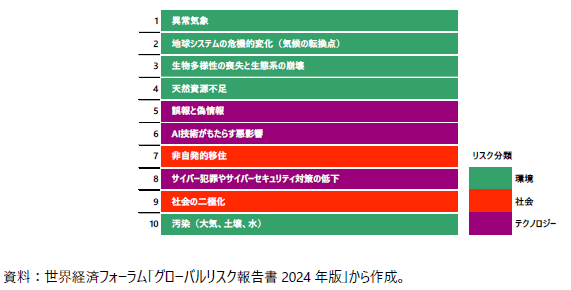
WMOによると、2024年は更に暑くなる可能性があり131、世界全体の長期的な平均気温の上昇を、工業化前(1850~1900年)と比べて2°Cより低く保つとともに1.5°C以内に抑える努力をするとの国際枠組み「パリ協定」132で定められた限界値に、世界はますます近づくことになる。
気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えることを目的に設立された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が2018年に発表した「1.5°C特別報告書133」は、世界の平均気温が、工業化前と比べて1.5°C上昇の場合と2°C上昇の場合とに分けて、生態系や人間の生活への影響やリスクがどの程度異なるかの予測をしている。
当該予測では、確信度はそれぞれ異なるが、例えば、温暖化の上昇幅を2°Cではなく1.5°Cに抑えると、150万~250万㎢の範囲(本州の約7~11倍)にわたり、永久凍土の溶解を何世紀にもわたり防ぐことが可能となるほか、2100年までの海面水位の上昇は、2°Cよりも10cm低く134、海面上昇に伴うリスクにさらされる人が最大1千万人減少する。また、地球の表面積のわずか0.1%でありながら、九万種を超える生物種が生息することが確認されている珊瑚礁135は、温暖化の上昇幅が2°Cであれば、ほぼ全滅(99%以上が消失)することが予測されているが、1.5°Cであれば、約70~90%の減少となる。さらに、気候に関連したリスクや貧困の影響を受けやすい人々の数は、温暖化の上昇幅を1.5°Cで止めれば、2°Cと比べて2050年までに最大数億人削減し得る。
同報告書は、上記に例示した予測などを示すとともに、温暖化の上昇幅を1.5°Cに抑えるためには、2030年までに世界全体の人為起源の二酸化炭素の正味排出量を、2010年比で約45%削減し、2050年前後には正味ゼロまで削減することが必要であることも示唆した。
パリ協定の下で、全ての締約国は、温室効果ガスの排出削減目標を五年ごとに設定・更新して、排出削減に取り組むこととなっているが、温暖化の上昇幅を1.5°Cに抑えるために必要な排出削減量と、各国政府が提出する排出削減目標の積み上げとの間にはギャップがある。また、排出削減目標の積み上げと実施状況との間にもギャップが存在する。同協定に基づく第一回グローバル・ストックテイク136に関する決定137では、世界全体の排出量は、パリ協定の長期的な目標達成に向けた緩和経路に沿っていないと指摘し、緊急の行動が必要であるとした。国連環境計画(UNEP)は、気温上昇が新記録を更新する中、世界は温室効果ガスの排出削減に失敗していると記し、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出がこのままのペースで続いた場合、世界の平均気温は、今世紀末までに、工業化前に比べ2.5~2.9°C上昇するとの見通しを示している138。
大気中の濃度が高まり、気候変動を引き起こすとされている温室効果ガスのうち、大気中に長くとどまる主要な温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素)の2022年の世界平均濃度は、WMOが解析を始めた1984年以降38年連続で過去最高を更新し、濃度の上昇傾向には終わりが見えない。地球温暖化に対して世界全体で最大の影響力を持つ二酸化炭素の濃度は、工業化前(1750年以前)の水準と比較すると約1.5倍、メタンは同約2.6倍、一酸化二窒素は同約1.2倍上昇した139。
人類が排出する二酸化炭素の吸収源は、陸域と海域の生態系だが、それらの生態系は、驚くほど速いペースで損なわれている。陸域生態系の二酸化炭素吸収源とされる森林は、膨れ上がる人類の食料、衣類、エネルギーを与えるため伐採され、その面積は大幅に減少した140。統計的には、世界全体として、森林が純減する速度は1990年から2020年にかけて低下している141が、地域によっては、逆に高まっている。加えて、一部の森林においては、生物多様性が確保されていないなど森林の質の劣化も議論となっている。半世紀以上にわたって現場で調査・研究してきた植物生態学者の宮脇(2013)142は、その土地本来の「潜在自然植生143」からはるかにかけ離れた森林は、量的に緑が豊かでも、自然災害や病虫害を受けやすく、大気浄化、水質浄化、水源涵養、炭素吸収固定などの環境保全機能も十分働かず、長持ちしないと指摘する。
森林を伐採し、土地を衣食住のために転用するなど土地利用が変化することなどに伴い、土壌も劣化している。「世界土壌資源報告144」によると、土壌は地球上の生命にとって必要不可欠な基盤であるにも関わらず、33%もの土地が、侵食、塩類集積145、圧密146、酸性化及び化学物質による汚染が原因で劣化し、人間が土壌資源にかける圧力は限界に達しようとしている。土壌は、食料生産と食料安全保障の基盤であるとともに、地球最大の水のろ過や貯蔵タンクとしての機能も持つ。また、地上の全ての植物よりも多くの炭素を貯留しており、土壌は、二酸化炭素などの温室効果ガスの放出を調整する役割を果たすとともに、計り知れない生物の多様性を宿し、生態系プロセスにとって重要な要となっている。「土地劣化と再生に関する評価報告書147」によると、土地劣化は、種の減少や絶滅、人間が享受する生態系サービスの消失を引き起こす。また、気候変動と合わさることで、世界の穀物生産量は2050年までに平均10%(地域によっては50%)減少することも予測されているところ、土地劣化を問題として認識する意識の欠如が、劣化防止に向けた行動を妨げる大きな障害となっていると同報告書は指摘している。藤井(2022)148は、厚み1センチメートルの土149を失うのは早いが、「その土が再生するには100年から1000年もの時間がかかる。人類には土がつくれず、植物と微生物の働きによる土壌発達を待つしかないため、土壌が劣化してしまってからでは遅い」と述べている。
森林伐採などを伴う土地利用の変化、土壌の劣化などを含む人為的な要因により、地球全体で大量の生物種が、かつてない規模で絶滅の危機に瀕している。「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」によると、生物多様性への脅威を取り除く行動をとらなければ、今後数十年で、絶滅危機にある推計100万種の動植物(動植物の平均約25%の種)の多くが絶滅するおそれがある。また、現在の絶滅スピードは、過去1,000万年間の平均に比べると、少なくとも数十倍、あるいは数百倍に達しており、適切な対策を講じなければ、今後更に加速することも示唆されている。昆虫類の個体群も、いくつかの場所で急速な減少が報告されている。世界の食料作物の種類のうち75%以上は、昆虫など動物による花粉媒介に依存する150。昆虫は、作物の受粉、糞や死骸、枯れ葉の分解、健全な土壌の維持、害虫防除など、人間の暮らしを支えている151。グールソン(2021)152は、私たちは、生態系を構成する何千もの生物の間で起きている多数の相互作用を理解するにはほど遠い状況にあり、どの生物が「必要」でどれがそうでないかを判断することはできないと述べている。
森林伐採などの土地利用の変化、土壌の劣化などは、もう一つの炭素吸収源で、地球最大の吸収源である海域の生態系にも深刻な影響を及ぼしている。森林と海はつながっており、森が作り出す豊かな腐葉土の有機成分は、川を介して海へと流れ込み、海の生態系をも支えている153。豊かな海は、森林によって支えられており、日本では、経験的に、魚介類を増やすためには、水辺の森林を守ることが大切とされ、こうした森林は「魚つき林(うおつきりん)」と呼ばれていた。松永(2010)は、過度な森林伐採など陸における人間活動が、「海の砂漠化」の要因になっていることを、科学的に示している154。
2023年の世界平均気温は、上述したとおり、WMOの観測史上で最も暑かったが、同年の海洋熱(海水温の上昇)、海面上昇、南極の海氷面積の減少、氷河の後退も過去最高の記録を更新した155。海水温が上昇すると、氷河や氷床の融解が進み、海面が更に上昇することで、沿岸域のコミュニティをますますリスクにさらすほか、珊瑚の白化や海洋の貧酸素化が加速することなどから、海洋生物種の存続が脅かされ、海域の生物多様性が失われる。また、大気中に放出される二酸化炭素が増え、海洋が吸収する二酸化炭素量が増えると、海洋酸性化が進行し156、生態系に更なる影響を及ぼすことや、海洋の二酸化炭素の吸収能力が低下することも指摘されている157。
これらの現象は、氷山の一角に過ぎないが、どれも複雑に絡み合い、影響が連鎖し合う中で、多くは加速度的に悪化している。「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」によると、世界の陸地の75%は著しく改変され、海洋の66%は累積的な影響下にあり、湿地の85%以上は消失した。過去50年の間に、地球全体の自然は、人類史上かつてない速度で変化しており、その変化の直接要因は、土地と海の利用の変化、生物の直接採取、気候変動、汚染、外来種の侵入で、これら五つの直接要因は、様々な根本的な原因(間接的な変化要因)によって引き起こされているという。そして、根本的な原因の背景には、生産・消費パターン、人口の動態と推移、貿易、技術革新及び社会の価値観や行動があることが示された。
英国政府の委託により、2021年2月に公表された「生物多様性の経済学:ダスグプタレビュー」は、1992年から2014年までの間に、全世界の一人当たりの生産資本(道路、建物、工場)は二倍になり、一人当たりの人的資本(健康、知識、スキル)は約13%増加した一方、一人当たりの自然資本のストックは、40%近く減少したと推計した。人類が過去数十年間、大いに繁栄してきたその方法こそが、自然に壊滅的な犠牲を強いてきたと指摘している158。国連の「新国富指標2023」159によると、1990年~2019年までの163か国(世界人口の98%を占める)の包括的な富(①人工資本、②人的資本、③自然資本)は、全体としては増加したが、同期間に世界人口は24億人増加しており、一人当たりの包括的な富は5%減少した。また、③自然資本は、同期間に1990年比で28%以上、一人当たり換算では50%と大幅に減少した。自然資本の減少幅が最も大きかったのは日本で、1990年比で70%減少した。
国際的な科学者チームが、2023年9月に発表した地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)160の改定版(三回目の評価)161では、私たちの住む地球のシステムの安定性と回復力を維持するために最も重要な九つのサブシステム(気候変動、生物圏の一体性、土地利用の変化、淡水利用、生物地球化学的循環、海洋の酸性化、大気エアロゾルによる負担、成層圏オゾン層の破壊、新規化学物質)のうち、六つ(気候変動、生物圏の一体性、土地利用の変化、淡水利用、生物地球化学的循環、新規化学物質)が既に限界値を超えていることが示された162(第II-1-5-2図)。また、地球のシステムにおいては、各サブシステムが独立しているのではなく、それぞれが相互作用とフィードバックにより関連し合って作動していることから、人間活動による環境への影響を、個別にではなく、地球システム全体で考慮する必要があると訴えている。特に、「気候変動」と「生物圏の一体性」は、中核のサブシステムで密接に相関しており、統合的に対応される必要があると述べている。
第Ⅱ-1-5-2図 プラネタリー・バウンダリー
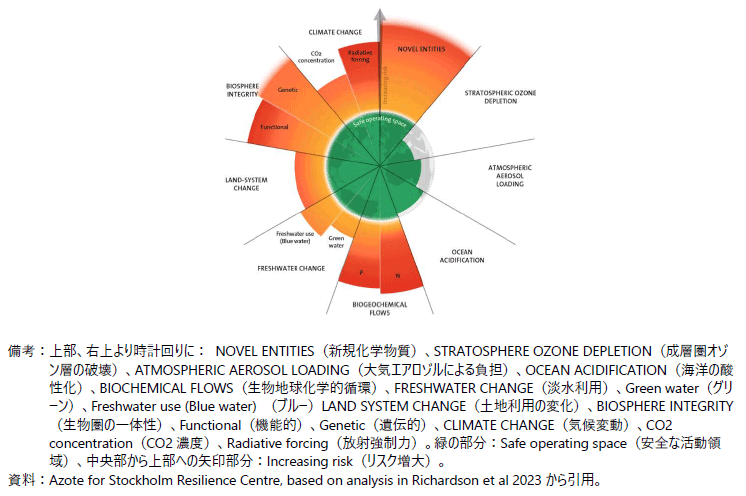
「全ては連鎖し、つながっている。」野生チンパンジー研究の第一人者である動物行動学者のジェーン・グドールは、私たちが自ら招いた解決すべき問題はたくさんあるが、これらは全てつながり合っており、全てを統合した形で理解し、解決する必要があると述べている163。また、生態学者ブライアン・ウォーカーは、閾値を超えないようシステムを強化する際、特定の領域だけを強化すると、別の領域で問題の起こる可能性があるため、常に全体を見通した上で強靱性(レジリエンス)の確保を考えなければならないと、語っている164。
気候変動対策は、生物多様性の保全と表裏一体である。以下では、気候変動と生物多様性の損失という地球規模の課題に対するこれまでの国際的な取組を取り上げつつ、地球のシステム全体を俯瞰した、統合的な対応が重要であるとする近年の動向を一部紹介する。
124 WMO Webサイト参照(https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2023![]() )。
)。
125 気象庁Webサイト参照(https://www.jma.go.jp/jma/press/2312/22d/2023matome_besshi2-2.pdf![]() )。
)。
126 国連広報センターWebサイト参照(https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/climate_change_un/what_is_climate_change/![]() )。
)。
127 UNDRR Webサイト参照(https://www.undrr.org/news/humanitys-broken-risk-perception-reversing-global-progress-spiral-self-destruction-finds-new![]() )。
)。
128 世界銀行Webサイト参照(https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/2c9150df-52c3-58ed-9075-d78ea56c3267![]() )。
)。
129 サブサハラ・アフリカ、東アジア・太平洋、南アジア、北アフリカ、ラテンアメリカ、東ヨーロッパ・中央アジア
130 World Economic Forum, (2024), “The Global Risks Report 2024”.
131 WMO Web サイト参照(https://wmo.int/media/news/wmo-confirms-2023-smashes-global-temperature-record)![]() )。
)。
132 2015年国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)にて採択、2016 年発効。
133 IPCC(2018)「1.5°Cの地球温暖化:気候変動の脅威への世界的な対応の強化、持続可能な開発及び貧困撲滅への努力の文脈における、工業化前の水準から1.5°Cの地球温暖化による影響及び関連する地球全体での温室効果ガス(GHG)排出経路に関する IPCC 特別報告書 政策決定者向け要約(SPM)」(2018年10月6日承認済みSPM IPCC-XLVIII/Doc. 5に基づく仮訳)。
134 特段の適応策が取られず、2010 年の人口に基づいた場合。
135 水産庁Webサイト参照(https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/tamenteki/kaisetu/moba/sango_genjou/![]() )。
)。
136 パリ協定の目標に向けた世界全体の進捗状況を五年ごとに評価する仕組み(パリ協定第14条に規定されている)。
137 UNFCCC Webサイト参照(https://unfccc.int/event/cma-5?item=4![]() )。
)。
138 UNEP, (2023), “Emissions Gap Report 2023”.
139 WMO Webサイト参照(https://wmo.int/news/media-centre/greenhouse-gas-concentrations-hit-record-high-again![]() )。
)。
140 国連食糧農業機関(FAO)の「世界森林資源評価2020」によると、世界の森林面積は、1990年の42億3,600 万haから2020年までの30年間で約1億7,800万haが減少。
141 FAO(2020)「世界森林資源評価2020」。
142 宮脇昭(2013)『森の力 植物生態学者の理論と実践』、講談社現代新書。
143 全ての人間活動を停止したとしたときに、その土地の自然環境条件の総和が終局的にどのような植生を支え得るかという理論的な自然植生(宮脇昭(2000)『鎮守の森』、新潮文庫)。
144 FAO(2015)「世界土壌資源報告」。
145 土壌中に塩類が蓄積することで、蓄積する塩類には、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、塩化物、硫酸塩、炭酸塩、重炭酸塩が含まれる。
146 土壌の表面に圧力がかかり続けることにより、土壌の密度が増加し、粗大孔げき(土中の隙間)率が減少すること。
147 IPBES(2018)「土地劣化と再生に関する評価報告書」。
148 藤井一至(2022)『大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち』、ヤマケイ文庫。
149 岩石の風化によって生まれた砂や粘土に、腐った動植物遺体が混ざったもの。
150 IPBES(2019)「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」。
151 Goulson, D., (2021), Silent Earth: Averting the Insect Apocalypse, (藤原多伽夫訳(2022)『サイレントアース 昆虫たちの「沈黙の春」』、NHK出版。).
152 Goulson, D., (2021), Silent Earth: Averting the Insect Apocalypse, (藤原多伽夫訳(2022)『サイレントアース 昆虫たちの「沈黙の春」』、NHK出版。).
153 宮脇昭(2013)『森の力 植物生態学者の理論と実践』、講談社現代新書。
154 松永勝彦(2010)『森が消えれば海も死ぬ 陸と海を結ぶ生態学』、ブルーバックス。
155 WMO Webサイト参照(https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2023![]() )。
)。
157 気象庁Webサイト参照(https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/mar_env/knowledge/oa/acidification_influence.html![]() )。
)。
158 Dasgupta, P., (2021), "The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review", London: HM Treasury.
159 UNEP, (2023), Inclusive Wealth Report 2023: Measuring Sustainability and Equity.
160 人類が生存できる安全な活動領域とその限界点。
161 Richardson, K. et al., (2023), “Earth beyond six of nine planetary boundaries”.
162 2009年の一回目の評価では三つ、2015年二回目の評価では四つが超えているとの評価。
163 Hawken, P., (2021), Regeneration: Ending the Climate Crisis in One Generation, (江守正多監訳、五頭美和訳(2022)『リジェネレーション[再生]気候危機を今の世代で終わらせる』、山と渓谷社、「はじめに」部分。).
164 ブループラネット賞創設30周年を祝うシンポジウムWebサイト参照(https://www.businessinsider.jp/post-259380![]() )。
)。
(2) 国連気候変動枠組条約と生物の多様性に関する条約(生物多様性条約)
国連気候変動枠組条約と生物多様性条約は、1992年にブラジル・リオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(地球サミット)に合わせて採択され、「双子の条約」とも呼ばれてきた165。国連気候変動枠組条約の目的は、人類の活動によって気候システムに危険な影響がもたらされない水準で、大気中の温室効果ガス濃度の安定化を達成することで、生物多様性条約の目的は、①地球上の多様な生物を生息環境とともに保全すること、②生物資源を持続可能であるように利用すること、③遺伝資源の利用から生ずる利益を、公正・衡平に配分することとなっている。
気候変動に対する具体的な政策などは、国連気候変動枠組条約やパリ協定等に基づき、1995年から毎年開催されている(新型コロナウイルス感染症拡大の影響による2020年を除く)締約国会議(COP)において議論されてきている(第II-1-5-3表)。その中で、近年、気候変動対策と生物多様性保全との関係を強調する動きが出てきている。国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)のグラスゴー気候合意166では、「気候変動及び生物多様性の損失という相互に結び付いた世界全体の危機並びに自然及び生態系の保護、保全及び回復が、気候変動への適応及び緩和のための利益をもたらすにあたり重要な役割を果たす」と記され、COP27で採択された「シャルム・エル・シェイク実施計画167」では、気候変動と生物多様性の損失という相互につながりあった世界危機は、包括的及び統合的な方法で早急に対処される必要があることが明記された。また、COP28で採択された第一回グローバル・ストックテイクに関する決定では、生物多様性条約に沿った政策を通じて、自然と生態系の保全、保護、復興の重要性が強調された。なお、COP28の会期中に開催された世界気候行動サミットでは、気候変動と生物多様性の目標を同時に達成するため、各国から総額17億米ドル(約2,500億円)の拠出が表明されている168。
第Ⅱ-1-5-3表 条約等に基づく主要な動向
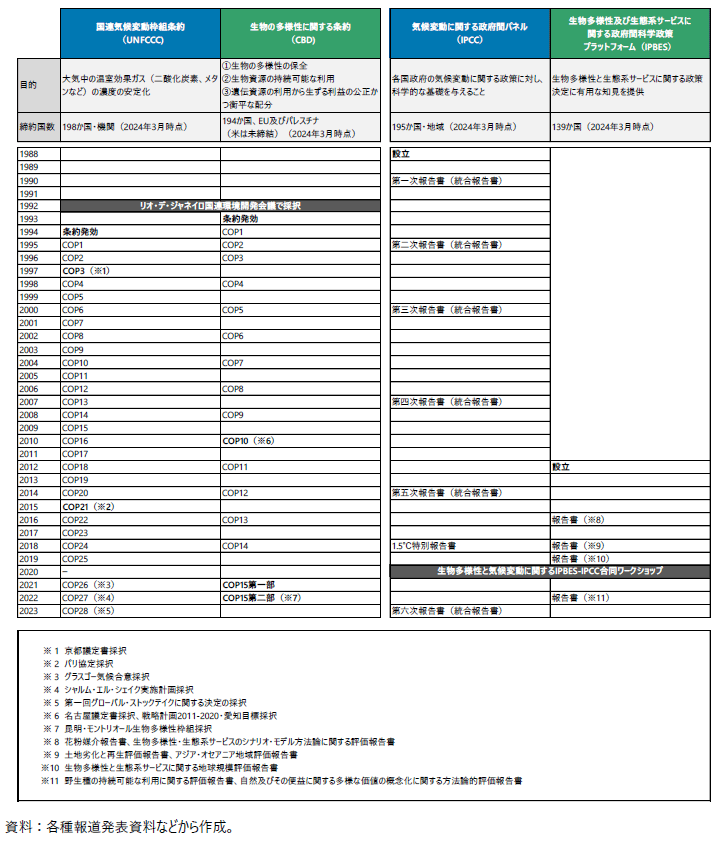
一方、生物多様性の保全に係る具体的な政策は、生物多様性条約に基づき、1994年以降、おおむね隔年で開催されているCOPで議論されている(第II-1-5-3表)。生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)第二部では、2010年に採択された「愛知目標」の後継として、2030年までの目標を定める「昆明・モントリオール生物多様性枠組169」が採択された。同枠組は、愛知目標で掲げた2050年ビジョン「自然と共生する世界」を引き続き掲げるとともに、それを達成すべく四つの長期ゴールを定めた。また、2030年までに生物多様性の損失を止め反転させる(ネイチャーポジティブ)ために緊急な行動をとるとのミッションの下、2030年までに陸域と海域の30%以上を保全する「30by30目標」を主要な目標の一つとして設定したほか、ビジネスにおける生物多様性の主流化、気候変動による生物多様性への影響の最小化など、計23の目標を掲げた170。クリスティアーナ・フィゲレス元国連気候変動枠組条約事務局長を始めとするパリ協定の主要な立役者は、「気候と自然の課題は絡み合っている。ネイチャーポジティブに向けた緊急行動をこの十年でとりつつ、経済の急速な脱炭素化を図る努力を強化し続けることによってのみ、パリ協定の約束の達成に希望が持てる」と声明で述べている171。我が国では、ネイチャーポジティブの達成に向けた施策の一貫として、2024年3月、四省庁172連名で「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」を取りまとめた173。同戦略は、気候変動対策とともに持続可能な社会への変革に必要なものとして、ネイチャーポジティブ経営への移行の必要性を示した上で、自然と共生する世界の実現に向け、企業の行動変容などを促している。
165 環境省Webサイト参照(https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r05/html/hj23010101.html![]() https://www.env.go.jp/content/000124381.pdf
https://www.env.go.jp/content/000124381.pdf![]() )。
)。
166 環境省Webサイト参照(https://www.env.go.jp/content/000049858.pdf![]() https://www.env.go.jp/content/000049875.pdf
https://www.env.go.jp/content/000049875.pdf![]() )。
)。
167 シャルム・エル・シェイク実施計画(https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_2_cover%20decision.pdf![]() )。
)。
168 COP28 Webサイト参照(https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_2_cover%20decision.pdf![]() https://www.cop28.com/en/news/2023/12/COP28-Galvanizes-Finance-and-Global-Unity-for-Forests-and-the-Ocean)。
https://www.cop28.com/en/news/2023/12/COP28-Galvanizes-Finance-and-Global-Unity-for-Forests-and-the-Ocean)。
169 環境省Webサイト参照(https://www.env.go.jp/content/000107439.pdf![]() )。
)。
170 外務省Webサイト参照(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page22_003988.html![]() )。
)。
171 Call From Paris Agreement Champions: Secure a Strong Sister Agreement for Biodiversity or Risk Undermining Climate Action (https://4783129.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/4783129/NDNP/PDFs/COP27-%20Call%20from%20Paris%20Agreement%20Champions.pdf![]() ).
).
172 環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省。
173 環境省Webサイト参照(https://www.env.go.jp/press/press_03041.html![]() )。
)。
(3) 気候変動に関する政府間パネルと生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム
気候変動に関する科学的な知見は、1988年11月にUNEPとWMOによって設立された政府間組織である気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が数年おきに発行している評価報告書が提供している(第II-1-5-3表)。2023年3月に公表された第六次評価報告書統合報告書は、1850年~1990年を基準とした世界平均気温は、既に2011年~2020年に1.1°Cの温暖化に達し、1970年以降の世界平均気温の上昇は、過去2000年間のどの50年間よりも加速していること、また、気候変動が人間活動の影響であることは疑う余地がないことを示した。なお、この十年間に行う選択や実施する対策は、現在から数千年先まで影響を持つと指摘している。
生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)は、2012年、生物多様性と生態系サービスに関する動向を科学的に評価し、科学と政策のつながりを強化する政府間のプラットフォームとして設立された。以降、七つの評価報告書などを発表している(第II-1-5-3表)。直近2022年に取りまとめられた「自然及びその便益に関する多様な価値の概念化に関する方法論的評価報告書174」は、人々の自然に関する価値観は多様であるにもかかわらず、多くの政策立案では狭い価値(例えば、市場取引で評価される自然の価値)を優先し、自然と社会、また将来世代を犠牲にするとともに、先住民及び地域社会の世界観に関連する価値をしばしば無視してきたと評価した。なお、生物多様性の減少傾向を反転できるかは、現在支配的な短期的かつ個人の物質的利益を過度に重視する価値観から転換し、社会全体で持続可能性に整合する価値観を醸成できるかどうかにかかっていると記した。
何年もの間、別々に活動が進められてきた両組織だが、2020年12月、合同ワークショップを開催した。同ワークショップでは、生物多様性の保護と気候変動の緩和・適応の間の相乗効果(シナジー)と負の影響(トレードオフ)が取り上げられた。例えば、気候変動対策として、太陽光や風力、バイオマスなど再生可能エネルギーの開発のために森林を伐採すれば、生態系がダメージを受けるだけではなく、気候変動が引き起こされる原因となっている温室効果ガスの吸収源の減少をも意味する。気候変動の緩和・適応のみに焦点を絞った対策は、生物多様性に直接的・間接的に悪影響を及ぼす可能性があることや、生物多様性の対策の多くが、気候変動の緩和・適応に相乗効果をもたらすことなどが挙げられ、両者を同時に考慮することの重要性が強調された。また、気候、生物多様性と人間社会を一体のシステムとして扱うことが、効果的な政策の鍵であることも示された。
174 IPBES(2022)「自然及びその便益に関する多様な価値の概念化に関する方法論的評価報告書 政策決定者向け要約」
(4) G7及びG20
2023年4月に開催されたG7 札幌気候・エネルギー・環境大臣会合では、気候変動対策と生物多様性対策のシナジーを強化する、自然を活用した解決策(NbS)を推進することの重要性が確認された175。同年5月に開催されたG7広島サミットでは、気候変動、生物多様性の損失、汚染といった課題に一体的に取り組む必要があることや、「気候危機」への対応は世界共通の待ったなしの課題であることなどが確認された176。また、同年9月に発出されたG20ニューデリー首脳宣言177では、我々は、一つの地球、一つの家族であり、一つの未来を共有していることが前文で掲げられ、気候変動、生物多様性の損失、砂漠化、干ばつ、土地劣化、汚染、食料不安及び水不足に対処する上で、健全な生態系の重要性を強調する点も明記された。
175 経済産業省Webサイト参照(https://www.meti.go.jp/information/g7hirosima/energy/pdf/communique-summary.pdf![]() )。
)。
176 外務省Webサイト参照(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page1_001703.html![]() )。
)。
177 外務省Webサイト参照(https://www.mofa.go.jp/files/100550685.pdf![]() )。
)。
(5) 第六回国連環境総会(UNEA-6)
2024年3月に開催された第六回国連環境総会(UNEA-6)において、我が国より提案したシナジー推進決議が採択された。我が国でも三つの世界的危機(気候変動、生物多様性の損失、汚染)を克服するため、相互に関連するこれら問題の相乗効果(シナジー)を拡大し、トレードオフを最小化する取組を我が国が主導して進めることにより、ネット・ゼロ178で、循環型で、ネイチャーポジティブな経済の実現を目指す必要がある。
178 温室効果ガスの排出量から吸収量や除去量を差し引いた正味の排出量をゼロにすること。
(6) 気候関連情報開示タスクフォースと自然関連財務情報開示タスクフォース
ビジネスの世界では、企業などの事業活動が気候変動、自然環境や生物多様性に与えるリスクと機会を、投資家や金融機関などが適切に評価して投資を行うことができるよう、企業はバリューチェーン全体を通じて、適切な情報開示をすることが求められるようになっている。
2015年、G20の要請を受けた金融安定理事会(FSB)により設置された気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)は、2017年、全ての企業が、「ガバナンス」、「戦略」、「リスクとインパクト管理」、「指標と目標」の四つの柱に基づき、11項目の気候関連財務情報を開示することを推奨する最終報告書を公表した。その後、実際の開示状況を示したステータスレポートが毎年公表されている(第II-1-5-4表)。
第Ⅱ-1-5-4表 TCFDとTNFDの主要な動向
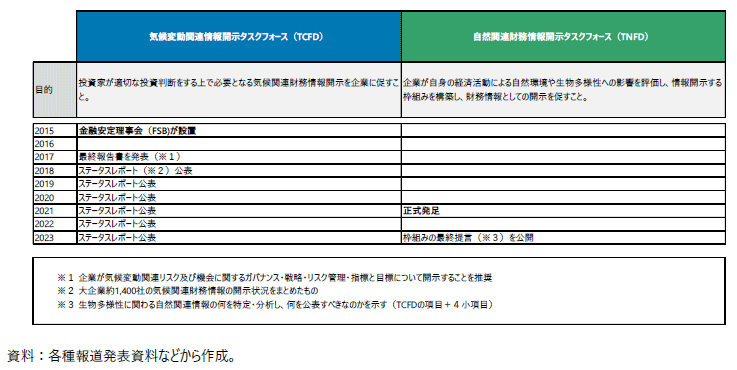
一方、TCFDの自然版ともいえる自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)は、2021年、国連開発計画(UNDP)、国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP FI)、世界自然保護基金(WWF)、環境NGOグローバルキャノピーの主導の下で発足した(第II-1-5-4表)。自然は、四つの領域(大気、海、淡水、陸)から構成されるとされ、これらの資源が組み合わさり、企業や人々の生活に対して価値を生み出す状態を環境資産(あるいは自然資本)と定義している。2023年9月に公表された情報開示枠組みの最終提言では、TCFDと同じ四つの柱に基づき全14項目を開示推奨項目とした。TCFDの11項目を全て内包し、両タスクフォースで整合性を取った形となっている。
本項では、気候変動と生物多様性の損失を取り上げ、現状につき概観するとともに、両者を統合的に対応することが必要であるとする近年の動きなどを紹介した。
首脳級のイニシアティブである「リーダーによる自然への誓約179」は、生物多様性の損失、生態系の劣化、気候変動という相互依存的な危機は、その大部分が持続不可能な生産と消費によって引き起こされており、緊急かつ迅速な地球規模の対策を必要としていると記している。地球上の総種数は、知られているものだけでも約175万種で、まだ知られていない生き物も含めると、1,300万種くらいだと推測されている(300万~1億種まで幅がある)180。そのうちの一種であるヒト(ホモ・サピエンス)による生産・消費活動(経済活動)が持続不可能なものとなっており、上述した危機を招いているということになる。
2000年、ノーベル化学賞受賞者のパウル・クルッツェンほかは、温暖で安定した気候の中で動植物の数や種類が増え、人類が台頭し、農耕と余剰生産が可能となった「完新世」の地質時代は終わり、私たちは「人新世」という地球の生態系と気候が人間の活動によって改変されている地質時代に入ったと提唱した。
「生物多様性の経済学:ダスグプタレビュー」は、「私たちの経済や生活、幸福は、いずれも最も貴重な資産である自然によってもたらされている」と記し、「私たちの経済は自然の外部にあるのではなく、自然の内部に組み込まれているのだという基本的な真実を理解し、受け入れることが解決に向けた第一歩」となると指摘している181。190人の研究者、専門家、科学者の国際的なグループが結集して地球温暖化を逆転させる100の方法を示した「ドローダウン」プロジェクトの編者でもあるポール・ホーケンは、地球は、私たちのコモンズ(共有地)で、私たちみんなを支えており、気候危機に対処し逆転させるには、地球の衰退を逆転させる必要があり、つながりと互恵主義が求められていると指摘した。また、同危機は、人間の問題であり、解決に向けた究極の力は技術にあるのではなく、私たち自身、全ての人々、全ての生き物に対する畏敬や尊敬、思いやりにかかっており、あらゆる意思決定と行動の中心に「生命」を据えることが必要であると述べている。そして、私たちがじっと考えながら待っている間に問題を解決してくれるような専門家グループはなく、一人一人の声が「私たち」になったとき、変化が起きるのだと記した182。
グテーレス国連事務総長は、「私たちが一つになった時、何ができるのかを私たちは目撃してきました」と語り、「一緒に取り組めば、途方もない課題に対処することができると、私たちは証明してきました」と利己を超え、協同した行動を訴えている183。
179 リーダーによる自然への誓約(仮訳):2020年9月の国連生物多様性サミットに先立って発足した首脳級イニシアティブ(https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/international/files/LeadersPledge-jp.pdf![]() )。
)。
180 生物多様性条約Webサイト参照(https://www.cbd.int/youth/biodiversity/![]() )。
)。
181 Dasgupta, P., (2021), "The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review", London: HM Treasury.
182 Hawken, P., (2021), Regeneration: Ending the Climate Crisis in One Generation, (江守正多監訳、五頭美和訳(2022)『リジェネレーション[再生]気候危機を今の世代で終わらせる』、山と渓谷社。).
183 国連広報センターWebサイト参照(https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/45006/![]() )。
)。
190 Transition Town Totnes Webサイト参照(https://www.transitiontowntotnes.org/about-us-2![]() )。
)。
191 パーマカルチャー:Permanent(永続的)、Agriculture(農業)、Culture(文化)の用語を掛け合わせた造語で、人間の持続可能な暮らしのためのデザイン・システムを意味する。
192 ロブ・ホプキンス(2013)『トランジション・ハンドブック』(城川桂子訳)、第三書館。
193 Rapid Transition Alliance Webサイト参照(https://rapidtransition.org/stories/transition-towns-the-quiet-networked-revolution/![]() )(2019年10月時点)。
)(2019年10月時点)。
2.人権問題への対応
グローバル化の進展によって、企業活動が人権に及ぼす負の影響が拡大する中、企業活動による人権侵害についての企業の責任に対する国際的な議論が更に活発になっている。近年、欧米を中心として人権尊重を理由とした法規制の導入も進み、企業はこれらの法規制への対応を迫られている。また、NGO等がグローバル企業の人権侵害への関与について名指しで批判するケースも生じており、人権侵害を理由とした製品・サービスの不買運動、投資先としての評価の降格、投資候補先からの除外、投資の引揚げ、既存顧客との取引停止などの経営リスクに直面する可能性が存在している。企業が直面するこれらの経営リスクを低減し、企業価値を向上させ、強靱で包摂的なサプライチェーンを構築する観点からも、サプライチェーン上の企業等も含めた人権尊重の取組を実施・強化していくことが必要となっている。
(1) 企業に人権尊重を求める海外の動き
2011年6月、「ビジネスと人権に関する指導原則」(国連指導原則)が、国連人権理事会において全会一致で支持(endorse)された。同原則では、人権を保護する国家の義務、人権を尊重する企業の責任、救済へのアクセス、という三つの柱を規定し、国家と企業とが、相互に補完し合いながらそれぞれの役割を果たしていくことが求められている。企業は、人権を尊重する責任を果たすため、①人権方針の策定、②人権デュー・ディリジェンス194、③救済(苦情処理メカニズムの設置を含む)を実施すべきとされている。また、同原則の履行として、各国に対し国別行動計画(National Action Plan(NAP))の策定が推奨されており、2023年末時点で日本を含む世界の26か国以上がNAPを策定している。
また、OECD多国籍企業行動指針及び国際労働機関(ILO)多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言の改定が、それぞれ2011年、2017年に行われた際、国家の人権保護義務や企業の人権尊重責任が盛り込まれた。さらに、OECD多国籍企業行動指針の直近の改定(2023年)では、企業によるサプライチェーンの下流へのデュー・ディリジェンスの適用範囲の明確化等、新たな規定が盛り込まれた。人権保護義務を負うことはもちろん、企業に人権尊重責任があることが国際的な原則となっており、企業はこれらの国際的文書に沿って行動することが求められている。
さらに、近年、欧米を中心として人権尊重を理由とする法規制の導入が進んでいる。例えば、ドイツでは、2021年6月、「サプライチェーンにおける企業のデュー・ディリジェンスに関する法律(サプライチェーン法)」が成立し、2023年1月に発効された。同法では、一定規模以上の企業に人権デュー・ディリジェンスの実施や、その結果に関する報告書の作成・公表等を義務付けている。
欧州では、2022年2月に欧州委員会が公表した、一定規模の企業に対して人権及び環境に関するデュー・ディリジェンスを義務化する「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令案」195について、正式な採択に向けた手続が進められている196。このほか、欧州委員会が2022年9月に公表した強制労働関連産品のEU域内における上市・EU域外への輸出を禁止する規則案も同様に立法機関での政治合意197を経て正式な採択に向けた手続へと移行している。
米国では、外交政策における人権重視を掲げ、欧州とも連携して、新疆ウイグル自治区における人権侵害への関与を理由とした制裁を含む措置を実施している。また、2021年7月には、同自治区での強制労働のほか、人権侵害に関与する事業体がサプライチェーンに含まれていないか、産業界に注意を促す「新疆サプライチェーンビジネス勧告書(2020年7月)」を公表198した。同年12月、中国の新疆ウイグル自治区で一部なりとも生産等された製品や、米国政府がリストで示す事業者により生産された製品は、全て強制労働によるものと推定し、原則として米国への輸入を禁止する「ウイグル強制労働防止法」が成立199し、2022年6月に施行された。同法に基づき、輸入貨物を差し止められた場合、輸入者は、輸入物品とその原材料が新疆ウイグル自治区で生産されていないこと等を示す必要がある。同法の対象である(輸入物品とその原材料が新疆ウイグル自治区で生産されたものを含む)場合、輸入物品が一部なりとも強制労働に依拠していないこと等を、輸入者が「明確かつ説得力のある証拠」を提出し証明する必要がある。2023年3月には、国土安全保障省税関・国境取締局(CBP)がウイグル強制労働防止法の執行状況について統計ダッシュボードを公開した。同ダッシュボードによると、2024年2月までに、ウイグル強制労働防止法に基づき、既に7,566件の輸入が差し止められ、そのうち3,096件の輸入が禁止され、3,135件の輸入が許可されている200。同年9月には、「新疆サプライチェーンビジネス勧告書」の付属書も公表201され、ウイグル強制労働防止法に係る執行戦略に従った適切な人権デュー・ディリジェンスの実施継続が企業に対して要請された。
こうした国際社会の動きも踏まえ、企業としても事業活動における人権尊重の取組を行っていく必要があり、自社内だけでなく自社のサプライチェーンやバリューチェーン全体を見据えた対応と情報開示が求められている。
194 人権デュー・ディリジェンス:人権への負の影響を特定し、防止・軽減し、取組の実効性を評価し、どのように対処したかについて説明・情報開示していくために実施する一連の行為を指す。
195 欧州委員会Webサイト参照(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_6599![]() )。
)。
196 本指令案は2023年12月にEU理事会と欧州議会の間で政治合意に至った後、一部の加盟国が本指令案について反対の立場を示す事態となったが、その後2024年3月に対象企業の閾値等について修正がなされた内容でEU理事会の常駐代表委員会において合意に至り、さらに当該修正案が欧州議会の法務委員会において承認されており、今後、同年4月下旬に予定される欧州議会本会議とその後のEU理事会本会議での正式な採択の手続を経て成立することが予想される。
197 欧州委員会Webサイト参照(https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-ban-products-made-forced-labour-union-market-2024-03-05_en![]() )。
)。
198 米国国務省Webサイト参照(https://www.state.gov/xinjiang-supply-chain-business-advisory/![]() )。
)。
199 米国議会Webサイト参照(https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6256/text?r=1&s=1![]() )。
)。
200 米国国土安全保障省税関・国境取締局Webサイト参照(https://www.cbp.gov/newsroom/stats/trade/uyghur-forced-labor-prevention-act-statistics![]() )。
)。
201 米国国務省Webサイト参照(https://www.state.gov/issuance-of-an-addendum-to-the-xinjiang-supply-chain-business-advisory/![]() )。
)。
(2) 我が国の取組
我が国政府は、国連指導原則を踏まえ、2020年10月に「「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)」を策定し、日本企業に対して、規模、業種等にかかわらず、人権デュー・ディリジェンスのプロセスの導入を期待する旨を表明した。
また、経済産業省は外務省と連名で、2021年9月~10月にかけて、政府として初めて、行動計画のフォローアップの一環として、日本企業のビジネスと人権への取組状況に関する調査を実施した(「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査」202)。調査結果を見ると、回答企業のうち、人権方針を策定している企業は約7割となっているほか、人権デュー・ディリジェンスを実施している企業は、約5割程度にとどまっている。また、人権を尊重する経営を実践する上での課題としては、「サプライチェーン上における人権尊重の対応状況を評価する手法が確立されていない」、「サプライチェーン構造が複雑で、対象範囲の特定が難しい」、「十分な人員・予算を確保できない」との回答が多く見られ、政府に対する要望として、ガイドライン整備を期待する声が最も多く寄せられた。
このような状況も踏まえ、企業が国際スタンダードに沿った人権尊重に積極的に取り組めるよう、2022年3月、経済産業省において、「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」を設置し、同検討会での議論を重ね、同年9月、「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」において、日本政府として「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定・公表した203。
同ガイドラインは、法的拘束力を有するものではないが、国連指導原則、OECD多国籍企業行動指針及びILO多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言を始めとする国際スタンダードを踏まえ、企業に求められる人権尊重の取組について、日本で事業活動を行う企業の実態に即して、具体的かつ分かりやすく解説し、企業の理解の深化を助け、その取組を促進することを目的としたものであり、 企業の規模、業種等にかかわらず、日本で事業活動を行う全ての企業を対象としている。同ガイドラインにおいて、企業は、国際的に認められた人権を尊重すべきとされ、その責任を果たすため、①企業トップを含む経営陣の承認を経た人権方針の策定・公表、②人権デュー・ディリジェンスの実施、③自社が人権への負の影響を引き起こし又は助長している場合における救済を行うことが求められている(第II-1-5-5図)。
第Ⅱ-1-5-5図 責任あるサプライチェーン等における人権尊重の全体像
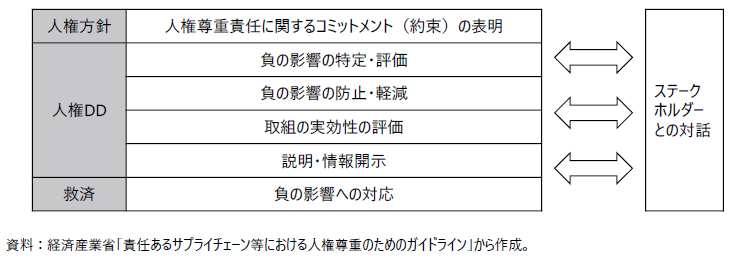
また、2023年4月には、具体的な取組方法がイメージできないなどの企業の声も踏まえて、経済産業省において、本格的に人権尊重の取組を行ったことのない企業が本ガイドラインに沿った取組を進めやすくする「サプライチェーンにおける人権尊重のための実務参照資料」を作成・公表した204。そのほか、ガイドラインや実務参照資料の活用を促すため、経済産業省主催の取組支援セミナーを開催し、周知徹底に努めた。
このほかに、経済産業省では、JETROやILOと協力して、企業の取組の促進に取り組んできている。2024年3月には、ILOへの拠出を通じて、ILO及びJETROが共同で、バングラデシュ、カンボジア、ベトナムに活動拠点や取引先を持つ繊維・アパレル、電気・電子機器等の業種の日本企業の人権尊重に係る取組をまとめた好事例集を作成及び公表した205。また、ILOへの拠出を通じ、全国社会保険労務士連合会と協力して、中小企業の人権尊重の取組をサポートできる専門人材育成にも取り組むほか、中小企業庁と連携して中小企業向けのセミナーを行うなど中小企業に対する支援も行ってきた。
さらに、日本国内だけでなく、アジア諸国においても、「ビジネスと人権」に取り組んできている。ILOへの拠出を通じて、アジアにおける責任ある企業行動の推進を目的として、バングラデシュ、カンボジア及びベトナムにおける日本企業の海外取引先企業などに対する人権デュー・ディリジェンスの実施支援、人権・労働環境向上のためのアドバイスの提供、国際労働基準に精通した人材育成支援や、タイ、インドネシアの機械産業等における技能開発支援などの事業を実施した。また、2023年9月には、アジア諸国でビジネスと人権に関する議論を深める機会として、ILOとの共催でインドネシア・ジャカルタにおいて、アジア諸国の政労使及びG7のメンバーを一堂に会した対話イベントを開催した。このイベントでは、包摂的成長と人権尊重の間の相乗効果の重要性に焦点を当て、ビジネスと人権に関する国際スタンダードを実践するための多様なアプローチの認識を促進した。
国際場裡では、2023年4月のG7貿易大臣会合及び同年5月のG7広島サミットにおいて、G7内外におけるビジネスと人権に関する議論を深める必要性を認識するとともに、企業活動における人権尊重の確保、ビジネスのための予見可能性の向上に向けた国際協調の強化等について合意に至った。同貿易大臣会合を受け、G7各国政府間のビジネスと人権に関する専門家のネットワークを通じ、情報交換にも取り組んだ。さらに、同年10月のG7大阪・堺貿易大臣会合では、ジャカルタで開催した対話イベントに対してG7を超えたビジネスと人権に関するアウトリーチと関与の強化の観点から歓迎の意が表された。
日米間では、2023年1月に、「サプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関する日米タスクフォース」を立ち上げ、2024年2月、同タスクフォースの第一回会合(政府間対話及びステークホルダー対話)を開催した。政府間対話では、サプライチェーン上の人権尊重及び国際的に認められた労働者の権利の保護等に関する日米の取組について情報を共有した。日本側からは、日本政府のガイドライン及びその普及啓発や発展途上国とのエンゲージメントを中心に報告した。一方、米国側からは、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)における労働関連事項への対応やウイグル強制労働防止法の執行状況等について説明を受けた。ステークホルダー対話では、日米政府関係者より、ビジネスと人権政策に関する報告を行った。産業界、労働組合、市民社会、国際機関から、人権デュー・ディリジェンスに関する取組等について紹介があった。
我が国政府としても、企業による人権尊重の取組を促進すべく、引き続き企業に対する情報提供、周知・啓発活動を推進していくとともに、各国政府との協調を進め、公平な競争条件の下で積極的に人権尊重に取り組める環境、企業にとっての予見可能性が高まる環境の実現に向け取り組んでいくこととしている。
202 経済産業省Webサイト参照(https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211130001/20211130001.html![]() )。
)。
203 経済産業省Webサイト参照(https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003.html![]() )。
)。
204 経済産業省Webサイト参照(https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230404002/20230404002.html![]() )。
)。