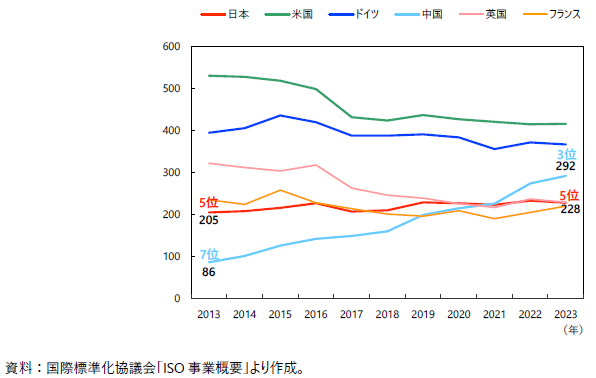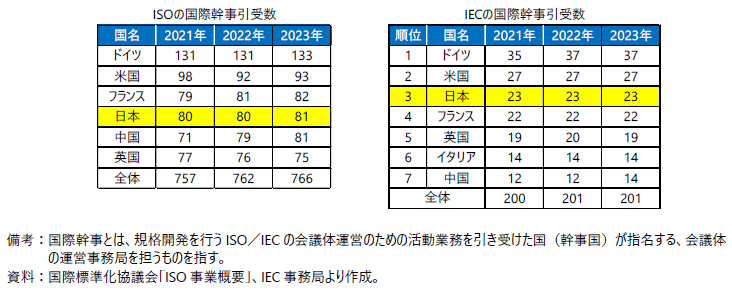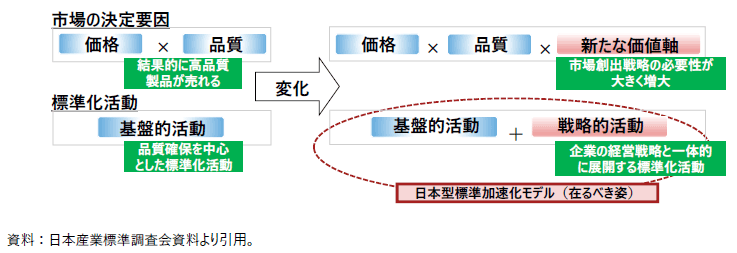第3節 新しい産業政策の潮流と多国間協力・ルール形成の必要性
本節では、中国、米国、欧州、そして我が国が展開する産業政策の目的と概要を整理し、諸外国で活発化する産業政策の実態を概観する。そして、各国による産業政策が貿易に与える影響について考察するとともに、多国間協力とルール形成のあるべき姿について展望する。
1.活発化する主要国の産業政策
米中対立等による地政学的リスクの高まりや、半導体や重要鉱物といった経済安全保障に関わる物資のサプライチェーンの脆弱性、カーボンニュートラルを目指す各国の取組の進展などを背景として、欧米や中国を中心に、国内産業競争力強化のための政策を積極的に打ち出す動きが進んでいる。
我が国も、令和6年度税制改正の大綱において、EVや半導体等の物資に対して生産量や販売量に応じた減税措置を講じる戦略分野国内生産促進税制を創設することを決定するなど、企業に対する重要物資の生産促進を加速させている。
(1) 産業政策を巡る最近の動向
主要国で産業政策を巡る動きが活発化する一方で、一部の主要産業において、経済性を考慮しない形での政府補助金等により生産能力の拡張が進んだ結果、深刻な過剰供給状態が発生する、あるいは発生する懸念があることが、過剰生産問題と呼ばれWTO等で問題視されているとともに、それにより引き起こされる貿易への悪影響へも厳しい目が向けられている。
EUは、2023年10月、中国から輸入されるバッテリー式電気自動車(BEV)に対する反補助金調査を開始した。2023年11月、フォン・デア・ライエン欧州委員長は、直接又は間接的な補助金により過剰生産能力が進み、市場歪曲が進むことを受け、同調査を開始したと述べている。さらに、同氏は、2024年5月にパリで行われたマクロン仏大統領と習近平国家主席との首脳会談でも、「世界は中国の過剰生産を吸収できない」と発言した60。
米国も中国への圧力を強めている。2024年4月に中国を訪問したイエレン米財務長官は、2023年に米中が設置した経済作業部会の枠組みの下で「国内経済と世界経済の均衡ある成長に関する意見交換」を開始し、中国政府と過剰生産問題などについて議論すると発表した61。そして、バイデン政権は2024年5月、中国から輸入される一部製品について、通商法301条62に基づく関税を引き上げると発表した。対象となる製品と関税引上げの時期及び関税率は、鉄鋼・アルミが2024年中に25%、半導体が2025年中に50%、EVが2024年中に100%、EV用リチウムイオン電池が2024年中に25%、天然黒鉛・永久磁石が2026年中に25%、太陽電池が2024年中に50%などとなっている。バイデン大統領は、発表当日の演説で、「中国はこれら全ての製品に多額の補助金を拠出し、世界の国々が吸収できる量をはるかに超える生産を中国企業に押し付けてきた。そして、余剰製品を不当に安い価格で市場に投入し、世界中の製造業者を廃業に追い込んだ」と訴えた63。
また、2024年5月23日から25日にイタリアで開催されたG7財務大臣・中央銀行総裁会議の声明(仮訳)では、「我々はまた、自由で公正かつルールに基づく多国間システムへの強いコミットメントを再確認する。G7の日本議長国下におけるレガシーに基づき、我々は、世界経済の強靱性と経済安全保障を強化し、システミックなショックと脆弱性から我々の経済を守るための協力を進展させる。この目的のため、我々は、重要かつ新興の技術を保護しつつ、サプライチェーンをより強靱で、信頼性が高く、多様で持続可能なものとし、有害な慣行に対応するために取り組む。我々は、必要に応じて、G7内外のパートナーとともに供給のデリスキング及び多様化を促進するための適切な措置を検討する。我々は、世界的に公平な競争条件を確保するため、広範な政策手段やルールを通じて、過剰生産能力につながるものを含む非市場的政策及び慣行、並びに歪曲的政策に対処するための協力を強化する。我々は、均衡の取れた相互的な協力への関心を再確認する一方で、我々の労働者、産業及び経済的強靱性を損なう中国の非市場的政策及び慣行の包括的な利用について懸念を表明する。我々は過剰生産能力の潜在的な悪影響を引き続きモニターし、世界貿易機関(WTO)の原則に沿って、公平な競争条件を確保するための措置を講じることを検討する。加えて、我々は、産業政策及び非市場的慣行に関するデータ及びこの分野におけるモニタリングの手段の質と利用可能性を改善するための、関連する国際機関による取組を奨励する。我々は、ほかの関連するトラックと協調し、補助金及びそのほかの産業政策・貿易政策がマクロ経済に与える影響を比較可能な情報に基づいてグローバルに評価し、産業政策・経済的分断・市場集中リスク・過剰生産能力に関連する課題についての第三国との対話を推進するための作業を支持する64」ことが示された。
60 欧州委員会Webサイト参照(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_24_2464![]() )。
)。
61 米国財務省Webサイト参照(https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2241![]() )。
)。
62 通商法301条は、米USTRが外国政府による①WTO等の通商協定違反、及び②不当・不合理・差別的な措置等に関する調査を行い、これらに該当する場合、関税引上げ等の制裁措置を講ずる規定。
64 財務省Webサイトから引用(https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/g7/index.htm![]() )。
)。
(2) 中国の動向
2024年3月、中国の李強首相は、第14期全国人民代表大会(全人代)第2回会議を開催し、政府活動報告において、「現代化産業体系の構築」や「科学教育興国戦略の実施」、「内需拡大」、「対外開放の拡大」など10項目を重点課題として挙げた。中国は、2021年に発表した第14次5か年計画(2021年~2025年)において、対外開放路線を継続しつつ(国際循環)、内需を拡大しながら(国内大循環)、自国の巨大市場の魅力により諸外国の投資・技術を引きつけるという双循環政策を打ち出しており、2024年の政府活動報告で示された方針もこれに沿ったものとなっている。政府活動報告で示された重点課題の一番目に掲げられた「現代化産業体系の構築」では、具体的な取組として、産業チェーン及びサプライチェーンの最適化・高度化の推進や、新興産業と未来産業の育成、デジタル経済の推進が挙げられている。
次に、中国が、どの業種にどれだけの補助金を交付しているかについて、令和4年版通商白書の分析を引用し概説する。中国の証券取引所へ上場する企業の財務諸表に記載された補助金額を、中国製造2025が指定する重点10分野別にまとめたものが第II-1-3-1図である。
第Ⅱ-1-3-1図 中国製造2025の重点10分野向け補助金の推移
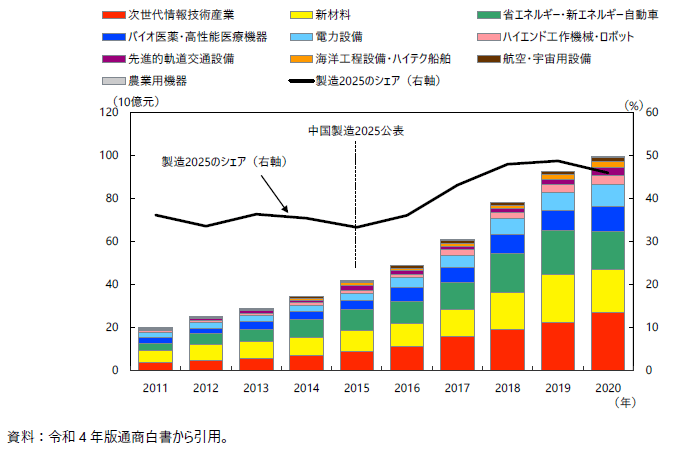
なお、中国製造2025とは、中国政府が2015年に発表した産業政策であり、中国を世界の製造強国に導くことを目的として、重点10分野における国産化率の引上げを目指すものである。第II-1-3-1図によると、2020年時点で最も補助金額の大きな分野は、半導体を含む次世代情報技術産業であり、次いで新材料、省エネルギー・新エネルギー自動車(EV等)となっている。ここでは、中国政府による半導体と新エネルギー自動車への補助金について概説する。
① 国家集積回路産業投資基金
中国政府は、中国製造2025において、半導体の自給率を2030年までに75%まで引き上げるという目標を掲げている。2014年に国家集積回路産業投資基金(1,390億元規模)を立ち上げ、2019年には同基金の第2期募集(2,040億元規模)も行った65。加えて、2020年8月には、一定の要件を満たす集積回路生産企業に対し、黒字化した年から10年間企業所得税を免除するなどの支援措置を発表した。
さらに、一部報道によると、中国政府は国家集積回路産業投資基金の第3期募集に向けて動いており、その規模は、2014年の第1期と2019年の第2期を上回る、3,000億元になる見込みであるという66。こうした報道から、中国政府が今後も半導体産業への投資を拡大していくであろうことがうかがえる。
65 経済産業省「半導体に係る安定供給確保を図るための取組方針」、(https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/semicon/torikumihousin_semicon.pdf![]() )
)
66 ロイター、2023年9月5日(https://jp.reuters.com/markets/japan/GWB7WLKPXBO3PA6DADI7IX7RRI-2023-09-05/![]() )
)
② 自動車購入税の免税措置等
EV等への支援措置も拡充傾向にある。中国の情報プロバイダーであるWindのデータ及びNikkei Asiaの調査によると、中国本土の上場企業5,000社以上のうち、2023年上半期に中国政府から補助金を受け取った上位10社中5社が、EV又はEVバッテリーを製造する地元メーカーであったという67。
中国政府は、2023年9月に「自動車産業の着実な発展に関する作業方案(2023~2024年)」を発表し、自動車購入税の減免措置を含む消費支援策の強化や、輸出促進策の実施、充電インフラの整備、自動車産業のサプライチェーンの安定性と円滑性確保などの施策を示した。中国政府は、バッテリー式電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池車(FCV)を新エネルギー車(NEV)と称し、これらに対する支援を強化している。作業方案によると、新エネルギー車については、2023年の年間販売台数目標として約900万台(前年比約30%増)が掲げられている68。
上述の施策のうち、自動車購入税の減免措置について、中国政府は2023年6月に2014年より続く同施策の延長及び改定を発表した。これにより、2024年1月1日から2025年12月31日までに購入された新エネルギー車は、1台当たり3万元を上限に自動車購入税が免除され、2026年1月1日から2027年12月31日までに購入された新エネルギー車は、1台当たり1万5,000元を上限に自動車購入税の50%が減税される69。
67 Nikkei Asia, September 21, 2023(https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-China/China-gives-EV-sector-billions-of-yuan-in-subsidies![]() )。
)。
68 中国工業情報化部ウェブサイト参照(https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_345e17e8729443eb8be3ecac76765874.html![]() )。
)。
69 JETRO Webサイト参照(https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/06/47d33451a8a22678.html![]() )。
)。
(3) 米国の動向
2023年4月、米国のジェイク・サリバン大統領補佐官はブルッキングス研究所で演説し、新ワシントン・コンセンサスと称する新たな産業・イノベーション戦略を発表した70。同戦略は、中間層の再興と雇用の創出、気候変動問題、中国との競争といったバイデン政権が重視する国内外の政策目標を体系立てて説明している。
まず、サリバン補佐官は、バイデン政権発足前に米国が抱えていた四つの課題を指摘し、それらへ対処するための五分野の政策を提言した。その中で第一に強調されたのが、現代的な産業政策の必要性であった(第II-1-3-2表)。
第Ⅱ-1-3-2表 新ワシントン・コンセンサスの概要
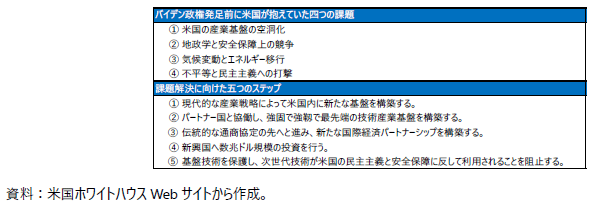
サリバン補佐官は、現代的な産業政策とは「経済成長の基盤であり、国家安全保障の観点から戦略的であり、民間企業だけでは国家的野心を達成するために必要な投資を行う準備が整っていない特定の分野」に的を絞った公共投資を行うことだと述べ、バイデン政権の立法成果であるインフラ投資雇用法(Infrastructure Investment and Jobs Act)とインフレ削減法(Inflation Reduction Act of 2022)、CHIPS及び科学法(Chips and Science Act)を着実に実行していくと表明した。
70 米国ホワイトハウスWebサイト参照(https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/![]() )。
)。
① インフラ投資雇用法
インフラ投資雇用法は、2021年11月に成立した総額約1兆ドル規模(うち新規支出は5,500億ドル)の超党派法である。バイデン大統領は、その規模について「アイゼンハワー元大統領の州間高速道路の建設以来となる最大規模のインフラ投資」71と述べている。
インフラ投資雇用法は、老朽化した全米の交通インフラ(道路、橋、鉄道、港湾、空港等)の補修に主眼が置かれているが、同時に、公共交通機関へのゼロ・エミッション車両の導入や、EV充電施設の整備、クリーン電力の普及に向けた送電網整備、クリーン水素ハブへの投資など、クリーンエネルギー関連技術の普及に必要なインフラ整備へも重点的な投資を行う72。また、同法には、製造業の振興と雇用創出の観点から、国内調達の促進が盛り込まれている。同法の一部として成立したビルド・アメリカ、バイ・アメリカ法は、連邦政府のインフラ計画に用いられる全ての鉄鋼、工業製品、建設資材を米国内で生産することを義務付けており、2023年8月にその詳細を定めた最終規則が政権から発表された73。
インフラ投資雇用法の成立から2年の節目となる2023年11月、ホワイトハウスは、同法の成果を発表した。それによると、建設業の雇用者数は、バイデン大統領の就任(2021年1月)以降に67万人(月平均2万人)増加し、同年10月には1939年の統計開始以来最多を記録したという。中でも、高速道路・道路・橋梁建設業では、大統領就任以降、雇用が38,300人増加し、うち37,600人は同法成立後に増加したとして、同法が雇用増に寄与していることを強調した74。米国政府は、同法により、クリーンエネルギー関連も含むインフラ整備と国内建設業・製造業の振興、雇用の増加を通じて、長期的な成長のための基盤を築くことを目指している。
71 米国ホワイトハウスWebサイト参照(https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/02/07/remarks-of-president-joe-biden-state-of-the-union-address-as-prepared-for-delivery/![]() )。
)。
72 米国ホワイトハウスWebサイト参照(https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/05/BUILDING-A-BETTER-AMERICA-V2.pdf![]() )。
)。
73 米国ホワイトハウスWebサイト参照(https://www.whitehouse.gov/omb/briefing-room/2023/08/14/biden-harris-administration-releases-final-guidance-to-bolster-american-made-goods-in-federal-infrastructure-projects/![]() )。
)。
74 米国ホワイトハウスWebサイト参照(https://www.whitehouse.gov/briefing-room/blog/2023/11/15/job-gains-in-construction-after-two-years-of-the-bipartisan-infrastructure-law/![]() )。
)。
② インフレ削減法
2022年8月、気候変動対策や医療福祉、税収強化などに主眼を置いたインフレ削減法が成立した。同法は、気候変動対策へ約3,700億ドルを投資し、サプライサイド(民間企業等)とディマンドサイド(消費者等)への税額控除などを通じてクリーンエネルギーのコストを引き下げ、同分野への民間投資を加速させるとともに、重要なサプライチェーンを強化することを目的としている75。
サプライサイドへの支援形態は税額控除が中心であり、同法は、投資税額控除による初期投資支援と、生産量や販売量に応じ一定額を控除する生産税額控除によるランニングコスト支援で、ライフサイクル全体の投資促進を図っている。投資税額控除には、再生可能エネルギー事業への投資に対する税額控除や、クリーンエネルギー機器及び自動車(燃料電池、EV等)を製造又はリサイクルする施設の改修・拡大・新設に対する税額控除などがある。また、生産税額控除には、再生可能エネルギー発電の発電量に応じた税額控除や、適格部品(太陽光・風力発電用部品、インバーター、バッテリー部品、重要鉱物)を国内製造し販売した際に適用される税額控除、クリーン水素の製造に対する税額控除などがある。なお、再生可能エネルギー関連を始めとする一部の税額控除には、資材の国内調達優遇措置が設けられており、申請者は、鉄鋼などの部品につき一定以上国内製品を使用すると最大10%の追加税額控除を受けることができる。
ディマンドサイドへの支援措置には、EV等のクリーン自動車の購入に対する税額控除(以下、EV税額控除という)や、エネルギー効率改善のための住宅改修費用に対する税額控除、住宅用クリーンエネルギー機器の購入に対する税額控除などがある。
上述のEV税額控除について、対象車両を購入する消費者は、一車両当たり最大7,500ドルの税額控除を受けることができる。しかし、最大の税額控除を受けられる車両となるためには、「車両の最終組立てが北米域内で行われていること」、「バッテリー部品の一定割合が北米で製造又は組み立てられていること」、「バッテリーに含まれる重要鉱物の一定割合が、米国ないし米国とのFTA締結国で採取・加工されていること、又は北米でリサイクルされていること」という三要件を満たさなければならない(第II-1-3-3表)。
第Ⅱ-1-3-3表 EV税額控除の要件
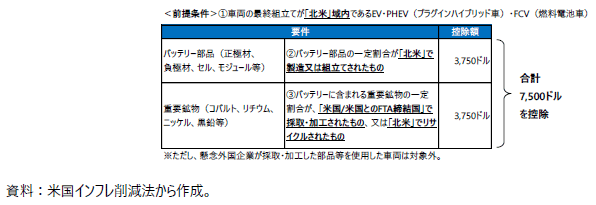
こうした、生産地や調達先等に関する厳しい要件は、複数の同盟国からの反発を呼ぶこととなった。EUのフォン・デア・ライエン欧州委員長は、2022年12月の演説で、「インフレ削減法は、不公正な競争を招き、市場を閉ざし、(中略)重要なサプライチェーンを分断するおそれがある」と非難した上で、米欧が緊密に連携し、クリーンエネルギー産業基盤を共同で強化する必要があると主張した76。また、EU、韓国は、2022年11月にEV税額控除等に対する政府意見書を米財務省へ提出するなどして米国側へ待遇の改善を求めた77。我が国も、有志国との連携の下で強靱なサプライチェーンを目指す全体戦略と整合的ではない等の内容からなる政府意見書を提出した。その後、我が国は2023年3月に「重要鉱物のサプライチェーンの強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下、日米重要鉱物サプライチェーン強化協定という)」を締結した。同協定は、EV用バッテリーの生産に不可欠な重要鉱物5種について、採取から加工に至るまでのサプライチェーンにおける貿易、環境、労働に関する日米協力を強化するものである。同協定を踏まえ、米財務省は、2023年3月に公表したガイダンスにおいて、日本をインフレ削減法上の「米国とFTAを締結している国」に位置付けた。これにより、日本国内で加工された重要鉱物も「バッテリーに含まれる重要鉱物の一定割合が、米国ないし米国とのFTA締結国で採取・加工されていること、又は北米でリサイクルされていること」との要件を充足することになった。
さらに、EV税額控除には、懸念外国企業からの部品及び重要鉱物を使用した車両を支援の対象外とする規定がある。具体的には、懸念外国企業が製造・組立てを行ったバッテリー部品を用いた車両は対象外となる。さらに、懸念外国企業が抽出・加工・リサイクルした重要鉱物を使用したバッテリーを搭載する車両も対象外となる。インフレ削減法によると、懸念外国企業には、SDNリスト(制裁リスト)に掲載されている者や、中国・ロシア・北朝鮮・イラン政府に所有若しくは支配され、又は同国政府の管轄若しくは指示に服する企業などが含まれている。
75 米国ホワイトハウスWebサイト参照(https://www.whitehouse.gov/cleanenergy/inflation-reduction-act-guidebook/![]() )。
)。
76 欧州委員会Webサイト参照(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_7487![]() )。
)。
77 JETRO Webサイト参照(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/11/62ef774d6cdb4401.html![]() )。
)。
③ CHIPS及び科学法
2022年8月、半導体生産支援と科学技術関連予算を柱とするCHIPS及び科学法が成立した。同法の半導体生産支援部分の歳出規模は約527億ドルであり、内訳は、半導体関連の設備投資などへの補助基金へ390億ドル、R&D基金へ110億ドルなどとなっている。米商務省は、米国内に少なくとも二つの最先端ロジック半導体工場の大規模クラスターを形成することや、現世代及び成熟ノード半導体の生産能力を向上させることなどを2030年までの目標として掲げており、2023年2月には最先端・現世代・成熟ノード半導体(後工程含む)に対する資金援助の申請受付を開始した78。同法の成立により、米国内における半導体関連の設備投資は好調である。米国半導体工業会(SIA)によると、これまでに全米で82の新たな半導体エコシステム・プロジェクト(半導体製造施設の新設や既存施設の拡張等)が発表され、民間投資額は3,170億ドルに上り、45,000人の新規雇用が生み出されたという79。
また、CHIPS及び科学法には、国家安全保障上のガードレール条項が盛り込まれている。同条項により、助成対象者は、懸念国(中国・ロシア・北朝鮮・イラン等)における半導体生産能力拡張や、懸念企業との共同研究などが制限され、違反した場合には助成金の返還が求められる。2023年9月、米商務省は、ガードレール条項に関する最終規則を発表し、その中で「製造拡大ガードレール」と「技術ガードレール」の詳細を規定した80(第II-1-3-4表)。
第Ⅱ-1-3-4表 CHIPS及び科学法のガードレール条項
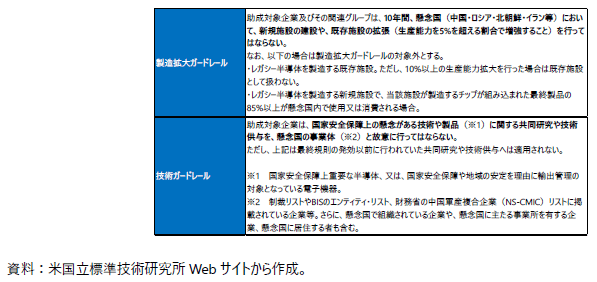
米国政府は、ガードレール条項によって、国家安全保障上重要な半導体や関連技術などの懸念国への流出を阻止するのみならず、同志国と半導体政策において連携することによって、グローバル・サプライチェーンの強靱性向上にも取り組んでいる。例えば、経済産業省と米商務省は、2023年5月に開催された「日米商務・産業パートナーシップ(the Japan-U.S. Commercial and Industrial Partnership : JUCIP)」において、より強靱な半導体エコシステムの構築に向けて連携することを確認した。両省は、日米共同タスクフォースのもと、技術開発及び人材育成協力に関するロードマップ策定に向けて一層連携すべく、CHIPS及び科学法によって米国に設立された国立半導体技術センター(NSTC)と、日本の技術研究組合最先端半導体技術センター(LSTC)間の協力を促進する81。
78 経済産業省(2023)『半導体・デジタル産業戦略』参照(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semiconductors_and_digital.pdf![]() )。
)。
79 米国半導体工業会(SIA)Webサイト(2024年3月20日現在)参照(https://www.semiconductors.org/the-chips-act-has-already-sparked-200-billion-in-private-investments-for-u-s-semiconductor-production/![]() )。
)。
80 米国立標準技術研究所Webサイト参照(https://www.nist.gov/system/files/documents/2023/09/22/09.22.2023%20-%20External%20Deck%20-%20Guardrails%20Final%20Rule.pdf![]() )。
)。
81 経済産業省「2023年5月27日報道資料」、(https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230526007/20230526007.html![]() )。
)。
(4) 欧州の動向
欧州委員会は2019年12月、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする(ネット・ゼロ)という目標実現に向けた成長戦略、欧州グリーン・ディールを発表した。フォン・デア・ライエン欧州委員長は記者会見の中で、「欧州グリーン・ディールは、一方では温室効果ガス排出量を削減し、もう一方では雇用を創出してイノベーションを促進させるものだ」と述べ82、脱炭素と経済成長の両立を標榜した。そして、2023年1月、欧州委員長は世界経済フォーラム年次総会(以下、ダボス会議という)で演説し、グリーン・ディール産業計画の構想を発表した。同計画は、ネット・ゼロ技術及び製品の競争力強化と気候中立への移行加速を目的としたものであるが、その一方で、中国の政府補助金や、米国インフレ削減法を始めとする同志国の巨額な産業補助金等への対抗が意図されたものと受け止められている。欧州委員長は、ダボス会議での演説の中で、日本やインド、英国、カナダ、米国等の国々がクリーン・テクノロジーへの投資を拡大していることを「地球にとっての朗報」と評価した一方、米国インフレ削減法のインセンティブ設計の一部に多くの懸念があると指摘し、「我々は、それぞれのインセンティブ・プログラムが公正で相互に補強し合うものであるよう努めるべきである」と訴えた83。
以下では、欧州委員会が発表したグリーン・ディール産業計画を中心に、EUや加盟国の代表的な産業政策を概説する。
82 欧州委員会Webサイトから引用(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_19_6749![]() )。
)。
83 欧州委員会Webサイト参照(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_232![]() )。
)。
① グリーン・ディール産業計画
2023年2月、欧州委員会は、グリーン・ディール産業計画の詳細を示した政策文書を公表した。前述したとおり、同計画は、欧州の気候変動目標を達成するために必要なネット・ゼロ技術及び製品について、EUでの生産能力を拡大するための環境を整備することを目的としており、財源には既存の復興基金(未利用の融資2,250億ユーロと新規補助金200億ユーロ)などが活用される。第II-1-3-5表のとおり、同計画は、「規制環境の整備」、「資金調達の迅速化」、「人材育成」、「貿易と強靱なサプライチェーン」の四つの柱で構成されている84(第II-1-3-5表)。
第Ⅱ-1-3-5表 グリーン・ディール産業計画の概要
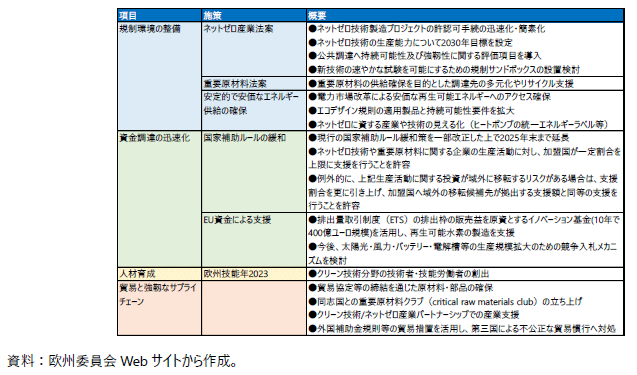
まず、一つ目の項目である規制環境の整備について概説する。欧州委員会は、2023年3月にネット・ゼロ産業法案と重要原材料法案をそれぞれ発表した。
ネット・ゼロ産業法案は、規制環境の整備や許認可の迅速化などを通じて、ネット・ゼロ技術のEU域内での生産能力を高めることを目的としている。同法案は、2024年2月にEU理事会と欧州議会との間で暫定的な政治合意に達しており、今後、正式な採択プロセスに進む予定である。暫定的な政治合意の内容によると、許認可の迅速化などの支援を受けることができる「ネット・ゼロ技術製造プロジェクト」の対象となるネット・ゼロ技術に、太陽光・太陽熱発電技術、陸上風力・洋上再生可能エネルギー技術、バッテリー・蓄電技術、ヒートポンプ・地熱技術、電解槽・燃料電池を含む水素技術、持続可能バイオガス・バイオメタン技術、CCS技術、グリッド技術などが指定された。EUは、2030年までにネット・ゼロ技術の域内生産能力を年間導入需要の40%まで高めることを目標としている。また、同法案では、公共調達に関する要件も規定された。具体的には、ネット・ゼロ技術に関する公共調達の選定基準に「持続可能性及び強靱性への寄与」という評価項目を導入することが盛り込まれている。この評価項目のうち、環境面での持続可能性に貢献することについては義務的な必要最低要件として規定されている一方、強靱性に関する要件は、特定のネット・ゼロ技術(又はその部品)について単一の域外国への依存度が50%を超える場合に適用される85。
重要原材料法案は、重要原材料の安全かつ持続可能な供給を確保することを目的としている。EUは、重要原材料の多くを中国などからの輸入に依存しており、サプライチェーンの多様化とリスクの軽減を急ぐ。同法案は、既存の重要原材料(Critical Raw Materials)リストを更新し、さらに、グリーンやデジタル、防衛、宇宙分野等の重要技術に不可欠で、将来的な供給リスクを抱えるものを戦略的原材料(strategic raw materials:SRM)として選定する。戦略的原材料については、2030年までにEU域内生産能力の確保と供給元の多様化を実現するために、域内年間消費量の最低10%を域内で採掘し、同40%を域内で加工し、同25%86を域内でリサイクルした原材料で賄うという目標が設定されている。さらに、同法案に基づき戦略的原材料の安定供給に資するとして認定された戦略的プロジェクトは、公益を有するものと見なされ、許認可期間の短縮や資金調達の支援などを受けることができる87。同法案も、ネット・ゼロ産業法案と同様、2023年11月にEU理事会と欧州議会との間で暫定的な政治合意に達しており、今後、正式な採択プロセスに進む予定である。
次に、二つ目の項目の資金調達の迅速化のうち、国家補助ルールの緩和について概説する。欧州委員会は2023年3月、2025年末までの一時的な措置として、EUの国家補助ルールを緩和する「暫定危機・移行枠組み」を採択した。EUは、加盟国間の競争環境を不当にゆがめる可能性があるとして、加盟国による特定の企業に対する国家補助を原則禁止しているが88、この枠組みの採択により、加盟国は、ネット・ゼロ技術や重要原材料に関する企業の生産活動に対し支援を行うことができるようになる。さらに、これらの生産活動に関する投資が域外に移転するリスクがある場合、加盟国は、支援割合を更に引き上げ、企業に対し域外の移転候補先で得られる支援額と同等の支援を行うこともできる89。つまり、同枠組みで規定された条件を満たせば、加盟国は、米国のインフレ削減法のインセンティブに匹敵する支援を行うことが可能になったということである。
最後に、貿易と強靱なサプライチェーンについて触れる。欧州委員会は、2023年3月に公表した政策文書の中で、消費国と資源国をつなぎ、重要原材料の安全で持続可能な供給を促進するため、「重要原材料クラブ」を設立すると発表した。この取組を通じ、EUは、パートナーと共に、「信頼性が高く、商業ベースで、透明性が高く、環境に配慮された重要原材料」の供給を促進する90。取組案では、サプライチェーンにおける労働者の権利と社会的に責任ある慣行の促進において同志国と協力することや、国境を越えて循環型・持続可能な経済を推進していくことなどが挙げられている。
84 欧州委員会Webサイト参照(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_510![]() )。
)。
85 EU理事会Webサイト参照(https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/06/net-zero-industry-act-council-and-parliament-strike-a-deal-to-boost-eu-s-green-industry/![]() )。
)。
86 欧州委員会の提案では15%であったが、その後、2023年11月のEU理事会と欧州議会の政治合意により25%へ修正された。
87 欧州委員会Webサイト参照(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661![]() )。
)。
88 欧州委員会Webサイト参照(https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/03/9715e56c1143f6ca.html![]() )。
)。
89 JETRO Webサイトから引用(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1563![]() )。
)。
90 欧州委員会(2023)「COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A secure and sustainable supply of critical raw materials in support of the twin transition」。
② 欧州半導体法
欧州委員会は、2022年2月にEU域内の半導体エコシステム強化を目的とした欧州半導体法を発表し、翌2023年9月に施行した。域内半導体産業への総額430億ユーロの官民投資により、EUの半導体分野における世界市場シェアを現在の10%から2030年までに20%以上へ引き上げる91。
同法は、EU及び加盟国による研究開発・イノベーション分野への投資に加え、EU域内初(first-of-a-kind)の半導体生産施設と認定された施設の計画、建設、稼働に対する迅速な審査などの優遇措置を与える。さらに、加盟国と欧州委員会は、半導体供給状況の監視と危機への対応において協働するための調整メカニズムを構築し、危機時には特定の域内生産施設に対し半導体などの増産と域内への優先供給を命じることができる。
91 欧州委員会Webサイト参照(https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/07/25/chips-act-council-gives-its-final-approval/![]() )。
)。
③ 加盟国が実施するEV補助金制度
EU加盟国の中でも、自動車産業が盛んなドイツとフランスでは、EV購入に対する補助金が導入されてきた。
ドイツ連邦政府は、2016年にEV等への買い替え促進を目的とした環境ボーナス(Umweltbonus)制度を導入した。同制度は、EV等を購入する個人や企業等に対し、連邦政府と自動車メーカーが共同で補助金を交付するものであったが、財源確保が困難になったことから2023年12月に終了となった。
フランス政府は、2023年9月にEV補助金制度を改正し、EVの製造・輸送過程におけるCO2排出量をベースに算定される環境スコアが60ポイントを超えるモデルに対象車を限定した92。環境スコアの算出に必要なEV製造過程のCO2排出量は、国・地域ごとに基準値が設定されている。環境スコアの条件を満たすEVの購入者は、最大5,000ユーロ(低所得者は最大7,000ユーロ)の補助金を受けることができる。
92 JETRO Webサイト参照(https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/09/eae49de44139c4f2.html![]() )。
)。
(5) 我が国の動向
① 戦略分野国内生産促進税制
我が国は、令和6年度税制改正の大綱において戦略分野国内生産促進税制を創設することを決定した。これは、戦略分野のうち、総事業費が大きく、特に生産段階でのコストが高いものについて、生産・販売量に比例した法人税額控除を行うものである。具体的には、EVやグリーンスチール、グリーンケミカル、持続可能な航空燃料(SAF)、半導体などが対象となる。単位当たりの控除額は対象物資によって異なるが、例えばEVでは、1台当たり40万円となっている(第II-1-3-6表)。また、本税制の対象分野のうちグリーントランスフォーメーション(GX)分野については、GX経済移行債による財源が活用される93。
第Ⅱ-1-3-6表 戦略分野国内生産促進税制における対象物資ごとの単位当たり控除額
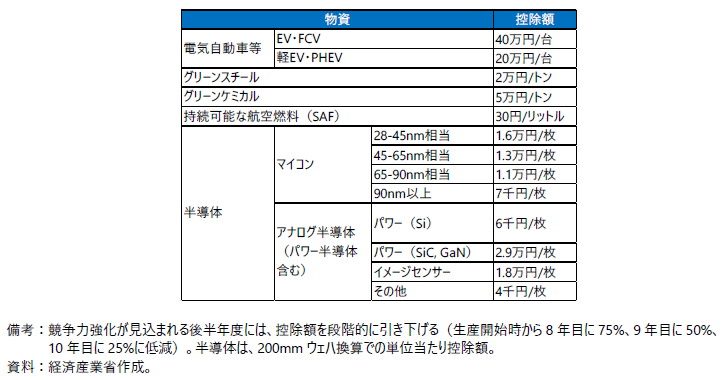
93 経済産業省「令和6年度(2024年度)経済産業関係 税制改正について」、(https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2024/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf![]() )。
)。
② 半導体の生産支援措置
2021年12月、高性能な半導体の生産施設等への投資を促進するための措置を定めた「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律」が成立し、翌2022年3月に施行された94。
同法に基づく支援を希望する半導体の製造事業者等は、経済産業大臣宛に「特定半導体生産施設整備等計画」を申請する。そして、同計画が高性能な半導体の安定的な生産確保に資すると認定されると、同事業者は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて助成金の交付を受けることができる。申請及び認定の対象となる計画の半導体は、演算を行う半導体(ロジック半導体)と記憶を行う半導体(メモリ半導体)となっている(第II-1-3-7表)。また、いずれの半導体に係る計画についても、10年以上継続生産することや、需給が逼迫した場合に増産に関する取組を行うことなどが求められる。
第Ⅱ-1-3-7表 半導体生産支援措置の申請・認定対象となる計画
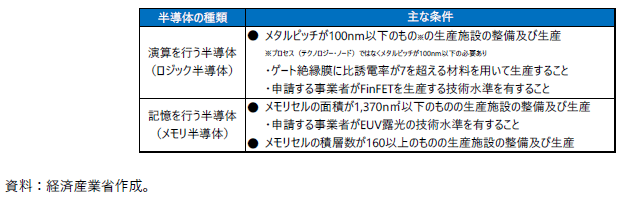
94 経済産業省「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(特定半導体生産施設整備等関係)」、(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/laws/semiconductor.html![]() )
)
③ 重要物資の安定的な供給の確保に関する制度
2022年5月に成立した経済安全保障推進法には、重要物資の安定的な供給の確保に関する制度(同法第2章)が盛り込まれている。これは、国民の生存に必要不可欠な又は広く国民生活・経済活動が依拠している重要な物資について、特定重要物資として指定し、その安定供給確保に取り組む民間事業者等を支援することを通じて、特定重要物資のサプライチェーンの強靱化を図るものである95。
2022年12月、特定重要物資として、抗菌性物質製剤、肥料、永久磁石、工作機械・産業用ロボット、航空機の部品、半導体、蓄電池、クラウドプログラム、天然ガス、重要鉱物及び船舶の部品の11物資が政令で指定された。また、2024年2月、新たな特定重要物資として先端電子部品(コンデンサー及びろ波器)が政令で指定され、既に指定されている重要鉱物の鉱種にウランが追加された。
民間事業者は、特定重要物資等の安定供給確保のための取組に関する計画を作成し、物資所管大臣の認定を受けることができる。認定を受けた事業者は、取組の実施に当たり必要な資金について、安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人を通じた助成や、長期・低利の財政融資を原資とした指定金融機関による融資などを受けることができる。なお、助成率の上限は事業ごとに異なるが、例えば、半導体関連の設備投資と技術開発は3分の1、蓄電池の設備投資は3分の1で技術開発は2分の1、重要鉱物は2分の1となっている96。
95 内閣府「重要物資の安定的な供給の確保に関する制度」、(https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/supply_chain.html![]() )。
)。
96 経済産業省「経済安全保障政策」、(https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/index.html![]() )。
)。
2.産業政策における多国間協力・ルール形成の必要性
(1) 産業補助金が貿易にもたらす影響
各国で産業政策が活発化する中、市場に大きな影響を与えるような大国間で産業補助金が交付された場合、両国の貿易や国際価格にどのような影響が生じ得るかについて、単純な経済学的仮定の下で考察していく。
完全競争市場の下、大国であるA国とB国の間で、財Cに対して産業補助金を交付した場合を想定する。A国とB国は自由貿易が行われる国際市場価格に影響力を持ち、両国の生産活動に応じて財Cの国際価格も変動するものと仮定する。また、財Cの需要曲線は右下がり、供給曲線は右上がりの形状であるとする。
今、A国とB国が、財Cについてそれぞれ自国において同じ形状の需要曲線と供給曲線に直面していると仮定すると、同一の国際価格の下で、自国内での需要と供給が一致するため、自由貿易が行われる環境下であったとしても、A国とB国との間で互いに貿易は発生しないこととなる。(第II-1-3-8図)。
第Ⅱ-1-3-8図 初期状態におけるA国とB国の市場均衡価格と生産量
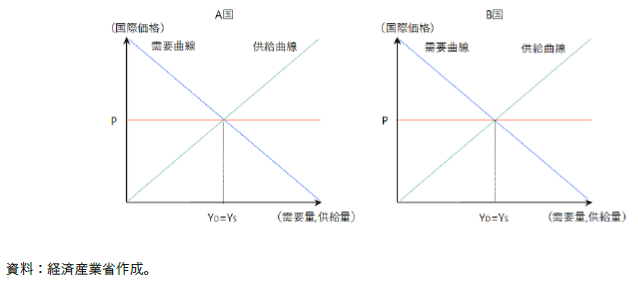
ここで、B国が、財Cを生産する自国企業に対して、生産一単位当たりの費用を補填する形の産業補助金を交付したとする。これにより、B国の生産力が高まり(供給曲線が右にシフト)、国際市場における財Cの供給量が増えた結果、国際価格がPからP*まで下落する。この結果、国際価格P*の下でA国では超過需要が、B国では超過供給がそれぞれ発生し、B国はA国に対し財Cを輸出する状況が生ずることとなる(第II-1-3-9図)。
第Ⅱ-1-3-9図 B国が自国企業に産業補助金を交付した場合の国際価格と貿易量の変化
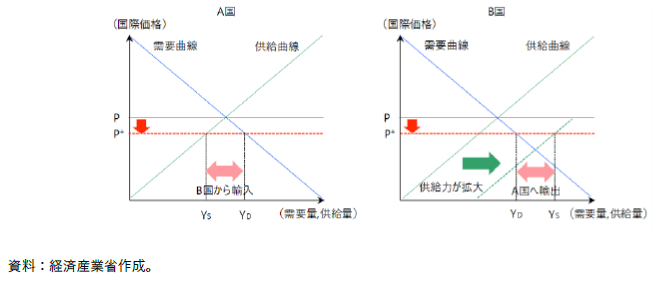
こうした状況下で、A国が、財Cを生産する自国企業に対して、生産一単位当たりの費用を補填する形の産業補助金を交付した場合を考察する。産業補助金によりA国の生産力が高まり、国際価格はP**まで下落する。これにより、再びA国とB国共に自国内で需要と供給が一致する状態へと回帰することとなる(第II-1-3-10図)。
第Ⅱ-1-3-10図 B国に加えA国も自国企業に産業補助金を交付した場合の国際価格と貿易量の変化
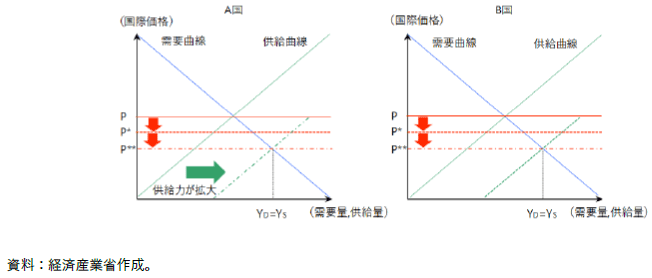
上述のとおり、国際市場価格に影響力を持つ大国間で産業補助金が交付される場合、生産力の拡大に起因する国際価格の下落が生じる。そして、どちらか一方が自国に産業補助金を出し、それを受けてもう一方も自国に産業補助金を出すような状況が生まれれば、供給力の拡大に伴い、国際価格が下落するという状況を生み出す。また、産業補助金の交付には財政支出が伴うため、企業又は国民の負担によってあがなわれることとなる。
ただし、サプライチェーンの維持・強化や、カーボンニュートラル社会の実現といった供給多元化や外部不経済を是正するものとして交付される産業補助金は、各国からの共通理解を得うるものであり、当該産業補助金に係る何らかの合意形成が当事国間で事前になされていれば、貿易摩擦に発展する懸念は低減できると考えられる。
一方で、持続可能性等に配慮しない国によって不当に安価な製品が供給されるような、公平な競争条件が確保されない状況は是正されるべきである。ここで、第II-1-3-9図で示した状況が、B国が不当に安価な製品を供給することによって生み出されたものであったとした場合、例えばインセンティブの活用により需要者側に働きかけることによって貿易価格の下落を伴うことなく、公平な競争条件を確保することも可能と考えられる(第II-1-3-11図)。
第Ⅱ-1-3-11図 公平な競争条件の確保の経済学的な考え方(イメージ)
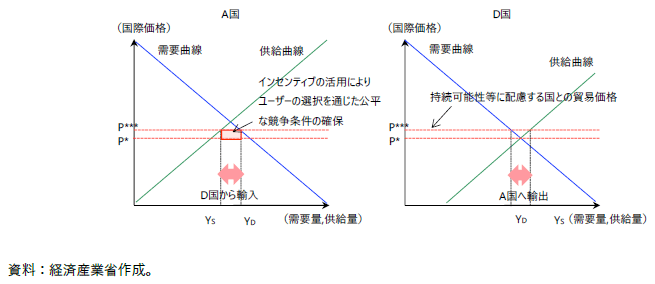
(2) 多国間協力とルール形成の必要性
上述のとおり、大国間の産業補助金競争は、両国の貿易や国際価格に影響を与えることを確認した。しかし、気候変動など民間企業だけでは解決できない社会的課題への対応や、地政学的リスクの高まりに伴う重要サプライチェーンの確保などの必要性から、各国政府による産業補助金の重要性が強く認識され、今後世界において産業政策を重視する傾向はますます強まっていくと見られる。
こうした国際情勢の中、我々はまず、一部の国が巨額の国家補助や政府調達、標準策定などで非市場主義的な政策や慣行を展開していることに目を向けなければならない。こうした政策は、一部の国の企業が不当に安価な製品を供給して、国内外の市場を席巻し、世界への影響力を高めることを可能にするため、結果として各国が一部の国へ過度に依存せざるを得なくなることに繋がる。その結果、そのような一部の国が経済的依存関係を武器化することも可能になる。これに対し、各国が自国産業保護を目的とする産業政策を導入するようになると、産業補助金競争により安定した貿易秩序が損なわれる可能性がある。
このような状況を回避するためには、ルールに基づく自由で公正な貿易投資体制を堅持することが重要である。各国で実施される産業政策が貿易歪曲的なものであってはならず、WTOを始めとしたルールの下、公平な競争条件(レベルプレイングフィールド)の確保に取り組む必要がある。非市場的な産業政策が貿易に与える悪影響について、幅広い国々と問題意識を共有し、多国間の取組を進めることが必要という認識の下、G7やOECD、WTO、日米EU三極等様々な国際フォーラにおいて、公平な競争条件の確保に向けた議論がなされている。【各議論の詳細は、第III部第1章を参照。】
また、設備投資や研究開発、重要鉱物開発といったサプライサイドへの支援のみならず、インセンティブなどを工夫したディマンドサイドへの働きかけは、不当に安価な製品に対する公平な競争条件の確保に寄与し得る。そうした観点から、今後、我が国政府は、価格以外の、持続可能性や信頼性等の原則やそれに基づく脱炭素、安定供給、サイバーセキュリティ等の要件をディマンドサイド支援(補助金等)で評価すること等を通じて、公平な競争条件を確保することを目指す。
同時に、一部の国への過剰依存の軽減や、保護主義の連鎖の回避に向け、国際連携を更に進めていくことが不可欠である。サプライチェーンの強靱化に向け、近年、我が国政府は、第1項で紹介した「日米重要鉱物サプライチェーン強化協定」や、「IPEFサプライチェーン協定97」への署名などに取り組んできた。経済安全保障や環境、人権などへ世界の関心が集まっていることは本章第1節及び第5節で述べているとおりであるが、これらは「非貿易的関心事項」と呼ばれ、近年、各国政府の政策に織り込まれるようになってきている。今後は、戦略物資を中心として、米欧を始めとする同志国と一体となって、上述した持続可能性や信頼性等の原則を評価する応募資格・評価基準などを通じて、供給力強化及び需要創出の好循環に向けた産業政策の協調を図るための議論を主導していくことが求められる。既に、米国とは2024年4月に開催された日米商務・産業パートナーシップ(JUCIP)閣僚会合や、インフレ削減法と日本のGX推進戦略のシナジーを最大化するための閣僚政策対話を通じて、また、欧州委員会とは2024年5月に開催された日EUハイレベル経済対話で立ち上げた「透明、強靱で持続可能なサプライチェーン・イニシアティブ」を通じて、こうした政策協調に向けた議論を進めている。
さらに、将来的には、AZEC等の国際枠組みやグローバル・サウス向けの政策にこうした議論を適用し、連携の輪を広げていくことが望ましい。我が国は、グローバル・サウス諸国とも各種政策対話等を通じて政策協調を図ることで、同諸国におけるレベルプレイングフィールドを形成しつつ、厳しい国際政治経済情勢の中で安定した貿易秩序を維持していくことを目指す。
97 経済産業省「2024年2月1日報道資料」、(https://www.meti.go.jp/press/2023/02/20240201002/20240201002.html![]() )。
)。