第1節 主要国における輸入の特定の国への依存の状況
今後、人口の減少が見込まれる我が国経済が持続的な成長を維持するためには、グローバルな成長の取り込みが必要不可欠である一方、そこに潜むリスクに対して適切に対応を行っていく必要がある。本章では、G7全体や米独と比較しても我が国の輸入は特定の国への依存の傾向が強く、調達先の分散化を進めていくことが急務となっていること、我が国グローバル企業の調達においても、特定の国への依存を低減させることが課題となっていること、さらにはグローバル・バリューチェーン全体でみてリスク評価を行うことが必要であることについて示す。
グローバルな成長の取り込みに関しては、我が国企業の更なる海外展開の推進に向けて、我が国企業と海外市場との密接な関わりの実態や、企業の実情に沿った海外展開の課題について取り上げる。また、競争力のある我が国製造業企業は、グローバルに展開し、我が国の雇用や投資に貢献しており、無形資産等を活用しながら、更なる成長拡大を実現していること、中堅企業を含む国内企業の競争力を強力に後押しし、グローバルな競争に勝ち抜ける企業を育成することが重要であることなどを示す。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、世界規模でサプライチェーンの寸断や混乱が生まれ、グローバル化の流れとともに調達先を特定の国に集中させてきたことの問題が露呈した。こうした状況を受けて、重要物資を始め、サプライチェーンを強靱化する動きが活発化しつつあるものの、現在でもなお、調達先の特定の国への依存の状況は続いている。加えて、近年では、一部の国において、こうした経済依存状況を悪用し、他国の外交政策及び国内政策並びにその立場を損なうことを企図するような行為、いわゆる経済的威圧と呼ばれる行為が多発しており、調達先の特定の国への依存の状況の精査やそれを踏まえた取組の加速が急務となっている。
そこで本節では、貿易統計でHS6桁品目レベルの2022年通年の輸入額のデータを用いて、G7及び米国、ドイツ、我が国における輸入の特定の国への依存の状況について確認していく。まず、輸入の特定の国への依存を把握する手法について解説する。集中度を表す指標であるハーシュマン・ハーフィンダール指数(以下、HHIという。)を用いて、HS6桁品目ごとに輸入の特定の国への依存状況について把握する。本節において分析の対象とする品目は、HS2桁01~24を除いたいわゆる鉱工業製品とした。HHIによる輸入集中度とは、品目ごとにおける各国からの輸入シェアの二乗和を100で除して算出したものである。ここで示しているHHIは、特定の国に完全に依存していれば指数は100となり、輸入国の分散が進むほど値が0に近づくものとしている。例えば、HHIが50を上回ると、輸入シェアが過半の国が必ず存在していることを示唆しており、HHIが25を下回ると、輸入シェアが過半の国は存在せず、少なくとも4か国以上の輸入先が存在することを示唆している。
第II-2-1-1図は、G7全体でみた品目別の輸入のHHIと、米国、ドイツ、我が国における品目別の輸入のHHIの分布を示したものである。
第Ⅱ-2-1-1図 主要国におけるハーシュマン・ハーフィンダール指数の分布
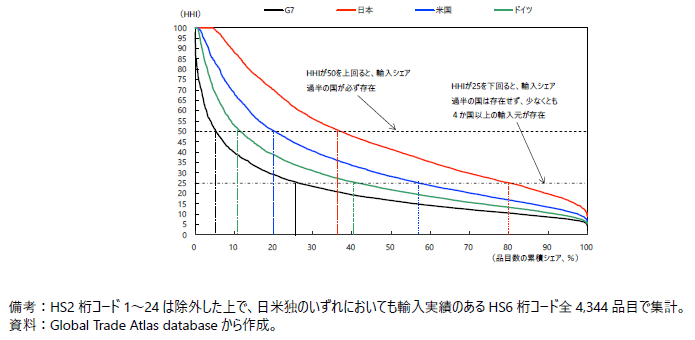
G7全体で見た品目別の輸入のHHIの分布208を見ると、HHIが50を超える品目は全体の5%程度となっており、これらの品目ではG7全体の輸入におけるシェアが50%を超える国が必ず存在していることを示している。国別に見ると、HHIが50を上回る品目はドイツでは1割程度、米国では2割程度となっているが、我が国では4割近い品目となっており、特定の国への集中度が高い状況にある。一方、G7では、全体の約4分の3の品目でHHIが25を下回っており、輸入シェアが過半を超える特定の国は存在せず、少なくとも4か国以上の輸入先があることを示している。国別に見ると、HHIが25を下回っている品目はドイツで6割程度、米国で4割程度となっているが、我が国では2割程度となっており、米独と比べても輸入先の分散が十分な品目が少ないことを示している。
第II-2-1-2図は、輸入シェアの50%以上を特定の国に依存している品目の数を国別に集計したものである。
第Ⅱ-2-1-2図 輸入シェアが50%以上を特定の国・地域に依存している品目の数(国別に集計したもの)
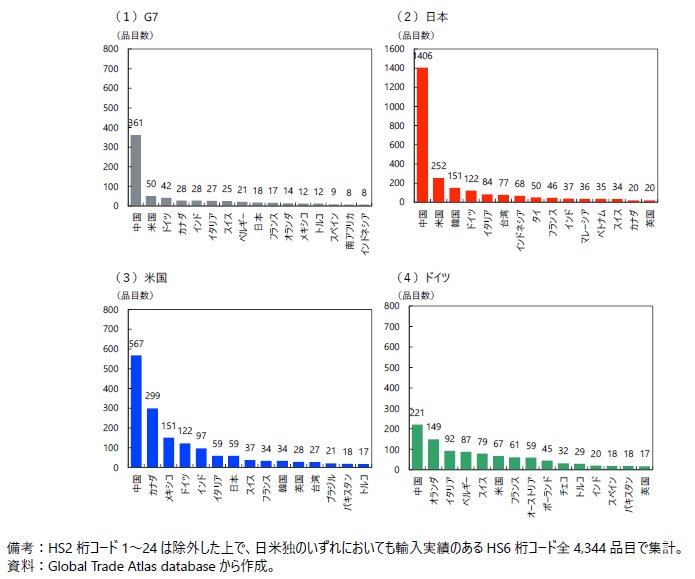
G7全体では中国が突出して多く、米国、ドイツ、カナダ、インドと続いている。我が国では中国が突出して多く、米国、韓国、ドイツ、イタリアと続いている。米国では中国が最も多く、カナダ、メキシコ、ドイツ、インドと続いている。ドイツでは中国が最も多く、オランダ、イタリア、ベルギー、スイスと続いている。
続いて、HHIが50を超える品目の数をHS2桁コードで集計したものが第II-2-1-3図である。
第Ⅱ-2-1-3図 HHIが50を超える品目の特徴(HS2桁ベースで集計したもの)
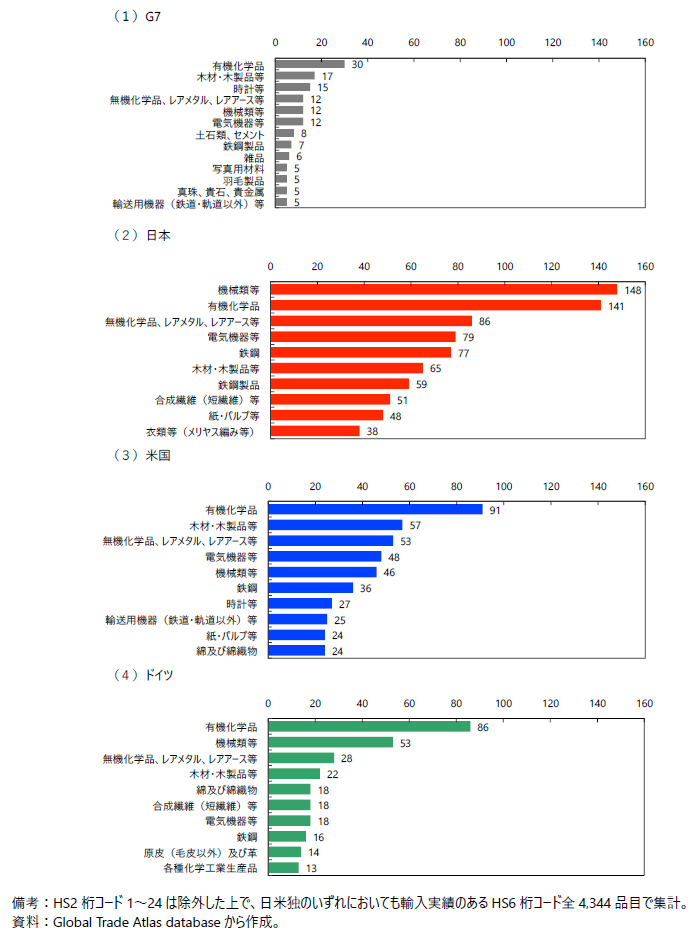
G7全体では有機化学品(HSコード29)が最も多くなっており、この傾向は米国、ドイツでも同様となっている。一方、日本では、機械類(HSコード84)が最も多くなっており、次いで有機化学品となっている。ドイツでも機械類は有機化学品に次いで多くなっている。また、日米独ともに3番目に多い品目としてレアメタル・レアアースを含む品目群(HSコード28)が挙がっている。また、日米では電気機器(HSコード85)や鉄鋼(HSコード72)も特定の国への依存度が高い品目が多くなっている。
以上をまとめると、G7全体や米独と比較しても我が国の輸入は特定の国への依存の傾向が強いこと、シェアが過半を占める品目数が多い国を見ると、日米独のいずれにおいても中国が最も多いこと、HS2桁分類で品目の特徴を見ると、有機化学品や機械類、レアメタル・レアアースを含む品目群に加え、電気機器類や鉄鋼でその傾向が強いことが分かった。米独と比べ、我が国は中国に対する輸入依存の傾向が強いように見受けられるが、一般論として、二国間で経済規模が大きいほど、また二国間の距離が近くなるほど、両国間の貿易量は大きくなる傾向にあることには留意が必要である。また、特定の国への依存の高い品目においても、その途絶が必ずしも自国の経済・社会活動に負の影響をもたらすとは言い切れないものも存在する点にも留意が必要である。本節では、輸入の特定の国への依存の状況に焦点を当てたが、次節では、我が国グローバル企業の調達における特定の国への依存の実態と課題について、アンケート調査結果を踏まえながら見ていくこととする。
208 HHIは、各国からの輸入シェアの二乗和を100除して算出したものであることを解説したが、この定義上、日米独のHHIはG7全体のHHIと比べて、HHIの算出に用いる国の数が1か国(自国分)少なくなり、この要因でG7全体のHHIは各国で算出したHHIよりも値が下振れることに留意が必要である。