第2節 デリスキングという潮流の中で求められる我が国企業の対応と課題
前節では、主要国における輸入の特定の国への依存の状況について見てきた。本節では、株式会社東京商工リサーチが実施した「令和5年度我が国企業の海外展開の実態及び課題に係るアンケート調査」209の結果に基づき、日本国内のみならず我が国企業のグローバルな事業活動の中で、調達の特定の国への依存の実態を把握するとともに、依存度低減の取組や課題などについて見ていく。
209 アンケート実施期間:2024年1月~2024年2月。調査対象:東京商工リサーチのデータベースの中から、日本に所在する海外現地法人を持つ企業(製造業、卸・小売業)を抽出。調査方法:配布・回収とも郵送。発送:7,280社、有効回答数:1,104社、回収率:15.2%。
1. 海外展開を行う我が国企業の置かれた状況と課題
(1) 調達に関する特定の国・地域への依存の状況
まず、我が国企業(海外現地法人を有する製造業と卸・小売業)の調達依存度の高い国・地域については、中国が4割強と最も多く、その後に大きな差が開いてASEAN6(タイ、インドネシア、フィリピン、マレーシア、ベトナム、シンガポール)、NIEs3(韓国、台湾、香港)が続く。また、「特定の国・地域への依存度が高いものは無い」と回答した企業も2割強存在している。調達依存度が高いと回答した国・地域ごとの依存割合については、中国に依存している企業では依存割合が3割以上の企業が約6割となっており、ASEAN6・NIEs3のそれと比較して大きいことが見てとれる(第II-2-2-1図)。
第Ⅱ-2-2-1図 調達依存度の高い国・地域と依存割合
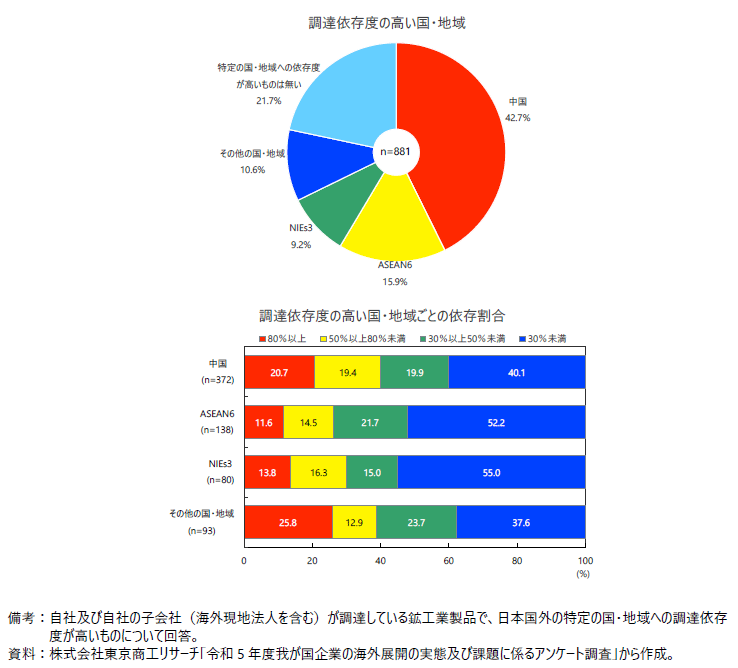
調達依存度が高いと回答した国・地域において、どの業種からの調達が多いかについては、「その他の国・地域」を除くといずれの国・地域に関しても金属製品製造業が1位となっている。また、台湾や韓国を含むNIEs3からの調達では、電子部品・デバイス・電子回路製造業も金属製品製造業と同率 (17.7%) で1位となっている。2位以下の特徴としては、中国からの調達では繊維工業 (12.6%) と電子部品・デバイス・電子回路製造業 (11.5%) が、ASEAN6からの調達では輸送機械器具製造業 (11.6%) が、NIEs3からの調達では鉄鋼業 (12.7%) と卸・小売業 (10.1%) が、それぞれ10%を超えている(第II-2-2-2表)。
第Ⅱ-2-2-2表 調達依存度の高い国・地域別にみた調達先上位5業種
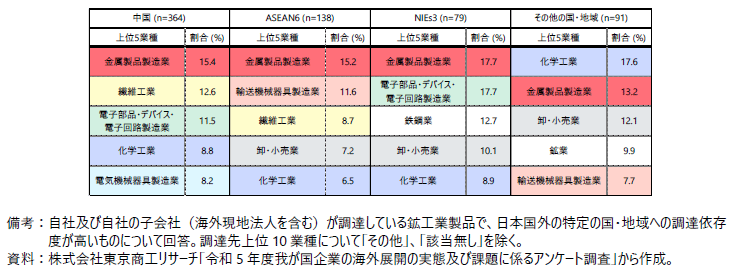
なお、調達依存度の高い国・地域にかかわらず、我が国企業の業種・従業員規模別にどの業種からの調達が多いかを見てみると、製造業では、従業員規模に比較的関係なく金属製品製造業が多く、従業員規模が大きくなるにつれて電子部品・デバイス・電子回路製造業、化学工業、輸送機械器具製造業が増加する一方で繊維工業は減少する傾向が見てとれる。卸・小売業では、従業員規模による調達先業種の変化がより顕著であり、従業員規模が大きくなるにつれて繊維工業、電気機械器具製造業、化学工業が増加する一方で同業種である卸・小売業からの調達は減少する傾向が見てとれる(第II-2-2-3表)。
第Ⅱ-2-2-3表 我が国企業の業種・従業員規模別にみた調達先上位10業種
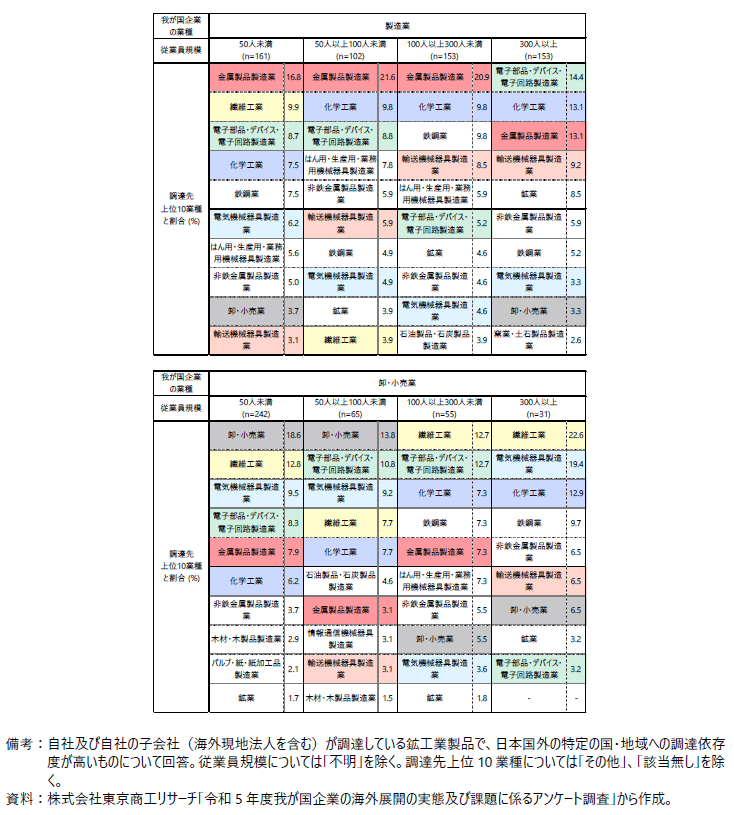
次に、調達依存度が高いと回答した国・地域において、我が国企業はどのような財を調達しているのかを見ていく。まず、調達依存度の高い国・地域ごとでは、いずれの国・地域でも生産財(鉱工業用生産財とその他用生産財)の占める割合が大きく、中国ではほかの国・地域に比べて資本財、建設財、消費財(耐久消費財と非耐久消費財)の占める割合が大きくなっていることが見てとれる(第II-2-2-4図)。
第Ⅱ-2-2-4図 調達依存度の高い国・地域別にみた調達財の種類
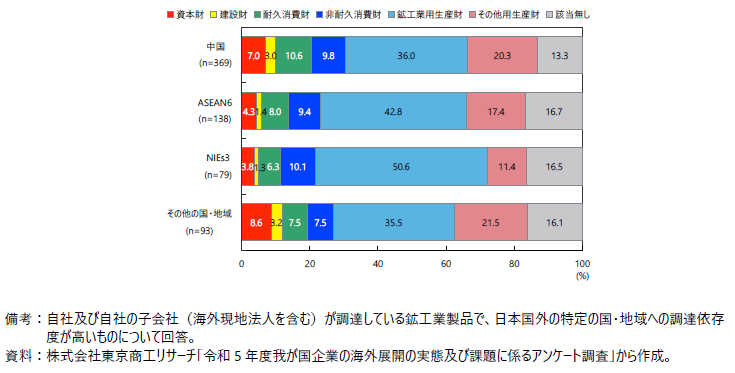
なお、調達依存度の高い国・地域にかかわらず、我が国企業の業種・従業員規模別での調達財を見ていくと、まず業種別については製造業では鉱工業用生産財が、卸・小売業では消費財(耐久消費財と非耐久消費財)の占める割合が大きくなっている。次に従業員規模別では、製造業と卸・小売業ともに従業員規模が大きくなるほどその他用生産財の占める割合が減少し、卸・小売業では更に資本財の占める割合が増加していく傾向が見てとれる(第II-2-2-5図)。
第Ⅱ-2-2-5図 我が国企業の業種・従業員規模別にみた調達財の種類
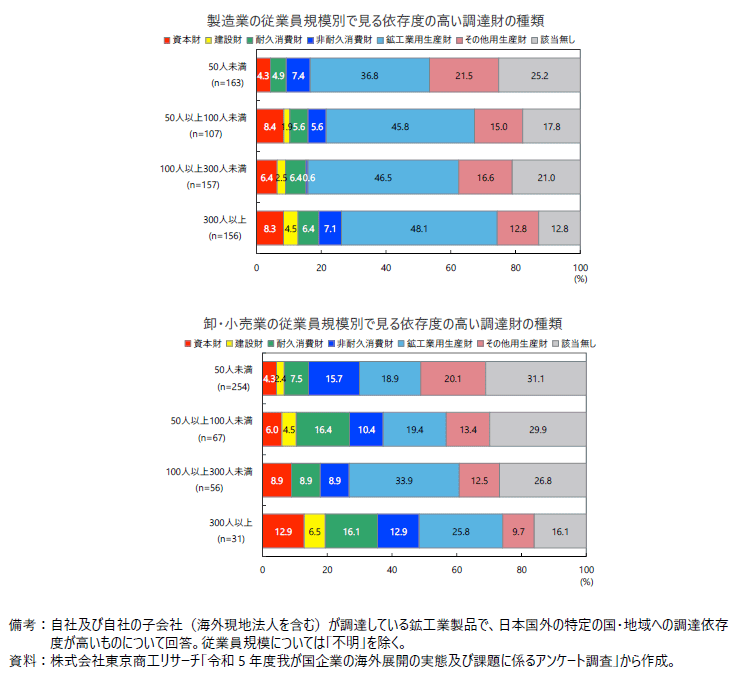
調達依存度が高いと回答した国・地域ごとに、どのような資本関係・支配関係の企業から調達している割合が大きいかを見ていくと、いずれの国・地域でも関連会社以外の企業からの調達が半分以上を占めている。ただし、ASEAN6では関連会社の比率も4割強となっており、我が国企業との資本関係・支配関係を有する企業が集積していることがうかがえる(第II-2-2-6図)。
第Ⅱ-2-2-6図 調達依存度の高い国・地域別にみた調達先企業の種類
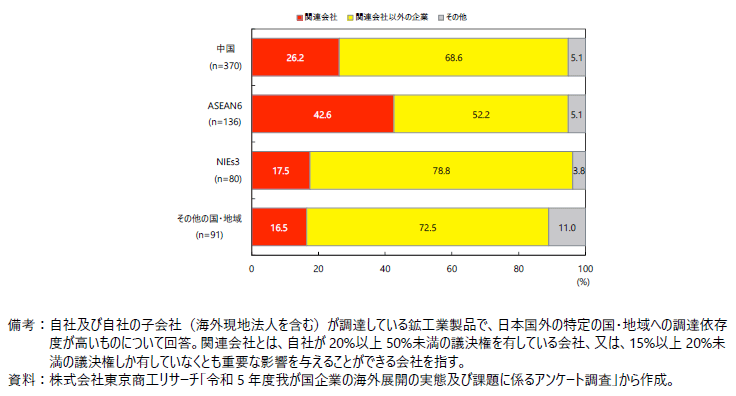
次に、調達依存度が高いと回答した国・地域について、我が国企業がどのようなリスクを具体的に認識しているかについて見ていく。中国については、「国家間等での緊張の高まり」(69.3%) 、「米中貿易摩擦」(52.9%) 、「貿易制限・関税」(50.3%) などが多く選ばれており、いずれも全ての国・地域の中で突出している。また、「不安定な政治体制」(19.8%) 、「人権問題」(11.5%) 、「強制的技術移転」(6.1%) の回答割合は中国の中では相対的に小さいものの、ほかの国・地域と比べると回答割合が高くなっている。ASEAN6については、「自然災害」(29.5%) 、「貿易制限・関税」(22.3%) 、「不安定な政治体制」(19.4%) 、「輸送・交通インフラ不全」(18.0%) などが多く選ばれているが、「自然災害」を除いてほかの国・地域と比べて突出している項目は見受けられず、それと同時に、「特にない」(24.5%) と回答した割合がほかの国・地域と比べて最大となっており、相対的に低リスクとみなされていることがうかがえる。香港、台湾を含むNIEs3では、「国家間での緊張の高まり」(59.3%) 、「米中貿易摩擦」(21.0%) 、「貿易制限・関税」(18.5%) が多く選ばれており、特に「国家間での緊張の高まり」については中国と並んでほかの国・地域と比べて突出している(第II-2-2-7図)。
第Ⅱ-2-2-7図 調達依存度の高い国・地域別にみたリスク認識の詳細
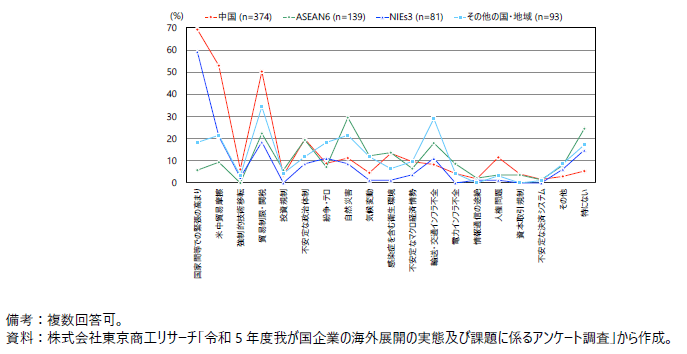
(2) 調達依存度を低減させる取組の状況と課題
これまで特定の国・地域への我が国企業の調達依存の状況を見てきたが、以降ではそうした状況を改善するリスク分散の取組について見ていく。まず、調達依存度が高いと回答した国・地域ごとの依存度の低減に向けた取組の状況を見ると、中国に依存している企業では、依存度の低減に関して何らかの取組を行っている割合(「既に依存度を下げている」と「現時点では依存度は下がっていないが今後下がっていく見込み」の合計 (31.5%) )と「取組の必要性は感じているが取り組むことが困難」(32.3%) と回答した割合が最大となっている。また、「現時点では取組の必要性は感じていない」(21.0%) と回答した割合は最小となっており、ほかの国・地域に比べて依存度の低減の必要性が強く感じられていることがうかがえる。一方、ASEAN6に依存している企業では、「現時点では取組の必要性は感じていない」(58.4%) と回答した割合が最大となっており、ほかの国・地域に比べて相対的に低リスクであると感じられていることがうかがえる。NIEs3に依存している企業については、中国とASEAN6の中間くらいの回答状況・リスク認識となっている(第II-2-2-8図)。
第Ⅱ-2-2-8図 調達依存度の高い国・地域別にみた依存度の低減に向けた取組の状況
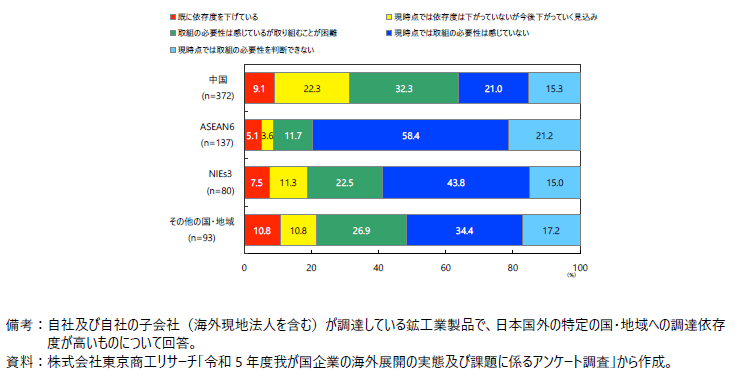
なお、調達依存度の高い国・地域にかかわらず、我が国企業の業種・従業員規模別での依存度の低減に向けた取組の状況を見ると、業種別では全体的に製造業よりも卸・小売業の方が取組の必要性を強く認識している(「既に依存度を下げている」、「現時点では依存度は下がっていないが今後下がっていく見込み」、「取組の必要性は感じているが取り組むことが困難」の合計)傾向が見てとれる。また、従業員規模別ではいずれの業種においても従業員規模が大きくなるほど、依存度の低減に関して何らかの取組を行っている割合(「既に依存度を下げている」と「現時点では依存度は下がっていないが今後下がっていく見込み」の合計)が増加する傾向が見てとれる(第II-2-2-9図)。
第Ⅱ-2-2-9図 我が国企業の業種・従業員規模別にみた依存度の低減に向けた取組の状況
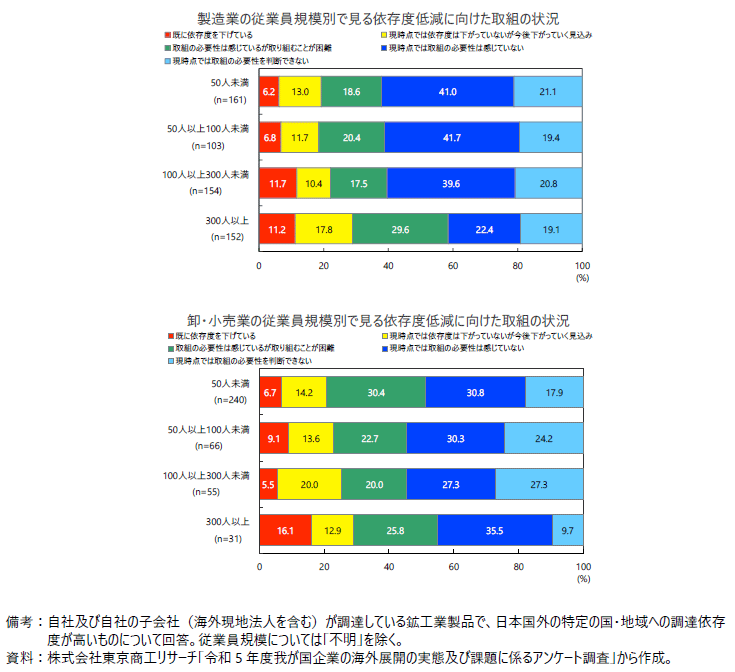
次に、調達の分散先として有望とみなされている国・地域について見ていく。第II-2-2-10図は、調達の分散先又は候補となっている上位3つの国・地域について、ウェイト付け集計し (1位:3点、2位:2点、3位:1点) 、平均=0、標準偏差=1となるようにスコアリングした結果を示したものであり、グラフはスコアが平均値を上回っている国・地域を示している。ASEAN6と日本が有望な分散先とみなされており、NIEs3、インド、中国がそれに続いていることが見てとれる。業種別では、有望な分散先の順位自体は変わらないが、製造業では非製造業と比べて日本を候補先として挙げる傾向が強いことが見てとれる。
第Ⅱ-2-2-10図 調達の分散先又は候補となっている国・地域
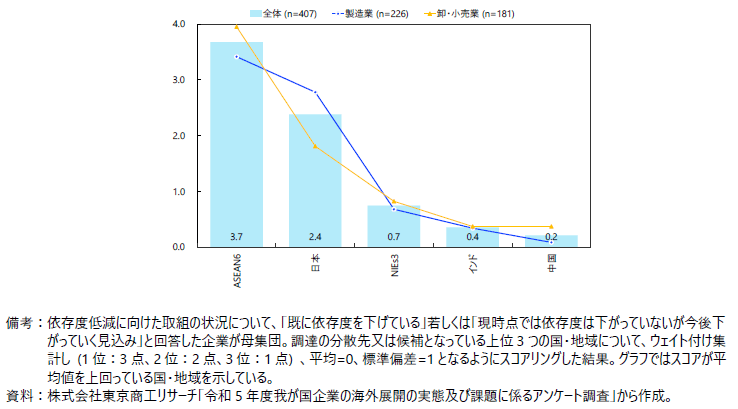
これら有望な分散先の国・地域ごとにその国・地域を選んだ理由について見ていくと、ASEAN6とNIEs3はよく似ており、「信頼できる安定したサプライチェーンを構築しやすい」、「コスト競争力が高く、良質な製品が安く手に入る」、「製品納入先との地理的な距離が近い」が多く挙げられている。日本では「信頼できる安定したサプライチェーンを構築しやすい」、「製品納入先との地理的な距離が近い」、「政治的に安定している、治安が良い」が多く挙げられており、ASEAN6に比べてよりリスクの低い調達の実現を期待されていることが見てとれる。インドでは「コスト競争力が高く、良質な製品が安く手に入る」、「信頼できる安定したサプライチェーンを構築しやすい」が、中国では「製品納入先との地理的な距離が近い」、「コスト競争力が高く、良質な製品が安く手に入る」、「信頼できる安定したサプライチェーンを構築しやすい」が、それぞれ多く挙げられている(第II-2-2-11図)。
第Ⅱ-2-2-11図 調達分散先の国・地域ごとの、その国・地域を選んだ理由
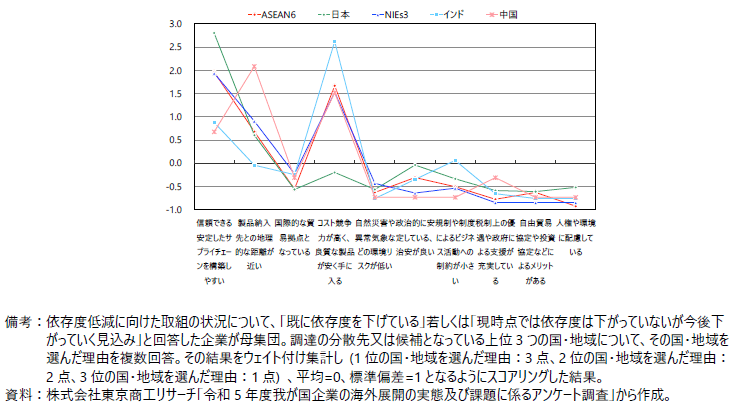
ここまで調達依存度の低減に向けた取組を実施している企業について見てきたが、ここからはそうした取組を実施していない企業について、その理由と背景を見ていく。まず、依存度の低減に向けた取組の状況について「取組の必要性は感じているが取り組むことが困難」と回答した企業のその回答理由に関しては、「代替調達先となる国・地域等で調達先企業が見つけられない」(62.7%) がほかの理由に対して大きな差をつけて1位となっており、「代替調達先となり得る国・地域等が分からない」(22.6%) が2位となっている。代替調達先の国・地域や調達先企業を選定した後に生ずるようなほかの理由については余り多く選ばれておらず、そもそも調達依存度の低減のための第一歩としての候補企業や候補国・地域の選定に課題を抱えている状況がうかがえる(第II-2-2-12図)。
第Ⅱ-2-2-12図 調達依存度の低減に向けた取組を行うことが困難である理由
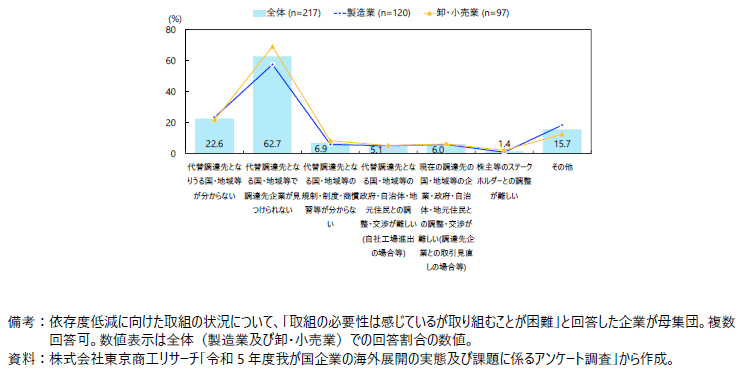
次に、依存度の低減に向けた取組の状況について「現時点では取組の必要性は感じていない」と回答した企業のその回答理由に関しては、「代替調達先が他にないため、依存度が低減できない」(49.2%) がほかの理由に対して大きな差をつけて1位となっており、その後に「自社生産等により即時代替調達が可能であるため」(19.5%) と「仮に調達が滞っても自社の生産・販売活動に大きな影響が無い」(19.5%) が同率で続いている。後者に関してはある意味において調達に係るリスクを織り込んだビジネスがなされているとも理解できるが、前者に関しては代替調達先の探索など、一層リスクを低減する余地があることがうかがえる(第II-2-2-13図)。
第Ⅱ-2-2-13図 調達依存度の低減に向けた取組に対して必要性を感じていない理由
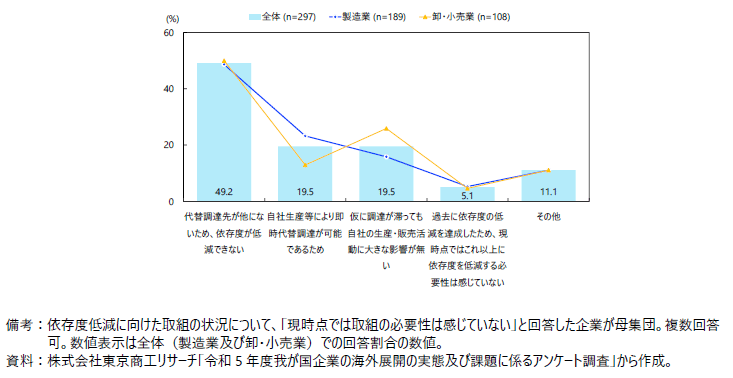
(3) 調達及び販売を含めたサプライチェーン強靱化に向けた課題
最後に、調達のみならず販売も含めたサプライチェーンの強靱化に向けた我が国企業の課題認識を見ていく。まず、業種と従業員規模にかかわらず、「自社だけでは、既存のサプライチェーンのリスクを分散するための、新たな調達先や販売先を見つけてくることが困難」、「サプライチェーンの強靱化に関する検討を行うための人材確保や社内体制整備ができていない」、「自社だけでは、既存のサプライチェーンに潜むリスクを認識することが困難」の三つを挙げる企業が多くなっており、続いて「自社の取引先の変更は自社を取り巻くサプライチェーン全体に影響を及ぼすため、自社だけの判断で強靱化を図ることは困難」が続いている。前者の三つはいずれも自社の有するリソース(人材、知見)だけでは取組が難しいことを示唆しており、知見を有する支援者からのサポートや、業界を通じた取組の必要性がうかがえる。
次に、業種にかかわらず、従業員規模が大きくなるほど「既存のサプライチェーンを見直して、更なる強靱化を行うことのメリットを見出しづらい」、「既にサプライチェーンの強靱化は達成していると認識しており、現時点ではこれ以上に取組を行う必要性は感じていない」と回答した割合は減少する傾向にあり、従業員規模の大きな企業ほどリスク認識が強いことがうかがえる。
また、両業種ともに、「サプライチェーンの強靱化に関する検討を行うための人材確保や社内体制整備ができていない」と回答した割合は従業員規模で大きな差は見受けられず、たとえ従業員規模の大きな企業であっても既存の体制では対応しきれていないことが見てとれる(第II-2-2-14図、第II-2-2-15図)。
第Ⅱ-2-2-14図 製造業の調達及び販売を含めたサプライチェーン強靱化に向けた課題認識
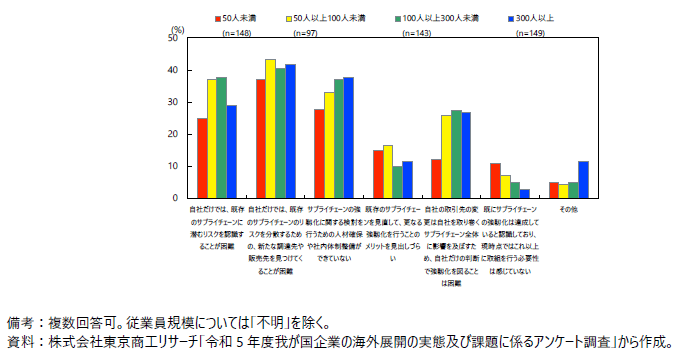
第Ⅱ-2-2-15図 卸・小売業の調達及び販売を含めたサプライチェーン強靱化に向けた課題認識
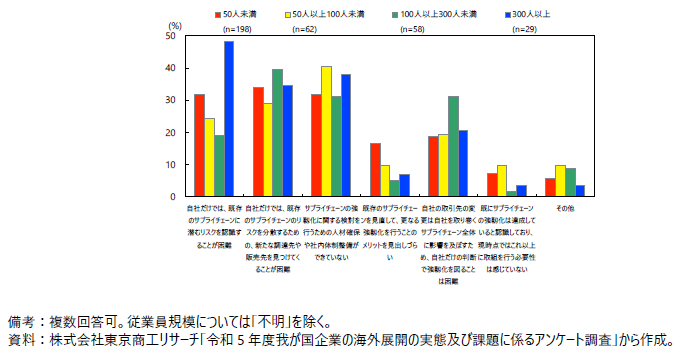
(4) 決定木を用いた依存度の低減への取組状況及び代替調達先の選択の特徴に係る追加的な分析
最後に、機械学習的な手法の一つである決定木(Decision Tree)を用いて、アンケートの結果について更に多層的に分類を行い、単純集計やクロス集計では見出すことが困難な特徴の抽出を試みる。決定木(Decision Tree)とは、金(2007)210によると、説明変数を何らかの基準を用いて分岐させて構築された判別・予測のモデルのことであり、分岐の過程が木のような構造で図示できることから決定木(Decision Tree)と呼ばれている。決定木では、用いられた説明変数や基準、並びにモデルの複雑性などの制御項目の範囲内において最も特徴が顕著に現れるよう分類が行われていると考えることができる。
まず、調達における依存度の低減に向けた取組への対応状況の違いについて、どのような特徴が見られるか決定木を用いて明らかにしていく。具体的には、調達における依存度の低減に向けた取組への対応状況を対応可能(既に依存度を下げている、又は現時点では依存度は下がっていないが今後下がっていく見込みと回答した企業)、対応困難(取組の必要性は感じているが取り組むことが困難と回答した企業)、対応不要(依存度の低減の取組の必要性を感じていない、又は現時点では判断できないと回答した企業)の三項目に類型化した上で、対応状況を規定する要因として、サプライチェーン強靱化に向けた課題認識や企業規模(従業員数)、業種、調達の依存度が高い地域、当該調達先の業種及び種類を用いて分類を行った結果が第II-2-2-16図のとおりである。これを見ると、第一に、調達における依存度の高い地域がアジア新興国(タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インド)である企業では、対応不要という回答が約70%を占めており、また、調達における依存度の高い地域が中国及びアジア新興国以外の国・地域である企業では、対応不要という回答が約50%であった。第二に、調達における依存度の高い地域が中国であり、従業員数が786人を超えている企業のうち、サプライチェーン強靱化における課題としてリスク認識の困難さを挙げている企業では、対応困難という回答が約80%を占めている一方で、同項目を挙げていない企業では約70%の企業が対応可能と回答していた。第三に、調達における依存度の高い地域が中国であり、従業員数が82人以上786人未満の企業では、対応可能という回答が約40%、対応困難という回答が約25%であった一方で、従業員数が82人未満の企業では、対応可能という回答が約30%、対応困難という回答が約40%であった。
以上より、中国に対する調達の依存度が高い企業は、対応の可否に差はあるものの、依存度の低減の必要性を感じている割合が高いということは、前述のクロス集計結果でも確認したが、決定木による特徴抽出によって、中国への調達における依存度が高い企業のうち、従業員数が少ない企業や、従業員数は多いものの自社のみでのサプライチェーンに潜むリスクの認識に困難を感じている企業では、依存度の低減に向けた取組への対応が困難であると感じている割合が高いことが明らかになった。また、アジア新興国への調達の依存度が高い企業は、依存度の低減の必要性を感じていない割合が高いことが明らかになった。
第Ⅱ-2-2-16図 調達における依存度の低減に向けた取組状況の回答別の特徴
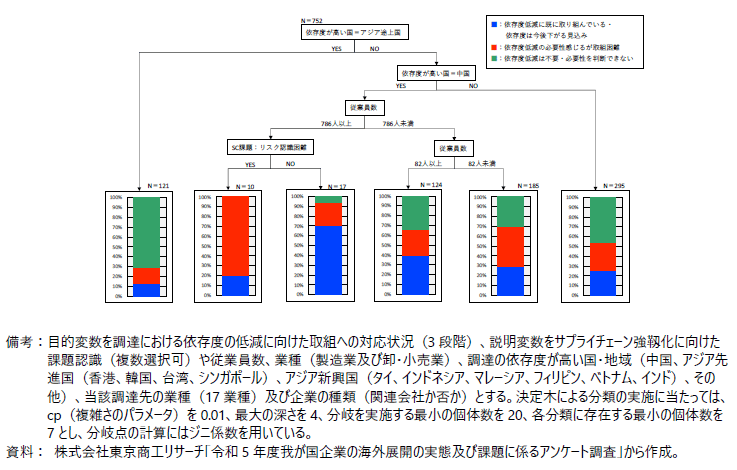
次に、依存度の低減への取組を既に実施している企業や、依存度が今後下がっていく見込みと回答した企業に焦点を当て、こうした企業の調達の分散先及びその候補となっている国・地域の選択にどのような特徴が見られるか見ていく。調達の分散先及びその候補は、日本、中国、NIEs、アジアの新興国(タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インド)、そのほかの5つのグループに分類する。説明変数としては、調達における依存度の高い国・地域及び当該国・地域への依存度、代替調達先及びその候補の選定理由、サプライチェーン強靱化における課題、従業員数、業種を用いる。これらの変数を用いて決定木による分類を行った結果が第II-2-2-17図である。なお、調査票においては、代替調達先及びその候補となる国・地域は、順位付けをして三つの国・地域を選択可能な形としているが、本分析においては順位付けについては特段考慮せず、選択された国・地域を全て同列に扱うこととしている。
第Ⅱ-2-2-17図 分散調達先の回答別の特徴
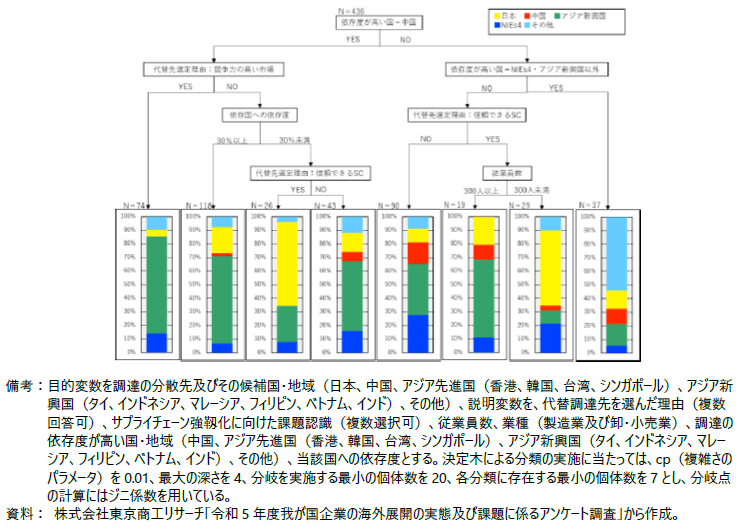
この結果から、第一に、調達における中国への依存度が高い企業のうち、調達の分散先の選定の理由にコスト競争力の高さを挙げた企業では、調達の分散先としてアジア新興国(タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インド)を選択した企業が約70%を占めていた。また、調達における中国への依存度が高く、コスト競争力の高さを選定の理由に挙げていない企業のうち、中国への調達の依存度が30%以上の企業では、調達の分散先としてアジア新興国を選択した企業が約60%、日本を選択した企業が約20%を占めていた。
第二に、調達における中国への依存度が高く、調達の分散先の選定の理由にコスト競争力の高さを挙げておらず、中国への調達の依存度が30%未満の企業のうち、調達の分散先の選定の理由に信頼できる安定したサプライチェーンの構築のしやすさを挙げた企業では、代替調達先に日本を選択した企業が約60%、アジア新興国を選択した企業が約20%を占めていた。一方で、調達の分散先の選定の理由に信頼できる安定したサプライチェーンの構築のしやすさを挙げていない企業では、調達の分散先としてアジア新興国を選択した企業が約50%、日本、NIEs、そのほかの地域を選択した企業がそれぞれ約10%ずつであった。
第三に、調達におけるそのほかの地域への依存度が高い企業は、調達の分散先としてそのほかの地域を選択する企業が約50%、アジア新興国を選択した企業が約20%、日本及び中国を選択した企業がそれぞれ約10%であった。
第四に、調達におけるアジア先進国及び新興国(中国を除く)への依存度が高く、調達の分散先の選定の理由に信頼できる安定したサプライチェーンの構築のしやすさをあげている企業のうち、従業員数が300人以上の企業では調達の分散先としてアジア新興国を選択した割合が約60%、日本を選択した企業の割合が約20%であった。一方で、300人未満の企業では調達の分散先として日本を選択した企業が約60%、NIEsを選択した企業が約20%であった。
第五に、調達におけるNIEs及びアジア新興国(中国を除く)への依存度が高く、調達の分散先の選定の理由に信頼できる安定したサプライチェーンの構築のしやすさを挙げていない企業では、調達の分散先としてアジア新興国を選択した企業が約40%、NIEsを選択した割合が約25%、中国を選択した企業が約15%であった。
210 金明哲(2007)『Rによるデータサイエンス(第2版)』森北出版
2. グローバル・バリューチェーン全体でみたリスク評価の必要性
ここまで、輸入や我が国グローバル企業の特定の国への依存の状況について見てきたが、輸入元や調達先の特定の国への依存の状況も含め、サプライチェーン全体で考えなければ、調達先の分散は表面的なものにとどまり、根本的な解決にはならない。グローバル・バリューチェーンの実態は、OECDの付加価値貿易(TiVA)を用いることにより把握が可能であることは、第I部第3章第3節で紹介したが、グローバル・バリューチェーンのリスクや強靱性を考える上で、貿易総額を基に評価する方法もある。ここからは、OECDのWebサイトに掲載されている、海外からの中間投入の総生産額を基にした指標である「国内生産活動に係る海外への露出度」(Foreign Production Exposure – Import side、FPEM)211を利用して考察していく。総生産額を基にするのは、グローバル・バリューチェーンの途中のある国で供給途絶というショックが起きた場合、ショックの影響を受けるのはその国の付加価値部分だけでなく、それまでの付加価値の累積を含めた総生産額になるとの考え方による。また、FPEMの大きな特徴として「全体」(英語ではLook through)を「額面(Face Value)」と「隠れた部分」(Hidden Exposure)に分けて考察することができる。「額面」とは、通常の貿易統計から観測される直前の輸入国からの中間投入を意味する。通常の貿易統計では正確に追えない、その先の中間投入供給国、更にその先に位置する中間投入供給国を「隠れた部分」として区別している212。
FPEMの分析に入る前に、まずは主要国・地域における中間財・サービスの貿易構造について概観する。第II-2-2-18図(1)は、OECDの国際産業連関表を用いて、主要国・地域における中間財・サービスの貿易構造を図示したものであり、円の大きさは域外との中間財・サービスの貿易額の大きさ、矢印の方向は中間財・サービスの輸出、矢印の太さはその輸出額の大きさを表している。これを一見すると、欧米間の中間財・サービスは密接なつながりがあり、中国、ASEAN、インド、韓国、台湾、香港、日本といったアジア諸国で中間財・サービスが互いに密接につながり合っている様子が分かるが、貿易は複雑に連関しており、欧米間で取引されている中間財・サービスもアジアを含むほかの国・地域を経由して供給されたものである可能性が高い。第II-2-2-18図(2)は、世界の産出額に占める各国・地域の中間投入額の割合を見たものであるが、中国が13.3%と最も高く、次いで米国が9.1%、その他世界が3.6%と続いている。これに対して、世界の産出額に対する各国・地域のシェアを示したものが、第II-2-2-18図(3)であるが、中国が22.0%、米国が21.5%、その他世界が6.1%となっており、産出額・中間投入額ともに中国が大きな存在感を示していることが分かる。
第Ⅱ-2-2-18図 主要国・地域における中間財・サービスの貿易構造
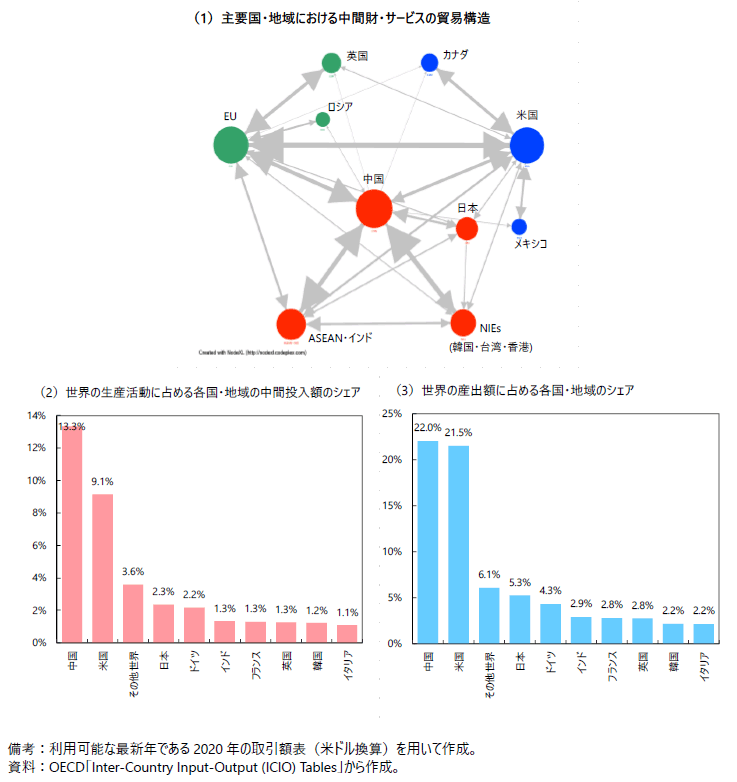
次に、FPEMを利用して、主要国・地域の海外からの中間投入の状況を比べたのが第II-2-2-19図である。各国・地域とも「額面」に比べて「隠れた部分」が大きく、貿易統計で観察される直接の中間財輸入国の更に先までグローバル・バリューチェーンが海外に長く伸びていることが示唆される。一般に海外に経済が開かれ、経済規模が小さい国は、FPEMが高い傾向にあり、OECD加盟国の中では、ルクセンブルグが最大で、米国が最小と報告されている213。アジア主要国・地域を見れば、ベトナム、タイ、マレーシア、フィリピンなどが高く、第Ⅰ部第3章で見た中国との後方参加指数の高い国と整合する。日本は指数としては必ずしも高くはないが、特定の産業や財に焦点を当てれば、事情が変わってくる懸念はある。もし、特定の国・地域へ依存が偏っていれば、グローバル・バリューチェーンの強靱性に懸念が生じる可能性がある。
第Ⅱ-2-2-19図 主要国・地域の海外からの中間投入の状況(2020年/FPEM)
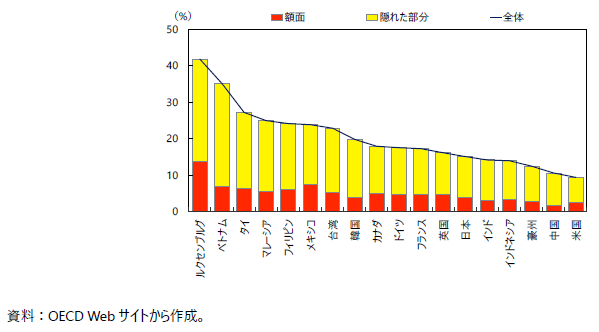
そこで中間投入元となる相手国の内訳を見ていくが、その前にいくつかの主要国についてFPEMの時系列推移を見ると、1995年から2010年頃まで多くの国で指数は上昇している(第II-2-2-20図)。特に「額面」よりも「隠れた部分」の拡大がより大きく、この時期はグローバル・バリューチェーンが拡大していたことを示唆している。世界の中でも国際的な生産分業が発達した日本などアジア諸国はFPEMの上昇が大きい。しかし、国によって多少時期は異なるものの、2010年代に入ると頭打ちの傾向が見られるようになる。特に中国については、2005年をピークに低下に転じており、国内の産業集積が進み、必要な中間財の国内生産が拡大したことを示している214。一方、米国はFPEMの数値に大きな変動はないように見えるが、バリューチェーンの強靱性に懸念はないのか、海外からの中間財の具体的な投入元を見ていく。
第Ⅱ-2-2-20図 主要国のFPEM推移
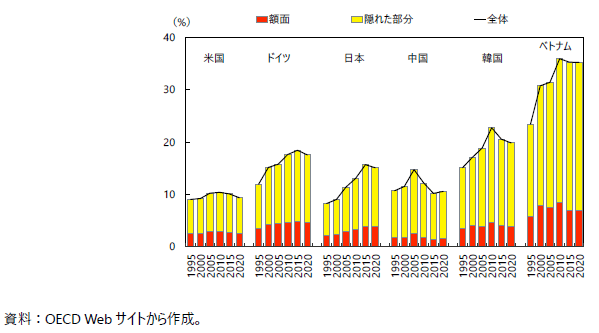
米国や日本を含め、いくつかの主要国の2020年時点の「額面」「隠れた部分」の具体的な中間投入元となる相手国・地域の構成を見たのが第II-2-2-21図である。総じて上位には近隣諸国・地域が挙がる傾向が見られる。例えば米国にとってはカナダやメキシコへの依存が、ドイツにとっては米国や欧州諸国への依存が、そして日本、中国、韓国、ベトナムにとっては米国やアジア諸国・地域への依存が強い。しかし、中国自身を除けば、これら諸国に共通して、中国が「額面」においても「隠れた部分」においても最大の中間投入元の相手国となっている。特に貿易統計で観測可能な「額面」よりも、貿易統計では正確にたどることのできない「隠れた部分」におけるプレゼンスが高い。例えば、米国にとって、「額面」の中間投入供給国としては、中国、カナダ、メキシコがほぼ拮抗しているが、「隠れた部分」を見ると、中国がカナダ、メキシコを大きく引き離すシェアを有している。これは中国が直接的な中間財の供給国であるとともに、直接には供給していない中間財についても、生産工程のその先の間接的な中間財供給国として存在感が大きいことを意味している。
第Ⅱ-2-2-21図 海外からの中間財投入の状況(FPEMの主要国・地域構成)
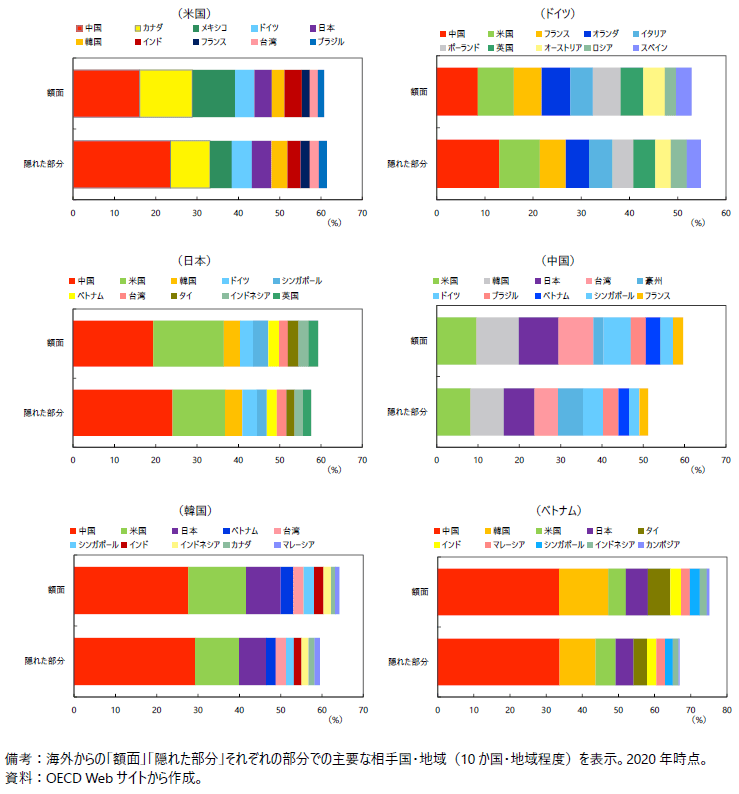
それでは中国のシェアは過去から大きかったのか、米国、日本を例に過去に遡及して推移を見たのが第II-2-2-22図である。米国の場合、1995年まで遡れば、中間財供給国としてカナダ、メキシコ、日本、ドイツのシェアの方が中国より遙かに大きかったが、25年の間に中国のシェアが急速に拡大してきたことが分かる。このように仮に海外全体でのFPEMに大きな変化がないとしても、中間投入元の相手国の構成に大きな偏りが生じる場合がある。日本の場合も、25年の間に中国のプレゼンスが大きく拡大して米国と逆転している。
第Ⅱ-2-2-22図 米国・日本のFPEMにおける主要相手国のシェアの推移
(1995年→2000年→2005年→2010年→2015年→2020年)
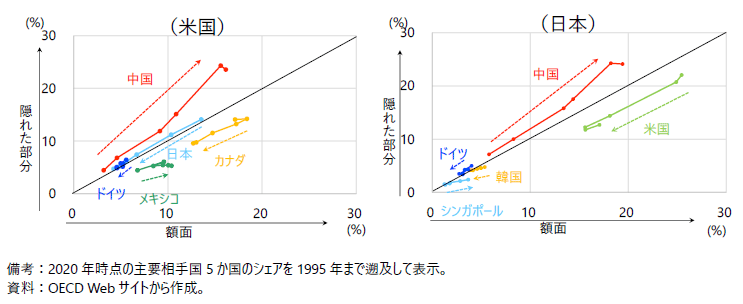
2020年時点の中間投入における中国からの中間投入はドイツなど欧州諸国では必ずしも大きくないが、米国や日本を始めとするアジア諸国・地域はより大きな値を示しており、特に中国との後方連関の強いベトナムを始めとしたASEAN諸国は中間投入の3割近くを中国に頼っている(第II-2-2-23図)215。
第Ⅱ-2-2-23図 中国からの中間財投入への依存(FPEM)
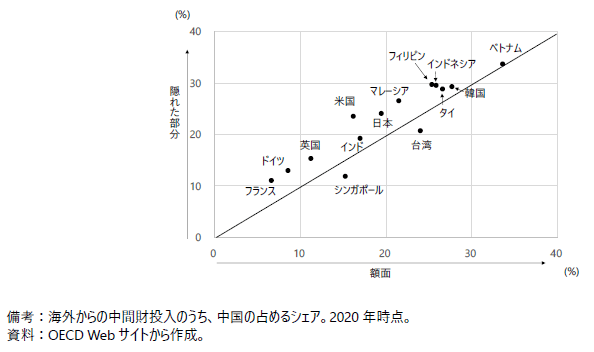
ここまでのFPEMの考察をまとめると、グローバル・バリューチェーンの強靱性の一つの指標として、国内生産に必要な生産額合計に占める海外からの中間財合計で見る見方がある。この指標を使えば、生産額の大きさだけでなく、グローバル・バリューチェーンの長さを反映した強靱性を考えることができる。また、中間財の直接の供給国と間接的な供給国で分けて考察することも可能である。その指標の一つであるFPEMを使うと、海外からの中間投入は、多くの国で2010年頃まで、特に間接的な中間投入が上昇して、その後は頭打ちとなっている。ただし、その間に日本、米国を始めとするいくつかの国では、中間投入元の相手国の構成に大きな変化が見られ、中国からの中間投入が急速に高まっている。中国からの中間投入は直接、間接の両面で上昇しているが、間接的な値の方がより大きい。2020年時点の中国からの中間投入はドイツなど欧州諸国では必ずしも大きくはないが、米国や日本を始めとするアジア諸国・地域ではより大きな値を示しており、特にASEAN諸国は中間投入の3割近くが中国からとなっている。
本節では、デリスキングという潮流の中で我が国企業に求められる対応について見てきたが、デリスキングを考える際には、バリューチェーンの一部ではなく全体を考慮することが重要であり、OECDの付加価値貿易統計や最近開発されたFPEM等の指標は、我々がこれまでリスクを認識しつつも具体的に示し得なかった事象を可視化する有力な手段を提供するものであるといえる。
211 詳細は以下のOECDのWebサイト参照。同サイトによれば、このような指標はBaldwin氏を始めとする著者の共著論文に基づいている。「FPEM」「FPEX」「FIR」「FMR」の4種類の指標が紹介されているが、ここでは中間投入を扱ったFPEMを取り上げた。なお、「国内生産に係る海外への露出度」はここでの仮訳(意訳)である。後ろで出てくる「全体」「額面」「隠れた部分」も同様。(https://www.oecd.org/industry/ind/gross-output-linkages-in-global-value-chains.htm![]() )「Gross output flows in Global Value Chains: New indicators to evaluate countries’ reliance on foreign intermediate inputs」
)「Gross output flows in Global Value Chains: New indicators to evaluate countries’ reliance on foreign intermediate inputs」
212 FPEMで「全体」(Look through)と表記される生産工程全体における総生産額は、OECDの国際産業連関表を基に、レオンチェフの逆行列を使って計算される。「額面」(Face value)とは直前の生産工程からの中間投入で、需要額に投入係数を乗じた、いわゆる第一次波及効果のことを指す。第二次以降の波及効果が「隠れた部分」(Hidden exposure)で、「全体」から「額面」を引いて計算している。ここでは海外部分について記載しているが、同様に国内の部分についても「額面」「隠れた部分」が計算され、OECDのWebサイトに公表されている(国内の場合「額面」に最終需要と第一次波及効果の双方を合計する)。当然のことながら、海外と国内の「額面」「隠れた部分」の合計は1.0(100%)となる。なお、「国内生産に係る海外への露出度」「全体」「額面」「隠れた部分」等の表記はここでの仮訳(意訳)である。
213 先に掲載したOECD Webサイトによる。なお、FPEMの分析に当たっては2024年1月26日に同サイトからダウンロードしたデータを利用した(https://www.oecd.org/industry/ind/gross-output-linkages-in-global-value-chains.htm![]() )。
)。
214 中国の生産には、外資企業、地場企業の両者を含む。日本を始め直接投資により外資企業が中国国内で中間財の生産を拡大したことや、そのスピルオーバー効果で地場企業が発達したこと等も影響していると考えられる。
215 インドネシアは、第Ⅰ部第3章第1節の付加価値貿易統計で見た中国との後方連関は必ずしも強くなかったが、FPEMでは大きな指数となっている。その理由として、OECDの後方参加指数とFPEMとは評価する内容が異なることが考えられる。後方参加指数は「輸出」をするに当たって、輸出品に相手国の付加価値がどの程度含まれているかを見るのに対して、FPEMは「国内で生産活動」をするのに当たって、相手国の中間投入がどの程度利用されているかを見る。インドネシアは資源輸出の割合が大きく、その部分には中国の中間財利用は限られるかもしれないが、国内で生産活動をする上では中国の中間財を利用していることは考えられる。

