第3節 我が国企業の海外市場との関わりと海外展開推進に向けた課題
前節では、我が国企業のグローバルな事業活動に伴うリスクについて、主に調達行動に焦点を当てて、実態と課題について整理を行ったが、本節では、我が国企業の更なる海外展開の推進に向けて、我が国企業と海外市場との密接な関わりの実態や、企業の実情に沿った海外展開の課題について取り上げる。より具体的には、本節の前半では、企業間の取引関係を分析することで、自社が、直接、輸出を行っていない場合でも、大半の国内企業が間接的に海外市場とつながっていることを明らかにする。本節後半では、企業アンケートを基に、輸出に焦点を当てて、直接輸出、間接輸出、輸出に関わっていないという段階ごとに、海外展開に向けた課題を検討していく。
1. 企業間取引に見る海外市場との関わり
(1) 直接輸出と間接輸出
ここでは「海外市場との関わり」として、輸出に焦点を当てて、我が国の国内に立地する企業のうち、どのくらいの割合の企業が海外市場とつながりを有しているかを見てみる。その際に、直接、輸出に従事している企業だけでなく、間接的に輸出に関わっている企業についても併せて考察する。例えば、輸出を行っている製造業企業に対して、生産のための部材を納入している場合や輸出商社などに対して、製品を納入している場合なども、海外市場につながっていると考えられる。
輸出に焦点を当てた類型として、第II-2-3-1図のような企業類型を考える。輸出を行っている企業を「直接輸出企業」とし、「直接輸出企業」に連なる取引関係を持つ企業を「間接輸出企業」と見なす。具体的には「直接輸出企業」を販売先に持つ企業を「1次間接輸出企業」、さらにその企業を販売先に持つ企業を「2次間接輸出企業」というように、4次までの間接輸出を考える216。「それ以外の企業」は、海外市場との関係が弱い、主として国内市場に立脚する企業と考えられる。
第Ⅱ-2-3-1図 輸出に係る企業類型
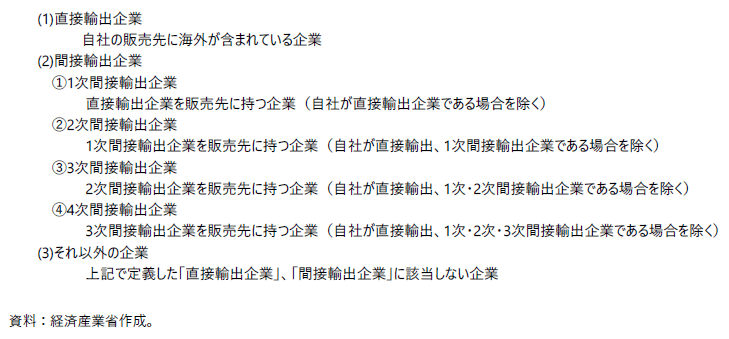
分析に当たっては、株式会社東京商工リサーチが有している企業データベース(TSR企業相関ファイル)を利用する。そこには企業情報(業種、従業員数、売上高等)とともに、企業間取引(仕入先、販売先、輸出の有無等)に関するデータが収録されている。データベースに収録され取引関係を追うことのできる製造業及び卸・小売業の約52万社を対象に、直接輸出を行っている企業、1次~4次までの間接輸出企業、それ以外に分類した。
その集計結果を示す前に、まずデータの分布について概観する。TSR企業相関ファイルのデータの業種別分布を経済センサスと比較したのが、第II-2-3-2図である。TSR企業相関ファイルは、製造業の場合、経済センサスの約6割の企業をカバーしている。製造業の中の業種別に見て、両統計でカバー率にやや相違はあるものの、業種の分布に極端な相違や偏りはないように見える。卸売業ではカバー率は約8割、小売業は約3割となっている。
第Ⅱ-2-3-2図 TSR企業相関ファイルと経済センサス
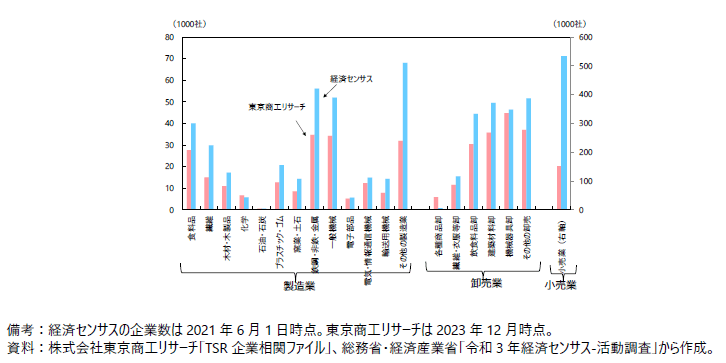
216 厳密には、5次以降も海外市場とつながりを持つことが考えられるが、海外市場からしだいに遠くなること、後で見るように対象となる企業数が限られていくこと等から、ここでは仮に1次~4次までを間接輸出と見なした。また、企業の取引関係というデータの制約上、生産工程における部材の供給だけでなく、生産設備の提供(設備投資関係)も含まれることになる。このため、ここでは海外市場に連なるビジネスの連鎖という観点から、設備投資も含めた広い意味での輸出について考察することになる。
(2) 輸出のタイプ別の企業数
輸出のタイプ別に分けて企業数を集計すると、直接輸出企業の背後には、遙かに多い数の間接輸出企業が存在していることが分かる(第II-2-3-3図)。特に1次、2次間接輸出企業は、それぞれ直接輸出企業の10倍近い企業数がある。3次は直接輸出企業の約3倍、4次はほぼ同数と、次第に少なくなるが、直接及び間接合計で、表面に見える直接輸出企業の約23倍もの企業が輸出に関わっていることになる。もちろん、納入される製品が必ずしも輸出に回るとは限らず、回るとしても一定割合にとどまることは考えられるが、間接的な輸出を通じて、海外市場とつながる企業は見かけ以上に多い。また、1次及び2次間接輸出企業の業種構成を見ると、製造業に属する企業が過半数を占めており、製造業企業が輸出において主体であることや生産工程における結びつきが強いことを示唆している。一方、卸・小売業も輸出の各段階において、関わっていることから、企業間取引の仲介者として介在し、重要な役割を果たしていることも分かる。
第Ⅱ-2-3-3図 輸出のタイプ別の企業数
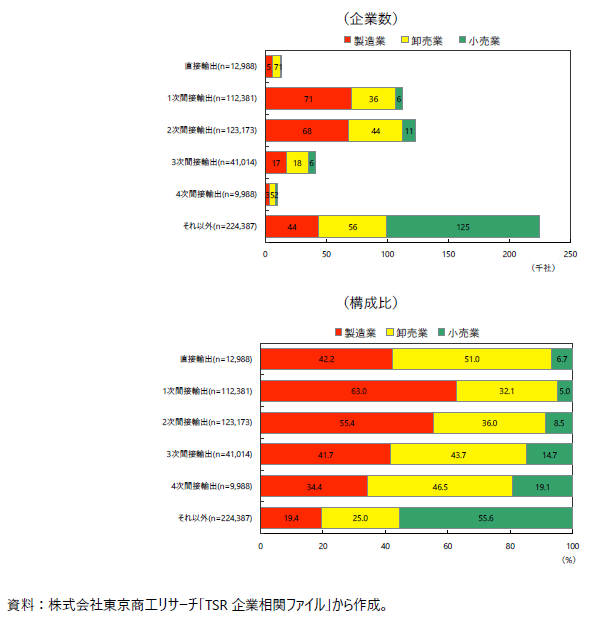
業種別に、どの程度の企業が海外市場とつながっているかを見たものが第II-2-3-4図である。製造業の場合、直接輸出企業はごく一部に過ぎないが、1次、2次とも、それぞれ製造業全体の3割強の企業が間接輸出に関わっており、既に2次までの間接輸出で3分の2、直接から4次までの輸出企業全てを合計すれば、製造業の約8割の企業が輸出に関係していることになる。卸売業も約7割が直接又は間接に輸出に関わっている。一方、小売業の場合は約2割と低く、主として国内市場に立脚する企業が多い。製造・卸売・小売業を合計すれば、データベースに登録された企業の約6割が海外市場とつながっている。
第Ⅱ-2-3-4図 輸出のタイプ別の企業数シェア(主要業種)
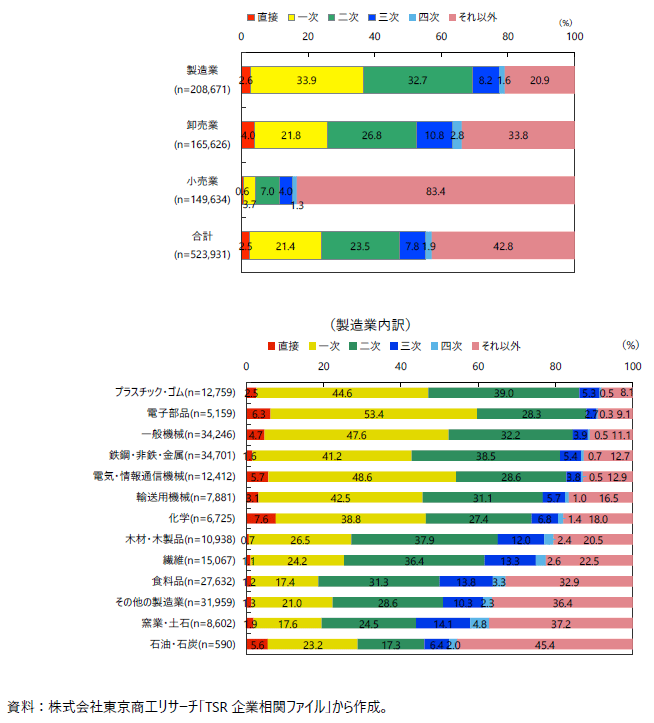
製造業の中では、特にプラスチック・ゴム、鉄鋼・非鉄・金属などの素材関係や電子部品、一般機械、電気・情報通信機械、輸送用機械等の機械関係が海外市場につながる企業割合が高い。これらの業種では、3次、4次は少なく、むしろ直接輸出から、1次、2次間接輸出までで既に約8割の企業が輸出に関与している。生産工程における分業関係が発達し、サプライチェーンに沿って企業間の結びつきが強いことが示唆される。
(3) 輸出のタイプ別に見た企業パフォーマンス
ここまで企業数ベースで見てきたが、輸出が我が国の雇用や経済へ与える影響を考える上では、直接又は間接輸出に従事している企業の従業員や売上げも見ておく必要がある。海外市場に連なる企業は、企業数から見た場合だけでなく、従業員、売上高から見れば、より一層高いシェアを占める。企業数ベースで約6割、従業員ベースで約8割、売上高ベースで約9割に及ぶ(第II-2-3-5図)。特に直接輸出企業は、企業数に比べて、従業員、売上高のシェアが飛躍的に拡大する。また、1次間接輸出企業も、企業数に比べて、従業員や売上高のシェアは約2倍に及ぶ。
第Ⅱ-2-3-5図 輸出のタイプ別のシェア(企業数・従業員・売上げ)
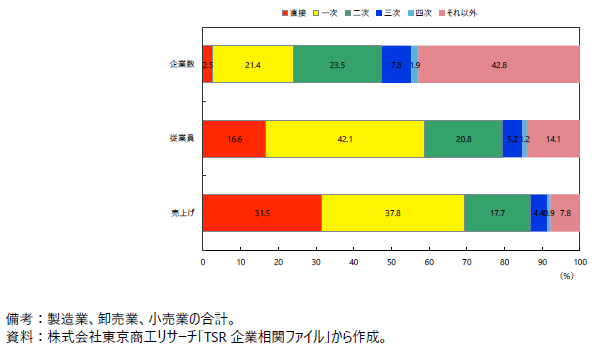
このように企業数に比べて、従業員や売上のシェアが大きいということは、輸出タイプごとに企業規模等に相違があるということを意味している。そこで輸出タイプ別に企業を比べてみたものが第II-2-3-6図である。まず、従業者数を見ると、直接輸出企業に比べて、間接輸出企業は規模の小さい企業が多く、その間接輸出企業の中では、海外市場から遠ざかるほど規模が小さくなる傾向が見られる。例えば、平均値は海外市場から遠ざかるほど明らかに小さくなっており、同じ輸出のタイプの中で、小さい順に企業を四分割した四分位の水準も、平均値ほど顕著ではないものの、同じ傾向がある。また、同様に事業の手広さという観点から、販売先企業数、仕入れ先企業数を見ても、海外市場に近いほど取引相手数は多く、事業活動は活発であるように見える。さらに労働生産性という面に焦点を当てれば、一人当たり売上高は、間接輸出企業の中でははっきりしないものの、直接輸出企業は明らかに間接輸出企業よりも高い水準にある217。なお、輸出に関わっていない「それ以外」の企業の場合は、平均すれば、直接及び間接輸出企業より低い水準にとどまっている。ただし、ここで留意すべき点は、間接輸出企業、輸出に関わっていない企業の中にも、直接輸出企業や海外市場により近い間接輸出企業に匹敵する規模や生産性の企業は存在するということである。
第Ⅱ-2-3-6図 輸出のタイプ別の企業パフォーマンス
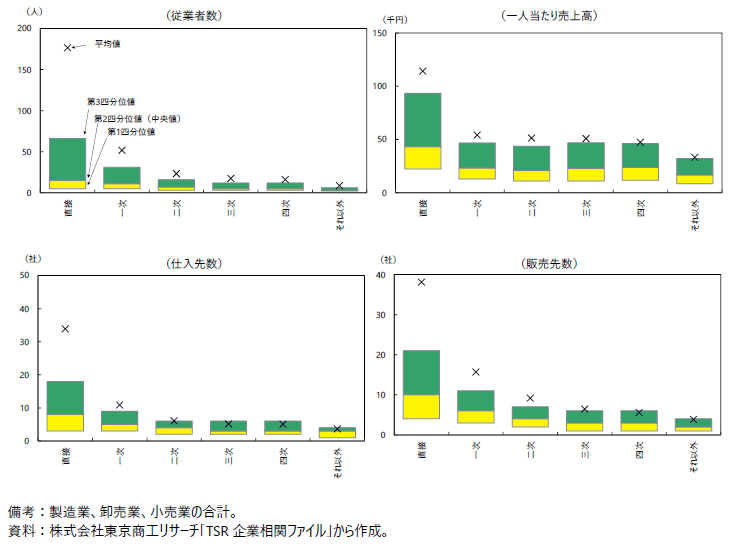
ここまでの内容をまとめると、我が国企業は自社が直接輸出を行っていない場合でも、多くの企業が直接的又は間接的に海外市場につながっており、海外市場の動向が我が国の幅広い企業に影響を与える。また、海外市場へのアクセスは、雇用やパフォーマンスとも関係しており、一般的には、直接輸出企業の生産性は間接輸出企業より高く、間接輸出企業の中では、海外市場により近い輸出タイプの企業ほど、従業員規模が大きく、より多くの取引先と手広く事業を行っていることが示唆された。一方で、個々の企業ごとにみれば、直接、輸出を行っていない企業の中にも直接輸出企業に匹敵する生産性や規模の企業は存在し、直接輸出等を通じて、より近い位置で海外市場へのアクセスを得ることができれば、一つのビジネスチャンスとなる可能性も秘めている。直接にも間接にも輸出を行っていない企業が輸出を始める場合も同様のことがいえる。
しかし、実際には輸出を始めるに当たって様々な問題があると考えられる。次項では、実際に直接輸出、間接輸出、輸出をしていない企業に分けて、将来の事業展開の方針、輸出を始めることになったきっかけ、輸出に当たっての課題などを調べた結果を紹介する。
217 直接輸出を行う企業の生産性が高いのは、海外市場に製品を供給するためには、必要な固定費用を負担しても、利益が確保できるだけの高い生産性が求められることが背景にあることが指摘されている。
2. 海外展開に向けた課題
ここではアンケート調査を基に、特に輸出に焦点を置いて、企業の海外展開の課題や問題点を考える。分析に当たっては、株式会社東京商工リサーチが実施した「令和5年度我が国企業の海外展開の実態及び課題把握に関するアンケート調査」218を利用した。同調査では、輸出に焦点を当てた海外進出の現状、今後の事業展開、課題や問題などを調査している。
218 アンケート実施期間:2024年1月~2024年2月。調査対象:東京商工リサーチのデータベースの中から、日本に所在する海外現地法人を持たない企業であり、①直接輸出をしている(製造業、卸・小売業)、②間接輸出をしている(製造業のみ)、③直接輸出、間接輸出のいずれもしていない(製造業のみ)企業を抽出。調査方法:配布・回収とも郵送。発送:11,750社、有効回答数:3,035社、回収率:25.8%。なお、集計に当たって、業種や従業員規模などは、同社の企業データベースの情報を利用した。
(1) 主要輸出先・顧客
まず、企業のプロフィールをつかむため、輸出先や顧客を概観する。主要輸出先について、直接輸出又は間接輸出を行っている企業に聞いた結果、最も多い回答が中国で、業種や輸出形態にもよるが、約半数の企業が中国向けの輸出に携わっている(第II-2-3-7図)。次に多い輸出先が米国で、製造業では4割以上の企業が対米輸出を行っている。3位以下に台湾、韓国、タイと続き、上位10位までのうち、8か国・地域がアジアであることから、アジア向け輸出に従事する企業が多いことが分かる。そのほかの地域に関しては、10位のドイツ以下、英国、フランス、イタリア等の欧州諸国や豪州、カナダ、メキシコなども主要輸出先に入っている。なお、業種・輸出形態別に見ても、個々の国・地域の順位はずれても、中国を始め、アジア向け輸出が多い傾向は共通している。製造業の直接輸出企業が最も幅広い国・地域に輸出をしており、卸・小売業の直接輸出企業、製造業の間接輸出企業が続いている。
第Ⅱ-2-3-7図 アンケート回答企業の主要輸出先
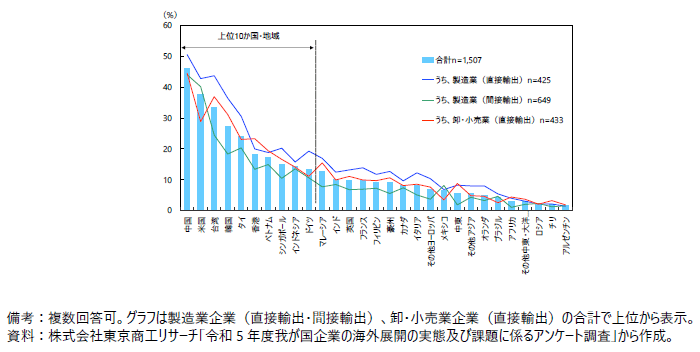
次に回答企業の輸出の顧客である納入先を見ておく。まず、直接輸出をしている企業の特徴として、①主要納入先の業種は、海外に所在する商社等の卸・小売業が最も多く、次いで加工組立型製造業となっている(第II-2-3-8図)。特に輸出者が卸・小売業の場合は、海外の卸・小売業を顧客とする割合が大きい。また、②輸出企業の従業員規模別に見れば、規模の小さい企業よりも大きい企業の方が納入先として加工組立型を始めとした製造業を選び、反対に卸・小売業を顧客とする割合は、規模の大きい企業よりも小さい企業の方が高い。
第Ⅱ-2-3-8図 輸出の主要納入先(輸出者の従業員規模別)
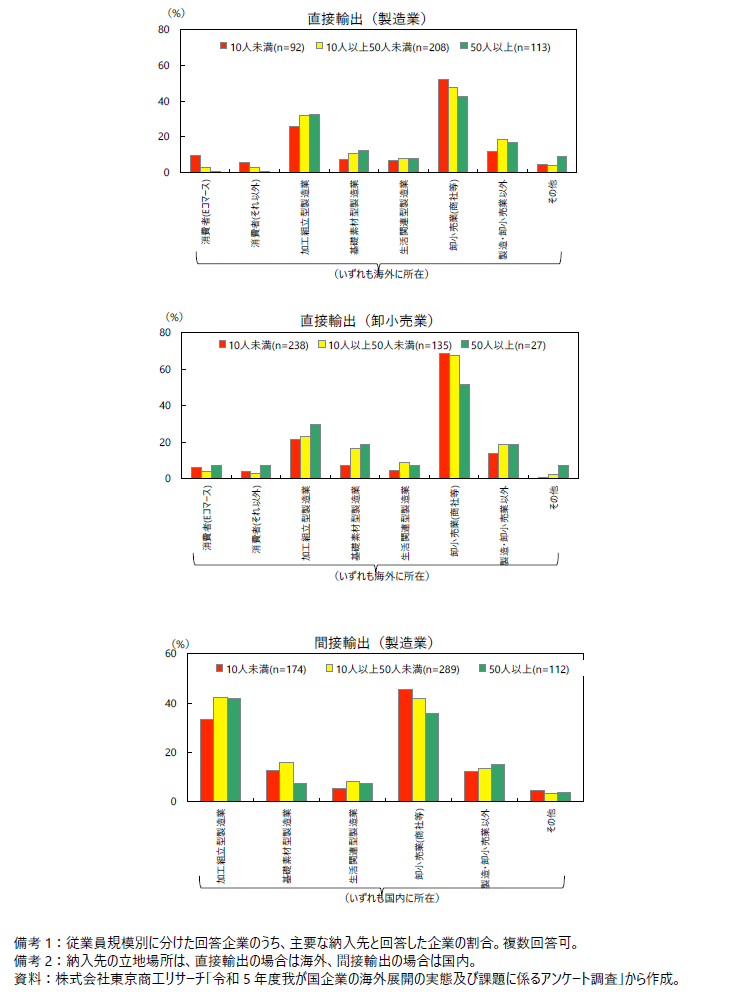
間接輸出をしている製造業の場合、①納入先の業種として、国内の卸・小売業と加工組立型製造業がほぼ拮抗している。②輸出者の規模別の特徴は、おおむね、加工型製造業顧客に対しては規模の大きい企業、卸・小売業顧客に対しては小さい企業の方が納入先に選ぶ割合が高い。結果として、大規模企業の最も多い納入先は加工組立型製造業で、小規模企業の納入先は卸・小売業となっている。
納入先を決める背景として、加工組立型製造業への納入は、部材を提供して生産活動に参加するグローバル・バリューチェーンに沿った動きが想起される。一方、卸・小売業への納入は、市場の情報や輸出のノウハウなどに知見のある商社などを通じた輸出が行われていることが考えられる。特に小規模な企業が卸・小売業を活用している姿が浮かぶ。
(2) 直接輸出企業の今後の事業展開と課題
ここからは企業の輸出のタイプごとに、今後の事業展開、課題認識等を見ていく。まず、直接輸出を行っている企業に、直接輸出を開始した理由を尋ねると、製造業では、「市場の成長性」、「輸出先との特別なコネクション」、「市場規模」、「納入先の海外拠点設置」等を理由として挙げる企業が多い(第II-2-3-9図)。これに対して、卸・小売業では、「市場の成長性」、「市場規模」とともに、「輸出先との特別なコネクション」、「知人や経営者からの紹介」の回答も多い。企業規模別に見ると、この「輸出先との特別なコネクション」、「知人や経営者からの紹介」は10人以下の企業に多く、小規模な企業の場合は、個々の企業あるいは個人的なつながりや出会いが重要な役割を果たしている可能性がある。一方、50人以上の企業では「市場の成長性」、「市場規模」、「納入先の海外拠点設置」が輸出のきっかけとして多い。
第Ⅱ-2-3-9図 直接輸出を開始した理由(直接輸出企業)
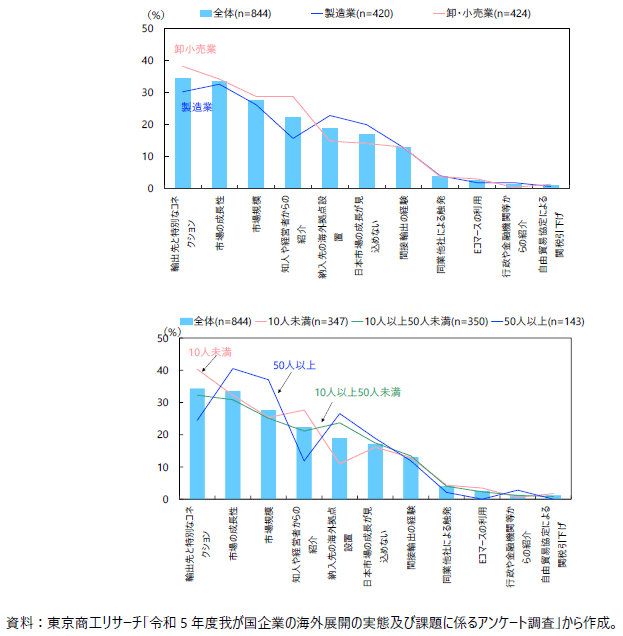
今後の事業展開を尋ねた結果は「現状維持」(36.1%)との回答が最も多かった(第II-2-3-10図)。一方、積極的に「輸出先の国・地域等を増やし、新たな販路開拓を目指していきたい」(29.5%)、「既存の輸出先で、シェア拡大や輸出品目の増加を目指していきたい」(20.3%)、「現地法人の設立など、直接海外に進出してビジネスを行いたい」(6.1%)など、何らかの意味で事業拡大を考えている3項目で回答の過半を占めた。なお、回答数は限られているが「輸出は今後縮小していく予定」(3.4%)との回答もあった。
第Ⅱ-2-3-10図 今後の事業展開(直接輸出企業)
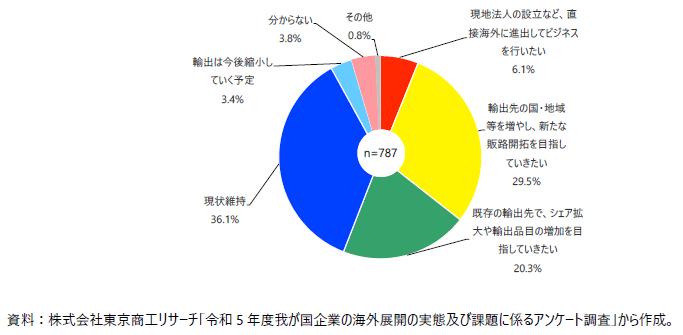
主要な課題認識を表示したのが第II-2-3-11表である。今後の事業展開の選択肢ごとに、それを選んだ企業が何を課題と認識しているかを見てみると、「現地法人の設立」のように直接海外に進出することを考えている企業の半分近くが「需要、商品価格、為替等の変動リスクの管理」(47.9%)、「信頼できるサプライチェーン」(43.8%)を課題として認識しているほか、「海外市場向けの商品開発」(37.5%)、「市場に関する情報が不足」(33.3%)、「規制、制度、商習慣の情報不足」(31.3%)など幅広い項目が超えるべきハードルとして強く認識されている。これらの項目はほぼ同率で並んでおり、多様な課題に対処していく必要があることを示唆している。同様に「新たな輸出先開拓」を目指す企業は「海外市場向けの商品開発」(39.7%)、「規制、制度、商習慣の情報不足」(37.5%)、「信頼できるサプライチェーン」(34.9%)、また、「既存輸出先でのシェア拡大」を狙う企業は「需要、商品価格、為替等の変動リスクの管理」(40.3%)、「海外向けの商品開発」(35.2%)、「資金・人材確保を含む供給能力の拡大」(32.7%)を始めとして、多くの項目に関心を寄せている。
第Ⅱ-2-3-11表 「今後の事業展開」と「今後、海外展開を行う上での課題認識」(直接輸出企業)
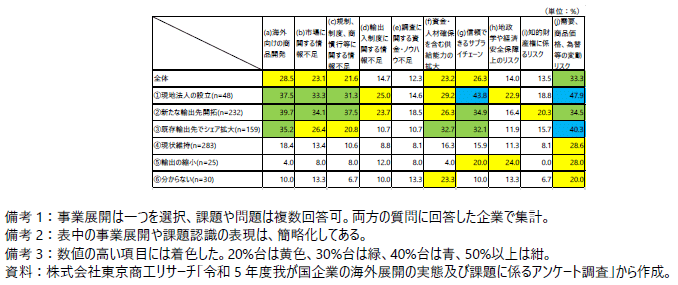
一方、今後の事業展開を「輸出の縮小」と回答した企業の場合、「需要、商品価格、為替等の変動リスクの管理」(28.0%)のほか、「地政学や安全保障上のリスク」(24.0%)、「信頼できるサプライチェーン」(20.0%)を課題として挙げている。
(3) 間接輸出企業の今後の事業展開と課題
次に直接輸出は行っていないが、間接輸出を行っている企業を見てみる。今後の事業展開では、全体の約半数の企業が「現状維持」(51.2%)と回答した(第II-2-3-12図)。次いで「間接輸出を通じた販路拡大を目指していきたい」(32.2%)が多く、3位に「分からない」(10.2%)が続いた。積極的な「現地法人の設立など、直接海外に進出してビジネスを行いたい」(2.4%)や「間接輸出を直接輸出に切り替えたい」(1.4%)、反対に「間接輸出は今後縮小していく予定」(1.6%)との回答は限られていた。
第Ⅱ-2-3-12図 今後の事業展開(間接輸出企業)
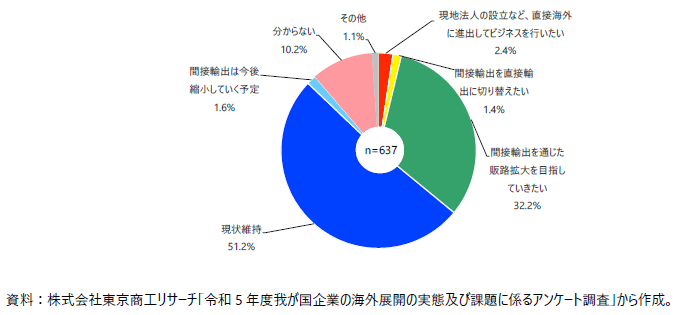
アンケートでは、直接輸出を行っていない理由を聞いている。今後の事業展開で「現地法人の設立」、「直接輸出への切り替え」、「間接輸出の拡大」など、何らかの意味で事業の拡大を考えている企業の場合、共通して回答企業の半数以上が「人材確保や社内体制」、「情報やノウハウの不足」の2項目を理由に挙げている(第II-2-3-13表)。そのほかに、「収益以上にコストやリスクが大きい」、「交渉能力がない」が重要である点も共通している。「直接輸出への切り替え」を考える企業では、「投資資金の不足」「生産能力が確保できない」との回答も多い。
第Ⅱ-2-3-13表 「今後の事業展開」と「現在、直接輸出を行っていない理由」(間接輸出企業)
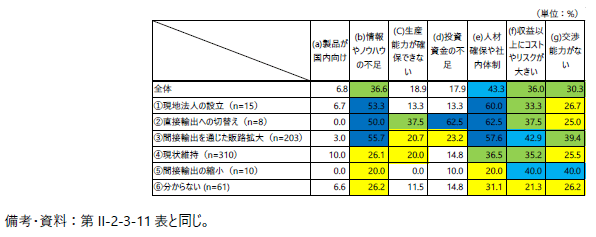
今後の事業展開を「分からない」と回答した企業の場合も、回答企業の約3割が「人材確保や社内体制整備」、「情報やノウハウの不足」の2項目を挙げており、実際にこれらの企業が方針を決める際に重要な項目といえる。一方、今後の方針で「間接輸出の縮小」を選択した企業では「収益以上にコストやリスクが大きい」、「交渉能力がない」が大きな理由であった。
なお、アンケートには自由記述欄も設けているが、今後の事業展開を「分からない」と回答した企業の中には、背景として親会社の判断に影響される旨の記載もあった。
(4) 非輸出企業の今後の事業展開と課題
最後に直接又は間接輸出のどちらも行っていない企業を見てみる。今後の事業展開は、最も多い回答が「現状維持」(41.7%)、次いで「国内向け事業の拡大を目指していきたい」(31.6%)が続き、国内事業を重視する回答は合わせれば約7割を占めた(第II-2-3-14図)。「事業を縮小していく予定」(3.2%)は限られるものの、「分からない」(14.1%)も一定数あり、「海外向け事業展開も行いたい」(7.4%)は1割以下であった。
第Ⅱ-2-3-14図 今後の事業展開(非輸出企業)
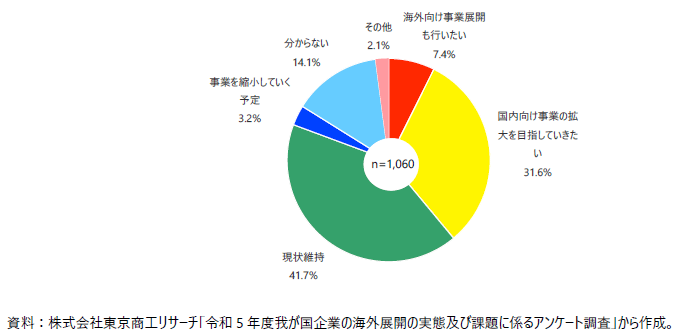
現在、直接輸出を行っていない理由を見ると、「製品が国内向け」で輸出に適さないとの回答が多い(第II-2-3-15表)。特に今後の事業展開で「国内向け事業の拡大」、「現状維持」を選んだ企業のうち、おおむね半数が理由に挙げており、製品の性格によって適切な市場を選択していると見ることもできる。一方で、「海外向け事業も行いたい」と考えている企業は、「製品が国内向け」(29.9%)であることを認めながら、それ以上に「情報やノウハウの不足」(53.2%)、「人材確保や社内体制整備」(41.6%)を強く理由として指摘している。そのほかに「投資資金の不足」(31.2%)、「生産能力が確保できない」(26.0%)も理由に挙げており、このような問題認識は、間接輸出企業の中で「直接輸出への切替え」を今後の事業方針と回答した企業に近い。そのような企業の中には、輸出を以前は行っていたが、「新型コロナや紛争等で中断したため、再開したい」とのコメントも見られた。また、「事業の縮小」を考えている企業にとって「人材確保や社内体制整備」は最大の理由とされており、今後の事業展開を「分からない」と回答した企業にとっても、製品特性に次ぐ理由と指摘されている。
第Ⅱ-2-3-15表 「今後の事業展開」と「現在、直接輸出を行っていない理由」(非輸出企業)
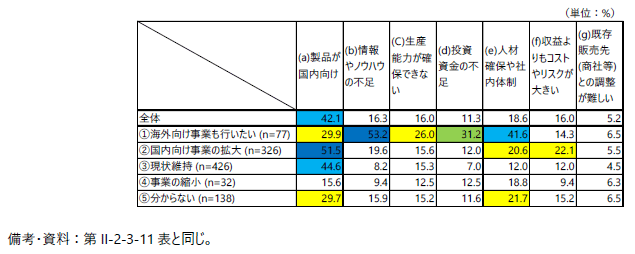
今後の事業展開と現在、間接輸出を行っていない理由を見ると、直接輸出の質問と同様に、「製品が国内向け」との回答が多い(第II-2-3-16表)。特に「国内向け事業の拡大」、「現状維持」を選択した企業であれば、おおむね半数が理由に挙げている。一方、「海外向け事業も行いたい」企業では、約3割の企業は「製品が国内向け」と認めながらも、それ以上に半数近くの企業が「販売先・納入先(商社等)が見つからないため」と回答している。
第Ⅱ-2-3-16表 「今後の事業展開」と「現在、間接輸出を行っていない理由」(非輸出企業)
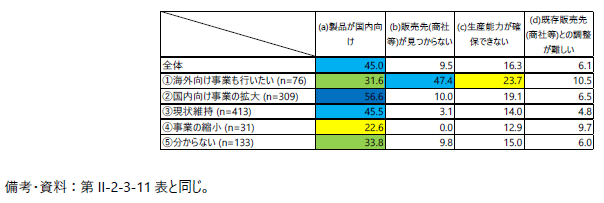
ここまでの調査結果をまとめると、直接輸出企業の場合、今後の事業展開として回答企業の4割弱が現状どおり輸出を続けていくと答え、半数以上が、輸出先の拡大、輸出先は拡大せずとも既存輸出先でのシェア拡大、現地法人設立などのさらなる海外展開など、前向きな方針を掲げていた。しかし、そのためには「需要、商品価格、為替等の変動リスク」、「海外市場向けの商品開発」、「信頼できるサプライチェーン」、「資金・人材確保を含む供給能力の拡大」、「市場に関する情報不足」、「規制、制度、商習慣に関する情報不足」など、様々な課題が超えるべきハードルとして強く認識されている。
間接輸出を行っている企業では、一部に現地法人の設立や直接輸出への切替えを考えている企業がいるほか、間接輸出を通じた販路拡大を考えている企業が約3割存在する。それら企業に共通して、「人材確保や社内体制整備」、「情報やノウハウの不足」が直接輸出を行っていない理由として挙げられ、間接輸出を通じた販路拡大を考えている企業では、「収益以上にコストやリスクが大きい」を挙げる企業も多い。
直接又は間接輸出も行っていない企業の場合、製品が国内向けという製品特性が多くの企業から指摘されているが、一部には海外向け事業も行いたいと考える企業も存在し、それら企業の半分近くが直接輸出の場合は「人材確保や社内体制整備」、「情報・ノウハウの不足」、間接輸出の場合は「販売先が見つからない」という問題を挙げている。この「人材確保や社内体制整備」は、今後の事業展開について事業の縮小や分からないと答えた企業にとっても重要問題に挙げられている。
これら人材、情報、ビジネスマッチング、輸出開始に伴うリスクへの対応等の課題や問題を乗り越えることができれば、我が国企業がより一層の海外展開を果たす可能性が開けることになる。また、近年の円安方向への動きは、輸出を新たに始める観点からは好機でもあり、この機を逃さず、これまで輸出をしたことがない中小企業・地域企業でも、その準備や具体的な商談・輸出を速やかに進められるよう、2022年12月より、経済産業省、中小企業庁、JETRO及び中小機構が一体となり、全国の商工会・商工会議所等とも協力しながら、①新たに輸出に挑戦する事業者の掘り起こし、②専門家による事前の輸出相談、③輸出用の商品開発や売り込みに係る費用への補助、④輸出商社とのマッチングやECサイト出展への支援、などを一気通貫で行う「新規輸出1万者支援プログラム」を実施している。こうした取組等により、中小企業・地域企業が輸出を通じて更なる成長を実現できるよう万全の支援を実施していく。
(5) 決定木を用いた今後の事業展開と海外展開の課題との関係に関する補足的な分析
これまで見てきたように、アンケートの結果として、直接輸出企業、間接輸出企業、直接又は間接輸出を行っていない企業のいずれについても、今後の事業展開についての考え方に対する回答として「現状維持」という回答が最も多い一方で、事業の拡大を考えている企業も一定程度存在していることが明らかになっている。そこで、直接輸出企業、間接輸出企業、直接又は間接輸出を行っていない企業それぞれの、今後の事業展開についての考え方を規定する要因について、決定木を用いた多層的な分類により明らかにすることを試みる。まず、直接輸出を行っている製造業の企業について、今後の事業展開についての考え方を「直接海外に進出してビジネスを行いたい」、「直接輸出の拡大を目指していきたい(新たな輸出先の開拓によるもの及び既存輸出先への輸出の増加によるものの両方を含む)」、「現状維持」、「直接輸出は縮小していく予定」の4類型とし、それを規定する要因として、輸出先の国・地域の数、輸出先の地域(中国、NIEs、アジア新興国(タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インド)、米国、米国以外の欧米、ラテンアメリカ及びオセアニア、中東、アフリカ)、直接輸出を開始した理由、今後の海外展開における課題、売上高、従業員数を用いて決定木による分類を行った結果が第II-2-3-17図である。
第Ⅱ-2-3-17図 直接輸出企業の今後の事業展開についての考え方の回答別の特徴
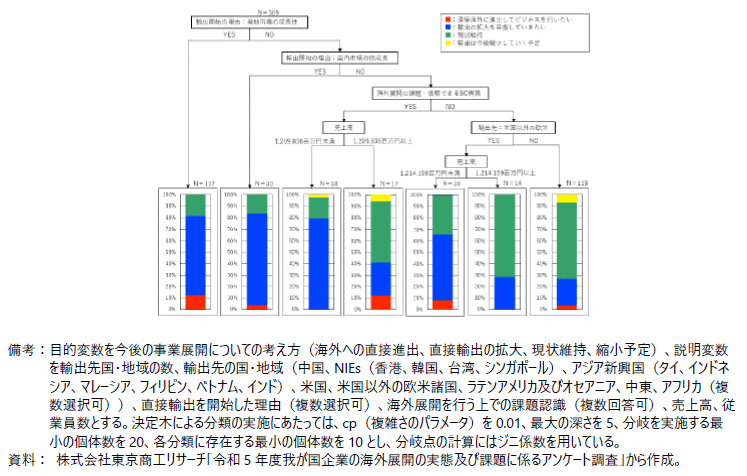
同図より、まず、直接輸出を開始した理由として輸出先の市場規模の成長性を挙げている企業や、輸出先の市場規模の成長性は挙げていないものの国内の市場規模の成長が見込めないことを挙げている企業では、「直接海外に進出してビジネスを行いたい」及び「直接輸出の拡大を目指していきたい」といった今後の海外事業の拡大に対して前向きな回答をした企業が8割以上を占めていたことが確認された。次に、直接輸出を開始した理由として輸出先の市場規模の成長性及び国内の市場規模の成長が見込めないことを挙げておらず、今後の海外展開を行う上での課題認識として信頼できるサプライチェーンの構築の必要性を挙げている企業のうち、売上高が約12億円未満の企業では、今後の海外事業の拡大に対して前向きな回答をした企業が8割程度を占めていた一方で、売上高が約12億円以上の企業では、今後の海外事業の拡大に対して前向きな回答をした企業は4割程度にとどまり、現状維持と回答した企業が5割程度を占めていることが確認された。さらに、直接輸出を開始した理由として輸出先の市場規模の成長性及び国内の市場規模の成長が見込めないことを挙げておらず、かつ今後海外展開を行う上での課題認識として信頼できるサプライチェーンの構築の必要性を挙げていない企業のうち、米国以外の欧米地域の国へと輸出を行っていない企業や、米国以外の欧米地域の国へと輸出を行っている売上高が約12億円以上の企業では、今後の海外事業に対して現状維持と回答した企業が7割程度を占めていた一方で、米国以外の欧米地域の国へと輸出を行っている売上高が約12億円未満の企業では、今後の海外事業の拡大に対して前向きな回答をした企業が6割程度を占めていたことが確認された。
以上より、直接輸出を行っている製造業の企業のうち、成長性の高い市場でのビジネスの展開を目的として直接輸出を開始した企業では、主に直接輸出の拡大を通じた今後の海外事業の拡大を考えている傾向が強いことが示唆された。また、輸出開始の際に市場の成長性は重視していなかったものの、今後の海外展開の課題として信頼できるサプライチェーンの構築の必要性を挙げている、売上高の規模が10億円程度を下回る企業は、今後の海外事業の拡大を考えていることから、こうした課題を挙げている可能性があることが示唆された。なお、今後の海外事業の拡大を考えている企業のうち、直接海外に進出してビジネスを行うことを考えている企業と直接輸出の拡大を目指している企業の間に際立った特徴の差異は見られないことが明らかになった。一方で、輸出開始の際に市場の成長性を重視しておらず、かつ、今後の海外展開の課題として信頼できるサプライチェーンの構築を挙げていない企業や、売上高の大きい企業では、今後の海外事業は現状維持と考えている傾向が強いことが示唆された。
次に、間接輸出を行っている製造業の企業について、今後の事業展開についての考え方を「直接海外に進出してビジネスを行いたい・間接輸出を直接輸出に切り替えたい」、「間接輸出による販路拡大を目指していきたい」、「現状維持」、「間接輸出は今後縮小していく予定」の4類型とし、それを規定する要因として、間接輸出先の国・地域の数、間接輸出先の地域(中国、NIEs、アジア新興国(タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インド)、米国、米国以外の欧米、ラテンアメリカ及びオセアニア、中東、アフリカ)、直接輸出を行っていない理由、輸出のタイプ(何次の間接輸出企業か)、売上高、従業員数を用いて決定木による分類を行った結果が第II-2-3-18図である。
第Ⅱ-2-3-18図 間接輸出企業の今後の事業展開についての考え方の回答別の特徴
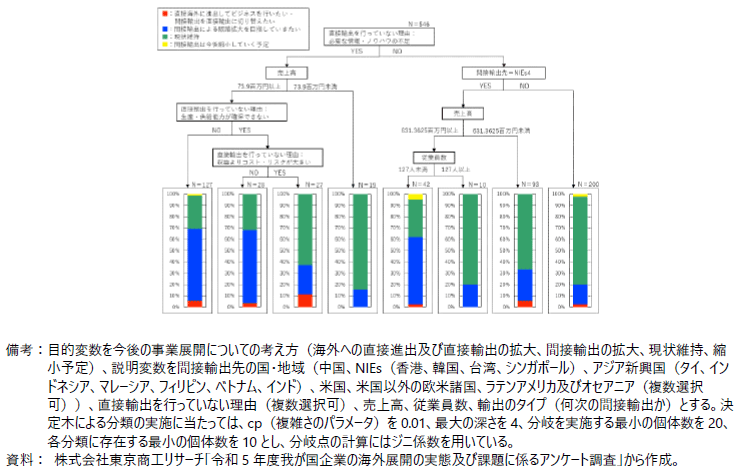
同図によると、まず、直接輸出を行っていない理由として「必要な情報・ノウハウの不足」を挙げており、「生産・供給能力を確保できない」ことを挙げていない、売上高が約7,400万円以上の企業では、今後の事業展開について、「直接海外に進出してビジネスを行いたい・間接輸出を直接輸出に切り替えたい」又は「間接輸出による販路拡大を目指していきたい」と回答しており、今後の事業拡大を考えている企業が約7割を占めていることが確認された。次に、売上高が約7,400万円以上であり、直接輸出を行っていない理由として「必要な情報・ノウハウの不足」及び「生産・供給能力を確保できない」ことを挙げている企業のうち、直接輸出を行っていない理由として「直接輸出による収益よりもコスト・リスクの方が大きい」ことを挙げていない企業では、今後の事業拡大を考えている企業が約7割を占めていることが確認された一方で、直接輸出を行っていない理由として「直接輸出による収益よりもコスト・リスクの方が大きい」ことを挙げている企業では、今後の事業拡大を考えている企業は約4割にとどまり、今後の事業展開を現状維持と考えている企業が約6割を占めていることが確認された。また、直接輸出を行っていない理由として「必要な情報・ノウハウの不足」を挙げており、売上高が約7,400万円未満である企業では、今後の事業展開を現状維持と考えている企業が約8割を占めていることが確認された。さらに、直接輸出を行っていない理由として「必要な情報・ノウハウの不足」を挙げていない企業のうち、間接輸出先がNIEsで無い企業では、今後の事業展開を現状維持と考えている企業が約8割を占めていることが確認された。最後に、直接輸出を行っていない理由として「必要な情報・ノウハウの不足」を挙げておらず、間接輸出先がNIEsである企業のうち、売上高が約6.3億円未満である企業では、今後の事業展開を現状維持と考えている企業が約7割を占めており、また、売上高が約6.3億円以上であり、従業員数が127人以上の企業では、今後の事業展開を現状維持と考えている企業が約8割を占めていることが確認された一方で、売上高が約6.3億円以上で、従業員数が127人未満の企業では今後の事業拡大を考えている企業が約6割を占めていることが確認された。
以上より、間接輸出を行っている製造業の企業においては、売上高が一定程度大きい企業のうち、直接輸出の実施のための情報・ノウハウの不足により直接輸出を行っておらず、直接輸出の実施に向けた生産・供給能力の確保が困難であると感じてはいない企業や、直接輸出による収益よりもコスト・リスクの方が大きいと感じてはいない企業、また、NIEsへの間接輸出を行っている従業員数の少ない企業では、主に間接輸出の拡大により今後の事業拡大を目指していきたいと考えている傾向が強いことが示唆された。なお、直接輸出への切り替えや直接海外に進出することによる事業拡大を考えている企業は非常に限定的ではあるものの、用いた変数にはそれらの企業のみに観察される傾向は存在しないことが示唆された。一方で、直接輸出の実施のための情報・ノウハウの不足により直接輸出を行っていない企業のうち売上高が小さい企業や、直接輸出の実施のための情報・ノウハウの不足を感じていない企業のうち、NIEsへの間接輸出を行っている売上高及び従業員数の大きい企業や、NIEsへの間接輸出を行っていない企業では、今後の事業展開を現状維持と考えている傾向が強いことが示唆された。
最後に、輸出を行っていない製造業の企業について、今後の事業展開についての考え方を「海外向け事業も行いたい」、「国内向け事業の拡大を目指していきたい」、「現状維持」、「事業を今後縮小していく予定」の4類型とし、それを規定する要因として、直接輸出を行っていない理由、間接輸出を行っていない理由、売上高、従業員数を用いて決定木による分類を行った結果が第II-2-3-19図のとおりである。
第Ⅱ-2-3-19図 輸出を行っていない企業の今後の事業展開についての考え方の回答別の特徴
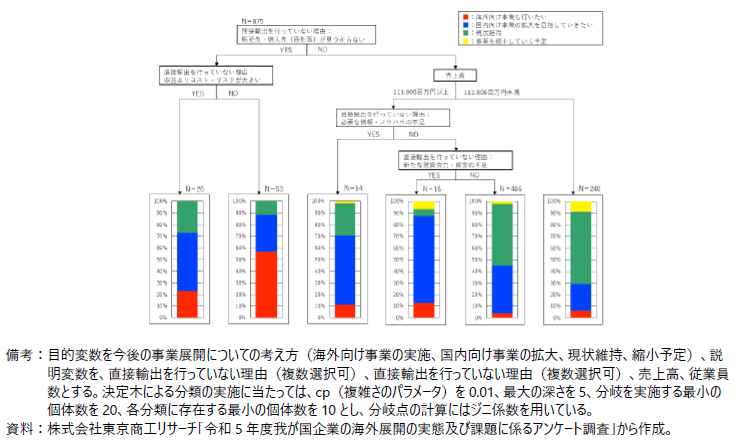
同図によると、間接輸出を行っていない理由として、「販売先・納入先(商社等)が見つからない」ことを挙げている製造業の企業のうち、直接輸出を行っていない理由として「直接輸出による収益よりもコスト・リスクの方が大きい」ことを挙げている企業では、今後の事業展開について「海外向け事業も行いたい」と考えている企業が約2割、「国内向け事業の拡大を目指していきたい」と考えている企業が約5割を占めている一方で、直接輸出を行っていない理由として「直接輸出による収益よりもコスト・リスクの方が大きい」ことを挙げていない企業では、今後の事業展開について「海外向け事業も行いたい」と考えている企業が約6割、「国内向け事業の拡大を目指していきたい」と考えている企業が約3割を占めていることが確認された。
間接輸出を行っていない理由として、「販売先・納入先(商社等)が見つからない」ことを挙げておらず、売上高が約1.1億円以上である企業のうち、直接輸出を行っていない理由として「必要な情報・ノウハウの不足」を挙げている企業では、今後の事業展開について「海外向け事業も行いたい」と考えている企業が約1割、「国内向け事業の拡大を目指していきたい」と考えている企業が約6割を占めていることが確認された。
間接輸出を行っていない理由として、「販売先・納入先(商社等)が見つからない」ことを挙げておらず、売上高が約1.1億円以上であり、直接輸出を行っていない理由として「必要な情報・ノウハウの不足」を挙げていない企業のうち、直接輸出を行っていない理由として「投資余力・資金の不足」を挙げている企業では今後の事業展開について「海外向け事業も行いたい」と考えている企業が約1割、「国内向け事業の拡大を目指していきたい」と考えている企業が約7割を占めている一方で、直接輸出を行っていない理由として「投資余力・資金の不足」を挙げていない企業では、今後の事業展開について「国内向け事業の拡大を目指していきたい」と考えている企業が約4割、「現状維持」と考えている企業が約5割を占めていることが確認された。
間接輸出を行っていない理由として、「販売先・納入先(商社等)が見つからない」ことを挙げておらず、売上高が約1.1億円未満である企業では、今後の事業展開について「現状維持」と考えている企業が約6割を占めていることが確認された。
以上より、輸出を行っていない製造業の企業においては、間接輸出を実施していない理由として「販売先・納入先(商社等)が見つからない」ことを挙げており、「直接輸出による収益よりもコスト・リスクが大きい」と感じていない企業では、今後の事業展開として海外向け事業も行いたいと考えている傾向が強いことが示唆された。また、間接輸出を実施していない理由として「販売先・納入先(商社等)が見つからない」ことを挙げており、直接輸出を実施していない理由として「直接輸出による収益よりもコスト・リスクが大きい」ことを挙げている企業や、間接輸出における「販売先・納入先(商社等)が見つからない」と感じておらず、売上高の大きい企業のうち、直接輸出を行っていない理由として直接輸出の実施に「必要な情報・ノウハウの不足」又は「投資余力・資金の不足」を挙げている企業では、今後の事業展開として国内向け事業の拡大を目指していきたいと考えている傾向が強いことが示唆された。一方で、間接輸出における「販売先・納入先(商社等)が見つからない」と感じていない企業のうち、直接輸出の実施に「必要な情報・ノウハウの不足」及び「投資余力・資金の不足」を感じていない売上高の大きい企業や、売上高の小さい企業では、今後の事業展開として現状維持を考えている傾向が強いことが示唆された。