第4節 グローバルな成長の取り込みを梃とした生産性・イノベーション向上、所得・投資の好循環の実現に向けて
本節では、我が国経済がグローバルな成長の取り込みを梃として生産性・イノベーション向上、所得・投資の好循環を生み出していくための課題について整理する。
1. 我が国製造業のグローバルな成長拡大に向けた課題
本項では、我が国製造業の賃上げ・雇用・投資の状況について確認した上で、我が国製造業がグローバルに成長・拡大するための方策を探るため、企業の資金の流れを可視化することで、企業が資金をどのように活用しているのか、その実態を明らかにする。その上で、企業が成長を加速させ、グローバルに飛躍していく観点から、無形資産投資や直接投資が企業の成長に与える効果に着目し、その効果について検証を行う。
(1) 我が国製造業の賃金・雇用・投資の状況
まず、我が国製造業のこの10年間における賃上げ・雇用・投資の取組状況について見ていく。第II-2-4-1図は、「経済産業省企業活動基本調査」の個票データを用いて、2012年度から2021年度にかけての一人当たり雇用者報酬の変化率、従業者数の変化率、有形固定資産の変化率ごとの企業の分布について、海外現地法人を有する企業(グローバル企業)、海外現地法人を有しない企業(国内企業)のそれぞれについて見たものである。その際、グローバル企業、国内企業のうち、中堅企業219の分布についても示している。これを見ると、グローバル企業は国内企業と比べて雇用や有形固定資産の伸び率の高い企業の割合が高いことが見て取れる。中堅企業に着目すると、グローバル企業のみならず、国内企業においても雇用や有形固定資産の伸び率が高い企業の割合が高い傾向が見られ、我が国の雇用や投資拡大に貢献している様子がうかがえる。第Ⅱ-2-4-1図 製造業企業の賃金・雇用・有形固定資産の変化率の分布(2012年度→2021年度)
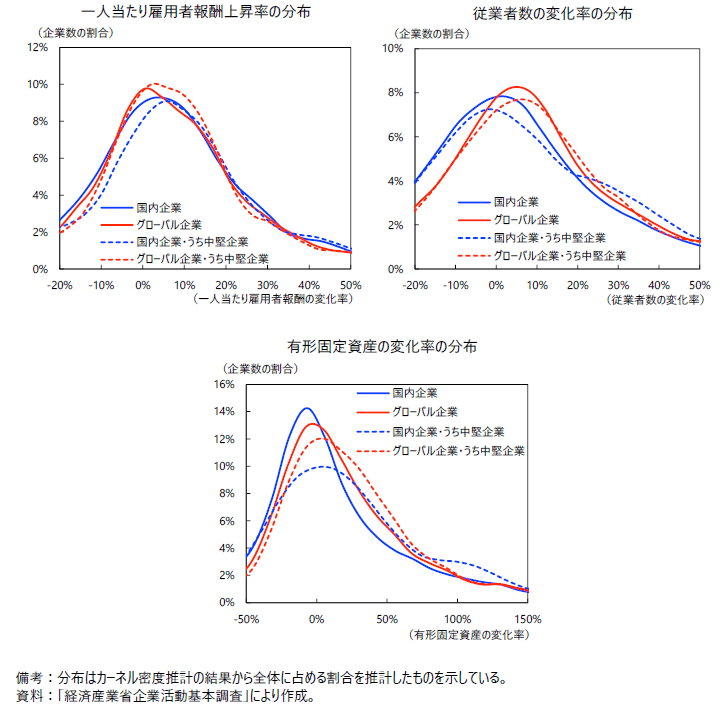
219 製造業においては従業者数が301人以上2,000人以下の企業のうち中小企業者ではない企業を中堅企業とする。
(2) 我が国製造業の資金活用の実態
貸借対照表には、負債の部と純資産の部の和と、資産の部が常に等しいという性質があることから、資金の調達を表す負債の部の各項目は、必ず資産の部のどこかの項目において運用されているとみなすことができる。(第II-2-4-2図)。
第Ⅱ-2-4-2図 貸借対照表のイメージ
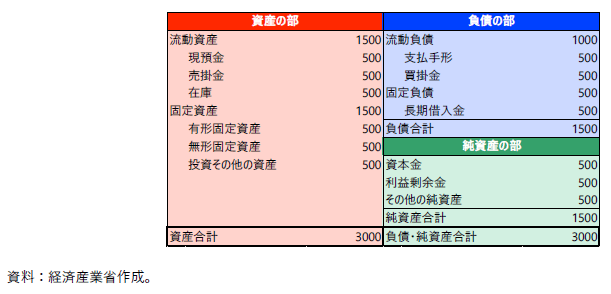
しかし、貸借対照表を確認することにより、資産の部と負債の部、純資産の部のそれぞれの内訳の金額の変化を確認することはできても、負債の部や純資産の部で調達した資金が具体的に資産の部のどの項目として運用されているのかといった資金の流れを確認することはできない。そこで、企業の貸借対照表上では、資産の部の合計と負債・純資産の部の合計の値は一致する、すなわち、ある年から別の年にかけての資産の部の合計の変化額と負債・純資産の部の合計の変化額は一致するという特性に着目し、構造方程式モデリング(SEM:Structural Equation Modeling)の手法を用いて、対象サンプル企業において、一定期間内に調達した資金がどのように運用されたのか、その全体的な資金の流れを構造推定する。「構造方程式モデリングとは、仮説として設定した多数の変数間の関係を、線形結合の形にモデリングして行う分析」(中小企業庁「平成30年版中小企業白書」付注1-4-1220より引用。)の手法221である。本項においては、貸借対照表の考え方に基づき、第II-2-4-3図のように、各負債及び純資産の科目の金額の変化が、各資産科目の金額の変化に対して同時に影響を与えると仮定し、構造方程式モデルを構築する。ここで、貸借対照表において、ある負債・純資産の科目が変化したとき、その変化分は必ず、いずれかの資産科目の変化分として計上され、各資産科目の変化分の合計値はある負債・純資産科目の変化分と一致することとなる。つまり、ある負債・純資産の科目の変化分は、各資産科目に対して分配されると考えることができる。そのため、ある負債・純資産の科目の変化額が各資産の変化額に対して与える影響はそれぞれ、ある期間の各負債・純資産の科目の変化額の各資産の科目に対する配分の割合(分配率)と解釈することができる。なお、データを用いて係数の推計を行う際には、企業ごとにある2時点間における変化額222を算出し、その当初時点の資産の部の合計値(同時点の負債と純資産の和)で除することで基準化を行っている。基準化により各企業の変化額が割合で表され、企業ごとの貸借対照表の規模の違いが制御されることから、企業全体の平均的な負債・純資産の変化額の資産への配分の傾向を統計的手法により検証することが可能となる。
第Ⅱ-2-4-3図 仮定した構造方程式モデリングのイメージ
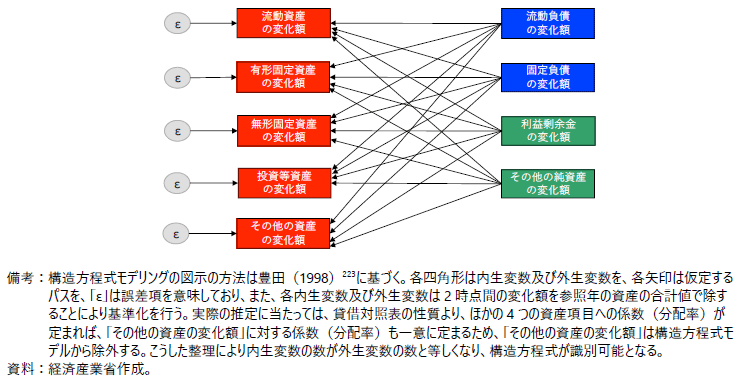
第II-2-4-4図は、2013年度から2021年度の期間における資本金10億円以上の製造業企業の資産の部の合計及び資産の部の各科目の動向を示したものであるが、流動資産や有形固定資産がおおむね横ばい傾向で推移する一方で、投資等資産は増加傾向であることが分かる。
第Ⅱ-2-4-4図 資本金10億円以上の製造業企業における資産の部の各科目の変化
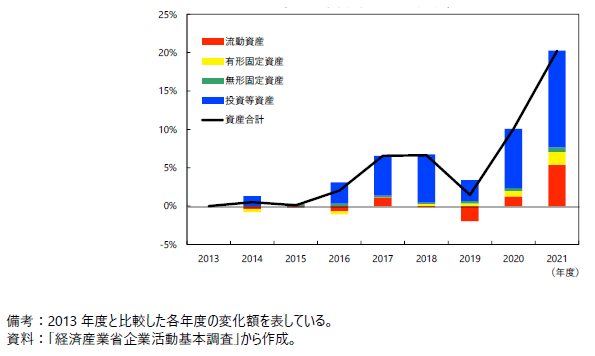
続いて、上述の手法に基づき、「経済産業省企業活動基本調査」を用い、2013年から2019年の期間の負債・純資産の変化額について、資本金10億円以上かつ外資比率が3分の1以下である製造業に該当する企業を対象に、2013年及び2019年の両時点において海外に子会社・関連会社(海外現地法人)を1社以上保有していた企業(構造方程式モデリングに関する推計では、以下、グローバル企業とする。)859社と、保有していなかった企業(構造方程式モデリングに関する推計では、以下、国内の大企業とする。)344社のそれぞれの構造方程式の推計を行った。推計結果を基に、負債の部の各項目の変化額の平均的な各資産項目への分配率を図示したものが第II-2-4-5図である。(推計方法及び結果の詳細については付注2.1を参照。)
第Ⅱ-2-4-5図 構造方程式モデリングに基づく負債の各部門の使途の推計結果
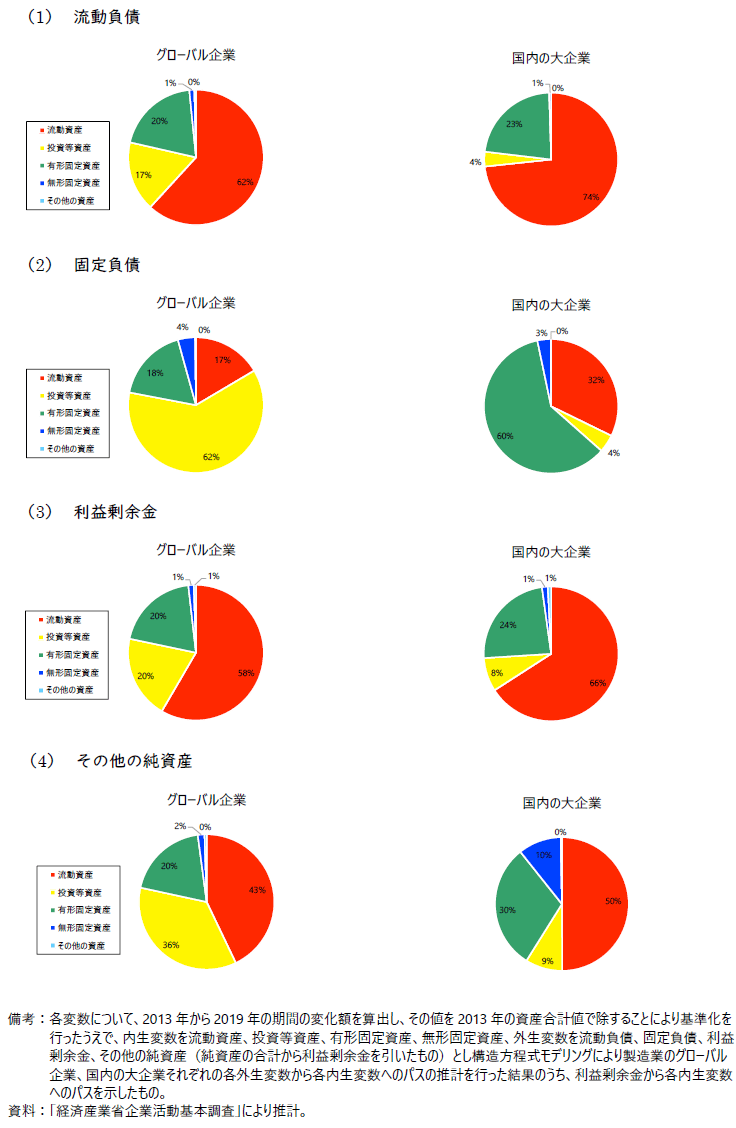
まず、負債・純資産の変化の資産への分配の様子をより仔細に見ると、流動負債の変化は、グローバル企業では約62%が流動資産に、約17%が投資等資産に、約20%が有形固定資産に流れる傾向があったと推計された一方で、国内の大企業では流動負債の変化のうち、約74%が流動資産に、約4%が投資等資産に、約23%が有形固定資産に流れる傾向があったと推計されたことが確認される。固定負債の変化はグローバル企業では約17%が流動資産に、約62%が投資等資産に、約18%が有形固定資産に流れる傾向があったと推計された一方で、国内の大企業では固定負債の変化のうち、約32%が流動資産に、約4%が投資等資産に、約60%が有形固定資産に流れる傾向があったと推計されたことが確認される。利益剰余金の変化は、グローバル企業では約58%が流動資産に、約20%が投資等資産に、約20%が有形固定資産に流れる傾向があったと推計された一方で、国内の大企業では利益剰余金の変化のうち、約66%が流動資産に、約8%が投資等資産に、約24%が有形固定資産に流れる傾向があったと推計されたことが確認される。その他の純資産の変化は、グローバル企業では約43%が流動資産に、約36%が投資等資産に、約20%が有形固定資産に流れる傾向があったと推計された一方で、国内の大企業ではその他の純資産の変化のうち、約50%が流動資産に、約9%が投資等資産に、約30%が有形固定資産に流れる傾向があったと推計されたことが確認される。
以上を踏まえると、2013年から2019年の期間の大企業製造業では、全体の傾向として、資産の部において、流動資産や有形固定資産がおおむね横ばい傾向であったのに対し、投資等資産は増加傾向であることが分かった。調達サイドから運用サイドへの資金の流れでは、固定負債の運用の仕方にグローバル企業と国内の大企業で顕著な差が見られ、グローバル企業では主に投資等資産に、国内の大企業では主に有形固定資産にそれぞれ向けられていることが分かった。また、利益剰余金については、グローバル企業では投資等資産と有形固定資産がほぼ同じ割合で向けられているのに対し、国内の大企業では有形固定資産の比重が大きいことが分かった。ただし、利益剰余金のうち流動資産に流れている傾向があることをもって、投資に活用されていないと判断することは早計である。研究開発投資や人的資本投資(能力開発投資)といった無形資産投資は、毎年の事業活動の中で費用として計上されているため、利益剰余金から流動資産に流れた資金は、こうした投資を反映している可能性がある。
220 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/h30/index.html![]() (2024年4月3日閲覧)
(2024年4月3日閲覧)
221 「構造方程式モデリングでは、相関分析、回帰分析、因子分析を統合した分析が可能であり、一般的なメリットとしては、潜在変数と呼ばれる直接は観測できない因子を含めての分析を行える点や、一つの分析内で複数の従属変数を設定できる点が挙げられる。」(中小企業庁「平成30年版中小企業白書」付注1-4-1 より引用。)ただし、本分析では貸借対照表上で観測できる変数同士の影響を確認することを目的としているため、潜在変数は扱わず観測変数のみを扱う。
222 2時点間の変化額を変数とすることで、各企業の時間不変の固有の要因(固定効果)は制御されると考えられる。
223 豊田秀樹(1998)「共分散構造分析<入門編>―構造方程式モデリング―」朝倉書店
(3) 直接投資・無形資産投資と企業の成長
以降では、投資を通じた企業の更なる成長拡大実現の観点から、直接投資や、人的資本投資、研究開発投資などの無形資産投資と、労働生産性や売上高といった企業の成長との関係について検証を行い、それぞれの投資と企業の成長との関係について整理する。
まず、企業への直接投資及び無形資産投資と、労働生産性との関係について検証を行う。「経済産業省企業活動基本調査」を用いて無形資産投資と労働生産性の影響について検証を行ったMorikawa(2019)224では、2013年から2016年の期間の製造業企業については、各企業及び各年各産業に固有の要因による影響を制御した上で推計を行うと、一人当たりの有形固定資産額はその額が大きくなるほど労働生産性が高くなるという傾向が確認されるものの、能力開発費、研究開発費、広告宣伝費225、ソフトウェア投資といった無形資産投資には、労働生産性との間に統計的に有意な関係性が確認されないという結果が得られている226。こうした結果も踏まえ、本項においては、推計期間を2013年から2019年までに延長し、また、製造業の企業のうち、同期間に海外に現地法人を1年以上有していた企業をグローバル企業、海外に現地法人を有していなかった企業を国内企業として更にデータを分割した上で、Morikawa(2019)と同様の手法を用いて推計を行った(推計の詳細は付注2.2を参照)。
推計の結果、製造業のグローバル企業では、一人当たりの有形固定資産、能力開発費、広告宣伝費のそれぞれについて、その水準が大きくなるほど、労働生産性が高くなるという傾向が確認された一方で、一人当たりの研究開発費及びソフトウェア投資額には、労働生産性との間に統計的に有意な関係性は確認されなかった。また、国内企業では、一人当たりの有形固定資産の水準が大きくなるほど労働生産性が高くなることが確認された一方で、一人当たりの能力開発費、研究開発費、ソフトウェア投資額、広告宣伝費には、労働生産性との間に統計的に有意な関係性は確認されなかった。推計結果のうち、グローバル企業と国内企業それぞれの能力開発費と労働生産性の関係性について第II-2-4-6図のとおり図示している。
第Ⅱ-2-4-6図 人的資本投資と労働生産性の関係
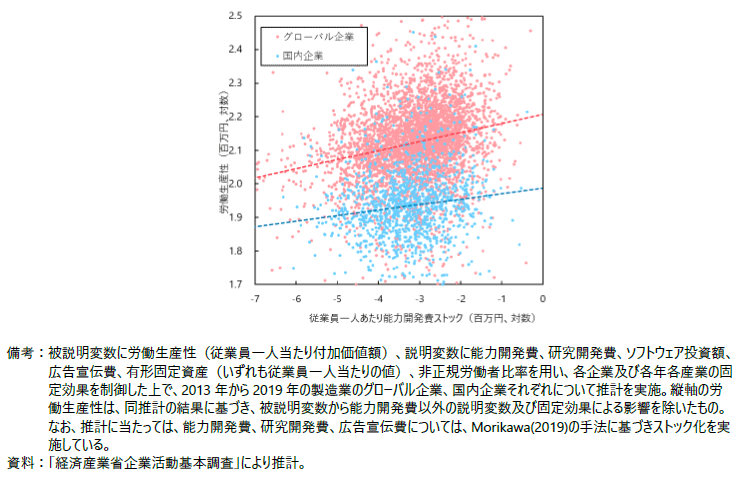
これらの結果から、海外現地法人の有無に関わらず、有形固定資産の増加により労働生産性が上昇する傾向が示唆され、製造業の労働生産性の上昇に対する有形固定資産の有効性が示唆された。一方で、無形資産投資については、海外現地法人の有無や投資項目によって労働生産性への影響は多様であることが示唆された。能力開発費や広告宣伝費について見ると、グローバル企業ではそれらの水準の増加により労働生産性が向上する傾向が示唆された一方で、国内企業ではこうした傾向は確認されず、国内企業ではこれらの投資の有効活用の度合いは、企業ごとにばらつきがあることが示唆された。また、ソフトウェア投資については、海外現地法人の有無に関わらず労働生産性の向上に対する影響は確認されなかった。労働生産性の向上のためにはソフトウェア投資を増加させるだけではなく、それを活用する従業員のスキルの向上(人的資本の向上)が重要であることから、こうした結果が得られたものと推察される。なお、研究開発費についても、海外展開の有無に関わらず労働生産性の向上に対する影響は確認されなかった。労働生産性と研究開発投資の関係性については、研究開発投資の活性化により労働生産性が上昇するという関係性では無く、労働生産性が高い企業が研究開発投資を実施することができるという関係性であることから、こうした結果が得られたものと推察される。例えばIto and Lechevalier (2010)227においても、日本の製造業企業では、労働生産性の水準が将来の研究開発投資の意思決定に大きな影響を与えることや、労働生産性の高い企業は研究開発投資の埋没コストを許容できるため、研究開発投資の実施が可能であることが示唆されている。
次に、研究開発投資と売上高の関係について検証を行う。一般的に、労働生産性が高い企業ほど効率が良いため、一人当たりの売上高も大きいという関係性が考えられることや、前述の検証結果より、労働生産性が高い企業が研究開発投資を実施しているという関係性も考えられることから、検証に当たっては各企業及び各年各産業に固有の要因による影響に加え、労働生産性が一人当たり売上高に対して与える影響についても考慮した上で、グローバル企業、国内企業228それぞれの国内での研究開発投資が海外現地法人を含む全世界での売上高に対して与える影響の推計を行う。労働生産性の影響を考慮していることから、推計結果は、労働生産性の水準が同一の場合の、研究開発投資と売上高の関係と解釈することになる(推計の詳細は付注2.3を参照)。
2013年から2019年の期間の製造業企業について推計を行った結果、労働生産性の水準が同一の場合、海外現地法人を含む従業員一人当たりの国内での研究開発投資額229が大きいほど、海外現地法人を含む従業員一人当たりの売上高230が大きいという傾向があり、かつ、グローバル企業では国内企業と比較してその傾向が顕著であることが確認された。また、労働生産性が高いほど、一人当たりの売上高が大きいという傾向が確認された。ただし、労働生産性については、労働生産性の向上により効率が高まり、一人当たりの売上高が増加するという直接的な影響と、労働生産性の向上により研究開発投資が増加し、それによって一人当たりの売上高が増加するという間接的な影響の両方が考えられる点には注意が必要である。一方で、研究開発投資については、上述の投資と労働生産性の関係の分析結果に基づくと、研究開発投資の増加が労働生産性の上昇を通じて売上高に対して間接的な影響を与えている可能性は小さいと考えることができる。この結果から、海外現地法人の有無に関わらず、労働生産性の水準が高いほど売上高が大きく、事業規模が大きいという傾向が示唆される。また、労働生産性の水準が同一の企業で比較すると、研究開発への投資の増加により売上高が増加し、事業規模が拡大するという傾向や、特に、グローバル企業では研究開発投資の増加による売上高の増加を通じた事業規模の拡大効果が大きいという傾向が示唆された。研究開発投資と売上高の関係について、第II-2-4-7図のとおり図示している。
第Ⅱ-2-4-7図 研究開発投資と売上高の関係
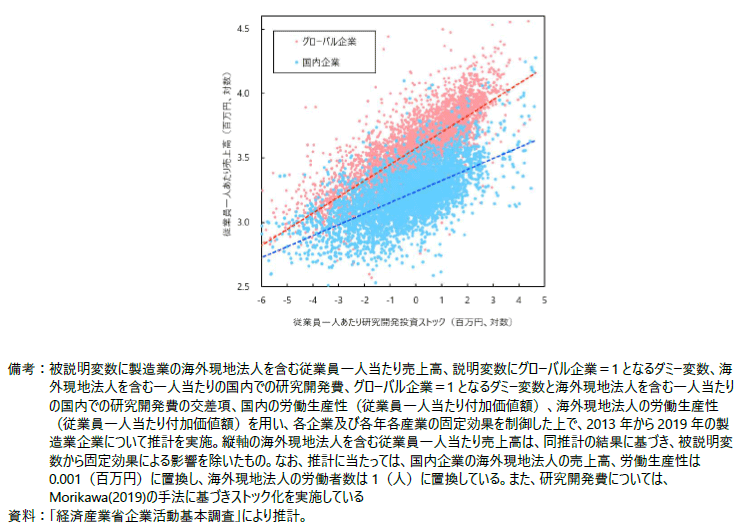
最後に、直接投資と売上高との関係について検証を行う。具体的には、国内及び海外現地法人の労働生産性が売上高に与える影響を考慮しつつ、各企業及び各年各産業に固有の要因による影響を制御した上で、1期前231の各企業の製造業の海外現地法人を含む従業員一人当たりの関係会社への投融資残高(国内向け及び海外向けの両方を含む)232と、当期の製造業の海外現地法人を含む従業員一人当たりの売上高233との関係について検証する。なお、本推計においては、推計期間において1年以上、海外関係会社への投融資残高のデータが存在していた企業をグローバル企業とし、海外現地法人を有していなかった企業を国内企業とする(推計の詳細は付注2.3を参照)。
2013年から2019年の期間の、製造業の企業及びその製造業の海外現地法人を対象として推計を行った結果、海外現地法人を持つ企業では、労働生産性の水準が同一の場合、前期の一人当たりの関係会社への投資額が大きいほど当期の一人当たりの売上高が大きいという傾向が確認された一方で、国内のみに拠点を持つ企業では労働生産性の水準が同一の場合の、前期の一人当たりの関係会社への投資額と当期の一人当たりの売上高の間に統計的に有意な傾向は確認されなかった。また、労働生産性が高いほど、海外現地法人を含む従業員一人当たりの売上高が大きいという傾向が確認された。これらの結果は、グローバル企業では国内及び海外の企業外への投資の増加により事業規模を拡大させている傾向が示唆される一方で、国内企業においては、国内の企業外への直接投資が事業規模の拡大に与える影響が限定的であることを示唆するものである。関係会社への投資額と売上高の関係について、第II-2-4-8図のとおり図示している。
第Ⅱ-2-4-8図 関係会社への投資額と売上高の関係
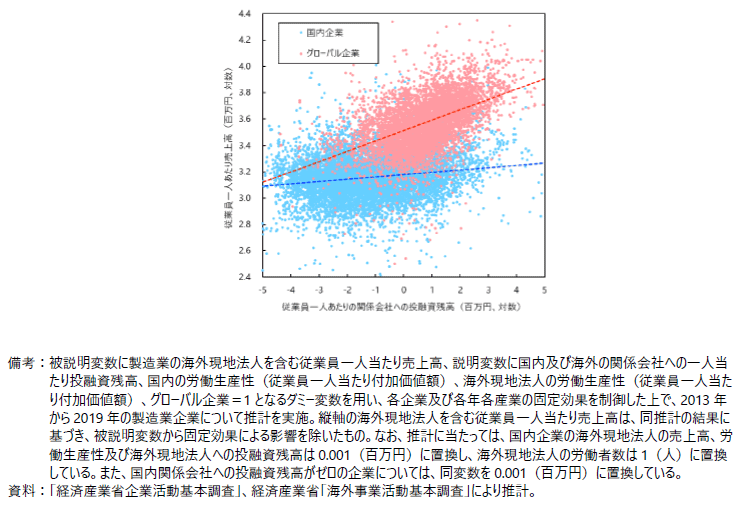
なお、企業の海外への直接投資(海外現地法人の保有)と生産性の関係性については、若杉ほか(2008)234などによると、これまでの経済学における理論及び実証分析においては一般的に、海外現地法人を保有している企業の方が、国内のみに拠点を持つ企業と比較して生産性が高い傾向にあると言われている。一方で、海外現地法人を保有している企業の方が、生産性が高いという傾向の背景にある因果関係については、生産性が高い企業が海外への直接投資という行動を選択可能であるという自然淘汰仮説が成り立つことは広く確認されている一方で、海外への直接投資を通じた知識や技術の吸収などにより生産性が向上するという学習仮説については不明瞭であるという。例えば、令和5年版通商白書235においても、傾向スコアマッチングを用いて製造業企業の海外展開の開始前後の生産性の変化を企業属性の類似した海外展開を行っていない企業と比較したところ、海外展開の開始による生産性の上昇の効果は確認されなかったという結果が得られている。これらの先行研究を踏まえると、上述の企業外への投資と売上高との関係の分析において、海外への投資の拡大が企業の生産性の増加を通じて一人当たりの売上高を増加させるという間接的な影響が見られる可能性は小さいと考えられる。
本項においてこれまで行ってきた、企業の投資と生産性、一人当たり売上高の関係性についての検証結果を整理したものが第II-2-4-9図である。本項の検証においては、海外現地法人の有無や投資の種類によって企業の成長に対する影響は異なることが確認されている。製造業のグローバル企業については、有形固定資産への投資に加えて、人的資本への投資などの無形資産投資を活用して生産性を向上させていること、また、高い生産性が海外への直接投資や研究開発投資の増加につながっていること、そして、それらの投資を通じて事業規模を拡大させていることが確認され、投資が労働生産性の向上や事業規模の拡大といった企業の成長に活用されていることが示唆される。特に、グローバル企業は国内のみならず海外の市場へのアクセスも可能となっていることから、研究開発投資による事業規模の拡大効果が国内企業と比較して大きく、また、関係会社への投資による事業規模の拡大効果も見られると考えられる。一方で、製造業の国内企業では有形固定資産への投資は生産性の向上に活用されているものの、無形資産投資の活用度合いには、ばらつきがあることが確認される。ただし、国内企業においても、労働生産性の高い企業では事業規模が大きいという傾向や、研究開発投資の増加により事業規模が拡大するという傾向も確認されており、投資の労働生産性の向上への活用には課題があるものの、投資は事業規模の拡大には活用されていることが示唆される。
第Ⅱ-2-4-9図 分析結果等を踏まえた企業の成長拡大経路
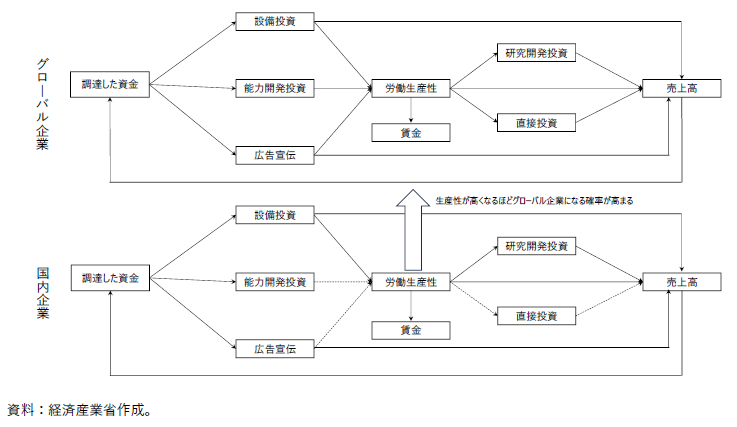
以上より、労働生産性の向上により、研究開発投資の活用や海外への直接投資の実施を通じた事業規模の拡大の実現の可能性が高まり、さらなる成長が見込まれるため、国内企業を含む今後の成長を志向する企業においては、まずは労働生産性を向上させることが重要であることが示唆される。
これまで本項では、まず、我が国製造業の賃金・雇用・投資の状況について確認し、グローバル企業は国内企業と比べ、雇用や投資の伸び率が高い企業の割合が高いこと、中堅企業ではグローバル企業のみならず国内企業においても雇用や投資の伸び率が高い企業が多いことを示してきた。また、構造方程式モデリングを用いて、貸借対照表から企業の資金の流れを可視化し、調達した資金がどのように運用されているか、その使われ方に焦点を当てて分析を行い、その上で、企業の投資と成長の関係性について検証を行ってきた。これらの検証から、企業は調達した資金を設備投資や人的資本投資に活用することを通じて労働生産性を向上させ、そして、労働生産性の向上や研究開発投資、直接投資を通じて事業規模を拡大させるというプロセスにより成長を実現し得ることが示唆された。特に製造業のグローバル企業では製造業の国内企業と比較して、利益のうち投資に回る割合が大きいこと、投資が労働生産性の上昇に対して効果的に利用されていること、労働生産性の上昇により海外への直接投資が可能となっていること、海外市場との結びつきが強まることから投資による事業規模の拡大効果が大きいことが確認されており、これらを通じてより高い成長を実現させていることが示唆された。また、今後の成長を志向する企業においては、労働生産性の上昇により、研究開発投資の活用や海外への直接投資の実施を通じた事業規模の拡大の実現の可能性が高まり、更なる成長が見込まれるため、まずは有形固定資産や人的資本への投資を行うことを通じて、労働生産性を上昇させることが重要であることが示唆された。ただし、国内企業については、能力開発投資や広告宣伝費を有効に労働生産性の上昇につなげられていないといった課題も浮き彫りとなっており、その有効性を高める取組や支援の必要性が示唆されているといえよう。
企業がグローバルな成長拡大を実現していくためには、企業のグローバルな活動の基盤となる環境整備を進めていくことが重要であり、次節では、こうした環境整備に向けた我が国の取組について取り上げる。
224 MORIKAWA, Masayuki (2019)” Employer-Provided Training and Productivity: Evidence from a Panel of Japanese Firms”, RIETI Discussion Paper Series 19-E-005
225 同論文においては能力開発費、研究開発費、広告宣伝費を恒久棚卸法によりストックの変数に変換した上で推計を実施している。
226 ただし、同論文によると、同期間の製造業とサービス業の両方を含むサンプルを用いて推計すると、能力開発費、研究開発費、ソフトウェア投資、広告宣伝費についても労働生産性との統計的に有意な正の関係が確認されるという。
227 ITO, Keiko and LECHEVALIER Sebastien(2010),"Why Do Some Firms Persistently Outperform Others? An investigation of the interactions between innovation and export strategies", RIETI Discussion Paper Series 10-E-037
228 前述の検証と同様、推計期間において海外に現地法人を1年以上有していた企業をグローバル企業、海外に現地法人を有していなかった企業を国内企業と定義する。
229 (国内での研究開発費ストック)÷(国内の従業員数+海外現地法人の従業員数)
230 (国内での売上高+海外現地法人の売上高)÷(国内の従業員数+海外現地法人の従業員数)
231 売上高の増加により関係会社への投資額が増加する、という逆方向の関係性も考えられることから、1期前の投資額を用いる。一般的に考えて、当期の売上高の増加により1期前の投資額が増加するという関係性は成立しないことから、1期前の値を用いることにより逆方向の関係性の影響を制御することができる。
232 (国内関係会社への投融資残高+海外関係会社への投融資残高)÷(国内の従業員数+海外現地法人の従業員数)
233 (国内での売上高+海外現地法人の売上高)÷(国内の従業員数+海外現地法人の従業員数)
234 若杉 隆平、戸堂 康之、佐藤 仁志、西岡 修一郎、松浦 寿幸、田中 鮎夢、伊藤 萬里(2008)「国際化する日本企業の実像-企業レベルデータに基づく分析-」RIETI Discussion Paper Series 08-J-046
235 https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2023/whitepaper_2023.html![]() (2024年4月5日閲覧)
(2024年4月5日閲覧)
2. グローバルな成長を取り込み、投資・イノベーション・所得の好循環を実現するための我が国の取組
我が国経済がグローバルな成長を取り込み、更なる成長を実現し、投資・イノベーション・所得の好循環を生み出していくためには、その基盤となる環境整備を推進していくことが重要である。以下では、自由で公正な国際秩序と経済安全保障の確保、輸出促進、対外直接投資の促進、対内直接投資の促進の大きく四つの観点から我が国の取組について見ていく。
まず、自由で公正な国際秩序と経済安全保障を確保する観点では、2023年5月に我が国が議長国となって開催されたG7広島サミットで確認された方針に基づいて、G7以外の国々との協力も模索しながら取組を進めていく。具体的には第Ⅱ部第1章第6節で見たように、我が国はルールに基づく国際経済秩序の維持に貢献しながら、その中で経済安全保障の観点を踏まえながら強靱なサプライチェーンを構築するとともに、グローバル・サウスを含めた各国との共存共栄関係を築いていく。この中でも特に経済安全保障の確保に関しては、技術優位性の確保、重要な物資・エネルギー・社会インフラ等についてのサプライチェーンの強靱化、情報保全制度の確保等を実施する。まず、技術優位性の確保については、経済安全保障推進法に基づき、我が国が中長期的に国際社会において確固たる地位を確保し続ける上で不可欠な要素となる先端的な重要技術の研究開発を進める「経済安全保障重要技術育成プログラム236(K Program) 」 を実施し、研究開発から技術実証まで一貫した支援を行う。次に、サプライチェーンの強靱化については、経済安全保障推進法において指定する、国民の生存に必要不可欠又は広く国民生活・経済活動が依拠している重要な物資である、特定重要物資の見直し・追加を行っていくとともに、当該物資の安定供給確保に向けた企業の国内生産基盤の確保のための設備投資等への支援等を行う。また、国民生活及び経済活動の基盤となっているエネルギー・交通・輸送・通信・金融等の「基幹インフラ」については、これに関わる経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業を行う者のうち、主務大臣が指定した事業者が重要な設備の導入・維持管理等の委託を行う際の事前審査制度を設け、安定的な役務の提供を担保する。さらに、急速に普及しつつある生成AIを始めとするデジタル化の進展や、サイバー攻撃の深刻化・巧妙化が進む中で、重要性が増しているサイバーセキュリティの観点に関しては、サプライチェーン全体での対策強化に向けてガイドライン等の管理・一元化を行いながら業種横断的なセキュリティ対策水準を定義し、各企業における取組を可視化する枠組みを構築する。その先行ケースとして、IoT製品のセキュリティ適合性を4段階のレベルで評価する制度を2024年度から一部運用開始し、政府調達等における活用を進めていく。また、先述のK Programにおいても、サイバー空間の状況把握や防御に関する技術等を重要技術に指定して研究開発を支援していく。最後に、情報保全制度については、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報にアクセスする必要がある者に対して、政府による調査を実施し、当該者の信頼性を確認した上でアクセスを認める制度であるセキュリティ・クリアランス制度が2024年5月に法制化されており、適切な執行を行っていく。また、こうした経済安全保障を確保するための施策の立案・推進に際しては、対内的には脅威・リスク分析や重要な物資に係るサプライチェーンの強靱化等について産業界との意見交換を実施していくとともに、対外的にはG7等の国際プラットフォームも活用しながら有志国・同志国との対話を活発化させていく。
次に、輸出促進については、我が国企業の輸出環境の整備、特に中堅・中小企業で輸出事業の経験がこれまで無い、又は浅い企業に対する支援、サービス貿易の促進等を行っていく。まず、輸出環境の整備については、政府出資の特殊法人である株式会社日本貿易保険 (Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) ) が融資保険を提供する海外企業に対して、将来的にスタートアップを含む我が国企業との取引の創出・拡大に積極的に取り組むことを条件づけることで、我が国企業の輸出環境改善につなげる「SEED (Support to Expand Emerging Deals) スキーム」を2023年5月に創設しており237、本スキームの活用を進めていく。また、近年民間企業によるサービス立ち上げが進んでいる、輸出入者のみならず運送業者や税関当局など貿易業務に携わる複数の関係者間でのデータ共有を可能にする貿易プラットフォームサービスの活用促進のための補助金の導入や、貿易に携わる関係者によって構成する検討会238での貿易DXの意義や課題についての議論、データの連携性を高めるためのトレードファイナンス等に係る国際標準改定の働きかけ等を通じて、貿易手続に関するデジタル技術を活用したコスト削減を推進していく。さらに地域に焦点を当てた施策としては、2023年度に策定した「日本とASEANの貿易デジタル化の推進に向けた取組のロードマップ」239の実現に向けたASEAN各国の取組を支援していく。次に、中堅・中小企業等の輸出促進については、専門家による無料相談やプロモーション等に係る費用への補助等をメニューとする、輸出未経験企業等を対象にした新規輸出1万者支援プログラム240を推進・強化し、民間事業者による輸出支援ビジネスを育成しながら、中堅・中小企業による輸出が自律的に拡大する仕組みの構築を目指す。さらに、サービス貿易の促進については、インバウンド(訪日外国人旅行)による需要の創出や、コンピュータサービスの国際収支赤字(いわゆる「デジタル赤字」)の解消に向けた取組等を行っていく。インバウンド需要創出に関しては、2023年5月に策定した「新時代のインバウンド拡大アクションプラン」241に基づいて戦略的に取り組んでいく。また、一部の地域や時間帯によっては、観光客による過度な混雑やマナー違反による地域住民の生活への影響や観光客の満足度低下への懸念が生じている状況への対応として、地方部の観光地の個性を引き出すようなデザイン・アート投資による高付加価値化を実現するなどして、地方部への誘客・分散化をより一層推進していく。さらに、世界的に有名な観光資源がなくとも招致可能なビジネス客の来日・延泊ニーズにも着目し、全国の自治体と連携しながら、これまでにない新たなビジネス・インバウンド市場の創出を目指す。また、特に足下では、2025年に我が国での開催が予定されている国際博覧会(大阪・関西万博)の機会をいかし、万博を契機とした全国への誘客促進やビジネス・インバウンド誘致を行っていく。そしてコンピュータサービスの国際収支赤字の解消に関しては、2023年6月に改定版を取りまとめた「半導体・デジタル産業戦略」242に沿って、クラウドプログラムやAIの開発力を高めるとともに、それらの開発に不可欠な計算資源と、デジタル産業を支える半導体の安定的な確保を進めていく。また、各種クラウドサービスに代表されるコンピュータサービスは、量子コンピュータの実装など今後破壊的な技術革新が進むと見込まれており、経済安全保障上重要な先端技術分野でもある。そのため、2023年10月に策定された「経済安全保障に係る産業・技術基盤強化アクションプラン」243において、デジタル赤字の解消に向けた数値目標(「デジタル自給率」的な指標)など、トップダウンの目標設定も検討することとしている。最後に、2023年8月24日に海洋放出を開始した東京電力福島第一原発におけるALPS処理水244に関しては、国際原子力機関 (IAEA) とも連携しながら水産物や海水等のモニタリングを行い、その結果を公表しているが、計画どおり安全に放出が行われていることが確認されている。一部の国・地域が科学的根拠に基づかない輸入規制措置を講じているが、措置の即時撤廃を求めていくとともに、輸出先の転換対策や国内加工体制の強化対策等を含めた水産業支援に万全を期していく245。
さらに、我が国企業の対外直接投資の促進については、グローバル・サウス諸国との連携、特にインドやアフリカ等の我が国企業の進出が相対的に進んでいない地域への進出や当該地域の産業人材育成への支援、資金調達支援等を重点的に行っていく。まず、グローバル・サウス諸国との連携に関しては、2023年10月に首相官邸において「グローバル・サウス諸国との連携強化推進会議」246が立ち上げられており、同推進会議は2024年6月に「グローバル・サウス諸国との新たな連携強化に向けた方針」を取りまとめた。その方針の中では、歴史、文化、宗教、政治体制、経済の発展度合いなど、多様な背景を抱える同諸国それぞれの事情やニーズに応えて、対話と協働による社会的価値の共創を実現することや、国際社会における協調を目指していくことなどが確認されている。この方針に基づきながら経済連携を強化するとともに、2023年度補正予算において1,400億円(国庫債務負担を含む。また、アジアの公正な脱炭素化移行加速化事業の一部を含む。)が措置されたグローバル・サウス未来志向型共創等事業の中で、グローバル・サウス諸国の抱える多様な社会課題の解決と我が国の産業構造高度化の双方に資するような未来産業を共創するフラッグシッププロジェクトの案件組成を支援すべく、実証調査や地域別戦略の策定を行っていく。また、特に中東・アフリカ等と連携するに当たっては、当該地域への供給拠点としてプレゼンスの高いインド等と共に面的に展開する第三国連携の枠組みを構築し、その枠組みを起点として、インフラ構築やファイナンス強化等をパッケージにしながら、重点分野・国を特定した戦略的取組を実施していく。次に、インドやアフリカ等の我が国企業の進出が相対的に遅れている地域に係る支援に関しては、現地のパートナー企業等との協業によるビジネス実証支援を行うとともに、我が国企業が当該地域でビジネスを行うに当たって必要な人材を現地で採用できるよう、産業人材の育成支援を行っていく。資金調達支援に関しては、国際経済環境が激変する中でも、NEXIの貿易保険制度を通じて企業のグローバルな挑戦を支えていくため、リスク管理と財務基盤の双方の強化を進める。その際、特にサプライチェーン強靱化やGX、国際連携を含む政策的意義の高い分野については、政府が企業の挑戦を下支えすべく、重点的な保険提供を可能としていく。
最後に、対内直接投資の促進については、2023年4月に策定された「海外からの人材・資金を呼び込むためのアクションプラン」247の中で、対内直接投資残高を2030年に80兆円とする従来の目標を引き上げ、2030年に100兆円とする目標とし、その目標を早期に実現することとしている(2023年末時点では50.5兆円)。同プランでは、「1.国際環境の変化を踏まえた戦略分野への投資促進・グローバル・サプライチェーンの再構築」、「2.アジア最大のスタートアップハブ形成に向けた戦略」、「3.高度外国人材等の呼び込み、国際的な頭脳循環の拠点化に向けた制度整備」、「4.海外から人材と投資を惹きつけるビジネス・生活環境の整備等」、「5.オールジャパンでの誘致・フォローアップ体制の抜本強化、G7等を契機とした世界への発信強化」の五つの柱に沿って取組を進めることとしている。これを踏まえ、まず一つ目の柱については、半導体やGX等の戦略分野に関して、海外の特定技術等を持つ企業の誘致を実現するために、国内外の産業拠点の立地要因等を比較分析し、その結果を基に国と地域が一体となり候補地域の産業基盤高度化や、海外の有望企業の経営者層の招聘や事業実施可能性調査への支援等の誘致施策を加速させていく。二つ目の柱については、2023年12月に我が国とASEANにおいて将来のビジネスリーダーとなることが期待される人材が集まり同時開催された「日ASEANヤングビジネスリーダーズサミット」及び「日ASEAN・Z世代ビジネスリーダーズサミット」248のように、国内外のスタートアップ・エコシステム関係者とのネットワークを構築・強化し、相互理解や信頼関係を築いていく。また、我が国企業とスタートアップ等の海外企業の国際的なオープンイノベーション創出のためのビジネスプラットフォームであるJETROのJ-Bridge249を通じて、我が国企業と海外企業との協業連携を進めていく(2023年度は31件創出)250。三つ目の柱については、産学官の関係者で協力して高度外国人材の獲得や定着・活躍への支援を行うために2022年度及び2023年度に国内6地域(北海道、東北、北陸、関西、中国、九州)で立ち上げた高度外国人材活躍地域コンソーシアム251を軸としながら、人材の獲得だけでなく、就労環境整備等の定着や活躍までも視野に入れた伴走型支援を企業に対して行っていく。四つ目の柱については、G7在日商工会議所連携会議(2023年度は4回開催)を始め、海外の政府機関・経済団体・企業・投資家等と連携し、我が国のビジネス環境の課題を把握し、例えば2024年度中に全省庁で運用開始が予定されているAIを活用した我が国の法令の翻訳システム252等のように、改善のために必要な対応を実施していく。最後に五つ目の柱については、地域別の誘致施策や海外企業の定着・二次投資に向けたフォローアップ策を議論するための「地域投資誘致フォローアップ連絡会議」(2023年度は北海道、近畿、九州で開催)を活用し、必要な施策を着実に実施していく。さらに、対日直接投資推進会議(2024年5月)において、「海外からの人材・資金を呼び込むためのアクションプラン」各施策の進捗についてはフォローアップを行い、加速・深化すべき事項である高度外国人材の確保、国内企業と海外企業との協業促進やビジネス・生活環境の整備を「対日直接投資加速化に向けた優先プログラム」として決定し、対日直接投資の更なる拡大を図ることとした。
加えて、国内企業の競争力を強力に後押しし、グローバルに勝ち抜ける企業の育成を支援していくことも重要である。とりわけ、中堅企業は、国内で事業・投資を拡大し、地域での賃上げにも貢献している重要な存在である。他方、中堅企業から大企業へと成長する企業の割合は国際的に低い状況であり、国内外の大企業と競争していくための成長投資等を十分に行えていないといった課題も存在している。そこで、政府は、2024年を「中堅企業元年」とし、中堅企業の成長を促進するため、中堅企業が活用可能な各府省庁の施策を取りまとめた「中堅企業成長促進パッケージ」253を策定した。こうした施策の活用を促進することにより、国内に基盤を構築しながらグローバル市場を獲得していく中堅企業の成長を後押ししていく。
このように、我が国はルールにもとづく自由で開かれた国際経済秩序の維持を重視しつつ、経済安全保障の観点を踏まえた強靱なサプライチェーンを同志国と連携しながら構築するとともに、グローバル・サウス諸国など成長の期待される地域とも共存共栄の関係を築き、グローバルな成長を取り込みながら、更なる成長を実現し、投資・イノベーション・所得の好循環を生み出していく。
236 内閣府Webサイトを参照 (https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/kprogram.html![]() )。
)。
237 株式会社日本貿易保険「2023年5月12日ニュースリリース資料」、(https://www.nexi.go.jp/topics/newsrelease/2023042704.html![]() )。
)。
238 経済産業省Webサイトを参照(https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/index.html![]() )。
)。
239 日アセアン経済産業協力委員会Webサイトを参照 (https://ameicc.org/aseanjapan_economic_co-creation_forum/summary/_data/Dissemination%20of%20Digitalization%20in%20ASEAN%20and%20Japan.pdf![]() )。
)。
240 JETRO Webサイトを参照 (https://www.jetro.go.jp/ichiman-export.html![]() )。
)。
241 国土交通省Webサイトを参照 (https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001612100.pdf![]() )。
)。
242 経済産業省Webサイトを参照(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semiconductors_and_digital.pdf![]() )。
)。
243 経済産業省Webサイトを参照 (https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/231031actionplan.pdf![]() )。
)。
244 ALPS処理水とは、東京電力福島第一原子力発電所の建屋内にある放射性物質を含む水について、トリチウム以外の放射性物質を、安全基準を満たすまで浄化した水のこと。
245 経済産業省Webサイトを参照 (https://www.meti.go.jp/press/2023/09/20230905001/20230905001-1.pdf![]() )。
)。
246 首相官邸Webサイトを参照(https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202310/17globalsouth.html![]() )。
)。
247 内閣府Webサイトを参照 (http://www.invest-japan.go.jp/committee/action_plan.pdf![]() )。
)。
248 経済産業省「2023年12月17日プレスリリース」、(https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231217003/20231217003.html![]() )。
)。
249 JETRO Webサイトを参照 (https://www.jetro.go.jp/j-bridge/![]() )。
)。
250 スタートアップに関する分析については、「令和5年版通商白書」第II部第2章第5節を参照。
251 JETRO Webサイトを参照 (https://www.jetro.go.jp/hrportal/region/![]() )。
)。
252 法務省Webサイトを参照 (https://www.moj.go.jp/content/001414686.pdf![]() )。
)。