第2節 中国の景気低迷と過少消費構造
米国が世界経済を牽引した裏側では、世界第二位2の経済大国である中国が、世界経済の成長エンジンとしての牽引力を失いつつあるという変化も起こっている。中国では、厳格な新型コロナウイルス感染症の封じ込め策(いわゆる「ゼロコロナ政策」)が解除された後も、景気の低迷が続いている。不動産市場の不況に伴う逆資産効果3や、当局の経済関連政策を巡る不確実性の高まり、さらには米国や欧州との地政学的な対立が逆風となっており、消費者マインドの三年間にわたる底ばい推移に見られるように、成長期待が中長期的に下方屈折したともいえる状況にある(第I-1-2-1図)。
第Ⅰ-1-2-1図 中国の消費者信頼感指数
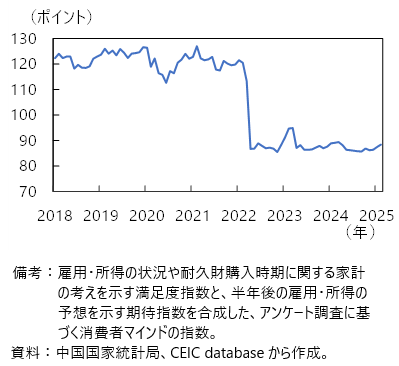
こうした構造的な需要の停滞を背景に、中国経済はデフレ圧力の増大に直面しているが4、その中でも、少なくとも2024年の後半までは、当局は地方政府や国有企業を含む財政規律を重視し、2008年の世界金融危機後に実施したような大規模な財政出動にはなお慎重であると理解されていた。成長率の鈍化が続く中で、世界金融危機後とは対照的に、コロナ禍後の中国の輸入は伸び悩みが鮮明である(第I-1-2-2図)。これは、中国向け輸出の多いアジアや一部の欧州の国にとっては、外需の弱含みを通じた景気の追加的な下押し要因となっている。
第Ⅰ-1-2-2図 中国の輸入数量
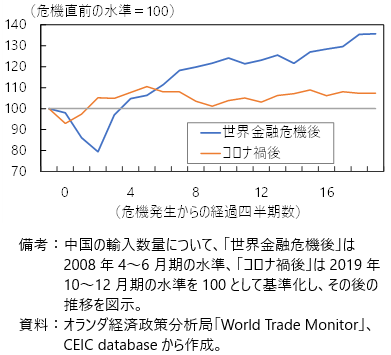
中国経済のデフレ圧力の高まりの背景には、需要が下振れする中でも供給サイドへの投資が調整されていないという事実もある。中国経済は、米国・EUや日本と比較してGDPに占める固定資本投資の割合が高く、2023年においても中国の固定資本形成は41%と、消費よりも投資に偏重した構造になっている(第I-1-2-3図)。また、資本ストックのGDPに対する比率を表す資本係数を試算すると、コロナ禍の時期を除いて、基本的に上昇トレンドを続けている(第I-1-2-4図)。日本と比べても高い資本係数の上昇に歯止めがかかっていないことは、経済規模に比して資本ストックが多く、生産効率が悪化している可能性を示唆する。
第Ⅰ-1-2-3図 主要国・地域のGDPの需要項目内訳(2023年)
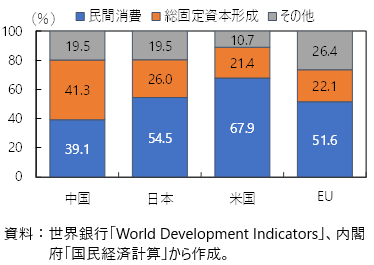
第Ⅰ-1-2-4図 日中の資本係数の推移
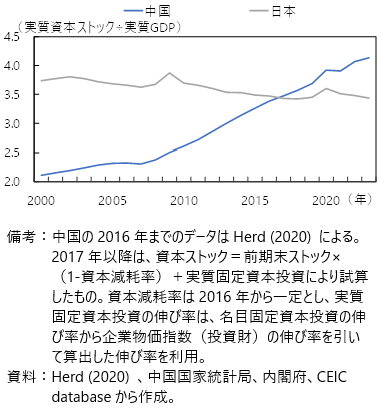
内需が下振れているにもかかわらず、政府が主導する積極的な投資、供給能力の積み増しが続いた結果、輸出単価の下落を伴って輸出が大きく増加するデフレ輸出の流れが見られ、世界中の多くの輸出先国・地域から懸念の声が上がっている。特に欧米諸国は、中国の市場歪曲的な措置とも関連付けて、過去にも問題となった鉄鋼だけでなく、近年中国政府が特に力を入れて支援してきた先端産業の分野を含む「過剰生産能力」の国際的な影響に懸念を表明している。
実際に、直近数年で中国国内の鉄鋼生産能力の余剰は再び拡大しており(第I-1-2-5図)、輸出全体及び鋼材、太陽電池等の品目の輸出単価は大幅に低下している(第I-1-2-6図)。加えて、足下では、米中貿易摩擦を回避する流れとみられる、アジア周辺国を始めとする新興国・途上国への輸出シフトも見られる(第I-1-2-7図)。一部には既に摩擦が生じつつあり、世界経済の不安定化要因の一つとなっている。
第Ⅰ-1-2-5図 中国の鉄鋼の生産能力と生産量の差の推移
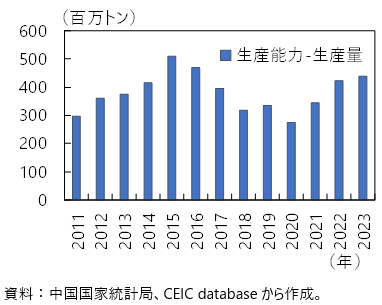
第Ⅰ-1-2-6図 中国の輸出単価・数量の推移
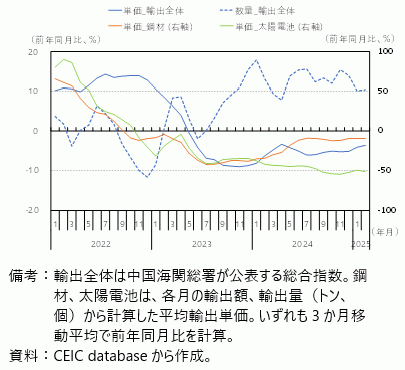
第Ⅰ-1-2-7図 中国の国・地域別の輸出額伸び率の推移
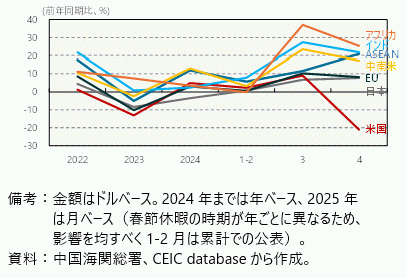
こうした過少消費構造、輸入停滞とデフレ輸出拡大の傾向は、中国の実質GDP成長率に占める最終消費の寄与が減少し、純輸出の割合が高くなっていることにも表れている(後掲の第I-5-3-1図)。産業構造や消費構造の転換には一定の時間を要すると思われるが、経済政策の重点を投資から消費に移し、供給サイドの過剰投資や過当競争を抑制することが重要である。さらに、国内需要を拡大する政策を強化するだけでなく、輸入障壁の削減・撤廃を含め、予見可能で公正な貿易関連政策・事業環境の整備を通じて、貿易を巡る緊張関係を緩和していくことが重要と考えられる(第Ⅱ部第2章第4節で詳述)。
2 名目ドルベース。
3 資産価格の下落により、保有資産の価値の減少を感じた家計が消費を抑制する効果。
4 第Ⅰ部第5章第3節参照。