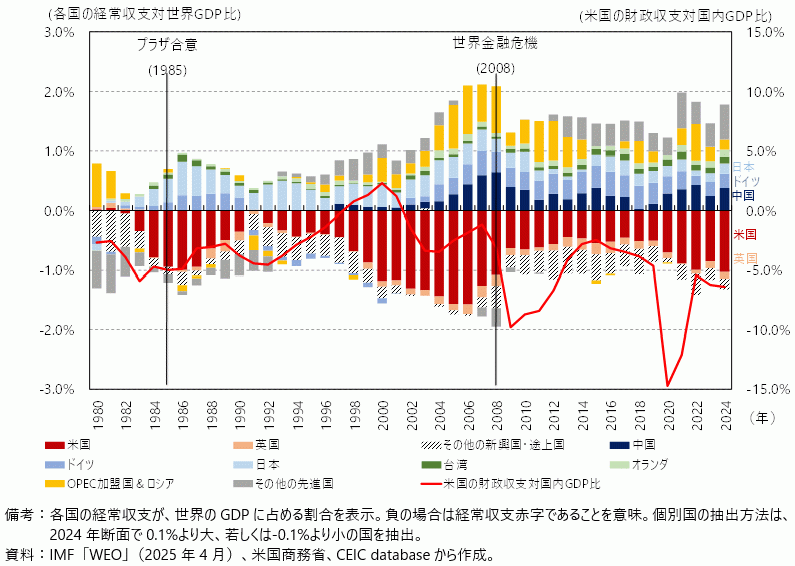2025年に入ってからの貿易政策を巡る劇的な変化と不確実性の増幅は、戦後のルールベースの国際経済秩序が岐路に立たされていることを強く印象づけた。同時に、戦後の国際経済秩序が様々な課題に直面していることは、近年の国際政治経済環境の変化の中で既に顕在化しつつあったことも確かである。そうした中で、国境を超えるビジネス活動を巡る不確実性は高まってきている。
戦後、西側諸国を中心に発展したルールベースの国際経済秩序は、冷戦終結後にグローバルな拡大と深化を遂げた。それは自由化を通じた具体的な貿易投資障壁の低減だけでなく、「ルール志向」の基本的理念5を具現化し、国際ルールによって国境を超えるビジネスの予見可能性を飛躍的に高めてきたことに、極めて重要な価値があった。しかし、近年の国際情勢の変化は、このルールベースの国際経済秩序を動揺させ、不確実性を増大させている。
本章では、①保護主義と貿易摩擦、②過剰生産能力と過剰依存のリスク、③地政学リスクと経済安全保障認識、④パワーバランスの変化とグローバルサウス、⑤デジタル化とグリーン移行への多様な対応に注目して、近年の動向と変化を概観する。こうした国際環境変化がもたらす不確実性を検討することは、転換期にある国際経済秩序の状況を理解し、今後の世界経済動向と貿易投資関係を展望する上で重要な視点である。
5 経済産業省(2024)
第1節 保護主義と貿易摩擦
1. 近年の貿易摩擦を巡る経緯
貿易政策の不確実性は、貿易投資や国内経済に負の影響を与える。冷戦後に世界の大多数の国々がWTOやFTA/EPAにコミットメントを示してきたことは、国境を超えるビジネスの予見可能性を大きく向上させ、貿易投資の拡大や経済成長に寄与してきた6。これはルールベースの国際経済秩序が提供してきた重要な価値である。
近年の保護主義の拡散と貿易摩擦の影響を考える上では、関税引上げ等による直接的な効果だけではなく、そうした貿易政策の不確実性が国境を超えるビジネス活動に与える影響を考慮することが不可欠である。2010年代後半からの経緯を振り返ると、米中対立を始めとする貿易摩擦の激化は、貿易政策を巡る不確実性を高めてきた(第I-2-1-1表)。米国第一次トランプ政権期には、中国産品に対して通商法301条に基づく追加関税を課し、中国も米国産品に対して追加関税に踏み切るといった数次にわたる関税引上げ合戦が行われた。また、米国は通商拡大法232条に基づく鉄鋼・アルミの輸入に対する追加関税を発動し、EU、中国、インド、ロシア、トルコはセーフガード協定第8条を根拠とする対米対抗措置を発動し、カナダ、メキシコはNAFTA上の規定を根拠とする対米対抗措置を発動した。米国の追加関税の実施に関しては、製品別・国別除外の扱い等を巡っても先行きを見通しづらい状況が続いた。
第Ⅰ-2-1-1表 近年の主な貿易措置の応酬
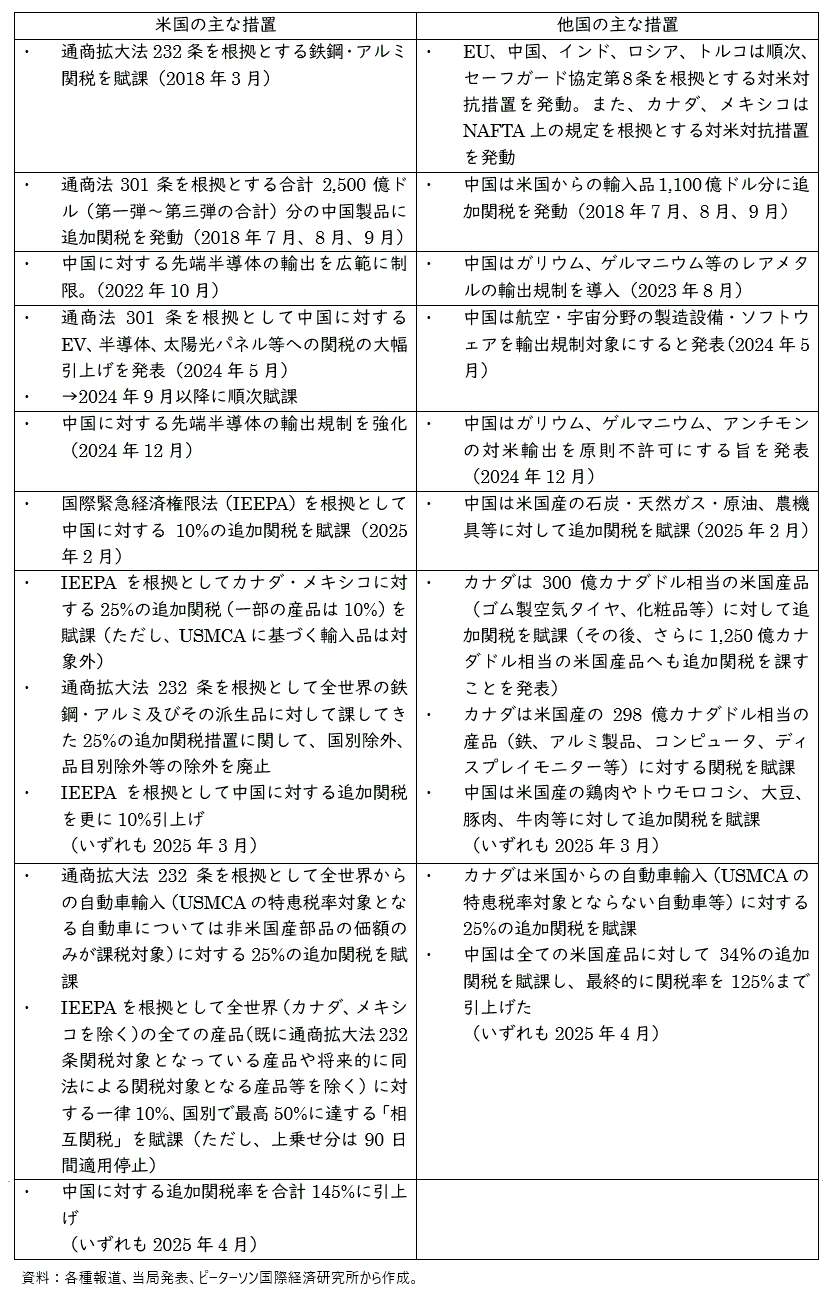
バイデン政権は、同盟国との協調を重視し、鉄鋼・アルミ関税の一部調整を行う一方で、中国に対しては第一次トランプ政権期の関税を維持し、先端半導体を始めとする戦略分野の輸出・投資規制や中国製品をサプライチェーンから排除するような動きを強めてきた。2024年には規制対象品目を一段と広げ、これに対して中国もレアメタルの輸出管理強化などの措置を打ち出した。こうした動きにより、米中貿易や関連ビジネスの不確実性は高止まりしていた。
加えて、米国で2022年8月に成立したインフレ削減法(IRA)に対しては、多数の国が、税控除の条件等に関してWTO協定に抵触する可能性を提起している。実際に、中国は同法に基づく税控除が自国産品を差別するものであるなどと主張してWTOにおける協議要請を実施し、その後、紛争解決パネルで審議されている。こうした動向は、貿易関連政策にかかる不確実性を一層高めた。
また、近年、経済的威圧と呼ばれる行為に対する懸念が高まっている。2023年10月のG7大阪・堺貿易大臣会合の声明では、「我々は、他の政府による正当な主権的選択に干渉する威圧的な経済的措置及びその威嚇に関する我々の共通の懸念を改めて表明し、そのような措置の再発が拡大していることを憂慮する。」と言及した。こうした行為は、ルールベースの貿易関係に対する信認を著しく毀損し、ビジネスにとっての不確実性を高める要因になる。
世界全体で見ると、貿易制限措置は増加の傾向にある。世界の貿易投資に影響を与える各国政策を集約したデータベースであるGlobal Trade Alertによれば、世界の貿易制限措置は2010年代後半から急増し、2022年以降は3,000を越える措置数で高止まりしている。また、その対象は財だけでなくサービスや投資にも広がりを見せていることがうかがえる(第I-2-1-2図)。
第Ⅰ-2-1-2図 世界の貿易制限措置の数
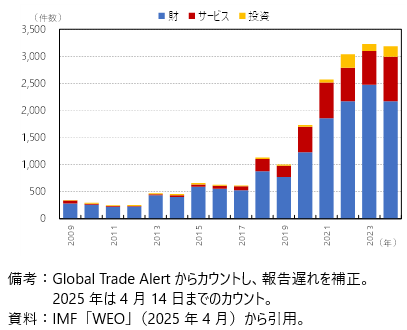
6 森川(2025)
2. 2025年の動向
2025年1月に米国の第二次トランプ政権が発足すると、通商政策を巡る不確実性は劇的に高まった。トランプ政権は2月、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づいて、合成麻薬の流入を理由に中国産品に対する10%の追加関税を発動した。一方の中国は、対抗措置として即座に米国からのLNG等に対する追加関税等を決定した。3月に入ると、トランプ政権は、同じくIEEPAに基づき、中国産品に対してさらに10%追加関税を発動し、対する中国は、米国からの鶏肉や小麦、大豆等への追加関税等を決定した。また、カナダ・メキシコに関しては、不法移民や合成麻薬の流入を理由に、IEEPAに基づき、両国の産品へ25%の追加関税(一部産品については10%)を1か月の延期の後に実施した(ただし、USMCAに基づく輸入品は対象外)。また、通商拡大法232条を根拠として全世界の鉄鋼・アルミ及びその派生品に対して課してきた25%の追加関税措置に関して、国別除外、品目別除外等の除外を廃止した。
さらに、通商政策を巡る不確実性を決定的に高めたのは、4月に入ってからの一連の動きである。4月2日、米国はIEEPAに基づき、メキシコ、カナダを除く全世界に対して一律10%、貿易赤字の大きい国に対しては最高50%の国ごとの税率に関税を引き上げる、いわゆる「相互関税」を発表した。翌日には、既に発表していた通商拡大法232条に基づく自動車の25%追加関税も施行した。その後、一連の変更・修正を経て、4月9日時点では、鉄鋼・アルミや自動車に対する25%の追加関税が実施され、中国に対する合計145%の追加関税が発表された一方、中国以外に対する相互関税は、引上げが行われる予定であった国別税率につき、4月10日から90日間適用を停止することが発表された(10%一律関税は維持)。その他にも、米国は半導体や医薬品等の産品に関する通商拡大法232条に基づく調査も開始している。これに対して、中国が125%の対米追加関税を実施するなど、他国は様々な対応をとっており、全体として貿易政策を巡る不確実性が高い不透明な状況となっている。
こうした第二次トランプ政権の関税賦課は、米国の実効関税率を大幅に上昇させ、4月9日の時点で1930年のスムート・ホーリー法による関税引上げの時期を上回る水準となっている(第I-2-1-3図)。一連の関税措置が、IEEPA等に基づく行政府の意思決定によって行われ、頻繁に変更・修正が重ねられていることも、不確実性を高めている一因である。
第Ⅰ-2-1-3図 米国の実効関税率
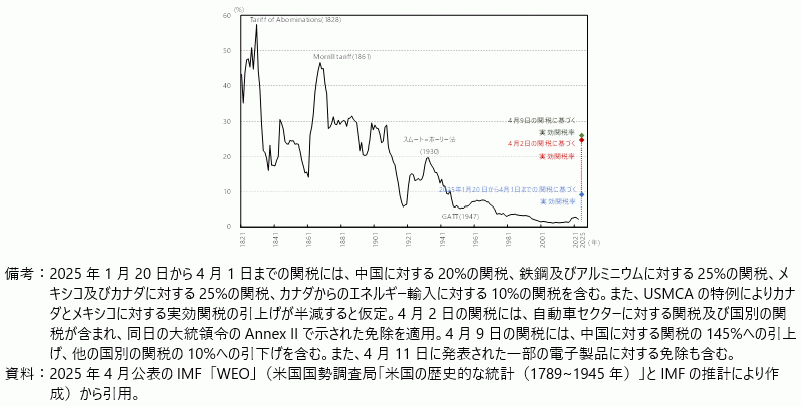
なお、一連の関税措置の背景として、第二次トランプ政権は米国の二国間での貿易赤字を問題視しているとされる。ただし、貿易赤字解消、製造業の国内回帰、雇用、経済安全保障、税収の確保、過剰なドル高の修正といった関連する政策目標の相互関係や優先順位、それらと関税引上げとの関係性は、必ずしも明らかではない。関税の引上げそのものに加えて、こうした政策的な一貫性を巡る曖昧さが、米国の通商政策を巡る不確実性を高める要因となっている。
ここで、世界各国の経常収支(対世界GDP比)のバランスを確認する(第I-2-1-4図)。足下で経常収支黒字が大きいのは、中国とドイツである。日本は近年、財・サービス収支が赤字だが、第一次所得収支黒字によって経常収支も黒字となっている。米国は直近、世界の経常収支赤字の大半を占め、世界金融危機の頃よりは低いが、プラザ合意の頃と同水準まで増えている。同時に、米国の財政収支も赤字が拡大傾向であり、対GDP比で見ると、足下では世界金融危機の後やコロナ禍の時期よりは低いものの、プラザ合意の頃を上回るようになっている。経常収支と財政収支の赤字がいずれも増大する、いわゆる双子の赤字の状態である。一般論として、過度な経常収支の不均衡は持続可能ではないとされる。現下の貿易摩擦の背景として、注視していく必要がある。
第Ⅰ-2-1-4図 主要国・地域の経常収支対世界GDP比と米国の財政収支対国内GDP比