第2節 過剰生産能力と過剰依存のリスク
近年、過剰生産能力と過剰依存のリスクが、不確実性の要素として認識されるようになった。一般論として、特に生産設備の短期的な調整が困難な重厚長大型の産業においては、景気循環の後退期に過剰生産能力が発生しやすい傾向にある。加えて、例えば中国の鉄鋼産業等では、約20年前から、計画経済から市場経済への移行過程において、国有企業に代わって民営企業が経済の担い手になる中で、両者の混在状況が過剰生産能力の要因になっているとの指摘が行われていた7。
その後、より幅広い分野において、一部の国の産業政策が、生産サイドの投資を過剰に促し、過剰生産能力となって、急激な輸出拡大につながっているとの議論も行われるようになっている。実際、2014年頃には鉄鋼や造船、化学繊維等の分野において、新興国を中心に、経済性を考慮しない形で生産能力の拡張が進み、過剰生産能力状態が発生した。これに伴う市況の低迷が収益の悪化を招き、貿易救済措置8の増加等につながった9。
特定産品の急激な輸入拡大は、場合によっては競合する他国の産業や製造基盤を短期間に損なわせ、同産品の供給を特定国に過剰に依存する状況を作り上げるとの懸念が指摘される。これは、既に述べたいわゆる経済的威圧行為を可能にする状況を作り出す要因にもなっている。
こうした中、2010年代後半以降、特に世界の貿易救済措置の調査開始頻度が増しており、足下では2024年の調査開始件数が大幅に増加した(第I-2-2-1図)。WTO協定で認められた貿易救済措置の活用は、ルールベースの国際経済秩序の下での各国の正当な権利だが、具体的な手続きや実施次第で、ビジネスの観点では不確実性を高める側面もあることには留意が必要である。この点も含め、過剰生産能力と過剰依存に起因するリスクの増大は、国境を超えるビジネス活動にとっての不確実性を高め、既存の国際経済秩序が直面する課題の一つになっている。
第Ⅰ-2-2-1図 世界の貿易救済措置の調査開始・発動件数
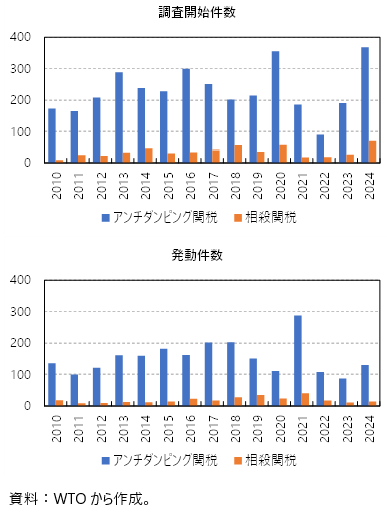
7 関(2006)
8 一般的に、アンチダンピング措置、補助金相殺関税措置、セーフガード措置を指す。それぞれの詳細については経済産業省(2024)参照。
9 経済産業省(2024)