第2章で見たような国際環境の変化は、国境を超える経済活動に広範な影響を及ぼしている。不確実性が高まると企業や家計の活動が下押しされることはかねてから指摘されてきたが、近年は特に各国の政策を巡る不確実性が構造的に高まってきており、その影響が一時的なものにとどまらない状況となっている。
本章では、国際経済秩序を揺るがしている構造変化のうち、認識レベルでの不確実性の増大について、足下までの状況を整理するとともに、それらが世界経済に及ぼしている影響を定量的に分析する。なお、本章における分析は、利用可能な2025年1月までのデータを用いており、その後の第二次トランプ政権による関税措置等の影響は含まれていない。
第1節 不確実性の構造的な増大
企業収益や国際貿易を直接的に下押しする関税等の政策は、当然ながら経済活動に大きな影響を及ぼす。しかし、実際にそうした政策変更やイベントが発生せずとも、その可能性があるだけで経済活動が萎縮し、場合によってはイベントの直接的な影響よりも経済へのインパクトが大きくなることがある。先行きに対する不透明感が高まると、企業や家計は様子見姿勢を強め、投資の先送りや高額品の購入を取りやめるといった行動を取りやすくなる。実際に経済・政策環境が変化せずとも、「景気がこの先悪化する可能性がある」という予想が広がるだけで、自己実現的に景気が悪化するのである。本節では、まず、こうした不確実性の状況について主要国・地域ごとに概観した上で、その増大が世界経済に与える影響を分析する。
1. グローバルな経済政策の不確実性
景気を悪化させる不確実性には様々なものがあるが、近年の国際政治経済環境の文脈では、各国の経済政策に起因する不確実性が重要である。2024年末以降は特に通商政策を巡る不確実性が注目を集めているが、近年のインフレ局面において各国の利上げの開始時期やペース等、金融政策の先行きの見方が分かれたように、政策的な不確実性は様々な分野で生じ得る。
不確実性は本来的に捉えづらいものであるが、各種の政策に関する不確実性を定量的に捉えることを試みた指標として、米国スタンフォード大学のブルーム教授らが考案した経済政策不確実性指数(Economic Policy Uncertainty Index: 以下、EPU指数)がある。EPU指数は、各国・地域の主要紙において経済政策に関する不確実性に言及した新聞記事数が全記事数に占める割合を指数化したものであり、数字が大きいほど不確実性が拡大していることを示す14, 15。
EPU指数は20か国程度を対象に作成されているが、まず、各国の指数をGDPウェイトで加重平均することで算出されている世界全体のEPU指数を見ていく(第I-3-1-1図)。
第Ⅰ-3-1-1図 グローバルな経済政策不確実性(EPU)指数
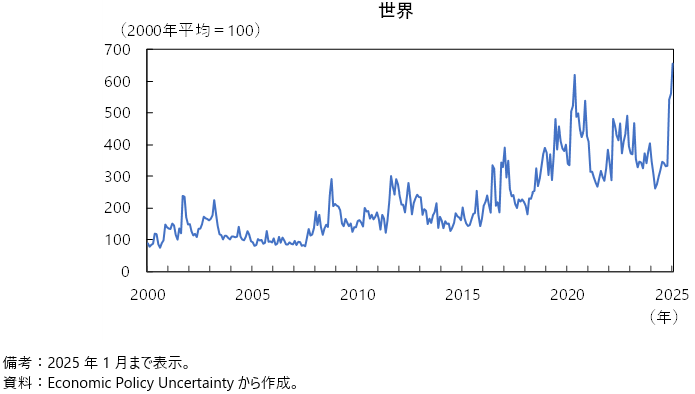
グローバルなEPU指数は、2000年代は米国同時多発テロ(2001年)やその後のイラク戦争の開戦(2003年)、そして2008年の世界金融危機時に明確に上昇したが、その他の時期は基本的に横ばい圏内で推移していた。この時期は、当初のイベント発生時に大きく高まるものの、状況が大きく変わらない限りは再び元の水準に回帰していくという、EPU指数の定常性が示唆されていた。
ところが、2010年代以降のグローバルEPU指数は、2000年代と比べて水準が全体的に切り上がったように見える。すなわち、2010年代前半に水準がやや上振れした後、2015年頃からは緩やかな上方トレンドを辿っている様子がうかがわれ、2020年の新型コロナウイルス感染症の拡大後に急騰した時期を経て、2025年に入った後には過去最高水準に達している。こうした上方トレンドの背景について、以下で主要国・地域のEPU指数について詳しく見ていく。
14 Economic Policy Uncertainty, ‘Economic Policy Uncertainty Index’, https://www.policyuncertainty.com/ (Accessed 24 April 2025).
15 同様のテキストベースの不確実性指数として、英国の定期刊行物「エコノミスト」の調査部門エコノミック・インテリジェンス・ユニット各国の報告書内における「不確実(uncertain)」及びそれに関連する言葉の割合を集計した「世界不確実性指数(WUI)」がある。経済政策に限らない不確実性を捕捉し、国のカバレッジもEPU指数より広いという特長があるが、各国現地の新聞記事を基にしたEPU指数の方が国ごとの不確実性を捉えるという点では実態に近いと考えられる。
2. 主要国・地域の不確実性
グローバル指数を構成する主要国・地域を見ると、2010年代以降のEPU指数の上昇トレンドが顕著なのは、欧州主要国16・中国・韓国である(第I-3-1-2図)。特に欧州は2010年代前半から、中国は2010年代後半からEPU指数が上向きのトレンドを示しており、グローバルなEPU指数を押し上げていると見られる。
第Ⅰ-3-1-2図 先進国・アジアの経済政策不確実性(EPU)指数
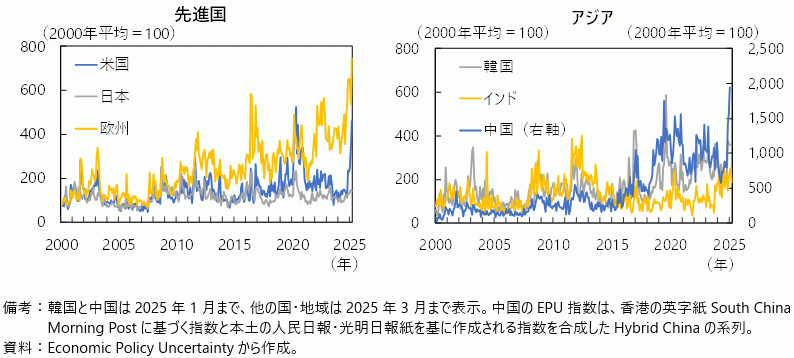
16 フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、英国の合成指数。
(1) 欧州
欧州主要国のEPU指数を見たのが第I-3-1-3図である。世界金融危機に伴う深刻な不況が続く中、2010年以降、金融市場では政府債務の持続可能性に対する懸念が大きく高まった(欧州債務危機)。問題の発端となったギリシャだけでなく、長期金利の上昇が波及したスペインやイタリアのEPU指数は、2010~2012年にかけて大きく上昇した。また、南欧の国債を多く保有するユーロ圏内の金融機関の経営が悪化したこともあり、債券売りの動きが一段と広がる中でフランスにおける不確実性も高止まりした。この間、ドイツの長期金利はマネーの逃避先として低下を続けており、EPU指数も低位で安定していた。このように、2010年代前半における欧州のEPU指数の上昇は、主としてドイツ以外の国における欧州債務危機が背景にあったと考えられる。
第Ⅰ-3-1-3図 欧州主要国の経済政策不確実性(EPU)指数
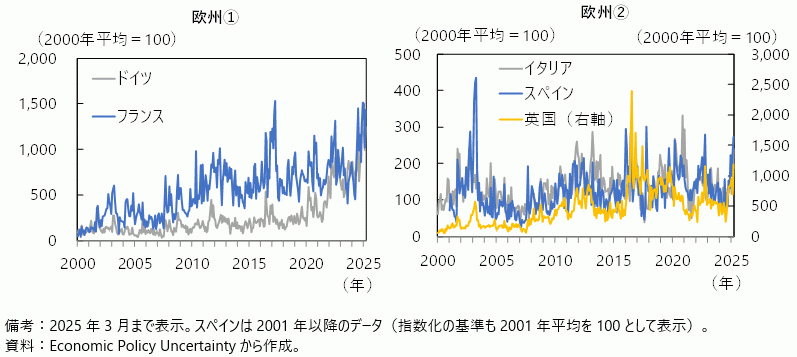
欧州債務危機は2012年以降収束に向かったが、その後は代わって各国で政治的な不透明感が大きく高まった。2011年の「アラブの春」以後、欧州に中東からの移民が数多く流入したことは、世界金融危機や欧州債務危機後の長引く不況と相まって、各国で反移民・反EUを掲げる大衆迎合主義的な主張への支持を強めた。
英国では、2016年の国民投票でEUからの離脱(Brexit)が大方の予想に反して過半の支持を集め、EPU指数は異常な水準に高騰した。Brexitの方針が決まった後もEUとの離脱交渉は困難を極め、英国・EU間の企業活動は数年にわたって強い不透明感に直面した。フランスでも2017年にEPU指数が急騰したが、これは同年4月における大統領選の第1回投票で極右政党の候補が第2位となったことの衝撃が影響している。大統領選後は不確実性の増大に一旦歯止めがかかったものの、燃料価格の高騰に対する反発から広まった「黄色いベスト運動」の拡大などを背景に、その後も2000年代の水準に低下することはなかった。この間、イタリアやスペインでも極右政党の支持が広がり、不確実性は上下動を繰り返した。
ドイツでも反移民を掲げる極右政党は東部州を中心に支持を広げたが、2010年代の終盤まで不確実性が大きく拡大することは避けられた。しかし、ドイツのEPU指数は、第一次トランプ政権期の米国・EU間の貿易摩擦17を背景に徐々に上向き始めた後、2020年の新型コロナウイルス感染症後に大幅な上昇を見せるようになった。感染抑制のための封鎖措置(都市封鎖)などにより、政策の予見可能性が低下したことは各国共通であったが、ドイツのEPU指数の動きの特徴は2020年以降に構造変化といえるような急激な上方シフトを見せたことである。その背景としては、まず、2021年の総選挙後に発足した社会民主党(SPD)・緑の党・自由民主党(FDP)の三党連立政権が当初から様々な意見対立を抱え、財政出動を含む経済政策の推進力が大きく低下したことがある。加えて、2022年2月のロシアによるウクライナ侵略とそれに伴うエネルギー価格の高騰は強い逆風となり、中国との関係悪化も相まってドイツ経済は製造業を中心とする構造的な不況に陥った。さらに、2024年秋以降は、連立政権の崩壊、その後の総選挙における極右政党の大幅な躍進、そして米国の第二次トランプ政権による通商・安全保障・内政を巡る強硬な発言・政策が不確実性を増大させ、ドイツのEPU指数は過去最高を更新した。
以上のように、2010年以降の欧州では、世界金融危機後の不況と欧州債務危機、移民の増加を背景とした大衆迎合主義の伸長と政治の不安定化、ロシアによるウクライナ侵略の逆風、そして米国による様々な政治的な要求の強まりといった形で、次々と不確実性を高める要因が生じ続けた。これにより、EPU指数も恒常的に押し上げられた。
17 第Ⅰ部第2章第1節参照。
(2) 中国
EPU指数の上振れが目立つ中国も、欧州と同様に複合的な要因が背景にあると考えられる。指数が上昇を始めた2015年頃は、世界金融危機後の大規模な景気刺激策が一巡する一方、人口増加率の低下といった経済に対する構造的な下押し圧力が徐々に顕在化するなど、中長期的な成長期待に陰りが見られた時期と考えられる。実際、2015年に中国人民銀行が人民元の切り下げを発表すると、金融市場では中国経済の先行きへの懸念が急激に高まり、各国株価の急落をもたらした。
その後は、2019年の香港における大規模な抗議活動や、新型コロナウイルス感染症の封じ込め策(ゼロコロナ政策)の厳格な運用、さらには2022年に習近平氏が国家主席として異例の三期目を決定した前後などに、一時的にEPU指数が上昇した。
しかし、近年のEPU指数の上昇トレンドをもたらしている最大の要因は、通商分野を中心とする米国との対立である。通商政策の不確実性に言及している記事数を基に作成されている中国の通商政策不確実性指数は、第一次トランプ政権期に重なる2017年~2020年末の間に大幅に上昇し、EPU指数のドライバーとなってきたことが分かる(第I-3-1-4図)。第一次トランプ政権期の後は通商政策不確実性指数の急騰は見られなくなったが、後を継いだバイデン政権も中国製品に対する規制強化は継続したことから、2017年以前と比べれば水準は上振れしたままであった。そして第二次トランプ政権の発足が確実となった2024年末以降、中国の通商政策不確実性指数は再び騰勢を強めつつある。
第Ⅰ-3-1-4図 中国のEPU指数と通商政策不確実性指数
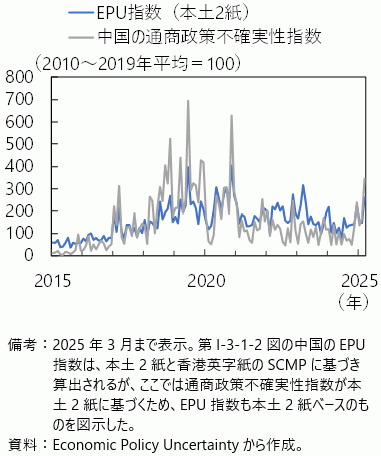
以上のように、グローバルEPU指数の上方トレンドを作り出しているのは主として欧州と中国における不確実性の高まりであり、米国との通商関係の悪化が主因のひとつである。
他方、米国自身のEPU指数は、少なくとも2024年末までは安定した推移を見せている。2020年のコロナ禍の初期や、2022年の利上げ開始前後の局面こそ上昇したものの、それ以外の局面では落ち着いており、上方トレンドにあるグローバルEPU指数とは対照的な動きを示している。
こうした乖離は、第Ⅰ部第1章第1節で触れたような米国経済の一強状態によるところが大きいと考えられる。欧州等の国内政治の不安定化が米国に直接影響するケースは少ないほか、第一次トランプ政権期の貿易摩擦についても、関税引上げ等の悪影響を上回る米国経済の強さがあり、全体としての景気や株価上昇は損なわれなかった。結果として、世界金融危機後に力強さを欠いたままの欧州経済や、成長期待が低下しつつある中国経済と比べて、経済の堅調さが米国の不確実性を抑えてきた。
このことは、VIX指数からも読み取れる。VIX指数は、米国のS&P500株価指数のオプション価格から算出される株価の先行きの予想変動率(ボラティリティ)を表したもので、主に投資家が市場の不確実性やリスクをどのように見込んでいるかを反映している。世界金融危機時のように金融市場における不透明感が高まると大きく上昇する傾向があるため、VIX指数は「恐怖指数」とも呼ばれる。VIX指数と米国のEPU指数を重ねると、2024年末以降を除き、両者はほぼ連動して推移している(第I-3-1-5図)。大統領選挙や貿易摩擦、コロナ禍といった不透明感を高めるようなイベントが発生しても、米国経済の足腰がしっかりしている限りは金融市場における不確実性が継続的に高まることはなく、それがEPU指数の安定的な推移をもたらしてきたことが示唆される18。
第Ⅰ-3-1-5図 米国EPU指数とVIX指数の推移
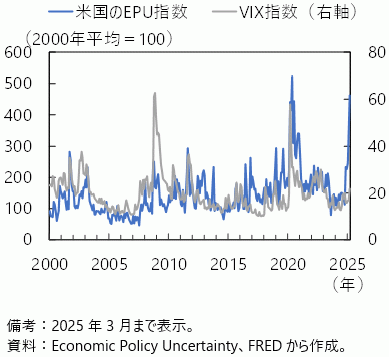
以上のように、米国のEPU指数はVIX指数と連動する形で安定してきたが、2024年末以降は水準が大きく切り上がっている。これは、第二次トランプ政権の発足に伴い、通商政策を始めとする不確実性が大幅に高まったためである。EPUの内訳指数である米国の通商政策不確実性指数は、2025年に入った後に第一次トランプ政権期の水準を遙かに超える過去にない上昇を示した(第I-3-1-6図)。
第Ⅰ-3-1-6図 米国の通商政策不確実性指数
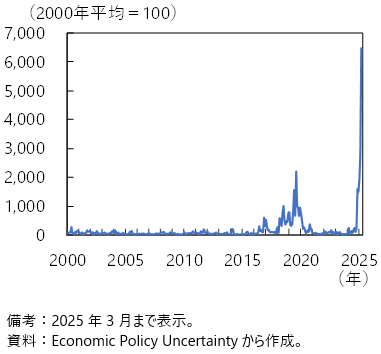
第二次トランプ政権が推進する関税政策は第一次政権期よりも遥かに広範囲にわたるほか、その進め方も、大まかな品目や対象国のみが突然発表され詳細は直前まで明らかにならなかったり、関税の発動直前や直後に一時停止や変更が発表されたりするなど、予見可能性の低い状況が続いた。4月初旬に公表された相互関税についても、発動直後に上乗せ分については90日間の停止が発表された。こうした通商政策を巡る不確実性の高止まりは、米国を含む各国の実体経済を大きく下押しする可能性が高い(次節参照)。
18 なお、近年、VIX指数とグローバルEPU指数との間に乖離が生じていることに注目が集まっている。例えば、IMF (2024) は、VIX指数を含む市場のボラティリティ指数がEPU指数から大きく下方に乖離しており、ボラティリティ指数が今後急騰するリスクを指摘している。こうした注目が集まる背景には、S&P500指数がグローバルに事業展開する多国籍企業を多く含むため、VIX指数はグローバルな金融市場における不確実性を表す指標と考えられてきたこと、また実際に2015年ごろまではVIX指数とグローバルEPU指数が基本的に連動してきたことがあると見られる。しかし、本文で記載のように、VIX指数と米国のEPU指数との連動性は(少なくとも2024年末までは)一貫して維持されていることから、VIX指数が反映しているのはグローバルというよりも米国の金融市場における不確実性であると考えれば、VIX指数とグローバルEPU指数の乖離は理解できよう。グローバルEPU指数とVIX指数との乖離ではなく、EPU指数におけるグローバルと米国との乖離がより本質的であるといえる。