第2節 不確実性の経済的影響
不確実性は、実体経済や金融市場に幅広い影響を及ぼす。以下では、その影響を定量的に分析する。
第I-3-2-1表は、EPU指数・VIX指数と主要な経済・金融変数の相関係数を見たものである。政策的な不確実性が構造的に高まっていることを踏まえ、2005年~2014年と2015年~2024年とに分けて算出している。あくまで時系列な相関関係であって因果関係を示しているわけではないことには留意が必要だが、一定の傾向が読み取れる。
第Ⅰ-3-2-1表 各種の不確実性指数と経済・金融変数の相関係数
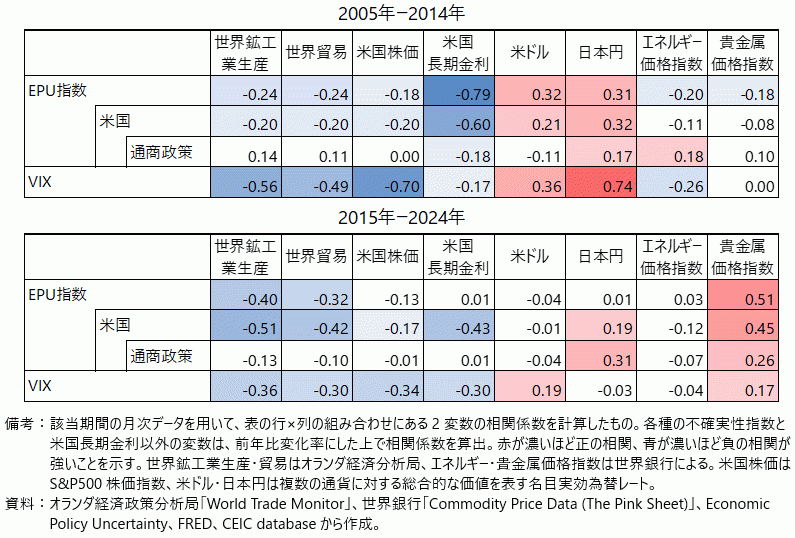
EPU指数は、いずれの期間においても世界の鉱工業生産や貿易量、株価とは負の相関関係にあり、政策的な不確実性の高まりは景気悪化を伴うものとなっている。生産や貿易量との相関は2015年以降の方が高く、近年は不確実性の影響が強まっていると見られる。一方、通商政策の不確実性と生産・貿易・株価はいずれの期間も相関度合は弱いが、2015年以降の相関係数はマイナスとなっている。通商政策不確実性指数はEPU指数全体と比べて急上昇を繰り返す傾向があり、計算上は経済変数との相関が低くなっているようだ。
景気悪化局面では、マネーはリスク回避姿勢を強める。その逃避先として、2010年代半ばまでは米国債や安全通貨とされた米ドル・日本円に資金が集まる傾向が強かった。一方、2015年以降の期間では、国債や米ドルよりも金を始めとする貴金属が買われやすくなっている。
なお、VIX指数と各変数の相関も、EPU指数と同様に景気や株価、金利と負の相関を示しているが、その相関の度合いは2010年代前半までの方が強い。リスク回避姿勢の強まりによるマネーの流入先がドルや円から貴金属にシフトしていると示唆されることは、EPU指数と各変数との相関から見てとれた内容と同様である。
こうした不確実性を示す指標と経済・金融変数との相関関係を踏まえると、2024年末以降のEPU指数の急上昇(前掲第I-3-1-1図)に見られるような不確実性の増大は、実際に関税等の政策変更が行われるかどうかにかかわらず、世界経済への下押し圧力になることが推察される。
ただし、単純な同時点の相関関係を見るだけでは、その定量的なインパクトを捉えることは難しい。そこで、経済・金融変数に影響を及ぼす他の要因をコントロールしながら、不確実性の影響がしばらく残存する可能性も考慮し、時系列分析の手法を用いて推計を行ったのが第I-3-2-2図である。ここでは、上記の分析でEPU指数と一定の相関が見られた世界経済、世界貿易、米国長期金利、米国株価を対象に、2025年1月におけるEPU指数の急騰から示唆される不確実性の急激な拡大が各変数に及ぼす影響を試算している19。なお、世界経済を表す変数としては、世界GDPの近似値としてG20の実質GDPを用いている20。
2025年1月の不確実性の増大により、世界の実質GDPは、不確実性が高まらなかった場合と比べ、1年後には最大1%程度下振れし、その後徐々にマイナスの影響が減衰していくと試算される。当初1年間の平均では下押し幅は0.7%程度となるが、トランプ政権発足前に2025年の世界経済が+3.2%拡大すると見込まれていたこと(2025年1月時点のIMF「WEO」による)を踏まえると、相応のインパクトであるといえる。同様に、世界貿易は1年後で最大3%程度、米国の長期金利は当初1年間に0.4%ポイント程度、米国株価も当初1年間に10%程度と、いずれも大幅に下振れする計算となる。その後も、各変数への下押し圧力は数年にわたって残存することが見込まれる。
以上の結果はあくまで機械的な試算であるほか、不確実性が一層急激に高まった2025年2月以降のデータは使用していない。他方、今後、不確実性が減退するようなプラスのショックがあればその影響は緩和されるため、幅を持って見る必要がある。それでも、2025年1月の不確実性の急激な高まりは、当面の世界経済にとって大きな逆風になり得るものと見ることができる。
第Ⅰ-3-2-2図 2025年初の不確実性増大の影響
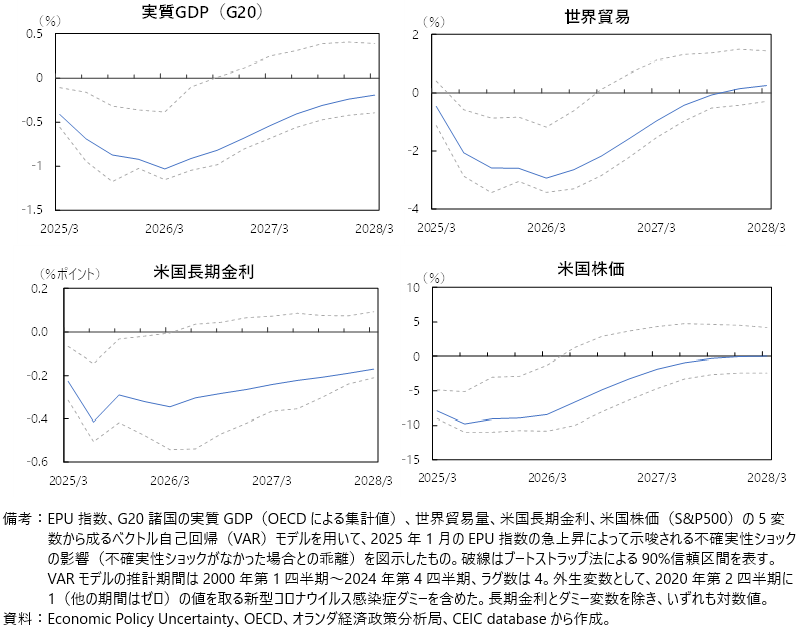
19 試算方法の詳細は付注参照。
20 先の第I-3-2-1表では月次データのため世界の鉱工業生産を用いたが、第I-3-2-2図の推計は四半期ベースのため、非製造業の生産も捉えられる実質GDPを用いた。