前章では、国際環境の変化を特徴づける認識レベルの要因として経済政策の不確実性の増大に焦点を当てたが、不確実性の構造的な増大と並び、国境を越えた企業活動に直接的な影響を及ぼしているのが地政学的な対立の深まりである。2020年のコロナ禍や2022年のロシアによるウクライナ侵略後の局面では、各国が政治的に対立・競合する国に経済的に依存している実態が明らかになった。その状況に危機感を強めた各国政府は、対立・競合する国への過度な依存リスクを低減させるサプライチェーン組み替え(デリスキング)の動きを見せているが、それが貿易関係全体にどのような影響を与えているかは明確ではない。本章では、地政学的な距離がグローバルな貿易関係にどのような影響を及ぼしているかを見ていく。
第1節 地政学的な距離
1. 地政学的距離の算出
国際政治経済関係における地政学的な対立が深まっている近年の状況に関して、各国の立場の違いを「地政学的な距離」と捉え、定量的に分析する研究が最近増えている。以下では、それらの先行研究で特に用いられてきた国連総会における各国の投票行動をもとに地政学的距離を算出し、各国の地政学的な対立の深まりの定量化を試みる。この分析枠組みは、国連総会における各国の投票行動がそれぞれの国益を一定程度表しているという前提の下、投票行動が類似している国は国際的な課題に対する立場が近い、すなわち地政学的距離の近い国であり、逆に投票行動が相反する国同士は地政学的距離が遠い国と仮定していることになる。
地政学的距離の具体的な算出方法は以下のとおりである。国連総会の投票行動(賛成、反対、棄権、欠席)のうち、欠席は国連分担金の未払い等によるケースが多いと見られるため、集計からは除外する。その上で、ある採決について、二国間の投票行動が一致する(すなわち、二国がともに賛成、反対、棄権のいずれかとなる)場合はその採決に係る距離を0、一国が賛成でもう一国が反対の場合は正反対の投票行動として距離を1とする。さらに、棄権という投票行動が積極的な賛否を表明しづらい中での一定の意志表示であることを踏まえ、二国間の投票の組合せが賛成と棄権、若しくは反対と棄権となる場合は両国の距離を0.5とする。こうして各採決における投票の異同を数値化し、それを分析対象期間の全ての採決について平均したものを、当該期間における二国間の地政学的距離と定義する(第I-4-1-1表)。指数の作成方法上、地政学的距離は0と1の間に分布し、0に近いほど地政学的距離が近い国、1に近いほど地政学的距離が遠い国となる。
第Ⅰ-4-1-1表 地政学的距離の算出例
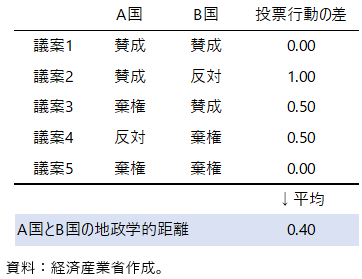
以上の計算を国連総会の全ての採決に適用することもできるが、総会採決にかけられる議案は毎年100件弱に上り、テーマの幅広さゆえに、全てを分析対象とすると各国の中核的な立場がぼやけてしまう可能性がある。そこで、採決にかけられる議案のうち特に重要なものに絞るという観点から、地政学的距離の算出対象を、米国国務省が議会向けに行う年次報告の中で「重要な議題(important issues)」と指定しているものに絞ることとする。「重要な議題」は米国の重要な国益に直接影響を与え、米国が他国に働きかけをする議題であると定義されており、米国国務省の戦略的な目標と整合的かどうかを基準に判断されるため、もっぱら米国視点の基準である。もっとも、国際政治における米国の影響力の大きさを勘案すれば、米国が重要議案として各国に働きかけを行うテーマは他国にとっても重要度の高い場合が多いと考えられ、議案を絞り込む基準として一定の有用性を持つといえよう。なお、「重要な議題」は全議案のうち、近年は2~3割程度を占めている21, 22。
21 地政学的な対立と貿易との関係を分析したMcKinsey Global Institute (2025, 2024)も同様に、米国国務省が重要と指定した議題を基に地政学的距離を算出している。
22 地政学的距離の指標としては、本章のような投票行動の単純な距離に基づくもののほか、Bailey et al. (2017) によるideal points estimateが使用されることも多い。これは、国連総会の投票データを基に、各国の潜在的な選好を表す理想点(ideal points)を空間モデルによって推計するものであり、推計された理想点の差分を地政学的な距離と見なすことができる。同推計値には、各国の本来の選好を議題の違いに左右されずに算出できるメリットがあるが、公表されている理想点のデータから各国の米国・中国に対する地政学的距離を算出したところ、本章の図とおおむね同様の傾向となった。そのため本章では、直感的な理解がより容易な、単純距離に基づく地政学的距離を使用した。
2. 米中に対する各国の地政学的距離
以上の方法に基づき、G20諸国(EUを除いた19か国)について、米国と中国に対する地政学的距離の推移を示したものが第I-4-1-2図と第I-4-1-3図である。年による議案のばらつきを調整するため、図は当年と前年の平均値を示している。
第Ⅰ-4-1-2図 G20諸国の米国に対する地政学的距離
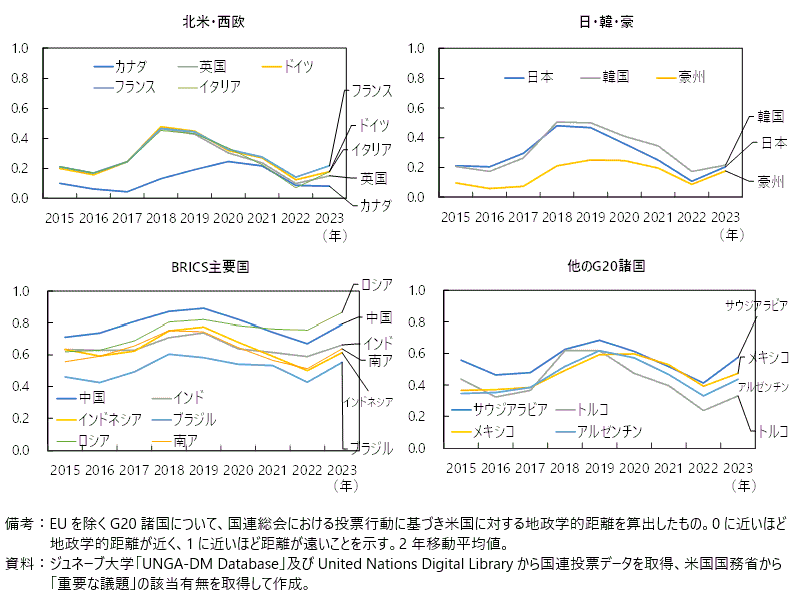
第Ⅰ-4-1-3図 G20諸国の中国に対する地政学的距離
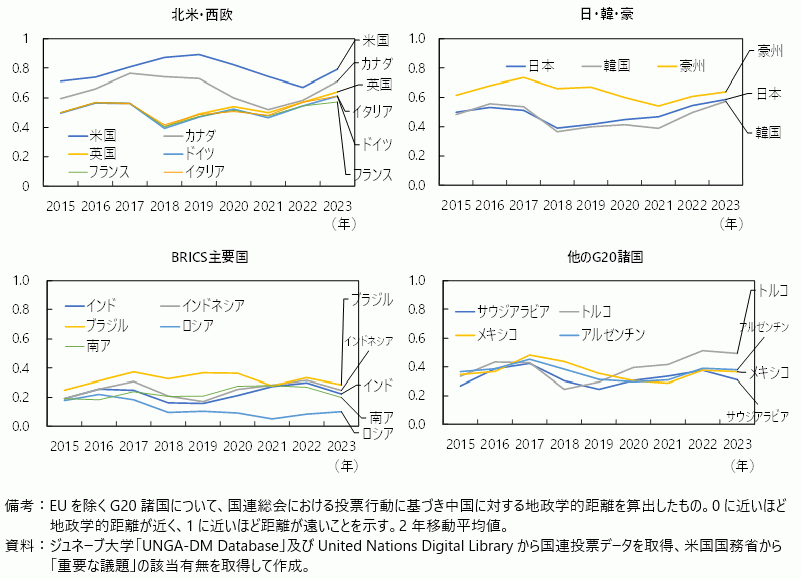
まず西側諸国の対米距離を見ると、第一次トランプ政権期の2017~2020年にかけて広がっていたが、バイデン政権期には急速に低下し、対米距離はオバマ政権期の水準に回帰した。期間を通じて、カナダや豪州が米国との地政学的距離が最も近く、欧州主要国や日本・韓国が続く形となっている。日韓のグラフは水準・形状とも欧州各国とほぼ重なっており、投票行動が近似していることが示唆される。
一方、BRICS主要国や他の新興国の対米距離は西側諸国よりも遠く、トルコを除けば、バイデン政権期でも目立った低下は見られない。同時に、西側諸国ほどのまとまりがなく、最も遠いロシア・中国と、経済的なつながりもあって相対的な近さを保っている中南米諸国とでは、対米距離に一定の差が生じている。
各国の中国に対する地政学的距離は対米距離の裏返しとなっており、西側諸国は中国との地政学的距離が遠く、新興国は比較的近いという傾向が見てとれる。その中にあって、西側諸国では欧州や日韓が2018年以降に中国との距離を拡大させ、米国・カナダ・豪州の対中距離と近くなっている。他方、新興国の中では、親中姿勢を強めるロシアと他の国とに一定の差が生じていることがうかがわれる。
以上をまとめると、米国がバイデン政権期に国際協調を重視する路線に回帰したことで、西側諸国間の地政学的距離は縮小した。その裏で、欧州や日本・韓国は中国と地政学的に距離を置きつつあり、西側諸国の対中スタンスは収束に向かっているように見える。もっとも、第二次トランプ政権の直近の政策を踏まえれば、今後再び米国と西側諸国を含む他国との距離が広がる可能性がある。新興国は、全体として見れば中国に近く米国と遠い立ち位置にあるが、対米・対中距離とも各国のばらつきが大きい。BRICS内でも、ロシアの中国接近が目立つ一方、他国は対中スタンスがほぼ変わらない、若しくは若干距離を取る動きが見られている。第Ⅰ部第2章第4節ではグローバルサウスの状況が様々であることに触れたが、こうした地政学的距離の分析からも、国際社会が米国と中国のどちらに与するかという単純な構図にはなっていないことが読み取れる。