第2節 世界貿易への影響
前節では、西側諸国と中国の地政学的距離が広がっていることを指摘したが、中国以外との関係にも一定の変化が生じ、それが貿易取引を含む国境を超える企業活動にも影響を及ぼしている可能性がある。そこで本節では、主要国の貿易相手国が地政学的にどのように位置付けられるかを分析し、サプライチェーンのデリスキングの動きが、実際にどの国・地域の貿易関係にどのような影響を与えているか検討する。
まず、主要国の貿易と地政学的距離の全体像を捉えるべく、各国の地政学的距離を貿易シェアで加重平均した「貿易上の地政学的距離」を見てみよう。地政学的距離の近い国との貿易が相対的に増加すれば低下、地政学的距離の遠い国との貿易の増加は上昇につながるため、デリスキングが貿易関係に影響を与えているとすれば「貿易上の地政学的距離」はゼロに近づくことが想定される。
直近のデータが得られる2022~2023年平均の地政学的距離を用いて「貿易上の地政学的距離」を算出したのが第I-4-2-1図である。米国や日本で若干数値の低下が見られるが、その度合はごく小幅であり、デリスキングの貿易全体への影響は必ずしも明確ではない。
第Ⅰ-4-2-1図 主要国の貿易上の地政学的距離
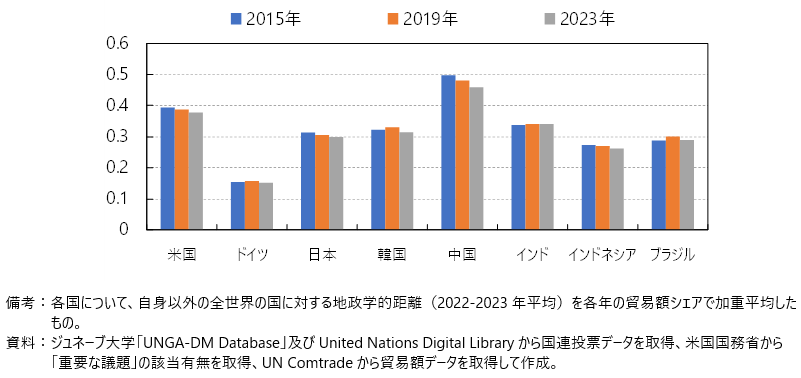
「貿易上の地政学的距離」は加重平均値であるため、地政学的距離の近い国との貿易が増えていても、それ以外の国との貿易も増えていれば計算上は距離が変わらないケースもあり得る。そこで、単なる加重平均値ではなく①地政学的距離の近い国との貿易、②中程度の国との貿易、③地政学的距離の遠い国との貿易、の3グループに分けて主要国の貿易動向を分析する。3グループに分けるのは、前節で概観した米国や中国に対する地政学的距離と同様、各国の他国に対する地政学的距離はばらつきが大きいと考えられ、近い国・遠い国の二分法ではそうした多様性を捉えられないためである。
国ごとに、自身以外の全ての国に対する地政学的距離を算出し、値の小さい3分の1の国々を①、値の大きい3分の1の国々を③、その中間の国々を②と分類した。日本の地政学的距離を用いてグループ分けを行ったのが第I-4-2-2図である。西側諸国が「近い国」、中南米等が「中程度の国」、中国・ロシアなどその他の国々が「遠い国」に分類されている。
第Ⅰ-4-2-2図 日本の地政学的距離の分布
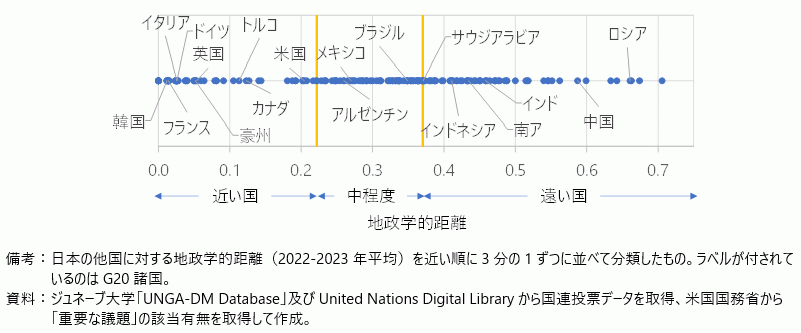
これと同様の分類を他の主要国についても行い、貿易シェアの変化を調べたのが第I-4-2-3図である。
第Ⅰ-4-2-3図 地政学的距離に応じた貿易シェアの変化
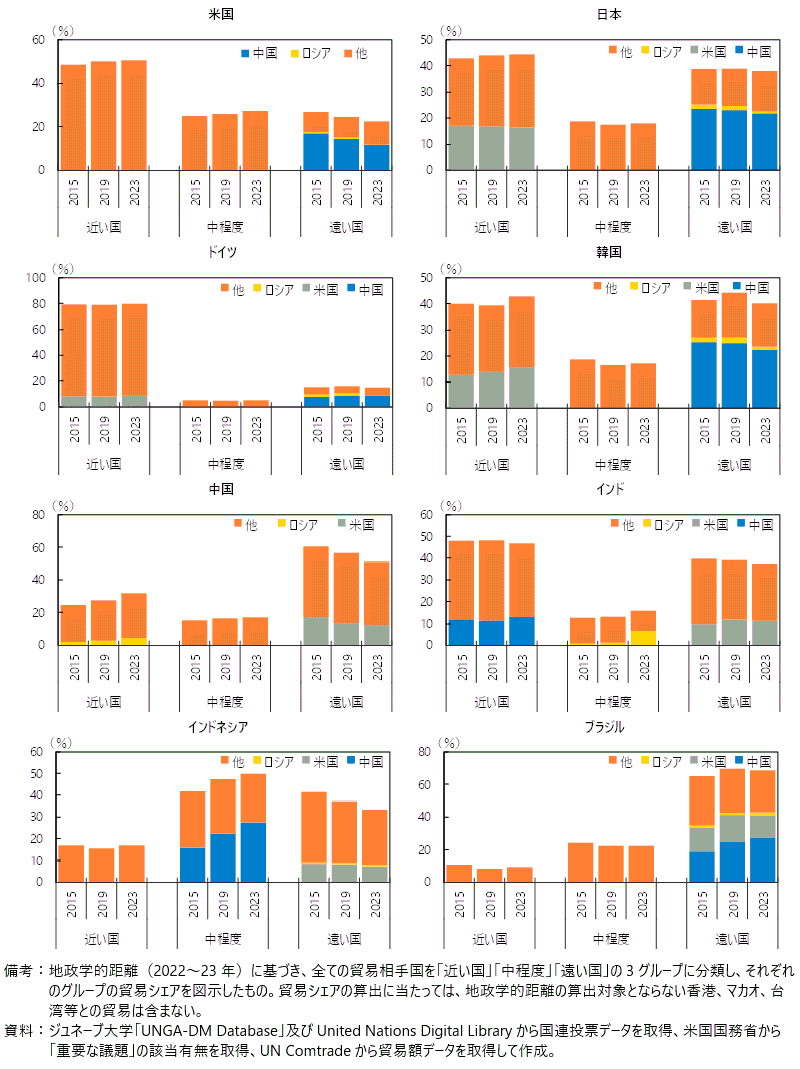
米国では地政学的距離が近い国や中程度の国との貿易が増える一方、遠い国との貿易シェアが低下している。デリスキングが地政学的距離の遠い中国との貿易を減少させていることが示唆される。ただし、必ずしも、同盟国や友好国など地政学的距離が近い国でサプライチェーンを構築するいわゆるフレンド・ショアリングだけが増えているわけではない。日本や韓国も「近い国」との貿易が増えているが、米国ほど中国との貿易を圧縮しておらず、デリスキングの進行は限定的である。この間、ドイツは「近い国」に分類されるEU加盟国との貿易が大半を占めるため、目立ったトレンドは見られていない。
他方、中国は直接的な対米貿易が減少しており、対米貿易投資のリスク増加を踏まえた一定の行動変化が示唆されるが、中国企業による第三国への貿易投資を通じた間接的な対米輸出も指摘されており、必ずしもデリスキングが進んでいるといえるかは明らかではない。他方、ロシアとの貿易関係を深めていることは、フレンド・ショアリングのひとつの形といえよう。
新興国では、インドネシアは、近い国との貿易シェアはほぼ横ばいだが、中程度の国との貿易が増加し、遠い国との貿易が減っている。中程度の国の大半は中国要因であり、経済的な実利をある程度優先している姿がうかがわれる。インドも同様の構図を示しており、エネルギーを中心に、中程度に分類されるロシアとの貿易関係を強化している。最後に、ブラジルは、地政学的距離の遠い国との貿易シェアが高まるという他国にはないパターンを示している。その主な要因はやはり中国との貿易拡大であるが、地理的にも遠く離れていることで欧米やアジア諸国のように地政学的な摩擦が生じる機会が少なく、フレンド・ショアリングを意識する必要性が相対的に低いことが背景にあると見られる。
本章の分析結果をまとめると以下のとおりである。国連総会の投票行動に基づく地政学的距離は、西側諸国は相対的に米国に近く中国から遠いのに対し、新興国は全体として更に米国から遠い立ち位置となっている。もっとも、米国の姿勢によって他の西側諸国と距離が広がる局面があったほか、新興国では西側諸国と比べて対米・対中スタンスともにばらつきが大きくなっており、各国の地政学的な立ち位置が多様であることが示された。
地政学的距離と国際貿易の関係を分析すると、近年注目が集まっているデリスキングの動きについては、全世界的に貿易関係全体の分断又はブロック化が進んでいることを示す明確な証左は今のところ見られない。地政学的な対立の中心である米国と中国の間では、直接の貿易関係が減少していることは確かである。しかし、地政学的距離が相対的に近い国も中間的な国も貿易を増やしており、いわゆるフレンド・ショアリングだけが進んでいるわけではない。むしろ、サプライチェーンの組み替えの実態は多様性が大きいと考えられる。また、日本・韓国・ドイツといった他の西側諸国では、デリスキングが貿易額全体に与える影響は現時点では限られている。インドネシアやインドなどは、地政学的対立の中で経済的な実利を優先して各国との貿易関係を維持・拡大していると考えられる。ブラジルのように地政学的距離の遠い国との貿易関係が拡大する傾向が見られる国もある。このように、米中対立の状況下で、今のところ、デリスキングの動きはサプライチェーンの多様化に向かっており、貿易関係の分断又はブロック化やフレンド・ショアリングが中心的な動きにはなっていない。もちろんこれは貿易全体で見たときの傾向であり、個別の品目ごとに見ると異なる傾向を示す可能性はあろう。
足下では、第二次トランプ政権が、中国だけではなく全ての国を対象にした関税措置を導入しており、その不確実性の高まりも相まって、サプライチェーンの再編の動きにも大きな影響を与えることが見込まれる。米国を含む各国のデリスキングの動きがどのような方向に進むかを、現時点で把握・予測することは困難である。これまでのデリスキングの動きが貿易関係に及ぼした影響を踏まえつつ、今後の地政学的対立の行方や各国貿易政策、企業によるサプライチェーン再編の動向を注視していく必要がある。