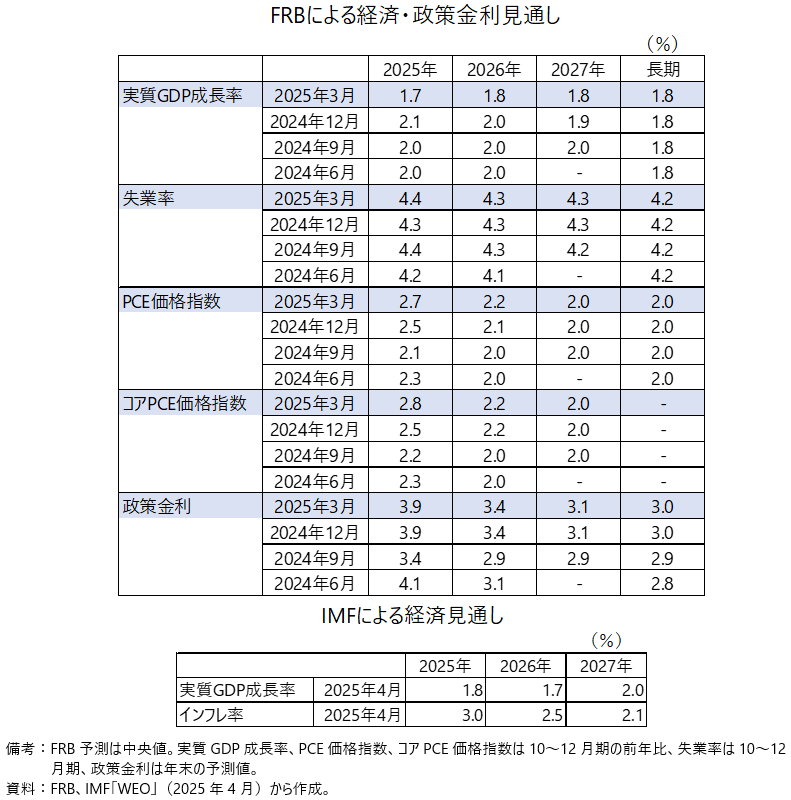本章では、各国・地域ごとの経済動向に焦点を当て、国・地域内経済及び対外経済関係の主要な経済指標の動きを見ていく。
第1節 米国経済
第1章でも述べたとおり、2024年の米国経済は、金利が高止まりする中にあっても、想定以上の底堅さを見せた。その背景には、家計の貯蓄や好調な労働市場が消費の拡大をもたらしたことや、大規模な経済・産業政策も背景に企業の設備投資が第3四半期まで増加したことなどがある。もっとも、2025年に入った後の経済指標には、減速感や景気後退の兆候が見られている。第二次トランプ政権の政策を巡る不確実性の高まりも含め、景気の先行きには注視が必要な状況となりつつある。
1. GDP
(1) 実質GDP成長率
2024年の米国の実質GDP成長率は、前年比+2.8%と前年(同+2.9%)とほぼ同じ高い伸びとなった。成長率は3年連続で2%台半ばから後半で推移しており、2%弱とされる潜在成長率を上回っている。政策金利が5%前後と金融政策が引き締められているにもかかわらず、景気の堅調さが目立っている。
需要項目別に見ると、年間を通じて個人消費が牽引役となった。設備投資は、金利高の中でも第3四半期までは増加を続けたが、第4四半期には13四半期ぶりに減少し、増勢が鈍化している様子がうかがわれる。金利感応度がより高いと見られる住宅投資は力強さを欠いた。この間、政府支出は国防支出や地方政府支出が押し上げる形でプラスを維持した(第I-5-1-1図)。
第Ⅰ-5-1-1図 米国の実質GDP成長率
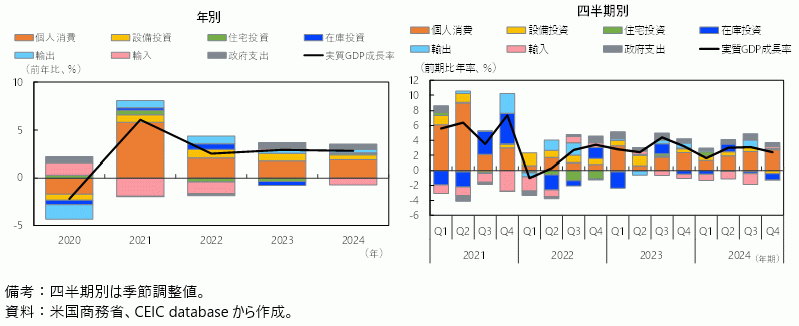
(2) 個人消費
2024年の実質個人消費は、前年比で+3%程度の力強い伸びを示した。内訳を見ると、食料品や日用品を含む非耐久財は物価上昇が響き、前年比+2%程度の伸びにとどまったが、耐久財は同+6%程度と大きく増加し、サービス消費も同+3%程度の堅調なペースで増加を続けた。もっとも、2025年に入った後の消費には減速感が見られ始めている。1月の個人消費は、名目で前月比-0.3%とおよそ2年ぶり、実質でも同-0.6%と1年ぶりの減少となった。2024年末から2025年初にかけて発生した大雪や、カリフォルニア州における2025年1月の山火事、年末商戦の反動減といった一時的な要因も影響したと見られるが、第二次トランプ政権の政策を巡る不透明感が個人消費を下押しするリスクも高まっている(第I-5-1-2図)。
第Ⅰ-5-1-2図 米国の実質個人消費の内訳
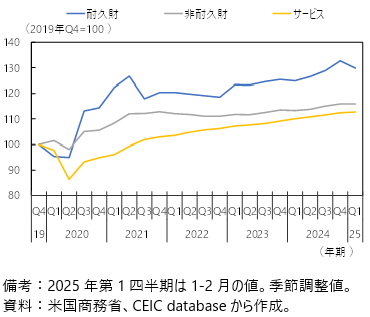
FRBがインフレ目標の指標として重視する個人消費支出(PCE)価格指数については、2024年前半は伸びの鈍化が続いたが、年後半にかけては下げ止まる動きを見せた。総合指数は2024年9月の前年比+2.1%を底に上向いており、2025年2月には同+2.5%となった。食品とエネルギーを除くコア指数は、夏場以降はおおむね同+2%台後半で推移している(第I-5-1-3図)。
第Ⅰ-5-1-3図 米国のPCE価格指数
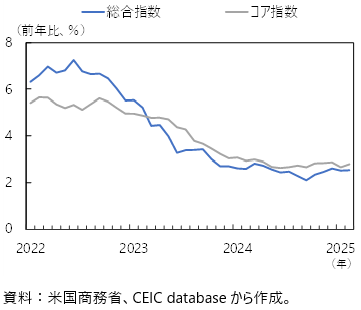
(3) 投資
① 設備投資
民間設備投資は、2024年第4四半期に減少するまで長らく前期比プラスで推移してきたが、徐々に勢いは落ちてきている。これまで、高金利環境の中でも設備投資が腰折れしなかった背景には、連邦政府が「CHIPS及び科学法」や「インフレ削減法」(いずれも2022年夏に成立)による大規模な補助を通じて製造業の工場建設等を後押ししたことや、相対的に外部からの資金調達が少なく金利上昇の影響を受けづらい知的財産投資が増加していたことがあったと見られる。しかし、2024年半ば以降は構築物投資や知的財産投資がいずれも勢いを失った。第2~3四半期は下支え役となっていた機器投資も、第4四半期にはマイナスに転じ、設備投資全体は13四半期ぶりに減少した。前期比での減少は一時的なものと見られるが、2022~2023年と比べ設備投資の勢いは徐々に弱まってきている(第I-5-1-4図)。
第Ⅰ-5-1-4図 米国の民間設備投資
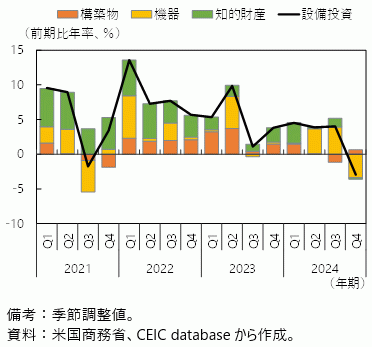
② 住宅投資
住宅投資は金利の高止まりが重石となっており、着工件数・許可件数(いずれも季節調整済み。年率換算)は140万戸前後でおおむね横ばいで推移している。足下の動きを見ると、2024年12月の着工件数は前月比+16.9%と大きく増加した後、悪天候もあって2025年1月に減少したが、2月には再び反発している(第I-5-1-5図)。
第Ⅰ-5-1-5図 米国の住宅建設許可、着工、完成件数
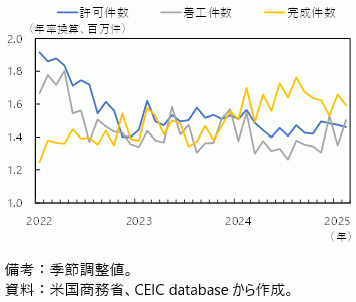
住宅ローン金利(30年)は、2023年秋に7%台後半まで上昇した後、幾分低下したものの、2025年初時点でも7%弱の高い水準で推移している。FRBは2024年に合計1%の利下げを実施したが、インフレ圧力の根強さから利下げペースが緩やかなものにとどまるとの見方が広がったことや、政府債務の増加に対する懸念などを背景に長期金利は高止まりし、それに伴って住宅ローン金利も下がりづらい状況が続いた。
本来、金利の高止まりは市況の弱含み要因となるが、住宅保有者がローンの借り換えを伴う住み替えに消極的になったため、2024年も中古住宅が市場に出回りづらい状況が続いた。住宅の供給が抑制される中で需要は相応に堅調だったことから、中古住宅価格(ケース・シラー価格指数)は平均して前月比+0.4%程度のペースで上昇が続いた(第I-5-1-6図)。
第Ⅰ-5-1-6図 米国の住宅ローン金利と住宅価格
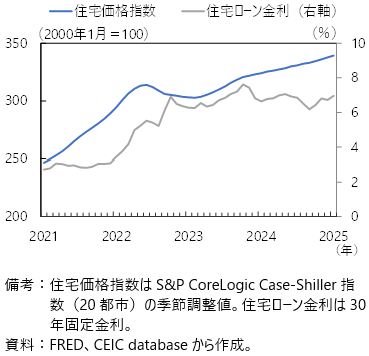
(4) 政府支出
政府支出は、2022年第3四半期以降、増加基調が続いている。2024年については、地方政府の寄与は2023年よりは低下したが、連邦政府の国防支出が拡大し、全体では堅調な増加が続いた(第I-5-1-7図)。
第Ⅰ-5-1-7図 米国の実質政府支出
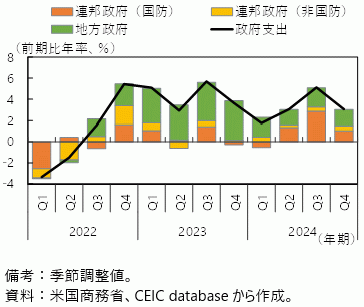
(5) 財・サービス収支
財・サービス収支(国際収支ベース)を見ると、名目赤字は2022年3月に1,019億ドルと、当時の過去最大を記録した。その後は緩やかに縮小していたが、2024年に入った後は再び拡大傾向を辿った。2025年1月には、輸入が前月比+10%と急増し、赤字は1,307億ドルと再び過去最大を更新した。これは、第二次トランプ政権による関税引上げ前に企業が輸入を急いだためと見られるが、堅調な内需を反映して貿易赤字は増加しやすい状況が続いている(第I-5-1-8図)。
第Ⅰ-5-1-8図 米国の財・サービス収支、輸出入(名目)
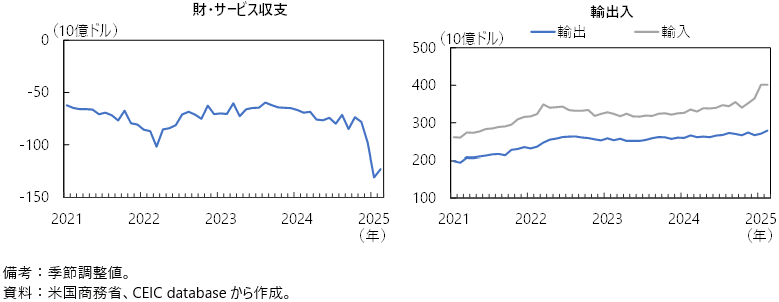
今後は、内需が減速に向かっていくと見られる中、広範な関税措置の導入やその不透明性が輸入に混乱と下押し圧力をもたらす可能性がある。他方で、他国による対抗関税を含む貿易措置の応酬は輸出の制約要因にもなり得るため、輸入減によって高水準の財・サービス収支赤字が解消に向かうかは不透明である。
(6) 鉱工業生産
2024年の鉱工業生産は、2023年以降の横ばい圏内の動きを続けた。製造業は、コロナ禍後の持ち直しが一服した2022年以降、ごく緩やかながら下降トレンドを辿っており、2024年を通じて低迷が続いた。この間、ハリケーンや大手航空機メーカーにおけるストライキ等も一時的な下押し要因となった。一方、鉱業は比較的堅調さを保ち、電力・ガスも時折下振れは見られるものの、基調としては増加している(第I-5-1-9図)。
第Ⅰ-5-1-9図 米国の鉱工業生産
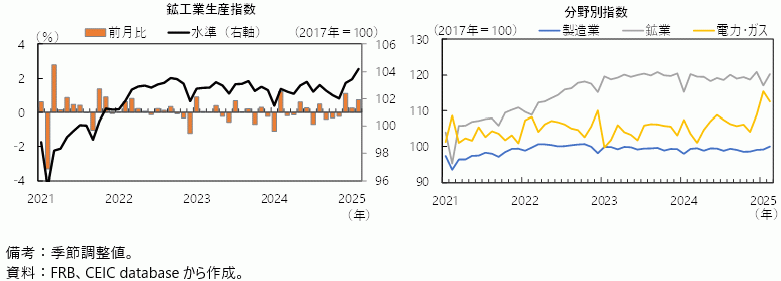
2. 物価
(1) 消費者物価
インフレ率は、依然としてコロナ禍前と比べれば高い水準にある。消費者物価の総合指数は、2022年6月のピークから2023年半ばにかけて順調に伸びが鈍化した後、2024年3月にかけて伸びが高まる局面が見られた。その後は再び低下トレンドを辿ったものの、2024年秋から2025年初にかけては一時的に伸びが高まる動きが見られた。2025年に入った後の上昇率は、1月が前年比+3.0%、2月が同+2.8%、3月が同+2.4%となっている。
食品とエネルギーを除いたコア指数は、2022年来の上昇率の鈍化が継続し、横ばい圏内の動きとなる時期を挟みつつ、2025年3月には前年比+2.8%となった。内訳を見ると、家賃を始めとするコア・サービス価格の伸びは低下を続けているが、先んじて下落してきたコア財価格が前年比±0%近辺まで戻ってきている(第I-5-1-10図)。広範に賦課された関税が価格転嫁されれば、財価格には更なる上昇圧力がかかることが予想される。
第Ⅰ-5-1-10図 米国の消費者物価指数
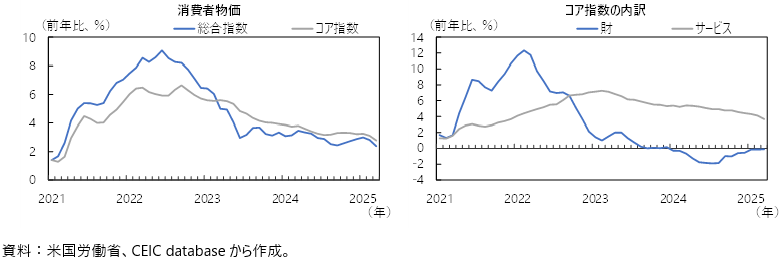
(2) 生産者物価
生産者物価の上昇率は、2023年半ばを底とする持ち直しの動きが継続した。2024年1月の総合指数は前年比+1.0%、食品・エネルギーを除くコア指数は同+2.0%であったが、2025年2月にはそれぞれ同+3.2%、同+3.4%となった。内訳を見ると、食品・エネルギーを除くコア財価格は前年比+1%台後半~2%程度の伸びで比較的安定した推移となっているが、賃金の上昇などを背景に、サービス価格は同+4%前後まで伸びを拡大させている(第I-5-1-11図)。
第Ⅰ-5-1-11図 米国の生産者物価
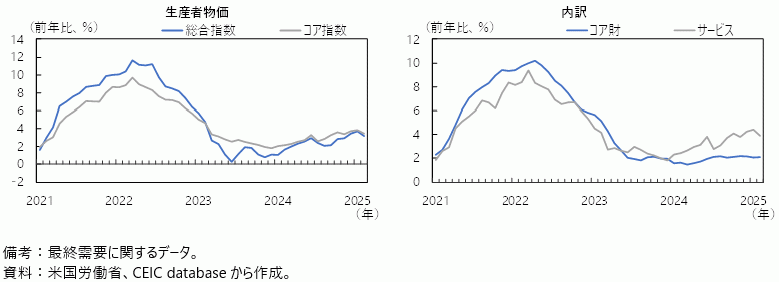
3. 労働市場
労働市場は引き続き堅調に推移した。非農業部門雇用者数は、2024年半ばまでは増加幅が緩やかに縮小していたが、その後、サービス業を中心に伸びが高まるような動きを見せており、2024年末から2025年初にかけては前月比+20万人程度のペースを維持している。労働参加率を見ると、プライム層の25~54歳はコロナ禍前の水準を超えて上昇トレンドが続いているが、55歳以上の労働参加率が下振れしたまま回復していないことを受けて、全体ではおおむね横ばいで推移している。失業率は、3%台半ばから4%台前半へ緩やかに上昇したとはいえ、低水準にとどまっている。求人数も、2022年のピークから続いてきた減少傾向が2024年後半には下げ止まっており、労働需給はタイトな状況が続いている。その下で、平均時給は前年比+4%前後の安定した伸びを維持し、3%程度のインフレ率(前項参照)を上回って推移している(第I-5-1-12図)。
第Ⅰ-5-1-12図 米国の雇用関連統計
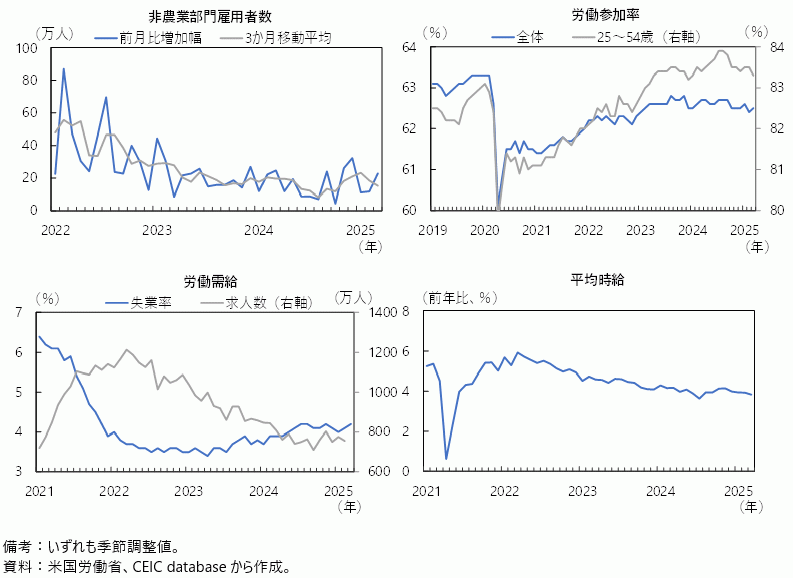
4. 金融政策
FRBは、2022年3月から急速なペースで利上げを進め、2023年7月に政策金利が5.25~5.50%に達してからは据え置きを続けてきたが、インフレがピークアウトしたことを受けて、2024年には利下げに転換した。FRBは9月に0.5%ポイント、11月に0.25%ポイント、12月に0.25%ポイントの利下げを行い、政策金利は合計1%ポイント引き下げられた(第I-5-1-13図)。
第Ⅰ-5-1-13図 米国の政策金利
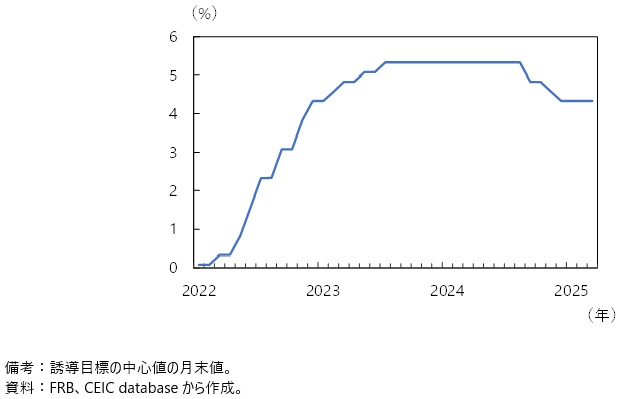
もっとも、インフレ圧力が依然として根強いことや、第二次トランプ政権の関税政策が先行きの不透明感や家計のインフレ期待を高めつつあることなどを背景に、2025年1月、3月の連邦公開市場委員会(FOMC)では政策金利は据え置かれた。3月のFOMCは、声明文で、「最近の指標は経済活動が堅調なペースで拡大したことを示唆している」と米国経済を評価した一方、「インフレ率は幾分高止まりしている」として利下げを見送った。
5. 今後の見通し
2025年3月に発表されたFRBによる経済見通しによると、実質GDP成長率の見通しは、2025年から2027年まで各年とも、前回12月から下方修正され、2025年は+1.7%、2026年と2027年は+1.8%となった。失業率は2025年が4.4%(前回:4.3%)と小幅に修正されたが、2026年と2027年は4.3%で維持された。PCE価格指数は、総合が2025年(前回:+2.5%→今回:+2.7%)と2026年(+2.1%→+2.2%)、コアが2025年(+2.5%→+2.8%)について、それぞれ上方修正された。これまでより景気の減速感が強まる一方、インフレ圧力が残存することが見込まれている。
また、同時に発表された政策金利見通しでは、2025年末の政策金利の誘導目標の中央値が3.9%、2026年末が3.4%、2027年末が3.1%と、段階的な利下げが続く見通しとなっている。
なお、2025年4月に発表されたIMFによる経済見通し(「参照予測」)によると、実質GDP成長率の見通しは、2025年が+1.8%、2026年が+1.7%、2027年が+2.0%であり、インフレ率の見通しは、2025年が+3.0%、2026年が+2.5%、2027年が+2.1%であった(第I-5-1-14表)。
第Ⅰ-5-1-14表 米国の経済・政策金利見通し