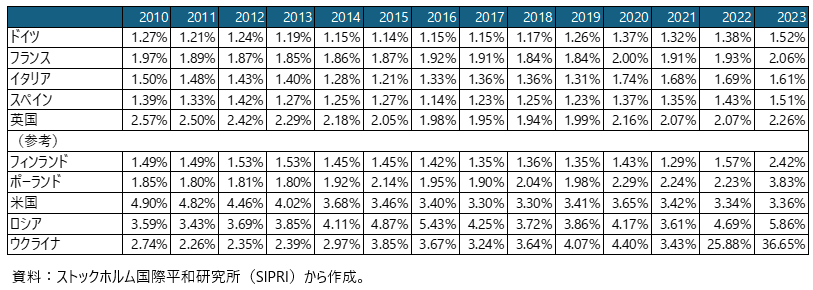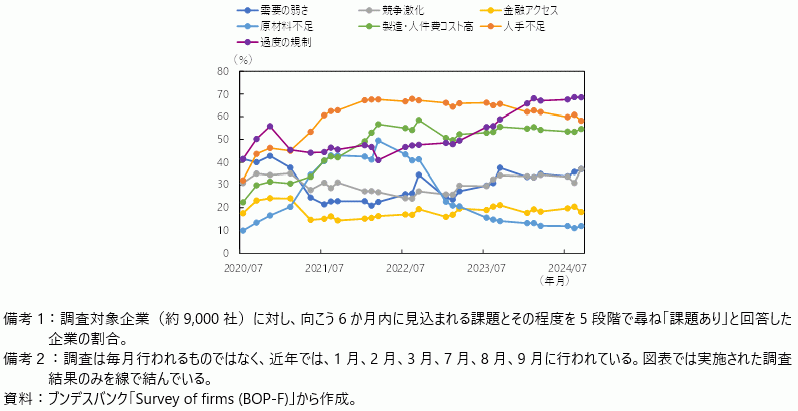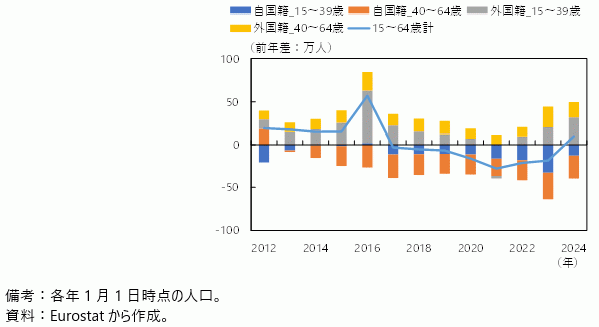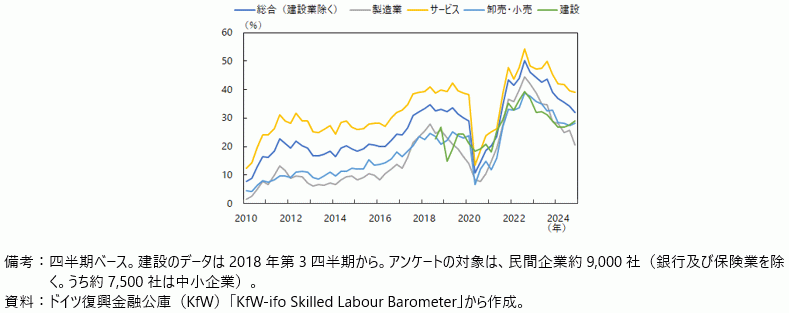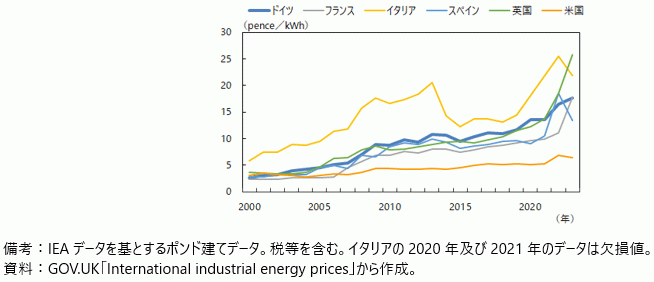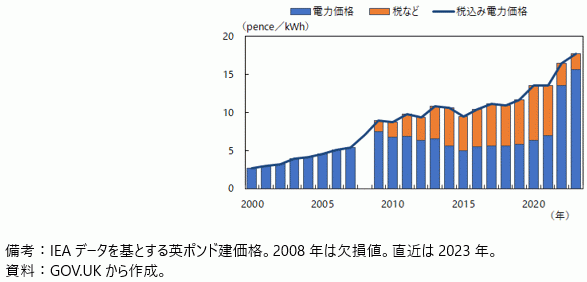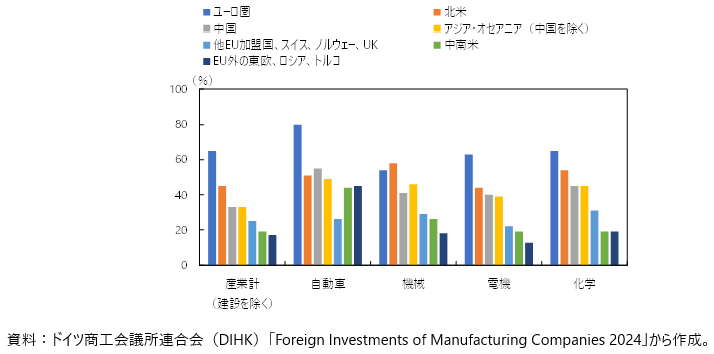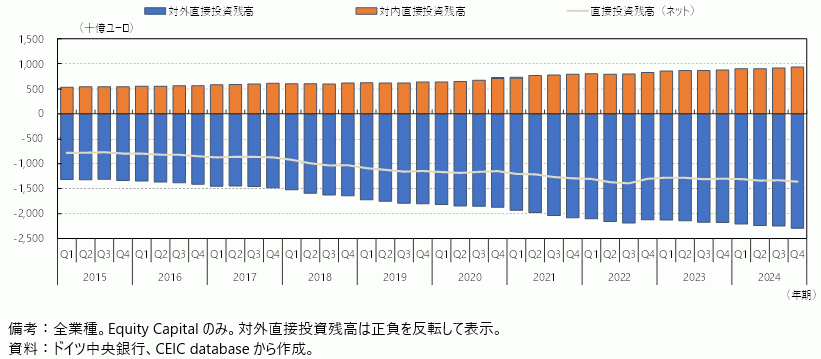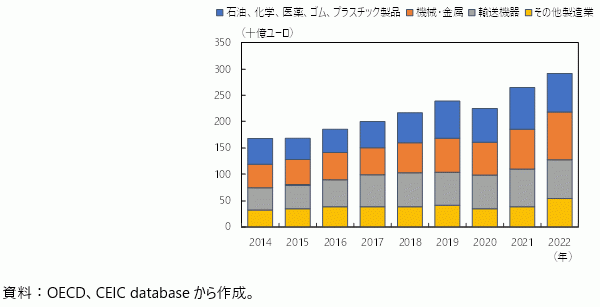第2節 欧州経済
2024年の欧州経済は、力強さは欠くものの、内需に牽引されて全体的には緩やかに回復した。一方、国別で見ると、ドイツが2年連続でマイナス成長を記録するなど、各国間でばらつきが目立った。2025年に入って、ユーロ圏の実質GDP成長率の伸び率は前期から加速したが、米国の第二次トランプ政権の関税政策など、不確実性の高まりがリスク要因となっており、先行きは不透明となっている。
1. 実質GDP成長率
ユーロ圏の2024年通年の実質GDP成長率は前年比+0.9%となった。インフレ率が2%台まで落ち着いてくる中、景気への配慮もあり欧州中央銀行(ECB)は2024年7月から利下げを開始したが、設備投資など固定資本形成の動きはまだ鈍い。家計消費は賃金の増加傾向から底堅さを保っているが、民需の寄与は総じて小さく、内需を支えたのは主に政府支出だった。同年前半、景気の下支え役となった輸出には減速傾向が見られるようになっている。
国別には、観光需要が引き続き堅調だったスペインなど南欧や夏季オリンピックによる押上げ効果が一定程度見られたフランスと、中国向け輸出の弱含みもあり製造業が苦戦したドイツなどで明暗が分かれた。ドイツは在庫の積み上がりや政府支出で落ち込み幅が緩和されたものの、2年連続のマイナス成長となった。南欧でもイタリアは、内需・外需とも弱含みで年後半の成長率はほぼ横這いにとどまった。英国では、インフレ率の落ち着きが鈍いことや、14年ぶりの政権交代で発足した労働党政権による経済政策の先行き不透明感が景気の重しとなった(第I-5-2-1図、第I-5-2-2図)。
第Ⅰ-5-2-1図 ユーロ圏・欧州諸国の実質GDP成長率の推移
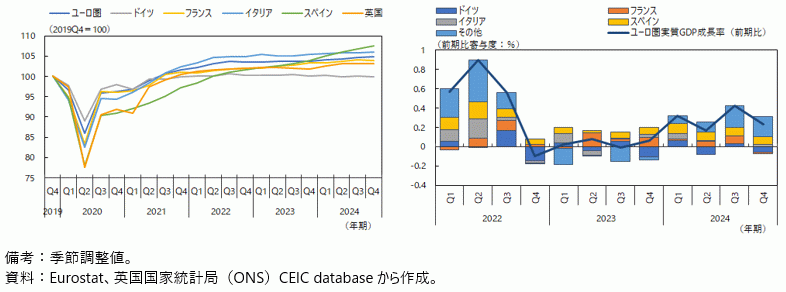
第Ⅰ-5-2-2図 ユーロ圏・欧州諸国の実質GDP成長率(需要項目別寄与度別)
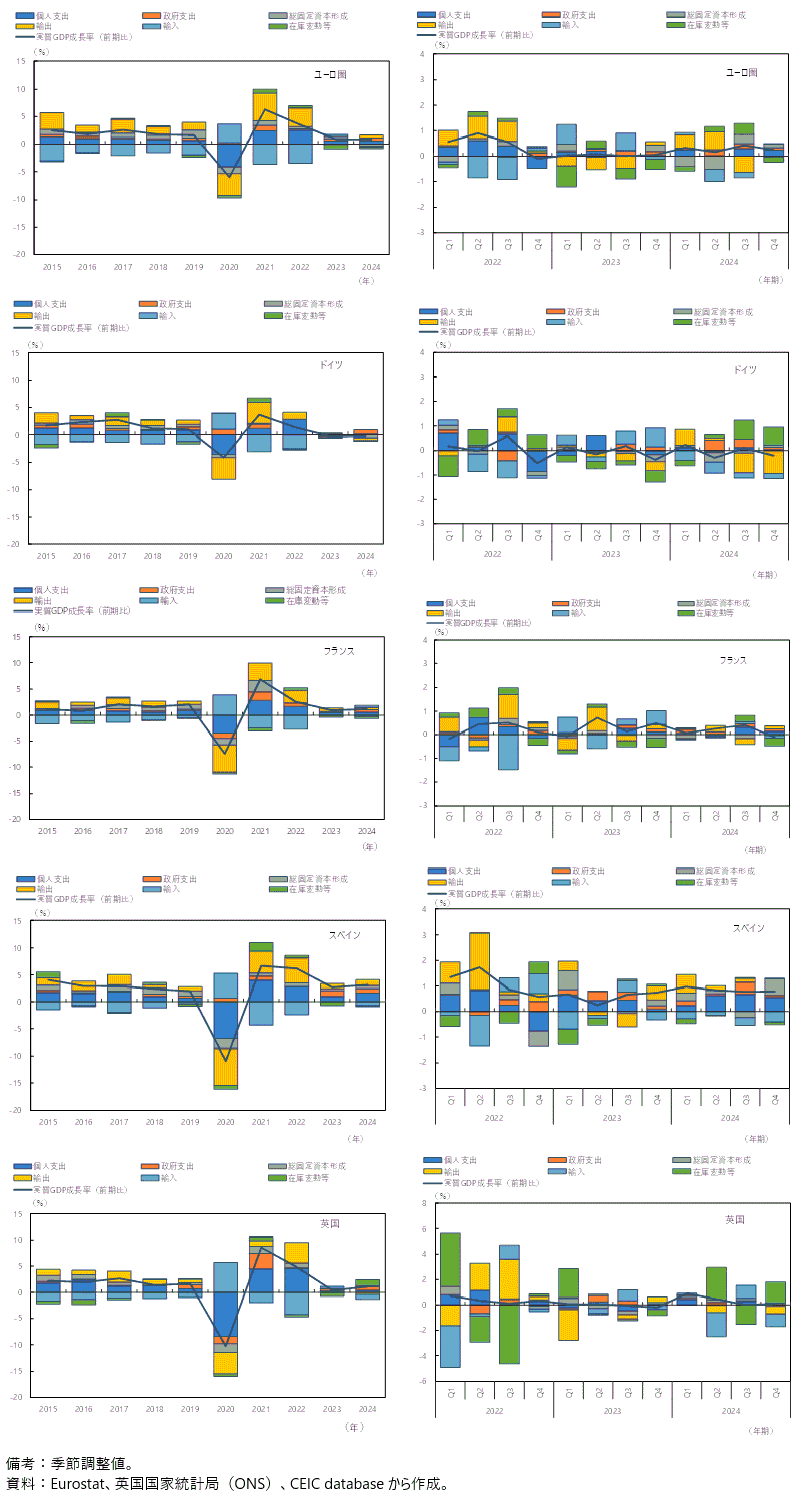
2. 消費者物価
ユーロ圏のインフレ率は、2024年央にかけて2%近くまで伸びが低下したが、その後、低下は足踏みを始め、足下では若干上向く動きも見られている(第I-5-2-3図)。サービス価格の伸びが前年比4%程度で高止まりしていることや、厳冬の影響などもありエネルギーが足下で幾分押上げに寄与していることが背景となっている。財については、工業財価格は、需要の弱含みから前年比マイナスになる時期もあったが、消費者に身近な食品関連の価格は2%をやや上回る伸びが続いている。なお、サービス物価上昇の背景にある賃金の上昇については、妥結賃金の伸びが落ち着く方向にあることから、2025年には伸び率が緩やかになっていくことが見込まれている。
第Ⅰ-5-2-3図 ユーロ圏・欧州諸国の消費者物価の推移
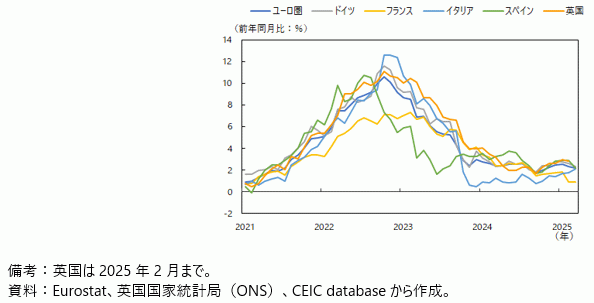
英国では、エネルギーコストの低下に伴う工業財価格の伸びの低下傾向は見られるが、サービス価格の伸びは前年比5%程度、食品価格の伸びは同4%程度とユーロ圏より高めに推移しており、2025年初のインフレ率は3%程度まで上昇した(第I-5-2-4図)。
第Ⅰ-5-2-4図 ユーロ圏・欧州諸国の消費者物価(品目別)の推移
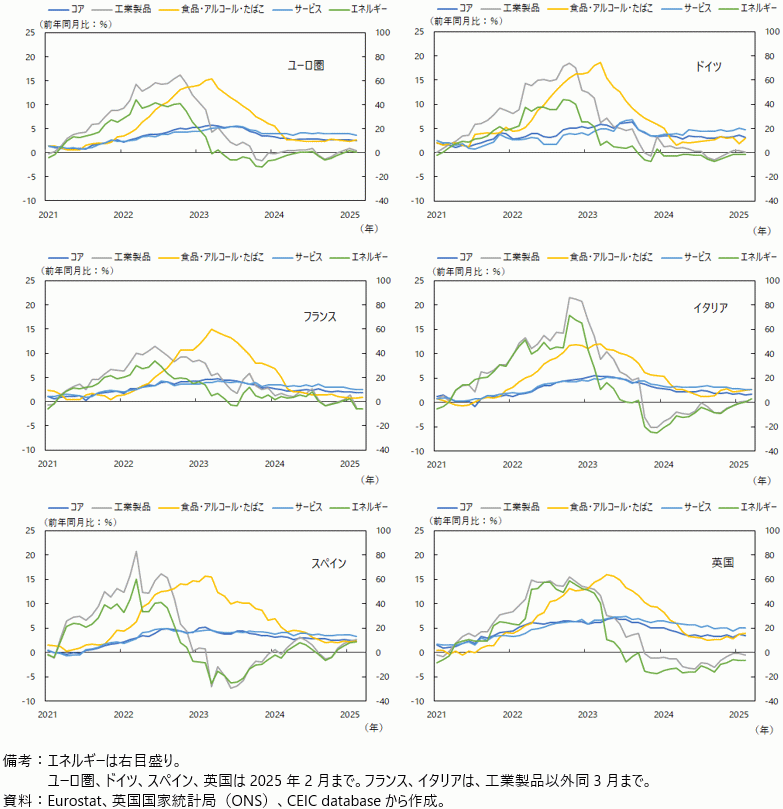
3. 個人消費
2024年の小売売上高の動きは緩慢だった。コロナ禍前のユーロ圏では、小売売上高(数量ベース)が前年比2%前後の伸びとなる年も散見されたが、2024年の伸びは前年比1%強の伸びにとどまっている。オリンピック効果が見られたフランスのほか、失業率の低下が続くスペインの消費は堅調だったが、ドイツなどでは景気や雇用の先行きへの不安から節約志向が強まり、消費が抑えられた。ユーロ圏全体として、食料・飲料・たばこが伸び悩む一方、それ以外は相対的に堅調だったが、イタリアは食料・非食料ともに弱く、2024年も前年比マイナスとなっている。水準も依然、コロナ禍前を下回った。
金額ベースで見た小売売上高は増加を続けている(第I-5-2-5図)。高めの上昇が続く物価が重しとなり、数量が伸び悩んでいることが示唆される。
第Ⅰ-5-2-5図 ユーロ圏・欧州諸国の小売売上高の推移
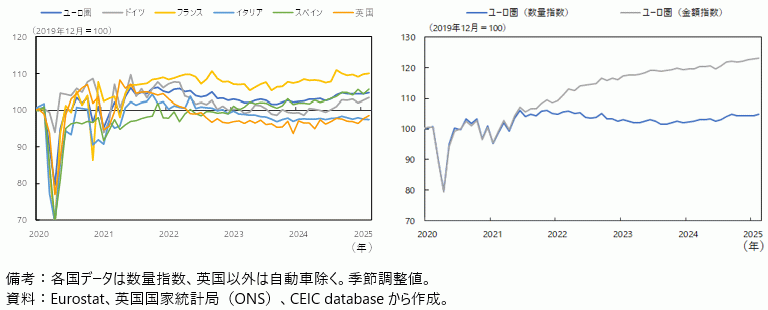
英国はイタリア同様、食料・非食料がともに弱含み、数量ベースの売上高は前年比横ばいにとどまった(第I-5-2-6図)。
第Ⅰ-5-2-6図 ユーロ圏・欧州諸国の小売売上高(品目別)
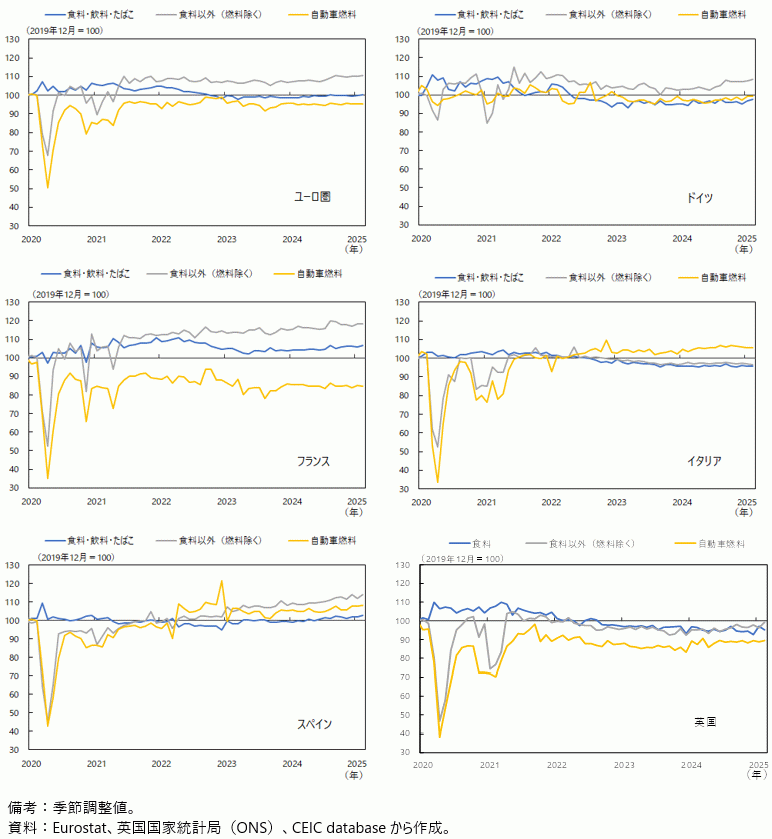
4. 生産
ユーロ圏の鉱工業生産は、2023年初をピークに失速し、2024年はコロナ禍前(2019年12月)程度の水準で一進一退を続けた(第I-5-2-7図)。中国向けなどで輸出が弱含んだドイツの弱さが目立つ。中間財、資本財、消費財いずれも不振が続いている(第I-5-2-8図)。ドイツの製造業低迷の背景には様々な構造要因も絡んでおり、生産のもたつきは根が深い。イタリアも生産の低下傾向が強かった。ドイツと同様に輸送機器の輸出が不調だったほか、繊維・衣料品・皮革製品も不振だった。消費財の生産が冴えず、中間財の生産も弱含んだ。
第Ⅰ-5-2-7図 ユーロ圏・欧州諸国の鉱工業生産の推移
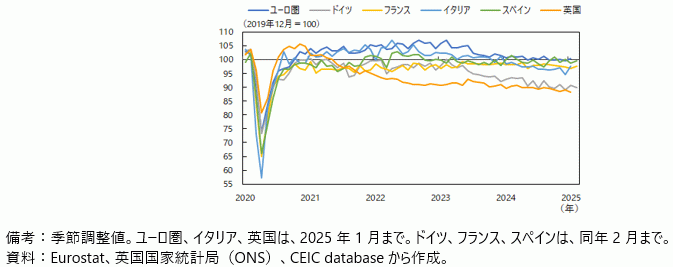
第Ⅰ-5-2-8図 ユーロ圏・欧州諸国の鉱工業生産(財別)
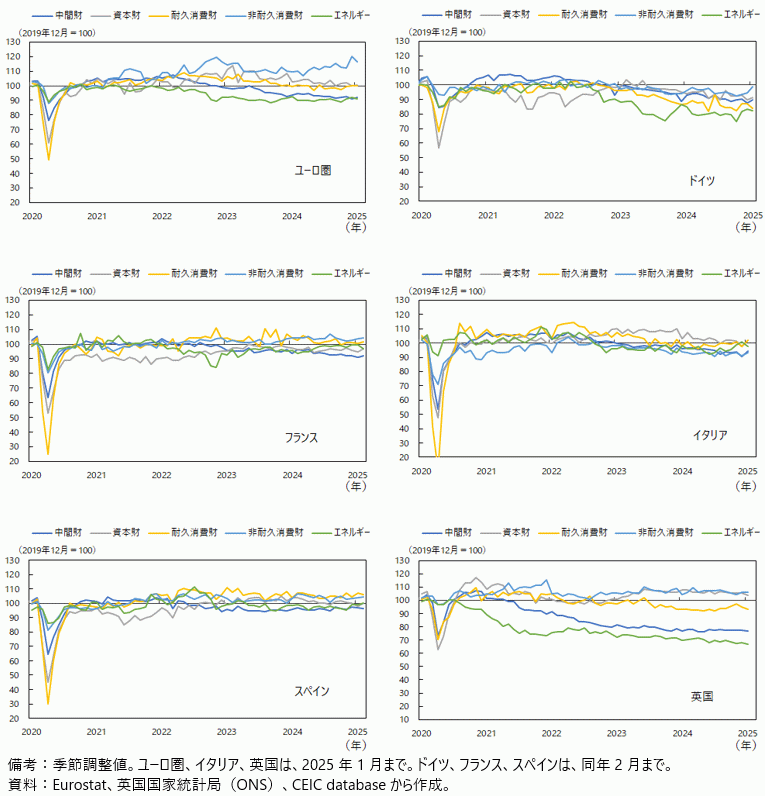
ユーロ圏の輸出入は、その半分程度が域内向けで、域内分業が進んでいる。ドイツなど主要国の製造業の低迷が他国に波及する懸念も高まっている。
英国は、耐久消費財の不振が続き、中間財もコロナ禍の時期の生産を大きく下回る状況が続いた。
5. 雇用
失業率は、多くの国で歴史的な低水準で推移した。ユーロ圏の失業率も2024年10月に6.2%まで低下している。景気が停滞気味なドイツやイタリアでも、失業率の悪化は限定的となっている。スペインでは堅調な景気に加え、2021年末~2022年初にかけて行われた労働法改革で、不安定な雇用の原因とされる有期雇用を制限するといった中道左派の社会労働党(PSOE)を軸とする左派政権の施策もあり、失業率の改善が続いているものと見られる。(第I-5-2-9図)。
第Ⅰ-5-2-9図 ユーロ圏・欧州諸国の失業率の推移
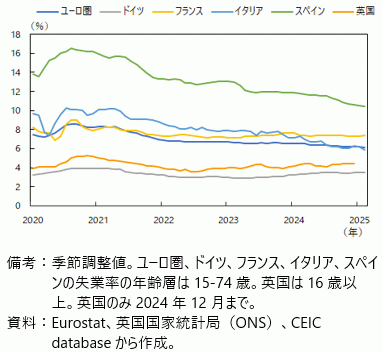
ドイツなどでは、景気に不安があっても熟練労働者の減少傾向もあって欠員率(人手不足感)は依然高く、これが堅調な失業率の背景の一つとなっている可能性が高い(第I-5-2-10図)。欠員率はユーロ圏全体でも2024年第4四半期に2.5%と2010年代前半と比べ1%程高くなっている。
第Ⅰ-5-2-10図 ユーロ圏・欧州諸国の欠員率の推移
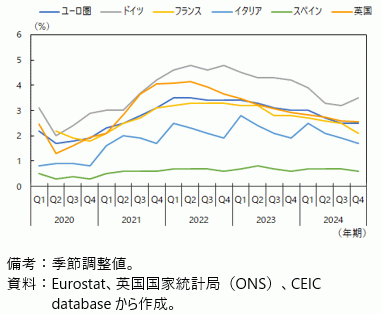
英国では、2024年に技能労働者ビザ申請に必要な給与基準が引き上げられた結果、ビザ申請件数が減るといった政策などが欠員率の低下を妨げている。もっとも、景気の先行きへの不安から企業には採用を絞る動きも見られ、失業率は4%台半ば程度で推移している。
6. 財・サービス収支
ユーロ圏の2024年の財・サービス収支は、中国向けなどの輸出の弱さはあったものの、エネルギー価格の落ち着きや内需の弱含みで輸入額が伸び悩んだ結果、黒字幅がやや拡大した。
ドイツの財・サービス収支は、輸出の鈍化で2024年後半に黒字縮小の方向に転じたが、通年では輸入鈍化の影響が大きく、黒字が増加した。イタリアも輸入額の減少幅が輸出額の減少幅を上回り、黒字幅が拡大している。スペインやフランスは、旅行需要やオリンピック効果によりサービス輸出が堅調で、財・サービス収支で見ると、スペインは黒字が拡大、フランスの赤字も縮小した(第I-5-2-11図)。
第Ⅰ-5-2-11図 ユーロ圏・欧州諸国の輸出入額(財・サービス)の推移
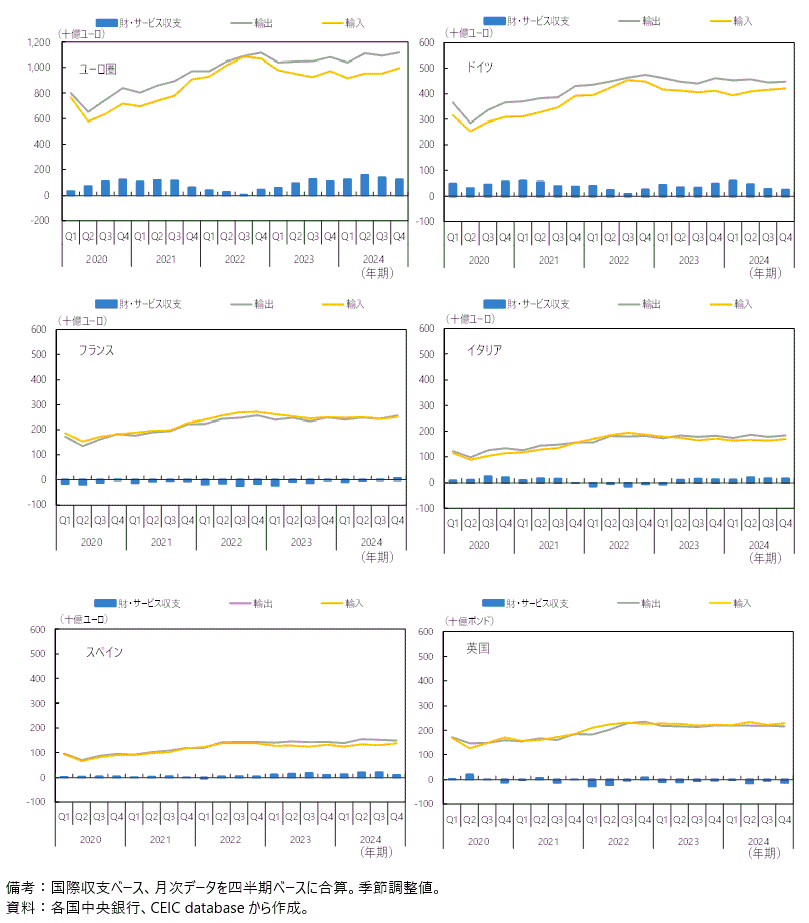
EU離脱を機に財貿易の赤字拡大とサービス収支の黒字縮小が見られた英国では、2024年もサービス黒字が貿易赤字で相殺される状態が続いた。こうした中、英国は2024年12月、CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)に正式に加入した。また、EUとの貿易縮小の原因は通関手続などの負担増にあると考える労働党政権は、貿易の円滑化に向けEUとの関係改善を急いでいる。第二次トランプ政権下の米国に対しては、米英間の貿易協定締結で通商摩擦の回避を目指している。
なお、EUは、特定国に重要鉱物などを過度に依存するリスクを低減するためデリスキングの姿勢を明確にしている。2023年6月には欧州経済安全保障戦略の柱として、経済安全保障に絡む各種リスクからの「保護」(Protecting)、競争力や成長の「促進」(Promoting)、信頼できるパートナーとの「連携」(Partnering)という「三つのP」を示した。ただし、2023年3月のフォン・デア・ライエン欧州委員会委員長の演説以降、欧州首脳は繰り返し、EUの目標はあくまでデリスキングであり、経済の分離を意味するデカップリングではないと説明している。
また、デリスキングの政策が貿易全体に与えている影響は必ずしも大きくはない。貿易統計で概観する限り、2024年時点で貿易関係に急激な変化は見られていない。ユーロ圏外からの輸入は全体の50%弱で安定しており、そのうち中国からの輸入の割合は足下15%前後で、2021年の16%台半ばからはやや下がっている程度である。2024年下期には、中国製の電気自動車に対するEUの相殺関税発動前の駆け込み輸入などもあり、中国からの輸入の割合が高まる動きも見られた(第I-5-2-12図)。
第Ⅰ-5-2-12図 ユーロ圏の対圏外輸出入に占める主要各国の割合
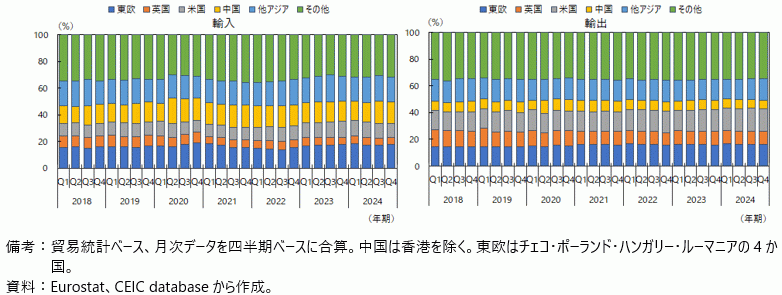
なお、2022年頃からは米国からの輸入の割合がじわりと拡大しており、足下は11%程度となっている。この点、第二次トランプ政権の鉄鋼・アルミ追加関税発動に対し、EUは対抗関税措置を発表しており、2025年4月末時点でその適用を一時停止中であるが、今後の貿易摩擦の行方が貿易関係に与える影響は注視する必要がある。
7. 今後の見通し
欧州では、観光需要の息切れ感やオーバーツーリズムのひずみが見え始めたほか、ドイツなど域内主要国の製造業不振の影響が他国に波及する懸念も高まっている。このため、ECBは引き続き景気にも配慮しつつ政策金利を中立金利程度まで引き下げると見られる。利下げの前提となるインフレ率は、2026年にかけて2%程度に収束する見通しで、実質所得の押し上げから消費は底堅く推移すると見込まれる。また、利下げを受け、2025年中に固定資本形成は徐々に持ち直し始めることが期待される。IMFの世界経済見通し(2025年4月)、欧州委員会の2024年秋の経済見通し、ECBのスタッフによる経済見通し(2025年3月)による実質GDP成長率の見通しは以下のとおりとなっている(第I-5-2-13表)。
第Ⅰ-5-2-13表 ユーロ圏・欧州諸国の実質GDP成長率の見通し
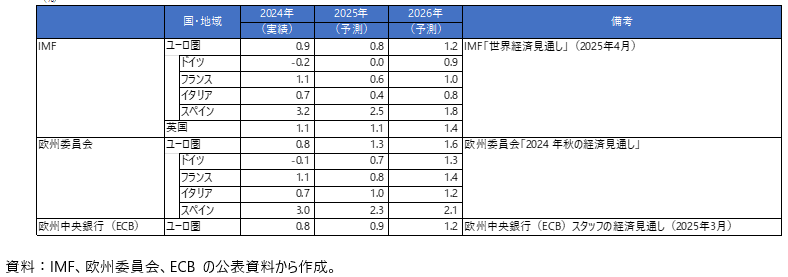
ただ、この見通しは下振れリスクをはらむ。第二次トランプ政権の通商政策に起因する貿易摩擦が、EUの製造業を含む経済活動への逆風となり得る。関税の応酬になれば域内の物価を押し上げる可能性もあり、ECBの利下げ判断に影響するおそれがある。また、通商摩擦に関連した不確実性の高まりで企業マインドが悪化すれば、設備投資が伸び悩むほか、消費の裏付けともなる雇用にも影響しかねない。
米国の政策スタンスの変化は安全保障面にも表れており、これを受けて、欧州では協調して防衛費を拡大する方向性が議論されている。その実現のための財政ルールの緩和についても議論されており、従前EU平均で2%程度となっていた防衛費について(第I-5-2-14表)、定義変更も交えつつ、GDP比で平均1.5%増額といった数字も聞かれる。これらが今後の景気や物価、金利に及ぼす影響も注視される。
第Ⅰ-5-2-14表 欧州諸国の軍事費対GDP比