第3節 中国経済
2024年の中国経済は、消費喚起政策を含む財政支出の効果もあって政府目標並みの成長となったが、不動産不況の長期化や個人消費の不振、デフレ傾向などから、停滞色が強い状況が続いた。第1章第2節で見たとおり、内需の低迷に対して、供給側の調整が進んでいないことから、輸入が停滞する一方で輸出は単価下落を伴いながら増加しており、GDP成長率への純輸出の寄与が大きくなっている。こうした状況は、貿易摩擦を始めとする内外のリスク要因を高めており、経済の先行きには下押し圧力が加わりやすい展開が続くと見込まれる。
1. GDP
2024年の中国の実質GDP成長率は、通年で+5.0%と、政府目標の「5%前後」を達成した(第I-5-3-1図)。第1四半期は、2023年から続く消費喚起政策の後押しもあり消費を中心に内需が下支えしたが、そうした効果は徐々に減衰し、成長率は低下する動きとなった。第3四半期以降は、米国やEUによる追加関税の発動を見越した駆け込みと見られる動きもあって純輸出の寄与が拡大した。2024年の終盤からは、消費喚起政策の拡充により消費が再び寄与を拡大したほか、純輸出も引き続き高い伸びを示している。
第Ⅰ-5-3-1図 中国の実質GDP成長率の推移
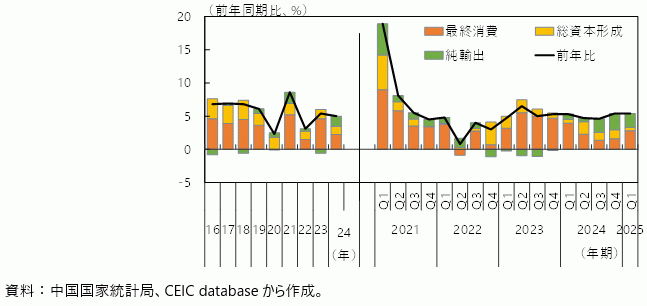
業種別に見てみると、第二次産業が伸びを拡大した一方、第三次産業の伸び率は低下した(第I-5-3-2表)。低迷が続く不動産は、政策支援の効果もあって徐々にマイナス幅を縮め、第4四半期には小幅のプラス成長に転じた。
第Ⅰ-5-3-2表 中国の実質 GDP 成長率(業種別)の推移
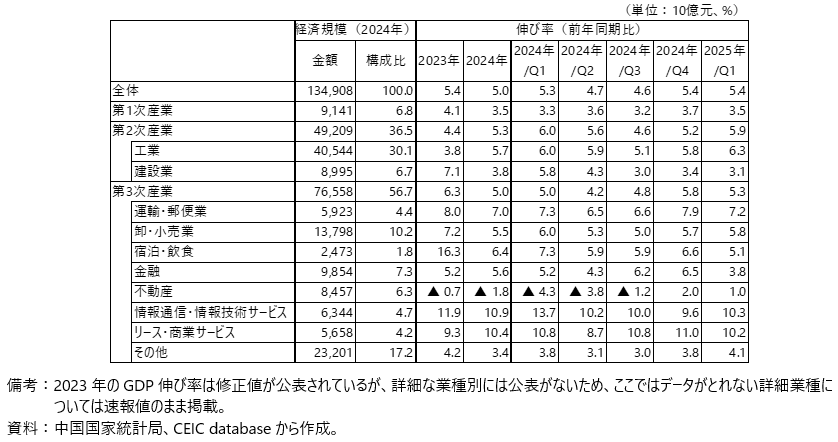
2. 工業生産
工業生産は2024年通年で前年比+5.8%と、2023年(同+4.6%)から拡大した(第I-5-3-3図)。主要な業種別に見ると、パソコンやスマートフォンの回復から電子・通信機器が伸びを大きく拡大したほか、堅調な新エネルギー車(電気自動車やハイブリッド車)生産に支えられ、自動車も比較的高い伸びを維持した。ただし、こうした工業生産全体の増加基調は、内需が強くない状況下で、後述するように、輸出超過の拡大と輸出単価の下落傾向につながっている。
第Ⅰ-5-3-3図 中国の工業生産
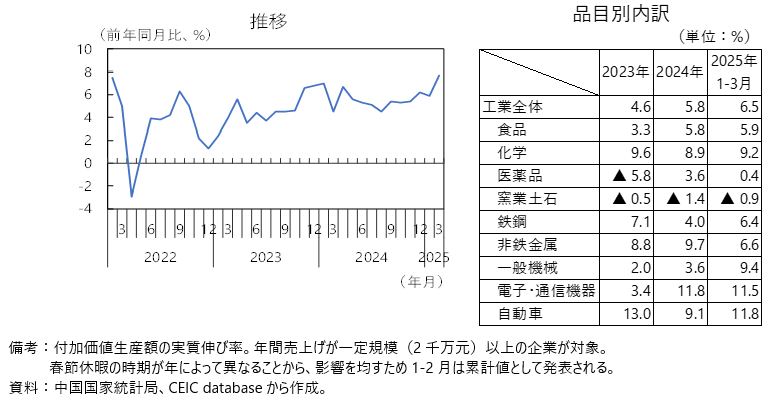
3. 固定資産投資
2024年の固定資産投資は前年比+3.2%と、2023年(同+3.0%)からやや拡大した(第I-5-3-4図)。製造業では、政府が2024年3月に発表した「大規模設備の更新と消費財買い替え推進」政策により、企業の設備・機械投資が大幅に増加した。企業業態別では、国有企業は一定のプラス成長となったが、民間企業は昨年に続きマイナス成長となった。2024年7月の三中全会(中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議)及び2025年3月の全人代(全国人民代表大会)では、民間企業の発展を支援する方針が示されており、今後、民間投資が持ち直していくか、注視が必要である。不動産開発投資は、2024年通年で前年比-10.6%と2桁のマイナス成長に陥った。不動産開発については本節「9. 不動産問題」でより詳しく見ることとする。
第Ⅰ-5-3-4図 中国の固定資産投資
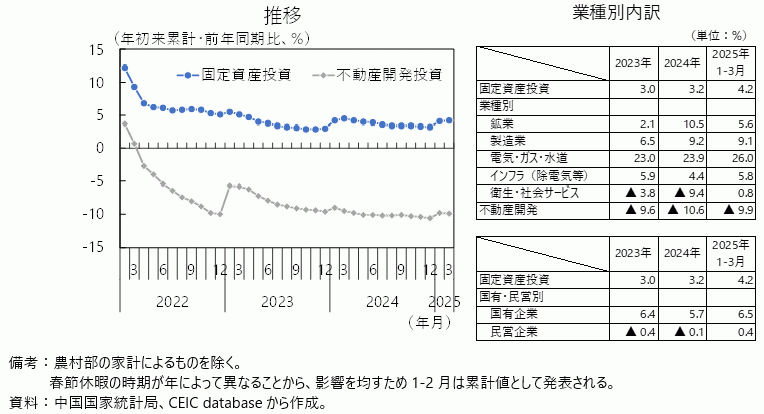
4. 小売売上高
2024年の小売売上高は前年比+3.5%と、2023年(同+7.2%)から伸び率が大幅に低下した(第I-5-3-5図)。コロナ禍前である2019年の同+8.0%にも遠く及ばず、消費は伸び悩む姿となっている。背景には、低調な消費者心理や節約志向が広がっていることがある。品目別では、「大規模設備の更新と消費財買い替え推進」政策の後押しから、家電・映像音響機器は高い伸びとなった。大型商品で消費に大きな影響を与える自動車は、買い替え推進政策の対象であり、年間販売台数は過去最高を更新したものの、新エネルギー車を中心とする価格競争の激化を受けて、売上高は前年比でマイナスとなった。
第Ⅰ-5-3-5図 中国の小売売上高
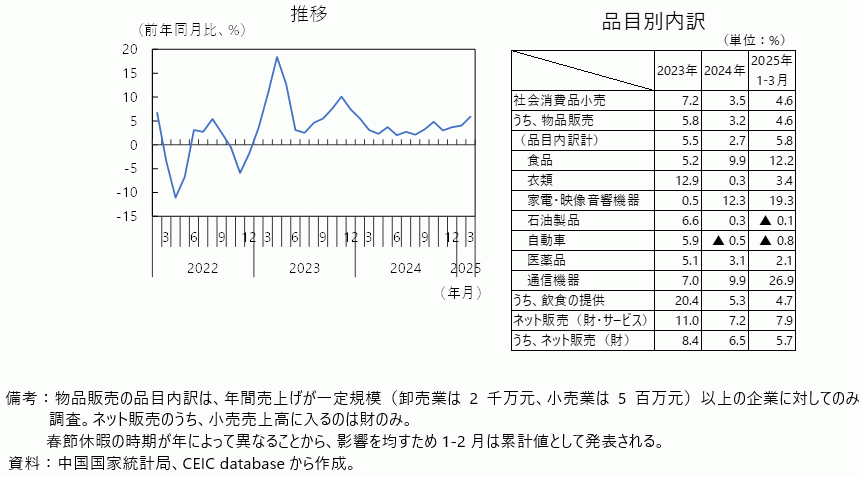
5. 貿易
2024年の輸出は前年比+5.9%、輸入は同+1.1%と、輸出入ともに前年のマイナス成長から増加に転じた(第I-5-3-6図)。とりわけ輸出の増加が顕著となっており、貿易収支は、+9,921億ドルと過去最大を更新した。
第Ⅰ-5-3-6図 中国の貿易動向
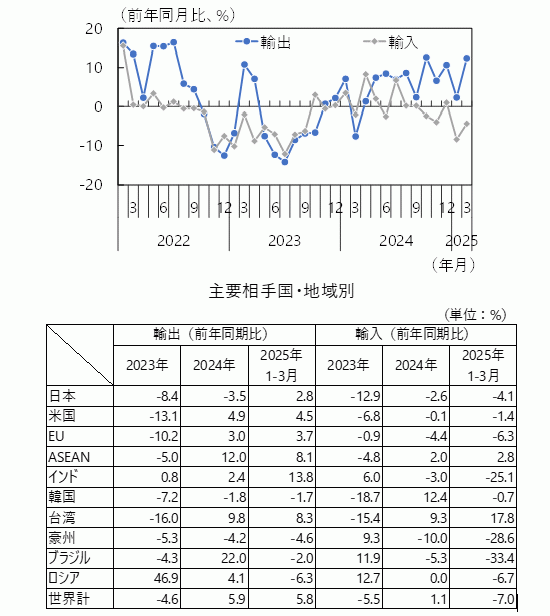
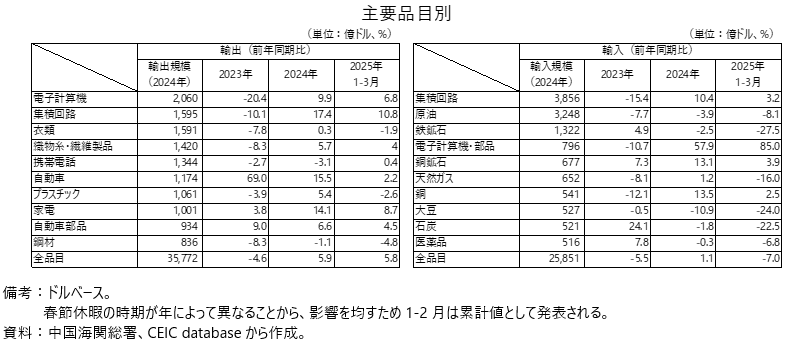
主要相手国・地域別では、米国、EU、ASEAN、ブラジルを中心に広く増加した。年後半には、EUの中国製電気自動車に対する追加関税が発動され、米国の第二次トランプ政権による対中追加関税が見込まれる中、駆け込み輸出と見られる動きが追い風となった。一方、輸入は内需の低迷から徐々に伸び幅を縮め、秋口には再びマイナス基調に転じた。
主要品目別に見ると、輸出では電子計算機や集積回路などのIT製品、衣類や家具などの労働集約型製品など、従来からの主要輸出品目が広く増加に転じた。他方、自動車の輸出は引き続き増加しているが、伸び率が大きく縮小した。
第1章第2節で見たとおり、中国の景気低迷に伴うデフレ輸出の増加、更には直近の米中貿易摩擦回避の流れと思われるアジア周辺国を始めとする新興国・途上国への輸出増加に対して、懸念が高まっている。
6. 物価
2024年の消費者物価は通年で前年比+0.2%と伸び率は前年から変わらず、政府目標の「3%前後」を大きく下回った(第I-5-3-7図)。食品・エネルギーを除くコア指数は、特に年央から減速が強まった。自動車などの耐久財価格の下落が全体を押し下げている。生産者物価は、2022年後半以降、2年半にわたってマイナス圏で推移している。
第Ⅰ-5-3-7図 中国の消費者物価・生産者物価の推移
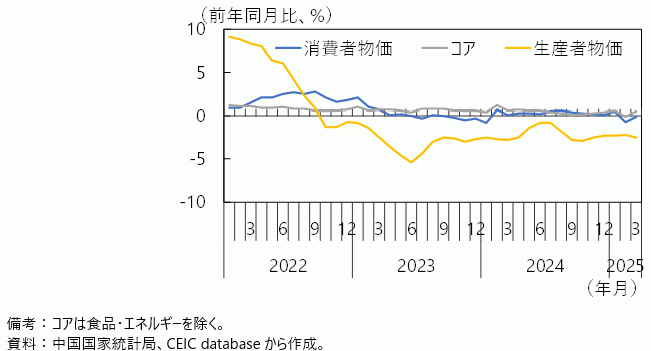
経済全体のインフレ圧力を測るGDPデフレーター(名目GDP÷実質GDP)の伸び率は、8四半期連続のマイナスとなり、中国経済はデフレ状態にあるといえる(第I-5-3-8図)。貸出伸び率の低下トレンドに見られるように、背景には需要の構造的な弱さがあると考えられる(第I-5-3-9図)。
第Ⅰ-5-3-8図 中国のGDPデフレーター
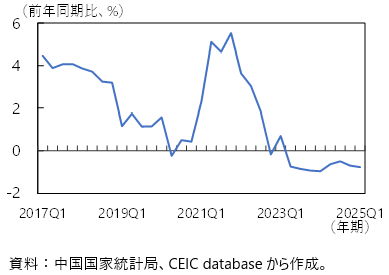
第Ⅰ-5-3-9図 中国の社会融資総量の推移
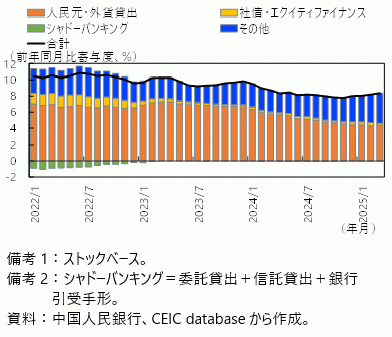
7. 雇用
2024年の都市部調査失業率は、年間を通じておおむね2023年と比べて同等以下の水準で推移した。2024年平均(各月の数値の単純平均)は5.1%と、政府目標の「5.5%前後」の範囲内に収まり、都市部新規就業者数は1,256万人と、年間目標である「1,200万人以上」を上回った(第I-5-3-10図)。しかし、中国国内の雇用環境は厳しい状況が続いている。
第Ⅰ-5-3-10図 中国の都市部調査失業率の推移
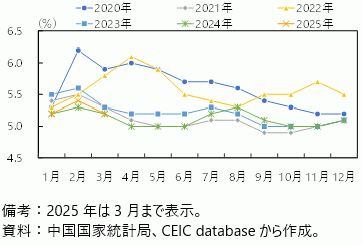
特に、若年層の失業率が高いことが懸念されている。国家統計局は、16~24歳の若年層失業率について算出方法を見直し24、2023年12月分から新たな基準で公表を再開した。旧基準と単純比較はできないものの、やはり若年層の失業率が高く、特に大学卒業時期である夏以降に失業率が高まっている。高学歴化により大卒者数は増加しており、今後も若年層の雇用状況の悪化が懸念される(第I-5-3-11図)。
第Ⅰ-5-3-11図 中国の都市部若年層失業率の推移
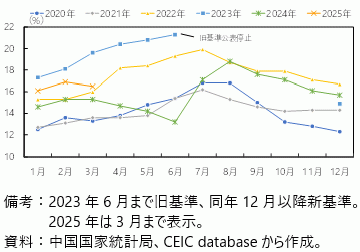
24 求職中の在学生が調査対象から除外された。
8. 政策金利
中国人民銀行(中央銀行)は、通年で緩和的な金融政策方針を維持した。特に7月の三中全会以降、政策金利を度々引き下げ、景気の下支えを図った(第I-5-3-12図)。住宅ローン金利が参照する 5 年物最優遇貸出金利(LPR)は、2024年に合計0.6%ポイント引き下げられ、後述する不動産関連支援策とともに不動産部門への配慮を見せた。もっとも、政策金利の引下げは貸出金利を引き下げ、銀行の利ざやを圧迫する。また、各国が金融政策を引き締める中での緩和的な政策は、人民元安の圧力を高め資本流出につながるおそれがあることから、利下げのハードルは高くなっている。
第Ⅰ-5-3-12図 中国の金融政策の推移
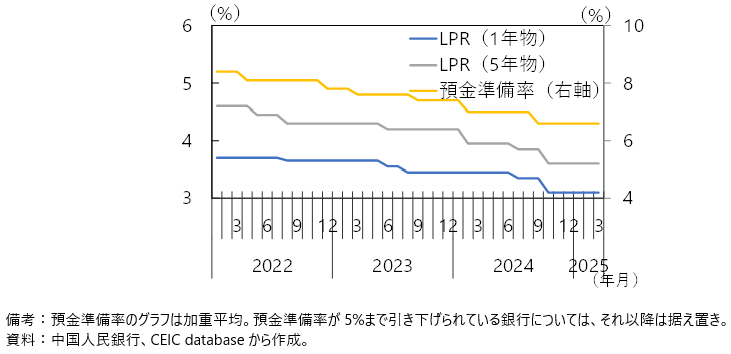
9. 不動産問題
不動産開発投資の大幅なマイナス成長に見られるように、不動産部門の不調は2024年も続いている。不動産開発は、建設資材や耐久消費財など関連部門への波及が大きく、経済全体への影響も大きいことから、政府も様々な対策を講じてきた。2024年5月には、住宅ローン金利の下限撤廃や頭金比率の一層の引下げなど需要側への施策と、不動産開発企業への金融支援拡大や地方政府による完成住宅在庫の買取りなど供給側への施策を同時に実施する包括的な対策を導入した。また同年10月には、販売済みにもかかわらず、不動産開発企業の資金繰り悪化により物件の建設が進まず購入者に引き渡されない「未完成物件」プロジェクトに対する与信規模を倍増させた。
こうした政策支援もあって、以前のように大手不動産開発企業が資金繰りに窮し、デフォルトやデフォルト危機が頻繁に報道されるような状況からは脱したと見られる。また、住宅価格は年後半からマイナス幅を縮めている(第I-5-3-13図)。もっとも、各種政策は、不動産市場の状況を悪化させないための措置が中心であり、住宅販売や不動産開発投資が力強く回復する見通しは描けていない。
第Ⅰ-5-3-13図 中国の新築住宅価格指数
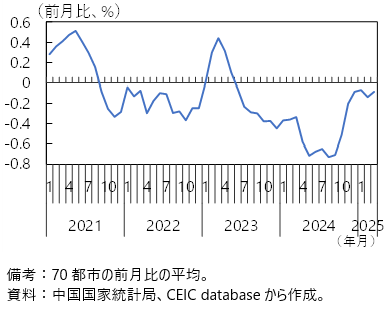
10. 地方政府財政
不動産市場の低迷は、土地の使用権を不動産開発業者に譲渡することで収入を得てきた地方政府の財政に影響を及ぼしている。土地使用権譲渡収入は減少が続き、2024年は2021年のピーク時からおおよそ半減した(第I-5-3-14図)。一方で、地方債の残高は拡大が続き、50兆元に迫る水準まで増加している(第I-5-3-15図)。
第Ⅰ-5-3-14図 中国の地方政府の土地使用権譲渡収入の推移
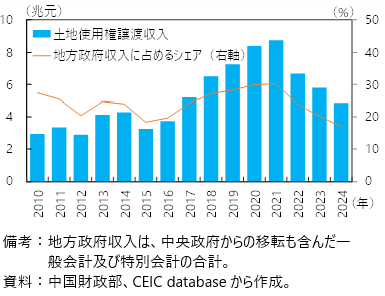
第Ⅰ-5-3-15図 中国の地方債務残高の推移
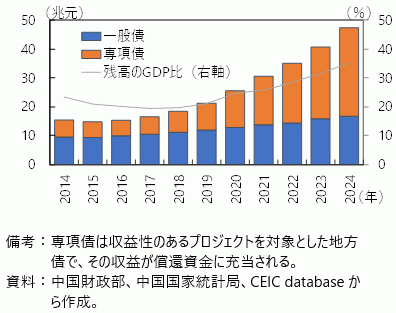
こうした中、中央政府は地方政府に対し、専項債の発行加速を奨励している。本来専項債はインフラ投資に充てられるものだが、不動産部門へのテコ入れとして、不動産開発会社が抱える在庫住宅の買い取りに充てることが可能となった。歳入が細り将来の返済が見通せない中で、地方政府財政は厳しい状態が続いている。
11. 今後の見通しと中国政府の政策
今後の中国の経済成長の見通しと中国政府の目標や政策について見ていく。主要な国際機関等の中国の経済成長見通しは、2025年はおおむね4.5%程度、2026年はそれよりもやや減速するといったものになっていた。しかし、IMFが4月に公表した「参照予測」では、4月4日までの米中による関税引上げ等を反映して、2025年・26年いずれも4.0%と大きく見通しを引き下げている(第I-5-3-16表)。
第Ⅰ-5-3-16表 中国の実質GDP成長率見通し
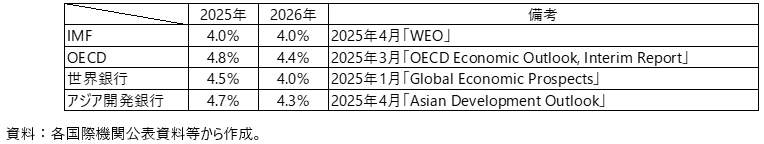
中国政府は2025年3月、全人代を開催し、今年の経済運営方針として、消費の押し上げや投資効果の向上など内需拡大を重要項目に掲げ、財政出動などを通じて景気を下支えすることを打ち出した。数値目標を見ると、2025年の成長率目標は「5%前後」、都市部失業率は 「5.5%前後」、都市部新規就業者は 「1,200万人以上」と昨年と同じ水準に設定された(第I-5-3-17表)。一方、消費者物価上昇率は「2%前後」と、昨年の3%前後から引き下げられた。足下の物価低迷を反映したものと見られる。
第Ⅰ-5-3-17表 中国の2025年の主要数値目標
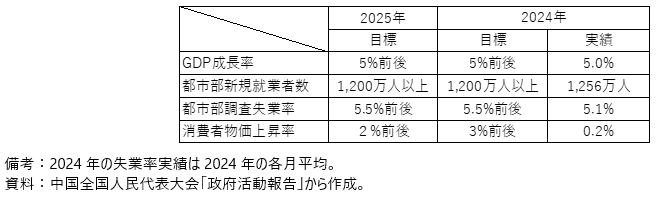
財政については、財政赤字の対GDP比目標を「4%前後」と、昨年の3%程度から引き上げ、財政政策を積極的に活用する姿勢を示している。また、重要な国家プロジェクトに充当するため昨年から発行を開始した超長期特別国債は、3,000億元増額し1兆3,000億元発行する。米国による対中関税引上げなどによる景気下押しも見込まれる下で、一定の財政拡充により景気の安定化を図るものとなっている。