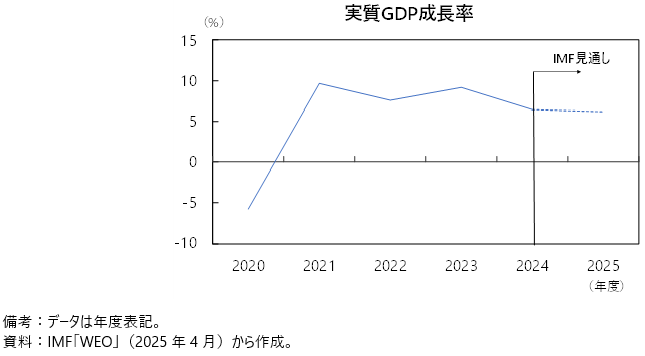第5節 インド経済
インド経済は、外需主導型のASEAN諸国とは異なり、サービス業を中心とする内需が牽引する形で、高い成長を続けてきた。このところ成長率は鈍化傾向にあり、米国の関税政策に関連した先行きの不透明感の高まり、成長期待の剥落などを受けた資本流出、及びそれに伴う通貨安、株安など一部に不安定な動きが見られるものの、比較的高い成長率を維持している。
1. GDP
インドの実質GDP成長率は、2023年度第1四半期(4―6月期)の前年比+9.7%をピークに徐々に鈍化が続き、2024年度第2四半期には同+5.6%と、2022年度第3四半期の同+4.8%以来の低い伸びとなった(第I-5-5-1図)。総選挙期間であったため公共投資が進まなかったほか、記録的な豪雨や食料品価格高騰による物価高の影響から消費が伸び悩んだことが背景となっている。供給面を見ると、豪雨が生産活動を下押ししたことから、製造業の落ち込みが目立っている(第I-5-5-2図)。もっとも、2024年度第3四半期は、政府支出の増加や、天候正常化による農村部の所得の回復、また年末の祭事関連の支出が伸びたことから、成長率は+6.2%に幾分持ち直す姿となっている。
第Ⅰ-5-5-1図 インドの実質GDP成長率
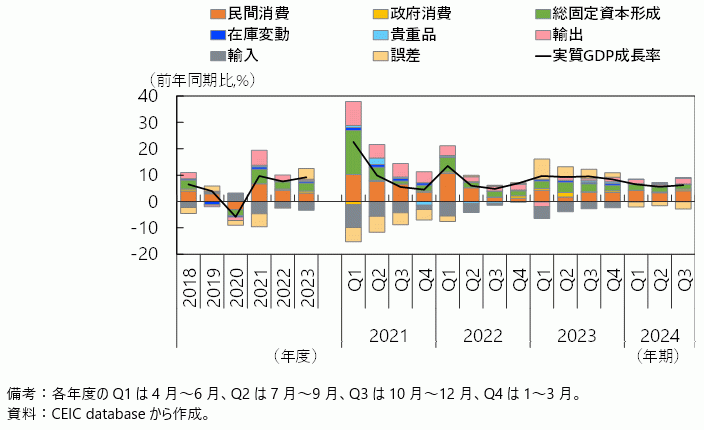
第Ⅰ-5-5-2図 インドの実質GVA成長率
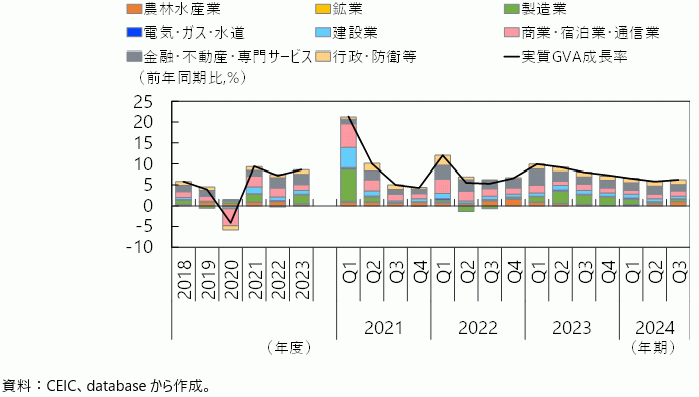
2. 消費・サービス動向
インドの消費動向を見る上で代表的な指標である二輪や乗用車の国内販売台数を見ると、インフレの高止まりと高金利環境を背景に、前年比の増加率が低下しており、民間消費が力強さを欠いた状態にあることが示されている(第I-5-5-3図)。一方、サービス関連企業の景況感を示すPMIを見ると、2024年の秋以降、仕入れコストの上昇などから低下傾向となっているものの、好不況の節目とされている50は上回り続けており、一定の底堅さを見せている(第I-5-5-4図)。
第Ⅰ-5-5-3図 インドの二輪と乗用車の国内販売台数
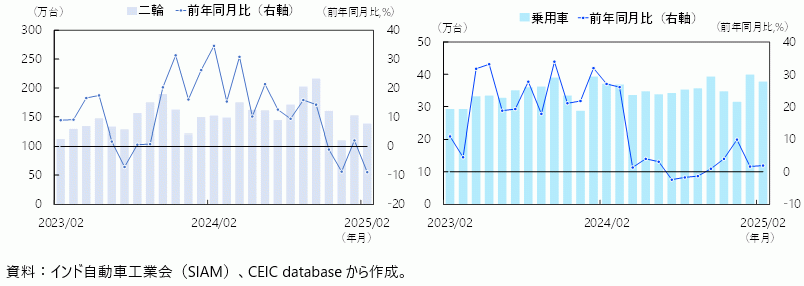
第Ⅰ-5-5-4図 インドのサービスPMIの推移
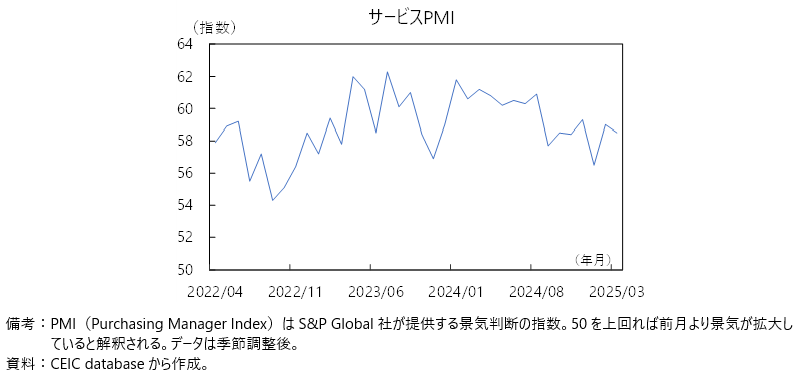
3. 外需動向
インドの財輸出は、景気回復力が弱い欧州向けや情勢悪化が続く中東向けなどが振るわず、力強さを欠く展開が続いている(第I-5-5-5図)。豪雨の影響で鉱工業生産が大きく落ち込んだ2024年半ばには大幅なマイナス成長を記録し、足下でも回復は鈍い。一方、サービス輸出は、2023年は低調な動きとなっていたが、2024年に入り、ICTや専門業務サービスを中心に、再び増勢基調となっている(第I-5-5-6図)。
第Ⅰ-5-5-5図 インドの財輸出伸び率の国別推移
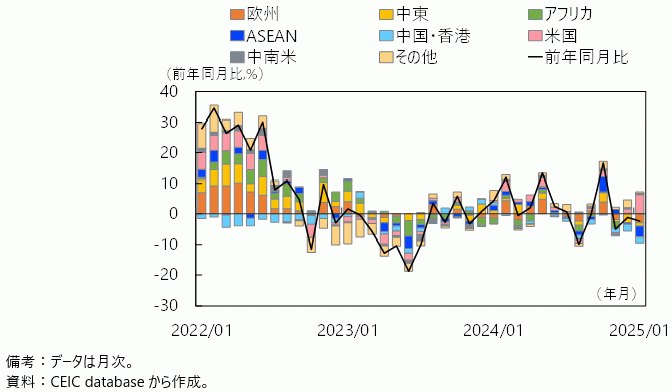
第Ⅰ-5-5-6図 インドのサービス輸出の項目別推移
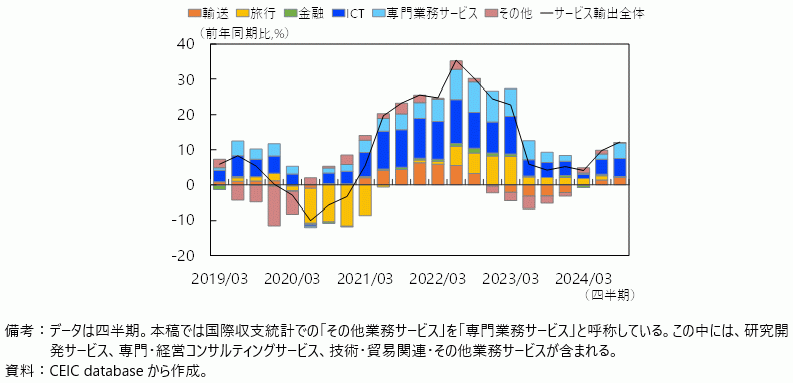
4. 国際収支
インドの経常収支は、サービス収支の黒字は拡大しているものの、大幅な財貿易の赤字により、赤字傾向が続いている(第I-5-5-7図)。財貿易の赤字は、財輸出の伸びが低迷している一方、輸入が拡大していることから、増加基調にある。輸入は、全体の約2割を占める原油や石油製品のほか、金などの貴金属関連の輸入拡大が全体を押し上げている。金融収支の方を見ると、証券投資を中心に旺盛な資金流入が続いていたが、2024年10月に大規模な資金流出が発生した(第I-5-5-8図)。2024年度第2四半期(7-9月期)の実質GDP成長率が想定を下回る弱さとなり成長期待が剥落したことや、新興財閥であるアダニ・グループのアダニ会長らがインド政府との贈収賄にかかわった容疑で米当局に起訴されたことなどによる、外国人投資家のリスク回避の動きが背景と見られる。その後、12月にかけて徐々に資金が戻る傾向も見られたが、足下では米国の金利高止まりやトランプ政権の関税政策の影響懸念もあって再び資金流出圧力が強まっている。
第Ⅰ-5-5-7図 インドの経常収支推移
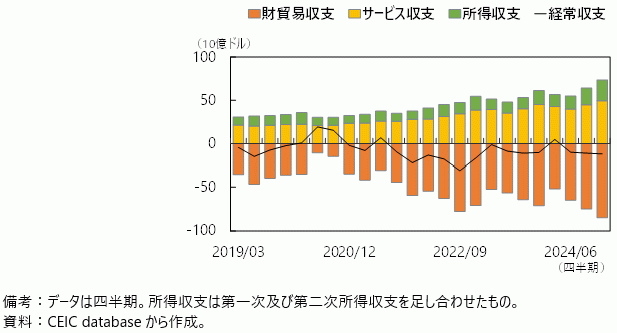
第Ⅰ-5-5-8図 インドへの外国投資の推移
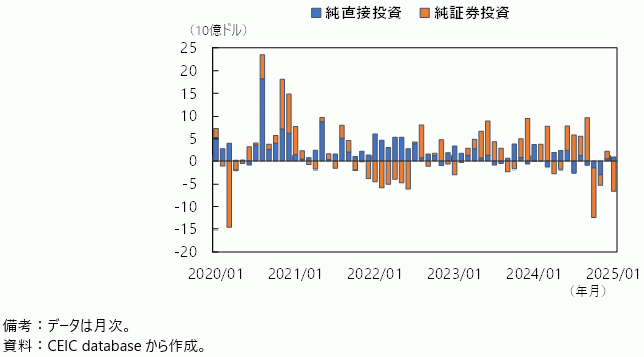
5. 通貨・株価
10月以降の資本流出は通貨及び株価への押し下げ圧力となっている(第I-5-5-9図)。通貨は2024年に入った後、安定的に推移していたが、10月の大規模な資本流出を契機に、急速にルピー安が進んだ。インド準備銀行は通貨の安定化を図るべくドル売りルピー買い介入を行い、足下では若干持ち直しの動きが見られる。対外脆弱性を評価する際の指標の一つである外貨準備高輸入比を見ると、一般的に目安とされる輸入額の3か月分を大幅に超える状況が続いており、直ちに対外流動性懸念を招く状況ではないが、通貨安に伴うインフレが家計消費の重荷となることが懸念される(第I-5-5-10図)。また、株式指数(SENSEX25)も為替同様に軟調な動きを続けていたが、足下では回復が見られる。
第Ⅰ-5-5-9図 インドの通貨(対ドル)と株価の推移
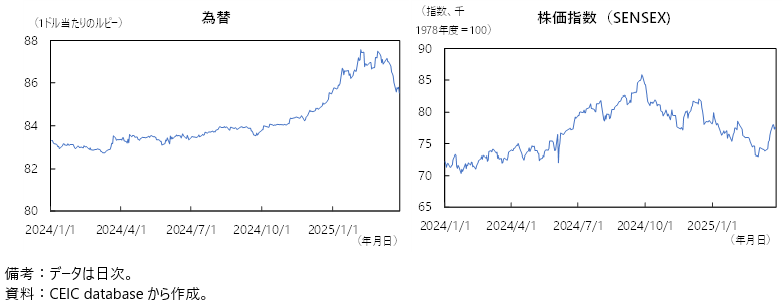
第Ⅰ-5-5-10図 インドの外貨準備高推移
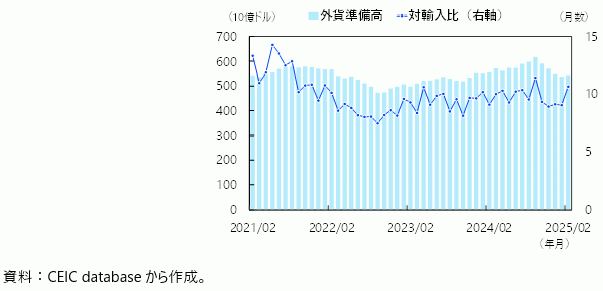
25 インドのボンベイ証券取引所(BSE)に上場する、代表的な30の企業の株価から構成されている指数。
6. 生産活動
インドの鉱工業生産は、製造業を中心に増加基調ではあるものの、やや力強さを欠く展開が続いている(第I-5-5-11図)。内訳を見ると、世界的な半導体需要の回復を受け電子部品・機器は回復傾向が続いているが、医薬品や食品、自動車などの生産が弱い状態が続いている。製造業PMIは、景気拡大を示す50超の領域で推移しており、3月には8か月ぶりの水準に拡大した(第I-5-5-12図)。
第Ⅰ-5-5-11図 インドの鉱工業生産指数
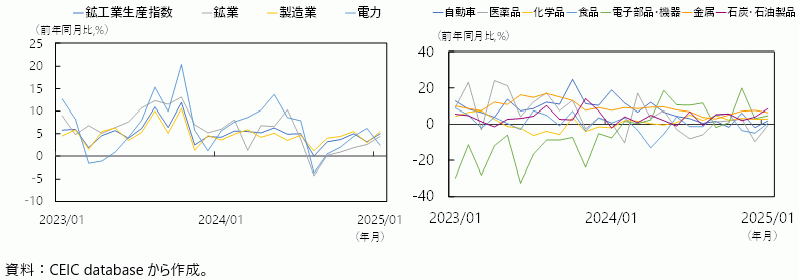
第Ⅰ-5-5-12図 インドの製造業PMIの推移
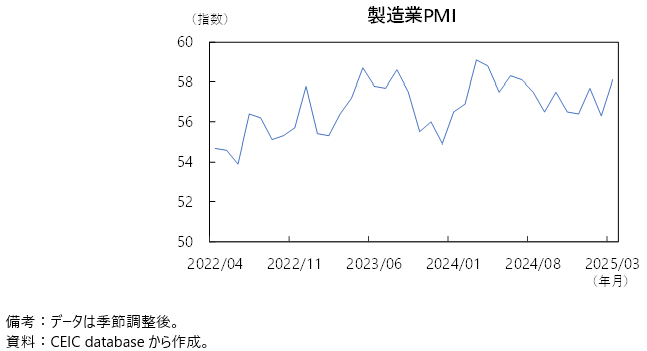
7. 雇用動向
インドの労働市場は構造的な改善が続いている。長年にわたって低迷が続いていた労働参加率は近年急上昇しており、同時に失業率は都市部、農村部とも低下傾向となっている(第I-5-5-13図)。こうした労働参加率の上昇はGDPを押し上げるものの、IMFは、労働参加率の上昇が農業部門でより顕著であることなどを踏まえ、より生産性の高いセクターへの人的資本の移動とはなっていない点が課題との指摘を行っている26。
第Ⅰ-5-5-13図 インドの労働参加率と失業率の推移
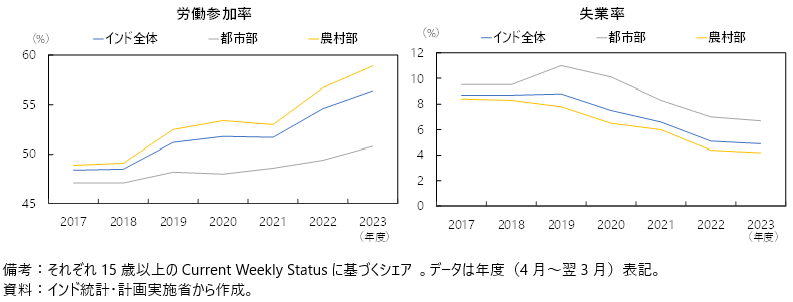
26 IMF (2025)
8. 物価・金融政策動向
インドの消費者物価指数(CPI)の上昇率は、CPIバスケットの5割弱を占める食料・飲料価格に大きく左右される(第I-5-5-14図)。2023年前半にかけて低下傾向にあったインフレ率は、同年後半以降に再び加速し、その後は5%前後での推移が続いた。背景としては、エルニーニョ現象等の異常気象による世界的な食品価格の高騰などが挙げられる。インド準備銀行は高止まりするインフレを背景に、政策金利を高めに維持してきたが、2025年2月には、食料価格が安定化し、インフレ率が目標の4%付近まで落ち着いたことから4年9か月ぶりとなる利下げを実施し、金融緩和方向へ転換した(第I-5-5-15図)。インド準備銀行は足下の内需の弱さを背景に更なる緩和余地があると示唆している。
第Ⅰ-5-5-14図 インドの消費者物価指数伸び率
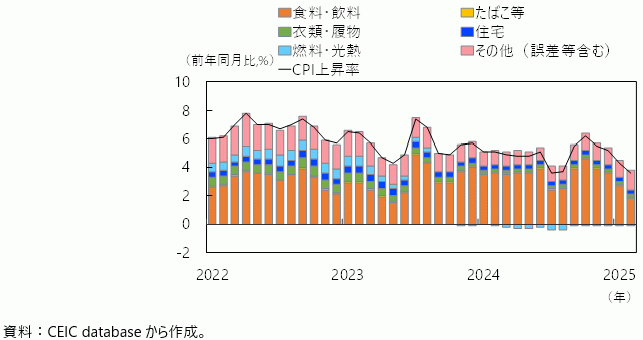
第Ⅰ-5-5-15図 インドの政策金利推移
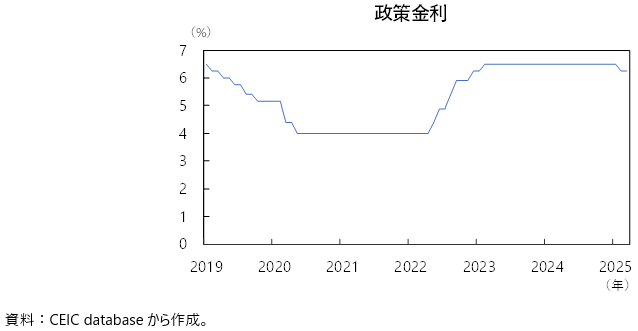
9. 今後の見通し
IMFの2025年4月公表の世界経済見通しによると、インドの2024年度の経済成長率は6.5%となると見込まれている(第I-5-5-16図)。昨年の選挙の影響で足踏みした公共投資の執行が進むことや、天候の正常化による農村部の所得の持ち直しから、内需が回復し、経済全体の回復基調を支えると見られている。2025年度は6.2%と、世界的な不確実性の高まりと貿易摩擦の影響を受け、1月の予想から0.3%ポイント引き下げられた。他方で、内需は農村部の所得回復を受けた堅調な消費が予想され、全体の落ち込み幅は限定的となった。
第Ⅰ-5-5-16図 インドの実質GDP成長率の見通し