国際政治経済構造は、大きな変動期を迎えている。第Ⅰ部第2章では、世界経済の不確実性を高めている五つの国際環境変化を概観したが、その背景には、ルールベースの国際経済秩序が直面する中長期的な構造変化がある。第一に、冷戦後のグローバル化が各国内や国家間の格差を拡大させたとの不満が、保護主義的な貿易政策や大衆迎合的な政治運動への支持の土壌になっている。第二に、デジタル化の進展はモノとサービスの融合やデジタルサービスの越境取引を促進し、貿易投資のパターンを変え始めている。第三に、気候変動を始めとする地球環境課題が世界的なグリーン移行の流れを生み出しており、それに貢献する貿易政策が求められている。第四に、経済安全保障認識の高まりは、サプライチェーン強靱化の政策的な必要性を生じさせ、とりわけグリーン移行等に不可欠な重要鉱物を巡る政策対応の重要性を高めている。第五に、こうした社会経済課題への取組を産業発展につなげる新たな産業政策が注目される一方、一部の産業政策が貿易投資、ひいては国際経済秩序に与え得る悪影響についても対応が求められている。今後、ルールベースの国際経済秩序の再構築を展望する上では、これら五つの構造変化と政策アジェンダを考慮に入れる必要があろう。
本章では、①格差の拡大と社会的分断、②デジタル化が変えるサービス越境取引、③グリーン移行と貿易、④サプライチェーンの強靱性と重要鉱物、⑤産業政策と国際経済秩序について、その背景や学術的議論の展開、国際的な動向、現状分析や課題整理を試みる。
第1節 格差の拡大と社会的分断
保護主義の台頭と貿易摩擦によって、国際経済秩序が揺らいでいる。背景には、冷戦後のグローバル化や貿易自由化によって、各国内や国家間の格差が拡大したとの不満の高まりがある。事実としては、過去30年間に世界の所得水準は全体として大きく向上し、絶対的貧困が減少してきた。他方、いわゆる「中国ショック」研究が示唆するとおり、輸入の急増が特定の産業や地域の雇用・所得に悪影響を与えた可能性がある。同時に、人々の自由貿易に対する不満は、所得格差をもたらす他の要因に比べて過大に表明される傾向にあることにも留意が必要である。また、輸入急増への対処として、利益の再分配を目的とした制限的な貿易政策を採ることは、副作用が大きく効率的な政策選択ではない。他方で、輸出国側に目を転じると、途上国を中心とする輸出主導成長もまた、国内の所得分配に偏りを生じさせやすく、過少消費というマクロ経済の不均衡につながる傾向があるとされる。第Ⅰ部で概観した国際環境の変化の中で、今後、国際経済秩序の再構築を模索していく上では、こうした貿易と包摂性を巡る状況と議論の動向を理解することが重要である。
本節では、近年の貿易と包摂性を巡る国際的な議論を概観し、特に輸入急増が雇用や所得格差等に与える影響とその含意について、貿易理論の展開と実証分析の蓄積も踏まえて検討する。さらに、輸入急増に対する人々の反応や政策対応についても触れる。また、輸出主導成長が国内の所得分配に与える影響とそのマクロ経済への含意についても見ていく。これらを通じて、貿易と包摂性という観点から、ルールベースの国際経済秩序の在り方を検討する。
1. 貿易と包摂性を巡る国際的な議論
グローバル化が進展した過去30年に、世界の所得水準は大きく向上し、絶対的貧困が減少してきた一方、グローバル化が所得格差等に悪影響を与え、コロナ禍を含め他国から生じるリスクの悪影響を受けやすくしているとの不満が高まっている。試みに、各国内の経済格差を示す代表的な指標であるジニ係数を見ると、2024年には、2000年との比較で、中国・米国・ドイツの格差が大きく拡大している(第II-1-1-1図)。
第Ⅱ-1-1-1図 主要国のジニ係数の推移
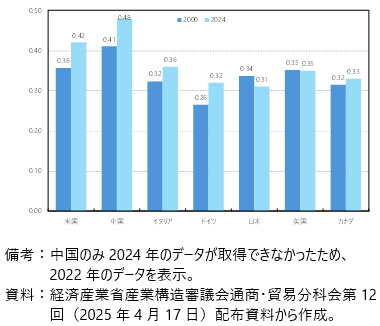
このような状況を踏まえ、WTOは、設立30年目となる2024年の世界貿易報告書で「貿易と包摂性」について取り上げた27。同報告書では、「包摂性」のコンセプトを、周縁化された国・地域、集団(少数者、脆弱な人々や労働者を含む)がグローバル市場に参加して裨益を受けることを妨げている障壁などを軽減することと位置付けた。その上で、①国・地域間の所得のばらつきと、②ある国・地域内での特定集団の損失という二つのレベルで、貿易と包摂性に関する検討を行っている。
①については、1990年代半ば以降、低・中所得国の貿易参加と所得格差の縮小速度には正の相関関係が見られ、全体として国・地域間の所得格差を狭めてきた一方、一部の国・地域は、貿易を持続的な成長の原動力として活用することができていないと指摘している。
第II-1-1-2表は、急成長を遂げた国・地域(LDC(後発開発途上国)卒業国やより高い所得階層になった国)は、急成長を遂げなかった国・地域(成長軌道から外れた国・地域やLDC)と比較すると、貿易への参加率が高まり、特定商品の輸出に依存する割合が低下してきたことなどを示している。その上で、途上国が貿易の利益を最大化するために、開放的な貿易政策を維持しつつ、適切な国内政策を実施する重要性を示している。こうした議論は、グローバルサウス諸国を始めとする新興国・途上国の、ルールベースの国際経済秩序に対する信認を維持していくためにも重要である。
第Ⅱ-1-1-2表 急成長を遂げた国・地域とそれ以外の国・地域との比較
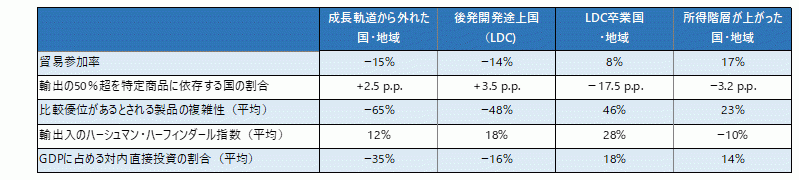
資料:WTO(2024)から作成。
②については、国全体としては開放的な貿易から恩恵を受けるものの、特定の集団(低技能労働者、女性など)、企業(中小零細企業など)や地域がその恩恵から取り残される傾向にあること、国内市場の様々な障壁がその傾向を強めていることを指摘している。例えば、中小企業や女性が所有する企業は貿易への参加の割合が相対的に低く、また、輸出企業では低技能労働者の雇用割合が低いことが示されている(第II-1-1-3図)。その上で、利益の再分配を目的とした制限的な貿易政策は失敗が多いため、公正な貿易政策と、労働市場・教育・再分配政策を含む補完的な国内政策が必要であることを指摘している。こうした議論は、各国内で、ルールベースの国際経済秩序に対する人々の支持を確保していくためにも重要である。
第Ⅱ-1-1-3図 国際貿易への参加割合(低技能労働者、女性、中小零細企業)
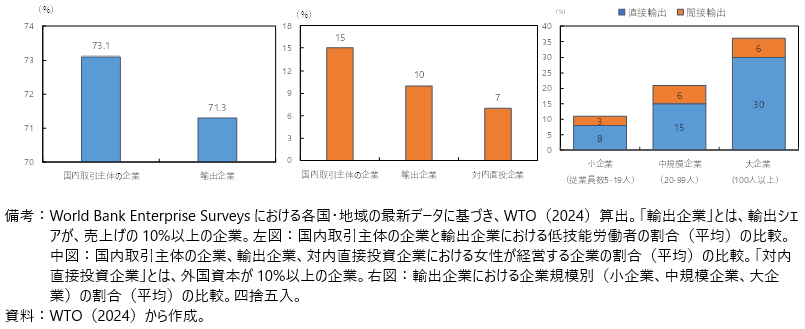
27 WTO (2024)
28 ある市場における集中度ないし寡占度を表す指標であり、ここでは輸出入の特定国への集中度を指している。
2. 中国ショックと輸入急増の影響
特に米国において、輸入急増の悪影響に関する学術的議論を巻き起こしたのが、「中国ショック」研究である。これは、2001年にWTOに加盟した中国からの輸入急増が各国労働者の雇用や賃金に与えた影響についての実証的な研究を指し、2010年代以降にその数が増加している。Autor et al.によれば、1980年代までは、比較的賃金差が少ない先進国間の貿易が主流だったこともあり、貿易が先進国の労働者の賃金や所得格差などに与える負の影響はほとんど観察されなかった。また、1990年代以降、米国で労働者の賃金や雇用に影響が見られ始めた時期にも、グローバル化や貿易の影響というより、技術革新等が主因だと考えられていた29。しかし、特に2010年代に入って、貿易が労働者市場に与える影響に関する研究が急速に増加した。その理由としてSasaharaは、中国ショックと呼ばれる中国からの輸入急増が注目を集めたことと、貿易の労働市場に対する影響に関する実証研究手法の発展を挙げている30。
経済学の伝統的な理論の中でも、貿易が国内の所得分配に与える影響は示唆されていた。「ストルパー・サミュエルソンの定理」31 は、二財間でのある財の「相対価格の上昇は、その価格を上昇させた財に集約的に用いられている生産要素(資本又は労働力)の実質的な収益を高めるが、もう一方の集約的に用いられていない生産要素の実質的な収益を低下させる」32ことを示した。これを労働者で考えると、貿易を行うことで、外国に比べて国内に多く存在する労働者グループの実質賃金は上昇し、そうでないグループの実質賃金は下落することを意味している。例えば、国内に高技能労働者が多い先進国は、途上国との貿易の結果、国内で高技能労働者の実質賃金が上昇し、低技能労働者の実質賃金が下落することになる33。Rodrickは、同定理が、貿易は特定の社会階層に対して相対的損失にとどまらず絶対的損失をもたらすことを示しており、それは移行期間の調整コストであるとか消費者物価の引下げ効果が上回るといった主張とは相容れないと指摘した34。
また、伝統的な貿易理論は基本的に、貿易の経済厚生や産業構造などに対する影響を分析する目的で構築されており、貿易が労働市場に与える影響には焦点が当たっていない。そのため、労働市場は完全競争的で常に完全雇用であり、離職は発生するが摩擦のない労働移動により全員が瞬時に同じ賃金で雇用されて、失業は発生しないという、実際の労働市場を考えると現実的でない仮定が置かれている35。この貿易と労働市場の関係に、上述の実証研究手法の発展を踏まえて光を当てたのは、労働経済学者であった。1990年代から2000年代にかけて、米国の財関連消費に占める中国製品の割合が上昇し、生産年齢人口に占める製造業の雇用割合が急速に減少した(第II-1-1-4図)。これに関し、Autor et al.は、中国からの輸入増によって、控えめに見積もっても、1990年~2000年の米国製造業の雇用減少の約16%、2000年~2007年の約26%が説明可能と分析した36。Acemoglu et al.は、1999年から2011年にかけて、中国からの輸入増により、米国の総雇用が200~240万人減少したと推計している37。他にも多くの研究が、中国からの輸入急増が米国の特定地域・産業の雇用や賃金に与えた負の影響を示した。一方で、経済全体への影響という観点では、中国産の中間財を輸入して生産を行う米国内産業に与えた好影響を示したWang et al.のように、雇用と実質賃金にプラスの影響を与えたと推計した研究がある38(第II-1-1-5表)。
第Ⅱ-1-1-4図 米国の財関連消費における中国の輸入浸透度と製造業雇用者数の割合
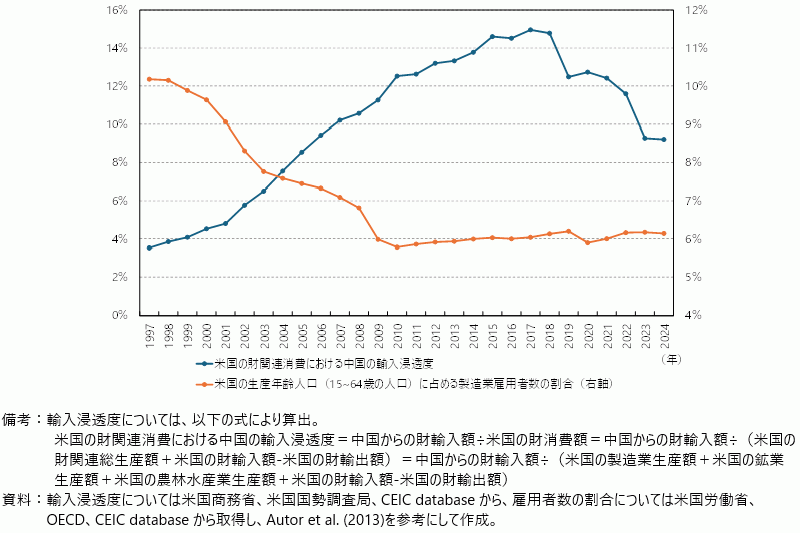
第Ⅱ-1-1-5表 中国ショックの主な研究
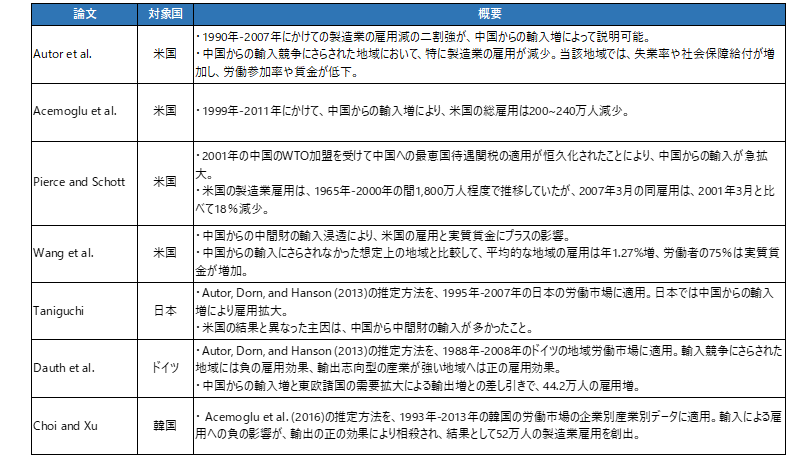
資料:各論文39から作成。
Sasaharaは、中国からの輸入急増の影響に各国で差異が生じる要因として、(1)労働市場の法制度や規範、(2)失業保険などの社会保障システム、(3)製造業の発展度合い及びそれが比較優位産業か否か、(4)グローバル・バリューチェーンへの統合度合い、すなわち貿易財が最終財か中間財か、(5)貿易収支、があり得ることを指摘している40。日本やドイツでは、米国に比べて中間財の輸入がより大きなシェアを占めており、国際的生産ネットワークを介して、中国と補完的な経済関係を築くことに成功していたと評価できるかもしれない(第II-1-1-6図)。
第Ⅱ-1-1-6図 中国の輸出に占める中間財のシェア
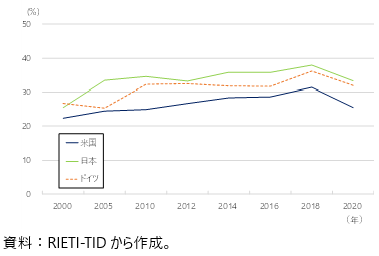
上記の五点のうち、特に(3)から(5)については、同じ国でも時間の経過に伴う産業構造の変化等によって影響が変わり得る可能性を示唆していることに留意が必要である。例えば、輸出品目類似度(Export Similarity Index)41を使って、中国と日本・ドイツ・韓国との輸出品目の類似度を見ると、2000年から2023年の間に、日本は28.7%から37.1%へ、ドイツは28.6%から44.7%へ、韓国は33.1%から38.3%へと上昇しており、いずれも中国との輸出品目の類似性が高まっている(第II-1-1-7図)。こうした産業構造の変化は、今後の中国からの輸出が各国の国内産業や雇用に及ぼす影響を変えていく可能性がある。
第Ⅱ-1-1-7図 中国と日本・ドイツ・韓国の輸出品目の類似度
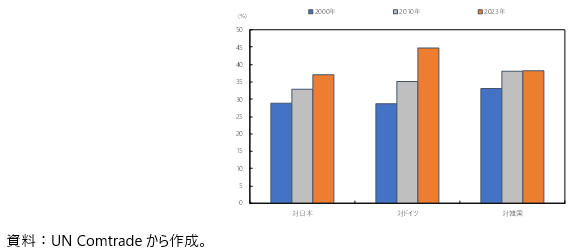
29 Autor et al. (2016)
30 Sasahara (2022)
31 スウェーデンの経済学者エリ・ヘクシャーとベルティル・オーリンによるヘクシャー・オーリン(HO)モデルから導かれる定理。
32 Feenstra (2015)
33 遠藤(2023)
34 Rodrik (2021a)
35 遠藤(2023)
36 Autor et al. (2013)
37 Acemoglu et al. (2016)
38 Wang et al. (2018)
39 Autor et al. (2013), Acemoglu et al. (2016), Pierce and Schott (2016), Wang et al. (2018), Taniguchi (2019), Dauth et al. (2014), Choi and Xu (2019).
40 Sasahara (2022)
41 2か国間の輸出品目の類似性を示す指標であり、値が100に近いほど輸出構造が似ていることを表す。計算は、①国ごとに輸出総額に占める各輸出品目のシェアを計算、②品目ごとにシェアの低い方の国の数値を抽出し、それを合計することで得られる。
3. 公正な貿易政策への支持
中国ショック研究は、他国からの輸入急増が、輸入品と直接的に競合する特定の地域・産業に悪影響を与え得ることを示した。同時に、実際の影響度は他の要因にも依存すること、一般的に経済全体としては貿易の恩恵が大きいことも示している。もとより、格差や雇用に影響を与える要因は貿易だけではない。むしろ一般的には、貿易や移民よりも技術革新や機械化、脱工業化、通常の企業の縮小・閉鎖の動きなどの方が、労働市場に大きな影響を与えるとされる42。内閣府政策統括官(経済財政分析担当)は、所得格差をもたらす主な要因として、(1)グローバル化、(2)技術進歩、(3)労働市場の制度・政策、(4)低い教育水準や訓練機会の不足等が指摘されているとした43。
しかしながら、グローバル化がもたらすショックは、しばしば文化や価値観、アイデンティティの側面と結び付き、保護主義的な貿易政策や大衆迎合的な政治運動への人々の支持につながりやすい44。Baldwinは、米国では、1980年代の自由放任主義による社会政策の縮小後に自動化、グローバル化、オフショアリングが起こったことで中間層が傷ついたという背景を説明した上で、中間層のプライドと結び付いた怒りが、経済的には問題を解決しない保護主義への政治的な支持につながっているとした45。
実際に、2024年から2025年春にかけて相次いだ主要国・地域内の選挙やその他の政治動向は、各国政治の不安定化を示唆している。インフレの高止まり、移民の増加や国内の経済格差に対する反発、過激な政治的主張が拡散しやすい傾向等を背景に、与党の敗北、過激な主張を行う政党の議席拡大、急激な政策転換などが見られた(第II-1-1-8表)。
第Ⅱ-1-1-8表 2024-25年の主要国・地域の選挙結果
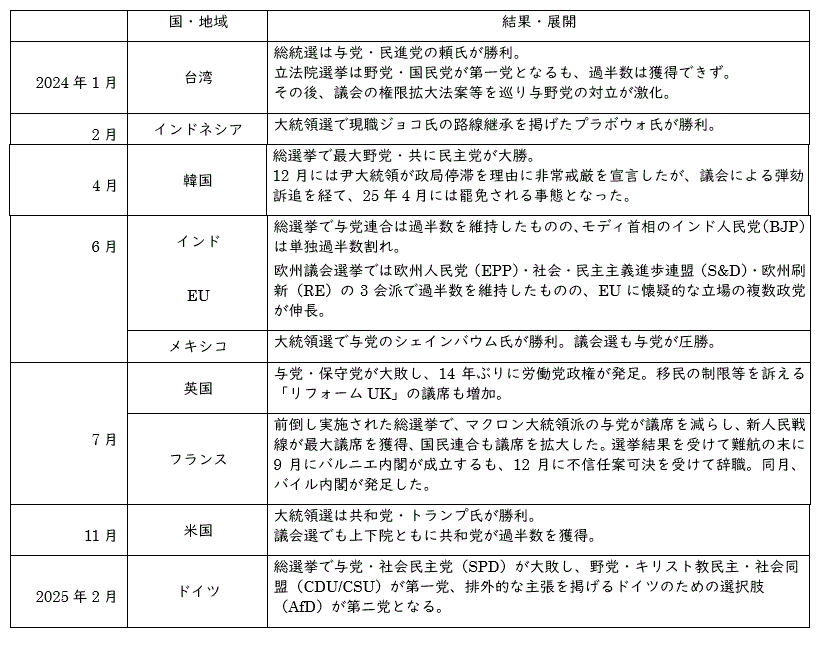
しかし、こうした政治の不安定化が、現時点で必ずしも各国・地域の保護主義的な貿易政策を強化する動きにつながっているわけではない。現時点ではほとんどの国・地域の政権が、これまでの国際貿易システムの維持・強化を擁護している。ただし、各国の具体的な政策実施において、保護主義的な措置や慣行が拡散しかねない状況にあることには留意が必要である。
格差の拡大に対して、予見可能で公正な貿易関係を損なうような保護主義的措置をとることは、最適な対応策にはなり得ない。遠藤は、国内での雇用喪失や賃金低下を抑制するために関税を含む制限的な貿易政策をとることは、効率的な政策選択ではない上に強い副作用があるとしている46。公正な貿易政策と補完的な国内政策が推奨される所以だが、民主主義国家においてそうした政策が採用されるためには、それを支持する人々の存在が不可欠である47。Sandelは、人々は消費者と生産者という二つのアイデンティティを持つが、能力主義とグローバル化によってその両方が傷ついた米国の人々の政治的不満に対しては、所得の再分配だけでなく労働の尊厳の回復を目指さなければ有効に対処できないと指摘した4849。
Rodrikは、「グローバルな経済には、それを統治する制度に乏しいという欠点があり、政府の力が強まれば保護主義や自給自足経済に傾き、市場の自由が強まれば社会的・政治的な支持を受けない不安定なものになるため、その絶妙なバランスが必要だ」と指摘した50。ルールベースの国際経済秩序が提供してきた予見可能性という貴重な価値を強化・再構築するためには、公正な貿易政策と補完的な国内政策の両方に関する人々の理解と支持を高めていくことが重要になる。
42 例えば、Nye (2025)
43 内閣府政策統括官(経済財政分析担当)(2017)
44 Rodrik (2021b)
45 Baldwin (2025)
46 遠藤(2023)
47 冨浦他(2013)は、日本でのアンケート調査により、特に都市部居住者、管理的職種、高学歴ないし高収入者が、また所得や年齢が上がるほど、輸入自由化を支持する傾向が強いことを明らかにした。
48 Sandel (2020)
49 例えば、第一次トランプ政権で米国通商代表を務めたロバート・ライトハイザーなどもこのような見方を共有している(Lighthizer (2023))。
50 Rodrik (2012)
4. 輸出主導成長と所得格差
中国ショック研究は中国からの輸入急増の影響に焦点を当てたが、包摂的な貿易という観点では、輸出国側で輸出主導成長がもたらす国内の所得分配への影響にも注意を払う必要がある。特に、中国を始めとして輸出主導で経済発展を遂げた新興国においては、一般的に輸出が経済成長や雇用拡大に良い影響を与える一方で、少なくとも輸出の直接的な利益は輸出産業に関連する地域・集団に多くもたらされるため、所得分配が偏る傾向がある。Dorn et al.によると、1970年~2014年における139か国のデータで見ると、貿易開放度の所得格差への影響は国ごとに異なるが、中国などの移行経済国では、貿易が開放されるほど、所得格差が拡大するという正の効果が見られている51。もちろん輸出もまた所得格差の一つの要因に過ぎないが、輸出の利益が国内の各種の制度的障壁によって均てんされず、そうした構造が維持されれば、輸出主導成長の時期を終えても包摂性が阻害されることになる。馬は、中国の所得格差拡大の主な原因は、政治及び社会制度(政党、戸籍制度や国有・非国有部門間格差等)によって国内市場が分断されていることにあると分析している52。結果として、社会経済的地位の高い、高学歴者、党員グループ、経営者や国有部門就業者、都市戸籍を有する者の多くが、中間所得層以上となっている。輸出主導成長がもたらす格差に対しては、公正な貿易政策を確実に実施するとともに、当該国の経済社会制度や産業発展の段階等も踏まえて、社会保障制度を含む様々な補完的政策を通じて包摂性を確保していくことが必要である。
第Ⅰ部第1章第2節及び同第5章第3節で触れたとおり、中国経済は不動産不況をきっかけに景気が低迷し、過少消費というマクロ経済の不均衡が顕在化している。こうした中、2025年3月の全国人民代表大会における「政府活動報告」では、内需拡大を重要項目に掲げて景気回復を目指す方針が示された。消費の押し上げによる内需拡大を最初の重要項目に掲げたことは、中国政府の課題認識を示している。しかし、構造的な内需不足の背景には、都市と農村を含む国内の所得格差や社会保障制度の未整備、若年層を始めとする高い失業率、不動産の資産効果への期待低下等があるとされ、短期的な解決は容易ではない53。
WTOは、貿易は経済成長と貧困削減に重要な役割を果たし得るが、特定の国・地域や人々を貿易の恩恵から取り残さないためには、開放的な貿易を補完する国内政策(社会保障制度など)と国際協力を促進する包括的な戦略が必要であるとした54。Engel et al.も、世界貿易は経済成長と貧困削減の主要な原動力になってきたが、貿易はしばしば社会の中に異なる損益をもたらし、またその効果は想定以上に継続的であることから、各国政府が貿易のもたらす分配への影響についての理解を一層深め、貿易の利益を幅広く共有するためのより包摂的な政策を実施することが重要と指摘している55。今後、各国政府においては、各国の固有の事情も踏まえつつ、公正な貿易政策とそれを補完する国内政策を充実することが、ますます求められるだろう。
51 Dorn et al. (2021)
52 馬(2021)
53 梶谷・高口(2025)、柯(2014)
54 WTO(2024)
55 Engel et al. (2021)