第2節 デジタル化が変えるサービス越境取引
デジタル技術の急速な発展とグローバルな普及により、世界の貿易投資構造を見る際に、財とサービスを統合的に分析する必要性が高まっている。従来、貿易関係を分析する際にはもっぱら財貿易に焦点が当たってきた。その理由は主に、①サービス貿易が財貿易に比べて小規模であったこと、②伝統的なサービス貿易は「観光」、「運輸」等の個別性の高いサービスが中心であり、財とサービスを統合的に分析する必要性が低かったこと、③詳細な品目分類に基づくデータによって把握できる財貿易に対して、サービス貿易は統計上の実態把握が困難だったことである。
しかし、近年は財貿易の拡大が失速している一方で、サービス貿易は増加を続けている。Baldwinはその主な要因として、「第三のアンバンドリング」を提起している56。すなわち、デジタル技術の進化によりオンラインサービス等が普及し、一部のサービスや知識の提供が、国境を超え、物理的な場所の制約を乗り越えて行うことが可能になったということである。これは、従来サービス取引の特徴と言われた「生産と消費の同時性」や「非在庫性」等の側面が、少なくとも一部のサービス貿易では変質していることも意味する。
こうした変化を背景に、Baldwin et al.の言う「モダン・サービス」(後述)の中でも、とりわけデジタル関連サービスの貿易が急速に増加している57。デジタル関連サービスには、知的財産権等使用料、通信・コンピュータ・情報サービス、専門業務サービス58が含まれるが、これらはサービス自体として貿易取引が増えているだけでなく、モノの製造・提供に対する中間投入として重要な付加価値の源泉となっている。デジタル関連サービスの拡大が、財とサービスの貿易投資を統合的に分析する必要性を高めているといえる。しかし、上記の統計制約等の背景もあり、デジタル関連サービス貿易の全体像は必ずしも十分明らかになっていない。
本節では、まず世界のサービス貿易の動向と類型を確認し、国際収支統計のサービス収支に表れるサービス貿易だけでなく、海外拠点を通じたサービス提供(モード3)やサービスの付加価値貿易(モード5)を含めて、モノとサービスの越境取引を統合的に捉える視点を示す。この統合的な視点は、第Ⅱ部第3章第3節で我が国のデジタル及びサービス貿易を分析する際にも活用する。その上で、世界と主要国・地域のサービス貿易の現状・特徴を整理し、世界のデジタル関連サービス貿易の現状について、利用可能なデータから可能な限りの接近を試みる。最後に、デジタル経済化に対応する政策課題として、DFFT(信頼性のある自由なデータ流通)とデータセキュリティ・サイバーセキュリティを巡る取組の状況を概観する。
56 Baldwin (2016)
57 Baldwin et al. (2024)
58 本稿では、国際収支統計での「その他業務サービス」を「専門業務サービス」と呼称している。この中には、研究開発サービス、専門・経営コンサルティングサービス、技術・貿易関連・その他業務サービスが含まれる。
1. サービス貿易の成長
世界のサービス貿易は、過去約20年の間に財貿易よりも高い成長率で伸びている(第II-1-2-1図)。2005年時点と比べると、2023年時点の財貿易は2.4倍程度であるのに対して、サービス貿易は約2.9倍となっている。こうしたサービス貿易の拡大ペースは、コロナ禍による旅行を中心とした対面型サービスの大幅な落ち込みにもかかわらず、財貿易を上回る速さとなっている。
第Ⅱ-1-2-1図 世界貿易額の推移
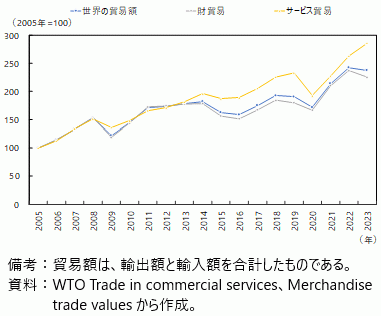
輸出入別に金額の上位20か国をリストアップすると、輸出入ともに米国や英国、EU諸国など先進国の構成比が高いことが分かる(第II-1-2-2表)。また、アイルランドやオランダ、シンガポールといったGDP規模がそれほど大きくない国が上位に入っている点も、財貿易と比べた時の違いとして挙げられる。年平均の成長率でみても、世界全体が+6.0%であるのに対し、アイルランドとシンガポールは、+10%程度の高い成長率を示している。
第Ⅱ-1-2-2表 世界のサービス貿易上位20か国(2023年)
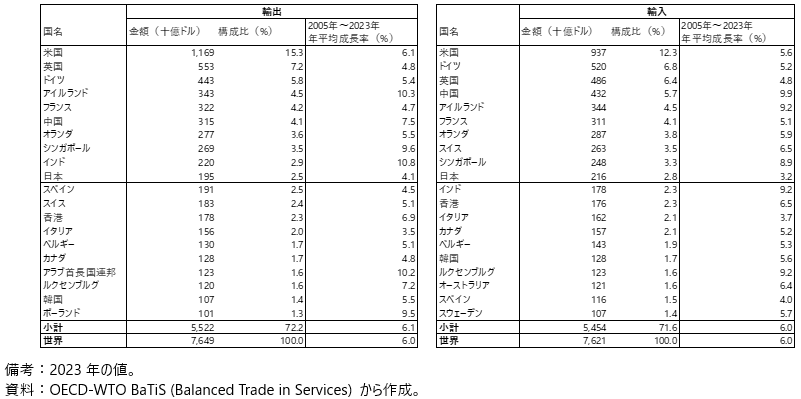
上位10か国の輸出シェアの推移を見ると、米国は15%前後の輸出シェアを維持している(第II-1-2-3図)。この間、アイルランド、シンガポール、インドの輸出シェアが傾向的に上昇している。
第Ⅱ-1-2-3図 サービス輸出上位10か国のシェア推移
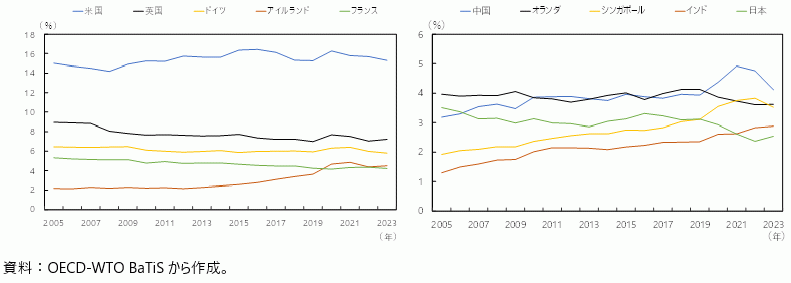
輸入シェアについても、輸出と同様の傾向が見られる(第II-1-2-4図)。すなわち、世界最大の輸入国である米国のシェアがおおむね横ばいで推移する中で、アイルランドやシンガポールなどのシェアが傾向的に上昇している。アイルランドとシンガポールが輸出と輸入の両方でシェアを拡大しているのは、デジタル関連の越境取引の変化によるものである。この点は、本節第3項で詳述する。
第Ⅱ-1-2-4図 サービス輸入上位10か国のシェア推移
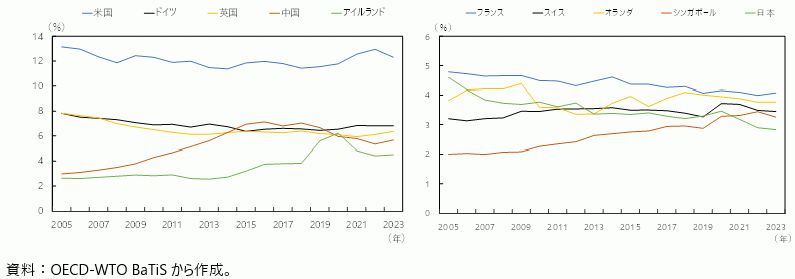
続いて、サービスの分野別の構成比を見ると、2005年から2023年にかけて、旅行、輸送といったサービスの割合が低下している一方、専門業務サービスや通信・コンピュータ・情報サービスの割合が増加していることが見て取れる(第II-1-2-5図)。この背景には、デジタル関連の貿易拡大が存在するが、この点は本節第4項で詳述する。
第Ⅱ-1-2-5図 世界のサービス貿易輸出構成の比較(項目別)
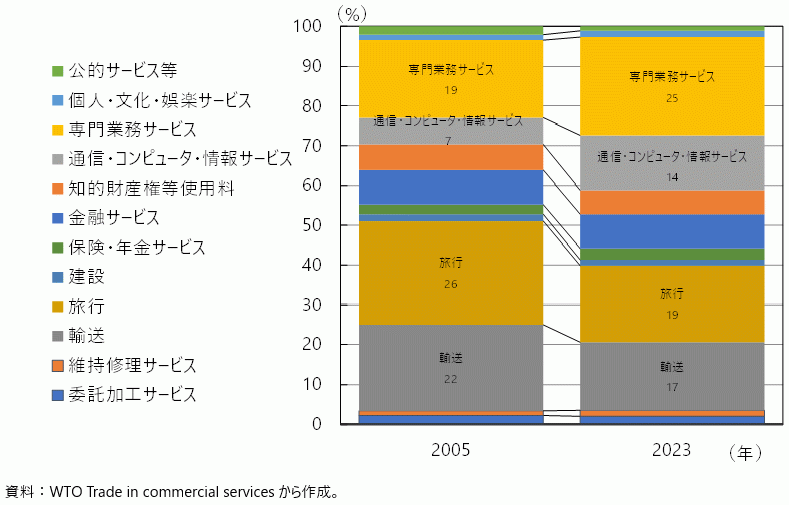
2. サービス貿易の類型
サービス貿易が何を指すのかについて、国際収支統計のサービス収支と、WTO・GATS(サービス貿易に関する一般協定)で定義されたサービス貿易の四つのモードでは差異がある。最も大きな違いとして、GATSでモード3とされる、ある国のサービス提供者が他国に設立した拠点を通じて行うサービス提供は、国際収支統計上はサービス収支に計上されない。国際収支統計では、金融収支(現地法人への対外直接投資等)や第一次所得収支(直接投資に対する配当等)に該当する場合のみ計上される。
加えて、近年、モノの製造・提供の過程でサービスが重要な付加価値投入となるケースが増えていることから、OECDや欧州議会は、サービス貿易のモード5(付加価値貿易)という概念を提示している5960。これは、国際収支統計上は財の貿易収支の内数となるため、サービスの付加価値を確認するためにはOECDが提供するTiVA等のデータを見る必要がある。サービス貿易の全体像を理解する上では、こうした異なる類型を統合的に理解する必要がある。
ここでは、近年のデジタル化によるサービス貿易の変容を念頭に置きつつ、サービス貿易の類型を整理する。GATSの四つのモードとモード5の分類の概要を第II-1-2-6表に示した。
第Ⅱ-1-2-6表 サービスの提供形態に基づくサービス貿易の分類
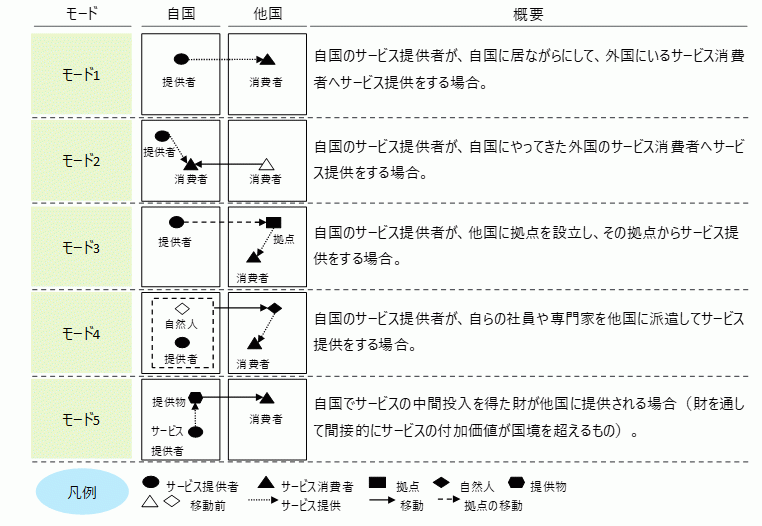
資料:外務省「サービス貿易の4態様」61、萩野(2022)から作成。
モード1は、サービスが国境を越えて取引されるが、提供者・消費者のいずれも物理的に移動しない形態である。クラウドサービス、ソフトウェア開発、オンライン金融取引、遠隔医療などがこれに該当する。デジタル化の進展により、このモードは近年急速に増加しており、特にデジタル関連サービスの多くはこのモードに分類される。例えば、伝統的にあまりサービス貿易の対象とならなかった教育分野でも、オンライン学習プラットフォームが急成長し、従来は対面授業が必須だった分野でモード1によるサービス提供が可能になっている。
モード2は、消費者が海外に移動して現地でサービスを受ける形態であり、旅行などが該当する。このモードは物理的な移動を伴うため、デジタル化による影響は限定的であると考えられる。しかし、バーチャルツアーや遠隔医療の進展により、一部のモード2のサービスがモード1へと移行しつつある。例えば、従来は物理的に病院のある場所でしか受診できなかった専門的な医療診断が、オンライン診療によって国境を越えて提供されるようになっている。
モード3は、企業が外国に拠点を設立し、現地市場でサービスを提供する形態を指す。外資系金融機関の現地支店設立や、国際法律事務所の海外オフィス設立がこれに該当する。デジタル化はモード3に対して、両面の影響をもたらしていると考えられる。一方では、クラウドコンピューティングやフィンテックの発展により、物理的な拠点を持たずともサービス提供が可能になっている。例えば、デジタル銀行は、従来の金融機関のように物理的な支店を設置することなく、モード1でグローバルに事業を展開できる可能性がある。一方で、デジタル化の進展がモード3を選択させるケースもある。例えば、各国のデータローカライゼーション(越境移転規制)62により、クラウド企業が各国にデータセンターを設置する必要性が高まっている。また、一部の多国籍企業は、リモートワークの普及に伴い、各地域での事業運営を最適化するため、分散型の拠点戦略を採用している。
モード4は、サービス提供者(個人)が外国へ移動し、現地でサービスを提供する形態を指す。例えば、海外派遣のITエンジニアや国際コンサルタントがこれに該当する。しかし、近年のリモートワークの普及により、モード4で提供されていた一部のサービスがモード1へと移行する可能性が高まっている。例えば、ソフトウェア開発やコンサルティング業務は、従来はサービス提供者が現地に赴く必要があったが、現在ではオンラインツールを活用し、物理的な移動なしに提供するケースが増加していると見られる。
モード5(付加価値貿易、Value-Added Trade)は、従来の四つのモードとは異なり、財に対する中間投入として組み込まれた形で取引されるサービスを指す。例えば自動車産業では、輸出前の段階で車両の開発生産・輸出のために投入される、研究開発、設計、輸送、金融、広告販売等のサービスの付加価値が大きな割合を占めている。こうした財の製造・提供に対して中間投入されるサービスの国際取引が「モード5の貿易」と呼ばれる。デジタル化の進展により、モード5の貿易は急速に拡大しており、設計・エンジニアリング、R&D(研究開発)、IoTによる生産最適化、財に含まれるソフトウェア群などが典型例として挙げられる。
59 Cadestin and Miroudot (2020)
60 Foltea (2018)
61 外務省「サービス貿易の4態様」、2019年3月4日、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/service/gats_5.html![]() (2025年6月5日閲覧)。
(2025年6月5日閲覧)。
62 EUのGDPR(個人情報(データ)の保護を目的とした規則であり、欧州経済領域域内で取得された「氏名」や「メールアドレス」などの個人データを域外に移転することを原則禁止している。)やインドのデータ保護法等を指す。
3. モノとサービスの越境取引の規模感
上述のようなサービスの5モードと、製造業の付加価値を全て考慮に入れたモノとサービスの越境取引は、どのような規模感になっているだろうか。Cernatは、世界全体での、製造付加価値の貿易とサービスの5モードの貿易の、それぞれの割合を試算している63。これによると、製造付加価値の貿易は37%、サービスの5モードの貿易は63%と、サービス付加価値の貿易の方が大きくなっている(第II-1-2-7図)。国際収支統計では、国境を超える財又はサービスの取引価値を集計しており、その観点では、世界のサービス貿易は財貿易のおおむね30%前後64にとどまる。しかし、サービスの特性を踏まえてモード3やモード5を含め、付加価値ベースで見ることにより、製造付加価値よりもサービス付加価値の貿易の方が大きなシェアを占めることが分かる。サービスの内訳を見ると、モード3が最も大きく、モード5はそれに次ぐ大きさを占めている。この推計からも、モノとサービスの越境取引の全体像を把握するためには、国際収支統計で捕捉されるモード1、2、4以外の取引も考慮することが重要であると分かる。
第Ⅱ-1-2-7図 製造付加価値輸出とモード別サービス輸出の構成
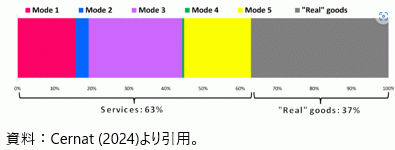
モード別に時系列の変化を確認するため、利用可能なデータがないモード5を除く世界のモード別サービス輸出額について、WTOが提供するTISMOSのデータで見る。これによると、2005年以降、世界のサービス輸出が趨勢的に増加する中で、モード2とモード4が伸び悩んでいる一方、モード1とモード3が特に増加傾向にある(第II-1-2-8図)。いずれも、デジタル化に伴って増加したサービス貿易が主因と考えられる。
第Ⅱ-1-2-8図 世界のモード別サービス輸出の推移
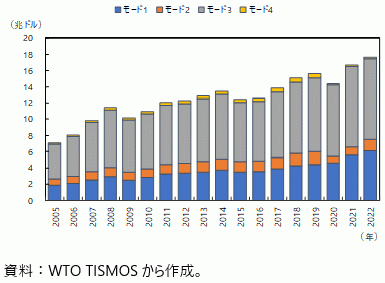
63 Cernat (2024)
64 WTO Statsに基づく。WTO Statsでは、財貿易を各国の税関記録により(貿易統計ベース)、サービス貿易を各国の国際収支統計により、それぞれ集計している。
4. モダン・サービスが主導するサービス貿易の拡大
Baldwin et al.は、伝統的な輸送と旅行以外の全ての商業的サービスを「モダン・サービス」と名付けている65。輸送や旅行という伝統的なサービスでは、サービス提供が対面で行われるという特徴があるが、モダン・サービスは、デジタルツール等を介して非対面でサービス提供が行われ得るという特徴がある。モダン・サービスの中で主要なサービスは、金融サービス、知的財産権等使用料、通信・コンピュータ・情報サービス、専門業務サービスである。ここでは、この四つのサービスを中心に、Baldwin et al.の言うモダン・サービスについて検討する。
まず、貿易額の推移を見ると、モダン・サービスは、サービス貿易の中でもコロナ禍の時期を含めてほぼ一貫して大きく伸びている(第II-1-2-9図)。内訳を見ると、上記4サービスはいずれも2005年比で増加しており、とりわけ通信・コンピュータ・情報サービスと専門業務サービスの伸びが大きい。
第Ⅱ-1-2-9図 モダン・サービスの貿易
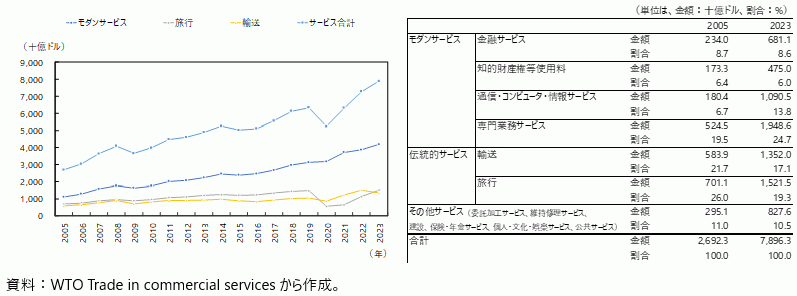
次に、サービス分類ごとにモード別の輸出額を見る(第II-1-2-10表)。これによると、「専門業務サービス」、「保険・金融サービス」、「通信・コンピュータ・情報及び視聴覚サービス」はいずれも、モード3が構成の過半を占めているが、モード1も比較的大きな割合を占めている。「知的財産権等使用料」は、その特性上、専らモード1になっている。
第Ⅱ-1-2-10表 世界におけるサービス・モード別の輸出金額(2022年)
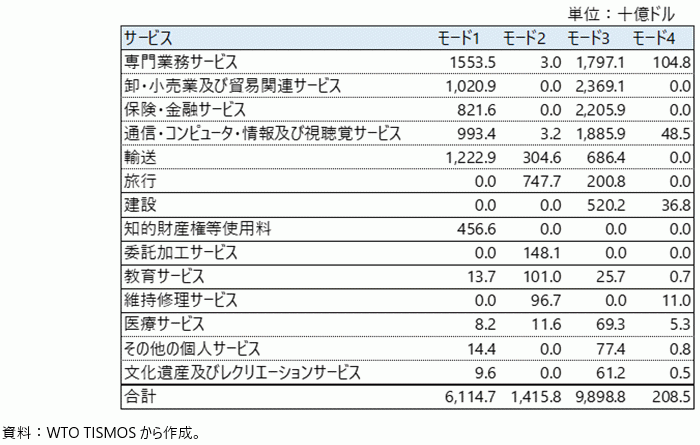
Baldwin et al.は、今後もこうしたモダン・サービスを中心としたサービスの拡大が続く可能性が高いと指摘している66。その論拠は以下のとおりである。
第一に、サービス貿易の障壁は財貿易の障壁よりも大きいが、その障壁は低下傾向にあることを挙げている。実際に、第II-1-2-11図が示すとおり、サービス貿易のコストは低下してきている。これには、各国の規制緩和、サービス分野を含むEPA等の進展、企業のグローバル戦略の変化等が影響を与えている。例えば、FTA/EPAの中で、金融、IT、教育などのサービス貿易の自由化が進められている例は多く、企業が国際市場でサービスを提供しやすくなっている。
第Ⅱ-1-2-11図 貿易コスト指標の推移
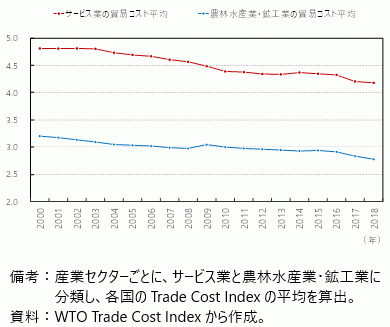
第二に、デジタル技術の発展と普及がサービス貿易の障壁を減少させていくことが挙げられている。国境を越えたデータ流通量は拡大を続けており、ITU(国際電気通信連合)によると、世界の2022年の越境データ流通量は1,229Tb/s(テラビット毎秒)で前年比25.4%増と大幅に増加し、2017年の292Tb/sと比較すると4.2倍に拡大した(第II-1-2-12図)。
第Ⅱ-1-2-12図 世界の越境データ流通量
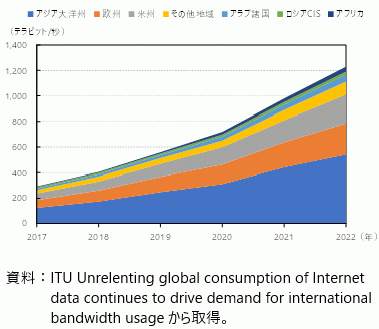
OECDの研究では、こうしたデジタルへの接続度67の上昇は国際貿易を増加させることが示されている(第II-1-2-13図)。
第Ⅱ-1-2-13図 デジタルの接続性が1%向上した時の貿易の増加率
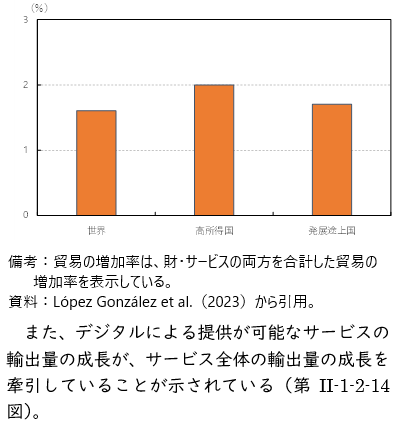
また、デジタルによる提供が可能なサービスの輸出量の成長が、サービス全体の輸出量の成長を牽引していることが示されている(第II-1-2-14図)。
第Ⅱ-1-2-14図 デジタルによる提供が可能なサービス貿易輸出額とサービス貿易全体の輸出額
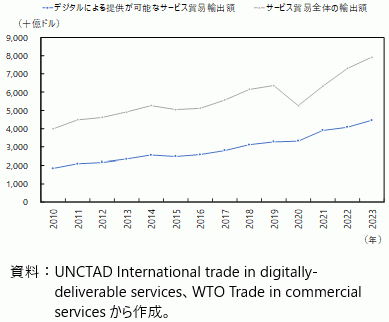
第三に、モダン・サービスの貿易拡大において、輸出能力と輸入需要の地理的制約が少ない点は、従来の財貿易と異なる重要な特徴である。財貿易では、生産能力や物流ネットワークが輸出量を決定する主要な要因となる。例えば、自動車や電子機器の輸出では、工場の生産能力や輸送手段の確保が不可欠であり、物理的な制約が貿易量を左右する。一方で、とりわけモダン・サービスの貿易は、デジタル技術の活用により、こうした物理的制約を受けないものが増えている。また、輸入需要に関しても、デジタル化の進展により、企業は地理的な制約から解放されつつある。伝統的な財貿易では、物流コストや通関手続の影響を受け、特定の地域市場への依存が避けられなかった。しかし、デジタル化されたモダン・サービスでは、オンライン広告やデータ駆動型マーケティング、AIによるターゲティング技術を駆使することで、世界中の顧客に対して迅速にアプローチできるようになっている。例えば、デジタルコンテンツ企業は、物理的な拠点や流通網に依存せず、世界各国で同時にサービスを提供することができる結果、サービスの供給者と需要者の間の地理的制約が低減し、モダン・サービスの貿易がかつてないスピードで拡大している。したがって、モダン・サービスの貿易は、財貿易とは異なり、輸出能力や輸入需要の地理的制約が少なく、デジタル技術の発展によってグローバルに展開しやすいという独自の強みを持つ。
第四に、モダン・サービスの拡大には、途上国に豊富に存在する安価な労働力を、物理的移動なしに活用できるという特質も関係している。実際に、労働コストが先進国に比べて低い一部の新興国では、国際的なサービス業務のアウトソーシングが進んでいる。例えば、インドのIT産業は、欧米企業向けのソフトウェア開発やカスタマーサポートを提供し、モード1やモード4を通じたサービス貿易を拡大させている。また、フィリピンのBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)産業は、コールセンター業務やバックオフィス業務を国際市場向けに提供することで、サービス貿易の成長を支えている。このように、途上国の安価な労働力の活用可能性が高まることは、先進国の企業がサービスを越境で外部委託しやすくなる要因となり、結果としてサービス貿易の拡大を促進している。
65 Baldwin et al. (2024)
66 Baldwin et al. (2024)
67 インターネットの普及率を代理変数として用いている。
5. 世界のデジタル関連サービス貿易の動向
サービス貿易の拡大を牽引するモダン・サービスの中でも、米国の大手デジタル関連企業を中心に急速に拡大してきたデジタル関連サービスが注目を集めている。デジタル関連分野では、高度な知識・技術を活用したサービスが国境を越えて取引されていることに加えて、クラウドサービスやデータ管理の越境提供が主流となりつつある。こうした変化により、グローバルなサービス貿易の流れは、従来の財・サービス貿易の構造とは異なる複雑なパターンを形成している。
そこで本項では、以下で見るデジタル関連サービスの定義を踏まえ、知的財産権等使用料、通信・コンピュータ・情報サービス、専門業務サービスの3分野に焦点を当てて、グローバルなサービス貿易の構造とその変化を分析する。また、これらのサービス貿易の流れを主導する主要国・地域の特徴を明らかにし、デジタル技術の発展がサービス貿易の流れにどのような影響を与えているのかを検討する。
(1) 国際比較におけるデジタル関連貿易の定義
まず、本項で扱うデジタル関連貿易の範囲について整理を行う。我が国の「デジタル貿易赤字」に関する議論では、松瀬他の定義に従い、知的財産権等使用料のうち著作権等使用料、通信・コンピュータ・情報サービス、専門業務サービスのうち専門・経営コンサルティングサービスを、デジタル関連貿易として扱うことが多い6869。しかし、本項での国際比較に利用するBaTiS統計70では、知的財産権等使用料の内訳が利用できないため、本項では、松瀬他よりもやや範囲を広げて、産業財産権等使用料も含むこととする(第II-1-2-15表)。産業財産権等使用料には、自動車の海外生産に伴う親子会社間の工業知財権の使用料など、デジタルとは必ずしも関係がない取引も含まれている点には留意が必要である。なお、第Ⅱ部第3章での我が国のデジタル関連貿易に関する分析は、松瀬他の定義に従う。
第Ⅱ-1-2-15表 デジタル関連貿易の定義
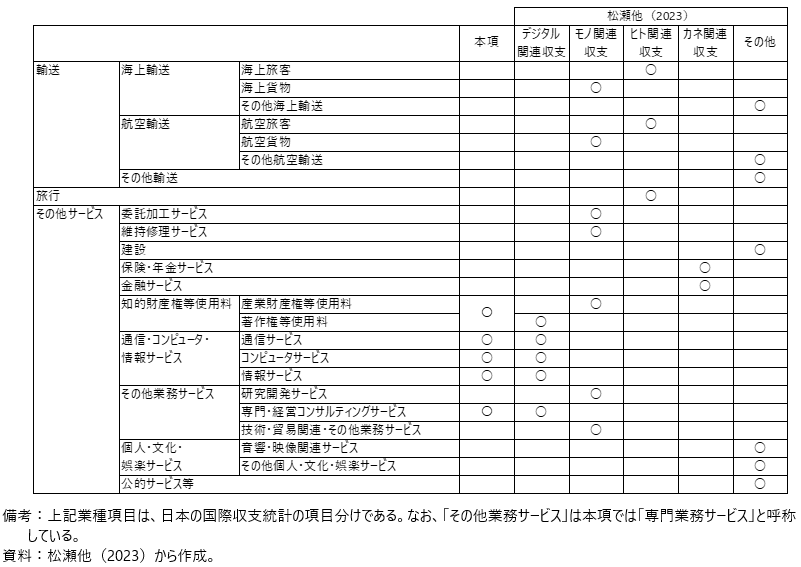
(2) デジタル関連のサービス貿易輸出
2023年のデジタル関連貿易収支を見ると、米国、インド、アイルランド、英国は黒字を記録している(第II-1-2-16図)。しかし、各国の輸出入の構成は大きく異なっている。米国は、知的財産権等使用料と専門・経営コンサルティングサービスで大幅な黒字を計上している一方、通信・コンピュータ・情報サービスでは赤字を抱えている。 これは、米国が、ソフトウェア等によるサービスの直接輸出よりも、知的財産権等使用料や高度な専門サービスの提供を通じて利益を上げているためと考えられる。一方で、デジタル輸出総額が大きいアイルランドは、通信・コンピュータ・情報サービスで黒字を維持しているものの、知的財産権等使用料と専門・経営コンサルティングサービスでは大幅な赤字となっている。 これは、アイルランドが欧州におけるITサービスのハブとして、多くの外資系企業のデータセンターや拠点を有していることに起因すると考えられる。これらの企業の活動の中心が通信・コンピュータ・情報サービスの提供であるため、この分野では黒字を確保しているが、多くの企業が知的財産権等使用料やコンサルティングサービスの対価を海外へ支払っており、その結果、これらの分野では赤字となっている。さらに、日本の主要なデジタル貿易赤字先の一つであるシンガポールも、世界全体とのデジタル関連貿易収支では赤字を記録している。シンガポールはアジアのITハブとして多くの外資系企業を誘致しているが、それらの企業が海外の本社に支払う知的財産権等使用料やその他のデジタル関連サービス費用が大きく、結果として全体の収支がマイナスとなっていると考えられる。
第Ⅱ-1-2-16図 各国別デジタル関連貿易収支額
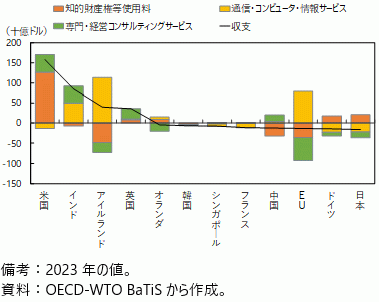
さらに、GDP比で見ると各国の特徴点がより明確になる(第II-1-2-17図)。まず、アイルランドは、デジタル貿易の対GDP比が他国と比べて非常に高く、デジタル関連貿易の中で特異な位置を占めていることが分かる。また、インドはGDPに対してデジタル貿易黒字が大きいことが読み取れる。一方、デジタル関連貿易の収支額で最大の赤字国であった日本は、GDP比で見ると、ドイツ・フランス・オランダ・韓国といった他の赤字国のGDP比と大きく変わらないことが読み取れる71。他の先進国と比較して、日本のデジタル貿易赤字は、経済規模との対比で著しく大きいわけではないと考えられる。シンガポールの赤字額は、GDP比では非常に大きくなっている。
第Ⅱ-1-2-17図 各国別デジタル関連貿易収支の対GDP比
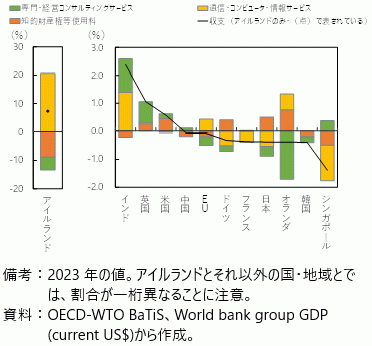
以下では、サービス項目別にグローバルなデジタル関連貿易の構造の特徴点を整理していく。
① 知的財産権等使用料
知的財産権等使用料の輸出額は、米国が世界の約4割を占めており、主要11か国で世界の輸出シェアの約8割を占める(第II-1-2-18図)。米国以外では、英国、ドイツ、アイルランド、オランダといった国の構成比が大きくなっている72。
第Ⅱ-1-2-18図 知的財産権等使用料の各国別輸出額推移
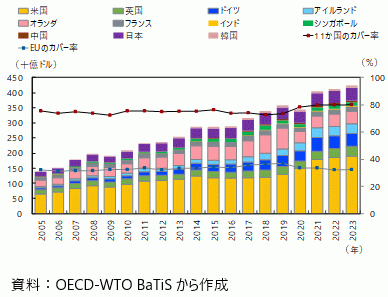
知的財産権等使用料の収支の特徴は、米国に次いで、アイルランドがハブのような役割を果たしていることである(第II-1-2-19図)。アイルランドは、米国から巨額の輸入をしている一方で、EU諸国やシンガポール、日本向けに輸出をしている。以下では、米国とアイルランドに注目して、その貿易の実態について整理する。
第Ⅱ-1-2-19図 知的財産権等使用料のフロー図
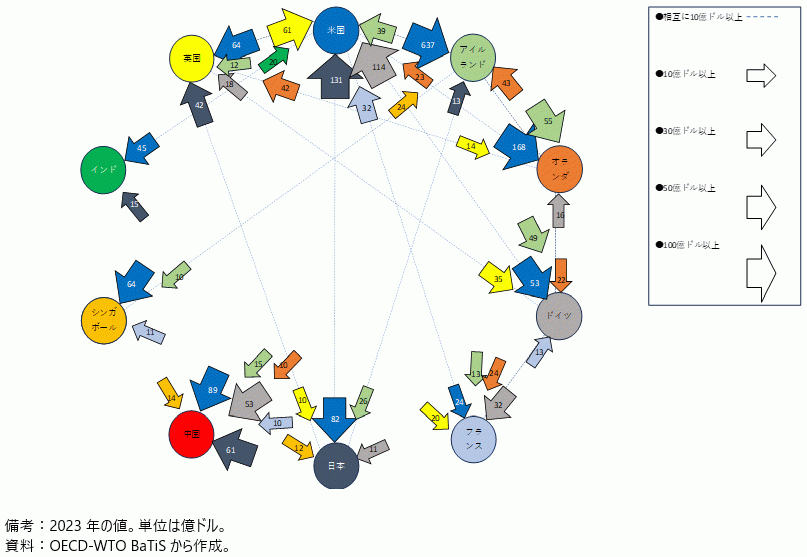
まず、輸出額が最大である米国における知的財産権等使用料輸出の内訳を見てみると、研究開発に関連するIP(知的財産権)が約5割を占め、ソフトウェアの複製・配布に関連するIPが約3割を占めている(第II-1-2-20図)。
第Ⅱ-1-2-20図 米国の知的財産権等使用料輸出の内訳
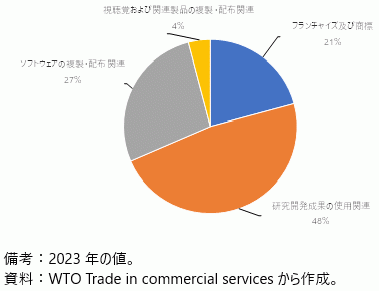
米国の知的財産権等使用料の輸出先を見ると、アイルランドへの輸出が2014年頃に増え、2019年から更に急速に拡大していることが読み取れる(第II-1-2-21図)。背景としては、米国の大手デジタル関連企業がアイルランドに進出していることが挙げられる。特に、Google、Apple、Microsoft、Facebook(Meta)などのテクノロジー企業は、アイルランドに欧州の拠点を設立し、欧州全域への事業展開を進めている。これらの企業は、アイルランドを拠点とすることで、EU市場へのアクセスを確保すると同時に、同国の税制優遇措置を活用してグローバルな利益管理を最適化している。背景には、アイルランドは多国籍企業向けの法人税率を低く抑えており、各国税制の中でアイルランドがIPを活用した利益移転のハブとして利用されてきた実態もある73。
具体的なIPの越境取引のスキームは複雑であり、データから把握することは容易ではないが、以下のような取引が示唆されている。まず、ECB(欧州中央銀行)によれば、アイルランド国内の多国籍企業グループ会社は、自らの非建設投資の中で国外親会社等からソフトウェア等の所有権を購入しているとみられ、これは統計上、研究開発サービスの輸入と総固定資本形成のうちIP製品投資として計上されるという74。また、米国企業がIPの使用権のみをアイルランドの現地法人に付与するケースもあり得るだろう。これにより、アイルランドの現地法人が米国本社からソフトウェアや特許技術の使用権を購入する形で知的財産権等使用料の支払いが拡大していると考えられる。
第Ⅱ-1-2-21図 米国の知的財産権等使用料の輸出先
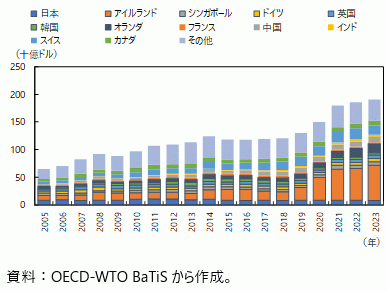
いずれのケースでも、アイルランドから第三国に対しては、デジタル関連サービスを提供することで、サービスの輸出として計上されるという構造になると考えられる。アイルランドの知的財産権等使用料の輸出が大きい理由として、米国企業から何らかの形で提供されたIP又はその使用権を利用して、他国から使用料を集めていることが示唆される。
② 通信・コンピュータ・情報サービス
通信・コンピュータ・情報サービスは、主要11か国で世界における輸出シェアの約7割を占める。特にシェアの大きい国は、アイルランド、インド、中国、米国である。また、通信・コンピュータ・情報サービス輸出に占めるEUのシェアは約5割となっており、4割弱の知的財産権等使用料及び専門・経営コンサルティングサービスに比べ、その割合は高くなっている(第II-1-2-22図)。
第Ⅱ-1-2-22図 通信・コンピュータ・情報サービスの国別輸出額推移
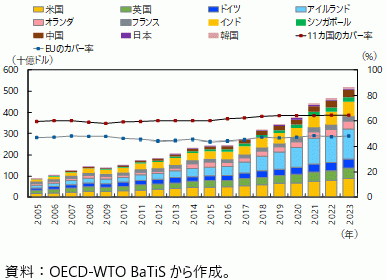
通信・コンピュータ・情報サービスの内訳は、コンピュータサービスが輸出額の約8割と大半を占めている。アイルランドや米国を個別に見ても同様に、コンピュータサービスのシェアが最も大きい(第II-1-2-23図)。
第Ⅱ-1-2-23図 通信・コンピュータ・情報サービス輸出額内訳(2023年)
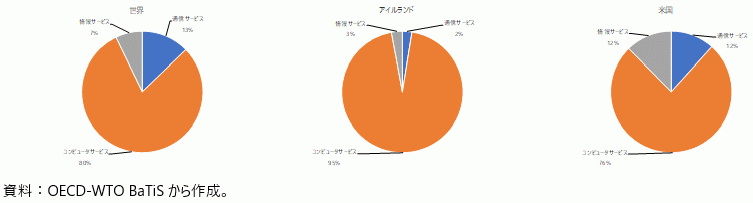
通信・コンピュータ・情報サービスの大部分を占めるコンピュータサービスの各国別輸出額を見ていくと、特にアイルランドの寄与度が高く、2015年頃より急激にシェアを拡大している。アイルランドがシェアを拡大している要因として、法人税率の低さなどを背景に、AppleやGoogleといった世界のデジタル関連大手企業がアイルランドに拠点を構え、ソフトウェアの開発や販売を行い、輸出していることが考えられる75(第II-1-2-24図)。
第Ⅱ-1-2-24図 コンピュータサービスの国別輸出額推移
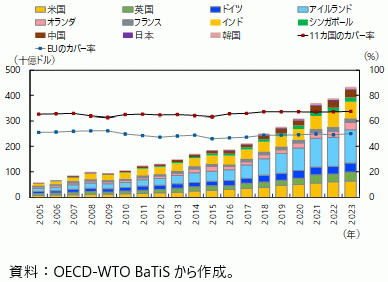
第II-1-2-25図では、通信・コンピュータ・情報サービスの貿易の流れを示している。知的財産権等使用料と比べて、欧米諸国だけでなくインドや中国も、欧米諸国と結ばれている。米国・インド間や、米国・アイルランド間の取引が特に大きい。これは、インドがアウトソーシング等のIT関連サービス大国であることが影響している。日本は輸入に偏っており、点線で結ばれる国の数が最も少ない。
第Ⅱ-1-2-25図 通信・コンピュータ・情報サービスのフロー図
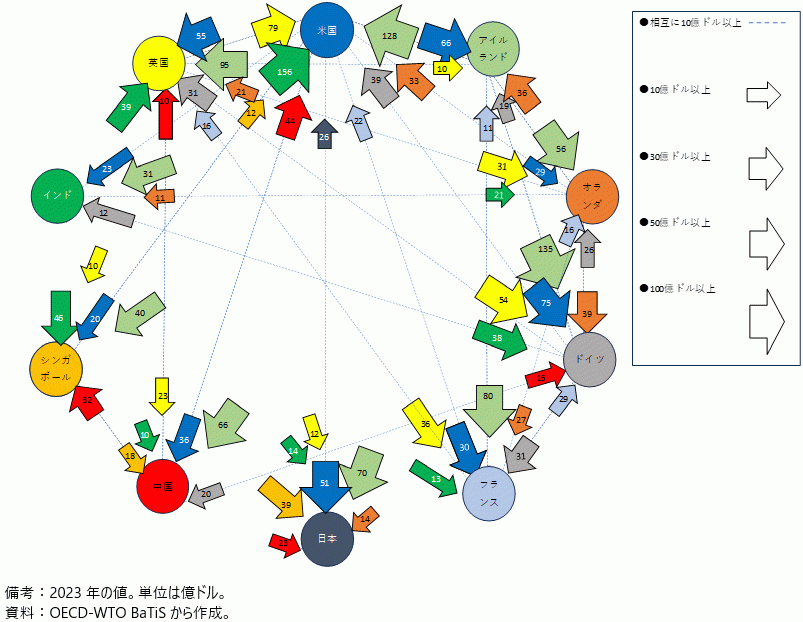
アイルランドが通信・コンピュータ・情報サービスを輸出している先について、時系列の動きを確認すると、ドイツや米国の割合が他国と比較して多い。また、近年は「その他」が急増しており、アイルランドから数多くの国に輸出が行われている様子がうかがえる。
第Ⅱ-1-2-26図 アイルランドによる通信・コンピュータ・情報サービスの輸出先
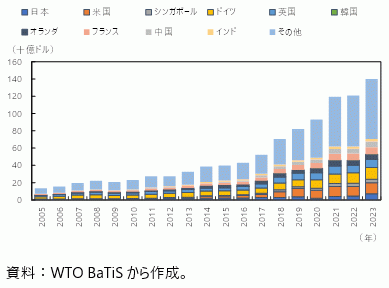
こうしたアイルランドの輸出について、付加価値額と国際収支統計上の貿易収支額を比較すると、アイルランドでは、通信・コンピュータ・情報サービスの総輸出金額よりも、自国が付けた通信・コンピュータ・情報サービスの付加価値額がかなり小さくなっている(第II-1-2-27図)。
第Ⅱ-1-2-27図 通信・コンピュータ・情報サービスの総輸出金額と付加価値輸出金額(2020年)
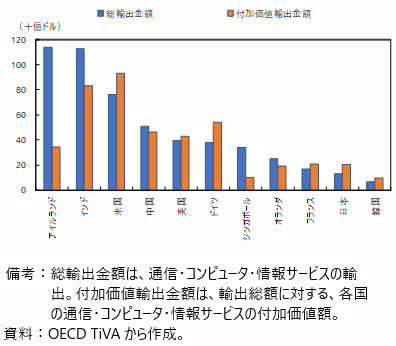
この点、アイルランドの通信・コンピュータ・情報サービス輸出の付加価値構成を見ると、米国やオランダといった自国以外の国からの付加価値の投入割合が大きくなっている(第II-1-2-28図)76。
第Ⅱ-1-2-28図 アイルランドの通信・コンピュータ・情報サービス輸出における付加価値由来国の構成(2020年)
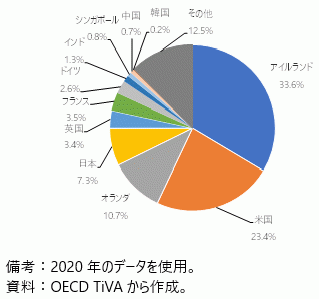
③ 専門・経営コンサルティングサービス
専門・経営コンサルティングサービスは、主要11か国で世界における輸出シェアの約7割を占める(第II-1-2-29図)。特にシェアの大きい国は、米国、英国、インドであり、時系列で見ると、米国の伸びが顕著となっている。
第Ⅱ-1-2-29図 専門・経営コンサルティングサービスの国別輸出額推移
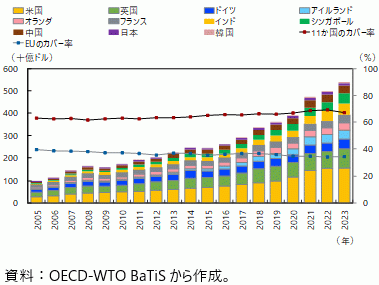
貿易のフロー図を確認すると、通信・コンピュータ・情報サービスと同じく、欧米諸国の取引が多く、ここでも、アイルランドが中心的な役割を担っていることが分かる(第II-1-2-30図)。アジアでは特にシンガポールが、欧米諸国と点線でつながっており、米国からの輸入が大きく、アジア諸国への輸出が多い。これは、米中などの大手デジタル関連企業の拠点がシンガポールにあるためと思われる。日本は、通信・コンピュータ・情報サービスと同様に輸入超過となっており、点線で結ばれる国の数が中国と並んで少ない。
第Ⅱ-1-2-30図 専門・経営コンサルティングサービスのフロー図
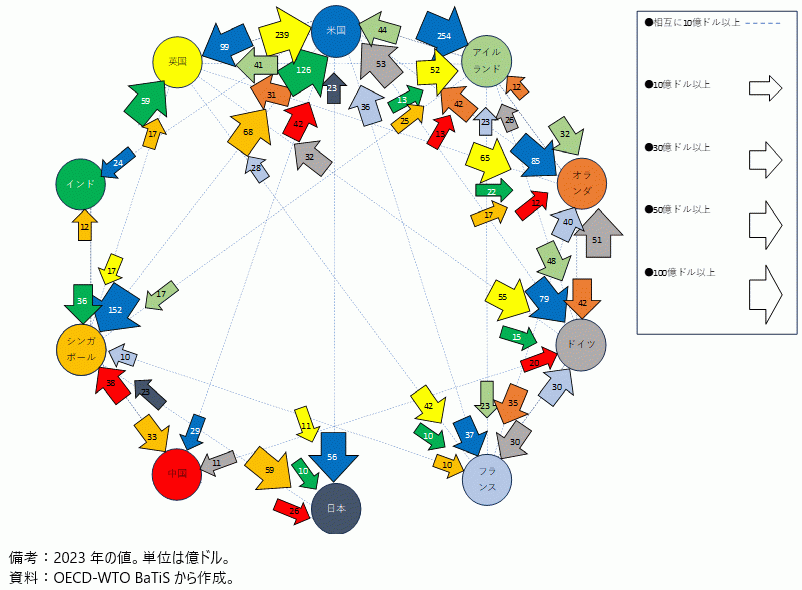
米国の専門・経営コンサルティングサービスの輸出先を見てみると、2020年頃からアイルランドやシンガポールへの輸出が大きくなっている(第II-1-2-31図)。
第Ⅱ-1-2-31図 米国における専門・経営コンサルティングサービスの輸出先
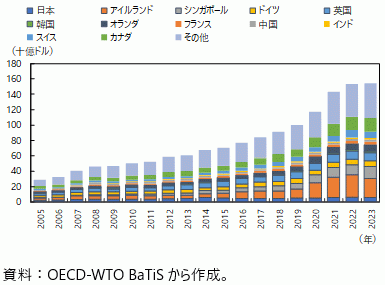
この背景には、インターネット広告市場の成長があると考えられる。米国の広告プラットフォーム企業がアイルランドの拠点を通じて広告スペースを販売する際、その取引が「専門・経営コンサルティングサービス」のカテゴリに含まれる場合がある。これにより、アイルランドの広告関連企業が米国の広告プラットフォーム企業に支払う費用が、米国の専門・経営コンサルティングサービスの輸出として計上される可能性がある。さらに、2020年以降のコロナ禍の影響も、アイルランド向けの広告関連取引の増加に寄与した可能性がある。コロナ禍の中でデジタル広告市場は急成長し、多くの企業がオンライン広告への投資を増やしたと見られる。このように、米国の専門・経営コンサルティングサービスのアイルランド向け輸出の増加は、単なるコンサルティング業務の需要拡大ではなく、デジタル広告市場の成長と密接に関係している。今後、欧州のデジタル規制強化(例:GDPRやデジタルサービス法)がアイルランドにおける広告関連取引にどのような影響を与えるのかも注視する必要がある。
68 松瀬他(2023)
69 例えば、JETRO(2024)や財務省(2024)でもほぼ同様の定義に従っている。
70 BaTiSは各国の貿易統計データを調整(balancing)したものであり、特に、2国間の貿易を捉えるのに最も適したデータとなる。BaTiSはBalanced Trade in Servicesの略称。
71 ただし、ドイツや日本はデジタル関連以外の知的財産権等使用料の黒字が大きいと思われる点には留意を要する。
72 先述のとおり、デジタル関連以外の知的財産権等使用料が含まれている点には留意を要する。日本も比較的高いシェアを占めるが、これは第Ⅱ部第3章1節で示すとおり、主に自動車等の海外生産に伴うものであり、デジタル関連貿易には必ずしも当たらない。
73 2020年をもって禁止されているが、かつては、「ダブル・アイリッシュ・ウィズ・ダッチ・サンドウィッチ」と呼ばれる、多国籍企業が税負担を最小限に抑えるために、知的財産権をアイルランドに移転し、さらにオランダを経由し、最終的にバミューダ諸島などのタックス・ヘイブンへ利益を移転する租税回避スキームが利用されていた。スキームの詳細は、富岡(2022)参照。
74 ECB (2023)
75 JETRO「新型コロナで拡大が見込まれるデジタル関連サービス貿易」、2020年10月8日、
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2020/1001/4d82aa39e7edee27.html![]() (2025年6月5日閲覧)。
(2025年6月5日閲覧)。
76 なお、アイルランドの通信・コンピュータ・情報サービス輸出に含まれる日本の付加価値が7.6%と比較的大きいが、そのうち約3/4は、「専門的な知識の移転ではない一般的な事業運営を支援する多様な活動」を指す管理・支援サービス業となっており、これ以上の詳細は不明である。
6. DFFTを巡る現状
ここまで見たとおり、近年のサービス越境取引の拡大は、製造業におけるサービス付加価値の増加や経済のデジタル化の進展と密接に関係している。従来の輸送手段や現地法人を介した取引に加え、無形のサービスがインターネットを通じて国境を越えて提供されるようになった。このことは、サービス貿易の成長に資するものであると同時に、従来とは異なるリスクを生み出している。焦点となるのは、データの取扱いである。サービスが国際的にデジタルな手段で提供されることの大前提として、データの円滑かつ安全な越境流通を確保することが求められる。しかし、データの取扱いに関する規制には、プライバシー保護や国家安全保障などの多面的な観点がかかわることから、各国間でデータ活用と安全性確保の両立を図っていくことが政策課題となっている。
こうした状況を踏まえ、2019年にスイス・ダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)にて、安倍総理大臣が「DFFT(信頼性のある自由なデータ流通)」を提唱し、同年のG20大阪サミットでは首脳宣言に盛り込まれた。DFFTとは、「プライバシーやセキュリティ、知的財産権に関する信頼を確保しながら、ビジネスや社会課題の解決に有益なデータが国境を意識することなく自由に行き来する、国際的に自由なデータ流通の促進を目指す」というコンセプトである77。
以下では、DFFT及びその基盤となるデータセキュリティ、サイバーセキュリティを中心に、デジタル時代のサービス越境取引を支える制度的課題と、それに対する国際的・国内的な対応の動向を検討する。
(1) DFFTを巡る国際的ガバナンスの展開
① G7における行動計画の策定とIAP構想
2019年のG20大阪サミット以降、我が国はDFFTを目指した取組を推進し、その理念は主要国の間に浸透してきている。例えば、G7ではDFFTが主要な政策課題の一つとして位置付けられている。2021年には、英国の議長国の下、G7首脳は「DFFTに関する協力のためのG7ロードマップ」を承認した。このロードマップは、データローカライゼーション、規制協力、政府によるデータへのアクセス、優先分野におけるデータ共有という四つの横断的分野におけるG7メンバー間の共同行動計画を定めている。さらに、翌年のドイツでのG7では「DFFT促進のためのG7アクションプラン」を承認した。同プランには、ロードマップで定められた四つの柱に対する行動へのコミットメントとして、①DFFTの証拠基盤の強化78、②将来の相互運用性促進のための共通性の構築、③規制協力の継続、④デジタル貿易の文脈におけるDFFTの促進、⑤国際的なデータスペースの展望に関する知識の共有が含められている。
さらに、日本が議長国を務める下で、2023年のG7デジタル・技術大臣会合(群馬県高崎市)では、DFFTを具体化する新たな国際枠組みとして「パートナーシップのための制度的取決め(Institutional Arrangement for Partnership。以下、IAP)」の設立が合意され、続く広島での首脳会合で承認された。IAPはDFFTを実装化していくための枠組みであり、実務的な議論・実行の場として位置付けられている。
② OECDによるDFFT実現に向けた検討
OECDも、DFFT実現に向けた知見の集積とルール策定で中心的な役割を果たしている。OECDの分析と提言は、G7やG20の議論にも供されており、前述のIAPでもOECDの知見が活用される見通しとなっている。OECDでは、DFFTの理念実現に向けた課題を整理する目的から、各国のデータ流通関連の規制とアプローチを整理した報告書を取り纏めている79。同報告書の中で指摘された論点の一つが、政府機関によるデータへのアクセス(government access)の問題である。法の執行や経済安全保障の観点から、政府が民間保有データにアクセスする行為について、その透明性と手続の適正さが担保されない場合、企業や個人の不信を招き、結果として国際的なデータ流通を阻害し得る。この観点から、OECDは、2022年に「民間部門が保有する個人データに対するガバメントアクセスに関する宣言」を行い、無制限で恣意的なガバメントアクセスに反対する姿勢を示した。今後は、こうした共通の姿勢をOECD非加盟国に広げていくことが重要である。
2023年には、グローバル企業への大規模な調査を実施し、越境データ活用におけるコンプライアンス上の課題を分析している。同調査では、各国で法制度が急速に整備され、複雑化しつつある中、企業は法的不確実性や情報不足、規制の不整合に直面している現状が明らかになっており、国際的な協調の必要性が指摘されている。
③ WTOにおける電子商取引交渉
2019年のG20大阪サミットでは、DFFTと合わせて、WTOにおける電子商取引交渉の加速も提唱された。この交渉は、WTOにおける有志国間交渉として、日本が豪州、シンガポールと共同議長国を務めて推進してきた。それから5年をかけた交渉が行われ、2024年7月には、共同議長国が交渉参加国・地域を代表して、「電子商取引に関する協定に係る安定化したテキストを達成した」旨の共同議長国声明を発出した。併せて公表した38条文からなるテキストでは、「電子的送信に対する関税賦課の恒久的な禁止」を始めとして、「貿易書類の電子化や規制の透明化などを通じた電子決済の促進による電子商取引の貿易円滑化」、「政府データの公開やインターネットのアクセス・使用を通じた開かれた電子商取引の確保」、「サイバーセキュリティ、オンライン消費者保護や個人情報保護による信頼性のある電子商取引の確保」などの規律が盛り込まれた。なお、越境データ流通促進やデータの国内保存要求禁止、ソースコードや暗号の開示要求禁止など、安定化テキストに含まれない条文は、将来の交渉での議論が想定されている。
④ 国際的な議論を踏まえた課題
DFFT実現に不可欠な「信頼(Trust)」の具体的構成要素について、国際機関における議論を踏まえて整理すると、少なくとも以下の四つの項目の実現が課題であると考えられる。
第一に、政府アクセスの適正化である。前述のとおり、OECD原則では濫用防止や透明性向上がうたわれており、これにより企業・個人が海外にデータを預けても恣意的にアクセスされないという安心感の醸成につながると考えられる。
第二に、データガバナンスに関する透明性である。企業によるデータ利用の目的や越境移転の有無を分かりやすく開示させるとともに、各国政府もデータに関する法制度や当局のアクセス要件を明示する必要がある。G7の声明でも「各種フレームワークやガイドラインは透明であるべき」と明記されている。
第三に、民間企業の認証・認定スキームの活用である。例えば、APECの越境プライバシールール(CBPR)は、企業が第三者認証を取得することで参加エコノミー間の個人データ移転を円滑化する制度となっている。2022年には、日本や米国など9か国が参加し、APEC外への拡大を目指すグローバルCBPRフォーラムが設立され、各国のデータ保護規制の相互運用性を高める国際認証制度として位置付けられている。
第四に、データの安全な流通には、暗号技術やアクセス制御、インターフェース仕様など技術面の標準化も重要と考えられる。製品・サービスのセキュリティ評価基準(例えば共通評価基準CCや各国のIoTセキュリティ認証)についても、相互承認を進め、「一度の認証で世界各国から信頼される」仕組みを目指す動きがある(我が国における取組は後述)。
(2) DFFT実現に向けた我が国の取組
我が国は、DFFTの理念を具体的な制度・施策として実現するため、国内外で様々な取組を進めている。ここでは、経済産業省が2025年1月に公表した企業向けマニュアル、国際的なデータ制度調和への参加(CBPRなど)を取り上げる。
① 産業データの越境データ管理等に関するマニュアルの整備
2025年1月、経済産業省は企業の国際的なデータ共有・利活用を推進するために「産業データの越境データ管理等に関するマニュアル」を策定・公表した。当マニュアルは、個人データ以外の産業データ(非パーソナルデータ)にも焦点を当てている点が特徴である。従来、パーソナルデータの議論はプライバシー保護の観点から国際的にも積み重ねられてきたが、企業が扱う生産データや業務データなどの非パーソナルデータについて包括的なガイダンスを提供するのは、本マニュアルが初となっている。
マニュアルでは、国際データ共有に伴うリスクを体系的に整理しており、企業が取るべき対応策を三つのステップごとに示している。最初のステップは、リスクの可視化である。このステップでは、想定するデータの共有・利活用において、関連する利害関係者及びデータとその所在を整理し、どこで国際的な共有・利活用が行われ、越境移転が起こるか把握した上で、想定されるリスクシナリオの整理を行う。第2のステップでは、洗い出したリスクの重大性と発生可能性を評価し、対応の優先度を判断する。第3のステップは、打ち手の実施である。マニュアルでは、想定される代表的なリスクごとに有効と考えられる対策の方向性が示されており、モニタリング、事前対応、事後対応ごとに、講じうる措置がリストアップされている(第II-1-2-32表)。
第Ⅱ-1-2-32表 主要な打ち手
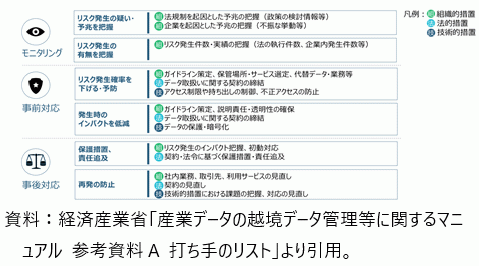
② 国際的な認証制度・ルールへの参画
我が国は、DFFT推進の一環として、国際的なデータ保護・認証の仕組みに積極的に参画している。前述のAPECの越境プライバシールール(CBPR)認証制度は、その代表例として挙げられる。CBPRは、参加エコノミー間で個人データを移転する企業に対し、各国共通のプライバシー保護原則への準拠を第三者機関が認証する仕組みで、日本は2014年に参加し、国内ではJIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)が認証機関として運用している。
また、我が国は欧州との間でも、データ流通の枠組み作りを進めている。2019年には、EUが域外国としては初めて、日本を「十分性認定」(GDPR水準で個人データを保護している国)し、日EU間で個人データが追加の保護措置なしに流通可能となった。さらに2023年10月、日EU経済連携協定(EPA)にデータの自由な流通に関する規定を追加し、データ・ローカライゼーションの禁止や政府アクセスの透明性といった原則を盛り込むことで大筋合意し、2024年7月には発効した。
このような二国間や地域の取組は、国際的なデータルールの整合化に寄与するものであり、DFFT実現に向けた重要なステップである。
(3) サイバーセキュリティを巡る各国の法制度と多国間調和
データの自由な流通と保護を支えるもう一つの柱がサイバーセキュリティである。サービス越境取引がデジタル化する中、データやネットワーク、システムの安全性確保は、国際的な信頼に基づく取引の前提条件となっている。ここでは、主要国・地域(米国、EU等)のサイバーセキュリティ関連法制度の最近の動向を整理する。
① 製造者・製品へのセキュリティ要件
米国で2020年に成立した「IoTサイバーセキュリティ改善法(IoT Cybersecurity Improvement Act of 2020)」は、連邦政府が調達・利用するIoT(Internet of Things)機器に最低限満たすべきセキュリティ基準を初めて定めたもので、米国国立標準技術研究所(NIST)に対して具体的な標準策定を命じている。これに基づき、デフォルトパスワードの禁止や脆弱性情報の開示義務など、IoT製品の基礎的セキュリティ要件が導入された。
また、2023年には、米国連邦政府が「U.S. Cyber Trust Mark」というIoT製品のセキュリティラベリング制度を提唱した。消費者向けワイヤレスIoT製品に適用され、対象商品の例としては、インターネットに接続された家庭用防犯カメラ、音声起動ショッピングデバイス、スマート家電、フィットネストラッカー、ガレージドアオープナー、ベビーモニターなどが含まれる。
② 重要インフラ事業者等への義務
米国の重要インフラに係るサイバーインシデント報告法案(Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act of 2022)は、2024年4月に規則案が公表された。そこでは、重要インフラ分野を対象に、サイバーインシデントが発生した場合、72時間以内にCISA(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)へ報告し、ランサムウェアの支払いを行った場合は24時間以内に報告することが求められている。
EUでは、2023年にNIS2指令(Directive (EU) 2022/2555)が発効している。同指令は、2016年NIS指令から対象セクターを拡大した上、対象「主要エンティティ」、「重要エンティティ」に対し、①サイバーセキュリティ・リスクマネジメントの強化、②重大なサイバーセキュリティインシデントについて発生を認知後24時間以内に早期警告、72時間以内にインシデント通知を管轄省庁等に報告すること等を義務付けている。
③ その他事業者のサイバー対策可視化
欧米を中心に、政府機関の請負業者等のサイバーセキュリティ対策を可視化、一部義務化する動きも加速している。
米国では、国防総省がその請負業者等と共有する機密性の高い情報の保護を目的に設計した、レベル1~3の三段階で構成される認証制度CMMC(Cybersecurity Maturity Model Certification)が定められており、2021年に改訂版のCMMC 2.0が発効している。また、2024年10月には最終規則が発表されている。
英国では、サイバー・エッセンシャルズ (UK Cyber Essentials)という制度が定められている。英サイバーセキュリティセンターが全ての企業に対して、一般的なサイバー攻撃への防御策を提供することを目的として設計した、自己適合、第三者診断の二段階で構成される認証制度となっている。
(4) 日本のセキュリティ制度整備
デジタル時代のサービス越境取引を支える基盤として、我が国も自国内のサイバーセキュリティ体制強化に注力している。ここでは、代表的な取組として、IoT製品のセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度と、サイバーセキュリティ戦略について紹介する。
① IoT製品のセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度
2025年3月、経済産業省とIPA(独立行政法人情報処理推進機構)は、近年急増するIoT製品のセキュリティ確保策として、JC-STAR(Japan Cyber-Security Technical Assessment Requirements)というセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度を導入した。同制度は、ルーターやウェブカメラ、センサー等、インターネットに接続可能な幅広いIoT製品を対象とし、共通の基準でセキュリティ評価を行ってラベルを付与するものであり、製品購入者(政府調達担当者、企業、消費者)がセキュリティ水準に応じた製品を容易に選択できるよう「見える化」することを目的としている。
具体的には、共通の最低基準(STAR-1)から高度な要件(STAR-2~STAR-4)まで、複数レベルの基準を設け、製品が満たしたレベルに応じて★マークを付したラベルを発行している(第II-1-2-33図)。
第Ⅱ-1-2-33図 適合ラベル(STAR-1のイメージ)

JC-STARの特徴は、日本独自の要件を反映しているだけではなく、海外の同種制度とも整合性を図っている点である。経済産業省は、米国、英国、シンガポールなど、他国と相互認証することを視野に入れている。
② 日本のサイバーセキュリティ戦略と制度枠組み
我が国は、2014年にサイバーセキュリティ基本法を制定し、以降、数年ごとに「サイバーセキュリティ戦略」を策定して、国家としての方向性を示している。直近の2021年戦略では、「自由で安全なサイバースペースの確保」を掲げ、経済安全保障上重要な技術・産業の保護、ゼロトラストセキュリティの推進、そして国際ルール形成への積極的な参加を目指している。また、2022年に成立した経済安全保障推進法により、政府が定めた基幹インフラの安定的な提供を確保するために指定された事業者は、特定重要設備(その設備の機能が停止すると役務提供ができなくなるような設備など)の導入・維持管理等の委託をしようとする際に、事前に届出を行い、審査を受けることが定められている。
官民連携の枠組みも整備されている。2019年、改正基本法に基づきサイバーセキュリティ協議会が設立され、政府機関、企業、教育機関など数百の団体が参加する情報共有・連携プラットフォームが形成された。これは民間の知見を政策に反映させたり、業種横断でインシデント情報や脅威インテリジェンスを交換したりする場として機能している。
(5) 今後の展望
デジタル時代のサービス越境取引における主要な制度課題として、DFFTとデータセキュリティ・サイバーセキュリティについて、国際動向と我が国の対応を概観してきた。データガバナンスとデータセキュリティ・サイバーセキュリティは、本来不可分の関係にある。すなわち、安全性と信頼性は自由な取引の前提であり、取引が行われない場合には、データセキュリティ・サイバーセキュリティ自体の重要性も高くならない。したがって、データ保護法制とサイバーセキュリティ法制を統合的に点検し、両者が補完関係にあるような枠組み構築が求められる。
また、そうした枠組みを構築していく上では、国際協調も重要である。我が国はこれまで、この分野における国際協調の議論をリードしてきた。今後も、IAPの場を活用しつつ、DFFTの実現に向けた国際的な制度形成や国際協調に取り組む必要がある。
77 デジタル庁「DFFT」、https://www.digital.go.jp/policies/dfft![]() (2024年10月16日最終更新)。
(2024年10月16日最終更新)。
78 国境を越えたデータ流通によって生ずる機会と課題に対する理解を深める作業を支援することへのコミットメントが示された。具体的には、プライバシー、データ保護、セキュリティ、知的財産権の保護に関連した、DFFTを可能にする既存の規制アプローチや手段の理解を深めることや、データローカライゼーション措置とその潜在的な影響(特に中小企業への影響)に係る理解を深めること、また、データローカライゼーションの代替案を検討する作業などを含む。
79 経済産業省「Ministerial Declaration: The G7 Digital and Tech Ministers' Meeting 30 April 2023」、
https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230430001/20230430001-summary.pdf![]() (2025年6月5日閲覧)。
(2025年6月5日閲覧)。