第3節 グリーン移行と貿易
貿易と環境の関連性については、これまでも貿易問題の一つとして国際的に議論されてきたが、近年、気候変動を始めとする環境問題へのグローバルな対応が進む中、グリーン移行を支える貿易政策に関する議論が活発化している。
本節では、貿易と環境を巡る過去の国際的な議論の経緯を整理し、近年の気候変動を始めとする国際的な取組の進展を見た上で、主要国・地域の気候・環境政策における貿易側面の動向と、最近の国際的な議論や取組を概観する。
1. 貿易と環境を巡る国際的な議論の経緯
貿易政策は環境問題と様々な関連性がある。炭素排出の削減に資する製品・サービスの貿易を促進し、それらをより広く早く普及させることは、国際的に炭素排出の削減を目指す気候変動対策にも貢献する。各国の環境規制の強度が異なる中で貿易投資が行われると、炭素排出の大きい産業が環境規制の厳しい国から緩やかな国に移転し、環境規制の効果が減殺されるという懸念がある。各国がカーボンプライシング(炭素価格付け)等の環境対策で様々な制度や基準を導入すると、その差異や多様化がビジネスにとって必要以上の貿易障壁になるおそれもある。貿易を円滑にするための手続の簡素化が、例えば違法な有害廃棄物の国際取引を見逃すことになってはいけないが、過剰な手続負担が貿易を阻害することも避ける必要がある。このように、貿易と環境の結節点には幅広い課題があり、近年のグローバルな環境問題に係る議論の展開は、貿易と環境の関連を考慮する必要性を一層高めている。
貿易と環境の関連性に対しては、地球環境問題が提起され始めた1970年代以降、徐々に国際的な問題意識が高まっていった。1992年の国連環境開発会議(地球サミット)では、貿易政策と環境政策を相互支持的にしていくという考え方が国際的に初めて示された80。WTO設立に当たって1994年に合意された「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」の趣旨を記す前文では、1947年のGATT(関税及び貿易に関する一般協定)にはなかった環境の保護・保全に言及された。WTOにおいては、貿易と環境に関する議論を行う常設委員会として、貿易と環境委員会(以下、CTE)が設置されている81。
その後、2010年代半ばまで貿易に関する国際的な議論で注目を集めたのは、環境目的に資する物品・サービスの国際的な普及を促進するための貿易自由化であった。WTO設立後の2001年、ドーハ・ラウンド交渉開始を決めたドーハ閣僚宣言において、「環境関連物品及びサービスに係る関税及び非関税障壁の撤廃及び削減」に関する交渉の立上げと、同交渉を行う貿易と環境に関する委員会特別会合(以下、CTESS)の設置が盛り込まれた。WTOでの環境物品サービスを含むドーハ・ラウンド交渉は2008年に停滞に陥り、それを受けて進められた有志国間の環境物品協定(以下、EGA)交渉も頓挫したため、具体的成果には至っていない(詳細は後述)。しかし、ここでの議論は、APECでの環境物品リストへの合意や、各国・地域の経済連携協定での環境物品サービスの自由化等につながった。なお、ドーハ・ラウンドでは、WTO協定と環境関連条約(例えば「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」)との関係性等も貿易と環境に係る交渉上の論点となっていた。
2015年の気候変動問題に関するパリ協定の採択や、2022年のプラスチック汚染対策に関する条約交渉の開始等を経て、貿易と環境の関連性に係る議論の機運は一層高まった。2022年の第12回WTO閣僚会合(MC12)の成果文書には、貿易と環境に関するパラグラフが含まれ、気候変動と関連する自然災害、生物多様性の喪失、汚染を含むグローバルな環境課題に対するWTOの貢献の重要性が認識された82。また、2020年11月、日本を含む50加盟国が、WTOで貿易と環境持続可能性の関連について議論を深めていく意思を示す共同コミュニケを発出した。これを踏まえ、有志国イニシアティブとして、「貿易と環境持続可能性に関する体系的議論(以下、TESSD)」が立ち上げられることとなった。TESSDは、参加国が個別あるいは共同で取ることのできる具体的な行動の特定や、貿易関連の気候措置が気候目標へどのように貢献できるかに関する議論、ベストプラクティスの取りまとめなどを行うことを目的としており、自由化交渉の開始を前提としない探求的な議論の枠組みである点に特徴がある。2022年からは、テーマ別の四つのWG(環境物品サービス、貿易関連気候措置、循環経済、補助金)で作業が開始され、2024年2月の第13回WTO閣僚会合(MC13)において、これらのWG(ワーキンググループ)の成果文書が発出された。同時期には別途、「プラスチック汚染と環境持続可能なプラスチック貿易に関する対話(DPP)」も立ち上げられている。WTOでは、常設委員会であるCTEとともに、これら有志国イニシアティブにおいて、環境物品サービスの貿易促進、貿易関連気候措置、貿易と循環経済やプラスチック汚染対策等について議論が行われている。
80 環境省「環境と開発に関するリオ宣言」、https://www.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-02/ref_05_1.pdf![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
81 WTO, ‘Trade and environment’, https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
82 WTO, ‘MC12 Outcome Document’, 22 June 2022, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/24.pdf&Open=True![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
2. 世界の気候変動対策の動向
地球規模の環境問題の中でも、とりわけグローバルな課題として注目され、取組が進んできたのが気候変動対策である。2025年1月、世界気象機関(WMO)は、2024年が観測史上最も暑い1年となり、世界全体の気温が産業革命以前と比べて約1.55℃上昇したと発表した83。世界中で異常気象が発生し、大規模な自然災害が各地で増加する中、気候変動問題への対応は、今や人類共通の課題となっている。
1992年5月、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目標とする「国連気候変動枠組条約」が国連総会で採択され、地球温暖化対策に世界全体で取り組んでいくことが合意された。同条約に基づき、国連気候変動枠組条約締約国会議(以下、COP)が1995年から毎年開催されており、1997年のCOP3では、先進国に対して法的拘束力のある温室効果ガス削減の数値目標を設定した「京都議定書」が採択された。2012年に行われた京都議定書第8回締約国会合(CMP8。以下、京都議定書締約国会合をCMPという)では、2013年から2020年までの第二約束期間の各国の削減目標が新たに定められた。しかし、米国の不参加や近年の新興国の排出増加等により、京都議定書締約国のうち第一約束期間で排出削減義務を負う国の排出量は世界の4分の1にすぎないことなどから、我が国を始めとする複数の国が第二約束期間には参加せず、全ての主要排出国が参加する新たな枠組みの構築を目指して国際交渉が進められてきた84。
2015年、フランス・パリにおいて、COP21及びCMP11が行われ、全ての国が参加する温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択された。パリ協定では、産業革命前からの地球の平均気温上昇を2℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求することなどが合意された。また、主要排出国を含む全ての国が、温室効果ガスの排出削減目標を「国が決定する貢献(NDC)」として5年ごとに提出・更新することが義務付けられた85。各国は、2030年及び2035年のNDCを国連気候変動枠組条約事務局へ提出しており、また、多くの国が2050年等の年限付きで炭素中立の実現を表明している86(第II-1-3-1表)。
第Ⅱ-1-3-1表 各国のNDC及びネット・ゼロに向けた長期目標
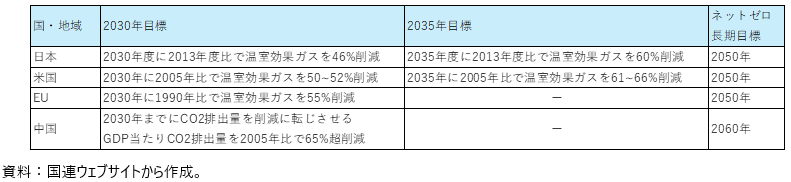
83 国際連合広報センター「2024年は史上最も暑い年に ― 国連の気象機関が発表(UN News 記事・日本語訳)」、2025年1月21日、https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/51488/![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
84 環境省(2024)
85 環境省(2024)
86 United Nations, ‘NDC Registry’, https://unfccc.int/NDCREG![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
3. クリーンエネルギーの需要と製造能力、貿易
世界がパリ協定の1.5℃目標達成とネット・ゼロの実現を標榜する中、クリーンエネルギーの需要は急速に高まっている。IEA(国際エネルギー機関)が2024年10月に公表した「World Energy Outlook 2024」によると、2013年から2023年の10年間で、世界のエネルギー需要は15%増加し、その増加分のうち40%はクリーンエネルギーが占めていたという87。2023年に新たに追加された再生可能エネルギー発電容量は560GWを超え、前年比60%増となっている88。
クリーンエネルギー産業における世界的な製造能力拡大も進んでいる。IEAが2024年10月に公表した「Energy Technology Perspectives 2024」によると、2021年から2023年にかけて、太陽電池モジュールの製造能力は450GW強から1.2TWへ、風力タービンのナセル89の製造能力は125GWから180GWへ、電気自動車(EV)の製造能力は1,050万台から2,220万台へ、バッテリーの製造能力は1.1TWhから2.5TWhへ増加した90。
同レポートで指摘された重要な点として、クリーンエネルギー産業のサプライチェーンが地理的に集中している事実が挙げられる。クリーンエネルギー産業と、その関連材料である鉄鋼、アルミニウム、アンモニアなどの生産国として他国を凌駕しているのは中国である。2023年末時点で、世界のクリーンエネルギー産業の製造能力に占める中国の割合は、バッテリー部品で85~98%、太陽電池モジュールとその部品で80~95%、風力タービン部品で50~65%となっている。2021年以降は、バッテリーのカソード(2021年の70%から2023年の90%)や、バッテリーのセル(80%から85%)、ポリシリコン(80%から90%)、太陽電池モジュール(75%から80%超)、風力タービンのブレード(50%から60%)、風力タービンのナセル(55%から65%)について、特に中国への地理的集中が進んでいる91(第II-1-3-2図)。
第Ⅱ-1-3-2図 国・地域別の製造能力(2023年)
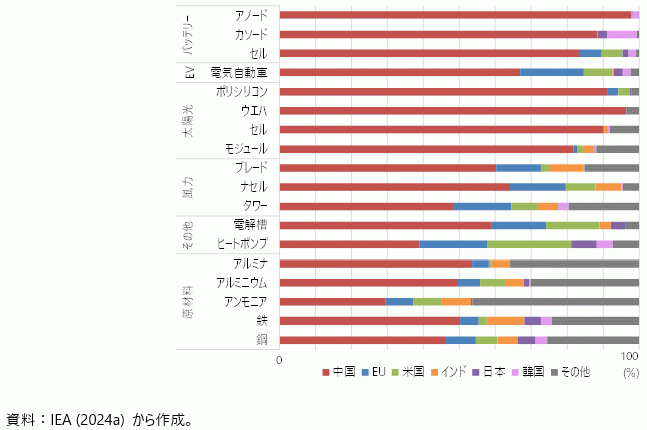
クリーンエネルギー需要の増加と製造能力の拡大を背景に、クリーンエネルギー関連製品の貿易も過去10年間で急速に拡大し、エネルギー移行を後押ししている。例えば、太陽電池モジュールの世界輸出は、2010年から2023年にかけて重量ベースで18倍増加し、2023年には1,000万トンを超えた。また、EVの世界輸出は、2015年から2023年にかけて台数ベースで20倍近く増加し、2023年に約300万台に達した92。
そして中国は、クリーンエネルギー関連製品の貿易においても世界最大の輸出国である。2023年には、EVの世界輸出に占める中国のシェア(台数ベース)は30%を超え、太陽電池では65%となった(第II-1-3-3図)93。
第Ⅱ-1-3-3図 主要輸出国による製品・原材料別輸出シェア(2010-2023)
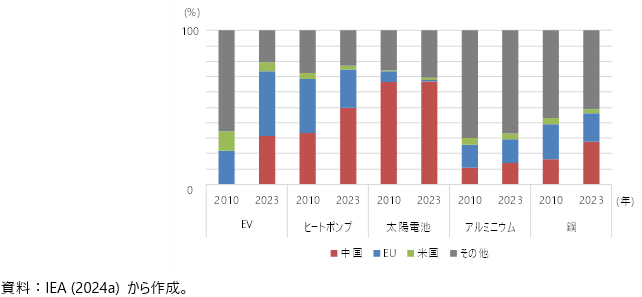
87 クリーンエネルギーとは、電力及び最終用途部門における再生可能エネルギー、原子力、及び低炭素燃料(CCUSも含む)を指す。
88 IEA (2024b)
89 ナセルとは、風力タービンを構成する要素の一つであり、増速機や発電機、ブレーキ装置、ローター軸、発電機軸、インバーター、変圧器といった主要な機器が格納されている部分を指す。
90 IEA (2024a)
91 IEA (2024a)
92 IEA (2024a)
93 IEA (2024a)
4. 各国・地域の主な気候・環境政策の貿易側面
国際的な気候変動対策がパリ協定下のNDCに基づく各国の自主的な取組に向かう中、主要国・地域はそれぞれの気候・環境政策を打ち出している。同時に、世界のクリーンエネルギー需要が高まる中、先に述べたクリーンエネルギー産業のサプライチェーンの地理的集中や、ロシアによるウクライナ侵略といった地政学的リスクの高まりは、世界各国の経済安全保障及びエネルギー安全保障上の懸念を惹起している。これらを背景に、世界各国は、自国のクリーンエネルギー産業を強化し、炭素中立に資する製品を優遇するような気候政策を加速させている。そして、各国が打ち出す昨今の気候政策は、貿易政策、産業政策、経済安全保障政策などと密接に連携している。以下では、米国とEU、中国の気候政策について、その貿易側面を取り上げる。
(1) 米国
2021年1月、米国のバイデン大統領は、就任早々、2020年に脱退したパリ協定への復帰に関する大統領令に署名し、同年2月に正式復帰を果たした。そして、同4月、米国は、約40の国・地域の首脳級を招いた気候サミットを主催し、「2030年に2005年比で温室効果ガスを50~52%削減」するというパリ協定に対応した新たな目標を発表した94。
2022年8月には、脱炭素化に資する技術の導入等を支援する「インフレ削減法(以下、IRA)」が成立した。同法は、民間企業や消費者等への税額控除及び補助金等を通じてクリーンエネルギーのコストを引き下げ、同分野への民間投資を加速させるとともに、重要サプライチェーンを強化することを目的としている。
IRAによる民間企業への支援形態は税額控除が中心であり、同法には、投資税額控除による初期投資支援のみならず、生産量や販売量に応じ一定額を控除する生産税額控除も盛り込まれている。投資税額控除には、再生可能エネルギー事業への投資に対する税額控除や、クリーンエネルギー機器及び自動車(燃料電池、EV等)を製造又はリサイクルする施設の改修・拡大・新設に対する税額控除などがある。また、生産税額控除には、再生可能エネルギー発電に対する税額控除や、クリーン水素の生産量に応じた税額控除、太陽光・風力発電用部品等の国内生産・販売量に応じて適用される税額控除などがある。
また、消費者側への支援措置には、EV等のクリーン自動車の購入に対する税額控除(以下、EV税額控除)がある。EV税額控除の対象車両を購入する消費者は、一車両当たり最大7,500ドルの税額控除を受けることができる。しかし、最大の税額控除を受けられる車両となるためには、「車両の最終組立てが北米域内で行われていること」、「バッテリー部品の一定割合が北米で製造又は組み立てられていること」、「バッテリーに含まれる重要鉱物の一定割合が、米国ないし米国とのFTA締結国で採取・加工されていること、又は北米でリサイクルされていること」という三要件を満たさなければならない95。
こうしたIRAの税額控除の要件に対して、一部の国はWTO紛争解決手続を開始した。2024年3月、中国は、同法に規定されているEVと再生可能エネルギーの生産を促進する税額控除が、「輸入品よりも国内製品の使用を条件としているか、中国原産の製品に対して差別的」であり、WTO協定に違反していると主張した96。
一方で、2025年1月に就任したトランプ大統領は、就任当日に「米国のエネルギーの解放」と題する大統領令に署名し、IRA等に計上された資金支出を一時停止して90日間のレビューを開始した97。加えて、米国は、同年同月に国連へパリ協定脱退の通告を発出しており、米国の気候政策とそれが貿易に与える影響は不確実性を増している。
94 United Nations, ‘NDC Registry’, https://unfccc.int/NDCREG![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
95 White House, ‘Inflation Reduction Act Guidebook’, https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/12/Inflation-Reduction-Act-Guidebook.pdf![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
96 WTO, ‘China initiates dispute regarding US tax credits for electric vehicles, renewable energy’, 28 March 2024, https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/ds623rfc_28mar24_e.htm![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
97 White House, ‘Unleashing American Energy’, 20 January 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/unleashing-american-energy/![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
(2) EU
欧州委員会は、2019年12月、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすること(ネット・ゼロ)を始めとするグリーン移行に向けた成長戦略として「欧州グリーン・ディール」を発表した98。フォン・デア・ライエン欧州委員長は記者会見の中で、「欧州グリーン・ディールは、一方では温室効果ガス排出量を削減し、もう一方では雇用を創出してイノベーションを促進させるものだ」と述べ、脱炭素と経済成長の両立を標榜した。欧州グリーン・ディール発表後、欧州委員会は気候変動対策にとどまらない幅広い環境関連政策を次々と発表した。
2021年7月には、2030年までに温室効果ガスを1990年比で55%削減し、2050年までにネット・ゼロを達成するという法的拘束力のある目標を明記した「欧州気候法」が施行された99。さらに、同年同月、欧州委員会は欧州気候法の温室効果ガス削減目標を達成するための政策パッケージであるFit for 55パッケージを公表し、EU排出量取引制度100の改正や炭素国境調整措置(以下、CBAM)の創設に関する規則案を含む13の法案を提案した。
CBAMとは、カーボンリーケージ、すなわち温室効果ガスの排出規制が厳しい地域から緩い地域への生産移転や、規制が厳しい地域で生産された製品が緩い地域で生産された製品に取って代わられてしまうことを阻止するための措置の一つである。具体的には、EU排出量取引制度を通じて域内産品に課される炭素価格に対応した価格を、域外から輸入される対象製品にも課すものである。CBAMの創設に関する規則は、2023年4月に欧州議会とEU理事会が採択し、同年5月に施行された。これによりCBAMは、2023年10月から2025年末までの移行期間を経て、2026年1月から本格運用が開始されることになった。EUはこれまで、カーボンリーケージ対策として、排出量が多く輸出入で国際競争にさらされている産業に対し、排出枠を無償割当してきた。しかし、EU排出量取引制度の改正により、CBAMの対象となる産業の無償割当は、CBAMの本格運用が開始される2026年から2034年にかけて、段階的に削減されることとなっている101。
CBAMの対象となる製品は、EU域外から輸入されるセメント、鉄鋼、アルミニウム、肥料、電気、水素である。ただし、規則には、移行期間が終了する2025年末までに欧州委員会が対象製品の見直しを行うと定められているため、今後対象範囲が拡大される可能性がある。対象製品の輸入業者は、本格運用が開始されるまでに「認可CBAM申告者」の資格を得るための申請を行い、EU加盟国の当局より認可を受けなければならない102。
その他、欧州グリーン・ディールの一環として、欧州委員会は森林破壊防止や循環経済への移行促進も進めている。2023年6月に施行されたEU森林破壊防止規則(以下、EUDR)は、森林減少防止や炭素排出量削減、生物多様性保護を目的として、EU域内で流通又は域外へ輸出する特定の品目に関し、当該品目の生産において森林減少を引き起こしていないことの確認(森林デューデリジェンス)を企業へ義務付けるものである。企業は、対象製品を域内に流通させるために、「森林破壊フリーで対象製品が生産されていること」、「生産国の法律に従って生産されていること」及び「これらの要件を満たすことを管轄する加盟国へ報告すること」という要件を遵守しなければならない。なお、域外からの輸入品に関しては、その製品をEU市場で最初に流通・販売する企業がこの義務を負う103。
また、循環経済への移行促進について、欧州委員会は2020年3月に新たな循環経済行動計画を発表し、同計画に基づいて、2024年7月にエコデザイン規則を施行した。同規則は、従来のエコデザイン指令を改正し、食品や医薬品など限られた例外を除く幅広い製品に対象を拡大したものであり、対象製品に求められる要件として、耐久性や再利用可能性、改良・修理可能性、エネルギー効率性等が規定された。これらの要件の詳細は、今後、製品ごとの特性に応じ委任立法で規定される予定であり、輸入品を含め、EU域内市場に上市される対象製品は委任立法の要件を遵守するものでなければならない104。
そして、欧州グリーン・ディールに基づく産業政策も具体化が進んでいる。2023年1月、フォン・デア・ライエン欧州委員長は、世界経済フォーラム年次総会で演説し、「グリーン・ディール産業計画」の構想を発表した。同計画は、欧州の気候目標を達成するために必要なネット・ゼロ技術及び製品について、規制緩和や資金調達支援などを通じたEU域内の生産能力拡大を目指している。同時に、同計画の中でEUは、サプライチェーン強靱化の観点から同志国との連携強化も進めるとしており、2023年3月に、重要原材料の安全で持続可能な供給を確保するための「重要原材料クラブ」の設立も発表した。その取組として、サプライチェーンにおける労働者の権利保護と社会的に責任ある慣行の促進において同志国と協力することや、国境を越えて循環型・持続可能な経済を推進し、高度なリサイクル能力を強化していくことなどが挙げられている。
2024年9月、欧州委員会は、「欧州の競争力の将来」と題するレポート(以下、ドラギレポート)を公表した。これは、フォン・デア・ライエン欧州委員長からの諮問を受けたドラギ元欧州中央銀行総裁が、欧州の競争力強化に向けた政策提言をまとめたものである。同レポートは、EUが直面する三つの課題と対応策を提示した上で、新たな産業戦略の実現に向け、戦略分野へ年間最大8,000億ユーロを投資することや、貿易・競争・産業政策を相互に連携させることなどを提案している105。
そして、2025年1月、欧州委員会は、ドラギレポートの提言を踏まえ、欧州委員会としての政策をまとめた「競争力コンパス」を公表し、三つの変革として「イノベーション格差の解消」、「脱炭素化と競争力のための共同ロードマップ」、「過剰な域外依存の軽減と安全保障の強化」を掲げた。二つ目の「脱炭素化と競争力のための共同ロードマップ」では、脱炭素化政策と産業・競争・経済・貿易政策が適切に統合されれば、強力な成長の推進力となるということが改めて強調された106。
98 European Commission, ‘The European Green Deal: Striving to be the first climate-neutral continent’, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
99 2024年2月、欧州委員会は、2040年までに温室効果ガス排出量を1990年比で90%削減することを勧告し、全てのステークホルダーとの協議を開始した。
100 排出量取引制度とは、企業による温室効果ガスの排出を金銭的コストに換算し企業の行動変容を促す政策手法である「カーボンプライシング」の一類型であり、企業ごとのCO2排出量に枠を設け、その排出枠の過不足を企業間で取引する制度。
101 JETRO(2024b)
102 輸入者は、移行期間中は輸入課金支払義務を負わないものの、製品単位当たり排出量等の情報の報告義務は課されるため、対象製品の輸入総量や製品単位当たりの温室効果ガス排出量等を記載した「CBAM申告書」をEU加盟国の当局へ提出しなければならない。なお、移行期間終了後は、EU加盟国の当局から必要数の「CBAM証書」を購入する形でEU排出量取引制度に対応した炭素価格を支払う。European Commission, ‘Carbon Border Adjustment Mechanism’, 28 March 2025,
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
103 農林水産省「EUの森林減少防止に関する規則への対応について」、2024年9月2日、
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/EUDR.html![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
104 JETRO(2024a)
105 European Commission, ‘The future of European competitiveness’, 9 September 2024,
https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
106 European Commission, ‘A Competitiveness Compass for the EU’, 29 January 2025,
https://commission.europa.eu/document/download/10017eb1-4722-4333-add2-e0ed18105a34_en![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
(3) 中国
2020年9月、中国は、国連総会において、2030年までにCO2排出量を減少に転じさせ、2060年に炭素中立を目指すと表明した。以降、中国は様々な気候関連政策を打ち出している。
2021年に発表した第14次五か年計画(2021~2025年)において、中国は、2025年までに2020年比で、GDP単位当たりのエネルギー消費量とCO2排出量をそれぞれ13.5%と18%引き下げるという数値目標を設定した。そして、2022年3月には、エネルギー関連政策の方針を示した「第14次五か年計画の現代エネルギー体系計画」を、2024年5月には、第14次五か年計画における目標の達成に向けた2024年と2025年の行動方針を定めた「2024-2025年省エネルギー・炭素削減行動方針案」をそれぞれ打ち出し、化石燃料消費の削減や再生可能エネルギーの活用などを推進している107。具体的には、砂漠地域での大規模風力発電所と太陽光発電所、洋上風力発電所、大型水力発電所の建設など、自然エネルギーを活用した発電所の建設を加速するほか、地域の特色に合わせてバイオエネルギーや水素エネルギーの開発も推進する108。
消費者向けのEV購入支援措置も引き続き実施されている。2023年6月、中国は、2014年より続く自動車購入税の減免措置の延長及び改定を発表した。これにより、2024年1月1日から2025年12月31日までに購入された新エネルギー車(EVやプラグインハイブリッド車等)は、1台当たり3万元を上限に自動車購入税が免除され、2026年1月1日から2027年12月31日までに購入された新エネルギー車は、1台当たり1万5,000元を上限に自動車購入税の50%が減税される109。さらに、2024年4月には、自動車の買い替えに対する補助金交付を発表した。消費者は、制度開始から2024年12月31日までに条件を満たす自動車の買い替えを行った場合、最高1万元の補助金を受給することができる。補助金の対象となる自動車は、中国政府が公表するリストに掲載された新エネルギー車又は排気量2.0リットル以下の燃料式乗用車である110。なお、本制度は2025年1月に更新され、2025年3月末現在では補助金額の上限が2万元となっている111。
その他、中国は、2021年7月より電力事業者を対象とした排出量取引制度を全国規模で導入した。制度開始当時の対象企業数は、年間CO2排出量が2.6万トン以上の石炭・ガス火力を有する約2,000社であった112。そして、2024年9月、「鉄鋼、セメント、電解アルミニウムを対象とした全国炭素排出量取引市場に関する作業計画(意見募集稿)」において、排出量取引制度の対象を、鉄鋼とセメント、電解アルミニウムへも拡大することを表明した。作業計画では、2024年~2026年は、対象業種への排出量取引制度の理解促進や排出量データの質の向上などに取り組み、2027年以降は、企業に割り当てる無償排出枠を縮小していく予定とされている113。EUのCBAMでは、購入するCBAM証書の量について、原産国で既に支払われた炭素価格分に応じた控除を受けることができることから、中国が排出量取引制度の拡大を進める背景には、CBAMの負担軽減も念頭に置かれているとの指摘もある114。
107 JETRO「加速する中国の炭素排出削減政策とビジネスチャンス」、2024年12月18日、
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2024/1101/983482b7dcbf39f1.html![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
108 JETRO「国務院、2024~2025年の省エネ・炭素削減行動プラン発表」、2024年6月12日、
https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/06/1a2ab3b564b86627.html![]() (2025年4月7日閲覧)。
(2025年4月7日閲覧)。
109 JETRO「新エネルギー車取得税の減免措置を2027年末まで延長」、2023年6月26日、
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/06/47d33451a8a22678.html![]() (2025年4月7日閲覧)。
(2025年4月7日閲覧)。
110 JETRO「乗用車の買い替え促進策を発表、最大1万元の補助金を支給」、2024年5月2日、
https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/05/f9a423f141ba2c52.html![]() (2025年4月7日閲覧)。
(2025年4月7日閲覧)。
111 ブルームバーグ「中国、乗用車買い替えの補助金制度更新-ハイブリッド車やEV対象」、2025年1月8日、
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-01-08/SPR5TMT1UM0W00![]() (2025年4月7日閲覧)。
(2025年4月7日閲覧)。
112 経済産業省(2023)
113 中国生態環境部, ‘关于公开征求《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案(征求意见稿)》意见的函’, 9 September 2024, https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202409/t20240909_1085452.html![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
ロイター「中国環境省、排出量取引の対象拡大へ EU炭素税を視野に」、2024年9月10日、
https://jp.reuters.com/markets/commodities/V74DWHCPWNMY3IWRG5WPMUS5VY-2024-09-10/![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
114 上野(2024)
5. 国際的な議論や取組
先述のとおり、国際場裏では貿易と環境の関連性は決して新しい論点ではない。同時に、近年のグローバルな環境課題の広がりや気候変動対策における各国・地域の取組の加速は、国際的な貿易と環境を巡る議論に新たな展開を起こしている。WTOの2022年世界貿易報告書は、気候変動と国際貿易をテーマとし、貿易及び貿易政策が低炭素製品・サービスへのアクセスを容易にすることや、イノベーションを加速させることなどを通じて、低炭素経済への移行を促進できると指摘した。同時に、各国政府がカーボンリーケージや国内産業の競争力低下を防止するために導入する貿易関連措置は、貿易摩擦を引き起こすとともに市場の不確実性を高めると警鐘を鳴らし、貿易に影響を与える気候・環境政策について国際協力を強化していくことが重要であると強調した115。以下では、WTO、OECD、APEC等の国際フォーラムや地域枠組み、二国間等における、グリーン移行の貿易側面に係る議論や取組を概観する。
115 WTO (2022)
(1) 環境物品サービス
環境物品サービスの貿易自由化は、先述のとおり、WTO設立後の2001年、ドーハ・ラウンド交渉開始を決めたドーハ閣僚宣言に交渉の立上げとCTESSの設置が盛り込まれ、CTESSにおいて関税削減・撤廃の対象となる環境物品リストに関する議論が行われた。しかし、ドーハ・ラウンド交渉全体が2008年に事実上膠着したために、WTOにおける多国間の環境物品サービス交渉も頓挫した。その後、環境物品の関税削減・撤廃の議論は、APECにて進展を見せた。2012年9月のAPEC首脳会議において、参加エコノミーは、2015年末までに環境物品54品目の実行関税率を5%以下に引き下げることに合意した。これには、再生可能エネルギー関連製品や汚水処理関連機材、大気汚染制御装置などが含まれる116。
これを受け、2012年11月、環境物品の自由化推進国・地域で形成する「環境フレンズ」メンバー(日本、米国、EU、韓国、台湾、シンガポール、カナダ、豪州、ニュージーランド、スイス、ノルウェー)は、WTOでの今後の環境物品自由化の交渉の進め方について議論を開始し、2014年7月には有志14加盟国・地域(日本、米国、EU、中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、カナダ、豪州、ニュージーランド、スイス、ノルウェー、コスタリカ)でEGA交渉を立ち上げた。有志国は2016年12月に交渉妥結を目指して閣僚会合を開催したが、対象品目に関する立場の懸隔が埋まらず、妥結には至らなかった。
近年のグローバルな環境課題に関する議論の高まりの中で、環境物品サービスについても新たな動きがある。上述のTESSDでは、環境物品サービスもテーマ別の四つのWGのうちの一つで作業が行われ、2024年2月のMC13で成果文書が発出された。環境物品サービスWGでは、環境物品サービスの貿易が気候変動への適応と緩和をどのように支援できるかについて、特に再生可能エネルギー分野(太陽光、風力、水力、グリーン水素、バイオ燃料)に焦点を当てて作業が行われた117。
環境物品サービスに関しては、貿易自由化にとどまらず幅広い普及促進を目的として、グリーン経済協定(Green Economy Agreement:以下、GEA)と呼ばれる二国間協定を締結する動きも見られる。GEAは、環境物品サービスの貿易や投資における非関税障壁を取り除き、低炭素排出技術の導入を加速することを目的としている。2022年10月、豪州とシンガポールの両政府は、世界初となるGEAを締結したと発表した。
インド太平洋地域における経済面での協力について議論する枠組みであるIPEFでも、同様の取組が見られる。2023年11月、米国で開催されたIPEF閣僚級会合及び首脳会合において、クリーン経済協定の交渉が実質妥結に至り、2024年10月に発効した。同協定には、主に「エネルギー安全保障及びクリーン経済への移行」、「産業及び輸送部門における温室効果ガス排出削減技術・解決策の促進」、「持続可能な土地、水及び海洋の解決策」、「クリーン経済への移行を可能にするインセンティブ・協力作業計画(CWP)」などに関する規定が盛り込まれている118。
116 外務省「世界貿易機関(WTO)における環境物品交渉(有志国・地域による共同発表)」、2014年1月24日、
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000536.html![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
117 WTO, ‘Trade and environmental sustainability’,
https://www.wto.org/english/tratop_e/tessd_e/tessd_e.htm![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
118 外務省「インド太平洋経済枠組み(IPEF)」、2024年10月16日、
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ipef.html![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
(2) 貿易関連気候措置
2021年7月に欧州委員会がCBAMの創設に関する規則案を公表して以降、WTOのCTEやTESSDなどの場でも、CBAMを含む貿易関連気候措置についての議論が活発化している。TESSDの貿易関連気候措置WGは、鉄鋼、アルミニウム、肥料、水素などの分野における炭素計測基準と脱炭素化措置の検討に重点を置きつつ、貿易関連気候措置の策定及び実施プロセスに関する意見交換を行っている。同WGは、2024年2月のMC13で発表した成果文書において、貿易関連気候措置を導入する際に各国政府が実施している透明性向上に関する取組や、外部ステークホルダーとの協議プロセスなどを共有した119。また、日本はCTEでの貿易関連気候措置に関する作業に貢献するため、2024年9月に提案文書を提出した120。そこでは、製品に含まれる炭素排出量の計測手法が各国ごとに多様化していくと、企業にとっての不要な貿易障壁になり得るとの認識の下、WTOにおけるガイダンス策定の可能性について提起している。
WTO以外の国際フォーラムでも、貿易関連気候措置の透明性向上と情報共有に関する作業が進んでいる。例えば、世界銀行のカーボンプライシングダッシュボードでは、世界各国が導入するカーボンプライシング措置の詳細を入手することができる121。また、OECDでは、2021年9月、コーマン事務総長が、炭素税(明示的炭素価格付け)や炭素価格に相当する措置(暗示的炭素価格付け)の最適な価格設定方法について合意する包括的枠組みを提案し、議論が進められている122。
119 WTO, Trade and environmental sustainability,
https://www.wto.org/english/tratop_e/tessd_e/tessd_e.htm![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
120 WTO, ‘Addressing trade-related climate measures at the WTO - Communication from Japan’, 25 September 2024,
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/CTE/W264.pdf&Open=True![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
121 World Bank, ‘State and Trends of Carbon Pricing Dashboard’, https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
122 環境省「資料1 ポリシーミックスとしてのカーボンプライシングの方向性」(カーボンプライシングの活用に関する小委員会(第20回)議事次第・配布資料)、2022年3月28日、https://www.env.go.jp/council/06earth/20_5.html![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
(3) 脱炭素基準の調和
炭素中立の実現に向けては、「産業の脱炭素化」、すなわち、産業が生産などの事業プロセスにおいて排出する温室効果ガスを削減することが重要である。とりわけ、製造工程において石炭由来のコークスを用いる鉄鋼業では、多くのCO2が排出されることから、日本を含む各国の鉄鋼企業は、炭素排出量を大幅に削減した「グリーンスチール」の市場投入を推進している。しかし、企業によって用いる技術が異なったり、国によって入手できる資源の状況が様々であったりすることなどから、何をもってグリーンスチールと見なすかという共通の基準が存在せず、これまで、鉄鋼業の脱炭素化を目指す様々な国際的なイニシアティブが、炭素排出量の測定方法やグリーンスチールの定義などについて議論を重ねてきた123。
こうした中、2021年5月に、G7が、当時の議長国である英国と米国の主導の下「産業脱炭素化アジェンダ(IDA)」を立ち上げ、産業の脱炭素化に関連する規制や基準、投資、調達、共同研究について協力を強化すると表明した124。翌2022年のG7気候・エネルギー・環境大臣会合では、G7議長国のドイツの要請によりIEAが作成した報告書「Achieving Net Zero Heavy Industry Sectors in G7 Members」が取り上げられた。同報告書は、CO2排出量が多い鉄鋼分野とセメント分野について、「ニア・ゼロ・エミッション素材」の定義を提案するものである。G7気候・エネルギー・環境大臣は、閣僚声明で、「当該報告書における諸定義を、(中略)ニア・ゼロ・エミッションの鉄鋼及びセメント生産の野心的な一般的定義に関する共通理解に至るための確かな出発点として認識する」「我々は、今後の産業脱炭素化のためのプロジェクトにおいて、諸定義を整合させるよう取り組んでいく」などと述べた125。
そして、日本が議長国を務めた2023年のG7気候・エネルギー・環境大臣会合では、附属文書「産業の脱炭素化アジェンダに関する結論」がまとめられ、具体的なアクションとして、鉄鋼の生産及び製品排出量のグローバルなデータ収集に着手することや、削減貢献量126の測定に関する国際基準について更なる議論を行っていくことなどが示された127。なお、2024年の閣僚声明においても、排出量測定手法やニア・ゼロ・エミッション素材の共通定義に関する国際標準などにG7が積極的に関与していることが強調されている128。
123 経済産業省「鉄鋼業の脱炭素化に向けた世界の取り組み(前編)~「グリーンスチール」とは何か?」、2023年8月10日、https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/green_steel_01.html![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
経済産業省「鉄鋼業の脱炭素化に向けた世界の取り組み(後編)~排出量の測定手法の共通化を目指して」、2023年8月24日、https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/green_steel_02.html![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
124 GOV.UK, ‘G7 Climate and Environment Ministers' meeting, May 2021: Industrial Decarbonisation Agenda (IDA)’, 8 June 2021, https://www.gov.uk/government/publications/g7-climate-and-environment-ministers-meeting-may-2021-industrial-decarbonisation-agenda-ida![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
125 経済産業省「細田副大臣がG7気候・エネルギー・環境大臣会合に出席しました」、2022年5月30日、
https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220530005/20220530005.html![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
126 削減貢献量とは、グリーン製品・サービスの普及を通じ、企業が社会全体の排出削減にどれだけ貢献したかという「貢献量」を算定したもの。
127 経済産業省「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」、
https://www.meti.go.jp/information/g7hirosima/energy/![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
128 経済産業省「齋藤経済産業大臣がG7気候・エネルギー・環境大臣会合に出席しました」、2024年5月1日、
https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240501001/20240501001.html![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
(4) 貿易と循環経済
資源を持続可能な形で最大限活用することで、廃棄物を減らし、資源枯渇にも対処する、環境に優しい「循環経済」への移行は、グローバルな環境課題の一つになっている。従来の経済システムは、大量生産から大量消費、大量廃棄への一方通行となる「線形経済」であった。これに対し、循環経済は、生産段階から再利用などを視野に入れて設計し、新しい資源の使用や消費をできるだけ抑えるなど、あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、サービスや製品に最大限の付加価値を付けていくシステムを意味する。そこでは、環境配慮設計や修理などによる製品の長寿命化、再利用、リサイクルが促進され、資源が効率的かつ循環的に利用され、天然資源の利用や廃棄物が減少することとなる。その結果、資源の採掘、運搬、加工から製品の製造、廃棄、リサイクルに至るライフサイクル全体での環境負荷が低減される129。グリーン移行に必要な重要鉱物を含む資源需要が世界的に増加している中、循環経済への移行は世界各国にとって重要な課題であり、各国・地域で様々な政策が打ち出されている。
製品のバリューチェーンは国境を越えてつながっていることから、循環経済は貿易と非常に密接にかかわっている。Yamaguchiによると、循環経済と貿易のつながりは以下の図のとおり整理される(第II-1-3-4図)。循環経済に影響を与える財貿易として、原材料や中間財、最終製品といったサプライチェーン内の貿易と、廃棄物やスクラップ、二次原材料、中古品といった使用済み製品の貿易の2系統がある。これに加え、循環経済に影響を与えるサービス貿易として、設計、保守、修理、製品サービス・システムといった様々なサービスの越境取引が挙げられる130。
第Ⅱ-1-3-4図 貿易と循環経済のつながり
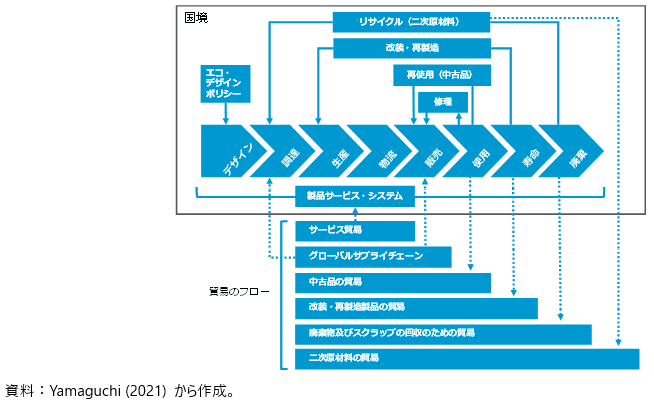
循環経済と貿易のかかわりが深いことから、各国が導入する政策や取組を協調させていくことが、循環経済への移行を円滑に進めるための鍵となる。TESSDの循環経済WGでは、循環経済の貿易側面に係る課題について認識を共有するため、電機電子機器廃棄物(E-waste)等の特定分野ごとの議論を通じて、貿易関連課題のマッピング作業を行った。2024年2月のMC13で発表した成果文書では、統計データや製品のトレーサビリティを含む透明性、製品デザインや拡大生産者責任(EPR)を含む規制基準、循環経済を促す貿易円滑化、適切な廃棄物管理、能力構築と技術支援、技術を含む貿易関連の国際協力を課題として提示している。
また、例えばASEANは、2021年10月に開催された第20回ASEAN経済共同体理事会において、「ASEAN経済共同体(AEC)のための循環経済フレームワーク」を採択した131。同フレームワークは、循環経済への移行に向けた五つの戦略的優先事項として、「循環型製品・サービスの基準調和と相互承認」、「循環型製品・サービスにおける貿易自由化と貿易円滑化」、「イノベーション、デジタル化、新興技術/グリーン技術の役割強化」、「競争力のあるサステナブル・ファイナンスと革新的なESG投資132」、「エネルギー及びその他の資源の効率的利用」を挙げている。ASEANは、この五つの戦略的優先事項の下、循環型製品・サービスの規格をASEAN域内の相互認証協定(MRA)などと調和させることや、循環型製品・サービスを巡る貿易障壁を最小限に抑えること、そして、民間セクターと学界、各国政府間の対話を促し連携を強化していくことなどをうたっている。
129 環境省(2024)
130 Yamaguchi (2021)
131 ASEAN, ‘ASEAN adopts framework for Circular Economy’, 21 October 2021, https://asean.org/asean-adopts-framework-for-circular-economy/![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
132 ESG投資とは、環境・社会・ガバナンスの要素を考慮した投資手法のこと。