第4節 サプライチェーンの強靱性と重要鉱物
企業が直面するサプライチェーンの途絶リスクは、昨今ますます多様化している。自然災害、地域紛争、パンデミック、投資先や調達先の政情不安、政策変更に伴う事業環境の急変や、気候変動や人権等の持続可能性への対応も課題となっている。国際アジェンダとしてのサプライチェーン強靱化は、コロナ禍後に注目されるようになった。2021年のG7首脳声明及び貿易大臣声明133では、コロナショックからの回復におけるサプライチェーン強靱化の重要性に言及され、その後も継続的に議論が行われている。
本節では、我が国におけるサプライチェーン強靱化に関する経緯、主要国や国際フォーラムにおける議論と取組の進展、近年注目されている重要鉱物を巡るサプライチェーン強靱化についての動向を概観する。
133 外務省「G7カービスベイ首脳コミュニケ(和訳)」、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100200083.pdf![]() (2025年6月5日閲覧)。外務省「G7貿易大臣コミュニケ(仮訳)」、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100195648.pdf
(2025年6月5日閲覧)。外務省「G7貿易大臣コミュニケ(仮訳)」、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100195648.pdf![]() (2025年6月5日閲覧)。
(2025年6月5日閲覧)。
1. サプライチェーン強靱化の経緯
(1) サプライチェーンの強靱性の定義
OECDは、サプライチェーンの強靱性を、サプライチェーンが混乱した後に通常のオペレーションに戻る能力と定義し、混乱の例として、紛争、戦争、極端な気象現象による自然災害、継続的な地政学的緊張、規制の不確実性、景気変動、サイバー攻撃の脅威、これらが物流及び輸送に圧力を与える結果としての頻繁な混雑、労働力やコンテナの不足、価格の上昇を挙げている134。企業レベルでは、サプライチェーンは取引先等との関係構築のコストをかけて生産性向上をもたらすものと想定されるが、混乱時の変化への脆弱性や情報収集の困難さ、代替性・多様性の確保等が強靱化の課題となり得る135。政府にとっては、そうした企業のサプライチェーン強靱化の課題対応を支援するだけでなく、経済全体としての安定供給リスクに対処することも重要な政策課題と認識されるようになった。2022年に成立した我が国の経済安全保障推進法では、国民の生存に必要不可欠な又は広く国民生活・経済活動が依拠している重要な物資について、特定重要物資として指定し、その安定供給確保に取り組む民間事業者等を支援することを通じて、特定重要物資のサプライチェーンの強靱化を図ることとしている136。
134 OECD (2025)
135 戸堂(2025)
136 内閣府「サプライチェーン強靱化の取組(重要物資の安定的な供給の確保に関する制度)」、
https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/supply_chain/supply_chain.html![]() (2025年6月5日閲覧)。
(2025年6月5日閲覧)。
(2) 我が国における取組の経緯
我が国では、コロナ禍以前からサプライチェーンリスクへの認識が高まり、取組が行われてきた。伝統的には、1970年代の石油ショックを始めとして、我が国の資源・燃料調達に関する脆弱性は強く認識されてきた。それに加えて、2010年の中国によるレアアース輸出規制を契機として、原料供給などの面で中国に大きく依存することのリスクが認識された。輸出規制への対応として、①代替供給源となる上流開発プロジェクトの形成、②研究開発による省資源化の推進、③中国政府の輸出規制に対するWTO提訴による措置の停止への働きかけ等の取組を実施した結果、レアアース全体で我が国の輸入に占める中国の割合は、2009年の85%から2020年には58%まで低減した137。
2011年に発生した東日本大震災では、多くの工場が被災し、中でも、主要な半導体製造工場の一部が被災したことにより、自動車を始めとした多くの最終製品メーカーにおいて自社製品の製造に必要な半導体を入手することができず、減産を余儀なくされることとなった。これをきっかけとして、平時の効率性のみを追求するのではなく、有事の際にも生産能力を維持できるよう、安全在庫の確保などによりレジリエンスを強化することの重要性が認識された138。また、同年のタイの洪水など、大規模な自然災害のたびに、部素材の供給途絶による減産や生産停止を経験する中で、事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)を策定する企業が増加した。
2020年のコロナ禍には、世界的にサプライチェーンの寸断が見られ、特に中国からの部材の供給が寸断され、日本国内での生産が滞ったことで、海外からの調達に関するリスクへの懸念が高まった。また、医療用品のような緊急物資については、需要が爆発的に拡大する中で物不足が見られた。これは、集中生産による経済性・効率性と供給途絶リスクへの対応力とのバランスを再検討する必要性を認識させるものであった。さらに、2022年のロシアによるウクライナ侵略では、ロシアからの輸入依存度が高いエネルギーや資源などの戦略物資についてサプライチェーンの供給リスクへの認識がこれまで以上に高まった。
加えて、近年、米中対立などの地政学的対立を背景とした、経済的威圧と呼ばれる、重要物資の輸出制限、関税引上げ、通関拒否等の経済的圧力を加えることにより、他国の政策を自国に有利な形に変更させようとする試みに対する懸念が高まっている。経済的威圧の手段として不買運動や輸入制限が行われる事例もあり、企業にとっては調達先の途絶に加えて販売先の途絶もリスクとなっている139。
このような状況に対し、政府は企業の海外生産拠点の多元化を支援するとともに、国内の生産拠点等の整備を支援してきた。2022年に成立した我が国の経済安全保障推進法では、四本柱の一つとしてサプライチェーン強靱化にかかる制度(重要物資の安定的な供給の確保に関する制度)を創設し、同法に基づき、特定重要物資を指定し140、民間事業者が行う生産設備への投資や研究開発等の取組を支援している。
137 経済産業省「資料3 鉱物政策を巡る状況について」(第1回産業構造審議会製造産業分科会鉱業小委員会資料)、2024年10月28日、https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/mining/pdf/001_03_00.pdf![]() (2025年6月5日閲覧)。
(2025年6月5日閲覧)。
138 経済産業省(2021)
139 日本経済新聞「経済的威圧にどう向き合う㊤ 久野新 亜細亜大学教授」、2023年9月13日、朝刊29面。
140 2025年3月末時点で、特定重要物資として、抗菌性物質製剤、肥料、永久磁石、工作機械・産業用ロボット、航空機の部品、半導体、蓄電池、クラウドプログラム、天然ガス、重要鉱物、船舶の部品、先端電子部品(コンデンサー及びろ波器)が指定されている。
2. サプライチェーンの強靱化のための各国政策の進展
ここでは近年の各国及び国際的なサプライチェーン強靱化の取組の進展を整理する。各国では、生産拠点の集中度が高くサプライチェーンの途絶リスクが大きい品目や安全保障上重要な品目について、具体的なリスクの特定や、それを踏まえた産業政策による産業基盤の強化など、サプライチェーン強靱化のための政策が展開されている。また、強靱なサプライチェーンは一国で実現できるものではなく、経済的威圧への対応を含め、同盟国・同志国を始めとした国際的な連携が不可欠であり、G7を始めとした様々なフォーラムで議論・取組が行われている。
(1) 米国
米国では、2021年2月にバイデン大統領により署名された大統領令(Executive Order 14017)に基づき、半導体、大容量電池、重要鉱物・素材、医薬品といった重要品目の調査を行うなど、サプライチェーンの強靱化に取り組んできた。2022年8月には、気候変動対策への投資を目的とする「インフレ削減法」と、半導体製造等を支援するための「CHIPS及び科学法」が成立し、国内投資促進やサプライチェーン強靱化へ重点を置く政策が展開された。「インフレ削減法」は、気候変動対策へ約3,700億ドルを投資し、供給サイド(民間企業等)と需要サイド(消費者等)への税額控除などを通じてクリーンエネルギーのコストを引き下げ、同分野への民間投資を加速させるとともに、重要なサプライチェーンを強化することを目的としている141。「CHIPS及び科学法」は、国内の半導体産業の振興を目的として、半導体製造施設などの建設や拡張などを行う企業に対して、最大390億ドルの助成と25%の投資税額控除を規定している。
バイデン政権は、2024年12月に発表された「2021~2024年サプライチェーンレビュー」報告書において、サプライチェーンを強靱化する上で、過去4年間で、①混乱への対応:新型コロナウイルスの感染拡大によるサプライチェーンの混乱に対し、サプライチェーン混乱対策タスクフォース(SCDTF)を立ち上げ、連邦政府、州政府、民間企業などとの連携を強化し混乱を解消、②インフラと製造業への投資とコスト削減:米国政府が2021年1月以降に行った投資が、1兆ドル超の民間投資を促進し、工場新設、製造業の雇用創出に貢献、③非市場的政策と慣行(NMPP)への対応:国家による過剰な補助金など、公正な競争環境を阻害するNMPPへの対応として、一部品目の関税率の引上げ142、という大きく3点が行われたと総括した143。
重要鉱物に関しては、内務省が「重要鉱物」を指定し、エネルギー省がエネルギー転換に係る原材料を「重要原材料」として指定し、各種法律に基づく支援を実施してきた。具体的には、バイデン政権下において、上述のインフレ削減法によるバッテリーや鉱物の生産設備投資に対する税額控除や、国防生産法による重希土類分離精製施設やグラファイト鉱山及び負極材製造施設の建設支援、インフラ投資雇用法によるバッテリー製造に対する助成金措置などを実施してきた144。
2025年1月に就任したトランプ大統領は、同年3月、国内での鉱物生産の拡大に向けた大統領令に署名した145。鉱物生産の優先プロジェクトの特定及び許可の迅速化、鉱物が埋蔵されている連邦政府所有地のリスト作成、国防生産法を活用した事業資金の融資等により、鉱物の国内生産を促進する内容となっている。
141 2025年1月に署名されたトランプ大統領による大統領令において、インフレ削減法で割り当てられた資金の支出を即時停止し、90日以内にレビューを提出することとされた。White House, ‘Unleashing American Energy’, 20 January 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/unleashing-american-energy/![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
142 通商法301条に基づき、鉄鋼・アルミ、半導体、EV、EV用リチウムイオン電池等に対する対中追加関税の引上げを実施。
143 JETRO「バイデン米政権「2021~2024年サプライチェーンレビュー」報告書を発表、通商法の更新を提案」、2024年12月20日、https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/12/9e433ace2ce19dd6.html![]() (2025年2月28日閲覧)。
(2025年2月28日閲覧)。
144 2025年1月に署名されたトランプ大統領による大統領令において、インフレ削減法とインフラ投資・雇用法で割り当てられた資金の支出を即時停止し、各機関は90日以内にレビューを提出することとされた。White House, ‘Unleashing American Energy’, 20 January 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/unleashing-american-energy/![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
145 White House, 'Immediate Measures to Increase American Mineral Production', 20 March 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/immediate-measures-to-increase-american-mineral-production/![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
(2) EU
EUは、重要原材料の多くを中国などからの輸入に依存していることから、サプライチェーンの多様化とリスクの軽減を急いでおり、2023年2月に発表されたグリーン・ディール産業計画の一環として、脱炭素化に貢献するクリーン技術や重要鉱物の域外依存からの脱却が進められている。2024年6月に発効したネット・ゼロ産業法は、ネット・ゼロ技術のEU域内での生産能力を高めることを目的としており、2030年までにEU域内需要の40%以上を満たすことを目標としている146。2024年5月に発効した重要原材料法は、重要原材料の安全かつ持続可能な供給を確保することを目的としており、特に戦略的重要性が高い「戦略的原材料」については、2030年までにEU域内生産能力の確保と供給元の多様化を実現するために、域内年間消費量の最低10%を域内で採掘し、同40%を域内で加工し、同25%を域内でリサイクルした原材料で賄うという目標が設定されている147。
半導体分野では、EU域内の半導体エコシステム強化を目的とした欧州半導体法が2023年9月に発効した。域内半導体産業への総額430億ユーロの官民投資により、EUの半導体分野における世界市場シェアを現在の10%から2030年までに20%以上へ引き上げることを目指している148。
また、2023年6月に発表されたEU初の「経済安全保障戦略」の下、欧州委員会は加盟国とともに、重要サプライチェーンの分析を実施し、リスクレベルの特定を進めている149。2023年10月には、欧州委員会はリスク分析の対象となる10の技術分野を公表し、うち先端半導体技術、人工知能技術、量子技術、バイオテクノロジーの4分野から着手し、加盟国と共同でリスク評価を実施するとした150。
経済的威圧への対応としては、反威圧措置(ACI)規則を制定している(2023年12月発効)。EU又はEU加盟国に対し、EU域外の第三国による経済的威圧が行われる場合であって、協議等によっても威圧の中止に至らない場合に、最終的な手段として、対抗措置(関税引上げ、政府調達からの排除、輸出制限等の協定上の義務の停止等の措置を含む。)を発動するための手続や基準等を規定し、威圧の抑止やその影響打ち消しを図る制度となっている。
146 European Commission, ‘The Net-Zero Industry Act: Making the EU the home of clean technologies manufacturing and green jobs’, https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/sustainability/net-zero-industry-act_en![]() (Accessed 28 February 2025).
(Accessed 28 February 2025).
147 European Commission, ‘EU secures access to diversified, affordable, and sustainable supply of critical raw materials’,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2748![]() (Accessed 28 February 2025).
(Accessed 28 February 2025).
148 European Commission, ‘European Chips Act’, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-chips-act![]() (Accessed 28 February 2025).
(Accessed 28 February 2025).
149 European Commission, ‘An EU approach to enhance economic security’, 20 January 2023,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_3358![]() (Accessed 28 February 2025).
(Accessed 28 February 2025).
150 European Commission, ‘Commission recommends carrying out risk assessments on four critical technology areas: advanced semiconductors, artificial intelligence, quantum, biotechnologies’, 3 October 2023,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4735![]() (Accessed 28 February 2025).
(Accessed 28 February 2025).
(3) 中国
中国は、対外開放路線を継続しつつ(国際循環)、内需を拡大しながら(国内大循環)、自国の巨大市場の魅力により諸外国の投資・技術を引き付けるという「双循環政策」を第14次五か年計画(2021~2025年)で打ち出している。「自主的・コントロール可能なサプライチェーンの能力強化」のため、サプライチェーンの主要部分は国内にとどめておき、外国からの技術移転を図るとともに、国家ファンドや標準政策を駆使し、先進的なコア技術の国産化を推進している。外国企業の中国依存を強化しつつ、自己完結型産業チェーンの確立のために脆弱部分を重点的に補強することで、サプライチェーン断絶に対する抑止力を構築している。
2024年3月の全国人民代表大会では「新たな質の生産力」の発展を加速させることを表明し、具体的な取組として、産業チェーン及びサプライチェーンの最適化・高度化の推進や、新興産業と未来産業の育成などが挙げられた。2024年7月の第20期中国共産党中央委員会第三回全体会議(三中全会)で採択された「改革のさらなる深化と中国式現代化の促進に関する決定」では、産業チェーン及びサプライチェーンの強靱性及び安全性を向上する制度を整備するとされた。
3. 国際的な取組の現状
(1) G7
G7では、2021年の首脳声明及び貿易大臣声明で、コロナショックからの回復におけるサプライチェーン強靱化の重要性に言及され、その後も継続的に議論が行われている。2023年5月のG7 広島サミットでは、「経済的強靱性及び経済安全保障に関するG7首脳声明」を採択し、①透明性、②多様性、③安全性、④持続可能性、及び⑤信頼性からなる「強靱で信頼性のあるサプライチェーンに関する原則」が、G7内外の信頼できるパートナー国との間で強靱なサプライチェーンネットワークを構築及び強化する上で不可欠な原則であることを確認した。また、経済的威圧に対する共同の評価、準備、抑止及び対応を強化するため、「経済的威圧に対する調整プラットフォーム」を立ち上げ、連携を強化していくとされた。調整プラットフォームの下、早期警戒や迅速な情報共有等を行い、適切な場合には、被害を受けた国等を支援すべく協調していくこととされた。
鉱物資源分野では、2023年4月に札幌で行われたG7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合において、世界中で需要が増加している重要鉱物に関する課題を克服していくための「重要鉱物セキュリティのための5ポイントプラン」が合意され、「長期的な需給予測」、「責任ある資源・サプライチェーンの開発」、「更なるリサイクルと能力の共有」、「技術革新による省資源」、「供給障害への備え」に、G7各国が協調して取り組んでいくとされた。
2024年3月のG7産業・技術・デジタル大臣会合では、半導体等の重要物資のサプライチェーン強靱化について議論が行われた。特にデジタル産業において、グローバル・サプライチェーンの強靱性を追求するために協力して取り組んでいくことの重要性を確認し、G7メンバー間の情報交換を促進し、ベストプラクティスを共有することを目的とした半導体コンタクト(PoC)グループを設立した。
(2) インド太平洋経済枠組み(IPEF)
インド太平洋経済枠組み (IPEF) の四つの柱のうちの一つとして、2023年11月に米国にて開催された閣僚級会合において、IPEFサプライチェーン協定が署名され、2024年2月に発効した。同協定では、サプライチェーン途絶時の影響が大きな重要セクター・物資を各国が特定し、三か国以上が通報した重要分野又は重要物品の強靱性と競争力を向上させるための勧告を提供する行動計画を策定することや、サプライチェーンの途絶の際の緊急の連絡経路として機能するIPEFサプライチェーン危機対応ネットワークの設置等が定められた。実際にサプライチェーンの途絶に直面した国は、締約国との間での情報共有、協力を進めることが可能となる。また、閣僚会合後に開催された首脳会合では、IPEF メンバーの重要鉱物サプライチェーンの強化に向けた緊密な協力関係を醸成することを目的とした「IPEF重要鉱物対話」の立上げに合意した。
2024年9月には、IPEFサプライチェーン協定の下に設置されているサプライチェーン協議会と危機対応ネットワークの対面での初会合を開催し、半導体、化学品、バッテリーに用いる重要鉱物、ヘルスケアに関する四つの行動計画チームが設置された。日本は危機対応ネットワークの副議長を務めており、危機対応ネットワーク会合では、サプライチェーン途絶の危機を想定した机上演習が実施された。
(3) 日米豪印
2022年5月の首脳会合において、グローバルな半導体サプライチェーンにおける日米豪印の能力及び脆弱性をマッピングし、多様で競争力のある半導体市場を実現するため、補完的な強みを一層活用することを決定した。同会合では「重要技術サプライチェーンに関する原則の共通声明」を発表した。2023年5月の首脳会合において、多様で、安全で、透明かつ強靱なクリーンエネルギー・サプライチェーンを促進し、持続可能かつ包摂的なクリーンエネルギーへの移行に資するために、「インド太平洋におけるクリーンエネルギー・サプライチェーンに関する原則声明」を発表した。
(4) サプライチェーン強靱化イニシアティブ(SCRI)
2021年4月に、インド太平洋地域におけるサプライチェーンの混乱に日豪印三か国で協力して対応するため、日豪印三か国の貿易大臣によってサプライチェーン強靱化イニシアティブ(SCRI)が立ち上げられた。マッチングイベントの開催や各国のベストプラクティス共有等のサプライチェーン強靱化に向けた取組を実施しており、地域大のサプライチェーン原則の策定や、サプライチェーン強靱化に資する共同プロジェクトの実施、各国の産学官との連携等に取り組んでいる。
(5) 日米韓商務・産業大臣会合
日米韓三か国は、2023年8月の首脳会合での合意を踏まえ、2024年6月、初の商務・産業大臣会合を開催し、半導体や蓄電池を含む重要分野におけるサプライチェーン強靱化で協力していくことで一致した。会合では、重要・新興技術等の協力、サプライチェーン強靱化、公平な競争条件、クリーンエネルギー等の経済分野における三か国の連携強化に向けて議論するとともに、半導体やAI、重要鉱物、クリーンエネルギー等の個別分野における協力について、共同声明を発出した。
(6) 鉱物安全保障パートナーシップ(MSP)
クリーンエネルギー移行に不可欠な重要鉱物資源(ニッケル、コバルト、レアアース等)のサプライチェーン強靱化を確保するため、米国の主導により、2022年6月に「鉱物安全保障パートナーシップ(MSP)」が立ち上げられた。G7、豪州、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、エストニア、インド、韓国の15メンバーが参加している(2024年11月時点)。①情報共有と協力、②投資ネットワーク、③環境・社会・ガバナンス(ESG)基準の引上げ、④リサイクルとリユースという四つの柱の下で具体的な活動を行っており、環境負荷が高い重要鉱物精錬過程の寡占状況に対処するため、高いESG基準の浸透を図り、同基準による戦略的な鉱山開発・精錬・加工、投資の呼び込みを目指している。
4. 重要鉱物を巡るサプライチェーン強靱化
サプライチェーン強靱化の議論の中でも、近年特に注目を集めているのが重要鉱物を巡る問題である。レアメタル等の重要鉱物151は、リチウムイオン電池、高性能モーター、風力発電のタービン、半導体などに用いられ、グリーン・デジタル等の先端技術・産業において必要不可欠である。2050 年の炭素中立実現に向けて、蓄電池・モーター・半導体等の部品の生産が拡大することが見込まれ、その生産に必要不可欠な鉱物資源の需要も急拡大すると予測される。2040年までの20年間で、クリーンエネルギー技術用途に限定すると、リチウムは約13倍、コバルトやニッケルも6倍以上の需要となるとのIEAの予測もある152。また、EVやAI・データセンター等のGX(グリーン・トランスフォーメーション)・DX(デジタル・トランスフォーメーション)の進展に伴う電力需要の増加により、銅の需要が増加し、世界的な需要の増加が見込まれている153。
重要鉱物を産出する国にはしばしば偏りがあり、政情不安が懸念される国から産出されるものも多い。また、鉄やアルミなどのベースメタルに比べて市場規模が小さいため、価格変動が大きいという特徴がある。こうした特徴に加えて、一部の重要鉱物では将来的に需要が供給を上回る「需給ギャップ」が生じ、世界各国との間で資源獲得競争が激化することも予想されており、安定供給確保が課題となっている154。
151 重要鉱物(critical mineral)の定義は統一されておらず各国で異なる。リチウムなどのレアメタルに加え、銅などのベースメタルも含まれることがある。
152 IEA (2021) のSTEPSシナリオ(公表政策シナリオ)によると、2040年鉱物資源(クリーンエネルギー技術用途に限定)の需要は、2020年比で、コバルト 6.4倍、リチウム12.8倍、ニッケル 6.5倍、レアアース 3.4倍となると予想されている。
153 経済産業省「資料3 鉱物政策を巡る状況について」(第1回産業構造審議会製造産業分科会鉱業小委員会資料)、2024年10月28日、https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/mining/pdf/001_03_00.pdf![]() (2025年6月5日閲覧)。
(2025年6月5日閲覧)。
154 経済産業省「重要鉱物に係る安定供給確保を図るための取組方針」(令和5年1月19日、令和6年3月29日改定)、https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/metal/torikumihoshin.pdf![]() (2025年6月5日閲覧)。
(2025年6月5日閲覧)。
(1) 重要鉱物の偏在の状況
多くの重要鉱物は埋蔵や生産が特定国に偏在しており、強靱なサプライチェーン構築の課題となっている。このサプライチェーンにおける依存は、鉱物の産出国の集中だけでなく、製錬工程が特定国に偏っていることが大きな特徴となっている(第II-1-4-1図)。製錬工程はコストの安い国や環境規制の緩い国に集中する傾向があり、特に中国への集中度が高い。
第Ⅱ-1-4-1図 重要鉱物の採掘及び精錬・加工シェア
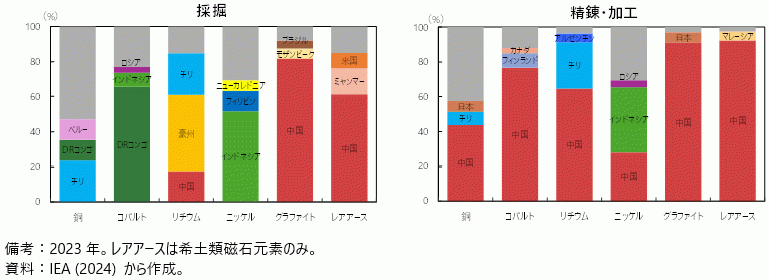
また、採掘が行われる場所と企業の本社所在地の間には相違がある。例えば、ニッケルについては、52%がインドネシアで採掘されているが、本社所在地155の観点から見ると、全体の約40%を中国企業が占めており、インドネシアの企業の割合は10%未満である。コバルトに関しては、鉱山の大部分がコンゴ民主共和国に位置しているが、欧州の企業や中国企業がそれぞれ供給の3分の1を占めている156。
高い生産の集中度は、サプライチェーンが極端な天候、貿易紛争、地政学的要因からの混乱に対してより脆弱になることを意味し、生産国からの供給が途絶した場合に、供給の大幅な不足が生じるリスクが高まる。また、サプライチェーンの寡占化は、特定の国や企業の市場支配力の強化につながり、価格支配や生産調整といったリスクも懸念される。
155 複数の企業により運営されるプロジェクトでは、最大のシェアを占める企業の所在地。
156 IEA (2024)
(2) 資源国による鉱物資源に対する管理強化
IRENAは、鉱物資源を巡る地政学的リスクとして、①外的ショック(戦争、災害、パンデミック等)、②資源ナショナリズム(収用、外国投資規制等)、③輸出規制(輸出禁止、輸出割当て、輸出税等)、④鉱物カルテル(生産調整、プライシング、市場割当て等)、⑤政治的不安定・社会不安(労働ストライキ、暴力等)、⑥市場操作(ショートスクイーズ、買占め等)の六つを挙げている157。ここでは、資源ナショナリズムや輸出規制等の資源国による鉱物資源に対する管理強化の動きについて見ていく。
近年、一部の資源保有国では、鉱物資源に対する国家の管理を強化し、採掘からの利益の拡大や、高付加価値化を目的とした措置を講じるなど、資源ナショナリズムの高まりが見られる(第II-1-4-2表)。具体的措置としては、鉱物産業の国有化・収用、輸出規制、税制やロイヤルティの強化、外国投資規制などが含まれる。このような資源ナショナリズムの動きは、重要鉱物の世界的な供給に影響を与え、原材料供給確保に対する懸念を引き起こす可能性がある。
第Ⅱ-1-4-2表 資源国による高付加価値化政策・資源ナショナリズムの動向
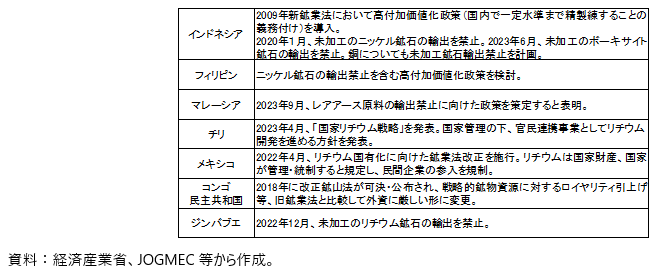
また、中国では、2024年10月にレアアース管理条例が施行され、サプライチェーン全体でレアアース産業の管理を強化している。同条例は、レアアース資源保護の強化、レアアースに対する管理体制の整備、レアアース産業の質の高い発展に向けた取組、レアアース産業チェーン全体の管理体系の整備、管理措置と不法行為責任の明確化などについて具体的に定めており、レアアースの国家所有についても明記している。
OECDの報告書によると、産業用原材料158に対して世界で導入された輸出規制の件数は、2009年と比べ、2022年に5倍以上に拡大した(第II-1-4-3図)。輸出規制の手段としては、輸出税、ライセンス要件の導入件数が大勢を占めているが、輸出禁止の導入件数が2020年以降、大幅に増加し、2022年には導入件数で首位となるなど、手段として多用される傾向が近年強まっている159。2009年から2022年にかけて導入された新たな輸出規制のうち、中国、インド、ベトナム、アルゼンチン、サウジアラビアが上位5か国であり、国別の導入措置数の半分以上を占めている(第II-1-4-4図)。
第Ⅱ-1-4-3図 産業用原材料に対する輸出規制件数
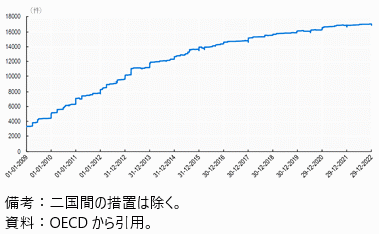
第Ⅱ-1-4-4図 産業用原材料に対する輸出規制措置の国別シェア(2009-2022年)
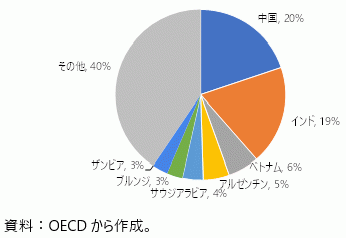
特に、日本が多くのレアメタル・レアアースの精錬工程を依存する中国は、近年、様々な貿易管理を実施している。2023年8月には半導体材料に用いられるガリウム及びゲルマニウム関連品目について、同年12月には車載用電池に用いられる黒鉛関連品目について輸出管理措置を開始した。2024年8月には、半導体材料等に用いられるアンチモン関連品目について輸出管理を開始した。2025年2月には、タングステン、テルル、ビスマス、モリブデン、インジウムの関連品目について、同年4月にはサマリウム、ガドリニウム等の7種のレアアース関連製品について輸出管理措置を開始した。輸出に政府の許可が必要な物質が増えているが、その実施には不透明性があり、サプライチェーンの不確実性が高まっている。
第Ⅱ-1-4-5図 ガリウム、ゲルマニウム、アンチモンの生産シェア
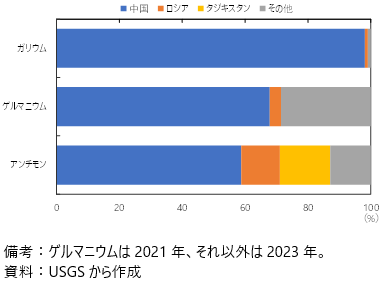
第Ⅱ-1-4-6図 中国のアンチモン製品の輸出推移
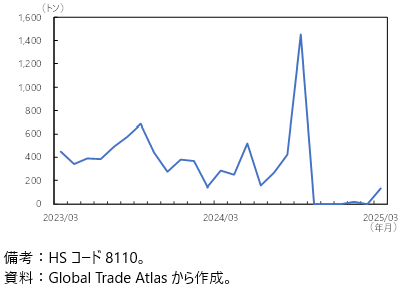
157 IRENA (2023)
158 58種の鉱物・金属及びそれらの金属廃棄物・スクラップ、6種の木製品が対象。
159 OECD (2024)