第5節 産業政策と国際経済秩序
近年、デジタル化がもたらす社会経済の変化、グリーン移行やサプライチェーン強靱化の必要性などを背景に、そうした変化を国内の経済発展、イノベーション、産業集積や雇用につなげるための産業政策への関心が国内外で高まっている。他方、一部の産業政策が国際的な負の外部性を生じ得ることは、過去にも指摘され、議論が積み重ねられてきた。実際、その一部はWTO協定を始めとする通商ルールの中で対処されている。他方、冷戦後のグローバル化が西側諸国だけでなく幅広い国々を取り込んで拡大・深化したことは、それまでには見られなかった市場歪曲的措置、非商業的な国有企業の行動、経済的依存関係の武器化といった新たな課題を提起した。しかし、そうした産業政策を巡る動向とルールベースの国際経済秩序との関係については、まだ必ずしも議論が深まっていない。
本節では、産業政策と貿易を巡る歴史的経緯と学術的議論、通商ルールとの関係について整理する。その上で、新たな産業政策論の展開と米EUの産業政策の潮流から、近年の経済社会的課題に対処する産業政策の役割について検討する。最後に、ルールベースの国際経済秩序の観点から、産業政策と通商ルールとの関係について展望する。
1. 産業政策と貿易を巡る歴史的経緯
近代国家の成立以降、欧米を含む多くの国々が、産業発展の過程でそれぞれの産業政策を実施し、成功と失敗が積み重ねられてきた。第二次世界大戦後、西側諸国で自由主義市場経済が制度化されると、産業政策は政府による非効率な市場介入になりやすいとの議論が強まった。しかし、1970年代以前の先進国では、航空宇宙・防衛産業政策など、特に戦略的な製造業を中心に様々な産業政策が展開されていた。例えば、米国では、防衛宇宙産業を中心とする産業政策が行われていた。特定の技術のブレークスルーは、シリコンバレーのような民間の技術普及によるところがあるものの、資金調達などの政府の積極的な政策的支援が果たした役割も大きい。欧州においても、当時、政府間で連携して産業政策を展開する動きが見られた。産業政策イニシアティブを立ち上げ、フランスとドイツの企業連合としてエアバス社を設立し、その後にスペインや英国が参加するなど、共同で産業政策を進め、域内の産業競争力を強化してきた。こうした動きは、民間航空機を巡る米欧間の長期間にわたる貿易紛争に発展した。
1980年代に入ると、ラテン・アメリカ債務危機を契機として、政府の役割を最小限の「市場の失敗」への対処に止め、産業政策を控える新自由主義の思想が台頭した。世界銀行やIMF(国際通貨基金)に代表される国際機関は、市場原理主義、小さな政府、健全財政、規制緩和、貿易・投資の自由化などに基づく経済政策運営を標榜する「ワシントン・コンセンサス」を支持し、発展途上国へこれを要求した。東アジアの奇跡と呼ばれる日本や東アジア新興国の高度成長の過程では、政府が市場を補完する積極的な役割を果たしたとする議論もあったが、ワシントン・コンセンサスを上書きするには至らなかった160。
冷戦後には、ワシントン・コンセンサスに支えられたグローバル化が進展した一方で、旧社会主義国や新興国との貿易投資関係が拡大するにつれ、市場歪曲的な産業政策が公正な国際競争環境に悪影響を与えているとの認識が高まった。しかし、2008年の世界金融危機後には、各国で産業政策に回帰する動きが見られるようになった161。学術的にも、政府と市場を二項対立的に捉える新自由主義に対する批判から、政府と市場を補完的に捉え、拡大する市場の失敗への対処、さらには市場の形成にも政府が役割を果たすべきとの議論が提起されるようになった。足下では、デジタル化がもたらす社会経済的変化や、グリーン移行やサプライチェーン強靱化の必要性などを背景に、多くの国が積極的な産業政策を打ち出す流れが起きている。
160 Birdsall et al. (1993)
161 安橋(2022)
2. 産業政策と貿易を巡る伝統的な議論
産業政策は、その目的、対象、手段、効果、副次的影響等の観点から様々な定義が行われている162。各国政府は産業の育成を明示的な目的としたいわゆる産業政策を実施しているが、環境や製品安全、安全保障等の他の目的を掲げた政策が産業に直接的な影響を与える例も多い。特定の産業を選定し(ターゲティング)、産業内や産業間での資源配分を変えようとするのが典型的な産業政策だが、対象を特定産業に限定しない科学技術等のための政策も産業発展に強い影響を与える。補助金・税制や業規制、関税等は直接的な産業政策の手段としてしばしば用いられるが、競争政策等の一般的な市場ルール整備や産業界との対話等のソフトな手段も産業政策の一部と位置付けられる場合がある。特定の産業政策がその数値目標を達成したか否かは狭義の産業政策の効果分析であるが、そうした効果検証は容易ではない場合も多く、むしろ構造的又は間接的な効果を重視する見方もある。産業政策が例えば貿易に与える副次的影響は重要な論点だが、貿易に影響を与える措置として何を議論の対象にするかを一義的に決めることは難しい。こうした産業政策の線引き問題が、産業政策を巡る議論を難しくしている一因である。ここでは特定の定義に依らず産業政策を巡る議論を概観する163。
多くの論者が産業政策の正当性として挙げるのは、「市場の失敗」の是正である。市場の失敗とは、外部性(環境問題を始めとする外部不経済など)や情報の非対称性、協調の失敗164などを要因とし、市場において効率的な資源配分が達成されない状態のことを指す。伊藤他は、産業政策を「競争的な市場機構の持つ欠陥―市場の失敗―のために、自由競争によっては資源配分あるいは所得分配上なんらかの問題が発生するときに、当該経済の厚生水準を高めるために実施される政策。しかもそのような政策目的を、産業ないし部門間の資源配分又は個別産業の産業組織に介入することによって達成しようとする政策の総体」と定義しており、市場の失敗を政策目的の中心に位置付けた165。Stiglitz et al.は、「産業政策の正当性は常に経済理論、特に市場の失敗に関する理論に根拠付けられてきた」と述べている166。
市場の失敗によって正当化される産業政策の類型については様々な議論があるが、ここでは貿易と関連の深い幼稚産業保護論と戦略的貿易政策について説明する167。
幼稚産業保護とは、既に海外には存在しているが、国内には存在しない産業を、一時的な保護によって確立することを目的とする産業政策を指す。特にこの議論が重要になるのは、対象産業に何らかの「規模の経済」(又は「費用逓減」)が働いている場合である。ある国が当該産業の一時的保護により産業を確立できた場合、同国内で規模の経済が働くほど、その国の生産拡大が価格を低下させ、需要を拡大させ、更なる生産拡大につながるという好循環が生まれる。
ここで、そのメカニズムを模式化して概略を説明する。ある幼稚産業が、生産数量の増加に伴って一個当たりの平均費用が低減する「生産コスト逓減」の働きやすい産業だと仮定する。この産業は既に海外に存在し、いわゆる小国の仮定で、製品は常に価格P*で輸入できるものとする(第II-1-5-1図)。国内生産がなく全てを輸入している状況から、国内に同じ産業を興そうとする場合、国内で一定規模以上の数量を生産しなければコスト低減の利益が得られない。少量生産は割高になり、国際価格P*まで低下させるためには少なくともX2の生産量が必要となる。逆に、仮にX2以上の数量を国内生産すれば、国内産品の価格が国際価格P*以下となり、輸入品を代替して国内販売ができる。最大の問題は、国内企業がX2以上の生産を実現できるかである。個々の企業にとっては、X2以上の生産に対する販売見込み等が必ずしも定かでない中で、生産に踏み出すことは難しいかもしれない。ここに政府による産業政策が国内産業の確立に寄与できる可能性がある。例えば、生産補助金で国産品の価格が国際価格P*以下に低下すれば、国内販売ができるようになる。また、外国産品の輸入を制限・禁止すれば、国内需要を満たすための国内生産が可能となろう。そして、生産量が増加するにつれて、費用逓減(収穫逓増)の産業特性によって価格低下が進むことから、一時的な産業保護をやめた後も、産業が自律的に回っていくことが可能になる。
ただし、当該小国の政府が一時的保護政策を採用することが同国の経済厚生上正当化されるためには、保護政策の結果として私企業ベースで採算がとれるようになること(ミルの基準)と、政策介入によって実現可能な利益が社会的費用を上回ること(バステーブルの基準)を満たす必要があるとされる168。また、こうした政策は、政府介入の非効率性やレントシーキング(個別利益の追求)の発生、技術ノウハウの欠如や民間インセンティブの歪曲等による失敗が起きやすいとの批判もある。
幼稚産業保護政策の貿易や国際的な所得分配への影響も、極めて重要な論点である。ひとたび規模の経済を確立すると、国際的な競争激化によって短期的な生産者余剰を減少させる可能性や、第三国への急速な輸出拡大を通じて当該国の同じ産業の成長機会を奪う又は産業基盤を破壊する可能性がある169。そのような影響をもたらす政策は、近隣窮乏化政策とも呼ばれ、他国政府による報復措置といった政治経済的な悪影響を引き起こし得る。
第Ⅱ-1-5-1図 平均費用が逓減する場合
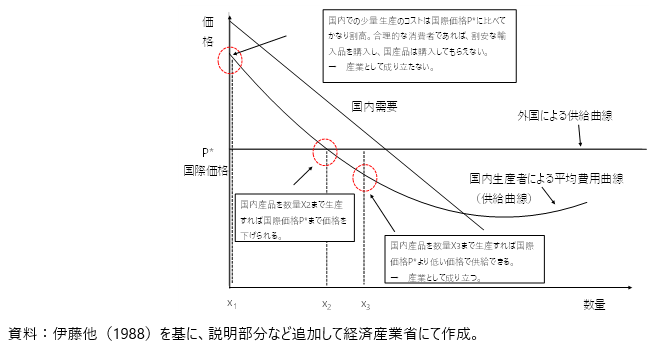
戦略的貿易政策とは、自国の産業、とりわけ先端技術産業において、①規模の経済、②技術集約による外部経済効果、③一国の経済成長や生活水準にとっての重要性などが存在する場合に、当該産業の保護・育成を目的として行う産業・貿易政策を指す170。先端技術産業の市場は寡占的であり、先行企業が価格支配力を持つために市場の失敗が起きる可能性がある。このとき政府は、政策によって国際市場における自国企業の競争力を高め、価格支配力を持つ外国企業から独占レント(競争市場で得られる利潤を上回る超過利潤)を自国企業へ移転させることができると主張する。手段としては、自国企業への補助金や、産業保護を目的とした管理貿易的手法、相手国への輸入拡大要求等が想定されている171。他方、戦略的貿易政策に対しては、その正当性・有効性に関する疑問が提起され、また貿易紛争の危険性等の副作用があるとの批判もあった172。
米国が1980年代以降の日米貿易摩擦の中で展開した政策が、戦略的貿易政策の典型例とされる173。当時、日本の対米貿易黒字が拡大する中、自動車や半導体といった先端技術産業において、米国から日本に対し、管理貿易的手法がとられるようになった。1981年、レーガン大統領は自動車産業救済策を発表し、日本へ対米自動車輸出の自主規制を求めた。同年に日本が表明した自主規制は1994年に撤廃されたが、その間、日本企業は、自動車生産の現地化を進め、対米直接投資を増加させていった。また、日米半導体摩擦では、1986年に日米半導体取極が締結され、日本市場へのアクセス拡大やダンピングの事前防止のための措置などが盛り込まれた。翌1987年には、米国が日本の協定違反を理由に日本製のパソコン等へ100%の関税を賦課する制裁を発動した。これに対し、日本側は制裁解除を求めて米国との二国間協議を継続し、1991年には日米半導体取極を一部修正の上、期限を延長した。1989年になると、日米構造協議が開始され、日本は、消費の拡大や流通構造の合理化、排他的取引慣行の改善などを要求された174。米国の戦略的貿易政策は、その後、日本の対米直接投資拡大による現地経済・雇用への貢献や市場アクセスの改善、そして日本経済の停滞によって下火となった。さらに、冷戦終結後のグローバル化の進展により、戦略的貿易政策はその保護主義的な側面が否定されるようになり、実態として、先進国間での政策的議論の対象から外れていくことになった。
162 一般性の高い定義の一つとして、OECD (2024) は、産業政策を「国内のビジネスセクターの業績を構造的に改善することを目的とした介入」と広範に定義している。
163 安橋(2022)が産業政策の様々な定義をまとめている。
164 協調の失敗とは、消費者の経済厚生を増大させるという観点からなされるべき協調が行われず、非効率な均衡が実現してしまうことを指す。
163 伊藤他(1988)
166 Stiglitz et al. (2013)
167 安橋(2022)は、幼稚産業保護論と戦略的貿易政策に加えて、情報共有を通じた産業政策、過当競争と参入抑制政策、研究開発と産業政策、その他の産業政策の理論を説明している。
168 伊藤他(1988)
169 渡邉、梶谷両氏もこの点は指摘しており、古くは日米貿易摩擦の期間に、日本の産業政策を分析した資料の中でも指摘されている(小宮他編(1984))。
170 経済企画庁(1993)
171 安橋(2022)
172 経済企画庁(1993)
173 日米貿易摩擦は1950年代の繊維摩擦まで遡ることができるが、本項では1980年代以降を扱う。
174 内閣府経済社会総合研究所(2011)
3. 産業政策と通商ルール
産業政策とWTO協定を始めとする通商ルールの関連性については、戦後の通商ルールの形成過程でも強く意識をされてきた。GATTの主要な目的の一つは、産業保護等のための差別的な国境措置を抑止するため、最恵国待遇原則に基づき、国境措置の制限と関税削減交渉を行うことであった。さらに、累次のラウンド交渉の中で、輸出入に関する国境措置だけでなく、貿易に影響を与える一定の国内措置(いわゆるBehind-the-Border Issues)も通商ルールの対象となった。これは、例えば国内の産業補助金、貿易に関係する投資規制、製品安全等の規制基準、サービス業の国内規制、知的財産権制度、政府調達等が公正な貿易関係を損なうことを防ぐためのルールであり、国内での産業政策を一概に否定しているわけではない175。典型的には、輸出拡大を交付要件とする産業補助金や、安全性確保等の政策目的で正当化できない貿易制限的な製品基準等が規律対象となっている。また、WTOの監視・審議機能、すなわち各国貿易政策の審査メカニズムや、通常委員会での多国間の議論を通じた各国政策の透明性向上、相互監視も、産業政策を含む各国政策の貿易影響に関する予見可能性を高めるために強化されてきた。
冷戦終結後には、経済発展の段階、産業構造、政治経済システム、産業政策等の背景が異なる多くの旧社会主義諸国や新興国・途上国がWTOに加盟した。その中で、市場歪曲的な産業補助金や非商業的動機による国有企業の行動が競争中立性を損なっている等の新たな貿易課題が指摘されるようになった。こうした、産業政策と公正な貿易関係を巡る新たな課題に対して、WTOでの通商ルール形成が停滞したため、CPTPPを始めとするFTA/EPAにおける課題対処の試みやG7等の場での議論が行われてきた。また、昨今では、学術研究においても産業政策と貿易の関係が整理されつつある。
以下では、産業政策の主要な手段の一つであり、また、公正な貿易関係との関連性が最も議論されてきた産業補助金について、議論の経緯を振り返る。
175 各分野のWTO協定における規律の概要については、経済産業省(2024a)の第Ⅱ部の補助金・相殺措置、貿易関連投資措置、基準・認証制度、サービス貿易、知的財産、政府調達の各章を参照。
(1) 産業補助金の影響と通商ルール
① 産業補助金の貿易促進効果に係る学術研究
産業政策の手段の中でも、とりわけ経済的なインセンティブの付与である補助金は、貿易を促進する役割を持つことが研究からも明らかになっている。Navarraは、米国の連邦政府補助金のデータを用いた研究において、産業補助金が、その直接の支給対象である産業の輸出を増加させ、さらに、間接的に川下産業の輸出も増加させたことを明らかにした176。また、Rotunno et al.の研究では、産業補助金が輸出と輸入の両方を促進させることが分かった177。ここで重要なのは、産業補助金が輸出促進を目的としているか否かにかかわらず、結果として貿易促進効果を持つということである。また、産業補助金が、例えばイノベーション等の政策目的を実現したかどうかについては、具体的な交付要件等によっても異なるため、実証研究の結果は様々であり、質的ではなく量的な効果しかなかったとする分析も多い。
産業補助金が貿易へ与える影響に関する実証研究については、世界各国の産業補助金に関する包括的かつ比較可能なデータが整備されていないことが研究の障壁になっているという問題も指摘されている。OECDによると、データ整備が困難な要因の一つは、各国政府による産業補助金の情報開示にばらつきがあり、また、開示される情報も限定的なことであるという。例えば、多くの政府は、支援を提供する政府機関名や支援の形態、受給者、金額と言った詳細な情報を公表していない。また、公表している場合でも、情報が集計された形式であることが多い。さらに、政府が公表した支援のうち、対象企業へ実際にどれだけの額が支払われたかについては、明らかにされていないこともある178。
176 Navarra (2023)
177 Rotunno and Ruta (2024)
178 OECD (2023)
② WTO協定における産業補助金規律
WTO協定では、「物品の貿易に関する多角的協定(附属書1A)」に含まれる「補助金及び相殺措置に関する協定(以下、補助金協定)」で、物品(サービスを除く)に対する産業補助金の規律を定めている。同協定が定義する補助金とは、政府又は公的機関からの資金的貢献によって、受け手の企業に利益が生じるものである。この補助金の定義には、助成金のみならず減税措置や物品・サービスの安価提供等も含まれる。補助金協定は、加盟国に対し、自由貿易を阻害する要因となり得る補助金の交付を禁止している。禁止の対象となるのは、輸出が行われることに基づいて交付される補助金(輸出補助金)と、輸入物品よりも国内物品を優先することに基づいて交付される補助金(国内産品優先使用補助金)である。また、これらに該当しない補助金であっても、補助金の交付先が特定の企業又は産業に限定されている場合は、特定性のある補助金とされ、他の加盟国が貿易上の損害を受ける場合には、相殺関税の賦課179やWTO提訴といった手段を取ることができる。
この特定性のある補助金について、補助金協定は、透明性確保の観点から加盟国に対して通報義務を課している。通報の対象となる事項は、補助金の形態(贈与、貸付け、減税など)、物品の単位当たりの補助金額、補助金の目的などである。一方で、通報義務を怠っても罰則は課されないため、実態としては必ずしも当該義務は順守されておらず、当該通報制度は十分には機能していないとの指摘もある。
179 特定性のある補助金が供与されている物品の輸出により、輸入国の国内産業の業況が悪化するなど、損害が発生する場合、輸入国政府自身の調査に基づき、当該産品に相殺関税を賦課することができる。
③ EPAにおける産業補助金・国有企業規律
WTOドーハ・ラウンド交渉が2008年の閣僚会合で合意に至らなかった頃から、新たな課題に対応する高水準のルールをEPAに盛り込む動きが強まった。特に市場歪曲的な産業補助金や非商業的動機による国有企業の行動については、日本が締約国となるCPTPPや日EU・EPAなどに規律が含まれている180。
CPTPPでは国有企業章を設け、国有企業の活動について、無差別待遇や商業的考慮に従った行動の確保を義務付けている。また、国有企業に対する非商業的な援助が貿易に悪影響を及ぼすことを規律するという、実質的な補助金規律も含まれている。日EU・EPAでも、国有企業に関して無差別待遇や商業的考慮に従った行動の確保を義務付けている。補助金章では、金額や期間の制限を付けない債務保証と、信頼性のある再建計画もなく企業再建を援助する補助金という、WTO協定にはない二つの禁止補助金が規定されている。
180 詳細は経済産業省(2024a)の第Ⅲ部第10章『国有企業、補助金』参照。
④ 国際フォーラムにおける議論
2017年12月に初めて開催された日米欧三極貿易大臣会合では、第三国による市場歪曲的な措置への共同対処を主要議題として、産業補助金・国有企業の規律強化、強制技術移転、市場志向条件、電子商取引等について議論が重ねられた。根底には、既存のWTO協定では適切に規律されていない産業補助金や国有企業の活動によって、公正な貿易関係が損なわれているとの問題意識があり、主にWTOでのルール形成を念頭に議論が行われた。
この課題は、同時期からG7及びG20でも議論されるようになった。2016年のG7サミット及びG20サミットでは、政府や関連機関による補助金が市場を歪曲させていることへの問題意識が確認された。その後も、G7及びG20貿易大臣会合の閣僚声明において、産業補助金についての国際的な規律を強化する必要性が確認されてきた。G7及びG20の閣僚声明には以下のような内容が含まれている。
2019年6月に日本で行われたG20貿易・デジタル経済大臣会合の閣僚声明には、「多くのG20構成国は、産業補助金についての国際的な規律を強化する必要性を確認し、及び農業に影響を及ぼす貿易の規律を改善するための現在進行中の国際的な努力を歓迎する」との文言が含まれた181。これは、2021年10月にイタリアで開催されたG20貿易・投資大臣会合の閣僚声明へも引き継がれた。
また、2023年10月に大阪で開催されたG7貿易大臣会合では、「産業補助金に関し、我々は、状況によっては補助金が正当な公共政策目的を達成するためのツールとなり得ることを認識しつつ、現行のWTOルールと最近の状況との間のギャップ、また、一部の国々によってとられた措置の根本的な透明性の欠如を含む、非市場的政策及び慣行に関連する問題に対処する上での課題をレビューし、認識した。このギャップ分析に基づき、我々は、国家によって実質的に管理される投資ファンドを含む国有企業によって提供される不透明で貿易を歪曲する補助金に対して、WTOの補助金及び相殺措置に関する協定を含め、一層効果的に対処するための適切な手段について更なる議論を行う必要性を共有する。我々は、効果的な多数国間の補助金に関するルール、有意義な政策審議及び公正な競争の基礎としての透明性の基本的重要性を認識し、WTOにおける補助金通報及び国内において補助金プログラムに関する情報を公に入手可能とすることを通じて、透明性を確保するための全てのWTO加盟国の継続的な取組の重要性を強調する。我々は、全てのWTO加盟国による透明性義務の遵守を改善する方法を検討する用意がある。」との閣僚声明が出された182。
なお、2024年2月末に開催された第13回WTO閣僚会合(MC13)では、「貿易と産業政策・政策余地を含む持続可能な成長」に関する閣僚間対話が実施され、その場で日本を含む多くの加盟国が、WTOにおける「貿易と産業政策」に関する審議の場を立ち上げるべきと主張した。一部の加盟国の反対によって閣僚声明には盛り込まれなかったが、WTOにおいても多くの加盟国が貿易と産業政策の関係を巡る新たな課題を認識している。
181 外務省「G20貿易・デジタル経済大臣会合閣僚声明(仮訳)」、
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/osaka19/pdf/documents/jp/Ministerial_Statement_on_Trade_and_Digital_Economy.pdf![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
182 経済産業省「G7貿易大臣声明(仮訳)」、2023年10月29日、
https://www.meti.go.jp/press/2023/10/20231029001/20231029001-b.pdf![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
⑤ 最近の学術的議論
現代の産業政策を巡る課題に対して既存のWTO協定や紛争解決手続が対応しきれていないとの議論について、学術的な論点整理も行われている。Bownは、経済規模が大きく貿易やサプライチェーンを通じて他国と密接につながっている中国の産業補助金を始めとする産業政策が、近隣窮乏化政策として国際的な負の外部性を生み出している可能性があると指摘した。そして、近年の貿易摩擦の少なくとも一部は、多角的貿易体制が中国に起因する負の外部性を抑制できていないことに対する米国の不満によって引き起こされていると指摘した。
その上で、中国の産業補助金の規模や影響を把握することが困難な要因として、他国経済へ影響を与え得る補助金が、WTO補助金協定の既存の定義に必ずしも当てはまらないことや、中国政府と企業の間の資金の流れが不透明であることなどを挙げている。中国が、補助金協定の定義を回避し得る多額で不透明な補助金を自国企業へ交付すると、米国を始めとする貿易相手国が、より多種の輸入品に、より高い関税率で貿易救済措置を発動する可能性が高まる。こうした貿易救済措置は、中国との競争で輸出価格を下げざるを得なくなる第三国の企業を巻き込むこともあり、国際貿易システムにおける緊張をますます高めることにつながる。
Bownは、中国の産業補助金がそうした国際的な負の外部性を生み出した事例として、造船業を挙げた。中国の造船業に対する産業補助金は、船舶の世界的な生産拡大に僅かに寄与したものの、その主要な影響は、自国の市場シェアの拡大、すなわち韓国と日本から市場シェアを奪取するという結果で現れたという。
さらに、中国の産業補助金問題に対してWTOが十分に機能できていない理由として、紛争解決手続が損害を被った企業等からの申請と証拠の提供を必要とするため、当該企業等が中国からの報復をおそれて申請をためらう可能性があることや、産業補助金の経済的悪影響を示す証拠が揃うまでの間に中国国内に当該産業が確立されてしまい、訴訟によってその悪影響を阻止するには手遅れであることを挙げた183。
183 Bown (2024)
4. 新たな産業政策論
ワシントン・コンセンサスの時代を経て、2010年代頃から、産業政策に関する議論に新たな展開が見られている。その議論の方向性は、政府が市場の失敗に適切に対処できていない、又は市場の失敗の所在が広がっているため、産業政策の射程を広げる必要があるというものである。これに加えて、市場の失敗への対処にとどまらず、市場の創出や形成にも産業政策が取り組むべきとの議論もある。
議論の方向性として重要な点は、政府と市場を二項対立ではなく補完的に捉えること、市場の失敗は引き続き産業政策の必要条件の一つだがその他の目的も含まれ得ると考えること、そして、個別産業を育成するターゲティングだけではなく水平的政策184も産業政策の一つの手段と位置付けることである。OECDによれば、産業政策のその他の目的には、グリーン技術のイノベーションや国家安全保障、地域格差の是正などが含まれるとされる185。第Ⅱ部第1章第4節で詳説したサプライチェーンの強靱化も、新しい産業政策の目的の一つに含まれ得る186。
Aiginger and Rodrikは、「産業政策の再生と21世紀のためのアジェンダ」の中で、産業政策の射程を拡大し、市場の失敗の是正を超えて、市場形成、持続可能性、責任あるグローバル化等の経済社会課題に対処することと位置付けた。また、その手段は、補助金等インセンティブを活用したトップダウンのターゲティングから、官民セクターの持続的協働を中心としたものに転換すべきとしている。産業政策は未知の領域での探求プロセスであるとしており、試行錯誤や失敗の可能性を織り込んでいることも特徴的である187。
Mazzucato は、「ミッション・エコノミー」の中で、「ミッション志向」の取組、すなわち官民が手を取り合って重要な社会課題を解決する手法が今、切実に求められていると主張した。そして、それを実現するために政府が果たす役割を考え直す必要があると述べた。同氏は、ミッション志向のアプローチを阻害する五つの思い込みとして、①企業のみが価値を生み出しリスクを取る主体であるということ、②政府の役割は市場の形成ではなく市場の失敗の是正だということ、③政府はリスクを取らずに裏方に徹するべきだということ、④民営化は税金の節約になりリスクを減らすということ、⑤政府が勝者(重要で成功しそうな技術・産業・企業)を選んではいけないということを挙げた。同氏はこれらを全て否定し、イノベーションを通じて経済成長を遂げてきた国では、政府が企業の重要なパートナー役を務め、企業が負いきれないリスクを引き受けてきた事実を指摘した。そして、そうした政府の積極的なイノベーション活動の成果として、現在のインターネット、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、クリーンエネルギー等の革新的技術の進展と、その関連市場・産業の創出を挙げた。同氏は、政府が自身の能力を高め、企業を含むステークホルダーとともに価値を創造する主体となり、市場を形成していくことで、包摂的で、持続可能で、イノベーション主導の資本主義が再構築されると主張した188。
こうした議論に対しては、様々な疑問や反論も提起されており、現時点でその目的、手段、条件等について必ずしも幅広い学術的合意が形成されているわけではない。例えば、Mingardiは、Mazzucatoの主張は根拠に乏しく、自身に都合の良い特定の事例を好んで用いていると批判している189。しかし、ワシントン・コンセンサスに対する実務的・学術的支持が後退する中で、新たな産業政策とその理論的根拠が真剣に議論されていることは注目に値する。
経済産業省では、2021 年の産業構造審議会総会以降、「経済産業政策の新機軸」と称して、こうした学術的議論を含めた世界的潮流も踏まえた新たな産業政策の強化をいち早く開始している190。
184 特定の企業や産業を対象とする政策を垂直的産業政策、企業を取り巻く制度的環境を整備することを通じて経済活性化を図る産業政策を水平的産業政策という。
185 OECD (2024)
186 Aggarwal and Reddie (2020) は、エコノミック・ステイトクラフト、即ち、軍事的ではなく経済的な手段を通じて他国へ影響を及ぼす手法は、戦略的に重要な経済部門を強化するための産業政策や貿易政策、規制政策の中に見られるとした。その上で、新たなエコノミック・ステイトクラフトは、経済的威圧を中心とする伝統的な手法に限定されることなく、戦略的地位を確保するために政府が用いることができる全ての経済的手段を含むべきだと述べた。
187 Aiginger and Rodrik (2020)
188 Mazzucato (2021)
189 Mingardi (2021)
190 経済産業省「資料2 経済産業政策の新機軸~新たな産業政策への挑戦~」(第28回産業構造審議会総会資料)、2021年6月、https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sokai/pdf/028_02_00.pdf![]() (2025年5月14日閲覧)。
(2025年5月14日閲覧)。
5. 米国・EUの新たな産業政策
近年、米国とEUも現代の経済社会的課題への対処と産業発展の両方を目指す新たな産業政策を立案・実施している。それぞれの新たな産業政策の概要と、その背景にある考え方を概観する。
(1) 米国
米国のバイデン政権は、老朽化インフラの補修とクリーンエネルギー関連インフラの普及に主眼を置く「インフラ投資雇用法」(2021年11月成立)や、気候変動対策に必須となる技術の導入へ税額控除などのインセンティブを付与する「インフレ削減法」(2022年8月成立)、半導体生産支援と科学技術関連予算を柱とする「CHIPS及び科学法」(2022年8月成立)といった複数の大型法案を成立させた。
バイデン政権が打ち出してきた産業政策の方針については、2023年4月にジェイク・サリバン大統領補佐官がブルッキングス研究所で行った「新ワシントン・コンセンサス」に関する演説で詳しく述べられている。サリバン補佐官は演説の冒頭、「金融危機は中流階級を揺るがした。パンデミックはサプライチェーンの脆弱性を露わにした。気候変動は生命と生活を脅かした。ロシアによるウクライナ侵略は、過剰依存のリスクを浮き彫りにした。だからこそ今、我々は新たなコンセンサスを構築する必要がある」と述べた。そして、米国が国内外のパートナーと共に推進する産業・イノベーション戦略は、「米国の経済・技術的な強みの源泉に投資し、多様かつ強靱なグローバル・サプライチェーンを推進し、労働や環境から信頼性の高い技術、優れたガバナンスに至るまで、あらゆるものに高い基準を設定し、気候や健康といった公共の利益を実現するために資本を投入するものである」と定義した。その上で、サリバン補佐官は、バイデン政権発足前に米国が抱えていた四つの課題を指摘し、それらへ対処するための五分野の政策を提言した(第II-1-5-2表)。その中で第一に強調されたのが、現代的な産業政策の必要性であった。サリバン補佐官は、「現代的な産業政策とは、経済成長の基盤であり、国家安全保障の観点から戦略的であり、民間企業だけでは国家的野心を達成するために必要な投資を行う準備が整っていない特定の分野に的を絞った公共投資を行うことだ」と主張した191。
第Ⅱ-1-5-2表 新ワシントン・コンセンサスの概要
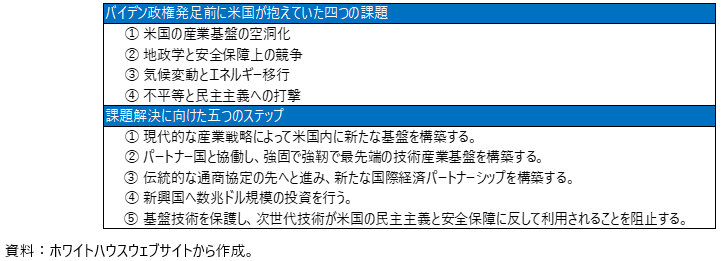
こうした考え方は、インフラ投資雇用法、インフレ削減法、CHIPS及び科学法の中にも色濃く表れている。これら三つの法律は、競争力の源泉となるクリーン技術や半導体などに大規模な資金を投じると同時に、サプライチェーン強靱化と国家安全保障強化の側面も持っている。具体的には、インフラ投資雇用法では、連邦政府のインフラ計画に用いられる全ての鉄鋼、工業製品、建設資材を米国内で生産することが義務付けられている。また、インフレ削減法のEV税額控除(クリーン自動車の購入に対する税額控除)では、「車両の最終組立てが北米域内で行われていること」、「蓄電池部品の一定割合が北米で製造又は組み立てられていること」、「蓄電池に含まれる重要鉱物の一定割合が、米国ないし米国とのFTA締結国で採取・加工されていること、又は北米でリサイクルされていること」という三要件を満たさなければ最大の税額控除を受けることができない。そして、CHIPS及び科学法では、国家安全保障上のガードレール条項が盛り込まれており、助成対象者は、懸念国(中国・ロシア・北朝鮮・イラン等)における半導体生産能力拡張や、懸念企業との共同研究などが制限され、違反した場合には助成金の返還が求められることとなっている。
なお、今後の米国トランプ政権下での産業政策については、基本的な考え方と具体的な目的・手段において大きな転換が図られる可能性もあり、不確実性が高い状況となっている。2025年1月に就任したトランプ大統領は、就任当日に「米国のエネルギーの解放」と題する大統領令に署名し、インフラ投資雇用法とインフレ削減法に計上された資金支出を一時停止し、90日間のレビューを開始した192。
191 White House, ‘Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan on Renewing American Economic Leadership at the Brookings Institution’, 27 April 2023, https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
192 White House, ‘Unleashing American Energy’, 20 January 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/unleashing-american-energy/![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
(2) EU
2023年1月、フォン・デア・ライエン欧州委員長は、世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)で演説し、ネット・ゼロ技術及び製品の競争力強化を目的とした「グリーン・ディール産業計画」の構想を発表した。同氏は、演説の中で、「(クリーンエネルギー市場における)競争に打ち勝つためには、産業基盤の強化に投資し続け、欧州をより投資やイノベーションに適した場所にする必要がある」と訴えた。そして、翌2月には、欧州委員会が同計画の詳細を示した政策文書を公表した。
2023年3月、欧州委員会は、グリーン・ディール産業計画に基づき、「ネット・ゼロ産業法案」と「重要原材料法案」をそれぞれ発表した。ネット・ゼロ産業法(2024年6月施行)は、ネット・ゼロ技術の域内での生産能力を高めることを目的とし、企業に対して規制環境の整備や許認可の迅速化などの支援を行うものである。支援対象となるネット・ゼロ技術には、再生可能エネルギーや蓄電池、水素製造の電解槽、二酸化炭素回収・貯留技術(CCS)などが指定されている。また、重要原材料法(2024年5月施行)は、グリーンやデジタルなどの重要技術に不可欠で、かつ将来的な供給リスクを抱える「戦略的原材料」について、域内での採掘と加工、リサイクルを促進するものである。
グリーン・ディール産業計画には、加盟国が補助金を拠出しやすくするための規制緩和も盛り込まれた。2023年3月、欧州委員会は、同計画に基づき、2025年末までの一時的な措置として、EUの国家補助規則を緩和する「危機・移行暫定枠組み」を採択した。この枠組みの採択により、加盟国は、ネット・ゼロ技術に関する企業の生産活動に対し、特定の割合を上限として支援を行うことができるようになった。さらに、そうした生産活動に関する投資が域外に移転するリスクがある場合、加盟国は、支援上限を更に引き上げ、企業に対し域外の移転候補先で得られる支援額と同等の支援を行うこともできるようになった。つまり、同枠組みで規定された条件を満たせば、加盟国は、米国インフレ削減法などのインセンティブに匹敵する支援を行うことが可能になったということである。
2024年9月、ドラギ元欧州中央銀行総裁は、前年のフォン・デア・ライエン欧州委員長からの諮問を受け、「欧州の競争力の将来」と題するドラギレポートを公表した。これは、EUが直面する課題を克服するための新たな産業戦略をまとめたものである。同レポートは、EUが直面する課題を①米中とのイノベーション格差、②エネルギー不安と脱炭素技術分野における中国との競争、③地政学的リスクの高まりと重要物資の他国依存の三つに整理した。そして、これらの課題の解決を阻害している要因の一つに、EU及び加盟国が実施する各政策間の調整不足を挙げた上で、「米国や中国に見られるように、現代の産業戦略は、国内生産を奨励する財政政策から、反競争的行動を罰する貿易政策、サプライチェーンを確保する対外経済政策に至るまで、さまざまな政策を組み合わせたものとなっている」と指摘した。そして、同レポートは、新たな産業戦略の実現に向け、戦略分野への年間最大8,000億ユーロの投資や、産業政策・競争政策・貿易政策の連携などを提案した。
そして、2025年1月、欧州委員会は、ドラギレポートの提言を踏まえ、欧州委員会としての政策をまとめた「競争力コンパス」を公表した。①イノベーション格差の解消、②脱炭素化と競争力強化のためのロードマップ、③過度な域外依存の軽減と安全保障の強化を三つの柱とし、横断的な取組として規制の簡素化や域内市場の障壁撤廃、資金調達などを実施するとしている193。
EUはこれまで、加盟国間の産業政策競争を抑制して域内単一市場を整備する観点から、競争政策を産業政策に対置する形で位置付けてきた。例えば、EUの国家補助規則は、加盟国による特定の企業や製品に対する国家補助が、域内単一市場での競争を歪曲することのないよう規制している194。こうした方針はEUとその加盟国による産業政策の制約となってきたが、近年のEUの政策転換は、産業戦略のために産業政策と競争政策・貿易政策・その他関連政策を連携させるという新たな展開を見せている。
193 European Commission, ‘An EU Compass to regain competitiveness and secure sustainable prosperity’, 29 Jan 2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_339![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
194 駐日欧州連合代表部「EUの競争政策について教えてください」、2021年11月9日、
https://eumag.jp/questions/f1121/![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
6. 新たな産業政策とルールベースの国際経済秩序
ここまで、産業政策と貿易を巡る歴史的経緯、学術的議論、通商ルールの発展を概観した上で、新たな産業政策論と米国・EUの産業政策の新潮流を見てきた。昨今、冷戦後の新自由主義の時代を経て、産業政策の役割が見直されている。その中では、産業政策が、デジタル化がもたらす社会経済的変化やグリーン移行、サプライチェーン強靱化といった社会経済課題への対処と産業発展の同時達成を目的としていることが特徴である。これら社会経済構造の大きな転換が求められるような課題に対しては、政府が民間セクターとの協働の中で必要な産業政策を積極的に実施し、民間企業の予見可能性を高めることが、社会経済的目標と産業競争力強化の両立につながると考えられている。
他方で、第Ⅱ部第1章第1節で見たとおり、近年の産業政策への注目の背景として、国家間及び各国内の格差等がグローバル化に対する不満の声を強め、保護主義的な貿易政策を支持する社会的土壌が生まれていることにも留意が必要である。通商ルール面では、2010年前後から提起されてきた市場歪曲的な産業補助金や非商業的な国有企業の行動、経済的依存関係の武器化等の新たな課題が、多国間のルール形成の停滞によって十分に対処されておらず、通商ルールへの信認にかかわる状況が続いてきた。WTO協定に基づく各国の貿易関連措置の通報や、多国間での審議を通じた透明性向上、相互監視にも改善の必要性が提起されてきた。学術面では、一部の産業政策が貿易投資に与え得る負の外部性について、Bown等によって論点整理が行われているが、国際的な共通理解の醸成には更なる議論の進展が求められる。
過去にも議論されたとおり、ある国の産業政策が近隣窮乏化政策や戦略的貿易政策と認識されれば、それが他国の報復的な産業政策や貿易摩擦の激化を招き、全ての国の経済厚生を低下させ、誰の利益にも適わない。新たな産業政策においては、そうした展開はグリーン移行などのグローバルな課題への対応にも大きな悪影響を及ぼしかねない。
こうした中で、社会経済的目標の達成につながる積極的な産業政策を立案・実施するに当たっては、ルールベースの国際経済秩序の下で、多層的な経済外交を通じて認識共有を図り、透明性と予見可能性を確保することが重要である。また、産業政策の目的や手段、影響に関する各国当局者間の実務的な議論を通じて、今後の通商ルールの在り方についても共通認識を醸成していく必要があろう。特に、市場歪曲的措置、非商業的な国有企業の行動、経済的依存関係の武器化といった課題は、国際経済秩序の強化・再構築のために対処が必要である。我が国として、予見可能な貿易投資関係の価値の重要性を踏まえ、各国政策の透明性の確保や建設的な政策的議論を含めて、信頼醸成と国際協調を積み上げ、ルールベースの国際経済秩序を強化していくことが重要である。