冷戦後のグローバル化が進む過程で、世界の貿易投資構造の変容に最も大きな影響を与えたのは中国である。Baldwin et al. は、中国が前例のない早さで製造業の圧倒的な生産能力を構築し、輸出を拡大させてきたことを指摘し、中国は今や「世界で唯一の製造業超大国」であると表現している195。その産業発展のメカニズムと産業政策、さらには近年の貿易摩擦を含む貿易投資関係の展開は、ますます大きな注目を集めている。とりわけ中国の周辺国は、中国の輸出・対外投資拡大と米中対立を始めとする国際環境の変化の中で、それぞれの対外経済関係をどのように管理するかという難しい課題に直面している。
本章では、中国の国内産業基盤や産業政策と、その貿易投資関係への影響を一体的に把握することを試みる。まず、中国が前例のない規模と速さで発展させてきた製造業の国内産業基盤をデータに基づいて確認する。その上で、中国の産業発展メカニズムに関する学術的な議論を概観することで、中国が急速な産業発展を実現した要因についての多面的な見方を示す。さらに、中国の産業政策の展開と、具体的な産業分野の発展過程をケーススタディとして検討することで、学術的な議論と実態の橋渡しを試みる。その上で、中国の産業発展が世界の貿易投資に与える影響を分析し、ルールベースの国際貿易システムに対する含意も含めて検討する。最後に、アジアの中で中国の輸出・投資拡大の直接的な影響を受ける韓国・ASEAN・インドについて、米中対立や中国の産業発展等の国際環境の変化がそれぞれの貿易投資関係をどのように変えているかを分析する。
195 Baldwin et al. (2024)
第1節 中国の産業基盤
ここでは、急速な発展を遂げた中国の産業基盤を、経済規模(市場と生産力)、業種・企業属性、競争環境、技術、産業資金という五つの基本要素から、データに基づいて概観する。
1. 経済規模(市場と生産力)
まず、中国の生産基盤で特筆すべきことは、改革開放以降、短期間で急速に経済規模が拡大したことである。中国の経済規模は2000年代に入って、次々と欧州主要国を追い越し、2010年には日本も追い抜いて、米国に次ぐ世界第2位の経済大国に成長した(第II-2-1-1図)。GDPの拡大は、生産面では、中国の生産力の増加を意味する。需要面では、国内産品に対するより大きな自国市場と、外国企業にとってのより大きな市場としての魅力を意味している。中国のGDP拡大は、2023年から2024年までの1年間だけで、アジアの中では、例えば2024年のフィリピン、ベトナム、バングラデシュのGDP総額に匹敵する増加であり、これが長期にわたって毎年繰り返されている(第II-2-1-2表)。近年、中国の成長率が低下してきているものの、このような巨大な市場が創出されることは、中国内外の企業にとって重要な意味を持つ。
第Ⅱ-2-1-1図 主要国・地域のGDPの推移
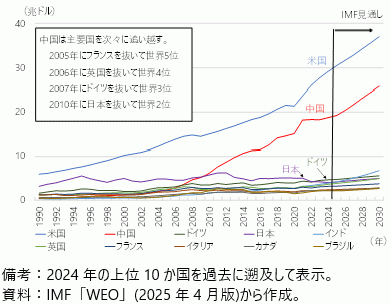
第Ⅱ-2-1-2図 中国の1年間のGDP増加額
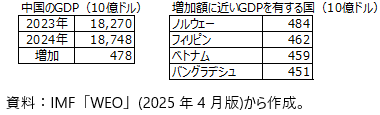
中国の産業構造を産業区分別の推移で見る。第1次産業のシェアは、GDPでも就業者でも低下して、第2次産業、第3次産業へと移行している。GDPのシェア及び伸びでは第3次産業が大きくなっているが、多くの先進国と比べればなお第2次産業、とりわけ製造業のシェアが大きい。また、就業者数で見ると、第3次産業の伸びが停滞して雇用のサービス化は足踏みしている一方、第2次産業は2010年代前半からおおむね横ばいで推移していて、なお重要な位置付けを占めている。中国が輸出主導成長の中で拡大した製造業の生産力は、なお国内経済の中で大きな存在感を持っていることが分かる(第II-2-1-3図)。
第Ⅱ-2-1-3図 中国の産業区分別GDP・就業者数の推移
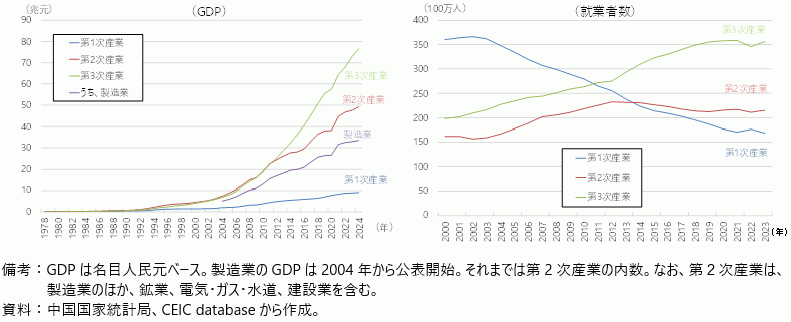
製造業分野において中国の生産力拡大がめざましいこと、既に現在の生産力が巨大であることを、主要国との比較によって確認する。データとしては、OECDが公開している付加価値貿易データベース(OECD TiVA)を利用する196。同データベースは、各国のデータを基に作成された国際産業連関表から集計されたもので、同じ基準で主要国や世界全体の指標を得ることができる。これによると、世界の製造業付加価値生産額は、1995年の6.0兆ドルから2020年の14.3兆ドルまで約2.4倍に拡大したが、国により変化の程度は異なり、米国やEUは、それぞれ約1.8倍、約1.5倍にとどまるのに対して、中国は約18.5倍にも拡大した(第II-2-1-4図)。中国は、WTOに加盟した2000年代初頭から大きく生産を拡大し、世界金融危機前後に米国を追い越した。ドル建の付加価値額が株式市場の暴落や為替レートの下落等で一時的に減少したこともあるが、2020年時点でEU28か国合計の約1.6倍、単独の国としては米国(世界第2位)の約1.8倍の付加価値生産額を誇っている。
第Ⅱ-2-1-4図 主要国・地域の製造業付加価値の推移
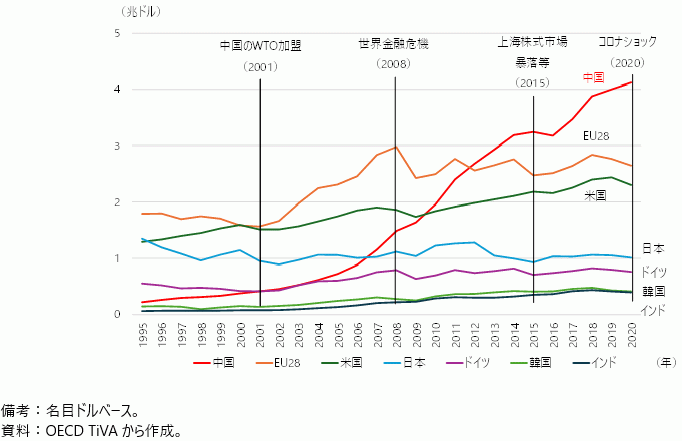
中国の中でも経済規模の大きいいくつかの省は、ひとつの省だけで製造業の世界上位国に匹敵する鉱工業生産を持っている197。例えば、広東省や江蘇省の鉱工業分野の生産は、国として世界第5位のインドを上回る。広東省と江蘇省の二省を合計すれば、日本の鉱工業生産とほぼ同等になる(第II-2-1-5図)。
第Ⅱ-2-1-5図 中国及び世界主要国の経済規模(2020年 / 鉱工業分野)
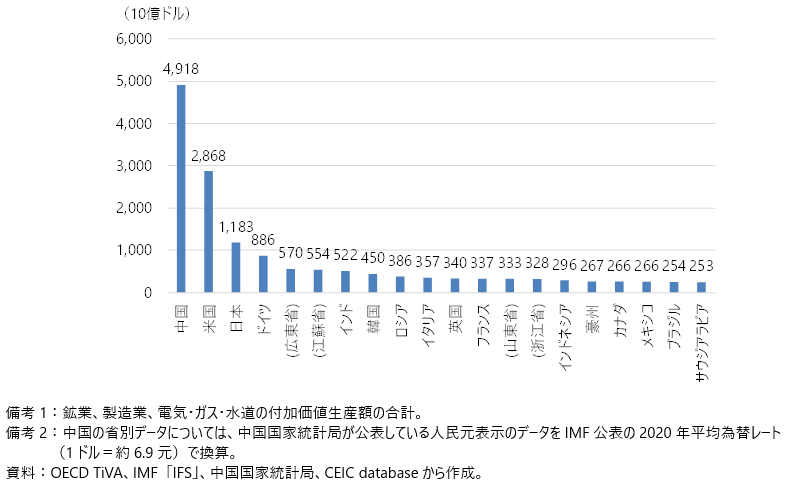
このような中国国内の製造業生産力の拡大は、経済のグローバル化が進む中での輸出の拡大と表裏一体であった。世界の製造業輸出に占めるシェアは、米国、日本、EU等が縮小する一方で、中国が急速に拡大した(第II-2-1-6図)。この傾向は、中間財の輸出に絞っても変わらない。すなわち、中国の輸出増加はグローバル・サプライチェーンへの参加拡大と一体であり、他国にとって中国は、製造業の競合相手として力を増したと同時に、重要な中間財供給者として各国の生産活動に大きく影響する存在となったことも示唆している。
第Ⅱ-2-1-6図 世界の製造業輸出における主要国・地域のシェアの推移
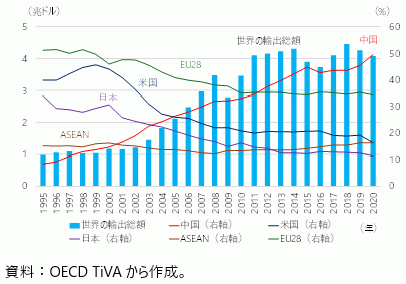
196 OECD TiVA 2023年版(https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/trade-in-value-added.html![]() )を利用。1995年から2020年までが対象。世界の主要国やEU、ASEANなどの地域計、世界合計などの集計がある。業種分類など共通の基準でデータの利用が可能。なお、EU28など年により加盟国に変化がある場合(英国のEU離脱等)でも全期間同一の構成国として集計されている。
)を利用。1995年から2020年までが対象。世界の主要国やEU、ASEANなどの地域計、世界合計などの集計がある。業種分類など共通の基準でデータの利用が可能。なお、EU28など年により加盟国に変化がある場合(英国のEU離脱等)でも全期間同一の構成国として集計されている。
197 中国の省別統計の関係から、中国統計の「工業」(鉱業、製造業、電気・ガス・水道)で比較した。
2. 業種・企業属性
中国の鉱工業分野の業種別、企業属性別の特徴を考察する。中国の製造業は衣類のような軽工業はもちろんのこと、外資企業の誘致等を契機に、家電、パソコンなど電気・電子機器等の生産も拡大し、さらには太陽光パネル、リチウムイオン電池、電気自動車など、先進的な産業まで幅広く国内に産業を擁している。少し業種が粗くなるが、先のOECDのデータベースで世界の製造業付加価値生産に占める中国のシェアを見ると、製造業全体で約3割を占め、業種別に見ても各業種で高いシェアを有している(第II-2-1-7図)。特に衣類などの繊維、セメントやガラスなどの窯業土石、鉄鋼などの卑金属が世界生産の半分近いシェアを占め、家電などの電気機器、パソコンや携帯電話などの電子機器も高いシェアを有している。なお、多くの産業において、最終製品を生産するために必要な部素材や部品を供給するサプライチェーンが国内に発達していることも、中国の強みとして指摘されている。
第Ⅱ-2-1-7図 世界の製造業付加価値に占める各国・地域のシェア(2020)
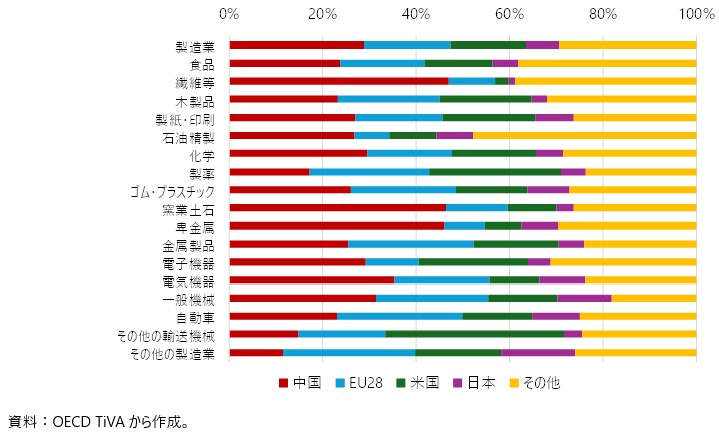
企業の形態別に見ると、中国は社会主義計画経済であった歴史から、もともと国有企業が大きなシェアを占めていた。改革開放以降、次第に民営企業が発達する道が開け、技術導入等を期待して外資企業の誘致も行われた。現在、工業分野における企業形態別の企業シェアを見ると、売上高ベースで、国有企業が3割強、民営企業が4割強、外資企業が2割強となっている(第II-2-1-8図)。業種別に企業形態の特徴を見ると、国有企業は、上流に位置するエネルギーを始めとする資源採掘、これら資源の精製加工、基礎的な素材生産、電気・ガス・水道等の分野でシェアが非常に大きく、鉄道車両、船舶、航空機、自動車などの重機械分野でもシェアが高い。一方、民営企業は国民生活に近い民生部門を中心にシェアが大きい。例えば食品、繊維、衣類、皮革、家具などであり、機械類でも一般機械、電気機械、情報通信機械に一定のシェアを持つ。また、外資企業は、情報通信機械や自動車などに高いシェアを有している。
第Ⅱ-2-1-8図 中国の主要工業分野の企業形態別売上高シェア(2023年)
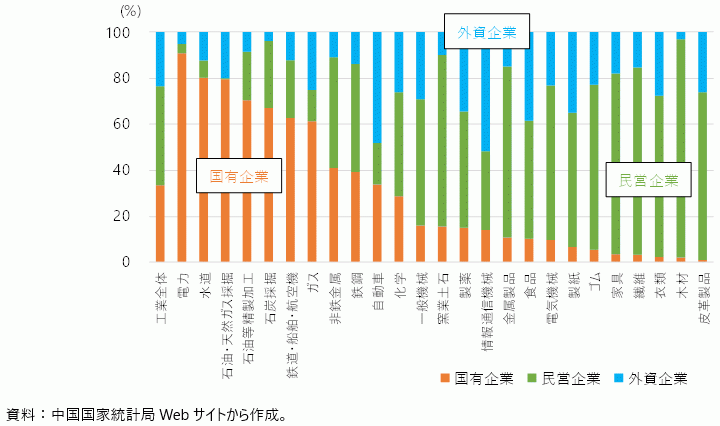
長期的な推移を見ると、2000年代、民営企業は売上高及びそのシェアを拡大し、中国の成長に貢献してきた(第II-2-1-9図)。この間、国有企業改革を通じて、混合経済制の中で国有企業が独占していた分野への民営資本の参入も認められた。しかし、国有企業を重視する方針が強まり「国進民退」が指摘されるようになった2010年代半ばから、民営企業シェアの拡大はほぼ頭打ちとなっている。足下では不動産部門の不況から国内需要が停滞し、民営企業の苦境が指摘されている。一方、民営企業の中でも、電気自動車など特定の分野では国有企業をしのぐ成長を見せる企業もある。なお、外資企業は2000年代半ばまでシェアを拡大させたが、それ以降はシェア縮小に転じている。
第Ⅱ-2-1-9図 中国の工業分野の企業形態別売上高の推移
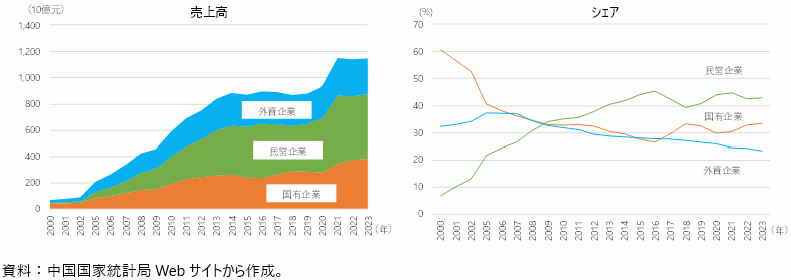
また、輸出に占める企業形態別シェアの推移を見ると、2000年代初頭は、国有企業と外資企業がシェアを二分しており、民営企業はほとんどシェアがなかった(第II-2-1-10図)。しかし、国有企業は大きくシェアを落とし、外資企業も2000年代半ば以降はシェアの低下が続いている。代わって民営企業が堅調にシェアを伸ばしており、足下では輸出の6割以上を占めている。
第Ⅱ-2-1-10図 中国の企業形態別輸出シェアの推移
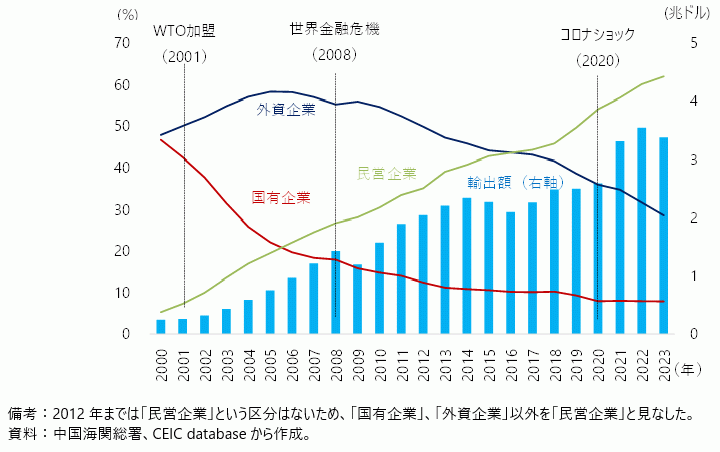
中国経済が急速に拡大する過程で企業も成長し、その中から、国際企業ランキングに名を連ねるような企業が多数輩出されている。例えば、「フォーチュン・グローバル500」に含まれる中国企業数は、2000年代初期は約10社に過ぎなかったが、次第に増加して、一時は米国を追い越すまでとなった(第II-2-1-11図)198。2024年は、ピークからは若干減少したものの、世界第2位の128社と、3位日本の40社、4位ドイツの29社を大きく上回り、首位米国の139社に迫るほどの企業数となっている。上位10社の中には、米国企業6社に対して中国企業3社が入っている。ランクインする大企業の中で、上位を占めるのはこの3社のような資源、エネルギー、金融分野等の大手国有企業である一方、民営企業も多数含まれており、中国が国有・民営を含めて世界的な大企業を擁するようになったことを示している。
第Ⅱ-2-1-11図 「フォーチュン・グローバル500」に選ばれた主要国の企業数の推移
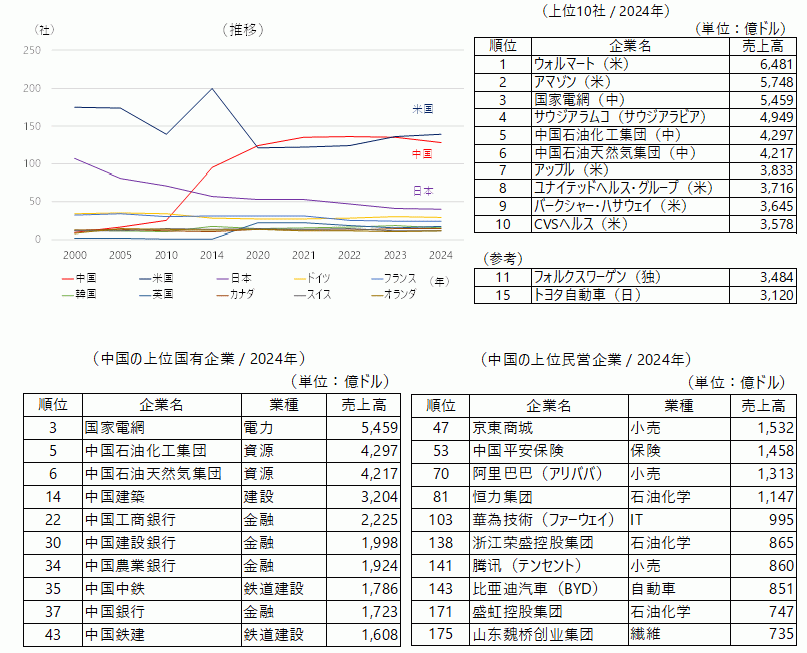
資料:Fortune Webサイト(https://fortune.com/ranking/global500/2023/![]() 、2025年2月21日閲覧)、中華全国工商業連合会Webサイト(2025年3月24日閲覧)から作成。
、2025年2月21日閲覧)、中華全国工商業連合会Webサイト(2025年3月24日閲覧)から作成。
198 米「フォーチュン」誌が、売上高を基に毎年公表する大手企業リスト。2024年版は2023年の売上高を基にしている。
3. 競争環境
中国市場の競争環境は、上述のとおり一部の国有企業が市場を占有する非競争的な分野が存在する一方で、企業の参入と退出が活発で、「内巻」と呼ばれるような過当競争が発生している分野も存在する(第II-2-1-12図)。その中で、非常に短期間での研究開発、社会実装、市場シェア拡大を目指す中国の企業文化又は市場特性も指摘されている。
第Ⅱ-2-1-12図 中国の企業開廃業率の試算
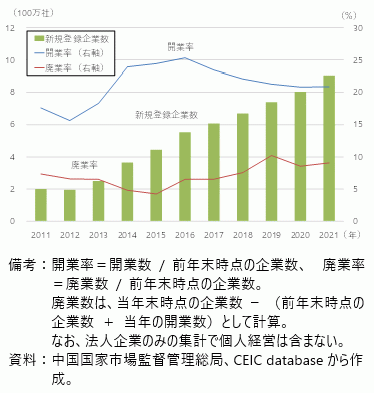
スタートアップ企業の出現と成長は、産業のイノベーション活動と新陳代謝を示唆するひとつの指標になる。ユニコーン企業と言われる、評価額10億ドルを超える未上場のスタートアップ企業の数を見ると、中国は米国に次いで多くなっており、研究開発とイノベーションを基にした起業の活発さを示している。ユニコーン企業を掲載する CB Insights の公表から集計すると、2025年2月時点で、世界には1,200社を超えるユニコーン企業が存在し、その過半数が米国にあるが、中国にも米国に次ぐ約160社のユニコーン企業が存在している(第II-2-1-13図)。ただし、近年、中国だけでなく世界的に、新たなユニコーン企業の誕生は減少してきており、企業数はほぼ横ばいとなっている。
第Ⅱ-2-1-13図 主要国のユニコーン企業数
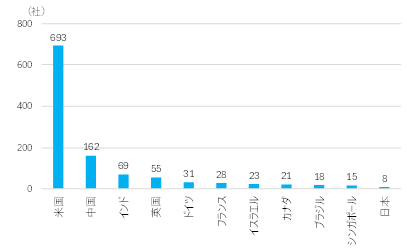
資料:CB Insights Webサイト
(https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies![]() 、2025年2月26日閲覧)から作成。
、2025年2月26日閲覧)から作成。
4. 技術
中国がどのように技術を獲得してきたかを考えてみる。改革開放当初、中国は、外資企業の合弁誘致によって、先進国の進んだ技術の移転や取引を通じたスピルオーバーを図ったことが指摘されている。「技術と市場の交換」とも言われるように、進んだ技術を有する企業には税制等の優遇措置等を用意し、中国への参入と引き換えに外資企業と中国企業の合弁を奨励したりもした。
また、外国企業からの技術移転だけでなく、中国自身が研究開発活動を活発化させ、着実に力をつけてきている。例えば、研究開発費の対GDP比を見ると、既に中国はフランスを追い抜いており、他の主要国との差も縮まってきている(第II-2-1-14図)。より重要な点は、研究開発費を実額ベースで見ると、むしろ、米国、中国の二強が際立っており、中国は3位の日本を大きく引き離し、首位の米国を追っていることである。
第Ⅱ-2-1-14図 主要国・地域の研究開発費の推移
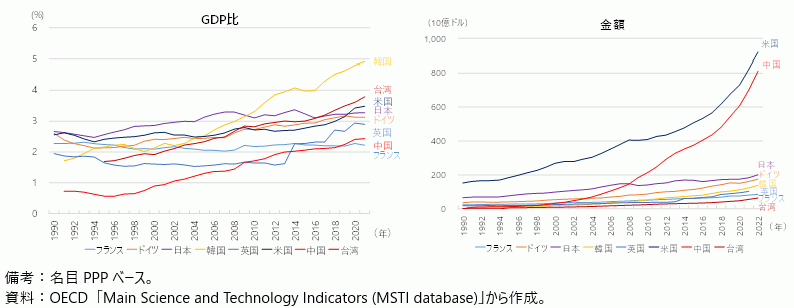
また、研究員数を見ると、中国は既に米国を追い抜き、数値だけでみれば、足下では米国の1.5倍にのぼる世界最大の研究人員を擁している(第II-2-1-15図)。その背景に、国内の高等教育卒業者や米国など先進諸国への留学生の増加という事実もある。このような海外留学組が帰国して、国内での研究活動や起業活動において活躍していることも指摘されている。
第Ⅱ-2-1-15図 主要国・地域の研究者数の推移
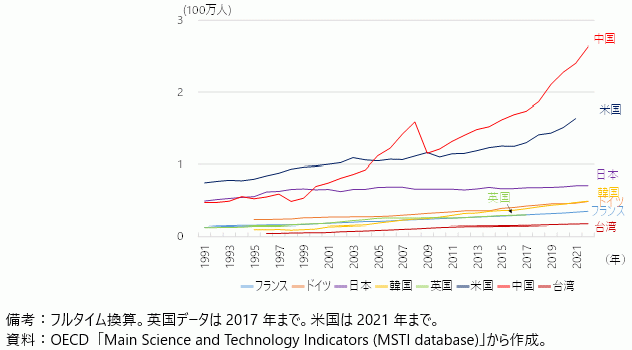
研究開発費や人員を擁するだけでは、必ずしも成果に結びつかない可能性もある。そこで研究開発活動の成果を表す指標として、世界知的所有権機関(WIPO)のデータを利用して、特許について国際比較をすると、特許申請件数、特許取得件数のいずれも、中国は2010年代初頭から半ばに米国を追い抜いて世界首位となっている(第II-2-1-16図)。
第Ⅱ-2-1-16図 主要国・地域の特許申請・取得件数の推移
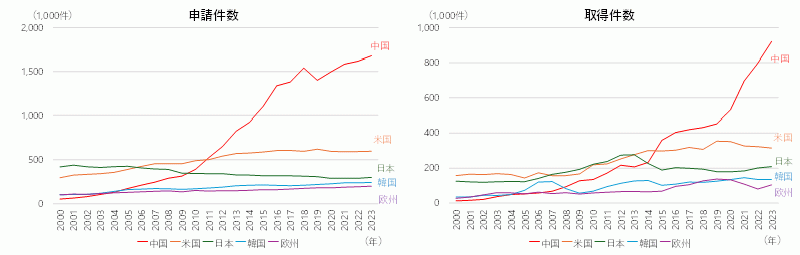
資料:WIPO 「World Intellectual Property Indicators 2024」
(https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4759![]() 、2025年2月26日閲覧)から作成。
、2025年2月26日閲覧)から作成。
国際的なイノベーションのランキングとして、同じくWIPOが公表しているグローバル・イノベーション・インデックスを見ると、中国は世界11位と、先進国と比較しても高いイノベーション活動・成果をあげていると評価されている(第II-2-1-17図)。
第Ⅱ-2-1-17図 主要国のWIPOグローバル・イノベーション・インデックス(2024)
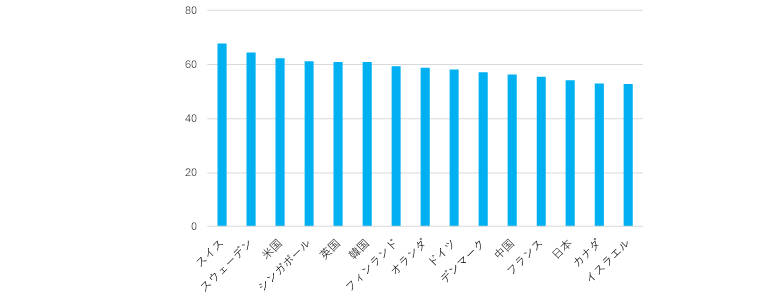
資料:WIPO 「グローバル・イノベーション・インディケーター(GII)」(https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/en/gii-2024-at-a-glance.html![]() 、2025年3月2日閲覧)から作成。
、2025年3月2日閲覧)から作成。
5. 産業資金
中国の産業への代表的な資金提供者としては、銀行、株式市場、政府引導基金、政府補助金等がある。年代やケースによって異なる提供者からの資金が利用されていると考えられる。
それぞれの資金の一般的な特徴や資金規模を概観していく。まず、企業の資金調達手段として最も重要と考えられる銀行からの借入れについて見てみる199。中国では、中国銀行などの大型国有銀行のほか、多くの銀行が融資を行っている。その時々の金融政策に影響されるが、銀行の融資総額は着実に増加しており、2022年の融資総額(残高)は個人向けも含めて約200兆元、前年比10%の増加となっている(第II-2-1-18図)。製造業を含め、様々な産業に資金を供給している。
第Ⅱ-2-1-18図 中国の銀行融資の推移
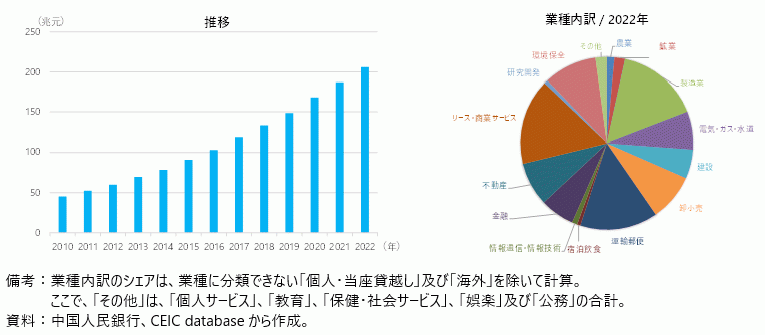
一方で、預金を集めて融資に回す銀行融資は、リスクの少ない大手国有企業や担保となる資産を有する企業への融資が優先され、信用度の低い企業(例えば中小の民営企業)や資産を持たない新興企業への融資に消極的となりがちである。銀行融資への過度の依存は、産業転換と高度化を遅らせ、銀行債務の累積を通じてシステミックリスクを高める懸念もある。新興企業のようなリスクの高い資金を調達するためには、リスクに見合った価格設定が可能な株式などの直接金融がより適していると言われる。中国政府は間接金融から直接金融への転換も進めている200。
中国においては、上海、深圳、北京の三つの証券取引所が設置されており、メインボードには大型国有企業や優良企業が多いが、革新的な新興企業向けに深圳証券取引所では創業板、上海証券取引所では科創板と呼ばれる市場も開設され、企業に直接金融による資金供給を行っている。上場企業は3証券取引所合わせて、金融を含め5,370社、時価総額は77兆元(2024年3月末)にのぼっている201。ただし、中国の証券取引所の上場手続き等の問題から、海外の証券取引所に直接上場する企業は多いとの指摘もある202。
これらに加えて政府の産業支援も指摘できる。政府引導基金は、政府の指導の下、政府自身が出資するとともに、より多くの資金を、金融機関や企業などから募り、重要産業に投資を行う。中央政府と地方政府が主導する両方があり、中央政府が主導する国家集成電路産業投資基金などが有名であるが、基金の数や出資額ではむしろ地方政府の方が多い203。資金提供の形態はケースによるが、基本的には投資が中心であり、銀行融資のように返済を前提とした債務性資金とは異なる。中国の民間シンクタンクの推計では、2010年代半ばに急増し、2023年第三四半期までに累計で約3兆元、1,600件近い基金が設立された(第II-2-1-19図)204。
第Ⅱ-2-1-19図 中国の政府引導基金の状況
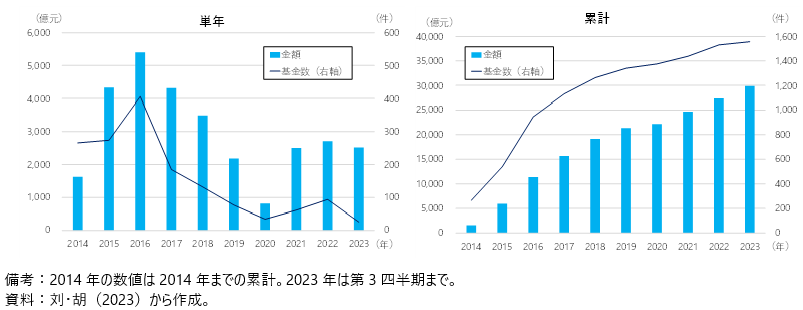
また、政府の産業支援として、政府から企業に直接資金を給付する政府補助金の存在もある205。中国政府による補助金の全体像は把握が難しいが、利用可能なデータとして、上場企業が受け取った補助金の規模を決算報告書から試算すると、2011年から2022年まで約5倍に拡大しており、2022年は約2,500億元の規模があると見られる(第II-2-1-20図)206。
第Ⅱ-2-1-20図 中国の上場企業に対する補助金の試算
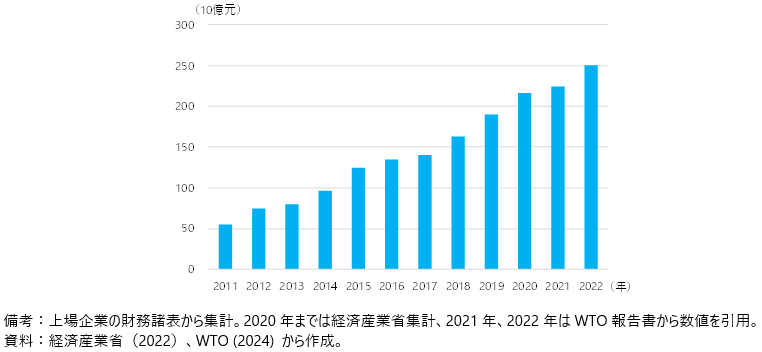
その他に、ベンチャーキャピタルの果たした役割も指摘されている。ベンチャーキャピタルは、未上場の新興企業(ベンチャー企業)に出資して株式を取得し、その企業が株式を公開(上場)した際に株式を売却し、大きな値上がり益の獲得を目指す投資ファンドで、官民ともに存在する。単に資金提供を行うのみならず、新興企業に欠けている経営スキルの提供やネットワークの活用など、幅広い支援で企業の成長を助ける場合が多い。その過程で情報やイノベーションのスピルオーバー、人的ネットワークの拡大など、一種のエコシステムが形成されることの意味も大きい。その金額規模を国際比較した資料を見ると、中国は米国には遙かに及ばないものの、欧州、日本を上回る規模の資金が提供されている(第II-2-1-21表)207。
第Ⅱ-2-1-21表 ベンチャーキャピタル投資の国際比較
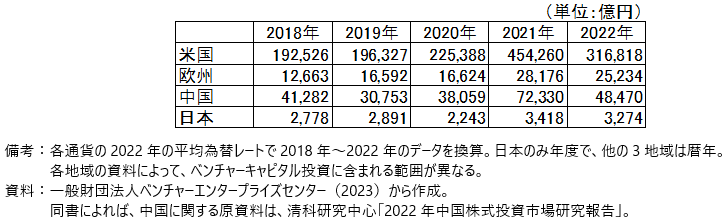
199 中国人民銀行が公表している、2024年の社会全体の資金調達額である社会融資総量約32兆元のうち、約半分に当たる約17兆元を人民元貸出が占める(フローベース)。また、関(2022)では、非金融企業部門の金融負債のうち、借入れが54.2%、債務証券10.8%、株式等19.0%、その他16.0%(2018年末)と報告している。
200 関(2022)
201 日本経済新聞「(きょうのことば)中国の上場企業とは~「国有」の存在感大きく」、2024年5月4日、3面。
202 Jin (2023)
203 丁(2024)
204 刘・胡(2023)
205 中国政府の産業支援には、他にも、低利融資、税の減免、土地など生産要素の安価提供などがあるが、ここでは企業に直接資金を提供する補助金を表記した。中国政府の支援は公開情報が限定的であり、スキームや交付要件等の詳細を含めて把握が難しい。特に地方政府レベルの支援について透明性の低さが指摘されている。その中で、上場企業に対する補助金は財務諸表の中に明記されるため、比較的試算しやすい。
206 経済産業省(2022)、WTO (2024)。
207 一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(2023)