第2節 中国の産業発展メカニズム
ここまで、中国の製造業が急激に拡大した背景にある産業基盤を、五つの要素ごとに見てきた。こうした要素がどのような因果関係で産業発展を実現したかを実証することは簡単ではない。しかし、中国の産業発展について多面的な理解を深める観点では、その産業発展メカニズムに関する学術的な議論を概観することは有益だろう。ここでは、①政治経済モデル、②地方政府間競争、③市場特性という三つに分類して中国の産業発展メカニズムを検討する208。
208 なお、マクロ経済の観点から、中国の製造業全体の生産・輸出が構造的に多い理由を、中国国内で所得・労働分配が抑制されていること、それによって生じるマクロ不均衡によって説明する議論もある(例えばPettis and Hogan (2024))が、ここでは中国における産業レベルでの発展のメカニズムに焦点を当てる。
1. 政治経済モデル
中国が改革開放をきっかけに市場経済化を進め、経済成長を実現する中で、中国の政治経済モデルに関する学術的議論が行われてきた。中国はそれまでの社会主義に基づく計画経済を改革して市場経済システムを段階的に導入した一方で、土地所有制や政党システム等に関して、他の資本主義国とは異なる特徴も維持している。近代化理論は、途上国が経済成長とともに民主主義体制に移行すると考えたが、現時点でそのような変化の潮流は見られない。高度経済成長期の日本や韓国、台湾等のシステムをモデル化した「開発主義国家」との一定の共通性も指摘されたが、中国では必ずしも特定省庁が経済発展を計画・主導しているわけではなく、地方政府や国有企業を含む各機関の分散的権力の下で発展しているという差異が注目された。
その中で、最も頻繁に議論されたのは「国家資本主義」である。国家資本主義というモデル自体も様々な観点から議論されたが、比較政治経済学の文脈では、所有権やその他の制度的・資金的介入を通じて経済運営を主導する広範かつ自律的な国家権力の役割が着目された209。その政策手段は、他の資本主義国からの学習を経て類型的には類似する手法を多く用いるようになっているが、本質的な差異もある。特に防衛・エネルギー・通信・金融等の戦略分野を中心に、選択的に、国家の強い影響力が行使されているとされる。また、後述するとおり、産業支援の全体像は不透明であるものの、その金額規模は、他国と比較して非常に大きいとされている。
しかし、国家資本主義モデルは、中国の広範な国家所有や国家権力を通じた政策方針の浸透・調整や、産業補助金を始めとする政府介入の内外市場への広範な影響といった特徴を指摘したが、それと実際の産業発展の間の因果関係に係る実証は容易ではない。丸川は、大多数の業種で補助金等を受ける企業が存在する中で、五か年計画の重点分野にどのような追加的な支援があったのか、元々成長が予測された産業が重点分野指定によって更に伸びたのかを検証するのは難しいと指摘する210。中央政府が公表する産業政策の目標と実際の政策実施が必ずしも一致しないとの分析もある211。
国家資本主義モデルはむしろ、国内経済運営に係る制度的脆弱性を補完するものとする説明や、内外の課題や脅威に対処するための動員システムとの説明において援用される傾向にある。第Ⅱ部第1章第5節で述べたとおり、産業補助金は一般論として貿易促進効果を持つとされるが、それは必ずしも生産性向上等を通じた産業発展を意味しない。中央政府の産業政策が産業発展に与える具体的な効果については、対象産業や手段ごとに子細に見ていく必要がある212。
209 Pearson et al. (2023)
210 丸川(2025)。その上で、丸川は、五か年計画の重点分野に指定された産業の営業収入・労働生産性の伸びが平均を上回ったかを検証すると、直近の第13次五か年計画の成功率は半分程度まで下落しているとしている。
211 Garcia-Herrero and Krystyanczuk (2024)
212 例えば、梶谷(2024b)は、アギオンらの研究では、産業政策が企業間の競争を促進するようにデザインされている場合には生産性引上げ効果が大きいこと、一方、ブランステッターらの研究では、補助金は生産性の上昇やR&Dの増加にはほとんど効果がないこと、さらに梶谷らの研究では、政府引導基金による出資は事業規模や純資産を拡大させたが、生産性や研究開発の向上に成果を上げていないこと等を指摘している。
2. 地方政府間競争
地方政府間競争は、中国の経済発展をもたらした重要なメカニズムと指摘されている。改革開放以降の経済発展の過程で、地方政府は各地域における経済や民政に関する意思決定の権限を委ねられ、高いGDP成長率を実現した地方政府幹部は昇進をかなえられた。この能力主義と昇進インセンティブが、地方間の競争を通じた経済発展をもたらした大きな要因とされる213。
産業政策に関しても、表向きには、中央政府が国全体の方針・計画を作成して、地方政府が地方の実情を勘案しながら具体策を実施するという関係にあるが、実態としては特に高度成長期の地方の裁量権は大きく、局面によって中央政府の方針に反した政策実施が行われることもあった。例えば、世界金融危機の際に行われた4兆元の景気対策では、その後、製造業の生産者物価が前年割れとなり、稼働率が低下するなど、過剰生産能力が問題となった。このときは中央政府である国務院からたびたび指導意見が発出されたが、地方政府が税収や雇用など地方経済の観点から抵抗し、中々実効性が上がらなかった。2015年に提起された「供給側の構造改革」で、当時の鉄鋼、石炭等の生産能力に削減目標が設定される等の対策が図られたこともある。
こうした地方政府の行動様式は、特に産業のキャッチアップ段階では、地方政府間競争を通じた政策効果の最大化を実現する効果が大きかったとされる。一方で、地方政府の財政や産業政策に関する低い透明性、GDP成長率を最優先するが故の無駄な投資、地方間での重複投資による資源の非効率な配分、地元企業や雇用を守ろうとする地方保護主義等の問題が生じやすいとの指摘もある。各地方に域内生産の最大化や雇用保護のインセンティブが働くことにより、特に景気後退局面では、全国の生産能力が国内需要を超過する状態が継続しやすく、国内需要で吸収できない製品の輸出量増加や価格下落を招くため、国際的な緊張をもたらすことになる。
213 ジン(2025)では市長経済(Mayor Economy)と呼んでいる。
3. 市場特性
中国の市場特性に着目して、企業による活発な市場参入と競争、効率的なサプライチェーン構築、実装と学習効果を通じた産業集積の形成等のメカニズムを指摘する議論もある。企業の活発な参入の理由としては、企業間での垂直方向への細分化、共通の技術・部材・市場の利用等による参入コストの低下などが指摘されている。また、需要面から市場を拡大するような政府の政策が、企業の市場参入を促し、価格低下や一層の需要拡大を導いたという指摘もある。
このメカニズムを説明する核となる概念は「規模の経済」である。規模の経済によって生産コストの逓減又は収益の逓増を生じるケースはいくつか指摘されている。第一に、製品一個当たりの固定費が減少することにより生産コストが減少する場合である。石油化学や鉄鋼など大規模な装置産業の場合が典型的に当てはまる。第二に、生産の繰り返しによる学習効果を通じて、技術やスキルが蓄積して歩留り率が向上するなど生産性が向上する場合である。半導体産業などがこれに当たると指摘されている。第三に、産業内に最終製品と複数の中間財が存在し、生産を繰り返すうちに中間財の多様性が増加し、分業関係が深化していく場合である。マーシャルの外部性とも呼ばれ、産業集積の利益を得られる。幅広い産業に当てはまるが、特に数多くの部品を必要とする機械産業で利益が大きい。
これを踏まえて具体的な議論を見ていく。渡邉の編著の各章では、中国の産業発展の特徴は企業の「旺盛な参入」と「価格の低下」が見られることだとし、それを実現させた要因を分析している214。中国では、特に国有銀行からの資金供給に頼れない民営企業を中心に、コストを削減して低価格を志向する企業行動が見られた。そのための仕組みとして、丸川は、「垂直分裂」と呼ぶ、企業間で生産工程を垂直方向に分業して、個々の企業が負担する設備投資や技術コストの範囲を狭める行動を紹介し、さらに「「支持的」バリューチェーン」と呼ぶ、優秀な部品サプライヤーのサービスを受けることで、経験やノウハウを持たない企業でも参入が容易になる仕組みを示した215。また、渡邉は「プラットフォーム」と呼ぶ、企業間で共通の技術、部材、市場等を利用することでコスト低下を図る枠組みが、参入障壁の引下げを通じて旺盛な参入を導いたと分析している216。このような企業行動が成り立つ前提として、自前にこだわらず積極的に外部調達を利用し、製品は広く外販するという、オープンで自由な取引関係が存在したことも指摘されている(第II-2-2-1図)。
生産工程の中で、技術難易度が高いために必要な固定費も高い基幹部品の生産は特定の企業が担当し、その基幹部品が外販によって多くの企業に供給され、共通の部材として利用されれば、その他の企業は開発費や固定設備費用を節約し、その他の工程に専念することができる。この結果、新規参入が容易になり、旺盛な参入が実現した。そして企業同士の競争が働き、価格の低下、需要の拡大が進んでいった。後述のとおり、山寨携帯電話がこのようなメカニズムで成長した具体的事例として挙げられている。
第Ⅱ-2-2-1図 中国で旺盛な参入を促す要因
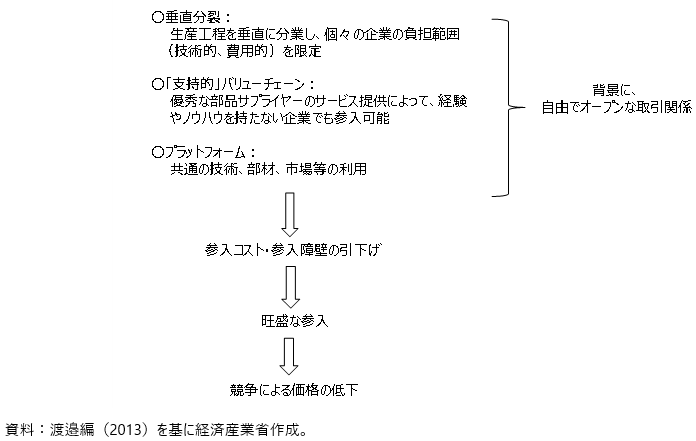
梶谷は、近年の電気自動車の産業発展過程における、「需要拡大型の産業政策」と「殺到する経済」の結び付きを指摘している217。「政府が補助金やインフラ投資によって市場をまず拡大し、しかる後にそこに民間企業が殺到することで分業が進展し、さらなる市場の拡大が生まれるという一連の好循環が生じる」。経済理論上の裏付けとしては、マーシャルの外部性を強調している。最終財産業と中間財産業が存在するとして、最終財の需要が拡大すれば、中間財に派生需要が発生し、中間財産業に新しい企業の参入が起こるとともに、中間財の種類が拡大し、より洗練された分業関係が構築されていく。このように生産に伴って分業が深化し、生産性が上昇していくことで、裾野産業を含む産業集積が形成され、中間財価格が低下していく。中間財価格の低下を受けて、最終財価格も低下し、それが最終製品の一層の需要拡大をもたらし、さらに中間財への追加需要を発生させる。このような最終財、中間財の両産業間の増幅効果もあって、一層の効率性、価格の低下を導いていくとしている(第II-2-2-2図)。
第Ⅱ-2-2-2図 需要拡大型の産業政策のメカニズム
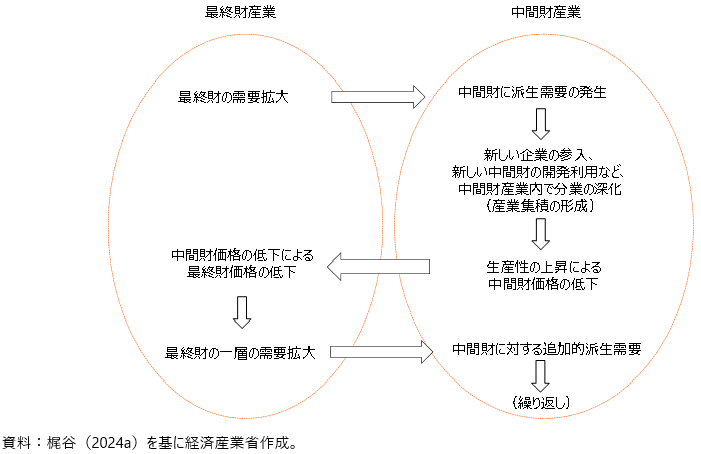
いずれのメカニズムでも、ひとたび規模の経済が働いて競争力が強まり、市場シェアを獲得すると、特に生産拡大に伴って費用が逓減していく製品においては、更に低価格を実現しやすく、ますます有利な状況が強まっていく可能性を示唆している。
関連する議論として、中国は新たな製品・サービスの開発から実装までの期間が非常に短く、急速な社会実装と普及が進むメカニズムがあるとの指摘もある。伊藤・高口は、中国における新たなIoTソリューションの迅速な普及について、政府の政策的支援、プラットフォーム企業の役割、政策的なグレーゾーンの存在に加えて、短い開発期間と低いエンドユーザーの初期導入コストを特徴とする「軽い」アプローチの重要性を指摘している218。この現象は、自動運転やドローン等の社会実装にも見られ、短期間での規模の経済の確立に貢献している可能性が示唆される。
214 渡邉編(2013)
215 丸川(2013)では「支持的」バリューチェーンは新規参入を容易にするが、これに依存したままでは製品の高付加価値化や他社との差別化は難しいことから、やがて垂直統合や社内の研究開発を高める方向へ向かうだろうとも指摘している。しかし、参入企業が跡を絶たない限り、この中国的産業組織は存在するだろうと述べている。
216 論文では、共通の技術や部品を利用する仕組みを「技術プラットフォーム」、調達や販売に共通の市場を利用する仕組みを「取引プラットフォーム」と呼んでいる。後の山寨携帯電話の例で登場する、多くの企業から基幹部品として共通に用いられたICチップセットは、研究開発費や固定設備を節約することができる技術プラットフォームである。また、多くの販売店が集積し、携帯電話や電子部品の取引が行われた北京の「華強北」電気屋街は、調達先や販売先を調べる調査コストを節約できる取引プラットフォームの例として説明されている。
217 梶谷(2024a)
218 伊藤・高口(2019)