第3節 個別産業の事例
中国の政治経済モデル、地方政府間競争、市場特性という産業発展に関する三つの観点を踏まえ、以下では具体的な産業分野における発展の事例を検討する。最初に中国の産業政策の変遷を整理した上で、山寨携帯電話、風力発電、太陽光発電、電気自動車の産業発展の過程を概観していく。これを通じて、中国の政治経済モデル、地方政府間競争、市場特性という要素が実際にどのように機能したのか、その共通性と多様性を検討する。
1. 産業政策の変遷
中国の産業政策の変遷について先行研究を基に概観する219。中国の産業政策は、改革開放後、計画経済から、市場経済を取り入れた経済体制へ移行する中で形成された。1989年、中国で初めて産業政策の名を冠した「国務院の目下の産業政策に関する決定」が国務院から公布され、政策の主体、優先順位、政府部門間の分担、投資の認可制度、目録設定などの産業政策の原型が示された(第II-2-3-1表)220。このときは主として産業構造の是正を目的としていたが、1994年には「90年代国家産業政策要綱」が公表され、インフラと基礎となる製造業の強化、積極的な支柱産業の振興(具体的には機械電子、石油化工、自動車、建設業)等が定められ、この下で個別業種の産業政策である自動車工業産業政策も作成された221。2001年に中国がWTOに加盟すると、外資の積極的な参入が行われるとともに、従来の高関税による保護などの手法は次第に影を潜め、通商ルールも意識した運営に変わっていった222。2006年の第11次五か年計画では、名称が「計画」から、「規画」に改称され、国家がビジョンを提案する意味合いに変わった223。それと同時に自主イノベーション、科学技術の振興が志向され、中長期科学技術発展計画も作成された。2011年の第12次五か年計画の際に、戦略支柱産業の選定が始まる。2015年に「中国製造2025」、「インターネット+」が発表され、2016年の第13次五か年計画では、製造業とインターネットの融合が提示され、新しい価値創造を目指す方針が示され、イノベーション主導の「国家創新駆動発展戦略」が公表された。
第Ⅱ-2-3-1表 中国の主要な産業政策の変遷
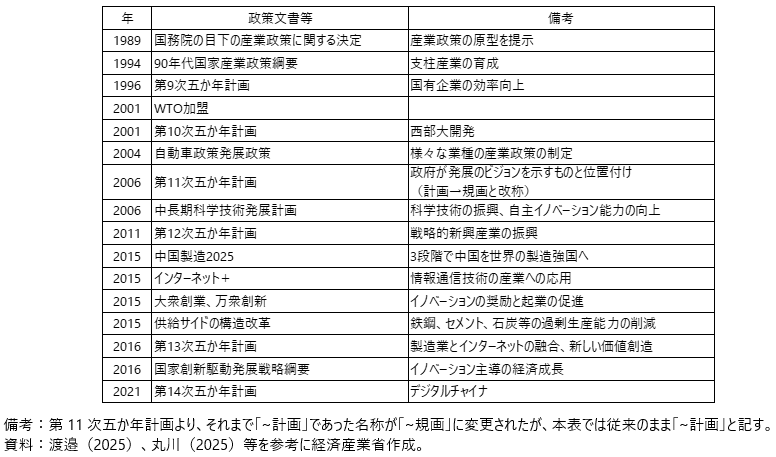
渡邉は、江を引用して、中国の産業政策の特徴は、特定の産業を対象とするターゲット型の政策であり、社会の資源を特定産業に優先的に配分することから、競争政策、公平な競争、競争中立性と矛盾する傾向が強いとの指摘を紹介している224。一方では、中央政府による総合的な産業構造への働きかけであり、結果的に産業間の調整が行われ、産業全体として規模の経済(マーシャルの外部性)の構築が出来ていることを評価する必要も指摘している。このマーシャルの外部性の構築そのものが、中国の産業競争力を突出させて強くしているという。また、産業政策の中には過剰生産の抑制も含まれ、2015年から「供給側の構造改革」が提唱され、鉄鋼、石炭等の過剰生産能力の削減が図られたこともある。
産業政策の立案・実施は、時代による変化はあるが、基本的に中央政府が国全体の方針・計画を作成して、地方政府が地方の実情を勘案しながら具体策を実施してきた。具体的にはまず、中央政府が奨励・制限・淘汰する産業の目録(リスト)を作成し、それに基づいて、投資・参入の許認可、強制的な淘汰、補助金、税制優遇、低金利融資、政府引導基金、政府調達における支援等が行われる。具体的な産業をリストに明示することで、政府が支援すると同時に、銀行や基金などが、投資の優先順位を決めることができる。一方で、これは特定の企業・産業に投資が集中し、過剰な供給能力が構築されがちな状況が生まれる要因ともなっている。地方政府は、こうした中央政府の方針も念頭に、地元経済を発展させるために、競って新規産業の創出や優良企業の誘致などを目指す産業振興を行ってきた。地方政府は、補助金や税制優遇等に加えて、土地・原燃料等の無償・安価提供等の政策手段を活用している。
219 渡邉(2025)、丸川(2025)、丸川(2020)
220 渡邉(2025)は、江(2021)を紹介しながら、中国の産業政策の歴史的変遷をまとめている。
221 丸川(2020)は、このときに初めて中国で「産業政策」の名を冠した政策が国務院から公布されたと指摘している。ただし、その目的は産業新興というよりは、投資、融資、外資導入等を規制・誘導して産業構造の不均衡(加工産業の投資過剰、エネルギー、運輸、素材の投資不足)を是正することにあったとしている。
222 丸川(2020)では、2001年のWTO加盟後は、従来の高関税等の手法は影をひそめ、1994年の自動車工業産業政策は無効となり、2004年に新しい自動車政策発展政策が発表されたとしている。
223 本稿では、これ以降も、日本で広く利用されている「五か年計画」の表記を使う。
224 渡邉(2025)、江(2021)
2. 山寨携帯電話
中国の携帯電話産業では、2000年代から2010年代にかけて、正規ブランドの製品とは別に、「山寨携帯電話」と呼ばれる非正規品を含めた低価格の携帯電話が急速に生産を拡大し、輸出でも途上国市場を中心に存在感を高めた225。丁・潘では、その低価格を実現させた背景として、法規制上の要因以外に、既に述べたような垂直的な分業関係やプラットフォーム(共通の技術、部材、市場)の利用等を通じた参入障壁の低下、旺盛な企業参入があったことを指摘している226。ここではその要点を紹介する。
山寨携帯電話の生産を支えたのは中小零細企業であり、当時のノキアなど国際的なトップブランドが、開発、資材調達、製造、販売などの工程を社内化していたのに対して、これらの企業は、生産工程を分割した分業体制をとり、小規模な企業でも参入が可能であったことを指摘している。このとき重要なのは技術的に高度で固定設備も必要な電子部品だが、メディアテック社等の有力企業が供給するICチップを多くの企業が共通に利用(技術プラットフォーム)することで、研究開発や固定設備のコストを節約したとしている。また、企業間の調達・販売では、深圳の専業市場を取引プラットフォームとして利用することで、取引先を調査するコストなどの取引費用も節約したと指摘している227。この結果、参入障壁が引き下げられ、多くの企業が参入した。ただし、共通のICチップという基幹部品を利用していることから、製品の差別化は困難で、その結果、激しい価格競争を招くことになった。その価格低下が一層の需要拡大を呼び、一層の企業の参入を促した。このように旺盛な参入から価格低下、より一層の需要拡大の好循環が働き、競争力が強化されたとされる228。梶谷は、山寨携帯電話の場合も、「需要が急速に拡大したことが、産業の新たな分業体制を自発的に生み出し、そのことが新規産業の参入を生み出し、生産性の向上をもたらす」というメカニズムが働いたと考えられる旨指摘している229。
225 もともと「山寨」とは山賊のすみかを指し、政府の生産許可を受けていない製造業者、正規のライセンスを支払っていないコピー商品などを意味しており、「闇携帯」とも呼ばれている。
226 丁・潘(2013)。中国では2008年まで、企業が合法的に携帯電話を生産するためには、研究開発センターと営業センターを設置し、2億元の登録資金を用意して、ライセンスを取得する必要があった。大部分の中小企業は、このような条件をクリアできず、やむなく無許可のまま生産を始めていた。また、これらの中小携帯電話メーカーは、特に初期には、国際トップブランド携帯の模造品を作る傾向があった。
227 深圳の「華強北」という電気屋街。ビルの中に小さな店舗が軒を並べ、携帯電話、電子部品等を扱っており、2010年頃、約3万店舗を抱えていたという。
228 このような山寨携帯電話は、2010年代に入ると、ファーウェイや小米など大手メーカーが低価格製品の販売に乗り出したことや、3Gを普及させたい通信事業者が大手メーカーと組んだ販売戦略で正規メーカー品を後押ししたことなどから、次第に下火になっていくが、ノキア等の外資企業の製品に対して地場企業を鍛え、人材を育て、中国の携帯電話産業を底上げする効果があった。
229 梶谷(2024)
3. 風力発電
世界主要国の風力発電の設備容量の推移を見ると、中国は2000年代後半から急速に風力発電を導入し、現在は世界一の発電容量を有している(第II-2-3-2図)230。その背景に国内企業の台頭があったが、2000年代初頭には中国国内の風力発電産業は未成熟であり、輸入に頼っていたという(第II-2-3-3図)。それではどのようにして中国の風力発電企業が育っていったのか、その要因を主として丸川、堀井を基に考える231。
第Ⅱ-2-3-2図 主要国の風力発電の累積導入設備容量
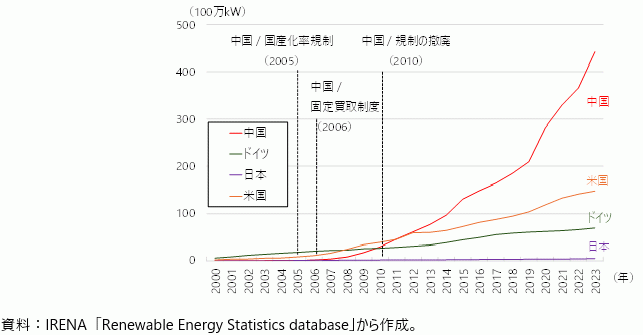
第Ⅱ-2-3-3図 中国の風力発電機の輸出入
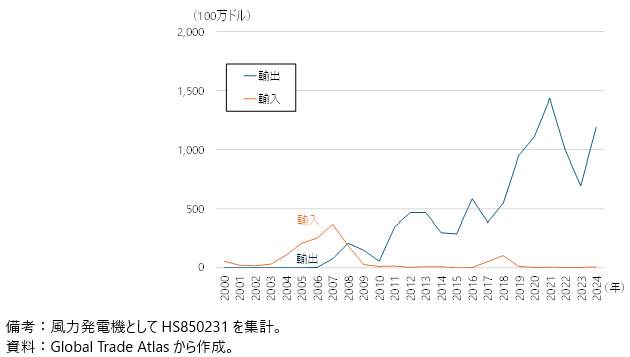
丸川は、風力発電設備産業が「風力発電に対する内需の拡大がもたらす経済的メリットを国内で獲得するために、幼稚産業保護政策の下で輸入代替産業として育てられた」として、国家主導で立ち上げられたことを指摘している232。政府の政策の推移を見ると、まず、2003年から政府自身が、コンセッション方式の国家プロジェクトとして、風力発電所の建設・運営を開始している(第II-2-3-4表)。これ以降、毎年、一定数の風力発電所が国家主導で建設されることになる233。さらに2005年、中国政府は「風力発電に関する要求的通
第Ⅱ-2-3-4表 中国の風力発電に係る法令・計画等
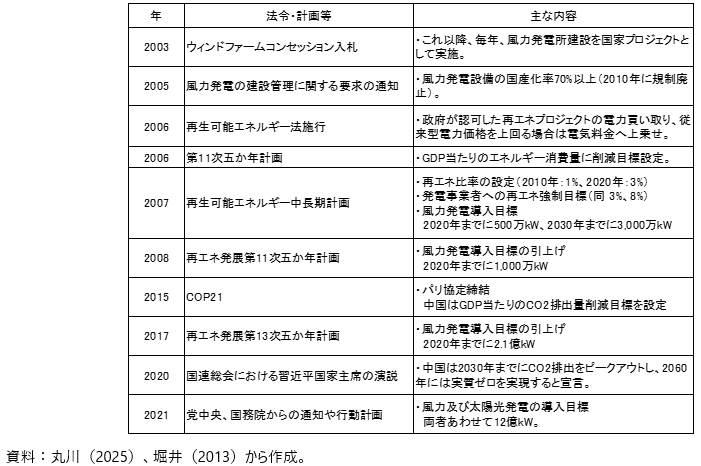
丸川は、政府主導で価格メカニズムを歪めて産業を立ち上げた弊害も指摘している。例えば、風力発電には需要を無視した参入が相次ぎ、2010年には目標の4.5倍もの設備容量となったことや、立地が風力発電に適した内モンゴル自治区など北部に偏在したため、送電網の限界等から買い上げられない(出力抑制)部分が多かったことなどを指摘している236。また、FIT制度についても、予想を超える参入企業数に対して、電気料金への賦課金が低く抑えられたため、再エネ業者に払う補助金の原資が不足して未払いが発生したことも指摘している。電気料金の値上げが難しいことから、買取価格が段階的に引き下げられ、補助金は廃止の方向に向かった。
一方で、世界的な地球温暖化問題への関心の高まりの中で、2020年、中国も2030年までにCO2排出をピークアウトし、2060年には実質ゼロを実現すると宣言した。これを達成するため、風力、太陽光合わせて12億kWという高い目標が設定された。2021年にFIT制度は終了したが、排出権取引が開始され、新エネルギーを多く導入した発電会社は、排出枠を売って利益を得ることが可能となった。
このような政策的な紆余曲折があり、結果として中国は風力発電大国となったが、その要因として、風力発電の業種特性も指摘されている。基幹部品のブレードなどは重量があり、輸送費が大きいため、現地生産が有利であった。同じ理由から、中国国内の生産は主として国内設置用で、輸出向けのシェアは低いことも指摘されている。
一方、堀井は、企業側の要因も分析し、当時の中国企業には風力発電の技術が不足しており、キャッチアップが必要だったと指摘している237。約1万点の部品のうち、多くの部品は中国が既に有していた機械産業からの応用が可能だったが、基幹部品のブレード、ギアボックスは技術の蓄積がなかった。重工系の大手国有企業が生産に当たったが、外国からの技術導入が鍵となったことが指摘されている。その際、中国国内に現地法人を設立していて競合関係にある外資企業は避け、別の外国企業から導入したことにより、研究開発などの投資コストを負わずに、先端技術を割安に入手することができた。
また、企業の分業関係を見ると、いくつかの外資企業の中国内生産法人は基幹部品を含む一貫生産(垂直統合)が基本だったのに対して、中国地場企業は分業体制を敷いており、ブレード等の基幹部品は有力な専門企業が生産することで、固定投資を少数の企業に集中させ、基幹部品を広く外販する体制をとっていた。最終工程を担う風力発電装置メーカーは、基幹部品を外部調達して組立工程に専念することで、参入や生産コストを引き下げることが可能となった。
230 IRENA, 'Renewable Energy Statistics database',
https://pxweb.irena.org/pxweb/en/IRENASTAT/IRENASTAT__Power%20Capacity%20and%20Generation/Country_ELECSTAT_2025_H1-PX.px/![]() (Accessed 13 March 2025).
(Accessed 13 March 2025).
231 丸川(2025)、堀井(2013)
232 丸川(2025)
233 堀井(2013)
234 政府が、再エネ発電事業者が収益をあげられるような購入価格を定め、その高値で買い取る負担を料金に上乗せして回収する制度。Feed in Tariff。
235 堀井(2013)では、制度上は固定価格による全量買取りとしながら、実際には入札による価格競争の上で、電力会社の供給量の一定割合以上を再生可能エネルギーとする、再生可能エネルギー利用割合基準(Renewables Portfolio Standard: RPS)制度に近い運用であったらしいことが指摘されている。
236 丸川(2025)。出力抑制率は、2015年には風力発電の15.5%、2016年には17.1%に上ったと指摘している。特に北方の寒冷地では、冬期は、熱、スチーム、ガスの供給源としても利用できる石炭火力が優先されるため、2015年1-3月期の吉林省で58%、遼寧省で40%に及んだ。
237 堀井(2013)
4. 太陽光発電
太陽光発電については、丸川を基に考えてみる238。既に見たように、風力発電は国家主導で中国の未成熟な幼稚産業を保護・育成したが、太陽光発電は、民間のベンチャー企業家たちが外国市場向けに生産・供給することを主眼として始まった。これに対して、一部の地方政府が個別企業に各種の支援を提供したが、中央政府は必ずしも積極的な産業育成を行わなかった239。
2000年代初期、中国の国内需要はほとんどなかったが、欧米や日本などの需要は固定価格買取制度の導入により拡大に向かっていた(第II-2-3-5図)240。これに目をつけた中国の新興企業は、中国国内で太陽電池の生産を開始して、ほぼ全量を輸出した。2000年代後半になると、これらの企業は米国に上場することで多額の資金を調達して、一気に生産を拡大し、中国の太陽電池の輸出が急速に拡大した(第II-2-3-6図)。しかし、2010年代に入ると、このような中国からの輸入急増に対して、欧米で貿易制限が課せられるようになった。その結果、中国のメーカーが苦境に立たされ、倒産も相次いだ。
第Ⅱ-2-3-5図 主要国の太陽光発電の累積導入設備容量
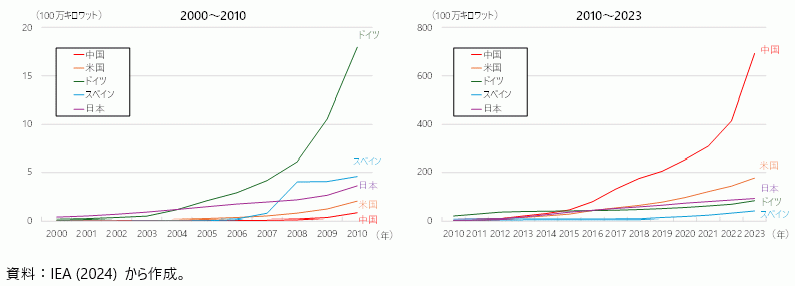
第Ⅱ-2-3-6図 主要国の太陽電池の輸出額
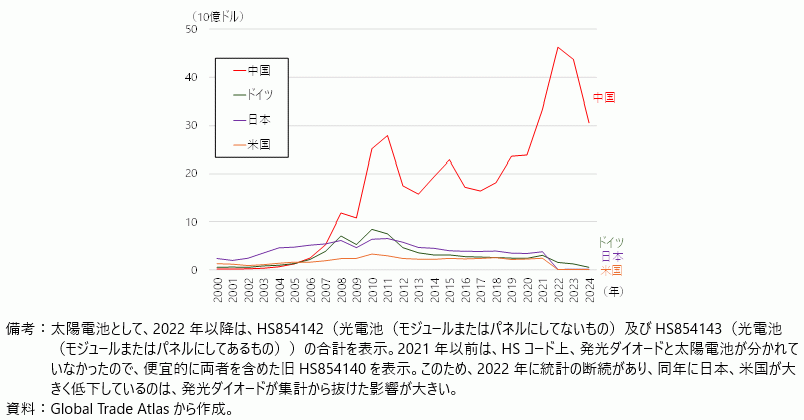
この状況に至って、中央政府は中国国内の需要を拡大する方針に移行し、太陽光導入目標を引き上げた(第II-2-3-7表)。もともと2007年の再生可能エネルギー中長期計画では、2020年までの導入目標が太陽光180万kWと、風力の500万kWに比べて非常に少なかったが、2012年の太陽光発電発展第12次五か年計画では、2015年までに2,100万kWと、5年前倒しした上に量を10倍以上に拡大し、翌2013年には3,500万kWと一層拡大している。これ以降、中国国内の設備容量は主要国を越えて大きく拡大していく。このような内需に支えられ、中国の太陽電池メーカーは息を吹き返した。その後、風力発電と同様に、送電網の限界や補助金の原資不足等に悩まされながらも、大規模生産の利益を享受し、積極的な投資と技術開発によって競争力を高めた。ただし、足下では需給バランスが崩れて過当競争が発生し、輸出単価の下落が顕著で、企業収益を圧迫しているとの報道もある241。
第Ⅱ-2-3-7表 中国の太陽光発電の設備容量の目標
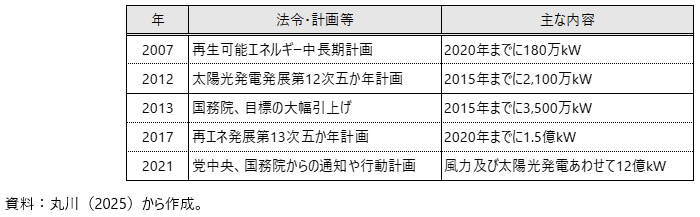
238 丸川(2025)を中心に、Marukawa (2012)、日本経済新聞「経済教室「結果オーライ」の再エネ振興 中国の産業政策のいま」、2023年3月10日(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD2211M0S3A220C2000000/)等を参照。
239 丸川(2025)では、中国の地方政府による支援も見られたことが指摘されている。地方政府が出資する事例もあったが、主に工業団地内のまとまった土地を提供するなどの支援であった。
240 IEA(2024)
241 東洋経済オンライン「中国の太陽光パネル「利益なき繁忙」の手詰まり(中国「財新」の1月17日記事を日本語で配信)」、2025年2月5日、https://toyokeizai.net/articles/-/855293 (2025年3月31日閲覧)。
5. 電気自動車
近年、中国で電気自動車の生産・販売が急増し、急速に産業として発展してきたことが注目されているが、これはどのような要因に支えられてきたのかを考える。
中国政府は、2010年に国務院が「新エネルギー自動車」を「戦略的新興産業」の一つとして挙げ、電気自動車(EV)を重点的に支援するようになった。2012年の「省エネ・新エネ自動車発展計画」(国務院)では、BEV・PHEVの生産・販売量を2015年に50万台、2020年に200万台とする具体的な数値目標を定めた。こうした政策の下で、購入補助金、税の減免、インフラ整備補助、デュアルクレジット制、ナンバープレート取得の優遇などの具体的な政府支援と規制が行われた。こうした政策支援の資金的規模は、正確なデータは得られないものの、他国と比較しても極めて大きかったと推計されている242。また、購入補助金については、支給対象を限定することで事実上国内メーカーを保護するスキームとなっていた問題が指摘される。例えば海外の有力な電池メーカーが指定電池メーカーのリストに含まれず、中国の電池メーカーの飛躍の要因となったとされる243。
同時に、産業レベルの発展メカニズムが機能しているとの指摘がある。まず、2014年頃から多数の起業家が電気自動車ベンチャーの立上げに動き、活発な新規参入が起こった。それ以前から大量に生産されていた低速四輪電動車が産業基盤となったとの指摘もある244。旺盛な参入は完成車メーカーだけでなくサプライヤーも含め、過当競争とも表現される激しい競争を生み、各メーカーが独自の戦略によってシェア拡大を目指した。丸川は、「(前略)新規参入が増えて、各社がさまざまな需要に応える多種多様なEVを開発したことで、中国産EVの市場が内外に拡大した効果は無視できない」としている245。
また、電気自動車の基幹部品のモジュール化を通じたオープンな取引も、産業発展の要因として指摘されている。電気自動車の主要部品として、コストと性能に大きなシェアを持つ蓄電池がありCATLなどの専業メーカーが有名である。また、駆動モジュール(モーター、インバーター、減速機など)は電動アクスル(e-axle)としてパッケージ化され、一つの部品として切り離して生産することが可能となった。かつて自動車は摺り合わせ型製品といわれたが、電子機器のようにモジュール化が進み、主要部品は外部から調達し、車体デザインとコンセプトだけ自社で開発する、ファブレス型電気自動車メーカーの参入が可能となった。実際に携帯電話メーカーの華為や小米、不動産業の恒大など異業種からの参入企業が現れた。
梶谷・高口は、中国政府の従来と異なる需要拡大型の産業政策と、それを契機とする「殺到する経済」に着目している246。政府の購入補助金や充電ステーションへの補助のような、需要を拡大する政府支援が、電気自動車の生産拡大を促し、それが蓄電池を含む部品産業への派生需要を生み、この分野への殺到ともいえる新規参入を誘発した。この部品産業の拡大が、マーシャルの外部性といわれる産業集積の効果を生み、中間財の価格を引き下げ、それが最終財である電気自動車の価格引下げや一層の需要拡大をもたらした。このような需要拡大策は、企業の自由な取引を前提としており、従来の特定企業の優遇とは異なる有効な産業政策となり得ると説明している。さらに、中国の電気自動車における需要拡大型の産業政策は、後述する自国市場効果を生み、規模の経済を確立して輸出を拡大させた可能性を指摘している。
ここで視点を変え、昨今、輸出の急増が見られる新エネルギー自動車の生産地の配置を概観する。地域別の生産台数を表示した第II-2-3-8図を見ると、鉱工業の付加価値生産額が大きい広東省や江蘇省等の生産台数が多い一方で、一部の地域を除き、ほとんどの地域で生産が行われていることが分かる。地理的な産業集積を通じた規模の経済の構築と同時に、地方間での誘致・競争が行われている可能性も示唆される。
第Ⅱ-2-3-8図 中国の地域別新エネルギー車生産台数
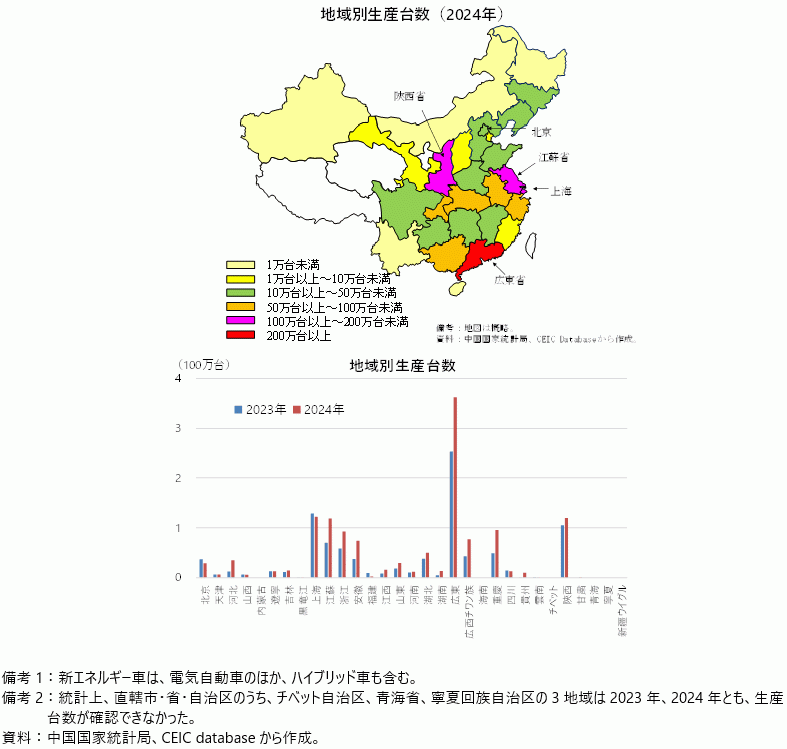
242 Scott Kennedy, 'The Chinese EV Dilemma: Subsidized Yet Striking', Center for Strategic and International Studies (CSIS) Blog, 20 June 2024, https://www.csis.org/blogs/trustee-china-hand/chinese-ev-dilemma-subsidized-yet-striking![]() (Accessed 31 March 2025).
(Accessed 31 March 2025).
243 丸川(2025)
244 梶谷・高口(2025)
245 丸川(2025)
246 梶谷・高口(2025)
6. 小括
ここまで、山寨携帯電話、風力発電、太陽光発電、電気自動車の4分野で、中国の産業発展の過程を概観した。これら4分野は、WTO加盟以降に中国国内で大きく拡大した製造分野の新産業という共通点があるが、中国の政治経済モデル、地方政府間競争、市場特性という産業発展メカニズムの3側面がどのように相互作用し、機能したかは分野ごとに多様性がある。ただし、産業レベルで見れば、積極的な政策介入の有無にかかわらず、創出された需要に対して多くの企業が参入し、国内市場での激しい競争、分業とサプライチェーンの効率化、実装と学習を通じて急速に産業集積の形成を進め、規模の経済を確立するという共通性は示唆される。また、太陽光発電では外需縮小への受動的対応として中央政府が開始した国内需要拡大型の政策が、電気自動車では中央政府によって戦略的に用いられた可能性があることも、一つの示唆と考えられる。いずれにせよ、風力発電、太陽光発電、電気自動車に共通して、産業の急速な発展段階において、中央政府の産業補助金や規制等による政策支援があったことは指摘されよう。