第4節 産業発展の貿易投資への影響
前節まで、中国の急速な製造業発展の背景にある産業基盤と発展メカニズムについて検討してきた。では、こうした中国の産業発展は、世界の貿易投資関係やルールベースの国際経済秩序にどのような影響を与えてきたのか。それは、第Ⅱ部第1章第5節で検討した産業政策と貿易との関係を巡る議論に、どのような含意を与えるだろうか。
第Ⅰ部第1章第2節で見たとおり、近年の中国経済は、コロナ禍後の景気低迷の中で過少消費という構造問題が顕在化し、輸入停滞とデフレ輸出が加速している。また、足下では米中貿易摩擦を回避する流れがアジア周辺国を始めとする新興国・途上国への輸出シフトの兆候を見せている。これらは近年顕在化している潮流だが、その根底には、本章で見てきた中国の中央政府の産業政策、地方政府間競争、規模の経済に支えられた中長期的な産業発展がある。こうした認識の下、本節では、中国の産業発展が貿易投資に与えた影響と、その世界の貿易投資関係やルールベースの国際経済秩序への含意について検討する。
1. 貿易理論の展開
中国の産業発展が貿易投資に与えた影響を考える前に、そもそも貿易が行われる理由と輸出国の条件を考えてみたい。伝統的な貿易理論では、各国間の貿易構造は、各国内の生産要素の賦存度等の違いに起因する比較優位によって決まり、自由貿易は全ての国の経済厚生を高めるとされた。ただし、この理論では、技術や生産要素の賦存量の差が小さい先進国同士で貿易が起きる理由が必ずしも説明できなかった。
これに対して、クルーグマンが提唱した新貿易理論では、消費者は製品の種類が増えることでも満足度が高まるとして、技術や生産要素の賦存量が近い国の間でも貿易が生じると説明した。この理論では、それまで考慮されていなかった、「規模の経済」(収穫逓増)が働くことや、貿易には距離や輸送量に応じた輸送費がかかることを仮定して考察している。こう仮定すると、ある財の生産は消費市場が大きな国に立地しやすいという結論が導かれる。規模の経済が働くため、自国の消費市場が大きいほど、製造単価を引き下げることができ、そこから市場の小さな国に輸出すれば輸送費も節約できる(反対に小国から大国に大量の財を輸出するには輸送費がかさんでしまう)からである247。
このように、ある財で大きな消費市場を持つ国には、需要以上に生産が集中し、純輸出国になるという傾向は、「自国市場効果」と呼ばれている。自国市場効果は、ある国の需要が増加して産業が立ち上がり、規模の経済が働き始めると、他国の生産拠点が移転してくる可能性を含意している。規模の経済(収穫逓増)が強く働く産業は、独占・寡占になりやすいことが指摘されてきた。
さらに、生産サイドでも、学習効果やマーシャルの外部性によって時間の経過とともに規模の経済が働く産業では、先行者が利得を得る効果はより強く現れる可能性がある。その場合、この大国では他国よりも急速に生産が拡大して、内需以上の生産分は海外に輸出される可能性が高く、貿易上の緊張関係を生み出す可能性もある。
その後、貿易理論では、メリッツが新々貿易理論を提唱した。そこでは、企業によって生産性が異なり、また輸出を開始するためには固定費もかかると仮定して、輸出に必要な最低限の生産性を超える企業のみが輸出を行うと考えた。貿易自由化は固定費の削減を通じて、より多くの企業が輸出に携われるようになるとともに、生産性の低い企業は市場から退出を促すことで、社会全体の生産性を上げるとした。さらにヘルプマンは、メリッツの理論に海外直接投資の要素を導入した。海外直接投資にはより大きな固定費用が必要と仮定して、生産性の最も高い企業は海外直接投資を選択し、多国籍企業として海外に展開し、次に生産性が高い企業が輸出を行い、それに及ばない企業が国内企業となると考えた。
247 田中鮎夢「国際貿易と貿易政策研究メモ(RIETIコラム)」、https://www.rieti.go.jp/users/tanaka-ayumu/serial/index.htm![]() (2025年6月6日閲覧)。
(2025年6月6日閲覧)。
2. 中国の輸出拡大
中国の輸出拡大がもたらした影響として、第Ⅱ部第1章第1節では、中国ショック研究の輸出先国側に焦点を当てた分析を見たが、ここでは中国側から見た産業発展と輸出拡大の状況を見ておく。中国では2001年のWTO加盟後、各国市場へのアクセスの改善にも助けられ、輸出が急増した(第II-2-4-1図)。2004年には前年比約35%という高い伸びを実現し、2001年から世界金融危機が起こる2008年までの間に、輸出額は約5.4倍、輸出の平均伸び率は年率約27%となった。Autor et al.が米国の製造業雇用に損害を与えたと指摘した中国からの輸入急増248は、これほど短期間で急激に起こったものであった。
第Ⅱ-2-4-1図 中国の輸出の推移
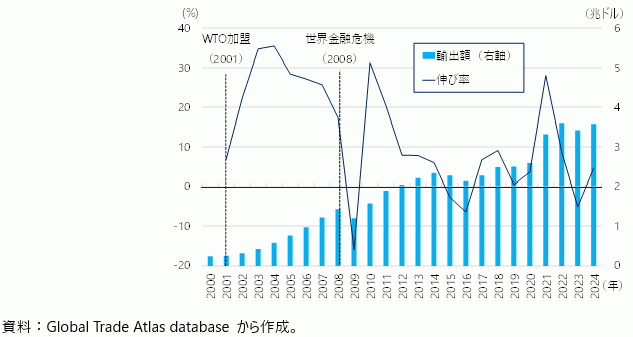
他方、中国から見ると、輸出の対GDP比率は、世界金融危機頃をピークとして低下傾向になった(第II-2-4-2図)。これは主に、世界経済悪化による輸出の萎縮とともに、4兆元の景気対策を契機に総資本形成等の内需が拡大したことが背景となっている。ただし、輸出の絶対額では長期的には拡大傾向を続けており、他国から見た中国の輸出は増加し続けた。
第Ⅱ-2-4-2図 中国のGDPに占める輸出のシェア
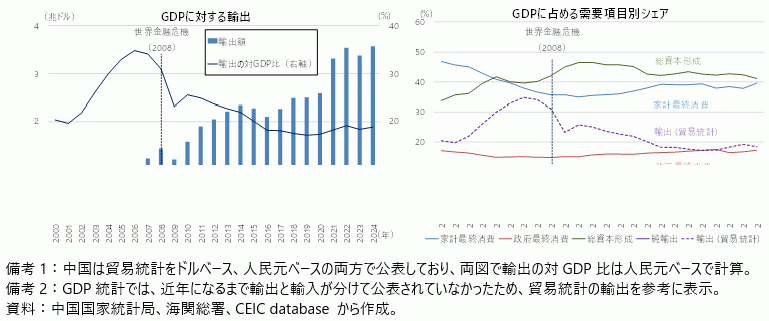
中国の輸出の量的な拡大だけでなく、輸出産品の質的変化にも着目する必要がある。中国の主要輸出品の推移を見ると、2000年代初期にはシェアが大きかった衣類、履物、家具などの軽工業品は、今なお主要輸出品ではあるものの、そのシェアを大きく減らしてきている(第II-2-4-3図)249。それに代わって、2000年代はパソコンのシェアが拡大し、2010年頃にピークを迎えている。次いで、2010年代は、携帯電話、集積回路のシェアが拡大して、それぞれ2010年代後半、2020年代初頭まで拡大が続いた。太陽電池も、2010年代から輸出を拡大してきている。2020年代に入ると、自動車、リチウムイオン電池のシェア拡大が目覚ましい。自動車については、中国は2020年後半から、ガソリン車を中心とする自動車の輸出を急速に拡大し、主要輸出品目の一つにまで発展した。EVは、金額・台数共にガソリン車よりも少ないが、それまでほぼ輸出がなかったにもかかわらず欧州やタイなどへの輸出が急増したことから、国際的な注目を集めた(第II-2-4-4図)。
第Ⅱ-2-4-3図 中国の主要輸出品の推移
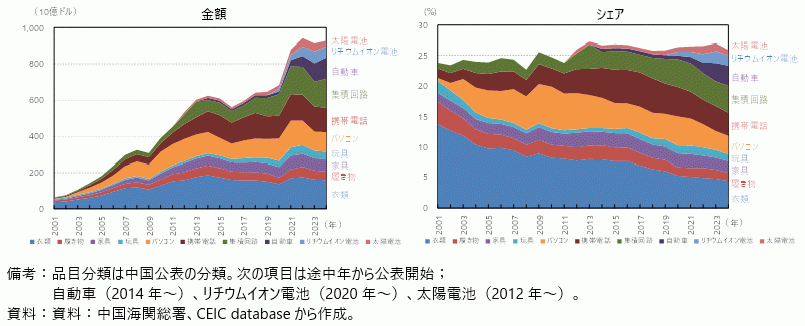
第Ⅱ-2-4-4図 中国の自動車(原動機別)輸出の推移
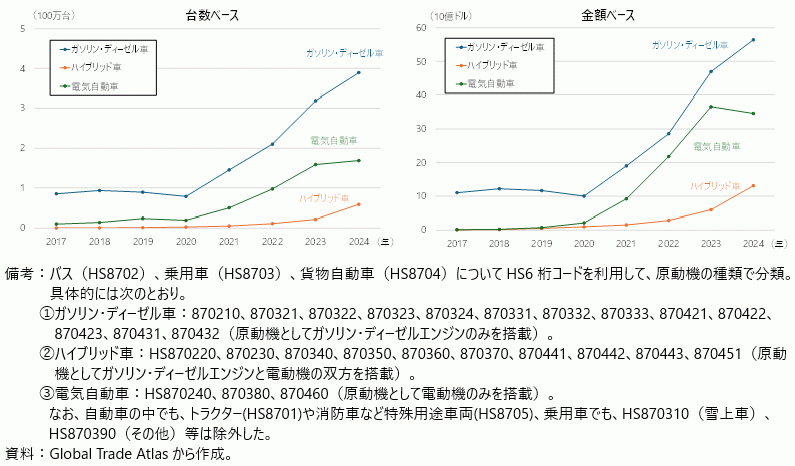
このように、先端産業を含む新たな産業の集積が中国国内で次々に創出され、規模の経済を確立した輸出産業となってきている250。
こうした中国の中長期的な産業発展に加えて、コロナ禍後の新たな要因が、中国の輸出のトレンドに変化をもたらしている。まず、第Ⅰ部第1章第2節で見たように、コロナ禍後の中国経済は、不動産不況をきっかけに景気低迷とデフレ傾向に陥ったが、政策的には生産サイドへの投資が促進され、国内消費が不足するマクロ経済の構造的な不均衡問題が顕在化している。その結果、直近ではGDP成長率の輸出依存が強まっているだけでなく、輸出全体の単価が下落するデフレ輸出の拡大傾向が見られる。輸出単価の動向には品目ごとの差異があるが、特に鉄鋼や太陽光発電パネルでは明確な輸出単価の下落傾向が看取される。
加えて、足下の米中貿易摩擦の激化が、中国の輸出先を転換させる可能性がある。足下では、2025年4月の第二次トランプ政権の関税政策を受けて、中国の輸出がアジア周辺国を始めとする新興国・途上国にシフトする兆候が見られる。今後の米国関税政策や中国の対応によってこの流れは変化する可能性もあり、注視していく必要がある。輸出単価の下落を伴う輸出拡大や輸出先の転換という新たな要因は、世界経済の減速傾向の中で、貿易摩擦を激化させる可能性が懸念される。
上記はあくまで直近顕在化している現象だが、その根底にある中長期的な構造変化として、WTO加盟後の中国の輸出拡大をどう見るかについて、中国の産業発展メカニズムに関する見方とも関連して議論が行われている。Bownは、中国の産業補助金を始めとする産業政策が、近隣窮乏化政策として国際的な外部不経済を生み出し、他国にとっての交易条件を悪化させた可能性があるとした251252。既存のWTO協定や紛争解決手続はこうした近隣窮乏化政策に有効に対処できていないとの問題提起を行っている。渡邉は、中国の産業政策が構築する規模の経済に着目し、単独で産業政策を実行した特定国に「規模の経済の利益」が集中し、他国がコストを引き受ける「市場の失敗」が起こるという問題を指摘した253。この問題に対しては、「規模の利益」を特定国が独占しない事前の仕組みと、独占が起こった場合に経済的な支配力を濫用しない事後の仕組みが必要であるとしている。この論点は、現下のルールベースの国際経済秩序を揺るがしている最も重要な構造問題と言え、その強化・再構築を展望する上で避けて通れない課題であろう。
248 Autor et al. (2013)
249 三浦(2025)。特に第II-2-4-3図は同レポートの図表4を参考にした。
250 なお、鉄鋼や化学等、シェアが大きく変わっていない輸出品は図表に含まれていないことに留意。
251 Bown (2024)
252 なお、中国自身にとっても、自分の購買力を示す交易条件(輸出価格/輸入価格)を改善させずに低位にとどめるという「弊害」が起きているという指摘もある(渡邉(2025))。
253 渡邉(2025)
3. 中国の対外直接投資の活発化
近年、中国の対外直接投資の動きは活発化している。中国の対外直接投資は、2000年代初頭はほぼ皆無だったが、次第に拡大し、2010年代半ばには対内直接投資を上回る規模まで成長した(第II-2-4-5図)。この頃の対外直接投資はM&Aが中心であり、グリーンフィールド投資は多くなかった(第II-2-4-6図)。しかし、2015年の為替レートの下落、外貨準備の急減を背景に、対外直接投資の管理が厳格化され、2016年をピークに減少に転じる。その後、2019年頃から対外直接投資が再度増加し始めている。この時期に増えているのは主にグリーンフィールド投資である。
第Ⅱ-2-4-5図 中国の直接投資の動向
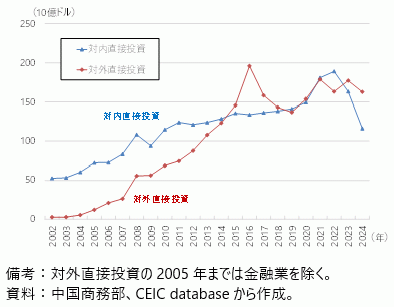
第Ⅱ-2-4-6図 中国の対外直接投資と&Aの推移
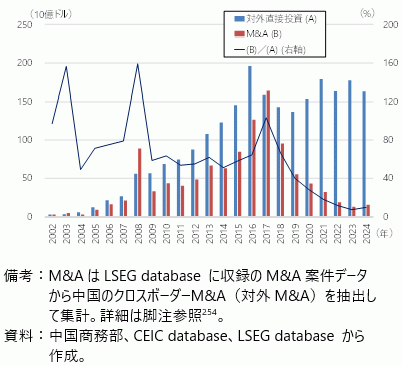
中国の投資対象国は、フローベース、ストックベースとも、香港が6割を占め、ケイマン諸島、英領バージン諸島など租税回避地と併せて7~8割、さらにシンガポール、ルクセンブルクなど金融センター向けも含めると相当な割合となる(第II-2-4-7図)。これら投資先国・地域を起点に、更に第三国に投資されているケースが多いと考えられるが、そうした投資の流れをデータから把握することは困難である255。それ以外の国を見ると、2023年時点のストックでは、上位には米国、豪州、英国、ドイツ、ロシア、カナダなど先進国が多く並ぶ。他方、2023年のフローを見ると、米国など先進国も含まれるが、インドネシア、ベトナム、タイ、カザフスタン、マレーシア、カンボジア、ラオスなど、ASEAN諸国や一帯一路の新興国が多く見られるようになっている。
第Ⅱ-2-4-7図 中国の主要相手国・地域別の対外直接投資(2023年)
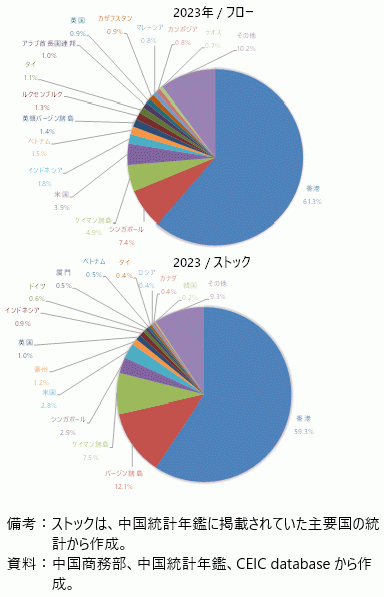
中国の対外直接投資の相手国・地域別の推移を見ると、近年ではASEAN諸国を始めとした周辺国や一帯一路沿線国向けが拡大する一方、米国、EUなど先進国向けは低下又は伸び悩んでいる様子がうかがえる(第II-2-4-8図)。論理的には、貿易摩擦の激化に対しては、摩擦を生じた主要輸出先に対して直接投資が行われ、現地での生産・雇用が拡大することで摩擦が緩和されるという考え方もあるが、現時点ではそのような顕著な動きは見られていない。
第Ⅱ-2-4-8図 中国の地域別対外直接投資の推移
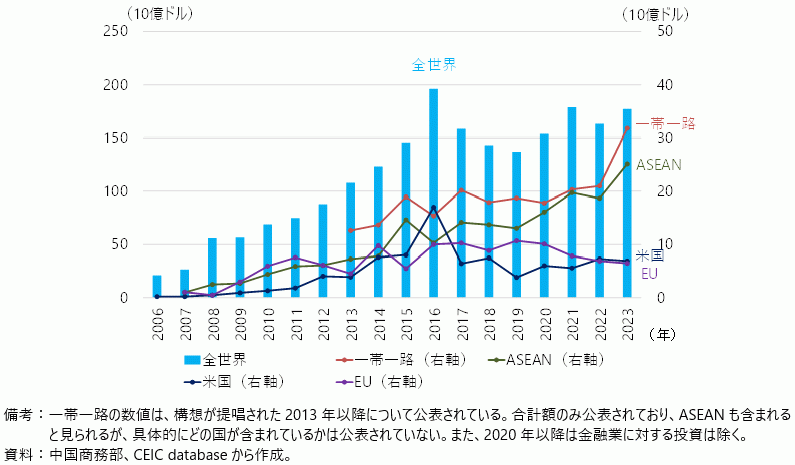
その背景として、2010年代半ばには、中国政府が不動産、娯楽・観光など非実体経済分野への過度な投資による資本流出を問題視し、審査を強化したことが指摘されている256。また、特に近年では、欧米諸国側での地政学的な懸念や技術流出への警戒、それを踏まえた投資審査の強化等が影響している可能性がある257。そうした中で、ASEAN諸国や一帯一路沿線国への直接投資は、資源・安価な労働力・消費市場へのアクセス確保や、貿易摩擦を回避するための生産移転等を進めている可能性を示唆する。こうした直接投資は、受入国との政治経済関係の強化につながる可能性もある一方、一部中国企業が投資先国で労働問題等を引き起こす例もあり、現地への具体的な裨益は注視する必要があろう。
254 具体的には買収側企業(親会社が存在する場合は最終親会社)の国籍が中国で、被買収側企業の国籍が中国以外の案件を集計。データ抽出は2024年11月8日時点。M&A取引の完了日の暦年で集計。買収額が公表されていない案件は結果的に集計から外れる。両統計で平仄が異なる点には注意。本M&A統計は最終親会社の国籍で判別されるため、第三国に立地する子会社が買収側企業としてM&Aを実施した場合、M&A統計では中国のM&Aとなるが、通常の直接投資統計では、第三国の直接投資と見なされ、中国の直接投資にはならない。M&Aと対外直接投資の比率は便宜的にM&Aの集計を中国商務部公表の対外直接投資額で除している。2000年代初頭は案件も少なく、数値の変動が大きい。なお、中国は本土のみで香港は含まない。
255 例えば香港については、中国本土の投資家が香港を起点に第三国に投資するケース(実質的な中国の対外直接投資)がある一方で、中国本土の投資家が外資企業優遇を得る等の目的で香港から中国本土に投資するケース(いわゆる「返程投資」)や、中国以外の第三国の投資家が香港を起点に中国を始めとするアジア地域内向けの投資を行っているケースもあり、香港の対外直接投資のデータから実質的な中国の対外直接投資の詳細を把握することは出来ない。こうした制約を認識した上、ここでは、取得可能な範囲のデータを活用して投資対象国を見ていく。
256 玉井(2020)は、2015年夏以降、人民元が元安方向に移行する中で、直接投資を装って、海外に資本を持ち出す企業が増えたことや、不動産、娯楽・観光など過剰な投資により経営難に陥る企業が増加したことを指摘している。特に2016年は、欧米の映画館、ホテル、不動産等への投資が増大した。
257 米国では、2018年、外国投資リスク審査現代化法により対米外国投資委員会(CFIUS)の審査が強化された。欧州では、2016年の中国による独工作機械のクーカ社買収を契機に中国への技術流出の懸念が高まり、2019年にEU対内直接投資審査規則が発効し、2020年10月から全面適用された(経済産業省(2024b))。
4. 中国の貿易投資関係に係る課題
(1) 近年の貿易関係における緊張の高まり
先述のとおり、近年、中国からの輸出増加が国際的な緊張を高めている。特に米国は、長年にわたる対中貿易赤字を問題視しており、近年の強硬な対中通商政策の背景になっている。米国は、中国からの輸入増加により貿易赤字が拡大し、2018年に一旦増勢は止まったものの、その後も高水準の赤字が続いている(第II-2-4-9図)。
第Ⅱ-2-4-9図 米国の中国との貿易の推移
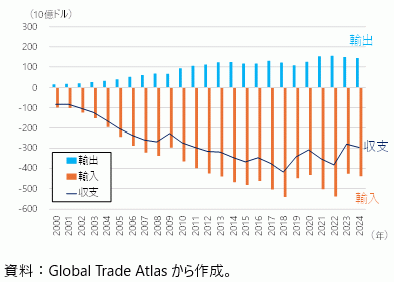
こうした中で、米国は2024年5月、通商法301条関税の見直しにより、中国産電気自動車に対し100%の追加関税を、中国産鉄鋼・アルミに対し25%の追加関税を賦課すると発表した。この際、バイデン大統領は、「中国は、巨額の補助金により世界が吸収できる以上の生産を支援し、過剰生産された産品を不当に安い価格で市場に投入し、世界中の製造業者を廃業に追い込んだ」と発言した。さらに、同年12月には、特定のタングステン製品に対して25%の追加関税を賦課し、太陽光パネル用ウエハー及びポリシリコンに対する追加関税を50%に引き上げると発表した。同じく12月には、米国は基礎半導体に対する新たな301条調査を開始している。
EUは、2023年10月に中国産バッテリー式電気自動車について、反補助金調査を開始した。フォン・デア・ライエン欧州委員長は、その理由として、中国では明らかに過剰生産能力が存在し、輸出に流れること、中国政府による直接・間接の補助金によりその傾向は強まり市場を歪めることを説明した。2024年7月に暫定課税が開始され、10月に最終報告書が告示されて最大約35%の補助金相殺関税を課すことが最終決定された。
こうした中国からの輸出増加に対する懸念は欧米諸国に留まらないが、加えて、中国と欧米の貿易摩擦が第三国に対しても影響を与える可能性がある。上述のような貿易措置によって欧米諸国に輸出出来なくなった製品が、周辺国や新興国等の第三国に流れ、急激な輸出増につながる可能性があるからである。
これを示唆するデータとして、中国産品に対する貿易救済措置の件数は増加傾向にある。2020年以降のアンチ・ダンピング調査開始件数が多いのは、インド、米国、EUである。2024年にはブラジル、コロンビア、トルコの調査開始件数が増加している。業種別では、2020年以降に最も件数が多いのは卑金属(鉄、アルミ等)で、次いで化学品や、風力発電塔等の機械類も多くなっている。2020年以降の反補助金調査開始件数が多いのは、米国、豪州、カナダ、EUであり、ブラジルやインドも活用している。業種別では、2020年以降に最も件数が多いのは卑金属(鉄、アルミ等)で、次いで機械類が多い。
こうした貿易関係を巡る緊張状態を改善するためには、貿易政策や産業政策に係る透明性を確保し、国際的な信頼醸成を進め、公正な競争条件を確保するための建設的な取組が重要になる。以下では主要な課題を指摘する。なお、WTO協定等との関係における具体的な諸問題の詳細については、毎年、経済産業省産業構造審議会不公正貿易政策・措置調査小委員会で公表されている不公正貿易報告書で説明されている。
(2) 政策/政府支援の不透明性
中国では、近年、一定の改善が見られるものの、公表されていない法令や指導文書の存在が指摘され、また交付された法令の中身が抽象的で、規制内容に不透明性が存在する例も見受けられる258。WTO協定上求められている補助金の通報が不十分であるという指摘もなされている。WTO事務局は、2024年の対中国貿易政策審査報告書で、様々な分野・産業への政府の資金的支援やその他のインセンティブ、政府引導基金を含む財政支援の全体像が明確に把握できないとし、このような透明性を欠いていることが、「過剰生産能力」の議論にも影響していると指摘している259。
また、中国政府の経済統計について、必要な詳細データが公表されない、一部統計の公表が停止される等の問題が、中国経済の全体像のより正確な把握を困難にしていることも、不透明性を高める一因になっている。昨今の事業環境の悪化に伴い、ビジネスや学界を含む人的交流が停滞していることも、政策や経済実態に係る適切な理解と共通認識の形成を妨げるおそれがある。
258 経済産業省(2024a)
259 WTO(2024)
(3) 産業政策の財政規模
中国は、近年、重点産業に対する補助金支出を拡大させる一方、その支出の透明性が低いことが指摘されている260。そこで、Dipippo et al. の試算により、主要国の産業政策による政府支援の規模を比較してみる261。これによると、中国の産業政策への支出は他の主要国に比べて極めて大きい。対GDP比で見ると、日米欧主要国はおおむね0.4~0.6%程度の範囲にあるが、中国は1.73%と約3~4倍にあたる(第II-2-4-10図)。金額ベースで見ると、その差は更に拡大し、第2位の米国と比べても3倍、日本と比べれば10倍の開きがあることになる。また、産業政策の構成比を比べると、中国の場合、市場金利以下の融資、補助金、(研究開発以外の)税制優遇が大きい(第II-2-4-11図)。補助金支出の透明性の低さは、歪曲性のある補助金交付を助長しやすく、鉄鋼・アルミ等の分野の過剰生産能力の問題につながっている疑いがある。これは他の途上国の産業発展にも悪影響を与える可能性がある重要な課題である。
第Ⅱ-2-4-10図 主要国・地域の産業政策による支出
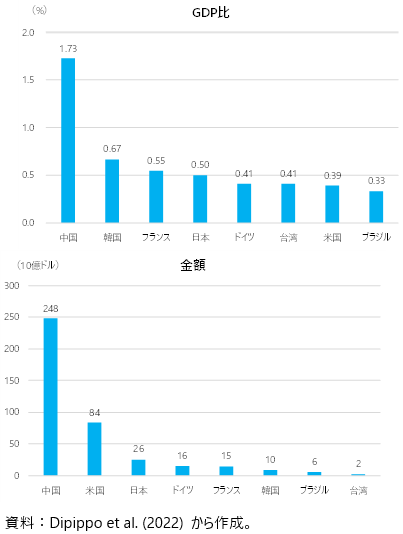
第Ⅱ-2-4-11図 図 主要国・地域の産業政策による支出の構成
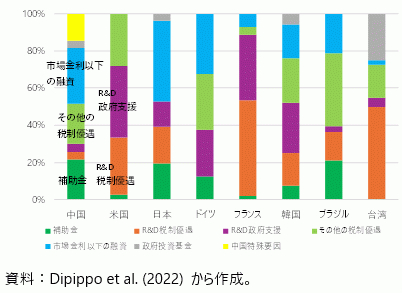
260 経済産業省(2024a)
261 Dipippo et al. (2022)
(4) 国有企業問題
競争中立性の観点でしばしば問題となるのは、国有企業の扱いである。改革開放政策の採用後、国有企業の低い効率性を背景に、国有企業改革が進められてきた(第II-2-4-12図)。1990年代末、国有企業は公共財などの部門に限るとの方針が打ち出され、非効率な中小国有企業を中心に民営化が進んだ(第II-2-4-13表)。その結果、第Ⅱ部第2章第1節で見たように、国有企業のシェアは低下してきたが、2000年代半ばに方針が変更され、国有企業の対象範囲が拡大された262。さらに2010年代半ば以降、国有企業は公益的な分野だけでなく、商業的分野にも残ることが規定され、それまで期待されていた民営化とは異なる方向へと進んだ。混合所有制として、一部の国有企業の株式が民間にも開放され、国有企業の経営に民営企業の知見を活用する方針が打ち出された。「より大きく、より卓越して、より強く」という標語にも見られるように、世界市場でも競争力のある国有企業を育成する方向へと転換したとの指摘がある。党による指導の強化もうたわれた。
第Ⅱ-2-4-12図 中国の企業形態別の総資産利益率の推移(工業分野)
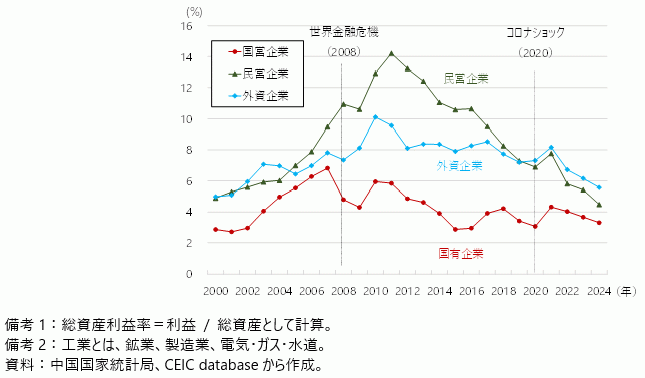
第Ⅱ-2-4-13表 中国の国有企業に関する主要な政策
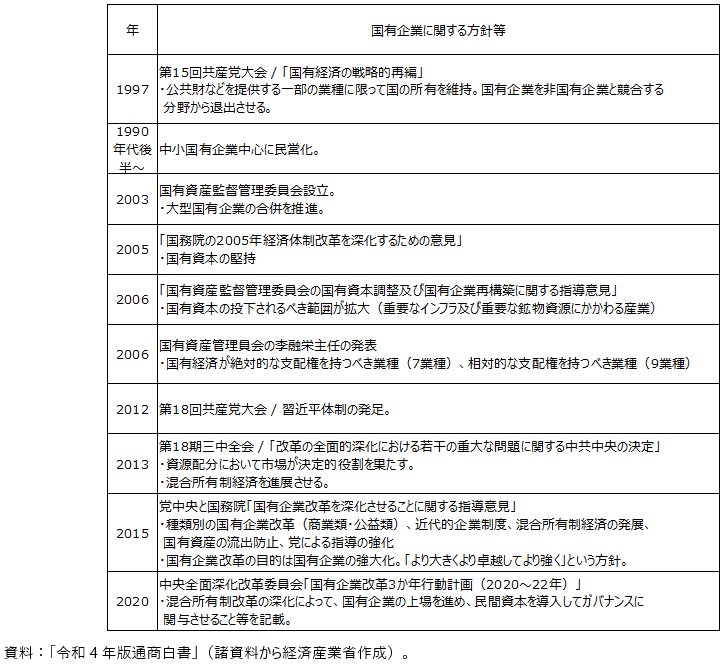
一方、民営企業は改革開放以降、その存在を認められて発展してきたが、既に見たように2000年代半ば以降に国有企業の重要性が見直される中で、「国進民退」と言われる、相対的に民営企業の重要性が後退する流れも生じた。混合所有制の下で、国有企業に対する出資が認められたが、ほとんどの場合、民間の出資比率が低く抑えられ、国家資本による支配が維持されているという指摘がある263。反対に、国家資本の出資を受けて国有企業化した民営企業もある。さらに、2020年代に入ると、教育産業やITプラットフォーマーなど一部産業に対する政府の規制が強化されるとともに、不動産部門の不況が重なり、民営企業は厳しい状況に置かれた。
国有企業の競争中立性を巡る懸念に対処するためには、国有企業に関する情報の透明性の確保、国家資本の目的や権限の範囲の明確化、商業的考慮に基づく行動を確保する仕組みを始めとする取組が重要となろう。
262 加藤・渡邉・大橋(2013)
263 関(2019)
(5) 内製化/国産品優遇
中国では、近年、政府調達や規制・基準を通じて国内産業を優遇したり、外資企業に過剰な負担を課して投資意欲を損なったりするような動きが見られ、中国の事業環境を巡る懸念につながっている。
① 政府調達
政府調達について、中国はWTO加盟時に、WTO政府調達協定に将来加入すること(現在も加盟交渉中)、政府調達手続について透明性を確保すること、外国から調達する場合は無差別待遇を供与すること等を約束している。他方、中国の政府調達法(2003年1月施行)では、政府調達において国内産品を調達することが求められている。また、2021年には中国財政部及び工業信息化部が41項目315品目の政府調達における国産調達率を定めた非公開の内部通達を傘下の地方政府部局に発出し、国産品を優先購入するよう指示したとの報道があり、輸入品が事実上排除されていないか、留意していく必要がある。中国政府は、外商投資法(2020年1月施行)及びその実施条例で、政府調達において外商投資企業が中国域内で生産した製品・サービスは内外資平等に扱うと規定した。しかし、2019年から、「安可」、「信創」と呼ばれる制度が施行され、非公表の「安可目録/信新創目録」という政府調達の推奨企業・製品リストによって、外資企業の製品は、輸入品も現地生産品も不利な扱いを受けているとの指摘がある。2023年12月には、コンピュータ等について情報セキュリティを理由とする政府調達標準が公表され、外国企業製の産品は入札が出来なくなっている264。その後も外国企業の製品・サービスがどのように扱われるか不透明な状況がビジネスの予見可能性を損なっており、中国日本商会は2024年白書で、政府調達において、内資・外資企業が平等に市場競争に参加できる環境の確立を要望している265。
264 経済産業省(2024a)
265 中国日本商会(2024)
② 基準認証
中国の化粧品規制では、新原料について当局への登録が義務付けられているが、登録実績が少ない上、技術的に当局が求める内容の提出が困難な場合もあることや、詳しい製造工程についての企業秘密の公開を求められるケースがあることが指摘されていた。現在でも、改善はあったものの、国際的に認められた試験方法が制限されているなど課題が残されている。また、オフィス機器に関する推奨性国家標準に中国内での開発・生産が要求されるとの情報があった。2023年8月に公表されたパブリックコメント案ではその要求は含まれていなかったが、仮に含まれており、事実上強制力のある形で運用された場合は完成品や部品の輸入が阻害されるおそれがあった266。加えて、サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法のいわゆるデータ三法に関する法制は、内容が不明瞭な点があるため、必要以上に貿易制限的な可能性があるほか、データの国内保存のための追加コストの発生やデータの利用を通じた円滑なビジネス活動を阻害するおそれもある。データ保護の名目で、外資企業が不利な立場に立たされる懸念がある267。
266 経済産業省(2024a)
267 経済産業省(2024a)
(6) 知的財産
知的財産保護に関する法制は整ってきているものの、模倣品・海賊版等の知的財産権侵害が後をたたず、改善が十分とはいえない。また、近年は、基準認証の規制を通じて、知的財産が漏出してしまう懸念も指摘されている。既に触れたが、中国の化粧品規制では、当局への提出情報に際して、製造工程の企業秘密が漏出する懸念が指摘されている。また、オフィス機器に関する推奨性国家標準でも、パブリックコメント案では含まれていなかったものの、具体的な運用により中国内での開発・生産等に向けて中国国内に技術を提供せざるを得ない場合には、事実上技術移転が強制される懸念があった。
5. ビジネスの動向と声
(1) 対内直接投資の減少
このような中で中国の対内直接投資は、2023年7-9月期に現行統計が遡及できる1998年以降、初めてマイナス(流出超過)となった(第II-2-4-14図)。新規投資に対して、撤退や回収が勝った可能性がある。対内直接投資は、2023年10-12月期に一旦はプラスに戻ったものの、2024年の4-6月期に再びマイナスとなり、7-9月期もマイナスが続いた。外国企業の対中投資意欲の減退を示唆するものとして注目を集め、その背景には、中国の景気停滞とともに、中国政府の政策の不透明さ、政府調達や技術移転など、公正なビジネス環境に逆行する動きが考えられる。
第Ⅱ-2-4-14図 中国の対内直接投資(国際収支ベース)の推移
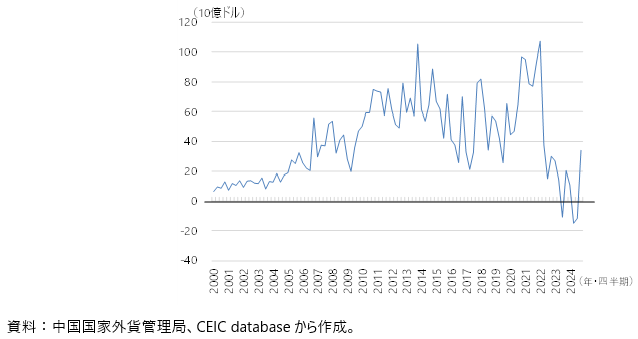
(2) 日欧米現地企業の評価
長期的に見れば、当初、中国は外資企業に対して技術移転を期待して優遇策を講じていたが、次第に特定の奨励産業に限るなど選別的な動きが見られるようになり、中国地場企業の成長から競争も激しくなり、現地での事業も厳しさを増してきている。むしろ、近年は既に見てきたような外資企業の投資意欲を削ぐような出来事も起きている。
このような動きに対して現地の外国企業が中国でのビジネスをどう考えているか見てみる。毎年、JETROは現地日系企業の動向をアンケート調査しており、その中で今後の事業の方向性も調査している。それによれば、近年、中国での事業を拡大するとの回答割合が低下してきており、2024年調査では約2割と過去最低を更新した(第II-2-4-15図)。ただし、現状維持を選んだ回答が2/3を占め、反対に縮小は約1割、第三国へ移転・撤退は約1%と、依然として中国を重要な拠点と考えていることがうかがえる。
第Ⅱ-2-4-15図 今後、1~2年の事業展開の方向性(在中日系企業 / 全産業)
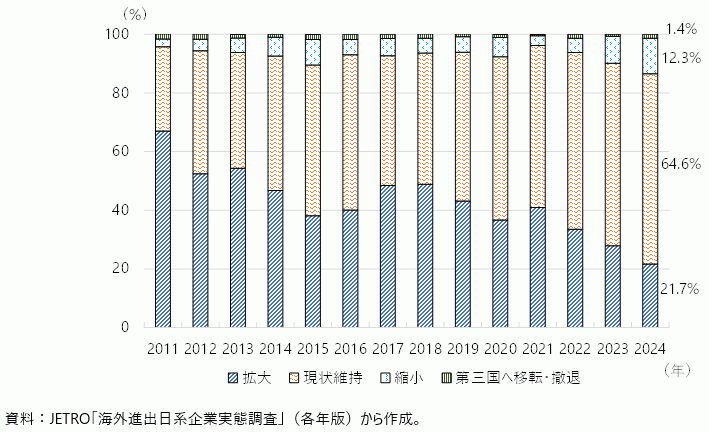
また、中国に立地する日系企業で構成する中国日本商会は毎年、日本企業が直面する課題や解決のための建議を白書としてまとめている。最新の2024年の白書では、全体コンセプトとして、「公平性と予見性・透明性の向上によるビジネス機会の確保」を訴えている268。その下で、中国側への要望を「公平な競争」、「対外開放」、「行政の予見性・透明性向上と円滑化」の3項目で要約している(第II-2-4-16表)。主な内容を挙げれば、「公平な競争」では、既に政府調達の項で記したように、輸入品と国産品の公平な競争や「安可」「信創」制度の明確化などを求めている。「対外開放」では、外資が参入できない分野(外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト))の更なる緩和を要望している。「行政の予見性・透明性向上と円滑化」では、ビザ免除措置の再開、審査期間の短縮、税関規則・規定に対する解釈・運用の統一や、基準認証の項で記したような中国サイバーセキュリティ関連法令の制定・運用における企業への配慮などを要望している。
第Ⅱ-2-4-16表 中国日本商会の主要な要望事項(2024年7月)中国日本商会の主要な要望事項(2024年7月)
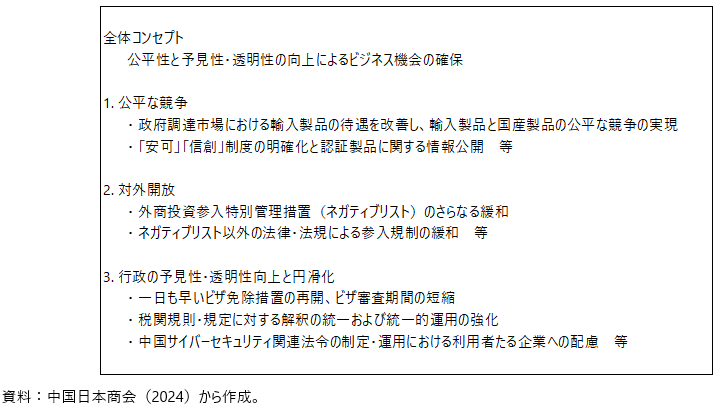
このような要望は日本に限ったものではなく、他の主要国と共通性がある。例えば、中国EU商会の2024/2025年版要望書を見ると、「市場アクセスと調達」等の6分野について要望を述べている(第II-2-4-17表)。日本商工会と同様に、政府調達において、「中国製」の基準を明確にするとともに、公平な競争環境を求めている。また、デジタルについては、越境データ移転がビジネスを妨げることのないよう配慮を要請し、知的財産保護に関しては、関連法規制は改善してきたものの、施行に関して課題が残されていると指摘している。
第Ⅱ-2-4-17表 中国EU商会の主要な要望項目(2024年9月)
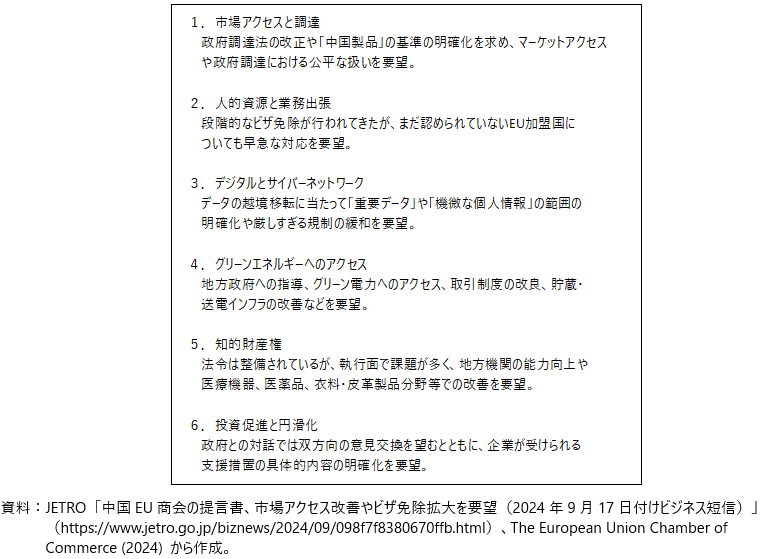
また、中国米国商会も、ハイレベルのコミュニケーション促進の重要性を訴えるとともに、出資形態にかかわらない全ての企業への平等な扱い、補助金などの透明性向上、ビジネス志向の政策や規制改革、データ越境移転への柔軟なアプローチ、外商投資企業への効率的かつ平等な市場アクセスの実現等を求めている(第II-2-4-18表)。
第Ⅱ-2-4-18表 中国米国商会の主要な要望項目(2024年4月)
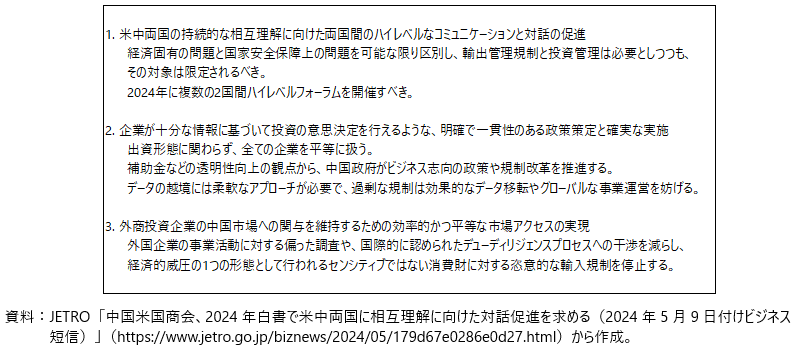
268 JETRO「中国日本商会2024年白書、人的交流やデータ移転、政府調達を建議」、ビジネス短信、2024年7月11日、https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/07/47d95d45086e14a3.html![]() 。中国日本商会(2024)。
。中国日本商会(2024)。