第5節 韓国・ASEAN・インドの貿易投資関係
特に2000年代以降の中国の製造業発展と輸出拡大、2010年代半ばからの米中貿易摩擦や対中貿易投資を萎縮させる中国の政策、近年の中国の景気低迷により顕在化した過少消費構造は、アジアを巡る貿易投資構造を大きく変容させている。地理的に米中対立のフロントラインに位置する韓国は、貿易投資関係でも米中間を揺れ動いている。ASEAN諸国は総じて米国・中国を含む全方位の開放姿勢を貫き、国境を越えるサプライチェーンの深化を通じて経済成長を実現している。インドは保護主義的な通商産業政策で中国からの輸入や投資も制限し、中国の代替投資先やデジタル関連産業の拠点として一定の成長を実現する一方、国内の製造業育成には困難を抱えている。同時に、幅広い品目の輸入における特定の国への依存という、アジア諸国に共通の課題も浮き彫りになっている。
本節では、これらアジア諸国が中国・米国との貿易投資関係にどのように対処しているかをデータに基づいて分析し、またこれらアジア諸国の輸入における特定の国への依存状況を確認することで、アジアを巡る貿易投資構造の変容を概観する。
1. 米中間を揺れ動く韓国
(1) 貿易
韓国の貿易は、長年黒字を計上してきた対中貿易収支が2023年に赤字に転落し、2024年も規模は縮小したものの2年連続の赤字となった。他方、対米貿易黒字は過去最高額を更新している。
対米・対中輸出の推移を見ると、韓国にとって中国は最大の輸出先であるが、対中輸出に頭打ちが見られる一方、2021年以降対米輸出が急増し、足下では両者は拮抗している(第II-2-5-1図)。
第Ⅱ-2-5-1図 韓国の対米・対中輸出の推移
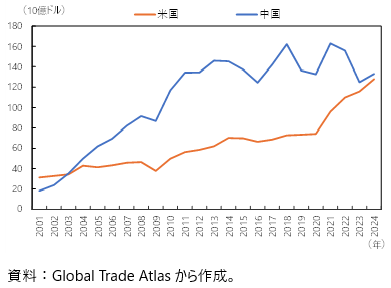
韓国経済は、1997年のアジア通貨危機以降、中国の急速な経済成長の恩恵を受けながら産業を発展させてきた経緯があり、半導体やディスプレー、自動車、造船、化学、鉄鋼など韓国の主力産業は、中国向け輸出の増加に伴って規模を拡大してきた269。しかし、対中輸出は2013年頃から伸び悩みが見られ、2023年は前年比-19.9%の大幅減となった。2024年は半導体の回復により増加に転じたものの、+6.6%と小幅な回復にとどまった。
輸出品目としては電気機器が47.7%と半分近くを占め、そのシェアは上昇傾向にある(2024年)(第II-2-5-2図)。中でも集積回路が最大であり、全体の3割超を占める。続いて、一般機械、有機化学品となっている。
第Ⅱ-2-5-2図 韓国の中国への主要輸出品目シェアの推移(HS2桁)
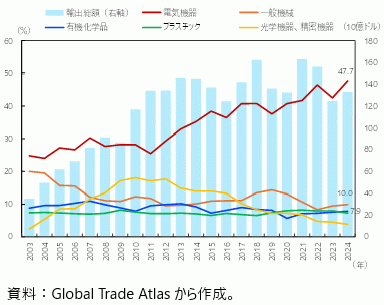
輸出動向は半導体市況の影響も受けるが、構造的な問題として、中国企業の競争力向上による韓国製中間財への需要の低下が、対中輸出低迷の要因として指摘されている270。中間財供給の観点から、中国の輸出(製造業全体、電子機器)に含まれる韓国の付加価値比率を見ると、特に電子機器では2007年にかけて上昇が見られたが、その後は一旦下落した後に横ばい圏内の動きが続き、2018年以降は低下傾向にあることが分かる(第II-2-5-3図)
第Ⅱ-2-5-3図 中国の輸出に占める韓国の付加価値シェアの推移
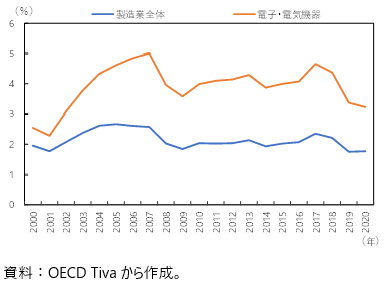
一方、対米輸出は2021年以降に急増している。輸出品目としては自動車関連が最大で、33.2%と全体の3分の1を占め、そのシェアは近年大幅に上昇している。次いで一般機械が20.9%、電気機器が16.3%となっている(2024年)(第II-2-5-4図)。具体的な品目では、乗用車や蓄電池が2020年比で大幅に増加しており、EVを含む自動車や車載用電池の輸出の増加が対米輸出増の要因となっている。
第Ⅱ-2-5-4図 韓国の米国への主要輸出品目シェアの推移(HS2桁)
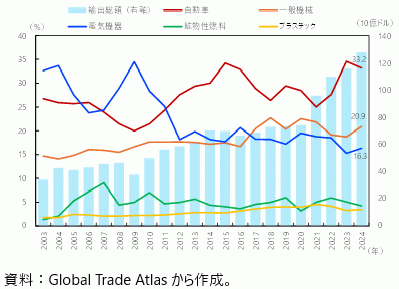
次に、対中輸入を見ていく。中国は韓国にとって2007年以降最大の輸入相手国となっており、2021年、2022年は輸入額が急増し、その後も高水準で推移している。全体に占めるシェアも中長期的に上昇してきており、2024年に22.1%を占めている(第II-2-5-5図)。
第Ⅱ-2-5-5図 韓国の中国からの輸入の推移
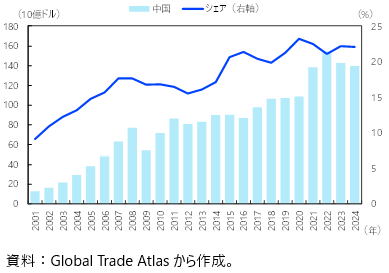
輸入品目は、輸出と同様に集積回路を中心とした電気機器が34.6%と最大で、次いで一般機械が12.8%、無機化学品が4.8%となっている(2024年)(第II-2-5-6図)。電気機器の中で最大品目である集積回路は輸入全体の13.8%を占めるほか、2018年頃から蓄電池が大幅に増加している。無機化学品では、水酸化リチウムやニッケル・コバルト・マンガン水酸化物等のリチウムイオン電池材料(HS2825)が大幅に増加しており、車載電池関連の輸入の増加が対中輸入増の一因となっているといえる。
第Ⅱ-2-5-6図 韓国の中国からの主要輸入品目シェアの推移(HS2桁)
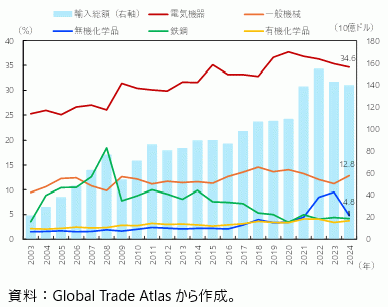
269 伊集院・日本経済研究センター編著(2024)
270 JETRO「韓国の貿易は転換点、対中・対米輸出は拮抗へ、対中貿易収支は赤字に」、2024年2月20日、
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2024/e19c0e82d604d739.html![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
(2) 投資
次に、韓国の対米・対中直接投資を見ていく。韓国企業は2000年代から対中直接投資を拡大してきたが、2007年以降はおおむね横ばいの範囲内で推移し、2021年、2022年に特定の大型投資案件による増加が見られたが、2023年、2024年は非常に少なかった。法人設立数を見ると、2000年代に法人設立が急増したが、2009年までに落ち着いた後は横ばいとなり、さらに2017年以降は減少傾向が強まった(第II-2-5-7図)。投資低迷の要因として、2016年の高高度防衛ミサイル(THAAD)配置問題を受けた中韓関係悪化や、米国の対中国輸出管理強化による中国での生産の制約といった要因に加え、現地生産コストの上昇や地場企業との競争激化等が指摘されている271。サムスンのベトナム移転による中国でのスマートフォン生産の終了や現代自動車の中国工場の売却など、韓国大手企業による中国事業の縮小や中国からの撤退の事例が散見される。
一方、対米直接投資は、2010年代から増加傾向にあり、特に2021年に急拡大し、その後も高水準で推移している(第II-2-5-7図)。米国のCHIPS及び科学法やインフレ削減法(IRA)に対応して、半導体メーカーや車載電池メーカーが大規模生産拠点の設立を進めていることを反映している。
第Ⅱ-2-5-7図 韓国の対米・対中直接投資の推移
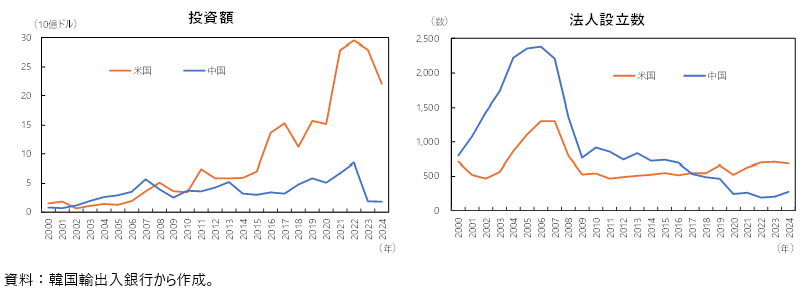
また、韓国への対内直接投資を見ると、中長期的な流れとしては、2000年代後半から米国による投資が増加してきている(第II-2-5-8図)。中国からの投資は2010年代初めから増加したが、2010年代半ば以降は頭打ちとなり、直近の2024年になって急激に増加した。
第Ⅱ-2-5-8図 韓国への直接投資の推移
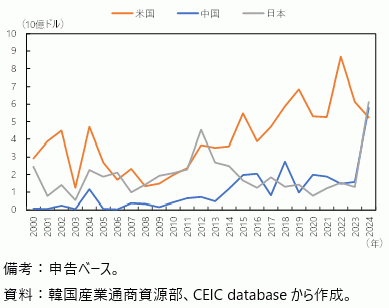
以上のように、韓国は2020年代に入って米国への輸出と直接投資の増加が顕著であり、米国からの直接投資の増加傾向と併せ、貿易投資における米国シフトが見られる。他方、中国への輸出や直接投資は横ばい又は減少傾向になる中で、中国からの中間財等の輸入は拡大している。特に、蓄電池の対米輸出が増える一方で、電池材料の中国からの輸入が増え、直接投資の事例も見られる点は注目される。今後の米国との貿易投資関係は、米中対立の行方や米国の関税政策・産業政策の動向によって影響を受ける可能性がある点には留意が必要である。
271 JETRO「韓国企業の海外進出先は中国から米国に大きくシフト」、2024年9月25日、
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2025/0101/6dea6fc9bf76e166.html![]() (2025年3月31日閲覧)。
(2025年3月31日閲覧)。
2. 全方位の方針を貫くASEAN
ASEANでは、中国の貿易投資プレゼンスが着実に拡大している。同時に、米中対立を背景に、中国企業やその他の外資系企業が製造拠点を中国からASEAN各国にシフトする動きが続いており、その影響もあって対米輸出の増加が加速している。
(1) 貿易
まず、ASEAN全体としての対米・対中貿易の動向を確認する。ASEANにとって中国は最大の貿易相手国であり、2023年の輸出総額の15.9%、輸入総額の23.9%を占める(第II-2-5-9表)。輸出入ともにシェアは上昇傾向であるが、特に近年、中国からの輸入シェアが上昇しており、これに伴い対中貿易赤字が拡大している。一方、対米輸出シェアは2011年以降上昇傾向にあり、輸出の増加を受けて対米貿易黒字は拡大している(第II-2-5-10図)。
第Ⅱ-2-5-9表 ASEANの日・米・中との貿易投資関係
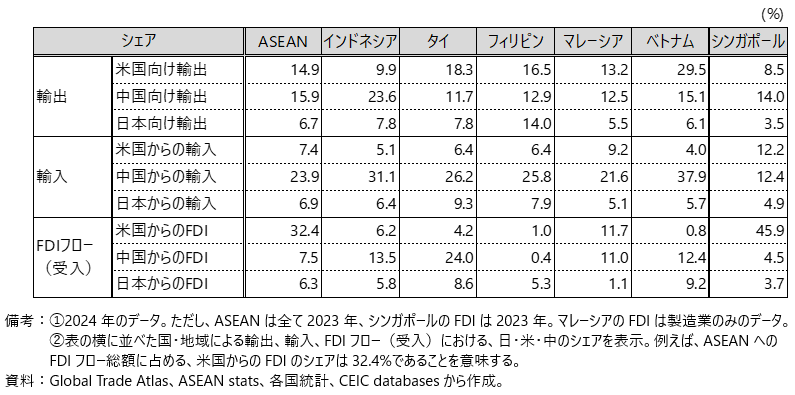
第Ⅱ-2-5-10図 ASEANの対米・対中貿易収支
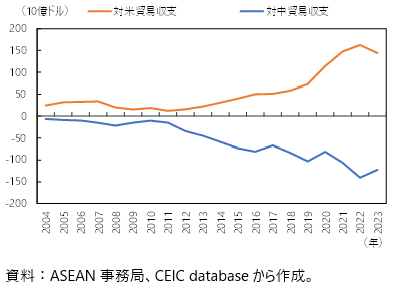
なお、中国側から見ると、ASEANは輸出総額の16.4%、輸入総額の15.3%を占め、中国にとってもASEANは最大の貿易相手となっている。
ASEANの輸入元国・地域シェアを見ると、中国からの輸入シェアは過去20年間に上昇傾向を維持し、2019年にASEAN域内を上回った。主要5か国について国別に見ると、全ての国で上昇傾向にあるが、特にベトナムでは2020年以降、中国のシェアが3割を超える高い水準となっている(第II-2-5-11図)。
第Ⅱ-2-5-11図 ASEANの輸入元国・地域シェア、ASEAN各国の中国からの輸入シェア
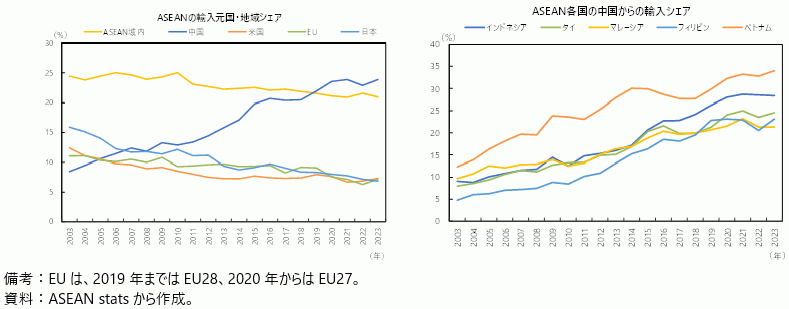
中国からの輸入品目を見ると、電気機器が最大であり、全体の30.6%を占める。次いで一般機械が15.1%、鉱物性燃料が4.9%となっている(2023年)(第II-2-5-12図)。具体的な品目では、電話機、集積回路、自動データ処理機械(パソコン等)、半導体デバイスといった工業製品が上位を占めている(第II-2-5-13表)。
第Ⅱ-2-5-12図 ASEANの中国からの主要輸入品目シェアの推移(HS2桁)
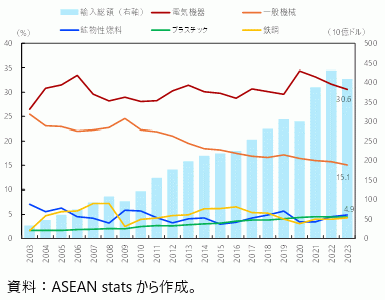
第Ⅱ-2-5-13表 ASEANの中国からの主要輸入品目(HS4桁、2023年)
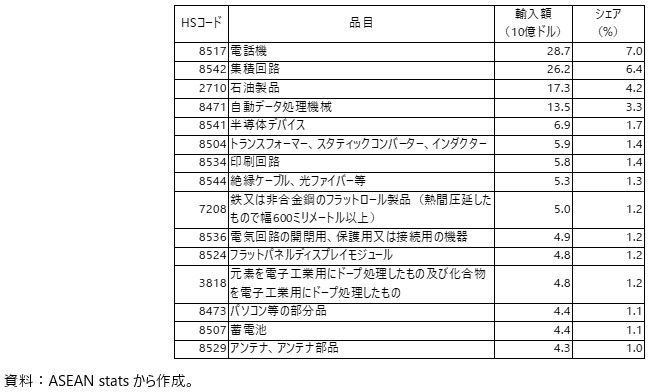
次に、ASEANの対米・対中輸出を見ていく。輸出先国・地域シェアを見ると、中国のシェアは2010年に米国を上回り、その後も上昇傾向が続いている。米国のシェアは、2000年代には低下傾向にあったが、2011年以降上昇に転じており、足下では両者は拮抗している(第II-2-5-14図)。なお、国別では、ベトナムやタイは米国のシェアが高い一方、インドネシアは中国のシェアが高いといった違いがある(第II-2-5-9表)。
第Ⅱ-2-5-14図 ASEANの輸出先国・地域シェア
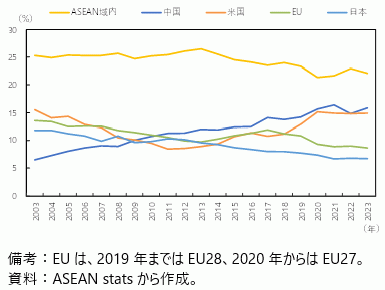
対中輸出品目を見ると、輸入と同様に電気機器が最大で全体の28.8%を占めており、次いで鉱物性燃料が10.0%、一般機械が8.2%となっている(2023年)(第II-2-5-15図)。具体的な品目では、集積回路が最大で、全体の14.7%を占める。
第Ⅱ-2-5-15図 ASEANの中国への主要輸出品目シェアの推移(HS2桁)
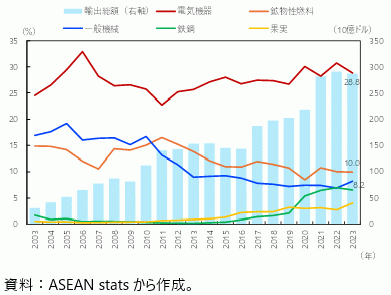
対米輸出を見ると、2018年以降大幅に増加しており、2023年の輸出額は2017年比で1.9倍となった。輸出品目を見ると、電気機器が36.1%と最大で、次いで一般機械が13.4%、衣類が8.5%となっている(第II-2-5-16図)。電気機器のシェアは近年大幅に上昇しており、輸出額は2017年と比べて2.7倍と大きく増加した。電話機、半導体デバイス、集積回路等が主要品目となっている。
第Ⅱ-2-5-16図 ASEANの米国への主要輸出品目シェアの推移(HS2桁)
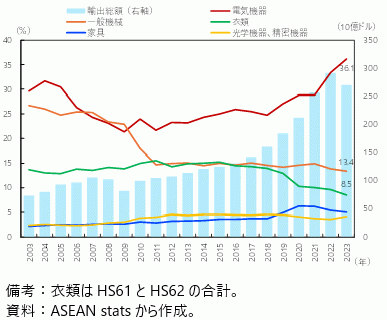
また、米国側の輸入を見ると、2018年以降は中国からの輸入が伸び悩む中で、ASEAN、特にベトナムからの輸入は大きく増加しており、米中貿易摩擦による貿易転換効果が示唆される(第II-2-5-17図)。ベトナムからの輸入は電話機や自動データ処理機械(パソコン等)を中心に拡大している。また、米国のASEAN、特にベトナムからの輸入に含まれる中国の付加価値を見ると、そのシェアは継続的に上昇しており、これらの国の対米輸出における、中国からの中間財供給の高まりが見て取れる(第II-2-5-18図)。
第Ⅱ-2-5-17図 米国の輸入の推移(中国、ASEAN、ベトナム)
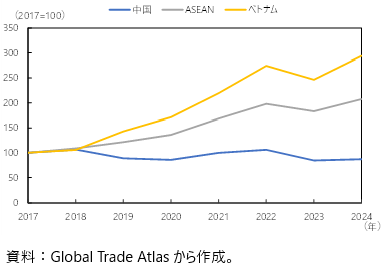
第Ⅱ-2-5-18図 米国のASEAN及びベトナムからの輸入に占める中国の付加価値比率の推移
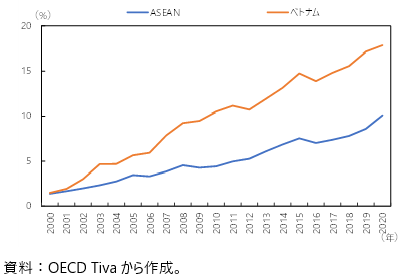
(2) 投資
次に、ASEAN諸国への直接投資の動向を見ていく。ASEANの統計によると、ASEAN全体への直接投資は増加基調で推移している(第II-2-5-19図)。2023年の投資国別で見ると、米国が32.4%と最大で、中国(7.5%)と香港(6.5%)も、それぞれ日本(6.3%)を上回っている。日本のシェアは近年減少傾向にあり、2020年頃までは中国と香港を合計したシェアと概ね同水準だったが、2023年には半分以下まで落ち込んだ272。2014年から2023年の直近10年間の累積額で見ると、米国(16.3%)、ASEAN域内273(14.8%)、日本(11.5%)、EU(11.3%)、中国(7.2%)、香港(5.8%)等が主要な投資国・地域となっている(第II-2-5-20表)。
第Ⅱ-2-5-19図 ASEANへの直接投資フローの推移(投資国・地域別)
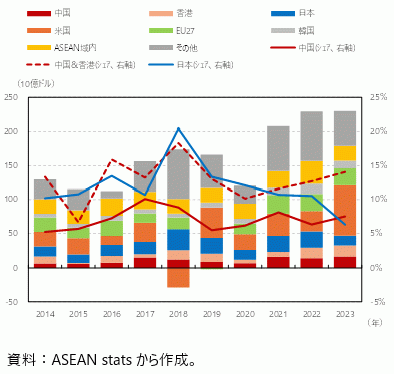
第Ⅱ-2-5-20表 ASEANへの直接投資の推移(投資国・地域別シェア)
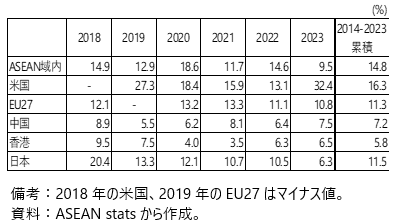
投資の受入国別では、シンガポールが毎年おおむね6割前後の受入国となっている。直近10年間の累積額で見ると、シンガポールが59.5%と最大で、インドネシア(12.1%)、ベトナム(9.1%)が続く。
中国からの投資は、2021年に急増してから高水準にあり、2023年は日本を上回り、個別国としては米国に次ぐ2位に浮上した274。業種別に見ると、特に製造業での増加傾向が注目される(第II-2-5-21図、第II-2-5-22図)。2018年以前は、中国のASEANへの投資は主に不動産と金融に集中していたが、その後、電子機器やEV 及びバッテリー関連(重要鉱物の採掘・加工を含む)など製造業への投資が増加してきている。米中貿易摩擦に対する懸念や、コロナ禍によるサプライチェーンの混乱等も背景に、中国の製造業企業が海外への拠点の分散を進めていることがうかがえる275。
第Ⅱ-2-5-21図 中国からASEANへの直接投資(業種別)
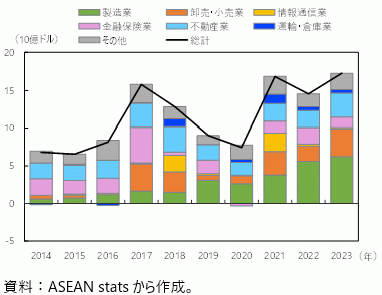
第Ⅱ-2-5-22図 ASEANへの製造業直接投資の推移(中国、香港、日本)
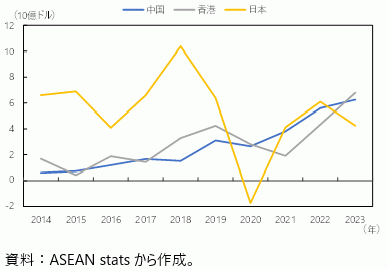
投資先国としては、シンガポールが中心であるが、中国企業のニッケル等の一次金属産業への積極的な投資を受け、インドネシアへの投資が増加している。また、タイ政府の統計によると、2024年のタイへの直接投資金額(認可ベース)において、中国はシェア24%と、シンガポールに次ぐ2位となった。分野別では機械・自動車、電気機器・エレクトロニクス、金属・素材が中心で、それぞれ2割以上を占める。
ASEAN各国側から見ても、中国からの直接投資の存在感は増大している。データが利用可能なASEAN各国の対内直接投資残高に占める、日本、中国と、中国・香港の合計276の推移を示したのが第II-2-5-23図である。元々中国からの投資が多かったカンボジアに加えて、マレーシア、インドネシアでは中国と香港の合計額は日本を超え、シンガポールでもほぼ同水準になった。タイでは引き続き、日本の残高が中国と香港を上回っているが、その割合は低下傾向にあり、日本企業による新規投資の停滞も示唆している。
第Ⅱ-2-5-23図 ASEAN各国の対内直接投資残高のシェア推移
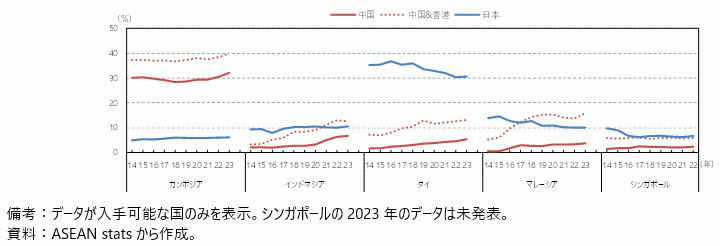
なお、中国側の対外直接投資を見ると、投資先としては香港が6割以上を占めるが、欧米への投資が伸び悩む中、全体に占めるASEANのシェアは上昇傾向にある。2023年は約14%と香港を除く国・地域別で最大の投資先となっている(第II-2-5-24図)。
第Ⅱ-2-5-24図 中国からASEANへの直接投資の推移
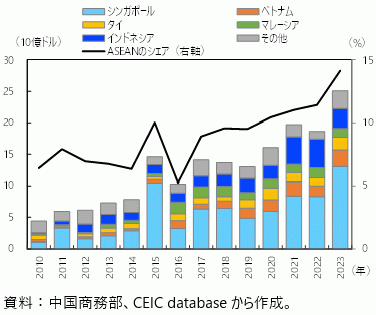
米国からの直接投資は、その大部分がシンガポール向けである。業種別では金融保険業が中心だが、米中貿易摩擦が本格化した2018年以降、半導体関連など製造業への投資が多くなっている(第II-2-5-25図)。また、2019年や2023年には専門・科学・技術サービス業も多かった。2023年は金融保険業を中心に投資額が大幅に増加したが、全体の9割超をシンガポール向けが占めた。
第Ⅱ-2-5-25図 米国からASEANへの直接投資の推移(業種別)
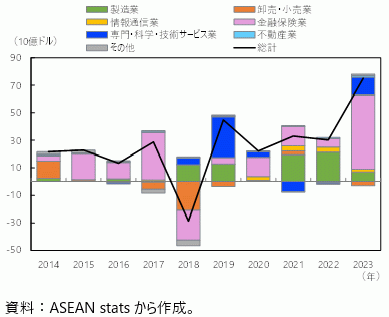
最後にASEANの対米・対中認識について触れる。ISEASユソフ・イシャク研究所が実施しているASEAN有識者への意識調査277の最新の結果では、ASEANが中国か米国のいずれかと同盟を迫られた場合、「米国」を選ぶべきと回答した割合が52.3%となり、「中国」を上回った278。前回調査(2024年公表)では、「中国」が50.5%と、2020年に設問が開始されて以降初めて米国を上回っていた。その差は僅かであり、米中間でのバランスを模索する様子が見て取れる。
ASEANは、国ごとに差異はありつつも全体として、米中対立の中でも全方位の方針を維持し、米国・中国双方と貿易・投資関係を深めてきた。中国とは貿易・投資関係が着実に深化している。ただし、一部の国では安価な中国製品の流入がもたらす国内産業への影響に対する懸念が高まっている。米国との関係では、米中貿易摩擦を背景に、対米輸出拡大の恩恵を受けている。しかし、ベトナムを始めとして対米貿易黒字が拡大しており、米国の関税政策等に大きな影響を受ける可能性がある点には留意が必要である。
272 先述のとおり、香港からの投資の相当割合が中国企業・投資家による投資と推測されるため、参考として中国と香港の合計額推移を点線で示した。
273 ASEAN域内のうち6割程度はシンガポール。ASEAN域内からの投資には、多国籍企業によるASEAN域内拠点を通じた投資が含まれる。
274 先述のとおり、香港を経由した「実質的な中国の対外直接投資」の額を把握することは困難だが、香港からの投資の相当割合が中国企業・投資家による投資と推測され、実質的な中国のシェアは更に高い可能性がある。
275 The ASEAN Secretariat and the UNCTAD (2024)
276 先述のとおり、香港からの投資の相当割合が中国企業・投資家による投資と推測されるため、参考として中国と香港の合計額推移を点線で示した。
277 同調査はシンガポールのシンクタンクISEASユソフ・イシャク研究所がASEAN加盟国の有識者に対して毎年実施しているもので、今回で7回目。
278 Seah et al. (2025)
3. 保護主義で国内産業育成を目指すインド
インドは、近年、内需が牽引する形で高い成長を続けてきたが、製造業の発展が遅れており、輸入の増加により貿易赤字が拡大している。インド政府は、2014年に製造業の振興策「Make in India」を打ち出し、高関税や非関税障壁による保護主義的な政策279の下、製造業の競争力強化を志向している。インド政府は、2025 年度までにGDPに占める製造業のシェアを25%に引き上げるという目標を掲げているが、サービス業主導の経済成長が続く一方、経済全体に占める製造業のシェアは高まっておらず、足下では低下している(第II-2-5-26図)。
第Ⅱ-2-5-26図 インドのGVAに占める製造業比率
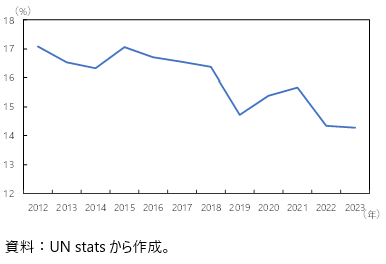
279 インド政府は、2014 年以降、国内製造業振興のために、予算法案(及びその後の予算法)や国内通達において様々な製品について関税引上げ措置を導入しており、WTO 協定譲許表において譲許税率を無税(0%)と定めているICT製品に対しても、関税率の引上げを行っている。また、近年、鉄鋼製品、電気電子機器など広範な分野に対して強制規格の導入を実施しており、対象となった製品の輸入又は国内販売に当たっては、インド工業規格(「IS規格」)の取得を義務付ける動きが加速している(経済産業省(2024))。
(1) 貿易
まず、インドの対米・対中貿易動向を見ていく。インドにとって中国は、最大の輸入相手国かつ貿易赤字国である。対中貿易赤字は2000年代半ばから拡大していたが、特に2021年以降に一段と拡大し、2024年の貿易赤字全体の3分の1に相当する規模になっている。一方、米国は最大の輸出相手国かつ貿易黒字国となっている(第II-2-5-27図)。
第Ⅱ-2-5-27図 インドの対米・対中貿易収支、インドの貿易黒字・赤字相手国(上位10か国)(2024年)
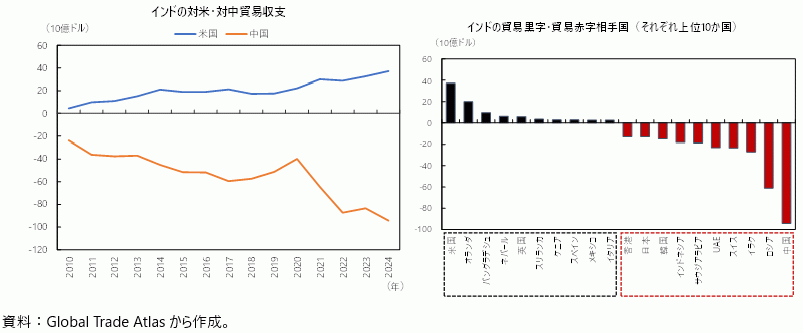
中国からの輸入はコロナ禍後に大幅な増加傾向にあり、シェアは15%程度で高止まりしている。輸入品目は、電気機器が33.2%と最大で、全体の3分の1を占める。次いで一般機械が22.7%、有機化学品が10.2%となっている(2024年)(第II-2-5-28図)。具体的な輸入品目を見ると、自動データ処理機械(パソコン等)、半導体デバイス、蓄電池といった機械類や、複素環式化合物、抗生物質といった医薬品関連で、中国のシェアが5割を超える中国依存度が高い品目が見られる(第II-2-5-29表)。
第Ⅱ-2-5-28図 インドの中国からの主要輸入品目シェアの推移(HS2桁)
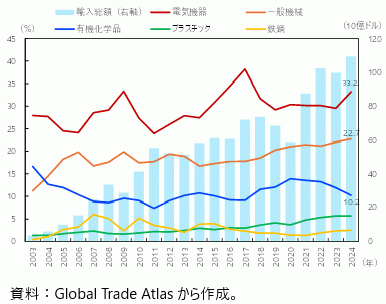
第Ⅱ-2-5-29表 インドの中国からの主要輸入品目(HS4桁)(2024年)
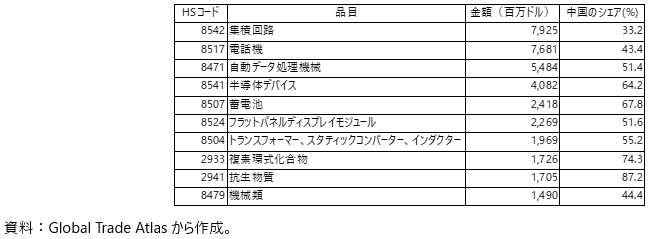
集積回路については2018年以降輸入が急増している。インドでは携帯電話などの一部エレクトロニクス関連の生産、輸出が増加しており(後述)、それらの製品の部素材である集積回路の輸入が増加していると考えられる。輸入相手国のシェアを見ると、中国及び香港で5割超を占めている(第II-2-5-30図)。
第Ⅱ-2-5-30図 インドの集積回路(HS8542)の輸入相手国シェアの推移
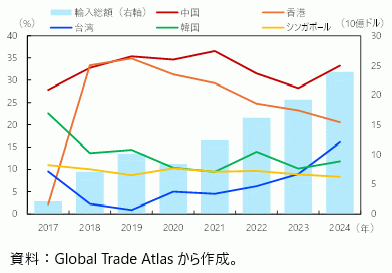
一方、中国向け輸出は、2017年以降増加傾向にあったが、2022年に大きく減少した。輸出品目は、鉱石が17.0%と最大で、有機化学品が8.3%、鉱物性燃料が8.1%と続く(2024年)(第II-2-5-31図)。一次産品の比率が高く、機械類のシェアの高まりは限定的である。また、中国の輸入に占めるインドのシェアは僅か0.7%と存在感は小さい。
第Ⅱ-2-5-31図 インドの中国への主要輸出品目のシェア(HS2桁)
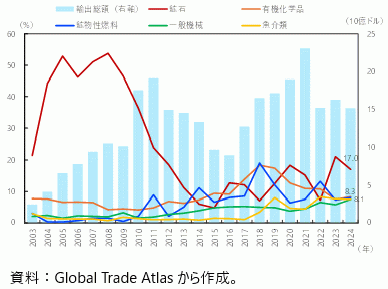
続いて対米輸出を見ていく。対米輸出は2021年に急増し、その後も上昇傾向にあり、輸出全体に占めるシェアは18.2%となっている。輸出品目を見ると、電気機器が15.6%と最大で、次いで真珠、貴石、貴金属が11.5%、医療用品が11.0%となっている(2024年)(第II-2-5-32図)。真珠、貴石、貴金属のシェアが低下する一方、電気機器のシェアが2022年以降急上昇した。電気機器では、特に電話機や半導体デバイスの増加が顕著である。また、2023年、2024年は、医療用品のシェアも上昇している。
第Ⅱ-2-5-32図 インドの米国への主要輸出品目シェアの推移(HS2桁)
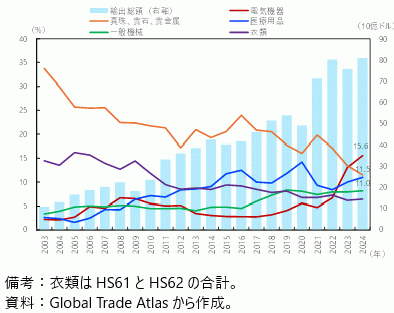
インドでは「Make in India」政策を受けて、エレクトロニクス製品等の製造業の一部で生産能力が拡大している。例えば、携帯電話については、OPPO や Xiaomiといった中国メーカーに加えてアップルやサムスンなどもインドでのスマートフォンの生産を本格化しており、携帯電話の輸出額は2018年比で19倍に増加した。輸出先としては当初はUAE向けが多かったが、2023年以降は米国向けが最大となり、全体の3分の1が米国向けとなっている(第II-2-5-33図)。
第Ⅱ-2-5-33図 インドの携帯電話の輸出額の推移
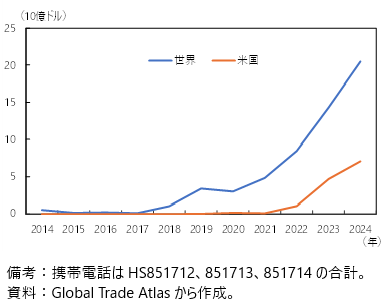
最後に、サービス貿易について触れる。第II部第1章第2節で見たように、インドは世界第9位のサービス輸出国となっている。輸出額は拡大傾向にあり、内訳としては、専門業務サービス(専門・経営コンサルティングサービス等)と通信・コンピュータ・情報サービスが中心である(第II-2-5-34図)。インドのIT産業は、欧米企業向けのソフトウェア開発やカスタマーサポートを提供しており、サービスの輸出先を見ると、米国が2割を占めて最大で、次いで英国となっている(第II-2-5-35図)。
第Ⅱ-2-5-34図 インドのサービス輸出の推移
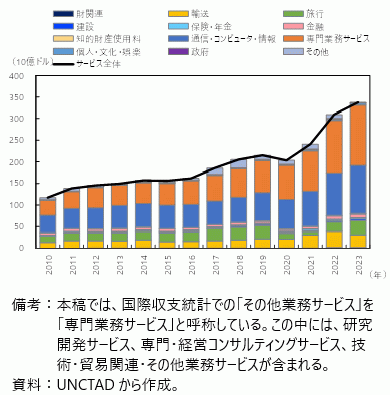
第Ⅱ-2-5-35図 インドのサービス輸出相手国シェア(2023年)
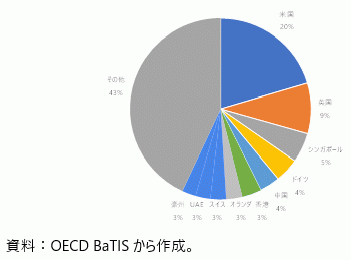
(2) 投資
続いて、対内直接投資について見ていく。インド政府は、投資誘致のための各種インセンティブを導入しており、2020年に導入された生産連動型優遇策(PLI)は、自動車、医療機器、蓄電池等の重点分野について、新規工場を設立した製造業企業に対し、売上高の増加額などに応じてインセンティブ(補助金)を支給する仕組みとなっている。
直接投資の推移を見ると、2020年に大幅に増加したが、その後は2023年にかけて減少するなど伸び悩みが見られる。投資元国としては、シンガポール及びモーリシャスが主要な投資国となっているが280、米国からの投資が2020年に急増し、その後も比較的高水準で推移している(第II-2-5-36図)。
米国からの投資は、2000年から2023年の累積額では3位であり、業種別ではコンピュータ(ソフトウェア、ハードウェア)が44%、サービス業が15%、自動車が6%と、コンピュータ関連が中心となっている。
中国からの投資は、小規模ではあるものの2014年後頃から急増していたところ、2020年4月から中国を含む国境を接する国からの全ての直接投資に対し事前許可制を導入した281ことを受け、2021年以降は僅少となっている(第II-2-5-36図)。
第Ⅱ-2-5-36図 インドへの直接投資の推移(投資国別と中国、香港からの投資)
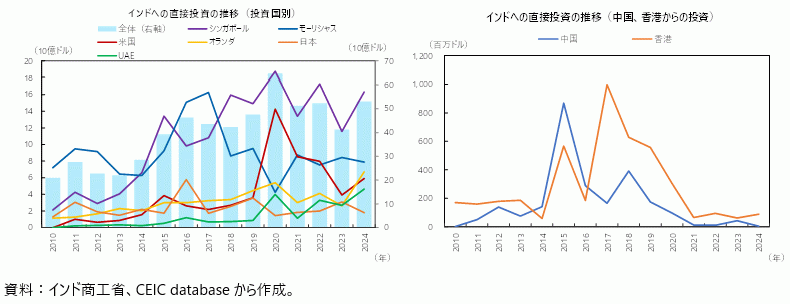
業種別の推移を見ると、サービス業(金融、ビジネスサービス、研究開発等)やコンピュータ(ソフトウェア、ハードウェア)が多くなっている。2020年にコンピュータ分野への投資が急増し、その後も2023年を除き高水準で推移している(第II-2-5-37図)。なお、UNCTADによると、2024年は、半導体及び一次金属分野を中心とした製造業への投資が増加したとされている282。
第Ⅱ-2-5-37図 インドへの直接投資の推移(業種別)
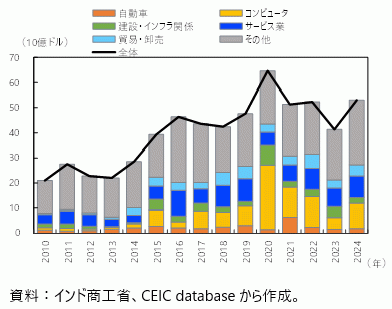
以上のように、インドは中国からの直接投資を制限してきたが、サプライチェーンから完全排除することは困難であり、バランスを模索している283(第II-2-5-38図)。米国との間では、2020 年に締結した「包括的グローバルパートナーシップ」や、「米印重要新興技術イニシアティブ」といった枠組みの下、様々な分野で連携を強化してきた。しかし、米国の対印貿易赤字は拡大傾向にあり、米国トランプ大統領はインドの関税率の高さを問題視している。2025年2月の首脳会談では、両国間の貿易協定の交渉を行うことに合意したほか、2030年までに両国間の貿易総額を現在の2倍以上の5,000億ドルへの拡大を目指すことを表明した。今後の対米・対中関係の動向には留意が必要である。
第Ⅱ-2-5-38図 インドの対米・対中貿易投資関係
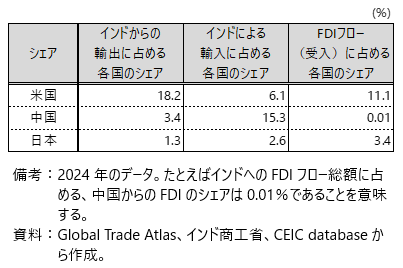
280 モーリシャスは、インドとの租税条約に基づく税制上の優遇措置から、欧米企業等によるインド投資の経由地とされてきた背景がある。なおモーリシャスとの租税条約は2016年に改正され、2019年3月末の移行期間後は通常税率が課税されることになった(西澤(2019))。
281 コロナ禍に伴う機会主義的な買収・取得を防ぐことが目的とされている。従来はパキスタンとバングラデシュのみが一律事前許可の対象であったが、インドと国境を接する国(又は投資の実質的支配者がそのような国に所在しているか市民である場合)に拡大された。
Press Information Bureau, Government of India, ‘Government amends the extant FDI policy for curbing opportunistic takeovers/acquisitions of Indian companies due to the current COVID-19 pandemic’, 18 April 2020.
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1615711![]() (Accessed on 9 June 2025).
(Accessed on 9 June 2025).
282 UNCTAD (2025)
283 インド財務省は2024年7月に公表した報告書Economic Survey 2023-2024において、インドの製造業を振興し、グローバルなサプライチェーンに組み込むためには、輸入依存あるいは部分的な投資受入によって中国のサプライチェーンに組み込まれることが避けられないとの見解を示した(Ministry of Finance, Government of India (2024))。
4. 輸入の特定の国への依存の状況
最後に、アジア各国(韓国、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インド)の輸入に関して、特定の国への依存の状況を確認する。ここでは、輸入の集中度を表す指標であるハーフィンダール・ハーシュマン指数(以下、HHI)284を用いて、鉱工業製品(HSコード25~97類)を対象として、HSコード6桁品目ごとに輸入の特定の国への依存状況について見ていく。
第II-2-5-39図は、韓国、タイ、ベトナム、インドと日本、米国、ドイツについて、品目別の輸入のHHIの分布を示したものである285。日本を含むアジア各国は、米国、ドイツに比べて、HHIが50を上回る品目が多い傾向にある。アジア各国の中では、インドは比較的少なく、逆にベトナムは多くなっている。その他の国は、対象品目のうち、おおむね4割前後の品目で集中度が高い状況である。
第Ⅱ-2-5-39図 各国のHHIの分布
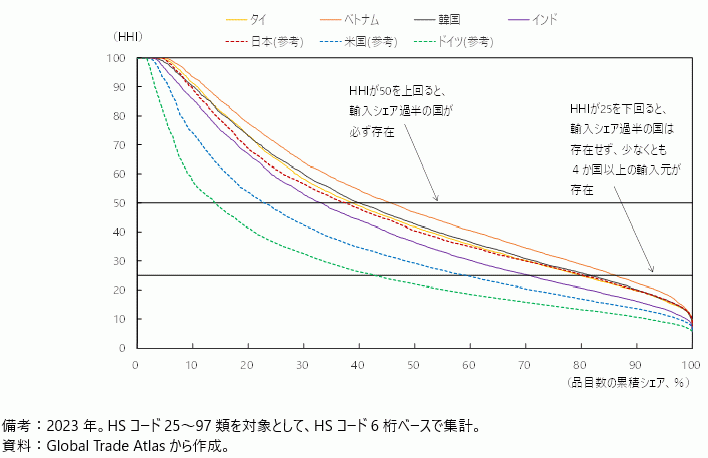
次に、輸入シェアの50%以上を特定の国に依存している品目の数を、輸入元国別に集計したものが第II-2-5-40図である。全てのアジア諸国で、中国が突出して多くなっている。これは、米国、ドイツと比較すると、アジア諸国に際立った特徴であることが分かる。とりわけベトナムは、対中依存品目が2,000品目を超えている。ASEAN諸国の中では、フィリピンとマレーシアが1,500品目未満と比較的少なく、インドや日本は更に少ない。なお、韓国、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナムでは、日本への依存度が高い品目数が2番目に多くなっている。
第Ⅱ-2-5-40図 輸入シェア50%以上を特定の国に依存している品目の数(国別に集計したもの)
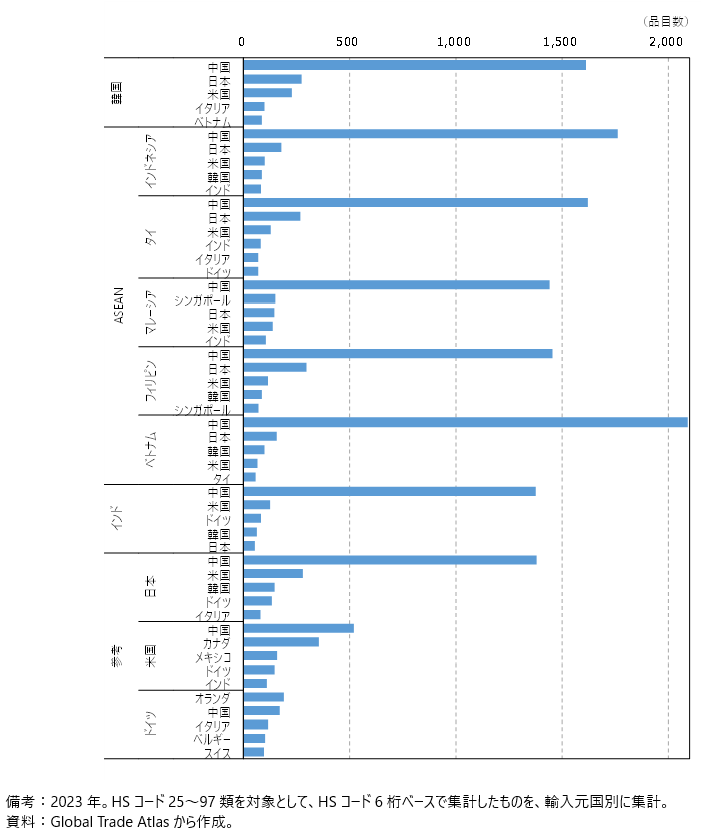
続いて、HHIが50を超える品目の数を、HSコード2 桁ベースで集計したものが第II-2-5-41図である。アジア各国いずれにおいても、有機化学品と一般機械が上位2位までに入っており、特にこれらの品目群で、特定の国への依存度が高い品目が多くなっている。また、電気機器、無機化学品も、多くの国で依存度が高い品目が多くなっている。
第Ⅱ-2-5-41図 HHIが50を超える品目の特徴(HS2桁ベースで集計したもの)
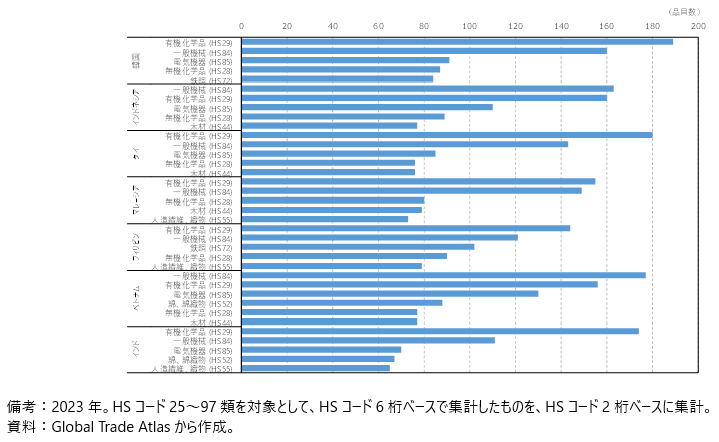
令和6年版通商白書第Ⅱ部第2章第1節では、日本、米国、ドイツについてHHIを用いた分析を行い、日本は米国、ドイツよりも特定国に輸入を依存する品目数が多いことを示した。上記アジア各国は概して、その日本と同等かそれ以上に、特定国に依存する品目数が多くなっている。特定国からの輸入に対する非対称な依存状況は、この地域の多くの国に共通の現象であることが分かる。ただし、その政策的な含意については、各国ごとの輸出入・投資のバランス、具体的な品目の特質や競合関係、サプライチェーン上の位置付け等を個別に見ていく必要があろう。
284 HHIによる輸入集中度とは、品目ごとにおける各国からの輸入シェアの二乗和を100で除して算出したものである。ここで示しているHHI は、特定の国に完全に依存していれば指数は100となり、輸入国の分散が進むほど値が0に近づくものとしている。HHIが25を下回ると、輸入シェアが過半の国は存在せず、少なくとも4か国以上の輸入先が存在することを示唆している。
285 インドネシア、マレーシア、フィリピンは、他のアジア諸国の曲線と重なるため、見やすさの観点から表に含めていない。