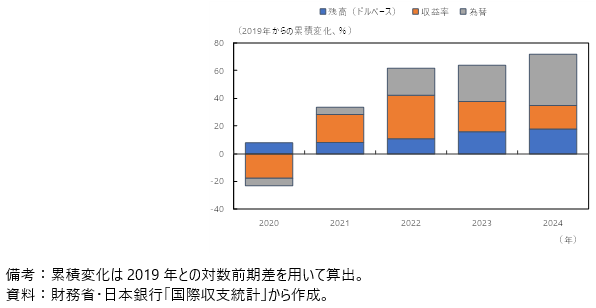我が国の貿易投資関係もまた、近年の国際政治経済構造の大きな変動に直面している。貿易摩擦の激化、過剰生産能力と過剰依存のリスク、経済安全保障認識の広がり、グローバルサウス諸国の存在感の高まり、デジタル化やグリーン移行への対応の多様性は、いずれも我が国企業が国境を超えるビジネス活動において直面する変化であり、高まる不確実性の要因となっている。同時に、デジタル化、グリーン移行、サプライチェーン強靱化といった新たな国際的潮流は、成長するグローバルサウス諸国を含めた海外市場におけるビジネスの新たな成長機会でもある。では、このような国際環境変化の中で、我が国の今後の通商関係をどのように展望すべきだろうか。その検討に当たって、まずは我が国のこれまでの貿易投資構造の変容を理解する必要があろう。
近年、我が国の国際収支構造に大きな関心が集まっている。我が国は長年、貿易収支黒字を維持してきたが、2011年の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故の後に赤字に転じ、その後も燃料価格や為替の動向によって赤字となりやすい構造となっている。さらに、デジタル貿易赤字の拡大が指摘される一方で、対外直接投資や証券投資が増えた結果として第一次所得収支の黒字が増加している。
こうした国際収支構造の変化は、昨今の大幅な円安の進行との関連に着目して議論されることも多い。しかし、その背後では、デジタル経済化等がもたらす産業構造の変化や、中国の産業発展と景気低迷、事業環境の悪化を始めとする国際的な事業・競争環境の変化が、企業の立地・投資戦略を変化させつつあることにも目を向ける必要がある。世界の財貿易の伸びは対GDP比で停滞しているが、サービス貿易は拡大を続けている。その背景には、世界的なデジタル技術の発展・普及等による、Baldwinの言う第三のアンバンドリングの進展がある286。加えて、ものづくりとサービスの融合が、産業の付加価値源泉の変化をもたらしている。従来、サービス貿易は、財に比べて規模が小さく、輸送や旅行等の個別分野が中心であり、統計上の限界もあったために余り注目されてこなかった。しかし、ものづくりとサービスの融合が進み、越境取引の形態が変わった今、財とサービスの貿易投資を一体的に分析する必要性が増している。さらに、それを踏まえた日本企業のグローバルな立地・投資戦略を見ることで、今後の日本の通商関係を巡る機会と課題を理解することができるだろう。
本章では、まず我が国が強みとしてきた製造業の輸出の状況を多角的に分析した上で、モノとサービスの越境取引を巡る新たな展開に、取得可能なデータから接近することで、財とサービスの貿易投資の全体像を把握することを試みる。さらに、我が国企業の立地・投資戦略を分析することで、現在の日本の製造企業やコンテンツ企業が持つグローバル戦略や産業立地上の日本の位置付けと課題、日本経済にとっての対外直接投資の意義について検討する。その上で、ものづくりとサービスの融合が進み、国境を超えるビジネス活動と付加価値源泉が急速に移行する時代における、我が国の通商関係について展望する。
286 Baldwin (2016)
第1節 国際収支構造
本節では、我が国の国際収支の動向を概観し、我が国の対外貿易投資の全体的な特徴を考察する。2023年は、第一次所得収支が高水準で推移する中、貿易収支の赤字幅が縮小したことから、経常収支全体では黒字幅が拡大した。2024年も同様の傾向が続いたことから、経常収支の黒字幅は一段と拡大している。他方、近年の財・サービス収支の赤字は継続している。
本節では、我が国の経常収支、財・サービス収支、第一次所得収支の動向を整理し、それぞれトレンドの変化を考察する。特に、これまで別々に見ることが多かった財とサービスを一体とし、対世界及び主要貿易相手国・地域との収支の推移を見ることで、我が国の財・サービス収支を統合的に概観する。
1. 経常収支の概観
(1) 経常収支
2024年の経常収支(速報値)は約29兆円の黒字となり、黒字幅は過去最高となった(第II-3-1-1図)。内訳を見ると、第一次所得収支が約40兆円の黒字と、過去最高であった2023年から一段と黒字幅を拡大させた。貿易収支の赤字幅が2年連続で縮小したことも、経常収支全体の黒字幅の拡大に寄与した。この間、サービス収支も、コロナ禍前にゼロ近傍まで縮小した後、一旦はコロナ禍の影響からマイナス幅が拡大したが、足下では、緩やかに赤字幅を縮小させている。
第Ⅱ-3-1-1図 日本の経常収支の推移
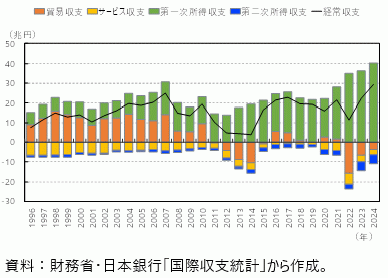
(2) 財・サービス収支の動向
① 財・サービス収支全体の動き
2024年の財・サービス収支(名目)は、約8.2兆円の赤字となっている(第II-3-1-3図)287。財とサービス別では、財の貿易収支が約5.5兆円の赤字、サービス収支が約2.8兆円の赤字となっている。財・サービス輸出に占めるサービスの割合は中長期的に増加傾向であり、2000年に比べて10%ポイント程度上昇している(第II-3-1-2図)。サービス輸出の存在感が高まっていると言えよう。一方、財・サービス輸入に占めるサービスの割合は、資源価格の変動の影響を受けながらも、中長期的には横ばい圏内で推移している。
第Ⅱ-3-1-2図 日本の財・サービス輸出入に占めるサービスの割合
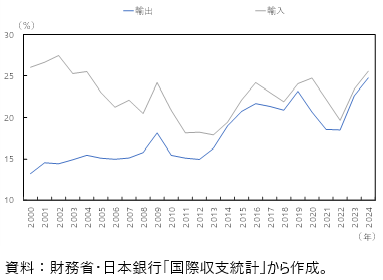
近年では、一部サービス業の規模は、製造業の主要産業並みになっている。さらに、財に含まれるサービス業の付加価値が非常に大きくなっており、財貿易とサービス貿易の垣根を超えて、我が国の産業競争力を考えていく必要がある。そこで、財貿易とサービス貿易を全体として、収支に与える影響を見ていく。
財・サービスの名目輸出は、全体として増加基調にある(第II-3-1-3図)。足下の輸出全体を押し上げているのは、輸送用機器である。また、旅行サービスや知的財産権等使用料も増加している。
第Ⅱ-3-1-3図 日本の財・サービス収支の推移(対世界)
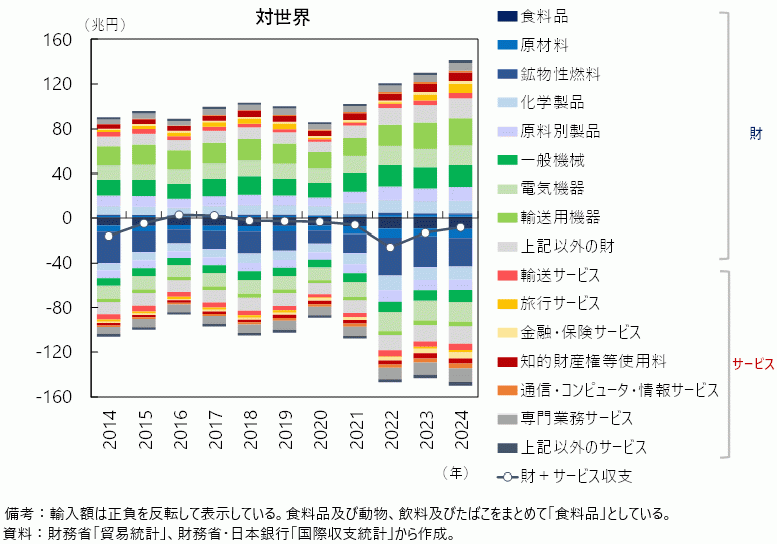
一方、輸入については、エネルギー・一次産品価格の変動を受けた食料・原燃料の増減が全体に大きく寄与している(第II-3-1-4表)。また、足下の輸入では、デジタル関連の輸入額と赤字が拡大傾向にある。この点は、第Ⅱ部第3章第3節で改めて取り上げる。
第Ⅱ-3-1-4表 日本の主要品目の輸出入額
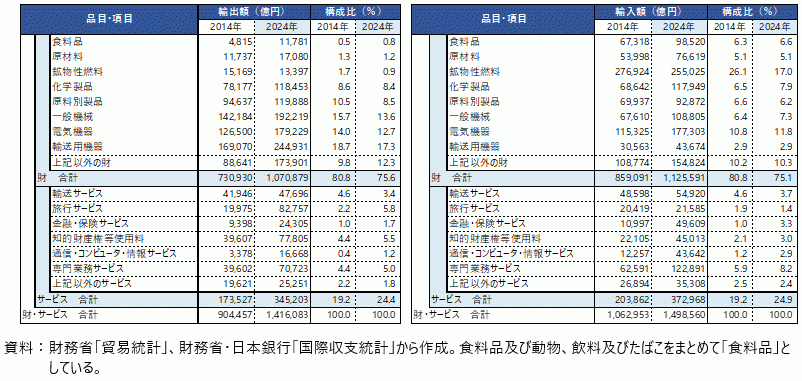
以下では、国・地域別の輸出入動向を見る。
287 本節における「財・サービス収支」は、貿易統計上の貿易収支と、国際収支統計上のサービス収支とを、合算して捉えている。
(i) 対米国
対米国の財・サービス収支は、足下で輸出入とも拡大している(第II-3-1-5図)。主に、最大の輸出品目である輸送用機器が、コロナ禍による供給制約の解消等により、輸出全体を押し上げていることが背景にある。また、一般機械も幾分増加しているほか、知的財産権等使用料等のサービスも存在感を増しており、2023年からは電気機器の輸出額を上回る大きさとなっている。この間、輸入については、特にデジタル関連のサービス輸入額(2024年で8.4兆円288)が拡大している。
第Ⅱ-3-1-5図 日本の財・サービス収支の推移(対米国)
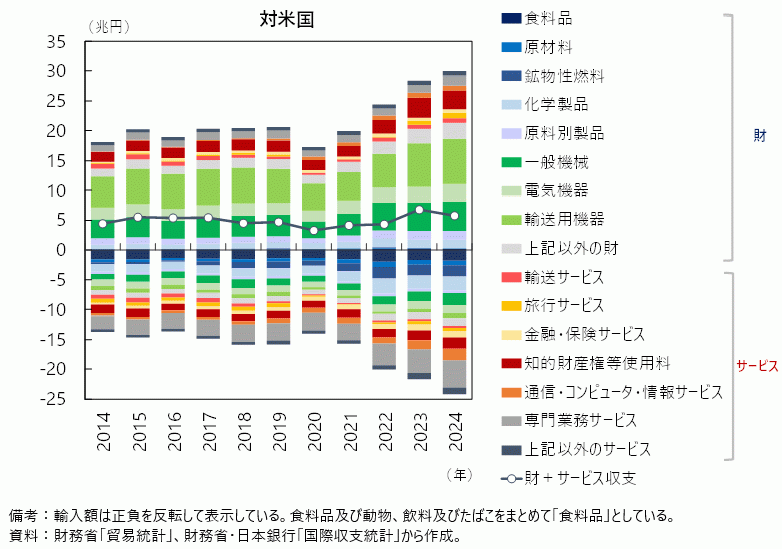
288 知的財産権等使用料、通信・コンピュータ・情報サービス、専門業務サービスの合計。
(ii) 対EU
対EUの財・サービス収支は赤字が継続している(第II-3-1-6図)。時系列では、コロナ禍の時期を除けば、輸出入とも緩やかに増加している。EU向けの輸出は、輸送用機器を中心とした機械類が主体となっている。輸入については、化学製品が最大のシェアであり、緩やかに増加しているが、中でも医薬品の占める割合が大きい。
第Ⅱ-3-1-6図 日本の財・サービス収支の推移(対EU)
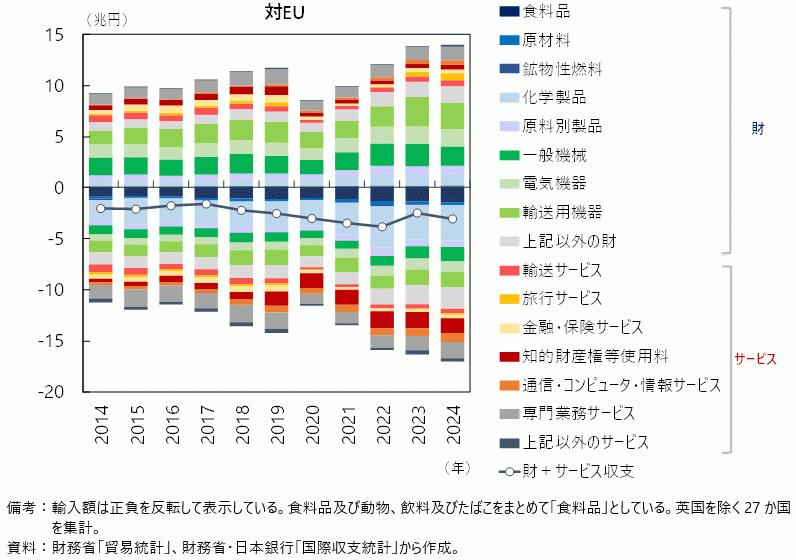
(iii) 対中国
対中国の財・サービスの輸出入は、2023年にいずれも減少した。また、収支は2022年から赤字幅が拡大傾向にあり、電気機器等の財輸入が増加している(第II-3-1-7図)。もっとも、電気機器輸入全体に占める中国のシェアは長期的に低下しており、代わりに台湾やASEAN10がシェアを伸ばしている(第II-3-1-8図)。
第Ⅱ-3-1-7図 日本の財・サービス収支の推移(対中国)
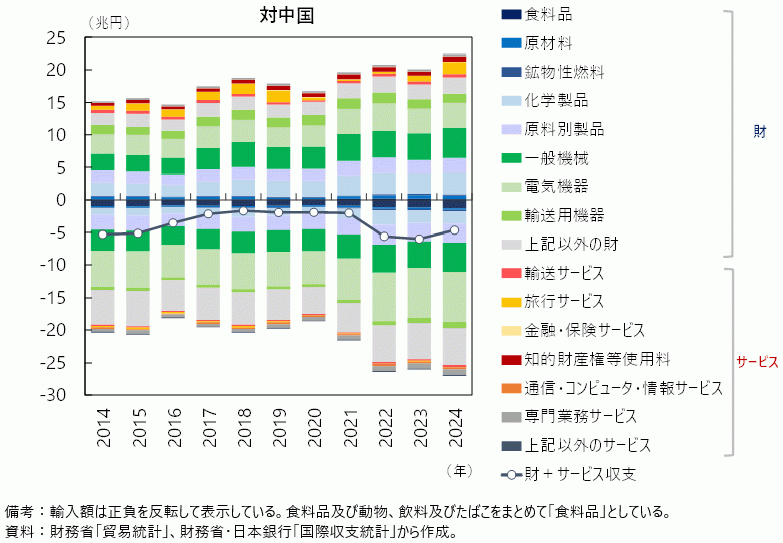
第Ⅱ-3-1-8図 日本の電気機器輸入の国・地域別シェア
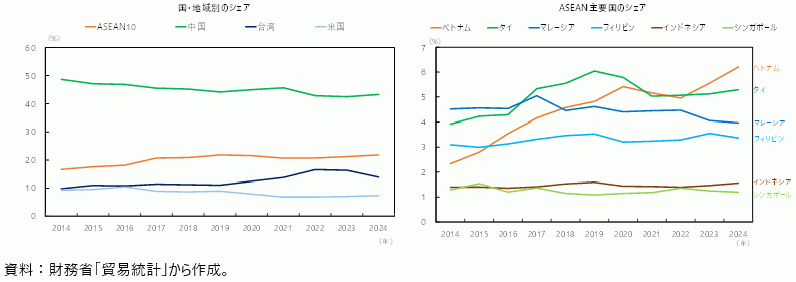
(iv) 対ASEAN10
対ASEAN10でも、足下で収支が赤字方向に動いている(第II-3-1-9図)。原燃料だけでなく、電気機器、デジタル関連のサービスの輸入が増加しており、収支悪化に影響している。シンガポールからのデジタル関連サービスの輸入については、第Ⅱ部第3章第3節で詳述する。
第Ⅱ-3-1-9図 日本の財・サービス収支の推移(対ASEAN10)
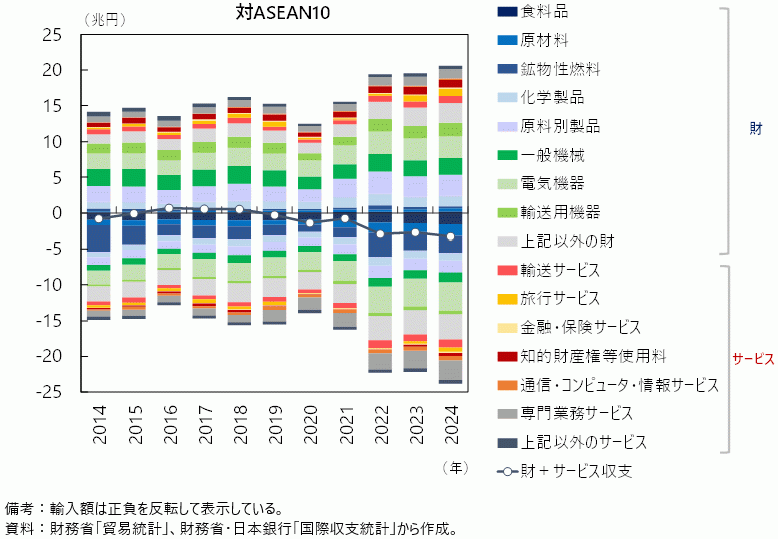
② 為替と財輸出の動向
日本の名目での財輸出は増加を続けている。ただし、2021年から2024年半ばにかけて為替の円安傾向が続いたことから、為替の輸出価格及び輸出数量への影響を考慮する必要がある。そこで、ドル建及び数量ベースの財輸出を確認すると、2022年以降の円安局面では、円建ベースの輸出が2020年から2024年にかけて1.6倍程度の増加となっている一方、ドル建及び数量ベースの輸出は伸び悩み、直近はむしろ減少傾向にある(第II-3-1-10図)。
第Ⅱ-3-1-10図 ドル建、円建、数量ベースの財輸出
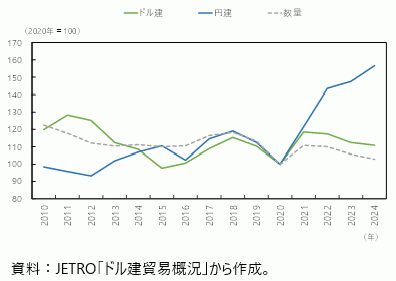
数量ベースとドル建ベースは、長い目で見ればほぼ同様のトレンドをもっており、特に直近では、ほぼ並行的に動いている。このことは、ドル建ベースで見れば輸出単価がほぼ変わらず、企業が現地通貨建での値上げをあまり行っていないということを示唆している。
この点を、実際の輸出の契約通貨構成を踏まえた輸出物価指数で確認する(第II-3-1-11表、第II-3-1-12図)。契約通貨構成を考慮した輸出物価指数で見ても、企業が契約通貨建の輸出物価を余り変化させていなかったことが確認できる。
第Ⅱ-3-1-11表 輸出物価の契約通貨別構成比
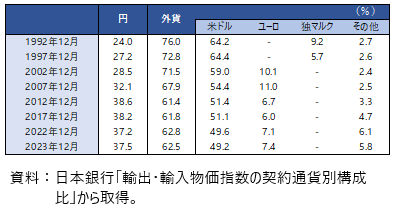
第Ⅱ-3-1-12図 輸出物価の推移
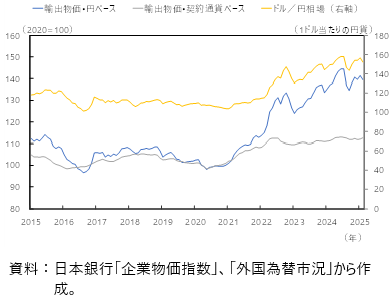
2024年の輸出及び輸入への影響を定量的に見ると、名目貿易収支の変動の大宗は、為替変動要因によるものであり、特に輸出については、契約通貨建、数量の寄与は限定的なものとなっている(第II-3-1-13図)。
第Ⅱ-3-1-13図 貿易収支の変動要因分解(2024年)
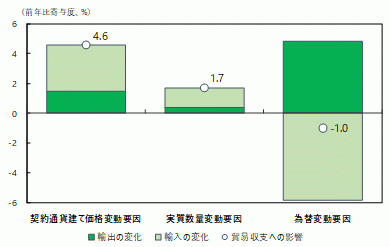
資料:日本銀行「企業物価指数」、「実質輸出入の動向」から作成。
こうした為替感応度の低さについては、様々な理由が指摘されている。まず、先ほど示したように、我が国輸出の契約通貨は、およそ半分をドルが占めており、ユーロやその他通貨を含めると約62.5%が外貨建の契約となっている。企業はこうした外貨建での価格設定をしており、為替には反応しにくいことが、佐藤等によって指摘されている289。
また、日本企業の海外進出に伴う企業内輸出比率の上昇も、為替感応度の低下に寄与していると見られる。佐藤によると、日本企業が企業間で輸出を行う場合、建値通貨の決定は輸出企業と輸入企業の間の交渉力によって決まり、輸出元、輸出先の通貨や国際決済通貨であるドルが選択肢となる291(第II-3-1-14図)。一方、企業内貿易の場合は、日本本社企業は自社の現地法人に為替変動リスクを負わせないため、現地通貨を選択することが多いと指摘されている。
第Ⅱ-3-1-14図 貿易建値通貨選択
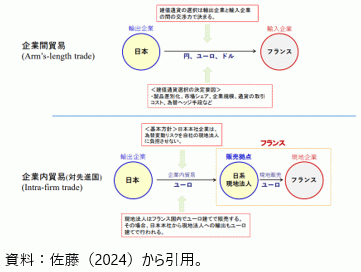
日本企業の企業内貿易比率は、日本企業が海外展開を進める中で趨勢的に上昇しており、直近では、輸出の50%強が企業内貿易となっている(第II-3-1-15図)。こうした企業内貿易比率の高まりは、現地通貨建の輸出物価の為替感応度を押し下げる方向に働いてきたと考えられる。
第Ⅱ-3-1-15図 日本企業の企業内貿易比率
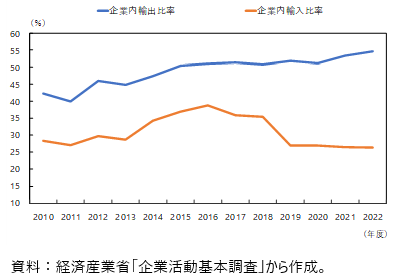
最後に、輸出製品の差別化又はニッチ化も、価格感応度の低下に寄与していると考えられる。製品の差別化が行われている場合、当該製品が他の製品で代替しにくくなるため、価格の上下に対して、需要の変動が小さくなる。その結果、特に価格改定に何らかのコストが伴う場合には、企業が価格を据え置く方が合理的と判断されることもある。この点、単価指数と輸出物価から輸出製品の付加価値指数を見ると、趨勢的に上昇している(第II-3-1-16図)。中国を始めとしたコスト競争力に勝る国がグローバル・サプライチェーンに参加する中で、我が国企業は既存の輸出財で差別化を行ってきたことが、こうした傾向の背景にあると考えられる。
第Ⅱ-3-1-16図 輸出の付加価値指数
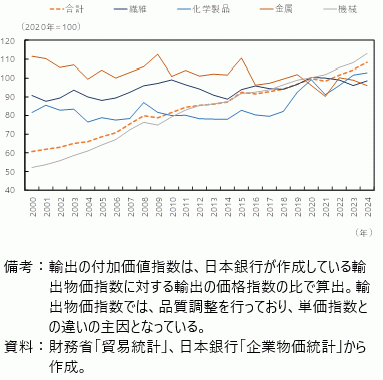
289 佐藤(2023)
290 経済産業省(2023)
291 佐藤(2024)
③ サービス収支の動向
第Ⅱ部第1章第2節でも見たとおり、Baldwin et al.は、輸送と旅行を除く、デジタル化の進展等の構造変化の中で重要性が増すサービス群を「モダン・サービス」と呼称している292。日本のモダン・サービスの収支は、悪化が続いており、主な下押し要因は、専門業務サービスや通信・コンピュータ・情報サービスといったデジタル関連である(第II-3-1-17図)。デジタル関連貿易については第Ⅱ部第3章第3節で別途分析を行うため、ここでは、それ以外の品目、特に、収支にプラスに働いている知的財産権等使用料のうち、産業財産権等使用料を中心に最近の特徴を確認する。
第Ⅱ-3-1-17図 モダン・サービス収支と内訳
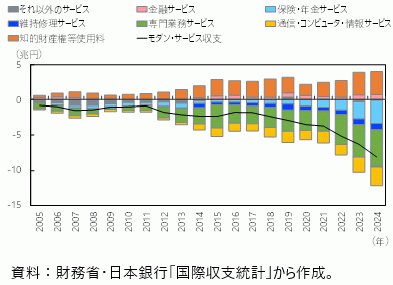
まず、収支が黒字となっている知的財産権等使用料は、産業財産権等使用料と著作権等使用料から構成される。近年、著作権等使用料の輸入が拡大しているものの、産業財産権等使用料による輸出の増加が全体の収支を押し上げている(第II-3-1-18図)。
第Ⅱ-3-1-18図 知的財産権等使用料の輸出入の内訳
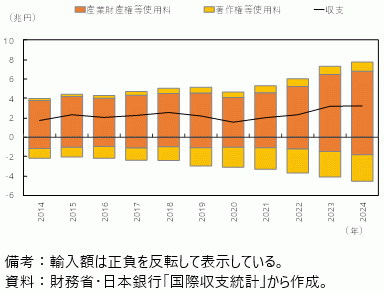
国際収支統計からは、産業財産権等が海外においてどの業種で利用されているか、詳細を把握することはできないため、総務省の「科学技術研究調査」293を用いて考察を行う。我が国の企業の技術貿易輸出の過半は、輸送用機械器具製造業が占めており、2021年度以降の増加は主に同業種によるものとなっている(第II-3-1-19図)。
第Ⅱ-3-1-19図 日本の企業の産業分類別の技術輸出
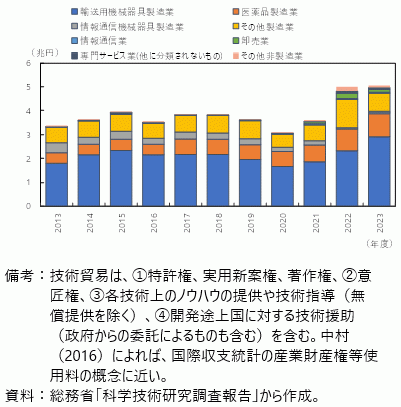
また、我が国技術輸出の多くは、親子会社間によるものが多い(第II-3-1-20図)。我が国企業が海外に製造拠点を設ける動きが、技術貿易関連の輸出の誘発につながってきたと考えられる。例えば、製造企業が設立した海外現地法人が現地で製造を行う際に、親会社の産業財産権を活用した事業収益のうち、一定の金額を産業財産権等使用料として親会社に支払うといったケースが代表的である。これらの事実は、松瀬他が産業財産権等使用料と自動車の海外生産台数との相関が高いと指摘していることとも整合的である294。
第Ⅱ-3-1-20図 日本の親子会社間の技術輸出とそれ以外の技術輸出
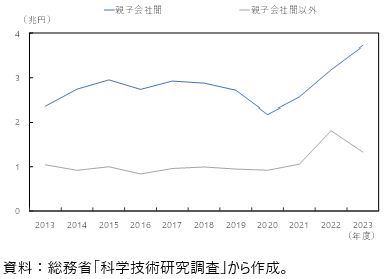
デジタル関連以外でモダン・サービスの収支を押し下げているのは、保険・年金サービスである。保険・年金サービスは、ケイマン諸島を除く中南米向けの支払いが大幅に増加している(第II-3-1-21図)。松瀬他によると、こうした国々では、税制上のメリットから再保険市場が発達しており、日本からこれらの国への支払が急速に増加している295。
第Ⅱ-3-1-21図 日本の国・地域別の保険・年金サービスの輸入
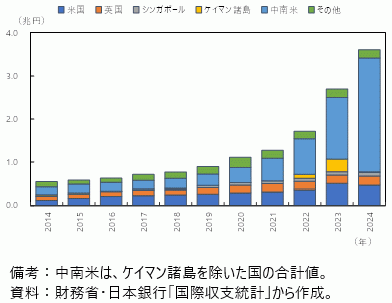
292 Baldwin et al. (2024)
293 2024年(令和6年)調査では、企業約13,500、非営利団体・公的機関約1,100及び大学等約4,100の合計約18,700客体を調査対象とし、そのうち91%(企業は87%、非営利団体・公的機関は99%、大学等は99%)から回答を得ている。
294 松瀬他(2023)
295 松瀬他(2023)
(3) 第一次所得収支の動向
過去最高の黒字を記録した第一次所得収支の動きを概観する。第一次所得収支の推移を見ると、2021年以降、黒字幅は拡大している(第II-3-1-22図)。この主因は、直接投資収益の増加であり、2020年時点では10兆円弱だったが、直近3年間はその2倍以上の25兆円近傍で、大幅な増加となっている。一方、2010年代半ば頃まで第一次所得収支の大半を占めていた証券投資収益は、相対的に緩やかな増加にとどまっている。
第Ⅱ-3-1-22図 日本の第一次所得収支の内訳
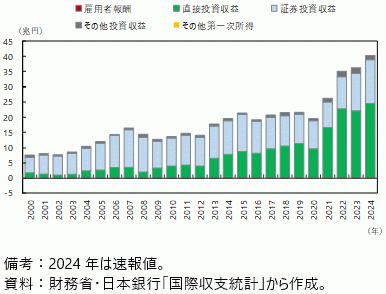
直接投資収益を地域別に見ると、2010年代まではアジア(中国を除く)や中国が中心であったが、2020年代に入って先進国の割合が急激に増加した(第II-3-1-23図)。この点、直接投資残高を見ても2020年代になって、米国や欧州向けの投資が増えている(第II-3-1-24図)。
第Ⅱ-3-1-23図 日本の国・地域別の直接投資収益の推移
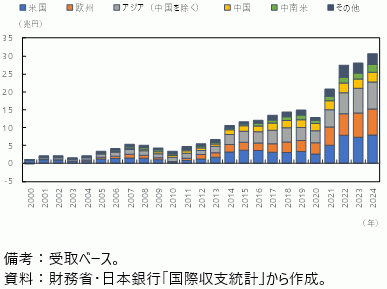
第Ⅱ-3-1-24図 日本の国・地域別の対外直接投資残高
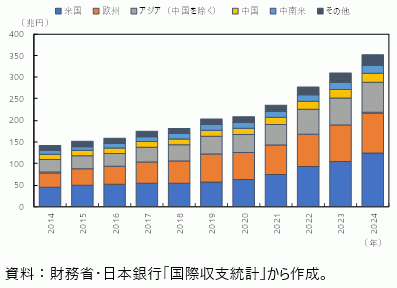
アジア、米国、欧州について、2019年から2024年の増加分を業種別に見ると、いずれも非製造業の増分が大きい(第II-3-1-25図)。
第Ⅱ-3-1-25図 日本の主要国・地域からの直接投資収益(製造・非製造業別)
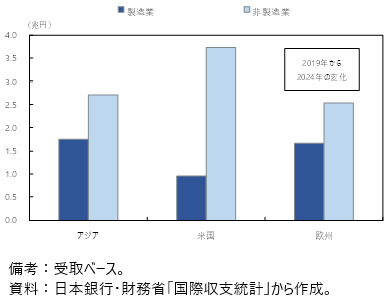
さらに非製造業の内訳を見ると、アジア、米国、欧州のいずれの地域においても卸売・小売業、金融・保険業による収益が拡大している(第II-3-1-26図)。また、通信業も共通してプラスとなっている。
第Ⅱ-3-1-26図 非製造業の直接投資収益
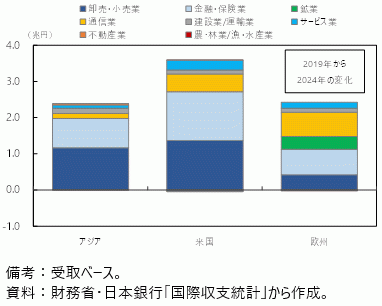
以上のような直接投資のトレンドは、我が国企業の海外展開の段階や外的環境が変わったことを反映していると考えられる。我が国企業による海外非製造業への直接投資の内容については、第Ⅱ部第3章第3節で更に分析する。
なお、名目輸出のケースと同様、直接投資収益についても、為替円安による押上げ効果がはたらいている点には注意を要する。この点、ドルベースと円ベースでの直接投資収益を比較すると、2021年以降、ドルベースの直接投資収益は増加していない(第II-3-1-27図)。
第Ⅱ-3-1-27図 日本の直接投資収益(円ベース、ドルベース)
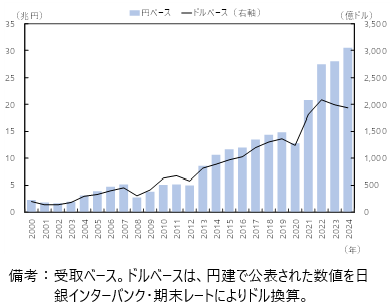
また、対外直接投資残高を見ても、円ベースに比べるとドルベースでの増加ペースは緩やかなものにとどまっている(第II-3-1-28図)。
第Ⅱ-3-1-28図 日本の対外直接投資残高(円ベース、ドルベース)
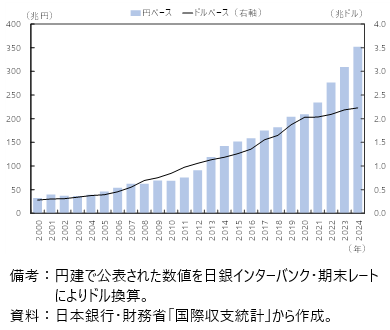
ここで、為替の影響について、第II-3-1-29表の方法で試算を行う。
第Ⅱ-3-1-29表 直接投資収益の残高・為替等の要因への分解方法
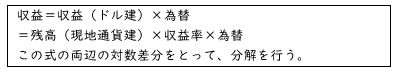
上記に基づく分解を行うと、直接投資収益の押上げ幅の相当部分は、為替要因による可能性が示唆される(第II-3-1-30図)。これを踏まえると、足下の第一次所得収支の水準は、為替の円安によって押し上げられている面が少なくないとみられ、今後の為替動向の影響を受けやすいと考えられる。もっとも、全ての海外現地投資がドル建で行われているわけではないため、当試算はある程度の幅を持って見る必要はある。
第Ⅱ-3-1-30図 直接投資収益の残高・為替等の要因への分解