第2節 財貿易
過去30年間に、先進国は軒並み財輸出の世界シェアを落としてきたが、その中でも我が国の世界シェアの低下は大きい。品目ごとに見ても、ほぼ全ての主要輸出品目で世界シェアを減らしてきている。我が国製造業は、多くの差別化された個別製品・部素材で高いシェアを持つニッチトップになっており、そうした製造業の技術と集積には競争力がある。しかし、それが我が国全体としての交易条件の改善にはつながっていない。我が国の貿易構造には、過去30年間の輸出品目の変化が少ないという特徴も看取される。これは、例えば第Ⅱ部第2章第4節で見た、中国の輸出品目のダイナミックな変化とは対照的である。イノベーションを通じた高付加価値化による新たな輸出産品、輸出企業、輸出先の開拓を通じて、我が国が世界に提供する付加価値を強化していく必要がある。
本節では、我が国の財輸出の構造を分析し、イノベーションを通じた高付加価値輸出の機会の開拓について展望する。
1. 我が国の財輸出の現状
(1) 我が国の財輸出の現状
① シェアから見た我が国の財輸出
第Ⅱ部第3章第1節で見たとおり、我が国の財輸出は数量ベースでは伸び悩んでいる。これには、世界貿易の停滞だけではなく、我が国の世界に占める輸出シェアの低下も影響していると考えられる。実際、1990年代半ばに10%弱であった輸出シェアは、足下、4%弱まで低下している(第II-3-2-1図)。こうした長期的なシェアの低下は、米国やドイツを始めとした先進国に共通して観察されているが、我が国については、下落幅が他国に比べて大きいことに加えて、他の多くの先進国でシェア低下が底を打った2022年以降の上昇幅が小さいという特徴がある。
第Ⅱ-3-2-1図 世界輸出に占める先進国のシェア
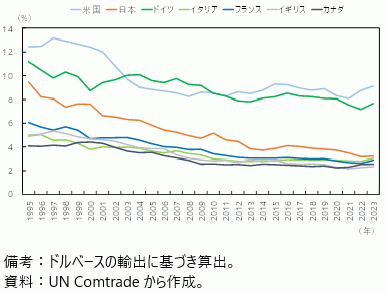
先進国の輸出シェアが中長期的に低下してきた一因として、中国の世界貿易におけるプレゼンスの拡大が挙げられる。中国は、2001年のWTO加盟の頃から世界貿易への参加度合いを高めており、その輸出シェアは過去25年程度で10%ほど上昇している(第II-3-2-2図)。なお、足下では、米中貿易摩擦や中国の経済状況の影響などもあって、中国のシェアは横ばいとなっており、日本を除く先進諸国のシェア低下に歯止めがかかっていることと表裏の関係になっているといえる。
第Ⅱ-3-2-2図 世界輸出に占める中国のシェア
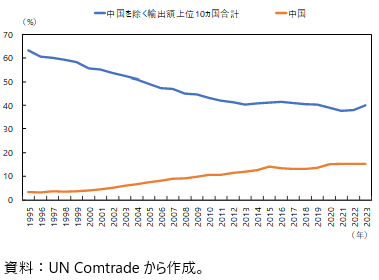
日本の輸出シェアの低下が輸出全体に及ぼした影響を見るために、ドルベースの名目輸出金額を世界貿易要因(名目世界輸出・ドルベース)とシェア要因に分解すると、近年の輸出の伸び悩みには、世界貿易要因よりも我が国のシェア低下の寄与が大きいことが分かる(第II-3-2-3図)。2019年対比で、2023年の名目輸出は小幅に増加しているが、そのうち、世界貿易要因による伸びを日本のシェア要因が打ち消すような姿になっている。
第Ⅱ-3-2-3図 輸出の世界貿易要因とシェア要因への分解
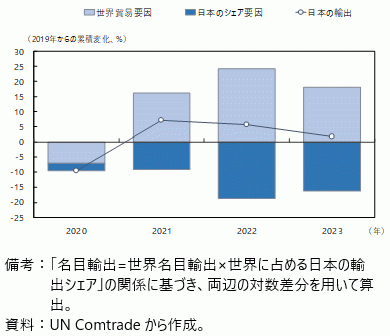
こうしたシェアの低下は、特定の財によるものではなく、幅広い財で共通している(第II-3-2-4図)。特に、機械類における輸出シェアの低下幅が大きくなっている。
第Ⅱ-3-2-4図 財別の輸出額と世界シェアの変化
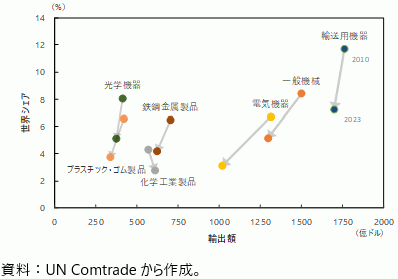
② 輸出シェア低下の背景
中国が輸出シェアを拡大する中で、先進国へのキャッチアップも進んでいる。輸出品目類似度(Export Similarity Index)296を使って、日本・ドイツ・韓国と中国との輸出品目の類似度を見ると、直近では相当程度、日本やドイツとの類似性が高まっていることが分かる(第II-3-2-5図)。
第Ⅱ-3-2-5図 中国と各国の輸出品目の類似度
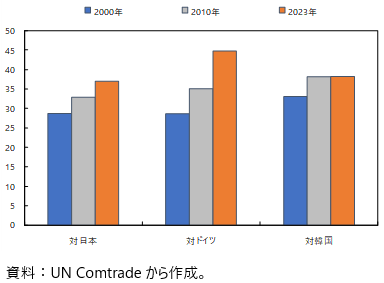
シェーデは、こうした中国を中心とした新興国のキャッチアップに対して、日本は複雑な製品や技術を必要とする上流工程への移行で対応したことを指摘している297。シェーデは、主要先端製品・部材の売上高と世界シェアに関するNEDOの報告書から、過去に比べて、世界シェアが高い小さなバブルが、特に部材系で増えていることに注目した。すなわち、我が国企業が、産業の川上でニッチトップとなっている製品を多く持つことを意味している(第II-3-2-6図)。また、こうした傾向は日本独自のものであり、米国、EU、韓国、台湾、中国を見てもバブルチャートの右下が空白地帯の国が多く、唯一、日本と似た傾向を持つのが、化学産業等に強みを持つドイツであるとも述べている。
こうした多くのニッチトップを抱えているという事実は、日本の技術力の高さを示すものであり、日本企業が戦略的に自社の強みをいかし、スマイルカーブの上方にある、より付加価値の高い製品にシフトしてきたことを示唆している。もっとも、こうしたニッチトップ戦略だけでは、市場が限定されがちなために輸出の面的な広がりを確保することが難しく、全体の輸出規模と競争力を維持できない可能性がある。
第Ⅱ-3-2-6図 主要先端製品・部材の売上高と世界シェア
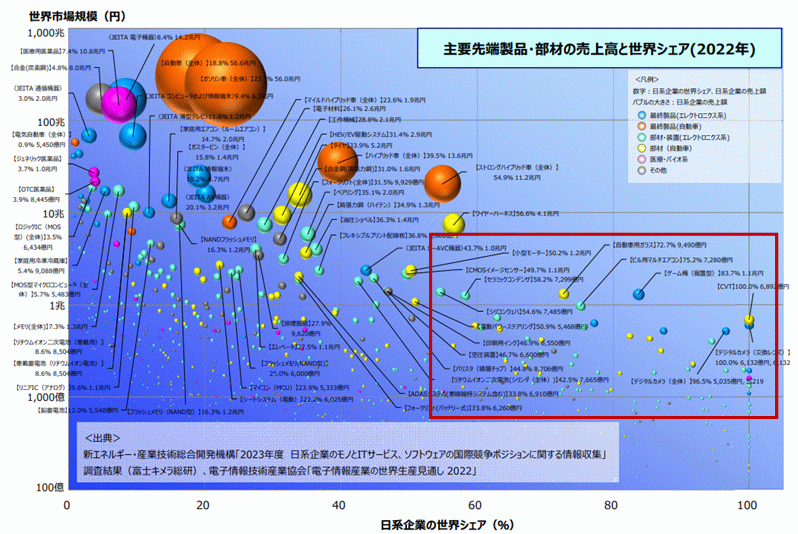
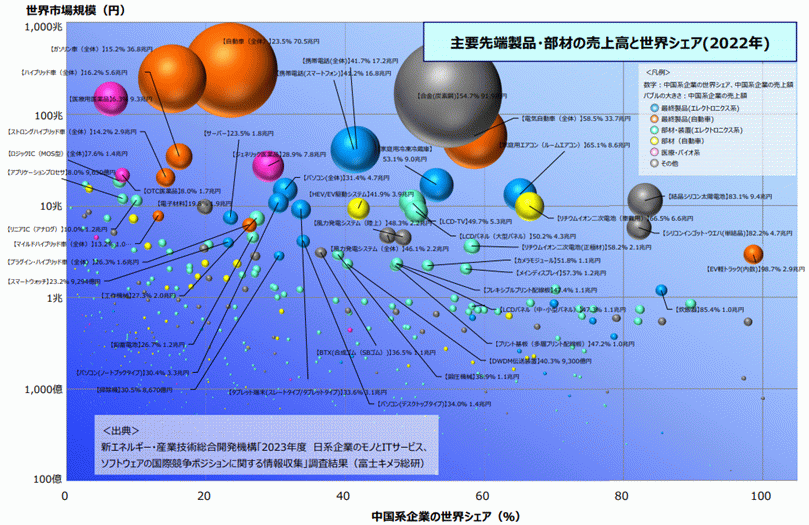
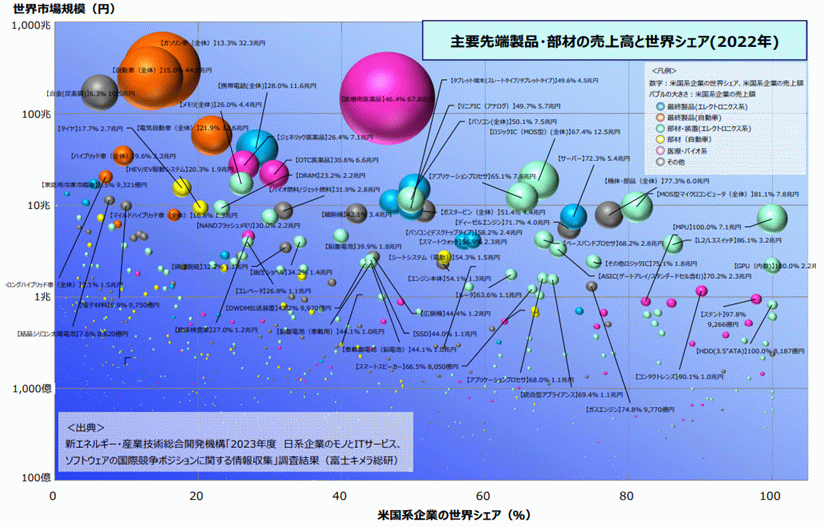
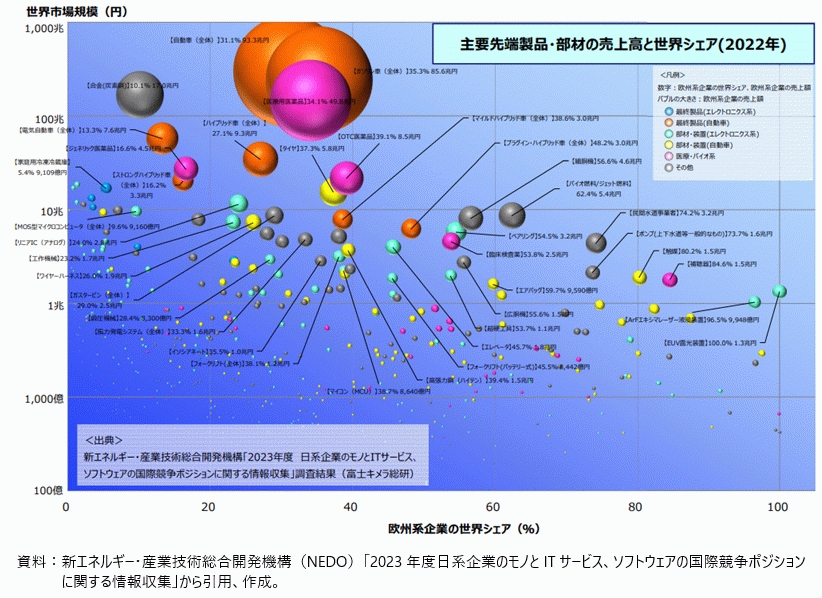
輸出規模の拡大という観点から、新しい輸出産業・製品の創出について検討する。まず、顕示比較優位(Revealed Comparative Advantage)指数(以下、RCA指数)298を用いて、我が国の貿易パターンから見た産業の新陳代謝の状況を確認する。第II-3-2-7図では、横軸に1995年時点のRCA指数、縦軸に2023年時点のRCA指数をとり、財別に点描している。1995年時点と2023年時点で、貿易パターンに全く変化がない時、各点は傾き1かつ切片0の直線上に並ぶ。他方、回帰線を引いたときに、切片が0より大きく、傾きが1より小さい場合には、1995年時点でRCA指数が高かった品目のRCA指数が、2023年時点では相対的に低下しやすいことを示す。傾きが1より大きい場合には、過去にRCA指数が高いものがより強くなりやすいことを示す。各国を比較すると、日本の傾きが最も1に近く、全体的な傾向としてRCA指数の相対関係に変化が大きくないことが分かる。ドイツについても同様の傾向が見られる一方、中国や米国は傾きが小さいことから、貿易構造を大きく変化させてきたことが分かる。
第Ⅱ-3-2-7図 RCA指数からみた各国の貿易構造
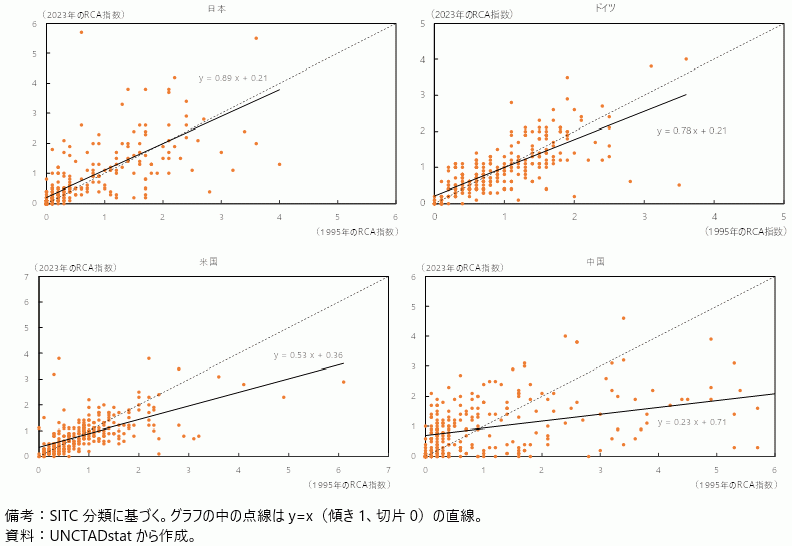
さらに、2023年時点の各国における輸出上位品目に注目すると、日本とドイツについては、1995年時点のRCA指数がほぼ全ての品目で既に1を上回っている。他方、米国と中国の2023年時点の主力輸出品は、1995年時点のRCA指数が1を下回る又は1近傍のものが多い。すなわち、この約30年間で新たな主力輸出製品を生み出していることが示唆される(第II-3-2-8図)。
RCA指数の変化がないことは、競争力のある産業をある程度維持出来ていることを示唆していると同時に、産業の新陳代謝やイノベーションが弱い可能性も示唆している。日本は長年にわたって、機械産業に強みを持ち、それを維持してきたことに加えて、サプライチェーンの上流に移行することでニッチトップを獲得してきた。これは、日本の企業が技術力や品質管理といった点で競争力を維持してきたことの証左といえる。他方で、産業の新陳代謝が活発な国では、新しい産業が台頭し、過去の産業のRCA指数が低下する傾向も観察される。RCA指数の変化が貿易を伸ばす上で必須の条件ではないものの、我が国の産業の新陳代謝が活発ではなかった可能性は重要な示唆と考えられる。
第Ⅱ-3-2-8図 各国の輸出上位10品目のRCA指数の変化
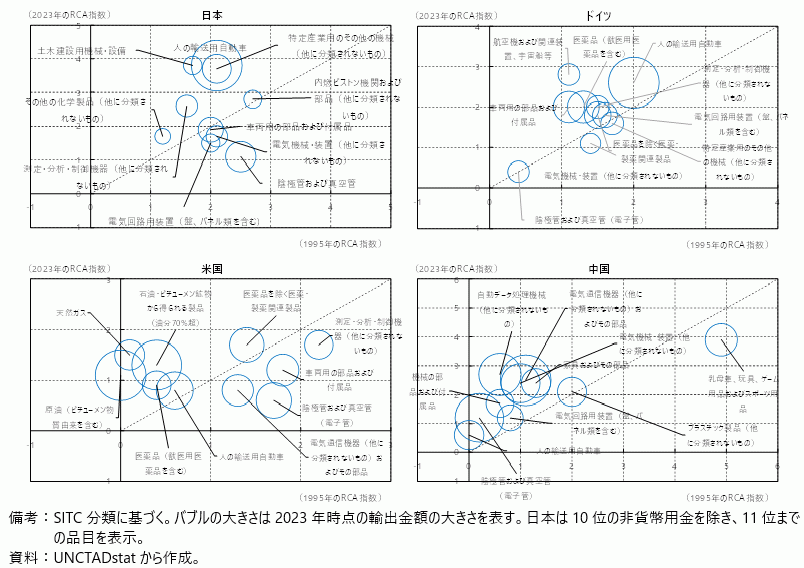
続いて、我が国が新たな輸出製品、輸出企業、輸出先を開拓できてこなかった可能性を、日本の輸出の内延と外延という観点から検討を行う。内延とは、既存輸出企業・既存輸出品目・既存輸出相手国による貿易取引を指し、外延とは、上記のいずれかが新規であるような取引を指す。伊藤他の分析によれば、我が国の輸出は、内延効果によって変動しており、外延効果による寄与は小さくなっている299(第II-3-2-9図)。
第Ⅱ-3-2-9図 日本の輸出の内延と外延
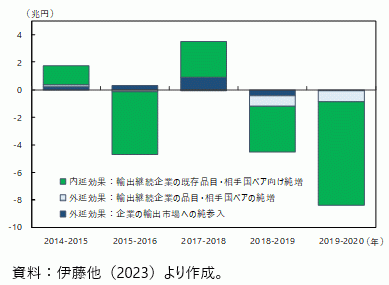
象徴的な事例として、2017年ないし2022年にHSコードが新たに追加された品目を新製品と捉え300、主な製品の輸出シェアを見ると、我が国はいずれの製品においても輸出シェアが低位にとどまっている(第II-3-2-10図)。
第Ⅱ-3-2-10図 新製品の貿易シェア(2023年)
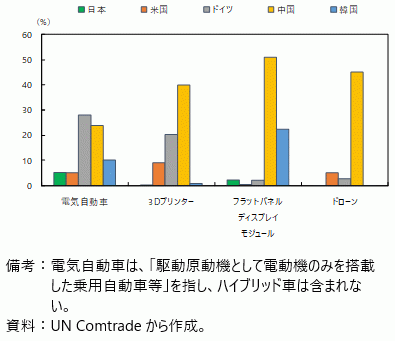
296 2か国間の輸出品目の類似性を示す指標であり、値が100に近いほど輸出構造が似ていることを表す。計算は、①国ごとに輸出総額に占める各輸出品目のシェアを計算、②品目ごとにシェアの低い方の国の数値を抽出し、それを合計することで得られる。
297 シェーデ(2024)
298 RCA 指数= (A国の特定品目の輸出額 / A国の総輸出額) ÷ (世界全体の同品目の輸出額 / 世界全体の総輸出額) という形で計算される。RCA指数の値が1を超える場合、その国はその品目において比較優位を持っていると解釈される。つまり、世界平均と比べて相対的に多く輸出していることを意味する。
299 伊藤他(2023)
300 税関によれば、HS2022の改定において、「魚等の粉、ミール及びペレット」、「たばこ等を含有する物品(電子たばこ等)」、「炭化水素のハロゲン化物を含有する混合物」、「積層造形用の機械(3Dプリンター)」、「フラットパネルディスプレイモジュール」、「電気電子機器のくず」、「無人航空機(ドローン)」、「航空機の部分品」のHSコードが新設された。ただし、「航空機の部分品」は他のコードからの移設となっている。財務省関税局・税関「HS品目表の2022年改正(HS2022)の概要」(HS2022改正説明会資料)、2022年2月4日、
https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/classification/hs2022_shiryo.pdf![]() 。
。
2. 財輸出の拡大に向けた論点
ここまで、我が国の財輸出が近年、ドル建の額や世界シェアで見て減少傾向にあることを概観してきたが、今後の財輸出拡大を展望する上では、イノベーションと高付加価値化による新たな製品、新たな輸出企業の出現を通じた外延の拡大が一つの方向性になり得る。ここでは、イノベーションを通じた財輸出の拡大の可能性について検討する。
(1) 輸出とイノベーション
日本企業の海外進出の状況は、イノベーション活動の実施有無との関連性が見られる(第II-3-2-11図)。全企業に占める海外進出している企業の比率は、10%弱となっている。これを、イノベーション活動の実行の有無別に見ると、イノベーション活動を実行している企業の海外進出率は12%程度である一方、非実行企業については5%程度にとどまっている。この傾向は、進出先の国・地域別に見た際も同様であり、いずれの国・地域においても、イノベーション活動を実行している企業の進出率の方が高くなっている。
第Ⅱ-3-2-11図 イノベーション活動の有無と海外進出の状況
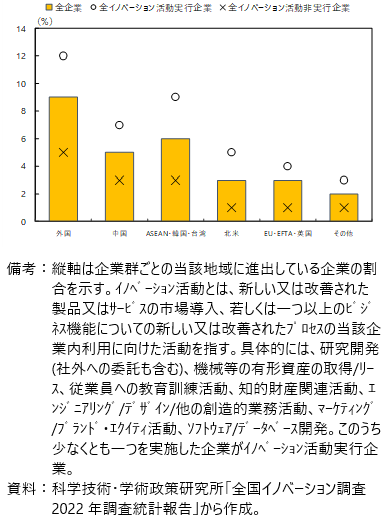
イノベーションと海外進出のこうした関係が観察される背景には、イノベーションが海外進出を促進するという因果と、海外進出がイノベーションを促進するという因果の双方向があると考えられる。前者については、新々貿易理論が提起した、「生産性の高い企業ほど輸出市場に参入しやすい」という議論と重なる。国際市場への参入には、輸送費、関税、規制適合コスト(例:現地の安全基準)などの固定費用が発生するため、これらのコストを負担できるのは、既に国内市場で高い生産性を持ち、十分な利益を上げている企業に限られるとされる。この理論は、米国、日本、EU、中国など、さまざまな国の企業データを用いた研究で裏付けられている。我が国の企業データを用いた研究では、輸出企業の平均的な労働生産性が非輸出企業よりも高いことが示されている301。
ただし、ここで注意が必要なのは、生産性の高い企業が必ずしも輸出を行っているとは限らない点である。戸堂は、R&Dを行っており生産性が高いにもかかわらず、輸出をしていない日本企業が多いことを指摘している302。輸出企業の比率に対して、R&Dを行っている企業の比率の方が高い状況は続いており、我が国には引き続き、輸出の潜在力を持ちながら輸出を行っていない企業は多いと考えられる。
逆に、海外に進出することで、生産性を上げる可能性も指摘されている。輸出を行うことで、企業はより厳しい国際競争に直面し、より効率的な生産方法や品質管理の導入に努めることで、生産性が向上する可能性があるほか、進出先で最新の技術や経営ノウハウを学ぶことが期待される。この点、Ito and Tanakaは、日本の輸出企業はR&D活動を行っている割合が大きく、さらに内部R&Dと外部R&Dを併用している割合が大きいと示されている303(第II-3-2-12表)。
第Ⅱ-3-2-12表 輸出企業とR&Dの関係
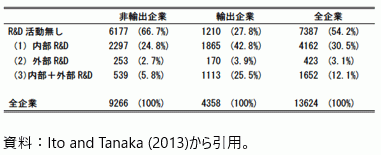
301 経済産業省(2016)
302 戸堂(2011)
303 Ito and Tanaka (2013)
(2) イノベーションの促進に向けて
① 我が国のイノベーションの特徴点
このように、イノベーションを推進していくことは、輸出の拡大につながっていく可能性が高い。我が国企業には、イノベーションにより成長していく潜在力が充分にある。例えば、GX分野では、我が国の関連特許スコアは高くなっている(第II-3-2-13図)。また、国内スタートアップの資金調達額は増加してきており(第II-3-2-14図)、国内スタートアップの育成環境が整備されてきていることから、こうした企業を育てていくことが重要である。
第Ⅱ-3-2-13図 各国企業のGX関連特許スコア
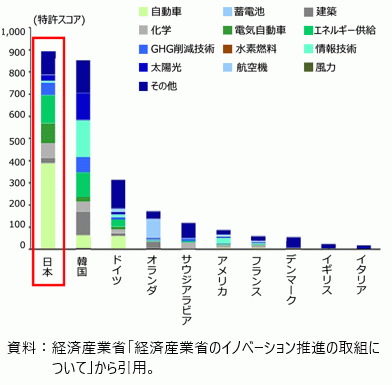
第Ⅱ-3-2-14図 国内スタートアップの資金調達状況
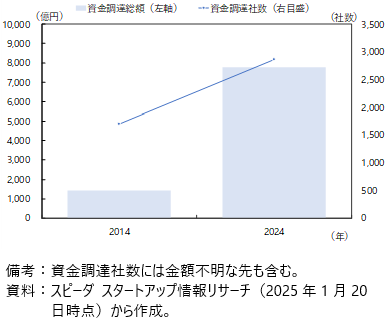
もっとも、こうした成長の潜在力があるにもかかわらず、我が国の研究開発の量と質は伸び悩んでいる。研究開発の量の面では、米中が急増し、ドイツ、韓国も伸びている中で、日本の研究開発費は横ばいとなっている(第II-3-2-15図)。
第Ⅱ-3-2-15図 企業部門の研究開発費の推移
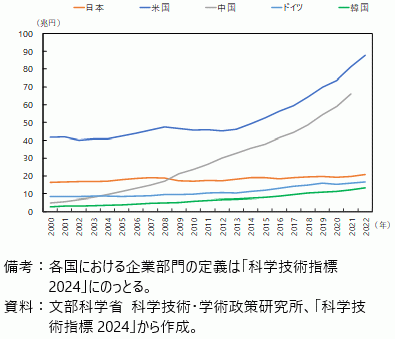
また、Galindo-Rueda and Vergerの定義に従って、OECDのデータを集計すると、我が国の財輸出に占める「R&D集約的な産業」(航空・宇宙、医薬品、電子機器・光学機器)304の割合は、低位に留まっている(第II-3-2-16図)。
第Ⅱ-3-2-16図 輸出に占めるR&D集約財の割合
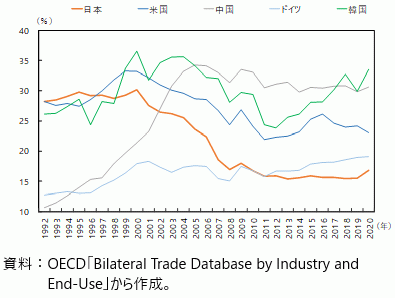
我が国の研究開発は、大企業を中心に行われている(第II-3-2-17図)。米国やドイツ、韓国なども大企業による研究開発投資額が大きいが、従業員数が500人未満の企業のシェアは、日本が最も小さくなっている。
第Ⅱ-3-2-17図 企業規模別研究開発投資額(2021年)
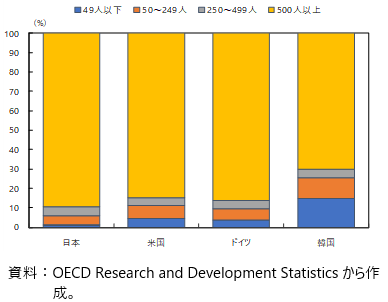
輸出金額を見ても、大企業が占める割合が高いという特徴がある(第II-3-2-18図)。内閣府によれば、「従業員数250人以上」と「従業員数50~249人」の二つのグループ間の輸出企業割合を見ると、日本はOECD加盟国平均に比べて、両者の輸出企業割合の差が大きいことが指摘される305。
第Ⅱ-3-2-18図 企業規模別の輸出企業数と輸出額
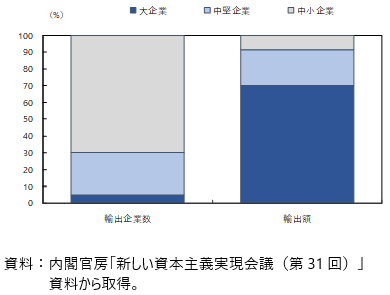
これらを踏まえると、中堅企業や中小企業の潜在力をいかしたオープンイノベーションには、更なる可能性があると考えられる。オープンイノベーションには、社内外を問わず優秀な人材と連携できるなどのメリットがある(第II-3-2-19表)。
第Ⅱ-3-2-19表 オープンイノベーションとクローズドイノベーションの考え方
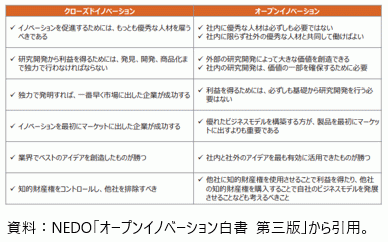
しかしながら、欧米企業と比べたオープンイノベーションの実施率は、現状では低位にとどまっている(第II-3-2-20図)。先に述べたように、イノベーションに取り組んでいる企業は海外進出にも取り組んでいる割合が高いことを踏まえると、オープンイノベーションの実施率の向上は、輸出促進にも寄与すると見られる。
第Ⅱ-3-2-20図 オープンイノベーションの実施率
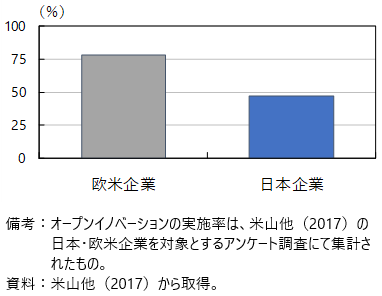
304 Galindo-Rueda and Verger (2016) では、これらの産業を「High R&D intensity industries」と位置付けている。
305 内閣府(2023)
② イノベーション促進に向けた施策
更なる産業競争力の強化に向けて、我が国では、研究開発の量と質の拡充、事業化・付加価値の創出、横断的な取組を柱としたイノベーション促進策が進められている(第II-3-2-21図)。
第Ⅱ-3-2-21図 イノベーション促進に向けた政策の考え方
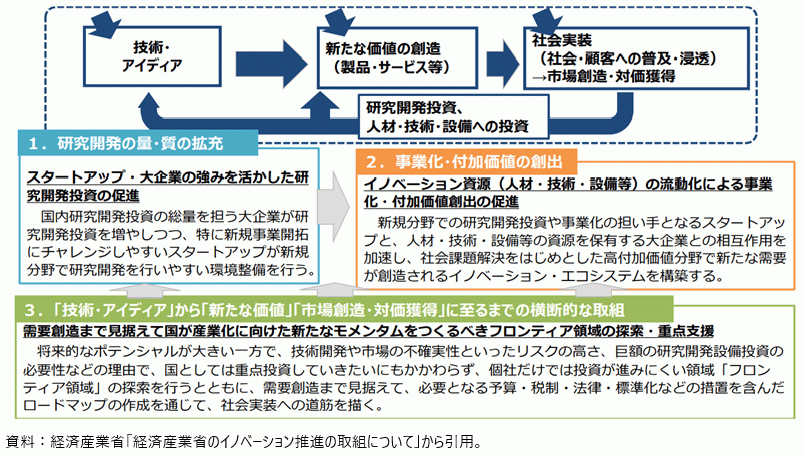
研究開発の量と質の拡充に向けては、民間企業の研究開発投資を促進するために、税制による後押しが行われている306。具体的には、イノベーションを促進するために、イノベーションのインプットである研究開発に着目した研究開発税制と、イノベーションのアウトプットである知的財産から生じる所得に着目したイノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)が設けられている(第II-3-2-22図)。
第Ⅱ-3-2-22図 研究開発税制とイノベーション拠点税制との関係
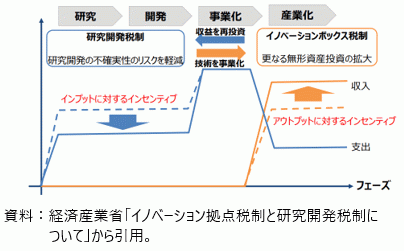
研究開発税制は従来から導入されていたが、令和5年度の税制改正では、一般型において、民間企業における研究開発投資の拡大を更に促すべく、試験研究費の額の増減に応じて法人税額に対する控除上限が変動することでインセンティブがより働く仕組みの導入が行われている。また、オープンイノベーション型の、スタートアップとの共同・委託研究を促す類型における研究開発型スタートアップの定義の見直しや、質の高い研究開発を促進し、革新的なイノベーションを生み出す観点から、博士号取得者等を雇用した場合に、その人件費の一部を税額控除する類型を新たに創設するなどの見直しが行われている。
オープンイノベーションの促進と同時に、イノベーションの国際競争が激化している中、研究開発拠点としての我が国の立地競争力を強化し、民間企業による無形資産投資を後押しすることも重要である。こうした観点から、イノベーション拠点税制307は、特許権・AI関連のプログラムの著作物から生じるライセンス所得・譲渡所得に対して、30%を所得控除する制度となっている(第II-3-2-23図)。こうした減税措置は、2000年代から欧州各国で導入が始まっており、直近ではシンガポールやインド、香港といったアジア諸国・地域でも導入が進んでいる。
第Ⅱ-3-2-23図 イノベーション拠点税制の概要
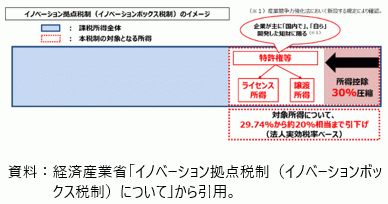
イノベーション投資の入口であるインプットにインセンティブを付与する研究開発税制と、出口であるアウトプットにインセンティブを付与するイノベーション拠点税制は、我が国におけるイノベーション推進に寄与するものと考えられる。研究開発税制は、研究開発の不確実性のリスクを軽減し、研究開発投資に対するインセンティブを高める効果を持つ一方で、イノベーション拠点税制は、国内で自ら研究開発した特許権等の知的財産から生じる所得に対して減税措置を設けることで、我が国の研究開発拠点としての立地競争力を強化する効果が期待される。
事業化・付加価値の創出に向けては、大企業はリスクのより高い新規分野での研究開発投資や事業化リスクを負いにくいこと、スタートアップでは事業拡大のハードルが高いことを踏まえて、大企業とスタートアップのそれぞれの特徴を生かしていくことが重要である。スタートアップ支援については、2022年に策定した「スタートアップ育成5か年計画」の下、人材・資金・事業の三つの柱に沿って、様々な支援策を打ち出している。スタートアップの課題は、ステージに応じて異なる。創業段階のプレシード・シード期には、人材・ネットワークの構築支援に加えて、資金面で、スタートアップに投資した個人投資家に対する優遇措置であるエンジェル税制や、日本政策金融公庫等を通じた創業を支える資金供給を拡大させている。その後のアーリー・ミドル期やレイター期においても、資金供給の拡大促進策や、公共調達や海外展開等を通じた事業拡大の支援、出口戦略の多様化といった、事業拡大の段階に応じた支援施策の整備を進めている(第II-3-2-24図)。
第Ⅱ-3-2-24図 スタートアップ育成5か年計画の概要
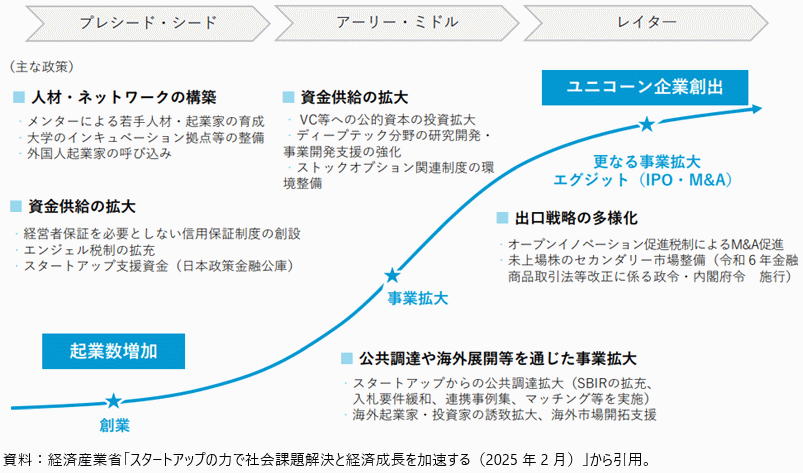
306 Bloom et al. (2019) によれば、イノベーション促進の政策として研究開発税制の有効性が学術的にも確認されている。
307 経済産業省「イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)について」、
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/about_innovation_tax.html![]() (2025年5月15日閲覧)。
(2025年5月15日閲覧)。