第3節 モノとサービスの越境取引
デジタル技術の発展とグローバルな普及は、ものづくりとサービスの融合を進展させ、モノとサービスの越境取引を統合的に分析する必要性を高めている308。日本の貿易投資構造も例外ではない。国際収支統計で見える我が国のサービス貿易に関しては、インバウンドの拡大により観光サービスの黒字が増えていることや、いわゆるデジタル貿易赤字が拡大していることに注目が集まっている。同時に、ものづくりとサービスの融合という産業の潮流も踏まえ、財とサービスの貿易投資の全体像を把握する観点では、サービスの海外拠点を通じた提供(モード3)やサービス付加価値の貿易(モード5)を含む越境取引についても検討する価値があろう309。
本節では、第Ⅱ部第1章第2節で行ったサービス貿易の類型整理と世界のデジタル貿易の動向を踏まえ、まず、日本のデジタル関連貿易の動向に焦点を当てて、その特徴点を整理する。その後、デジタル関連にとどまらず、我が国のモノとサービスの越境取引を統合的に分析することで、我が国の財・サービスの貿易投資の実態に接近を試みる。その際、国際収支統計上のサービス収支に表れるサービス貿易(主にモード1・2・4)にとどまらず、事業者の海外拠点を通じたサービス提供(モード3)や、モノの製造・提供に中間投入されたサービス付加価値の貿易(モード5)を含めて見ることで、包括的な分析を試みる。
308 第Ⅱ部第1章第2節参照。
309 第Ⅱ部第1章第2節参照。
1. デジタル関連貿易の動向
(1) デジタル関連貿易の動向
デジタル関連貿易の定義や範囲は文脈によって異なるものの、第Ⅱ部第1章第2節で見たとおり、日本国内の議論では、第Ⅱ-1-2-15図で示している松瀬他の定義を使い、著作権等使用料、通信・コンピュータ・情報サービス、専門・経営コンサルティングサービスをデジタル関連サービスに含めるのが一般的である310。この定義に従うと、2020年頃から、デジタル関連サービスの輸入増加を受けて、デジタル関連貿易の赤字幅は拡大傾向にある(第II-3-3-1図)。足下の動きに着目すると、著作権等使用料、通信・コンピュータ・情報サービス、専門・経営コンサルティングサービスの輸入がいずれも増加していることから、デジタル関連貿易の赤字幅は一段と拡大している。
第Ⅱ-3-3-1図 デジタル貿易収支の動向
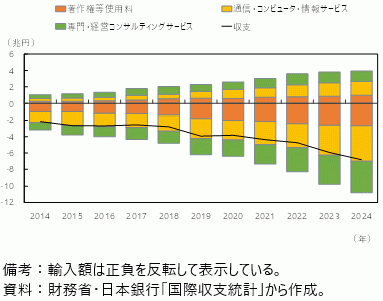
デジタル関連貿易の実体を把握するには、こうしたデジタル関連サービスの輸入増加が、実際の取引数量の増加によるものなのか、それとも為替円安に伴う輸入価格の上昇によるものなのかを分解できることが望ましい。しかし、サービス貿易に関してはデータの制約があり、財輸出のように数量と価格に分解することは容易ではない。この課題に対応するため、一つの代替案として、貿易の決済通貨が主に米ドルで行われていると仮定し、ドルベースの輸出入を数量の代理指標として活用することが考えられる。ただし、実際の決済通貨の詳細は不明であるため、結果の解釈には一定の留意が必要である。
WTOの統計を使って、ドルベースの通信・コンピュータ・情報サービスの輸入動向を見ると、2021年以降は、ドルベースでは横ばいで推移している一方、円ベースでは増加を続けている(第II-3-3-2図)。この対照的な動きは、円安が急速に進んだ2022年以降のデジタル貿易関連収支の悪化に、為替が少なからず影響していることを示唆している。
第Ⅱ-3-3-2図 日本の通信・コンピュータ・情報サービスの輸入
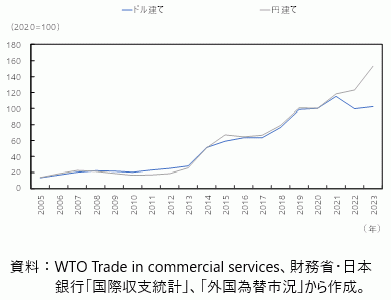
このことを踏まえると、足下のデジタル貿易赤字拡大は幅を持って解釈する必要はあるが、長い目で見れば、輸入が増加基調にあることは明白である。以降では、①著作権等使用料、②通信・コンピュータ・情報サービス、③専門・経営コンサルティングサービス、の各分野において、輸入増加の背景を詳しく分析する。
310 松瀬他(2023)
(2) 著作権等使用料
著作権等使用料は、主にソフトウェア、音楽、映像、キャラクター等の使用料であり、例えばオペレーションシステム(OS)やアプリケーションを搭載した端末を販売する場合に、端末の販売会社がこれらのソフトウェアの著作権を有する会社に支払うライセンス料などが含まれる(第II-3-3-3表)。
第Ⅱ-3-3-3表 著作権等使用料の範囲
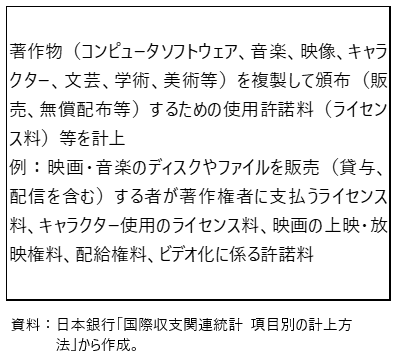
注意が必要なのは、ここに含まれるのは使用料のみということである。国際収支統計上、知的財産関連の取引は、権利の種類や著作物の種類によって様々な項目に分類される(第II-3-3-4表、サービス分類の全体像については第II-1-2-15表)。例えば、近年増加している、日本の消費者から海外配信プラットフォーマーへの直接支払は、著作権等使用料ではなく、音響・映像関連サービスに計上される。他方、海外配信プラットフォーマーの日本法人が海外の本社等に著作権使用料を払う形を取っている場合は、著作権等使用料に計上される。ただ、こうした計上の仕方は、各企業の会計処理・報告次第という実態もあるため、全体としての把握が難しいのが実情と考えられる。
第Ⅱ-3-3-4表 知的財産の取引の計上項目
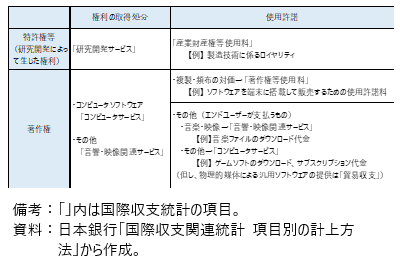
著作権等使用料が含まれる知的財産権等使用料の輸入を地域別に見ると、米国が過半を占めているものの、近年は「その他」も増加している(第II-3-3-5図)。
第Ⅱ-3-3-5図 日本の知的財産権等使用料の支払(国・地域別)
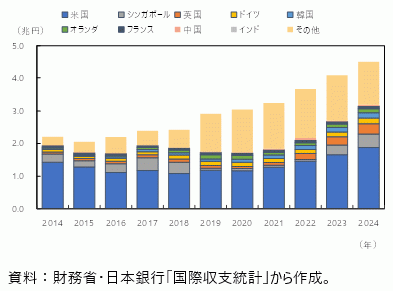
「その他」の国について詳細に検討すべく、WTO及びOECDが公表しているBaTiSで、日本の知的財産権等使用料の支払先国を見ると、米国に次いでアイルランドからの輸入が大きいことが読み取れる(第II-3-3-6図)。
第Ⅱ-3-3-6図 BaTiSデータにおける日本の知的財産権等使用料の支払(国・地域別)
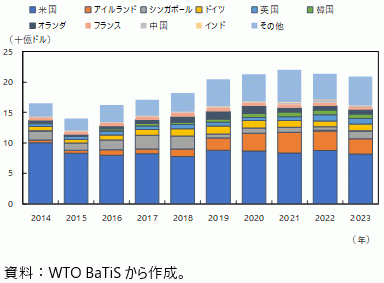
米国の我が国からの知的財産権等使用料の受取を見てみると、ソフトウェアの複製・配布関連のライセンスが最も多く、次いで研究開発成果の使用関連のライセンスが多い(第II-3-3-7図)。
第Ⅱ-3-3-7図 米国の日本からの知的財産権等使用料の受取内訳
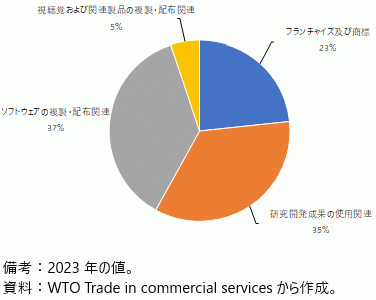
なお、日本の知的財産権等使用料の支払内訳を見てみると、著作権等使用料が6割、産業財産権等使用料が4割となっている(第II-3-3-8図)。
第Ⅱ-3-3-8図 日本の知的財産権等使用料の支払内訳
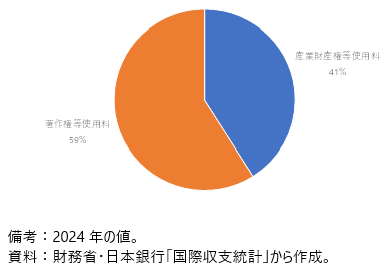
(3) 通信・コンピュータ・情報サービス
続いて、通信・コンピュータ・情報サービスについて確認する。その捕捉範囲を確認すると、コンピュータには、ソフトウェア委託開発費やクラウドサービスなどの利用料に加えて、ゲーム等の汎用ソフトウェアのダウンロードやサブスクリプションの代金等が含まれている(第II-3-3-9表)。
第Ⅱ-3-3-9表 通信・コンピュータ・情報サービスの範囲
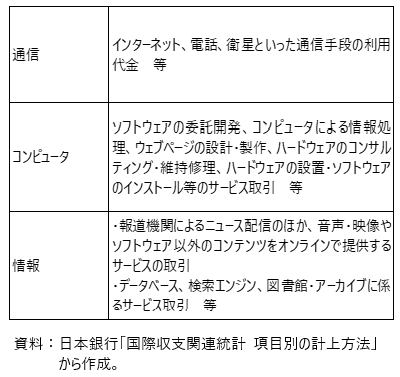
通信・コンピュータ・情報サービスの時系列の動きを見ると、コンピュータサービスが輸出入ともに大半を占めている(第II-3-3-10図)。先述のとおり、コンピュータサービスには多様なサービスが含まれるが、近年のクラウドサービスの利用拡大が増加の主因の一つと考えられる。総務省の報告によると、日本のパブリッククラウドサービス市場は急速に拡大しており、2023年には約3兆円の規模に達している。また、海外大手クラウドサービス(AWS(Amazon)、Azure(Microsoft)、GCP(Google))の利用率が非常に高い311。日本のコンピュータサービス輸入が4兆円程度であることを踏まえると、クラウドサービスの影響は小さくないと考えられる。
第Ⅱ-3-3-10図 日本の通信・コンピュータ・情報サービスの輸出入の内訳
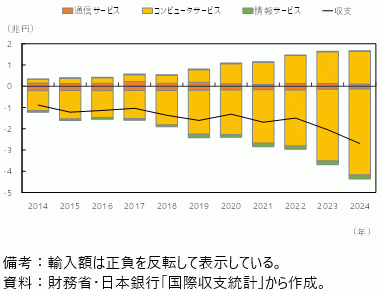
クラウドサービスを提供している海外大手企業の多くは米国企業であるが、通信・コンピュータ・情報サービスの国・地域別収支では、米国に次いでシンガポールに対する赤字が大きくなっている(第II-3-3-11図)。この背景としては、シンガポールに米国企業の東アジア市場(日本を含む)を統括する拠点が設立され、シンガポールの当該統括拠点が米国本社へライセンス料などの知的財産権等使用料を支払い、そのライセンス等を使用してシンガポールから日本へ通信・コンピュータ・情報サービスが輸出されるという流れがあると見られる。
第Ⅱ-3-3-11図 日本の通信・コンピュータ・情報サービスの国別収支の動向
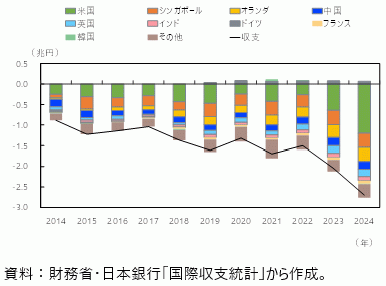
この点を確認するために、まず、日本が輸入する通信・コンピュータ・情報サービスの付加価値が創出された国・地域を見ると、シンガポールの割合が小さくなる一方で、米国や中国は大きくなっている(第II-3-3-12図)。
第Ⅱ-3-3-12図 日本の通信・コンピュータ・情報サービス輸入の付加価値構成(国・地域別)
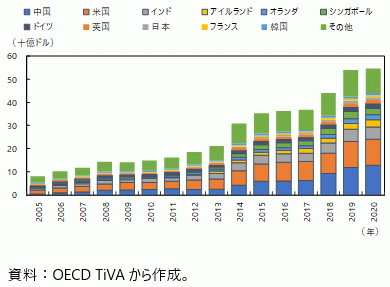
また、日本がシンガポールから輸入する通信・コンピュータ・情報サービスの付加価値構成を見ると、その過半はインドや米国、中国を始めとしたシンガポール以外の国で生み出されていることが分かる(第II-3-3-13図)。
第Ⅱ-3-3-13図 日本のシンガポールからの通信・コンピュータ・情報サービス輸入の付加価値構成(国・地域別)
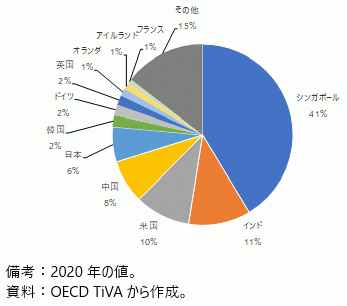
さらに、シンガポールの情報通信業の対内直接投資残高を見ると、2020年以降に米国からの投資残高が急増している。また、米国と比べればまだ規模は小さいが、中国及び香港からの投資残高も近年急増している(第II-3-3-14図)。このことは、米国、中国のデジタル関連企業がシンガポールに現地法人を設立し、日本向けを含む越境サービス提供を行っていることを示唆している。
第Ⅱ-3-3-14図 シンガポールにおける情報通信業の対内直接投資残高
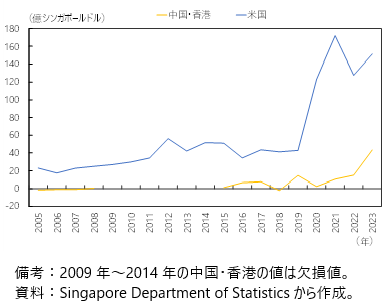
別途、米国の情報サービス企業のアジア・太平洋地域での売上を見ると、シンガポールが最大となっており、米国デジタル関連企業がシンガポールに現地拠点を設立してサービス提供を行っていることと整合的である(第II-3-3-15図)。
第Ⅱ-3-3-15図 米国の情報サービス企業のアジア・太平洋地域での売上
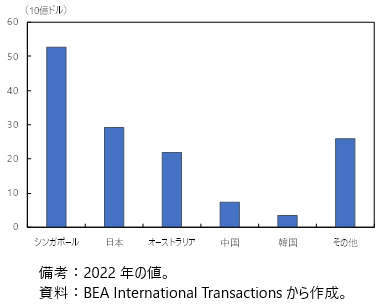
中国企業のシンガポールを経由したサービス提供を間接的に示唆するデータとして、日本のシンガポールからの通信・コンピュータ・情報サービス輸入に占める中国源泉の付加価値額は、2010年代前半から急増している(第II-3-3-16図)。これは主に、中国のデジタル関連企業がシンガポールに設立した現地拠点からサービス提供を行っているためと考えられる312。
第Ⅱ-3-3-16図 日本のシンガポールからの通信・コンピュータ・情報サービス輸入に含まれる中国による付加価値の推移
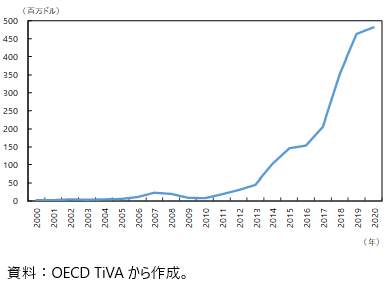
さらに、日本の米国や中国からの通信・コンピュータ・情報サービス輸入について、付加価値の源泉国も確認する。米国と中国それぞれから日本が輸入している、当該サービスの付加価値源泉国の内訳を見ると、ほぼそれぞれの国内で生み出されている(第II-3-3-17図、第II-3-3-18図)。米中では、外国企業ではなくそれぞれの自国企業が、国内で付加価値を創出していることが分かる。
第Ⅱ-3-3-17図 日本の米国からの通信・コンピュータ・情報サービス輸入の付加価値構成
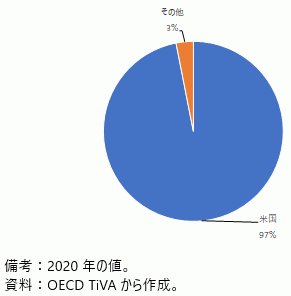
第Ⅱ-3-3-18図 日本の中国からの通信・コンピュータ・情報サービス輸入の付加価値構成(国・地域別)
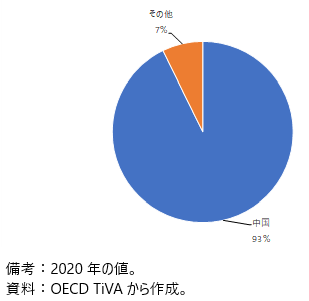
311 総務省(2024)
312 なお、TiVAでは、日本のシンガポールからの通信・コンピュータ・情報サービス輸入に含まれる中国源泉の付加価値の業種別内訳を知ることはできない。そこで、OECD国際産業連関表で、シンガポールの情報通信産業の生産高に占める中国からの中間投入の業種別構成を試算すると、情報通信業が大宗を占める。したがって、日本のシンガポールからの輸入に含まれる中国源泉の付加価値も、情報通信業が多いと考えられる。
(4) 専門・経営コンサルティングサービス
専門・経営コンサルティングサービスには、法務、会計・経営コンサルティングのほか、広報、広告・市場調査に係るサービス取引が計上される。このため、厳密には、対面でのコンサルティングサービス等、デジタル関連以外のサービスも含まれる(第II-3-3-19表)。しかし、ウェブサイトの広告スペースを売買する取引が広告の部分に含まれること等から、松瀬他では、当項目をデジタル関連に含めている313。
第Ⅱ-3-3-19表 専門・経営コンサルティングの範囲
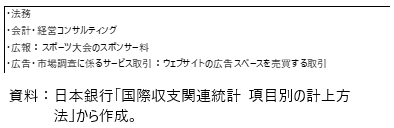
我が国の国際収支統計では、専門・経営コンサルティングサービスの地域別のデータが公表されていないため、同項目を内訳に含む「専門業務サービス」で地域別の動きを確認する。第II-3-3-20図を見ると、米国からの輸入が最大であり、次いでシンガポールとなっている。時系列の推移に着目すると、米国からの輸入が足下でも増加しているほか、シンガポールからの輸入が2019年頃から急増している。まだ大きな割合ではないが、中国からの輸入も徐々に増加している。
第Ⅱ-3-3-20図 専門業務サービスの国別収支の動向
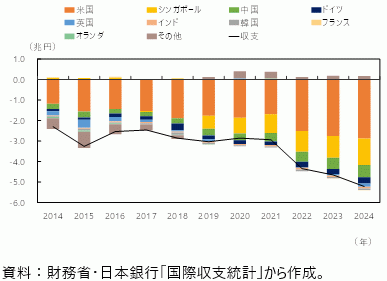
米国からの輸入の内訳については、米国側の統計から詳細に把握することが可能である。米国から日本への専門・経営コンサルティングサービス輸出の内訳を見ると、広告及び関連サービスの割合は必ずしも高くはなく、全体の過半を事業・経営コンサルティング及び広報サービスが占めている(第II-3-3-21図)。
第Ⅱ-3-3-21図 米国から日本への専門・経営コンサルティングサービス輸出(構成比)
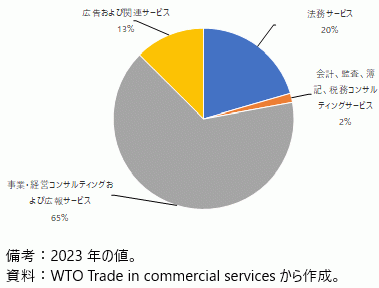
また、時系列の動きを見ると、日本向け輸出の増加を牽引しているのは、事業・経営コンサルティング及び広報サービスとなっている(第II-3-3-22図)。
第Ⅱ-3-3-22図 米国から日本への専門・経営コンサルティングサービス輸出(時系列)
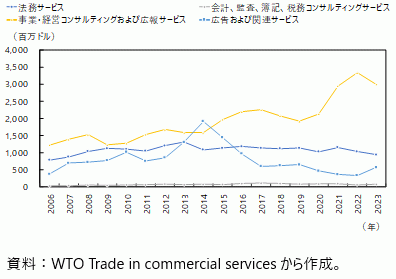
日本の輸入が米国の次に多いシンガポールは、対日収支に関するサービス分野別のデータを公表していない。そのため、参考までに、シンガポールの対世界輸出における専門・経営コンサルティングサービスの内訳を確認すると、広告及び関連サービスのシェアが大きいことが分かる(第II-3-3-23図)。これは、第Ⅱ部第1章第2節で見たとおり、米国の大手検索サイトを始めとするデジタル関連企業が、アジア地域の統括拠点をシンガポールに置いていることが影響していると考えられる。
第Ⅱ-3-3-23図 シンガポールから世界への専門・経営コンサルティングサービス輸出の構成比
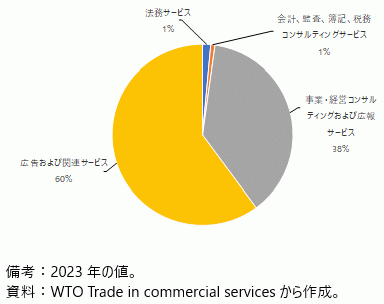
また、内閣府は、インターネット広告における日本国内の広告費支出額(国内生産分+輸入分)と国内広告会社の売上額(国内生産分+輸出分)との差が、専門・経営コンサルティングサービスの赤字額と近似していることを踏まえて、当該分野における赤字額の増加は、大宗が、近年の海外へのインターネット広告関連の支払額の増分で説明できるとしている314。したがって、我が国における専門・経営コンサルティングサービスの輸入拡大は、米国の大手検索サイトの広告関連による寄与が大きいと考えられる。
313 松瀬他(2023)
314 内閣府(2024)
(5) 対内直接投資(モード3)
海外デジタル関連企業による日本国内拠点を通じたデジタル関連サービスの提供(モード3)については、全容を明らかにするのは難しいが、対内直接投資等の情報から検討する。まず、通信業の対内直接投資は、2024年末の残高が約2.9兆円と大きくはないが、2018年に急増し、その後も増加傾向にある(第II-3-3-24図)。同じく通信業の対内直接投資収益は、2024年において約6,600億円と増加しており、収益率も非常に高い(第II-3-3-25図)。
第Ⅱ-3-3-24図 日本における通信業の対内直接投資
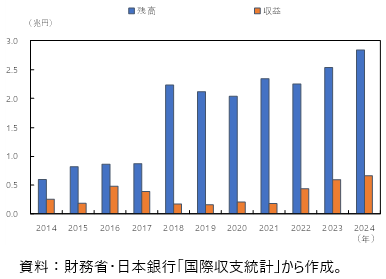
第Ⅱ-3-3-25図 通信業の対内直接投資収益率
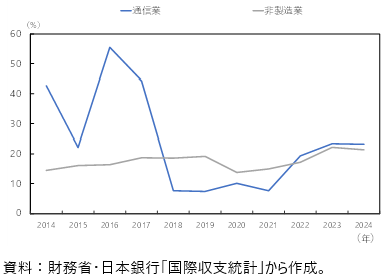
近年、海外の大手デジタル関連企業が、日本国内での大規模データセンターの建設・運用に向けた積極的な投資を発表しており、これにより通信業への対内直接投資が押し上げられると思われる(第II-3-3-26表)。この動きの背景には、生成AIやクラウドコンピューティング市場の急拡大があり、それに伴う膨大なデータ処理需要に対応するため、低遅延・高帯域の通信環境を確保する必要性が高まっていることが挙げられる。さらに、日本国内にデータセンターを設置することでデータを国内保管し、顧客企業等の信頼を獲得する狙いもあると見られる。
第Ⅱ-3-3-26表 海外大手デジタル関連企業による日本への投資
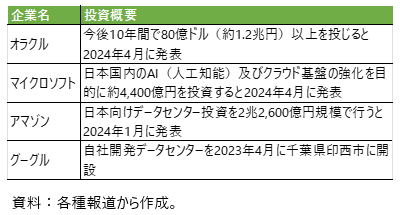
(6) 付加価値貿易(モード5)
デジタル関連サービスの輸入について全体像を把握するためには、付加価値貿易(モード5)の観点から分析を行うことも重要である。先述のとおり、デジタル化がものづくりとサービスの融合を進展させていることを踏まえれば、輸入財に中間投入されるデジタル関連サービスの付加価値も高まっている可能性が高いからである315。ただ、現時点ではこうした分析を行うためのデータが充分に整備されていない。そこで、ここでは関連する情報から問題提起を行うにとどめる。
日本のいわゆるデジタル貿易赤字に着目して、その構造と今後日本が取るべき戦略をまとめた経済産業省若手新政策プロジェクトPIVOT「デジタル経済レポート」316でも、モード5の重要性が指摘されている。例えば、日本の主要な生産品目である自動車において、世界全体の自動車OEM(完成車のメーカー)の売上に占めるハードウェア(財)とソフトウェア(デジタル関連サービスに由来)の比率の予測を行っている(第II-3-3-27図)。それによれば、自動車におけるソフトウェア317の重要性の高まりによって、その比率が6%(2021年時点)から38%(2040年時点)まで増加すると予測されている。たとえハードウェアの製造や品質に優位性があっても、ソフトウェアの競争力で劣るようになれば、その製品自体の競争力を維持するのが難しくなるだろう。このように、デジタル関連サービスは、自動車にとどまらず日本が従来強みを有している製造業において、サービス付加価値という形でその重要性を増しているといえよう。
第Ⅱ-3-3-27図 自動車OEMの売上予測(ハードウェア・ソフトウェア別)
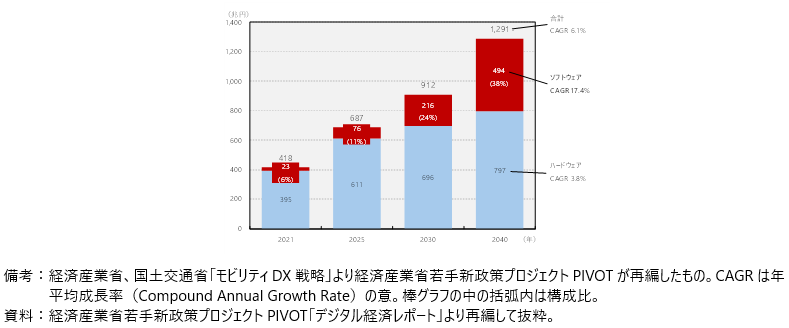
315 第Ⅱ部第1章第2節第2項「サービス貿易の類型」参照。
316 経済産業省(2025)。当該レポートでは、デジタル関連サービスの貿易収支について、国際収支関連統計を用いた分類でなく、有価証券報告書等を用いた個社の取引データに基づくより細かな分類で定義していることに注意ありたい。
317 自動車において重要となるソフトウェアとしては、自動運転など先進安全装備に関するもの、車内エンターテイメントに関するものなどが存在する。
2. 我が国のサービス越境取引の多面的分析
(1) サービス貿易の整理
第Ⅱ部第1章第2節や前項のデジタル関連貿易で見たように、国際収支統計のサービス収支に表れる取引だけではなく、海外拠点を通じたサービス提供(モード3)や付加価値貿易(モード5)を含めて見ることで、我が国のモノとサービスの越境取引を統合的に理解することができる。これは、財・サービスの貿易投資を巡る構造変化を踏まえると、極めて重要な視点である。
これまでも財輸出における卸小売・販売金融・アフターサービス等の重要性は指摘されていたが、近年のものづくりとサービスの融合やサービス付加価値の増大により、製造業におけるサービスの役割は質的に変化している。例えば、製品設計、デジタル中間投入、生産等の管理システム、デジタル・マーケティング、モノのサブスクリプションサービス(MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)等)といった、付加価値の大部分をサービスが占めるケースが増えている。国際収支統計では、財とサービスの収支が分離されるが、これら財・サービスの貿易投資を全体として把握しなければ、実態を正確に捉えられない可能性がある。直接投資や付加価値貿易を含む多角的視点を導入することで、日本企業がグローバル市場でどのように事業活動を展開し、競争力を発揮し得るのか、より精緻に分析することができる。
本節では、国際収支統計のサービス収支を超えて、対外直接投資及び海外拠点を通じたサービス提供(モード3)や付加価値貿易(モード5)の観点を考慮しながら、我が国のサービス越境取引の実態を、より詳細に検討していくこととする。
(2) 付加価値貿易から見たサービス付加価値
まず、我が国の財・サービス輸出全体に占めるサービス付加価値の規模を、OECDのTiVAによって確認する。2020年の財・サービス輸出の内訳を見ると、財輸出が79.6%、サービス輸出が20.4%を占めている。これを付加価値の源泉で見ると、大きく絵姿が変わってくる。国内製造業由来の付加価値が38.2%であるのに対し、国内サービス業由来の付加価値が46.4%と、サービス付加価値の方が大きくなっている(第II-3-3-28図)。(なお、海外由来の付加価値は、製造業・サービス業を含めて13.3%である。)サービス自体の輸出だけでなく、我が国の伝統的な強みである製造業の財輸出においても、国内のサービス付加価値が中間投入として重要な役割を果たしていることが分かる。
第Ⅱ-3-3-28図 日本の財・サービスの輸出シェアと輸出付加価値シェア(2020年)
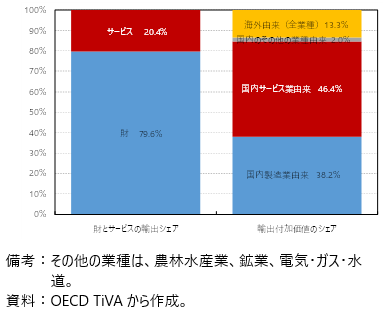
さらに、国内サービス業由来の付加価値を業種別に見ると、卸小売等(39%)、専門サービス(26%)、運輸(13%)、情報通信(8%)、金融保険(7%)が上位を占める(第II-3-3-29図)。Baldwin et al.の言うモダン・サービス318が大半を占めており、デジタル関連サービスを含め、こうしたサービス付加価値の重要性は今後も増していく可能性が高い。
第Ⅱ-3-3-29図 国内サービス業由来の付加価値の業種別内訳(2020年)
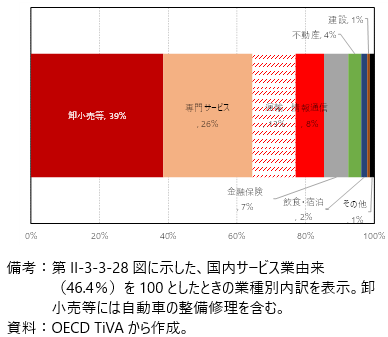
輸出付加価値を更に詳細に見ると、製造業者による輸出(おおむね財輸出から輸出サービス業者の付加価値を除いた部分に該当)は61.7%、サービス業者による輸出は38.2%となっている(第II-3-3-30図)。この数字を付加価値の源泉別に分解すると、製造業者による輸出61.7%のうち、14.4%は国内サービス業によって創出された付加価値である。一方、サービス業者による輸出については、38.2%のうち31.9%と、大部分の付加価値が国内サービス業によって生み出されており、国内製造業の付加価値は2.6%にとどまっている。
第Ⅱ-3-3-30図 日本の財・サービス輸出における付加価値構成
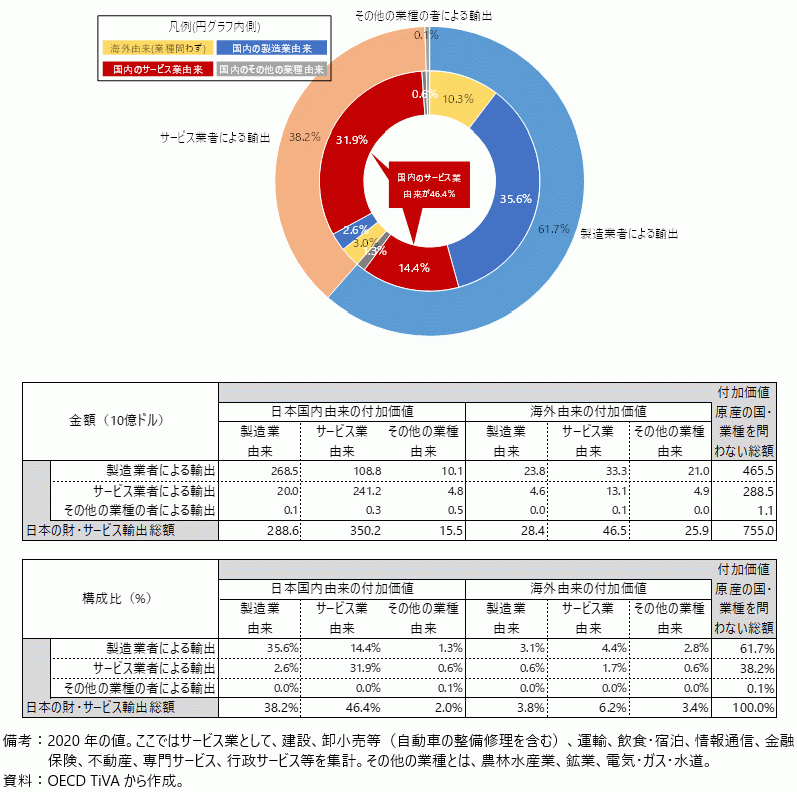
次に、製造業者の輸出に占める国内サービス業の付加価値の内訳を見ると、卸小売等、専門サービス、運輸、情報通信の順に大きくなっている(第II-3-3-31図)。2015年と比較すると、卸小売等が減少しているのに対し、専門サービスや情報通信は付加価値が増加している。デジタル関連サービスの付加価値の増加が影響している可能性もある。
第Ⅱ-3-3-31図 製造業者の輸出に占める国内サービス業による付加価値の業種別内訳
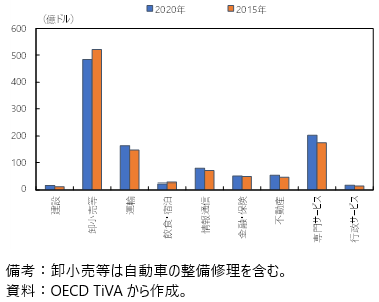
さらに、製造業者の業種別に見ると、国内サービス業に由来する付加価値が大きいのは、総輸出金額の大きい輸送機械や情報通信機械などの機械関連であることが分かる(第II-3-3-32図)。付加価値を生み出しているサービスの構成を見ると、業種間で顕著な差異は見られないが、情報通信機械における専門サービスや情報通信の割合が幾分高めとなっている。これには、ITソフトウェア等の付加価値分が計上されているものと考えられる。
第Ⅱ-3-3-32図 製造業者の業種別輸出に占めるサービス付加価値の構成
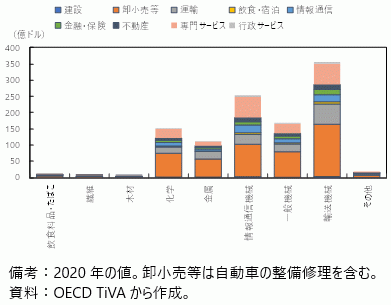
続いて、サービス業者の輸出については、各産業の輸出のうち、大部分は自産業による付加価値で構成されている(第II-3-3-33図)。仔細に見ると、付加価値額はそれほど大きくはないが、専門サービスが卸小売、運輸、情報通信、金融・保険など幅広いサービスに寄与している。これら業種のサービス輸出が伸長するにつれて、専門サービスに対する需要も高まっていく可能性がある。
第Ⅱ-3-3-33図 サービス業者の業種別輸出に占める国内サービス業による付加価値の内訳
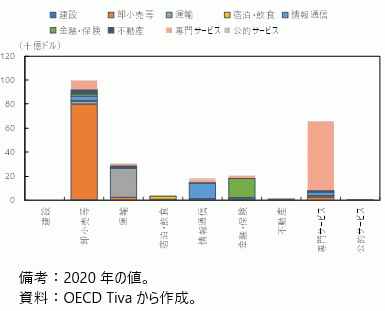
318 Baldwin et al. (2024)
(3) 海外拠点を通じたサービス輸出(モード3)
① モード3輸出の整理
モード3の輸出金額の推計は発展途上であり、我が国では、現状、モード別の海外へのサービス提供の統計が包括的な形で整備されていない。そのため、我が国サービス業の海外拠点を通じたサービス輸出については、いくつかの統計を用いながら、幅をもって見ていく必要がある。
まずは、WTOが提供しているTISMOS(Trade in services by mode of supply dataset)を用いて、我が国のモード3を含むサービス貿易(ただし、モード5は含まない)の特徴を明らかにしたい。モード3を考慮した場合のサービス収支を見ると、モード3が大幅な黒字となっているため、我が国のサービス収支は全体として黒字となっている(第II-3-3-34図)。時系列で見ると、モード1が足下で赤字幅を拡大しているが、それを上回るペースでモード3の収支の黒字幅が拡大しており、世界金融危機時の振れを除けば、傾向的に全体の収支の黒字幅が拡大してきている。
第Ⅱ-3-3-34図 モード3を含めた日本のサービス貿易収支
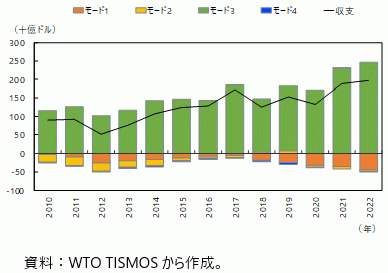
この背景には、モード3の輸出が増加傾向にあることが指摘できる。第II-3-3-35図を見ると、モード3の輸出は、他のモードの輸出と比べて、大きく輸出額を伸長させてきたことが分かる。
第Ⅱ-3-3-35図 我が国のモード別輸出の推移
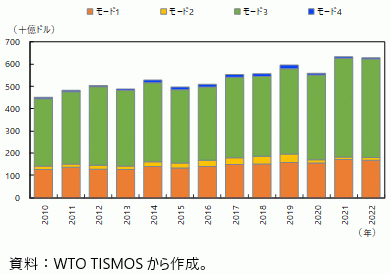
第II-3-3-36図で、輸入も含めてモードごとの規模を確認すると、まず輸出側では、モード3の輸出はモード1の輸出の約3倍の大きさになっている。輸入側では、モード3とモード1がほぼ同程度の金額となっており、海外企業が日本国内の拠点を通じて提供しているサービスも、無視できない大きさとなっている。
第Ⅱ-3-3-36図 我が国のモード別の輸出入
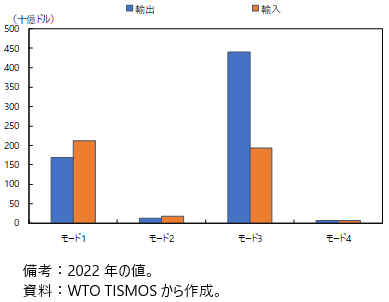
こうしたモード3の輸出額の大きさは、我が国のサービス貿易の特徴であるといえる。第II-3-3-37図では、世界と日本のサービス輸出のモード別構成比を示している。これによると、世界のサービス輸出の56%がモード3であるのに対し、我が国では70%にのぼっている。つまり、日本企業は、サービスを海外に越境提供するという形態(モード1、2、4)よりも、海外拠点を通じてサービス提供を行う形態を多くとっていることが示唆される。
第Ⅱ-3-3-37図 世界と日本のサービス輸出のモード別構成比
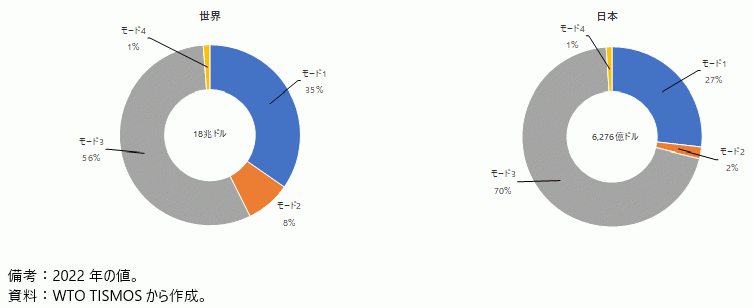
次に、サービス別・モード別に輸出の内訳を世界と比較すると319、まず、「卸売・小売業及び貿易関連サービス」における海外へのモード3のサービス提供が顕著に進んでいることが分かる(第II-3-3-38図)。また、「専門業務サービス」や「通信・コンピュータ・情報及び視聴覚サービス」も、輸出の全体額とその中でモード3の占める割合が大きい。
第Ⅱ-3-3-38図 世界と日本の輸出サービス種類別のモード構成
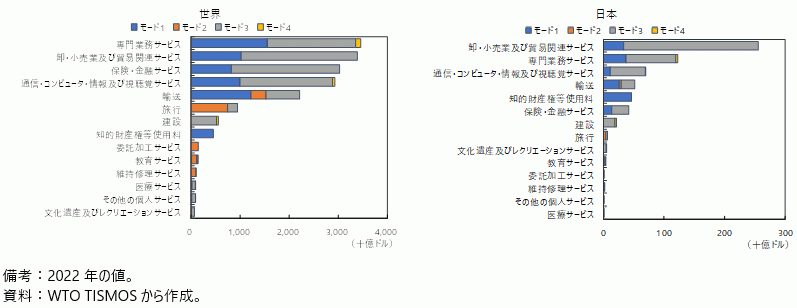
サービス別にモード3輸出の推移を見ると、「卸・小売業及び貿易関連サービス」を中心に増加を続けている(第II-3-3-39図)。また、全体の中での割合は大きくないものの、「通信・コンピュータ・情報及び視聴覚サービス」や「保険・金融サービス」も、モード3輸出を緩やかに伸ばしている。
第Ⅱ-3-3-39図 我が国のモード3輸出の業種別推移
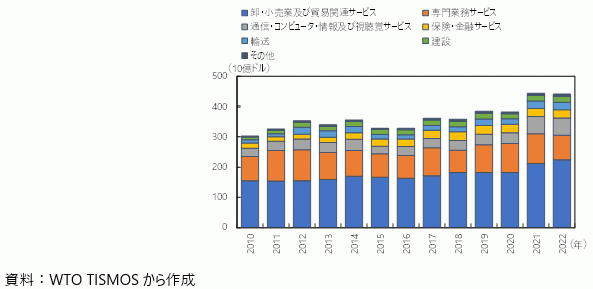
319 コロナ禍の影響が残る2022年時点のデータを用いていることから、「旅行」など人の往来が必要なモード2が低めに出ている可能性がある。
② サービス業への対外直接投資
モード3について、TISMOSは海外拠点を通じたサービス輸出を推計データで示しているが、あわせて海外でサービス提供を行う現地法人等に対する対外直接投資のデータを見ることで、より実態に迫ることができるだろう。実際、国際収支統計でも、海外の非製造業への海外直接投資残高が趨勢的に増加していることが確認できる(第II-3-3-40図)。
第Ⅱ-3-3-40図 非製造業の対外直接投資残高
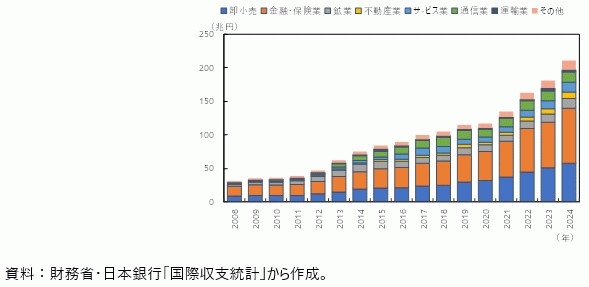
TISMOSからは、我が国のどのような業種の企業が海外でモード3のサービス提供を行っているかや、モード3輸出の大宗を占める卸小売の中身がどのようなサービスかを知ることはできない。桜・近藤は、サービス業の海外進出に関しては、親会社の業種と子会社業種の差異に注意を払う必要があることを指摘している320(第II-3-3-41表)。国際収支統計における業種別対外直接投資は、現地法人の業種で分類を行っている。例えば、我が国の自動車会社が海外に現地販売拠点を設立する場合は、対外直接投資統計上は現地側の業種で卸小売業と分類されるが、親会社は製造業である。
第Ⅱ-3-3-41表 非製造業の進出形態
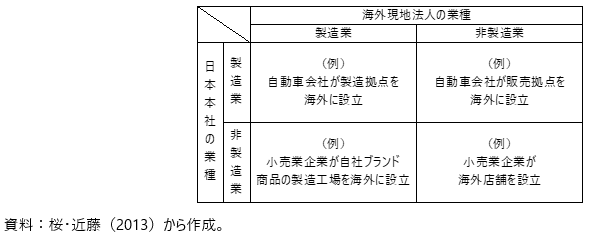
そこで、海外事業活動基本調査を用いて、上記の整理に基づいた日本本社・海外現地法人の業種組合せ別の売上高を計算すると、我が国の海外現地法人売上の55%は、現地法人が非製造業となっている。そのうち、日本本社が製造業のケースが29%、日本本社が非製造業のケースが26%となっている(第II-3-3-42図)。現地法人が製造業の場合、日本本社もほとんどが製造業であることと対照的である。
第Ⅱ-3-3-42図 日系企業の海外現地法人売上の日本本社・海外現地法人業種別構成
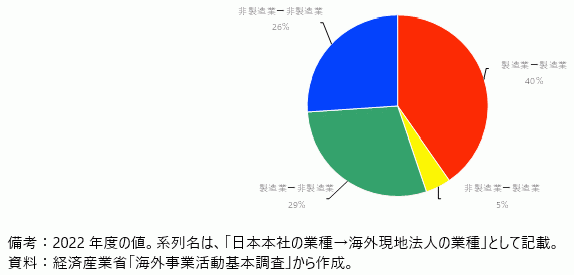
非製造業現地法人の売上高内訳を示したのが、第II-3-3-43図である。現地法人の業種で見たときに、最も売上高が大きいのは卸売業となっている。この点は、TISMOSの推計データで、モード3輸出の構成比が最も大きい業種が「卸・小売業及び貿易関連サービス」であることとも整合的である321。この卸売業の売上高を日本本社の業種別で見ると、非製造業よりも製造業の方が大きい。これは、我が国製造業が、海外市場での販路拡大等のために、海外現地に卸小売・販売金融・アフターサービス等の子会社を設立しているケースが多いことを反映していると考えられる。
第Ⅱ-3-3-43図 非製造業の現地法人売上高
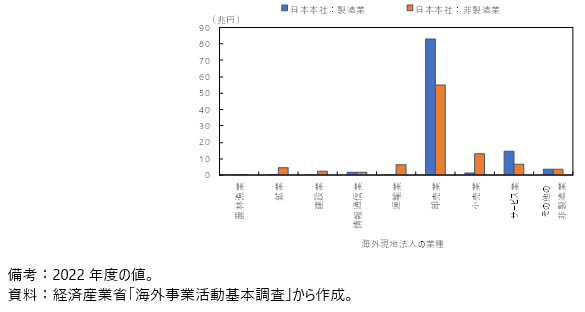
こうした、日本本社が製造業で現地法人がサービス業というケースは、モノの輸出を含む海外展開をバリューチェーンの中で補完するサービス業への対外直接投資の好例といえる。とりわけ現地販売に必要なサービス拠点は、海外消費地に立地することに価値があり、日本国内の事業活動を損なうことなく、むしろ輸出を含むモノの販路拡大や情報収集等に貢献するという意味で、輸出と対外直接投資の好循環を生む事例であると考えられる。
320 桜・近藤(2013)
321 TISMOSでモード3の推計には、各国のForeign Affiliates Statistics等が利用されていると見られる。