第4節 製造業とコンテンツ産業のグローバル戦略
近年の国際環境の変化は、国境を超えるビジネス活動にとっての不確実性を高め、その行動を変化させている。米中対立や経済的依存関係の武器化を始めとするサプライチェーンリスクの変化だけでなく、グローバルサウス諸国の経済成長や、中国の産業発展と景気低迷、事業環境悪化等の経済的要因も、国境を超えるビジネスの海外市場における期待成長率を変化させている。
その上で、前節まで我が国の財・サービスの貿易投資の変化を見てきたが、それでは、上記の環境下で我が国企業はどのようなグローバルな立地・投資戦略を展開しようとしているのか。また、どのようなグローバルな企業成長の機会や課題の認識を持っているのか。
本節では、このような問題意識から実施した、海外に拠点を持つ製造業に対するアンケート調査の結果を分析する。また、近年、海外展開を拡大させているコンテンツ企業に対するヒアリングを踏まえ、コンテンツ産業の国境を超えるビジネスの現状や課題について整理する。加えて、我が国経済成長と産業競争力強化の観点から、対外直接投資の意義について検討する。
1. 我が国製造業のグローバルな立地・投資戦略に係るアンケート調査
(1) アンケート調査の概要
今般、海外に拠点を持つ我が国製造業のグローバルな立地・投資戦略を把握する目的で、アンケート調査を実施した。調査対象企業や実施期間は以下の表にまとめた(第II-3-4-1表)。調査内容は主に、①国内・海外の生産拠点及び研究開発拠点に関する現状と投資計画、②グローバルな企業成長の機会と課題、経営戦略における優先事項、③日本国内における投資の利点と課題等である。海外に拠点を持つ製造業3,540社にアンケートを送付し、およそ10%の359社から回答を得た。アンケート実施期間は3週間であった。
第Ⅱ-3-4-1表 アンケートの概要
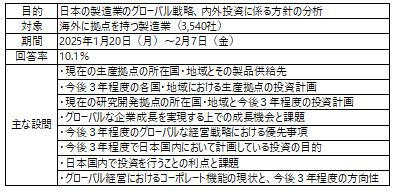
アンケート回答企業の日本標準産業分類に基づく業種分類や日本本社の企業規模については、「17.はん用機械器具製造業」から「23.輸送用機械器具製造業」までの機械に関係する企業がおよそ半数を占めた(第II-3-4-2表)。企業規模としては、大企業が88社(25%)、中堅企業が103社(29%)、中小企業が168社(47%)となっている(第II-3-4-3表)322。
第Ⅱ-3-4-2表 アンケート回答企業の業種分類
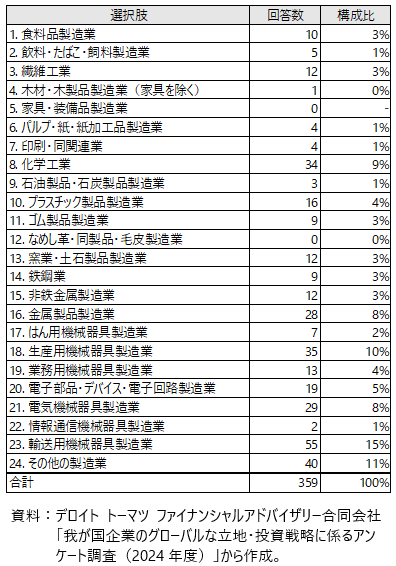
第Ⅱ-3-4-3表 アンケート回答企業の企業規模
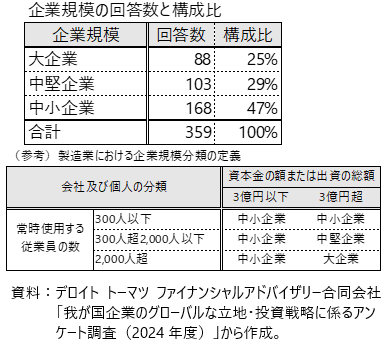
アンケート回答企業の生産拠点・研究開発拠点が、調査時点において存在する国・地域をそれぞれ確認する。生産拠点については、日本(325社)を除くと、中国(155社)、タイ(82社)、米国(69社)、インドネシア(65社)の順番となった。研究開発拠点については、同様に日本(277社)を除くと、中国(40社)、米国(34社)、EU(26社)の順番となった。(第II-3-4-4表)。
第Ⅱ-3-4-4表 アンケート回答企業の生産拠点が存在する国・地域、研究開発拠点が存在する国・地域(調査時点)
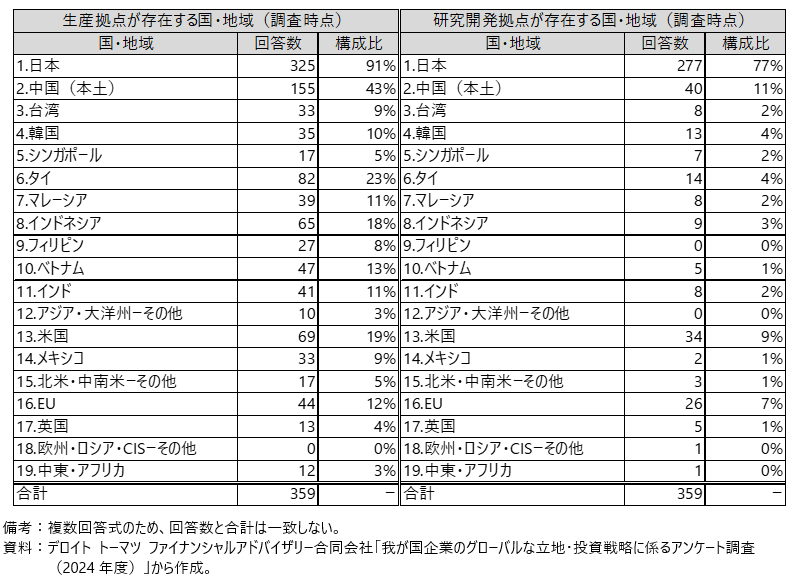
322 本アンケート結果における割合の記載は、小数点第1位を四捨五入している。
(2) アンケート結果の分析
① 生産拠点の立地戦略
過去の通商白書でも指摘してきたとおり、我が国の製造業は、特に1980年代以降、国際貿易投資環境、プラザ合意後の為替レートの変化、国際 的な労働コストの相違等に対応して、積極的な直接投資を行い、北米やアジアを始めとして海外進出を進めてきた。製造業の海外現地法人の進出時期を見ると、中国は2000年代前半にピークを迎えて減少傾向にあり、タイ、ベトナム、インドネシア、インド等は2010年代前半に進出が増加した323。
今回のアンケート結果で、生産拠点が現時点で存在する国・地域を見ると、こうした経緯を反映して、上位は順に、ASEAN6、中国(本土)、米国、欧州となっている。これは、海外事業活動基本調査における製造業の現地法人企業の国・地域別分布の順位とおおむね整合的である(第II-3-4-5表)。
第Ⅱ-3-4-5表 海外事業活動基本調査と本アンケートの国・地域別拠点分布
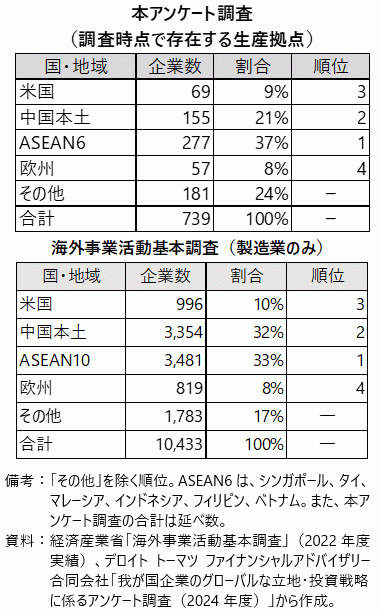
次に、生産拠点に対する投資計画を見る。第II-3-4-6図は、今後3年程度の生産拠点に対する投資計画に関する回答結果について、国・地域別に整理したものである。
第Ⅱ-3-4-6図 今後3年間の生産拠点への投資計画の有無とその位置付け
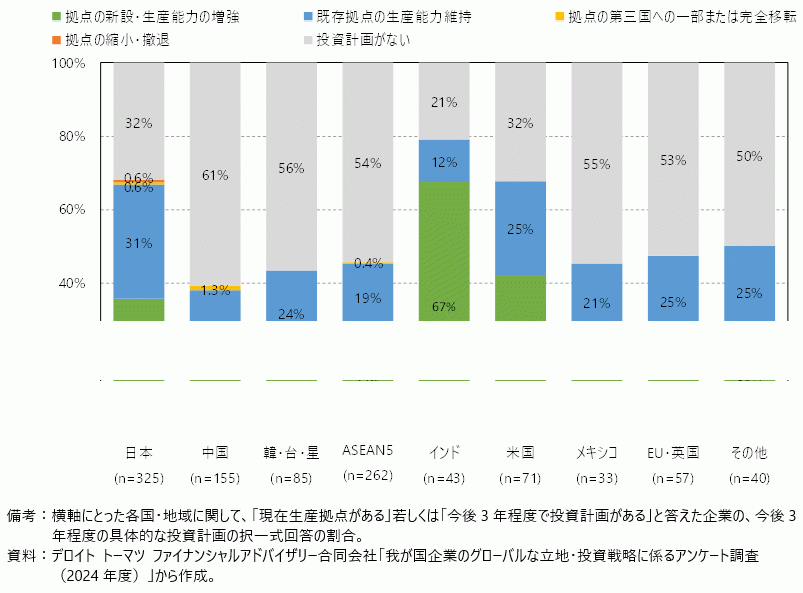
投資計画があると答えた企業の割合324は、インド(79%)、日本(68%)、米国(68%)の順で高かった。また、生産拠点への投資計画の内容として、「拠点の増強」と回答した割合は、インド(67%)が非常に多く、米国(42%)と日本(36%)も高い割合となっている。
日本国内での投資計画を持つ企業が、他国・地域と比較しても高水準となっていることが注目される。日本政策投資銀行による設備投資計画調査の結果でも同様の傾向が看取されており、国内投資の機運は高まっていることがうかがえる。
米国については、本調査後の第二次トランプ政権の関税政策をきっかけに通商政策の不確実性が急激に高まったことを考慮する必要はあるが、近年は米国が世界経済を牽引してきた中で、製造業にとって重要な投資先と認識されていることがうかがえる。
なお、アジア地域では、インドに次いで、フィリピン(59%)、ベトナム(53%)への投資計画を持つ企業の割合が高く、既に現地展開が進んできた国よりも、足下で成長が見込まれる国への投資を重視している傾向がうかがえる。
他方、中国、メキシコ、タイ、インドネシア、マレーシア等では、投資計画がないと答えた企業の割合が過半となった。特に中国は直近、経済停滞や競争激化、事業環境の悪化等を受けて、中国への新規投資を控える動きが報じられている。今回の調査でも、中国での投資計画を持つ企業は39%、内数としての「拠点の新設・生産能力の増強」を計画している企業は15%のみにとどまった。
JETROによる日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査325と本調査の結果を比較すると、中国、ASEANへの投資についてはおおむね整合的なものの、米国投資へのポジティブさとメキシコ投資へのネガティブさがより強く表れている。これは、本調査の実施時期(2025年1月20日~同年2月7日)が第二次トランプ政権によるメキシコ・カナダへの25%関税賦課について報道されたタイミングと重なったことも影響している可能性がある。
なお、投資後の製品の供給先については、総じて現地市場の割合が高く、消費地立地を一層進める傾向が看取できる。他方、ベトナム(68%)、中国(56%)、フィリピン(56%)、タイ(54%)、インドネシア(50%)、マレーシア(50%)は、日本への逆輸入を行うと回答した企業も半数以上となっている(第II-3-4-7図)。JETROによる海外進出日系企業実態調査等とも合わせ見ると、日本の人手不足等を理由に生産拠点をASEAN等に移転し、一部逆輸入を行う流れが存在する可能性も示唆される326。
第Ⅱ-3-4-7図 生産拠点への投資後の製品の供給先
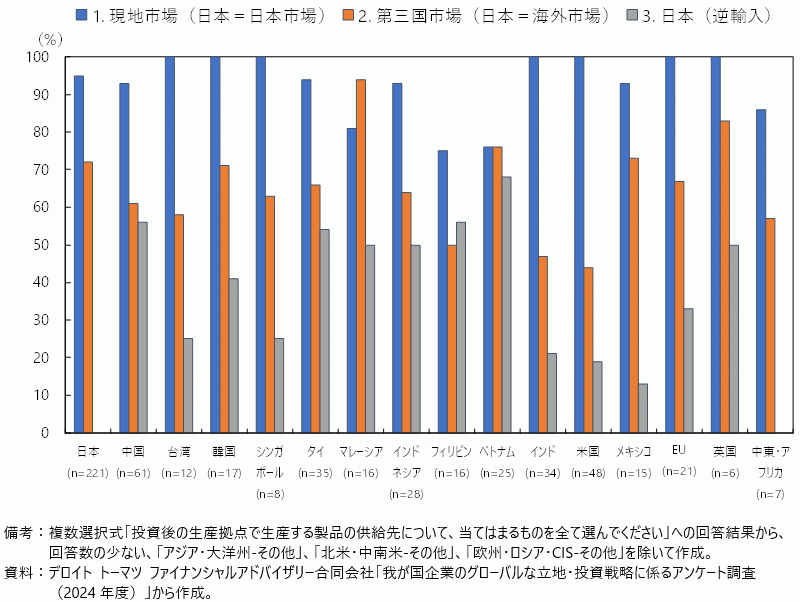
最後に、日本国内の生産拠点に対する投資計画を企業規模別に見ると、大企業だけでなく中堅企業や中小企業も多くなっている。特に中堅企業は、「拠点の新設・生産能力の増強」と回答した企業が45%と、全企業の36%より高く、生産拠点を維持するための投資よりも、生産能力を拡大するための投資の割合が高かった(第II-3-4-8図)。また、投資後の生産拠点で生産する製品の供給先について、海外市場と答えた割合も74%と高水準である(なお、全企業の回答割合は72%)。2025年2月27日に開催された新しい資本主義実現会議(第31回)でも、中堅企業は設備や人への投資に積極的であり、輸出においても大きな役割を果たしているとされた327。今後、輸出の拡大を目指す上での中堅企業の重要性が示唆されている。
第Ⅱ-3-4-8図 中堅企業の今後3年間の生産拠点への投資計画の有無とその位置付け
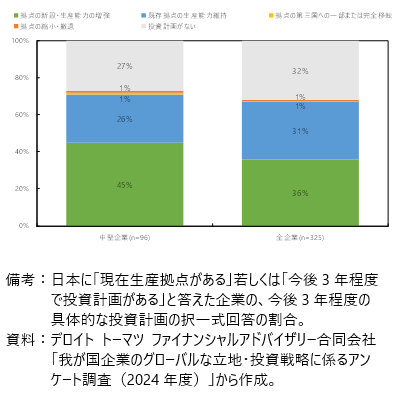
323 経済産業省「資料4 製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性」(第14回産業構造審議会製造産業分科会資料)、2023年5月、https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/pdf/014_04_00.pdf![]() (2025年6月5日閲覧)。
(2025年6月5日閲覧)。
324 具体的には、第II-3-4-6図に示した5つの選択肢(①拠点の新設・生産能力の増強、②既存拠点の生産能力維持、③拠点の第三国への一部または完全移転、④拠点の縮小・撤退、⑤投資計画がない)のうち、⑤を除く①~④の回答の合計。③と④はネガティブな投資計画であるが、図を見ると分かるようにそれらの回答割合は非常に小さく、実質的には①と②の回答の合計にほぼ等しい。
325 JETRO(2024a)
326 JETRO(2024b)
327 内閣官房「資料1 基礎資料」(内閣官房新しい資本主義実現会議(第31回))、2025年2月27日、
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai31/shiryou1.pdf![]() (2025年6月9日閲覧)。
(2025年6月9日閲覧)。
② 研究開発拠点の立地戦略
研究開発拠点の現状と今後3年程度の投資計画について見ていく。研究開発拠点は、日本に持つ企業が277社と圧倒的に多く、基盤技術の開発や、グローバル市場に投入する新製品開発を担っている割合が高い。海外では、先進国に93社、途上国に87社328が立地する。その機能は、当該国・地域向けのローカライズが先進国で60%、途上国で83%と高くなっているが、先進国では基盤技術の開発(44%)やグローバル市場に投入する新製品開発(51%)も相応に高くなっている(第II-3-4-9図)。
第Ⅱ-3-4-9図 現在の研究開発拠点で実施している研究開発の性質
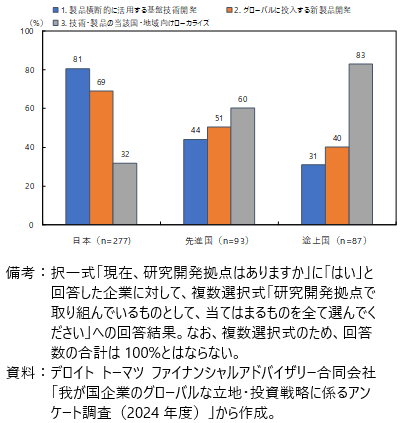
今後3年程度の投資計画を見ると、日本では149社が研究開発拠点への投資計画を持っている。そのうち53%は「拠点の新設・能力の増強」であり、投資後に取り組む研究開発は引き続き基盤技術開発や新製品開発が中心となっている。他方、回答母数が少ないことに留意が必要なものの、先進国で「拠点の新設・能力の増強」の後に基盤技術開発(57%)や新製品開発(71%)を行うとする割合が、現状よりもかなり増えていることは注目に値する(第II-3-4-10図)。
第Ⅱ-3-4-10図 拠点の新設・増強後に取り組む研究開発の性質
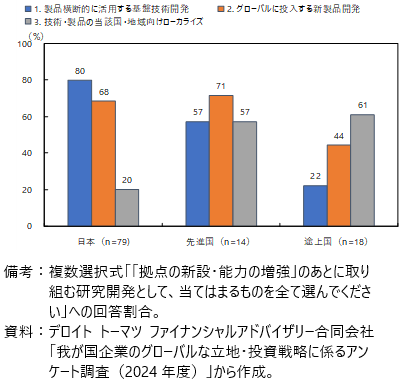
③ グローバルな企業成長の機会と課題、経営戦略における優先事項
ここからは、我が国製造業が持っているグローバル戦略に関連する回答を見ていく。グローバルな企業成長の機会を聞いた質問に対しては、企業規模を問わず、先進国又は新興国・途上国の市場拡大と回答している企業が非常に多い(第II-3-4-11図)。
第Ⅱ-3-4-11図 グローバルな企業成長の機会(企業規模別)
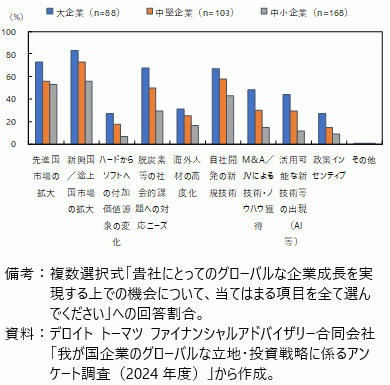
大企業の大きな特徴として、「脱炭素等の社会的課題への対応ニーズ」を成長機会と捉えている割合が68%と、中堅・中小企業と比較して顕著に高くなっている。大企業を中心に、内外の社会的課題にソリューションを提供することで自社の成長につなげるという成長戦略を描いていることがうかがえる。「新興国/途上国市場の拡大」の回答の多さを合わせ考えると、グローバルサウス諸国における社会経済課題に対応する共創の取組を成長機会として重視していることが強く示唆される。
「自社開発の新規技術」を成長機会と捉える企業は規模にかかわらず相対的に多いが、「M&A/JVによる技術・ノウハウ獲得」や、「活用可能な新技術等の出現(AI等)」は、大企業の方が機会と考える割合が高い(第II-3-4-12図)。
第Ⅱ-3-4-12図 企業規模別で差の大きくなった項目(グローバルな企業成長の機会)
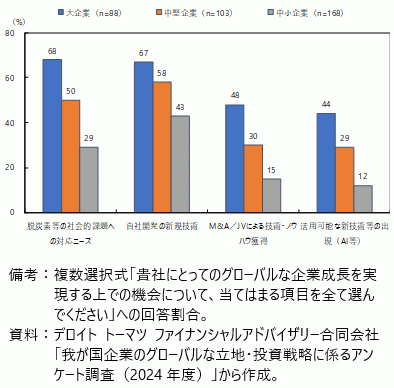
次に、グローバルな企業成長を実現する上での課題について聞いた。回答としては、「自社の研究開発力」、「新規事業の企画を担う人材・ノウハウ」、「新たな販売先/市場を開拓する人材・ノウハウ」という、社内の創造的活動を担う高度人材や技術の必要性を挙げる回答が非常に多くなっている。企業内外での人材育成や研究開発力の向上が、課題として強く認識されているといえる。
加えて、企業規模にかかわらず、「生産現場の人材確保」を挙げる企業が多くなっており、国内の人手不足が課題として認識されていることがうかがえる(第II-3-4-13図)。
第Ⅱ-3-4-13図 グローバルな企業成長の課題(企業規模別)
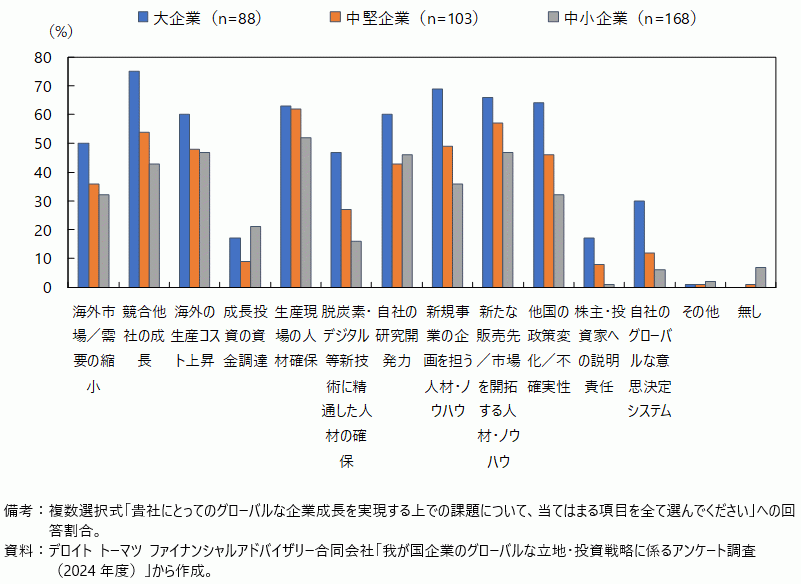
また、「競合他社の成長」、「脱炭素・デジタル等新技術に精通した人材の確保」、「新規事業の企画を担う人材・ノウハウ」、「他国の政策変化/不確実性」、「自社のグローバルな意思決定システム」を課題とする回答は、大企業で顕著に多かった。海外で他国企業との激化する競争に直面している大企業の方が、競合他社の脅威を実感する機会が多いと考えられる。さらに、多くの大企業は「脱炭素等の社会的課題への対応ニーズ」を成長機会と捉えているものの、そうした「脱炭素・デジタル等新技術に精通した人材の確保」や「新規事業の企画を担う人材・ノウハウ」が十分でないと認識していることがうかがえる。加えて、多国間でサプライチェーンを構築し、活動している大企業の方が、他国の政策変化や不確実性から受ける影響を強く認識し、また、グローバルな意思決定システムの改善の必要性を感じる傾向にあると推察される(第II-3-4-14図)。
第Ⅱ-3-4-14図 企業規模別で差の大きくなった項目(グローバルな企業成長の課題)
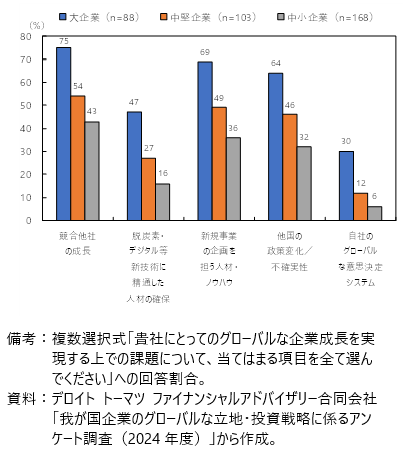
続いて、グローバルな経営戦略における優先事項について聞いた。ここでは、大企業で「脱炭素・デジタル等新技術を活用したイノベーション」と「グローバルな組織経営改革」を挙げる回答が多いことが注目される。
「研究開発力の強化」は企業規模にかかわらない優先事項だが、関連性があると思われる選択肢として、大企業は「M&A等技術経営資源獲得」、中堅・中小企業は「高度人材の確保」を挙げる回答がより多くなっていることは特徴的である。
大企業及び中堅企業では、中小企業に比べて、国内よりも海外での生産能力強化と回答する比率が多かった。「既存製品の販売強化」は、企業規模にかかわらず重視されている(第II-3-4-15図)。
第Ⅱ-3-4-15図 グローバルな経営戦略における優先事項(企業規模別)
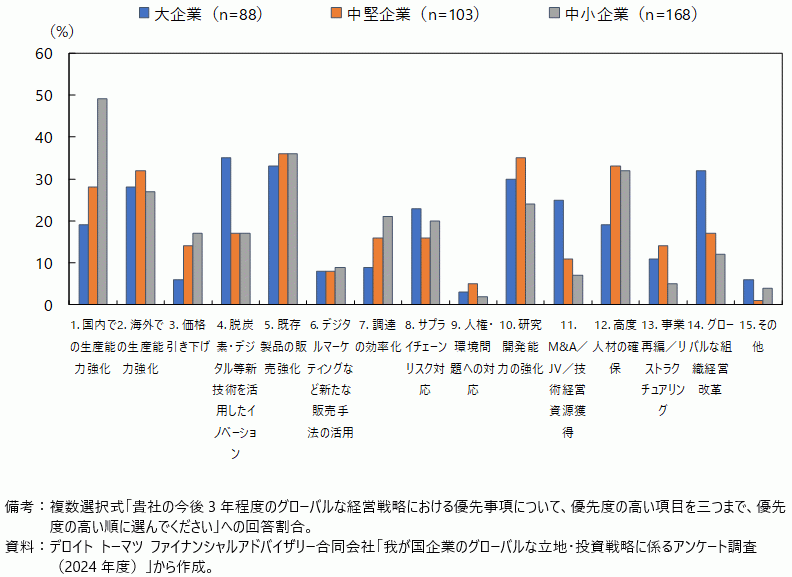
328 先進国と途上国の分類はIMF WEOの分類を参考にした。具体的には、先進国・地域は米国、ユーロ圏、英国、韓国、台湾、シンガポール等。途上国・地域は中国、インド、インドネシア、タイ、ベトナム、メキシコ、アフリカ、中東等。なお、アンケートへの回答のうち、「アジア・太平洋―その他」、「北米・中南米―その他」、「欧州・ロシア・CIS―その他」は対象国を特定できないため除外した。
④ コーポレート機能
海外拠点を持つ製造企業のコーポレート機能についても聞いた。これは、日本国内の本社にどのような機能が置かれるかという立地戦略の観点と、企業が海外展開の中で組織構造や経営管理をどのように高度化しようとしているかというCX(コーポレート・トランスフォーメーション)の観点の両面から重要な設問である329。多くの大企業が、上述の経営戦略における優先事項として「グローバルな組織経営改革」を挙げたことは、その重要性を示している。
今回のアンケート調査では、経営企画機能について、現状は、日本本社に主要な権限を集約しているとの回答が89%に上る一方、大企業では今後3年程度の方向性として、現状維持が約半数にとどまり、海外との権限関係の見直しや組織・内部手続見直しを実施する企業が合わせて31%に上っている(第II-3-4-16図)。大企業を中心に、グローバル展開の中で、経営企画機能に関するCXを進めようとしている企業が相当数存在することを示唆している。
第Ⅱ-3-4-16図 経営企画部門の今後3年程度の方向性
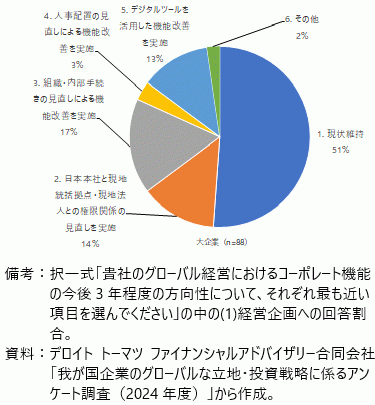
その他、知的財産管理やマザー工場機能、人事管理、財務・経理・税務会計は7割以上の企業が本社に権限集約している一方、広告販売戦略やデジタル化・ITインフラ提供は約3割の企業が現地法人に主要な権限を委譲している(第II-3-4-17図)。
第Ⅱ-3-4-17図 コーポレート機能の現状
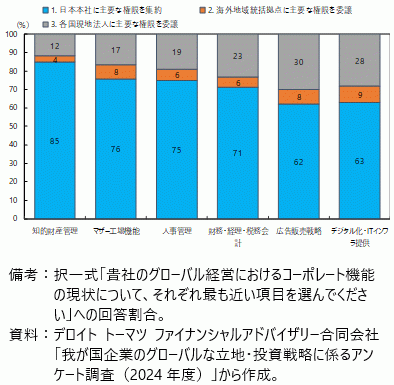
329 経済産業省(2024)
⑤ 日本国内での投資の目的、利点と課題
上述のようなグローバルな立地・投資戦略の下で、日本企業が国内投資をどのように位置付けているかを見ていく。既に見たとおり、日本国内で生産拠点や研究開発拠点への投資を計画している企業は相対的に多いといえる。日本での投資の目的については、「生産の自動化・省人化」や「老朽化した生産設備の更新」の回答が比較的多くなっている。同時に、生産拡大のための投資も、国内向けと輸出向けを含む回答を合わせると相当数存在する(第II-3-4-18図)。
第Ⅱ-3-4-18図 日本国内での投資の目的
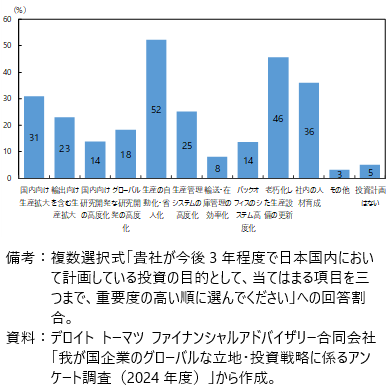
同時に、「社内の人材育成」は、企業規模にかかわらず目的とする割合が高い(大企業36%、中堅企業32%、中小企業38%)。
大企業では、「輸出向けを含む生産拡大」が32%と、「国内向け生産拡大」よりも多くなっている。中堅企業(23%)や中小企業(18%)でも、「輸出向けを含む生産拡大」を目的とする企業が一定数存在する。「グローバルな研究開発の高度化」も、大企業で26%、中堅企業で21%が国内投資の目的に挙げている(第II-3-4-19図)。
第Ⅱ-3-4-19図 日本国内での投資の目的(企業規模別)
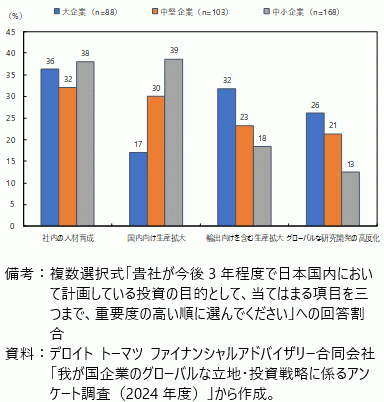
全体の傾向としては、日本政策投資銀行による設備投資計画調査(2024年)とも整合的だが、同調査(全体設備投資額に対する各投資動機の金額ウェイトを算出。)における「合理化・省力化」よりも、本調査における「生産の自動化・省人化」の割合が多くなっている330。
次に、日本国内で投資を行う利点と課題について聞いた。利点としては、「技術ノウハウの集積」(55%)、「高度人材確保」(33%)、「原材料/調達先企業」(19%)が高くなっており、国内に存在する技術・人材・産業の集積は、引き続き貴重な価値と認識されている。また、「納入先企業/市場」(38%)、「需要/成長性」(24%)を利点とする企業も多く、国内の需要規模はなお重要な要素と考えられる(第II-3-4-20図)。
第Ⅱ-3-4-20図 日本国内で投資を行うことの利点
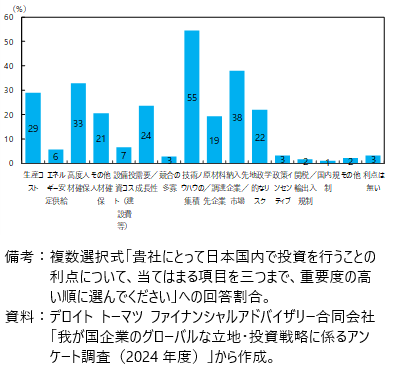
他方、日本国内への投資の課題として、「設備投資コスト(建設費等)」(42%)を挙げる企業が非常に多く、昨今の建設費・資材・生産設備の高騰や産業用地不足等が、投資に当たっての大きな課題と認識されている可能性がある。日本政策投資銀行による設備投資計画調査では、近年、設備投資の計画と実施の乖離率が拡大していると指摘されているが、その要因の一つになっている可能性もある。新しい資本主義実現会議でも、産業用地の供給が需要に追い付いていないという課題への対応が議論されている331。
「生産コスト」については、利点に挙げる企業(29%)が中堅・中小企業を中心に一定数存在する一方で、全体としては課題に挙げる企業(48%)の方が非常に多くなっている。
「高度人材の確保」は、利点と課題に同等に挙げられている一方、「その他人材確保」は課題とする企業が多く(32%)、ここでも国内の人手不足の問題が大きいことが示唆されている。大企業を中心に「地政学的リスク」を利点に挙げる企業(22%)が多く、日本の地政学的な環境は、グローバル展開するビジネスから前向きに捉えられている(第II-3-4-21図)。
第Ⅱ-3-4-21図 日本国内で投資を行うことの課題
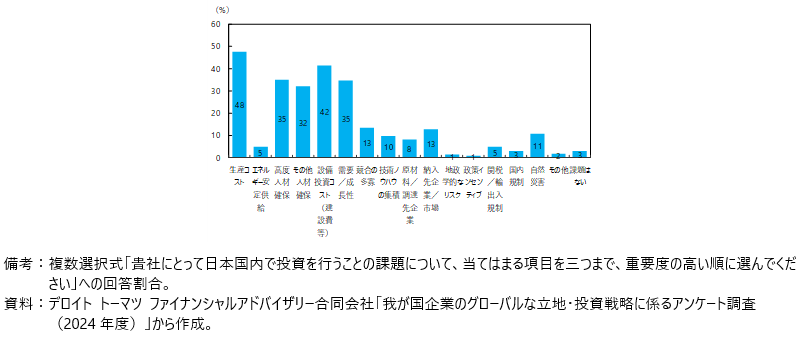
第II-3-4-22図では、日本国内で投資を行う利点と課題について、利点をプラス、課題をマイナスとしてグラフに表している。グラフから、「設備投資コスト(建設費等)」、「生産コスト」、「その他人材確保」、「需要/成長性」、「競合の多寡」については課題と認識している回答が多く、「技術ノウハウの蓄積」、「納入先企業/市場」、「地政学的なリスク」、「原材料/調達先企業」という回答は利点と捉える回答が多かったことが分かる。
第Ⅱ-3-4-22図 日本国内における投資の利点と課題
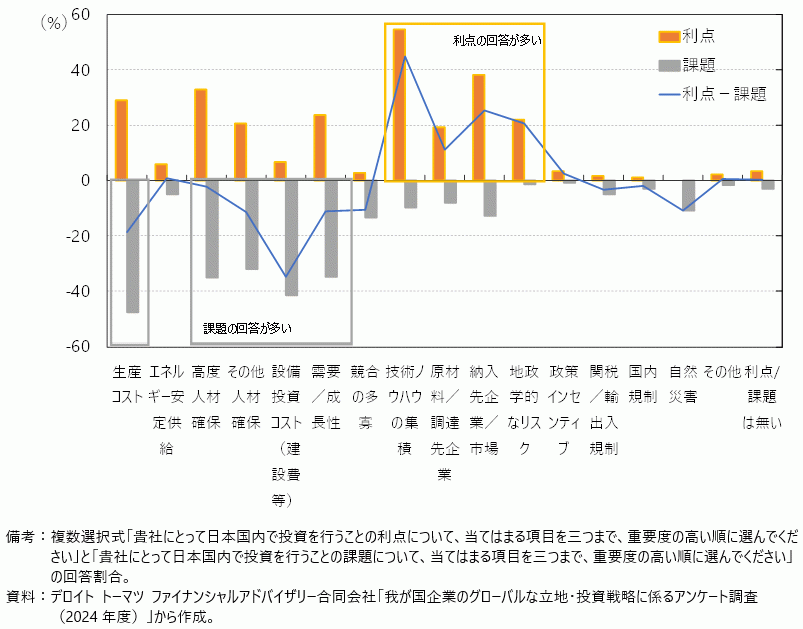
330 日本政策投資銀行(2024)
331 内閣官房「資料1 基礎資料」(内閣官房新しい資本主義実現会議(第31回))、2025年2月27日、
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai31/shiryou1.pdf![]() (2025年6月9日閲覧)。
(2025年6月9日閲覧)。
(3) アンケート調査の示唆
1980年代から北米や東南アジアへの展開を進めた我が国製造業は、特に世界金融危機後に対外直接投資を大きく増加させ、消費地立地の傾向を強めてきた。その後、中国や東南アジアへの現地法人の新規設立は2010年代までに一巡し、製造業による現地販売拠点等の非製造業への投資や、グリーンフィールドではなくM&Aによる投資など、業種・業態や個別企業によって、グローバルな立地・投資戦略が多様化していることがうかがえる。その背景には、米中対立や経済的依存関係の武器化等のサプライチェーンリスクの変化、デジタル化・グリーン移行などの国際潮流、グローバルサウス諸国の成長に伴う生産や市場を巡る環境変化、中国の産業発展による競合関係の変化や中国の事業環境の悪化等の様々な国際環境の変化があるだろう。そうした環境下で、我が国製造業のグローバル戦略も岐路に立っていると考えられる。
今回のアンケート調査でも、そのような我が国製造業の状況の一端が示唆された。これまで生産拠点に対する積極的な投資が行われてきた中国では、新規投資への慎重さが際立っている。我が国が中長期的に存在感を発揮してきたASEAN諸国にも、一部に日本の人手不足への対応も示唆される逆輸入を含む投資があるものの、全体として積極的な投資の動きが見られないことは懸念材料である。他方、これまで生産拠点の少なかったインドだけでなく、世界経済の成長を牽引してきた米国に対する投資には積極姿勢が見られた。
そうした中、日本国内への投資を重視する方針が強く示唆されたことは興味深い。設備投資コスト(建設費等)や人手不足等の課題は意識される一方で、技術ノウハウの蓄積や高度人材の存在といった既存の産業集積のメリットはなお残っていることが示唆される。中堅企業は国内で積極的な投資計画を持っていることも注目された。今後は、自動化・省人化や設備更新だけではない、研究開発・人材育成・生産拡大等の企業成長のための積極的な投資が広がるかどうかが重要になる。
この観点で、特に大企業を中心に、新興国・途上国の市場拡大と脱炭素等の社会的課題への対応ニーズを成長機会と捉えていることは、グローバルサウス諸国との共創を通じた成長の可能性を感じさせる。グローバルな経営企画部門の機能改善に問題意識を持つ大企業が多いことも、今後のグローバル戦略の展開を考える上で重要な結果であった。研究開発能力の強化、技術経営資源の獲得、高度人材の確保といった高付加価値化を進めるための課題が経営戦略の優先事項に挙げられており、国際環境の変化の中で、我が国製造業がグローバルな競争力を着実に高めるための鍵になるだろう。
2. コンテンツ産業の海外展開に係る現状と課題
(1) コンテンツ産業の海外展開
モノとサービスの融合や、サービス付加価値の重要性の高まりという潮流の中で、コンテンツ産業は、とりわけコロナ禍後に国内外で新たな市場が広がっている分野として注目される。我が国は昨年6月、知的財産戦略本部において「新たなクールジャパン戦略」を策定した。その中で、我が国は2010年頃からクールジャパンに着目した政策を行ってきたが、「世界的に動画配信サービスが普及していく中で、日本のアニメやマンガが、海外において一部の層だけでなく、一般的な多くの若者を惹きつけている。アニメそのものに限らず、これを実写化したドラマやテーマソングも人気を博している。家庭用ゲームも、元々競争力があったが、デジタル配信に適応して海外展開がさらに伸びている。ゲームのキャラクターを活用した映画や長らく難しいとされてきた字幕付の実写映画も大ヒットしている。」として、コンテンツ産業を巡る新たな展開を指摘した。
日本のコンテンツ産業の国内市場規模は、2023年で13.3兆円(前年比1.0%増)に上る。海外展開はアニメ、ゲーム(家庭用)を中心に年々拡大傾向にあり、直近の海外における売上規模では2022年の4.7 兆円から2023年の5.8兆円(前年比23.2%増)332へと大きく増加した。これは鉄鋼産業や半導体産業の輸出額を上回る規模である。これを踏まえ、「新たなクールジャパン戦略」では、日本発のコンテンツの海外市場規模を2033年までに20兆円(中間目標として2028年までに10兆円)とすることを目標として掲げた333。このように、日本の付加価値産業の海外展開を育成・支援していく観点で、コンテンツ産業の重要性が高まっている(第II-3-4-23図)。
第Ⅱ-3-4-23図 コンテンツの国内市場と日本のコンテンツの海外売上
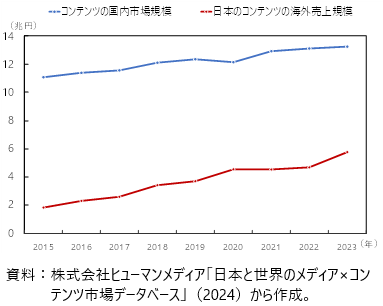
世界のコンテンツ市場は、データの取得可能な国・地域を合計しただけでも2023年時点で199.9兆円に達する(第II-3-4-24図)。その内訳を見ると、最大の米国が約84.0兆円となっており、それに中国(約42.5兆円)、欧州(約34.1兆円)等が続く。米国と中国は規模が大きいだけでなく、成長も著しい。ASEANやインド等は、足下の規模は5兆円近傍であるが、将来的に人口増や経済成長が見込まれ、中長期的な成長が期待される市場である。後述するコンテンツ関連企業へのヒアリングにおいても、主な海外展開先として大市場である米国、中国、欧州、また、文化的近接性のあるASEAN・韓国・台湾等のアジアが挙げられることが多かった。
第Ⅱ-3-4-24図 各国・地域のコンテンツ市場規模
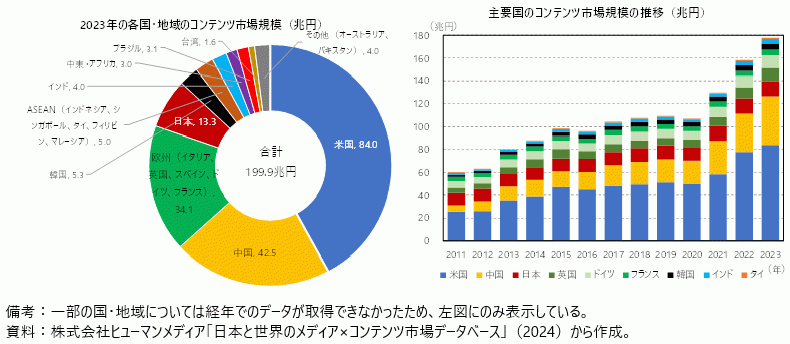
332 株式会社ヒューマンメディア(2024)
333 知的財産戦略本部(2024)
(2) コンテンツ産業の越境取引の類型
第Ⅱ部第3章第3節で述べたとおり、サービス関連の越境取引は一般的にデータ制約があり実態把握が困難だが、コンテンツ産業ではその傾向が更に強くなる。理由として、IP(知的財産権)を中心とするビジネスモデルであり、企業のビジネス実態として契約関係に多様性があり、同じコンテンツに係る取引でも、商流のどこで国境を超え、どの統計分類として集計されるかが一義的に決まらないことが挙げられる。どのようなIPを誰がどこ(国内又は海外)で保有するのか、商流の各段階においてコンテンツをどのような形態(財、サービス、IP)で取引するかによって、国際収支統計を始めとする各種統計に記録される区分が異なることに留意が必要である。音楽や動画等の海外プラットフォーマーの存在も、商流・契約を多様化させる要因になっている。
第II-3-4-25図は、コンテンツ企業の海外との取引について、典型的な類型に絞って場合分けしたものである。まず、IPビジネスで鍵となるのは、当該IPを保有し、そのIPを他者に使用する許諾を与える主体であるライセンサーと、ライセンサーから当該IPを使用する許諾を受ける主体であるライセンシーである334。今回は、一次的なライセンサー(原作者や映画製作委員会等335)とライセンシー(ライセンスビジネス企業等)が国内主体であって、当該ライセンシーが海外ビジネスを展開する場合の主な取引関係を分類した。
第Ⅱ-3-4-25図 コンテンツ産業の越境取引の類型
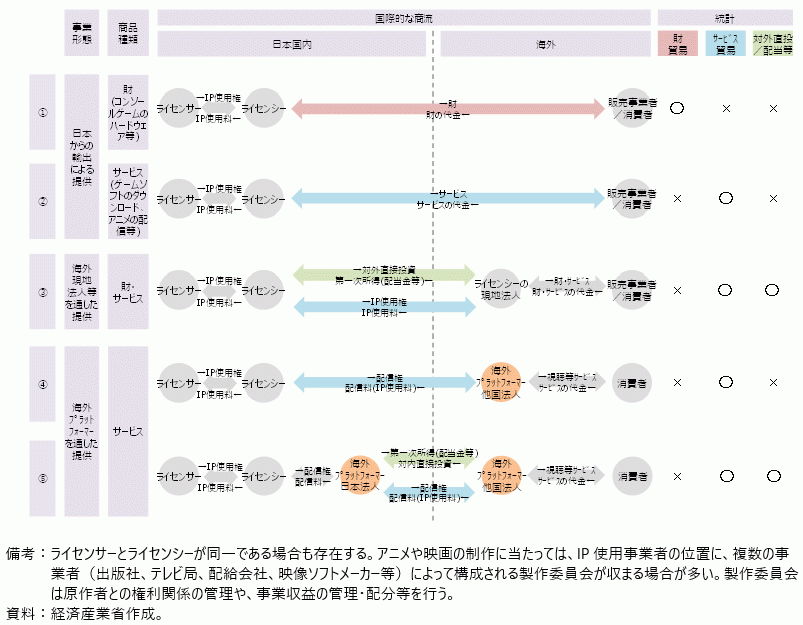
①・②は、伝統的な財・サービスとしての貿易である。①は、日本国内でコンテンツIPを使用して製造した財(コンソールゲームのハードウェアや玩具・カード等のグッズ等)を輸出し、海外の販売事業者又は消費者に提供するケースである。これは国際収支統計上の財貿易として計上される。②は、ゲームのソフトやアニメ等を日本から自社サイト等を通じて海外の消費者に直接販売するケースである。これは国際収支統計上のサービス貿易として、「知的財産権等使用料」以外の各該当サービス分類に計上される。
③は、コンテンツIPの使用権を、国内ライセンシー(IP使用事業者)から資本関係のある海外現地法人に付与し、現地法人がIPを使用した財、サービスを提供するケースである。①・②と異なるのは、(1)国内ライセンシーから海外現地法人に対して、コンテンツIPの使用権を付与し、その対価が「知的財産権等使用料」としてサービス貿易に計上されること、(2)別途、国内ライセンシーから海外現地法人への出資が対外直接投資として、出資に対する配当金等が第一次所得収支としてそれぞれ計上されることである。
④・⑤は、海外プラットフォーマーに対して音楽や映像等のコンテンツIPの使用権を付与し、同プラットフォーマーが海外配信するケースである。この時、契約主体が海外プラットフォーマーの本社や他国子会社なのか、それとも国内子会社なのかによって、統計上の扱いが変わってくる。④は、本社又は他国子会社と直接契約をする場合であり、その場合は著作権等使用料を受け取るサービス貿易として計上される。他方、⑤は、日本子会社との契約であり、海外プラットフォーマーの本社や他国子会社が配信主体となる場合には、日本子会社が著作権等使用料を受け取るサービス貿易としての計上に加えて、日本子会社への出資が対内直接投資、日本子会社からの配当金等が第一次所得収支に計上されると考えられる。
なお、④・⑤は、国内ライセンシーが海外プラットフォーマーに使用権を許諾する契約を想定しているが、例えば映画やドラマ等の映像コンテンツ制作において、海外プラットフォーマーから国内のクリエイター等に対して制作委託する取引もあり、その場合には、当該作品のIPは当初から海外プラットフォーマーに帰属することになる。海外プラットフォーマーの本社や他国子会社からの委託であれば、その委託料がサービス貿易に計上されると考えられる。
上記は、コンテンツ産業の越境取引の実態を把握し、我が国の貿易投資関係を統合的に理解する観点からの分類だが、コンテンツ企業のビジネス実態としては、この分類自体が重要とは必ずしも認識されていない。各企業は、海外とのビジネスを行うに当たって、自社のコンテンツIPの価値を最大化するために、現地の市場環境や法制度等も踏まえ、誰とどのようなIP関係の契約を結び、海外における商流拡大、販売促進、権利保護等を行うか、という観点から取引形態を決めていると考えられる。
334 ライセンサーがライセンシーに対して許諾するIP使用権の範囲はケースによって差異がある。範囲が狭いケースではアニメ制作やグッズ制作など特定のIP事業領域に絞って許諾する場合もあれば、範囲が広いケースではIPの管理や各種展開を包括的に許諾(委任)する場合もある。
335 「製作」と「制作」という言葉について、映像(アニメ・映画等)やゲームなど一部のコンテンツ産業においては、「製作」がビジネス的な意味合いで用いられ、「制作」が創作活動的な意味合いで用いられている。本稿ではそうした使用実態を踏まえて、「製作委員会」など「製作」の使用が通例化している場合を除いて、「制作」で統一している。
(3) コンテンツ産業の声
上記の認識を踏まえ、コンテンツ産業の海外展開について具体的に実態を把握するため、海外に子会社を持ち、映像(アニメ、映画等)、ゲーム、グッズ、出版、音楽等を事業とする代表的なコンテンツ関連企業に対してヒアリングを行った。その結果を、①海外市場とビジネスモデル、②コンテンツ制作・管理、③課題に分けてまとめる。なお、各社の主な事業領域の別については第II-3-4-26表のとおりである。
第Ⅱ-3-4-26表 ヒアリング対象企業の主な事業領域
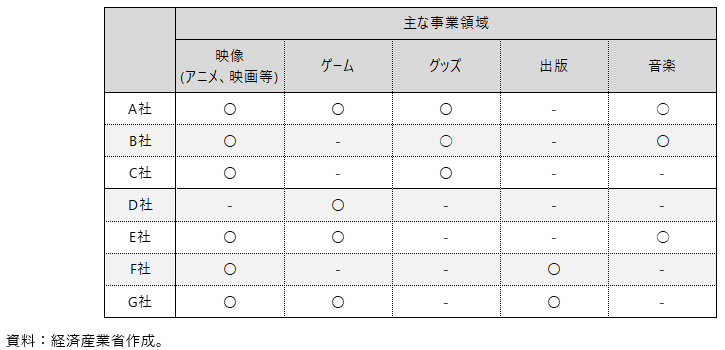
① 海外市場とビジネスモデル
海外展開における注力市場としては、大市場である米国、欧州、中国や、文化的近接性のあるASEAN・韓国・台湾などのアジアが挙げられることが多かった。いずれも一定の市場規模若しくは成長性があり、コンテンツを楽しむことのできる余裕があるような比較的豊かな国・地域となっている。中でも米国は、多くのコンテンツ領域で最大の市場となっており、米国で流行したものがその後に他国でも流行するというトレンドの発信地としての性格も持っているとされた。中国は市場の拡大スピードが著しく、多くの企業にとって重要性が高まっているが、地場コンテンツの成長も見られる。また、タイやインドネシアなどの東南アジア地域では、擬人化されたキャラクターが含まれるコンテンツへの許容性が高いこと等、日本との文化的な特質の近接性を指摘する声もあった。他方、市場環境の問題として、コンテンツの総量規制や販売前の事前認可等の現地規制の問題や、模倣品・海賊版の氾濫が展開の障害となるケースもあり、予見可能性の向上を期待する声が聞かれた。
海外展開のビジネスモデルとして、映像、ゲーム、出版、音楽等のコンテンツの海外販売に関しては、デジタルデータの形式で供給される割合が増えており、海外への販売自体は、過去と比べて容易になってきている。なお、出版における電子書籍による販売は、日本、韓国など特定の市場においてのみ広く普及しているという特徴がある。これは、電子書籍という形態に対する人々の受容性や、海賊版サイトのまん延によって電子書籍の販売が伸びない等の事情が影響していると考えられる。
コンテンツの売上を大きく左右するのはそのコンテンツ自体の面白さ・魅力であり、制作会社のブランド力の寄与は限定的である。したがって、現地の文化、価値観、トレンド等を踏まえて海外市場で売れるコンテンツを見極める、目利きの力が重要となる。また、コンテンツを売るための仕掛け作りも重要である。ファンが自主的に開催するイベントをサポートするなど、グッズも含め各コンテンツが売れるようになるにはどうすれば良いか考えながら、現地の市場に入り込んで販売促進を行う必要がある。この観点で、制作や販売等の収益に直結する事業を持たず、専らこうした販売促進を行うための現地法人を設立するケースもある。
配信と制作の両面で存在感が高まっている海外プラットフォーマーとの契約形態はケースバイケースであり、コンテンツ企業側の日本本社・海外現地法人と、海外プラットフォーマー側の本社・日本子会社・他国子会社が、個別事情に応じた契約形態をとっている模様である。なお、プラットフォーマーに関する見方として、特に出版では、日本に圧倒的な占有率を持つプラットフォーマーが存在しないことで、クリエイターが買い叩かれづらく、適切に評価される環境が保たれている側面があり、それを守っていくことがコンテンツ産業の健全な育成につながるという意見も聞かれた。
個別の声は以下のとおりである。
A社(映像、ゲーム、グッズ、音楽等を手掛ける)
● 権利保護に関しては、国によって制度や保護範囲が異なるため、商標登録や著作権登録、キャラクターデザインなどの意匠権登録は海外でも入念に行っている。
● IP利用料は、ライセンサーである日本本社に集まるようになっている。また、海外現地法人に対しては、経営管理という形で日本本社から経営指導や役務の提供も行っているため、海外現地法人からのサービス収入も生じている。
● 海外プラットフォーマーと契約する際の相手方が海外本社か日本支社か否かについては、税務や法務リスクは鑑みつつも、世界中のファンに最適な商品・サービスを提供出来ることが重要なので、意識した区分をしていない。
● 海外での商品販売の成功においても、コンテンツ自体の面白さは必須条件である。さらに場合によっては現地に直接拠点を設け、現地の消費者の価値観や余暇の過ごし方などの実態を深く理解し、コンテンツを売るための仕掛けをつくることも非常に重要。例えば、現地で体験型のイベントを実施することが販売拡大につながるケースもある。
● 日本でキャラクターのライセンスビジネスができる人材の数は限られていたが、最近は、ノウハウを持った人材が次第に育ってきている。
B社(映像、グッズ、音楽等を手掛ける)
● 海外プラットフォーマーと契約する際の相手方は、主に海外本社となるが一部で日本支社との契約もある。つまり、大部分は越境の取引をしていることとなる。
C社(映像、グッズ等を手掛ける)
● IPの管理は日本本社で行っている。海外販売のための現地子会社にはIPの販売権を持たせ、現地の他資本の企業(配給会社、テレビ局、配信会社など)へ販売するケースが多い。1か国にとどまらずグローバル一括で配信される場合には、日本本社が契約を行う。
● 海外プラットフォーマーとの契約については、ケースごとに異なる。米国本社との契約もあれば、日本の子会社や欧州の子会社と契約するケースもある。
E社(映像、ゲーム、音楽等を手掛ける)
● 海外で販売する際には、自社の現地子会社や海外の他資本の企業にIP使用を許諾したり販売を担わせたりする。ケースバイケースで現地子会社にてローカライズやマーケティングを行う。自社がIP使用料の徴収や収益配分を受ける許諾物に関しては監修を行う。
● 現地子会社からはIP使用料の他にも、配当金という形で日本に資金が戻るケースもある。
● 海外プラットフォーマーとの取引において、日本子会社と契約を結ぶケースもある。
F社(映像、出版等を手掛ける)
● コロナ禍に外出自粛が生じた時期には、消費者が自宅に居ながらにしてデジタル配信でコンテンツを楽しむといった巣ごもり需要が増加した。それによってデジタル事業の拡大にも一層の弾みがついたように思う。
● 日本の出版産業の強みは、プラットフォーマーが市場を独占しておらず、クリエイターが自由に作品を制作できること。プラットフォーマーが販売を独占してしまうと、クリエイターに対する買い叩きが発生する、プラットフォーマーによる表現への過度な介入等が入ることで自由に制作できなくなるといった懸念がある。我が国のように多数のチャネルが存在することは望ましいと考えている。
G社(映像、ゲーム、出版等を手掛ける)
● 海外市場で受け容れられ、売れるコンテンツを目利きする力が重要。字幕や吹き替え版の制作にはコストが掛かるので、全てのコンテンツについて行うことは難しい。
② コンテンツ制作・管理
コンテンツの制作については、今回ヒアリングを行った企業は保有するIPの大部分を日本で生み出していた。そうしたコンテンツ制作には、原作としてのIPを最初から制作する場合と、既にある原作を用いてアニメや映画などの派生IPを制作する場合の両方が存在する。そして、そのIPから生ずる利益は、基本的に、IP使用料等の形で最終的に日本の本社へ返ってくるとの説明があった。コンテンツ制作の一部を、海外子会社や他資本の協力会社が担う場合であっても、中核となる部分の企画・開発は日本で実施している実態が示唆された。製造業における国際的な分業体制や市場近接地での現地生産に類似するコンテンツ制作の体制を敷いているケースは少なかった。一部コンテンツの派生IP制作を海外企業に委託するケースでも、制作文化やIP価値の理解を深めるために段階的に協力関係を深めるステップを踏むとの説明もあった。
我が国のコンテンツ制作の強みとしては、既に数十年間の歴史を通じてコンテンツ制作文化が日本に根付いていることから、クリエイター人材が国内でしっかり育っているという声があった。その背景として、八百万の神という言葉に象徴されるような、様々な物事に神々が宿ると考えるアニミズム的な国民性(動物等の擬人化といったアイデアに活きる)や、表現の内容や方法についての許容性の高さ(コンテンツの多様性に活きる)が存在しているのではないかという意見が複数あった。
コンテンツの価値管理の観点で、個々のコンテンツのコンセプト・世界観をしっかり守りながら展開を行うことが非常に重要であるという声がしばしば聞かれた。例えばこのキャラクターであればどういう発言を行うか、どういう動作・姿勢・立ち位置を取るかといった細かな部分まで、原作者と相談・確認を行うなど統一性をもって管理する必要がある。それを軽視し、いたずらに制作の量的拡大を追求しようとすると、かえってコンテンツの個性や世界観を失わせてしまい、結局、ビジネスを棄損してしまう可能性があるという。逆に、こうしたコンテンツの世界観の管理を行うことは、例えば親世代がその幼少期に慣れ親しんだコンテンツを自らの子どもと安心して一緒に楽しめるというように、IPの生み出す価値を増幅する効果もある。
個別の声は以下のとおりである。
A社(映像、ゲーム、グッズ、音楽等を手掛ける)
● 八百万の神という言葉が古くからあるように、あらゆるものに神々が宿ると考えるのは日本の文化の特徴だと考えている。これは擬人化が大事なキャラクタービジネスにおいて、例えば道具やロボットにも命があるという発想を持つことができるため、創作のために非常に重要。
● もともとグッズ産業は映像等のコンテンツ産業の川下という認識があった。しかし、現在はその考えを改め、単なるグッズではなく、顧客が感情移入、感情表現をするための装置という発想で捉えている。
B社(映像、グッズ、音楽等を手掛ける)
● 音楽の権利は、ISRC(International Standard Recording Code)の登録をオリジナルの原盤制作国で行う。
C社(映像、グッズ等を手掛ける)
● 登場人物やストーリーの設定など、作品の主要な部分を企画する工程は日本で行っている。ただし、そうした企画の工程が将来的に海外で出来ないかというとそうとも限らないと思っている。
● 日本では、圧倒的な漫画文化を下地として、クリエイターの卵が各地におり、物語を創ることができる人材が激しい競争環境の中で育っていると理解している。また、動物や道具が命を持ったキャラクターとして作品の中で活躍するような、一見すると奇想天外な物語の設定を抵抗感なく受け入れるという感覚が、八百万の神という言葉に象徴されるように昔からあり、それが様々なアイデアの源になっているのではないかと思う。
D社(ゲーム等を手掛ける)
● IPのクオリティ世界観の管理は重要な課題と認識。そのため、IPのことをしっかり理解してくれる企業とパートナーシップを組んできた。例えば、このキャラクターはコンセプトや設定上こういう立ち振る舞いをするといった表現上の管理は重要であり、社としてIPごとにガイドラインを設定するなど、しっかりとコストをかけて対応している。
F社(映像、出版等を手掛ける)
● 制作するコンテンツの質を上げるには、いたずらに制作の量を追求しない姿勢が必要。ヒットコンテンツが生まれるには一定の制作量が必要ではあるが、売れるヒットコンテンツには限りがあり、量を増やせば増やすだけ売れるというビジネスではない。
G社(映像、ゲーム、出版等を手掛ける)
● 日本は表現の自由度や許容性が高いと考えており、それがコンテンツの種類やジャンルの幅広さの背景となっている。設定や表現の多様性が、日本のコンテンツの強みの一端を構成している。
③ 海外展開に係る課題
各社がコンテンツを海外販売する際には、現地の法令対応だけでなく、吹き替えや字幕の作成といった言語対応から、現地の宗教や習慣の観点から受け容れられる表現へと修正すること等も含めた、ローカライズやカルチャライズ(輸出先国の文化や規制・制度に合わせて作品の内容を改変すること)を適切に実施することが重要であり、各社ともその対応に多くのコストをかけている。多数の国・地域の法令や文化等の調査を行うコストに苦慮しており、政府に最新の基本的な海外情報の提供を期待する声があった。
また、現地の規制当局への働きかけについて、政府と業界団体や企業がより連携を取って対応していくべきという声があった。なお、中国などの市場に関しては、特殊な規制に個社努力で対応するのは限界があるとの声もあった。模倣品・海賊版対策については、官民連携して引き続き取り組んでいくべきという意見が多数あった。
その他、アーティストの海外公演時のビザ取得の支援や、JLOX+(クリエイター・事業者支援事業費補助金(クリエイター・事業者海外展開促進))等による継続的な支援とともに申請等に係るコスト軽減に向けた手続き簡素化を求める声があった。特にビザ取得に関しては、アーティストのマネジメントを行う事務所等の多くが小規模事業者であり、ビザ取得の手続だけでも海外公演を行うことの大きな障害になるという実情が聞かれた。コロナ禍による対面イベント開催自粛を経て、リアルな価値提供の重要性が再び注目されている中で、その需要に応える上で重要なポイントといえる。
個別の声は以下のとおりである。
A社(映像、ゲーム、グッズ、音楽等を手掛ける)
● 日本で作った作品を海外に展開する際に、想定していなかった点を指摘されて規制当局に止められることがある。例えば、作品のキャラクターが現地の宗教に関係する動物を擬人化していることや、同性愛的な描写があること等。昨年、自社の若手社員が世界各国の法律や慣習について分かりやすい一覧表を作成し、社内で表彰された。各社が個別に必要な情報は個社で集めるべきだが、共通する基本的な情報は、政府が情報収集・提供してもらえると有り難い。
● 足下では、欧州の化学物質規制が最も大きな課題。欧州では新しい規制で、グッズの素材の成分を分析しなければならないが、販売している多種多様なグッズを製品ごとに分析するとなると、欧州に輸出する採算が取れなくなり、欧州でのビジネスが困難。規制対策について、業界団体だけでなく、政府の積極的な関与が期待される。
● 中国は、海外映画の国内での放映枠数が規制されている。現地企業等との共同制作であれば規制にはかからないが、権利保護の観点から難しいこともある。また、中国は、ゲームの版号336がなかなか取れない。他方、模倣品対策について、現地当局の職員が日本のコンテンツに対して理解があり、協力的に対応してくれるケースもあった。
B社(映像、グッズ、音楽等を手掛ける)
● カルチャライズは、特に漫画やアニメで重要。デジタルコンテンツがこれほど海外に出ていこうとしているのは、歴史上初めてのこと。現地のビジネス慣行を含めた情報は調べ切れないところもあるため、政府にはタイムリーな情報提供をしてもらえると有り難い。
● アーティストの海外公演時のビザ取得については、中小規模のマネジメント事務所などでは特に苦慮している。韓国は政府と業界団体でビザの取得について支援があるため、そのような仕組みを日本でも導入できないか。
● JLOX+では、アニメの海外言語の字幕や吹き替えの作成にかかる費用を補助する制度があり、活用している。しかし、申請等のコストが大きく見送ってしまう状況も発生しているため、手続の簡素化を求めたい。
● 模倣品・海賊版対策について、官民連携して進めていきたい。ベトナムや中南米の被害が大きい。昨年ブラジルで、CODA(一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構)と連携して悪質な海賊版サイトを摘発したのは良い実績だった。
C社(映像、グッズ等を手掛ける)
● 言語対応に関しては、自社のコンテンツの主なターゲットである低年齢層の子ども達への普及を図るためには、字幕だけでなく吹き替えの作成も必要。字幕をそうした子ども達が容易に読めるかというと難しい部分がある。
D社(ゲーム等を手掛ける)
● 現地特有の規制に悩むことがある。自社のゲームを中国のユーザーがプレイされる場合、そのシステムとして、ユーザーのプレイ情報を取得・越境送信して、その状況によってゲームの設定や特典を調整する等、双方向のデータのやり取りが必要。しかし、ユーザーの情報を取得・越境送信する部分が現地の規制に抵触してしまい、提供を諦めるケースが生じている。
336 中国でゲームを配信する際に必要な許認可。2018年以降、許認可数が減少している(JETRO「2023年2月3日 海外発トレンドレポート ゲーム市場は拡大も、配信許認可に留意(中国・上海発)」、
https://www.jetro.go.jp/biz/trendreports/2023/43868c6dbf359b61.html![]() (2025年6月9日閲覧)。
(2025年6月9日閲覧)。
(4) コンテンツ産業への我が国の政策的な支援
コンテンツ産業が海外展開を始め、今後成長産業として飛躍していくための官民のアクションをまとめるべく、経済産業省では、2025年5月9日に「エンタメ・クリエイティブ産業戦略」の中間取りまとめ337を公表した。近日中の成案を目指し、それに基づいたアクションを講じていくこととしている。この中間取りまとめにおいては、コンテンツ産業の海外売上高20兆円(2033年時点)を達成することは決して容易ではなく、「8つの不足」へ対応すべく、「10分野100のアクション」を実行すること、抜本的な支援策と支援体制の見直しが必要であることなどが述べられている。
クリエイターの現場の声や、コンテンツ企業の声を集めて把握した「8つの不足」とは、①海外で「魅せる」機会、②国内で「魅せる」「作る」拠点、③クリエイターの働く環境の改善、スキル向上と収入増の好循環、④「収入ギャップ」の解消、⑤新規技術・コンテンツの取込み、⑥海外勢との戦略的連携、⑦海賊版対策・正規版転換、⑧総合的な支援体制などの不足を指す。こうした不足を解決するために、10分野(①ゲーム、②アニメ、③漫画・書籍、④書店、⑤音楽、⑥映画・映像、⑦デザイン、⑧アート、⑨ファッション、⑩「みる」スポーツ)において、例えば配信プラットフォーマーと制作会社の契約条件の改善・透明化に向けた取組(アニメなど)、出版物の翻訳ツールの開発支援やカルチャライズへの支援拡充(漫画・書籍、アニメなど)、海外の規制に関する情報収集・整理と、規制への対応やイコールフッティングに向けた政府間での連携や交渉(ゲーム、アニメなど)、海外展開を念頭に置いたローカライズ・プロモーション等に対する支援や、国際共同制作、グローバル視点のアワードを含む国際的イベントの推進(アニメなど)、海外展開の支援に向けたJETROの体制強化(分野共通)などの100のアクションを講じることとしている(第II-3-4-27表)。
第Ⅱ-3-4-27表 エンタメ・クリエイティブ産業戦略案における「10分野100のアクション」の代表例
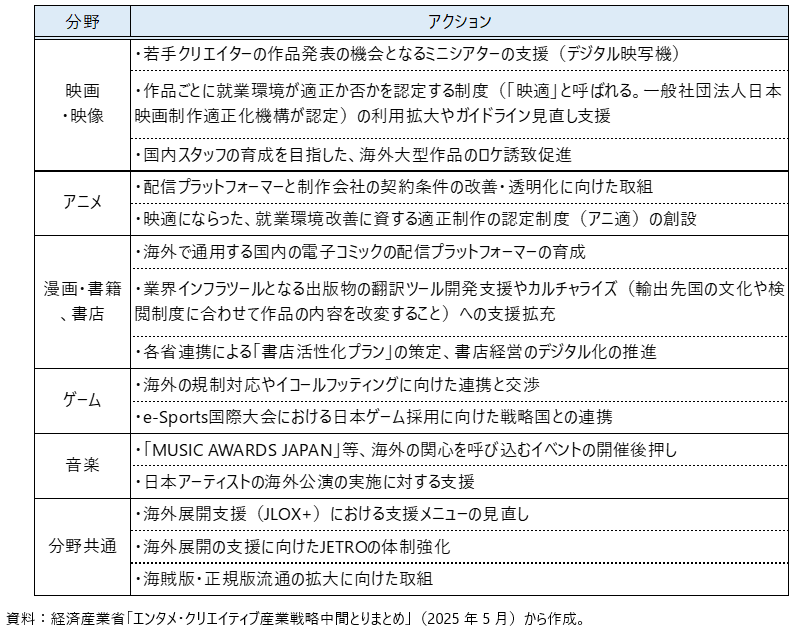
337 経済産業省「エンタメ・クリエイティブ産業戦略 中間とりまとめ」、2025年5月9日、
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/entertainment_creative/pdf/20250509_1.pdf![]() (2025年6月9日閲覧)。
(2025年6月9日閲覧)。
3. 通商政策と対外直接投資
本節ではここまで、我が国製造業のグローバルな立地・投資戦略(第1項)、成長著しいコンテンツ産業の海外展開の状況(第2項)を確認してきた。本項では、我が国の通商政策における対外直接投資の位置付けを、本章で分析してきた日本の財・サービスの貿易投資構造を踏まえて整理する。
(1) 対外直接投資について
近年、我が国の国際収支構造に関する議論が深まる中で、経常収支黒字に寄与する第一次所得収支、とりわけ直接投資収益338の拡大が注目を集めた。その際、直接投資から得られる収益には、国内に還流する直接投資収益と、還流されずに現地で再投資される再投資収益があり339、「対外直接投資は収益の国内への還流が少ない」といった指摘もなされている340。ここで注意が必要なのは、そうした議論が何を問題にしているか、である。近年の議論の多くは、昨今の急激な円安の要因を問題にしている。すなわち、大幅な経常収支黒字にもかかわらず、キャッシュフローベースで見ると対外直接投資収益の多くが外貨のまま現地で再投資されており、円に対する需要増につながらない、ということになる。しかしながら、これはあくまで為替や国際収支の観点であって、それをもって必ずしも実体経済、産業やビジネスの観点で問題があるとはいえない。
また、「海外投資よりも国内投資を優先すべき」といった声もあるが、対外直接投資には、海外市場の開拓に加え、配当を通じた国民所得の拡大、海外のイノベーションの取り込みによる国内産業の高付加価値化などのメリットも大きく、国内投資か海外投資かといった単純な二項対立で議論されるべきものではない。そもそも対外直接投資は、一義的には民間企業が利益や様々なリスクなどを勘案しながら判断するものであり、政府の役割は、民間企業がグローバルに最適な投資判断を行うことができる予見可能性の高いビジネス環境を整備していくことが基本になる。
ここで対外直接投資に関するデータを確認する。対外直接投資収益は近年増加傾向にあり、直近では2,000億ドル程度になっている(第II-3-4-28図)。そのうち、国内に還流する配当金の割合は、2010年~2023年の平均で約53%であり、これは米国・カナダ・韓国・イタリアよりも高く、他の先進国と比較して低い水準ではない(第II-3-4-28図)。また、投資家にとっての投資に対する配当という観点で、国内企業の配当割合と比較すると、同期間の国内全産業の当期純利益に対する配当割合は約50%とほぼ同水準である(第II-3-4-29図)。対外直接投資残高に対する収益率も中長期的に増加傾向で、直近は10%弱(2024年)となっており、過去の新規投資及び再投資のストックに対して、確実に利益が上がっていることが分かる(第II-3-4-30図)。換言すれば、利益の現地での再投資も、将来の収益の源泉になっているといえる。
第Ⅱ-3-4-28図 対外直接投資収益の構成と主要国比較
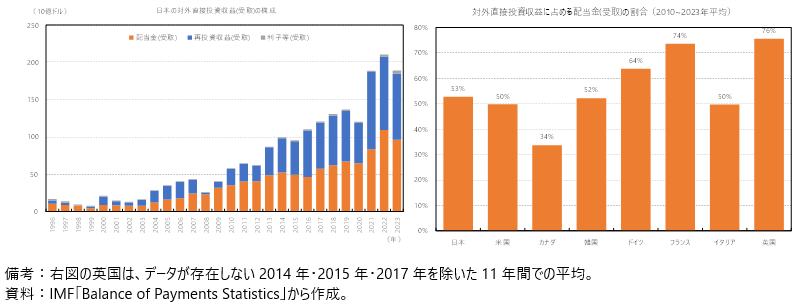
第Ⅱ-3-4-29図 国内全企業の配当金額と配当割合
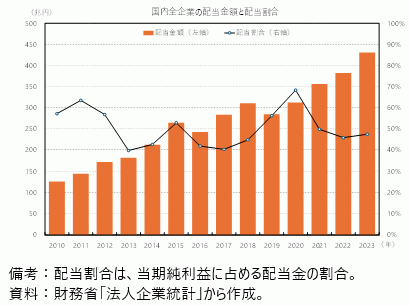
第Ⅱ-3-4-30図 日本の対外直接投資残高と収益率
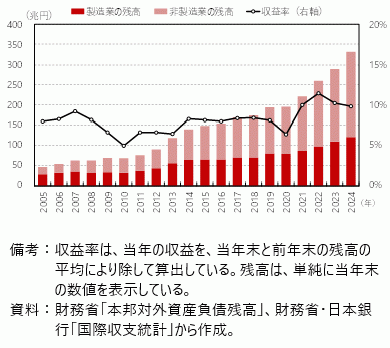
その上で、政策的には例えば、交易条件の改善の観点から、日本が国内に保持すべき高付加価値機能の海外流出を避けつつ、海外のイノベーションを取り込む、あるいは、自律性の確保の観点から、特定の国・地域に過度に依存する構造に陥らないようサプライチェーンの多元化を進める、といった形で対外直接投資が進むことが重要である341。第II-3-4-31図は日本の交易条件の推移を示したものだが、過去約30年間にわたって悪化傾向にあり、海外のイノベーションの取り込みも含めて、輸出産業の高付加価値化は重要な課題となっている。
第Ⅱ-3-4-31図 日本の交易条件
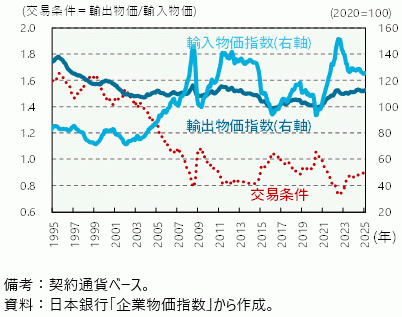
上記の認識を前提として、政策的支援を行う対象となりうる対外直接投資としては、例えば、①先進的なビジネスやイノベーションの行われている海外で日本企業が事業を展開することで、日本企業の高付加価値化を実現するようなケース(国内外の投資が一体となって競争力のあるバリューチェーンを構築)、②経済安全保障やエネルギー政策等の観点から必要なケース、③他国・地域とのウィンウィンの戦略的関係を構築するという外交上の要請に応えるために必要なケースなどが考えられる。
338 国際収支統計における対外直接投資は、日本から海外に向けた、議決権の割合が10%以上の出資関係がある親子会社間の投資及び一定上の間接的な出資関係がある企業間の債権投資や貸借取引などを指す(日本銀行(2022))。ここにはグリーンフィールド投資もM&Aによる投資も含まれる。
339 詳細にいえば、対外直接投資収益は、①配当金・配分済支店収益、②再投資収益、③利子所得の三つに区分される。①は、親会社と子会社の間で受払された利益配当金、及び支店の収益のうち本社に送金されたものを計上する。②は、子会社の内部留保を親会社の持分比率に応じて計上する。③は、直接投資家(親会社等)と直接投資先(間接出資先を含む)との間及び兄弟会社間の貸付け・借入利子や債券利子を計上する。
340 例えば、財務省(2024)では、「第一次所得収支の黒字は過去最大となる一方、その多くが国内に還流せずに海外で再投資されている」としている。
341 交易条件とは輸出価格指数を輸入価格指数で除した比率であり、輸入価格に対して輸出価格が上昇(下落)する場合には、交易条件は改善(悪化)し、自国にとって貿易を行うことが有利(不利)となる(内閣府政策統括官(経済財政分析担当)(2011))。