第5節 グローバルサウス諸国との共創
1. グローバルサウス諸国との協力強化の重要性
国際政治経済関係において中長期的にパワーバランスが移行する中で、グローバルサウス諸国の存在感が増している342。我が国企業にとっても、新興国・途上国の市場の拡大と高度化は、引き続きグローバル戦略における重要な成長機会である。これまで述べてきた日本の対外貿易投資構造の変化を踏まえ、高まる不確実性の中でルールベースの国際経済秩序を強化・再構築していく上で、グローバルサウス諸国との新たな関係の構築が重要になっている。
グローバルサウスという言葉は、近年、新興国・途上国を総体として指す言葉として使われることが多いが、グローバルサウス諸国とされる国々の歴史的背景や社会経済的な状況、政治体制、地政学的な立場は多様であり、一括りに捉えることは必ずしも適切ではない。各国がそれぞれ直面する具体的な社会経済的課題に、共創のパートナーとして連携して取り組むことが重要である。
本節では、グローバルサウス諸国の中でも、日本が歴史的に強い社会経済的な関係を構築してきたASEAN諸国との協力を振り返り、また足下の環境変化を概観することで、今後のグローバルサウス諸国との連携強化の方向性について検討する。
342 第I部第2章第4節参照。
2. 日本とASEANの協力関係
日本は、特に1980年代以降にASEAN諸国が経済成長を遂げる過程で、社会経済的な協力関係を深化させてきた。第二次世界大戦後、東南アジア諸国が植民地からの独立と国民国家の建設を進める中で、日本の協力関係は戦後賠償から始まり、1977年の「福田ドクトリン」で「東南アジアの国々との間に、政治、経済のみならず社会、文化等、広範な分野において、真の友人として心と心のふれ合う相互信頼関係を築きあげる」と表明したことを一つの契機として、さらに広範な友好協力へと発展していった。その中で、ASEAN諸国への直接投資を通じてグローバル・バリューチェーンを構築した製造業を中心とする日本企業は、現地で積極的な雇用、人材育成、現地調達を行い、現地の産業と雇用の基盤を構築することにも貢献した。政府としても、こうしたウィンウィンの経済関係を深化させるため、ASEAN諸国への政策支援や人材育成、インフラ整備のための支援を積極的に行ってきた。以下でその経緯を概観する343。
343 特に1980年代以降の経済産業協力については、大庭(2023)、大泉(2018)、末廣・山影(2001)を参照した。
(1) 1980年代以降の経済産業協力
ASEAN諸国の中でも、シンガポールは1960年代から、インドネシア・マレーシア・タイは1980年代から、外国資本を導入した輸出志向型の製造業育成などが奏功し、比較的早期に経済発展を遂げていった。その頃の日本は、既に戦後の復興を遂げ、経済大国としての役割を担うようになり、ODA(政府開発援助)などを通じた経済協力を拡大した。また、1985年のプラザ合意による円高の進行なども大きな背景として、1980年代後半以降は、日本の製造業がASEAN地域に積極的に直接投資を行い、域内での生産ネットワークを発展させた。
この時期、日本は貿易・投資の両面においてASEAN諸国の経済に主要な位置付けを占めていた。第II-3-5-1図はASEANから見た輸出入の相手国シェアの推移を示したものである。日本のシェアは、1980年当時でASEANの輸入の22.1%、輸出の29.5%を占め、いずれも最大であった。その後、日本からの中間財をASEAN各国で組み立て、欧米等の第三国に輸出する世界大の三角貿易が発展する中で、輸出先としての日本のシェアは減少を続けた一方、輸入先としてのシェアは90年代半ばに全体の約1/4まで上昇した。その後は、ASEAN域内の分業体制が発達したことなどに伴い、日本の輸入先としてのシェアも減少に転じている。
第Ⅱ-3-5-1図 ASEANの輸入相手国シェア(左図)、輸出相手国シェア(右図)
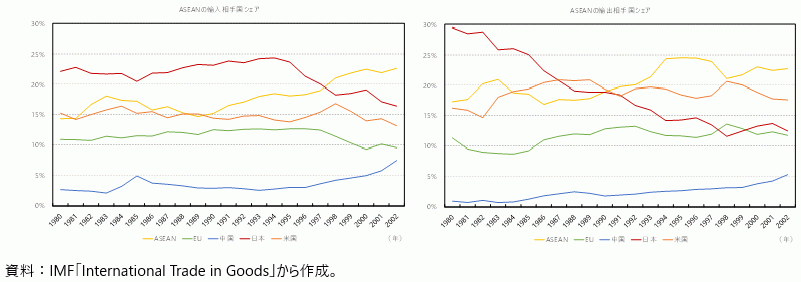
直接投資の推移を見ると、日本は1970年代から継続的にASEAN諸国に対する直接投資を行い、1980年代後半からその額を急激に増やした344。アジア通貨危機が起こる1997年に80億ドル近くまで増加した後は、やや水準を落としたものの、引き続き多くの対ASEAN投資を行っていた(第II-3-5-2図)。こうした長期間にわたる継続的な直接投資が、日本企業によるASEAN大の生産ネットワークの構築に寄与した。
第Ⅱ-3-5-2図 日本からASEAN諸国への対外直接投資額
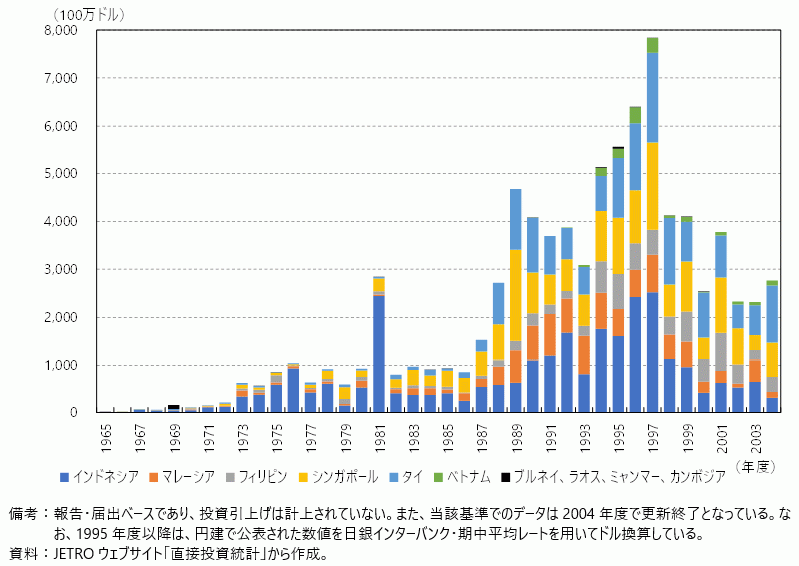
実態経済面の関係深化と併せて、我が国はASEAN諸国との関係で様々な経済産業協力を展開してきた。1980年代後半に「アジア製造業開発支援3か年計画(New “AID” Plan)」を打ち出し、技術協力、資金協力、投資促進、輸入促進等を有機的に連携させて、アジア地域の工業化の深化を通じて経済発展を支援しようとした。1992年には、日本とASEANの関係を更に深め、経済分野における政策対話を行うために、日・ASEAN経済大臣会合が発足し、2024年までに30回継続して開催されている。1994年の日・ASEAN経済大臣会合では、ASEAN加盟前のベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーの円滑な市場経済移行の支援等を目的としたインドシナWG(ワーキンググループ)345の設置が決定され、ソフト面のインフラ整備や産業協力が議論された。
東アジア経済に大きな悪影響を与えたアジア通貨危機を経て、1997年には第1回日・ASEAN首脳会議と第1回ASEAN+3(日中韓)首脳会議が開催され、通貨危機からの経済回復に向けた取組が議論された。産業協力の観点では、ASEANの拡大やアジア通貨危機を踏まえ、ASEANの統合深化や直接投資を含む幅広い産業協力について議論するため、1998年に日・ASEAN経済産業協力委員会(AMEICC)も立ち上げられている。同時期から、タイやインドネシア等に対して産業構造調整事業や中小企業政策支援として資金的支援にとどまらない政策支援を行い、その後も続く知的政策支援や政策対話の先駆けとなった。
2000年代には、ASEANを中心とする東アジアの地域統合の議論が活発化した。2002年1月、小泉総理大臣はシンガポールにおける政策演説で、日ASEAN包括的経済連携構想を重要な土台とし、日・ASEAN関係を基礎として、東アジアにおける「共に歩み共に進むコミュニティ」の構築を目指すことを提唱した。日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)は、2005年に交渉を開始し、2008年に署名されている。さらに、我が国が主導して2008年に設立されたERIA(東アジア・ASEAN経済研究センター)は、東アジア経済統合推進のため、「経済統合の深化」、「発展格差の縮小」、「持続可能な経済成長」を柱に、実践的な政策研究、提言、普及を進めてきている。
2015年には、安倍総理大臣がASEANを始めとしたアジア地域との「質の高いインフラパートナーシップ」を提唱し、長期的な費用対効果に優れた質の高いインフラ整備によって、アジア地域の膨大なインフラ需要に応えていく方針を示した。具体的には、融資能力の拡大など機能を強化したADB(アジア開発銀行)と連携し、約1,100億ドルの投資をアジア地域に提供することなどを表明した。
日ASEAN友好協力50周年を迎えた2023年には、これまで日本とASEAN が培ってきた信頼を原動力とし、これからの未来を共に創る「共創」をキーワードに、将来を見据えた新しい時代の方向性を示す日ASEAN 経済共創ビジョンが策定された。それと軌を一にして、AZEC(アジア・ゼロエミッション共同体)構想の推進や、日ASEAN自動車産業共創イニシアティブの立上げ、ヤング/Z世代ビジネスリーダーズサミットの開催などが行われ、これから将来の50年間を見据えた経済関係の強化・共創が進められている。
344 ただし、プラザ合意後の円高の影響には留意が必要である。
345 その後、ベトナムのASEAN加盟に伴い、「カンボジア・ラオス・ミャンマー・ワーキンググループ(CLM-WG)」に名称変更。
(2) 日本企業のASEAN諸国の現地社会経済への貢献
ここでは、先述のような日ASEAN間の経済産業協力の深化の過程で、日本企業がASEAN諸国の経済産業の発展と地元雇用に大きく貢献してきたことを、海外法人数、雇用、調達の三つのデータから確認していく。
まず、進出先の国・地域別での、日系企業の海外現地法人数を確認する。地域別の現地法人数で見ると、ASEANが7,661法人で最大となっており、設立・資本参加時期別でも、中国が最大となる2001年~2005年と2006年~2010年を除いて、ASEANが一貫して最大となっている。個別の国・地域別でも、タイ(3位)、ベトナム(4位)、インドネシア(6位)、シンガポール(7位)、マレーシア(9位)、フィリピン(11位)の6か国が上位20位までに入っている(第II-3-5-3表)。
第Ⅱ-3-5-3表 日系企業の国・地域別の海外現地法人数(設立・資本参加時期別)
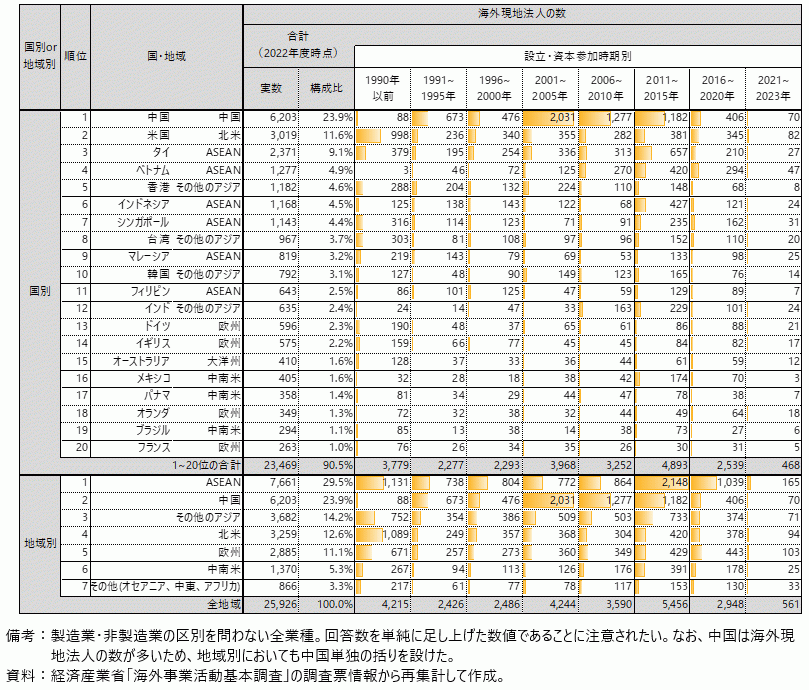
次に、ASEANにおける日系企業の海外現地法人による雇用と調達の状況を、経済産業省が行っている「海外事業活動基本調査」から確認する(第II-3-5-4図)346。まず雇用を見ると、2014年に日系現地法人のASEANでの雇用が約200万人に達し、その後の約10年間は安定して約200万人前後の雇用を生んでいることが分かる。そのうち、日本側から派遣された従業員の割合はおおむね1.0%~1.5%にとどまり、直近は減少傾向にある。現地において大きな雇用を創出していることがうかがえる347。
調達については、直近2021年の日系現地法人による現地調達額は約25兆円に達する規模となっている。なお、ここでいう現地調達額は、当該国内での調達に限ったものであり、他のASEAN加盟国からの調達は含まれていない。例えば、タイの現地法人がインドネシアから調達を行った場合には、現地調達額には含まれない。さらに、その内訳を見ると、現地地場企業からの調達がほぼ一貫して最大となっており、2021年には約12兆円に達している。直近10年程度を見ると、現地の日系企業からの調達は横ばいないし減少傾向であるのに対して、地場企業とその他の企業(当該国における日系以外の外資系企業)からの調達が増加傾向にあることも分かる。
こうしたことから、雇用と調達の双方において、日系現地法人が現地の経済に貢献している様子がうかがえる。
第Ⅱ-3-5-4図 日系企業の在ASEAN海外現地法人による雇用と調達の状況
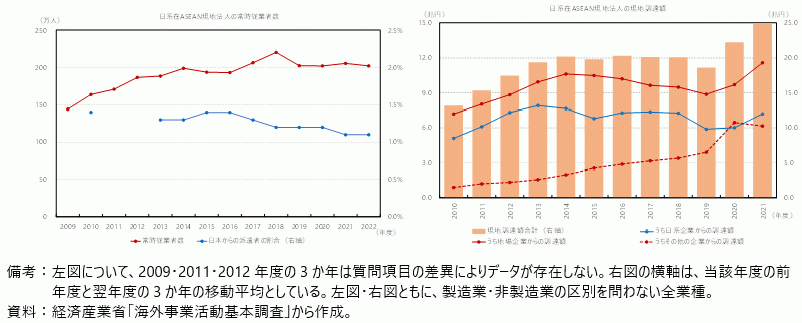
346 「海外事業活動基本調査」はアンケート調査であり、雇用数や現地調達額等の実数は、回答数を単純に足し上げた数値であることに留意。
347 なお、このデータは現地において採用された常時従業者の総計であり、国籍別に分けることは出来ない。日本側から派遣された従業者だけでなく、現地法人により直接雇用された日本人を含む外国人従業員なども合計されている。
(3) ASEANにおける日本の技術・人材協力の蓄積
こうしたASEANと日本との経済的な関係の深化には、企業と政府が一体となって進めてきた側面もある。その具体例として、JICA(独立行政法人国際協力機構)とAOTS(一般財団法人海外産業人材育成協会)による技術・人材協力の状況を確認する。
JICAは日本のODAを一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力を行っている。その一環で、人を通じた技術協力を目的として、日本の技術・知識・経験を生かし、開発途上国の社会・経済開発の担い手となる人材の育成や組織能力の強化、制度づくりへの協力を行っている。具体的には、開発途上国の課題解決の中核を担う人材を研修員として日本に招き、それぞれの国が必要とする知識や技術に関する研修を行う研修員受入事業や、開発途上国の課題に合わせた専門家を日本から派遣する専門家派遣事業などを実施している。
次に、AOTSは、1959年に民間ベースの国際的な技術協力機関として設立された団体であり、開発途上国を始めとする海外諸国の産業人材の育成を担っている。経済産業省もその事業を支援しており、相手国・地域の発展度合いや日本企業の進出状況・ニーズを踏まえた人材育成を行っている。その国際技術協力の一環として、具体的には、開発途上国を始めとする海外の企業(日本の民間企業の全額出資先企業や合弁先企業、生産委託先や販売代理店など)などの技術者を研修生として日本に受け入れて研修を行う受入研修事業や、そうした研修を日本ではなく海外で行う海外研修事業、現地子会社等に対して出資又は取引関係にある日本の企業などから従業員をAOTSの専門家として派遣する専門家派遣事業などを実施している。また、日本での受入研修事業の参加者が、それぞれの母国へ帰国したのちに自発的に同窓会を設立しており、そのネットワークは46か国・75か所に拡がっている。
第II-3-5-5表は上述のJICAとAOTSによる事業の実績人数と対象地域をまとめたものである。開始時点の違いには留意が必要であるものの、全世界においてJICAによる受入研修は約70万人、専門家派遣は約22万人の実績があり(2023年度時点)、AOTSによる受入研修は約21万人、海外研修は約24万人、専門家派遣は約1.1万人の実績がある(2023年度時点)。また、その対象地域はASEANの規模が非常に大きく、JICAによる受入研修は約21万人、専門家派遣は約9万人の実績があり(2023年度時点)、AOTSによる受入研修は約10万人、海外研修は約13万人、専門家派遣は約7.5千人の実績がある(2023年度時点)。この実績を見ることによっても、日本がいかにASEANと深い関係性を築いてきたかがうかがえる。
第Ⅱ-3-5-5表 JICAとAOTSによる人材協力の実績
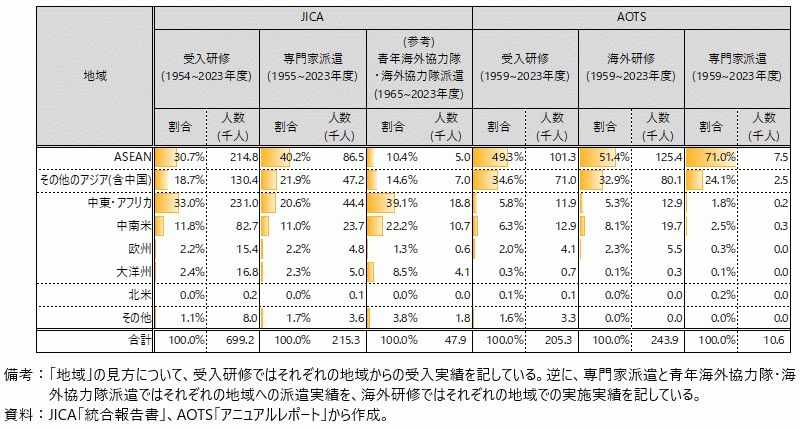
(4) ASEANから日本への強い信頼感
ASEAN側の人々が日本をどのように見ているかについて、シンガポールのシンクタンクであるISEASユソフ・イシャク研究所が2019年から毎年実施している調査の結果から概観する。本調査は、ASEAN加盟国348のビジネス従事者、研究者、政府職員などに対して、ASEANの置かれた国際的な環境などへの認識や意見を問うものであり、例年約1~2千人から回答を得ている。
第II-3-5-6図は、主要な国・地域が東南アジアに与える影響力についての認識を聞いた結果である。これによると、最も影響の大きな経済力を有する国・地域では、中国が群を抜いて多く選ばれており、直近3年間は約6割を占めている。それに続いてASEANと米国が多く(それぞれ約1~2割)、日本は2025年で約5.5%と第4位に位置している。次に、最も政治的・戦略的な影響を及ぼす国・地域としても中国が最も多く選ばれているが(約4~5割)、この問では米国の割合も大きい(約3割)。それに続いてASEAN(約1~2割)であり、日本は約3.8%と第4位になっている。
第Ⅱ-3-5-6図 主要な国・地域が東南アジアに与える影響力に対しての、ASEANの人々の認識
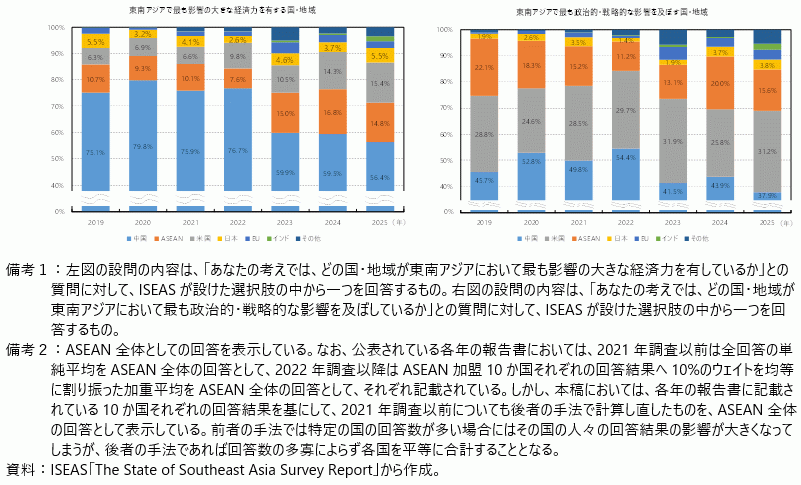
一方で、主要な国・地域に対する信頼感を問うた結果(第II-3-5-7図)を見ると、調査において回答を求めた五つの国・地域(日本・中国・米国・EU・インド)の中では日本への信頼感が調査期間を通して最も高く、直近の2025年では信頼できると回答した割合は66.8%に達し、信頼できないと回答した割合は16.5%にとどまっている。他の4か国・地域と比較しても、日本がASEANの人々から高い信頼を得ていることが示唆されており、今後、日本がASEANとの社会経済的な共創パートナーとしての関係を深めていく上での貴重な資産であるといえよう。
第Ⅱ-3-5-7図 主要な国・地域に対するASEANの人々の信頼感
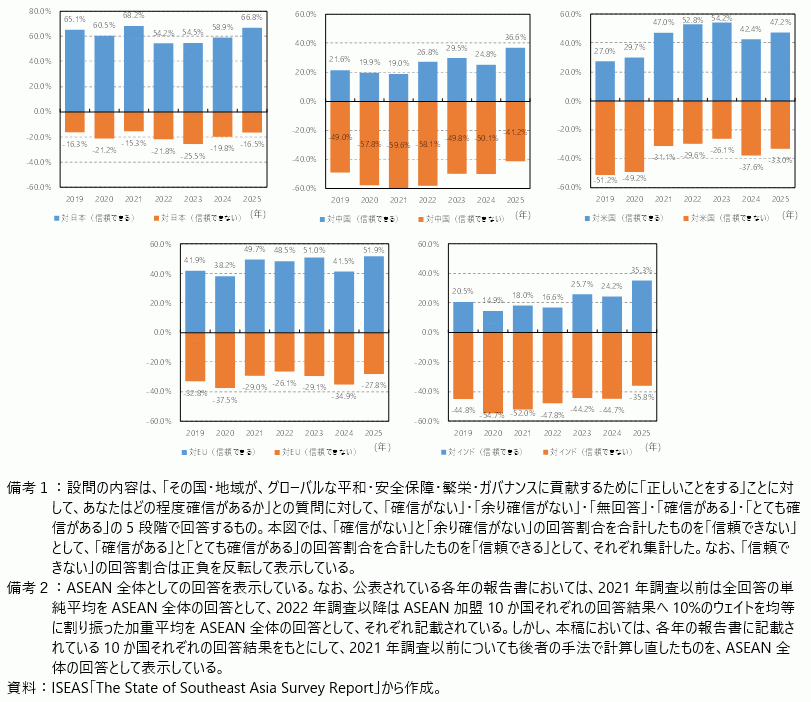
348 2025年調査では、ASEAN加盟予定国である東ティモールも初めて調査対象に追加された。ただし、人口や経済の規模の差異にかかわらず10か国の加盟国全てに百分の十の重み付けを付与したASEAN平均としての回答結果報告においては、東ティモールの回答結果は除かれている。
3. 今後のグローバルサウス諸国との協力:共創パートナーシップに向けて
ここまで、グローバルサウス諸国との協力の在り方を考える上での我が国の重要な経験として、日本が最も深い関係を構築してきたASEAN諸国との関係深化の経緯を見てきた。今後は、より広いグローバルサウス諸国との関係で、相手国が抱える具体的な社会経済課題に寄り添いながら、長期的なコミットメントの下に、協力関係の深化を模索していくことが重要である。以下ではその機会と課題を検討する。
(1) 日本企業のグローバルサウス諸国への進出状況
我が国企業は、前掲の第II-3-5-3表から分かるとおり、今や世界中に数多くの拠点を設置し、幅広く進出している。また、直近の事業拡大意向については、JETRO海外進出日系企業実態調査(全世界編、2024年度)349によると、インド、ブラジル、UAEなどの国々においてその意向が強く(第II-3-5-8図)、現地進出や事業展開において、幅広いグローバルサウス諸国を視野に入れている状況がうかがえる。
第Ⅱ-3-5-8図 日系企業の主要国・地域における事業拡大意欲
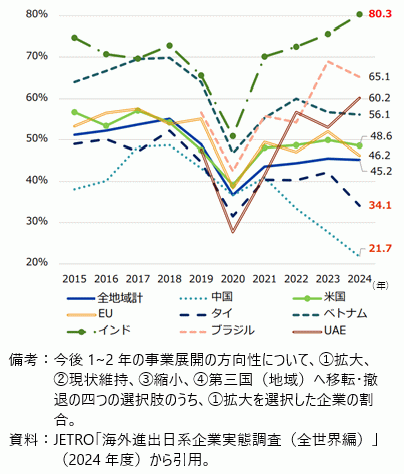
先述の我が国による技術・人材協力については、現地進出をしている日系企業からの要望をベースに実施されるAOTS事業はASEANを中心としたアジア地域が主な対象となっているが、JICAの実施事業はアジア以外の地域においても広く実績が蓄積されている。また、青年海外協力隊・海外協力隊派遣事業に関しては、中東・アフリカ、中南米、大洋州などの地域でも多くの実績を有しており、日本とそれら地域との人的交流・協力関係の基盤となっている(第II-3-5-5表)。
他方、日系企業が今後の事業を検討するグローバルサウス諸国の中には、これまで日系企業の進出の実績が多くなく、現地の情報や人的関係等が蓄積されていない国々も含まれている。そうした国々へ新規進出や技術・人材協力を行う際には、当該国と地理その他の面で近接していたり、既に深い人脈やビジネス上の関係を有していたりする第三国と協力して進出するという選択肢もある。その具体的な一例として、経済産業省では、2024年12月に開催された第3回日アフリカ官民経済フォーラムにおいて、日本企業のアフリカ進出を加速すべく、インド、中東、欧州などの第三国企業との連携強化を支援することを確認している。
349 JETRO (2024)。JETROの海外事務所ネットワークを活用して抽出した海外83か国・地域の日系企業(日本側出資比率10%以上の現地法人、日本企業の支店・駐在員事務所)18,186社を対象にアンケートを実施。7,410社より有効回答を得たもの。
(2) 受入留学生の出身地から見る日本とグローバルサウス諸国のつながり
グローバルサウス諸国との中長期的な人的関係を構築していく上で、受入留学生は一つの礎となり得る。ここで、日本の受入留学生の数と出身地を、アジアの中で多くの留学生を受け入れている中国と比較することで、その特徴を概観する。第II-3-5-9図は、日本と中国それぞれの受入留学生の総数とその出身地域の構成を示している。日本への留学生の総数は、コロナ禍の時期に一時的な減少が見られたが、その後は回復傾向にあり、直近の2024年では約34万人となっている。その出身地域の構成は、アジアが群を抜いて多く、例年おおむね9割強を占めている。アフリカは約2.7千人、中南米は約2.5千人、中東は約1.3千人、大洋州は約0.8千人と、それぞれ総数としては少数にとどまっている。中国への留学生を見ると、2000年から確認可能な最新データである2018年まで、ほぼ一貫して大きく増加しており、2018年には約49万人に達している。出身地域の構成を見ると、アジアの占める割合が最も大きく2018年においても約6割を占めているが、その割合は減少傾向にある。その代わりにアフリカの割合が増加しており、2018年時点で17%に達していることが注目される。
第Ⅱ-3-5-9図 日本と中国の受入留学生の総数と出身地域シェアの推移
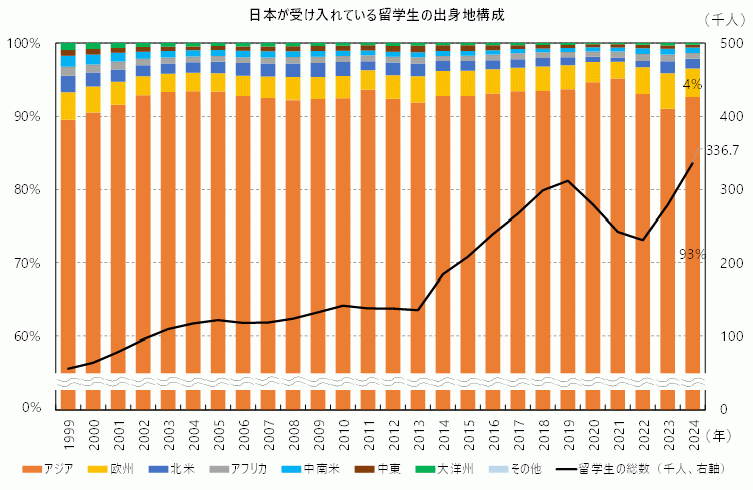
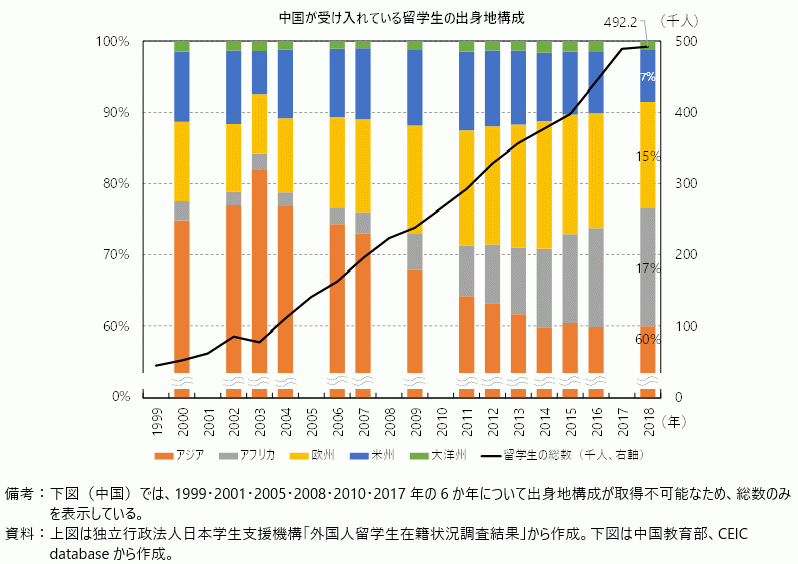
第II-3-5-10表は、日本と中国の受入留学生の出身国・地域の上位15か国を、それぞれ確認可能な最新年のデータで確認したものである。日中間で上位に入る国・地域に差異があり、日本にはネパール、ベトナム、ミャンマー、スリランカといった国々から、より多くの留学生が来ていることが分かる。ただし、絶対数としては中国が急速に受入留学生数を増やし、2000年代半ばには日本を越えてその差を広げてきており、グローバルサウス諸国との人的関係の強化が進んでいることを示唆している。
第Ⅱ-3-5-10表 日本と中国への留学生の出身国・地域
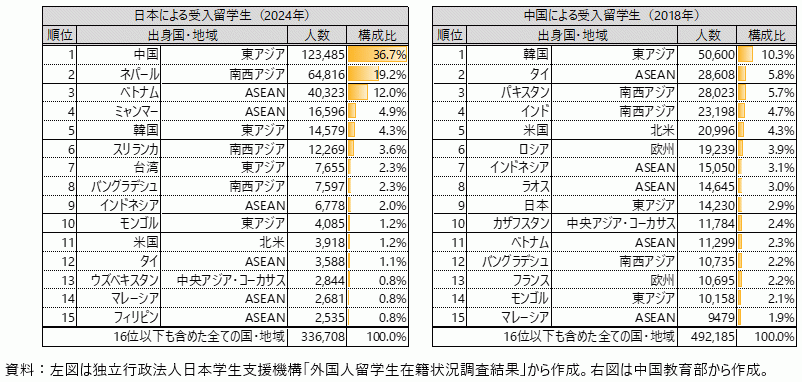
(3) グローバルサウス諸国の経済発展と社会経済課題の変化
先述のとおり、グローバルサウス諸国の実情は多様であり、今後の協力関係を考えるに当たっては、各国の個別の状況に応じた具体的な社会経済課題に、共創のパートナーとして連携して取り組む姿勢が重要になる。
例えばASEANでは、多くの加盟国が経済成長を実現しただけでなく、特にデジタル分野等でのイノベーションエコシステム創出拠点として魅力が高まっている。従来、ASEANは豊富な労働力などを背景として生産拠点としての魅力が大きかった。しかし、経済成長を背景として購買力が向上し、消費市場としての魅力が次第に高まっており、さらに現在では日系企業のイノベーションのパートナーともなるような多様なスタートアップが登場してきている。ASEAN諸国では、金融、交通・物流、医療など山積する社会経済課題の解決が求められていること、急速に成長するGDP、若者人口や中間層の拡大等が、活力あるエコシステムの裏側に存在している(第II-3-5-11表)。日本企業にとってASEANは、イノベーションを通じた共創という観点でも、その重要性が高まっているといえよう。
第Ⅱ-3-5-11表 ASEANのイノベーションエコシステム
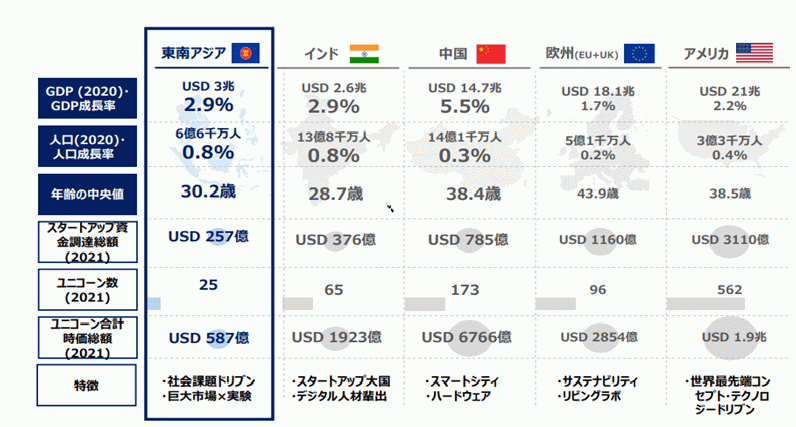
資料:JETRO「東南アジアにおけるイノベーション創造活動に関する調査」(2022年8月)350より引用。
350 JETRO (2022)
(4) ASEAN諸国とインドの産業政策の展開
グローバルサウス諸国は、それぞれの抱える現下の社会経済課題への対処に取り組んでいる。そうした各国の個別事情に対応した政策的な取組を理解し、パートナーとして協働していくことが重要になる。ここでは具体的に、ASEAN諸国とインドの産業政策の展開を見ることで、今後の共創の取組の可能性を検討する。
ASEAN諸国やインドは、近年、相対的に高い経済成長を実現してきたが、それぞれに、現下の国際環境や国内経済・産業構造の中で、産業発展に向けた課題を抱えている。これに対し、半導体などの成長分野を中心に製造業の高付加価値化を志向する国や、サービスやデジタル部門の発展、高度化を進める国など、政策対応は様々である。
インドネシアでは、国内の雇用創出に向けた外資規制の緩和や産業の高付加価値化政策がとられている。資源国であるインドネシアでは、ジョコ前大統領が、一次産品の高付加価値化を目指したコモディティの「下流化政策」を推し進めてきた。2020年には、世界的にも埋蔵量シェアが高いニッケルに関して、未加工での輸出を禁止する措置をとり、結果として中国から同産業への投資が流入した。その後、ニッケル加工品の輸出は急増している(第II-3-5-12図左)。さらに、2023年6月にボーキサイトの輸出を禁止とし、一次産品の対象範囲を広げたほか、2024年10月に発足したプラボウォ新政権も、2025年2月に発表した中期開発計画において、下流化政策を一層進める方針を示した。ただし、ボーキサイトや銅、石炭等への禁輸措置拡大は、国内の精錬能力不足もあって効果的な投資促進につながらない可能性があるといった指摘もある。
第Ⅱ-3-5-12図 インドネシアのニッケル輸出(左)とマレーシアの投資承認額推移(右)
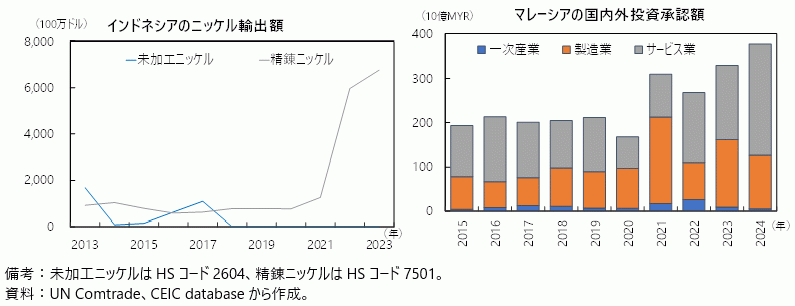
マレーシアでは、工業化とともに一定の経済発展を達成した中で、産業部門の高度化やデジタル経済等の次世代産業育成、さらに高度人材の呼び込みといった政策が打ち出されている。2023年には国家政策である「マダニ経済政策」及びその中核をなす「新産業マスタープラン2030」が発表された。半導体分野の高度化を目指すほか、高付加価値な雇用機会の創出やそれに向けた国家のデジタル化などに注力する。近年はこういった政策に基づく公共投資プロジェクトやデータセンターの需要増加等の追い風を受け、国内外の投資が急増している(第II-3-5-12図右)。2025年1月には、シンガポールとも経済特区設立に関して覚書を締結し、更なる投資拡大が期待されている。
フィリピンでは、脱工業化が急速に進む中、2023年初めに公表された「フィリピン開発計画2023-28」において、デジタル経済の促進やサービス業の振興が強調された。特に、近年拡大するビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)産業に代表される、製造業のサービス化に伴う需要を国内産業に取り込む考えである。また、ドゥテルテ前政権から続くインフラ投資の拡大は、マルコス現政権下でも続いている。投資のボトルネックとなっているインフラ整備を加速させるほか、2024年12月には、法人税の引下げや税制優遇等を盛り込んだ企業の優遇法案(CREATE MORE)を改正する等、外資誘致に向けた投資環境の整備を行っている。
タイでは、産業の高度化を目指した政策「タイランド4.0(2016年)」や「バイオ・循環型・グリーン(BCG)経済モデル(2021)」を打ち出したが、重点産業への投資の活性化には至っていない。2024年に発足したペートンタン新政権は、喫緊に取り組む課題として、高水準な家計債務問題の解決や景気回復等の10項目を発表した。中長期的観点から、裾野産業育成に向けた現地調達率の向上や、自動車産業のEVシフト、半導体やデータセンターといった注力産業にも言及したが、足下では景気回復に向けた現金給付等の財政出動が優先され、構造改革の機運は後退している。
シンガポールでは、少子高齢化や交通問題、経済成長の鈍化といった構造的な課題の解決に向け、2014年にリー首相が打ち出した「スマートネーション」政策に基づく経済のデジタル化推進が進められている。2017年に当該政策の旗振り役となる「スマートネーションデジタル政府オフィス(SNDGO)」が設置されて以降、国民デジタル認証システムの導入や電子決済の普及、デジタル技術を活用した公共交通機関の高度化等が進められてきた。結果として、デジタル経済の付加価値(情報通信部門及びその他部門のデジタル化に伴う付加価値創出額)は急速に拡大し、2023年にはGDP比17.7%と、金融や保険部門、製造業に匹敵する産業となっている。2024年5月に就任したウォン首相は、10月に当該政策の第二段階として「スマートネーション2.0」を発表した。信頼性の向上(Trust)、個人と企業の成長(Growth)、コミュニティの団結(Community)の3点に重点を置き、とりわけAIの更なる導入と活用や、新たなデジタルインフラ法制定によるオンラインの信頼性強化に取り組む方針が示されている。
ベトナムでは、2045年の高所得入りを目指し、更なる工業化やイノベーションの促進を図っている。2024年には、ターゲット産業としての長期的な半導体産業育成に向けたロードマップを公表し、半導体産業を主軸に更なる工業化を進める方針である。新たに共産党トップに就任したラム氏は、汚職の摘発や省庁の再編に着手し、投資誘致のボトルネックとなっている非効率な行政の改革を図っている。近年は特に、米中間の貿易摩擦を背景とする中国からの生産移管の受け皿の一つとなってきた(第II-3-5-13図左)。2023年には米国との外交関係を包括的戦略的パートナーシップへ格上げした。ベトナム政府は半導体産業への投資拡大を目指している。今後も高い経済成長の見通しや貿易摩擦回避の動き等を背景に投資の流入が期待されるが、対米貿易黒字拡大による米国との貿易摩擦が懸念されている。
インドでは、モディ首相の「Make in India」政策の下、雇用創出に力点をおいた製造業促進政策が展開されている。2020年に発表した生産連動型インセンティブ(Production Linked Incentive)では、自動車や電子機器・部品等の14業種に対して、投資や売上の一部に対する補助金の支給といった優遇措置がとられているほか、2021年には半導体分野への重点投資を目的とした「半導体ミッション」を立ち上げた。足下では当該品目への投資や輸出拡大が見られるなど、政策効果が一部出始めている(第II-3-5-13図右)。一方で、関税を含めた保護主義的な政策が多用されるなど、政策面の不確実性が高いほか、インフラの未整備や企業ガバナンスへの懸念等、ビジネス環境を不安視する向きも多く、こうした問題の解決が加速していくかどうかが注目される。
第Ⅱ-3-5-13図 ベトナムの米中輸出入シェア(左)とインドの半導体輸出(右)
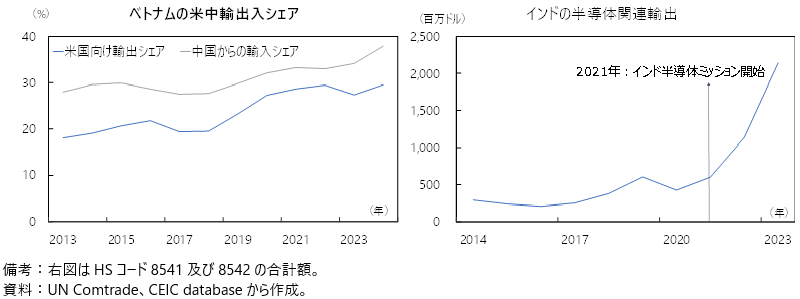
このように、ASEAN諸国やインドは、それぞれの発展段階や産業構造を踏まえ、貿易摩擦の激化やサプライチェーンリスクの高まり、一段と加速するデジタル分野の革新やグリーン移行といった社会経済的課題に対処しつつ、より高度な経済構造に移行することを目指している。
(5) 今後のグローバルサウス諸国との協力の方向性
上記を踏まえ、今後のグローバルサウス諸国協力の可能性を、ASEAN諸国を例に考える。ASEAN諸国が共通に抱える経済社会課題の中でも、炭素中立の実現に向けた取組が注目される。多くのASEAN加盟国は炭素中立の実現を目標として表明しているが、その電源構成を見ると、ラオスやカンボジアなど水力発電の比率が高い国を除いて、電力の大宗を石炭・天然ガスなどによる火力発電に頼っている。各国の経済成長に伴い更に電力需要が拡大する中で、現実的な形で着実に取組を進めることが必要となる。
こうした状況を踏まえ、2022年1月、岸田総理大臣が、アジア各国が脱炭素化を進める理念を共有し、エネルギー移行を進めるために協力することを目的として、AZEC351構想を提唱した。翌2023年3月にはAZEC閣僚会合が開催され、脱炭素化に向けて、各国の事情に応じた多様かつ現実的な道筋を実現することなどを確認した共同声明が発出された。2024年12月に初めて開催されたAZEC首脳会合では、脱炭素に向けた基本原則に加えて、ERIAにアジア・ゼロエミッションセンターを設立することなどに合意した。その後、工業団地のグリーン化や再生可能エネルギーを用いた発電など、具体的な協力案件が数多く進行している。
こうした取組は、ASEAN諸国との関係だけにとどまるものではない。これまで日本がグローバルサウス諸国と構築してきた深い結び付きや、日本が獲得している強い信頼感をいかしながら、今後は各国の有する成長力と日本の高い技術力を梃子として、長期的なコミットメントの下に、経済社会課題を共に解決し将来の成長につなげていく「共創」を展開していくことが重要である。
そうした取組の一環として、経済産業省はグローバルサウス未来志向型共創等事業を実施している。これは、グローバルサウス諸国の抱える個別の課題を共に解決する共創を通じて、当該地域の成長力をいかし、日本企業の市場獲得や日本国内のイノベーション創出、サプライチェーン強靱化などを同時に実現するためのものである。詳細は第Ⅲ部第2章第3節で述べるが、この事業において、数多くのグローバルサウス諸国での協力プロジェクトが進行している。
351 豪州、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの11か国によって構成される。