近年、国際政治経済構造は急速に変化しており、ルールベースの国際経済秩序を揺るがしている。特に、保護主義の台頭や地政学的リスクの増大、デジタル経済化の進展など、さまざまな要因が不確実性を高めている。このような状況下で、我が国は持続可能な経済成長を実現するために、戦略的な通商政策を展開する必要がある。
通商政策の一義的な目標は、我が国企業の海外展開支援や我が国企業が活躍する環境・ルール整備、その基盤としての諸外国との経済関係の強化等を通じ、「世界の課題解決を通じて我が国の世界における付加価値を最大化すること」である。
我が国の世界における付加価値を最大化するに当たり、まず重視すべきKPI(Key Performance Indicator: 重要業績評価指標)は、貿易・サービス輸出額及び対外直接投資収益である。我が国の輸出額は、2024年時点で財が約107兆円、サービスが約35兆円であるが、世界のサービス貿易の拡大や我が国の今後の産業構造を考えれば、輸出におけるモノとサービスの融合を含むサービス付加価値の重要性をより認識し、輸出拡大に取り組む必要がある。
また、対外直接投資については、その収益が国民所得につながり、国内投資とも両立し得るものとして一義的には企業の戦略的判断に任せるべきものであるが、日本が保持すべき高付加価値機能の海外流出は政策的に懸念すべき動きでもあり、対外直接投資について政策的に支援する上では、その内容が重要となる。政策的支援を行う対象としては例えば、①先進的なビジネスやイノベーションが行われている海外で日本企業が事業を展開することで、日本企業の高付加価値化を実現する(国内外の投資一体として競争力のあるバリューチェーンを構築)、②経済安全保障やエネルギー政策等の観点から必要な海外投資等を行う、③他国・地域とのウィンウィン(Win-Win)の戦略的関係を構築するという外交上の要請に応えるための重要なツールとして海外投資等を行うものが考えられる。
さらに、高付加価値型の経済・産業構造の実現に向けた輸出・海外展開等の促進といった観点から、交易条件(輸出物価/輸入物価)の改善も重要である。我が国の交易条件は過去30年において悪化傾向にあり、高付加価値産業の輸出先確保や海外のイノベーションの取り込みといった交易条件の改善に向けた取組が必要である。
加えて、国際情勢が厳しさと複雑さを増す中、経済安全保障の確保がますます重要になってきている。重要な資源・物資の安定供給の確保・調達源の多様化などによりサプライチェーンの強靱化を進め、特定の国・地域に過度に依存しない対外経済関係を確保すること(自律性の確保)や、生成AIや量子、バイオテックなどの分野で破壊的技術革新が加速している中、我が国の優位性、不可欠性を活用した事業の海外展開を戦略的に推進することで、諸外国の社会課題解決等に貢献すること(不可欠性の確保)は、「我が国の世界における付加価値を最大化する」上での重要な基盤である。
本白書では、このような通商政策の目標を達成していく上で、以下の三つの視点から我が国の通商政策の方向性を示す。第一に、保護主義の台頭を踏まえた国際経済秩序の揺らぎへの対応について、第二に、海外活力の取り込みに向けた輸出先の確保とグローバルサウス諸国・同志国との共創について、第三に、サプライチェーン強靱化に向けた内外一体の経済政策について、それぞれの課題と具体的な取組を詳述する。
これらの視点を通じて、我が国が直面する対外経済関係の課題に対処し、持続可能な経済成長を実現するための戦略を明確にする。特に、グローバルサウス諸国や同志国との共創を通じて、新たな市場を開拓し、経済成長を支えるための施策を概観する。また、サプライチェーンの強靱化を図るための国際協調や国内施策の重要性についても言及する。
第1節 保護主義の台頭を踏まえた国際経済秩序の揺らぎへの対応
近年、米国一強から多極化する国際秩序、各国政治の内向き化、格差拡大などを背景とするグローバル化や既存の国際枠組みに対する不満などにより、国際経済秩序が揺らいでいる。こうした中で、経済安全保障上の懸念を理由とするものも含め、関税、輸出管理等の貿易制限的措置が増加している。また、保護主義的な貿易措置だけでなく、各国内の産業政策において国内産品を優遇するなど、市場の分断を招きかねない自国第一主義的な政策が増加している。
無秩序なパワーベースの国際競争に陥った場合、人口減少が進み、多くの資源・エネルギー・食料供給を海外に依存するという構造的な制約を抱える我が国は非常に厳しい立場に陥るため、ルールベースの国際経済秩序を再構築することが極めて重要である。
一方で、ルールベースの国際貿易システムの中核を担ってきたWTOは、ルール形成機能の停滞や紛争解決制度の機能低下により、市場歪曲的措置等の新たな課題に十分に対処できないだけでなく、保護主義に対する抑止力が低下し、国際的なルールに対する規範意識の後退が懸念されている。さらに、多極化する国際社会の中で、BRICS等が新興国・途上国の意見を国際的に糾合して影響力拡大につなげる動きを見せる一方、G7等の第二次世界大戦後の自由主義的な国際秩序を牽引してきた枠組みは影響力が低下しつつある。
このように、自国第一主義が進み、 WTOを始めとした従来のルールベースの国際経済秩序が十分に機能していないという足下の現実の中で、着実に海外に高い付加価値を提供しながら重要な資源・物資を調達するといった通商政策目標を達成するためには、強かな経済外交が求められる。
1. 多層的な経済外交の展開
上述のような国際情勢認識の下、我が国の生存領域を確保する観点から、基本戦略として、多層的な経済外交を展開することが重要である。多層的な経済外交の展開に当たっては、以下を中心とした取組が必要となる。
(1) 相手国とのウィンウィンの関係構築
近年、米中対立、ロシアによるウクライナ侵略、中東紛争を始めとする地政学リスクが高まっている。また、各国の国内選挙において極端な主張を持つ勢力が躍進しており、自国第一主義・保護主義の影響力が強まり、各国の政権運営が困難になるなど、国際情勢が大きく変化している(第III-1-1-1図)。
第Ⅲ-1-1-1図 各国・地域の選挙動向
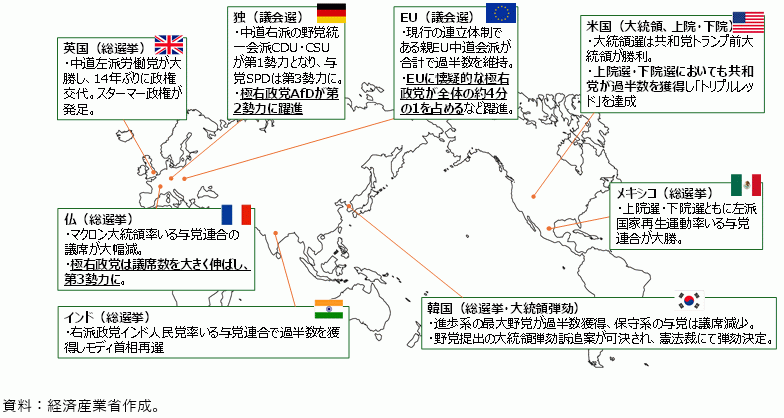
こうした中、二国間及び多国間において対話を粘り強く進め、公正な貿易政策を推進しつつ、経済安全保障を確保し、各国とのウィンウィンの関係構築を目指すことが重要である。
例えば、我が国企業が相手国に対して積極的な投資を行い、相手国の経済成長や雇用に貢献すると同時に、現地市場や資源へのアクセスを確保することが考えられる。こうしたウィンウィンの関係を積み上げ、長期的な関係構築を進めていくことが重要である。これにより、相手国との信頼関係を強化し、安定した経済関係を構築することができる。
(2) 同志国との連携と政策・制度の調和
特定のイシューに応じて、価値観を共有する同志国と連携し、政策や制度の調和を進めることが重要となる。
具体的には、2022年1月、岸田総理大臣が、施政方針演説において、アジア各国が脱炭素化を進めるとの理念を共有し、エネルギー移行を進めるために協力することを目的として提唱されたAZEC(アジア・ゼロエミッション共同体)では、各国の事情に応じた多様な道筋で、現実的かつ着実にアジアの脱炭素化を進めていく必要性を共有し、AZECの枠組みを通じて、我が国の多様な技術やファイナンスを活用し、世界の脱炭素化に貢献していくこととしている。
また、経済安全保障分野に関しても、2024年のG7サミットで、非市場的政策・慣行やそこから生じる過剰生産能力問題への対応、経済的威圧への対処、サプライチェーン強靱化等に向けて、G7での連携を進めることで一致している(第III-1-1-2図)。この一致の下、経済的威圧に対する強靱性を構築すべく、WTOを含めた外交的な取組や国際協力を強化するとともに、G7を超えたパートナーと共に、「G7経済的威圧に対する調整プラットフォーム」も含め、潜在的な事案、発生しつつある事案、進行中の事案に対処している。同時に、サプライチェーン強靱化については、透明性・多様性・安全性・持続可能性・信頼性から成る「強靱で信頼性のあるサプライチェーンに関する原則」を、G7を超えたパートナーとともに実施し、経済的要因のみならず上記の原則に関する要因も考慮した基準について、G7内での連携を追求している。加えて、国家安全保障上の重要性を踏まえ、インド太平洋地域の同志国と連携し、自律性のみならず、AI・デジタル基盤等の不可欠性確保に向けた連携強化を図っていくことが重要である。
第Ⅲ-1-1-2図 2024年のG7サミットでの一致内容
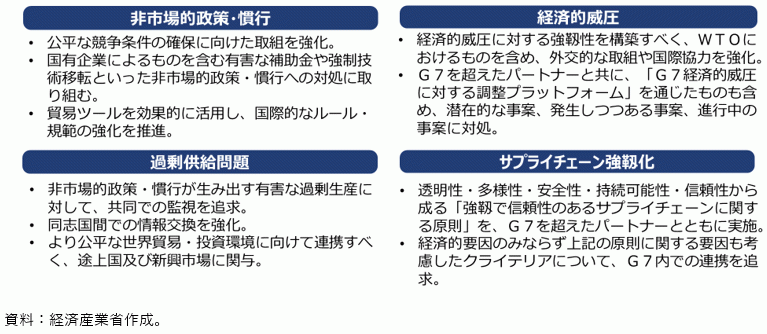
さらに、同志国との連携を強化するためには、定期的な対話の場を設けることが重要である。例えば、定期的な首脳会談や閣僚会議を通じて、政策や制度の調和を図ることが求められる。また、共同プロジェクトを通じて、具体的な成果を上げることで、同志国との信頼関係を強化することができる。
(3) ルールベースの国際経済秩序の維持・強化・再構築
ルールベースの国際経済秩序を維持・強化し、再構築するための取組を進めることが重要である。これには、WTO改革や新たな国際ルールの策定が含まれる。昨今、WTOの機能低下が指摘されているが、こうした中でも粘り強く、ルールに基づく多角的貿易体制の維持・強化に向け、WTOの交渉機能、審議・監視機能及び紛争解決機能の回復・強化に取り組むことが重要である。
具体的には、WTOの交渉機能については、現代の貿易課題に対処する新たなルールを実現するため、投資円滑化協定や電子商取引に関する協定など、有志国間での交渉を推進し、その合意をWTOの法的枠組みに早期に組み込むための取組を進める。WTOの審議・監視機能については、各国の協定履行状況を監視し、各国措置の協定整合性を明確化し、必要な是正を要求していく。また、「貿易と産業政策」、「貿易と環境」といった新たな課題についての加盟国間の議論を活性化していく。紛争解決機能については、第二審(上級委員会)の機能が停止していることを踏まえ、引き続き加盟国間で紛争解決制度改革の議論を進めるとともに、改革実現までの間の暫定的な対応として、MPIA(多数国間暫定上訴仲裁アレンジメント)352への参加メンバー拡大などを模索していく。
EPA(経済連携協定)等を通じた新たな国際ルールの策定も重要である(第III-1-1-3図)。具体的には、CPTPPの一般的な見直しにおいて、サプライチェーン強靱化等の現代的な課題に対応できるよう、協定のアップグレードを図り、他の経済連携協定と比較して高水準かつ最先端の通商ルールを実現する「ゴールドスタンダード」として、世界のルール形成を主導していく。CPTPPへの新規加入については、①高水準なルールの維持を大前提とし、②それらエコノミーの貿易に関する約束の遵守状況(トラックレコード)を考慮しながら、③締約国の全会一致で対応していくというオークランド原則を満たすことを前提としつつ、高水準のルールの適用拡大を目指すとともに、透明性のある履行を確保していく。
第Ⅲ-1-1-3図 日本の経済連携の推進状況(2025年3月現在)
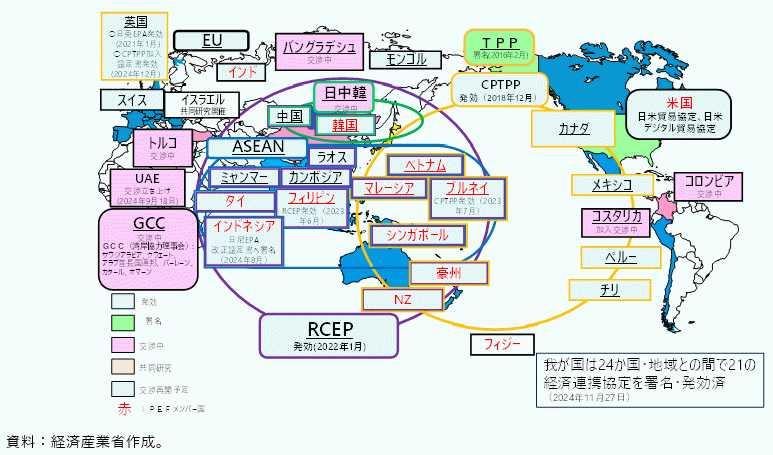
352 第2章第2節第3項参照。
(4) グローバルサウス諸国との経済関係の強化
上述のような多層的な経済外交の実施に当たっては、経済成長が期待されるグローバルサウス諸国を取り込み、経済関係を強化することも重要な課題である。
グローバルサウス諸国は、人口増加や経済成長が期待される地域であり、今後の世界経済の成長エンジンとなる可能性がある。我が国は、これらの国々との経済関係を強化し、新たな市場を開拓することが重要である。
グローバルサウス等における我が国企業の市場獲得・競争環境を有利にすべく、貿易・投資関係の強化を通じたサプライチェーン強靱化やEPAの重要性を認識し、新興国等とのEPA交渉や、アフリカ・南米・中央アジア諸国等との投資協定交渉を推進するとともに、発効済の協定を着実に履行していくことが必要である。
また、国家安全保障上のインド太平洋地域の重要性を踏まえ、自律性のみならず、AI・デジタル基盤等の不可欠性確保に向けた連携強化を図っていく。
2025年2月現在において、我が国は、現在、82の国・地域との間で54本の投資関連協定を発効済であり、3本が署名済となっている。さらに、交渉中のものを含めると、96の国・地域をカバーしている(第III-1-1-4図)。こうした取組を通じ、グローバルサウス諸国との一層の関係構築を推進していく。
第Ⅲ-1-1-4図 日本の投資関連協定の締結状況(2025年2月現在)
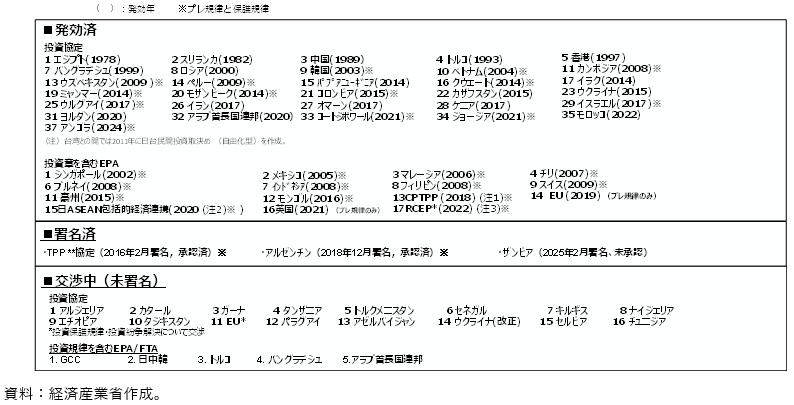
また、我が国企業の「勝ち筋」が見える国・分野等を念頭に、優先度に応じて戦略的かつ集中的に、グローバルサウス諸国への事業展開に関するマスタープラン策定や実現可能性調査(FS)、実証事業の支援を実行し、我が国と相手国双方の経済成長や社会課題解決に貢献していく観点も重要となる。グローバルサウス諸国は、2050年には全人口の3分の2を占める成長力の高い市場であり、重要鉱物資源等の経済安全保障上の重要なパートナーである。インドが主催し約120か国が参加した「グローバルサウスの声サミット」に見られるような国際秩序形成における一定の発信力を持つ動きもある。こうした位置付けを踏まえ、またそれぞれのグローバルサウス諸国が置かれた状況の多様性を前提として、グローバルサウス諸国との関係の方向性についてまとめた、主要な地域別戦略の概要を次項において整理する。
2. グローバルサウス諸国をめぐる地域別戦略の方向性
グローバルサウス諸国をめぐっては、様々な国が関係性を強化すべく競争が発生しており、日本としても各地域・国との経済関係を強化していくことが重要である。
(1) アジア大洋州
同地域は、東南アジアを中心として特に日本企業が投資と協力を積み重ねてきた地域であり、累積投資によって形成されたサプライチェーンを最大限活用し、日系製造業の競争力を維持・強化していくことがまず重要である。また、脱炭素化の実現に協力しつつ資源の安定調達を確保しながら、相手国ニーズに応じたインフラ開発協力によって成長ポテンシャルを取り込み、社会課題に対応するイノベーションやビジネスモデルを共創して、市場を確保していく。さらに、経済安全保障の観点から、インド太平洋地域における信頼できるAIエコシステムの構築のため、同志国・同盟国等との連携を推進する。
(2) 南西アジア
同地域は、日本企業にとってビジネスの潜在的機会が豊富な地域であり、日本やASEANを上回る経済規模(4.4兆ドル)と、世界の4分の1を占める人口(約18.8億人)の大市場である中で、日本企業の営業利益見込や黒字割合・シェアは増加している。ただし、企業からの関心は高まっているものの、政策の不透明さや市場の特殊性について企業から懸念の声があり、政策による案件組成後押しや、政策対話の場を活用したビジネス環境の改善の働きかけが必要である。中長期的には、経済安全保障、産業多角化の観点から経済連携強化を検討していく。さらに、経済安全保障の観点から、インド太平洋地域における信頼できるAIエコシステムの構築のため、同志国・同盟国等との連携を推進する。
(3) 中東
同地域は、ロシア産原油・ガスに対して米欧が制裁措置を科している中でも原油・ガスを安定的に供給できる地域であり、エネルギー安全保障の観点から非常に重要である。また、化石燃料のみならず、脱炭素エネルギーでも重要なパートナーであり、ASEANと同等のGDP規模など、新興国としての潜在力も大きく、イノベーションや新しいビジネスの実験場としての側面もある。同地域との歴史的に良好な関係を最大限に活かし、各国の国づくりや地域全体の経済発展への貢献を通じて、同地域の安定とビジネス機会の拡大を実現していく。
(4) アフリカ
同地域は、若年層を中心とした人口増加や世界平均よりも高い経済成長率という成長力の高い市場であり、重要鉱物を始め豊富な天然資源を有する経済安全保障上重要な地域でもある。また、人口増加や豊富な天然資源に裏打ちされながら、国際場裡における発言力を高めており、自由で開かれた国際秩序形成において重要な発信力を持つという観点からも重要である。特に資源については、政府が相手国との対話の機会を率先して設けることで日本企業の関心を高めていく必要があり、同時にODAや人材育成など包括的な関係構築を通じた企業投資の環境づくりが必要であることから、こうした取組を通じて同地域の資源国との長期的な関係を構築し、将来的な日本企業の参入機会の拡大を図る。
(5) 中央アジア・コーカサス
同地域は、ロシアのウクライナ侵略等の影響を受け、地政学や経済安全保障面での重要性が増加すると共に、市場の潜在性や連結性の観点からも重要な地域である。同地域における、経済の外部依存、弱い連結性、不十分な社会資本・制度整備といった経済構造上の課題を共に解決するために、GX(グリーン・トランスフォーメーション)等での産業高度化やDX(デジタル・トランスフォーメーション)等を活用した連結性強化・社会課題解決、人材育成・社会制度整備における協力を進め、同地域の成長の取り込みや、相互連結性の強化を目指す。
(6) 中南米
同地域は、安定的な人口増加に加えて労働生産人口比率も高く、海外日系人の約6割が居住するといった特徴を持っている。市場規模がASEANの約1.8倍と経済成長の潜在力が高く、鉱物資源供給大国が多い地域である。喫緊の課題としては、米国の関税措置といった既存の産業やサプライチェーンに対する急激な変化が起こり、北米向け自動車産業の対応の必要性が生じている。また、中長期的には、資源への更なるアクセス確保を目指すと同時に、同地域の一次産品輸出に依存するモノカルチャー経済の傾向といった課題の解決も見据えCN燃料(バイオ燃料、合成燃料(e-fuel))、次世代自動車といったGX領域や、防災、農業、医療といったDX領域において、協力を推進していく。
3. インテリジェンス機能の強化
めまぐるしく変化する国際情勢を適時・適切に把握し、海外市場の獲得、経済安全保障の強化などを達成するためには、インテリジェンス機能の強化も不可欠である。
地政学的状況、主要国の内政状況等に関する情報分析と共有の在り方、有効なインテリジェンスの方法論・戦略、国内外の行政機関への働きかけの方法論・戦略等の検討を行う。それを踏まえ、今後、JETROなどの海外拠点の調査・働きかけ機能を強化しつつ、我が国企業との連携を図り、適切な経済産業政策の立案や我が国企業の活動促進のための、我が国全体の国際情勢に関するインテリジェンス機能の強化に向けた検討を行う。この際、経済安全保障分野において、効果的な経済安全保障施策の立案・実行のために進めている経済インテリジェンス強化に係わる取組とも連携を図っていく。