第3節 サプライチェーン強靱化に向けた対外経済政策
近年、地政学的リスクや自然災害、パンデミックなどの影響により、サプライチェーンの脆弱性が顕在化している。特に、新型コロナウイルス感染症拡大は、世界中のサプライチェーンに大きな混乱をもたらし、各国が自国の供給網の脆弱性を再認識する契機となった。我が国は資源・エネルギーや戦略物資の多くを海外に依存しているため、サプライチェーンの強靱化が急務である。
また、過剰生産能力や非市場的な政策・慣行を背景とした特定国からの製品・原材料の輸入増によって、同国への非対称な依存が進めば、それ自体がサプライチェーンの脆弱性となるのみならず、こうした依存関係が武器化され、経済的威圧を受けるリスクも生じる。こうした観点を踏まえ、特定国への過度な依存を避けるための対策が求められる。
1. サプライチェーン強靱化に向けた国際協調・連携の推進と国内施策の検討
サプライチェーンの強靱化を図るためには、同志国間での国際協調・連携が不可欠である。以下のような取組が求められる。
(1) 関税措置を踏まえた支援
米国の関税措置について、その対象から我が国を除外することを求めていくとともに、我が国の産業・雇用を守り抜くため、その影響を評価し、必要となる国内対策を速やかに実行に移すため、「米国関税対策本部」を経済産業省に設置した。また、短期の対応として、各地の経済産業局、政府系金融機関、商工団体、中小機構等に特別相談窓口の設置を行った。さらに、関税影響を受けた中小企業のセーフティーネット貸付けの利用要件の緩和、官民金融機関に対し影響を受ける中小企業の相談に丁寧に応じるよう要請、NEXIを通じた海外子会社への融資に対する保険の付与、関税措置に起因した損失をNEXI輸出保険のカバー対象にする等、資金繰り・資金調達支援を実施している。加えて、地域の中堅・中小自動車部品サプライヤーに対して経営アドバイスや施策紹介等を行う「ミカタプロジェクト」や、設備投資等に対する支援策(ものづくり補助金、新事業進出補助金の優先採択)を展開している他、サプライチェーンにおいて適切な価格転嫁が阻害されないよう、関係業界に対し要請を行う等、具体的な支援策を実施している。
(2) 非価格基準による需要喚起
過剰生産能力や特定の国への過剰依存といった課題に対応するため、 G7等の多国間や二国間の枠組みを通じて、同志国間での産業政策面の協力を戦略的に推進することが重要である。
特に、非価格価値を持つ製品が市場で正当に評価されるよう、需要サイドの政策ツールへの非価格基準の導入を更に進める必要がある。具体的には、EV(電気自動車)、蓄電池、重要鉱物、半導体といった重要物資を、民間企業、消費者、政府などの需要家が調達する際に、政府が講じる補助金、促進税制、政府調達といった政策ツールに対して、調達先の多角化などの安定供給、サイバーセキュリティ対策、脱炭素への貢献といった非価格基準を評価基準として導入することで、単に価格のみで物資が選定されないようにするものである(第III-1-3-1図)。
第Ⅲ-1-3-1図 需要サイドへのアプローチ
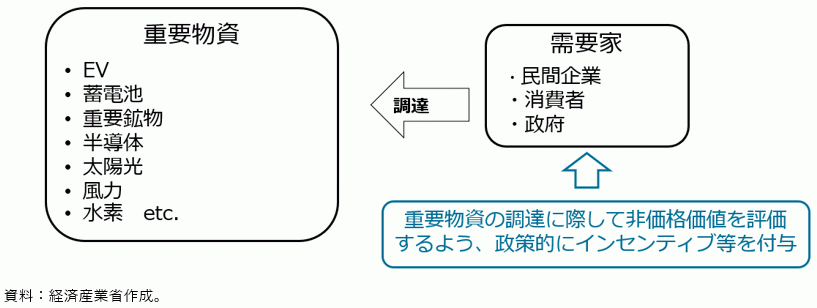
こうした考え方について、2024年のG7プーリア・サミットでも、以下のとおり合意した。
「過剰生産に起因するものを含め、経済的強靱性には多様化及び重大な依存関係の低減を通じたデリスキングが必要であることを認識しつつ、我々は、「強靱で信頼性のあるサプライチェーンに関する原則」、すなわち透明性、多様性、安全性、持続可能性、信頼性を実施する。我々は、経済のダイナミズム及び開放性を維持しつつ、G7内及びG7を超えて、パートナー及び民間部門に積極的に関与することによってこれを行う。我々は、官民の部門に対し、需要と供給の両方において、戦略的物品のサプライチェーン強靱性を強化するための連携した取組を行うよう促す。これは、経済的要因のみならず上記の原則に関する要因も考慮した、関連する基準についてのG7内での将来の連携のために、重要物品、戦略的部門及びサプライチェーンを共同して特定することを追求することを含む。」
また、こうした非価格基準の導入は、同様の基準をグローバルに広げていくことが重要であり、同志国との政策協調による非価格基準の調和を実現するため、AZEC等の国際枠組みやグローバルサウス向けの諸政策を通じて、グローバルサウス諸国との連携も目指していく。
(3) 経済安全保障対話
同志国との間で経済安全保障に関する対話を強化し、サプライチェーンの脆弱性に対する共通の認識を持つことは重要である。また、同志国政府等の関係機関と連携し、第三国に対する啓発や能力構築(キャパシティビルディング)などに対する協力を進めていくことも重要である。
こうした観点から、非価格要素を考慮する重要性の啓発(公正市場アプローチ)等に関するグローバルサウス向け研修などの事業を実施する(第III-1-3-2図)。
第Ⅲ-1-3-2図 米国等第三国との協力によるグローバルサウス向け啓発事業
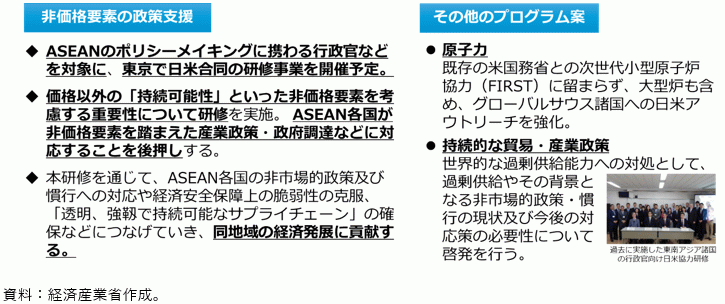
こうした研修を通じて、同志国の非市場的政策及び慣行への対応や経済安全保障上の脆弱性の克服、「透明、強靱で持続可能なサプライチェーン」の確保などにつなげ、同国・地域の経済発展に貢献する。
(4) サプライチェーン上の人権尊重の取組促進
欧米では、企業に対してサプライチェーン上の人権尊重を求める法規制の導入が進展している(第III-1-3-3図)。日本政府としては2022年9月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(「政府ガイドライン」)を策定し、企業に人権尊重の取組を求めているが、企業の取組を促すためのアプローチは様々であり、企業が予見可能性を持って国際スタンダードに則った人権尊重に取り組めるようにすることが重要である。このため、G7・OECD等を活用した加盟国との議論、「サプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関する日米タスクフォース」における議論等を通じて、各国との情報共有など国際協調を進める。
第Ⅲ-1-3-3図 人権に係る欧米の関連法規制の動向
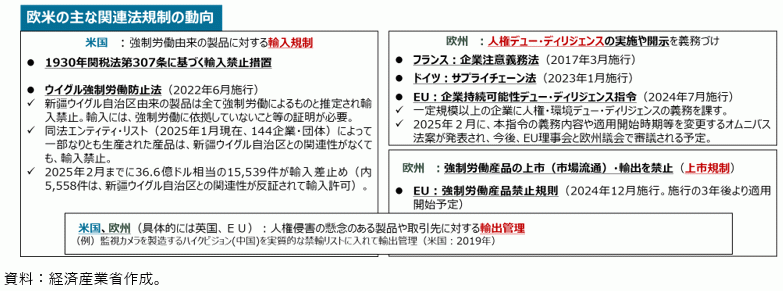
我が国企業の取組状況としては、業界団体によるガイドライン等の策定も進み、人権尊重の取組を進める企業は着実に増加している。一方、企業規模で見ると取組状況に差がある。また、取組を進めている企業も、一社・企業だけでは解決できない複雑な問題がある、サプライチェーンの構造が複雑・膨大であり、課題の特定が難しいといった、サプライチェーン全体で取組を実践することの難しさに課題を感じているとの調査結果が出ている(第III-1-3-4図)。
第Ⅲ-1-3-4図 人権に係る日本企業の取組状況
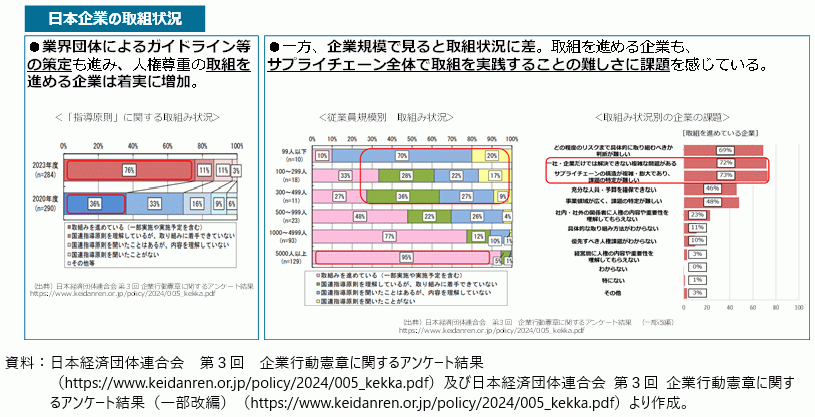
我が国企業がサプライチェーン上の人権尊重の取組を適切に進めながら国際競争力を維持・強化できるよう、政府ガイドラインの更なる普及・定着に向け、中小企業や海外取引先を含めた企業への取組支援、企業の取組状況を客観的に評価する仕組みの検討等を推進する。
(5) 規制的アプローチの検討
諸外国に先んじた規制的アプローチを検討し、サプライチェーンの強靱化を図ることが重要である。EUを中心として規制的なアプローチにより国際的なルール形成を主導する動きがあるが、2024年のドラギレポート354の発表など、最近ではEUの競争力強化を重視し、再評価・規制緩和に向けた動きも見られる(第III-1-3-5図)。我が国としても、こうした動きに先んじ得る適切な規制的アプローチを追求していく。
第Ⅲ-1-3-5図 EUの主な規制的アプローチの動向
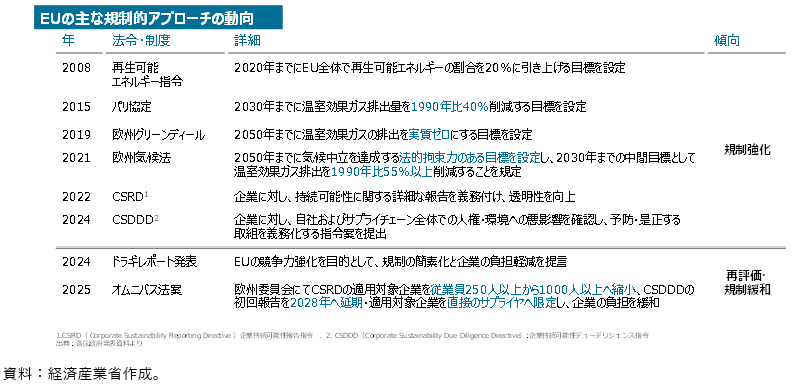
354 第Ⅱ部第1章第5節参照。
2. 国際協力枠組みの拡大・強化
サプライチェーンの強靱化を図るためには、同志国連携を進める国際協力枠組みの拡大・強化が不可欠である。サプライチェーンの強靱化に向けて、多国間や二国間での協定等に基づく協力を推進していくことが重要である。
同志国間での連携は、地域協力枠組みである、IPEFサプライチェーン協定、日米豪印などの枠組みや、セクター別の枠組みである、鉱物安全保障パートナーシップ(MSP)、強靱で包括的なサプライチェーンの強化(RISE)に向けたパートナーシップ、バイオに関する日米韓印EU会合(Bio-5)などを通じて進めている(第III-1-3-6図)。
こうした枠組みに基づく同志国連携は、サプライチェーンの脆弱性を特定し、特定国に依存しないサプライチェーンの構築などの平時の協力に加えて、危機対応メカニズムの構築や机上訓練等を通じた危機対応における協力の円滑化といった危機時の協力も進めている。また、CPTPPの一般的な見直しの機会において、サプライチェーン強靱化に対応できるよう、透明性・多様性・安全性・持続可能性・信頼性の原則と他のフォーラムからの教訓に基づき、協定のアップグレードを図っていく。
第Ⅲ-1-3-6図 有事の対応も含めた国際協力枠組み
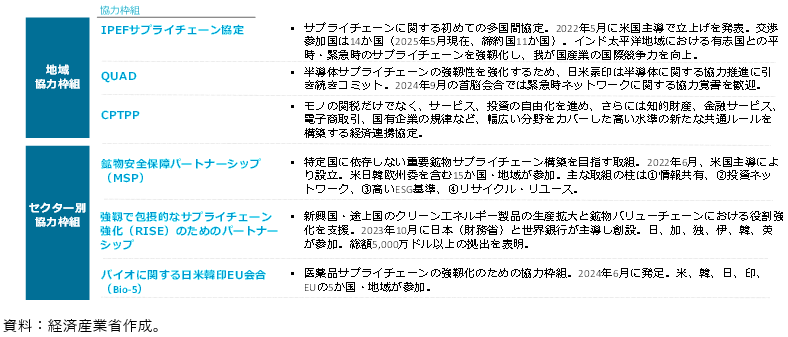
今後も、こうした枠組みに基づく同志国連携を強化していくとともに、同志国との二国間協力を含め、協力枠組みの拡大・強化を進めていく。
3. 我が国企業の海外展開支援
サプライチェーン強靱化を図るためには、特定国への輸入依存度が高い物資の供給元の多角化を進めていくことや我が国の優位性事業を通じた同志国やグローバルサウス諸国が抱える社会課題の解決への貢献が重要であり、その目的に資する我が国企業の海外展開を支援する政策が求められる。
第2節で述べたように、我が国企業の海外展開の中で、グローバルサウス諸国の位置付けは重要である。グローバルサウス諸国が抱える課題の解決を通じて、当該国・地域の市場の成長力を活かしつつ、我が国の国内におけるイノベーション創出等につなげ、国内産業活性化を目指すと共に、グローバルサウス諸国との経済連携を強化することを目指す。このため、経済産業省は、我が国企業が行うインフラ等の海外展開に向けたFS事業及び小規模実証事業の実施に必要な費用の一部補助を目的とする、グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金を実施し、サプライチェーン強靱化に向けた実証事業を支援している(第III-1-3-7図)。
第Ⅲ-1-3-7図 サプライチェーン強靱化に資する日本企業の海外展開支援
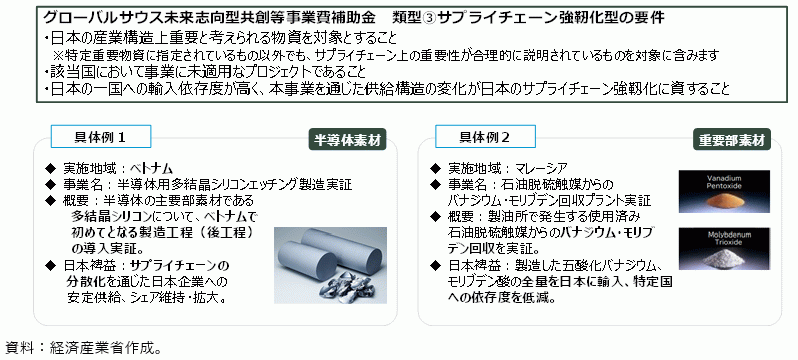
同様に、ルールベースの国際経済秩序の維持・強化・再構築に向けて、我が国と価値を共有する国の輪を拡大させることにも資する観点から、脱炭素技術や通信ネットワーク技術など我が国が優位性を有する技術や事業の海外展開を通じて、グローバルサウス諸国等の抱える社会課題への対処に貢献することも重要である。
こうした取組を通じ、我が国企業の海外展開を支援するとともに、我が国のサプライチェーン強靱化にも資する事例を積み上げていくことが重要であり、こうした取組を今後も推進していく。
4. エネルギー・鉱物資源の権益確保・調達先多角化の推進
エネルギー・鉱物資源の権益確保と調達先の多角化は、サプライチェーンの強靱化において重要な要素である。資源外交、JOGMECによる上流開発支援、NEXIによる貿易保険等を活用し、エネルギー・鉱物資源の権益確保・調達先多角化を推進する。
資源ナショナリズムの高まりや地政学リスクの上昇等を背景に、エネルギーの安定供給及び経済安全保障の観点も踏まえた資源外交が必要となる。加えて、GXの流れの中で、水素・アンモニア等の脱炭素燃料へのシフトや、バッテリーメタル等の鉱物資源の必要量が拡大するなど、我が国として確保すべき資源や付き合うべき国が拡大しつつある。
我が国は、これまで資源国とサプライチェーンを構築してきたという実績を踏まえ、先進的な技術と支援策を有する利点を活かしつつ、総理大臣・閣僚等によるハイレベルの外交機会の創出などの取組を通じ、資源国と世界に先駆けた互恵的関係を構築し、サプライチェーンの強靱化を進めていく(第III-1-3-8図)。
第Ⅲ-1-3-8図 石油・天然ガスの安定供給確保に向けたプロジェクト
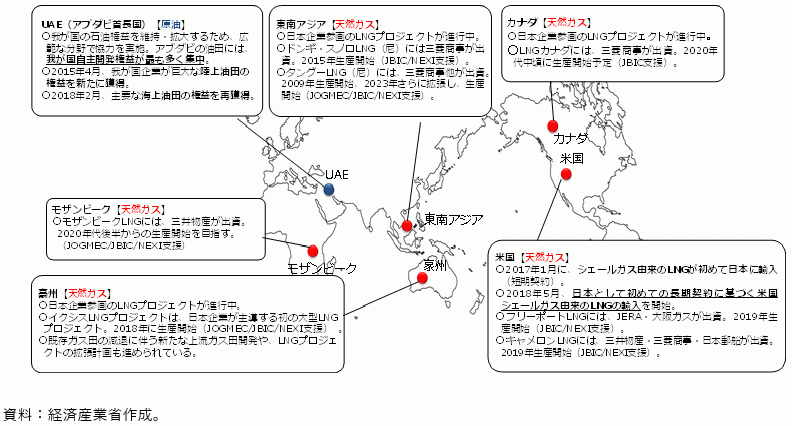
また、JOGMECによる、我が国の資源開発プロジェクトへの出融資・債務保証によるリスクマネー供給支援や、NEXIによる資源の安定供給確保に資するプロジェクトに対する保険引受を通じて、上・中流の開発プロジェクト支援を強化し、エネルギー・鉱物資源の調達先の多角化を推進する。
5. インド太平洋を中心とした同志国とのRun Fasterパートナーシップの推進
大国によるパワーベースの競争時代において、国際連携の中で、「ルールベースの国際経済秩序の再構築」や、「透明、強靱で持続可能なサプライチェーン構築」等を目指していくためにも、破壊的技術革新が進む領域を中心に、技術優位性を磨き上げ不可欠性まで強化することが経済安全保障上も重要である。そのためには、我が国の将来の自律性・不可欠性確保に向け、産業支援策と産業防衛策を有機的に講じる「Run Faster」戦略を加速させていく(第III-1-3-9図)。特に、AI(人工知能)・先端コンピューティング、量子、バイオ、宇宙分野は各国が激しく競争を進め、安全保障の面でも重大なインパクトをもたらすものであり、「Run Faster」戦略の重点分野に位置付ける。Run Fasterパートナーシップは、上記戦略を同盟国・同志国等と連携して産業・技術基盤共創に向けた産業支援策と産業防衛策を一体的に進めるための枠組みであり、まずはインド太平洋地域を中心に取組を進める。
第Ⅲ-1-3-9図 Run Faster戦略(イメージ図)
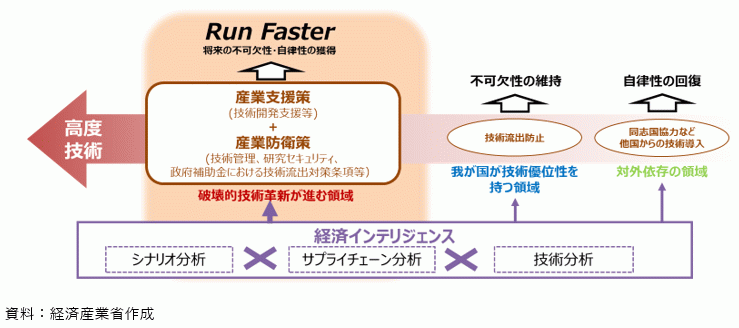
具体的には、我が国と同志国政府との間で支援すべき分野・プロジェクトを特定した上で、産業支援策と産業防衛策を一体的に講じるとともに、社会実装を進めるため、両国の政策資源を戦略的に投資していくことが考えられる。また、同パートナーシップにおいて、不可欠性強化の連携に加えて、今後の国際テクノロジー秩序作りを主導する観点から、要すれば、経済インテリジェンス分野の協力や技術に関する官民対話など同志国間で共有するテクノロジーサプライチェーンの将来の規範づくりに資する事項等について議論することも視野に検討を進める。