第1節 各国との取組
1. 北米
(1) 日米経済関係 最近の動き
バイデン政権の最終年となった2024年は、2022年に成立した「インフレ削減法」や「CHIPS及び科学法」に基づくクリーンエネルギーや半導体製造等の国内投資の促進策が継続的に推進された。対外経済政策では、5月に、1974年通商法第301条に基づく中国への追加関税に関し、2022年よりUSTR(米国通商代表部)が行っていた見直しの報告書が公表された。バイデン大統領はUSTRに対し、EVに対しての追加関税の関税率をそれまでの4倍となる100%とするなど、一部品目について、対中追加関税の引き上げを指示した。このほかにもバイデン政権は、半導体・AI・量子の分野について、中国等を対象にした対外投資規制措置や、半導体製造装置等に係る新たな対中輸出規制措置を発表するなど、先端技術分野において中国を意識した政策が打ち出された。
日米関係については、4月に岸田総理大臣の国賓待遇での公式訪問が行われ、日米首脳会談や首脳共同声明において、経済面で多くの成果が盛り込まれたほか、連邦議会上下両院合同会議において岸田総理大臣が行った演説の中では、日本は世界最大の対米直接投資国であり、日本企業が約8,000億ドルを投資し、米国内で約100万人の雇用を創出している点などに言及する等、日米の経済関係が強固に結びついていることが示された。
経済産業面での日米の連携・協力も進展し、連邦政府、連邦議会や州政府の関係者も多く来日した。齋藤経済産業大臣は、4月と6月に米国を訪問し、米国関係閣僚との面談に加え、日米比・日米韓の商務・産業大臣会合をそれぞれ初開催した。それぞれの米国訪問の概要は以下のとおりである。
① 2024年4月 第3回JUCIP閣僚会合の開催・ポデスタ大統領上級補佐官と閣僚級で対話・日米比商務・産業大臣会合の初開催
齋藤経済産業大臣は、4月9日から13日にかけて、岸田総理大臣による、我が国の総理大臣として9年ぶりの国賓待遇での米国公式訪問に同行する形で、米国ワシントンD.C.を訪問し、日米首脳会談や日米比首脳会合を始めとした首脳行事に出席した。
閣僚級でも、ポデスタ米国大統領上級補佐官と、米国インフレ削減法と日本のGX推進戦略のシナジーを最大化するための政策対話を開催したほか、レモンド米国商務長官と、日米商務・産業パートナーシップ(JUCIP)の第3回閣僚会合を行い、サプライチェーン強靱化や重要・新興技術における経済産業省と商務省の協力について議論した。これらを含め、経済産業大臣として、首脳会談の成果を具体化させるべく米国の関係閣僚との議論を行った。
このほか、日米比首脳会合の開催に際し、レモンド米国商務長官及びパスクアル・フィリピン貿易産業大臣との間で、日米比商務・産業大臣会合を初開催し、三か国の経済協力強化における共通の関心について議論を行った。
② 2024年6月 第4回JUCIP閣僚会合の開催・日米韓商務・産業大臣会合の初開催
齋藤経済産業大臣は、6月25日から28日にかけて米国ワシントンD.C.を訪問し、米国の関係閣僚との二国間会談のほか、同志国関係閣僚との多国間会合を行った。また、産業界との連携強化を念頭に、ビジネス関連イベントに出席した。
二国間会談については、レモンド米国商務長官とのJUCIPの第4回閣僚会合や、タイ米国通商代表との会談を通じて、日米間の経済分野における協力の進展について議論した。
多国間会合については、前年の2023年8月に行われた日米韓首脳会合における合意を踏まえて、レモンド米国商務長官及び韓国の安德根(アン・ドックン)産業通商資源部長官との間で日米韓商務・産業大臣会合を初開催し、サプライチェーン強靱化や、重要・新興技術開発の促進と保護、クリーンエネルギー等の分野における協力について議論し、共同声明を取りまとめた。また、この三カ国会合に先立つ形で、ベステアー欧州委員会上級副委員長がオンラインで加わり、四閣僚でサプライチェーン強靱化について議論を行った。
これらに加え、米国商務省主催の対米投資促進イベント「セレクトUSA投資サミット」でのJETRO主催の「ジャパンセッション」に出席し、日米経済関係の強化等に関するスピーチを行った。また、日本経済団体連合会、全米商工会議所、全国経済人連合会(韓国)が参加する日米韓のビジネスイベントに出席した。
米国では2024年11月に大統領選挙が行われた。共和党のドナルド・トランプ氏が民主党のカマラ・ハリス氏を破り、翌2025年1月20日に、第47代米国大統領に就任した。選挙戦中から関税の賦課に言及をしていたトランプ大統領は、就任初日に「米国第一の貿易政策」と題した大統領覚書を発表した。そこで、商務長官や米国通商代表等の関係閣僚に対して、不公正かつ不均衡な貿易、中国との経済・貿易関係、経済安全保障に関する調査等を行い、4月1日までに是正措置等の勧告を含む報告書を提出することを指示した。さらに、2月以降、カナダ、メキシコ及び中国に対する追加関税措置、鉄鋼・アルミニウム製品及び派生品に対する25%の追加関税措置、自動車及び自動車部品に対する25%の追加関税措置、相互関税措置等について発表した。
そのような中で、2月7日には、ワシントンD.C.において、石破総理大臣がトランプ大統領との間で初の対面での首脳会談を行った。会談において両首脳は、日本が5年連続で最大の対米投資国であることを始め、経済面でも両国が緊密なパートナーであることを確認した。その上で、両首脳は、両国におけるビジネス環境を整備して投資・雇用を拡大していくこと、互いに産業を強化するとともにAIや先端半導体等の技術分野における開発で世界をリードすること、また、成長するインド太平洋の活力を取り込む取組を力強く推進していくことを通じて、日米のパートナーシップを更に高い次元に引き上げていくとの認識で一致した。また、双方に利のある形で、日本へのLNG輸出増加も含め、両国間でエネルギー安全保障の強化に向けて協力していくことを確認した。
③ 2025年3月 第二次トランプ政権の関係閣僚との会談を実施
武藤経済産業大臣は、2025年3月9日から12日にかけて、米国ワシントンD.C.を訪問し、第二次トランプ政権の関係閣僚等との会談を行った。
訪問中は、ラトニック商務長官、グリア通商代表、ハセット国家経済会議委員長とそれぞれ会談を行った。武藤経済産業大臣からは、両国におけるビジネス環境整備を通じた投資・雇用の拡大、日米両国の産業強化に向けた協力などを通じ、日米の経済関係の更なる発展を図っていきたい旨を伝えた。また、会談の中で、米国政府がこれまで発表してきた関税措置について、我が国がその対象となるべきでない旨を申し入れた。米国の関税措置が、我が国の産業や日米両国におけるビジネス環境の整備や投資・雇用の拡大に与え得る影響について、我が国の考えを説明した。
加えて、ハガティ連邦上院議員(共和党・テネシー州選出)と会談し、日米経済関係等について意見交換した。
(2) 日米貿易投資関係の更なる発展に向けた取組
日米両国でのサプライチェーン強靱化に向けた関心が高まる中、日本からの対米直接投資残高は年々増加し、2024年末時点で、日本の対外直接投資残高全体の35.3%に相当する124兆円に達した355。2023年末時点で、米国にとって日本は国別で最大の投資元(7,833億ドル、前年比221億ドル増)であり、2019年以降、5年連続で首位となった356。また、在米日本企業による米国内の雇用者数は96.9万人(世界第2位)であり、このうち製造業の雇用者数は52.9万人(世界第1位)である(2022年)357。
日本企業は、全米各地で研究開発分野への投資を活発に行い、イノベーションの源泉としてきた。日本企業による米国内での研究開発費は、年114.7億ドルであり、これは世界第3位である(2022年)358。
こうした日本企業の活動を後押しするため、経済産業省やJETROは、①州知事等への個別アプローチ、②対米投資促進のためのセミナー開催、③両国企業の現地でのマッチングイベント開催などに取り組んでいる。例えば、2024年6月にメリーランド州で開催された、米国商務省主催の対米投資促進イベント「セレクトUSA投資サミット」において、JETROが主催した「ジャパンセッション」に齋藤経済産業大臣が出席し、日本企業の投資・雇用を通じた米国地域経済への貢献や、日米連携によるサプライチェーン強靱化の実現、JETROによる支援を通じた日米経済関係の強化等に関するスピーチを行った。また、JETROは、EV、半導体、ヘルスケアなど日米間で関心が高い分野をテーマに複数のビジネス環境視察ミッションを実施し、日本企業が投資環境やインセンティブの現状を視察する機会を提供した。
これらの取組は、2024年7月に実施された「グラスルーツからの日米関係強化に関する政府タスクフォース(「各地各様のアプローチ」)」第7回フォローアップ会合(議長:村井内閣官房副長官)でも報告され、日本企業による投資・雇用創出に関する発信をより一層強化し、日本企業の技術・供給力が米国にとって不可欠である点の積極的な打ち込み等を実施していくこととされた。
2024年度は、米国の地方政府との協力関係がさらに進展した。2024年6月の齋藤経済産業大臣の訪米時には、ノースカロライナ州、オクラホマ州及びグアム準州の知事や、ミシガン州、インディアナ州及びテキサス州の商務長官らと立ち話を実施した。また、サウスダコタ州、ユタ州、オクラホマ州及びアラスカ州などの州知事や州政府関係者が訪日する機会を捉えて、武藤経済産業大臣や加藤経済産業大臣政務官、松尾経済産業審議官ら経済産業省の幹部が会談を行い、日本企業の各州における米国社会・経済への貢献や、日米協力の重要性等について意見交換を行った。また、経済産業省とJETRO、ユタ州政府と共催で、日米の企業向けオンラインビジネスセミナーを実施し、日米双方での投資促進施策等の説明を実施した。
このほか、複数の米国連邦議会関係者が経済産業省を訪問し、齋藤経済産業大臣等の経済産業省幹部が面談を実施した。
また、日米両国のビジネス関係者での連携強化を図る日本・米国中西部会、日本・米国南東部会等の会合が米国で開催された。経済産業省も、JETROと連携して、州政府等の関係者に日本企業と米国社会の歴史的関係や、投資・雇用等の地域経済への貢献の深度を説明し、継続的なグラスルーツ連携の重要性を訴えた。
355 財務省「直接投資・証券投資等残高(地域別)」
356 米国商務省「Direct Investment by Country an Industry, 2023」
357 米国商務省「Foreign Direct Investment in the United States (FDIUS), Employment by Industry and Country 2007-2022」
358 「Activities of U.S. Affiliates of Foreign Multinational Enterprises, 2022」
(3) 日加経済関係
日本とカナダは、普遍的価値を共有するインド太平洋における重要なパートナー国である。カナダはエネルギー・重要鉱物に恵まれた資源国であるとともに、先端産業技術研究の分野等でも強みを有しており、日本にとってサプライチェーン強靱化や国際社会におけるルール形成の観点からも重要なパートナーである。
これらの観点から、経済産業省は、カナダ政府との連携を積極的に図っている。2023年に署名したバッテリーサプライチェーンに関する政府間の日加協力覚書に基づき、日本企業によるカナダ進出の円滑化と、日加間の持続可能で信頼性のあるバッテリーサプライチェーンの構築を進めている。2024年には、バッテリーサプライチェーン協力覚書に基づく第1回局長級対話をカナダで開催した。日本からは野原商務情報政策局長、カナダ側はグレゴリー革新・科学・産業省次官補が参加し、持続可能で信頼性のあるグローバルなバッテリーサプライチェーンの構築に向けた意見交換を行うとともに、政策情報の共有、貿易・投資促進、研究開発などについて今後の対応策などを議論した。
また、2023年に署名した量子・AI等の産業技術分野に関する政府間の日加協力覚書に基づき、日加間における①先進製造、②AI、③クリーン技術、クリーンエネルギー及び炭素削減技術、④ライフサイエンス、⑤量子、⑥半導体などの科学技術分野の協力の発展を図っている。
経済産業省は、JETROを通じて、日加企業の相互進出・連携を後押ししている。2024年度は、対日投資促進の枠組みを活用したカナダ企業の日本進出支援や各種広報活動支援、また、2024年6月にトロントで開催されたテック系スタートアップ展示会「Collision 2024」においては、日系スタートアップの北米でのビジネス展開やマッチングの支援等を実施した。
2. 欧州
(1) EU関係
EU(欧州連合)は、27か国が加盟し、人口約4.5億人359、名目GDPは世界全体の2割近く360を占める政治・経済統合体である。EUは、域外に対する統一的な通商政策を実施する世界最大の単一市場を形成し、単一通貨のユーロには、20か国が参加している。自由、民主主義、法の支配、人権などの価値や原則を共有する我が国にとって、重要なパートナーである。
ドラギ元欧州中央銀行総裁は、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長からの諮問を受け、2024年9月に「欧州の競争力の将来」レポート(ドラギレポート)を公表した。三つの構造変化(米中とのイノベーション格差の解消、高いエネルギー価格への対応、地政学的リスクへの対応)に対応するための「新たな産業政策」の打ち出しや、戦略分野への年間最大8,000億ユーロの投資、競争政策・貿易政策との連携等を提言した。
フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長(ドイツ出身)は、2024年12月に二期目となる新体制を発足させ、同日、コスタ欧州理事会常任議長(ポルトガル出身)が就任した。この新体制の下、5年間の政策として、2025年1月に「競争力コンパス」を公表した。これは、ドラギレポートの提言内容を具現化したものであり、今後の重点分野として、①米中とのイノベーション格差の解消、②脱炭素化と競争力強化の両立、③過剰な域外依存の軽減と安全保障の強化の三つの柱を掲げる政策を公表した。具体的には、以下のとおりである。
①米中とのイノベーション格差の是正:スタートアップやスケールアップ向けの環境整備、ベンチャーキャピタル(VC)市場の創設、デジタルインフラへの投資、研究開発の促進など。
②脱炭素化と競争力強化の両立:産業・経済・通商政策と脱炭素化政策の統合、安価なエネルギーの提供、クリーンテック製造業の強化など。
③過剰な域外依存の軽減と安全保障の強化:域外国とのパートナーシップの推進、防衛産業能力の強化、緊急時に備えた域内連携など。
気候変動(グリーン)分野については、2023年2月、欧州委員会がネット・ゼロ移行のために必要となる技術を欧州内で確保するために「グリーン・ディール産業計画(GDIP)」を発表した。同計画を踏まえ、2024年5月に、欧州内における特定の重要原材料の供給確保に関するプロジェクト支援を規定した「重要原材料法」が、同年6月に、ネット・ゼロ産業の製造容量に関する目標設定や導入拡大に向けた規制整備・許認可の迅速化などを規定した「ネット・ゼロ産業法」が施行された。また、2025年2月には、「気候変動に対処し、競争力を強化し、経済の強靱性を確保し、人材を保持するための事業計画」として、「クリーン産業ディール」を発表した。高いエネルギー価格、不公正な国際競争及び複雑な規制に対処する早急な支援を必要とするエネルギー集約型産業と、将来の産業競争力の中心であり産業の変革や循環性及び脱炭素化にとって必要なクリーンテック分野に主な焦点を当てている計画となっている。
関連する政府間の会合としては、2024年6月に、日EUエネルギー閣僚会合及び初となるハイレベル水素ビジネスフォーラムを開催し、齋藤経済産業大臣とシムソン欧州委員会委員(エネルギー担当)が出席した。クリーンエネルギー分野において供給・需要サイドで協力し、透明性、多様性、安全性、持続可能性及び信頼性の原則に基づき、脱炭素、安定供給、サイバーセキュリティといった価格以外の要件の適切な評価について検討する日EUクリーンエネルギー産業政策対話の設置や、水素分野における協力に関する共同工程表の作成等の合意を内容とする共同プレス声明を発出した。同会合では、日EUの水素関係機関の連携を促進するための協力文書の署名を実施した。
また、同日には、日EU企業の水素連携に関する意見交換会を開催し、岸田総理大臣、齋藤経済産業大臣、シムソン欧州委員会委員(エネルギー担当)が出席した。岸田総理大臣から、日EUが連携し、透明かつ強靱なサプライチェーンを構築し、世界のクリーンエネルギー市場をリードしていく考えを述べた。
デジタル分野では、2024年8月に、世界初の包括的なAIに関する法的枠組みとしてAI法が施行され、2026年8月から本格適用が開始される予定である。また、2023年7月に開催した日EUデジタルパートナーシップ第一回閣僚級会合に続き、2024年4月には、第二回閣僚会合を開催し、共同声明を発出した。同会合では、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持し、DXに向けた共通の価値観とビジョンを推進する上で、これまで以上に緊密な戦略的パートナーシップを構築することの重要性を再確認した。また、日EUビジネス・ラウンドテーブルや日EU産業協力センターの取組を含む、ステークホルダーの関与の重要性を強調した。
経済安全保障分野については、2023年6月に、欧州委員会が経済安全保障戦略を発表した。この戦略では、経済安全保障の強化、リスクの低減、重要セクターにおける技術的優位性の向上を目指した、EU独自の戦略的アプローチが構築されている。その中では、パートナー国との協力の重要性も強調されており、その一環として、日本との協力を示す日EUハイレベル経済対話が挙げられている。2024年5月には、齋藤経済産業大臣、上川外務大臣、ドンブロフスキス上級副委員長兼貿易担当欧州委員を共同議長とする日EUハイレベル経済対話第五回会合をフランス・パリで開催した。同会合では、経済安全保障、透明、強靱で持続可能なサプライチェーン、WTOについて議論を行い、また、国際情勢の不透明感の高まりを受けて、「透明、強靱で持続可能なサプライチェーン」を構築するため、持続可能性や信頼性など「共通の原則」に基づく需要創出に向けた政策の必要性を確認した。
関連して、2023年10月に、欧州委員会は、莫大な補助金で人為的に価格を抑え、EU市場を歪曲しているとの見方から、中国製バッテリー式電気自動車(BEV)に対する反補助金調査を開始した。調査の結果として、2024年7月に、中国のBEVバリューチェーンは、国家補助により不公正に競争市場を歪めており、EUメーカーに経済的損失を与えるおそれがあると判断し、中国製BEVに対して暫定的な相殺関税措置を発動すると発表した。同年10月には、中国製BEVに対する相殺関税措置が発動された。
加えて、2024年5月に、欧州委員会は、企業活動による人権や環境への悪影響を予防・是正する義務を企業に課す「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令案」を採択し、各加盟国で施行後2年以内に実施する国内法化を経て、適用が開始される予定である。2024年11月には、強制労働により生産された製品のEU域内での流通、域外への輸出を禁止する「強制労働禁止規則案」を採択し、施行3年後から適用が開始される見込みである。
359 外務省「欧州連合(EU)概況」、2024年3月14日、https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/data.html![]() 。2023年。
。2023年。
360 IMF「WEO」(2023年10月)、2023年。
(2) 英国
英国は、基本的価値を共有するグローバルな戦略的パートナーであり、日本とは経済的な結びつきが強いだけでなく、近年は安全保障・防衛協力を含め、関係を強化している。
EUからの離脱後、英国は欧州域外への関与を強化する姿勢を強めている。中でもインド太平洋地域は、2021年3月に発表され、2023年3月に改訂が行われた「競争時代におけるグローバル・ブリテン」で、英国の国際戦略における重要な地域と位置付けられている。CPTPP加入への強い意欲はその一端であり、2021年6月には加入手続開始が決定され、2023年3月に加入交渉が実質妥結し、2023年7月に英国の加入に関する議定書が署名され、2024年12月に正式に加入した。
岸田総理大臣は、2024年6月のG7プーリア・サミットの際にスナク首相と会談を行い、「強化された日英のグローバルな戦略的パートナーシップに関する広島アコード」(以下、日英広島アコード)に基づき、安全保障、経済、AIを含む幅広い分野で、日英間で具体的な協力が急速に進展していることを歓迎した。
2025年3月には、武藤経済産業大臣がレイノルズビジネス・貿易大臣と第二回日英戦略経済貿易政策対話を日本で開催した。同対話は、エネルギー安全保障・ネットゼロ省と科学・イノベーション・技術省の関与の下で開催され、経済安全保障を軸に、貿易、原子力、洋上風力、水素、太陽エネルギー、CCUSなどのクリーンエネルギー、量子を中心とするイノベーション、防衛、宇宙、自動車などの産業における二国間協力を重点的に進めることに合意した。また、対話に先駆け、洋上風力に関する協力覚書に署名を行うとともに、日英産業界同士の覚書も両大臣立会いのもとで署名した。
同日には、武藤経済産業大臣、岩屋外務大臣、レイノルズビジネス・貿易大臣、ラミー外務大臣との間で、第一回日英経済版2+2閣僚会合を日本で開催した。同会合は、2024年11月に行われた日英首脳会談で立上げに一致したものであり、国際経済秩序が大きな挑戦を受けているという認識の下、自由で公正なルールに基づく国際経済秩序の維持・強化を通じ、基本的価値を守るべくともに行動していくというコミットメントを共有するとともに、経済安全保障、自由で開かれた国際貿易、エネルギー安全保障、グローバルサウスについて議論を行った。
(3) ドイツ
2021年12月の三党連立政権樹立後、2022年4月に、ショルツ首相が初のアジア訪問国として日本を訪問した。2023年3月には、日独政府間協議が東京で開催され、経済安全保障分野を中心に両国間の協力を更に拡大・深化することを確認した。
2024年7月には、岸田総理大臣がドイツを訪問し、ショルツ首相と会談を行い、自由で公正な国際経済秩序を維持・拡大していくために、産業構造や高度な技術力において共通点を持つ日独の連携が重要であるとの認識を共有し、両国間で経済安全保障に関する協議枠組みを創設することで一致した。
さらに同月、イタリアで開催されたG7貿易大臣会合に齋藤経済産業大臣が出席した際に、ハーベック副首相兼経済・気候保護大臣と会談を行い、経済安全保障を中心とする二国間関係の連携強化について意見交換を行った。
2024年11月には、7月の首脳会談で創設に合意した日独経済安全保障協議が開催され、サプライチェーンの強靱化、非市場的政策・措置及びそこから生じる過剰生産能力への対応、経済的威圧への対応、重要・新興技術の保護・育成など、経済安全保障に係る重要課題について意見交換を行い、今後も、経済安全保障分野における専門的知見の共有を含め、二国間の連携を強化していくことで一致した。
また、2024年12月には、日独間の産業協力の深化・発展について意見交換を行う経済産業省と独経済エネルギー省(現在の独経済・気候保護省)との対話である日独次官級定期協議の第22回目が実施され、経済安全保障や、国際情勢の変化に伴う両国の経済情勢・政策に関する交換、エネルギー・気候変動や、産業分野での二国間経済協力等に関して意見交換を行った。
(4) フランス
フランスとは、2023年12月に発出した、「特別なパートナーシップ」の下での日仏協力のロードマップに基づき、協力を進めている。
2024年4月に、齋藤経済産業大臣はリステール対外貿易・誘致担当大臣と会談を行い、スタートアップを含む産業協力や重要鉱物分野を含む経済安全保障での連携など、二国間関係について意見交換を実施した。
2024年5月には、フランスで開催されたOECD閣僚理事会に出席した際、ル=メール経済・財務・産業・デジタル主権大臣と会談を行った。同会談後に「重要鉱物分野の協力に関する日仏共同声明」の署名を行い、持続可能なサプライチェーンの構築に向けて、更なる協力の強化で一致した。
また、OECD閣僚理事会に出席した岸田総理大臣は、マクロン大統領と会談を行い、経済安全保障分野において更に連携を強化していくことやスタートアップ分野での協力強化、民生用原子力に関する協力を進展させることで一致した。同月、日本は、パリで開催された世界最大級のスタートアップ、オープン・イノベーションイベントのビバテックに主賓国として参加し、60社からなるジャパン・パビリオンを出展した。同イベントに参加した岩田経済産業副大臣は、フェラーリ・デジタル担当国務長官と「日仏スタートアップ及びイノベーション協力に関する共同声明」に署名した。
また、2024年9月には、文部科学省と経済産業省は仏原子力・代替エネルギー庁と高速炉の開発に係る協力の内容を取りまとめた合意文書を更新し、高速炉の研究を長らく続けてきたフランスの研究機関及び民間企業の知見をいかしながら、日本の高速炉実証炉開発プロジェクトを推進していくことに合意した。
(5) 中・東欧
2024年11月に、竹内経済産業大臣政務官が、日本を代表するエネルギー関連企業と政府機関計24社を帯同し、ルーマニア及びポーランドを訪問した。ルーマニアでは両国間で初開催となる日ルーマニア・エネルギーフォーラム、ポーランドでは第二回日・ポーランド政府間協議へ出席した。
ルーマニアでは、ブルドゥジャ・エネルギー大臣、イヴァン研究・イノベーション・デジタル化大臣、オプレア経済・起業・観光大臣とそれぞれ会談を行い、原子力、水素、再生エネルギー、CCUSを含むエネルギー分野、エネルギー転換に向けた協力に関する共同声明に署名した。また、チョラク首相と会談を行い、2023年に格上げされた戦略的パートナーシップの枠組みに沿って、二国間の経済関係を強化することを確認した。
ポーランドでは、チャルネツカ産業大臣と会談を行い、「原子力分野での協力に関する覚書」に署名した。また、ヤロス開発・技術副大臣と共に開催した第2回日・ポーランド政府間協議に併せて、ヤロス副大臣と竹内経済産業大臣政務官の立会いの下、NEXIとポーランド輸出信用機構(KUKE)の協力覚書が署名された。
(6) EU域外
2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略は長期化の様相を呈しているが、ウクライナの復興に向け、G7を始めとした国際社会が結束して支援に取り組んでいる。
2024年6月のG7プーリア・サミットの際、G7首脳は、「ウクライナのための特別収益前倒し融資」を立ち上げることで一致した。
2024年6月には、ドイツで経済産業省、JETRO、在独日本大使館が主催する「日・ウクライナ官民ラウンドテーブル」を開催した。同会合では、岩田経済産業副大臣、武村農林水産副大臣、深澤外務大臣政務官がスヴィリデンコ第一副首相兼経済相、シュルマ大統領府副長官と会談を行い、日ウクライナ官民ラウンドテーブルにおける民間企業間の協力案件の合意を歓迎するとともに、更なる協力に向けた意見交換を行った。
その翌日には、ドイツ政府及びウクライナ政府が主催するウクライナ復興会議に岩田経済産業副大臣が出席した。同会議中、岩田経済産業副大臣は、ポーランドのパヴェウ・コヴァル・ウクライナ開発協力担当政府全権代表と会談を行い、ウクライナ復旧・復興の要衝となっているポーランドとの間で、ウクライナ復興に向けた両国の更なる連携について意見交換を行った。
2024年2月に開催された日ウクライナ経済復興推進会議で、岸田総理大臣は、JETROのキーウ事務所を開設することを発表した。2024年10月に事務所開設と共に開所式が行われた。同式典には、シュミハリ首相、スヴィリデンコ第一副首相兼経済大臣が出席し、石破総理大臣からはビデオメッセージが寄せられた。
2024年12月には、武藤経済産業大臣とスヴィリデンコ第一副首相兼経済大臣が会談を行い、今後のウクライナにおける復興支援に関する意見交換を行った。今後も、各国と連携しながらウクライナ復興支援を推進していく。
3. 中国・韓国
(1) 中国
① 今後の方針
2024年11月、APEC首脳会議(於:リマ)において、日中首脳会談が行われた。会談では、引き続き「戦略的互恵関係」を包括的に推進し、「建設的かつ安定的な関係」を構築するという大きな方向性を共有していることを確認し、石破総理大臣から、日中関係が発展して良かったと両国民が実感できるような具体的成果を双方の努力で積み上げていきたい旨強調した。また、首脳レベルを含むあらゆるレベルで、幅広い分野において意思疎通をより一層強化し、課題と懸案を減らし、協力と連携を増やしていくために、互いに努力することを確認した。また、ALPS処理水の海洋放出と日本産水産物の輸入規制に関する発表を両国できちんと実施していくことを確認し、石破総理大臣から、中国による日本産水産物の輸入回復を早期に実現するよう求めた。
こうした中、経済産業省は、中国に対して、邦人安全の確保、日本産水産物の輸入規制の是正を求めつつ、ビジネス環境整備の要請とビジネス協力の具体化の両輪で政策を展開している。具体的には、輸出管理法・データ関連規制といった国内法制度の予見可能性向上や外商投資規制の緩和等を通じた、公正・公平な競争環境の実現を求めるとともに、日中共通課題である、省エネ・環境を含めたグリーン経済分野やヘルスケア分野等に加え、コンテンツ分野を含め、個別の政策連携分野での協力強化に向けた取組も行っている。
② 主な進捗
中国による日本産食品に対する輸入規制については、2024年9月に、ALPS処理水の海洋放出と日本産水産物の輸入規制について「日中間の共有された認識」を発表し、中国側は、国際原子力機関(IAEA)の枠組みの下での追加的モニタリングを実施後、日本産水産物の輸入規制措置の調整に着手し、日本産水産物の輸入を着実に回復させることとなった。2024年10月・2025年2月・同年4月には、この追加的モニタリングの一環として、中国を含む参加国の分析機関による試料採取等が実施された。ビジネス環境に関しては、2024年11月のAPEC閣僚会議(於:リマ)、2025年3月の日中韓経済貿易大臣会合(於:ソウル)の2回にわたり、武藤経済産業大臣と王文濤(オウ・ブントウ)商務部長が閣僚級会談を行った。武藤経済産業大臣から、ビジネスに関わる企業関係者の安全確保や透明で公平なビジネス環境を確保することが極めて重要である旨発言し、邦人安全の確保、中国の輸出管理措置の運用の適正化、過当競争や国産品優遇策の是正などを強く求めた。また、2024年 9 月 20 日に発表された「日中間の共有された認識」が着実に履行されていることを評価し、日本産水産物の輸入回復を早期に実現するよう求めた。また、両大臣は、「日中輸出管理対話」及び「日中サービス貿易政策対話」の着実な実施を評価するとともに、「第2回日中ビジネス環境円滑化ワーキンググループ」を日本で、「第18回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」を中国で開催することを歓迎したほか、大阪・関西万博の開催成功に向けて、両国で緊密に連携していくことで一致した。その他、第三国市場での民間経済協力等についても意見交換を行い、両大臣は、今後も様々な機会を活用して、緊密に意思疎通を重ねていくことで一致した。
また、2025年3月、第6回日中ハイレベル経済対話が東京にて開催された。日本側からは岩屋外務大臣、大串経済産業副大臣他、中国側からは王毅(オウ・キ)中国共産党中央政治局委員・外交部長、鄢東(エン・トウ)商務部副部長他が出席し、マクロ経済政策、「戦略的互恵関係」の下での経済協力、貿易・投資・ビジネス環境、地域・マルチ協力等について議論した。日本産水産物の輸入規制について、双方は、2024年9月に発表した「日中間の共有された認識」が着実に履行されていることを共に評価し、日本側から、日本産水産物の輸入を近く再開するよう求めた。双方は、IAEAの枠組みの下で追加的モニタリングを引き続き実施していくことを確認し、分析結果に異常がないことを前提に、日本産水産物の輸入再開に向けて、関連の協議を推進していくことで一致した。
なお、「日中輸出管理対話」に関しては、経済産業省と中国・商務部との間で、東京で第1回、5月に中国・上海で第2回、10月に東京で第3回、2025年3月に中国・北京で第4回を開催し、両国の輸出管理に係る関心事項について意見交換を行った。
また、「日中ビジネス環境円滑化ワーキンググループ」に関しては、2024年9月に、経済産業省と中国・商務部との間で、両国の経済団体も参加する形で、第1回を中国・江蘇省にて開催し、両国のビジネス環境改善に係る関心事項について意見交換を行った。
さらに、「第2回日中サービス貿易政策対話」に関しては、経済産業省と中国・商務部との間で、2024年12月に北京で開催し、コンテンツ分野の相互交流を含む両国のサービス貿易分野の発展に向けた取組や関心事項について、意見交換を行った。加えて、「第2回日中ハイレベル人的・文化交流対話」に関しては、経済産業省も参画し、この中で、コンテンツを通じた双方向の交流を充実させることを確認するとともに、外国コンテンツに対する規制の透明化や、海賊版対策に関する相互協力の重要性を確認するとともに、日中映像作品共同制作覚書について早期署名に向けて努力することで一致した。
グリーン経済分野では、2024年11月に、経済産業省、一般財団法人日中経済協会、中国国家発展改革委員会及び商務部、中国駐日本国大使館の共催で、日中のエネルギー・環境分野の協力プラットフォームである「第17回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」を開催した。第13回が行われた2019年以来、5年ぶりの対面開催となり、日本側から、武藤経済産業大臣、浅尾環境大臣、岩田経済産業副大臣、進藤日中経済協会会長他、中国側から、趙辰昕(チョウ・シンキン)国家発展・改革委員会副主任、李飛(リ・ヒ)商務部副部長、呉江浩(ゴ・コウコウ)駐日本中国特命全権大使他、両国合わせて約650名の官民関係者が参加した。
ヘルスケア分野では、JETROと協力し、2024年7月31日に中国の山東省・済南市、翌8月1日に山東省・日照市で「日中高齢者産業交流会」を、同年11月28日~11月30日に北京市で「中国国際福祉博覧会」を実施し、日本の介護サービス・福祉用具の事業者と中国現地企業とのビジネスマッチングを行った。
その他にも、中国・商務部とは鉄鋼や知財分野等で、中国・工業信息化部とは電機電子製品環境分野等での対話・交流を行った。
(2) 韓国
① 日韓関係
日本にとって韓国は、世界第3位の輸出先であり、世界第5位の輸入先である361。また、韓国にとって日本は、世界第6位の輸出先、世界第3位の輸入先となっている362。日本と韓国は、お互いにとって重要な貿易相手国であるとともに、国際社会における様々な課題への対応に協力していくべき重要な隣国である。
日韓関係は、2023年3月16日に行われた日韓首脳会談において、首脳間のシャトル外交の再開や、政治・経済・文化など多岐にわたる分野で政府間の意思疎通を活性化していくことで一致した。政府・民間の双方で、幅広い分野の協力が進展している。
361 財務省「貿易統計」、2024年。
362 KITA(韓国貿易協会)、2024年、https://stat.kita.net/stat/world/major/KoreaStats06.screen![]() (2025年6月5日閲覧)。
(2025年6月5日閲覧)。
② 進捗状況
二国間会談については、国際会議の機会等を活用して、安德根(アン・ドックン)韓国産業通商資源部長官との会談を相次いで実施した。2024年4月22日及び6月26日には、齋藤経済産業大臣との会談が実施され、今後の日韓の経済関係を強化していくため、炭素中立や、WTO・IPEF等の通商分野における協力について意見を交わし、引き続き、意思疎通を図っていくことで一致した。また、2025年3月30日には、武藤経済産業大臣との会談が実施され、エネルギーを始め各産業分野での協力が進展していることを歓迎するとともに、引き続き、日韓関係の協力強化を図っていくことで一致した。
経済産業分野における政府間対話等については、2024年9月5日に釜山で、木原資源エネルギー庁首席国際炭素中立政策統括調整官と崔然禹(チェ・ヨンウ)産業通商資源部エネルギー政策官による日韓エネルギー協力対話を開催し、エネルギー分野の協力について意見交換を実施した。
また2024年6月14日及び2025年3月26日に、相次いで「日韓水素アンモニア等協力対話」を実施した。両国の水素アンモニア関連機関がこれまで議論してきた内容と協力議題について報告し、政府及び関連機関が今後の協力拡大に向けた議論を行った。
加えて、2024年4月に開催された大臣会談での合意をもとに設置された「日韓グローバルグリーン政策対話」を、2025年1月17日に実施した。炭素国境調整措置を始めとして、GXをとりまく世界情勢の変化に適切に対応するため、日本と韓国が緊密に連携することの重要性を確認した。
その他、2025年1月13日に第2回日韓スタートアップ政策対話を実施した。自国のスタートアップの海外展開や、海外の投資家・起業家の日本への呼び込み強化などに関する施策や現状について情報共有や意見交換を行い、今後も緊密に連携を続けていくことで一致した。
さらに、2025年2月27日には第1回重要鉱物分野における日韓ハイレベル対話を実施した。重要鉱物のサプライチェーンにおける両国間の関係強化に向け、両国の重要鉱物政策の共有、鉱物資源の備蓄協力、第三国における共同生産及びオフテイクについて意見交換を行った。
主な政府関係機関間の交流については、2024年1月に、韓国標準科学研究院(KRISS)と産業技術総合研究所(AIST)が、量子情報科学を連携分野として新たに盛り込んだ研究協力覚書(MOU)を締結した。また、同年9月21日に、ソウルにおいてJETROと大韓貿易投資振興公社(KOTRA)が、定期協議と共同フォーラムを開催した。
また、主な日韓の経済団体間の交流等については、2024年5月14日、15日の二日間にわたり、日韓経済協会と韓日経済協会等において「日韓経済人会議」を東京で開催し、2024年11月25日には、大阪で日本商工会議所と大韓商工会議所が「日韓商工会議所首脳会議」を開催した。日本経済団体連合会と韓国経済人協会は、2024年10月18日、ソウルで第31回首脳懇談会を開催し、両国が直面している様々な課題に対する協力の拡大に向けた方策を討議した。
(3) 日中韓
基準認証分野では、2024年7月、ソウルで、第22回北東アジア標準協力フォーラム(NEASフォーラム)が開催された。日本、中国、韓国の国家標準化機関、規格協会、民間の標準化専門家など標準化関係者約130名が、対面またはオンラインで参加した。
NEASフォーラムでは、三か国の標準化政策・活動に関する情報交換を行ったほか、国際標準化機構(ISO)中央事務局及び国際電気標準会議(IEC)アジア地域事務局の代表者が参加し、アジア地域における地域関与政策について講演を行った。また、三か国共同で個別案件の国際標準化に向けた協力を実施する提案について議論が行われ、日本からは、「ファインセラミックス」と「走査型プローブ顕微鏡」に関する国際標準化協力を提案した。
NEASフォーラムに併せ、日中韓政府間会合、日中政府間会合及び日韓政府間会合を開催した。さらに、標準分野における若手人材育成に係る日中韓共同プログラムが初めて実施された。
コンテンツ分野では、2024年9月24日に、「第17回日中韓文化コンテンツ産業フォーラム」を中国の杭州で開催した。本フォーラムでは、日中韓の文化コンテンツ産業の交流と協力、特に、デジタル経済と実体経済の融合により、文化観光の新たなシナリオと新たな消費の創出を促進するというテーマについて議論した。また、日中韓三か国は、政府間のみならず関係機関や産業間の積極的な協力を通して、三か国の文化コンテンツ産業の共同発展と成長を促進していくことで合意した。
また、地域間協力として、2024年11月12日から15日にかけて、大分県別府市で、第22回「環黄海経済・技術交流会議」を開催した。「持続可能な環黄海経済圏の形成~炭素中立・高度外国人材に係るベストプラクティスの共有と環黄海地域への展開~」をテーマに、日本では7年ぶりに対面で開催し、日本側は経済産業省九州経済産業局、韓国側は産業通商資源部、中国側は商務部を代表として、各国の政府機関・地方行政機関・企業・経済団体など約300人が参加した。
知財分野では、2024年12月4日に、特許庁、中国国家知識産権局(CNIPA)、韓国特許庁(KIPO)が中国・上海で「第24回日中韓特許庁長官会合」を開催した。意匠・商標・審判など三庁間での協力について議論を行うとともに、3か国知的財産協力の10年ビジョンにおける三つの具体的な協力に対する今後の進め方について話し合い、次回会合に向け、更なる検討を進めることとした。さらに、「IP公共サービスを通じたより良いビジネス環境の構築」をテーマとした日中韓特許庁シンポジウムを開催し、日中韓の各庁担当者や各国実務者によるテーマに沿った講演が行われた。
そして、2025年3月30日に、韓国・ソウルで日中韓経済貿易大臣会合が開催され、日本からは武藤経済産業大臣、議長国の韓国から安德根(アン・ドックン)産業通商資源部長官、中国から王文濤(オウ・ブントウ)商務部長が出席した。会合では、経済連携を含む多国間協力、ビジネス環境整備などの実務的協力について議論を行い、共同声明を公表した。日中韓FTAについては、武藤経済産業大臣から、第9回日中韓サミットにおける共同宣言を踏まえ、RCEPを超えた質の高い互恵的な協力を実現するために、経済面における様々な課題についても議論していく必要がある旨を述べ、交渉を加速するための議論を続けていくことで一致した。また、ビジネス環境の改善に向け、グローバルに公平な競争条件を確保するための取組を継続するとともに、サプライチェーン強化のため安定的な供給確保を図り、輸出管理の分野における意思疎通を強化することを確認した。
4. ASEAN・大洋州
(1) 総論
日本とASEANは、2023年に友好協力50周年を迎えた。経済産業省は、これまで日ASEANが培った”信頼”を原動力とし、これからの未来を共に創る「共創・Co-Creation」をキーワードに、将来を見据えた新しい時代の方向性を示す「日ASEAN経済共創ビジョン」を策定するなど、年間を通じて様々な取組を実施した。
2024年は、AZEC構想や「日ASEAN次世代自動車産業共創イニシアティブ」の推進、「日ASEANヤングビジネスリーダーズサミット及び将来世代ビジネスリーダーズサミット」の開催等を行い、マルチ・バイの経済関係の強化・共創に向けて、多くの成果を上げた。
また、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、豪州、ニュージーランド及び太平洋島嶼国と、通商分野での協力や日本企業のビジネス展開について議論を深め、各国との関係強化に努めた。
引き続き、ASEAN及び大洋州地域との経済関係の更なる強化に向けて、APEC、ASEAN 経済大臣会合、官民対話など様々な国際フォーラムの場を活用し、日本企業の投資・進出支援や現地人材育成等の投資環境整備支援を進めていく。
(2) 日ASEAN関係
① 日ASEAN経済大臣会合等での取組の概要
2024年9月21日、ラオスのビエンチャンで、経済産業省、ASEAN事務総長及びASEAN加盟国による第30回日ASEAN経済大臣会合が開催され、日本から吉田経済産業大臣政務官が出席した。会合では、吉田経済産業大臣政務官から、日ASEAN経済共創ビジョンの実現に向けて策定した「未来デザイン&アクションプラン」の進捗報告書を示し、改訂された同アクションプランが承認された。また、2023年に立ち上げた「日ASEAN次世代自動車産業共創イニシアティブ」に基づき2025年に策定予定とされた「次世代自動車マスタープラン」に向けて、ERIAの支援が歓迎された。その中では、特に運輸分野での公正なエネルギー移行及び脱炭素化において、多様な道筋を認めるべきであることについて認識共有を得た。さらにデジタル領域では、日本の新たな提案である「日ASEAN AIイノベーション共創ロードマップ」の策定に対して、賛意を持って留意された。
② 日ASEAN経済共創ビジョンにかかる取組
(i) 未来デザイン&アクションプランの改訂
日ASEAN経済共創ビジョンの実現に向けて、日本政府とASEAN各国の政府が取り組むべき施策を取りまとめた「未来デザイン&アクションプラン」について、施策の進捗が歓迎された。また、日ASEAN女性起業家サミットや自動車セクターにおける協力など、今年度の新たな施策を追記する改訂も承認された。
(ii) 日ASEAN経済共創フォーラムの実施
2024年12月、「日ASEAN経済共創フォーラム」を開催した。武藤経済産業大臣からは、分断が顕在化する世界情勢において、日本とASEANの信頼関係に基づく共創の重要性が述べられた(代読)ほか、日ASEAN間での今後の協力を見据えた、次世代自動車産業、デジタル・AI分野における協力、GXにむけた施策等に関する議論が行われた。
(iii) ヤングビジネスリーダーズサミット、Z世代ビジネスリーダーズサミットの開催
2024年12月、京都府京都市で、日ASEANヤングビジネスリーダーズサミット2024及びZ世代ビジネスリーダーズサミット2024が開催された。2023年、日ASEAN友好協力50周年を機に経済産業省が創設した両サミットでは、日本とASEANの将来のビジネスリーダーとなることが期待される人材が集まり、相互の理解・信頼関係を構築・強化することを目的として、経済・ビジネス上の課題、社会課題を共有するとともに、解決に向けた協力の在り方を議論した。
両サミットの成果物として、日本とASEANの若手ビジネスリーダーが主体となって、リーダー間の交流を加速するための委員会の立ち上げに合意したことなどを内容とする共同宣言を発出した。
(3) ASEAN各国との関係
① インドネシア
2024年5月、OECD閣僚理事会に際し、齋藤経済産業大臣がアイルランガ・ハルタルト経済担当調整大臣と会談を行い、日尼EPA、AZEC構想の推進、次世代自動車分野での協力等の多岐にわたる議題につき、議論を行った。
同月、齋藤経済産業大臣が、日経フォーラム第29回「アジアの未来」への参加のため訪日したアリフィンエネルギー鉱物資源大臣と会談を行い、日本とインドネシアが主導して立ち上げたAZECの下で、アジアのエネルギー移行を強力に推し進めることで一致した。
同年6月、齋藤経済産業大臣がアグス・グミワン・カルタサスミタ工業大臣と会談を行い、両国の未来を担う産業・人材を共に創る「共創」の実現に向けて、自動車、エネルギー分野等について意見交換を行った。
同年8月、AZEC閣僚会合に際し、齋藤経済産業大臣がアイルランガ・ハルタルト経済担当調整大臣、ロサン・ペルカサ・ルスラニ投資・下流化大臣と第2回AZEC Japan-Indonesia Joint Task Forceを開催し、再生可能エネルギー、廃棄物発電、送配電を含む多くのプロジェクトの進展を確認した。加えて、経済産業省とインドネシア・エネルギー鉱業省との間で、包括的なエネルギー協力に関する覚書に署名した。また、ロサン・ペルカサ・ルスラニ投資・下流化大臣よりAZECへの期待が寄せられ、AZECの推進に向けて協力していくことを確認した。
同年11月、APEC閣僚会議に際し、武藤経済産業大臣がブディ・サントソ商業大臣と会談を行い、10月の商業大臣への就任について祝意を伝えるとともに、EPA、RCEP、WTOなどの通商分野及び大阪・関西万博等に関する意見交換を行った。また、引き続き両国の経済関係を深化させることで一致した。
2025年1月、インドネシアを訪問した石破総理大臣は、プラボウォ・スビアント大統領と会談し、エネルギー安全保障の確保と多様な道筋による脱炭素化に向けて、資源・インフラ協力の推進を確認するとともに、AZEC構想下の具体案件の進捗を歓迎した。
同年2月、2023年5月の開催に続き、経済産業省及び経済担当調整府の次官級を議長とする第3回日・インドネシア官民経済対話(トラック1.5)を実施し、「デジタル」、「グリーン産業」、「人材育成」、「事業環境整備」等について議論を行い、今後の協力が確認された。
② マレーシア
2024年5月、岸田総理大臣は、訪日したアンワル首相と会談し、エネルギー移行や脱炭素化、レアアースを含む重要鉱物、デジタルやサイバーセキュリティ、サプライチェーンの強靱化など、経済安全保障に関する幅広い分野での協力を確認した。
同年6月、齋藤経済産業大臣はIPEF閣僚級会合等に参加するためシンガポールを訪問した際、ザフルル・アジズ投資貿易産業大臣と会談した。IPEF等の通商分野における連携を確認するとともに、半導体や航空機などの産業協力やAZECにおけるプロジェクトの推進等、これからの日マレーシア、日ASEANの経済関係を深化させていくことで一致した。
同年8月、吉田経済産業大臣政務官はAPECエネルギー大臣会合に出席するためペルー・リマを訪問した際に、ファディラ・ユソフ副首相と会談した。AZECでの連携強化、CCS(二酸化炭素回収・貯留)や水素分野における二国間エネルギー協力について意見交換をした。また、同月、齋藤経済産業大臣は第2回AZEC閣僚会合に参加するためインドネシアを訪問した際に、ラフィジ・ラムリ経済大臣と会談を行った。第3回AZEC閣僚会合を来年マレーシアで、両国で協力して開催することを確認するとともに、アンモニア、CCUS(二酸化炭素回収・貯留・利用)、SAF(持続可能な航空燃料)等について二国間協力を進めていくことで一致した。
同年10月、東京で、経済産業省及びマレーシア投資貿易産業省の審議官級を議長とする「第2回日マレーシア官民産業政策対話」が開催された。「サプライチェーンの強靱化(半導体、自動車)」、「ESG(環境・社会・ガバナンス)」、「スタートアップ支援・デジタルイノベーション」について官民を交えた議論が行われ、今後の協力が確認されるとともに、次回対話をマレーシアで開催することで合意した。
2025年1月、マレーシアを訪問した石破総理大臣は、アンワル首相と会談した。経済分野について、半導体や航空機部品といった重要なセクターにおけるサプライチェーンの強靱化やレアアース開発に関する協力を進めること、またエネルギー安全保障の確保と多様な道筋による脱炭素化に向けて、資源・インフラ協力の推進を確認した。具体的には、マレーシアからの今後の液化天然ガス(LNG)安定供給について確認するとともに、CCS、アンモニア発電、送電線分野での連携、海洋温度差発電、バイオマス分野の技術協力、水素やLNGなどの協力を更に進めていくことを確認するとともに、AZECにおいても協力を一層強化していくことで一致した。
③ フィリピン
2024年4月、齋藤経済産業大臣は米国ワシントンD.C.で、米国のジーナ・レモンド商務長官、フィリピンのアルフレド・パスクアル貿易産業大臣との、日米比商務・産業大臣会合に参加し、三か国の経済協力強化における共通の関心について議論を行った。三閣僚は、重要鉱物のサプライチェーン、半導体、オープンRANの展開、クリーンエネルギー、インフラ整備など、三か国の貿易・投資協力機会の可能性について議論し、5月にマニラで開催されたインド太平洋ビジネスフォーラム(IPBF)や、6月にシンガポールで開催されたIPEFクリーン経済投資家フォーラムなどを通じて、日米比首脳会合で確認された経済分野における成果の推進に向けて協力することを約束した。その後、岸田総理大臣、米国のバイデン大統領及びフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領の間で日米比首脳会合を行い、岸田総理大臣からは、日米比首脳会合の初開催を歓迎した上で、「世界が複合的な危機に直面する中、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向けて、同盟国・同志国との重層的な協力が重要であり、日米比三か国は、太平洋でつながれた海洋国家であり自然なパートナーである、インド太平洋地域の平和と繁栄のためにも、日米比協力の更なる強化を確認し、その具体的な方向性を示したい」旨を述べた。また、マルコス大統領から、バイデン大統領のイニシアティブに感謝しつつ、これまでの日本及び米国からの支援に謝意表明するとともに、日米比協力を一層強化したい旨の発言があった。
同年6月、齋藤経済産業大臣はシンガポールにて、IPEF閣僚級会合に参加していたアルフレド・パスクアル貿易産業大臣との会談を行った。日米比商務・産業大臣会合で推進することを確認したオープンRANのフィリピンにおける展開や、クリーンエネルギー分野での協力を推進していくことで一致した。また、AZECの取組の推進や、IPEF等の通商分野における協力の推進を確認した。
同年8月、齋藤経済産業大臣は、インドネシアにて、AZEC閣僚会合に出席していたロティリヤ・エネルギー大臣との会談を行った。アンモニアや原子力に関する日本企業等の取組について、今後も連携して進めていくことで一致し、協力してAZECの推進に取り組んでいくことを確認した。
④ シンガポール
2024年6月、齋藤経済産業大臣はシンガポールに出張し、IPEF閣僚級会合及びIPEFクリーン経済投資家フォーラム、日星共創プラットフォームに出席した。また、各国の代表者と二国間経済関係について意見交換を行った。
IPEF閣僚級会合は、全IPEFパートナー14か国が出席する形で開催され、日本からは、齋藤経済産業大臣、辻󠄀外務副大臣が出席した。同会合において、2023年11月に実質妥結に至ったクリーン経済協定、公正な経済協定、IPEF協定(各協定の横断的事項を扱うためのIPEF評議会の開催等について規定するもの)の三つの協定の署名式が行われ、齋藤経済産業大臣から「IPEFはインド太平洋地域において、21世紀的課題に対応するルールや協力の枠組み作りを主導する重要な取組である。パートナーとの協力により、三つの協定への署名という大きな成果を得ることができた。クリーン経済協定は今後、具体的な協力を進めていくフェーズに入る。「域内水素サプライチェーン・イニシアティブ」や「クリーン電力イニシアティブ」の下で、引き続き協力していきたい。2024年2月に発効したサプライチェーン協定についても、パートナーとともに、サプライチェーン強靱化に向けた平時・緊急時の取組を具現化していきたい」旨を発言した。IPEFクリーン経済投資家フォーラムでは、政府関係者、クリーン経済関連企業・スタートアップ、投資家の計300人以上が出席した。齋藤経済産業大臣は、日本の産業界が中心となって計画中の「日本水素ファンド」に、IPEF域内での案件組成を進めるための「IPEFウィンドウ」を設置することに加え、日本がIPEFで提案した水素及びクリーン電力に係るイニシアティブの進捗等を紹介した。また、2024年4月に日本で行われた日シンガポール官民経済対話で立上げが合意された日星共創プラットフォームのキックオフセミナーが開催され、齋藤経済産業大臣、タン・シーレン第二貿易産業大臣兼人材開発大臣の出席の下、日本とシンガポールの企業、投資機関、政府機関などから約200名が参加し、両国のオープンイノベーション施策の共有や、両国企業のオープンイノベーションに係る取組や連携の可能性、分野ごとに両国企業間のオープンイノベーションを加速するための取組について議論された。
2024年8月、齋藤経済産業大臣は、インドネシア・ジャカルタで行われた第2回AZEC閣僚会合の機会に、タン・シーレン第二貿易産業大臣と会談を行った。会談では、官民によるオープンイノベーション促進の重要性について一致するとともに、引き続き、協力して、AZECの推進に取り組んでいくことを確認した。また、CCSに関する協力覚書の作成を歓迎した。
⑤ タイ
2024年6月、石井経済産業大臣政務官は、チャヨティッド通商代表議長と会談し、脱炭素や自動車など日タイ協力の強化について一致した。また、2023年12月の首脳会談で立上げ検討に合意した「エネルギー・産業対話」の早期立上げに向けて、引き続き協力していくことを確認した。
2024年11月、岩田経済産業副大臣は、ナピントーン商務副大臣と会談を行い、通商分野、知的財産制度、コンテンツ産業、大阪・関西万博等について意見交換を行った。両大臣は、WTOなどの通商分野について意見交換を行うとともに、両国の知的財産制度に係る連携及び映画、アニメ、ゲームといったコンテンツ産業における連携の推進に向けた協力をしていくことを確認した。
同月、武藤経済産業大臣は、APEC閣僚会議に出席するためペルー・リマに出張し、ピチャイ商務大臣との会談を行った。武藤経済産業大臣から、日タイの投資・ビジネス関係の更なる強化に向けた連携を呼びかけるとともに、WTOなどの通商分野及び大阪・関西万博等について意見交換した。また、タイへの投資についても意見交換を行い、今後も連携していくことで一致した。
同月、武藤経済産業大臣は、エーカナット工業大臣と会談を行った。武藤経済産業大臣は、タイの自動車産業における競争力確保の重要性について述べるとともに、「エネルギー・産業対話」の早期開催を呼びかけた。両大臣は、同国の次世代自動車産業構築に向けて連携していくことで一致した。また、タイで事業を行う日本企業へのグローバルサウス未来志向型共創等事業を活用した具体的なプロジェクト支援、人材育成協力、大阪・関西万博などについて意見交換を行い、今後も様々な分野で連携していくことで一致した。
2025年1月には、「日タイ官民自動車ビジネスフォーラム」を開催した。本フォーラムでは、オンラインを含め約700名の参加者を前に、日本とタイそれぞれから自動車産業に関わる官民のステークホルダーが登壇し、四つのテーマでパネルディスカッションを行った。パネルディスカッションに先立ち、武藤経済産業大臣とマーリット外務大臣それぞれのビデオメッセージによる開会挨拶を行い、日タイの自動車産業における歴史的な絆を確認するとともに、次世代自動車産業の発展に向け、日タイ「エネルギー・産業対話」の早期開催を含めた両国の更なる協力の必要性を発信した。また、日本からは松尾経済産業審議官、タイからはナリット投資委員会長官がそれぞれ基調講演を行った。日本からは「GX・DXに対応した自動車産業政策について」をテーマに、EV(電気自動車)、FCV(燃料電池自動車)、ハイブリッド、バイオ燃料や合成燃料(e-fuel)の活用も含む「多様な選択肢」を通じて脱炭素化を実現していく、マルチパスウェイ戦略が日本の戦略の主軸であること、タイとは、次世代燃料、データ利活用、循環経済などの分野を通じて次世代自動車産業の共創を進め、今後も信頼するパートナーであるタイに寄り添い、共に未来を創っていくとのメッセージを発信した。さらに、パネルディスカッションでは、四つのテーマ((1)アジアの自動車生産/輸出ハブとしてのタイの強みと課題、(2)自動車のサプライチェーンの現況と今後の展望、(3)循環経済とエコシステム、(4)水素・e-fuel・バイオ燃料等のポテンシャル)で、両国のステークホルダーが参加し活発な議論が行われた。
2025年2月、武藤経済産業大臣は、タイのピチャイ副首相兼財務大臣と会談を行った。両大臣は、両国の自動車産業における脱炭素化の実現と国際競争力の強化の重要性について意見交換を行い、「エネルギー・産業対話」の早期開催に向けて緊密に協力することで一致した。 また、「日タイ投資フォーラム」に出席し、歓迎挨拶を行った。挨拶では、タイにはASEANで最多の約6,000社の日系企業が進出していることなどに触れ、両国の強固な経済関係を歓迎した。また、タイとの経済協力の柱である自動車産業について、長きにわたるサプライチェーン構築に関する連携の歴史、同国が輸出・生産のハブであり続けるための「マルチパスウェイ戦略」の重要性と、それを実現するバッテリーや水素等に関する先駆的な取組について言及した。さらに、大阪・関西万博が、タイのパビリオンのテーマである「大きな幸福のため、いのちをつなぐタイ」というテーマの下、高齢化という両国の共通課題の解決に向け、ビジネス交流が更に深まる機会となることへの期待を述べた。
⑥ ベトナム
2024年5月、齋藤経済産業大臣はレ・ミン・カイ副首相と会談を行い、2023年に格上げされた両国の新たなパートナーシップ関係のもと、新産業の創出や裾野産業の育成、高度人材の育成、AZECを通じたエネルギー協力等における分野で、両国の取組を連携して進めていくことを確認した。
同8月には、上月経済産業副大臣はグエン・マイン・フン情報通信大臣と会談を行い、デジタル化に関する取組や半導体分野における人材育成等の協力について意見交換、両国の取組を進めていくことを確認した。
同月、吉田経済産業大臣政務官とグエン・ホアン・ロン商工副大臣は、APECエネルギー大臣会合の際に意見交換を行い、AZECでの連携強化や、エネルギー移行分野での二国間協力を進めていく方針で一致した。
同12月には、第7回「日ベトナム産業・貿易・エネルギー協力委員会」を東京で開催し、共同議長である武藤経済産業大臣及びグエン・ホン・ジエン商工大臣は、グローバルサウス未来志向型共創等事業の活用を始めとしたサプライチェーン強靱化、レアアースなどの重要鉱物の安定確保に向けた協力及びAZECの下でのエネルギー移行や、洋上風力、原子力、LNG分野におけるエネルギー協力等について議論を行い、両国の取組を更に強化していくことを確認した。また、共同閣僚声明を発出した。
2025年2月、武藤経済産業大臣はグエン・ホン・ジエン商工大臣と会談を行い、日本におけるエネルギー政策の状況やベトナムにおける原子力発電所の建設計画について議論した。また、両大臣は、事務方での協議を含め、引き続き、実現可能な協力を進めていく意向を確認した。加えて、AZEC の下でのエネルギー協力、グローバルサウス未来志向型共創等事業の活用等を通じた産業協力について議論し、両国の取組を強化していくことを改めて確認した。
⑦ カンボジア
2024年5月、保坂経済産業審議官はスン・チャントール副首相と会談を行い、日本からカンボジアへの投資促進等について意見交換を行った。さらに、同10月、武藤経済産業大臣は、ラオスで開催されたAZEC首脳会合に出席した際に、ケオ・ラタナック鉱業エネルギー大臣と会談を行い、工場のグリーン化やバイオマス等に関連するカンボジアとの協力について確認し、今後も連携していくことで一致した。
⑧ ラオス
2023年9月、吉田経済産業大臣政務官は、ラオスにて開催された日ASEAN経済大臣会合の際に、マライトーン商工業大臣とともに、グローバルサウス未来志向型共創事業補助金を活用し現地経済特区の脱炭素化に取り組む日ラオス等関係企業によるLOI(意向表明書)調印式に出席したほか、マライトーン商工大臣とラオスにおける日本企業の取組や、ハンディクラフト産業への技術協力の進展について意見交換を行った。
(4) 大洋州各国との関係
① 豪州
2024年6月、齋藤経済産業大臣は、シンガポールで開催されたIPEF閣僚級会合において、ドン・ファレル貿易・観光大臣と会談を行い、「特別な戦略的パートナー」である豪州と、WTOやCPTPP等の通商分野での協力等における日豪連携の重要性を相互に確認した。また、AZECの取組の推進やクリーンエネルギー、LNG、重要鉱物など、資源エネルギー分野での協力を深化させていくことで一致した。
2025年1月には、武藤経済産業大臣がジャスティン・ヘイハースト駐日大使と会談を行った。「特別な戦略的パートナー」である日豪両国間で、資源・エネルギーや通商政策を始めとする様々な分野について意見交換を行うとともに、2025年大阪・関西万博等も通じて、日豪関係を引き続き強化していくことを確認した。
同月に、武藤経済産業大臣はマデレーン・キング資源大臣兼北部豪州担当大臣と会談を行った。LNGや石炭等の資源の安定供給と信頼できる投資環境の確保、そして重要鉱物のサプライチェーン強化に向けた協力について意見交換を行うとともに、大阪・関西万博等も通じて引き続き日豪関係を強化していくことを確認した。
② ニュージーランド
2024年5月にパリで開催されたOECD閣僚理事会において、齋藤経済産業大臣はマクレイ貿易大臣と会談を実施し、WTOやIPEF、CPTPP、RCEP等の通商分野における協力等を確認した。また、齋藤経済産業大臣から、ALPS処理水の海洋放出について、ニュージーランドが日本の立場に支持を表明していることに謝意を示すとともに、引き続き高い透明性をもって情報提供していく旨言及しました。
③ 島嶼国
2024年7月17日、東京で、経済産業省、外務省、JETROの三者により、太平洋島嶼国の要人と日本企業との関係構築や、太平洋島嶼国における日本企業のビジネス機会の創出を目的とした「第4回日本・太平洋島嶼国経済フォーラム」を開催した。
経済産業省からは上月経済産業副大臣、外務省からは高村外務大臣政務官、太平洋島嶼国・地域からは首脳・閣僚等が出席し、日本企業など66社・機関が参加した。上月副大臣は、島嶼国が抱える、気候変動、エネルギー、廃棄物処理などの社会課題の解決に貢献するための経済産業省の取組や本フォーラムへの期待を述べた。
なお、このフォーラムで、上月経済産業副大臣はクック諸島のマーク・ブラウン首相と会談を行った。会談では、マーク・ブラウン首相より、日本が引き続き機械等の分野において世界一であり、日本に期待をしている旨が述べられた。
同様に、パプアニューギニア(PNG)のジェームズ・マラペ首相とも対話を行い、PNGも参加表明している万博の成功への期待と、両国間のより緊密な連携の重要性を確認した。
2024年10月、フィジーで太平洋島嶼国における社会課題と日本のスタートアップ等が有するソリューションをつなぐビジネスマッチングを開催した。日本側は経済産業省通商政策局審議官、駐フィジー日本国大使を始め約40名、島嶼国側はPNG投資促進庁(IPA)長官を始め、太平洋諸島フォーラム(PIF)加盟国から約40名、合計約80名が出席した。ビジネスマッチングイベントでは、フィジー、パラオ、PNG、サモアの4か国から、各国が抱える社会課題についてプレゼンが行われ、日本企業12社から、各社が有するソリューションについてピッチが行われた。また、6社については、ビジネス展開に関するMOUや売買契約等の締結を実施した。島嶼国における日本企業・技術に対する期待の高さをあらためて理解するとともに、島嶼国地域との経済関係強化を進めていくことを確認した。
5. 南西アジア
(1) インド
① 二国間協力
インドの人口は2023年時点で14億人363を超え世界第1位となり、また、GDP成長率は8.2%364と高い水準にある。2024年にナレンドラ・モディ首相が3期連続となる当選を果たした。引き続き、「Make in India」等の様々なイニシアティブを打ち出し、経済改革、製造業振興による雇用の創出、投資促進のためのビジネス環境整備、インフラ整備等を進め、インドの国際競争力強化に取り組んでいる。日本とインドは、特に人材育成、エネルギー、デジタル等の分野で協力を進めており、2023年時点でインドに進出している日系企業は1,400社365となっている。
日印関係においては、2014年に二国間関係を「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」と宣言する等、これまでも良好な関係を構築してきた。2024年は「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を締結して10年の節目に当たり、多数の政府要人が往来した。
2024年7月には、額賀衆議院議長を筆頭に経済界との官民合同ミッションを組成して訪印し、モディ首相やジャイシャンカル外相ら多数の政府要人と会談を行った。額賀衆議院議長とモディ首相との会談時には、ITを始めとした幅広い分野において、5年で5万人以上の双方向の人材交流を行うことを提案した。2024年9月には、ヴァイシュナウ鉄道、情報・放送、電子・IT大臣が来日し、齋藤経済産業大臣と会談し、半導体やAIを含めたデジタル分野での新たな連携について議論した。
そのほか、2024年8月に、プラサダ商工/電子・IT閣外大臣、2024年9月にバジャン・ラル・シャルマ・ラジャスタン州首相、2025年1月にヒマンタ・ビスワ・シャルマ・アッサム州首相とモハン・ヤーダヴ・マディヤ・プラデシュ州首相が来日し、それぞれ経済産業副大臣や経済産業大臣政務官と会談を行った。これらの要人面談では、日印両国間の緊密な経済関係を踏まえつつ、日印特別戦略的グローバル・パートナーシップの下での企業間協力も含め、日印の更なる経済関係の深化について意見交換が行われた。2025年3月には、日本商工会議所日印経済合同委員会訪印団とともに依田大臣官房審議官(通商政策局担当)が官民ミッションとしてモディ首相に表敬した。5年で5兆円の官民投融資目標が、2年で約3.8兆円366を達成していることを報告するとともに、2021年時点でインドに進出する日本企業がインドからアフリカ等の第三国に1.1兆円367相当の輸出を行い、インドにおける7,000億円の外貨獲得に貢献している旨説明した。
さらに、2024年1月には、近畿経済産業局が、関西の経済団体や自治体・支援機構等によるインドビジネスに関する最新動向の共有や、協働での事業実施を検討する場として、「関西インドビジネス交流促進連絡会議」を創設した。2025年2月には「日本・インド・アフリカ官民フォーラム」を開催し、インドを足掛かりにアフリカまで広がる巨大経済圏を狙う世界戦略の展望や課題、官民の果たす役割について議論した。また、本フォーラムにおいて武藤経済産業大臣は、「アフリカの持続可能な経済発展のための日印協力イニシアティブ」を打ち出した。このイニシアティブは、日本とインドが協力して、インドにおける日本企業の集積・拠点化を通じ、アフリカ諸国での民間主導のビジネスや投資を推進することを目的としており、今後、2025年8月に開催予定のTICAD9に向けて、更に機運醸成を促進していく。
363 世界銀行「World Development Indicators」
364 世界銀行「World Development Indicators」
365 在インド日本国大使館、JETRO「インド進出日系企業リスト」
366 インド財務省及びJICA公表資料より、JETRO、JCCII、NRI算出。
367 海外事業活動基本調査を用いて佐藤隆広教授・加藤篤行教授が算出。
② 日印産業協力
人材交流については、2024年7月、額賀衆議院議長がモディ首相と会談し、日印間で次の世代を共に創造するために、ITを始めとした幅広い分野で人的交流を推進すべきとの考えを示した。具体的には、①日本企業とインド人学生とが交わる接点の強化(インド人学生に対する日本企業への就職促進支援等)、②日印の大学間、企業と大学間・企業間での共同研究の推進と両国のスタートアップ支援の拡大、③日本企業によるインドのものづくり人材育成支援、④これらの取組の基盤造りとしての日本語教育や留学の促進を通じて、今後5年間で5万人以上の日印の架け橋人材交流を提案し、モディ首相は全ての点に賛成すると応じた。2024年12月には、このような日印間の人材交流促進に向け、「グローバルサウスとの連携強化に資する共創型技術人材交流事業」において、インド人材の育成・活用推進を目的とする予算が措置された。このほか、2016 年 11 月の日印首脳会談で決定した 10 年間で 3 万人のものづくり人材の育成を目指し、製造業の人材育成に係る「日本式ものづくり学校(JIM)」及び寄附講座(JEC)の新規開設に取り組んでおり、2024年度には、新規のJIM 3件が開校し、合計でJIMは40校、JECは12講座が展開されている。
半導体協力については、2023年7月に署名された「日印半導体サプライチェーン・パートナーシップ」に基づき、同11月に第1回日印半導体政策対話がオンラインで開催された。さらに2024年5月には、半導体分野における人材・研究開発での協力に関する会合がオンラインで開催され、日印の半導体関連企業や研究機関などから計100名以上が参加した。また、同9月、齋藤経済産業大臣は、ヴァイシュナウ鉄道、情報・放送、電子・IT大臣と会談を行い、「日印半導体サプライチェーン・パートナーシップ」におけるこれまでの成果を確認した。
エネルギー協力については、2022 年3月の岸田総理大臣訪印時に、日印エネルギー政策対話の下で取り組んできた二国間協力分野を拡大し、11分野で、政府間の情報交換のほか、官民ワークショップの開催、研究開発や人材育成など、両国のエネルギー分野での協力関係を一層強化していく「日印クリーン・エネルギー・パートナーシップ」を発表した。2023 年 3 月の日印首脳会談時にも、同パートナーシップの下で両国の協力を促進していくことで一致している。2025年1月から3月にかけて、日印エネルギー対話の下の四つのWG(電力・省エネルギー、新・再生可能エネルギー、石油・天然ガス、石炭)が開催された。
デジタル分野での協力については、日印デジタルパートナーシップの下、日本企業とインドの優秀なIT人材のマッチングを支援する Japan-Dayという就職説明会が、インド工科大学(IIT)ハイデラバード校で2018 年以降毎年開催されており、2024年8月には第7回として「Japan Career Day(ジャパン・キャリア・デー)2024」が開催され、日系企業18社及び学生450名以上が参加した。また、2024年8月には、経済産業省とJETROの主催で、バンガロールにおいて「日印イノベーションピッチ」が開催された。同イベントは、両国の大企業とスタートアップ企業の協業を促進するピッチイベントで、会場には日印の政府関係者・企業関係者から200人以上が参加した。ほかにも、2024年度から「グローバルサウス未来志向型共創等事業」が行われており、インドでは13件のデジタル分野でのプロジェクトの支援が行われている。
2019年に梶山経済産業大臣とゴヤル商工大臣の間で立ち上げられた日印産業競争力パートナーシップについては、2024年6月にデリーで第6回次官級会合が、保坂経済産業審議官とシン印商工省産業国内取引促進局次官との間で開催された。2022 年3月の日印首脳会談時に合意された5年5兆円の投融資目標の実現に向けて、両国で人材協力を含めた産業協力及びインドにおけるビジネス環境改善を一層推進することで一致した。また、2024年度には、同パートナーシップ下で省庁横断的に設置されている、中小企業・進出日本企業課題解決(ファスト・トラック・メカニズム)・自動車・物流・鉄鋼の各分野別ワーキンググループが相次いで開催され、各分野における二国間協力の方向性の協議が行われた。
(2) バングラデシュ
バングラデシュは、ベンガル湾に面し、成長著しい南アジアと東南アジアを結ぶ戦略的要衝にあり、南西アジア地域の発展において重要な役割を果たす国である。日本とは1972年の外交関係の樹立以来、友好的な関係を築いており、日本はバングラデシュにとって最大の二国間援助供与国である。また、バングラデシュは、2026年にLDC(後発開発途上国)からの卒業を目指しており、それに向けて両国間で様々な経済協力を推進している。
2014年8月には、バングラデシュへ進出している日本企業が直面するビジネス課題の解決や、両国間の投資・貿易促進を目的として「日本・バングラデシュ官民合同経済対話(Public-Private Joint Economic Dialogue: PPED)」が立ち上げられた。本対話はこれまでに計6回開催されており、四つのワーキンググループ(投資環境、税・金融、産業多角化、エネルギー)の下で議論が行われた。2023年4月に行われた首脳会談時には、両国の関係を戦略的パートナーシップに格上げした他、両国間の官民協力を通じたバングラデシュの産業高度化を促進する枠組みである「日本・バングラデシュ産業高度化パートナーシップ(Bangladesh-Japan Industrial Upgrading Partnership: BJIUP)」が立ち上げられた。本パートナーシップについては、2025年2月にボシール商業商担当顧問が来日し、大串経済産業副大臣と面会した際に、2025年内に第一回会合を開催することで合意している。
2024年3月に交渉開始が決定された「日・バングラデシュEPA」については、2025年3月末時点で計4回の交渉会合が実施されている。
(3) パキスタン
2022年9月、里見経済産業大臣政務官を日本側共同議長として、第7回官民合同経済対話をイスラマバードで開催した。対話では、日本パキスタン間の経済関係の深化のため、貿易及び投資環境整備等が議論された。また、同地訪問中の里見経済産業大臣政務官は、カマル商業大臣(パキスタン側共同議長)のみならず、シャリフ首相、マフムード産業大臣、フセイン投資庁長官等と会談し、国交樹立70周年を境として、一層パキスタンとの経済関係を強化していくことについて一致した。
(4) スリランカ、ブータン等
スリランカは、2009年に26年間続いた内戦の終結以降、経済成長が加速していた。しかし、慢性的な赤字に加え、コロナ禍の影響により観光収入が減少したこと等により、外貨不足が深刻化し、2022年春以降には経済危機に陥った。同国に進出している日系企業のアンケート調査によると、2023年8~9月には経済回復の傾向にあるという結果が出ている。2024年11月には、2022年の市民の抗議活動以降、最初の大統領選が開催され、アヌラ・クマーラ・ディサナヤケ大統領が就任した。2019年に第11回官民合同経済フォーラムが開催されて以降の経済関係強化が期待される。
ブータンは、2023年に、ジグミ・ケサル・ナムギャル・ワンチュク第五代国王陛下による新たな特別行政区の設立と、ゲレフ・マインドフルネス・シティ構想が発表された。同構想は、参入する企業や人々がブータンの文化や伝統に配慮しつつも、機動的イノベーション事業を創出していくことを目指す。この特別行政区は、ブータン国中南部地域にあるゲレフ市・サルパン県に、約2,000km~2,600kmを跨ぐ形で新規に都市を形成していくことが想定されており、今後、境界線を含めた事業の詳細が決定される。ブータンの他、ネパールやモルディブについても、各国の状況に応じて、経済連携強化の在り方について検討していく。
6. 中南米
(1) 今後の方針
中南米地域は、6.5億人超の人口を擁し368、巨大な消費市場や中間所得層も多く、日本の高付加価値製品の輸出先として魅力的であるとともに、労働生産人口も比較的若く、安価な労働力を活用した生産拠点としての役割を担うほか、日本企業の潜在的な投資先、進出先としても有望である。また、中南米地域は、経済、エネルギー及び食料等安全保障の観点からも我が国にとって重要な地域であり、気候変動対策やデジタル関連産業の基盤を支えるリチウム、銅や幅広い産業分野で利用される鉄鉱石等の鉱物資源、大豆、とうもろこし、鶏肉を始めとする食料資源の日本向けの供給を支えている。
世界銀行によれば、2024年の中南米における経済成長率は2.2%である369。世界的なインフレやブラジルの金融引締め政策、貿易相手国の米国の成長率低下などの影響を受け、2021年の7.2%370、2022年の3.9%371、2023年の2.2%から連続で軟化した。国・地域ごとでは、メキシコ・ブラジル等の主要国では、難しい経済・財政政策のかじ取りが必要となるが、一部の中米・カリブ諸国はコロナ禍による景気後退からの回復基調が継続し、成長率が拡大すると予想される。
中南米地域の政治面では、コロナ禍に起因する経済悪化や大衆迎合主義の台頭を受け、直近は左傾化の潮流(ピンクタイド)が顕著との論調もある。しかし、2023年8月、グアテマラ大統領選挙ではジャマテイ氏(右派)が当選、同12月、アルゼンチン大統領選挙ではミレイ氏(右派)が当選するなど、従来の保護主義的な動向ではなく、権威主義的な体制を批判し、市場にも配慮した穏健な経済政策を模索する国も現れている。世界情勢が不安定化する中で、中南米諸国は、民主主義、法の支配、基本的人権の尊重など基本的価値を共有するパートナーとなり得る国も多く、価値観外交として日本と中南米における経済関係を更に強化していく必要がある。
中南米地域は、伝統的に米国と強い経済関係を有していたが、中国の同地域での経済的影響力が高まっている。例えば、ブラジル、チリ、ペルー等において、中国は最大の貿易相手国となっているほか、中南米地域のインフラ整備プロジェクトに積極的に投資を行っている。他方、米国は、引き続き主要な貿易投資相手国としての地位を維持しているが、2025年1月の第二次トランプ政権発足以降、中南米諸国(キューバは除く)に対して各種関税措置を講じており、これが米国と中南米地域との間の貿易投資に及ぼす影響については、今後注視していく必要がある。
368 世界銀行「World Development Indicators」
369 世界銀行「Global Economic Prospects」(2025年1月)
370 同上。
371 同上。
(2) 日・中南米における経済分野の協力について
中南米地域では、メルコスールとEUの間で継続していたFTA交渉について、2024年12月にメルコスール主要4か国との政治合意に達するなど、中南米の国・地域との貿易拡大を目指す動きが見られ、同地域における新たなビジネス機会が拡大する可能性がある。加えて、世界情勢の不安定化を背景とした、経済、エネルギー及び食料安全保障に対する関心の高まりや、サプライチェーン強靱化を通じた重要物資の安定供給確保に対する要請の高まりなどを背景に、日本と中南米諸国との間で、重要鉱物、水素・アンモニア、バイオ燃料及び合成燃料(e-fuel)など資源・エネルギー分野において新たな協力が推進されている。さらに、日本企業が有する技術やノウハウを活用しながら、成長著しい中南米諸国における産業の高度化や顕在化する社会課題の解決を目指す動きも見られる。
例えば水素に関して、メキシコでは、在メキシコ日本商工会議所内に水素分科会が設置されており、2024年9月にJETROメキシコ事務所主催の水素フォーラムを開催した。また、ペルー・エネルギー鉱山省と経済産業省との間で、2024年11月に「エネルギー移行に関する協力覚書」を締結するなど、具体的連携に向けた機運が高まっている。加えて、ブラジルとの間では、2024年5月、岸田総理大臣のブラジル訪問時に、ブラジルのバイオ燃料・合成燃料(e-fuel)等に関する高い潜在力と、日本が有するハイブリッド車等の高効率モビリティに関連する先端技術を結び付け、世界の炭素中立の実現に貢献する「持続可能な燃料・モビリティ・イニシアティブ(Initiative for Sustainable Fuel and Mobility: ISFM(アイスファム))」を立ち上げた。ブラジルと共に、その重要性を世界に発信するべく、2025年3月のルーラ・ブラジル大統領訪日時には協力覚書を締結した。
鉱物分野においても、2024年5月に、ブラジル(ミナスジェライス州経済開発局、ミナスジェライス州開発促進公社)とJOGMECの間で、「重要鉱物資源分野に関する協力覚書」が締結された。また、2024年11月には、ペルー・エネルギー鉱山省と「金属鉱物分野における協力の促進を目的とした新たな覚書」が締結された。2024年10月には、アルゼンチンでJETRO鉱物ミッションが実施された。
農業、ヘルスケア、防災等の社会課題分野でも、日本と中南米地域の間で連携できる可能性が高い。2024年5月の岸田総理大臣のブラジル訪問時や、2025年3月のルーラ・ブラジル大統領訪日時に発表された、日ブラジル間の協力案件の中にも、社会課題解決に有用なプロジェクトが多く含まれていた。2024年9月にコロンビアで開催した「第1回日コロンビア貿易投資・産業協力合同委員会」でも、社会課題分野における協力可能性が議論された。
経済産業省は、今後も、幅広い分野において、グローバルサウス未来志向型共創等事業等を活用しつつ、本邦企業の中南米地域におけるビジネス機会の拡大及び現地進出を支援すべく、ビジネス環境の整備等を図っていく。
なお、メキシコでは、自動車分野の日系企業を中心に、USMCAや米国インフレ削減法(IRA)等を活用した北米地域内でのサプライチェーンの構築と強靱化が図られてきたが、2025年に入ってからの米国による各種関税措置によって、ビジネス環境は不透明になっている。その対応策として、メキシコの製造拠点から中南米地域への輸出を検討するなど、輸出先を多様化し、ビジネスリスクを分散させようとする日本企業の動きも見られる。経済産業省は、メキシコ国内の日系企業と連携を取りつつ、柔軟な対応・支援を行っていく。
(3) 進捗状況
① 中米・カリブ地域
メキシコについては、2024年8月、吉田経済産業大臣政務官がメキシコを訪問し、メキシコ日本商工会議所及び現地進出日系企業関係者と会談を行った。会談では、今後の日メキシコ経済関係強化に向けた期待やメキシコにおけるビジネス環境の課題等について意見交換を行った。また、日墨協会関係者と面談し、二国間の関係強化に向けて意見交換を行った。
同10月、シェインバウム大統領就任式が実施され、中曽根弘文特派大使が出席した。この際に、エブラルド次期経済大臣と会談を行った。会談では、元外務大臣でもある同大臣と、二国間関係、特に経済関係の重要性について認識を共有したほか、両国の新政権の下、より一層関係を強化していくことを確認した。また、中曽根特派大使は、メキシコ日本商工会議所の幹部と懇談を行った。懇談では、各企業や同会議所の近年の活動、当地でのビジネス環境等につき意見交換を行った。
同11月、メキシコで、メキシコ日本商工会議所創立60周年記念イベントを実施した。イベントでは、武藤経済産業大臣よりビデオメッセージでお祝いの言葉を述べるとともに、2025年は日メキシコEPA発効20周年を迎えるに当たり、エブラル経済大臣らメキシコ政府関係者と連携して両国経済の更なる発展に向けて取り組む旨発言した。
USMCAにおける労働分野の紛争早期解決メカニズム(RRM)については、2024年度末時点で計31件の要請が行われた。2022年までは、その全てがメキシコ内の自動車関連部品工場における労働権侵害の疑いに基づくものであったが、2023年以降は、アパレル、鉱山開発、航空貨物、食品分野など対象分野が拡大しており、日系企業もその内数に入る。そのほとんどは、メキシコ政府による積極的な協力によって、短期間での解決に至っている。他方、2025年3月、米国第二次トランプ政権は、メキシコ・カナダ産品に追加関税を発動しつつ、USMCA原産地規則を満たす産品を適用対象から除外するなどの動きが生じており、USMCAを巡る動きについては、今後も注視が必要である。
ドミニカについては、2024年5月及び6月、ドミニカにおける鉄道/インフラ海外展開セミナーを実施し、浦田経済産業省製造産業局審議官が冒頭挨拶を行った。
コスタリカについては、2024年8月、トバル貿易大臣が訪日し、石井経済産業大臣政務官と会談を行った。会談では、二国間経済関係の強化や、ルールベースの貿易体制の維持・強化等について意見交換するとともに、WTO改革や、来年コスタリカが議長を務めるOECD閣僚理事会での取組における連携の重要性などを確認した。また、ブルネル副大統領、トバル貿易大臣らが出席するコスタリカ貿易省主催の昼食イベントが実施され、石井経済産業大臣政務官が出席し、冒頭挨拶を行うとともに、今後の二国間経済関係のますますの活発化への期待を述べた。
ガイアナについては、2025年1月、ラムサループ投資庁長官が訪日し、古賀経済産業副大臣と会談を行った。会談では、防災・気候変動分野等での更なる協力や炭素中立の実現に向けた二国間経済関係の強化について意見交換を行うとともに、大阪・関西万博の成功に向け、引き続き連携を強化していくことを確認した。また、ラムサループ投資庁長官と日本のスタートアップ企業との意見交換を行うとともに、農業分野における共創を模索した。
② 南米地域
コロンビアについては、2024年9月、依田経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当)がコロンビアを訪問し、第1回日コロンビア貿易投資・産業協力合同委員会を開催した。本委員会では、ビジネス環境改善や貿易投資促進に向けた意見交換を行った。また、本年からコロンビアにて実施されるグッドデザイン賞の設立イベントが開催された。
チリについては、2024年5月、石井経済産業大臣政務官がチリを訪問し、ウィリアムス鉱業大臣と、鉱業分野における二国間協力の今後の在り方について意見交換を行った。また、サンウエサ外務次官(国際経済担当)と会談を行い、リチウム開発などでの協力、APECやWTO等のマルチの場でも両国が連携していくことに合意した。このほか、8年ぶりに開催した鉱業分野における第2回官民合同会議に出席した。
同6月、齋藤経済産業大臣が、ウィリアムス鉱業大臣と、持続可能なリチウム資源開発への協力や鉱業分野の日チリ官民合同会議の定例化を新たに追加するために、鉱業及び鉱物資源分野に関する協力覚書改訂に署名した。また、同日、ウィリアムス鉱業大臣は、JOGMEC及び駐日チリ大使館共催の「チリにおけるクリティカルミネラルとリチウムの持続可能な開発戦略セミナー」に参加し、ウィリアムス鉱業大臣から直接、チリの鉱業政策や投資環境などについて説明があり、セミナー出席者と意見交換を行った。
ペルーについては、2024年5月、石井経済産業大臣政務官がペルーを訪問し、ムーチョ・エネルギー・鉱業大臣と、鉱業分野における二国間協力の今後の在り方について意見交換を行った。また、ゴメス通商観光副大臣と会談を行った。会談では、石井経済産業大臣政務官より、APECでの投資課題における両国連携や鉱業分野の更なる協力関係を強化していくことを提案するとともに、今後も様々な機会を活用して緊密に意思疎通を重ねていくことで一致した。このほか、5年ぶりに開催した鉱業分野における第2回官民合同会議に出席した。
同7月、齋藤経済産業大臣は、水素研修のために訪日したムーチョ・エネルギー・鉱業大臣と会談を行った。会談では、ペルーが鉱物資源分野において重要な供給国であることを確認し、両国の経済関係の強化の重要性についての認識を共有するとともに、エネルギーや鉱業分野における協力について意見交換を行った。同8月、APEC貿易担当大臣会合の場で、吉田経済産業大臣政務官はムーチョ・エネルギー・鉱業大臣と会談を行った。会談では、エネルギー移行分野での協力や鉱業分野での対話などを進めることについて意見交換を行った。同11月、安永日本ペルー経済委員会委員長が石破総理大臣を表敬し、ペルーで開催された第15回日本ペルー経済協議会で採択された共同声明を手交した。共同声明は、鉱業・農業分野における各種手続の簡素化や、脱炭素化への取組推進に向けた戦略的税制、二国間クレジット制度(JCM)の導入などの必要性を主張するもので、安永委員長は2024年10月、ボルアルテ大統領にも手渡した。同11月、武藤経済産業大臣とムーチョ・エネルギー・鉱業大臣は、エネルギー移行に関する協力覚書を署名及び締結し、ネット・ゼロ/炭素中立という共通の目標を追求することの重要性を認識しつつ、再生可能エネルギー、省エネルギー、水素・アンモニア等の分野における協力を促進・深化することに合意した。
ブラジルについては、2024年5月、岸田総理大臣がブラジルを訪問し、日・ブラジル・ビジネスフォーラムにジェラルド・アルキミン副大統領兼開発・産業・貿易・サービス大臣とともに出席した。同フォーラムでは、岸田総理大臣が冒頭挨拶を行い、経済分野における両国の連携には極めて高いポテンシャルがあり、「日ブラジル・グリーン・パートナーシップ・イニシアティブ(GPI)」の下で、官民で連携し、日ブラジル協力を強化していく旨述べた。その上で、デジタルやグリーンの分野を含め、様々な分野での貿易・投資関係を一層強化していく旨述べるとともに、ブラジルにおける日本のスタートアップ支援も強化する旨述べた。また、岸田総理大臣はルーラ大統領と、ブラジルが高いポテンシャルを有するバイオ燃料・合成燃料(e-fuel)等と、ハイブリッドエンジン等の日本の高効率モビリティを組み合わせて、炭素中立の実現を目指すべく、新たな国際枠組みである ISFM(アイスファム)を立上げることに合意した旨述べた。これに加えて、岸田総理大臣及びアルキミン副大統領の前で約40件のMOU等の発表式を行った。
2025年3月、ルーラ大統領が国賓として訪日し、JETRO、経団連、ブラジル全国工業連盟(CNI)共催の下で、日・ブラジル経済フォーラムが開催された。両国政府・民間企業等から500名超が参加し、両首脳の前で官民合わせて84件の覚書等が発表されるとともに、経団連及びCNIは「日本メルコスールEPAの早期実現を求める共同声明」を両首脳に手交した。また、首脳会談後の覚書等発表式においては、ブラジル関係省庁(開発産業貿易サービス省、鉱山エネルギー省、外務省、港湾空港省)とISFM(アイスファム)に関する覚書・アクションプランに合意した。この合意により、バイオ燃料等と高効率モビリティの組み合わせを通じた脱炭素化の重要性を、協力して世界に発信することとなった。さらに、2024年5月に署名された「日伯産業共創イニシアティブ」をベースに、新たな分野を追加し、協力の範囲と質を新たなレベルに引き上げた「日伯産業統合イニシアティブ」の立上げにも合意した。「日伯貿易投資促進・産業協力合同委員会」を通じて、行動志向の取組を進めていくこととした。
アルゼンチンについては、2024年11月、パソ経済省調整担当長官(生産・商業・産業・農業総括担当)が訪日し、松尾経済産業審議官と会談を行った。会談では、アルゼンチン進出日系企業によるアルゼンチン経済再建への貢献や、鉱物・エネルギー分野について意見交換を行った。
太平洋同盟については、2024年4月、ペルーからチリに議長国が引き継がれた。日本は、太平洋同盟諸国を民主主義、法の支配等の基本的価値を共有する重要なパートナーと捉えており、ともに成長し、相互の利益になる形で、DXやGX等の官民双方が関心を有する分野での協力を拡大している。引き続き、太平洋同盟諸国と共に、共通の課題に取り組み、具体的な協力を推進していく方針である。
メルコスールについては、2024年11月、武藤経済産業大臣が安永日本ブラジル経済委員会委員長及びピメンタ・ブラジル日本経済委員会委員長と会談を行った。会談では、日本ブラジル経済合同委員会で採択された「日伯経済関係の推進に向けた共同声明」及び「日本メルコスールEPAの早期実現を求める共同提言」が手交された。これに対して、武藤経済産業大臣は、日本とブラジルの二国間及びメルコスールとの経済関係強化に向けて両国経済界から具体的な提言を頂いたことと、日本とブラジルの経済関係強化に貢献してきた両国経済界関係者の努力に対する感謝を述べた。その上で、メルコスールとの経済関係の強化は、貿易投資の拡大や日本企業の競争条件の確保の観点からも重要であることを指摘し、外交関係樹立130周年を迎え、大阪・関西万博にブラジルパビリオンが出展される2025年以降も、日本とブラジル及びメルコスールとの人的交流と経済交流がより活発になることへの期待を示した。2025年3月、日・ブラジル経済フォーラム(上述)が開催された際に、経団連及びCNIは石破総理大臣及びブラジル・ルーラ大統領に、「日本メルコスールEPAの早期実現を求める共同声明」を手交した。
7. ロシア・中央アジア・コーカサス
(1) 日露関係
2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナへの侵略が長期化する中、日本政府は、G7を始めとする国際社会と連携し、個人・団体等に対する制裁、銀行の資産凍結等の金融分野での制裁、輸出入禁止措置等の対露制裁を維持・強化している。
また、ロシアによるウクライナへの侵略により、経済分野を含めた二国間関係を従来どおりとすることは困難な状況であることから、2016年に提案された8項目の「協力プラン」を含む、ロシアとの経済協力に関する政府事業は、当面見合わせることを基本としている。こうした状況下で、これまでにロシアに進出してきた日本企業には、ビジネス環境の悪化やロシア政府による対抗措置等によって、多大な影響が生じている。経済産業省は、JETROやNEXIに相談窓口を設置し、影響を受ける日本企業の事業活動について支援を行うとともに、進退を含めた経営判断に迫られる日本企業に対して、その経営判断に資するよう情報提供等を実施している。
(2) ロシア・ベラルーシ等輸出入等禁止措置・資産凍結等措置
ロシアによるウクライナへの侵略に対し、我が国はG7を始めとする国際社会と連携しつつ、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、ロシア向け輸出入に関する制裁措置を実施してきた。2024年度は以下の措置を実施した。(以下、措置の施行日・適用日を基準に記載)
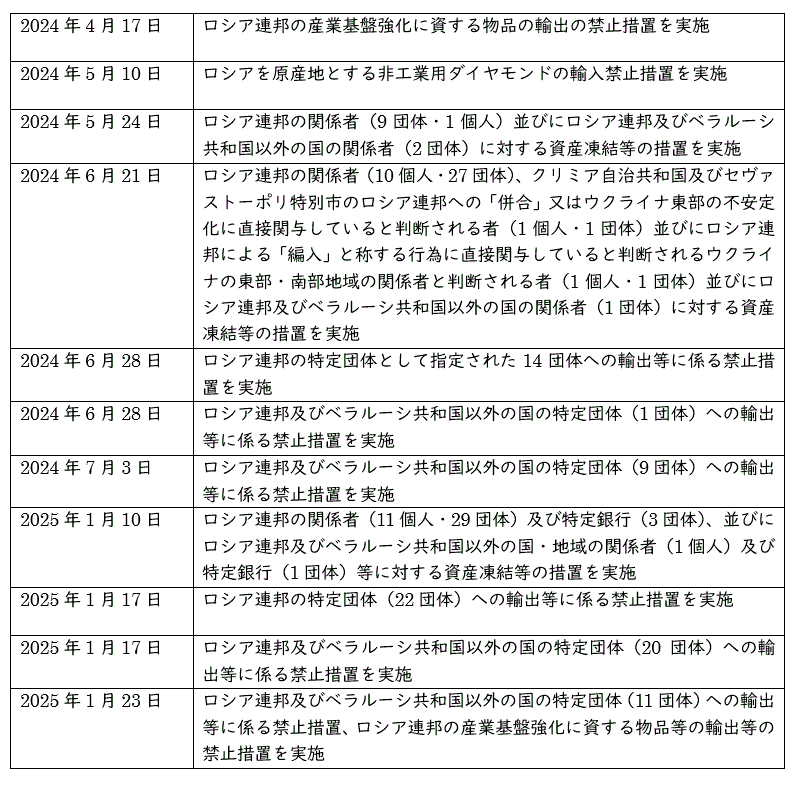
2025年3月時点で経済産業省が実施しているロシア・ベラルーシ等に係る輸出入等禁止措置の概要は、以下のとおりである。
(1)国際輸出管理レジームの対象品目372のロシア及びベラルーシ向け輸出等の禁止措置
(2)ロシア及びベラルーシの軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品373の両国向け輸出等の禁止措置
(3)ロシア向け化学・生物兵器関連物品等374の輸出の禁止措置
(4)ロシア及びベラルーシの特定団体(軍事関連団体等)375への輸出等の禁止措置
(5)ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体(軍事関連団体等)376への輸出等の禁止措置
(6)ロシア向け先端的な物品等377の輸出等の禁止措置
(7)ロシア向け産業基盤強化に資する物品378の輸出の禁止措置
(8)ロシア向け石油精製用の装置等の輸出等の禁止措置
(9)ロシア向け奢侈(しゃし)品379の輸出の禁止措置
(10)ロシアからの一部物品380の輸入等の禁止措置
(11)「ドネツク人民共和国」(自称) 及び「ルハンスク人民共和国」(自称)との間の輸出入の禁止措置
372 対象品目:工作機械、炭素繊維、高性能の半導体等及び関連技術
373 対象品目:半導体、コンピュータ、通信機器等及び関連技術、催涙ガス、ロボット、レーザー溶接機等
374 対象品目:化学物質、化学・生物兵器製造用の装置等。
375 対象団体:ロシア559団体、ベラルーシ27団体
376 対象団体:48団体
377 対象品目:量子コンピュータ、3Dプリンター等及び関連技術
378 対象品目:貨物自動車、ブルドーザ、シリンダー容積が1,900ccを超える自動車、自動車用エンジンオイル等
379 対象品目:アルコール飲料、宝飾品、グランドピアノ等
380 対象品目:アルコール飲料、木材、上限価格を超える原油及び石油製品、非工業ダイヤモンド等
(3) 日・中央アジア・コーカサス関係
中央アジア諸国は、東アジア、 南アジア、中東、欧州、ロシアを結ぶ地政学的な要衝に位置し、石油、天然ガス、ウラン、レアメタルなどの豊富な天然資源を有する。また、コーカサス地域は、アジア、欧州、中東をつなぐゲートウェイ(玄関口)としての潜在性と、国際社会の平和・安定につながる地政学的重要性を有している。
2024年6月20日、齋藤経済産業大臣は、ウズベキスタンのクドラートフ投資・産業・貿易大臣と会談を行い、「中央アジア+日本」対話・首脳会合381に向けて、両国の更なる協力関係強化を確認するとともに、GXやDX等の経済・エネルギー分野を始めとした二国間協力について意見交換を実施した。
2024年8月9日、カザフスタンのアスタナにおいて、中央アジア5か国及び日本企業約40社を含む約450名が参加し「中央アジア+日本」ビジネスフォーラムを開催した。DX、GX、インフラ分野等での協力拡大に向けて各国代表者が講演を行うとともに、日本企業と各国企業・政府との協力案件を34件披露した。
2024年9月9日、齋藤経済産業大臣は、キルギスのイブラエフ・エネルギー大臣と経済・エネルギー分野における二国間協力について意見交換し、エネルギー移行に係る政府間覚書を披露するとともに、キルギスエネルギー省と日本企業との水力発電所建設等に係る覚書披露に立ち会った。
2024年10月31日、武藤経済産業大臣は、ウズベキスタンのクドラートフ投資・産業・貿易大臣と会談を行い、グリーン、デジタル分野などを始めとした経済・エネルギー分野における二国間協力について意見交換を行うとともに、JCMの活用を含め、両国に裨益する再生可能エネルギープロジェクトの推進に向けた協力を進めることを確認した。
2025年3月17日、武藤経済産業大臣は、カザフスタンのヌルトレウ副首相兼外務大臣と会談を行い、GXを始めとする両国間での経済協力について意見交換を行うとともに、JCMを活用した再生可能エネルギープロジェクトの推進や、安定した投資環境の整備に向けた協力を進めることを確認した。
381 2024年8月に開催を予定していたが、災害対応及び危機管理のため延期となった。
8. 中東
(1) 今後の方針
中東地域382は、我が国原油輸入の9割超383、天然ガス輸入の約1割384を依存するエネルギー安全保障上重要な地域である。域内人口は約3.8億人(平均年齢27.9歳)385、名目GDPは約4.5兆ドル(ASEANの1.18倍)386と大きく、また、歴史的に親日的な国が多く、市場としての潜在力も大きい地域である。域内には、国際原油市場に大きな影響力を有する世界有数の産油国であり、巨大開発プロジェクトに取り組むサウジアラビア、進出日系企業拠点数350以上387、かつ在留邦人約5千人388を誇り中東の地域統括拠点を多く有するUAE、欧州等への輸出のための製造拠点の機能を果たすトルコ、イノベーション大国であるイスラエル、人口・経済規模・技術力等多くの可能性を有するものの米国の経済・金融制裁により貿易・投資等取引が困難なイラン等、特色の異なる多様な国々が存在する。我が国と各国との関係も様々であり、それぞれの実情を踏まえ、産業多角化や貿易・投資環境改善への支援・働きかけ等を通じて互恵的な関係を築くことで、中東地域との経済関係の強化・市場の拡大と、同地域の安定確保を目指す。
また、2024年12月、日本とGCC(湾岸協力理事会)は、サウジアラビアで、日・GCC・EPA交渉再開後の第1回会合を開催した。本会合は、前年に日・GCC間の首脳レベルでEPA交渉の再開に一致したことを受けて開催されたものである。日・GCC間においてさらなる経済関係の強化と投資促進の後押しとなるものにすべく、交渉が継続している。
382 本節での中東地域は、イラン、バーレーン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、オマーン、カタール、サウジアラビア、パレスチナ、シリア、トルコ、UAE、イエメンを指す。
383 資源エネルギー庁「資源・エネルギー統計年報」、2023年。
384 財務省「貿易統計」、2023年。
385 国連「World Population Prospects 2024」、IMF「WEO」(2023年10月)
386 世界銀行「World Development Indicators」
387 外務省「海外進出日系企業拠点数調査」(2023年調査結果)、2023年10月1日時点。
388 外務省「海外在留邦人数調査統計」、2024年10月1日時点。
(2) 進捗状況
① サウジアラビア
2017年3月に日サウジ両国首脳間で合意した「日・サウジ・ビジョン2030」のもと、日サウジ間の伝統的な協力分野であるエネルギー協力にとどまらず、広範な分野での二国間協力が進展している。
2024年5月、ムハンマド皇太子兼首相の訪日がサルマン国王の健康状態を受けて延期されたが、アブドルアジーズ・エネルギー大臣を代表とする関係閣僚は予定どおり訪日した。その際、経済産業省・JETRO・中東協力センター(JCCME)とサウジアラビア投資省が主催する日・サウジ・ビジョン2030ビジネスフォーラムや、サウジアラビア政府主催の日本・サウジ企業との対話(ラウンドテーブル)が行われた。齋藤経済産業大臣は、アブドルアジーズ・エネルギー大臣やファーレフ投資大臣等関係閣僚とともにこれらに出席した。同ビジネスフォーラムでは、日・サウジ・ビジョン2030やライトハウス・イニシアティブといった両国間の協力枠組みの進展並びに大阪・関西万博を成功させ、そのバトンを2030年万博の開催地であるサウジアラビアにしっかり引き継いで行く等の挨拶を行った。同ビジネスフォーラムには、日・サウジ両国の政府関係者・企業約330名が出席するとともに、日本企業・団体とサウジアラビア政府・企業・団体間の新たな協力覚書や契約の締結が30件発表された。また、ムハンマド皇太子兼首相の訪日延期を受け行われた日・サウジ・テレビ首脳会談では、両首脳を議長として包括的な二国間関係の強化を図る「戦略的パートナーシップ協議会」の設置に一致したほか、経済多角化・強靱化、地域安定化等についての意見交換が行われた。(同協議会設立の覚書については、2025年2月に行われた第2回日・サウジアラビア外相級戦略対話の際に署名された。)
2024年9月、石井経済産業大臣政務官は、訪日中のファイサル・サウジeスポーツ連盟会長による表敬を受け、日サウジ間のゲーム・eスポーツ分野における二国間協力について意見交換を行った。
2025年1月、武藤経済産業大臣はサウジアラビアを訪問し、ファーレフ投資大臣とともに、日・サウジ・ビジョン2030の進捗について民間企業とともに議論する日・サウジ・ビジョン2030閣僚ラウンドテーブルを開催した。武藤経済産業大臣からは、金融、ヘルスケア、クリーンエネルギー、ゲーム等の分野で新たな協力プロジェクトが合意されたことを歓迎するとともに、これまでの日本によるサウジアラビアへの協力がサウジアラビアのGDPに与える影響についての試算を紹介した。また、大阪・関西万博を成功させ、2030年に予定されるリヤド万博へとバトンをつないでいく決意を述べた。本イベントでは、両大臣立会いの下、新たに署名された13件の民間MOU等が披露された。加えて、同ラウンドテーブルに先立ち、ファーレフ投資大臣と会談し、日・サウジ・ビジョン2030の下、引き続き両国間の協力を官民で推し進めていくことを確認し、大阪・関西万博の開催時期を踏まえつつ、第8回日・サウジ・ビジョン閣僚会合の日本開催に向け、引き続き連携していくことで合意した。さらに、コロナ禍を経て2019年以来5年ぶりの開催となる、日本とサウジアラビア両国の民間同士の協議枠組みである日・サウジ・ビジネスカウンシルに出席し、日・サウジ・ビジョン2030における更なる協業を促すための、ビジネスカウンシルとの連携の重要性等について挨拶を行った。
また、武藤経済産業大臣は、サウジアラビア・ダラーン市で、アブドルアジーズ・エネルギー大臣と会談した。両大臣は、サウジアラビアが日本にとって最大かつ、最も信頼できる原油供給源の一つであり、さらに信用あるパートナーであることを強調し、ライトハウスイニシアティブを始めとしたエネルギー協力の進展を歓迎し、今後も幅広い分野で協力していく必要性を確認した。さらに、武藤経済産業大臣は、ファイサル・サウジeスポーツ連盟会長と会談を行い、日・サウジ・ビジョン2030の下、ゲーム・eスポーツ分野における両国関係者がウィンウィンとなるような協力の方向性について意見交換しつつ、両国でゲーム・eスポーツ分野の協力を積極的に進めていくことに合意した。
② イラン
米国の制裁下という困難な状況にあるが、2024年度には、IrREA(Iran Renewable Energy Association)幹部等向けの再エネ技術研修や、PIDA(Private Investors of Desalination Association)幹部向けの海水淡水化技術研修を、JCCMEが実施するなど、協力を継続している。
③ イスラエル
2024年8月、松尾経済産業審議官は、ギラッド・コーヘン駐日大使と会談し、日・イスラエル両国の経済連携強化のための意見交換を行った。
④ トルコ
2024年10月、上月経済産業副大臣は、経団連とトルコ海外経済評議会(DEİK)との間で開催された第27回日本トルコ合同経済委員会に出席した。委員会では、冒頭の挨拶にて、両国の外交樹立100周年というメモリアルイヤーの機会を捉えて、両国の経済関係の更なる発展に向けたメッセージを発出した。併せて、同日に署名された経団連とDEİKの共同声明、及び、トルコ・チャルックエナジー社とJBIC(国際協力銀行)による脱炭素・GX推進を目的とするパートナーシップ強化のMOUの披露式に立ち会った。また、出席していたトゥズジュ貿易副大臣との間で会談を行い、日トルコEPAの早期妥結や、二国間の経済関係強化に加え、ルールベースの多角的貿易秩序の維持・強化に向けた取組などについて議論した。
さらに同日、上月経済産業副大臣は、訪日したチョンカル・エネルギー天然資源副大臣と共に、経済産業省とトルコエネルギー天然資源省の共催で行われた第1回日本トルコ・エネルギーフォーラムに出席した。同フォーラムでは、省エネルギー、再生可能エネルギー、新燃料・技術の三つの分野において、具体的な提案や活発な意見交換がなされ、両国間の幅広い分野において協力の潜在性があることを確認した。終了後、両副大臣は、会合議事録に署名するとともに、両国企業間による新燃料及び循環型社会分野等の協力に関するMOU署名(三菱商事株式会社とCalik Enerji、三菱商事株式会社とDB Tarimsal Enerji)に立ち会った。また、フォーラムに先立ち、両副大臣は会談を行い、今後の日トルコ間のエネルギー面における協力の可能性について意見交換を行った。
⑤ カタール
2024年10月、上月経済産業副大臣はアル・マッリ駐日大使と会談し、LNGを始めとするエネルギー供給における両国の信頼関係を確認するとともに、2023年の岸田総理大臣のカタール訪問時に、両国の関係が戦略的パートナーシップに格上げされたことに触れ、更なる経済分野での連携について意見交換を行った。
⑥ オマーン
2024年3月、岩田経済産業副大臣のオマーン訪問時に、経済産業省と商工業・投資促進省との間で署名した共同声明に基づき、両国のビジネス交流が進められている。
同4月、岩田経済産業副大臣は、訪日中のスナイディ経済特区・フリーゾーン庁(OPAZ)長官と会談し、今後のビジネスミッション派遣を通じた両国ビジネス関係者の交流や、オマーンの経済特区・フリーゾーンへの日本企業の進出について意見交換を行った。
同12月、両国の共同声明を踏まえ、JCCMEによるビジネスミッションがオマーンを訪問した。滞在中、オマーン商工会議所でのビジネスセミナーやエネルギー鉱物資源省等とのラウンドテーブルを通し、オマーンの政府関係機関や民間企業とビジネス交流を行うとともに、カイス商工業・投資促進大臣を表敬訪問し、両国の更なる連携強化に向けた意見交換を行った。さらに主賓国として招待された同国新聞社が主催する「ルウヤ・ビジネス・アウォード」に参加し、ミッション参加企業や、両国のビジネス交流に関する取組が紹介された。
⑦ イラク
2024年8月、JCCMEが第19回イラク・ビジネスセミナーをオンラインで開催し、駐イラク日本大使や農業省・水資源省を始めとしたイラク政府機関が講演を行った。
⑧ アラブ首長国連邦(UAE)
2022年に日UAE両国の首脳間で合意された「包括的・戦略的パートナーシップ・イニシアティブ(CSPI)」の下、従来のエネルギー協力に加え、先端技術等の非エネルギー分野における協力も加速しており、両国間で活発なハイレベルの往来が行われた。
2024年4月、吉田経済産業大臣政務官は、UAEを訪問し、再生可能エネルギー・環境技術をテーマとする世界最大規模の展示会である「ワールド・フューチャー・エナジー・サミット(以下、WFES)2024」開会式に出席するとともに、日本パビリオンや日本企業の展示ブースを視察し、関係者との間で、日本が有する先端的なクリーンエネルギー技術等について意見交換を行った。また、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)総会にも出席し、世界全体でネット・ゼロを目指すことの重要性や、更なる再生可能エネルギーの導入拡大に向けたイノベーションの重要性について発信するとともに、再生可能エネルギー分野におけるIRENAやメンバー各国との協力を確認した。さらに、日UAE両国間のビジネス環境や協力等について議論する、民間主体の協議体「日UAEビジネスカウンシル」の第1回会合に出席し、開催への祝辞を述べた。これら国際会議等への出席に加え、ジャーベル・アブダビ国営石油会社(ADNOC)CEO兼産業・先端技術大臣兼日本担当特使、ラ・カメラIRENA事務局長と会談を行った。
同5月、齋藤経済産業大臣は、アル・ファヒーム駐日大使の表敬を受け、原油供給における長年の協力に基づく両国の信頼関係の確認を含む、二国間の経済協力について意見交換を行った。
同7月、齋藤経済産業大臣及び吉田経済産業大臣政務官は、訪日中のジャーベル産業・先端技術大臣及びゼイユーディ貿易担当国務大臣と会談し、齋藤経済産業大臣からは、石油・天然ガス分野に加え、エネルギー移行を含む幅広い分野に協力の裾野を広げていく考えを述べるとともに、日UAE両国が双方にとって重要なパートナーであることを確認した。また、両国大臣の立会いの下、資源エネルギー庁とADNOCの間における日UAE産油国共同備蓄の覚書及びJBICとADNOCの間における事業開発等金融に係る一般協定が署名された。
同9月、日本とUAE両国政府は、日UAE・EPA交渉開始を決定した旨を発表した。その後、2024年11月に第1回交渉、2025年2月に第2回交渉を行い、EPAをさらなる経済関係の強化と投資促進の後押しとなるものにすべく、交渉が継続している。
同10月、リサイクル関連のビジネスミッション団と共にアル・マッリ経済大臣が、国内最大級のデジタルイノベーションの総合展である「CEATEC」出席のためにマズルーイ起業・中小企業担当国務大臣が、それぞれ訪日し、松尾経済産業審議官と会談して、両国間での循環経済や中小企業・スタートアップに関する協力等について意見交換を行った。
同12月、経済産業省、内閣府、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、JETRO及びUAE宇宙庁共催により、アブダビで「日UAE宇宙官民ワークショップ」を開催した。同ワークショップは、2023年7月の岸田総理大臣のUAE訪問時に署名された両国の宇宙分野での協力覚書に基づくもので、日本側から26社、UAE側から23社の宇宙関連の大手企業やスタートアップを含む、両国の官民宇宙関係者総勢約200名が参加し、日UAE間の将来の協力に向けた活発な意見交換や交流が行われた。
同月、古賀経済産業副大臣は、東京で開催されるUAE経済省主催の投資促進イベント「Investopia Global – Tokyo」に参加するため訪日したアル・マッリ経済大臣と会談し、UAEの再生可能エネルギーのポテンシャルや日本の資源循環に関する技術の活用、日UAE・EPA交渉促進等を通じた二国間経済交流の拡大に向けた意見交換を行った。さらに、「Investopia Global – Tokyo」では、アル・マッリ経済大臣、マズルーイ起業・中小企業担当国務大臣、日UAE両国のビジネス関係者が集う中、松尾経済産業審議官が基調講演を行った。
2025年1月、武藤経済産業大臣はUAEを訪問し、昨年に続いて開催された「WFES2025」の開会式に出席し、ムハンマド大統領を始めとする要人と懇談するとともに、先端技術やAIに関する日本企業の技術を展示する日本パビリオンにおいて大阪・関西万博への来場を呼びかけた。また、ジャーベル産業・先端技術大臣と会談し、気候変動対策や先端技術分野での協力関係の進捗について確認しつつ、宇宙分野における両国の宇宙産業基盤の発展に向けたロードマップ作成など、具体的な議論の開始に合意した。ハルドゥーン・アブダビ執行関係庁長官との会談では、UAEのソブリンウェルスファンドとの連携を含めた、協力拡大の可能性について議論した。さらに会談に合わせ、武藤経済産業大臣、ジャーベル産業・先端技術大臣、ハルドゥーン長官立会いの下、日本企業によるアブダビの医療施設へのがん治療装置納入に向けたエンジニアリング契約の披露並びに、ADNOCによるLNGバリューチェーンからのメタン排出削減に係るCLEANイニシアティブへの賛同意思表明が行われた。
⑨ クウェート
2024年7月、日アラブ経済フォーラムにおいて、齋藤経済産業大臣は、ブーシャハリー電力・水・再生可能エネルギー大臣兼住宅問題担当国務大臣と会談を行い、2019年の第4回東京開催を最後に、コロナ禍以降延期されていた日クウェート電力・水分野政策対話の開催に合意した。その後、2025年2月、クウェートにおいて日クウェート電力・水分野政策対話が開催され、両国間の現状と課題について共有し協力の可能性について話し合われた。
⑩ 日本・アラブ経済フォーラム
2024年7月10日から11日にかけ、外務省及びアラブ連盟との共催で、第5回日本・アラブ経済フォーラムを開催した。10日に開催された官民経済カンファレンスには、齋藤経済産業大臣が出席し、開会挨拶を行った。また、11日に開催された閣僚会合には、日本側から、齋藤経済産業大臣、上月経済産業副大臣、上川外務大臣及び辻󠄀外務副大臣が出席し、アラブ側参加者との間で、日本とアラブ諸国の経済関係強化に向けて議論を行った。併せて、各国閣僚等と、齋藤経済産業大臣及び上月経済産業副大臣が会談を行い、二国間経済協力について意見交換を行った。
9. アフリカ
(1) 総論
アフリカは、豊富な天然資源とともに、若年層を中心に14億人を超える人口を抱え 、2050年には約25億人(世界の人口の約1/4)に増加すると予測される。過去20年間、他地域に比べても高い経済成長率を維持し、経済力を向上させるとともに、G20やWTOなど国際場裡における発言力を高めている。このような中、アフリカは、世界からの投資先として注目されている。
従来、資源・インフラを中心としていたアフリカビジネスは、各国の産業発展や、医療・食糧ニーズの増加、急速なデジタル技術の発達を背景とした一足飛びの電子金融導入、電子商取引の普及などを通じて、様々な分野での社会課題解決に向けた事業の展開など、多様化しつつある。また、電力・運輸・港湾等のインフラ分野の需要は引き続き大きい。2021年1月にはアフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)の運用が開始され、アフリカ域内貿易の促進が具体的に進むことが期待される。
我が国は、質の高いインフラ整備の推進、投資協定や租税条約の締結促進などとともに、TICADや日アフリカ官民経済フォーラムなどの官民が一体となった対話の場を活用し、アフリカ各国との経済関係を強化している。また第三国や国際機関との連携を強化することを通じて、日本企業のアフリカ進出を支援していくとともに、進出した企業のアフリカにおける円滑な業務遂行をサポートしている。
(2) 進捗状況
2024年12月にコートジボワール・アビジャンで、日本からは大串経済産業副大臣、共催国であるコートジボワールからはマンベ首相、ディアラスバ商業・産業大臣出席のもと、第3回日アフリカ官民経済フォーラムを開催した。アフリカ各国から約20名の閣僚級が出席し、40か国から企業・団体約100社など、官民約1,200名の参加があった。また、マンベ首相の基調講演を始め、武藤経済産業大臣もビデオメッセージにて参加した。全体会合を通じ、日・アフリカ官民参加者の間で、日本との共創を念頭に、アフリカの経済多角化・産業高度化の将来像を提示し、アフリカの社会課題解決とグリーンで持続可能な成長の両立の実現に関して議論が行われた。そして我が国から、①日本企業とスタートアップの連携強化に係る枠組み(「日本アフリカ産業共創イニシアティブ(JACCI)」)、②インド等第三国との連携強化、③ファイナンス支援策を発表した。
官民一体でアフリカビジネスを継続的に議論するプラットフォームである「アフリカビジネス協議会(JBCA)」(2019年6月発足)では、官民の参加者間でアフリカビジネスに係る情報共有と意見交換を行い、関係省庁・機関による支援策の検討・実施・見直し等を行っている。具体的には、①アフリカ政府・企業とのネットワーキング・マッチング機会の提供、②アフリカ各国のビジネス環境改善の促進、③各省庁・機関横断による支援策の連携促進等を目標に掲げ、活動を行ってきた。
JBCAには、経済産業省、外務省、経団連、経済同友会を始め、約450の企業・団体・官公庁・国際機関が所属している(2025年3月時点)。中堅中小企業、投資環境改善、農業、ヘルスケアなどをテーマとしたWG(ワーキンググループ)が、アフリカビジネス展開に関する課題の吸上げや、現地事情などの関連調査、日本企業と現地関係機関との関係構築等を実施している。
2022年8月には第2回本会議を開催し、JETRO理事長の共同議長就任や、JETRO・国際協力機構(JICA)の事務局への参画等の機能強化が確認された。また、中堅中小企業、農業、ヘルスケアなどをテーマとしたWGが発足し、現地経済団体・企業との関係構築・マッチングや調査ミッションなどを継続的に実施する。特に経済産業省が主宰する中堅中小WGは、2022年5月、2023年1月に実施し、アフリカビジネス進出企業の取組や公的機関による支援メニュー等を紹介した。
2024年度には、JETROがオンラインと対面を組み合わせて日本企業とアフリカ各国とのネットワーク構築を支援した。オンライン商談会は、2024年度に計3回開催し、これまでと異なる分野として、キャラクターライセンス分野(2024年7月~8月)、モロッコ日用品デザイン(2024年10月~11月)、アジア・アフリカ広域農業資機材・アグリテック・漁業資機材(2025年1月~2月)の各テーマで実施した。海外見本市では、ナイジェリアのラゴス国際見本市(2024年11月)にジャパン・パビリオンを設け、会期中に約3万2,000人の来場者を集めた。ビジネスミッションは、エジプト(2024年9月)とアルジェリア(2025年2月)に、水素等の再生可能エネルギーや水インフラを含むグリーンビジネスの促進を目的に派遣、エジプトに現地進出を検討するメーカー等を対象とした製造業ミッション(2025年1月)、モロッコに自動車産業ミッション(2025年2月)を派遣した。この他、アフリカ18か国を対象に、市場動向調査からパートナー先候補の紹介、商談設定までを支援するアフリカビジネスデスクを通年で設置し、これら事業を活用した日本企業は、のべ約190社を数えた。
2024年8月、東京でTICAD閣僚会合が開催され、経済産業省からは石井経済産業大臣政務官が参加し、プレナリーセッション3“経済”で開会挨拶を行った。挨拶の中では、日本とアフリカがともに社会課題解決と持続可能な成長を両立できる社会を作り上げる重要性について述べ、経済産業省・JETRO・アフリカ側ホスト国の共催で行う「第3回日アフリカ官民経済フォーラム」をコートジボワール・アビジャンで開催予定であることを発表した。また、万博公式キャラクターの「ミャクミャク」と共に壇上にあがり、2025年に開催される大阪・関西万博を通した日本・アフリカの経済関係強化をアフリカ各国の閣僚に呼びかけた。
2024年11月には、武藤経済産業大臣がモロッコのジダン投資・公共政策統合・評価担当大臣と会談を行った。会談では、欧州・サブサハラアフリカの間に位置し、アフリカから欧州市場への輸出拠点となっているモロッコへの日本企業の参入を通じた経済関係の深化の在り方等について意見交換を実施した。また、会談後には、日本企業によるモロッコへの投資・貿易活動を促進するための協力覚書に両大臣が署名した。
2025年2月にはヒチレマ・ザンビア大統領を迎えて「日本・ザンビアビジネスフォーラム」、 3月にはマシャティーレ・南アフリカ副大統領を迎えてビジネス・ラウンドテーブルを開催し、日本企業に対して同国のビジネス環境を紹介した。「日本・ザンビアビジネスフォーラム」には、経済産業省からは竹内経済産業大臣政務官が出席したほか、ヒチレマ・ザンビア大統領と会談を行った。
2025年2月、南アフリカ・ケープタウンでアフリカ鉱業投資会議「マイニング・インダバ2025」が開催され、経済産業省からは古賀経済産業副大臣が参加した。この会議で、古賀経済産業副大臣はザンビア、コンゴ民主共和国、及び南アフリカの要人と会談するなど、鉱業分野等における日アフリカ間の一層の関係強化に取り組んだ。また、南アフリカ訪問の機会を捉え、南アフリカの貿易投資大臣、電力エネルギー大臣とも会談を行い、各分野での二国間関係の強化について意見を交換した。